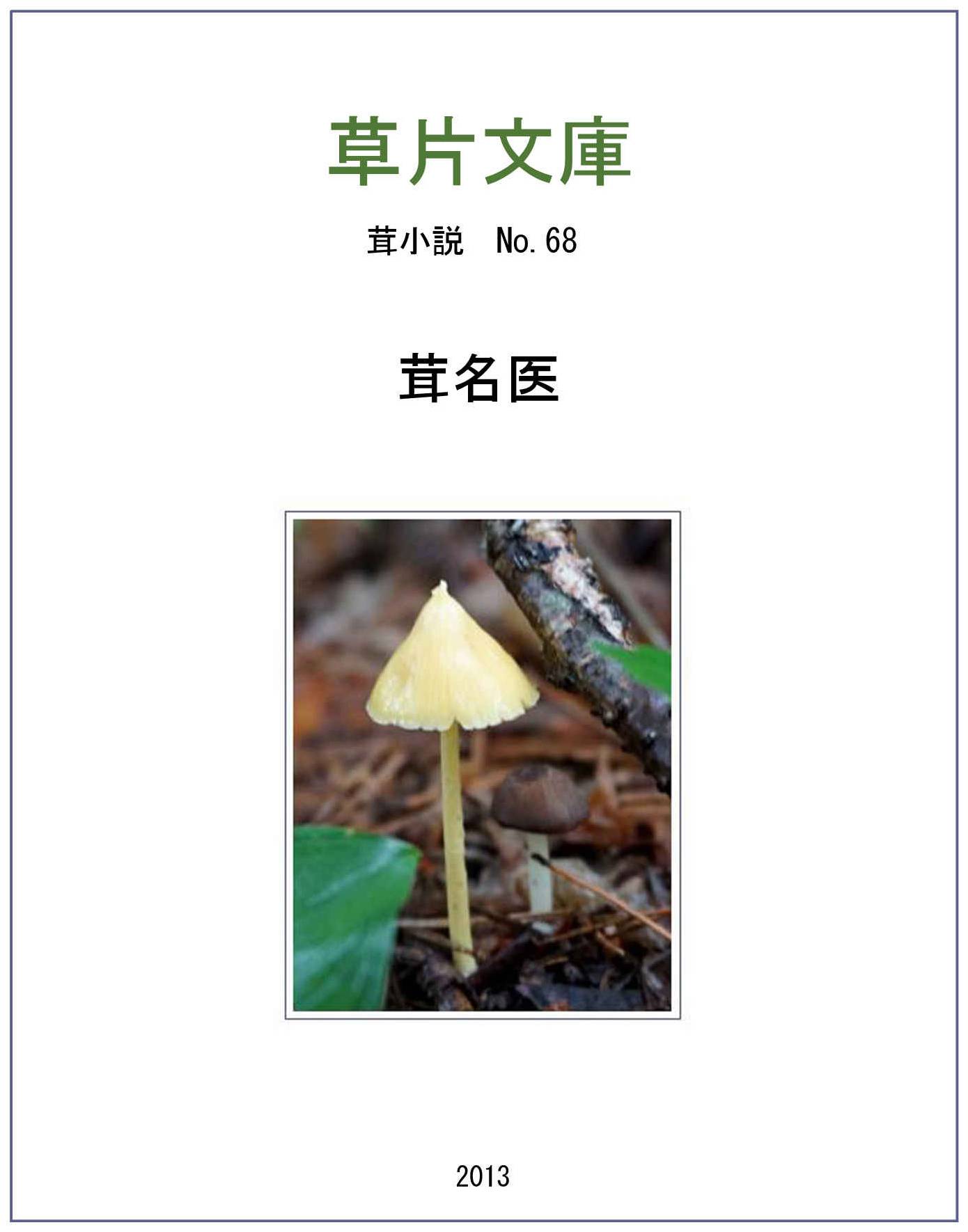
茸名医
今日の診察が終わった。
土曜日は受付を十二時までとしているが、昼もほとんど食べずに三時過ぎまで患者を診た。いつものことである。三時に終わればましなほうかもしれない。
「あなた、ここにお昼と夜の食事用意しておきますね、会計終わったから、これで行きますね」
家内の声である。
「ああ、お父さんによろしくな、風邪薬処方してあるから持っていってあげて」
「はい、ありがとう」
家内の藻衣子(もいこ)には医院の経理と雑務をまかしてある。
父親が風邪を引いたらしい。明日は休診日であるし、藻衣子は久しぶりに、実家に帰り、一人暮らしの父親を泊まりがけで面倒を見ることにしていた。長女の美(み)藻子(もこ)も仕事場から直接合流するということだった。
「私も失礼します」
「どうもありがとう」
通いの看護婦の一人、平井さんである。二人の看護婦が交互に手伝ってくれている。どちらも家庭持ちで、よく働く女性たちだ。とても助かっている。
私は手を洗い、白衣をハンガーにかけて診察室を出た。
二人がそろって出ていったあと、用意してあったサンドイッチをつまみ、紅茶を飲んだ。
一階の居間の廊下のガラス戸を開けると、秋の気持ちのよい風が入ってきた。空を見上げると、青空が広がって、細い雲が薄くたなびいている。
サンダルを履いて庭に出た。自分では手入れができない庭も、家内がよく世話を焼いてくれている。木々のほどよく刈り取られている枝が、のびのびと庭を覆っている。木の下には、私は名前を知らないが、山野草類がよく繁っている。
今年は茸が多い。金木犀の下に紅天狗茸が生えている。赤くてきれいだが猛毒である。小さな落葉茸の仲間が落ちた葉からたくさんでている。
私は部屋に戻った。やはり齢である。診療を終えるとちょっと眠くなる。パジャマに着替え、遅い昼寝をしに寝室に入った。
かなり寝入ってしまって、起きたのは七時を過ぎていた。
キッチンに行って冷蔵庫を開けてみる。いくつかの料理がラップに包まれ入れてある。取り出して電子レンジにいれて温め夕食の用意をした。テレビをつけると、天気予報がしばらく晴天が続くと言っている。
昼寝を長くしてしまったので寝るのは遅くなる。このような土曜日の夜はいつも二階の居間で映画のDVDを見る。見始めると何本か立て続けに見てしまう。
その日も二本ほど見終わって、さて次のはどれにしようかと思案していた時である。零時を少し回った頃であった。医院の玄関の呼び鈴が鳴った。たまに急病人を連れた人が来る。車の止まる音もしなかったので近くの人であろう。
一階に降り、パジャマの上に白衣をひっかけて、玄関を開けた。案の定、怪我人であった。
年の頃三十程の男が一人、右手で頭を押さえてうずくまっていた。
「どうしました」声をかけると、男は顔を上げ、角刈りの頭から押さえていた手を離した。見ると右の側頭部に血がこびりついている。
処置室の中に招き入れ、傷を見ると頭の皮が剥がれている。
「どうしたのです」
その男はしどろもどろに「転んで、擦りむいたんで」と言った。
事件ではなさそうであるが、転んだだけで頭の皮が剥がれるだろうか。酒を飲んでいるようでもないし、誰かに襲われた風でもない。とりあえず水洗いをして、アルコールで消毒をした。
「沁みるでしょう」
「大丈夫です」
これだけの傷にアルコールをつけると普通の人は飛び上がって痛がるが、全く平気な顔をしている。とても我慢強いのか感覚がにぶいかである、
剥がれた皮はやはり縫っておいたほうが良いだろう、頭に局所の麻酔薬を塗布して、皮を縫い付けた。
そのころになると、男の表情も少し明るくなった。
「こんなひどい怪我、どうしたんです」
「あわてていて、坂で滑ってコンクリートに擦り付けちまいまして」
「ばい菌が入るといけないので、消毒にまたきてください。それに、塗り薬と、抗生物質も一応出しておきますから、明日は休みなので、月曜日に一度きてください。もし、その部分が腫れ上がるようなことになったら、明日でもかまいませんから来てください。様子によっては外科の病院を紹介します、保険証はお持ちですか」
男は首を横に振った。
「次に来るときに持ってきてください」」
「はい」
「ご家族に連絡はしましたか、遠いのですか、タクシーを呼びましょうか」
「いや、一人もんで、歩いても帰ることができます、携帯もあるので必要ならタクシーを呼びます」
「そうですか、お大事になさってください」
「ありがとうございます」
彼は、名前と住所を書いて、意外と元気な様子で帰っていった。
患者が帰った後、映画を見るのは明日にしてと思い、寝酒にウイスキーを取り出した。テレビのニュースなどを見ながら、ちびりちびりと飲んでいると、また医院の呼び鈴がなった。
一晩に何人かの急患がくることもあり珍しいことではない。特に子供の発熱が多い。
酒臭いかもしれないがしょうがない。診察室に降りて、白衣をひっかけると、鍵を開けた。
「すみません、怪我をしてしまって」
若い女性が病院の入口前でたたずんでいた。着ているピンク色の長袖のワンピースの左腕のところに血がにじんでいる。
「ともかくお入りください」
私は女性を診察室に通した。
「転んでしまって」と女性はワンピースの腕をまくりあげた。白く細い腕に黒くなった血の固まりがこびりつき、その表面からジクジクと血が滲みだしている。明らかに擦った傷である。
ワンピースの上半身を脱いでもらうと、腕をとった。
「大した傷じゃないから消毒しておけば大丈夫でしょう」
傷口を水で洗い、「しみますよ」とアルコールをつけ、その後に傷薬を塗った。
女性は痛いという顔を全く見せず、傷の手当を見ている。このくらいならば、あまり包んでしまうのもよくないだろうと思い、消毒をした後はガーゼをメンディングテープで止めただけにした。
「明日までガーゼをつけておいて、あとは外していいですよ、ただばい菌が入るといけないので、きれいにしてください。まだ風呂の湯には浸けないように、どっちみち沁みるので無理でしょう、明日は休みなので、明後日、様子を見せてください」
そう言って、女性の腕を放した時である。女性の腕がくにゃっと肘の関節から反対方向に曲がった。
おやっと思って、もう一度女性の腕をとって女性の顔を見た。ブロンドの髪は染めたものではなく、自然のようだ。日本人離れした彫りの深い顔は、なんとなくマリリンモンローに似ていないくもない。そういえば、先ほどきた男性は渥美清に似ていた。
「痛くはないですか」腕を上下させ、私は女性に聞いた。
「いえ」顔色一つ変えない。
「肘の関節のところが折れているようですが、これで痛くないのは不思議ですね、レントゲンを撮りましょう」
内科医だが腕くらいなら調べることができる。私はレントゲン技師の資格までもっている。
女性にそのままでいいからと、レントゲン室にきてもらい、セッティングする間、待ってもらって撮影した。
今のレントゲン装置はコンピューターにそのまま映像がでるので便利である。
女性の腕は、やはり肘の関節が離れていた。おかしなことに、骨は折れていないようである。関節が抜けているようなのである。
「これで痛くないですか」
女性はうなずいた。
私は女性の二の腕と手首を持つと思い切り押してみた。くきっという感じでおさまり、不思議なことに右腕はしっかりした。
「もう一度レントゲンを撮りましょう」
レントゲンの画像を見ると、関節は何事もなかったようにはまっていた。
「動かしてみてください」
女性は腕を右に左に動かた。
「痛くありませんか」と聞くと、うなずいた。
私はとりあえず、添え木を当て包帯を巻いた。
「家は遠いのですか、タクシーを呼びましょうか」
女性は首を横に振った。
「近くなので歩いて帰ります、ありがとうございました」
女性には次に来るときに保険証を持ってくるように言って送り出した。
奇妙なことであった。明後日来たら外科に行くように言うべきであろう。
こうして、私はやっと床にはいることができた。
次の日は休みである。ゆっくり寝ることが出来た。
朝九時頃、ベッドから降り朝風呂に浸かった。その後朝食を作った。朝食といっても、グレープフルーツを切って、トーストにハム、レタス、紅茶といった至って単純なものである。あればそれにヨーグルトくらいか。
トーストにハムを挟んで食べていると、また病院のブザーが押された。
まだパジャマのままだが、白衣をひっかけて病院玄関の戸を開けた。
赤ら顔の男が立っていた。
「足をやられちまって」
「まあ、入って」
私は診察室に招き入れ、椅子を勧めた。男はびっこを引きながら、椅子に腰かけた。
「左足なんで」
ズボンの上から足を持ってみると、脛のあたりでぶらんぶらんしている。
「折れてるな、痛いでしょう」
「いえ、それほどでも」
ズボンを脱がして、左足の脛のところを見ると紫色になっている。何かがぶつかったようだ。触れてみると明らかに骨が折れている。しかし触っても男は痛そうな顔をひとつとしてしない。
車椅子を持ってきて、乗るように促し、レントゲン室につれていった。
やはり骨がポッキリ折れていた。ただ不思議なことは、転んだり落ちたりしても、普通は折れる部分ではないところがきれいに折れていた。
「どうしました」
「いえ、転んで」
「とりあえず、応急措置をしておきますから、明日にでも大きな病院で見てもらってください。手術することになりますよ」
出血も見られないので、添え木を当て、痛み止めと抗生物質をだした。
「タクシーできたのですか」
「いえ」
「それで歩いてきたのですか」
「へえ」
「痛くなかったのですか、歩くのは無理ですよ、どなたか家の方に迎えに来てもらった方がよいでしょうね」
「へえ」
「松葉杖をかしましょう、タクシーを呼びましょうか」
「いや、携帯で呼びますから」と、車椅子からおり、片足をひきずり器用に歩いて外に出ていってしまった。
昨夜から奇妙な患者が続く、あれだけの怪我をしていたら、痛いと思われるのに、だれしもが痛くないと言う。
私は食べかけの朝食に戻った。
その日も天気は良かった。庭をぶらぶらしていると、近所の若い雄猫が遊びに来ていた。陣太郎と呼ばれる猫である。家内が猫好きでかまうものだから、いろいろなところから猫が遊びに来る。
元気に駆け回り、木にかけ登ったり、木の間を飛び回った。三本生えていた紅天狗茸の一本の首が折れた。
しょうがない猫だ、と思いながら、ほかのところを見ると、いろいろな茸が踏み荒らされている。今年は茸が豊作だ。といっても、私には食べられる茸かどうかはわからない。このあたりの庭に生えるようなやつは、食べることができても大した味のものではないのだろう。
陣太郎は勢い良く庭から飛び出していった。
部屋に戻った。午前中は久しぶりにのんびりと、なにをするでもなく過ごし、昼は炊いてあったご飯を茶漬けにして簡単にすませた。
午後は映画でも見ようかと、DVDの棚から2001年宇宙の旅を取り出すと、プレイヤーにかけた。古い映画だが好きなものの一つである。
この映画を見ると「生命の定義」を考えさせられる。コンピューターが意志を持つということは有り得るのだろうか。生命を考えてみると、ただの化学反応で動いているとしかみえないようなものも生き物として分類されており、「生命」の範疇にいれられている。とすると、DNAを持たなくても自分で増え、自分で判断するコンピュータがいるとすればそれは生命だろうか。
などと、若い頃に考えたことを思い出しながら映像を見た。
映画が半ばにさしかかった頃である。また病院のブザーがなった。
玄関の戸を開けると、首を右側に傾けた女性がいた。
「首がおかしくなりましたの、診ていただけますか」
「ええ、どうぞ」診察室に案内すると、女性の首に手を触れてみた。首の腱が伸びているようである。ただ、骨に異常をきたしているかどうか調べる必要があるだろう。レントゲン室に来てもらい、写真をとった。
頸椎骨が少しずれているかもしれない。
「どうなさいました」
「寝違いのようです」
「うーん、寝違いだとこれほどの変化は見られないでしょう、何か無理をしませんでしたか」
「いいえ」
「骨が少しだけどずれているようですね、とりあえず首を固定しましょう。明日大きな病院に行くようにしてください。紹介状は書きます」
「はい」
「かなり痛いでしょう」
「いいえ」
「不思議ですね、無理をしないようにしてください、それとかならず大きな病院に行ってくださいね」
「はい」彼女は素直に頷いた。
隣町の私立病院への紹介状を書いて持たせ、女性を送り出すと、居間に戻った。どうも昨日から外科系のおかしな患者ばかり来る。しかも、誰一人として保険証を持ってきていない。今時医者に行く時は必ず持ってくるのが常識である。
2001年宇宙の旅を見終え、映画は止めて、本を読むことにした。
中井英夫の幻想博物館を書棚から取り出した。大学時代に買った本であるが、とても面白かった記憶がある。幻想連作短編集である。
読み始めたところに電話が鳴った。家内からだ。父親の風邪がかなりひどいので、もう一日泊っていいかというものだった。
「いいよ、今日の夕食はなにかとって食べるよ、明日は風邪がはやっているから患者も多いだろうけど、箱田さんが来るし大丈夫だ、それより昨夜から四人も変な怪我の急病人が来たよ」
「そう、すみません明日、昼頃には帰るから」
ということで、今日も一人ですごすことになった。
中井英夫の本を読んでいると、また、患者が来た。双子の子供を連れたお母さんである。
三人とも膝っこぞうを紫色にしている。
「おや、三人一緒に転んだんですか」
「ええ、かなり強く打ったんで、お皿が割れたのではないかと心配になって来たんです」
お母さんの膝をちょっと触れてみた。確かに膝蓋骨がおかしくなっているかもしれない。双子の子供の膝を触ってみると、こちらは大丈夫のようだ。ともかくレントゲンをとることにした。
やはり、お母さんの膝はひびが入っていそうだが、子供の方は打ち身だけのようだ。お母さんの膝をとりあえずサポーターで固定した。
「坊やたちの膝っこぞうは打っただけだから、塗り薬を出しておきます、お母さんの膝はひびが入ってますので、大きな医院に行ってくださいね」
「はい、ありがとうございます」
「ふつうは痛くて歩けないのですけどね」
「大丈夫です」
母親は双子をしたがえて帰っていった。
一人くらい痛いと言う患者がいてもよいのに本当に不思議だ。
私はまた、ソファーで寝転びながら中井英夫の小説を読みはじめた。
どうもそのまま寝てしまったようだ。ブザーで起こされた。
時計を見ると、もう五時に近い。この時期になると、外は薄暗くなっている。あわてて、診療室に降りて、玄関を開けた。
杖を突いた老人が立っていた。診察室に案内すると、椅子に座って手を胸にあてた。
「胸が苦しくてな」
「咳はでますか、風邪でしょうかな」
「いや、風邪はひいとらん」
「喉を見ますので口を開けてください」
老人は口を大きく開けた。脂のたまった歯がでこぼこに並んでいる。喉は特に赤くなったり腫れたりはしていない。
「それではシャツを上にあげ、胸を見せてください」
肋骨の浮いた胸に聴診器をあててみても、肺に特段の異音は聞かれなかった。喘息気もなさそうである。
ふと、胸を見ると、右側の肋骨がすべて沈んでいるように見えた。左右が何となくバランスがとれていない。これは経験者じゃないと気がつかないかもしれないことだろう。
肋骨に軽く手を触れてみた。折れている。
「痛くないですか」
「うん、痛くないな」
「肋骨が折れているようですけど何かしました」
「ああ、転んだんだ」
それを早く言ってくれればいいのにと思い、レントゲン室に案内した。
案の定、右側の四本の肋骨が折れているかひびが入っている。
「これで痛くないことはないのですけどね」
「大丈夫だ」
不思議なことである。老人の痩せた胸にシャツの上からコルセットをはめた。
「外科医院に行ってください」
「ああ、明日、家族の者と行きます」
私は紹介状を持たせて送り出した。老人は、「すまんの」と言いながら杖を突いて、出ていった。
六時をまわっていたので、天丼の出前を頼み、冷蔵庫の中から、チーズと煮てあった芋を取り出しビールを飲んだ。テレビではこのところの熱さについて解説している。秋になってもかなり暑い。
勝手口の呼び鈴が聞こえた。以外と早く出前が来た。
戸を開けると、若い鉢巻姿のお兄ちゃんが、天丼を抱えている。
「へい、お待ちどうさまで、遅くなったので、これは、食べてください」
天丼に、鶏肉と野菜の煮物をつけてくれた。
「いや、とても早く来たので驚いているんだ」
お兄ちゃんの右手の手の甲が擦れて血が滲んでいる。
「どうしたの、その手」
「壁に擦り付けちまって」
下を向いて頭をかいた。
「病院の方にいらっしゃい、薬塗っとこう」
「すんません」
病院の入り口を開けると、お兄ちゃんはそちらに回ってあがってきた。診察室に招きいれると、手の甲を水洗いし、消毒薬を塗った。チンキで手の甲が紫色になった。
「すんません」
ガーゼをあてて紙絆創膏で簡単にとめた。
「寝るときははずして、消毒薬だけ塗ってください、風に当てた方がよい」
「ありがとうございます」
「えーと。天丼いくらかな」
「いえ、治療代がないからただでいいです」
「そうはいかない」
「いえ、おやじに言うとなぜ代金などもらったと怒られます」
「それじゃあ、かえって悪いね、まあ、いただくことにするか」
「へい、こちらこそ毎度ありがとうございます」
若いお兄ちゃんは喜んで帰って行った。
天丼を食べながらビールを飲み、映画を見た。久しぶりにビールを三本も開けたので早くから眠くなった。
まだ、九時にならないうちにベッドにはいると、すぐ眠りに落ちた。
「お父さん、よく寝てるわ」
居間のほうから声が聞こえてきた。
「ビールを三本も飲んだからよ、珍しいわね、調子がいいのね」
娘の美藻子と家内の藻衣子の声である。
目を開けると、日が射している。もう朝だ、それにしても、あの二人はお昼頃に帰る予定だったのではないだろうか。
「帰ったのか」
寝室から声をかけると、美藻子が戸を開けてのぞいた。
「昨日の夜帰ったわよ、箱根の温泉よかった、お父さんも来ればよかったのに」
「え、母さんの実家に行っていたのじゃないのか」
「なに言ってるの、飲人(のみと)さんも一緒に、母さんと三人で久しぶりに温泉に行ってたのじゃないの、お父さんは行きたくないって、残ったのじゃない」
「うーん、そうかなあ、おじいちゃんの風邪はどうだった」
「おじいちゃんは二十年前に亡くなったじゃない」
藻衣子が部屋をのぞいた。
「一人じゃ寂しかったんじゃありません」
「馬鹿いっちゃいけない、一昨日の夜から、昨日の昼も、休診日だっていうのに、怪我人がたくさん来て大変だった」
「そんなに来たの」
「ああ、ずいぶんレントゲンも撮った」
「大変だったのね」
私はやって来た怪我人のことを詳しく話した。
「どこの人たちだったのかしら」
「診察室に、書いておいたよ」
「そう、後で見てみるわ」
そのとき、庭から娘たちを呼ぶ飲人君の声が聞こえた。
「庭に来てごらんよ」
美藻子と藻衣子は一階に降り、庭に面した廊下のガラス戸を開けた。私もベッドから出ると下に降りた。
飲人君が朝日の当たる木の下を見ている。
「茸を見てごらん」
「今年は多いわね」
飲人君は驚いた顔で茸を指差している。
「そうじゃないよ、見てごらん、たくさんの茸に包帯が巻いてある。紅天狗茸には首のコルセットがついている」
庭の茸たちに包帯が巻かれていたり、ガーゼがついたりしている。
「なーにそれ、お父さんやったの」
美藻子が私を見た。
飲人君が言った。
「茸の手入れをしたんですね、それにしても、こんな小さなものに、包帯を巻いたり、コルセットを作ったり、ガーゼを切ってテープで留めたり、こんな細かなこと僕にはできないですね、さすが外科の名医と言われていただけありますね、九十近くなって、こんなに細かなことができるなんて信じられませんよ」
「あなたは内科だから無理ね」
美藻子が飲人君に言っている。
そう、私は引退して、もうこの病院は外科ではなく、義理の息子、飲人君がやっている内科である。ふっとそれを思い出した。
「さあさ、もうすぐ診察が始まるし、朝ご飯を召し上がりなさいな」
藻衣子がダイニングルームにみんなを誘った。
私は思い出して言った。
「昨日、出前を頼んだら、お金を取らなかった。出前のお兄ちゃんが手を擦りむいていたんで、消毒してやったんだ」
「あら、出かける前に、三朝庵に寄って天丼たのんどいたのよ、おつまみも、お金はそのとき払ったのよ」
藻衣子が言った。
みんながダイニングルームに行った後、私は庭に降りて茸を見た。
茸たちは包帯を巻いて元気よく、私に微笑んでいた。
茸名医
私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県富士見町 2016-8-1


