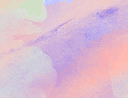魔女と少年
「魔女さま! もうご飯、できていますよ」
そう言って、ヘイムがベットの上で丸くなっているわたしの耳元で、フライパンの底におたまを打ちつける。なんとも古典的な起こし方だが、わたしを起こすにはこれが一番だと彼は知っているのだ。
わたしがむくりと身体を起こすと、ほらほら、とヘイムがわたしの手首をつかんでダイニングテーブルまでひっぱる。わたしを椅子に座らせると彼は向かいの席に座り、いただきます、と手を合わせた。
「きょうは魔女さまが好きなコーンスープをつくりましたよ」
おかわりもありますからね、とトーストをかじりながらヘイムが言う。
彼はヘイム=アーベントロート。十五歳。十年前、森の入り口に捨てられていたのをわたしが拾った。
わたしは人間なんて大嫌いだからそのまま放っておこうとしたのに、わたしの使い魔が、彼の両親は貧乏だったのだ、と言った。もうひとり、ヨルンという息子がいて、弟のヘイムを育てるほどの余力がなかった、と。そんなことを言われたからといって心変わりするようなわたしではなかったはずなのに、気付いたら腕にその子供を抱いていた。
「わたしの森の入り口にこんなものを捨てられて困っているだけだわ」
わたしは誰にともなくそんな言い訳をした。
「いつか大鍋で煮て食べてやるんだから。せめてもっとおいしそうな身体になりなさいな」
そう言って、三食欠かさず食べさせた。
「ああもう、そんな汚い服は脱いで、お風呂に入って、それでこれを着なさい」
そう言って、毎日風呂に入れて、きれいな服をあたえた。
「わたしがいなくてもご飯くらいはつくれるようになりなさいね」
そう言って、料理を教えた。
そうしているうちに十年が経ち、やわらかな栗色の髪と、ブルーグレーの瞳をもった、心の優しい少年に成長した。今では料理も洗濯も掃除もヘイムがしてくれるようになってしまった。
「魔女さま、手が止まっていますよ。あまり食欲がありませんか?」
心配そうなヘイムの声で我に返る。顔を上げると、眉を下げてこちらを見ていた彼と目が合う。なんでもないわ、と首を振ると、ほんとうに具合が悪いなら言ってくださいね、と念を押された。
別に具合が悪いわけではなかった。悩んでいたのだ。
ヘイムはこのままここにいていいのだろうか?
ヘイムが十歳になったあたりから、漠然と抱いていた思い。
言葉や文字の読み書き、簡単な計算、それから料理。それらはわたしが教えた。でもほんとうならば、ヘイムの年頃の子どもたちは学校に行って学び、友だちをつくり、遊んだり、恋をして、大人になっていく。それなのに、ヘイムにとっての「世界」はわたしだけなのだ。それでほんとうにいいのだろうか? ヘイムの「世界」を狭めていいのだろうか?
「ヘイム、学校に行きたいとか思わないの?」
「学校? 生きていくうえで必要なことは全て魔女さまが教えてくれました。行く必要性を感じません」
「そういうことではなくて……」
ヘイムの返事にわたしは閉口してしまう。わたしが「世界」を狭める、のではなく、もうすでに狭めてしまっていたことに気づいたからだ。
ヘイムはもうすでに、「外の世界」への興味を失っていた。
彼は、黙り込んだわたしを不思議そうに見ていた。
「魔女さま、『魔女集会』の準備はもう済んでいるのですか?」
夕食後、洗い物をして濡れた手を拭きながら、ヘイムがそんなことを聞いてきた。
『魔女集会』とは、年に一度開かれる魔女たちの集まりのことだ。ベテラン魔女から新米魔女まで、魔女同士の交流や、これからの魔女界の在り方、決まりごとの確認をするための会である。毎年集まる場所が変わり、今年の開催地はわたしが住む、このリュッケルンの森だった。開催地になった森に住む魔女は、食事やスイーツ、飲み物の準備をはじめ、魔女たちが泊まるための寝る場所やお風呂などの準備をしなくてはならない。ヘイムの言う準備、とはそれらのことだろう。
「寝る場所とかお風呂は魔法でなんとでもなるけど、お料理はどうしようかしらね」
魔女集会で出す料理には魔法を使わない、というのが、『魔女集会』始まって以来の暗黙の了解となっていた。
「エルハ―ヴの森から紅茶を仕入れたらどうですか? この季節ですから、ブラックティーのチョコレートチャイとか」
エルハ―ヴの森に住んでいる魔女は紅茶に詳しいことで有名で、魔女自ら紅茶の茶葉を扱う店を営んでいる。チョコレートチャイとは、ほんのりチョコレートのような風味のある紅茶の種類だ。ヘイムの提案にわたしは頷く。
「いいわね。それじゃあ伝書鳩を飛ばさなくちゃね」
それから寝るまでの間、『魔女集会』に出すための料理についての話で盛り上がった。今ではヘイムのほうがわたしより料理が上手で、『魔女集会』当日もヘイムが料理をつくることになった。
『魔女集会』当日、陽が沈んで、ぞくぞくと古今東西の魔女たちが集まってきた。新米魔女のサリーの箒の操縦が危なっかしくて、ヘイムが腕によりをかけてつくった料理が並んだテーブルに突っ込みそうになったこと以外は、なんのトラブルもない。
食事は立食パーティ式だ。それぞれの箒を、わたしが魔法で作り出した箒置き場に置いた魔女から、皿を手に取り、好きな料理を取り、好きな飲み物を飲む。ヘイムの提案だったチョコレートチャイは好評だった。
「あんなに大量の注文、なにに使うのかしらと思ってたらこのためだったのね」
エルハ―ヴの森の魔女、アリッサはわたしのところに来てそう言った。その節はどうも、とわたしも笑みを返す。
招待状を「参加」で返してきた魔女たちが全員集まったところで、『魔女集会』の代表でベテラン魔女、アンダルシアの森に住むベロニカがみんなの前に立って咳ばらいをしたとき、パンパンッと、銃声が聞こえた。猟銃の音だ。ザワッと、魔女たちにどよめきが広がる。ガサガサと茂みをかきわけ現れ
たのは、数十人にも及ぶ人間の男たちだった。
「やっとこの日が来た。今夜、この森に世界中の魔女たちが集まると聞いて、この日しかないと思った。十年前、アーベントロート家の息子、ヘイムを攫い、夫婦を悲しみの淵に立たせた魔女もここにいるのだろう」
先頭を歩いていた男がそう言うと、後ろの男たちは一斉に銃を構えた。
なにかがおかしい。
ヘイムは捨てられたのだ。わたしはかわいそうだと思って拾って育ててきた。攫った? なにかの間違い……
ハッとして、わたしはヘイムがいるほうに目を向けた。ヘイムは、真っ青な顔でわたしの目を見ていた。わたしの目を見て、小さく首を振った。
「人間を脅かしてきた魔女ども! とっつかまえて火炙りにしてくれる!」
その声とともに、男たちが魔女の集団に突進してくるように走り出した。
銃声と悲鳴が響き渡る。
銃で撃たれたぐらいで魔女は死なないが、火炙り――肉体を失ったらそれで終わりだ。魔女たちは、次々に箒を掴んで空に逃げようとするが、撃ち落とされる者、箒置き場にたどり着く前に捕まえられて縄で拘束される者――。 つい少し前まで和気あいあいと食事を楽しんでいた場所が、惨劇の場へと様変わりした。
わたしはヘイムのほうへと駆け寄る。ヘイムだけは守らなくては。ヘイムは、ヘイムは、わたしの息子同然なのだ。
最初はめんどうなものを拾ったと思った。魔女を毛嫌いし、迫害してきた人間の子どもなど――そう思っていたのに。それなのに、手を差し伸べてしまった。生きる上で必要なことを教えたり、彼の「世界」についてらしくもなく悩んだり。今まで、こんなことなかった。
今、ヘイムを失うかもしれない。そうなって初めて、彼がいかに自分の中で大切なものになっていたか気づいた。
恋じゃない。愛、だ。
五百年近く生きてきて、初めての感情。
「ヘイム!」
彼のもとにたどり着くと、きつく抱きしめる。
「ヘイム、わたしはお前のことをさらっ――」
「魔女さま!」
わたしが言いかけたのと、銃声と、ヘイムの声が重なる。ヘイムが、わたしの腕の中から抜ける。いつの間にわたしより背が高くなった彼。視界が暗くなる。わたしに覆いかぶさった彼の身体に、ドンッ、という衝撃。そして、その衝撃が三発続いた。
音が、消えた。
銃声も、悲鳴も、なにもかも聞こえなくなって、自分の心臓と、ヘイムの心臓の音だけが、聞こえる。
「まじょ、さ、ま……へいき、ですか」
荒い呼吸音とともに、苦しそうな声が聞こえる。
「わたしは、平気、だけど……ヘイム、が……!」
ヘイムの身体を離し、地面に横にする。彼の胸に滲む、血。
「いいん、です。魔女さまが、ぼくを、ひろって、くれた、あの日、から……ぼく、は、まじょ、さまを、まも、る、ため、だけ、に――」
僕を攫った、とは言わなかったヘイムに、涙が頬を伝った。
「まじょさま、だいすき、でしたよ――」
ヘイムが、少しだけ笑って、目を閉じた。あの、綺麗なブルーグレーを見ることはもうできないだろう。
「馬鹿な子。わたしは撃たれたぐらいじゃ死なないのに――」
わたしは泣きながら、笑いながら、彼の頬を撫でた。
誰かが森に火をつけたのだろう。視界がオレンジ色に染まる。
「わたしだって、だいすきよ、ヘイム」
わたしは、ヘイムを抱きしめたまま、目を閉じた。
オレンジ色の炎が、頬を撫でた。
魔女と少年
Twitterではやっていた、魔女集会で会いましょう、というタグに触発されて書きました。
もしかしたら、こんなような話のイラストを描いた方がもういらっしゃるかもしれません。