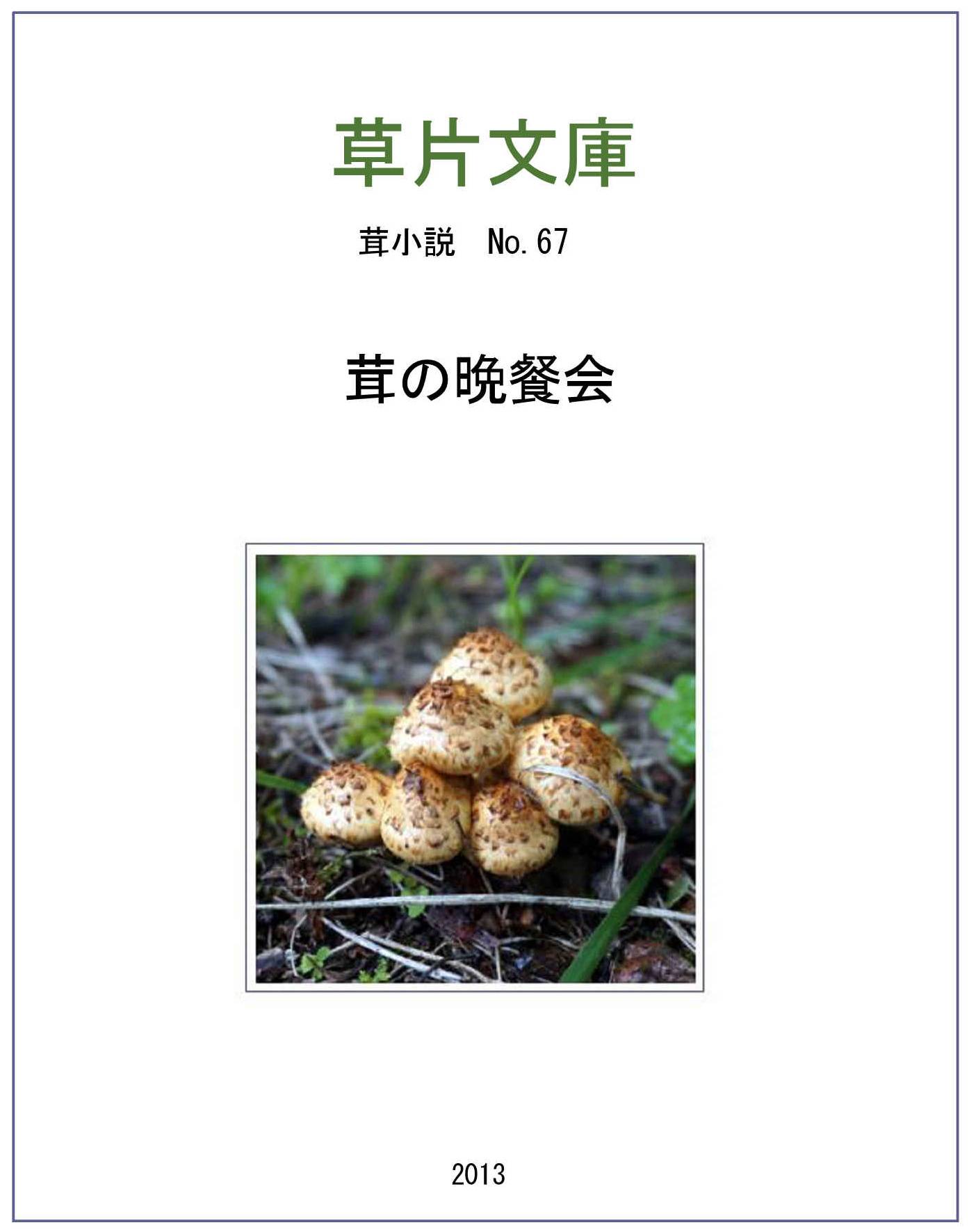
茸の晩餐会
大山から丹沢方面にいく道がある。そこをしばらく行くと、林の中にきれいな水の湧いているところがある。幾種類もの木々に囲まれ、泉の畔には何種類かの羊歯(しだ)が青々と瑞々しく生えている。一匹のまだ子供の山椒魚が泉から這い出して、のそのそと、羊歯の間に入っていく。
青年は泉の縁でかがむと水の中をのぞいた。青い空と周りの木々が水面に映り、水中がよく見えなかった。角度を変えて反射しないところを選んで中をのぞいたが、なぜか真っ黒でなにも見ることができない。水の底にはきれいな魚が泳ぎ、水草が湧き出る水に揺れていることだろうと期待したのであったが、それは外れた。彼は写真機をかまえると、泉を中心にそのあたりの写真を撮った。しばらくたたずんでいたが、その後、もときた道を戻っていった。
水底では赤い茸と白い茸がゆらゆら揺られながら話をしていた。
「ほほ、あの人間、いっちゃった、もっとしつっこくのぞいたらおちょくろうと思ってたのに」
「ありゃだめだよ、バカまじめのちんちろりんだ」
「なあに、それ」
「知っていることしか知らないんだ」
「そりゃそうじゃないの」
「いやさ、知らないことも、想像力で補って、知っちまうのが人間てものだ」
「そうね、そうじゃない人間もいるのね」
「昔は人間の頭は良かった、我々も頼もしい生き物が出てきたものだと思ったものだよ、だがな、人間は化けることを忘れた動物だ」
「そうね、能力が狭くなった生き物ね、でも、想像力が強くなったと思ったのに」
「今の人間は退化の一途をたどっているのだ」
「そう、どう、遊びに行く」
「そうしようか」
水の底でゆらゆらしていた茸は大山椒魚に姿を戻して、泉から陸に上がった。羊歯が大きく揺れ、頭の大きな山椒魚が二匹顔を出した。
山椒魚は沢をくだり、岩魚(いわな)が沢山いるところに向かった。腹が減ったのさ。
大山椒魚がでていった泉の底では、小さな茸が十本ほどゆらゆら揺れている。
茶色の茸が揺れながら周りの茸に言った。
「どうだい、おれたちは町にでも出てみないかい」
「町に行ってどうするね」
「わたしはいやよ、あんな野蛮なところ」
「旨いものを探してこようよ、誰が一番旨いものを持ってくるか、競争しよう」
「人間の食うものから選ぶのか」
「町を散歩するだけじゃつまらないじゃないか」
「あいつ等、何でも食っちまう」
「ああ、だが、他の動物と違うのは、料理ってことをする、生で喰わずに、いろいろなものを混ぜて食い物を作る」
「ああ、あの能力はたいしたものだ、我々にはまねができん」
「そうだな、だが、我々は自然の中で一番旨いものは何か感じることができる、水の味なんぞは、人間にはわかるまいよ」
「その通りだ、それが一番だな」
「ともかく、人間が料理したものを持ってくることにしよう」
遊び盛りの若い茸たちだ。
彼らは若い山椒魚に戻って岸に這い上がった。
水底では少し萎びかけた大きな赤い茸が三個、ゆらゆら揺れながら話をしている。
「おいは、明日、三百歳になる」
「わしゃ、去年三百になった」
「私は、来月に二百八十八になるのよ」
「生まれた頃は、水がもっと美味しかったなあ」
「そうじゃな、だが、今でもこの泉の水が一番うまいし、香りもよい、だから外に出たくない」
「たしかに、長老の言われる通りじゃ」
「私も出たくない」
「だが、あの若い者たちが言っていた、人間が料理した食べ物とはなんであろうかのう」
「人間は火を使えるのじゃ、だから、焼いたり、煮たり、味を変えて食べ物を作る」
「どんな味でしょうな」
「私たちも行ってみましょうか」
「わしゃ、面倒臭い、若い連中が持ってきた物のご相伴にあずかろうじゃないか」
「そうね、それがいいわ」
そこに、とてつもなく大きな傘を持った黒い茸が、ふわりふわりと水中をただよって、赤い茸たちのところにやってきた。水母みたいな泳ぎ方だ。
「おー、有名なお方がきた」
「この方はどなた」
老女の茸が尋ねた。一番年寄りの老翁が答えた。
「最近この泉に来た、本で有名になった方じゃ」
「どんな」
「何十年か前じゃが、この老人は岩の間に閉じこめられていてな」
「そりゃ大変でしたね」
黒い茸が老人たちの話を聞いて傘を横に振った。
「いやいや、つい、怠けてしまいましてな、うまい魚を鱈腹食らって穴の中で寝ていたら、いつの間にか頭が大きくなっちまい、外に出ることができなくなったんですわ。背中に緑色の苔が生えるのはやなものでしたが、のんびりしておりましたじゃ」
「それで、食べ物はどうなさったの」
「それが、向こうからやってきてくれましてな、海老はくるは、蛙はくるは、みんな食っちまいました。それでますますからだが大きくなって、外に出られなくなりましたな」
「茸にお戻りになったら出られたでしょうに」
「ところが、ほれ、ご覧の通り、傘もでっかくなってだめでしたな」
「それだけではないんだよ、この御仁は作家の目にとまり、小説の主人公にされたんだよ」
「はは、そりゃあ、そうですがね、人間の世界のことで、私の境遇はかわりませんでしたよ」
「どうしてその作家は御仁のことを知ったのかね」
「その作家は釣りが好きで、鱒を釣りにきて、私を見つけましてね、どうするんじゃ、などと声をかけていきましたよ、ちょっと岩をどけてくれりゃいいものを、そう思いましたな、そのときは」
老女の茸が尋ねた。
「どうやって出てこられましたの」
「それが、その作家が年をとるにつれ、私のことを思いだして可哀想になってきたとみえて、小説の結末を変えたのです。そりゃあ読者や他の作家から非難轟々でしたよ、なかなか感性の強い作家だったのでしょうな、自分がその立場になったらやりきれないと思ったのでしょう、年をとると気が弱くなる」
「年をとって閉所恐怖症になったんじゃないの」
「それもあるかもしれませんな」
「ともかく、その作家が結果を変える気になったことで、私は穴からでられて、ここにたどり着いたのです」
「だけど、小説でそうなったからといって、あなたが穴から出られるわけはないが」
「誰も知らない事実ですが、その年とった作家が、また、私のいるところにきて、震える手で岩をどかすと戻って行きました。最初にそうするべきだったと思ったのでしょう」
「それも小説になりますな」
「人間の世界ならね」
「ところでみなさん、集まってなにをなさってますのかな」
「若い連中が町に行ってましてな、人間の料理を持ってくるのですわ、どの料理がうまいか競うそうです、わしらも人間の料理を食べさせてもらおうと思ってな」
「そりゃあ、おもしろそうだ、仲間にいれてくれまいか」
「もちろんじゃ、おたくはいくつになったかな」
「百五十八歳で」
「いくつから閉じこめられたのじゃ」
「八十八のときでした、二十年間ですな」
「まあ、出られてよかったですの」
年とった茸たちがそんな話をしているとき、町では若い茸から変身した山椒魚たちが、人間たちを気にしながら、どのレストランに入ろうかうろうろしていた。
尾に赤い疣のある山椒魚が変わった匂いが漂ってくる店を見つけた。
「俺はここに入る」
山椒魚はレストランの裏口に回り、戸の隙間から中に入った。ピザ屋である。
釜から出したばかりの焼きたてのピザが皿の上に乗せられている。山椒魚はそれをくわえるとさっと外に出た。
隣の隣はトンカツ屋だ。左目の上に黄色い疣のある山椒魚が、裏口で戸が開くのを待っている猫の後ろにいる。猫は山椒魚に気がついたが、振り向くとふにゃっと笑って、「俺について来い」と言った。
「ありがとうござんす」
山椒魚は猫の後ろに隠れた。
「玉や」という声が聞こえると、裏の戸が開いた。山椒魚もついて入った。玉はご飯のあるところに急いだが、山椒魚は厨房に入った。
台の上に並べてあった揚げあがったトンカツを一枚くわえると、玉のところにいった。山椒魚はくわえたトンカツをひらひら振って見せた。
玉は山椒魚を見ると、うなずいて裏の戸の前に行き、「にゃああ」と大声で鳴いた。電話をしていたトンカツ屋の奥さんが電話の相手に「ちょっと待って」と受話器を脇において、「また出るのかい」と言いながら戸を開けた。
山椒魚は猫に挨拶をすると、急いで外に出た。うしろで、「なんだい、玉、出たいのじゃないのかい」という奥さんの声が聞こえた。
緑色の疣が左手の甲にあるまだ若くて小さな山椒魚は、ドーナツ屋の裏の戸を難なく押して中に入った。荷物を抱えた従業員のために、押して開ける戸になっていたのだ。山椒魚は中に入ると、ドーナッツを尾っぽに通して、尾を立てたまま外に出た。
フライドチキンを取りに入った白い疣が口の脇にある山椒魚は、堂々と裏の戸を尾っぽでたたいた。平べったくなって待っていた、「誰です」という声と共に、戸が開いた。その隙をねらって、するっと中に入った。山椒魚は大きなチキンをくわえ、お店の入り口から出ていった。誰も気がつかなかった。黒い模様入りの大理石の床は山椒魚の模様と良く似ていたからだ。
そば屋に入った足の脇に青い疣のある山椒魚は、店主がそばに入れるために揚げたばかりの大きなエビの天ぷらをくわえると、開いていた裏の出口から外に出た。
赤い疣が尾っぽの背中に三つもある山椒魚は、フランス料理屋にはいった。厨房では色とりどりの野菜やら肉がぐつぐつ煮えていた。ビーフシチューだ。どうやって持っていったらいいんだ。山椒魚はちょっと困った。すると、うまい具合にパックに詰めたシチューがいくつか置いてあるではないか。山椒魚はしめしめとそれをくわえて外に出た。
同じことをした山椒魚がいた。黒い疣が目の下にある山椒魚はカレー屋に入った。ちょっと刺激的で魅力があった。そこで同じ悩みを抱いたのだが、パック入りのカレーが出来上がったのである。そいつをくわえて外に出ると、シチューをくわえた山椒魚と鉢合わせした。町の側溝の中である。お互いにくわえているものを下に置くと、
「似ているが、匂いは似てないね」
「そうだな、俺が持ってきたのはインドだ」
「俺はフランス」
「ヨーロッパの匂いとアジアの匂いだな」
「ああ、こりゃうまそうだ」
と幾ばくかの会話をした後に、再びくわえると一緒に戻っていった。
茶色の疣が体中にある山椒魚は中華料理屋に入った。うまそうなものがたくさんありすぎる、と悩んだ。最後に選んだのは肉饅頭だった。
ほかにも数匹の山椒魚たちが思い思いのレストランに忍び込み、いろいろな料理を盗んできた、いやいただいてきたのである。
このようにして、若い山椒魚たちは、それぞれのぶんどり品を持って、泉に戻ってきた。
泉の近くに大きな倒れた木が一本横たわっていた。
若い山椒魚たちはその上に盗んできた人間の食べ物を並べた。
「みごとなものだ」
「どれもうまそうだな、すこしずつかじってみよう」
一匹が提案し、もう一匹が水の中にいる連中に叫んだ。
「試食会をはじめますよ」
水底で茸になってふらふらしていた年とった山椒魚たちが、姿をもどしてぞろぞろと水辺にあがってきた。
「若い連中が持ってきた人間の料理とやら、面白そうですな」
「ほんと、はじめて食べるものばかりだもの」
年寄りたちが若い山椒魚の周りに集まった。
「おじいさん、おばあさん、どうぞ、前のほうに」
若い山椒魚たちは年をとった山椒魚を倒木の前に案内した。
一匹の若い山椒魚が木の上に並べられた人間の料理を説明した。
「端からいきますが、最初にピザ、イタリアの料理、トンカツ、日本の料理、ドーナッツ、アメリカ料理、フライドチキン、アメリカ料理、ビーフシチュー、フランス料理、カレー、インドと日本、肉饅頭、中国料理、アインスバイン、ドイツ料理、ボルシチ、ロシア料理、ハラーススープとパプリカチキン、ハンガリー料理、キムチ、韓国料理、アイラのシングルモルトウイスキー、イギリス、こりゃ料理じゃないな、あとは、いくつかの日本の家庭料理であります」
「ずいぶん、いろいろ盗ってきたものだ、大したものじゃ」
年とった山椒魚は驚いた。
「なんと、酒まで、あります」
「酒ってえのは一度飲んでみたいと思ってたんですよ」
長い間岩の間に閉じこめられていた山椒魚が言った。さらに続けた。
「岩の間に何十年もいたのだが、たまに、鯰がきてくれて、猿が作った酒のことを話してくれたものよ、飲むと気持ちがよくなって、よく眠れるそうな、岩の間から出られないなら、せめて、そういう薬があるといいと思ったものよ、しかも美味いと話をしておった」
「だが、若いのが持ってきたのは異国のもので、かなり強いらしい」
「ほう」
若い山椒魚が声を上げた。
「それでは、みなさん、どうぞ自由にお召し上がりください。みなが口にすることができるよう、少しずつ味わっていただきたいと思います」
「若い連中もばかになりませんな、大したもんだ」
年よりの山椒魚も、若い山椒魚も料理を口に入れた。
「このウイスキーって奴はききますな」
「じゃが、旨いな」
「わしゃ、ハラーススープが気に入った、鯉をこんな風に料理するたあ、人間も大したもんだ」
「なかなか、チーズがいい、ピザが気にいりましたぞ」
「牛の肉をこんなに煮込んで柔らかく美味くするとは大したものだ、ビーフとは外国の言葉で牛ということを始めて知りましたぞ」
「私は、エビフライ、エビの生もいいけど、こうするのも美味しいわ」
「泉の手長エビをとっつかまえて人間にたのんだらどうだ」
「あのばあさん手長エビはかわいそうよ、なついているじゃない」
「はは、冗談さ」
「豚肉も旨いよ、塩うでにしたやつ」
「ああ、アイスバインね、ドイツって国のやつだ」
好きな料理のことをいいながら、年寄りと若者が一緒になって楽しいひと時を過ごしていた。
宴たけなわなとき、がさがさと草をかき分ける音がして、二人の人間が現れた。山椒魚たちはあわてて茸に変身した。
「あら、これみて、倒れた木の上に、いろいろな食べ物が置いてあるわ」
「そうだな、おかしいな、どれも食べかけだ」
「ウイスキーまであるわよ、あなたの好きな、シングルモルト、しかも、アイラよ」
「そうだね、誰かここで宴会でもしていたのかな」
「食べかけということは、何かあって、急に席を立ったのね」
「熊でも出たのかな」
「このあたりに熊がいるとは聞いたことがないわ」
「しかし、この料理はみな少しずつだ、それに、世界の料理だよ」
「ほんと世界の料理の博覧会」
「鴉(からす)がくわえてきたのかな」
「みて、木の周りに、きれいな茸たちが生えている」
「綺麗だね、写真を撮っておこう、茸が宴会を開いていたように見えて面白い」
彼は一眼レフをカバンから取り出して、いろいろな角度から写真を撮った。
「わたしも撮っておこう」
彼女はデジタルカメラのシャーターを押した。
「この写真、展覧会に出すと、賞をもらえるかもしれないよ、茸の晩餐会という題を付けよう」
「そうね、だけど、私たちが食べ物を並べて撮影したと言われるわね」
「それだっていいさ、茸は自然だから、それだけだって面白いよ」
「それにしてもきれいな茸ね、どう、採っていって、名前を調べない」
「うん、その前に、料理を片づけて茸だけの写真を撮っておこう」
「そうね、このゴミ、ほおったまま帰れないわね」
「料理はまとめてどこかに捨てても土になるよ、パックは持って帰ろう」
「ええ」
彼らは料理を林の中に捨てた。ウイスキーも泉の中に捨ててしまった。
そのあと写真を撮ると、ビニール袋を出して茸をみんなもぎとって入れた。
女性は袋の中の茸を見た。
「あれ、みんなもう萎れちゃった」
男がのぞいた。
「そうだね、だけどいちおう持って帰ろう」
そう言いながら二人は去って行った。
しばらくたつと、倒れた木の周りからもぎとられた茸がにょきにょきと顔を出した。
茸は大きくなると、再び山椒魚に変わった。
「ほ、あぶなく見られるところでしたな」
「ほんとうに、みなさん、料理は食べましたかな」
「ほとんど味わいました、たまにこういう宴会もいいですね」
「若い人たちに礼を言わなければ」
「人間の料理というのもバカにならんですな」
「そのものの味もいいが、手を加えるのもおつですな」
「虫を捕まえたら、木の実と一緒に食べてみますかな」
「日に干して、乾燥した魚もいいかもしれん」
「我々も食べ物を工夫してみようじゃないか」
「さて、みなさん、そろそろ、泉の底に戻りましょう」
三百歳の山椒魚が言った。
「茸に化ける術を覚えておいてよかったですな」
「ほんとうに、茸だと、ちぎられてしまっても、地下の菌糸は残っていますから、生き返ることができますな」
「そう、それに我々は、切り刻まれても生き返る能力がありますからな、人間がつけた「はんざき」という別名は裂かれてもまた生き返るという意味じゃ、茸になれるからいつまでもいきられるのじゃがな」
「しかし、植物は根子ごと持っていかれてしまえばおしまいだし、昆虫やカエルなどでも同じ、やっぱり土の中に菌糸を張っている茸が一番安心じゃな」
「ほんに、ほんに」
山椒魚たちは泉の底にたどりつくと、また茸に姿を変えて、水中をふらふらと漂っているのだった。
茸の晩餐会
私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県富士見町 2015-9-24


