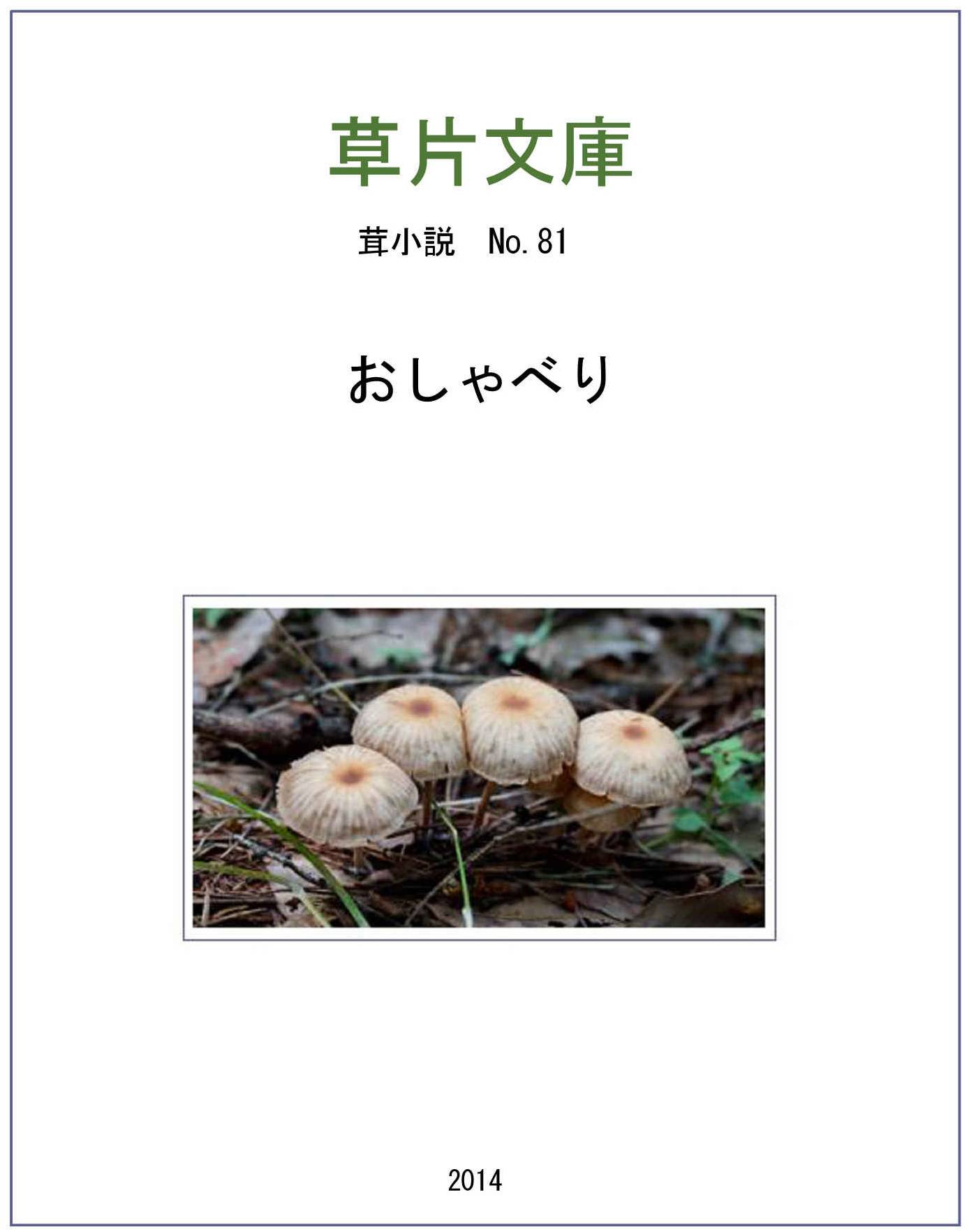
おしゃべり
山歩きをしていて道に迷ってしまった。
ともかく、稜線にでようと上に向かって林の中の道なき道を歩いていると、どこからともなく声が聞こえてきた。
覆い茂った林の下草の中からのようだ。草をかき分けて中をのぞくと、いくつもの茸が輪になっている。
茶色の茸が傘をパクパクさせている。
「北海道からでは大変ですね」
「そうだなあ、じゃが、風に乗れば早いものよ、二日で来たわい」
「それは早い、わたしゃ、九州から一週間かかっちまった」
「北海道はどんな茸がいいですかな、今年は」
「東北と同じじゃよ、舞茸、香茸、そうそう、ずいぶん冬虫夏草のやつが生えよった、なんと千年に一回生えるか生えないかというやつもだよ」
黄色い茸が傘をパクパクさせた。
「なんに生える奴ですかい」
「それがな、北海道にしかいない蝦夷(えぞ)栗鼠(りす)じゃ」
「冬虫夏草は虫に生えるのじゃないんですかい」
「ほとんどは虫じゃがな、ああいうのに生えるのがたまにはいるんじゃ」
「あの肉食茸は嫌いだ」
真っ赤な傘の茸が言った。
「まあ、冬虫夏草に生まれたくて生まれたのじゃないからな、仕方ないさ」
「ところで、なんで生きた栗鼠に入り込むんですかね」
北海道の年寄り茸は答えた。
「実はわしは一度その茸に会ったことがあるのじゃがな、栗鼠につくのではないのだそうだよ、栗鼠のからだの中にいる寄生虫だそうだ」
「それじゃ、やっぱり虫なのですね」
「うむ、じゃが、回虫は昆虫じゃないがな」
「その冬虫夏草はなんという名前ですかい」
「回虫茸じゃ、ずいぶん大きな冬虫夏草でな、人間が知ったら目の色を変えよるだろうよ、あいつを煎じればほとんどの病を治す」
「ふーん、そんな奴がいたんですね」
「九州も面白い奴がでましたよ」
白い傘がしゃべりだした。
「溶岩から生えた真っ黒な茸がいた」
黒い傘が聞き返した。
「黒い茸かい」
白い茸がうなずく。
「ただ、あんたさんと違って、柄のところも真っ黒さ」
「そうか、それで、溶岩たあ、味気のないところに生えたもんだな」
「動物の糞(くそ)に生える奴よりいいでしょう」
「糞の方が栄養があらあ、分解しがいがあるぜ」
「いやな、その黒い茸はな、溶岩に生えて、見る間にその溶岩を砂にしちまうほど貪欲なんだ」
「溶岩のなにを食ってるんだ」
「熱だよ、冷めたばっかりの溶岩に生えて、残りの熱をあっという間に吸い取ってバラバラにしちまうんだ」
「ほーそれはなんていう茸だ」
「マグマ茸、これも火山が爆発したときに、ほんのたまにでるそうだ、話してみるといい奴さ」
「そりゃあ激しいやつだろう」
「そうだよ、胞子が地下の燃えたぎる赤いマグマの中で何千年と生きていて、マグマが外にでて冷えると生えてくるんだ」
「迫力だねえ」
「うーん」
「それでね、その茸を人間が食べると、百人力さ、熱に強くなるし、力はでる」
私は話を聞いているうちに、珍しい茸を探してみる気になってきた。
茸たちは話題を変えていた。
赤い傘が動いた。
「今年はよかったが来年はどうなるだろうねえ」
「関東はあまりよくないだろうね、梅雨に雨が多すぎて、菌が流れちまうだろう」
「北海道は梅雨はないが、雨が多そうだ」
「九州もかなり雨が多いと思う」
「どこも雨が多いんだな」
北海道の茸が言った。
「だがな、それでも、茸がよく生えるところがあるじゃろうな」
「そりゃあ、ありますがな、京都では、鞍馬の山の赤い岩のあたりの松には、ぎょうさんの立派なまったけが生えますな」
「北海道は雲仙岳の麓にいろいろな茸が生えると思うんじゃ」
「秋田は湯沢の奥の小安のあたりだすな」
「九州は珍しく唐津のあたりが良さそうで」
「長野は八ヶ岳の奥に入ったあたりですな」
「だが、珍しい茸は生えないな」
「たしかに、来年は豊作じゃあないから、ほとんどないでしょうな」
「ところがな、おもしろい茸が生えるということを聞いた、天候に左右されない茸でな、地震が引き起こした地滑りの上に生える、地滑茸じゃ、関東に中規模の地震が起きる、そのときこのあたりもかなり揺れる」
「それで、その茸はなにするんじゃ」
「その茸が生えると、土が変わるそうじゃ、そのおかげでほかの茸が大きく育つんじゃ、このあたりは、舞茸もでるし、香茸も、占地もな。それが大きく育つんじゃ」
「ほう、そりゃおもしれえ」
「その滑り茸とやらは、今までにどこかででたことがありますかな」
「神戸、福島、熊本や仙台、大変な地震のあったところは、茸がよくでた。今でもでとる。きっと人知れず地滑り茸が生えておるのじゃろう」
私はそんな話を聞いて、来年は北海道や九州に行こうと決心をした。
私は上を目指してまた歩いた。
その途中、大きな杉の木の根本に洞があり、またもや話し声が聞こえてきた。
「来年は、阿寒湖におかしな茸が出るそうな」
「なんでやんす」、
「マリモ茸っていうそうで、マリモの中で育って、大きくなると、湖の水面に浮んできて、胞子を撒くのだそうな」
「そんな奴がいるんすか」
「何でも、何十年に一度だそうで、その胞子が光るのだよ、夜にいくつものマリモ茸が水面に浮かんで、マリモ茸が胞子を放つと、波間がきらきらときれいに光ってこの世のものとは思われんそうですよ」
なにがしゃべっているのか祠をのぞくと、暗い中で二つの月夜茸が傘をパクパクさせていた。この山にはおしゃべりな茸がたくさん棲んでいるとみえる。
「人間がその茸を食ったらどうなるね」
「光るんだ」
「どこが」
「体中が光るそうだ、しかも死ぬまで光るんだとさ、阿寒湖の魚がそいつを食って、光っていたそうだ」
「光るというのは俺たちの仲間か」
「いや、どうも、松茸の仲間らしい」
「どうしてマリモなんかから生えるのだろうね」
「阿寒湖のほとりに生えていた赤松に松茸が生えて、そいつが湖に落ちたそうだ、そうしたら、マリモの中にはまっちまって、体質が変わったらしい」
「マリモ茸は松茸の匂いがするのかい」
「するらしいよ」
私はそこまで聴いて上に向かった。
しばらく登ると、木々の中から空がちらちら見えるようになってきた、稜線にでるにはあと少しのようである。そのとき足元の大きな羊歯(しだ)の中から声が聞こえた。
「ねええ、名古屋の犬山城の庭内に変な茸が生えているそうよ」
「なあに、それ」
「透き通った茸だそうよ」
「どうして透明になったの」
「なんでも、何百年も生えたままだったからだそうだよ、風に晒されているうちに色がとんで、透き通ったそうなの、水晶茸っていうそうよ」
「なんの仲間なの」
「あたいたちと同じなのよ」
私は羊歯の下をのぞいてみた。二つの真っ赤な玉子茸が話をしていた。
「それで、人間が食べたらどうなるの」
「透き通るのよ」
「大変、透明人間になるの」
「ううん、皮膚や脂肪が透き通るだけだから、体の内臓が見える人間になるの」
「うああ、気味が悪い」
私はそこを後にしようと足をあげた。
玉子茸が言った。
「あれ、今、私たちの話、人間が聞いていたようよ」
「迷い込んだのかしら、この山には人間は入れないはずなのに」
「なんとかしないと」
「茸山の主に報告しておこう」
「そうね」
私は茸の話を聴きながらそこを離れた。ちょっと歩くと山の上にでた。予定より一つ東寄りの山の中を歩いてきてしまったようだ。だが、上から見ると、帰り道がだいたいわかる。大したずれではない。少し歩いてくと予定の道に戻った。ほっとして登ってくる途中の林の中の茸のおしゃべりを思い出した。茸が話をするはずはないし、幻覚でも見たのだろうか。そのときは不思議なことと感じなかったのはなぜだろう。茸が話していた回虫茸、マグマ茸、地滑り茸、マリモ茸、水晶茸、どれも話としてはとてもおもしろい。そんな茸が本当にあったら大変なことである。
そこで今さ迷ってきた林を振り返ると、赤っぽい煙が立ち上りはじめている。
奇妙な匂いもただよってきた。何が起きているのだろう。
見てみたい。そう思うと矢も盾もたまらず、もう一度その林に戻った。煙がたなびくところには、人の大きさほどもある、どでかい紅い茸から赤い胞子が流れ出ていた。
風に乗って私の方に胞子が飛んで来た。巻き込まれる。逃げようと思ったときはすでに遅く、胞子に取り巻かれた私は、茸たちの歌声に包まれてしまった。
色とりどりの茸が目の前で踊りはじめた。私の体が勝手に動く。茸の中に入って踊り始めた。私の体に茸がぶつかる。柔らかいビロードのような、アルパカの毛のような、猫の毛のような、ふんわりして、あまりにも心地よい感触だ。二つの茸に挟まれたときには、そのまま天にまで昇るような心地よさに気が遠くなりそうであった。
今度は黒い茸の頭が私の顔に押しつけられた。唇に茸の頭が触れると、柔らかい女性の唇が押しつけられたような快感が体に走った。踊りながら茸の中を浮遊していくと、いつの間にか茸たちの傘の上で横たわっていた。茸たちが私を持ち上げて、踊っている。
そのうち、頭の隅に真っ赤な光が走ったかと思うと、あまりの気持ちのよさに、気が遠くなってしまった。
しばらくして目を開けると、横たわっている私の周りに茸たちが立ち尽して、私を見下ろしていた。
「生きてる」
白い茸の傘が動いた。
「まだ生きていた」
別の茸がそう言った。
「生きていちゃあまずかろう」
赤い茸が他の茸にきいている。
「大丈夫だ、もう脳がいかれている」
「それじゃ、ほっとくか」
「いいだろう」
私の意識はふたたび遠のいていく。
どのくらい経ったかわからない。いきなり私の目が開いた。顔の上には大きな羊歯が覆い被さっている。林の下草の中で倒れているようだ。体をおこすと、脇に大きなしなびた茸が倒れているのが目に入った。この茸が赤い胞子をだしていたことを思い出した。
やっとの思いで立ち上がると、その茸をむしり取り、背中のザックに入れた。足がふらふらするが、何とか、歩くことができた。
ゆっくりであったが、麓までたどり着くことができた。
麓には救急車とパトカーが来ている。何かあったのかと、その脇を通り抜けようとしたとき、警察官が気がついて、○○さんではないですかと私の名前を呼んだ。
私がうなずくと、警察官が大丈夫ですかと聞いてきた。
「はい」と声を出したつもりであるが、声は出ず、ただうなずいていた。
救急車から救急隊員が私に毛布を持ってきてかけてくれた。私はそのまま救急車につれていかれた。
警察官も一人同乗して病院に運ばれた。
いろいろな検査をされ、点滴の管をつけたまま病室に運ばれた。
警察官が医者に言っている。
「質問をしていいでしょうか」
「短くならかまいませんが、言葉が出ないようです、一週間なにも食べていなかったようです、長い質問はもう少し回復してからの方がよいと思います」
「はい」
警察官は私の方に向いて「これはあなたのですか」と手に持っていたザックを持ち上げた。青いザックは自分のものであったのでうなずいた。
「中に入っている、この茸もそうですね」と聞いたので、うなずいた。
「この茸を採りに山に入ったのですか」
私はうなずいた。それは大きな間違いであることに後で気がつくことになる。山でその茸を採ったかという単純な質問であると思い、勘違いしてうなずいたのである。
警察官が、医師と看護婦に、なにやら確認をしていた。
それから私は警察病院に回された。頭がはっきりしないし、足がガクガクして歩くことがぎごちない。言葉は少しだが口に出すことができるようになった。
警察官の質問に少しは答えられた。
「山でどのようなことをしたか話せますか」
私は何とか答えた。
「茸が珍しい茸の話をしていたのを聞きました」
「どのような珍しい茸ですか」
「マグマに生える茸や、食べると体が透明になる茸や、いろいろありました」
「あなたは、その茸と話をしたのですか」
「いや、茸が話をしているのを聞いただけです」
そんな会話を一日三十分ほど毎日行っている。
足がかなりしっかりしてくると、テレビのある休憩所に行くことが許された。テレビではワイドショウをやっていた。二人組の有名な音楽家の一人が覚醒剤常習で逮捕されたことをなにやら詳しく解説している。話のきりがついたところで、女性のアナウンサーがもう一つ薬の話題があると切り出した。するとぼやけた顔写真が出てきて、とある大学の物理学の教授が、山に幻覚茸を探しに行き、一週間行方をくらまし、珍しい幻覚茸を持って、山から下りてきたというものであった。それだけでなく、本人の血液中からは多量の幻覚茸の成分が検出されたということであった。新しい物質のようで、一週間その教授はその茸を服用していたようだと説明している。
警察の調べでは、その教授は幻覚茸を見つけるために山に行ったと言っているということであった。幻覚剤などが一般の人にも浸透してきていることの警鐘を発してその番組は終わった。
私はため息をついた。これをどのように収拾したらいいか、これから考えなければならない。といっても茸が話をするなどと言ったことは不用意なことであった。明らかに幻覚症状だ。わざわざそのような茸を探しに行ったのではないことをなんとか納得してもらおう。調べてもらえれば、今まで、薬を使用したことなどないことからもわかるだろう。あの茸の胞子を吸ったことは認めて、はじめてのちょっとした出来心ぐらいに考えてもらい、情状酌量にしてもらうのがよいかもしれない。
そういうことで、流れに任せることにした。
これは、きっと茸たちが私に口止めをしたのである。大学を辞職して不思議な茸を探す旅に出るのもいいだろう。もし見つかれば身の証にもなる。
おしゃべり
私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県茅野市 2016-8-3


