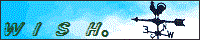
WISH。
それはふとした瞬間だった。
悩み多き青春。すべてのものに意味はある。
プロローグ
中田歩(なかたあゆむ)は朝靄が煙るホームで一人、電車が来るのを待っていた。
引っ掻き傷が出来た顔が、少し痛んでいる。
酒を飲まない父親の光彦が、珍しく酔って帰って来たのは、昨晩のことだった。
ノックもせずに光彦は歩の部屋に入ってくるなり、手にしていた封筒を押し付けてきたのだった。
「何?」
訝る歩に光彦は、行き成り捲し立てはじめた。
「つべこべ言わず、その会社に行け」
「は?」
「うちの会社の取引先だ。お前を欲しいと言ってくれている。悪い話じゃない。給料もかなり良い条件で面倒見てくれるそうだ」
「パパ、何を言っているの? 俺言ったよね。もう野球はやらないって」
「野球しか能のないお前が、何が出来るって言うんだ。良いから黙って大人の言うことを聞きなさい」
売り言葉に買い言葉だった。
埒が明かない口論に嫌気がさし、部屋から出て行こうとする歩は、肩を掴まれ、反射的に光彦を突き倒す。
もろく飛ばされてしまった光彦に、歩は軽い衝撃を覚える。
光彦が怒るのも無理もない。歩とて、自分が成し遂げようとしていることが、どれほど愚かなことか分かっている。しかし、どうしても心が納得しないのだ。あの日から。
それは中学生活最後の試合に挑んでいる時だった。
三対0で迎えた最終回。二アウト、ランナー一塁。残すところあと一人のところまでゲームは来ていた。
ケガをしてしまった選手に代わり、バッターボックスに立ったのは、補欠選手。試合経験が少ないのは、様子から伺える。
勝てる。
歩はその姿を見て、確信した。
しかし運命というのは皮肉なもので、残すところ一球で、あっさり打たれてしまった。
信じがたい事実に、肩を落としむせび泣く選手たちに、顧問であり、担任教師だった神津が放った一言が、歩の胸に突き刺さった。
「人生、何が起こるか分からない。だからこそ面白い。だからこそ一日一日を大事に生きなければならない。今日のことを教訓にして、自分に甘んじることなく、明日を生きて欲しい」
なぜ、と聞かれても説明が出来ない感情が、歩を突き動かす。
5歳で野球に目覚め、寝ても覚めても野球一色の人生だった歩である。その甲斐あって、数校からスカウトされている。
モヤモヤが取れないまま、新学期を迎えて居たある日、他愛もない近所の人の一言で、歩は大きく揺れ動かされてしまった。
ヒーローになる。
ばかげていようが何であろうが、そう思ってしまったから仕方がない。
思い立ったら吉日。
歩の性分である。
受験なんてしている場合ではない。何をどうしていのかさえ分からないまま、歩の心は突っ走り始める。進路相談の席で、高校へは進まないとまで、言い出す有様の歩に、母親の君江はどれほど神経を擦り減らされただろう。
一度言い出したら、言うことを聞かない歩である。
野球をやらないとはいえ、勉強をほとんどしてこなかった歩に残された道はただ一つ。野球推薦で高校へ進むしかなかった。
親の思惑通りになり、歩は晴れて高校生になった。
推薦で入った以上、せめて一年生の間だけでも、野球をするしかないと、光彦に言われ、歩は渋々練習に参加していたが、以前のようなやる気は起きてこないままだった。
そんなある日、水道場で歩に声を掛けてきたやつがいた。
「お前、やる気ある?」
がっちりとした体格で、やたら目力ある、中島伸章(なかじまのぶあき)だった。
彼も歩と同じ待遇で、この学校へ入学して来ていた。春休みを返上して、練習に参加させられてきたのも同じである。同級生の中で、一番身近なはずの彼だが、歩はこの中島が苦手だった。
水を出しっ放しでポカンとする歩に、中島は鼻を一回鳴らし、去って行った。余程、歩という存在がお気に召さないらしい。何か言いたげにしては、今のように去って行く。理由を聞くには、あまりに偉大素いると、歩は思う。
常に冷静沈着で、捕手としての才能は抜群の中島。到底足元にも呼ばない、と常日頃から歩は尊敬の眼を向けている相手だった。
急速に二人の距離が縮んだのは、二年生の秋だっただろうか。三年生が引退し、残された下級生の中からの、中島が主将に選抜された。生真面目ゆえに、中島と他の選手たちとの衝突がしばしば起こるようになり、その間に割って入ったのが歩だった。それからだった。なんとなく話をするようになり、気が付けば無二の親友になっていた。三年間、野球を続けるつもりがなかった歩は、中島の巧みな誘導に遭い、甲子園まで連れて行ってもらったのだった。
三年生の秋、歩は晴れて野球から解放されたのだが、ここでまた頭を悩ますことになる。
新たな進路問題だ。
高校入学する条件を鵜呑みにしていた歩としては、何を今更と思うのだが、言葉巧みに歩の説得に当たり始める。
歩の決意は固く、頑なにそれを拒否し続けた。
その結果、普段温厚である光彦が、怒りを顕わにして、歩とぶつかる場面が増えるようになった。
進路問題が片付かないまま、歩は高校を卒業する日を迎えていた。
光彦ともう一週間以上、歩は口を利いていない。
季節はずれの雪があちらこちらに残り、吐く息が白く濁らせる。
浅はか。
そう言われてしまえば、元も子もない。
無謀だ。
そう思われても仕方がない。
沸々と湧いては消えて行く言葉に、歩は顔を顰める。
「お前、何を考えているんだ?」
十月に入り、何かと中島に絡まれる歩は、にやにやするばかりで、本質を話さないままやり過ごしてきていた。
一年生のころから、練習をよく見に来ている人物がいたのは知っている。その人物が、プロ野球関係者というのは、人伝に教えられていた。だが、その人物たちの目的が、自分にあるとは、歩はつい最近まで知らずに過ごしてきた。
ドラフトの話が持ち上がり、盛り上がる大人たちを横目に、歩は黙々と夢の実現させる計画を練っていた。
先立つものが必要。
そう思い、アルバイトをしようとするが、悉く両親の邪魔が入った。
中島の重圧もかなりのもので、日に一度は野球を続けない理由を聞かれ、うんざりさせられていた。
八方塞がりになった歩は、だんだん口数が減り、机へうつ伏して過ごすようになっていった。
必然的な原理である。特別な理由などどこにもない。ただ面倒になっただけ。
卒業するのも危ぶまれた歩だったが、毎日の補修で、何とかこの日を迎えることが出来た。
思い残すことは、中島との関係を修復できないまま、卒業しなければならないことだった。
退屈な式典が終わり、いざ帰ろうとする歩に、女子たちが群がりはじめる。中には男子も交じっていた。
自分の身に何が起こっているのか分からないまま、歩は全速力で、校舎中を逃げ回る羽目に陥ってしまっていた。
そして、歩は校庭に黒ずんだ雪の塊へ身を潜め、脱出の機会を伺う。
開け放った窓から、女子たちの声が漏れ聞こえてくる。
当分帰れそうもない状況に、歩はげんなりと、しゃがみ込む。
諦めの境地に入った歩は、携帯ゲームをやり始めていて、後ろに立つ中島の気配に、全く気が付かずにいた。
「お前さ」
唐突に声を掛けられ、歩は肩をピクリとさせる。
「なかじぃ」
「こうなること、予測できたでしょ?」
笑って誤魔化そうとする歩に、中島は首を振る。
「お前さ、もっと自分を自覚した方が良いと思うぞ」
その言葉に、歩はきょとんとした表情で中島を見返していた。
「お前に、学習するって言葉はないわけ? この三年間で、ラブレータ―何通貰った? バレンタインのチョコ、いくつ貰った? 確か、食いきれなくて、部員全員で手伝ったよな」
「うにゃ、あれは何かの間違いで」
「で?」
「でって。頭の良い、なかじぃなら分かるっしょ」
「分からない」
「またまた。幻想ですよ。幻想。妄想した、恋ってやつですぜ。相手は誰でも良かったたですぜ、旦那」
「あっそ。なら一人で帰りやがれ」
無言のまま踵を返す中島に歩は縋りつく。
「何? 放せよ」
「そう言わず、助けてよ」
「嫌だ」
手を振り払われても必死な形相で歩は中島に泣きつく。
「おお友よ、中島大明神様、どうかこの迷える子羊を助けたまえ」
「アホか。誰が大明神じゃい」
「そんなことを言わず、女子、マジ怖いっす」
わざとらしく瞬く歩をしばし見つめた後、中島はおもむろに口に手を当てた。
それが何を意味しているのか、分かっていない様子の歩に、中島の目が鈍く光る。
「おーい、中田なら」
思いがけない中島の行動に、歩は慌てふためく。
何せ、中島は捕手。声が通りは人一倍である。そんなのに喚かれたら一溜りがない。
歩は慌てて中島の口を塞ぐ。
「プハッ。お前、オレを殺す気か? このくそ力」
むせて涙目になっている中島を見て、歩は笑いをかみ殺しながら言い繋ぐ。
「なかじぃはそんな薄情じゃないって、オレは信じている」
半瞬ほど置く中島に、歩は首を竦めてみせる。
「残念でした。俺は超薄情人間です。では」
この三年間というもの、いつもこんな調子だった。
中島は笑う歩を眩しく見つめる。
掴みどころがなくて、イラつかされたこともあったが、いつの間にか歩のペースに巻き込まれてしまっていた。
あの日もそうだった。
主将になるのは、本当は歩の方だった。
しかし歩はそれを断り、中島を推薦した。
納得できない中島は歩を待ち伏せて、その理由を問い詰めた。
暗がりに見えるバックネット。
わずかな光に照らし出された歩が、凛とした目で中島を見詰める。
「オレじゃあかんでしょ。なかじぃにはオレが持っていないものが、沢山あるっしょ。その太い眉に、分厚い唇。その顔で睨まれたら、従うしかないっしょ」
どこまでも不真面目な歩に、中島は幾度となく腹立ちを覚えた。捕まえたかと思うとするりと抜け出ては、屈託のない笑顔で……。
ハッとした中島は、軽く首を振り自分の思考を戻す。
「なかじぃ?」
手を掴まれ、執拗に瞬きを繰り返す歩を、中島はつい見入ってしまっていた。
「助けろよ」
ふざけて歩に手を掴まれた中島は、顔を強張らせる。
「ぜってい、やだ。何度も言うが俺は薄情なんだ」
「いやいやそんなわけがない。あなた様のような大先生が、私目のような弱者を見捨てるわけがありません。私は、あなた様を信じております」
芝居がかった物言いに中島もつい笑ってしまう。
「お前さ、さっきからなんなわけ? 今日のお前、変だぞ」
「そっか? オレとしてはこの三年間の集大成を、なかじぃに見てもらおうと」
「何の集大成だよ」
「うーんそれは……、細かいことはどうでも良いから、オレを助けてくれるの? くれないの?」
「態度悪っ」
「すいません。すいません。お願いします。この通りです。助けてくれた暁には、中島が言うこと、何でも聞くから、助けて頂戴」
「言いましたね。その言葉、しかと預かった。武士に二言はありませんな」
ニヤッとする中島に歩は慌てて言い直す。
「ああだけど、オレが出来ることだからな。危ねぇ、危ねえ」
額の汗を拭う真似をする歩の頭に、中島は拳骨を落とす。
「おふざけはここまでだ。行くぞ」
中島は歩の首根っこを摘み上げ、自分の前を歩かせる。
二人は人気がない裏門へと出て来ていた。
「なかじぃ、この門って開くの?」
フェンス全体がツタで覆われ、僅かな隙間から見え隠れしている、鉄作の門扉。
歩は神妙な顔をして、中島を見る。
この場所に近づいたものは忽然と姿を消し、二度と戻ってこない。という噂がある。
顔を引きつらせる歩を一瞥した中島は草をかき分け、あっさりフェンスを乗り越えて行ってしまった。
「なかじぃ、無事か?」
中島の返事はすぐに戻ってこなかった。
「なかじぃ?」
歩は足がすくんでしまっていた。
「わっ」
歩が飛び上がる。
「はい、ビビり」
「マジ、そういうの、止めて。心臓停まるかと思った」
「良いから、早く乗り越えて来いよ」
一瞬ためらいを見せた歩だったが、女子たちの声が近づいてきているのに気が付き、慌ててフェンスへ手を掛ける。
「おっと」
ツタが足に絡まり、バランスを崩してしまっていた歩は、中島に受け止められていた。
「悪い」
「いや、大丈夫だ」
ぶっきらぼうに答えた中島は、歩にプイと背を向ける。
「こっちだ。ついて来い」
「なかじい、オレ、重大なこと、思い出しちゃった」
振り返る中島に、歩は頭を掻いて見せる。
「オレ、戻るわ」
中島は、大きなため息を吐く。
「アホか。犬死する気?」
「オレ、犬じゃないぞ。バカにするなよ」
「そういうことじゃなくって、何で今逃げ出してきたところへ、人間である、中田歩君は帰ろうとしているのですか? これで満足ですか?」
「中島君。君の果敢な行動はたたえよう。だがしかし、オレには重大な勤務が残されていることに気が付いたのだよ」
「はは。中田歩君、それを言うなら、任務ではありませんか?」
「そうとも言う」
「で、どのような重大な勤務が残されているというのですか?」
「荷物一式を、教室へ置いてきてしまった。女子たちはそれを人質に、罠を張っていると思われる。だがここで怯んでは男が腐る。命がけの任務になると予想される。中島よ、オレの無事を祈っていてくれ」
呆れた中島は、歩の頭に拳を落とす。
「痛いな。マジ取りに行かないと」
「良いから、早く乗れ」
そこで初めて車が止められていることに気が付いた歩は、改めて中島の顔を見る。
「乗れって?」
「親父から借りてきた」
「マジ?」
「つべこべ言わずに、さっさと乗れ」
後部座席へ押しやられた歩は、有無なしに、頭から中島の着ていたブレザーを被せられてしまう。
「俺が良いって言うまで、身を低くしてか売れていろよ。絶対に見つかるなよ。お前、マジヤバいからな」
「ヤバいって?」
大げさな物言いに、歩は笑って聞き返す。
「だから顔を出すなって。それ被っていろって」
起き上がる歩を見て、中島は顔を顰める。
「嫌だよ。臭いし」
「失礼な。昨日母親が洗濯してくれたし、アイロンまで掛けてきたんだぞ」
「ワァ、母の愛ですな」
「煩い。やっぱ、お前降りろ。助けてやるの、辞めた」
「嘘嘘。本当にごめんなさい。謝ります。って、マジ? なかじぃ、超ありがとう」
足元にごつごつしている物があることに気が付いた歩は、目を輝かし喜ぶ。
「お前、それ持って正門へ行ってみれば? 凄いことになっているから」
「凄いことって?」
キョトンとする歩を見て、中島はやれやれと首を振る。
「お前さ、校長とかに何か言われなかったか?」
そう聞かれた歩は、本当に思い当たらない様子で、中島を見詰め返す。
「ああもう良い。とにかく、姿、隠しとけ」
「了解しました」
本当に理解できているのか怪しい歩だった。
眉を顰めた中島はサングラスを掛け、静かに車を発進させる。
「何だ、あの人だかり」
その声にぎくりとした中島は思わず振り返ると、歩が窓の張り付くように外を覗いていた。
「おいバカ、顔を引っ込めろ」
あっという間に車は囲まれてしまい、中島はクラクションを鳴らし続ける。
知っている顔を見つけ、のんきに手を振り返している歩を見て、中島はがっくり肩を落とす。
「なかじぃなかじぃ。俺たちって有名人ぽくねぇ。良くテレビでこんなのみたことあるよな」
どこまでも能天気な歩に、中島はもはや返す言葉がなかった。
必死でクラクションを鳴らす中島に、歩は身を乗り出しはしゃぐ。
「行け中島。ぶっちぎれ」
「アホ歩。あとで絞め殺してやる」
「止めて。オレ、まだ死にたくないよ」
はしゃぐ歩に、中島は顔を顰める。
「やった。もう誰も追いかけてこないですぜ、旦那。やりましたな」
後ろを振り返り言う歩は、眉を顰め、中島の顔を覗き込む。
「もしかしてなかじぃ、緊張している?」
余裕のない表情で、中島は一点に集中していた。
「煩い。少し黙っていてくれ」
何事かと、歩は首を傾げる。しかしその理由はすぐに分った。
車線変更が迫って来ていた。
伝わってくる緊張感に、歩も真顔に戻る。
「大将、大丈夫ですかい?」
「何とかなる。俺に出来ないことはない。教習所の先生も、センスが良いって褒めてくれていた。焦らず慌てず速やかに。行くぞ。行くぞ」
ハンドルに胸を押し付け、挑む中島の形相を思い出し、歩は口元を緩ます。
「なかじぃすまん。俺何も言わず行くわ」
独り言ちり、歩は入ってきた列車へ乗り込む。
中島との珍道中は、歩にとって大切な思い出になった。
桜が咲くにはまだ早い公園を、二人は無言のまま、歩みを進めて行く。
ふと中島が足を止める。
それに合わせて歩も、のんびりと池へ足を向けていた。
水面に姿を落とす木々を眺め、歩は大きな欠伸をしながら中島を顧みる。
「なかじぃ、今日はありがとうな」
礼を言われ、中島は歩の頭に手を乗せたかと思うと、すぐに池へ目を移す。
「なかじぃ、今日のお礼に、ジュース奢るわ。何が良い?」
「いらん」
不愛想な返事に、歩は眉を寄せる。
「遠慮するなよ」
「ジュースは良いから、お前の本心を俺は聞きたい」
真顔で言われ、歩は戸惑う。
「えっと。本心とは?」
「お前、俺に何か隠し事をしているだろ」
「いや、別に」
顔色を変える歩を見て、中島は小さく笑う。
「もう隠すな。俺なら何を聞かされても大丈夫だから」
「そう言われても」
がっしりと肩を掴まれ、歩は顔を歪ませる。
言うしかない。頭の中でそう分かっていても、なかなか口にすることが出来ない歩である。中島の真剣な眼差しが辛く、歩はつい、目をそらしてしまっていた。
逃げ場がない歩である。
中島の目はみるみる赤くなり、光るものがそこにはあった。
観念をする時なのは、痛いくらい分かっている歩だが、とてもこんな状況で口にすることではない。
「お前、躰のどこか悪いのか?」
男泣きをする中島を見て、歩は申し訳なく思う。
そんな美談なんかではない。話せば怒られるか、笑われる。大いに予想が付く。歩にはその覚悟がない。野球を辞める理由に、無理やりあてがったような節がある。大きく胸を張って言える代物ではないのは、自分がよく知っている。
「俺には隠し事、なしだ。一人で抱え込むな。俺に何ができるか分からないけど、少しくらい力にならせてくれ」
これ以上、話を大きくされては困る、と悟った歩は覚悟を決め、重い口を開く。
「ごめん」
「謝るな。水臭い」
「そうじゃなくて。オレ、どこも悪くない」
「嘘を吐くな」
「吐いていない」
「ずっと静かだったじゃないか。思いつめた顔もしていたし」
「それは親と揉めていて、夜とか眠れていなかったから、ボーってしていただけで」
「いや違うね。唯一得意科目である体育だって、不様な姿見せていたし。怪我でもしているのか、それとも別に躰のどこかに変調があるかのどっちかだ。俺の目を見くびるなよ」
「見くびってなんかいないし。なかじぃ、考え過ぎだよ。マジ寝不足だっただけで、躰、ぴんぴんしているから大丈夫だ」
「健気すぎるお前。だから俺はお前を」
何かを射かけた中島は、顔をそっぽに向かせる。
「なかじぃがそこまで言ってくれるなら、オレ話すけど、笑うなよ」
歩の言葉の意図が理解できない中島だったが、鼻をすすりあげ、頷く。
「絶対笑うよな」
「笑わない」
「絶対」
「絶対」
大きく頷く中島を見て、歩は頭を掻く。
「実はオレ、ヒーローになろうかと思いまして」
半瞬遅れて、中島は聞き直す。
「ヒーローって、今言ったか?」
コクンと頷く歩を見て、中島は眉を顰める。
「そこまでして、隠したいのかお前」
信じようとしない中島に、歩は肩を竦める。
「これがマジなんだな」
「そんな訳、あるか。お前、年棒いくら出すって言われているか知っているか? 億単位だぞ。それを蹴って、ヒーローになるって。いやいや、そんなことがあってはいけない。これは真っ赤な嘘だ。歩は俺に心配を掛けさせないように言っているだけだ。そうだ、お前は、俺にヒーローのように病魔と闘って、復活して見せると言いたいんだな。そうか、それなら理解できるぞ」
「なかじぃ戻って来い。オレ、全然そんなこと言ってないぞ。ただのヒーローになりたいだけだ。話を作るな」
「んな訳がないだろ? そんな理由、誰が認めるか」
胸倉をつかまれ、歩はお道化る。
「もう、決めたことだから」
しばしの沈黙が二人を包んだ。
「風、冷たくなってきたな」
先に口を開いたのは、中島だった。
「帰るか」
肩を竦め、歩が言う。
中島が大きく伸びをして、歩を見たのはその時だった。
「お前って、前から思っていたけど、ウルトラバカだよな」
「何だそれ」
「覚えているか歩。入学したてのころ、選手選抜で確実に選ばれるはずだったお前は、わざとミスを連発した」
「そうだったかな」
「そうなんだよ。お前のせいでレギュラー落ちしそうな先輩に悪いと思って、お前はわざと平凡なフライを落とし、バットを振るタイミングを外した」
「思い過ごしじゃないの。オレ、人が言うほど野球、上手くないですから」
「そうなんだ。お前ってやつはいつもいつも」
「良いから、早く帰ろうぜ」
「歩、お前が何を成し遂げようとしているのか、オレには全く理解できない。けど、これだけは言っておく。何がっても、俺だけはお前の味方だ」
熱く語った中島は、歩を抱きしめる。
「おいなかじぃ、苦しいよ。止めろよ。放せよ」
「いいじゃないか。俺は猛烈に感動をしているんだ。お前ってやつはどこまでもバカで、良い奴過ぎ。絶対お前なら大丈夫。負けるな」
「分かった。分かったから離れろって、人が見ているじゃないか」
「オレは歩が好きだ。大好きだ」
「はいはい」
「お前はどうなんだ。歩」
「はいはい。好きですよ。オレも」
「マジか。だったら俺ら、付き合うか」
「はい?」
冗談交じりに言う中島を、歩はギョッとした顔で突き飛ばす。
「ごめん。そういう趣味は」
半瞬置いた中島が、腹を抱えて笑い始める。
「バカ。俺だってそういう趣味、ねーよ」
「何だよ。ビビらせるなよ。マジ焦った」
「ちょっと、辛気臭くなっちゃったからな、和ましてやろうと思っただけだ。心配するな。俺だって、頼まれたって嫌だわ。でも、友人として、お前を応援するっていうのは、マジな話。ま、精々頑張って、精進をしてくれたまえ。通行人Aになれた暁には、俺に知らせるように」
「通行人Aって……」
「はじめなんて、そんなものでしょ」
「そっか。じゃあめでたく通行人Aになれたその暁には、祝杯を挙げようぞ」
「御意」
心の救いになった一言だった。
東京に近づくにつれ、不安が歩の胸をつぶして行く。
腹の虫に鳴かれ、歩は苦笑する。
出掛けに放り込んできた水を取り出そうとバックを開けた歩は、見覚えのない封筒を見つけ、眉根を寄せる。
中身を見た瞬間、歩の頬を温かいものが伝う。
君江からの手紙だった。
誰にも内緒で家を出たはずなのに、君江にはお見通しだった。
そして、歩はすがすがしい気持ちで、ホームへ降り立っていた。
――通称東京の叔父さん。
倉嶋昇は母の弟で、歩にとって近寄りがたい存在だった。とにかく怖い。の印象が強い。光彦と同じような眼鏡を掛けているのにも拘らず、醸し出す雰囲気はまるで違っていた。あの眼で見られるたび、どれだけ君江の後ろで震えたことか……。
しかし、そんなことを言っている場合ではないのだ。
無駄な抵抗は、重々承知の上。
歩は見つけたコンビニへと入って行く。
まっすぐ昇の家へ向かう気になれない歩は、その足で近くの公園へと入って行く。
地元ではまだ咲いていなかった桜が、池へ向かって枝を伸ばしている姿が、ユラユラと水面に映し出される中、一羽のカルガモが気持ち良さそうに泳いで行く。
不意に中島の顔が浮かび、歩は苦笑いをする。
最後の最後まで、中島は誤解をしたままだった。
また、会うことはあるのだろうか?
感傷に浸っていた歩は、羽音に気が付き足元に目をやる。
いつの間にか、ハトが集まり始めているのに気が付いた歩は目を細める。
自分が投げるえさに、群がるハトたち。
面白くて仕方がなかった歩だったが、突然見知らぬ女性に声を掛けられ、目を見開く。
「あなた、あの看板が見えないの?」
歩は言われた方へ目をやるが、取り立ててそれらしいものは見当たらなかった。
「公園の入り口に、看板が出ていたでしょ?」
言葉が微妙に替えられ、歩は眉根を寄せる。
「ハトに餌を上げないでください。って書いてあったでしょ?」
きっぱり言い切られて、歩はぎこちなく微笑む。
それだけ言うためにと、来た道を戻って行く女性を眺めながら思う。
しかし、東京はすごいと、次の瞬間唸る。
うわさでは聞いていた。
多少、何があっても平気なつもりでいたが、あの奇抜な服装には目を点にさせられてしまう、歩だった。
――そして、その30分後、歩は神妙な顔つきで、倉嶋家の前へ立っていた。
大きく深呼吸して、伸ばす指が震える。
チャイムが家の中でなっているのが、やたら大きく聞こえ、歩の心臓が大きく脈打つ。
待つこと数秒。
てっきり会社へ行ってしまったと思っていた昇に出て来られ、歩は顔を引きつらせる。
挨拶する声が上ずる。
相変わらず笑ってくれない目に、歩は恐れをなす。
「歩君、朝食は?」
歩は叔母である美津子が好きだ。
この京都訛りの柔らかい口調が、昔から気に入っていた。出来れば母親もこんなだったらいいのにと、何度も思ったことがある。
「済ませてきました」
美津子の問いに素直に応じた歩だったが、昇は顔をムッとさせる。
「キミ、まずは挨拶だろうが」
些細な物言いを見つけては文句を言ってくる。
これも昔から苦手だった。
「すいません。おはようございます。しばらくお世話になります」
あなた、そんな言い方をしなくても。歩君、怖がっているじゃありませんか」
仲介へ入る美津子を、昇は一瞥してから、歩へ戻す。
「嫌われて結構。好かれようとも思わない。そもそもだ。なぜ君はこんなあやふやな人生の選択をしている? きみはこんな所へ居るべき人間ではないだろう」
「あなたそれは」
「姉の頼みだから、君をしばらくは置くが、この状況を軽んじてもらっては困る」
「あなた、時間大丈夫ですか?」
「君に言いたいことは山ほどある。おいおい話すことにしよう。行ってくる」
「はい。行ってらっしゃい」
不機嫌のまま昇は出かけて行き、歩はやっと息を吐き出す。
「驚いちゃったわね。でも、悪い人じゃないのよ。あんなこと言っているけどかわいくて仕方がないのよ。今日だって、あなたの顔を見るまでは会社へ行けないって待っていたのよ」
寝耳に水だった。
歩は思わず、昇が出て行った方を見てしまう。
「ああいう人だから厳しいこと、いっぱい言うと思うけど、あなたを憎くて言うんのではないからね。仲良くやりましょうね」
出されたお茶を口にしながら頷く歩に、美津子は優しく微笑む。
「親父、行った?」
そっとドアを開け、中の様子を伺いながら、従妹の薫子が顔をのぞかせたのは、間もなくのことだった。少し遅れて、きちんとした身なりで入って来た由紀子が、嬉しさのあまり歩へ飛び付く。
大歓迎を受けた歩だったが、早くもその夜、後悔し始めることになる。
会社から戻った昇は、朝に増して不機嫌全開で、むっつりとした表情で端を進めていた。
時より視線が歩へ向けられる。
針の筵に座らされているようで、居心地が悪い歩だった。
食事も済み、歩の手を引っ張る由紀子を見て、昇が待ったをかける。
「歩君、少し、話をしないか」
歩は生唾を飲む。
従妹二人は顔を見合わせ、キッチンから出て行く。
ただならない雰囲気を醸し出され、歩の心臓は二倍の速さで脈を打ち始める。
「君は人生というものを、どう考えているのか言ってみなさい」
唐突な質問に、歩は言葉を詰まらせる。
「姉には言うなと言われたが、僕にはどうしても納得がいかない。君は将来を嘱望される、選りすぐられた逸材とうたわれる人物が、この世の中に、どれほどの人数が居るのか知っているかい? 希少な価値が君にはあった。それをどうし、君は台無しにする? 君は親不孝者だ。僕はそんな生き方、絶対に認めない。君は間違っている。そもそも上京してきたのは、なぜだ? 君は人生から逃げているだけだ。悪いことは言わない。ここでしばらく頭を冷やして、一からやり直しなさい」
耳が痛い話である。返す言葉がない歩は俯く。
「あなた、もうその辺で」
美津子に助けられ、歩は部屋へ戻ることが出来た。
どっと疲れが押し寄せる。
「歩、ママが風呂入りなさいってって、寝ているの? 起きろ歩。風呂だ風呂」
いつの間にかうとうとしてしまっていた歩は、耳元で騒がれ、飛び起きる。
「ああお姉、抜け駆け禁止」
「抜け駆けなんかしていないよ。ママに言われて、風呂入れって伝えに来ただけだもん」
「ああ風呂。ありがとう、今行く」
「歩、風呂の場所分かる? 私が案内してあげる」
由紀子の嬉々とした声に、薫子が面白がって言い繋ぐ。
「歩、お風呂の入り方、分かる? 私が、お、し、え、て、あ、げ、る」
話についていけない歩は、目を大きく見開くばかりだった。
心身ともに、へとへとだった歩は、一刻も早く床へ就きたい気分なのだが、いつもの通り、従妹の二人は放っておいてくれなかった。
補習や部活に出かけている日中、寝ておくべきだったと、歩は後悔し始める。
部屋に入ろうとする歩を押しのけ、薫子が押し退けて行き、そのあとにアイスを抱えた由紀子が続く。
「超ムカつく」
「だよね」
「あんないい方、しなくてもいいのにね。歩、アイス、食べるでしょ?」
由紀子からアイスを手渡され、歩は訳が分からないまま、笑みを作る。
薫子が由紀子の手から、アイスを引っ手繰る。
「ああお姉、横取りずるい。ストロベリーは私の」
「ええ私だって、ストロベリーが良いよ」
「ああだったら、オレはバニラでも」
「歩はそれで良いの」
「もううるさいわね。そこまでお揃いにしなくても良いでしょ」
「そんなんじゃないもん」
口を尖らし涙ぐむ由紀子を見て、薫子は大きなため息を吐く。
「分かったわよ」
そんな二人のやり取りを聞いていた歩は、知らないうちに頬を緩ませてしまっていた。
「何がおかしいのよ」
「いや。やっぱお姉ちゃんだなって思って」
「仕方がないでしょ。由紀子、一度言い出したら、しつっこいんだから」
「そんなことないもん。歩に変なこと吹き込まないでお姉」
「あるある」
「ないです」
「もうそんなこと、どうでも良いから。もうおしまい。でさ、あんた、何で東京へ来たわけ?」
この話の展開が速いのは、薫子の専売特許で、昔から歩は泣かされてきた。
「ああそれ、私も聞きたい」
アイスを食べきった由紀子が、ケロッとした顔で言い繋ぐ。
絶句する歩に、薫子は容赦なく言葉を浴びせる。
「ねぇどうしてよ。話し、聞かせなさいよ」
間髪入れずの攻め。下手なことを応えれば、倍返しの攻めにあう。慎重にならざるを得なかった。
「それは、何となく」
「何となくだ?」
目が血走っている。薫子怖い。
恐怖におびえる歩を見て、薫子に拍車がかかる。
「バカを言うな。あたしを誤魔化せるとでも思って? さぁ吐きなさい。洗いざらいすべてを、この薫子様に言いなさい」
ものすごい迫力で言い寄られ、歩は息をのむ。
「はいはい。その理由、私、知っているかも。パパたちが話していたの、聞いちゃったかもです」
歩はギクリと、由紀子を見る。
「あれでしょ、行きたい球団じゃなかったって話でしょ?」
的違いの言葉に、歩は笑みを零す。
「何を笑っているの? 阪神とか西武とか行きたくないってごねたんでしょ」
「歩はお子ちゃまですね」
「ちげーし、適当言うな」
「だったら教えなさいよ。親戚中の期待の星だったあんたが、どうしてプーになったわけ?」
「お姉。デリカシーなさすぎ。それじゃパパと同じじゃない」
「止して、あんなのと同じにしないでよ」
「歩、困っているじゃない。可哀そうだよ」
「どっちが。有らぬ噂を立てられたまま、無視し続ける方が、余程ひどいと思うわ。私は真実を知ったうえで、味方になってあげたいの」
「それもそうだけど」
「特にうちの野球部の奴らだけにはさ、予測でいい加減な話、言われたくない」
「お姉、まさか歩のこと、学校で喋っているの?」
「普通するっしょ。その子、うちの従兄って。あんただって、自慢したくならなかった? 甲子園だよ。ホームランだよ。有名人だよ」
「それはしたかったけどさ。何となく、出来なかったもん」
「でさ、何で来た?」
薫子の巧みさに、歩は隠し事を通せた試がなかった。おねしょをしてしまったことも、昇が怖いことも、すべてこの調子で白状させられていた歩である。しかし今度ばかりは口を割るわけにはいかないと、頑なに口を閉ざす歩だったが、じりじりと詰め寄られ、逃げ場を失い、居た堪れなくなってしまっていた。
「どうしてって。やりたいことが少々」
「何、聞こえない」
耳に手を当てて聞き返す薫子。
言葉では、絶対勝てない相手である。
「お姉、意地悪すぎ。歩、遣りたいことがあるって言っているでしょ」
「だから、遣りたいことって何? 私はそれが知りたいの」
「お姉、そんなの言い訳に決まっているでしょ。歩は東京へ来たかっただけなの。特別やりたいことなんてないの。だからそれは不問だよ」
由紀子にきっぱり言い切られ、歩は複雑だった。
「それだけの理由? 東京に出てきたかったなら、巨人にでも入団すればいいだけの話しでしょ。そしたらパパに、あんな酷いこと、言われなくて済んだのに」
「そう簡単な話じゃないんだよお姉。ドラフトで決まるんだから、もしかしたら、仙台とか、福岡の球団へ入らなければならないかもなんだから」
「逆指名すればいいことだけでしょ」
「そうかもだけど、歩は気が小さいの。言えないのよ。言えたとしても、風当りに耐えられないの」
由紀子の勝手な力説に、歩は口を挟む余地がなかった。
「まさか、そんな理由」
「そうなの。だから歩を責めたら、可哀そうだよ」
由紀子に庇われ、何とも情けない気分の歩だった。
「あんたってさ、昔から煮え切らない奴だったよね」
薫子にぽつりと言われ、歩は思わず聞き返す。
「え? 何の話?」
「覚えていない? おばあちゃんの七回忌の席でさ、パパが聞いていたじゃない? 歩君は将来的には、どこの球団を目指すのかいって。その時も、今みたいな顔をして、結局答えなかったよね」
「それって、何歳の時の話しよ」
「私が小学三年の時だったから、歩は五年生か」
「ね、どうして?」
薫子はいつも、歩の痛いところをついてくる名人だ。
由紀子が興味津々で、歩を見詰める。
「ああ」
ああじゃなくって、野球を捨ててまで、東京へ来たかった理由って何?」
薫子に詰め寄られ、歩は冷や汗をかく。
うっかりした事は言えない。言ったら最後。
歩は慎重に言葉を選ぶ。
「強いて言えば」
身を一つ乗り出す二人に、歩は身を引く。
「自分の可能性を、見出したかったとか」
歩の答えに、薫子が冷たい目を向ける。
「歩、嘘、下手過ぎ。大学受けたけどダメだったとか? 失恋とかして、腑抜けになったとか、もっとましな嘘を言いなさいよ」
「お姉、少し黙っていて。歩の実力だよ。大学なんて、推薦ですいすいでしょ。歩の美貌を前にして、女子がフルわけ、ないでしょ」
「そっか。スポーツ推薦なら、勉強できなくてもいいのか。色男、金と力はなかりけりってわけだ。歩、私にその半分でも分けてくれ」
「お姉」
「これは失敬。と言うか、何でうちらが言い合いをしなければならないわけ?」
勝手にやり合っての言い草に、歩は笑うしかなかった。
「お姉、もう止そうよ。歩、困っている。これ以上責めるの、可哀そうだよ」
「だって歩見ていると、イライラするんだよね」
「じゃあお姉、部屋出て行きなよ」
「嫌よ。こんないじりがいがある奴、私が放っておくわけないでしょ」
「出たドS女」
「お褒めの言葉、ありがとうございます」
「でもさ、勇気あるよ。だって、本当は光彦おじさんと、野球を辞めるのを反対されて、家、飛び出して来ちゃったのよね? 何か、当てでもあったの?」
由紀子の言葉に、歩は目を瞠ってしまう。すべてを知っていて、今迄話をしていたことになる。
歩はつくづく、女は怖いと思う。
「あんた、何も考えていなかったでしょ」
「何もって、一応、金は、貯めていたし、何とかなるだろうと」
「甘いなぁ」
手を拱く薫子に言われ、歩は言い返すことが出来なかった。
「無鉄砲過ぎだよ」
由紀子にまで突っ込まれ、歩は力なくうなだれる。
「よくまぁ、当てもないくせに、度胸がると言うかなんと言うか」
薫子が、マスカラを分厚く塗ったまつげを瞬かせる。
「どうにかなるものかと」
「ならないでしょ。所持金はどの位あったわけ?」
由紀子の問いだった。
「10万ほど」
「わぁ凄い歩君。頑張って貯めたね。とでも、うちらが言うと思う? そのお金、本当は自分で貯めていないでしょ」
「良くお見通しで」
「てやんでぃ。お上の目はごまかせても、この薫子様の目はごまかされませんぜ」
「もうそういうの、いらないから。で、自己資金はいくらだったの」
歩はそろりと指を三本立てて見せる。
二人は呆れて、顔を見合わせる。
「無謀すぎる。それじゃあ、パパに言われても仕方がないわ。服買って、食事したらすぐになくなっちゃう金額よ」
「それはお姉だけ。それにしても少なっ」
「ダメかな?」
「ダメだよ。ホテルに泊まるとしたってさ、一泊が関の山だよ。それにこのご時世、家出人扱いされて、警察にすぐ通報されてしまうと思うよ」
「うんそれはあるかもね。歩、童顔だしね。だけどそれよりも、私はもっと最悪なことがあると睨んだ」
「その心は?」
「パパラッチ」
「そっか。雑誌とか新聞とかにスクープされたりして。朝の情報番組で発表されちゃうわけ」
「そうそう。前みたいにね」
「あったあった」
「嘘を言うな」
「嘘ではありません。ママが見つけて、録画したから、何ならお見せしましょうか?」
「もしかしたらさ、もうカメラはむけられているかもよ」
薫子の言葉に、由紀子が言い繋ぐ。
「ないです」
「どうして言い切れるの? 歩は知らないかもしれないけど、結構有名人よ」
ベディキュアをしながら、薫子に言われ、歩はムッとする。
「それは絶対にないです。普通に、ここまで来ましたから」
「これだから田舎者は困る」
薫子の言葉を受けて、由紀子も面白がって歩を冷やかす。
「無知って、恐ろしいわ」
居た堪れなくなった歩は、つい声を荒げる。
「ちょっと待った。少し君たち、言い過ぎではありませんか」
反論する歩に、一瞬、口を閉ざしたものの、二人はすぐに、元の調子へ戻る。
「歩って、自己評価低すぎだと思う」
「それ、私も言いたい」
「でしょ。野球部が盛んではないうちの高校でも有名ってことはさ、見る人には分かるっていう話でしょ」
ここまで断言され、さすがの歩も否定するのに疲れて来てしまっていた。
「もうその話、終わりにしない?」
「しない。はっきりさせておこうよ」
「お姉に、私も賛成」
「中田歩君、君はね重大なミスを犯してしまっていたのだよ。それに今も気が付いていませんね」
薫子がおかしな口調で喋るのを、由紀子が大真面目な顔で頷く。
「もうだから、勘弁してよ。オレはミスなんかしていないし、有名人でも何でもないからスクープはされない」
「中田、お前、お前ってやつは、どこまでおバカちゃんなのだ」
悪乗りをする薫子に、歩は顔を歪める。
「もうお姉、種明かしをしてあげたら?
私たちだって、パパに聞かされるまでは、気が付かなかったんだしさ、それに私、飽きてきちゃった」
「そうだね。私もそろそろ出かけたいし、教えてあげますか。歩、あんた、このバック担いできたのよね?」
コクンと頷く歩を見て、薫子は笑いを噛み殺す。
「それでは皆さん、ここに書かれている文字の御唱和お願いいたします」
そう言われ、歩はやっと薫子たちの言っている意味を理解する。
金文字で、高校名が書かれているのである。ご丁寧なことに、名前入りでもある。当たり前のように、毎日持って歩いていた歩の頭から、すっかりそのことが消え去ってしまっていた。
「あとさ、その髪型も致命的だよね」
夏に引退をしたと言っても、今までの風習で、卒業式前にしっかり刈ってしまっていたのである。
絶句する歩を見て、二人は大笑いをする。
「よし、じゃあ私はそろそろ」
こんな夜遅くに、どこへ出かけるのか、ポケットに忍ばせていたリップグロスを塗り終えた薫子が、おもむろに立ち上がる。
話に夢中で今まで気がついていなかったが、着ているものも、派手なものである。
「ちょっと、化粧濃くない?」
由紀子に突っ込まれた薫子が、歩に顔を接近させる。
「歩もそう思う?」
息がかかるほどの距離である。従妹とはいえ、女子にここまで接近されたことがない歩の顔がみるみる赤くなる。
「よく、分からないけど、こんな遅くにそんな恰好で出かけるのは不味いでしょ」
やっとの思いで言葉を絞り出した歩に、薫子は意地悪く笑う。
「都会の女子は、こんなの普通よ」
「普通ってことはないと」
「何、居候の分際で、私に意見をするわけ?」
薫子に凄まれ、歩はたじろぐ。
「お姉。歩から離れて」
由紀子にはがされた薫子が舌を出し、おどけて見せる。
「と言うことで、あとはよろしく」
いつの間にか、靴を押し入れに忍ばせていたらしく、薫子は窓からさっさと出て行ってしまった。
「お姉にとって、歩がこの部屋を使ってくれるのは、大助かりだよね」
しばらく顔を外に出していた由紀子が、振り返り微笑む。
意味深の笑みである。
「お姉と隆君、ラブラブなんだ」
「えっと、それって、今会いに行ったってこと?」
「朝まで帰ってこないと思うから。帰ってきたら、鍵、開けてあげてね。今までは私が、起こされていたから、助かっちゃう」
「いやいや」
「歩、今、変な想像したでしょ」
「していない、していない」
「嘘だ。ところで歩って、付き合っている子とかいるの?」
頬を赤く染める由紀子に、さすがの歩もそれが何を意味しているのか分かった。
大人びた表情をする由紀子に、歩は顔を引きつらせる。
「由紀子ちゃん、もうこんな時間だし、部屋へ戻った方が」
「歩って、鈍感だよね?」
「鈍感と言われましても」
ただならぬ雰囲気に、歩は後退る。
「ねぇ、歩知っている? 従妹同士って、結婚できるのよ」
「結婚って、由紀子ちゃん。冗談はそのくらいにして」
「歩、私、私ね」
「わわわ。ゴメン。オレ、トイレ」
思わず、部屋から逃げ出す歩だった。
刺激が多すぎて、一睡もできずに歩は朝を迎えていた。
薫子が帰って来たのは、明け方の4時である。
「歩、ただいま」
窓から入って来た薫子が抱き付く。その拍子に、二人して崩れ落ちる。
「臭い。酒、飲んだの?」
「少しだけだよ」
「未成年、飲酒禁止」
「真面目か」
「こういうの、オレ、良くないと思う」
「固いこと言わないでよ。家出少年のくせして」
薫子の胸が目の前にあり、歩は目のやり場に困る。
「歩、可愛い。顔、赤くなっている」
「煩い。早くどけよ」
「歩、女の子と付き合ったことないでしょ」
「だったら何?」
「私が、教えてあげようか」
「ふざけるなよ。退けよ」
「何、ムキになっているのよ」
「なっていない」
「歩、変わったね」
押し退けらえた薫子が、冷ややかな目で言う。
「オレは、変わってなんかいない。お前たちが、どうかしていると思う」
「はぁ? それどういう意味よ」
言い返そうとする歩の口を、薫子が慌てて塞ぐ。
廊下を歩く音だった。
誰かがトイレに、起きてきたらしい。
静かになるのを待って、薫子は廊下の様子を伺う。
「じゃあ。パパたちには内緒でよろしく」
素早く自分の部屋へ戻って行く薫子を、歩は薄笑いで見送る。
歩は寝る暇もなく、美津子に起こされていた。
何とも気まずい雰囲気である。
不機嫌なままの昇が、読んでいた新聞を畳み、訝る。
「眠れなかったのか?」
「いえ。はい」
昇は眉間にしわを寄せる。
「環境が変わったから、仕方がない。それでだね、今日、君を連れて行きたい場所がある」
緊張の面持ちで歩は返事をする。
「このまま、何もしないというのも良くないことだし、姉からもくれぐれもって頼まれている以上、私に責任がある」
「あなた、回りくどいですよ。仕事をね、紹介するってことよ。気に入らなければ、断っても良いわよ」
「美津子、お前は少し黙っていなさい」
「あら。怒られちゃった」
首を竦めた美津子が料理をしに戻る。
「かいつまんで言えばそういうことだ」
歩はおかしくなり、笑いそうになってしまう。
一見、亭主関白かと思いきや、美津子がうまくリードしているのだ。
そして歩が連れて来られたのは、新聞販売所だった。
歩の顔を見て、一瞬の間を作った所長が、にこやかに手を差し出す。
簡単な紹介を済ませ、昇は会社へと出社し、残された歩は仕事の説明を受けることになった。
そこで、歩は持田を紹介される。
歩の持ち場は、この持田が担当している、団地一帯になるらしい。
所長が紹介をするが、二コリもせず、一瞥するだけで行ってしまったのだった。
「不愛想な奴で、すまんな。悪い奴ではないと思うけど……、何かあったら、遠慮せず、何でも言ってくれ」
人当たりの良い笑顔に、歩は救われた気がした。
それが持田との出会いだった。
持田という男は、実にやりにくい男で、口数が少なく、何を考えているのかさっぱり分からないのだ。挨拶をしても、ちらっと見るだけで返ってきた試はない。仕事の教え方も大雑把で、質問にも満足に答えてもらえず、歩は多々困らされてしまっていた。
六月に入り、歩は取り立ての免許を、何度もにやけ顔で眺める。
念願かなっての原付免許だった。
本当は普通車免許が欲しかったのだが、昇の許可が下りなかったのだ。
仕事もだいぶ慣れ、免許取得をしたことで、配達区域も広げて貰っていた。
歩の頬は緩みっ放しである。
生活費などいらない。と言われた歩だが、僅かな金額でもと、昇へ強引に渡してきていた。
その日も、歩は昇へ意気揚揚と、お金が入った封筒を手渡す。
封筒の中身を確認した上るが、数秒間黙り込む。
気が気でない歩だった。
「あの」
昇の笑みを始めてみた気がする。
思い下けない笑みに、歩は戸惑いを隠せずにいた。
「こんなに、気を使わなくてもいいんだ。これは大事にしまっておきなさい」
多く入れた分のお札を介され、歩は負けじと押し返す。
「でも、僕の気持ちですから。受け取ってください」
昇は半瞬ほど間を置き、提案を持ち掛けたのは、その時だった。
歩は目を瞠ってしまっていた。
怖いばかりの昇だった。まさかあんな優しい笑みで、食事へ誘われるとは、思いもしなかった歩である。
新聞を配達している間も、歩の頭からそのことが離れずにいた。
店の前、昇を見つけ、歩は唾を飲む。
普段着の昇が、歩に気が付き手を軽く挙げる。
今まで想像したことがなかった、昇の姿だった。
先に暖簾をくぐる昇の後に、歩は通いた。
入ってきた二人へ、店主の威勢のいい声が飛び交う。
「おお珍しいね。倉さんが、こんな時間にやって来るなんて」
「実は甥に、是非大将のラーメンを食べさせてやりたくって、連れてきたんだ」
「へぇ甥っ子さん。あんちゃん、随分良い顔しているね」
「そうだろ」
「倉さん、ご自慢の甥っ子さんという訳だ。で、何にしましょう?」
「私はいつものチャーシューで、歩君は何がいいかね。遠慮はいらないから、何でも好きなものを、頼みなさい」
「同じもので。あと、ここはオレの奢りですから」
きっぱりと言い返す歩に、昇は苦笑する。
「そうだった。じゃあお言葉に甘えて、ビールも頼んでいいかな?」
「お。倉さん珍しいね」
「オレには、コーラー下さい」
「はいよ」
歩は腹を決めていた。
砕けた喋り方をする歩に、昇は目を細める。
何かある、そう思いつつ、歩は単純に嬉しかった。
店主と会話をする昇が、光彦と重なる。
ずっと歩の胸の奥に、突っかかっていた。
歩は話し掛ける機会を狙っていた。
ラーメンも食べ終わってしまい、店には二人きりだった。
汗を拭く昇に、歩は意を決し話し掛ける。
「昇おじさん、話って」
「うん。いや、そう大袈裟なことではないんだけど……」
いつもと違って歯切れが悪い物言いに、歩は目を大きくする。
歩にも考えがあった。
上京したてのころ、昇に言われた一言がずっと頭に残っていた。
「いやぁ何、もうすぐ夏になる。開放的な季節だ。何て言うか。ほら、ウチにも年頃の娘が二人もいるだろ」
心のどこかで、矢張りと思った歩は、頷く。
「いやぁ、従妹とは言っても、男と女だ。つまり……」
正直、最近の由紀子の言動に歩も悩まされていた。視線が熱く、目のやり場にも困らされていた。
「すまんが……」
歩は頭を掻く。
思い当たる節がありすぎて、申し訳なく思う。
「そういうことなら、オレも言いやすいです。実はオレも、そろそろ一人暮らしをしたいと考えていたから、おじさんにそう言ってもらえて良かったです」
「すまない」
頭を下げられ、歩は申し訳なく思う。
余程喉が渇いていたのか、昇は水を勢いよく飲み干す。
一呼吸置いたところで歩は、ため息を吐く。
怪訝な顔をする昇に、歩は首を竦める。
「問題は、うちの母ですよね」
歩と離れて暮らすことは、光彦以上に反対だったはず。昇に預けることで、自分を納得させたのだろうと思う。君江にはそういうところがあるのだ。もの分かりが良いふりをして、実はということは、今までも何度もあった。それは仕方がないことでもあると、歩は理解していた。忙しい父親の分も果たして来た君江である。親子二人の生活の方が長いのだ。きっと大騒ぎをする。この世の終わりのように泣きわめく。むしろ、上京をすると言った時にしなかったことが不思議なくらいだった。
「姉さんには、私から話そう。部屋探しも、手伝うよ」
帰り道、昇がふと足を止め、歩の顔を見る。
「君、姉さんとはちゃんと連絡取りあっているのだろうね」
歩は顔を強張らせる。
先ほどまでの笑みはなく、いつもの昇に戻っていた。
半瞬ほど遅れて、歩は返事をする。
昇はにこりともせずに、鼻を一つ鳴らす。
「君は、親をどう思っているのかな?
歩は苦笑いをする。
「連絡くらいしてやりなさい。大体君は、すべてに於いて、間違っている。言うならば自立する前に、身なりをきちんとするべきだ。君は何も分かっていない。君一人で、ここまで大きくなったって訳じゃないだろ? 親の反対を押し切って、折角用意された疎かにして、身勝手過ぎる。分かっていないから教えるけど、親って言うものは、子供を心配する生き物なんだ。それは何歳になっても変わらない。親は親であり続ける。だから、子供は全力で、子供でいなければならない」
いささか強引な説ではある。がしかし確かなことでもある。
「君ね、いくらあの強い姉さんだって、一人息子だ。心配で堪らないはず。光彦君だって、これにしかりだ。いいかい、明日、必ず連絡を取りなさい。これは命令だぞ。帰ったら美津子にも言っとくから」
あまり酒が得意ではない昇は、歩の肩を借りなければ、まっすぐ歩くこともままならない状態だった。
「君はいい男だな」
話の論点がずれ始め、歩は苦笑いを浮かべる。
「冗談じゃないぞ。あいつらが褒めちぎるのも無理はない。君は実にハンサムだ」
よろけて転びそうになる昇を引っ張り返す歩の頭を、昇は何を思ったか頭を叩きだす。
「僕も負けてはいなかったんだぞ。昔は、僕だって、ハンサムと言われたことがあったんだ。姉さんから聞いたことないか?」
曖昧な返事をする歩に、昇は豪快な笑い声を上げる。
「美津子に聞いてくれ。僕とあいつは大恋愛で結ばれて、はい。薫子と由紀子が生まれました。良い人生ですよ。君、懸命に生きるっていうのは、悪いことじゃない。夢、大いに結構。だがだ、だがだね、それだけでは人はダメになる。多少は無理も我慢も必要なものだ。君みたいに堪え性がないと、苦労をする。苦労するんだ。だから私は心を鬼にして君に言う。分っとるのか」
家へ着くまで昇の力説は続き、美津子の腕の中で崩れ落ちるように寝てしまった。
部屋へ戻りかけた歩を、昇が呼び止める。
「歩君。悪いことは言わない。今からでも遅くない。君は野球人生を進むべきだ」
半分眠った状態の昇の言葉だった。
美津子が、ごめんね。と唇を動かす。
歩は深々と頭を下げ、部屋へ戻る。
廊下から昇を介抱する、美津子の声が聞こえていた。
歩は鼻の奥が痛くなる。
歩は窓を開け、空を見上げる。
もう少し、きちんと話し合うべきだったのかな?
今更思っても仕方がないことだが、一日も欠かさず、あの日の光彦の顔が頭から離れたことはなかった。
深いため息を吐き、歩は窓を閉める。
翌日、歩は難しい顔で電話ぼっくの前に立っていた。
いざ掛けるとなると、何から話していいものなのか、糸口が見つからないのだ。
受話器を持ち上げては、辞め。出ては入り、又同じことを繰り返す。
今までどうやって話していたの、かさっぱり浮かばないのだ。
腕時計に目を落とす。
そろそろ販売所へ行かなければならない、時間が迫っていた。
大きく深呼吸してボタンを押して行く。
自分でも笑ってしまうくらい、指が震えている。
呼び出し音が耳の中で木霊していく。
受話器が上がる音がして、聞き覚えのある声が返って来た。
君江の声だ。
歩の胸をドキッとさせる。
すぐに声が出なかった歩に、受話器の向こうの君江が、気味悪がる。
電話を切られそうになり、歩は慌てて受話器にかぶりつく。
「待って。切らないで。母さん、オレだよオレ」
「はい。どちらのオレ様でしょうか?」
「もう母さん。オレだよ、声聞いて分かんねーの? 歩だよ」
「歩?」
「そ、オレ」
「怪しい」
「怪しいって、信じてくれよ」
「信じたいのは山々ですけどね。昨今世知がなくて。どちらで情報を得たのか知りませんが、こういう電話、本当に困るので、お辞めください」
「だからふざけないで母さん、まじめに聞いてよ」
「じゃあ歩だって証拠、言って貰っていいです?」
「証拠って」
「ないなら」
「ああ分かったよ。折角推薦校がありながら、高校進学をしないと駄々をこね、親の反対を押し切り、家出同然で上京したバカ息子のオレですけど、中田君江さん、これで分かって頂けたでしょうか?」
受話器越しで笑っている君江に、歩はムッとする。
「もしもし?」
「はい。バカ息子さん。お元気でしていましたか?」
「ええ。暖かい母親の恩情で、優しい叔父様のご厄介に預かり、大変光栄に暮らさせていただいておりますけど、それが何か?」
「あらそれはそれで。って、あんた、何で公衆電話から掛けているの?」
「うん。昇叔父さんの家からするのは、ちょっと気が引けたから。駅まで出てきた」
「あら、本当の歩だったのね」
「まだ疑っていたの?」
「まぁこっちも、いろいろあるのよ」
歩が家を出て行ってからしばらく、嫌がらせ電話が、日に数本掛けられてきていた。
「だってねぇ、家を出てからもう二か月も過ぎたのにねぇ、一度も電話を寄越さなかったしね。そりゃねぇ、なりすましサギとかに思われても文句も言えないでしょ」
「はいはい。オレがわるうございました」
「あら、ばかに素直じゃない。随分大人になりましたね」
「母さんからかわないで。オレの話、真面目に聞いてよ」
君江は受話器を握り直し、目を細める。
「あら。私は何時だって真面目よ。歩のことは特に」
歩はお手上げだとぼやいたあと、一呼吸置く。
「母さん、オレ、実は昇叔父さんの家、出ようと思うんだ」
「え? どうして? 叔父さんに何か言われたの?」
大きな声を出され、歩は思わず受話器を遠ざける。
「落ち着いて母さん。叔父さんはずっと居ても構わない、って言ってくれているけど……。なんか違う気がして。仕事も、ああオレ新聞配達をしているんだけど、金とかが、目途が立ってきたし、自立するのは、今かなって思って」
「何を言っているの? 稼ぐって言っても、たかが知れた金額でしょ? 本当に一人でやっていけると思っているの?」
興奮しきった君江の声に、歩は顔を顰めながら、言い返す。
「オレ、東京で、一人で頑張ってみたいんだ。このままじゃ、オレ、反対を押し切って出て来た意味がない。分かってくれよ。母さん」
歩は、受話器を置いてからもしばらく、そこから離れることが出来なかった。
その日、夕食に遅れて帰って来た薫子が、ただいまも言わずに、ニヤニヤと歩に話しかける。
「歩、今日の11時ごろ、駅前にいなかった?」「え? 何で知っているの?」
「で、公衆電話の中で物憂げに悩んでいたでしょう?」
「物憂げかはともかく、電話していたけど、何で? 気持ち悪いな」
薫子はにやけて答えをじらす。
「いい加減にしなさいか。大体こんな時間まで、どこをほっつき歩いていたんだ」
叱る昇を、薫子は睨みつける。
親の心、子不知。
よその親子だとよく分かるもんだな、と歩はそんな二人を、固唾をのんで見守る。
昇なりに薫子を心配しての、一言だった。
ついさっきまで、昇は美津子に、何度も薫子の行き先を問い詰めていた。
「薫子、返事くらいしなさい」
「煩いな」
「煩いとは何だ」
舌打ちをする薫子に、昇は今にも飛び掛かって行きそうな勢いで立ち上がる。
「薫子、待ちなさい」
部屋へ戻るのを美津子に阻止され、薫子は口をへの字に曲げる。
「パパに謝りなさい。ご飯もちゃんと食べないとダメでしょ」
歩はこんな時、どんな顔をしていいのか分からない。食事の手が止めて、ついつい周りの様子を伺ってしまう。
薫子は、不貞腐れて席に着く。
歩の隣の席だ。
「歩君、気にしなくて良いのよ」
薫子の食事の用意しながら美津子に言われて、微笑み返すが、顔が引きつっているのが、自分でもよく分かる。
重たい空気が広がって行く。
「お姉ちゃんが、焦らすからややこしくなるんだよ。どうせパパのことだから、学校をサボって遊んでいたんじゃないかって、思っているんだよ。お姉は誤解されやすいタイプなんだから、ちゃんと話しておいた方が良いよ」
由紀子は、おかずに出されていた焼き魚を起用の身をはがしながら言うと、チラッと歩を見る。
「歩だって困っているじゃない」
「そうよ、今までどこへ行っていたの? 連絡くらいしなさい」
美津子がそう言うと、薫子は制服のポケットから携帯を取り出し、歩の前へ置く。
シルバーの携帯が派手にデコレーションされ、ストラップにこんなに大きなクマがぶら下がっていたら邪魔だろうと余計なことを思いながら、歩は画面を覗き込む。
素秒間固まった歩は、目を見開いて薫子を見返す。
「サボってなんかいないし、学校でちゃんと勉強をしていました。あのね、今は情報社会だよ。ちょっといい男が電話をしているなんて話題、電波に乗って世界中にだって広がっちゃう時代なんだから」
歩が公衆電話の前で考えている姿に、電話をかけている姿。電話を切って、ホッとしてバイクに乗り込む前、缶コーヒーを飲む姿までが、画像がで撮られている。
「歩はもう少し、自分のことを分かった方が良いよ。歩くらいの顔立ちの男子が、物憂げにして立っていると目立っちゃうし、話題にも名ちゃうご時世だよ。正体だって、すぐにばれちゃうし、居場所も検索されてしまう時代なの今は」
あまりの恐ろし兄、歩は言葉が出なかった。
「歩、もっと自覚を持ちなさいよ」
薫子が苛立った声で言うと、昇が咳払いをする。
「ねぇパパもそう思ったから、歩をここから追い出すことにしたんでしょ? 私はともかく、由紀子はね~」
「薫子」
昇よりも早く、美津子が叱った。
「それって、どういう意味?」
キョトンとした顔で歩は聞き返していた。
「鈍感!」
薫子に即答され、歩が目をぱちくりさせる。
居た堪れなくなった由紀子が部屋を飛び出して行く。
これで良かったのか、歩は正直分らなかった。
昇と美津子が目配せをする。
歩の渾身の演技だった。
何も知らない薫子は、歩に軽蔑の目を向けてから、部屋を出て行った。
苦笑する歩に、二人は深々と頭を下げる。
――そして土曜日。
歩は忠犬ハチ公の銅像の前で立っていた。
君江と待ち合わせをしているのだが、どうしてここを指定したのか、歩にはさっぱり訳が分からなかった。
「あのぅ」
後ろから声を掛けられた歩は、相手の顔も見ずに、ムッとした声で答えた。
「待ち合わせしているんです」
「ずいぶんと、機嫌が悪いのね」
歩は、ハッとして振り返る。
「何だ、母さんか」
「なんだは随分ね」
「さっきから変な人に声を掛けられて、困っていたんだ」
「変なって?」
「行こうか」
促す歩の顔を、君江は面白がるように顔を覗き込む。
「何よ。教えなさいよ」
曖昧な言葉を繰り返す歩に、君江は執拗に尋ねた。
昔からそう言う性格だと知っていたが、このしっつこさはいささか気に触る。
煩い、の一言で片づけたいところだが、君江の嬉しそうな顔を見た歩は仕方なく、ぼそぼそと答える。
「モデルになりませんとか、所属はどこってとかも聞かれた。それに……」
「それにそれに。どうしたのよ?」
君江を一瞥した歩は、深いため息を吐く。
「何よその態度。久しぶりに会った母にすることかしら?」
弱いところを突かれた歩は、口を尖らせて答える。
「付き合っている人、いるんですかとか聞かれたの」
「ほー」
「何がほーだよ。さっさと行くぞ」
歩の顔がみるみる赤くなり、君江は何を思ったか腕をからめて、にっこり微笑む。
「何?」
「ねぇこれから何する? 映画? それとも食事?」
ふざけるのにもほどがある。
甘ったるい話し方をする君江に、歩は顔を顰める。
「良いから合わせて」
顎をしゃくられ、歩はようやく事情を呑み込めた。
制服を着た女子が、後をつけてきているのだ。
さっき、歩に話しかけてきた女子だった。
それにしたって、設定に無理がある。
歩はチラッと、後ろを振り返る。
諦めをつけてくれたらしく、駅構内に入る頃には、姿は見えなくなっていた。
「もういないよ母さん。離れて」
「ええ~まだ良いじゃない」
子供のようにはしゃぐ君江を、歩は無碍にすることはできなかった。
「こんないい男に出会ったら、デートをしなきゃ損損」
歩の気も知らずに、君江はやたらはしゃいでいた。
通りすがって行く人たちに見られているようで、歩は顔を伏せて歩く。
それは電車に乗ってからも続けられ、歩は、ほとほと困り果ててしまっていた。
最寄りの駅に着き、やっと君江の手から解放されたのも束の間、今度は歩が強く掴まなければならなくなる。
好奇心旺盛の君江は、目を放したすきにどこへでも行ってしまうのだ。
ここまでくれば安心だろうと手を放したのがいけなかった。
横断歩道を渡り切った歩は、後ろを振り返り慌てふためく。
催事場の前、悪びれる様子もなく、君江は店員と楽しそうに話し込んでいた。
「母さん、勝手にいなくならないでよ」
「歩、これパパ、絶対好きだと思わない?」
「はいはい」
「これも好きよね。でも荷物になっちゃうかしら?」
「分かったから。いい加減にしろよ。そんなの後でもいいだろう?」
自分でも驚いてしまうような強い口調で言ってしまい、歩はハッとして君江の顔を見る。
「そう。じゃあそうする。忘れないでよ」
「ああ」
不愛想に言う歩の腕を、君江はまた嬉しそうに掴む。
少し躊躇いはあったが、歩は小さく息を漏らす。
やっとの思いで目的地である不動屋に辿り着いた二人は、中へと入って行く。
入って行く歩の顔を見た女子店員の一人が、あっという顔をしてみせる。
歩らしくない厳しい顔つきで、まっすぐその女子店員の前へと進んで行った。
「先日はどうも」
歩の態度の悪さに、君江は顔を顰めさせる。
「先日の物件、親同伴なので、見せてもらえますか」
君江は気になり、歩を突っつく。
ちらっと見たものの歩は何も教えようとはしなかった。
女子店員は、いそいそと書類を用意し始める。
「やっぱ辞めます」
歩は説明を始めるとすぐに席を立ち上がる。
「歩」
「良いから行こう」
君江の制止も無視をして見せを後にする歩に、女子店員が後を追ってくる。
「あの、先日は失礼いたしました」
歩は振り返ることもせず、前を歩いて行く。
「どういうことよ」
「いや別に」
「別に、って顔、してないわよ」
「相手の素性も確かめずに、勝手な思い込みで、警察へ通報しようとしたんだあの店員」
「え? それでどうしたの」
「販売所の電話番号と、免許書を見せた」
「それで分かってもらえたんでしょ」
「そうだけど、何だか許せなくって。オレ、今度来るとき、親、連れてきますって啖呵切って、店を出てきたんだ」
「有言実行したって訳ね。あなたって子は」
「悪い。これだからガキって言われちゃうんだよな。分っているんだけどさ、どうしても譲れなかったんだ」
「もう仕方がないわね。それでどうするの?」
「別の不動産屋に行こう」
会わないうちにだいぶ大人びたと思ったが、中身はまだまだ子供である歩に、君江は目を細める。
そのあと、部屋はすぐに決まり、歩と君江は蕎麦屋へ腰を落ち着かせていた。」
久しぶりの親子水入らずにどことなく気恥ずかしさを感じつつ、君江は歩の顔を見入る。
「何だよ。そんなじろじろ見るなよ」
「良いじゃない。二か月ぶりの親子の再会よ。少しは感傷に浸らせなさいよ」
舌打ちをする歩に、君江はつい笑ってしまう。
あれやこれやと話したかったことや聞きたかったことが、あれほどあったというのに、おかしなものである、歩の顔を見た途端、満足してしまうのだから。
歩が照れくさそうに眼を上げる。
歩とて、君江には言わなければならないことがあった。が、面と向かってではどうしても素直に言い出せずにいた。そのうちそばが運ばれてきて、君江は、おいしいおいしいと、嬉しそうにそばを啜って行く。
ふと、昇に言われた言葉が歩の脳裏を過る。
「母さん」
君江が微笑む。
「いろいろごめん」
潔く頭を下げる歩に、君江はこみ上げてくるものがあった。
「何よ、改まって」
「昇おじさんに言われたんだ。大人ならきちんとけじめをつけて来いって」
「あら、昇にしては上出来」
「オレさ、あんなこと言って出てきたけど、まだ何にも出来ていなくて」
歩は胸を張れない自分が情けなくて仕方がなかった。
「だから言ったでしょ。現実はそう甘くないのよ」
「ですね」
「分かればよろしい。これはかあさんからのプレゼント」
「これって」
「私たちに悪いと思うなら、これを使ってきちんと連絡はしてきなさい」
「母さん」
新しく買い換えられた携帯を前に、歩は泣きそうだった。
そして君江はその足で返って行き、歩はしばらくホームで佇んでしまっていた。
第一章 自分の価値
引越しの日は、薫子達の試験も終わる頃を見計らってこの日にした。これは美津子のたっての希望で、普段から勉強に興味を持たない二人なのに、ガタガタと荷造りされた日には一夜漬けすらしなくなってしまう、と嘆いたからだ。それに比べて、昇は一日も早くという意見で、それは歩も賛成だった。
二人の着る服は、露出度が高すぎて目のやり場に困る。平日は学校へ行っているからまだ良かったが、これが試験期間だ夏休みだとなって来ると、必然的に一緒にいる時間が増えてしまう。という事はこのセクシーな格好をした二人に遭遇する時間も、回数も増えるということで、これじゃあ昇が心配するのは無理がない、と歩は納得させられてしまう。もっと厄介なのが、妹の由紀子だ。やたらと歩に勉強を教えてもらいたがる。
勉強はと言う歩に、中学校くらいの勉強は分かるでしょと迫ってくるのだ。
野球しかしてこなかった歩は、当然ながら、教科書を目の前にして、固まってしまっていた。
かわいいと由紀子に言われ、歩の顔は真っ赤になる。
引っ越すことがばれてからは、一波乱も二波乱もあった。
悪の根源は、すべて昇にあるとされ、歩は身をつままされる思いに駆られる。
引っ越し当日、二人は示し合わせたように、留守をしていた。
気まずさだけを残し、歩は荷物を運び出す。
いよいよ新しい生活が始まる。
開け放った窓から心地の良い風が入り込み、隣にある公園の木にセミが止まり、やかましさに、つい耳を塞ぐ。
引っ越しもひと段落氏、三人で近くのファミリーレストランへ向かう。
歩は不思議な気分だった。
二人に挟まれて歩いていると、まるで家族といるようで、鼻の下あたりがこちょば痒い。
歩はそっと昇を見やる。
昇はいつになく無口だった。
「何だか申し訳ないことをしたわね」
腰を落ち着かせ、開口一番に美津子が言う。
「本当に面目ない」
二人に頭を下げられ、歩はいささか慌ててしまう。
「もともとは、僕の我侭から掛けた迷惑なんですから」
「迷惑なんかじゃなかったのよ。ずっと男の子が欲しかったし、この人なんか息子だったら良かったのにって、昨日もぶつぶつ言っていたのよ」
歩は、驚きの眼で昇を見る。
「いやなに、僕も昔は野球をやっていたしな。キャッチボールくらいはやりたかったなと思ってさ」
照れ臭そうに言いながら、昇は投げる振りをして見せる。
初耳だった歩は、ますます驚きで目を見開く。
「今じゃ見る影もないけどね」
自分の出っ張った腹を、昇は摩って見せる。
和やかな空気が、歩は愛おしく思えた。それと同時に、君江や光彦のことを思う。
鼻の奥が痛くなった歩は、ぎこちなく笑って、美津子の他愛もない話に頷く。
窓から入ってくる日差しが傾き、部屋に影を作る。
「そろそろ」
昇が首に巻いたタオルで汗を拭き立ち上がる。
本来なら、上京する時、こんな風に見送られていたのなら、どんな風になっていたんだろう。
今更ながら、歩は遠い日のことを思い出し、胸を痛ませる。
玄関で立つ二人へ、歩は深々と頭を下げる。
顔を上げた歩は、昇から際出されたものを見て、目を瞠る。
「これは君の物だから、君が使いなさい」
歩名義の通帳だった。
その通帳には、今まで生活費として渡していた金額がすべて入金されていた。
「君がこんなことを心配しなくても、ちゃんと姉さんからお金は預かっていたし、それに、男の子を持つ親の気分って奴を、充分に味あわせて貰ったしな。今度は、成人したら一緒に酒でも飲んでくれればいいから」
二人が帰って行ってしまってから、歩は寝っ転がり、ぼんやりと天井を眺めていた。
光彦も、こんなのを望んでいるのだろうか?
「……ヒーローインタビューか」
呟いた声に、歩は泣きそうだった。
夏の暑さがいくぶん和らいだある日、歩は思いがけない人から声を掛けられ、作業をする手を止める。
「あんちゃん、一人暮らしをはじめたんだって?」
折込を挟み込む作業をしていた持田が話しかけて来たのだ。
「何、いつごろからよ?」
「最近です」
「そうけ」
持田はそう言うと、軽々と歩よりも多い新聞の束を軽々持ち上げ、バイクへ積み上げる。
持田のことはあまり好きではない歩だが、この時ばかりはベテランの貫録を痛感させられてしまう。
歩がもたもたしているうちに、配達員のほとんどが店を出発してしまっていた。
歩は焦ってエンジンを掛ける。
「気付けてや」
所長の言葉に、歩は軽く手を挙げる。
「焦んなくてもいいからね。戻ったらうちへ来なさい」
所長の奥さんが、ニコニコと手を振る。
歩がひとり暮らしを始めてすぐ、この習慣が始まった。
とにかく猫かわいがりをしてくれているのだ。断っても、朝食をたっぱに詰めて持って帰らされる有様で、歩は複雑な心境だった。
「どうだ。あの団地の階段地獄は?」
歩が戻ると、入り口の前でたばこを吸っていた持田が声を掛けて来たのだ。
「半端じゃないです。よくあそこを持田さん、配っていましたね」
少し戸惑いながら、歩は答えた。
「ああ。老体に鞭を打って頑張ってた。あんちゃんが来たから、所長にお願いしたんだ。あそこは若者に任せようって」
顔色一つも変えずに言うと、持田はプハーと煙を吐き出した。
持田は、本当にうまそうに煙草を吸う。歩が見とれていると、吸うかと煙草を差し出してきた。
困惑する歩を余所に、上機嫌の持田は珍しく良く喋る。煙草の代わりにと言ってジュースまで奢ってくれた。それからは、拍車をかけたように、配達先の犬が放し飼いは困るから始まり、小うるさい親父の話をうんうんと頷きあい、分かる分かると手を叩いて笑って、快活に話題が続いた。
所長夫妻の好意を断る、いいきっかけが出来たと、歩はそんな持田に懐くようになる。
持田は、第一印象とだいぶ違い、本当の良くしてくれる。
歩は毛嫌いしてしまっていた、自分が恥ずかしかった。
持田と過ごす時間は有効で、実に楽しい。
仕事は勿論のことそれ以外にも、パチンコの台の選び方や馬券の買い方を教わり、競輪場では、大当たりさせ、興奮冷めやらない思いを味あわせて貰った。
大人の仲間入りした気になり、少し有頂天になっていた。
「あんちゃん、女の経験は?」
聞かれて、歩は苦々しく笑う。
「何だ、こっちの方もチェリーちゃんか」
持田に前を強く握られ、歩は逃げ惑う。
「ヨッシャ、それじゃ今日は竿おろしだ」
「竿って?」
「風俗連れて行ってやる」
青ざめる歩に、持田がにやける。
「あんちゃん良いもの持ってそうだから、女がひーひー喜ぶぜ」
「オレは、ちょっと」
「何や、ノリが悪いなぁ」
「そっち系は、まだいいかな」
「何や、怖気付いたのか? ただ女の上で腰振るだけでいいんだ。旨くすれば、金にだってなる」
「は?」
「冗談だ冗談。しゃーないな。ほんなら飯、食いにでも行くか」
話がすり替えられ、歩はホッとする。
酒の味を知ったのも、持田のおかげだった。
持田は、歩が東京に来て初めて、気を許した人だった。
ニュースで木枯らし一号が吹き荒れたと報じられ、バイクを走らせていると鼻水が出て仕方がなかった。
「いい男が台無しだな」
歩がバイクを止め、汚れた軍手で鼻を擦っていると、持田が販売店の中から煙草を吸いに出てきた。
「参ったよ。団地で汗かくことを忘れて厚着して行ったら、帰り寒くって」
歩は、鼻を啜った。
「この時期は難しいんだよな。寒いからといって厚着していくと汗掻いて、かえって汗で冷えるかんな。そういう時は、背中にタオルを一枚入れておけばいいんだよ」
持田は煙草を銜えると自分の背中からタオルを引っ張り出した。
「こうしておけば汗かいた時、これだけ抜けば多少は違うぜ」
尊敬の眼で大絶賛する歩に、持田は足で煙草を揉み消しながら訊いた。
「あんちゃんこれからの予定は?」
「部屋に帰って寝るだけです」
「そんじゃ、飯でも食いに行くか?」
「すいません。オレ今日、金持って来なかったから」
申し訳なさそうに断ると、持田はゲラゲラと笑い出す。
「奢ってやるから付いて来い」
二人は、近くの定食屋に腰を落ち着かせた。
奢りということに気兼ねした歩は一番安い物を頼もうとする歩に、男なら大盛りをがっつり遠慮せずに食べろと、大盛り定食を2つ頼む。それに持田は日本酒を付け足した。
朝からですかと歩の素朴な質問に、オレ等の仕事は今が夜みたいなもんだと言いながら、ポケットから煙草を取り出す。
大盛りの丼飯と焼き魚の定食をあっという間に平らげた歩は、店に吊るされたテレビから流れるニュースを眺めていた。
嫌な話だった。
ストーカーに殺されてしまった、可愛らしい女性の顔写真が映し出され、次に現場になった場所が映る。
点々と残された痕跡が生々しく、その時の残酷さを物語っている。
「怖いですね」
歩がテレビ画面を見たまま言うと、チラッとだけ目を上げた持田が、愉快そうに言う。
「ああ。スキよスキよも嫌いの内ってな」
持田は酒を一気に飲み干す。
歩はテレビ画面に見入ったままだった。
「なぁ、あんちゃん。おまえいくら貰っているんだ?」
驚いた歩が振り返ると、持田は二杯目の酒を店員に頼んでいた。
「どうしたんですか? 持田さんなら見当がつくでしょ」
持田は運ばれて来た酒を一口飲むと、安いなと呟く。
これは酒が相当回ったなと思った歩が、そろそろと言い掛けると、安すぎるだろうと持田は繰り返した。
「持田さん?」
両手で顔をゴシゴシと擦ったあと、グイと持田は顔を歩に寄せる。
「あんちゃんも一人暮らしじゃ何かと入用があるだろう? 大丈夫なのか?」
「何とか……」
正直な答えだった。
持田はギョロッとした目を血走らせている。
「あのさ、実は良い儲け話があるんだけど、一枚乗っかってみないか?」
酒臭い息が吹きかかる。
目に落ち着きがなく、やたら周囲の人の動きを気にし出した持田は、顔を引こうとする歩を無理やりひき戻し、良いから大人しく聞けと凄む。
「あんま、人に聞かせたくないんだけどよ。あんちゃん真面目に頑張っているから教えるけど、どうだ? やってみるか?」
「なんか、やばそうな話なんですか?」
歩の質問に、持田はイラついたように煙草を銜える。
「ヤバイというか、ちょっとした大人の仕事だ」
持田は煙を吐き出しながらそう言うと、酒を口に運んだ。
テレビから菓子のCMソングが流れ、アイドル歌手が満面の笑みを浮かべている。
「その気になれば4、50は軽く稼げる。どうだやってみないか?」
歩は口篭る。
「いらっしゃいませ」
奥から威勢のいい声が飛び交い、持田は一旦、話を打ち切り、水を運ぶ中年のおばさんに、ごちそうさんと声をかける。勘定はここに置いとくよと軽く手を振り、先に店を出て行くが、歩は頭が混乱して、しばらく動けずにいた。
歩は部屋に帰っても、持田の言葉が頭から離れずにいた。
「大人の仕事って?」
「いや、そんな大したもんじゃないんだ。少しばっか、大人の話しに付き合ってあげればいいだけなんだ。あんちゃんは見たくれがいいから、その気になれば100万は軽くいけるんじゃないかな」
「100?」
「しっ! 声がでかい」
「すいません。100万って、一か月でですか?」
「いや、上手くやれば一晩でいける」
「でも、話すだけでそんなお金を稼げんですか? やっぱりやばいことじゃ」
「あんちゃん、見かけによらずに臆病だな」
持田がニヤニヤと笑いながら、煙草を吹かす。
自転車を引っ張る手に、自然と力が込められていた。
「東京はいろんな仕事があるからな。やり方、考え方しだいではいくらにでもなる。特に若いうちは何だって金になる」
歩は目を見開き、持田の顔を食い入るように見てしまっていた。
「ただ、時間は不規則になる」
「水商売ですか?」
「まぁそんなとこかな。オレの知り合いが店をやっているから安心なんだ。心配は要らない。それは保証する」
「でも、オレ未成年だし、酒は……」
「それ、本気で言っている? 別に身分証明書を提示するわけでもないし、僕、童顔なんですって言えばいいだけさ。その方が、受けもいいしな。大人の世界だ。誰も難しいことは言わねー。まぁ酒が飲めないって言うなら、それでもいい。少しばっか、欲求不満のおばさんに、優しく微笑んでくれればいいんだ。簡単だろ?」
「簡単て……」
そこで二人は別れた。
答えなど出せるはずがない。
歩は頭を抱えてしまっていた。
なぜか答えを持田は急いでいた。
今晩にでも、その店に行ってみないかと言われている。夕刊を配り終えたその足で向かえば、すぐに働ける。とも言っていた。
あっという間に暮れて行く空を見上げ、歩は階段を駆ける足を速める。
最後の棟を配り終える頃には、すっかり日は落ちていた。
憂鬱な気分のまま戻った歩は、販売店の脇から持田にひょいと顔を出され、ギョッとする。
「ど、どうしたんですか?」
目をひん剥かせ訊く歩を、ギョロっと目を動かした持田が、腕を引っ掴み、暗がりに引きずり込む。
販売店の脇は、閑静な佇まいになっている
暗がりに、ぼんやりと持田の輪郭だけが浮かび上がる。
「今朝の話、考えてくれたか? オーナーが早く会いたがっているんだ」
「すいません。オレはやっぱり、いいです」
「楽で簡単。それに越したことはないだろう? 30万だぞ? こんなおいしい話を断るのか?」
持田の目が血走る。
「あんちゃんに行ってもらわないと、オレが困るんだよ」
持田に胸倉を掴まれ、歩の顔が引きつる。
「何言ってんですか? そんな上手い儲け話なら持田さんがやればいいじゃないですか?」
「あんちゃんよ、ちっとも世の中っていうものが分かってねぇな。何にでも商品価値つうもんが、あんだよ。誰でも良いわけじゃない。あんちゃんの知名度と、そのマスクがあって、初めて成り立つんだ」
「出来ないものは、出来ないです」
「それじゃ困るんだよ。どうしても、俺にはまとまった金が必要なんだ」
持田は、グイと歩を引き上げる。
「おーい。そんな所で何してんだ?」
それは所長の声だった。
歩は弾かれるように持田の手を振り払い、急ぎ足でその場を離れる。
前を通り過ぎようとする歩に、何かあったのかと所長が声を掛けた。
何でもないんですと言う歩の答えに、背後から持田の声が被る。
「何でもないっすよ。今度は二人でどこに行こうかって話していただけで」
「ふーん。こんな暗がりでか?」
所長は、ゆっくりと自分の前を通り過ぎて行こうとする、持田の腕を掴む。
「あいつに、何をしようと企んでいる」
凄む所長の手を振りほどいた持田が、半笑いで返す。
「なんもしないっすよ。東京見物ですよ。嫌だなー、疑ってんですか? 」
と、持田は話をはぐらかせた。
「中田、どっか行ってみたい所があんのか? あるなら、俺が案内するぞ」
店内に戻って来た所長に訊かれ、歩はきょとんとする。
「何、かみさんがおまえさんのファンで、前から、どっか、一緒に行きたいって言われてんだ。なっ」
事務仕事をしていた奥さんが、はにかむような笑みを浮かべる。
「高校球児の時から、大ファンだったんだよね。もうあの中田がうちへ来るって、聞いて、どんだけ嬉しかったか。最近、なかなかうちへ顔を出してくれなくなって、超寂しかったのよね」
ガハハハハと笑う奥さんに、歩は顔を引き攣らせて笑い返す。
「嫌だもう、ミーハーに思わないでよ!」
「ミーハーって、今時使わないぞ」
そう言いながら所長は持田を見る、
「そう言うことだから、こいつにはもうちょっかいは出すな」
所長に苦言を呈され、持田は苦虫を噛んだような表情を浮かべ、店を出て行く。
これで事が済んだと、歩は安易に考えていた。
ホッとしている歩を座るように、所長が促す。
「あいつとはもう付き合うな」
開口一番に言われ、歩は返答に戸惑う。
椅子を引いた所長が引出しから何かを取り出し、歩の顔を見る。
「ここにはいろんな経歴を持つ奴が来ている。多少荒っぽいこともしてきた奴も、正直いる。俺はそれでもきちんと働いてさえくれればいいと考えている」
一呼吸置いた所長が、歩の顔をジッと見て言い繋ぐ。
「だがあいつはダメだ。折を見て止めて貰おうと思っている」
「どうしてですか?」
思わず叫んでしまう歩を宥めるように、所長は肩へ手を置いて来る。
歩の躰がピクリとする。
詳しい説明をしたがらなかったが、歩は頭の中で話を繋げてみた。
要するに、持田は職歴こそ長いが、ここへ来て、日はまだ浅い。無口な男で、今まで挨拶すらろくにしなかった奴が、歩に急接近し始めたのを、所長は胡散臭く見ていた。
ここのところ、持田宛に、変な電話も掛かって来るようになったのも、その一つの要因になっている。
「なぁ中田、おまえ、あいつに何かされていないか?」
「何もされていないですよ」
歩は自分が逝った言葉を噛みしめる。
確かにここにきて驚かされることはあったが、しかし、歩にとってやはりいい兄貴分として、持田は君臨している。どうしても悪く思えなかった。
「それなら良いや。でも、注意しろよ、大人ってやつは面倒だからな。俺を親父だと思って、何でもいいから相談していいからな。あいつもいるし」
奥さんが大きく何度も頷いて見せる。
「ありがとうございます」
元気なく言う歩の肩を、所長が叩いて来る。
身をよけてしまう自分に、苦々しく笑う歩だった。
翌日、持田は無断で欠勤した。
その次の日も一切連絡が取れずにいる。もう一日様子を見てクビだなと話している矢先、ふらりと持田が店へ姿を現した。
理由は話さなかったが仕事を辞め、給料を現金で貰って行った、と配達を済ませた歩は聞かされ、ホッとしている自分に気が付く。
口ではあんなことを言っていたが、正直、持田があの時見せた表情にが歩の頭から離れなかった。すべて仕組まれていたことかと思うと、夜もおちおちと寝ていられない気分になっていた。
完璧に、人間不信に陥ってしまっていたのだ。
季節はすっかり冬に入っていた。
朝起きるのが辛く、その日も手がかじかんで仕方がなかった。
持田のことは、すっかり忘れてしまっていた歩だったが、配達を終え、バイクの横に立っている姿に、心臓が大きく脈を打つ。
頬がこけ、目が落ち窪み、店を辞めてから半月しかたっていなかったが、あまりの変わりように、歩は驚く。
「どこか悪いんですか」
持田がおもむろに、ポケットからナイフを取り出す。
「あんちゃん頼むよ。オレと一緒に来てくれよ」
持田の手が微かに震えを見せていた。
持田はやたら落ち着きがなかった。
脅しながら、あたりをキョロキョロしている。
人が来るのを警戒してのことだろうと、その時の歩は思った。
「良いから、俺の言うう通りにしろ。悪いようにはさせない。な、俺とお前の好じゃねーか」
だんだん東の空が、明るみ帯びて来ていた。
歩は千載一遇のチャンスを待った。
持田が後ろを見た隙を狙って、歩は掛けに出る。
「一応だけど、もしもって時に役に立つだろうから」
持田が店を辞めたその日、所長が一冊の本を歩に手渡す。
それを機に、歩は躰を鍛える意味で、配達先でもある道場に通うようになっていた。
習い始めたばかりで、どこまで通用するのか自信はなかったが、やるしかない。
歩は必死の攻防で、持田の手からナイフを落とさせる。
まさかの抵抗に、持田は狼狽えていた。
足元に落ちたナイフを拾うとする持田を、歩は後ろから羽交い絞めする。
「持田さん、止めてください」
「ウワっ」
渾身の力で歩を弾き飛ばした持田だったが、その時調度団地から人が出てきて、二人の様子に驚き、悲鳴を上げる。
その声に反応して、持田が一目散で逃げて行く。
「大丈夫ですか?」
住人に声を掛けられたが、歩の耳には全く入らなかった。
「警察、呼びますか?」
歩は無意識のまま、首を横に振り、そのまま落ちていたナイフを拾うとフラフラとバイクに戻って行く。
気がすっかり動転していた歩だが、途中、川にナイフを投げ捨てる。
恐怖がヒシヒシと湧いて来ていた。
その足でアパートへ直接戻った歩は、カーテンを閉め切り頭から布団を被る。
店へ、気分が悪くなったと連絡を済ませ、歩は一切の連絡を絶った。
カーテン越しに、薄っすらと日差しが零れてきている。
まるで時間の感覚がなくなっていた歩は、その光が朝のものなのか昼のものなのか分からずに、天井をぼんやり見上げていた。
いつまた、持田が現れるのかと怖かった。付けられて来たんじゃないかと妄想に駆られ、ちょっとしたもの音に怯える有様で、布団から離れられなくなってしまっていたのだ。
歩は、気が変になりそうだった。
突然、玄関の鍵が開く音が聞こえ、歩はガタガタ震える。
落胆した歩の目から、大粒の涙が零れ落ちる。
玄関が開けられた風圧で部屋の扉が、音を鳴らす。
パッとドアが開き、一気に明かり差し込む。
歩は悲鳴とともに布団を払いのけ、部屋に隅へ逃げ惑う。
「ごめんなさいごめんなさい。殺さないで。お願いします。言うことを聞きますから」
「おい、落ち着きなさい。僕だ。昇だ。しっかりしなさい」
頭を抱える腕を解かれ、歩は目を見張る。
背広姿の昇だった。
「所長が、君と連絡が三日も取れないって、知らせて来たんだ。カーテンも開けずに何を」
「開けないで!」
カーテンを開けようとする昇に、歩は叫ぶ。
尋常じゃない様子に、昇は何かを感じ取った様子で、会社に連絡を取り、玄関の鍵を閉める。
「さぁ、これでよしだ。話を聞かせなさい」
ドカッと腰を下ろした昇に言われ、歩は忙しく瞳を動かす。
何から話していのか、分らなかった。
「歩君」
強く言われ、歩は持田のことをポツリポツリ話し始める。
「しかし、どうしてそれを早く、相談しなかったんだ?」
すべてを話し終わった歩に、昇は険しい表情を浮かべていた。
「すいません。こんなことになるとは、思っていなかったんです。それに、心配も掛けたくなかったし」
「心配って。あのな。一人で解決できる問題と、そうでないものがあるだろう? 現に命まで狙われて、もしものことがあってからじゃ遅いんだぞ」
きつい口調ではあったが、昇は眼鏡を曇らせていた。
「すいません」
歩は力なくうな垂れて、謝る。
「もしものことがあったら、僕は姉さんに何て言って謝ればいいんだ? 預かった者としての、責任はどう取ればいい?」
歩は、何も言い返せなかった。
「君は未成年だ。何をするにも、保護者責任というものが付いて回る、強いて言えば半人前だ。気を使ったつもりだろうが、それはかえって、迷惑だって、何故気が付かない? 君は、預けられている者としての、礼儀が分かっていない。「ホウレンソウ」っていうのを知っているかい?」
「野菜の?」
「いや、業務用の」
歩は俯いて、知らないです、と答える。
「「報告、連絡、相談」。これは社会を、円滑にさせる大切なものだから、覚えておきなさい」
昇は、嫌がる歩を連れ、警察に出向いた。
「警戒を強めてくれると言ってくれたが、これで本当に護られた事にはならないと思うから、用心はした方が良い。何ならしばらくうちに来るか」
歩は、首を横に振る。
一人になるのは怖いが、それで大切な人たちが傷付けられてしまう方が、耐えられないと歩が言うと、引っ越しをするかと昇が提案する。手続きや言い訳は僕の方でするから、君は何の心配もいらない。そうしなさい。何なら一度実家に帰るって言うのも手だがと言う昇に、住所は知られてないと思うからと様子をもう少し見させてくれと頼む。
大丈夫なのかいと顔を覗き込まれ、歩は、少し笑って頷く。
枯れ葉が風で道を転がり、柿の実が朱く夜空に浮き上がり寒々としている。
翌日、昇に付き添われて、歩は新聞配達の仕事を辞めた。
第二章 東京の空は果てしなく
一週間前身元不明の男性が電車へ飛び込んだ。被害届に記された人物像に類似していると、連絡を受けたのは夕べ遅くだった。親戚のものという男性が、持田本人と確認したと言う。歩は、複雑な気持ちで電話を切る。闇金融から、相当の額を借りてしまっているらしいという話は、所長から聞かされていた。
淡々と警察から教えられた内容を話し終えた昇は、これからことを尋ねられ、歩は返答に困った。
実家へ戻れというのが昇の意見だった。
しかし歩はそれに素直に頷けずにいた。
正直、人と会うのが怖い歩だが、昇の強い眼「このままと言うわけにはいかないだろ? 君を預かった以上、僕にも責任がある。悪い気とは言わない、もう一度出直すつもりで」
「それは出来ません」
どうしてそんな強気なことを言ってしまったのか、歩自身、分っていなかった。
「では聞くが、ここに留まらなければならない理由は、何かね?」
「分かりません」
「分からないって」
「分からないけど、分らないから、ここに残りたい。それではだめですか」
「そんな無責任な」
頑なに拒み続ける歩に、昇はほとほとあきれ果てたようだった。
目を合わせようとしない歩の肩を昇は叩き言う。
「とにかく仕事は見つけないと。なんなら所長に言ってもう一度使ってもらえるようにしてやろうか?」
やっと顔を上げた歩に、昇が頷いて見せる。
歩はああと思う。
絞り出すように礼を言い、大丈夫とくわえる歩に昇はそれ以上何も言わなかった。
朝を待って飛び上がった歩は、部屋を見回す。
嫌なことがあった時、君江がいつもそうしていたように歩もしてみようと思い立ったのは昨夜のこと。
怖い思いもさせられたが、持田を恨む気持ちはなかった。
思い出すのは、販売上で交わした会話や、一緒に遊びまわった楽しさばかりで、やるせなさで胸が痛んだ。
そんな時だった。
「腹が立つわ」
そう言っては、ムキになって家の掃除をしていた君江の姿を思い出したのは。
やけ食いならぬ、やけ掃除に、歩は何度となく、バカにしてきたのだが……。
「やってみると意外と気分が晴れるもんだな」
自然と笑みが零れる自分に、歩は驚く。
きっと昇から連絡を受けたのだろう。
携帯の電源を入れた歩は、眉根を寄せる。
呆れてしまうくらい入れられた着信履歴。
返答に困った歩はズボンのポッケトにしまいかけ、思い直す。
どんな言葉でも良い、待っている人への誠意は見せるべき。
短い言葉を綴り歩はまた電源を落とす。
部屋の片隅置かれた段ボールへ目を向ける。
それは今、君江の声を聞いてしまったら、くじけそうな気がしたからだった。
気は晴れたものの、何もする気が起きないでいる歩は、突然鳴ったチャイムに躰を固くする。
「歩、生きている?」
薫子の声だった。
急いでドアを開けた歩の顔を見て、薫子は吹き出す。
「何、死にそうな顔をしているのよ」
「どうしてここが?」
「さぁ。テレパシーかしら。いい男の匂いをかぎ分ける力だけはあるのよ私」
薫子の冗談を笑う気になれない歩だった。
「あんた、何で携帯切っているの? おばさん大騒ぎで様子見て来て欲しいって、うちに電話があったみたい。ママが来ても良かったんだけど、齢が近い私の方が話がし易いだろうからって。で、どうしちゃったわけ?」
詳しい話は聞かされていない様子を見て、歩は閉口する。
「仕事、嫌になっちゃったとか」
部屋を見回りながら聞く薫子に、まぁそんなところと、歩は嘯く。
「それでか。実家に戻る気がないなら、またうちへ来なさいってさ」
窓に寄りかかりながら薫子に言われ、歩はぎこちなく笑う。
「そうよね。やっと手に入れた自由を、そう易々と手放さないわよね。ここなら彼女も引っ張り込めるわけだし」
「彼女って、そんなのいないし、て言うか、薫子と一緒にしないでくれない」
「失礼な。までも元気そうじゃん。マジもっと落ち込んでいるのかと思った」
驚く歩を見て、薫子が意地悪く笑う。
絶句する歩に、薫子はカバンを取り出し一枚の紙片を渡す。
「働けよ若人。そして私を潤すがよい」
ふざけて言う薫子の顔を、歩はまじまじと見る。
「帰らないなら、稼がなきゃでしょ? うちが行っているバイト先を紹介してもいいけどさどうする?」
「自分で探してみる」
薫子はがっかりしたようでカバンを肩にかけ、そのまま玄関へと進んで行く。
「何?」
「見て分かんない? 帰るのよ」
「それは分かるけど、オレが自分で探すの嫌そうだったから」
「別に。じじぃがうるさいからハローワークの地図持ってきたけど、一緒のところで働いても有かなって思っただけだし」
「ひょっとして、オレのこと話しちゃったとか」
一瞬ギョッとした薫子だったが、すぐに開き直り、口を尖らせる。
「ええ言いましたけどそれが何か」
「いつ?」
「先ほどこの携帯で、イケメンの従兄が仕事を探しているって」
「で?」
「どんなイケメンかみたいから一度連れて来いと言われましたけど。一緒に行っていただけるのですかね」
怒った口調で言われ、歩は苦笑する。
面倒くさい状況になることは、歩でも分かった。
断る歩に、薫子は怒りを顕わにして帰って行った。
呆れもしたが、ホッとさせられた部分もあった歩はようやく外に出る気が起きる。
ハローワークへ出向いた歩は、そこで大きな問題に直面していた。
検索機の前、歩は固まる。
業種項目選びで、歩はやっと自分の愚かさに気づいたのだ。
でまかせではあったが、上京してきたのには理由があった。
嘘になってしまうのは嫌だと思った歩は仕事を選ばず、ハローワークを後にする。
歩は巨大なビルの谷間へ突き落された気分になる。
あの夏と同じだった。
敗北感が、歩の気力を奪っていく。
フラフラとした足取りで、歩は商店街まで戻って来ていた。
ヒーローになるって決めて来たのに……。
光彦や君江、そして中島の顔が目に浮かんでは消え、歩は目を潤ませる。
そんな時に限って、歩は思ってしまうことがあった。
持田なら、ひょとしたらその術を知っているかもしれないと。
自分でも気が付かないうちに、歩は持田に依存していたのだ。
弱い自分をもみ消してくれると、心のどこかで逃げ場所にしていた。
「責められたもんじゃないな」
歩は独り言ちて苦く笑う。
あんなことさえなければ、持田は良い兄貴分だったのに。
歩はつくづく思ってしまう。
歩は自分で頬を叩く。
今度こそ、一人で何とかしてみせる。
決心を新たに、歩は店先を一軒一軒見て歩く。
新聞配達をしているとき、何度も目にしたアルバイト募集広告。職種にこだわるつもりはない。できることから始めてみようと、歩は考えていた。
商店街は切れてしまい、あれほど見ていたはずの募集が見当たらなかった。
あと残っているのは数件。
国道沿い、転々と見える店を眺めながめる。
ゆっくりとした足取りで歩いて行く。
バタバタと風に煽られて、募集の文字が見え隠れしていた。
「理想だけでは生きていけない。現実に目を向けろ」
散々、光彦に言われた言葉だ。
中をそっと覗き見る。
まばらに座っている客と、きびきびと働いているウエイトレスが一人。
歩は大きく深呼吸をして中へ入って行く。
運命は自分で切り開く。
――歩は、隣に立っている御木脇(みきわき)にばれないように必死で欠伸を噛み殺していた。
深夜のアルバイトは、接客というよりこの睡魔との闘いが主だ。休憩が開けると満腹になった分、途端に眠気が殺人的に襲い掛かってくる。
入っている客はまばらで、することもなく、平和な時間が過ぎて行く。
「若いって、いいね」
御木脇の口癖が始まる。
髪をひっ詰めた御木脇恭子は、大人びた横顔で言う。
美希脇が働きだしたのは、まだ子供が小さかった頃。
寝ている間なら寂しい思いをさせないだろう、とこの仕事を選んだのだが、その息子も中学三年生になり、今度は学費が掛かるからこの仕事が辞められないと、入店初日に聞かされていた。
そんな歳の子がいる年齢には全然見えない。
化粧も、薫子のものとは比べようがないくらい自然で、嫌味がない。
「また、そんなことを言って」
女子大に通っている中村が長い睫をぱちぱちさせながら言うと、御木脇はしみじみと言い返す。
「だって本当のことだもの」
今日はやけに実感がこもっているな、と歩は改めて、三木脇の顔を見る。
「どうかしたんですか?」
ドリンクバーのグラスを補充しながら訊く歩に、御木脇はわざとらしい溜息を吐く。
「中田君、ここに来てどのくらい経った?」
「どのくらいって? まだ数えるほどしかいないですよ、オレ」
「そうでしょ。だけど、言わなくてもおおよその仕事の流れは分かるようになったでしょ?」
「何となく」
「それが若い証拠なのよ。これがね~歳をとると、そう簡単にはいかないの。もう地獄の忍耐力よ」
大げさな表現に、中村がケタケタ笑い出す。
「笑いごとじゃない」
御木脇が溜息交じりで言うと、事情を知っている中村が笑いながら歩に教えた。
「中田君より少し前に入ったパートさんがいるんだけど、その人が究極なのよねぇ御木脇さん」
御木脇は首を竦め、接客に向かう。
「それがなんで、御木脇さんの溜息になっているの?」
面と向いて歩に訊かれ、中村は直視できずに目を逸らした。
「扱いづらいんだって」
歩は何となく御木脇を目で追ってしまう。
「ちょうど帰ってきたから本人に訊いてみたら? 私、トイレ掃除に行って来るから」
「私の顔に何か付いている?」
歩の視線に気が付いた御木脇は戻るなり訊いた。
「なんか、さっきの話が気になって」
「ああ、その話か。大したことじゃないの。ちょっと勝手が違う人で困ったなと思って」
「勝手って?」
御木脇は眉間に皺を寄せ、難しい顔をして見せる。
「仕事だから、必死で覚えてもらわないと、困るのよね。性格だから、歳だからなんて言語道断でしょ? ミスだって、最初は仕方がないわ。でも、繰り返さないように努力は必要だと思う。彼女はそれが出来ないのよ。店長は経験者だから、安心しているみたいだけど、だから教えづらいってこともあるのよ。一番困るのは知ったかぶりよ。前の店ではどうだったかは知らないわ。でも、ここでは、ここのやり方があるの。きっと、これは私だけのこだわりだと思うけど……、参ったな。中田君に、こんなこと言っても仕方がないんだけどね。嫌ね、歳をとると愚痴っぽくなって」
御木脇の目には、薄っすらと涙が浮かんでいた。
この強気な御木脇を、こうも困らせる人物ってどんな人なんだろう?
歩は軽率だが、そのおばさんに会ってみたいと思った。
12月に入ると、埃臭い国道沿いもイルミネーションが施され、幻想的な雰囲気を醸し出している。
店の前にも大きなモミの木が置かれ、色とりどりのライトがともされる。
「中田ちゃん悪い。明日から夕方からのシフトに変更ね。入りは5時からで、10時に上がれるよ~ん」
小太りでいつも制服が窮屈そうに見える店長の百瀬に、軽い口調で言われた歩は苦笑する。
「断る余地はないんでしょ」
「当然。中田ちゃんだって、特別断る理由なんてないんでしょ」
店長の無責任な感じが、歩は好きになれずにいた。
御木脇が愚痴るのも何となく納得いく。
毎度のことだから慣れたけど、今日だってそうだ。
「バイトの子が一人休みが入っちゃったから、中田ちゃんロングでお願いね」
「オレ、今日は」
「良かったよ。君が入ってくれて」
にっこり微笑んで、まったく聞き耳を持たずに本社へ出かけられてしまったのだ。
さすがに歩もこの扱いには、腹を立てていた。
込み始めた店内。
何組か入口で並んで待っていた。
平日にしては尋常ではない込み方に、歩は顔を顰める。
テーブルを片し終わって戻った歩は、新たな客の来店に接客に向かう。
「こちらにお名前を」
事務的に言う歩は、客のえっと言う声に初めて顔を見る。
そして二人同時に、ええーっと声をハモらせてしまっていた。
久しぶりの再会だった。
「中島」
「中田。久しぶりじゃん。元気していたか?」
「まあ一応」
待ち合い席の客が、怪訝そうにそんな二人を見ていた。
ハッとした歩が営業用の口調に戻る。
「お客様、喫煙されますか?」
「いいえ」
吹き出しそうになりながら、中島に応えられ、歩は顔を火照らす。
「大変申し訳ございません。本日大変混み合っておりまして、一時間ほどお待ちいただくようになりますが、お待ちになられますか?」
「ああ、構わないよ。ここに名前を書けばいいんだよな」
「順番が来ましたらお呼びいたしますので、こちらでお待ちください」
店内へ戻って行く歩を、中島は眩しいそうに細めた目で追う。
休憩に入った歩は、喩えようのない脱力感に見舞われていた。
実に情けない話である。
あれほどまでに啖呵を切って野球を辞めたのに、自分ときたら上京してきた目的すらつい最近まで、忘れていた有様で、それに比べ中島はしっかりと目へ突き進んでいる。帰り際、差し出された名刺を見せられた時、歩は言葉を失ってしまっていた。
「何やってんだオレ」
一人ご散り、自ずと深いため息が出ててしまう歩だった。
そんなことをぼんやり考えていた歩は、後ろから暖かなものが頬にあてらえ、焦って振り返る。
「おはよう」
出勤して来たばかりの御木脇だった。
「鯛焼き、おいしそうだから買ってきちゃった。一緒に食べよう」
髪をきっ詰める前の御木脇は、どこか柔らかく見える。ニット帽を外し、マフラーを取りながら、歩の隣に陣取った三木脇がたい焼きを歩に一つ渡しながら、自分もおいしい層にかぶりつく。
「もうこの時期は嫌になっちゃう。混んでいるから、出勤時間を繰り上げてくれって、店長から連絡が来ちゃって、稼げるのは有難いけどさ。これ当たり。尻尾まであんこ入っている。ほら中田君も冷めないうちに食べて食べて」
「まじっすか?」
「あのね中田君、前から言おうと思ったけど、君、言葉足りなすぎよ。今のだって、出勤を早められたことなのか、あんこが尻尾まではいいているのか、どっちに対しての言葉か分からないじゃない」
「すいません。両方の意味です」
「あら、そうなの。これは失敬」
軽く笑いあった後、御木脇は更衣室へと消えて行き、歩はたい焼きを尻尾からかぶりつく。
御木脇が言うように、あんこが甘すぎずにおいしかった。
御木脇の差し入れは、歩好みが多い。さりげなくした会話を覚えているらしく、今まで一度もはずしたことがない。
食べ終わってお茶が恋しくなり、立つのも面倒だなと思っていると、目の前にお茶が出て来て、歩は驚く。
「お茶が飲みたくなったでしょう?」
当然そのままホールへ出るのかと思った御木脇が、自分の前に腰を落ち着かせるのを見た歩は、少し目を大きくし見詰める。
歩の心を読んだのか、御木脇は少し早めに来たから、と、含め置きして躊躇いがちに言葉を言い繋いだ。
「あの、頼みがあるんだけど」
御木脇のあら余った言い方に、歩は襟を正す。
「そんな畏まらないで、尚更言いにくくなる」
苦笑いで言われ、歩は尚更、何事だろうと思う。
フッと笑った御木脇が、嫌だなーと言いつつ、お茶を口へ運び、ようやっと本題に入る。
「不躾で申し訳ないけど、今度、うちの息子と会ってくれない?」
「息子さんに?」
突拍子もない話に、目を丸くした歩は思わず訊き返しいた。
「実はうちの子、あなたのファンなの」
しばしの沈黙が流れ、御木脇が静かに言い繋ぐ。
「君、野球していたでしょ?」
薫子たちが言っていた通りだと、歩は改めて思う。
「まぁ一応」
一呼吸置いて応えた歩に、ホッとしたような顔で、御木脇は一気に用件を話し始めた。
「うちの子も野球をずっとしていてね、今年高校受験を控えているんだけど、何を考えているのか、さっぱり分からなくて、困っているよ。反抗期なのかしらね、私が言いうことなすこと全部気に入らないようで、もうどうしていいのか。こんなこと頼むべきじゃないって、重々承知している。こんなこと頼まれて、困るだろうなとも思った。だけど私も切羽詰っているの。どうかこんな愚かな母親を助けると思って、中田君からひとこと言ってもらえないかしら。君が一緒に働いているって話したらうちの子、目をキラキラさせて、会って話してみたいって言うの。まともに話せたの久しぶりで、お願い。この通り」
御木脇に両手を合わせられ、歩はフッと笑みを零す。
「オレも勉強しなかった口だしな。役に立たつかどうか分からないけど、会うくらいならいいですよ」
「本当。ありがとう」
パッと顔を明るくする御木脇と、君江が重なり、歩の胸がチクンと痛んだ。
本来立つ場所へ行くべきなんだろうな、そう思いT載る歩だったが、その術が思い当たらず、暗い気持ちになるばかりだった。
行き交う人の塊を、歩は珈琲を飲みながら眺めていた。
人懐っこい笑みで手を振る御木脇を見つけ、歩は軽く会釈をする。
二人して休みが合うことがなく、だいぶ日が経ってしまっていたが、まだ受験勉強に身が入っていないらしく、無理やり歩の休みに合わせて今日を選んだ、御木脇の親ごころには、脱帽である。
「うちの息子、御木脇啓太です。今日は無理言ってごめんね。今日は私の奢り。好きな物食べて」
三人は場所を変え、落ち着きのある和風レンストランの席に着いていた。
丸刈りの少年が、歩の前でしゃんと背筋を伸ばして座っている。御木脇にあまりにそっくりで、歩の顔が綻ぶ。
「ごめんなさいね。折角の休みなのに。ほら、敬太からもちゃんとお礼を言って」
「大丈夫ですよ。そんなに気を使わなくても。オレ暇だったし」
そう言いつつ、歩は啓太をチラッと見る。
啓太の羨望の眼差しにさらされ、歩は照れ臭かった。
「野球やっているんだって?」
啓太の覇気が良い返事に、歩は目を細める。
かつて自分がそうだった。
懐かしさとほほ笑みさが、入り混じる。
「ポジションは?」
「ファーストです」
「へぇ、内野手か」
ウエイトレスが料理を運んで来た。
人と話すことをあまり得意としない歩である。上手く言葉が繋がらず、ぎこちない会話になってしまっているのは、自分でも痛いくらい分っていた。
「私たちってどんな風に見えるのかしら?」
そんな二人を見かねてだろう、御木脇がそんなことを言い出したのは。
歩は唸って見せた。
この雰囲気を変えなければと思っていたのは、歩も同様。
啓太だけが意味不明なことを言い出した母親に、怒りの目を向けるが、御木脇はさらりとそれを交わし、歩は心の中で感嘆する。
「敬太も一緒だから、恋人同士じゃないわね」
「強いて言えば、年の離れた姉と弟。まぁ親子には見えないだろうと思うけど」
一笑しあったのち、御木脇が啓太を炊きつける。
「啓太、中田さんに訊きたいことがあったんじゃないの?」
「訊きたいことって、何?」
反抗期とは言え、そこはまだ15歳。顔を赤くした啓太が遠慮がちに歩に質問してきた。
「中田さんはどうして、プロに進まなかったんですか?」
「う~ん、やっぱりそこか」
痛いところを突かれ、歩は頭を掻く。
ウソを吐こうと思えばいくらでもつける。けど、歩はまっすぐ見つめる啓太に真摯でいようと思った。
「オレ中学三年生の夏に、はたと気が付いてしまったんだ」
「気が付いたって、何をですか?」
「オレ、野球がしたかったのかなってさ」
御木脇親子が顔を見合う。
「だって、ちゃんと甲子園まで行って、活躍していたじゃない」
御木脇に口を挟まれ、歩は苦笑する。
「あれは惰性。親に言われて仕方なく」
「仕方なくでも何でも、あそこまで頑張れたのは、君の才能でしょ? そう易々と捨てれるものなの?」
つい熱くなってしまった御木脇が、しまったと言う顔をし、頭を下げる。
「才能って何なんでしょうね。甲子園へ行った。でもそれはオレだけの力じゃなかったし、たまたま運が良かった、と言うと怒られそうだけど、なんか違う気がして」
「じゃあ君はどうして頑張れたの? やりたいことでは無かったら、そこまで頑張れるとは、私には思えないわ」
「僕もそう思います。いくら頑張っても才能に目がない奴はレギュラー入りなどできない。ましてや甲子園なっかいけないし、プロから誘われるなんて以ての外だと思います」
啓太に身を乗り出して言われ、歩はたじたじになる。
「そうか、そうだよな。でも、オレはオレを貫き通したかった」
歩は自分の言葉を噛みしめていた。
納得いかない御木脇親子が、首を傾げる。
「そこまで言うには、何かやりたいことでもあるの?」
御木脇の質問に、歩は即答することが出来なかった。
言葉に行きつまった歩に、啓太が言い募る。
「僕、中田さんがプレーするとこ、またみたいです」
「そうよ。手段はまだまだあるはずよ。答えを出すよ、早過ぎよ。故障とかじゃないのならだけど」
言葉では説明できない自分の中のもやもやに、歩は歯がゆかった。
「ごめん。のこのここんなところへやって来たけど、君にアドバイスすることなんて、オレにはできない。今も迷走中だし」
「じゃあ野球はもう」
「しないと思う」
その言葉に偽りはなかった。
気まずさをかき消すように、御木脇が明るい声で帰りを促され、その場は終わった。
別れ間際、敬太にサインをせがまれ、仕方なく色紙に大きく自分の名前を書いた歩は、我ながら汚い字だなと呟き、渡す。
「オレ、これ大事にします」
嬉しそうに胸に抱く敬太を見て、こんな自分を大事に思ってくれていると思うと、歩は目頭が熱くなった。
「その横に一言添えてよ」
御木脇の要望だった。
人生何が起こるか分からない。
迷うことなく、歩はこの言葉を書き添えた。
「渋いこと書くわね」
「そっすか? 多分、この言葉があったからかな」
呟くように言う歩の顔を、御木脇が不思議そうにのぞき込む。
「さっきの質問の答えになるか分からないけど、オレ、この一言に尽きると思ったんです。やりたいことがるなら、可能性があるなら、それに自分を掛けてみようて」
照れ笑いをした歩が、啓太の頭をガシガシと撫でる。
「何が起こるかなんて、誰にも分からない。だから、オレは、自分の気持ちに正直にいようと思って、生きている。敬太君も今、何がしたいのか、それをするにはどうしたらいいのか、よく自分の声を聞くといいよ」
「はいっ」
気持ちの良い返事である。
軽く手を挙げ、別れを告げた歩を啓太が呼び止める。
「中田さん、もし良かったら、オレの練習に付き合って貰えませんか?」
「ごめん。その頼みは聞けない」
「どうしてですか? 遊びのようなものですよ。それくらいなら」
「だからこそ、オレはやらない。それはオレを信じて羨望してくれたみんなに対して失礼なことだし、野球の神様に対しての冒涜だと思う。だからオレは一切、野球とは関わらない」
「気負い過ぎよ。そのままだと、自分で自分の身を亡ぼすことになるわよ。もっと肩の力を抜いて、人生はまだまだ先が長いのよ」
歩は、苦笑するしかなかった。
言われていることも、このままではいけないことも分かっている。だが、どうしていいのか分からないのも実情。虚しさが胸を突きあげる。
歩が目を反らしてきたことを目の前に突き付けあたような気がした。
御木脇親子が帰って行き、一人残された歩はポケットに手を突っ込み、背中を丸める。
やたら寒さが身に染みた。
歩はふと足を止め、指先にあたっていたものを取り出す。
駅から続く青白いライトが縁取る道を歩いている途中、歩はふと立ち止まり振り返る。何の変哲もないこの道もライト一つでこんなにも見違える。一人取り残された気分だった。無性に人に話したくなり、携帯を取り出す。
ひんやりした風が頬を撫でて行く。歩は、国道沿いのガードレールに座り、ぼんやりと夜空を見上げる。
東京に来てから、こうやって空を眺めることなどなかった。見るもの、聞くものすべてが初めてで、馴染むことに必死だった気がする。
駅前の賑わいと違って、国道は静かなものだ。人通りもまばらで、車も、時折通って行くだけだった。
小さなライトがだんだん近づいて来る。それに気が付いた歩が立ち上がると同時に、クラクションが短く鳴らされ、静かに目の前で止まる。
白のカローラ、中島の車だ。
窓が開き、お待たせと中島が顔を覗かせる。
「悪りぃな」
「悪くないよ。ちょうど今日は練習が休みだったし」
助手席に歩が座ると、中島はすぐに車を走らせる。
「久しぶりだよな」
そう言う中島に、うんそうだよなと言いながら、指を折り始める。
「ずいぶん会っていない気がするけど、まだ一年もたっていないんだな。なかじぃ、老けた?」
「人のことを年寄り扱いにするな。お前の方が誕生日は先だろうが」
「なんかさ、ますます貫禄が付いたよな、その眉」
「うっせー」
そう言って二人はゲラゲラと笑い出す。
中島は、卒業式の時より数段運転が上手くなっていた。
「さて大将、これからどうしましょ?」
「うん。中島は飯食った?」
「食ったけど、食えないわけじゃないから、どっか行くか?」
「いや、オレも食った」
「じゃあ、どうする?」
「う~ん、この先の道を真っ直ぐ行って、交差点を左に折れる。百メートル先にコンビニがあるからそこで飲み物を買ってだ、またその先を少し行ったところにぼろっちぃアパートがあるから、そこまで旦那御願いします」
「何だそれ?」
「オレんち、狭いけど気兼ねなくのんびり出来る」
歩の提案に、中島は笑って承諾した。
一年も満たない再会のはずだが、大人びて見える中島が眩しくて仕方なかった。
依然とはまるで違う運転ぶりに、歩は軽く口笛を吹く。
意味もなく笑いあう二人にわだかまりはもうなかった。
招待された部屋をもの珍しそうに中島が、見まわす。
「男の一人暮らしって聞いたから、もっと散らかっているかと思ったけど、綺麗にしてんだな。俺の部屋も掃除してくれよ」
「こんなの普通だよ。一間しかないから片付けないと寝る場所もなくなっちゃうから仕方なくやっているだけで、しまえるものは全部押入れにぶっこんで、あとは見ての通り端に寄せて積み上げれば出来上がりだ」
「それって、片付けって言わないよな?」
「言わない」
あっさりと認める歩に、中島は腹を抱えて笑い転げる。
「とにかく乾杯だ」
「酒じゃないのが残念」
「まだ言うか」
「だって、なかじぃならいけると思ったから」
そう言う歩を、中島が羽交い絞めにする。
「ごめんなさい。もう言いません。ギブです。許して~」
そして、二人で大笑いして、あまりの煩さに壁を叩かれ、シーッと二人は口に指を当てた。それがまたおかしくって、声を堪えてまた笑う。
上京してからの話は尽きない。
あっという間に時間が過ぎていった。
中島は大学野球の厳しさと面白さを延々に語り、歩は聞き役に徹した。
自分の中にあるもやもやを聞いて欲しくて中島を呼んだのだが、いざ話そうとすると言葉が見つからずにいる。
明け方、二人は漸く眠りに就いたが、一時間もしないで、アラーム音がけたたましく部屋に鳴り響く。
歩は横で眠っている中島に目をやり、今日くらいは良いか。と呟くが思い直して起き上がるとそっと部屋を抜け出す。
早朝のピンと張り詰めた空気が心地良い。
寝不足で気だるさはあるが、悪くない。
不本意に仕事を変わってしまったことや、敬太の言葉がグルグル頭を駆け巡る。本当にこれで良かったのか、もう一人の自分が問いただしてきていた。
答えを出せないまま戻った歩を、大の字になり高いびきの中島が出迎える。
図体が大きい割にかわいい寝顔をしていると、ことあるごとにからかったことを思い出し、歩はフッと口元を緩ます。
難しく考えても仕方がないこと。
バスルームへ姿を消して行く歩を、中島は薄目を開けてみていた。
「悪い癖だな。一人で抱え込みやがって」
寝返りを打ち、中島は一人ごちる。
言葉にしなくても、歩が何か悩んでいることは、嫌になるくらい伝わって来ていた。
あの日からずっと頭から離れなかった。
シャワーを浴び終わった歩が出てくる音に気が付いた中島は、固く瞼を閉じ直す。
音だけで何をしようとしているのか、想像できた。
瞬く間に良い香りが鼻を衝き、喩えようのない幸福感に心が満たされていくのが辛く鳴きそうになっている中島のことなど知る由もない歩である。
手際よくコーヒーを淹れ、サンドウィッチを作り終え、しばしなかじまの背中を眺めた末、尻に一発けりを入れる。
すぐに起きない中島にもう一発お見舞いした歩は、テレビを点け部屋を片付けだす。
わざとらしく目を擦り起き上った仲居島は、目の前に作り立ての食事を並べられ、慌ててトイレへ駆け込む。
「なかじぃ、早く出ろよ。コーヒー冷めるだろ」
ノックを強くしながら言われ、中島は自分の顔を叩き仕切り直し出て行く。
「うっせーな。トイレくらいゆっくりさせろよ」
「ちゃんと手を洗えよ」
「おまえ、その癖まだ治ってねーのな」
「は?」
「マネージャーの仕事、取らないように言ってください」
かつて中島に訴えてきたマネージャーの口まねをして見せた。
「ウワーッ。出た。吉江だ。折角の親切を台無しにするやつ」
「ちげぇだろ。明らかにお前が間違っていただろ。仮にもレギュラーのお前がする仕事ではなかったよな」
「そっか。そんなの関係ないと思うけどな。まいいや。早く食べなよ。今日も練習あるんでしょ?」
時計を見上げながら言う歩に、中島は盛大なため息をついて見せる。
何食わぬ顔でサンドウィッチを一つつまみ口へ運ぶ歩に倣って、中島も一口齧り顔を綻ばす。
芝居がかっていて胡散臭い。
「美味い。おまえ料理できるんだ」
「ああいう仕事をすると、簡単なものは作らされるんだ」
「へぇ。料理を運んでいれば良いだけかと思っていた」
中島は感心しながらコーヒーを一口飲んで、美味いと、いちいち唸ってみせる。
「オレも最初は驚いたけど、今ではデザートなんかもちょちょいのちょいだぜ」
歩が胸を張って見せる。
ひとしきり笑った歩は、テレビを点ける。
「今日、練習は何時から?」
表示されている時間を見た歩が訊くと、中島は携帯を開きスケジュールを確認する。
「今日は……三時からだ」
「じゃ、もう少し寝ていけば」
歩は、中島のカップになみなみとコーヒーを注ぎ直した。
中島は隅に積んである本を一冊手に取り、首を傾げる。
……太極拳?
「ところでおまえ、例の夢はどうした? 俺にはただのフリーターにしか見えないけど?」
本をぺらぺら捲くる中島に訊かれ、歩は一瞬動きを止める。
「ちゃんと探しているよ。ほらこうやって」
何の躊躇いもなく積んであった本の一番下から求人雑誌を引っ張り出すと、歩はニカッと笑った。
「おまえ本気か? どこの世界に、求む! ヒーロー戦隊。時給850円って広告が出ているんだよ?」
「違うの?」
「あのな……」
冗談冗談とへらへら笑ってみせる歩に、中島は冷ややかな視線を送る。
「おまえ、その話題を避けていただろう?」
ば、ばれている。
いやぁそのーえっとーと、その後の言葉が出てこない歩を見て、図星かよと食べかけのサンドウィッチを口の放り込み、コーヒーで一気に胃袋に流し込ませた中島は立ち上がると、ほれお前も立てと歩の腕を引っ張った。
「どこ行くんだよ?」
「ネットカフェ!」
「ネットカフェ? 何しに?」
「おバカなお友達が、夢を叶える為に情報を仕入れに行くんだよ!」
WISH。

