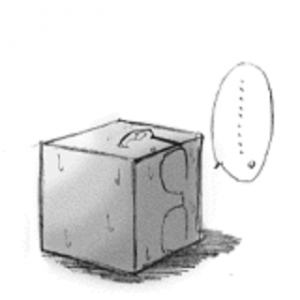安達原異説
──能『安達原(黒塚)』(註一)より
今は昔──神龜丙寅と申しますから、聖武天皇の御代のことでございました。奈良の都から遠く離れた陸奥国では蝦夷が叛乱して陸奥大掾・佐伯児屋麻呂様が弑され、これを誅するために藤原宇合様を持節大将軍とした軍勢が都から遥々遠征するなど、北の国は些か騒然としておりました。
さて、蝦夷と陸奥の境である多賀城より南西に三十里ほどの処に、安達原と申します、広い広い草原がございました。陸奥国でも屈指の大河・阿武隈川の東岸で、人の背丈よりも高い草に覆われて目印となる安太多良山も見えず、その頃は辺りに住まう者も往来する者も少なく、たいそう寂しい場所であったそうでございます。
いつの頃からか、この場所を通る旅人には、奇妙な噂が流れておりました。
曰く、安達原には旅人を殺してその肉を喰らう、鬼が棲む、と。
なにしろ都から遠く離れた鄙の地でございます、そのような噂は特に珍しいものではございませんでした。この時代、街道とは名ばかりの足踏み道でございましたから、一足そこから外れれば忽ち深い森に迷い込み、或いは川に落ち、そのまま命を落とす者も少なくございませんでしたし、村落を出れば追いはぎ・夜盗の類が常に旅人を狙っていたような時世でございます。しかし、安達原に異類が棲むとの噂は、日ごとに強くなるばかりでございました。安達原の周囲の村々には、帰らぬ夫や息子を知らぬかと尋ね歩く狂女の姿も日ごとに増え、人喰いの鬼の噂はいつのまにか方々に拡がっておりました。しかし、安達原に何がいるのか、自ら確かめようとする者は、誰ひとりとしておりませんでした。
さて、その年の長月暮れ、紀伊国は那智の東光坊阿闍梨祐慶という修験僧が、廻国修行のため各地を渡り歩く途上、お供の僧とお二人でこの地にお立ち寄りになりました。聖武天皇が大仏建立の詔をお出しになる前のことでしたから、かような鄙の地に僧侶が訪れることは稀なことでございました。村の者の言うことに、この先の安達原には人喰いの鬼が棲むゆえ、死にたくなくば引き返して海沿いを北上されるのがよかろう、と。東光坊様は仏法を奉じる修験者でございましたから、そのような噂は根も葉もないこと、と相手になさいませんでした。学問を究めて衆生を導く僧侶として、そのような噂に怖じて引き返すのは恥だと考え、それならば本当に鬼が棲むか、拙僧が確かめてみよう、と仰せになりましたので、村の者たちはたいそう驚いて東光坊様をお引き留めしましたが、東光坊様はかような鄙の地にも遍く仏法をもたらすために私は来たのだと言い、どうしても安達原に入ると仰います。村の者たちはやむを得ず、村のうちで最も勇気のある若い男子を選んで、強力(荷運び夫)として東光坊様の道案内に付けることにいたしました。阿武隈の流れに沿うて歩き続けるうち、秋の短い陽は忽ちに落ち、西の空に赫々と輝いた残照もたちどころに失せ、辺りはすっかり暗くなってしまいました。
なにせ、ただただ草地が広がるばかりの寂しい場所でございます、月影もない闇夜、星々で方角を確かめつつ松明の明かりでそろそろと歩んでおりました一行でございましたが、折からの風に流された雲で次第に空は覆われ、いつしか道を見失うてしまいました。獣の遠吠えの声、水鳥の羽音など、僅かな音でさえも怖気をかきたてます。北国の風は冷たく吹きつけ、誰も一言も発することができず、ただ黙々と歩み続けておりましたところ、東光坊様のお供の僧が遠くに灯りを見つけたのでございます。人けの全くない草原に急に灯火が見えたことに、東光坊様は少し不思議の感を抱きましたが、人心地がついたお供の僧は強力の若者を先頭に立たせて先を急ごうといたします。東光坊様もその後に随って、一行は灯りを目指して急ぎ進みました。
そこは、小さな小屋でございました。岩屋の前の地面を掘って竹を両側から渡した上に藁を葺き、板塀を立てて土を塗っただけの、都の周りではもう見なくなった古い形の住居でございました。
灯りは屋根の隙間の明かり取りから漏れております。中からは細く立つ煙と共に、次のような声が聞こえてまいりました。
「げに、侘人の習ひほど、悲しきものはよもあらじ。かゝる憂き世に秋の来て、朝けの風は身に沁めども、胸を休むることもなく、昨日も空しく暮れぬれば、睡む夜半ぞ、命なる。あら定めなの生涯やな」
どこか疲れの色が滲んだ、女の声でございました。ああ、このようなわびしい身の上ほど悲しいものはないであろう、かくも苦労の多い世に心休まることもなく、空しく暮れて眠るだけの生涯がわたしの定めなのだろうか──女は誰に語るともなく、ひとりごちていたのでございます。
「申し訳ないが、この家に入れてはもらえないだろうか」
東光坊様は恐る恐る小屋の内に向けて声を掛けました。
「おや、どなたさまでございましょう」
「旅の者でございます。陸奥国に初めて入り、この安達原にたどりつきましたが、道に迷ってしまいました。どうか私どもを憐れんで、一夜の宿を貸してはいただけないでしょうか」
小屋の主は少し考えた後に、このように答えたそうでございます。
「人里から遠く離れた野辺の、粗末な小屋でございます。冷たい松風が吹き抜け、月影すら届かぬようなこんな小屋に、お泊めするわけにはまいりません」
女は粗末な小屋を羞じている様子でございました。東光坊様はなんだそんなことか、と思いながら、なおも懇願いたしました。
「旅の途中の仮寝でございます。もてなしなど不要、どうかお泊めください」
「妾ですら落ち着かぬようなこんなところでは──」
「いえいえ、どうか」
樞を挟んでそのようなやりとりを幾度か繰り返したのち、主はそこまで仰るのなら、とようやく樞を開けたのでございます。小屋の主は、どこか憂いを帯びた年増の女でございました。麻で織った簡素な着物、少しほつれた髪には白いものが混じっておりました。一行が招き入れられた小屋のなかには、茅の筵が敷かれており、地面を掘っただけの床にはところどころ雑草が生え、焚火が小さく燃えております。女の申した通り、ごくごく粗末な小屋でございました。女はすっかり恥じ入った様子で、小屋の隅に控えております。女の背後には筵が掛けられており、元々あった岩屋に続いているようでございました。
「今宵のお宿、まことにありがたく存じます」
東光坊様は炉端にくつろぐと、女に丁重に礼を述べました。このような人けのない野辺になぜ女が一人で暮らしているのだろうと不審に思いながらも、寒風で冷やされた躰が炎で暖められると、それまで張り詰めていたものがふっと緩んでまいりました。女は小屋の隅でただただ恐縮しておりますが、東光坊様はその脇に、見たことのない道具があるのを目にされました。
「おや、そこにある道具は見慣れぬものですが、なんと申すものでございますか」
「これは枠桛輪と申します。妾のような賤の女の生業には欠かせぬものでございます」
枠桛輪とは、麻糸を繰るための糸車のことでございます。小さな台の上におよそ一尺四方の枠が載っており、糸が巻き付けられております。そこから延びた糸は隣の台に横向きに取り付けられた小さな枠に繋がっており、そこには把手がついておりました。
「これは珍しい。夜もすがら、どうかひとつやって見せてはいただけませんか」
「いえいえ、このような賤しい業、お見せするほどのものではございません」
東光坊様は女がすっかり恥じ入っているのをよいことに、少々無遠慮な態度となっておられましたが、女は硬い表情のままじっと焚火を見つめております。その瞳に焚火の炎が映り、ゆらゆらとうごめいておりました。
「あなたは、実に情け深いかただ」
東光坊様が焚火を眺める女の眼をじっと見つめて語りかけますと、その声に女は少し顔を上げ、じっと何かを考えておりましたが、おもむろに枠桛輪の前に座りますと、把手を握ってゆっくりと回しはじめたのでございます。
「賤が績麻の夜までも、世渡る業こそ、物憂けれ」
女はゆっくりと糸を繰りながら、歌うようにつぶやくのでございます。
「浅ましや人界に生を受けながら、かゝる浮世に明け暮し、身を苦しむる悲しさよ」
せっかく人として生を受けたにもかかわらず、このような賤しい身の上で苦労の多い生活をしなければならない、なんと悲しいことか、と女は嘆くのでございました。
「かように儚いことを仰るな、まずは生身を助けなければ、成仏の縁もございませぬぞ」
東光坊様はもの悲しげな女の様子にいたたまれなくなり、思わず力を込めて仰いました。
「明け暮れ暇なき身なりとも、心だに誠の道に叶ひなば、祈らずとても終になど、仏果の縁とならざらん」
日々の生活に追われているような身であっても、真実の道に心が適っているならば、祈らなくても必ずや成仏の機縁となるでしょう、と東光坊様は女を慰めようとしたのでございます。しかしながら、この時代に伝わっておりました仏法には、まだ女人成仏を説いた教えはございませんでした。無論、東光坊様は女人が成仏できぬことをご存じであられましたが、あまりに女がもの悲しい様子であったので、何とか慰めずにはおられなかったのでございましょう。しかし、女は枠桛輪を廻しながら深い諦めの混じった調子で続けました。
「この世にしばらく仮の生を受けたとして、六道を輪廻して延々と生死を巡るだけで、心は迷うばかりでございます。どのような者でも、今よりも若いということはなく、最後には老いて死ぬるさだめ。かように儚い夢のような世を厭うわけではございませんが、むなしい心を恨んだところで、仕方のないことでございましょう」
女は廻る枠桛輪を見つめて、静かに涙を流しておりました。
「穂に出づる秋の糸薄、月に夜をや待ちぬらん。今はた賤が繰る糸の、長き命のつれなさを、長き命のつれなさを思ひ明石の浦千鳥、音をのみひとり泣き明かす、音をのみひとり鳴き明かす」
女は糸を繰りつつ、麻糸に譬えて長く生き過ぎてしまった自らの命のむなしさを嘆き、明石の浦の千鳥が一羽で鳴くように、ひとり泣き明かしているのです、と切々と歌うのでございます。東光坊様は不思議な心地でおられました。この女、今は賤しい姿で鄙に一人住まっているが、教養もあり、当意即妙な機知にも富んでいる、何か事情があるのやもしれぬ、とひとり考えるのでございました。
さて、夜も更けて晩秋の空気はいよいよ冷えておりましたが、思わぬ長話で薪の蓄えが少なくなっておりました。女はおもむろに立ち上がり、東光坊様に申しました。
「今宵は余りに冷えております。妾が薪を集めてまいります。しばらくお待ちいただけませんでしょうか」
「お気持ちはありがたいが、このような月もない真夜中に女性がひとりで出かけるなど……」
「いえ、妾はこの辺りのことを知悉しております、ご心配には及びません」
「それではお待ち申そう、早々にお戻りくだされ」
それでは、と樞を開きかけて、女はふと東光坊様を振り返り見て、こう申しました。
「妾が帰るまで、この閨の内は、ご覧になりませぬように」
女は、狭い小屋の奥に掛けた筵の向こうを指しながら東光坊様をじっと見つめたのでございます。その顔には、何か真剣さが漂うておりました。
「心得た、決して見るようなことはせぬ。安心して出かけられよ」
東光坊様は女の真剣さに気圧されつつ、はっきりとお答えになりました。
「そちらのお供のお坊様も、決してご覧になりませぬよう」
「心得ております」
女は東光坊様のお供の僧にも念を押すように繰り返し、しかと約束したことを確かめると、樞を開けて外へと出ていったのでございます。
女がいなくなりますと、三人の男だけが残されました。互いに言葉を交わすこともなくしばし焚火を見つめておられるうちに、東光坊様とお供の僧は昼間の疲れが出たのか、うとうとと微睡まれたのでございました。さて、その中でひとり、強力としてついて参った若者だけは、眠ることができずにおりました。
どうも変だな、と若者はひとり腕を組んで考えました。坊様と女が話したことはよくわからんが、こんな夜更けにひとりで平然と出かける女がいるだろうか。ましてここは、鬼が棲むという安達原。あの女、何か秘密があるに違いない。閨といってもただ筵が掛けられているだけ、見るなと言われると殊更に見たくなるのが人の習いだ。坊様は女に決して覗き見るようなことはせぬと約束されたが、おれは約束したわけではないからな。いやいや、いけない。おれは坊様のお供だから、坊様の約束は、おれの約束だ。だが、見たい。いったいあの閨の内に、何があるのか。見たい。坊様はすっかり眠っておられる。今ならば気づかれまい。おれだけがこっそりと覗いて、何も見なかったことにすればよい。そうだ、それならば坊様は約束を違えたことにはならぬ。
若者は二人の僧が眠っていることを確かめると、物音をたてぬよう、ゆっくりと筵の方へ近づいてまいります。そうして、恐る恐る筵の奥を覗き込んだのでございました。
「わあッ!」
若者は驚きのあまり大きな声をあげ、その拍子に筵が落ちて閨の奥があらわとなりました。若者の声に驚いて目を覚まされた東光坊様も、何事かとそちらをご覧になりました。
それはそれは凄惨な光景でございました。男女も明らかではない人の屍が、ばらばらとなってうず高く積みあがり、膿や血が滴り落ちております。腐った皮膚がただれ、激しい死臭が満ちて鼻を突き、三人は思わず顔をそむけたのでございます。折れた白骨には、肉を喰いちぎった跡も見てとることができました。小さな小屋ではございましたが、天井に届かんばかりの死骸の山、いったいどれほどの数があるのか、見当もつかぬほどでございました。
「なんということだ、ここは噂に聞いた鬼の棲み処であったか!」
東光坊様が叫び、三人は慌てふためいて我先に外へと出られたのでございます。とにもかくにも、一刻も早くこの場を去らねば自分たちも鬼の餌食となってしまう。どこへどう逃げればよいのかもわからぬまま、三人はとにかく走り続けたのでございました。
「いかにあれなる客僧止まれとこそ、さしも隠しゝ閨の内を、あさまになされ参らせし、恨み申しに来りたり」
背後より凄まじい声が響き渡り、三人は思わず背筋を震わせ更に一心に走りますが、次第に息も切れ、不案内な土地ゆえ、とうとう先回りされてしまったのでございます。
赫っと目を見開き三人を睨みつける姿は、既に人ではございませんでした。右手に打ち杖を持っておりましたが、左肩には集めた柴の束を負うているではございませんか。これはまさしく、先ほどの女が妖変した姿であると、東光坊様は観念なさいました。冷たい野風が烈しく吹きつけ、空には暗雲が低く垂れ込めて雨が降り始めておりました。時折、稲光までもが迸っております。闇の中に稲妻が走る度に、鬼女の不気味な様相がはっきりと浮かび上がるのでございました。
鬼女は今にも一行に襲い掛かろうと、一足ずつ歩み寄ってまいります。右手の杖を振り上げたところ、またも稲妻が閃き、怒りに燃える貌が、もうすぐそこにまで迫っておりました。
最早これまでかと思われたその時、東光坊様は数珠を取り出されますと鬼に正対し、両手を合わせて一心に祈祷を始められました。お供の僧もすぐさまこれに倣い、僧二人は声高らかに仏に加護を求められたのでございます。
「東方に降三世明王」
「南方の軍荼利夜叉明王」
「西方に大威徳不動明王」
「北方に金剛夜叉明王」
「中央に大日大聖不動明王」
二人の僧は交互に五大明王の聖名を叫びつつ、両手で数珠を揉み続けております。またも稲妻が走ると、続いて雷鳴が野辺に轟き渡り、雨風は一層激しさを増し、周囲の草は大きく揺れておりました。
「唵呼嚕呼嚕旋荼利摩登枳、唵阿毘羅吽欠娑婆呵、ウン・タラタ・カン・マン!(薬師如来よ、地水火風空よ、命の限り帰依し奉る、速やかに守護し給え)」
東光坊様が真言を唱えられますと、不思議なことに、にじり寄ろうとした鬼女の足が止まり、大地に吸い付けられたかのようにびくともいたしません。不動明王の神通力でございましょうか、鬼女が必死に躰を動かそうともがけばもがくほどに躰は重くなり、濡れた荒縄で締めつけられるように苦しくなってくるのでございます。それまで荒々しく怒りの形相をあらわにしていた鬼女でございましたが、次第に呻き声を漏らすようになりました。東光坊様はなおも力強く祈り続けておられます。そのうちに、段々と鬼女の足許が覚束なくなってまいりました。一歩、また一歩と、少しずつ鬼女は後ずさりをはじめたのでございます。
「見我身者発菩提心、聞我名者断悪修善、聴我説者得大智慧、知我心者即身成仏(註二)」
東光坊様は、ここぞとばかりに声を張り上げて偈を唱え、鬼女を更に責め立てられます。鬼女は打ち杖を取り落とすと、右手で目を塞ぎ頭を左右に振りました。風で乱れた髪が鬼女の顔を覆い隠し、その表情は見えなくなりました。気づけば、それまで激しく降っていた雨がいつの間にか弱まっております。鬼女は目が見えぬのか、よろよろと辺りを彷徨っておりましたが、心なしかその姿が小さくなったように思われました。風ばかりがごうごうと唸り、辺りの草を大きく揺らし続けております。
「ああ、安達原の黒塚に隠れ住んでいたこともあらわになってしまった。妾の姿は賤しく、そしてみすぼらしい……」
そう申す女の声も吹き荒れる夜嵐に紛れ、やがてその姿も、背の高い草の陰に隠れて見えなくなってしまったということでございます。
こうして、東光坊様がたは、辛くも難を逃れたのでございました。
こののち、鬼女がどうなったかを知る者はございません。しかし、時が流れ人は移ろっても、安達原の鬼女の物語は幾度も語りなおされ、今もなお、人々の心の中に宿っておるのでございます。
これが、奥州安達原は、黒塚の物語でございます。
──ところで、あなた様は、奇妙なことにお気づきになりませんでしたでしょうか。
女がまことに人をとって喰らう鬼であったならば、自らの棲み処に入り込もうとした東光坊様のご一行を、なぜはじめは拒んだのでございましょうか。招き入れておいて襲いかかれば、易々と獲物を得ることができたはずでございますものを。
或いは、筵を掛けただけの閨の向こうに積み置かれた死骸から、死臭が漂ってこなかったのは、なぜでございましょうか。筵の向こうを覗き込むまで、誰も死骸があることに気づかなかったのはなにゆえでございましょうか。鬼女がその不思議の力で臭いを消していたとして、それならばなぜわざわざ決して見るなと言い置いて、その場を離れたのでございましょうか。その場を離れれば、正体を見破られるおそれがあったにもかかわらず。
更には、東光坊様に聞かれているとも知らずにふと漏らしたもの悲しい独言は、果たして人をおびき寄せるための鬼の謀りだったのでございましょうか。客人を凍えさせまいと、夜更けにもかかわらず柴を集めに出た心は、獲物を油断させるための偽りだったのでございましょうか。だとすればなぜ、鬼と妖変してもなお、柴の束を負うていたのでございましょうか。
こうして語り終えた今でもなお、わたくしはこれらのわだかまりを解くことができずにおります。
もしかすると女は、約束を違えられたことを怒っていたにすぎぬのではないでしょうか。閨の内にはそもそも死骸などなく、おぞましい屍の山も、恐ろしい鬼も、東光坊様がたが知らず抱いていた怖気が見せた、まぼろしだったのではございませんでしょうか。
閨の内にあったものが本当は何であったのか、そして女が何者であったのか、なにしろ遠い遠い昔の物語でございますゆえ、今となりましては知り得ようもございません。果たして、何がまことであったのでございましょう。
嘗ての安達原のような寂しい場所も、今はずいぶんとすくなくなりました。そのかわりに人心は寂寞とし、ひどく荒んでいるようにも思われます。いにしえより、鬼は寂しさの極まる処に棲むと謂われております。だとすれば、今は人けのない草原ではなく、各々の心の裡にこそ、鬼は棲むのやもしれませぬ。
己が裡の鬼に、心を喰い破られませぬよう、どうか、ゆめゆめご用心なさりませ。
それでは、今宵はこれにて──
了
安達原異説
註一 観世流では『安達原』、他の流派では『黒塚』と呼ばれている。作者不詳(一説には金春禅竹とも)
註二 不動経の偈《げ》(仏を讃嘆する詩句)の一部。「我が身を見る者は菩提心(仏を求める心)を起こし、我が名を聞く者は悪を断ち善を修し、我が説を聴く者は大いなる智慧を得、我が心を知る者は即身に成仏せん」と読み下す。
〈参考文献〉
『能の女たち』杉本苑子 文春新書 文藝春秋社(2000)
『能・謡曲選』松田存・西一祥編 翰林書房(1993)
作中の詞章の引用はいずれも『能・謡曲選』に収録された観世流のものである。
なお、冒頭部に「弑す」「誅す」の語を用いているが、これは作品の世界観を演出するためのものであり、アイヌの方々を差別する意図のものではないことを付記しておく。また、神龜丙寅長月はユリウス暦で726年10月にあたり、これは『奥州安達ヶ原黒塚縁起』などの記述に従ったものである。能の詞章には真言が含まれているが、真言宗の伝来(空海の帰国が大同元年・ユリウス暦806年)よりも一世紀近く早く、時代的な錯誤が生じている。これも演出の一部であるとご理解願いたい。
※ 文字コードセットに起因して、閲覧環境によっては一部表示されない文字があります。ご了承ください。