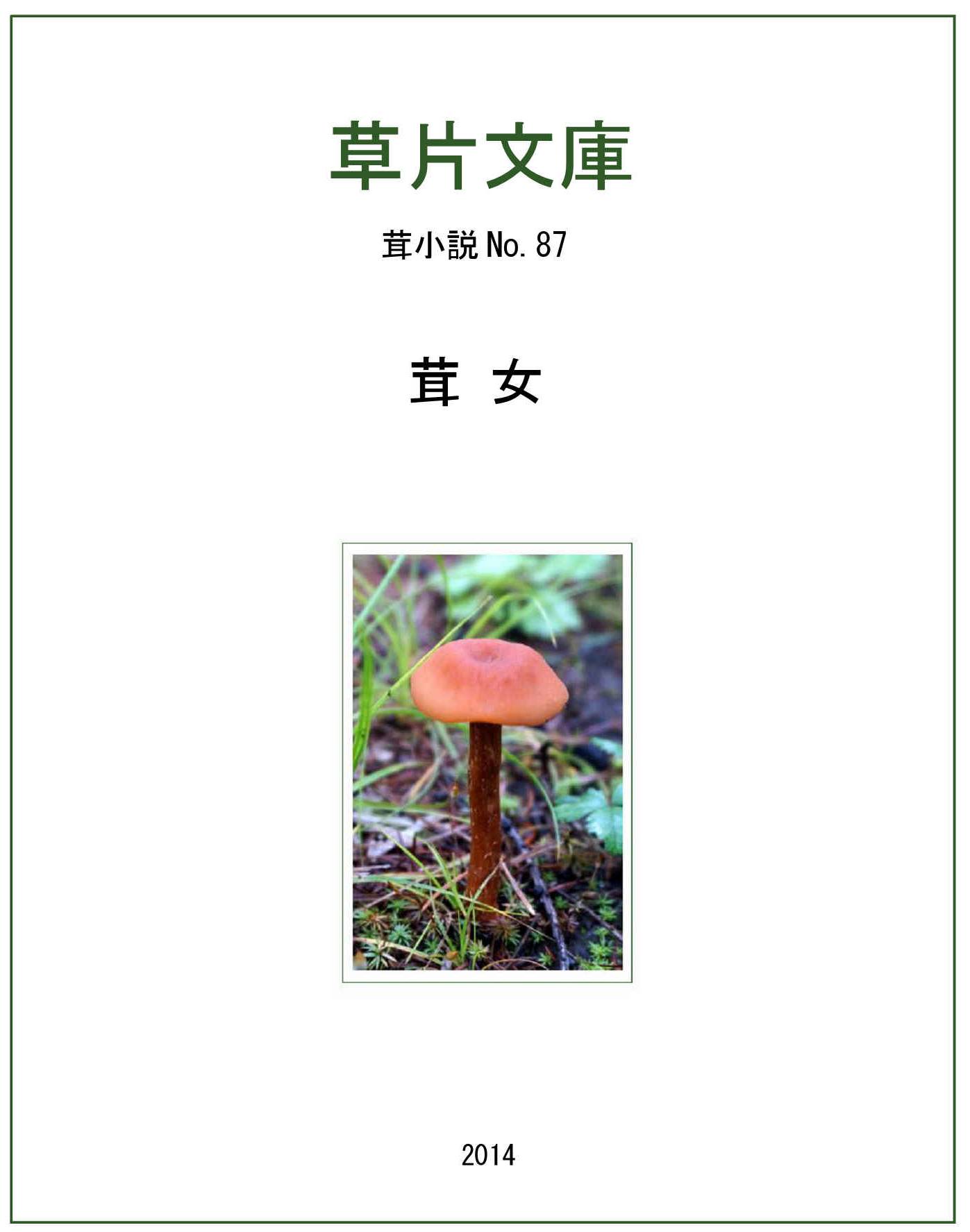
茸女(きのこめ)
ある北の国の話である。
寒い国の山奥、秋はとても早い。
立秋を過ぎ、秋の風が吹き始めると、村人たちは、風に混じって流れてくるかすかな歌声を楽しみにしていた。途切れ途切れにしか聞こえないが、誰しもが歌声で気持ちがなごみ、冬の支度に疲れた身体が癒されていた。
いつものように柔らかな雨が続くと、歌声は少しばかり甲高くなり、雨がやんで、空高く青空が広がると、それはさわやかな声になった。
「ちゃん、今日の声はやさしかったね」
娘の絹が父親の平助に声をかけた。と、雲の切れ間から日が射してきた。
「明日から晴れるべえ」
「そいじゃ、茸採りにいくだか」
「んだ」
「あたいもいく」
「そうだなあ、明日はまだあまり生えておらんじゃろうから、近くにいくぞ」
「ん、ちゃん、あれは誰が歌ってるんだ」
「あれはな、茸女(きのこめ)といってな、落ち葉から顔を出した茸の中にいるんだとよ」
「きれいな人なの」
「誰も会ったことはないな、妖怪の仲間じゃ、あの歌声に誘われて男がいくとな、枯れ葉にされちまうんだとよ」
「女は誘われないの」
「男を誘うんだと」
「あたいも会ってみたいけどね」
「そうか、でもやめとけ、どうなるかわからんで」
明くる日の朝早く、平助は絹をつれて裏山にはいった。思っていたより、いろいろな茸が生えている。
絹は十になったばかりだが、なかなかのしっかり者で、昨年死んだ母親のかわりに、家の中をやり繰りしている。兄やんがいるが、十二になったときに、町に丁稚奉公にだされている。
このあたりは、絹も山菜採りや茸採りにくるので、よく知っていた。
「父ちゃん、今日はどっちの山だか」
「ドングリ山の方にいくべ」
そのあたりでは珍しく、杉や桧ではなく、ドングリの木がたくさん生えている山があった。そこには栗鼠(りす)やいろいろな鳥がいて、子供たちもよく遊びに行くところだ。だから大人たちはここでは猟をしない。昔、流れ玉が子供に当たったことがある。
「ドングリ山で、みいちゃんやまっちゃんたちとよく遊ぶの、栗鼠っこが寄ってくるよ、かわいいんだ」
「そうか、茸はどうだ」
「うん、生えている、でも真っ赤なやつが多い」
「ドングリ山の日の当たる方は、きっといい茸が生えている」
「うん」
「それにな、ドングリ山を越して、隣の臼山にいくと、いい茸が採れっだよ、だけどな、危ないとこがあるから、今日はドングリ山だけだ」
二人がドングリ山の道を登っていくと、木々の上でざわめきがおきた。栗鼠たちが枝の上をあわてて駆け上っていく。
平助と絹は立ち止まって上を見た。葉っぱの陰に栗鼠のしっぽだけ見える。
「栗鼠たちがおどろいているよ」
平助は道からそれて、木々の間に入っていく。下草は丈が低いので歩くのに苦労がない。
それにしてもそんじょそこらに、赤い茸が生えている。
「真っ赤な茸じゃ、きれいだな」
絹は赤い茸をけっとばした。茸の首がぽろっとおちた。
それを見た平助は絹に言った。
「そんなことしちゃだめじゃ、その赤い茸は旨いんじゃ」
「毒に決まってるじゃろ、真っ赤じゃ」
「いやな、卵茸というんじゃ、ほら、根本に真っ白の壷のようなものがあるじゃろ」
「うん、卵みたい」
「そうじゃ、だから卵茸じゃ、これをな、炒めると旨いんじゃ」
「こんな、真っ赤なの、誰も食べんよ」
「富山の薬売が教えてくれたんじゃ、なんでも、西洋じゃ、旨い茸といわれているそうじゃ、薬売りがな、花ばあさんの家でこの茸を炒めたんじゃ」
「喰ったんか」
「おらと、甚平が食べたが、花ばあさんは喰わんじゃった」
「そいじゃろ、あたいもいやじゃ」
「だがな、おらにはとても旨かったぞ、腹も下さんじゃった」
「そいじゃ、採るか」
絹は赤い茸を摘むと籠に入れた。蹴っ飛ばしたやつも拾った。
絹は目が早い。
どんどん籠の中に赤い茸が積み重なっていく。
「ほれ、これは違うから気をつけれ」
平助が足元の赤い茸を指さした。
「白い壷がないからじゃろ、しかもその茸の傘には白い点々がついている」
「絹は賢いな、そうだ、この茸は紅天狗茸といってな、猛毒じゃ」
「すぐわかる」
そういいながら、絹は赤い茸を籠の中に入れた。
「たくさん採れたじゃ、籠いっぺえだろう、もう帰るべ」
「なーんだ、もう終わりか」
「一人で遊んでいくか」
「うん、栗鼠と遊ぶ、ちゃんかえっていいよ」
「それじゃ、昼には帰れよ」
「うん、そいじゃ、なんか葉っぱも採ってこうか」
「そうだな、今頃は喰えるのが少ないけどな」
「別の茸見つけたら採って帰る」
「ああ」
平助は茸がいっぱいになった大きな籠をしょって、小さな空の籠を絹に渡した。
平助と分かれた絹はドングリ山の林の中の切り株に腰掛けた。
「ほれ、ドングリ」
絹が拾ったドングリを前に投げると、さわさわと木の枝が揺れて、栗鼠が三匹おりてきた。栗鼠は絹の前でちょこんと座るとドングリを手に持った。
「おいで」
絹は栗鼠のほうに手を伸ばした。栗鼠はあわててドングリを咥えて木の上に登っていってしまった。
「つまんないな」
絹は臼山に行ってみることにした。父ちゃんは危ないところがあると言ってたが、ちょっとならいいだろう。深く入ったことはないが、少しだけ登ったことがある。
ドングリ山を横に歩いていくと裏側にでる。下に降りていくと、臼山との間を流れる臼川がある。この谷川は大きな石がごろごろしていて、水はちょろちょろとしか流れていない。
絹は気をつけながら、石を飛んで川の反対側にいくと、臼山の林の中に入った。
ドングリ山とは違って、ちょっと薄暗く、下草も丈が高い。子供がいくと迷子になりそうな場所である。奥に入ると若い男たちでも迷うらしい。何人もの男が入ったまま帰ってこないということだ。
絹は敏捷で勘がよかった。獣道らしきものを上手く見つけて登っていくと、木がまばらになり、泉のある平坦な場所に出た。臼川からそんなに離れていない。
泉は大きな水たまり程度であったが、水は透き通り、水底のきれいな砂がポコポコと膨らんで水が湧き出る様子が手に取るようによく見えた。蟹がのそのそ歩いている。絹はしゃがむと水を手にすくって飲んだ。冷たい。甘くておいしい水だ。
蟹があわてて石の間に隠れた。
絹はその周りを歩いてみた。きれいな広場だ。
大きな木の裏側をのぞくと、根元に茶色の茸が大きく手を広げるように生えていた。
「舞茸だ」
絹はこの茸を知っていた。ちゃんはこの茸をとると町に売りにいく。絹の小さな籠には入らない。絹は自分の両手を伸ばしてみた。一抱えはありそうだが持てなくもない。絹はとても嬉しくなった。
舞茸は帰りに採ることにして、回りをもっとよく見ることにした。
広場のはずれに大きな岩が一つあった。絹の背の倍ほどもあろうほどの岩である。所々に苔がつき、茶色の小さな茸もいくつか生えている。岩の周りを回ってみると、ちょうど絹の目の高さのところに、拳ほどの穴があいていた。
絹はのぞいてみた。真っ暗でなにも見えない。蛇が顔を出しそうだ。
さて、そろそろ帰ろう。絹が岩からはなれ、泉のところに戻ろうと歩き出すと、後ろのほうから、風のような歌声が流れてきた。
「あ、あの声」
風と一緒に家の中にまではいっくる女の声。きれいな声。
絹は振り向いた。誰もいない。父ちゃんは茸女といっていた。誘われると枯れ葉にされてしまう。
絹はちょっと怖くなって、あわてて木の下にいくと、大きな舞茸を地から引き離した。茸を抱えると、急いで臼山をおり、ドングリ山を通って家に向かって走った。
下りだから楽だ。
家に帰りつくと、平助が畑から戻ったところだった。
「けえったか」
「ああ、茸女の声が聞こえた」
絹は肩で息をして、手に持っているものを平助にさしだした。
平助は鍬を置くと、絹の手にしているものを見た。
「お、絹、すげえ茸を採ったの、舞茸がドングリ山に生えてたんか」
絹は空の籠を土間におろすと、顔を横に振った。
「いんや、臼山にあった、重かった、父ちゃんへのみやげだ」
「臼山に行ったんか」
「ちょっと入っただけだ」
「そうか、気をつけねばな、臼山にゃあなんかいるかもしれね」
「うん、茸女の歌声がした、臼山に住んでいるかもしれんじゃ」
「そうか、でもなんもなくてよかったの」
「うん」
「昼飯喰ったら、町に行くから、そいつを売ってきてやろう、小さいけどこんな早く珍しい、結構高く売れる」
「そいだらいいな」
「何か買ってきてやる、なにがほしい」
「うん、なんでもええ」
「そいじゃ、卵茸を油で炒めてくれや、昼飯にしよう」
「いいよ」
絹は鍋に油をしいて、卵茸を炒った。赤い色が黄色っぽくなった。塩を少しばかりふると、味見をした。確かに美味しい。手際よく茸を料理すると、昼の支度をした。
「ほんに絹は飯炊きが上手くなったな、この茸もうめえ」
平助は二杯も飯を食った。
「さあ、いくべ」
町に出るといっても、家から歩いて一時間はかかる。
平助は編んだ草鞋や笠、それに畑でとれた野菜も舞茸と一緒に籠に入れて背負った。
「はよう帰ってな」
「ああ、みいちゃんとでも遊んでな」
「うん」
平助が出て行くと入れ替わりに、大きな茶色の虎猫が家に上がってきた。飼っているというか、勝手に入ってくるというか、わからないけど、絹は「ごん助」と呼んでかわいがっている。
「ごん助、飯をやるよ」
残っていた味噌汁を古くなったご飯にかけて、目の前に置いてやった。ごん助は大きな頭を器に突っ込んで喜んで食べた。
絹はいつものように、隣のみいちゃんの家に遊びに行った。隣と言っても林を一つ越したところにある。
みいちゃんは矢助さんの娘で同い年である。みいちゃんの家はずいぶん大きい、家に行くと、ばあちゃんが顔を出した。
「やああ、絹ちゃん、いつも元気じゃな、美乃はなあ、風邪引いちまって、熱あるんだや」
みいちゃんは美乃という。
「ありゃ、じゃ、ちょっと会って帰るべ」
絹はいつものように、ことわりもせず、家に上がると、美乃の部屋にいった。しかし、美乃はそこにはいなくて、もっと広い部屋に寝かされていた。
「紅い顔してるな」
美乃は水枕をおでこに載せている。
「絹ちゃん、今日の朝も声はきれいだったなあ」
「うん、おら、山の中で聞いた、みいちゃん治ったら、一緒にいこう」
「うん」
「じゃあ」
絹が家を出ようとすると、ばあちゃんが声をかけた。
「すぐよくなるから、また遊んでな、平助どんはどうしてる」
「町に野菜売りにいった」
「そうか、そいじゃ、一人か」
ばあちゃんはお菓子が入ったお捻りを絹に渡した。いつもばあちゃんが大事にしている飴玉が中に入っている。
「ありがとう」
飴玉を口に入れると、家に戻った。
家では、ゴン助が縁側で平べったくなって寝そべっていた。
「ゴン助、ドングリ山、いくべか」
声をかけると、絹は大きな籠を背負って家を出た。またドングリ山に行くつもりである。ゴン助も起きあがると、のろのろと、絹についていった。
絹はドングリ山につくと、切り株の上に腰掛けたが、栗鼠は寄ってこなかった。それもそのはず、どういうわけか、いつもなら途中から引き返してしまうゴン助がここまでついて来てしまったのである。
「ゴン助、なしてここまで来たんじゃ」
絹は切り株の上に、むりむりと乗って来たゴン助の頭をなでた。
しばらく風に吹かれていると、歌声が聞こえてきた。歌詞は全くわからない。きっときれいな女の人が歌っているのだろう。天気が良くなったためであろうか、青空に薄い雲がたなびくような、すっきり、ゆったりとした歌声である。雨が降っているときは、強く、訴えるようで、それでいて、浸みこんでくるような歌声が聞こえてくる。
「茸女に会ってみたいねえ」
ゴン助相手に絹がささやいた。ゴン助は素知らぬ顔で、枝の上のほうで遊んでいる栗鼠を見ていた。
「また、行ってみよう」
絹は朝登った臼山へ向かった。ゴン助もついて来た。
登って行くと、茸女の歌声が近くに聞こえるようになった。舞茸を採った泉の広場にくると、歌声はすぐそばに聞こえる。広場の端にある大きな岩から聞こえてくるのじゃないだろうか。
絹は岩のところにいくと、ゴン助が岩の裏に回った。
「おほほほほ、ゴン助、ついて来たの」
誰かが、ゴン助に声をかけた。
絹がゴン助のところにいくと、岩の穴の中から、真っ紅な茸が顔を出していた。
真っ紅な茸は岩の上に飛び上がった。
その茸が空に向かって歌い始めた。いつも聞いている歌声だった。
ゴン助が首を傾け、大きな顔の小さな目を閉じて聞いている。
紅い茸が絹の方を向いた。
茸女に会ってしまった。どうしよう、枯れ葉にされてしまうかもしれない。でも、男の人だけだと父ちゃんは言っていた。俯いていた絹は顔を上げ茸を見た。そのとたん、茸が消えた。そして、女の人が現れた。
余りの美しさに眼を見張った。
紅い茸が薄絹をまとった女の人にかわっている。岩の途中に腰掛けて、白くてきれいな足をくんでいる。
「絹、よく来ましたね」
絹はこわごわとうなずいて女の顔を見た。死んだお母ちゃんとどこか似ている。お母ちゃんの顔は黒かったけど。
茸女はまた歌いだした。歌声は風に乗って村に流れた。この声が村を豊作に導いてくれる。
急に後ろの方からがさがさと草をかき分ける音が聞こえた。そのとたん、茸女はあっというまに紅い茸になって、するりと岩の穴の中に消えていった。それと同時に後ろから声がした。
「平助どんとこの絹だべ」
振り返ると、二人の若い男が猟銃を持って立っていた。村はずれの源じいさんの息子たちだ。猟師をしている。乱暴者で、村の人たちからは好かれていない。
「うん」
「籠しょって、なんでえ、茸でも採るんか」
「うん、散歩じゃ、ついでに茸があったら採ろうと思って」
「まだ生えてねえだろう、このでぶ猫、おまえのか」
ごん助が二人を見上げている。
「うーん、まあ、そうじゃ」
「今、こっちのほうから、女の声が聞こえたが、おまえが歌ってたんか」
「いんや、この奥の方から聞こえてきた」
「近くに聞こえたがな、わしら、歌っている女が見たくて来たんじゃ、そいだら、おまえがおった」
「父ちゃんが言うてたよ、茸女は男を誘って枯れ葉にするんだって」
「しっちょるよ、昔からの言い伝えだわ、とてもきれいな女だそうだ」
絹はちらっと岩の穴を見た。二人の男は絹の目線に気がついていた。
「わいらは、ほれ、今日はこんなに山鳥を獲った、天気が良くなったからだ、一羽やろうや、平助さんと喰いな」
男の一人が山鳥を一羽、絹の背負っていた籠にいれた。なんだか今日はやけに親切で気持ちが悪い。この二人はけちでも知られている。
「だけんど、悪いわ」
「いいさ、偶然だがよ、縁があったんよ」
「ありがとう」
絹は急に重くなった背中の籠をおっこらとしょと家に帰った。ゴン助も一緒に帰った。鳥はしばらくおいておいた方が旨くなる。父ちゃんが帰ったら軒に吊してもらおう。鳥の入った籠を土間に置いた。
次の日から雨が降り出した。
雨はだんだんひどくなり何日も続いた。いつもだとあの歌声が聞こえ、雨がおとなしくなるのに、雨は強くなる一方である。茸女の声は聞こえてこない。
平助が村の寄り合いから戻った。
「大嵐が来そうじゃ、用意をしなきゃな、村の長老がいつもとは違う、気をつけれと言っておった。」
「うん、おら、水を汲んでおく」
家からちょっといった山肌に、水が湧き出ているところがある。絹は皮袋と桶を持って、何度も往復した。
夕方食事の用意をしながら絹は兵助に聞いた。
「源さんのところに、嫁がきたという話を、みいちゃんのばあちゃんがしていたよ」
「そうらしいのう」
「お嫁さんどこからきたんじゃ」
「しらんな、あそこによく嫁がきたものじゃ」
「なんで」
「あんな乱暴な奴らじゃ、嫁がかわいそうじゃ」
「ふーん、でも、山鳥くれたじゃ」
「どうしてかな、珍しいこともあるものじゃ」
「父ちゃん、茸女の歌が聞こえんな」
ずいぶん長い間、歌声が聞こえてこない。
「そうじゃな、雨が降るときは、雨がやむようにと、茸女は歌うのだが、どうしたのだろうな」
「茸女が歌わんから、雨がひどくなってるんじゃろ」
「そうかもしれんな」
嵐はひどいものだった。山が崩れて村の中心に土砂が流れた。絹の家は後ろが山にもかかわらず被害はなかったが、村に流れ込んだ濁流は家々を押しつぶした。川も氾濫し、人々は命辛々安全な場所に逃げた。それでも逃げ遅れた者の多くが命をなくした。
源じいさんの家も押し流され、二人の息子たちの命もとられた。嫁にきたばっかりの若い嫁さんの行方もわからなかった。色の白い美しい娘だったと、周りの人々は探し回ったがみつからなかった。
平助と絹は被害にあった親戚に野菜を届けたり、壊れた家の片付けや補修を手伝って、ありがたがられた。
源じいの家の近くに住む親戚に行ったときである。おっ父が大工仕事を手伝っているとき、一緒に来た絹はする事もなく、周りをぶらぶら歩いたりして遊んでいた。絹が源じいの倒れた家の前にくると、泥の中に紅いしなびた茸が落ちていた。茸女の茸に似ている。そう思った絹は茸を拾うと紙に包んで懐に入れた。
夕方、家に帰ると、絹はしなびた赤い茸をぬるま湯で洗った。
「絹、なにしてる」
平助がのぞき込んだ。
「紅い茸か、しなびとるじゃないか、元には戻らんな、戻っても毒じゃろう」
その夜、絹は紅い茸を枕元において寝た。
絹の夢枕に臼山で会った女の人が立った。白くきれいな肌をした女の人だった。茸女はお母ちゃんに似た細い目で絹を見るといった。
「あの二人の男たちに、さらわれてしまいました、ずーっと私を捕まえようとしていたのです。気を付けていたのですが、ずるがしこい男たちは、私が飛び出た瞬間、穴に土を詰めてしまいました。私は外に出ると茸女にかわります。戻るところがなく、私はそのまま連れられて、あの家に閉じこめられました。しかし、あの嵐のときに家がつぶされ、私も一緒に死にました。そうして、茸に戻ったのです」
そう言うと、茸女は紅い茸にかわり、絹の夢の中から消えていった。
明くる朝、絹は紅い茸を持って、臼山に行った。
夢で茸女がいっていたように、大岩の穴は土で固められていた。絹は用意してきた箸で土を掻きだした。
土がなくなると、中から冷たい風が吹き出した。
風と共に真っ黒い茸と真っ白い茸が飛び出してきて岩の上にのった。
黒い茸はおじいさんに、白い茸はおばあさんの姿になった。
おじいさんが手を伸ばした。
「絹、ありがとよ」
絹はしなびた紅い茸を渡した。受け取ったおじいさんはおばあさんに渡した。
「かわいそうなことをした、もっと山奥に棲家を用意すればよかったが、茸女はあの泉が好きでなあ」
「ここを離れたくなかったのよ、いろいろな動物もきて楽しかったのだよ、あの猫もそうじゃった」
「ゴン助もよく来ていたの」
「そうだよ、可愛い猫だね」
おばあさんは受け取ったしなびた紅い茸を、手でもむと粉にして、器に入れた。
おじいさんが、泉から水を汲んできて、粉になった紅い茸にかけた。
真っ赤な水ができた。
「絹や、これを飲んでくれないか」
「なんだべ」
「飲むと茸女になるんじゃ、絹が茸女になってくれないか」
「茸女になったら、どうなるんじゃ」
「きれいな声で村人たちに歌うようになる」
「おら、歌などうとうたことがないじゃ」
「茸女になればみな歌えるようになる」
「でも、父ちゃんが一人になっちまう」
「絹が茸女になったことを知ったら喜ぶぞ、お前の父ちゃんは死ぬまで絹のきれいな声を聞けるのだから」
絹はこっくりうなずくと、手を伸ばすと、おばあさんから器を受け取って、真っ赤な水に口をつけた。
甘かった。今まで、こんなに甘い飲み物を飲んだことがなかった。
「おいしい」
おじいさんとおばあさんは微笑んだ。
「全部お飲み、そうすると、おまえは茸女になる。茸女の歌は雷神の気持ちを静め、風神の激しさを静め、人間を安心させるのだよ」
絹は甘い水を飲み干すと、その場で真っ赤な茸にかわった。
「さあ、茸女におなり」
おばあさんが言うと、真っ赤な茸は真っ白な肌をもった若い女の子になった。
「おじいさん、おばあさん、これから、雨がしとやかに降り、風がなぐように、歌います」
おじいさんとおばあさんは茸神にもどって、岩の穴の中に入っていった。これから、絹もこの穴の中の茸神の世界で暮らすことになる。ごん助は岩の上で丸くなった。
絹だった茸女は歌い始めた。
歌声は村を覆いつくした。村人たちは歌声が変わったことを知った。
あの朝、山に行ったまま戻ってこない絹を兵助が心配していた。
兵助はドングリ山に探しにいったが絹はいなかった。臼山にいってみた。
泉の広場にいくと、大きな岩の上に女の子が腰掛けていた。
茸女じゃ、枯葉になっちまう。平助は逃げようかどうしようか迷った。
茸女は鈴を転がすような声で空高く歌った。見るとそばにゴン助がいる。
「ちゃん、だいじょうぶじゃ、いつでも茸を採りにおいで」
絹の声だ、平助は茸女を見た。茸女も平助を見た。絹に似ている、絹は茸女になっちまったのか。
茸女が再び歌い始めた。
泉のまわり一面に茸が顔を出した。
ぼーっとみていた平助に茸女が木の下を指差した。大きな舞茸が生えてくるところだった。平助は絹の歌声を聞きながら、茸を採った。
平助は毎日泉にかよった。ゴン助も一緒だった。いつもいろいろな茸が生えていた。
平助の採ってくる茸はいい値段で売れた。
こうして、その村には、大人になった絹の声が風とともに流れてきた。
村にはいつもほどよい雨が降り、ほどよい風が吹き、稲はたわわに実った。
秋の晴れたある日の朝、いつものように茸女の清らかな歌声が聞こえてきた。
その日、七十になった平助は目を覚ますことなく、静かにこの世を去った。
茸女(きのこめ)
私家版「茸女譚、2017,一粒書房」所収
表紙茸写真:著者 長野富士見 15-9-24


