Lambency
第一章『夢落人』
少年は捕虜であった。痛々しく冷え切る錆びた鉄格子が中に鎖で繋がれて横たわる少年の自由を奪っていた。虚ろな目が宙を泳ぐ。彼のふっくらとした頬は削げ落ち、やつれていた。腐臭に満たされた不衛生極まりない監獄。その部屋の隅のひび割れた糞尿瓶から洩れだした屎尿が蠅と共に床にへばりつく。朽ちるに任せた簡素な椅子。黴に蝕まれた麻布の襤褸。石畳を掘り返された床に密生する苔。汚泥の檻に閉じ込められた少年は、既に笑顔の作り方さえも忘れてしまった。
地下の牢屋へと続く階段を誰かが降りてくる音がする。それは鉄格子の隙間から差し出される一日一回だけの食事の合図だった。虫が這う乾いたパン一切れと欠けたコップ一杯の濁水が凹んだ盆に乗せられて少年の前に現れる。彼は拒否することなく、丁寧に食べた。少年には反抗する気力はもはや残っていない。彼の継ぎ接ぎの目立つ囚人服の隙間から見える無数の青痣と切り傷や擦り傷が、その虚さをまざまざと表す。少年は豪快に吐いた。床にこびりついた黒緑の吐瀉物と深紅の血液が生臭い。それでも少年は食べることを止めなかった。
少年は軍事貴族の末裔だった。彼を使役する無慈悲な絶対的権力者――とは言え、少年を酷使する残忍な近衛軍の兵士らもまた、神として崇め奉られている不可侵的権力者の忠実な下僕であるのだが――は、少年の父親を殺した。財産収奪。住民虐殺。土地を侵略者は手中にした。
抵抗する住民は手当り次第、晒し者にされた。小さな町に不釣り合いな甲高い恐怖の悲鳴。冷酷な笑みを湛えた兵士が女の柔肌を蹂躙していく。子供は串刺しにされ、屈強な男たちは、嬲り殺された。一閃。男の首が曇天を飛ぶ。少年の父親の頸は、城門の前に無作法に置かれ、下級兵士に狂気の高笑いと共に泥の中へと蹴飛ばされた。
少年は父の後を追い、死を選んだ。だが、彼はその肢体と顔立ちを不覚にも、近衛軍大将に見初められた。舐め回すような雄の視線。粘つくような不快な笑み。放り投げられた場所は、自分の城の地下に造られていた牢屋の一室。何年も何十年も手入れがされていないであろうその場所は、皮肉にもそれを造った血族の末裔を閉じ込めた。
「今日から貴様は、我らの奴隷だ。貴様の父親を筆頭に、貴様ら一族は軍事貴族でありながら不要な争いを嫌ったな。どうせ、この牢も初代か二代目以来、使用もしなかったんだろう。宝の持ち腐れだ。なんとまあ、自らの血族の拷問に利用されるとは、夢にも思わんだろうよ」
地を這う蟲のような声が少年の耳にこびり付く。
「――敗者の貴様には裏切りの名が相応しいとのこと。皇帝からの名を受け取れ、今日から貴様の名は、クライムだ」
その台詞は、彼を縛る洗脳の始まりに過ぎなかった。
外の景色を見ることもままならない地下では、時の流れは止まっていた。しかし、夜の訪れを少年に告げるものが一つだけある。この度重なる戦争がある限り、例え地下から動けなくとも少年には時間を知ることができる。不本意ながら。毎日きっちり定刻に少年のもとへやってくる一人の人物がいた。荒々しい獣の鼻息が少年の肩越しに聞こえる。
「また、あいつが誰かの命を奪ったのか」
彼は誰にも聞こえぬよう、ぼそりと呟いた。近衛軍大将ウェインが少年で命を確かめようとするときはいつもそうだった。無気力に支配される体。屈辱の時間の始まりだ。この束の間の時間だけ、彼を鉄格子に拘束する黒革の首輪が乱暴に外され、細い腕が紐と縄で縛られていく。
かちゃり。鉄格子が開き、血みどろの男性を招き入れる。「今日は、何人殺したんだろう」クライムは悍ましくも、そう思わずにはいられなかった。少年の煤けた薄い顎を持ち上げる節くれ立った指。相手の顔が近づけば近づくほど、避けられない大将の身体に染み込んだ死臭。上辺だけの芳しい香りでは、消すことのできない匂い。
ウェインは無骨に少年を抱き上げた。乾いた枝のような口唇に奪われる豊潤な果実。醜く成熟したウェインの舌が少年の唇の割れ目から侵入し、その奥で眠る蕊にねっとりと絡みつく。苦痛と侮辱の渦。クライムは、湧き上がる怒りの衝動を流すまいと必死に堪えていた。額から滴り落ちる脂汗。口内を蠢く舌。大将の征服欲に、クライムはただ身を任すしかできなかった。時に犬のように従順に、時に猫のように気まぐれに、ウェインに教えられた男を悦ばせる術を淡々とこなしていくだけしか能がない。そう、思われていた。
ウェインは、極上の柔らかな肉を食い尽くしたかのような満足さにほくそ笑む。蛇のように眼をぎらつかせて、憔悴しきったクライムの耳から首にかけて舌を這わせ、嫌らしい動きをした手が彼の胸を滑る。少年の未熟な体つきの割に逞しい筋肉が、女の柔らかさとは違った味を醸し出していた。彼が抗う気力を捨てたことをいいことに、大将は我が物顔で蹂躙していく。痛みに溢れ出す弱弱しい少年の涙が、荒れ狂うウェインの性癖に火をつける。命を奪い尽くしたその手で、命を生み出す秘所に触れる行為の何と愚かで、皮肉なことか。少年は、初々しい小さな外性器を主の慣れた手付きで弄ばれ、恍惚とも絶頂とも似つかぬ境地に放り出された。物欲しそうな表情の少年に膝を付かせ、自らの股間に彼の放心する顔を押し付ける大将。少年の柔らかな唇と滑りのある舌先がその蠕動を促す。緩やかな律動が徐々に激しい情動へと変化する。大将の頬は紅潮し始め、呼吸の間隔が短くなる。少年の耳元で囁かれる語句の連鎖のみの命令。疑うことを知らずに繰り返される少年の頷き。ウェインが快楽の限界を迎えると、少年は白濁した愛の塊を口内に溢れさせた。
ウェインは寸暇も与えずに、仏頂面で少年を壁際に押し付けた。クライムの怯える姿に、大将は征服欲を刺激されたのか、躊躇いもなく彼を責め立てる。ただ、己が快感を得るために。敗者の生を貪りつくすために。誰かを壊すことで己の存在を示すかのように。掻き乱されるひ弱な四肢。クライムの瞳から流れ出す涙。朦朧とする彼の意識。小さな独房に木霊する衣擦れの音が艶やかさのない情事に色を足す。一度きつく少年の身体が抱きすくめられたかと思うと、ウェインはほとばしる劣情を繰り返し、繰り返しその奥深くに注ぎ込んだ。
気が付くと、監獄の床で一人服をはだけて少年はうずくまっていた。絶句。絶望。絶叫。喉は破裂し、口が裂ける。男の生と死が入り交った腐臭が手の甲から爪先まで染みついて取れない。少年の瞳が最後の涙を振り絞り、枯れた。裂けた口先から流れる白と赤の液体。男に押さえつけられた体の痺れが抜けない。感覚がおぼつかない足取りで少年は古びた椅子に向かう。そこには、動くのをやめた時計が、相も変わらず背にかかっていた。二時四十七分十三秒。父が命を絶ったのと同じ時刻をずっと指していた。硝子が割れて針が剥き出しの懐中時計。
「――僕は、あの日死んだのだ」
その言葉は深く、切なく、憐れだった。
少年は微睡むように、束の間の眠りの優しさに包まれた。その日は少年を責め倒す命落とした者の怨霊と亡霊は全く夢に姿を現さなかった。ぼんやりと人を象る靄が、夢の中に沈む彼の意識を抱く。優しさと穏やかさが、少年を柔らかく包む。
「父さん……?」
少年は意識の片隅で、光の霞に呼びかける。最愛の人の影は、何度も何度も少年を抱きしめようとしたが、ただその光はクライムの手を、胸を、腹を、顔を虚しくも通り抜けた。目の前で崩れていく鏡のような光の欠片。少年は声にならない叫び声を喉の底から上げる。
「――僕を置いて行かないでよ、父さん……」
少年は、縋るものがないまま現実へと放り出されたのだった。
擦れる金属音。鼻腔を刺激する煙。咽喉を麻痺させる味。この不愉快で鋭利な刺激が彼を叩き起こすに至った。はっと上体を起こした少年が狭苦しい牢屋の違和に気づいて後ろを振り返ると、見知らぬ青年が煙管を口に咥えながら、風化して削れた岩壁に背を預けていた。独房と廊下を結ぶ扉が開いている。
「やっと起きたか……クライム」
青年の唇から吐き出される棘のある言葉と白煙。
「俺の名は、ベルナルド。貴様の監視役だ」
立ち枯れた樹木の軍服に染み込む汚泥と血糊。右頬に逆十字の切り傷の跡のある男が苛立たしげに少年を呼ぶ。「腹は決まったか?」
少年は、近衛軍大将の寵愛を経ても、過酷な肉体使役や限界に達する飢餓を経てもなお、近衛軍の要求――彼自身が諜報要員として軍の一角を担うことを拒否し続けていた。青年は、年端にも行かない少年の「捕虜」としての生存本能のなさに、敵ながらも見上げたものだと感服していた。少年は、無表情の裏に怒気と猜疑を圧し殺しながら青年を睨み付ける。それは、手足の自由を奪われた中での溢れ返る反抗心の精一杯の表現だった。
「――どうして僕を生かす? この用なしの体なぞに未練はない、殺せ」
手枷足枷が少年を縛る以上、彼は青年に自分を殺すように乞うことしかできない。彼は無力な自分がもどかしくて堪らなかった。だが、その虚しい言葉の塊は青年に悉く両断される。甲高い笑い声が反響した。
「貴様はあの武芸に秀でた重鎮ピエタ家の男児だ。使い道はある……何より男色家のウェインの立派な妾の役を果たしているではないか。それに、俺は苦痛に歪む美しい顔を愛でるのが好きでね。つまらないから、そう簡単に貴様を死なせやしないよ」
「――何が言いたい?」
「貴様は、次の戦争に駆り出される――軍令だ」
クライムは床に唾を吐く。
「――好きにしろ」
戦場で死ねるなら――冷静になりつつあるクライムの意識が告げていた。自分がどう動こうがもはや、先祖の名誉は穢されまい。自分が生き永らえて恥を晒し続けるだけの人生ならば、支配者の玩具として戦場に立ち、散り際に操者の寝首を掻くのも悪くない。一思いに暴れ、仇を討とうと少年が思っていた時だった。ベルナルドが勘繰るようにクライムを呼ぶ。
「――クライムよ、俺との取引に応じてみないか?」
「取引だと……?」
少年の額の脇を冷や汗が伝う。
「そう、貴様にとっても悪くはない内容だ。まあ、貴様に選ぶ自由はないだろうがな」
青年は少年の瞳をじっと見つめると、一度切った言葉を繋いだ。
「――次の戦争で貴様に大将ウェインを抹殺してもらいたい」
クライムに凌辱の限りを尽くした近衛軍大将は、確かに彼にとっても邪魔な存在だった。しかし、ベルナルドの利害と思惑が明らかになっていない以上、クライムは警戒した。身構える少年を無視して、青年は殊さら不快そうに話を続ける。
「俺にとっても、悪趣味の胸糞悪い大将は追放したい存在だ……あれさえいなければ、俺は……」
「――断る」
「まだ歯向う気力があるとは見上げた奴だな。貴様からその無駄口を叩ける余裕をなくすことがどれだけ容易いか……貴様は知るまい」
強がる少年をじりじりと崖に追い立てるのが至福だと言わんばかりの悪魔の笑み。口に咥えていた煙管を右手に持つと、青年はふうと盛大に息を吐き出した。
「貴様が捨て駒として連行される場所は、ネウマ」
少年の呼吸が止まる。走る鼓動。痺れる指先。床と同化し始める体温。
「――貴様の母親の故郷だったな」
「ど、どうしてそれを……」
考えていなかった事態に少年が動揺する。瞳孔が開き、焦点が忙しく動いている。
「我らの諜報員が猛威を奮えばこのような些事、瞬時に片が付く」
青年は目を細め、再び煙管を吸い始める。
「フラジョレットの居城に侵攻した際も怪しいと感じていたが、領地の女子供のいくらかを妻の故郷へ疎開させるとは天晴な名君魂よ。反吐が出る」
少年の脳裏に描かれる戦争風景。自らが身を以て体験したあの惨事を今度は自らが引き起こす。その生々しさに体が震えた。
「ここまで言えばいくら貴様でも理解は容易いであろう。返事はいらぬ……貴様の活躍を期待している」
かつかつかつと独房に響き渡る甲高い靴擦れの音。ちらちらと視界を揺らめく蝋燭の火さえ憎らしくクライムには思えた。
「決行は次の満月の時――五日後だ」
捨て台詞を残して独房の前の渡り廊下からベルナルドは姿を消した。
骨と皮だけになった痣塗れの痛々しい体を引き摺り、少年は壁に寄り掛かった。やり場のない憤怒。こみ上げてくる衝動。こめかみに手を押し付けて、頭痛を鎮めようとしても、左胸に手を押し当てて、鼓動を抑えようとしても、何も変わりはしなかった。ただ、目頭が熱くなるだけ。クライムは歯を食いしばり激情に流されるのを辛うじて耐えていた。そうしなければ、ただでさえ脆いこの体が打ち砕かれてしまう気がした。彼の歯と歯の間の僅かな隙間から漏れ出した言葉が地面に落ちて割れた。
「父さん……母さん……」
現実は悪夢よりも酷かった。
ベルナルドがクライムの監視に就き、彼の次の戦争への出兵が決まったことで、以前のような衛生状態の悪い食事からは解放された。とは言え、クライムの劣悪な環境が変わるわけではなかったため、相変わらず捕虜に対する扱いは酷いものだった。財政が逼迫する中、捕虜の食事の改善だけでもベルナルドの軍内圧力の大きさを物語っていた。小匙三杯分の優しさがまだ残っていた青年の取り計らいで、クライムはよく彼と面会していた。
「これを吸え、気分が楽になる」
ベルナルドが差し出す白い粉末と煙管。彼は手燭で粉に着火させると、クライムに有無を言わさずに手渡した。今日は珍しく彼自身は煙管を持っていないらしい。普段、彼の首に巻かれている黒い布は彼の口から首を覆っていた。
「恐怖や不安を消してくれる薬だ。俺の分を分けてやるくらいしかできないが、遠慮なく使え。くれぐれも一度に使いすぎるなよ、薬が切れたときに使い物にならない下級兵を幾人も見てきたからな」
嫌そうな顔をして応じるクライムの口に無理矢理煙管を加えさせるベルナルド。それまで少年の体を蝕んでいた無数の痛みが誘惑の煙の吸入で驚くほど消え去った。張り詰めていた緊迫感も徐々に溶けた彼は、蝋燭の灯りに這い寄り、鉄格子を隔てて監視役に自分から話し始めた。
「おまえはどうして僕を匿う?」
「俺が手を汚さずに実行できそうな相手が貴様しかいないからだよ」
淡々とベルナルドは格子越しに告げた。無機質な声音が低い天井に跳ね返る。
「例え貴様が大将の殺傷に失敗しても、捕虜の反逆として内密に片づけられる些末なことさ。貴様が万一成功しても、俺が貴様を服従させればいいだけのこと」
その時の報酬はそうだな、とベルナルドが腕を組みながらしばしの間首を捻る。訪れる静寂に白霧が広がる。その静謐を破り、口を開いた青年が零した言葉は傲慢の限りを尽くしたものだった。
「成功した暁には、近衛軍への推薦状を書いてやろう」
捕虜という奴隷身分の貴様に与えうる最大の恩寵だ、とベルナルドは言う。クライムは間髪入れずそれに応酬する。
「――興味ない」
一呼吸置いて少年は唾と共にベルナルドに向かって言葉と唾を投げ捨てた。
「父さんを殺した張本人の下に就いて働くなんて、考えただけで吐き気がするね」
「そう言っていられるのも今の内だけだ」
歪んだ鉄格子から背を離すと、青年は手燭を持って歩き出した。去り際に少年に絶望を贈りつけながら。
「貴様、なぜ皇帝陛下がおまえにその名を下されたと思う?」
流し目は、言った。「自らの手で血族を殺すからだよ」
その日の夜、クライムは謎の浅黒い乳液を「明日の戦に支障が出るから、無理やりにでも睡眠をとってもらう」という強迫を受け、咳込みながら苦い乳液を飲み干した。舌にまで響く胸糞悪い苦み。「薬だ」と言って定期的な配給を受ける煙よりも性質が悪かった。水で口をすすごうと思っても、汚らしく濁った少量の雨水しかクライムの独房には置かれていない。どうしようもなかった。段々と立っているのが辛くなる。視界が回る。瞼が重くなる。意識までもがどこか手の届かないところへ行ってしまいそうだ。クライムは、両足で自分の体を支えられなくなり、固い石畳の床に突っ伏した。彼の体は苦痛に耐えきれず、そのまま深い眠りへと落ちて行った。
長い夜だった。何も覚えていないほど、心地のよくわからない眠りをクライムは貪った。うっすらと記憶と意識が戻った頃に彼が気づいたことだが、鼻血がたらりと垂れている。黄ばんで黴塗れの囚人服の袖が赤に染まっていることから、無意識に血を拭ったのだろう。まだ血は流れていた。なぜか頬がひりひりするし、頭皮が上に引っ張られたような痛みもする。心なしか、寝違えたわけでもないのに首回りが痛い。体を動かす分に支障はないが、あの大将に寝込みを襲われたのかと思い、せっかくの眠りを台無しにされたような朝だった。寝起きは最悪。思わず機嫌の悪さがクライムの顔に出た。
定時の見回りに、ベルナルドがやってきた。朝食の目印である盆を今日は持っていない。代わりに、クライム以上の不愉快の渦が彼の顔を覆っている。動揺するクライムを余所に、ベルナルドは、ぶっきらぼうに鉄扉を開け放つ。彼は、小脇に抱えたパンをむんずと掴んで少年の顔に力の限りぶつけた。パンはクライムの顔に大きく食い込んでから、割れてぼとりと床に落ちた。よほど機嫌が悪かったのだろう。
「貴様はいつまで寝てるんだ? この俺様の起こしにも反応しないなんていい度胸だな、おい。二回、俺様が起こしたことにもどうせ気づいてないんだろ」
男の声量がだんだん小さく鋭くなっていく。
「いい加減、食事を摂って支度しやがれ、屑が!」
目にもとまらぬ速さでクライムの胸倉を掴むと、ベルナルドは勢いよく怒声と共に床に叩きつけた。
「昨日の薬の分量を間違えた俺にも非があるからな、手加減はしてやる。貴様の頭と股間を踏み潰すのはやめておこう。これで目が覚めただろ」
「当たり所が悪ければ、永眠するところだぞ……ブラッド」
「悪運の強い貴様がそう、易々と死に急ぐわけがあるまいよ」
先ほど収まった鼻血がまたぶり返している。大方、起き掛けの痛みと鼻血はベルナルドに起こされたためと見て良かった。あの強引で短気な彼のことだ。ちっとも目を覚まさないクライムに腹を立てて殴ったり、首を絞めたりという暴挙に及んだのだろう。少年の身にしてみれば、まったく笑えないことだが。
ベルナルドは泥と血で汚れた顔を襤褸で拭うクライムに冷笑を浴びせてから、指だけを背後に向けて、命令を吐き捨てる。殴ってすっきりしたのか、少しだけ彼の顔は晴れ晴れとしていた。「小憎らしい」クライムは、ここに来てから何度目かわからない殺意を彼に抱いた。
「そこの鍵は開けておいてやるから、早く二階奥の広間まで来い。ただし、椅子に掛けてある服を着込んでからだ。くれぐれも汚らしい格好とみすぼらしい顔だけはするな。品位が下がる」
クライムの返事を聞くと、ベルナルドは独房から足早に出て行った。去り際に、ふと思い出したように居直って言葉を口にした。
「それと。俺のことはブラッド少将と呼べ。わかったな」
クライムは彼が背中を向けているのをいいことに、「面倒くせえ」と顔をしかめた。
最初にクライムを起こしに来たときに、ベルナルドは一式の軍服を支給していったようだ。嫌そうな顔をしながらも、クライムは二か月ぶりに清潔な衣類に袖を通せることに内心歓喜した。黴臭く、穴だらけで急所を隠すぐらいしか用をなしていなかった服を脱ぎ棄てられる快感。それと裏腹に、親の仇である軍の制服に腕を通さなければならないという罪悪感。ベルナルドの命令を無視するという選択肢もはっきりと存在していたが、少年は素直に命令に従うことしか考えられなかった。
真新しい軍服に着替えたクライムは、しばらくぶりの着衣の感覚に少しだけ困惑した。それと同時に、長かった牢獄生活を振り返る。淡々と繰り返される時間の流れさえも、そこにはなかった。クライムは懐に形見の懐中時計を忍ばせて、鉄扉を開ける。冷たい感触。錆がざらつく嫌な音に迎えられて、少年は鎖と汚泥の部屋にそっと別れを告げた。
久しぶりの靴と布の感触に戸惑いを覚えながらも、クライムはベルナルドに命じられた二階の大広間へと向かう。看守の目が痛い。所詮、あの少将の態度が騎士団全員の態度とは違うのだ。靴擦れに心の痛みを紛れ込ませて、クライムは急いで看守が指さす方向へと足を進めた。地下の泥と蛆塗れの捕虜置き場とは異なり、清潔に整えられた廊下が彼には眩しかった。
塵一つない邸宅。かつての我が家。時々、ふと襲い来る見ず知らずの他人に思い出の場所を蹂躙される屈辱感、劣等感、敗北感。地下から一階へと続く階段を上がりきると、屋敷の玄関正面に飾ってあった彫刻像はすべて姿を消していた。恐らく、ベルナルドらの軍資金として闇商人に流れたのだろうとクライムは思った。付け加えるならば、一階から二階へと上がる階段の踊り場に飾ってあったピエタ家代々の当主の肖像画も姿を消していた。惨めだった。自分の生きた証が段々と消えてゆく。そして、家族も名前も、何もかも。
二階の長い廊下を恐る恐る歩いていくと、突き当りに大広間があった。三回のノックの後、クライムは重い扉をぎいと引く。隙間から漏れる胸糞悪い大将ウェインの声。ベルナルド少将の「入れ」という鋭い命令に肩を竦めながら、二人の軍の中枢の前に歩み出た。片膝を付き、上辺だけの忠誠を取り繕う。この敵の従順な態度に満足した様子で、軍の頂点を司るには、いささか馬鹿と阿呆が過ぎる大将が、にたにたと粘着質な笑みを浮かべてクライムに話しかけた。何度聞いても、少年の背筋には悪寒が走る。
「あの反抗的な手に負えない少年が、たった二か月の監禁でここまで従順な子猫になるとは。あのときに殺さず、粗末な命を生かした我らの温情に感謝するがいい」
がははと小物臭い笑い声を広間に響かせた後、気を取り直したようにウェインは、真面目そうな面持ちで本題を切り出す。
「おっと、前口上が長くなってしまったな。貴様に我らの軍服をわざわざ着せ、こうして招集したのか。今日から捕虜として貴様を監禁するのではなく、一介の兵士として貴様を使うことにした。何せ、度重なる戦争で最強と謳われた我が軍も兵士の消耗が激しい。貴様の実力如何を問わず、我が軍の手駒として使おうと先日の軍法会議で決まってな」
現金なウェインのことだから、どうにかしてお気に入りの性欲処理道具の生存方法を探ったに違いない。きっと、その裏の事情まで把握しているベルナルドに一杯喰わされたのだろう。兵士として駆り出す代わりに、面倒は自分が見る、と。あいつのことだ、どうせ大将を屠るための道具の確保が最優先事項だったはずだ。こんな状況になっても、自分自身を観察できる冷静さを、今までクライムは恨めしいとは思ったことはなかったが、この時ばかりは多少それに嫌気が差した。あくまで道具の一部としてやり取りされている自分の分析など、つまらないばかりか生きる気力を自分から失くして行っているのと等しい。
「本日から貴様は、そこにいるベルナルド少将付きの小姓として身を粉にして働くがよい。待遇は、今日に迫った戦での功績で決めさせてもらう。精々、虫けらは虫けららしく死地に這いつくばることだな。もしくは我が軍の性奴隷として一生を捧げても、もちろん構わんがな。どちらが賢い選択かは、頭の回る貴様であれば容易いであろう?」
「我としては、貴様が飼い馴らされた子猫でいるのが一番いいのだがな」と傲岸に満ち溢れた満面の笑みでクライムを見つめてくる大将に、ほとほと呆れ果てたのかベルナルドがウェインの名前を呼んで強引に現実に引き戻す。我に返った大将は、部下に一瞥をして上司面で命令を出す。
「ブラッドよ、その坊主を連れて下がれ。そして、貴様にそいつを譲ってやった我の寛大さと慈悲に跪くがよい」
上司の投げかけには一切の興味関心すらも持たずに、ベルナルドは跪いているクライムを見下すと、零下の命令を飛ばす。
「何をもたついている。さっさと行くぞ、クライム」
形だけの敬礼を大将にすると、クライムはベルナルドに続いて大広間から退室した。長い廊下をかつかつと急ぎ足で抜けると、二人は一階に降りて食堂らしき場所へと辿り着いた。ちょうど二階の大広間の真下である。そこでは多くの兵士が食事を摂っていた。彼らは少将の姿を目に留めると、一斉に椅子から立ち上がって彼に向って敬礼をする。一部の者は上司のために席を譲ろうとする仕草を見せたが、ベルナルドの手がそれを制止した。
「俺たちは空いている隅の席で構わん。俺は、このでき損ないの新入りに説教を垂れに来ただけだ。普段通りに食事を続けろ。多少の無礼には目を瞑る」
「は!」という大合唱に迎えられ、クライムとベルナルドは空いていた廊下側の隅の席へと腰かけた。席に着くやいなや、無言で彼はクライムに「俺の分と合わせて二人分の給仕をして来い。仮にも貴様は俺の小姓であろうが」と重圧をかける。
クライムは、回りを見よう見まねで食事の配膳を行う。牢獄生活の時とは大違いの豪華な献立に、内心驚きを隠すことが彼はできなかった。綺麗な水、ふわふわのパン、温かいスープ、そして、骨付きの肉。戦争前だからということもあろうが、目が眩むような食べ物である。スープ一滴こぼさないように細心の注意を払いながら、真っ先に少将の元へと盆に乗せられた食事を運ぶ。「まあまあだな」という褒めか貶しか微妙な言葉を背に受けながら、クライムは再び自分の配膳のために席を立つ。戻ってきたときには、当たり前だが既にベルナルドは食事を堪能していた。
最初は二人とも無言でパンを頬張り、肉にしゃぶりついていたが、この圧迫感に折れたのは、やはりクライムの方だった。無言でスープをすするベルナルドに、少年は耐えきれなくなった質問をぶつける。
「――ウェインに対して、いつもあんな感じなのか?」
「貴様の質問とは、そんなものか。ふっ、くだらんな。いけ好かない奴に媚を売る必要などない。そもそも、俺は皇帝に忠誠を誓い、皇帝の命でこの軍に名を連ねているだけ。それ以上でもそれ以下でもない」
朝食を食べ終わったのか、ベルナルドはスプーンをかちゃりと置いて少年を見据えて語り出した。理路整然とした語り口から彼の中将としての知能の高さが伺える。クライムはパンを食べる手を止めて彼の口の動きに集中した。「明日の作戦だ」と言って少将は話し始めた。
「ウェルトには、四大領邦があることは知っているな?」
「東のピエタ家、西のプファイル家、南のクラウディウス家、北のベグラーベン家だろう」
「そうだ。聡明なプファイルとクラウディウスの両家は、サミュエル陛下のご方針に賛成の意をはっきりと表明した。軍事貴族のプファイル家も、法服貴族のクラウディウス家も、要職が皇帝直々に賜われている。しかし、意固地にも反対の意を表明し、ウェルトの配下となることを拒み続けてきたのが貴様の生家ピエタ家と、明日の侵攻対象であるベグラーベン家だ。以前と変わらない自治を認めろなどという傲慢さ、片腹痛いわ」
ぐいと蒸留酒の勢いで水の入ったグラスを空にするベルナルド。上気こそしていないが、瞳には怒りが宿っている。
「貴様らピエタが計画以上の粘りを見せたのが気に食わん。兵の摩耗が予想を上回ってしまった。非常に腹が立つが、前にも言った通り、貴様を今日の作戦時に陽動として最前線に駆り出す。兵の消耗と損失を最小限に抑えるために、ベグラーベンの領地一帯を焼き討ちにする。最初は使い物にならん土地だろうが、一帯を畑にすれば問題はないだろう」
無表情で黙りこくるクライムを余所に、少将は席を立ち、すたすたと歩み去る。
「詳しい話は、ベグラーベンに向かう時にでも話してやろう。膳を片づけたら、この屋敷の裏庭まで来い。貴様が使えるのか見極めてやる。武器はその際に支給してやるから、心配しなくともよい」
クライムに短い命令を残して、ベルナルドは食堂から消えた。
食堂に取り残されたクライムは朝食の摂取後、少将に告げられたとおりに屋敷の裏庭に向かった。もともとは自分の家なのだから迷わないのは当然であったが、所々置かれていたものが消えていたり、見ず知らずの騎士が屋敷を闊歩しているのを見たりすると、一抹の寂しさをクライムは感じずにはいられなかった。
壊滅の日から季節が巡り、外の庭園には相も変わらず蔦が生い茂っている。朝露に濡れた緑が眩しい。規則正しく並んだ花壇には、壊滅が訪れる前に庭師が植えた花々の種が芽吹き、若草色の葉を太陽に向かって大きく広げていた。小高い丘の上に位置する元ピエタ家の屋敷から、クライムは領地一帯を見渡した。何も変わらずにあるのは、領地を取り囲む黒い森と壊されることのなかった民家だけ。不気味な静けさの町に、生命の息吹をもたらす季節がやってきたことに皮肉を感じ得なかった。少年は、同調しつつある華やかな過去の記憶を振り払い、屋敷の外を一周して裏庭へと回った。
ゆっくりとしたクライムの登場に怒りを露わにするわけでもなく、ベルナルドは煙管を吹かしながら虚空をぼんやりと見つめて待っていた。クライムの姿を目にすると、口に咥えていた煙管を離し、ふうと煙を吐いた。快楽を授けるあの匂いがクライムの鼻をくすぐる。
「――貴様が住んでいた頃の面影は、もはやあるまい。時の流れは残酷だな」
ベルナルドは呟いた。まるで、自分に言い聞かせているような口ぶりで。再び煙管を咥えると、右の腰に差した剣を鞘ごとクライムの方へ放り投げる。それと同時に、「貴様に支給された剣だ。早く装備しろ」と少将は顎で指図をした。少年は鞘の懐かしい感触に、はっとするとベルナルドを睨みつける。少将は「まあまあ、そんなに怒るな」と身振りで示した後、こう言った。
「貴様に父親の形見を支給したら面白いというただの余興だよ。貴様も安っぽい我が軍の剣を支給されるよりはよほど使い勝手がよいだろうに。死の悼みを弄ぶなという気持ちはわからんでもないが、敵にわかれという方が無粋で愚鈍だと思うが。それとも、俺たちを仲間だと見なし始めたのか。監禁された後のほんの少しの優しさで狂いでもしたか?」
「――うるさい」
少将は煙管を軍服のポケットに差すと、面倒くさそうに左手で重厚そうな剣を握り、切っ先をクライムの方へ向けた。「貴様は相手にならない」といった素振りである。
「かかってこい。貴様には片腕で十分だろう」
ベルナルドの判断は、この上ないくらいに妥当であった。二ヶ月もの監禁の末に弱った体には、先ほど投げた剣を両手で支えるのが精一杯だろう。今では軍服に覆い隠されて見えないが、その重ね着の下には多くの痣が残っているはずである。しかも、彼ほどではないが、少年は半分阿片中毒に陥っている。筋力の衰えが激しい少年に俊敏な動きを求めてはいない。捨て駒として、ある程度の身体能力の確認ができればそれで十分であった。本気になる必要性など鼻から少将の頭にはなかった。
反対に、蓄積されてきた散々な罵倒と嘲笑に幾らか腹が立っていた少年は、鞘を投げ捨て、ここぞとばかりに青年の挑発に無言無表情で応酬する。じりじりと間合いを詰める二人。刀身が露出した獣の牙が互いの隙を見極めあう。穏やかな風が若葉を吹き散らす中、緊迫した空気の磁場が少年と青年を包んだ。先に動いた方が負けとでもいうような張りに張りを重ねた糸が密接に絡まり合う。しばしの閑。息を殺して。瞬きを止めて。歩を戻して。
糸が切れた。
無我の突進を少年がかける。疾駆。隙だらけの猛進を流すため、身を翻して青年は衝撃との追突を避ける。
間髪。
右下に構えていた剣が左上に踊る。
猛攻。
痩せ細った体とは思えないほど切れの良い体裁きが休む暇を青年に与えない。本能を剥きだしにした二匹の肉食獣が互いの喉元を切り裂こうとして、牙と爪で懐に潜り込もうとする。打っては下がり。銀の色は交差する。唸り声は甲高く。闘志の瞳は互いを射抜く。
反動。
力で劣る少年が助走での補完を利用して青年の胸に一閃。刹那、青年が少年の脛を払う。
一転。
少年の視界が踊る。牙が削れ、獣は倒れ込む。悔しさに滲む顔。悦と興に綻ばせる唇。勝負はついた。だが、まだ足を引き摺って少年は立ち上がる。
「貴様ごときにこの俺が押されるとはな……それだけでも、俺は驚いている。これで十分だ。貴様の実力云々は測れた。これ以上、貴様の体力を消耗するのは無益だ、剣を鞘に納めろ」
少年の耳に言葉が届いていないのか、落ちていた剣を杖代わりにして彼は立ち上がろうとする。転ばされた際の衝撃は重篤なものではないと踏んでいた青年の表情が暗くなる。
「命令だ。剣を納めろ、クライム」
地に倒れる前とは違う少年の気配に青年は思わず身構える。少年は青年に同じ構えで走りかかる。閃光。走り込む中で下段に構えていた剣筋を上段に変える。その狙いは左目。
鋭い爪が剣を通じて青年の腕に鈍い衝撃を伝える。目を庇った腕に流れる電流。青年の利き腕は、痺れで一時感覚をなくした。青年は利き腕とは逆の手で左の腰に下げた剣を久しぶりに大気に晒す。少年は狂気に染まっていた。青年は初めて出会う恐怖に身がすくんだ。その隙を突かれて、少年の細腕に握られた剣が猛威を奮う。腹に食い込む峰。振り飛ばすほどの威力はないものの、油断していた青年を押し倒すには十分な一撃であった。
天高く上げられた腕が振り下ろされる。喜々とした表情の横を通り抜ける涙。歯を食いしばり、少年は渾身の一撃を落とした。空を斬る音が青年の耳に届く。迫りくる恐怖から少年は目を閉じた。
青年は、その研がれた剣先が喉元に達する前に少年の脆い刃を折った。体を捩じり、片足を跳ね上げる。揺らぐ景色。体勢を崩した少年が目を開けた時には、もう遅かった。皮だけなのかと錯覚させるほど薄い少年の腰に、分厚い青年の革靴が激しい接吻を施す。剣は宙を舞い、少年は地を跳ねた。甲高い金属音と鈍い落下音が両手を取り合って地面で反射する。
「地べたに背を付けられた相手なんて何年ぶりだ……大分油断していたとはいえ。クライム。貴様はなかなか使える、中級兵士よりもよっぽどな」
土埃を払い、少将が立ち上がる。半分気を失っているクライムの頬に平手を打つと、にやにやしながら言葉を継ぐ。思いのほかの収穫に、少将自身も満足しているようだった。ベルナルドは懐を漁ると、小瓶に入った浅黒い液体を取り出して地べたにうずくまるクライムに投げ渡す。少年は渋い顔をしながらも、しっかりと受け取った。さらに少将は少年に歩み寄り、小さな掌に煙管と白い粉末の入った薬包紙を押し付ける。
「鎮痛剤だ。今は興奮が冷めていないから痛みを感じないだろうが、数か所打撲しているはずだ。従軍する前に飲んでおけ。それと、煙の支給だ。恐怖と興奮が和らぐ」
クライムは精一杯の苦々しさを見せつけながら、一気に乳液を飲み干す。ベルナルドは豪快な少年の飲みっぷりに驚嘆の表情を一瞬だけ作ったが、その顔は事務的な命令に掻き消された。少将は訓練の疲れを癒す間も与えずに、少年になすべきことを伝える。
「井戸で一度顔を洗って来い。汚らしい顔での従軍は許さぬ。そのあと、貴様には厩舎の掃除と馬の世話をしてもらう。厩舎はここから東の場所にある。馬のいななきを頼りにすれば、すぐにわかるはずだ」
ベルナルドは顎に手を当てて命令に漏れがないか一通り逡巡すると、誰にというわけでもなく頷いて少年に背を向けて去ろうとする。
「――貴様には期待している。俺の宿願の達成も近い」
口の中に苦みを消すために少将の姿が見えなくなると、クライムは父親の形見の品を鞘に戻した。緊張が溶けるにつれ、襲いかかる打撲の痛み。視界がちらつく体に鞭を打って彼は裏庭近くの井戸へと足を運んだ。
井戸の水は清らかで、冷たかった。ざぶざぶと顔を洗うと、麻痺していた体も徐々に現実の感覚を取り戻していた。耐えきれない痛みではなかったが、クライムはもらった煙管に粉を入れて火をつけた。ベルナルドは、丁寧にも松の木くずに火をつけたものを、阿片液を飲み干した瓶に移してクライムに渡していた。ふわりゆらりと、白霧が少年の発達途中の神経回路を犯す。急速に締め付ける頭痛に少年は頭を抱えて転がり込んだ。
煙管を口から離して、ふうと煙を吐く少年の目にだぶって映る過去の傷痕。生まれては消え、表れては溶けを繰り返す家族の顔。最期まで自分を庇って亡くなった父親。直前まで自分の身を案じてくれた母親。可愛がってくれた家臣の皆。幻影は一層鮮やかに、はっきりとクライムの目の前に表れては彼を惑わす。囚われてはいけないという自制も、誘惑の煙の前には役に立たない塵芥となっていた。
再び煙管を取り出して、煙を肺一杯に吸う頃には、粉々に意識は割れて欠片が散らばっているだけだった。それを拾い上げることもせずに、心の中に風が吹くに任せて飛ばされるのをただクライムは傍観していた。自分が壊れていくことに興味も恐怖もなかった。なるようになれ。それだけだった。
遠くで馬がいななく声がする。快楽に酔った重い腰を上げると、クライムはよろよろと厩舎に向かった。死の淵を歩む少年には、眩しいほど生気に溢れる馬たちが憎らしく輝いて見えた。
馬のいななきは、ある種の生臭さを伴って少年に襲い掛かる。馬の息が上がるたびに、少年の顔に吹き付けられるそれに、クライムは悍ましさとも悔しさとも、苛立ちとも取れる蟠りを心の底に留めたまま、その世話を終えた。戦の前の空模様にしては、のどかで穏やかすぎる白々しい青さに少年は一瞥を送る。彼は腕を組みながら、厩舎の壁に寄り掛かってうとうととし始めた。興奮冷めやらぬ馬が地面を断続的に蹴っている。土埃が舞い、蹄の音が軽快に少年の耳に残響した。
規則正しい金属音が馬の荒々しい息遣いに混じって聞こえてきた。土と金属がぶつかる音に加えて、金属と金属が擦れる独特の甲高い嫌な振動がうつらうつらとしているクライムの耳を通して、彼を揺さぶり起こす。眉をひそめながら、少年が異様な気配に目を開けると、きっちりと装備を固めた大勢の騎士たちが大将と少将に率いられて、厩舎傍の庭先に綺麗に隊列を組んでいた。剣を携えた歩兵、飛び道具を背負った弓兵に大別されている。
ベルナルドがクライムの名を呼びながら、厩舎の横の少年の前に進み出た。少将は、「終わったか?」と短く聞く。少年は口答えもせずに「はい」と答えた。少年は身仕舞を正して隊列に加わろうと歩き出すが、その動きをウェインに止められた。この居丈高の人物の人を不快にさせる能力は一級品で、今日もまた、にたりとした粘ついた嘲笑が顔に張り付いている。「何を自然に軍の規律に加わろうとする?」という無言の――否、この場合は大将の顔にすべてはっきりと書かれているのだが、重圧が降り注ぐ。あくまで本題の話を逸らしながら、軍令に従わなければならない少年を焦らす大将は、やはり性格が悪い。これぞ、悪役の小物と言った具合に、だ。
「クライムよ。馬の些事、ご苦労であった。総員、持ち場に付け。出陣の儀を執り行う」
「ブラッド。我の代わりに今日の戦について話を頼む」
「――今回の戦はベグラーベン家の降伏が目的であるが、この可能性は極めて低い。ピエタの惨事があってからというもの、彼らの抵抗はなりを潜めたが、ウェルトに歩み寄ろうとする姿勢は微塵も感じられぬ。そこでだ」
大将は何もわかっていないのか、一切を少将に委ねて目を閉じて他の騎士と共に必死に耳を傾けていた。一方、ベルナルドは淡々と機械的に説明を行っていく。クライムは聞き零さぬように一言一句、噛みしめるように聞いていた。脳裏に浮かぶのは、ピエタ家が侵攻される際もきっと同じようなことが行われていたのだろうな、というやり場のない思い。
「宣戦布告の礼を既に軍は、ベグラーベンに対しとった。その回答はまだない。期日はあと数刻で過ぎ去る。例え、降伏の名乗りを上げたところでもう軍には届かぬ」
鎧で身を包んだ少将は、その隙間からベグラーベン家に対して送りつけた書状の写しを配下の騎士たちに見せながら、「一回で理解しろ」と暗黙裡に強制する。
「戦をすることは確定した。兵士は極力失いたくないため、ピエタの捕虜を積極的に使う。こいつに先陣を切って領地を火の海にさせるのだ。ピエタの一人息子とあれば、友好関係にあったベグラーベン庶子とそれなりに顔見知りであろう。その裏切りとあれば、彼らの動揺と混乱を一度に引き出せるはずだ。敵陣の戦意喪失にも繋がるやもしれぬ。残りの兵は俺を含めた将軍の護衛、ベグラーベン領地における収奪を担ってもらいたい。ピエタの捕虜の監視は俺がやる。気を揉む必要はない」
騎士たちのどよめきが大きくなる。当たり前だ。つい、先日まで捕虜であった人物――例えそれが、自分たちに体力的にも精神的にも及びもしないちっぽけな少年であっても、警戒するのが彼らの習性である。あの馬鹿な指導者を除けば。少将は、「静粛に」と鋭く発すると、「大丈夫だ、問題ない」との言葉を残し、次に繋いだ。
「先ほど、こいつに訓練を付けていたら、二ヶ月の監禁では相当弱っていたらしくてな。俺が負傷させてしまった。捕虜出身とはいえ、今回の作戦の中枢を担う。こいつがいないと、作戦が狂うのは必至だ。馬を一頭こいつにやってくれ。三等馬で構わぬ」
御馬番の騎士が「は!」と敬礼をして去ってゆく。その姿を見送ると、ベルナルドは「以上だ」と部下に告げ、クライムを引き連れて列の先頭に戻っていった。
少将の話を聞いていたのかは別として、艶々と光る毛並みの黒馬に既に跨る大将は、一応ながらどこかの騎士団の隊長と名乗るだけの風格が備わっていた。それを醸し出しているのは、恐らく馬の方ではあったが。ウェインのぽっこりと突き出た腹には、窮屈そうな鎧が不釣り合いに見えた。鎧の方が持ち主の体格に悲鳴を上げている。ベルナルドは、「見下ろされるのは我慢ならぬ」と小さくクライムにだけに聞こえるように呟くと、金色のたてがみの美しい白馬に飛び乗った。手綱を引き、馬を捌く手つきは流石武将と言ったところである。同じ目線になったところで大将は口の端を釣り上げて、少将に問う。
「悪鬼と言われた貴様も、こやつの可愛らしさに惚れこんだか?」
「――野豚の貴様と同類にするな。怖気が走る」
言葉を剣とするならば、悉く大将の突きは少将の切り返しによって流されていた。むしろ負傷しているのは大将である。
「――貴様も我の妾とならぬよう、口を慎め。隙あらば食われるぞよ」
「気色が悪い。俺が貴様に忠誠を誓ったわけではないことを忘れたのか?」
「大法螺を吹く男よ。貴様の出自が軍全体に、いや捕虜にまで知れ渡る可能性を知った上での無駄口とやらと我は取っていいのかえ?」
二人の火花散る睨み合いの中、居たたまれなくなったクライムに助け船を出したのは、偶々少年捕虜に三等馬を持ってきた先ほどの御馬番の騎士だった。見慣れていることなのか、「御取込み中申し訳ございません、ブラッド少将。少年捕虜に三等馬をお持ちいたしましたこと、ここにご報告申し上げます」と簡潔に述べると、クライムには見向きもせずにすたすたと持ち場に戻っていった。はっと我に返ったベルナルドは、大将に構っている場合ではないと馬の向きを変えた。「総員、しばし待機せよ」と号令すると、彼はクライムに支給された栗毛の馬に乗るように指示する。少年に先だって列を外れて庭の隅へ馬を歩かせ、背で少年に言葉を投げかけた。なぜだか、大将は恨めしそうにこちらを見ていた。
「クライム、個別の作戦遂行の命令だ。俺のところへ来い」
慣れない馬の手綱をぎこちなく捌き、クライムはベルナルドの傍に寄る。着けていた兜をわざわざ外し、ベルナルドはクライムの耳元で蚊の鳴くような声で囁いた。馬の鼻息で消されてしまいそうな小さな低い声を漏らさぬように、少年は全神経を集中させて耳を研ぎ澄ます。
「この戦は、貴様の軍への忠誠を見る機会でもある。昨夜の軍法会議で決まったのは、貴様の忠誠の証としてある物を俺たちに差し出すこと」
「――それは何だ?」
訝しむように、クライムはベルナルドを見る。
「貴様の母親の頸と心臓だ」
少年の息が詰まる。かつてこんなに息がしづらいと感じたことがあっただろうか。
「この戦の核の人物である貴様の母親の殺害と、ベグラーベン家の陥落が今回の最重要遂行事項だ。貴様が首を取った時点で俺たちは城壁から侵入し、領地一帯に火を放つ。貴様は火に飲まれぬように、地下に潜れ。諜報員の情報によれば、ネウマには所々地下壕があるはずだ。それと共に貴様は、不潔な黒豚の屠殺もある。ゆめゆめ忘れるな」
かちかちと歯が鳴る。指先が痺れたまま、震えが止まらない。何の役にも立たない見栄と誇りがなければ、今この場で絶叫して、失禁して、崩れ落ちてしまいそうだった。驚愕と恐怖、狭心に視点は忙しなくちらつき、瞳孔は夜を駆ける猫のように見開かれる。
「――何を怯えている?」
怯える少年を鼻で笑うと、ベルナルドは痛烈な一言をクライムの胸元に押し付けて去った。それは心臓を抉り出すように、ゆっくりと且つ強引に少年の正気を毒していった。思わず、唇を裂けるまで噛みしめる。疼痛が辛うじて、少年が少年であることを保たせていた。
「もう、貴様は戻れぬ。穢れた俺たちと同じなんだよ」
豊かな農場が領地一帯に広がるのどかな田園風景を切り裂く叫び声。「ウェルトが攻めてきたぞ!」忙しく叩かれる教会の鐘。南西の方角に見える不気味な鎧の集団。家の中にいた女たちは窓を閉め、扉を引いて閉じ籠り、外に出ていた子供たちは一目散に教会の聖堂に駆け込んだ。
寝静まった街を武装した男が剣や斧、弓を携えて盾を作る。近づいてくる帝国軍に対して雄たけびを上げ、各々が愛用の武器を構えた。一歩も通さぬという気迫が充満していた。「帝国の犬め!」
ぼうと低い音が響く。開戦の合図だ。流星のごとくネウマの街に降り注ぐ矢。応酬をするかのように標的に絞られる弦。きりきりと限界まで引かれた矢が人間の手を飛び出して、喉元を狙う。ばたばたと泡を吹いて倒れていくさまが愉快だと矢は、襲い続ける。
馬の速度は上がり、帝国軍の高笑いが風に乗ってネウマの街に落ちてきた。門の防御壁を軽々と馬が飛び越える。至近距離で放たれる火薬の付いた矢に乗って、華麗に馬から飛び降りたベルナルドが剣戟を披露する。ウェインは門を壊し、後に続く歩兵を招き寄せた。当初の作戦とは打って変わり、短期戦に持ち込むようだ。火が舞う中、クライムは馬に乗ったままネウマの街に侵入する。
火が家屋に移り、真っ赤な花を咲かせていく。かつて見た光景に、逃げ出したい衝動に駆られるが、クライムにはもはや行動に移す気力を完全に奪われていた。抵抗の二文字は、少年の思考回路から排除されていた。家屋から家屋へ、人へと際限を知らず火は踊り狂う。断末魔が木霊する。馬に跨り、クライムはネウマの街の最奥を目指す。火の粉が少年の頬を焦がした。
麻痺した脳がベグラーベンの居城を誤認する。それは少年の憎悪と相まって、噂だけに聞くマクシミリアンの王城として少年の脳内で処理される。馬を乗り捨てて腰から剣を引き抜く。鎧の重さなど気にならないくらいに少年は興奮していた。城門を守る兵士を目にも止まらぬ速さで刺し殺した。剣を肉塊から引き抜くたびに顔にかかる血飛沫。少年が兜を上げて苦痛に捩れる兵士を一瞥すると、彼らは驚愕の眼をしたまま、息を引き取った。城門の守りは、不気味なほど手薄だった。
少年は剣を一旦鞘に納めると、勢いよく扉の引き金を引く。背後でベルナルドの言葉が反響する。ぼろぼろになった少年の心は、汚れきっていた。
ベグラーベン城は異様な静けさに包まれていた。白い大理石で覆われた床と鎧がぶつかる音のみが響くだけだ。何を目的に怒りを沸騰させて歩いているのか、クライムには判断する術がなかった。ましてや、自分を突き動かす得体のしれないものの正体も。城内の中央を分かつ廊下は長く、暗かった。ぎいと右斜め前の扉が開く。びくっと剣を身構える少年。
隙間から漏れる光に小さな影が映し出されていた。顔一杯に怯えを描いた小さな少女が少年の名を呼ぶ。ただ、その名は少年の脳には、文字の羅列としてしか映らない。少女の儚い問いに、少年は答えなかった。 「パパは……どこ?」
少女は涙を堪えて少年を詰問する。一回り体の大きい少年に立ち向かう彼女の足はぷるぷると震えていた。しかし、少年は答えなかった。
「――母さんはどこだ?」
少女は首を横に振る。
「――わ、わからないわ」
目を逸らして必死で隠そうとする少女の首元を掴み、少年は居丈高に脅す。
「答えろ。さもなければ、お前の父さんの命はないと思え」
再び、少年は少女に問うた。
「母さんはどこだ?」
口を堅く閉ざした少女は、喉に剣を突き付けても割ろうとはしなかった。少年は苛つき、舌打ちをする。少女を人質にとることを思いついた少年は、剣を突き付けたまま腕で彼女を抱え直す。「暴れたら殺す」と再三、少年が少女の耳に吹き込むと大人しくなった。
人気のある方を探しながら少年は廊下を進んだ。「任務遂行」の四文字が少年を縛り、正常な思考を麻痺させていた。死んでもいいと思っていた頃が嘘のようだ。解放されてから数週間で、少年は死ぬことが怖くて堪らなくなっていた。もう、既に人も殺した。何もかもに躊躇いがなくなり始めていた。
廊下の左右の壁面に供えられている蝋燭が途中から消え、長い廊下一帯が薄暗がりに包まれた。少年が進む方向とは逆の方向から、誰かが近づいてくる音がする。その音の主は、クライムの手前一部屋分のところで立ち止まると、静かに声を上げた。暗がりでその姿はよくわからない。
「その子を離しなさい」
「叔母様!」
クライムの腕から身を乗り出して、少女が叫ぶ。ドレスの袖は濡れていた。目を擦りながら、少女は少年の腕を抜け出そうとする。少年は、懐かしい声音に思わず戸惑い、言われるがまま少女を離してしまった。たったったと少女は女性の元へと駆けて行き、彼女の足元の影に隠れた。女性のドレスの裾から垣間見える小さな愛くるしい緑青色の瞳が少年を睨みつけている。
「あなたは逃げなさい。子供のいるべき場所ではないわ」
「でも……」
「――あなたがいなければ、ベグラーベンの血は絶えてしまうの。わかるわよね」
少女は短く息を吸うと顔が崩れそうになるのを、歯を食いしばって耐えながら頷いた。両手で握っていた女性の裾を名残惜しそうに離すと、一目散に闇の奥深くへと消えた。女性は少女の姿が完全に見えなくなるのを待ってから少年に向き合い、慈愛に満ちた目で優しく告げた。
「――殺しなさい」
あなたがどんな形であれ生き延びてくれれば、と続ける女性はクライムに穏やかに微笑んだ。
予想していなかった事態に混乱する少年の背後から、聞き覚えのある粘ついた声が降ってくる。後ろを振り向くと、血塗れになったウェインが少年の肩に手を置いて彼の良心の最後の砦を奪いにかかっていた。
「いい子だ、クライム。そのまま殺せ」
目を見開いてパニックに陥る少年は、その場にへたへたと座り込んでしまう。女性がウェインを敵愾心に溢れた表情で見つめていた。「所詮使えない奴であったか」とでも言うように、ウェインはわざとらしく大きな溜息をつく。恐れ戦いて大将を見上げるクライムは、どうしたらいいかわからないとはっきりと助けを求めていた。
「命を恵んでやった我に逆らうのかえ?」
その言葉で硬直したクライムは、ふらふらと立ち上がり眼前の女性を見据える。呼吸が早くなっていた。剣先が揺れる。視界がぼやけ、惨劇の日に重なる。父親の首を刎ねるベルナルドの姿が闇の中にはっきりと映し出されていた。少年は幻影に向かって憎悪と憤怒の矛先をあらん限りの力でぶつけた。右下段に父の形見の剣を構え直し、少年は疾駆する。
剣が生々しく肉に突き刺さる音がした。上から咳込む音と共に血反吐が舞い降りる。弱弱しく少年を抱き締める柔らかな腕。温かな血液に混じって冷たい雫が少年の額に落ちていた。戸惑いを隠せない少年に、女声は優しく彼の耳元に言葉を残す。
我に返る少年の目に飛び込んできたのは、最愛の人の死に顔だった。女性の腹から止めどもなく零れ落ちる血液が少年と彼女の足元に水溜まりを作っていた。少年の肩にずしりとのしかかってくる重みが彼を現実に呼び戻す。剣を抜いた両手は真っ赤に染まり、それを握る気力は立ち消えた。剣が床に転がった。女性を抱えて膝をつき、己の罪科を悔やむ少年。涙は枯れたままだった。
「いい子だ、クライム」
ウェインはたった一言だけ呟くと、踵を返して城から去ろうとする。少年は、最愛の人を抱きかかえて一度床に安置すると、転がった剣を拾い上げて大将の背に突き付けた。
「――何をしているのだ?」
少年は答えない。答えは血がこびり付いた剣が示していた。
「裏切るのかえ?」
がははと相変わらず小物臭い笑いを響かせると、真面目を取り繕ってウェインは続けた。
「――我に逆らうとは面白い。貴様の軟弱な体など、一捻りも甚だしい。死ぬのは貴様の方だ。野心の塊の隼に縋るなぞ、愚かしい裏切り者め」
少年は大将を睨みつけた。両目とも血走っている。
「ベルナルドの洗脳は流石だな。我も貴様を使って憎たらしいあやつを屠ろうと思っていたのだが……先を越されてしまったか。相変わらず我の隙を掻い潜りおる奴よ」
自嘲気味につぶやくウェイン。少年の剣より随分大きな剣を背から抜く。いつも目にしている鈍重な姿からは想像の付かないぐらい俊敏な体裁きで少年と対峙した。体型とは不釣り合いな軽やかな動きに少年は焦りを隠せない。一応ながらウェルト軍近衛大将を務めているのだ、伊達に軍事貴族の出身ではないらしい。大将はにたにたと笑みを口端に浮かべ、じりじりと間合いを詰めていく。
クライムは狂気に染まった自分に気づき始めていた。生への異様な執着と罪からの激しい逃避が少年を更なる異常な殺戮の狂気へと駆り立てる。自分の中に眠っていた――否、巣食ってしまったという方が正しいだろう――制御不能な得体のしれない何か――それは、理性はおろか情動や本能とも一線を画した別の根源的なものである――が解き放たれた。
どす黒い怨念を纏わりつかせたような気迫。少年は生きているものの、死んでいた。殺るか殺られるかの二択に、少年は恐怖を感じなくなっていた。そこにあるのは、執念のみ。
刹那、刃が走った。少年の腕を裂き、血液と共に脂肪を掻きだした大剣。少年の剣は男の心の臓を刺突し、大量の血液を蒔き散らかした。この世の声とは思えない雑音がわんわんと残響する。ウェインの最期の叫びだった。
「呪ってやる! 貴様も彼奴も我の何が憎い? 帝国の忠実な犬であり続けた我のどこが! 貴様は罪の名に一生縛られるがいい!」
捨て落ちた大剣を拾うと、雑音を消すために少年は男の首を両断した。耳障りな音は瞬時に途切れた。紅の雨が降る。体から切り離された自由な首は、ころころと転がって壁にぶつかって止まった。歪んだ醜い顔がクライムを凝視している。少年は、自分の背格好に不釣り合いなぐらい重い剣を持ち主の首に頭から突き刺した。それを墓標の代わりだと言わんばかりに。ベグラーベン城は、文字通り死の城と化していた。
少年は重たい鎧を脱ぎ捨てて、最愛の人の亡骸に駆け寄った。生まれてきたときから無限の愛情を注いでくれた唯一無二の女性を殺してしまった少年の後悔は、海よりも深く山よりも高かった。女性の指で輝く指輪を自らの指に嵌めると、クライムは彼女の胸の上に突っ伏す。涙はおろか嗚咽さえも漏らすことのできない自分を恥じた。静謐だけに支配される死者。それは執念に縛られる少年には到底触れることができない領域だった。
少年は懐を探り、一枚の懐紙を取り出す。剣についた血痕を丁寧に拭き取った。そして、冷たくなっていく女性の頬に触れて、口元を流れていた血を少年は舐めた。古くなった鉄の味が舌を這いずり回る。歯の裏に残った血の滓は、少年の鼻粘膜を刺激しただけだった。
そっと少年は、愛しい人の乳の肉を削ぎ落とした。まだほんのりと温かさが残る肉塊に付着する滑らかな血液を愛おしそうに舐めて、啜り出す。癖になる鉄の味が口腔内に広がる。舌で肉を愛撫すると、それを歯で引きちぎった。咀嚼するたびに味蕾を刺す肉片が少年の唾液と絡まり、粉々にすり潰される。粘つきながら絡まったそれは、喉の奥へと蠕動しながら送られていく。少年は無我夢中で呑み込んだ。クライムの剣を握る手が躊躇いと恥じらいを忘れて、死人の指を、腕を、脚を、腹を、顔を無残にも蹂躙していく。
少年は猛禽の眼をしていた。歪んだ愛が少年を導く。女は肉を抉り取られて、生前の姿を留めてはいなかった。それでもなお、少年は飢えが満たされるまで女の肉を貪り喰らう。「ずっと一緒にいよう」少年は既に聴力を失った最愛の人に喜々として語りかけていた。不快な咀嚼音と反芻音が静寂を破り続ける。
少年が手にする剣は少年の命を生んだものを奪った。それはまだ鞘に納まることを知らずに、女の左胸を開ける。役目を終えた心臓がそこに眠っていた。クライムは器用に剣を用いて、女の体と心臓を繋ぐ血管を切った。大事そうに女の体内から取り上げると、掌大の臓器に少年は接吻を施した。
母の心臓は何も応えず、父の形見は何も言わなかった。
少年は、冷たい心臓を軍服のポケットに丁重に仕舞い込んだ。剣を血溜まりの床に置き、少年は女の眼球を掘り取る。てらてらと体液に濡れてまるで飴玉のよう。少年は一度匂いを嗅ぐと、満足そうに微笑んでそれらを口に含んだ。口の中で蕩けだす目玉を下で転がしながら堪能する少年。何かが潰れる音が異様な大きさを伴って、廊下に響く。ごくり。少年は軍服の袖で口元を拭いた。
少年は母の血液を付着させたまま、父の形見の剣を鞘に納めて立ち上がった。鎧は脱ぎ捨てた状態で放置した。「僕には不要なものだ」と。壁際に落ちていたウェインの頭蓋を汚らしい剣に突き刺したまま、引き摺って来た道を辿ってその城を後にした。
空が赤かった。暮れなずむ橙の雲を抱く空は、鮮やかに燃えていた。帝国軍が放った火が柱となり、街を取り囲んでいた。肉が焼け焦げた臭いと細かな灰を伴った煙が少年の眼と鼻を刺激する。酸素が薄い。少年は、ずるずると首を引き摺りながらベルナルドを探した。足が鉛のように重い。一刻も早く火を逃れ、地下に潜らなければならなかった。壕の場所さえ把握していない少年はまず、この使い物にならない頭蓋を少将に見せたかった。腕の筋肉が引き攣る。
燃え尽きた死骸が転がるネウマの大通り。幼き頃、母に手を引かれて歩いた道が血と骨で彩られていた。ごうごうと燃え盛る炎は際限を知らずに空へと背を伸ばす。がらがらと崩れていく煉瓦の壁。少年が周りを見渡すと、既にネウマには帝国兵が一人残らず撤収した後だった。大通りの真ん中を落下してくる屋根に気を配りながら、少年は彷徨った。家々の扉は無残にも破壊され、火に巻かれていた。辛うじて火災を逃れている家の扉からは、輪姦の限りを尽くされた女の死体が乱暴に積まれているのが見える。棚や机の引き出しは荒らされており、金目の物や食料は粗方盗まれたようだ。
城からひたすら通りを下り、門の前へとクライムは辿り着いた。ほとんどが住民の遺骸の中、点々と軍の兵士の遺体が打ち捨てられている。逃げ遅れたのか、それとも火の回る速さを追い越せなかったのか、倒れて痙攣している馬も転がっていた。門の付近は最も火の手が強く、立っているのがやっとだ。足元はふらつき、立ち眩みに身を委ねてしまいそう。肺が徐々に悲鳴を上げ始める。大通りから外れた西の方角に人影が霞んで見えた。敵か、味方か。確たる証拠もないまま、少年は揺らぐ影を頼りに近づいていった。
熱さで皮膚がただれてしまいそうな熱風の中、ベルナルドが空を仰いでいた。兜も鎧も脱ぎ捨て、灰褐色の短髪が火の粉と踊っていた。密集した住居地帯でベルナルドは、少年が何かを剣に突き刺しながら自分の方へ来るのを見ると、待っていたと言わんばかりに彼を迎える。
「――ベルナルド、少将」
少年は息も絶え絶えに少将に帰還を報告する。戦果は片手に携えていた。
「貴様の活躍、ご苦労であった。俺たちの軍もベグラーベンの当主を殺害することに成功した。上級兵の報告によれば、この地の財産も大方収奪したようだ。帝国の領土に近々ネウマも正式に組み込まれるだろう」
満足げにベルナルドはクライムに告げる。
「貴様が握るその剣は、ウェイン大将の物だと思うが、違うか?」
「はい、その通りです」
「――ということは、貴様は大将の抹殺に成功したのだな?」
そう言うと、ベルナルドは剣に突き刺さる生首をじっくりと眺めた。不快な物体を興味津々にといった具合だ。長い距離を引き摺られたせいで、ウェインの首は額の肉が削げ落ち、髪が禿げていた。ぎょろりと飛び出た目玉が醜悪さを一層醸し出していた。
「はい」
少年は機械的に短い返事をしただけだった。
「見事だ。すべては計画通り。素晴らしい」
思わず少将は感嘆の声を上げる。命令通りに事が運ぶとは恐らく思っていなかったのだろう。厳格を絵に描いたような男の顔が喜びに解れていた。
「――して、貴様の母親の心臓はどこだ?」
少年は軍服を漁り、静かに母の一部を少将に恭しく捧げる。
「――俺が預ろう」
ベルナルドの白い手袋の上に乗った血みどろの臓器。
「火の勢いが強い。逃げるぞ」
クライムを呼び、ベルナルドは細い小路の突き当りの家に侵入する。玄関と広間を突っ切った先にある寝室に二人は入った。全くの無人であった。炎に閉ざされた静けさが煉瓦造りの家を支配する。少将は二つのベッドをどかし、その床を調べると、地下へと続く抜け穴を見つけた。それはかなり深く風が吹き抜けていることから、どこかへ通ずる道らしい。吹き荒ぶ風は、燃え滓の焦げ臭さがしなかった。町の外に続いているようだ。
「ここを降りると、近隣の村に出るらしいな。この家以外にも複数こういう設備はあるらしく、既に他の地下壕を使って兵は逃げた。戦死した者を除いて……」
指を折ってベルナルドは欠員せざるを得なくなった兵の数を数える。成功したとはいえ、片手では足りないぐらいの兵がこの世を去ったようだ。大将は兵に入ってはいないだろう。あくまで軍に所属していた兵ではなく、謀反者として処分するつもりらしい。
「その首は捨てておけ。サミュエル皇帝に捧げる戦果としては大層見苦しいものだ。だが、剣は勿体ない。こいつに不釣り合いなぐらい高価な一級品だ。捨てられては困る」
少将は続けて呟いた。
「稀代の鍛冶職人フォルジュの手によるものは競売にかければ、何億リアンにも跳ね上がる。そのような代物をなぜ驢馬が持っているんだか」
そのことだけでもベルナルドは腹立たしいようだ。刀身が剥きだしの剣のやり場に困った少将は、その家の絨毯を失敬して即席の鞘を作る。大剣を巻いて腰の革ベルト一本を用いて、鞘から暴れないように固定すると、もう一本の革ベルトに括り付けながらうまく背負った。
「しかし、謀反者ベグラーベンとピエタの混血の心臓を皇帝に奉るのは如何なものか」
掌に置かれたままの心臓を見つめたまま、ベルナルドは溜息を尽く。熱気で乾燥した血が凝固して血管の切り取り口を塞いでいる。死んで幾時間か経ったのだろう。弾力性を失い始めている肉の壁が男の指圧を押し返す。垂直抗力と重力の釣り合ったベクトルが狂ったように。男は、不気味な一つの死んだ臓器を勢いよく握り潰した。
男の指が肉壁に食い込んだかと思うと、出口を無くした血液が爪で作られた小さな傷口目掛けて飛び込んでくる。どろり。不健康そうな血の塊が傷口をこじ開けてベルナルドの革靴の上に落ちた。ぱっくりと空いた穴からは、動脈弁と静脈弁が顔を覗かせていた。
「ベグラーベンとピエタの混血は……ここで絶えた。残るはクライム、貴様だけだ」
静かにベルナルドが言葉を吐き捨てると、不気味な殺気を纏った少年が少将の前に立ちはだかる。
「ベルナルド少将」
「何だ?」
不可解な気配の変化に、少将は怪訝な顔をして応じる。利き手は腰の剣の柄に触れていた。
「どういう料簡でそれを潰した?」
それまでの従順な態度とは打って変わり、少将の胸倉を掴んで問い正す。背の低いクライムがベルナルドを宙に浮かすことはできなかったが、彼の剣幕は真剣そのものだった。視線は少将を見据えて離さない。
「――僕の一部となるはずのものをなぜ、潰した?」
「な、何を言っている、クライム……」
少将の目に、少年の口元の血痕が止まる。青年の脳を横切る一筋の電流。
「おまえの一部をもらおうか。対価としては安いぐらいだ」
「貴様……もしかして……」
少年は、青年が言葉を言い終わらないうちに壁に突き飛ばすと、剣を鞘から抜いて彼の端正な顔に刃を刺した。耳を劈く悲鳴。途切れた瞬間に抜かれる剣先。再び断末魔のごとく絶叫が迸る。男の顔を走る血液と房水。様々な体液が混じってぽたぽたと床に染みを作る。生臭い匂いが鼻を衝く。
左手と両膝をつき、項垂れる少将。右手は顔に添えられ、指と指の隙間から赤い流動物が零れ落ちていた。鼻からも赤い雫が垂れている。少年は無表情に佇み、剣を抜くと同時に引きちぎった物体を「まだ足りない」と不満げに見つめる。白濁した水晶体。毛細血管は破裂し、角膜は剥離していた。瞳孔から網膜に至るまで一直線に貫かれた眼球が、青年の眼窩から抉り取られて少年の掲げる剣に串刺しされている。眼底から剥かれた眼筋が痛々しさを倍増させていた。
「お、俺の右目を!」
獣の遠吠えのように狂った雄叫びを上げながら、少将は床をのた打ち回る。少年は少将の苦しむ姿にほくそ笑むと、ウェインそっくりの粘ついた笑みを顔一面に貼りつけて見下す。剣を地に差し、片足で眼球を丁重に引き下ろす。クライムは純真無垢な子供のように、盛大に血と組織液でぬるぬるとした小さな球を磨り潰した。少年のブーツの底にはタンパク質の粉砕片が溝に溜まっている。嘲笑が止まらなかった。
ベルナルドは真っ赤に染まる視界の端で少年の姿を捉えて苛んだ。興奮の波が去り、段々と冷静さを取り戻していた少年にとって、少将の怒りはただただ恐怖でしかなかった。ちらつくのは、足元に広がるぬかるんだ血の沼と白く柔らかい滓。自分が何をしたのか、少年は思い出したくもなかった。ぎょろぎょろと片目だけの少将が、この世に存在する逃げ場という逃げ場を少年から奪おうとしていた。この傷で助かるはずもないという諦観と、野心という生への執着が引き起こした燃え盛る憤怒。煉瓦の壁を隔てて燃え滾る灼熱に劣らぬ激しさだった。
「どうして、俺を傷つけた! 答えろ、少年!」
少年は、既に名前すら呼ばれなくなっていた。
「貴様の声なぞ、聞きたくもないわ! 業火の中で自らの罪を悔やむがいい!」
ふらふらになりながら、青年は少年を渾身の力で蹴飛ばした。腰の剣を引き抜くと、寝室の窓をばりばりと割った。燃やし尽くして燻っていた火が、ここぞとばかりに民家の中へとなだれ込む。煉瓦造りの家屋の中に流れ込んだ炎は、木造の家具に引火してさらに成長を遂げる。ベルナルドはよたよたとよろめきながら、焦点の合いにくい片目で地下壕へ下って行った。地下と地上を分ける床の蓋は周到に閉められた。少年は腹を空かせた火柱の格好の獲物として、密閉性の高い煉瓦の家に一人取り残された。
息が詰まる。少年が衝撃から目を開けると、そこは火に呑まれていた。熱風が天井を巣食い、がらがらと音を立てて屋根が落下する。煙は酸素を喰い尽し、二酸化炭素を吐き続ける。少年は剣で軍服の裾を切ると、口と鼻を覆った。応急処置でしかなかったが、少年は、生き残る時間を少しでも稼ぎたかった。
少年が非難する途中、部屋の棚に置かれていたランプに肘が当たった。それは倒れ、油が零れた。我先にと火が油を貪り食らうと、瞬時にそれらは肥大化する。玄関の扉をこじ開けて、少年は外へ出た。背後から迫り来る火は少年の罪科を呪う。
「――うっ」
酸化した空気がそこには充満していた。淀んだ空気が催す吐き気が少年の足を遅くする。「逃げなくては」その命の使命感だけが少年を死地で奮い立たせていた。刺激臭のせいだろうか。鼻水が止まらない。焔の光が異様な輝きで襲ってくる。視界が眩しい。道が反射して白くぼやける。どこに逃げたらいいのかさえ、少年はわからなくなり始めていた。
汗が毛穴から滝のように流れる熱さなのに、少年の背筋には寒気が走る。震えが止まらない。体が重い。きりきりと針を刺すような腹痛。明らかな体の異変が次々と少年を死の淵へと引きずりおろす。口から涎が止まらず、じんわりと口布を濡らした。ぶり返す全身の痛み。服用していた浅黒い乳液が切れたらしい。体の節々の痛みはさらに強烈だった。
少年は教会の前で力尽きた。門前には、子供たちの死体が並んでいた。フラジョレットの時と同じ光景が眼前で繰り返される。少年の過去の引き金は弾丸よりも早く引かれた。
幻聴が少年を襲う。屈強な父の絶叫。少女の怯え。清廉な母の悲鳴。征服者の呪い。
幻覚が少年を虜にする。父の首が飛ぶ。母の腹を刺す。友が殺され、親族が嬲られる。男は吊るされ、女は犯される。燃えていく民家。崩れていく街並。荒らされていく、壊されていく、奪われていく。
逃げ場を探し求めて、少年は狂ったように叫び続けた。
火は三日三晩燃え続けていた。黒焦げた街の死骸からは、死んだように眠る少年が絶えず、うわ言を繰り返す。右腕の裂傷は赤く腫れ上がり、膿んでいた。心は壊れ、思考を停止していた。黄金色の髪は煤塗れで、汚らしく。軍服は血反吐で、汚らわしく。それは戯言を垂れ流す人形のようだった。少年は喉が潰れるまで繰り返す。「僕は、あの日死んだのだ」と。
外伝『身捧人』
「貴様、いい目をしている」
小さな薄汚い少年の目の前に現れた男は、少年を見るなりそう言った。
「この私が憎いか?」
本音を言えばそうだった。この男に限らず、自分がこの現状に甘んじなければならない要因全てが腹立たしかった。少年は男を睨む。
「スラムに視察に来たのは久しぶりだが……こうも生きのいいのが残っているとは。身分に甘んじたていたらくな武臣どもより、このような幼子を一から教え諭す方が私には性に合うのだ」
頭のてっぺんから爪先まで真っ黒な男は言う。「貴様、スラムへ来てどのくらい経つ?」と。
「気がついたときには、ここにいた」
少年は話すのも億劫だと言わんばかりに返答する。小さな細められた猛禽の眼に、男は満足げに笑みを浮かべた。男はしゃがみこみ、少年の顔を覗き込む。これでもかというくらい、まじまじと。
「――外を見てみるか」
少年は答えない。男を取り巻く家来の気色が殺気立つが、男が静止する。
「私を警戒するか。当然の反応だ。だが、私は貴様に問うている。外が見たいか」
薄い愛想笑いの下には、男の本性が見え隠れしていた。それは、一度目の問いよりも少年にはっきりと見せつけるように。婉曲的な体裁の裏には、不可避な脅迫があった。それは、つまり「今ここで頷かなければ殺す」ということ。少年は頷いた。
「――なかなか処世術がわかっている。いい子だ」
艶やかな黒外套を翻して、男はそこから立ち去ろうとする。背が少年に随行を強いていた。
「そうだ。貴様の名を聞いていなかったな。名乗れ」
「――ベルナルド」
「名は体をなす、か。貴様、面白いな。ますます気に入った」
男は顔半分を覆うマスクを取り、少年に告げた。艶めかしい唇が大気に晒され、名を紡ぐ。
「私はサミュエル=マクシミリアン。いずれ、この世の王となり、神となる男だ」
サミュエルは、家臣が抗議するのを一つも耳に入れないでベルナルドに手を差し伸べた。少年は恐る恐る男のきめ細かな手に触れた。その手はあたたかく、優しかった。緩やかな鼓動が繋がれた指先を通じて流れ込んでくる。少年は、どこか懐かしい感覚に戸惑いを隠せなかった。
サミュエルの長く艶やかな黒髪が風に流れた。白く滑らかな肌はがっちりとした骨格を覆う。身に纏う衣類ためられた香りは、男の体臭と混じり独特の芳しさを醸し出していた。決して女性と見間違えることはない体格ではあるけれど、両親を知らない少年にとっては、知識を超えた美しさが舞い降りたといっても過言ではなかった。例えるなら、人知の及ばない神が両性の姿を借りて表現したものであろう。少年はそう思った。「神様は、王様なんだ」と。
その後、少年はサミュエルに連れられて外に出た。マクシミリアン城に少年は、サミュエル付きの小姓として住むことになったのだ。当時、サミュエルの気違いじみた処遇に先代皇帝を始め、多くの者が最下層出身の少年の住込みに反対した。無理もない。厳格な身分制の上に胡坐を掻いてきた一族の集合体が王家と言ってもよかったから。今になっても、どうして自分のような汚らしい人間が、いや、彼らは自分のことを人間とみなしてはいなかったろう、畜生がこの城に居残られ続けたのか不思議でたまらない。ベルナルドは常々感じていた。「今でこそ、どこぞの新興貴族に劣らない振る舞いをすることができるようになったが、あの時の俺は酷かった」
その理由の一つを挙げるならば、とベルナルドは考える。彼が崇拝してやまないサミュエルが常軌を逸した思考の持ち主であったからといえよう。悪く言えば、気違いや狂人として罵られの対象とはなるが。弟君であるローレンス陛下の聡明な判断にも助けられていたかもしれない。
現皇帝のサミュエルは、先代皇帝――つまり彼の父親であるが――の衆愚的な政治に対し、ほとほと呆れていた。有力四大貴族の機嫌を取らねば、何一つ進まない政治に危機感を抱いていたのだ。その時のピエタ家・ベグラーベン家の強硬姿勢は目に余るものがあったのは確か。当時の政治は、王権が地にまで失墜していた象徴であった。
サミュエルは、隣国への留学経験を生かしながら、老衰しつつある先代の補佐として、若いころから政治的手腕を発揮し、閣議にも積極的に加わっていた。保守的すぎる老閣にとっては、若造の戯言だと当時は思われていたらしい。暗殺や謀反の噂は風よりも早く。嫌悪と憎悪の情は言葉よりも明らかで。先代の取り成しがなければ、サミュエルの提言は、よほどのことがない限り認められることはなかった。先代の重用ぶりと反比例を描くように。
一方で、城に籠りきりであった先代の体制を反省し、彼は弟のローレンス陛下と共に城下の視察に精を出していた。活発な商業地区や貴族の居住地区といったメインストリームだけではなく、ベルナルドが居住を強いられていたようなスラムの巣窟にまで足を運んでいた。彼との出会いも、それがきっかけである。
少年だった彼が最終的にマクシミリアン城での居住を認められたのも、死を悟り始めた先代の取り成しのおかげだった。何度も何度も重ねて開かれる閣議。身の置き所のない少年は、閣議が閉会するまで、ずっと牢屋へと投獄されていた。「何をしでかすかわからぬ存在をこの城に入れるわけにはいかぬ」その暗唱語句の繰り返し。強情なサミュエルは、一切その重鎮貴族の言い分を耳に入れようとはしなかった。ローレンスが「養子として迎え入れるのはどうか」という妥協案を示すものの、サミュエルは強硬に「家臣案」を主張したまま、引き下がらない。先代は、従来の王家と貴族の対立の悪化に気を病み、病床に伏してしまった。そして、弱弱しく彼は告げる。「我の最期の願いじゃ。これから皇帝となる我が息子に賭けてみてやってはくれんか」
先代は、ベルナルドにサミュエルの立場を託して息を引き取った。その言葉通りに、少年は小姓として、相談相手として、影武者として、参謀として、側近としてどんどん出世していった。その様竜のごとしである。主君の言葉通りに少年への徹底的な教育が施され、底なし沼のように少年は貪欲に吸収していった。学問では飽き足らず、武術も一通り叩き込まれた。
「俺を通して、あの方は何を見ているのだろう」
サミュエルが見ているのは、現実に存在する自分ではない。悲しい事実が、捻くれた少年と青年の狭間で彷徨う男を揺さぶり続けている。そうなりたい。そうならなければ、自分に価値はない。しかし、その一番の疑問は、少年から成年へと成長し続けていく中でベルナルドの中から薄れていった。彼の出自を正確に知る者がいなくなるとともに。
サミュエルに恩を返したい。ただその一心で、ベルナルドは危険な任務にさえ、彼の身代わりとして従軍したり、敵軍への潜入をしたり多々の軍功を挙げてきた。認めてほしい。それだけのはずだった。だが、それなりの地位を城内で獲得したとき、彼は自分の内部の変化に気づく。彼自身、忠誠を超えた内部から自分を突き動かす激しい感情の渦に困惑をし始めていた。もっと粘ついた切望が彼の心を支配しつつある。純粋な憧れが変容する。彼の言葉一つ一つが、彼の所作一つ一つが艶めかしく、ベルナルドを図らずも刺激する。
「ベルナルド。私を満足させてくれ」
非情な訓練の前に、危険な任務遂行の前に、何度も耳元で囁かれた言葉。聞き飽きるほど、そしてその言葉は年月を経るにつれて本質を変化させてしまうほどに。ベルナルドは、自分の姿を鏡で見るたびにこう問うたものだった。「俺はあの人が求めている理想であり続けられるのか」その答えは、新月の夜に必ず訪れる劣情がはっきりと彼に伝えていた。
ベルナルドがついに一人前の武将として名を馳せるようになった頃、彼は皇帝サミュエルに近衛軍の設立を申請した。皇帝の間に傅くベルナルドにサミュエルが一時、書類から目を上げて彼の姿に目を留める。彼は、「何用だ?」と短く返す。
「陛下、この度は王政改革の一環として近衛軍の創設を検討していただきたく」
「今の軍制に不満でもあるのか、ベルナルドよ」
サミュエルは家臣の進言に多少の懸念を露わにする。
「はい。今の軍制は皇帝は直属軍が持てません。重鎮軍事貴族の役職として、皇帝守護の任が賄われている状態です。それでは、今後王権と貴族の対立が悪化した際に、皇帝の御身が危ぶまれ……」
「私の政が信じられぬと?」
「――いえ。万が一を想定してのことです」
ペンを置き、サミュエルは肘をつく。漆黒の瞳がベルナルドを射抜いた。
「貴様の武威では用をなさぬか?」
「私めが前に出たら、陛下の影となる意味がありますまい」
「ふっ。あのころの汚らしい餓鬼が私に提言をするようになるとはな。天晴。ならば、貴様の成長の証を私に見せろ。そして、満足させろ」
皇帝はにこやかに微笑むと、「期待している」の一言をベルナルドに投げた。
彼は、敬礼をすると、いそいそと皇帝の間から退室し、その日から軍制改革に熱心に取り組んだ。隣国への留学経験を持つサミュエルに諮問しながら、作られた騎士団を基調とした皇帝の直属軍。身分の関係上、ベルナルドが大将となることはできなかったが、それでも自分は少将として重役に就いた。後には大将へと上り詰める。愚鈍な新興貴族さえ、手玉に取ってしまえば容易い。大将ウェインは所詮、飾りでしかない。そういう野心の元、綿密に練られた軍隊であった。
「だからこそ、俺は……こんなところで死ぬわけにはいかぬ……陛下をお守りするのは、この、俺だ……大将として、名実ともに、陛下の傍で……あの方をお守りするのだ……」
左目から止めどもなく流れ続ける血液が生暖かい。朦朧とする意識。何としてでも、マクシミリアン城へとたどり着かねばならない。その生々しく湧き上がる情動だけが瀕死の一人の家臣に生を与え続けていた。サミュエルの寵愛の独占。そして、ピエタ家の餓鬼への際限ない憎悪。野心の達成は目前であった。なのに、なのに。ベルナルドは歯ぎしりをする。
「あの餓鬼め……許さぬ。この俺が、俺が必ず息の根を止めてやる……」
第二章『世迷人』
閑静で整った石畳の文化都市アインザッツ。完璧なまでに均整の取れた街の中央には、荘厳な彫刻を携えた美しい噴水が平和を告げていた。白い鳩が優雅に日向ぼっこをしている。穏やかな風がそよぐ昼下がり。花壇にはシラーの花が植えられていた。
金色の絹髪を左の襟足で束ね、黒い丈の長いコートを羽織っている青年がいた。冷たい大理石造りの分厚い壁に寄り掛かって。目深に被られたシルクハットが彼の表情を隠す。
「――下らない思い出、久しぶりに夢に見たな。それも忌々しいくらい鮮明に、さ。見たくもないものに限って何度も、何度も。どうして、忘れたいのに忘れさせてくれねえんだよ……畜生」
活気のある大通りから離れた大きな一角にでんと構えるウェルト帝立大図書館。青年は、そこの中央玄関からちょうど西に八十度ずれた場所にいた。見るからに、上流階級の貴族の出で立ちをした青年は、上着のポケットから時を止めた懐中時計を取り出して口づけを施す。まるで、それはおまじないのような儀式。
二時四十七分十三秒。彼の持つ、当時としては珍しい時計がその役目を放棄したのは、約十年前。彼はこほんと一度だけ咳払いをすると、やけに慣れた足取りでそびえ立つ図書館へと入っていった。往来は疎らで、静かに教会の鐘が鳴る。図書館の窓の内、ステンドグラス調のものには聖母が抱きかかえる清き幼子が描かれ、光を受け輝いていた。幾つかには割れた痕跡が残っている。
青年の手でぎいと引かれる大きな扉。悪鬼のような彫刻が青年を見下ろす。口元に淡い笑みを湛える青年。からんと踊る鈴の音が来訪者を告げた。俯いたまま、青年は赤絨毯の上をかつかつと歩いた。玄関口に椅子を構える図書館の主に一瞥もくれずに。明らかに外部の者ではないかと疑念を抱かせるような怪しい素振りは一切していないものの、彼はどことなく引っ掛かりを残す人物であった。とは言え、言葉や形にはできないが。
「はて、君は見慣れない顔だね。在地でも上級でもなさそうだが、君は辺境の新興貴族かね? 名を名乗りたまえ」
初老の貴族が青年を呼び止める。白髭を蓄えた顔が歪む。無理もない。
「これはこれは、ゴドフリー図書館長殿。ご挨拶もせずに通り過ぎてしまい、申し訳ありません。私は、名乗るほどの名前は持っておりませんよ。ウェルト帝国と言っても、辺鄙な場所の出ですから。ここを利用するには、名を名乗らなければならない規則でしたかな?」
青年はあくまでにこやかに返答する。ただし、その言葉は薔薇の棘のようだった。
「――いや。儂の思い過ごしだったようだ。君が少しばかりウェルトの指名手配犯に似ていると思ってしまったものでね。似ているというのは厄介ですな。これはすまないことを申した。無礼を許してくれたまえ。ゆっくりと書に興じるがよい」
「それならば、よかった。自由に使わせていただきますよ」
青年は軽くお辞儀をすると、書庫の奥へと姿を消した。
アインザッツの書庫は帝国内で一番広い。宗教・地誌・歴史・芸術・事典。色とりどりの書物が一堂に会していた。恐らくウェルトで、これ以上の本を手にすることは不可能と言っていいだろう。所狭しと並べられた書棚の中にもまた、窮屈そうに身を寄せ合う本がいた。本棚からあぶれ出た可哀そうな本は、背から繋がれた鎖によって宙ぶらりんと空を漂っていた。老いも若きも懸命に書を読んでいるのが見えた。ご苦労なこった。青年は目を流しつつ、彼らを鼻で笑っておいた。「本と顔の隙間が親指一本分って、どんだけ目が悪いんだよ」とでもいうように。
青年は、林立する書棚には目もくれずにひたすら歩き続けていた。中央の赤絨毯を突っ切ると、テンポよく右左を順々に進む。迷うことなく、疑うことなく。辿り着いた先には、小さな金属板が不自然に括り付けられた大理石の壁がある。本棚の影となり、回りの目から隔絶された一角だった。
「――俺の推理が間違ってなければ、ここなんだよな」
青年は壁に数回ノックをしながら、ぼやいた。
実を言うと、図書館長が青年の顔を見たことがあると言っていたのは、紛れもない事実であった。その顛末は今から数か月先に遡る。青年は、この大図書館に忍び込むために下見に来ていたのだ。もちろん、その時は今のような貴族の出で立ちではなく、盗賊紛いの出で立ちをして。青年は、図書館の側壁に飾られたステンドグラスを堂々と破り、数冊の本を盗んだ。指名手配犯というのも、ここに端を発する。しかし、その彼の粗雑な犯行は、あくまで今日のための布石にすぎなかった。
「汝、未熟な者が愛故に失う物とは何か。小賢しい暗号だぜ、全く」
先日の犯行は、この仕掛け扉を見つけるためであった。青年の目的は、各地の帝立図書館に眠る禁書を持ち帰ること。何か月にも渡る綿密な情報収集によって、ここアインザッツ帝立図書館の地下書庫にS級の禁書が眠っているということを掴んだ。
この大図書館の壁が煉瓦造りを模した大理石なのは、この扉の構造を隠すため。恐らく、ここに施された絡繰り扉の開錠方法は大理石ブロックを押して答えを記す類のはず。そう推察した青年は、頭を捻る素振りも見せずに暗号を解き始める。立方体に刻まれたブロックを青年が押していく。一段目は三つ。二段目と三段目は一つずつ。青年が動かした大理石がかちゃりという音と共に嵌っていく。四段目のブロックを三つ嵌めたときに、一際大きな音がして分厚い隠し扉が開いた。階段が下へと続いている。
「洒落を効かせた回答とは言え、愚問だ。愛は盲目。そして、自分か」
青年は呟くと、勢いよく地下へと導く螺旋階段を下りて行った。
何週目かわからないぐらいの円を描いて、青年は走っていく。薄暗く埃っぽい風が喉と鼻を刺激する。「飛び降りた方が早いんじゃね」とは思うものの、命が惜しくて、そんなことは青年にはできなかった。時折、前回の侵入事件よりも警備の目が薄くなっていることに一抹の不安を感じはしていたが、自分の計画の首尾の良さの感動が勝って杞憂はどこかに吹き飛んだ。
合計二十一週目の弧を描き終わると、再び先ほどの金属板と絡繰り扉が現れた。しかもその数四つ。正しい扉は一つなのか、それとも禁書のレベルによって収蔵されている部屋が違うのか。青年にはわからなかった。手当たり次第、開けていくしかないと踏んだ彼は、まず左手の扉の暗号を読み始めた。
「貴様に与えうる最高の王冠の名称を応えよ。ってこれ、戯曲の一節じゃないか。他にもそういう類の奴だろうか」
右へと一つ青年は進んだ。
「その王冠が置かれる場所は何処か」
さらに右へと青年は金属板を覗き込む。
「貴様に欠けている物は左に同じ。貴様はそれを何度も味わう」
一番右の扉にはただ一言。
「英雄が一度だけ味わうものは何か、答えは貴様の背後にある。この答えは皆同じってことかい。それで、禁書棚へ続く扉は俺の背後にあるってことだな。目の前の扉はすべてフェイク。なるほど、不変の原理を答えにしておけば、将来に渡って安泰だ。だが、俺のお気に入りの劇作家をモチーフにした時点で、その杞憂はすべてなし崩しに崩れたがな」
青年は、階段の裏にある扉を叩いてそのブロックが可動式であるのを確認すると、滑らかな手つきで答えを押し始めた。しかし、先ほどのような小気味よい開錠音はしない。
「まともに入力してもダメということは、――ふむ、この四問の答えの最大公約数を取れということか」
無表情でこちらを見つめたままの壁は、動こうとはしない。彼は答えを押そうとするが、盤面のブロック数が足りない。何か違う表現方法であることは間違いない。だが、どうやって。
「――答えそのものは合っている。大文豪ベーヴンシュペーアをモチーフにした回答なのは疑いようのない事実。さて、どんな答え方をすればいいものやら。目的地を目の前にして、めんどくせえ……」
縦六、横六の盤面で表現できる単語などたかが知れている。この既存の方法自体が間違っているのか。青年は思考を巡らす。確かに先ほどの答えは、一文字だった。そう考えると、求められているものは文字である可能性は低い。ここまで部外者を寄せ付けない絡繰りの城塞が同一の暗号解読を要求するというのは、普通ならば考えにくい。裏を掻くのが目的ならば、その可能性も考えられるが。どう見ても手間取るやり方を貫いているこの図書館にその狙いはないだろう。青年は熟考する。途端、青年の脳に電撃が走った。
「なるほど、数字か」
青年はぎりぎりと歯ぎしりをしながら、苛々と石板を押す。かちゃり。扉が開いた。
「――大仰に手間取らせやがって」
彼は、「早くしないと」と少し焦りながら奥へと靴を進める。引かれた扉の盤面には、二桁の数字が押されている。それは、皆がこぞって忌み嫌う数字であった。
「だー、もう! 何でこんなに巧妙なんだよ! 迷宮かよ……」
言葉にならない叫び声を情けなくも青年は上げた。四つの謎解きをした後は迷宮が待っていた。見渡す限り壁、壁、壁。これで迷子になって三十五回目である。よくもまあ、スタート地点に戻ってこれたな、と感心する暇もない。依然、先ほどの数字の盤面の扉から一歩も進歩がない青年の顔には幾つもの皺が増えていた。「俺は、迷路が苦手なんだよ」と言い訳がましい苦情を上げるも、誰もその声に応える者はいなかった。いたらいたで、今頃帝国兵に追われるという大変なことになっているだろうが。
「こんなのがあるって知ってたら、誰か連れてきたのにさ……」
後悔先に立たずである。
「えっと、整理すると。最初の角は右。二番目は左で、三番目はまっすぐ。四番目が左で五番目がまっすぐ……か? ここまでは正しい。三十五回も実証したんだからな。問題はこっから先だ。あと二つ分かれ道があるんだが……」
禁書の棚までの道のりは遠い。「あと何回かかるんだろう」青年は遠い空を見遣る。物理的には見えないが。地下だから当然だけれど。青年の濁った心では、雲一つない青空を拝んでいる心境なのである。
振りだしに戻ってから五十七回の試行が経過した。声にならない雄叫びが青年の口から漏れる。声が響くから大声を出してはいけないという理性との戦いであった。ちっぽけな。
青年は抑えきれない興奮をひた隠しにしながら、やっとの思いで出会えた五つ目の絡繰り扉の右脇に掲げられた金属プレートを読み上げる。
「何々……これは?」
今までとは違う長ったらしい問いに、青年は面食らってしまった。
「気づかぬうちに過ぎ去っているものとは何か」
しばしの沈黙。
懐から鉛筆と紙を取り出して、青年は答えを勘案し始めた。みみずの這ったような綴り字がびっしりとメモに蔓延る。胃がむかつき始めた。今日一日で何回苛々すれば気が済むんだろうと思いながら、青年は被っていたシルクハットを遠くへ思いっきり投げ飛ばした。瞳が怒りに燃えている。
「何で、こんなとこで躓かなきゃならないんだ! 禁書まで多分もう少しだろう! というか、何で情報が隠し扉までなんだよ、一階の! 俺たちのパトロンとかいう貴族の情報、宛にならなさすぎだろ!」
ついでに青年は、持っていた鉛筆をばりばりと折ったあと、メモ帳と共に壁に当てつけた。
「くっそ……一か八か、試してみるか」
しかも、この扉は先ほどまでの盤面押し型ではなく、二十六の文字が書かれた石板を左から順に押していく型だった。解答は合計七行。青年が考えている答えも同じく七行で回答できるものであった。まだ、希望はある。
「六、十五、十八……」
間違えないように、青年は一つずつ慎重に角砂糖のようなブロックを押していく。遠くで小さく鍵が開いたような音がした。三文字目までは合っているようだ。その調子で四文字目、五文字目、六文字目と順々に押していく。
「最後の一文字は、五番」
かちゃ。確かに聞こえた。鍵の開く心地よい音が。しかし、扉は押しても引いても何も起こらない。青年は、計画狂いの腹立たしさに任せてとりあえず、強く扉を蹴ってみた。何も起こらない。ただ、青年の爪先が痺れただけである。次に、青年は扉を殴ってみた。何も起こらない。ただ、青年の拳が腫れただけである。二つ合わせて、非常に痛い。
「――一体どうなってんだ……」
青年が疲れて、というかすべては自業自得なのだが、扉に全体重をかけて寄り掛かった時、扉がくるりと回転した。つかの間の絶叫。彼は回転扉の向こう側へと真っ逆さまに落ちて行った。
転がり続けて、転がり落ちて。急な階段が作る角度が青年の体に痣を刻む。二、三回は階段の直角が青年の鼻筋にジャストミーツしていた。痛い。
天井が、落ちてきた先が見えない。光がほとんど拒絶された空間に青年は取り残されていた。薄くぼうと揺らめく何かが見える。誰かが先にここに訪れていたのだろうか。青年は恐る恐る近づいてみた。腰に潜ませたナイフを手に。
手探りで身を隠す物の影を見つけて、――手の感触から書棚だと思われたが――青年は一歩一歩踏みしめながら寄った。誰もいない地下の部屋の壁にランプが一つかかっている。なんと不用心なことだろう。今にも消え落ちそうな火を灯したランプを彼は手に取った。左手のナイフと交代だ。
か細い光が彼の目をその場に順応させる。広いと思っていた最も深い地下の一室は、一階の大閲覧室の二十分の一という狭さ。そこにあるのは、背の高い、高い本棚が五つ。ゆったりと腰かけるように安置された本たちは、美しかった。深奥の姫といった風に不純物の混じった呼吸や汗、湿度に見舞われていないのだから。指紋とも滅多に出会わないのだろう。青年が興味本位で本棚から取り出した深海の色をした本には、金の絹糸で刺繍をされた表紙に帝国の紋章が縫われている。その隣に大きく「P」と書かれた文字。粗い色と荒い糸。明らかに検閲の証拠であった。本の中に小さな羊皮紙が差しこまれており、「出版を禁ず」という走り書きがしてある。背表紙には『百科全書』という文字列。鎖には繋がれていない。
「これ……何でも帝国王家に対する中傷で発禁扱いになったんだっけ。こんなに分厚いのに、著者は報われねぇよな。密出版されてるってのは聞いてたが、まさか初版がこんな美しいものだなんて思いもよらなかったぜ」
青年は、自分の目の色と同じ蒼玉の表紙にかけた手をふと止める。
「しかし、これは盗むには値しねぇな。密出版されてるんじゃ、価値が下がる」
重いし、もしかしたらあいつがもう地下経路で入手してるかも。彼の思考は廻った。
「――事典系よりもむしろ、国家機密級の歴史書と宗教書だな」
長い黒外套を脱ぎ、ランプのあった机の傍の椅子に適当に投げかけると、彼は意気揚々と口を動かした。さも、楽しくて堪らないといった風である。
「さて、どこにあるかな。俺とかくれんぼ、しようじゃないか」
端から一冊ずつ背表紙を確認するだけの地道な作業。お目当ての本が見つかるたびに腕に抱えていく。事典がないだけましではあるが、確実に彼の腕のキャパシティ以上の本が見つかっていた。床に積み上げられていく山のような書籍。羊皮紙で綴られている分、無駄に嵩張るし、何よりも重い。
「『ウェルト帝国実紀』、『帝国通史』に『マクシミリアン王家秘史』か。宗教系は『旧約聖典』と『新約聖典』でいいのか?」
うーむと悩む青年。
「しかし、『ウェルト帝国実紀』は帝国宮廷勤めの歴史家が記した歴史書だろ。帝国内の大学の歴史学講義も、この書物を元に行われるって聞いたっけ。中立を保ち続けてきた歴史書じゃなかったのかよ」
謎は深まるばかり。
「そして、『マクシミリアン王家秘史』。アーネスト=クラウディウスってどっかで聞いたような気がするんだが。俺の知り合いにいたのか?」
ぱらぱらと生年が本をめくると、日誌形式のような、覚書のような微妙な書式の本であった。
「ハルモニア教の『新約聖典』と『旧約聖典』は、帝国国教の根本聖典だろうに。こんなところで誇りを被ってるよりは、聖殿に飾ってやる方がよっぽど報われるだろうに」
本に積もった埃をぱんぱんと叩いて落としてやる。中身を見ると、青年は思わず苦笑した。
「――古代文字か。よほどの聖職者しか解読はできないんだろう。俺は少ししか読めないしな」
ハルモニア教の由来はなんだったか、と不信心な青年が頭を捻る。
「唯一神ディユから啓示を受けた聖女ハルモニアが、その神の御言葉を書き留めたことに端を発する。歴名にも用いられているぐらいに帝国内で、ハルモニア教は権威を持っている。教皇と枢機卿が皇帝の王政を補佐する形を取っている政体を見ても明らかだな」
現在、聖女を出した家柄として帝国内では「聖女の御子」として、王家と共に崇められているルスキニア家が代々、教皇を輩出しており、王家の分家であるブルームン家が代々、枢機卿を務めていた。どちらも厳格な世襲制である。
持ち帰るには多すぎる量の書。想像以上の収穫に当の本人が戸惑っている。欲を言えば、すべて手に入れたいのだが。そんな物を携えてここを無事に脱出できる保証は万に一つもない。そうでなくとも、可能性は限りなく薄い。
何回もの逡巡のあと、「あ」と声を漏らして青年は立ち止まる。大きな厚い表紙の本と本の間に挟まれた小さな薄い日記――あるいは手帳とも言うが――が見つかった。ぱらぱらとめくると、「羊皮紙がもったいない」と言わんばかりにびっしりと書き詰められた文字、文字、文字。題名は『教会内部改革に関する提言について』とある。
「提案書の類だろうか?」
宛先はイノセント教皇。ハルモニア教の第十一代目の教皇である。差出人は誰だと不思議に思い、彼が後付を見るとウルスラ=シルウェステルという聞き慣れない修道女の名前である。
「まあ、これも都合が悪い書類なんだろうな。持って帰るか」
背伸びをして、青年はその手帳を床に落とす。書籍の陳列が強引に抜いた反動でがしゃがしゃと崩れ落ちる懸念があったが、なんとか何事もなくクリアできた。
「あと目ぼしいものと言えば、発禁された小説とか戯曲だ。さて、ここから選別しなくちゃか……」
ぶつぶつと深刻に苦慮し始める青年は、独り言まで言いだした。普段は比較的冷静な彼が、誰に向けてと言わずに壁に向かって話すのは珍しい。相当のことのようだ。青年の葛藤は続く。
「――お、これは……」
青年は一冊の本の前で立ち止まる。彼の前にひっそりと佇む本は、『ベル・グロリア』と書かれた背表紙を青年に見せていた。
「あの、ベーヴンシュペーアの秘蔵本じゃないか!」
この青年は、超が付くほどの大文豪ベーヴンシュペーアの虜で、恋をしているといってもよいぐらいの嵌りようである。彼の目が眩むのも無理はなかった。大文豪が書いた『ベル・グロリア』は、発禁処分に留まらず戯曲等、民衆の娯楽にまで押し寄せた規制の波の犠牲だ。とは言え、文豪はその発表及び上演を禁止されてはいたものの、題名を変えて堂々とそれを演じさせてはいた。だから、最新の脚本は流通していないし、ましてや発禁処分を受けたものが見つかるのはコレクターにとっては偶然降ってきた幸運に近い。
「そうだな、聖典はいい。戯曲と歴史書を持って帰ろう」
今まで、青年は本棚しか見ていなかったため、書庫全体を初めて見渡した。部屋の隅にはごたごたと美術作品が乱雑に積まれている。好奇心を掻き立てられ、青年は喜々と近づいてみた。ランプの灯りだけを頼りに一つずつ積まれているのを解体していく。
「これって……うちのギルドにいる奴の作品じゃないか」
数枚の額縁に入れられた絵画、重たそうな彫刻が没収されていた。それぞれ裏に作品名と作者名が丁寧に刻印されていた。見える範囲の物を上げていくと、『仇花人』・『陽創人』・『世迷人』と書かれている。彫刻には『個性無き番人』と流ちょうな筆跡で彫られていた。
「――こいつ、宮廷絵師だったのか?」
この絵を制作したのは、青年のギルドに居候している芸術家だった。反乱軍のリーダーをパトロンに、潜伏制作を今でも続けているらしい。この発表を阻止された絵画を見る限り、現皇帝サミュエルとその弟ローレンス、妃のフィオナとローレンスによく似た男の肖像画である。いくら王権が憎い青年と言えど、彼らの顔を知らない訳ではなかった。しかし、なぜデーヴィッドの作品に王家の肖像画がという疑問が湧いてくる。
「小さい奴があるな。これだけ、回収しておくか。一応、俺の仲間だし、な」
青年は『憧憬』と書かれたとても小さな絵を本の隙間に差し込んだ。そこには、生まれたばかりの少女の愛らしい姿が描かれていた。習作なのだろう。色付けはなく、鉛筆で粗く下書きがされていた。
青年がギルドへ持って帰る戦利品に対してはっきりと意思を決めたところで、脳内がクリアになったのか、ある一つの疑問が浮かび上がる。
「――ちょっと待てよ。何でこんなに警備が薄いんだ?」
一瞬の空白。
「もしや……」
青年の頭の中で響き渡るどよめき。頬を伝う脂汗。
「ばれてる?」
落ち着こうと青年は、椅子に掛けた黒コートを取りに行く。
「逃げる時にいっぱい帝国兵がいるんじゃないか、このパターンは」
最悪のシナリオが手招きをして青年を誘う地獄絵図が頭の中で出来上がっている。吐き気がする。きっと、ゴドフリー図書館長が帝国兵に密告したのだろう。それはそうと、ここは地下。出口はご丁寧に一つしかない。と言っても、転がり落ちた先が見えないのでこの地下書庫に閉じ込められたも同然だった。
「地下から逃げる方法なんて、ないだろ……」
考える時間はここにいる間しかない。青年はコートを置いておいた椅子とその机に何かがあるのを発見した。誰かが以前にここを訪れたもう一つの動かぬ証拠。
「ん?」
机の上には、現皇帝の系図を記したページが露出され、椅子には閉じたままの『マクシミリアン王家系図(上)』が置かれている。中に指し示すかのように一枚のメモ書きが挟まっていた。
「これは……」
青年は脳に銃弾が貫かれたような衝撃を受け、急いで机上の本を閉じて小脇に抱えた。抱きかかえるには腕が危険水準に達していたが、それを上回るほどの収穫をした。椅子を思い切り蹴飛ばし、机の下へとしゃがんだ。そこの床を再び蹴り押すと、がらがらと音を立てて何かが動いた。二つ目の隠し扉だ。ここから上に行ける。青年は一枚のメモ書きを信じて、地上へと続くであろう階段を上った。
大きな矢印と小さな文字が記された紙切れ。普段の青年なら、誰が書いたのかもわからない紙に詰め込まれた情報など鵜呑みにしなかったろう。薄暗い密室空間で、それも外に憲兵がうじゃうじゃいる状況を想定した青年が、救いを求めて得体のしれない言葉に縋ったのも無理もない。ただし、それは五分五分の確率だった。幸いにも迷宮の出口になるのか、不幸にも拘束への招待状になるのか、どちらにせよ青年には見当はつかなかった。前者を信じたいという微かな祈りだけが青年の体を上へ上へと運んでいく。
何段上ったかわからなくなったとき、青年は壁、というか床から漏れる光に目を刺激された。可動式のブロックタイルなのだろう。青年は本を抱えていない方の手でゆっくりと動かした。
光と共に声が隙間から零れてくる。幼い少女の声。ぎこちない声の伸ばし方。まるで誰かをうかがっているようなおどおどした調子で。青年は驚かせないよう、細心の注意を払いながら地上へと体を晒した。
鈴のような心地よい音色が途切れる。
「誰かいるの?」
少女は視界には入らない誰かに向かって尋ねる。精一杯張りつめた緊張が痛々しい。
「出てきなさい」
青年はどさりと脇に抱えた大量の本を床に下ろしてから、少女に敵意がないことを体で示す。ひらひらと揺れる掌。震える声で問いただす少女。
「あなたは誰?」
「もっともな質問だ。だが、相手に名前を尋ねるときは、自分から名乗るのが筋ってもんだぜ。御嬢さん」
「――私は、マリア」
少女は躊躇いがちに青年に名を告げた。視線が地に落ちている。
「――俺の名はクライム。帝国指折りの義賊、さ」
彼女の様子をちらちら見ながら、青年はきょろきょろと辺りを見渡す。古ぼけた廃屋。にしては、調度品やら建材が良質であった。だが、貴族の屋敷にしては平坦すぎる。教会だろうか。
「マリア、お前はここで何をしてたんだ?」
「ここ、私とお母さんの思い出の場所。だから、お別れを言いに来たの。お母さんがずっと一緒に歌ってくれた歌でお別れの挨拶、してた」
壊れかけた椅子から軽やかに飛び降り、たどたどしい言葉で少女は言う。小さな彼女にはまだ酷すぎる現実だったのだろう。服が心なしか濡れている。さっきの歌は、鎮魂の祈り歌だったのか。
「小さいころ、お母さんと一緒に来たことがあるこの場所しか、私はお母さんと会えない。だから、ここまで来たの」
そんなことより、と少女は座っていた机から軽快に飛び降りると、クライムに興味津々な様子で尋ね返す。
「――クライムはこんな誰も来ないような教会で何をしてたの? 町の外、たくさんの兵隊さんいる中、どうやってここに入ったの?」
少女は訝しげに青年を見る。やっぱりな、と青年は零してから自分の置かれている状況を説明した。
「俺は、帝国の悪い奴ら専門の泥棒なんだ。今日は、その仕事でそこの図書館に忍び込んだんだが、迷っちまってな。まあ、うろうろしてたら隠し扉があってさ。辿ってきたらここに着いたってわけ」
「だから、どさどさっていう大きな音がしたんだ。クライムは泥棒なんでしょ。だから兵隊さんがいっぱい来てるんだよね?」
「正解」と青年が少女に返してあげると、ちょっとだけ少女は嬉しそうに笑った。「泥棒ってもっと怖い人かと思ってた」
「さて、マリア。そこの床の穴は俺が図書館から登ってきた道で、逃げるのには全く向いてない。正面玄関以外の出口でお前が知ってる逃げ道ってないかな? マリアもここで兵隊さんに捕まるの、いやだろ?」
もしよければ、とクライムは続ける。
「俺たちは、ここから離れた繁華街カデンツァに拠点を置いている。マリアのような孤児を引き取って暮らしているんだ。お前がよければ、一緒に逃げるか? ここにいるってのも、危ないだろ。最近は子供の人買いも増えてる。それに、俺が引き起こしたことだ。この憲兵の監視はな」
「――いいの?」
「ああ、もちろん。ただし、俺の盗んできたもの、少しは運ぶの手伝ってくれよ」
マリアは強く頷き、青年の服の袖をつかんで囁いた。
「私、兵隊さん嫌い。だから、クライムと一緒に逃げる。手伝う」
青年が登ってきた床のそばに乱雑に置いた本の山を見ると、マリアはきらきらと目を輝かせる。初めて本を見たのだろう。この国は、識字率は決して高くない。孤児の少女が字を読めることは、ほぼないに等しい。クライムは思った。「――俺も、純粋に本を愛せたことがあったかな」遠いあの惨劇よりも、前のことを思い出すことなどなかったように思う。いいことばかりでもなかったはずだが、それでも少しくらい感動を覚えていればいいものを。自分の薄っぺらい人生の軌跡に苦笑が漏れる。
「――綺麗」
うっとりと本の表紙を眺めている少女。恐る恐る中を開こうとするが、なかなか踏み出せない。隣で見ていたクライムが笑いながらマリアに教える。
「本は、こうやってめくるんだ。文字がいっぱい書いてあるだろう。俺たちの家にはいっぱい本があるぞ。マリアの好きな綺麗な本がさ。あとで好きなの、読んでやるからな」
嬉しさを体全部で表しながら、少女はクライムの盗品の中からお気に入りのものを探す。少女の体格と一致した本――『ベル・グロリア』のエメラルド色の表紙に興奮しながら、マリアはクライムを急かす。
「あのね、クライムが登ってきたところのちょうど反対側にね、スラムに通じる抜け道があるよ。スラム抜ければ、アインザッツからも出れる。でも……」
「でも?」と青年は続きを促す。
「私、ここに来てからスラムにいたんだけど、あそこの人たちはお金で動くから、今は無理かも」
少女は言う。「たぶん、兵隊さんもそのことは知ってるから、お金をあげてクライムを捕まえようと必死だと思うよ」
「こっちにも金はあるんだが、それでもだめか?」
「わかんない……」
しょんぼりして、マリアは俯く。「ごめんなさい」と小さな声が地に落ちた。
「マリアのせいじゃない。スラムと憲兵、どっちが強い?」
「たぶん兵隊さん――って、クライム。戦えるの?」
「まあ、そこそこな。じゃあ、案内してくれ。スラムへ。いざとなれば強行突破だ。アインザッツを出るぞ」
少女に手を引かれ、クライムが上がってきた床と正反対の壁を叩く。ぎぎと鈍い音がして、石壁がのろのろと動き出した。憲兵がよそ見をしている隙をついて二人は、そっと廃れた教会を後にした。
「おい、クライムとかいう奴を見つけたか?」
「――クライム? あの時の書籍泥棒のことか?」
「お前、そんな軽犯罪で俺たちが動くと思っていたのか?」
「そうじゃないのかよ」
「いやいやいや。我らが追っているそのムカつく金髪美形は、あのピエタ・ベグラーベン侵攻戦争の時の捕虜だ」
「捕虜だと? 脱走したのかって、それもう十年以上前の話だぞ」
「我も詳しくは知らないのだが、大将を瀕死に追いやった張本人だそうだ」
「俺たちのような下級兵で大丈夫なのかよ? いくら選抜された近衛兵っていってもよ」
憲兵のたちの会話が聞こえる。素性までばれていたのか。「あの図書館長め……腐った狸面しやがって」恐らく、ゴドフリー図書館長は近衛軍の諜報員だったのだろう。
「こっちだよ、クライム」
マリアが立ち止った場所は、いかにもスラムといったような廃屋の立ち並ぶ薄暗い壕だった。こんな美しい文化都市のまさに恥部といった具合の共同体がそこに存在していた。腐臭と汚臭が入り混じって、涙腺と鼻腔を絶えず刺激する。金属製の首輪を付けられた少年少女。粘ついた笑みを貼り付け、客の懐具合を換算している奴隷商人。紛い物だけを取り扱う違法商人。体力だけが取り柄でありそうな極道者。野生動物のように常に睨みを消さない子供たち、大人たち。艶めかしい姿態の娼婦。
「クライム、あの人たち。助けてくれるかはあの人たち次第だよ」
マリアが若干怯えながら青年に告げる。確かに先ほどまでの輩よりは、がたいがよく、卑しい笑いを口に乗せている。少女が「金で動く」と言っていたのは正しいようだ。
「ここ一帯を取り締まってるボスだよ。あの人たちに楯突いたらここで暮らしていけないの」
気を付けて、と彼女は続けた。スラムでの刃傷沙汰のほとんどはこいつのせいらしい。
「おい、お前がスラムの頭か?」
「――わいに何の用だ? けけけ。新入りか? 憎たらしいほど綺麗な面しやがって。男娼用の宿でも作っておけばよかったな、けけけ」
「俺は別に、スラムに住むためにお前と話してるわけじゃない」
クライムは金を懐から出す。
「ここら一帯、憲兵に囲まれちまって身動きが取れねぇんだ。金はやる。人働きしてくれねぇか?」
「けけけ。金ねぇ。あんさん、名前を名乗りな」
「――クライムだ」
スラムのボスは、汚らしい笑みを一層気色悪くして青年ににじり寄る。
「けけけ、生憎だねぇ。わいら、数刻前に帝国兵からたーんまり金、もらってるんさ。今、アインザッツ内を逃げまくってる罪人を捕獲すれば、報酬なーんと二倍。けけけ。勘の鋭いあんさんなら、わいが最後まで言わんでも、わかるじゃろ? けけけ」
ボスの周りにいた腰巾着が歓喜と言わんばかりに、クライムとマリアを取り囲む。じりじりと詰められていく間合い。ちゃきりと露わにされた錆の目立つナイフに、少女が冷や汗を額から頬へと伝わせる。
「マリア。俺の分の本を持って隠れろ。そうだな……目もつぶっていろ、俺がいいと言うまで」
クライムはコートに隠れていたレイピアの柄を握る。惨劇の日と重なる人影。狂気の花が芽を出した。
マリアが目を開けた時、足元にはごろごろと転がっている男があった。正面には、埃を被った剣を拭う青年の姿。彼は後ろを振り返って、マリアを呼ぶ。
「――クライムがやったの?」
青年は何も答えなかった。彼の頬には、泥飛沫が点々と飛んで、優しさに満ちていた瞳は凍り付いていた。
鞘に剣を納めた青年はしゃがみこみ、腹を抱えてうずくまるスラムのボスの胸倉を掴んで問い質す。クライムよりも二回りほど小さく肥え太ったボスは小物臭が酷かった。
「命を取られたくなかったら答えろ。俺とて無益な殺生はしたくはない」
「は、はいでさあ」
出会い頭の生きの良さはどこへやら、スラムのボスは情けなくも大人しくクライムに従ったかのように見えた。だが、最大の悪態をついて「嘘こけ」小さく吐いたのを青年に聞き咎められてしまった。馬鹿である。脂ぎった顔に更なる脂汗が流れていた。
「何か言ったか?」
「いいえ、なーんにも」
クライムは薄汚いボスを地面に叩き付けると、懐から一リアン銅貨を取り出して、ボスの脇に投げてやる。ボスは、「こいつ、何を考えてやがんでい」といった間抜け面をして青年をぼうっと見つめている。理解の閾値を超えていたのだろう、青年の行動が。
「お前らが帝国兵になんて従わなきゃ、十万リアンは軽く行ってたのにな、ご愁傷なことだ。まあ、いい。アインザッツから俺たちは脱出したいのだが、一番帝国兵が手薄なのはどこだ?」
「それをわいらに偵察して来いと?」
クライムは右斜め上の方向を見てから、再度ボスを見下ろして言う。
「そんなのは当たり前のことだろう? 俺としては、監視が薄いことを前提に、カデンツァに一番近い門までの最短ルートを示してほしいんだがな」
渋るスラムのボス。「傲岸な」と青年は零したが、「しょうがない、あと二リアン増やしてやる。いいな?」問答無用といった強硬姿勢をクライムは崩さない。強者に従うという理論が徹底しているスラムでボスが青年に従わざるを得ないのは、必然だった。
「旦那は全く人使いが荒い。旦那の逃亡手引きをする以上、あと十倍はないと」
「報酬は、お前らが成果を出してからだ。一刻も早い報告を待っているぞ」
ボスはいつの間にか、クライムを認めたようだ。スラムのごろつきに言葉少なに命令した後、ボス自身もアインザッツの表通りへといそいそと駆けて行った。
「――マリア。もう出てきても大丈夫だぞ」
クライムは思った。「無理もないか」いきなり出会った男の豹変ぶりに怯えてしまったのだろう。青年はただそこで彼女を待っていた。
「――クライム、もう怖くない?」
どのくらい時間が経っただろう。少女は目を真っ赤にさせて物陰から姿を現した。
「ああ、大丈夫だ」
「怖いクライムは、いや」
「――ごめんな」
少女の要求は、青年にとってもどうしようもないことだった。体と頭に染み付いてしまった死の恐怖。圧迫感。鉄臭さによって容易に思い出し得る幼少の記憶。自分に向けられる敵意さえ、クライムの呼吸を乱した。吹き出す鮮血の生温かさが、憎悪と後悔を呼び起こして今が今でなくなる感覚に襲われる。死への導きに怯える相手の顔が、憎らしいほど自分そっくりに映って見えた。それがさらにクライムの動揺と混乱に拍車を懸ける。あの惨劇の日から、単純に数えて十年は経過している。それなのに。
「俺が弱いから、だよな」
「――クライムは弱くないよ、でも、クライムの中に別の人がいるみたいで怖かったの……」
だから、そのままでいてねと微笑む少女。「あ、そうだ」と彼女は物陰に置いた本を青年に渡す。
「あのね、あのね。この本、あたしでもわかったんだよ!」
そう言ってはしゃぐマリアがクライムに渡した本は『マクシミリアン王家系図(下)』だ。「ん?」と青年の頭には三連続の疑問符が浮かぶ。
「マリア、字が読めるのか?」
「うん。少しだけだけど読めるよ」
系図を開いて、「これがサミュエル皇帝でしょ、その横にローレンス皇子って書いてあるの」と喜んでいる。その一方で、クライムはマリアの出自に疑問を持ち始めていた。字が読める庶民がいないことはない。商人とかは商売上必要だからという理由で、読み書きと計算を教えられる。もちろん、貴族は読めるのだが。商人社会での子捨ては聞いたことがない。労働力として子供は大切だと聞いた。早くから丁稚奉公に出して、店を継いでもらうためだ。それならば、マリアは最近の貴族社会の子捨てと離婚の犠牲者なのか。クライムの頭はすっきりしない。
教会が免罪符の販売と積極的な寄進の奨励を始めたためか、現世での苦しみは金によって救われるという風潮がウェルト帝国にはできつつあった。特に貴族社会には、その考えが蔓延しているといっても過言ではない。金を教会に払えば何をしてもよい。堕落した価値観が帝国を支配していた。一方では、高額な税金徴収や寄進によって肥え太っていく貴族がいる。他方では、徴税によって金を失い、没落していく庶民たち。貴族の傲慢さは留まることを知らずに、金を手に入れれば土地を求めていく。そのせいで多くの孤児や家無しが生まれ、スラム街が国のあちこちにできるようになった。ピエタ・ベグラーベン侵攻戦争を発端とした多くの対内・対外戦争も帝国内の民衆を大きく蝕んでいた。
クライムが思いを巡らせている中、マリアは頓狂な声をあげる。
「ねぇねぇ、なんでローレンス皇子の横に書いてある名前はぼやけてるのかな。なんか、わざと消した跡みたいだけど」
「生まれてすぐ死んだとか、そういうのじゃないか?」
「でも、そういう人って前の方見ると、みんな書いてあるよ? あと、お城を出て違うところに行っちゃった人だって、みんな」
マリアが開いたページに書いてある人名と生年や在位期間、没年までクライムがしっかりと目を通してみると、なるほど彼女の言うとおりだ。王家を出て臣下としての道を歩んだ者までも、どの家に養子として迎えられたのかまで詳細に書かれている。ぱらぱらとほかのページを繰ってみても、故意に消された名前はローレンス皇子の隣の名前だけ。黒のインクで塗りつぶしたりなかったのだろう。彼の生年だけが紙の上にいた。皇子と同じ生年である。彼はローレンス皇子と共に双子として、この世に生を受けたらしかった。
「あとね、このお妃様。あたしのママと同じ名前!」
「――フィオナ様か?」
そういえば、八年前ぐらいに首都アリアで結婚パレードをしたとかいう話を聞いた覚えがある、と青年は言った。ここでクライムの頭に古風にも電球がつく。彼は心の中で「まさかな」とだけ呟いておいた。
しばらくマリアとクライムが本を読みながら談笑していると、小物臭いスラムのボスたちが汗だくになりながら戻ってきた。数人は腕や脚に傷を負っている。
「だ、旦那ァ。大変でさァ」
「なんだ、ボス? どうかしたのか」
はあはあと絶え絶えになった呼吸をクライムは整えさせてやると、ボスは弾丸のように話し始めた。
「最初は帝国兵だけの囲いかと思って鼻歌でも歌いながら偵察してたんでさ。ですがね、旦那。教会の僧兵がこぞってアインザッツを取り囲んでやがんでぃ」
「僧兵が……?」
「これはいやーな感じがしますぜ、旦那。中の悪い帝国兵と僧兵が一緒になってアインザッツの守りを固めてんのかは知りやせんが、旦那を躍起になって探してますぜ? いったい何をやらかしたんでさぁ」
「――何でもない。俺は一介の盗賊さ」
クライムは声を落として言う。あの事件の関係者として探されているのは、青年にもわかっていた。王族関係者に名を問われたら、彼は逃げ場がないことを知っていた。
名縛りの呪い。王族だけが行使できる拘束と従属の呪いである。反逆罪や不敬罪など、王家に対する不義のためにその呪いは使われるというが、真相は闇の中だ。重罪犯罪者を牢に捕える代わりに、彼そのものの精神を崩壊に追い込む。名を体から遊離させることで、新たな人格を洗脳する仕組み。元の名を記憶する者がいなくなったときに、その者の死を意味する。クライムはまだ、自分の過去の名前があったことぐらいは覚えている。ただ、それがどんなものだったのか、そこからはもうわからない。だから、まだあの日の前の自分のことを知っている人間がいるのだ。
そんな彼の考えに気に留めるわけでもなく、ボスは思い出したように話し出す。口が達者な男だ。
「盗賊といやァ、カデンツァに一流の義賊ギルドがあると聞きやしたが。旦那はそこの若頭と馴染みがあるんで? そこの頭と仲が宜しくねぇと、盗賊と名乗れないと風の噂で聞いたような、ないような」
「ああ、カイルのことか? お前みたいな三流……いや四流五流のチンピラでも知ってんだな」
ここで、今まで黙って利口に話を聞いていたマリアが口を挟む。
「カイルってだーれ?」
「自称カデンツァ一の色男さ」
「色男?」
「かっこいいってこと」
「クライムよりも!?」
きゃっきゃと嬉しそうに顔を輝かせるマリアは、さすが年頃の女の子といった風であろうか。
「なんでぃ、旦那はカイルの若頭のとこのお方でしたかぃ。そんなら、さっさと言ってくだせぇよ。カイルの旦那からアインザッツ一帯を任されてるんですよ、わいらは」
思わず二度ボスを見るクライム。「まじかよ」隠せない驚きが顔に表れていた。
「そんなことはともかくとして、旦那はこれからどうすんでぃ? とりあえず言われてきたことは調べましたけどさァ」
そこらへんに落ちている小枝を拾うと、ボスは地面にアインザッツ全体の見取り図を描く。最下層で暮らすということは、上層とはまた違った感覚で生きているものだ。目の付け所が違う、と青年は思った。常に視線にさらされている彼らが逃げ隠れて生きるために編み出した術なのだろう。その図面には事細かく裏道や廃屋が記されていた。そのほとんどが、クライムの知らないものばかり。伊達にアインザッツスラムのボスを名乗っているわけでもなさそうだ。とりあえず三流にまで格上げしておこう、とクライムは思った。顔には決して出しはしなかったが。
「わいらが知ってるアインザッツから抜け出す方法は三通りあるんだな。まず、オーソドックスな正面突破法だが……正門は、帝国兵ががっちり固めてるんで旦那たちが通るのは無理でさ」
「一応、エレミア砂漠を抜ける方法を考えてるんだがな……それはどうだ?」
「一番の迂回路ですねぇ、まあわいらのスラムを通って裏門を抜けるのが正攻法ですが、わいらの秘密の抜け道を教えて進ぜやすぜ。そっちの方が足がつかんでしょう。裏門にも、多少とはいえ帝国兵がおりやした。旦那の腕なら、その嬢ちゃんを庇いながらでも突破はできるでしょうがねぇ……」
眉を顰めるボス。その顔は、似合わないぐらい険しい。
「その喧噪で大ごとになるのは間違いないんでね。あとは、アインザッツ大聖堂の地下通路っていう手がありやすが、今日は妙に僧兵が多い。アインザッツ大聖堂管轄のウルスラ様は、僧兵導入に反対だったような気がするんだがなぁ」
「やけに教会の肩を持つじゃないか、ボス」
わざとクライムはボスに話を振ってみる。
「いやあね、ウルスラ様はわいら下層民にも優しく接してくれるんでさ。大聖堂の抜け道もスラムの教区民には教えてるんだ。いざという時の避難のために使いなさいと。最近はスラム狩りみたいな物騒な事件も多いからねぇ」
ボスの配下が「旦那よりひでぇやつがちらほらいるんですよ、奴隷商人とか人斬りとかねぇ」と話を継いだ。「ウルスラ様は、わいらの数少ない味方でさ」ぼそっと呟くスラムのチンピラたち。
「で、どうすんでぃ? 腹はくくれましたか、旦那に嬢ちゃんや」
「エレミア砂漠の移動手段はどうしてる?」
クライム一人なら、砂漠の移動など徒歩でもなんとかなるが、マリアがいるとなるとちいとばかり厄介だ。か弱い女の子を燦々と照りつける炎天下の下、昼夜通して歩かせるわけにもいかない。
「――あんまりエレミア砂漠を渡ることがないんで、何とも言えやせんがねぇ……そういや、キャラバン隊の世話になる者がいたような気も。そのキャラバンもカイルの旦那の支部ですからねぇ、旦那ならきっと何とかなるとは思うんですが、一つ問題があるんでさぁ」
問題ってなんだ、と青年が尋ねると、ボスは神妙な面持ちで答える。
「なんせ、そのキャラバン隊がいつ来るかがわからないんでさァ。決まった日にちや時間があるわけでもなし。砂嵐のように気まぐれなんですぜ、あのキャラバン隊は」
わいらの持ってる知識はこれくらいでさァ、とボスが申し訳なさそうに言う。クライムにとってみれば、これ以上有益な知らせはなかった。彼は懐から金袋を取り出して、報酬を弾んでやる。当初示した額の十倍だ。その額を人数分、クライムはボスに渡した。
「ほら、感謝の印として受け取っておけ。ボスよ」
「――旦那、こんなに受け取れやせんて。畏れ多すぎて」
「何、弾んだ分もう一つ働いてもらうさ」
マリアは、話をしっかりと聞いていたようで身支度をしている。
「何なりと仰せくだせぇ、旦那。わいら、旦那の手足になって働きますぜ」
びしっと敬礼をするボスたち以下スラムの住人。喧嘩を吹っかけてきた奴らと同一人物かと疑うくらい従順になったのをクライムは苦笑しながら、彼らに任務を命じる。それは、ボスらスラムの住民にとって偵察よりも簡単なことだった。
「そうだな、一発派手に暴れて来い。でかい教会に金髪の男が逃げたって言っておけば問題ないだろう」
「旦那、そんなもんで大丈夫なのかぃ?」
「――大丈夫だ、問題ない。頼んだぞ」
クライムはマリアを呼ぶと手を引いてスラムの奥へと進む。先導するのは、ボスの腹心の部下たちだ。ボスは「野郎ども! 旦那の頼みとありゃぁ、派手にやらかすぜぇ」と大声を挙げてスラムの住民をかき集めた。ぞろぞろとした集団がアインザッツの中心へと消えたのを見届けると、クライムたちは部下の案内の後について行った。
ボスの部下に連れられ、スラムの民が掘った抜け道からクライムとマリアは無事アインザッツから脱出することができた。ちょうどアインザッツの西にあたる広大なエレミア砂漠が二人の眼前に広がっている。エレミア砂漠とは名ばかりで、砂地の多いステップ地帯だ。もちろん、乾季と雨季が交互に来る。ちょうどアインザッツ周辺は、乾季の真っただ中だった。日差しの強さだけは砂漠の名を冠するにふさわしい。
「砂嵐が酷いな。吹き飛ばされるなよ、マリア」
「大丈夫」と言って彼女は青年の服の裾を掴む。クライムはふと心細さを覚えたのか、手を少女に伸ばした。少女は嬉しそうに一回り以上大きい彼の手を握る。
「危ないから、離すな」
青年は少女の手を取り、もう片方の腕で本を抱えながら一歩一歩踏みしめるように砂地を歩いた。縺れそうになる足を何とか動かして、マリアもクライムにくっついて歩く。日差しが強い。早くどこか休める場所を見つけなければ、という焦りが彼を襲う。
「これから、どうするの?」
目を細めながら、マリアがクライムに問う。
「――いったんカデンツァに出る前に、フォンセに寄る」
「フォンセってどこ?」
「このエレミア砂漠内にあるオアシス都市だ。そこに行けば、水も食べ物もしっかりしたものがある。もちろん、この暑さからも逃げれるさ」
「――頑張る」
そう言った少女の顔からは、汗が伝っている。長らくアインザッツに暮らしていたせいか、彼女はそんなにつらくはなさそうだ。むしろ、寒冷な土地で育ってきたクライムの方がすでに限界に達しつつあった。途中、砂漠で元気よく旅人の前に現れるサボテンを青年は少しだけ刈り取って、「水分だ」と言って少女に渡す。サボテンの道管を流れる微々たる水でも、彼らにとっては至極おいしいものだった。マリアが興味本位で、水を吸ったサボテンの破片にかじり付く。思ったより不味かったようで、顔を盛大にしかめていた。青年は少女がいじらしく思え、新たにみずみずしいサボテンを渡してやる。
「クライムもかじってみなよ」
「まずかったんだろ?」
「いいからいいから」
そう言ってマリアはクライムからナイフを奪い取ると、適当にサボテンの腕を切り取り、クライムに押し付ける。彼が水を啜ったのを見届けると、マリアはクライムに飛びついて強引にその欠片を口の中へと押しやった。「苦っ」という青年の咳き込み。少女は彼の反応が面白かったらしく、腹を抱えて笑っている。「元気だな」と呟きながら、クライムはマリアにつられて久しぶりに笑顔を見せた。そうしているうちに、五本ぐらいのサボテンの腕が人間のナイフの犠牲になった。
サボテン狩りをしつつ、水分を補給する二人ではあったが、限度を知らずに彼らを照りつける日光が彼らの体力を奪い続けていることには変わりはない。ひりひりと痛み始める腕と顔。
「アインザッツってなんで砂漠の近くにあるのに、そんなに暑くないんだろうね……」
思わず零れるマリアの愚痴。腕を露出している分、日焼けは酷いが帽子が日差しを遮ってくれている分、まだよかった。「いつまで歩いてなきゃいけないのかな」
少女が手を繋ぐ先を見上げると、彼女以上に疲労の激しい男の姿があった。
「大丈夫なの、クライム」
もはや、にこりと微笑むことしかできない青年。無理もない。身元が発覚することを恐れて相当着込んでアインザッツにやってきているのだ。黒外套は脱いで、本と共に抱えてはいるものの、長袖の服は捲ることしかできない。汗でぴっちりと纏わりついて、不快感をさらに高めた。
歩幅が小さくなり、二人は無言で歩き続ける。周囲に距離を視認できるものがないため、同じ場所に取り残されているのではないかという不安が徐々に二人を襲う。マリアが時々クライムの様子を伺うと、彼は気力で無理やり体を酷使させているように見えた。「早く、誰か見つけなきゃ」少女は焦りを隠せない。
「クライム、いったん休もう。歩いてた方が楽もかもしれないけど、お水、取らなきゃ」
マリアはクライムを座らせてじっとしているように告げる。荷物を彼の傍にいったん置くと、彼女は彼の腰からナイフを抜き取った。そして、近くのサボテンまで走っていくと、その幹を力いっぱい削り取った。二、三回もやると、彼女は慣れた手つきで輪切りにしていく。
「クライム! ほら、これ口に含んで」
少女が青年のもとへ駆け寄るも、青年はぐったりとこめかみを押えて倒れ込んでいた。慌てるマリア。腕に抱えていたサボテンが零れ落ちる。
「クライム、クライムってば。起きて、こんなところで倒れたら死んじゃうよ」
ぱちぱちと青年の頬を叩いたり、肩をゆすったりして懸命に彼を起こそうとするが、彼は呻き声をあげただけで起きることはない。歯を食いしばり、痛みを堪えるので手一杯のようだ。
「どうしよう……」
肩をゆすり続けるマリア。クライムは何度も咳き込んだ。細かい流砂がさらに彼の気管を圧迫する。
「これ、もうしちゃダメだ。クライムの咳が酷くなる」
青年の名を何度も呼びながら、彼女は彼の姿勢を上の方に向けてやる。目をうっすらと開けて、青年は首を横に振った。
「クライム……」
泣きたくなるのを我慢しながら、マリアがもう一度クライムのための水を取りに行こうとしたとき、彼女の背後から声がした。
「こんなところで、人に会うたあ、奇遇だねぇ。どうしたい、御嬢ちゃん。こんなとこにいたら、その綺麗な肌が焼けちまうよ」
少女が振り向くと、そこには白い異国情緒溢れる衣服に身を包んだ人が荷車から顔を出していた。顔下半分を隠し、男女曖昧な印象をさらに強めている。「――お姉さん?」
「一発であたしを見抜くたあ、御嬢ちゃん、見る目があるねぇ。ところで、あんたの後ろに倒れてる男は、連れかい?」
「うん。私、クライムとアインザッツからここまで歩いて来たんだけど、いきなり頭抱えて倒れ込んじゃって……ねぇ、助けて」
少女はか細い声で男女不明瞭な人に頼み込む。便宜上、彼女ということで統一しよう。
「――可愛い御嬢ちゃんの頼みとありゃ、断るわけにはいかないねぇ。その男、金は持っているようだしさ。あたしのことは、ロビンと呼んでおくれ」
ロビンは名乗ると、荷車の中に消えた。怒鳴り声が車内に漏れだす。「子分ども! 一仕事しておくれ、すぐ外にいっぱしの男が熱病にやられてる。運んでやりな!」女というには、少し低い声に尻を叩かれて、屈強な男が数人中から出てきた。「お嬢! この金髪の男ですかい?」
「そうだよ、その嬢ちゃんも、そこに置かれてる荷物も中に入れておくれ。頼んだよ」
ロビンの言葉に、「承知しやした、お嬢!」との返事が飛ぶ。マリアもクライムと共に担がれて荷車の中に運ばれた。目まぐるしい事態の展開の速さに、少女は理解が追い付かない。そのまま、ロビンの部屋に彼女は通された。
「ロビンお姉ちゃん、ありがとう。助けてくれて」
「――いいんだよ。ここはあたしたちの島だ。ここで死人が出る方がよっぽど悪いさ」
「ねぇ、クライムは大丈夫なの?」
不安そうな少女の瞳。ロビンは、マリアの一途さが胸に痛かった。彼女は自分の痛みを億尾にも出さずに、丁寧に答える。
「あの男、クライムというんだね。大丈夫、エレミアの熱にやられただけさ。ここでは、元気になるまで回付させることは難しいけれど、意識を取り戻すくらいはどうってことない」
「――よかった」
少女はほっとしたように、へたへたと床にしゃがみこんでしまう。よほど大事な男なのだろう、ロビンは思った。自分には叶わない思い。一度捨てた思いが彼女を締め付ける。
「あたしたちは、ソルフェージュに向かう。運よく今、途中で立ち寄る場所に腕のいい医者が滞在しているようだから、そいつに診てもらおう」
ロビンは、懐から軟膏を取り出すと蓋を開けて少女を呼ぶ。
「おいで」
マリアは、言われたとおりにロビンに近寄った。
「お嬢ちゃん、名前は?」ロビンは少女に尋ねる。「私は、マリア」少女は答えた。
「腕を出して。日焼けに効く渡来の薬だ」
白いクリーム状の薬を指いっぱいに取ると、ロビンはマリアの腕に刷り込んでいく。
「ロビンお姉ちゃんは砂漠で何をやってるの?」
「あたしかい? あたしたちは、ウェルトのずっと向こうにある国を渡って、珍しい品物を持って帰ってきてんだ。それをウェルトで売るのさ、高い値段でね。砂漠の向こうにある国と交換してるから、ここは通り道ってわけ」
「そうなんだ。あのね、ロビンお姉ちゃん。アインザッツにいるボスに、ロビンお姉ちゃんのこと聞いたんだけど、同じ人?」
「あら、ボスを知ってるのかい?」
ロビンが「目を瞑っておくれな」と少女に伝える。薄く掌に薬を伸ばすと、優しくマリアの焼けた顔に塗り込んでいく。「こんな柔らかい肌の子を砂漠の炎天下に連れ出すとか、あの男は何をやっているんだか」ロビンは冷たい視線を、壁を隔てた先で眠る男に送った。
二人が談笑している最中、先ほどクライムを抱えて荷車に乗り込んだ男がどたどたと大げさな音を立ててやってきた。「どうしたんだい? 客人がいるだろう」ロビンは眉をひそめる。
「お嬢、それどころじゃないんでさ!」
「何があったんだい、話してごらんよ」
「それが大変なんでさ。あの男、蠍の刺し傷が複数見つかったんで」
ロビンは立ち上がり、血相を変えて部屋を飛び出す。帳一枚でできた帳を抜け、青年の元へと急いだ。ロビンはマリアに言う。「お嬢ちゃん、あんたはそこで待ってな。あたしが戻ってくるまでそこにいるんだよ」少女は強く頷いた。
急ぎ足でクライムが横たわる部屋へ向かう彼女の後を追う男が今の状況を説明する。
「塩水を薄めたのを飲ませてたんですが、一向に良くなりませんで。汗の吹き出しも異常だったもんで、服を脱がせて熱を取ろうとしたら」
「――見つかったんだね、刺し傷が。よくやったよ、遅けりゃ、お陀仏だ」
あの少女の泣き顔を拝むのは御免こうむるよ、とロビンは呟いた。彼女はクライムに近づいて、脈を取る。思っていたよりも弱い。彼女は青年の足首に刺された三箇所の傷跡を忌々しく見つめる。
「蛇蝎症だね……あんたら、毒は吸い出したのかい?」
「当たり前でさ。だけど、けっこう回っちまってやすぜ。こいつの様子からだと」
「――ねぇ、あんた。今までの経験から、持ってどのくらいだい?」
青年の病状を告げに来た男は、俯いて一度考えた後、じっと彼を見つめてから答えた。
「――日が明けるまで、といった頃合いでしょうか、お嬢」
クライムは苦しそうに胸を押えたり、頭を抱えたりしながら横になっていた。呻き声が漏れ、汗が額から止めどもなく流れ出している。手下の男がクライムの口に水を注ごうとするが、咳き込まれ思うように受け付けてくれない。
「複数刺されたのは、熱病のせいだろう。ちっ、性質が悪いね。御者係に伝えておくれ、フォンセまで夜通しで駆けるよ!」
熱病で意識が朦朧としていなければ、ロビンたち砂漠の流浪の民の経験から得た知恵でも、対処はまだ足りた。だが、水もろくに受け付けないクライムの体に鞭を打てば、どのような形であれ、芳しくない結果は目に見えていた。
「あんた、アーネストが今どこにいるか噂は聞いているかい?」
ロビンの切羽詰まった問いに名乗りを上げる男。「アーネストの旦那は、今フォンセにいるらしいですぜ。長い滞在になるとかで」
ロビンは「そうかい」と言ったきり黙り込む。訪れる静謐にしびれを切らした手下の一人が苦々しく口を割る。
「しかしお嬢、今の時期フォンセは雨季に入って……」
「――今の状態じゃ、あいつに頼るしか手立てはないよ。分かってるさ、蛇蝎症の男だけじゃなくて、あの子も危ないことくらい」
ロビンは、部下がフォンセに行くのを渋りたい気持ちは十分理解していた。雨季には、乾季とは比べ物にならないほど病が流行る。こんなことがなければ、フォンセに寄らずに、プリローダ平原に舵を切ることもできた。だが、少女にかつての思い出を重ねた自分に、彼女の小さな願いを捻り潰すことは、到底ロビンにはできなかった。
「――わかっている。あんたたちの言いたいことも。だけど、あんな小さな女の子の笑顔も守れないようじゃ、あんたたち男が廃ると思わないのかい?」
うっと黙り込むロビンの手下たち。
「こうしよう、フォンセにはあたしが乗り込む。あんたたちは、そこまで連れて行ってくれさえすればいいさ。あの子を、見てておくれな」
「そんなことすりゃ、お嬢が……」
「大丈夫、フォンセにはあたしの昔馴染みもいるんだからさ」
ロビンは、白い外套を翻して手下の静止を振り払った。顔を覆っていた口布を取り、エレミアの外気を吸いに荷車から出た。
日が落ち、涼やかな風がラニの頬を撫でる。まだ、馬車が走る道は砂が多く、雨の気配は感じられなかった。「――あたしったら、馬鹿だね」一人の少女に自分の、いや、愛する人の面影を重ねてしまうとは。ロビンは、溜息をついた。「どんなに遠くへ離れても、結局は忘れられないんだね。東方の商人が忘れ薬でも持っていたら、ばか高い値段でもあたしは買うだろうよ」一人の自嘲が風に乗ってどこかへ落ちた。
こつこつと荷車を渡る音がする。部下には来るなと言ったはずだが、とロビンが後ろを振り返ると小さな少女の姿があった。顔には影が落ちている。
「ねえ、クライムの体、思ったより悪いんでしょ?」
あれだけ取り乱していれば、事態が呑み込めていなくともわかるか。ロビンは思った。
「――熱にやられているだけなら、なんとかなったんだけどね。蠍に刺されているんだよ、あいつ」
「蠍に刺されると、どうなるの?」
まっすぐな目。怖くなるほどに。
「毒が回って死んじまう……手遅れなら」
ロビンはいったん言葉を切った。マリアの肩が震えている。
「私が目、離さなきゃこんなことにならなかったのに……私のせい、私の」
「――あいつをフォンセに連れて行く。そこにあたしの知り合いがいる。腕のいい医者がね」
「いいの?」
少女の目に浮かぶ真珠の欠片。「――助けてくれるの?」
「御代は、大人になったら払っておくれ。それまで気長に待ってるよ」
ロビンは、微笑んだ。少女の目尻から一粒の真珠が零れる。
「ありがとう」
夜風に乗って言葉は空に輝いた。
しばらくすると、夜風が冷たさと湿り気を運んできた。ロビンは指を擦って、雨の訪れを直感的に悟る。マリアが佇んで彼女を見つめる中、ロビンは、空を見やりながら少女に問うた。
「――マリア。雨の時期、ここが危ないのは知ってる?」
「そうなの? どうして?」
ロビンは手招きをしてマリアを傍に呼ぶ。
「雨の時期は、病気が流行りやすい。特に危ないのがね。クライムをフォンセに連れて行くけれど、あいつがちゃんと元気に戻って来れるかわからない。ほんとは、あんたに内緒にしてフォンセに行くつもりだったんだけど、マリア、じっとしてる性質じゃないでしょ?」
あたしが呼ぶまで、部屋から出ないでって言うのも守れなかったわけだし、とロビンは続けた。舌を出して目を泳がせる少女。「忘れてた」と漏らす。
「どうする? 死んでしまうかもしれない危険があるの、わかってる?」
「――クライムが苦しんでるのに、ここで座ってるのなんてできないよ」
「そう、あんたに何言っても引き留めるのは無理そうね。それじゃ、一つ聞いていいかしら」
ロビンは膝を折り、マリアの目をじっと見つめた。「あの男にどうして、あんたはついていくの?」
少女は、一拍の間をおいて噛みしめるように言葉を選びながら思いの丈を吐き出した。
「――助けてくれたから。私の場所をくれたから」
だから、クライムがいなくなるのは嫌なの。彼女は告げた。
「――いなくなるんだったら、私もいっしょ」
さも当然というように。少女は言い放った。一点の曇りもない心からの言葉。女は背筋に寒気を感じた。彼女は自分の動揺を隠すために、少女に話を振った。
「マリア、あんたの気持ちはよくわかったわ。それなら、フォンセに行く準備をしないとね。服を着替えてもらうわ」
ついてらっしゃい、とロビンは言う。二人が向かった先は、先ほどのロビンの部屋だった。彼女は大きな箱を開けて手探りで何かを探し出す。
「あんたの背丈に合った布、あったかしらねぇ……」
箱の中から次々と出てくる煌びやかな布や手触りの良い布に驚きを隠せないマリアを余所に、ロビンはああでもない、こうでもないとぶつくさ言いながら発掘作業を続行する。「これね」と大分経ってからロビンがマリアに纏わせたのは、彼女と同じ真珠色をした絹の布だった。
「じっとしてなさい」
ロビンに言われたマリアは、直立不動の姿勢を取った。その彼女の服に器用に布を取り付けて肌が見えている箇所を覆っていく。外套のように。口も隠せるように。
「肌が見えていると、無意識に作った傷口からかかっちゃうことがあるから注意するのよ」
少女は、ロビンが触れる温かさに懐かしさを感じていた。
何かが落ちる音と共に、馬車が揺れる。絶え間ない轟音が襲い、会話を途切れさせた。束の間の温かい安らぎを壊すように、大きな叫びがロビンの名を呼ぶ。「お嬢、雨季に入りやした! 注意して下せえ! もうすぐフォンセですぜ!」途切れ途切れでしか聞こえない声に、ロビンが近づく。
「クライムの容体はどうだい? あたしが頼んでおいた治療は済ましたんだろうね!」
「もちろんでさあ!」
声を返す巨体。「毒抜きと冷却、水分だろう、お嬢」筋肉の塊は自信ありげに答えた。
「安心するんじゃないよ、フォンセまでのあいつの命はあんたに預けてるんだからね」
声の鞭が部下を厳しく叩く。敬礼しながらそそくさと持ち場に戻る巨漢。
「それより、あとどのくらいでフォンセに着くんだい? マリアが待ちくたびれちまうよ」
えっという言葉の後に、一瞬の沈黙が訪れる。
「な、なあお嬢。フォンセにこの子を連れて行くんで……?」
恐る恐る首領に尋ねる一人の部下。そんな馬鹿な、と彼らの顔には書かれている。
「――しょうがないだろ、マリアが決めたんだ。あたしがちゃんと連れ帰る。心配するんじゃないよ」
でも、と言いかけた口を男たちは閉じた。首領が決めたことに従うのが自分たちの役目。彼女が死地に身を投じるなら、自分たちも身を捨てる覚悟だった。しかし、ロビンはそれを許さない。ならば、自分たちに残された道は、彼女が帰ってくるのを祈り待つことだった。
「――私は大丈夫。ちゃんとクライムとラニお姉ちゃんと戻ってくるから」
笑顔の少女に男たちは何も言えなかった。少女は何も知らないのだ。これから向かうフォンセが地獄絵図と化していることに。そして、男たちはロビンの思惑を知らなかった。彼女は、彼らの知らないところで別の依頼を受けていた。
年長の部下がロビンの横に進み出て、そっと耳打ちをする。
「たった今、フォンセの野郎から文が届きやしたんで。フォンセ近隣の町や村は壊滅したそうで」
「――なんだって?」
「野郎のお師匠さんが先に向かったそうなんですが、着いたころには手遅れだったようで。エレミアの南は死の街と化してるらしい」
「あいつからの伝言かい……奴は嘘をつくような男じゃないしね。信用できるだろう。伝書鳩が持ってきたのかい?」
「そうでさ……俺以外は文字が読めないから、こう平静ですけど。知ってでも、お嬢は行くというんですかい?」
沈痛な響きがラニの鼓膜を震わせた。
「アーネストに頼むしかないんだ。わかっておくれな」
あの子を連れて行くのは気が引けるけど、それでもあんたたちが目を離した隙にいなくなっていたというよりはいいだろう、とロビンは言い訳をする。男はただただ黙って首を横に振った。
「――俺には何がいいのか、わかりやせんよ……俺は、俺たちはお嬢の信じた道についていくことだけでさ」
雨の音が首領と部下の心に重い石を乗せるように、断続的に鳴り響く。悲しげな音色を意に介さないのは、無知な少女だけ。憂鬱な男の呟きに重なるように、馬を御す手下が雨音に負けじと怒鳴る。
「お嬢! フォンセに着きやした!」
ロビンはマリアについてくるよう促し、すれ違いざまに部下の男に言う。
「――頼んだよ」
青年はまだ、目を覚まさない。顔色は悪化し、ぽつぽつと発疹が足の辺りを中心に浮き出ていた。ロビンは、弱った青年を抱きかかえながら、少女と共に轟々と流れ続ける空の涙の中に姿を消した。取り残された馬車に滝の音だけが木霊した。
泥が行く手を阻む中、マリアとロビンはフォンセの街にやって来た。豪雨に喧噪がかき消されているだけなのか、それともアーネストの言う通り流行病の猛威になす術もなかったのか。街には人の気配がほとんどなかった。鼻を突く異臭。大通りには、水溜りの中に人が横になって積み上げられていた。明りのない街。幽霊に支配されている感を匂わせる。道行く二人を邪魔するように転がる死人。彼らの腐ってどろどろとしている皮膚は、ロビンが見る限り黒く爛れていた。
雨を遮るものもなく、二人はクライムを抱えながら一軒の家に辿り着いた。ぼうと蝋燭が揺らめいているのが窓から見える。
「すまないね、あたしたちは旅の者だよ。この街に腕のいい医者がいると聞いてやって来たんだ。どこにいるか、教えてくれないか?」
ロビンは扉の先で数回ノックしながら、アーネストの滞在先を尋ねる。彼女の声を聞いて、ドアがぎいと開き、その家の主人は手招きをしてロビンとマリアを家の中に入れた。少女が青ざめていることに、ラニは幾許かの後ろめたさを隠しきれなかった。その二人の様子を見て、家の主が口を開く。
「――この僕のことか? 旅の者。久しぶりだな、ロビン。その抱えている男は、患者だろう? 詳しいことは聞いている。見せてくれ、治療をする」
品のいい青年がロビンからクライムを受け取り、粗末な寝台へ運ぶ。
「君たちは適当に座ってくれ。生憎、菓子や茶を出している余裕がない。ロビン、勝手がわかるだろう。君は」
「まあね、あんたがいいならあたしが出すわ。変なところに気を回させちゃって悪いわね、アーネスト」
ロビンは立って台所へ向かおうとする。
「――ポットに煮沸したぬるま湯がある。それをもう一度沸騰させて使ってくれ。くれぐれも蛇口は捻るなよ」
「わかったわ」
女が消え、マリアは居間に取り残された。ぽつんとわけのわからない場所で、手持無沙汰なのか部屋の中をきょろきょろと見渡し始める見たことのないものが棚に窮屈そうに収まっており、まさに「取ってください」と言わんばかりだ。少女に寝台近くの棚と引き出しを指差しながら「そこだけはいじらないでくれ」とアーネストは言う。
彼は、小さな背の低い机の上に燭台を運び、腰から三本の年季の入ったナイフを取り出した。マリアはちょこんと椅子に腰かけながら、興味津々といったように見ている。アーネストは、片方の腕でナイフの刃を火に当て熱していく。もう片方の腕は、「門外不出」の紙が貼られた棚を漁って一本の瓶を取り出した。ラベルには「消毒用酒」と書かれている。その瓶の蓋を開け、豪快に熱したナイフにかけていく。しゅうと小気味よい音を立てながら、酒は蒸発した。鼻につんとくる匂いが漂う。
「――すごい、ね」
「見るのは初めてだろうね、御嬢さん。これから僕はこの男の治療に取り掛かる。そこから動かないでじっとしていてくれないかな。おしゃべりもほどほどに」
こくこくと頷くマリア。それを見ると、アーネストは微笑んだ。雨で濡れたクライムの服を一本目のナイフでびりびりと破る。脚回りの布が切られ、蠍に刺された箇所が露わになっていく。血は止まっているようだ。湿った不衛生な止血帯を解き、傷の状態を診る。発疹と痣が酷い。水疱には点々と血が混ざり始めていた。
「毒を出したのか……蠍というより蛇の噛み傷に近いな、これは」
アーネストは酒を傷口に垂らし、青年の脈を取る。血圧が低い。彼は台所に届くよう、大声でロビンを呼んだ。ロビンは茶を持ち、居間へ戻るところだった。
「おい、ロビン! そこに木の深めの器があるだろう? スープを盛る大きな鉢だ」
「あるわよ、それがどうかしたの?」
「そこに煮沸した湯を全部入れてくれ。棚に塩がある。鉢の半分以上、湯があるなら指で二つまみ塩を入れて混ぜてくれ。混ぜる際には金属の箆を熱で殺菌するように」
「了解したわ」
ロビンはマリアが座る椅子の前のテーブルに茶と菓子を置くと、踵を返して戻っていった。アーネストはロビンに指示し終わると、布の袋のようなものと別の酒瓶を棚から取り出し、その袋の中にどばどばと赤ワインを注ぎ込んだ。口を握りしめて思いきり振っている。「これぐらいで大丈夫かな」と呟くと、机にある木製の入れ物へ口を下にしてきつく握る手を開いた。
溢れだす蒸留酒。さらに彼は大きな鳥――鷹の羽だろうか――を棚にあるグラスの中から抜き取り、羽毛をむしり始めた。はらはらと床に落ちていく毛を余所に、綺麗に羽軸だけに仕上げた。彼は続いて二本目のナイフでその先端を針のように削る。アーネストはまたもや、それを燭台でさっと熱し、ワインをかける。一通り終わると、先ほどの袋のようなものの口に羽軸を糸で縫いつけた。まるで簡易な注射器のようだ。
ロビンが器を抱えて戻ってきた。「できたよ、アーネスト」その声を聞くと、彼は袋の半分ほど中に注いでくれと頼んだ。彼は紐で上側の口を縛ると、羽軸の針をクライムの静脈に刺し、皮袋のようなものに入った補水液を一定の間隔で押す。それは針の中を通り、青年に滴下されていった。しばらくして、アーネストが彼の血圧をはかると、正常の値に戻っていた。
「解毒薬は地下にある。僕が取ってくる間、ロビンは患者とあの子を見ていてくれないか?」
「もちろんよ」
クライムの顔色が安定しているのを確認すると、アーネストは言伝もほどほどに、居間の右奥にある階段へと向かった。マリアが席を立って、クライムの様子を見ようとする。「ちょっとだけだぞ」と小さく笑むアーネスト。こつこつと響く足音だけがその場に残った。
脚から伝わる久しぶりの地下のひんやりとした感触。「地下へ行くのは、ちょうどあの時以来だ」アーネストの脳裏に描かれる地獄絵図。この雨の時期になると、新たな流行病がこの地で猛威を振るい、多くの人々を死に至らしめた。目の前の者を救えなかったという後悔をどのくらい前に味わったろう。最初の患者を診てから、どれくらい師匠のもとで経験を積もうと彼を越えられるものではなかった。そのことを忘れていたのかもしれない。彼は過ぎ去りし日々を思う。「愚かな自分だった」と。見習いの分際で、ラニから買った東方由来の先進的医学書や薬。新しい舶来品がもたらした効能は大きく、彼の名声を上げた。鼻を高くしていたアーネストに爺ジョルジョは厳しく言い放った。「自分の才を使えなければ、宝の持ち腐れだ。愚弟よ、その意味をもう一度考えろ」未だその言葉が彼を苦しめているのは確かだった。
この家は師匠である爺ジョルジョの持家だ。今回の流行病の治療をした彼がフォンセを去った後、アーネストは無理を言ってここを使わせてもらっていた。彼は、この地一帯を襲った死痘病の決定的な治療法を一人で見つけようとしていたのだ。この地で生まれた病は必ずぶり返す。いつか帝国内のどこかで、複数の都市が壊滅的被害を受けるのは目に見えていた。アーネストは、ぽつんと生き残ったフォンセの市民を訪れては、診療を施して経過観察を行い、医書の古典と東方伝来の医書とを照らし合わせて、有効な治療法を探した。彼なりの懺悔なのかもしれなかった。
地下の研究室もあの日を境に、随分汚れた。クライムの水分補給に使った注射器も、この実験室で生まれたものだ。耐久性のある袋状のもの、しかもそれは手軽に製造できるものでなければならない。その結果、見つかったのが豚の膀胱だ。フォンセには牧畜を生業としている者もいたから、材料として不足はない。針は、ロビンが飼っている伝令用の鷹の羽をもらった。大きいものが必要なら牛を、小さいものでよければ兎を使えばよい。アーネストの発見により、砂漠旅行者が助かることが多くなった。かつては蛇蝎症と共に恐れられていたエレミア熱病も、今ではそれほどの脅威はない。
彼はランプに火を灯しながら、階上よりは幾分か小汚い棚のうちの一つの中を探し出した。取り出したのは彼の掌に収まるぐらいの小瓶二つ。どちらにもラベルが貼ってあり、「蛇蝎症解毒薬」「死痘病解毒薬」と書かれている。
この二つの解毒剤はアーネストの長年の研究で生まれたものだ。師匠ジョルジョが収集した古書を読み耽り、アーネスト自身が買い求めた外界の医療技術を学んだ彼が漸く手に入れたものだった。
月桂樹と小柑橘の葉を磨り潰し、岩塩と硫黄を混ぜ込む。胡桃と無花果の実を砕き合わせ、炭の粉末を加えた。その中に、鴨の血液を数滴落とす。蛇蝎症の場合は負傷した馬の患部の膿を混ぜ、死痘病の場合は罹患した牛の血漿を加えた。蜂蜜と蒸留酒を繋ぎとして使い、滑らかになるまで二つの材料群を練ると、解毒薬は出来上がる。それを患部に塗り込んで効力を得た。
だが、この薬の恩恵が薬そのものの効能に依るものなのか、気休めとして働いただけなのか定かではない。それでも、今までアーネストの治療を受けた患者は言う。「塗布された箇所の症状は快方に向かった」と。
「あの患者を何処かで見た気がするのは、気の迷いからかな」
小瓶を手に取った彼は思う。一階の寝台に横たわる青年によく似た少年を昔、治療した覚えがある。そして、彼にそっくりな人物をアーネストは知っている。
「――まさかな」
私的感情を振り払うように、彼は急ぎ足で階段を駆け上がった。この時、彼はかつての記憶を掘り返されるなど夢にも思っていなかった。
できる限りの急ぎ足で階段を上り、アーネストは休む間もなく次の処置に取り掛かった。棚に眠る箆の束のうちの一つを取り出し、蛇蝎症用の解毒薬をクライムの傷口に塗布する。硫黄特有の腐卵臭がつんと漂った。治療を行う彼の背後の棚の下段から、清潔な麻布を取り出すと彼は、残っていた殺菌済みのナイフでびりびりと最適な大きさに破った。二枚ほど切ったあと、それを傷口に重ねた。歪な形の残った切れ布を細長く折り畳み、簡易な包帯を作った彼は、丁寧に巻いた。処置を終えたアーネストは、着込んでいた白衣を脱ぎながら言った。
「これで粗方の治療を施した。脱水症状が改善すれば、直に目を覚ますだろう」
「――ありがとう、アーネスト。助かったよ」
「で、君たちの訪問はこれだけかい? ロビンはともかく、こんな砂漠をどうして君たちが歩いているんだ?」
彼は、極めて妥当な質問を返す。
「それね、あたしもこの子から聞いただけだから何とも言いようがないのだけれど。その男、カイルのギルドの一員らしくてね、アインザッツに用事があったみたいよ」
ロビンは思わせぶりに言った。「ああ、なるほど」とアーネストは呟く。
「じゃあ、この子は? まだ、十にも満たないじゃないか」
「私は、私、アインザッツで、一人で……一人暮らしてたの。クライムが逃げてきたところで、教会で会って、それから一緒にここまで来た、の。一人で暮らす必要ないって言ってくれて……一緒に行こうって……」
アーネストは逡巡する。確かに、最近のアインザッツは人買いが横行していると聞いている。スラムの形成も激しく、数か所に点々とできたスラム街が勢力を広げようとして刃傷沙汰を起こしているというのは、一部の者の中では重々知られている事実だった。だからこそ、カイルが馬鹿っぽくは見えるが、彼の父親の代から仕える一重鎮的弟子をアインザッツに派遣したのだ。それがあのボスであった。
「そうか。この男、クライムと言ったかな。彼の所属するギルドには君のような子供がたくさんいる。だから、心配しなくていい」
とはいえ、病魔に滅ぼされた街から幼子を連れて出るというのは、なかなか骨が折れる。アーネストは困った。カイルの拠点であるカデンツァに彼女を連れて行くことよりも、まずはこのフォンセから連れ出すことの方が困難であった。死痘病の危険性が最も高いのは、何よりも明らかで。マリアという名の少女の素性が気にはなるが、この際どうでもよいだろう。
「ねぇ、アーネスト。あたし、思っていたんだけれど」
「なんだ?」上の空の返事をアーネストはロビンにした。彼は考えことを邪魔されるのが嫌いな性質である。
「この子、いやね。あたしの勘違いかもしれないんだけどさ。昔に見たことあるんじゃないかってね。クライムっていう名前がどうもしっくりこないんだよ」
はっとして振り返るアーネスト。「君、読心術でも使えるのか?」
「そういうわけではないわ。そう、この子どこかで見たことがあるって感じる理由の一つにね。いるのよ、ほんとにそっくりな人が」
ロビンはここで言葉を切った。その不自然さに視線を移したアーネストが叫ぶ。
「おい、マリアちゃん。どうした!」
「――ちょっと、だるいの……暑くて、気持ち悪い……」
先ほどまで地に着いていた足は震え、上体は傍にいたロビンに投げ出している。息は荒く、目は虚ろだ。アーネストの目の合図を受けて、女が少女の服を脱がせる。彼女の腹には出血斑が少しではあるが、できていた。何人もの患者を診てきたアーネストには、少女の症状が敗血症系の死痘病であることが一目でわかった。まだまだ病状の進行度合いは軽いものの、油断を片時も許さない状況だ。
「――最悪だ、くそ」
アーネストは白衣の片方のポケットに忍ばせた死痘病の解毒薬を手に取ると、ロビンに預けた。不審な顔をするロビン。「どうして、あたしに渡すんだい?」
「まずは、殺菌消毒だ。蛇蝎症の解毒薬と混ざると危険だから、君が持っていてくれ。クライムをどかすわけにもいかないし、そこのソファにマリアを抱きかかえて待っていろ」
「――あたしは、この子と一緒にいて大丈夫なのかい?」
心配そうな顔でロビンはアーネストに尋ねる。
「あんたの仕事を増やすのだけは、ごめんだよ」
彼女は言い放った。しかし、彼は知っている。ロビンの思惑は、そんな単純で慈愛に満ちたものではないことを。彼女は隠しているようだったが、アーネストは薄々気づいていた。どうも、不穏な空気を彼女はまとっているらしいことを。しかも、少女絡みである。
「ロビン。君は一度、軽い死痘病に罹患している。抗体ができてしまえば、この類の病気にはかからないよ。僕の作った解毒剤の検体になったのを忘れたのか?」
「――そうだったね。すまない、マリアの治療に専念しておくれ」
「言われなくとも」
アーネストはぶっきらぼうに告げると、彼は折り畳んで椅子に掛けておいた白衣を再び着て、酒瓶と箆、麻布を持ち出した。棚にしまっておいたナイフを燭台で炙り、おおざっぱな殺菌を施す。アーネストの右大腿に装着しているナイフ専用のホルスターに入れて、マリアの横たわるソファへと急いだ。クライムを処置したのと同じ手順でマリアを治療していく。
「――アーネスト、さん。ありがとう、ごめんなさい……」
マリアは、まだ意識があるのか医術を施す男に感謝と謝罪の意を零した。
「そんな言葉が吐ける内は、そんなに心配することはないさ。何、謝る必要も、感謝する必要もない。大丈夫、僕はすべきことをしているだけだから。慣れぬ土地で、突然の出来事に体が悲鳴を上げてしまったのだろう。ここは、僕とロビンに任せてゆっくり休め」
少女の耳元で囁くとアーネストは、マリアの面倒をロビンに任せて薬湯を二人分作るために台所へと向かった。ロビンに少女を任せて良いものか、躊躇いが生じたが仕方なかった。アーネストは自らに言い聞かせる。「自分が同じ空間に存在する限り、彼は凶行には走るまい」と。
台所の引き出しに、こぎれいに整えられている可愛らしい小瓶の数々。その中から、彼の頭に描かれた順序で一つずつ取っていく。隅で燃え始めた窯の上に適当な大きさの鍋を吊るすと、彼は何種類もの乾燥植物――ほとんどがハーブであり、残り数種類が東洋由来の滋養回復と解毒・解熱、利尿に良いとされる植物であるが――を大匙一杯ずつ放り込んだ。
「――ロビンは、変わってないな」
ぼやくアーネスト。勿論だが、自分のことは棚に上げて。ロビンは、世界を騙すために偽って生きている。彼を構成する世界を。つまり、彼にとって、身近な人たちを裏切って彼は暮らしている。
アーネストもまた、変わっていなかった。ロビンが身近な世界を欺いているとすれば、彼はもっと大きな世界を相手に騙し続けていた。ロビンと彼が根本的に違うことと言えば、彼らを貫く意志が愛か偽善かだけであった。彼らそれぞれが、抱くことのできない感情を求めて互いを必要としているのかもしれなかった。短絡的に言うならば、「ただ、君に興味があったからだよ」と言うに違いない。
「相変わらず、処置の繊細さと打って変わって、あんたの薬はおおざっぱ極まりないねえ」
「マリアはどうだ?」
鍋にひのきのおたまを突っ込んでぐるぐるとかき回しながら、アーネストは尋ねた。
「寝ちまったよ。すやすや寝息立ててるさ」
ロビンは悪びれた様子もなく、薬湯を盛るための器を棚から数個取り出した。
「――結局、君はあの子に嫉妬していたんだろう? いや、昔の自分を見ているようで消したくなったというべきか」
「あんたには敵わないね、いつになっても全部御見通しってわけかい」
乾いた笑いが口から洩れる。居間で眠る二人を起こさないように、声を殺しながら。
「そうさ。あたしは自分の気持ちをあんたにまで隠そうなんざ思わないよ。あの子を、マリアを殺したい衝動に駆られたのは言うまでもない事実さ。そうじゃなきゃ、こんな病魔の巣窟に連れてなんて来ないだろうよ。つくづく自分の意地汚さがいやになるねえ。歪んだ愛情のたどり着いた先がこんなだとはね」
こんな性格なんだもの、もう治そうとしても治らないのさ。そう、悲しげにロビンは零した。
「どんなに偽っても、演じきれないものだね。自分の理想っていうのは」
静かな声が薬湯の鍋に沈下した。
「――君は、そんな生き方で幸せなのか?」
「あんた自身にそのまま返してやるよ」
湯が沸騰する音のみが聞こえる。あとは一切の沈黙がその場の主導権を握った。
「――あたしは、不幸じゃない。それだけは言えるわ。幸せからは程遠いけれど、それでも誰かを恨んで呪って生きていくよりは、ずっと幸せだと思うの。もし、あのまま兄と共に生きていたら、兄も愛した人も憎んでいただろうね。まあ、その代償は思ったより大きかったのだけれど」
静寂を割って飛び出した言葉は、意外にも今を肯定していた。
「それは、君の性別を言っているのか。仮面暮らしの有様を言っているのか。名を捨てた後悔なのか、それとも、時折訪れる殺人衝動なのか……いや、君が僕をも欺いて、あの子を売ろうとしたことかな?」
アーネストの言葉を折ってロビンが続ける。彼女は焦りに焦っていた。恐らく、彼の推測が図星なのだ。
「すべて、かもね。捨てたものと残ったもの、新しく拾ったものとの葛藤が今のあたしなんだ。いいこと尽くめというわけにはいかないけれど、あたしは自分を認めるしかないんだ。何をやっても、ね。いつまでも逃げてるあんたと違って。あたしは、マリアを殺そうとしたことを後悔はしていないわ」
吐き出した後、押し黙るロビンを横目にアーネストは続けた。
「君は忘れられたり、捨てられるだけいいのさ。僕はそれができない。君が些細なことだと言って悩まなくて済むことすら、僕は悩む。それを隠すために、女に走るのかもしれないね。一夜限りの戯れだけが一時の幸せ。ふっ。言われてみれば、ただ逃げてるのは、僕だけなのかもな。君は強いよ、ロビン」
薬湯をこぽこぽと椀に注ぎながら、アーネストはため息をついた。彼にとって、現在とは否定以外の何物でもなかった。
「――あんたは、家や身分を捨てたのを後悔してるのかい?」
「してるさ。今でも、街に出ると苛まずにはいられない。僕は、あの時怒りで逃げて良かったのかって。僕は家も身分も、主人さえも見限ったんだ。本当なら、死んで当然の命を師匠が生かした。それを感謝はすれど、責めはしていない」
アーネストから薬湯の入った椀を盆の上に乗せて、ロビンは居間へと向かおうとする。
「――もし、あんたが生きているのを後悔しているなら、一つだけ言っておく。あんたの記憶で救われている奴もいるんだ。あんたの生きがいはそれでいいじゃないか」
ロビンの言葉は思ったよりも深く、アーネストの心に沁み渡った。
「ありがとう、盟友」
「そんなことを言われる立場じゃないさ。俺も、あんたに救われてる。どんな汚い仕事を引き受けようと、お前は俺の友人でいてくれるな? アーネスト」
「――何を言ってるんだ。君が国を追放されようと支えてきたのはこの僕だ。それを今更疑うというのかい?」
ふふふと彼は笑った。その顔は、まだロビンが女になる前の頃と似ていた。
「俺は、マリアを殺す依頼を受けていた。いや、マリアというと語弊があるな……」
一度言葉を切った後、ロビンは言い放つ。その眼光は鋭く、男のものだった。
「ローレンスの御子を抹殺せよ。俺の受けた依頼だ」
「――僕の前でそんなことができるのかい?」
アーネストは静かに諭した。ロビンにはわかっている。怜悧な彼に露呈した時点で、この依頼は失敗だ。彼は大きく首を横に振った。
「しないよ、もう。お前の厄介にはなりたくないんでね。俺のところに来た依頼など、端から期待されていないに決まっている。適当に言い訳をつけて報酬なしにしてもらうさ」
気にすんな、とアーネストに言うと、ロビンは口布を引き上げて薬湯を運びに台所から姿を消した。湯気が彼の足跡を示す。小声で、彼の名が呼ばれた気がした。
アーネストは、ロビンのいた場所を見つめながら佇んでいた。仕える予定だった主君に何があったのか、彼が知りうることはできない。しかし、自分の代わりとして彼に忠誠を誓っている男のことを思うと、胸が痛んだ。
「――僕たちは、どこですれ違ってしまったのだろうな」
外伝『現逃人』
懐かしい風が男の耳元に吹き付ける。ふわりと彼の髪を攫うそよ風。海と空が混じる匂い。遠くで鳴る汽笛。にぎやかな人々の声。そこは、男の故郷だった。
「――僕は、戻ってきたのか?」
一歩一歩、煉瓦を踏みしめる足が疑っている。潮風が再び彼の頬を撫でた。「おい、アーネストじゃないか。おかえり」鼻を刺す磯の香りが彼を教え諭す。「お前が戻ってくるなんて、何年ぶりだ?」故郷ソルフェージュの門で、顔なじみの船頭が男の名を呼びながら、盛大に手を振っている。
「――エドガー、久しぶり」アーネストは、ぎこちなく彼に声をかけた。
「なんだよ、白々しい。俺とおまえの仲、だろ? ほら、乗れよ。おまえの家まで連れて行ってやるよ」
エドガーは、緊張で固まるアーネストの体を強引に船に乗せた。彼は知らない。アーネストが十数年失踪していた理由を。
ゆらゆらと揺れながら大きな通りを進む小舟。時折揺れ違う船に挨拶をしながらエドガーが梶を取った。黙り込むアーネスト。その姿にあきれ果てたのか、エドガーは話しかける。
「久しぶりの故郷だってのに、何だよ、その浮かない顔はよ」
「いつも通り、だろ。僕が仏頂面をしてるのは」
アーネストは気が進まないのだ。一度捨てた家に戻ったところでどうなる。彼の思いは伝わらない。
「おいおい、俺とアルが一体何年の付き合いだと思ってんだ? おまえさんの仏頂面具合なんか俺には丸わかりさ。どうして、そんなに渋るんだ」
アーネストは黙り込んだ。
「おまえが親父さんと喧嘩して、家を出たのは知ってる。アルの従弟から聞いた。おまえも、もう大人だろ。今が潮時なんじゃないのか?」
「エド、ギルバートから全部聞いたのか?」
「全部ってなんだよ。さっき言ったことしか知らない。俺が深く詮索したところで、おまえが折れて帰ってくるわけでもなかったしな。ただ、ギルはおまえのこと相当捜してたみたいだぜ。まあ、元老院就任が決まってからは、それどころじゃなくなってたみたいだけど」
そうか、とアーネストは、エドガーから目を逸らす。確かに、エドガーの言うとおり、自分は岐路に立っているのだろう。何もせず、何も言わず消えていく道が一つ。引き返して自分の過失を認める道。どちらも険しい茨の道であることは、アーネストにはわかっていた。過去を清算する。忘却ができない彼にとって、もしかしたらそれが唯一の救いなのかもしれなかった。
「なあ、エド。話してしまったとしても、僕は赦されるんだろうか」
「――もし、神が許さなかったとしても、俺が許す。救いは神だけが与えるものじゃない。そう言ってたのは、どこの誰だったか」
くすりと笑って、豪快に大回りの進路を取り始めるエドガー。「料金上乗せで頼むぜ?」
「金はある。主よ、聞いてくれるか?」
少しだけ、吹っ切れたような爽やかさを浮かべてアーネストは答えた。
「いいとも、盟友」
世界は案外、軋んだ音を立てないくらいには寛容だった。
船の進む速度で、アーネストの目に入っては出ていく見覚えのある風景。水路を流れる水の硬さも、汚れも見知っているはずなのに、なぜだか余所余所しい。鼓動が言葉の吐露を絶え間なく促していた。彼は、覚悟を決めたのか、おもむろに口を開いた。
「僕が家を出たのは、ほんの些細なことなのかもしれない。今思っても、僕は馬鹿だったと思う」
八年前、アーネストは行方をくらました。ピエタ・ベグラーベン侵攻戦争が終結してから数年後のこと。彼は、名門クラウディウス家の嫡男であった。港町ソルフェージュを皇帝から与えられ、この地を何代にも渡って統治してきた。ある程度の自治が認められ、交易で栄えたこの街は、瞬く間に評判を集めて多くの商人が移住してきた。国中の物資が集まる地。この街の名は商人がいる場所にこそ轟く。皇帝もまた、重要な交易地として、ソルフェージュ一帯を手厚く保護した。他国との交易権もクラウディウス家に一任し、彼の一家はウェルト帝国内でも屈指の重鎮となった。
何一つ不自由が存在しない暮らし。先代が敷いた敷石の上をまっすぐに歩けば、何もかもが手に入るはずだった。それなのに。何が不満だったというのだろう。
「――僕は、裏切ったんだ」
嫡男として、継がなければならないことがあった。それは、勿論家業であった徴税請負人を襲名すること。若き皇子ローレンスに仕えること。それだけではない。クラウディウス家の悪事もまた、アーネストを通して続いていくはずだった。
徴税請負人として、クラウディウス家はソルフェージュ周辺の村々も含めた土地の税金を王家に代わって徴収していた。そのうち、一定の額が彼らの収入源となっていたわけだが、先々代の頃からであろうか、水増し徴収を始めるようになった。国家に対する詐欺。そんなことは、承知の上で彼らは始めた。罪悪感の欠片などなく。その額は年々増加を続ける。クラウディウス家は暴利を貪る巨塊として、この港町に君臨をするようになった。長年慣れ親しんできた街の人々は、決して彼らを恨まなかった。矛先はすべて、マクシミリアン王家に向いた。止まらない横暴な取り立てに住民は、ますます王家に対する不信感を抱く。領邦の特権だとでも言うかのように、一家の暴虐さは際限を知らなかった。
「小さい頃から親しんできた街のみんなと、僕自身を育ててくれた家。これから仕えることになるローレンス様。そのどれに対して恩義を売ればいいか、僕はわからなくなった」
エドガーは、アーネストの話に口を挟むわけでもなく静かに聞いていた。アーネストは、自嘲気味に親友に尋ねる。「――ふっ、僕のことを見限っただろう。僕は臆病な卑怯者だ」
「だから、逃げたのか?」
エドガーは聞き返す。「でも、おまえは逃げ切れなかったんだろう?」
「どうして、そう言うんだい?」
「――行方が分からなくなった後のアルのことは、ここに来る旅人からよく聞いてる。錬金術師の爺の下について医術を学んだんだろ」
アーネストの方を向くわけでもなく、エドガーは風にその言葉を乗せた。
「それは……」
行く宛てもなく、ひたすら歩き続けた日々。ソルフェージュから一歩も外に出たことのない温室育ちに、どうして逃げ出すことができたのだろう。今となってしまえば、悪運だけが強かったと結論付けるしかあるまい。アーネストは門を掻い潜り、夜道を獣と夜盗に怯えながら北を目指した。自尊心だけが辛うじて彼を支えていた。どこかの町に流れ着くまでは、野垂れ死ぬわけにはいかない。飢餓が襲ってきても、道端の雑草や木の実を食い繋いで生きた。この時ほど、人間の生命力のしぶとさを有難く感じたことはない。だが、もうすでに儚い希望に縋って生きようとする清純な心は消え去っていた。何を糧にして生きればいいのか、彼自身にも判別できなくなり始めていた頃。アーネストは、名も知られない小さな村で一人の老人と出会った。
「僕が生きて償うべき罪だと諭されたから。欺いたなら、欺き通せ。偽善でもいい。僕が償うべきは、今この時から逃げたことだ」
老人ジョルジョは何も聞かなかった。それが今までの救いだった。アーネストが話したこと以外、彼は何も詮索しなかった。どうせ、聡いジョルジョのことだ。どこからか仕入れた情報を繋ぎ合わせて、アーネストの素性を知り得たに違いない。でも、一度も戻れとも言われなかった。
彼は小さな村で瀕死のアーネストを治療した。その頃にはアーネストの栄養失調も限界に達しており、見るも無残な風貌だった。駄々を捏ねて、逃げ出そうとする少年に爺は一喝する。村の住民に無理を言って分け与えてもらった食料を爺は少年の口に捩じり込んだ。
「自分の命を粗末にする奴がどこに行こうというのだ? 何からお前が逃げているかなど、わしは興味などない。だがな、これ以上逃げたところで誰がお前を受け入れる? 過去から逃げたところで、未来はないぞ」
ジョルジョの言葉は辛辣で、アーネストの麻痺していた心が悲鳴を上げた。堰き止めていた感情が氾濫するかのように涙がぽたぽたと落ちる。爺はそっと少年の頭を撫でた。
「――お前が逃げた理由が、理不尽な世界への憤りなら、わしと同じだ」
アーネストは一度零れ落ちた涙の素を拾い上げることができず、そぼふる雨に打たれる花のようだった。押し寄せる後悔、孤独。
「お前を取り巻く世界から逃げたとしても、結局何も変わらん。それでも、お前が逃げたいと言うのなら、わしは喜んで力を貸そう」
ジョルジョは言った。決して身分秩序外の身分に甘んじるわけでもなく、誇りに満ちた言葉だった。「――まやかしの慰めにしか、救いはないのかもしれん」
それから、アーネストはジョルジョを師と仰ぎ、修行を積んだ。膨大な知識の詰め込み。師匠の実地見学。この二つの繰り返しで何年が過ぎただろう。それに加えて、ジョルジョはアーネストに教えていたことがある。
「お前が得なければならない大切なものが何か、わかるか? 愚弟よ」
「知識の他に、ですか? 師匠」
頷くジョルジョ。アーネストは首をかしげて悩んだ。
「――思いやり、でしょうか」
「馬鹿たれ。なぜ、お前が神の視点を持つのだ? そうではない。お前に限らず、わしらすべてに必要なものは、信頼だよ。それがなければ、どうしてわしらは治療を施すことができる? 無知であることを自覚しないで、どうする? だからこそ、互いに信頼せねばならんのだ。信頼がなければ、思いやりも生まれん……それは、単なる妄想の産物だ」
だからこそ、わしらは平等に愛することができる。続けて師は語った。
「だがな、エドガー。僕は師に救われたんだ。逃げ続けていることには変わりはないのだけど、それでも、僕は生かされている。その事実だけで十分さ」
師から医術者を名乗る許可を与えられて数日後、アーネストは初めての患者を診た。生まれて初めて、自分が必要とされている実感を得た。そして、自分がこの世に生きているということも。
「――そうか、おまえの中で答えが出ているなら、俺がいなくても大丈夫だな」エドガーは微笑んだ。逞しく、柔らかな笑みだった。
巻き戻されるアーネストの記憶。カイルに呼び出されて、初めて治療をした少年。心を奥底まで閉ざし、言葉を失っていた。何も話さず、動かず、呼吸をしているのかさえ怪しく。まるで存在の仕方を忘れてしまったかのように、うずくまる少年がいた。体中、傷と痣だらけで。破れかけたウェルト帝国の軍服を着て。腐臭がした。人を殺した匂い。冷え切った手をアーネストは握ってやる。
「今すぐじゃなくていい。いつか悪夢が覚めるまで、僕が一緒にいるから。君は独りじゃない」
少年の目は何も捉えていなかった。
「――爺が言ってた。覚めない悪夢なんか、ないんだ。世界は案外、温かくて。居心地がいいんだよ。責めを負って下を向くくらいなら、上を向いて歩けってさ」
息をするだけの少年が、初めてアーネストの顔を見た。その時の彼の顔は、確か。
愛する親友の名を叫び、アーネストは飛び起きた。
「なんだ……夢か……」
エドガーは何を伝えたかったのだろう。アーネストは思う。
「弱気になった僕を叱りに来たのかな」
最後に思い出した少年はやはり、彼だったのだ。思い出せ、ということだろうか。
「あの少年が、また僕のもとに運ばれてくるなんて。なんて、因果なことだろう」
アーネストは、起き掛けのベッドの上で呟いた。
「また、会えたね、クライム。もう、僕がいなくてもしっかり生きているじゃないか」
彼は穏やかな笑みを湛えて、寝室を出た。
第三章『仇花人』
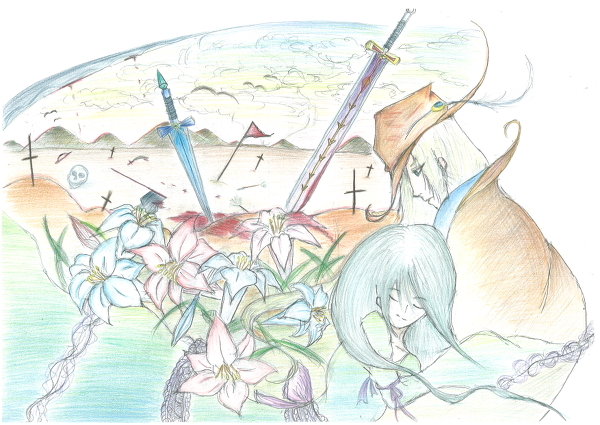
「なぜ、彼女が……」
国境付近のバルフォイ侵攻戦争の最前線で指揮を執っていたローレンスが祖国ウェルト帝国に帰還したのは、この戦争が始まってから一か月後。長々と続く侵攻戦争の発端であるピエタ・ベグラーベン侵攻戦争から、すでに十年以上の月日が流れていた時のこと。皇帝である兄サミュエルの代理として、彼は戦地に赴いた。
最初は短期間の指揮だという名目で赴任したものの、敵軍の抵抗が激しく、当初の見込みよりもずるずると長引いた戦争だった。一か月もの激闘の末、ローレンス率いるウェルト帝国軍が国境の要所を押さえたため、祖国の勝利も確定し、長期に渡った戦争は終結の兆しを見せていた。五年以上前に始まった戦争もあと数日で決着がつく。敵対関係にある両国ともども、民の疲弊が激しく、早く停戦協定を結びたくて堪らないといった状態であった。難航するとみられた和平交渉も、弁舌が達者なローレンス直属の部下フィリップ・ヘルツォグが有利に進め、幾らかの領地を帝国に併合することに成功した。
部下からの速報を耳にしたローレンスが、感情を表に出さなくとも、祖国に朗報を持ち帰ることができるという名誉心に満たされたのは言うまでもない。率いる幾千もの兵も勝利の喜びに酔い、彼の心はますます高鳴った。遠くの空を見遣るローレンス。祖国で彼の帰りを今か今かと待ち侘びるかつての最愛の人を想うと、逸る気持ちを抑えられなかった。祖国まで一週間かかる道を彼らは喜々として駆け、五日で祖国へ帰還することができた。
首都アリアは、虹が落ちたかのような美しさであった。祖国ではすでに、凱旋パレードの準備が着々と進められ、ローレンスらが到着するころには、帝国歌が軽快に、華やかに演奏されていた。長らく聞いていなかったメロディーに、心なしかローレンスの疲れで固くなった表情がほぐれる。彩り鮮やかな服で着飾った国民が祖国の勝利と、それに貢献した勇猛な騎士を祝福するため、街道の左右から惜しみない拍手を送っている。はしゃぎまわる子供たちが眩しい。「あの子はどうしているだろう」と自然に宙へ浮くローレンスの心。家族や恋人に歓迎されるローレンス配下の騎士たちは、満面の笑みを浮かべ、幸せに包まれていた。ローレンスは、彼らの夢や願いを壊さずにいられたという安堵感にさえ浸っていた。ふっと脱力する体。張り詰めていた緊張が溶けていく。しかし、祖国に意気揚々と帰還した彼を出迎えたのは、悲しい挽歌であった。
「ご苦労。貴様の采配振りは相変わらず見事なものだな、ローレンス。感謝をしている」
「勿体なきお言葉。身に余る光栄にございます、サミュエル陛下」
「そう畏まる必要はない。面を上げよ。この度の戦果、期待以上のものであった。後々、貴様には褒美を遣わそう。しかし、貴様が不在の間の悲しい事実も報告せねばならぬ。私とて、貴様にこの事実を告げるのは心が痛むのだ。一度しか言わぬ。心して聞くがよい」
首都アリアの南に位置するマクシミリアン城にて、皇帝サミュエルに戦果報告を一通り済ませたローレンスに突然告げられた訃報。青天の霹靂。皇帝は最愛の妻の死だというのに、乾いた声で淡々と弟にその事実を告げた。城の外で流れ続ける行進曲は、もうローレンスには他の騎士と同じように聞こえてはいなかった。視線を逸らした先に見えた凱旋パレード。軽やかなハーモニーは、悲痛に覆われた重苦しい、死者を悼むエレジーにさえ彼には聞こえていた。煌びやかな衣装もまた、萎れかけた薔薇と同じように色褪せ、見るも無残に変色してローレンスの瞳に映っていた。
「私の正室フィオナは、先日私との子をもうけたがために、静養するために彼女の故郷へと帰したのは知っているな」
「勿論にございます、陛下」
「――だが、フィオナが帰還したのは、故郷チェレスタではなく、魔の森クラヴィーアだそうじゃないか。私は、その事実を知ってすぐ彼女をアリアに戻した。だが、フィオナは口を割ろうとしない。貴様の帰りを待ち、事情を聴取しようと思っていたのだが、ローレンス。貴様、何か知りはしないか?」
ローレンスの背に悪寒が走る。心臓ごと鷲掴みにされるような言い難い恐怖。
「――陛下の思し召し以上のことを知ることは、いくらフィオナ様と仲睦まじい身とはいえ、存じ上げませぬ」
声を震わせないよう、動揺が面に出ないよう、ローレンスはサミュエルに告げる。
「そうか。私とて、貴様を疑いたくはない。話を元に戻そう。フィオナは、魔女の嫌疑があるため、理由を作り彼女の再び生家へと帰した。皇帝の妻が仮にも魔女の疑惑があると民に知られては、マクシミリアン家の存続も危ういからな。異端審問にはせず、そのまま離縁に俺は持ち込もうとした。だが、悲しいかな。数日後、私がアインザッツの別荘を訪れた時には、彼女は何者かに殺されていたのだ」
「フィオナ様が……魔女、であると?」
「教皇イノセントと枢機卿アーサーが言っていた。貴様も彼らの目利きを疑うわけではあるまい。何件も異端審問を請け負っている彼らを」
「ですが、王家の破滅を企む陰謀とはお考えにはならなかったのでしょうか」
「私がその可能性を考えぬとでも?」
「――いえ。私めが動揺しているだけにございましょう。彼女は私めにとっても大切な人にございましたので……」
「私情が表に出ることは当たり前だ。構わぬ。喜びに浸っている民に知られぬよう、できる限りの喪に服せ。私が命じなくとも、貴様ならわかるだろう。フィオナの遺体はアインザッツの屋敷にて一時的に保管してある。最後に貴様も彼女に会いたいだろうと考えてのことだ」
「――有難き幸せ。陛下の御慈悲、頂戴いたします」
「手数をかけるが、貴様に一つ頼みたいことがある」
「は。なんなりと仰せ下さいませ」
「――フィオナを大神殿に葬ってやってくれ。私は公務の都合上、離れることができぬ。異端審問にかけていない彼女なら、マクシミリアンの墓地に葬ることもできるであろう。大司教らに聞けば、万事取り計らってくれるはずだ。ローレンス、頼んだぞ」
兄は、弟の「御意」の一言を耳にすると、軽く頷いた。外遊のため、従者が皇帝を呼びに馳せ参じると、彼は外套を翻して姿を消した。ローレンスはサミュエルの退室まで顔を伏せたまま、その場に膝をついてじっとしていた。
ローレンスは空虚な面持ちで皇帝のいない玉座に一礼だけすると、血相を変えて城を後にした。首都アリアを離れ、アインザッツの屋敷へ、側近のリチャードとフィリップを従えて馬で駆けた。いつもと同じ道が今日は異様に長く感じられる。焦りが彼らの平静を奪う。一筋の滝が頬を途切れることなく伝う。ローレンスにそれを拭う余裕は一つもなかった。
彼が屋敷に着くころには、もう日が落ちかけていた。夕日に照らされた赤煉瓦の屋敷は物音ひとつせず、悪魔の棲む巣窟のような不気味さと、世捨て人の住む小屋のような静けさを同時に醸し出していた。ぎいと音を立てて扉を開けると、そこには椅子の背に両腕を置いてくつろいでいる女がいた。「フィオナ!」と叫んでローレンスは彼女に近づいた。扉の前で呆然と立ち尽くす二人の家臣を横目にして。しかし、そこにあるのは安らかな顔で眠っているフィオナの彫刻だった。生きているのかと錯覚させるくらい美しい死に顔を湛えて、彼女は眠っていた。
彼女の胸には銃で撃たれた痕跡があり、彼女が着ていた浅葱色のドレスの左側は真紅に染まっていた。彼女の手に握られた安物の短剣には、血がこびり付き、床一面には紅い花が点々と咲いていた。床木に染みこんだ血痕から見て、既に数日は経っていると見てよかった。ローレンスは、彼女の手から柔肌には似合わない短剣を取り、手で彼女の手を包み込んだ。宝石のように冷たく固かった。白くきめ細かな彼女の手には、転々と青黒い斑模様が浮き出ており、彼に彼女が帰らぬ人になってしまったことを暗に告げている。ローレンスは、狂おしいほど愛しいフィオナを静かに抱きしめ、最後の別れの口づけをした。溢れるばかりの愛と慈しみを込めて。だが、彼は知っていた。彼女が「魔女」の疑いのために殺されたのではないことを。
気が付けば、日はすっかり落ちて雨のそぼ降る音が窓を通して聞こえてきた。薄闇で満たされる部屋の中で、ローレンスは、何も言わずにフィオナの傍で声を殺して泣いていた。部屋に反響する嗚咽。リチャードとフィリップも、いつの間にか燭台を携えて主君の隣に来ており、彼らは帰らぬ人が好んだ色とりどりの花を抱えられるだけ抱えていた。
「フィオナ様がお好きだったこの花たちを捧げれば、少しでも御心のお慰みになるかと思い、お持ちいたしました」
「――ありがとう」
フィオナが屋敷の庭で育てていたという色鮮やかな花々。彼女は、時々ここに立ち寄って花と屋敷の手入れを行っていたのだろう。甘く淡い思い出の場所に生きる花。それだけが男の手元に残る彼女の生きていた証だった。その美しい花は彼の潤んだ瞳には眩しく、目元から再び流れ出す激流にローレンスはただ身を任せるより他はなかった。その流れの中で、彼は彼女と過ごした懐かしい日々を垣間見た。サミュエルの要求を呑む前の、二人で笑いあった日々が彼の眼前に蘇る。
共に誓い合った将来。兄の非情な言葉。ルナの悲嘆に暮れる横顔がローレンスを締め付ける。「僕が弱かったから」後悔だけが部屋に溜り、積もっていく。フィオナだけではない。ローレンスもまた、未練を断ち切ることができなかった。
「――あなたといたいの。夢を見させて」
フィオナは艶めかしく彼を誘った。絹布を通じて、男の背に触れる柔らかな双丘。二人の鼓動の同調が、男の理性を崩していく。女は妖しげに、口唇を男の首筋に這わせる。男の怨恨と衝動が女を抱きすくめた。暴力的な愛しさが二人を惑わす。一夜限りの艶やかで、刺激的な快楽に二人は溺れてしまった。禁忌を犯してまでも。彼は迫りくる残酷な現実から背を向けるようにして、外套を翻し庭先に出た。屋敷の外では薄暗い曇り空の下、花々がローレンスを慰めていた。ただ風に花を揺らしながら。
燭台の炎が揺らめく中、ローレンスらは庭先で摘んだ花で花飾りを作った。そして、彼らは美しいフィオナの最期の姿を脳裏に焼き付けるため、ただただじっと彼女を見つめていた。そうしているうちに夜は深まり、雨がぽつぽつと降り出した。窓を叩く雨音は、憂国の騎士を責めていた。部屋には雨の音だけが残り、微かな吐息の気配さえかき消した。嵐の到来だろうか、何度も雷が鳴り響く。それは、最愛の人を見殺しにしたローレンスへの神々の怒りとさえ受け取れた。彼は無言の責め苦に耐えられず、立ち上がり玄関へと向かった。
「ローレンス様、どこへ行かれるのです」
「少し独りになりたい。客室へ行く」
リチャードは主を一人にするのを躊躇っていたが、部下の心配を余所に、主人は玄関に置かれていたランプを取り、火をつけると二階の客間へと足を運んだ。こつこつこつと足音が誰もいない暗闇の踊り場に木霊する。廊下はより深い闇に覆われ、ローレンスは、よく利用していた客室までの道のりが気の遠くなるほど長く感じた。がちゃりと声を立てて笑う扉に迎えられ、彼はランプの灯りを頼りに、カーテンを閉めて寝台に腰を下ろした。
被っていた帽子を机の上に投げる。何も変わらない規則正しい客間の風景のはずなのに、彼にはそれが歪んで見えた。上がる心拍数。震える指先。枯れた喉。熱を帯びる目頭。胸がはち切れそうなほどの後悔と自責。叫びたくなる衝動。
「――神が二人の罪科を見抜いたのだ」
声にならない悲鳴。襲いかかる頭痛。瞳から零れだす熱い涙。冷静さを取り戻そうと爪を立てた左の手の甲には血が滲んでいた。その痛みは、混乱で意識が肉体から遊離していたローレンスを少しだけ現実に引き戻した。掻き傷の痛みで我に返ると、途端にどっと疲れが彼の両肩にのしかかってきた。睡魔がローレンスの耳元で囁き、眠りへと誘う。現実と感情の交差が目まぐるしい一日を過ごした彼が足掻き切る術はなく、そのまま寝台へと着の身着のまま倒れこんだ。海の底へと溺れてしまうような感覚。押し寄せる閉塞感。悪夢は、彼に逃げることを許さなかった。
はっとしてローレンスが目を覚ますと、夜が明けていた。
「後悔の意味が分かる時、それは既に遅し。その通りじゃないか」
彼は誰にともなく窓に向かって呟いた。昨日の夜から降り始めた雨は、いつの間にか止み、閉じられたカーテンから差し込む穏やかな光は、フィオナのいない静けさを一層際立たせる。いつもは訪れが楽しみであろう賑やかな小鳥の囀りも、彼は素直に喜ぶことができなかった。泣き腫らしたぐしゃぐしゃな顔のまま、彼は階下に行った。一階に下りていくと、そこにはリチャードの姿はなく、フィリップだけが彼を待っていた。一睡もできなかったのだろう、部下の顔はやつれていた。
「リチャードは、ここ数週間の付近の様子を探りに行きました。御心配なさらないでください。しばらくしたら戻ってきますので」
「――そうか」
「リチャードが戻り次第、神殿に参上しようとの所存にございます。サミュエル皇帝の勅命の通りに」
「フィオナをこのままにしておくわけにも行かぬ……賢明な案だ」
「もしかしたら、大司教のウルスラ殿が何か知っているかもしれません。フィオナ様は足繁くお通いなさっていましたから」
「――わかった。屋敷の裏に馬車があるはずだ。フィリップよ、手配を頼む」
「承知いたしました」
部下の退室を認めると、主はふと惹きつけられるようにフィオナの使っていた文机に目を遣った。そこには、太陽の光を受けてきらきらと輝く小さな小瓶があった。淡く青く光る小さな小瓶をローレンスは、不審に思い机の上からその小瓶を手に取ってみる。瓶の蓋は緩く閉められているだけで、中には紺碧の液体が少し残っていた。瓶が置いてあった場所には、一枚のメモが残されており、それにはフィオナの流麗な字で「さあ、毒よ。あなたの仕事にかかりなさい」とだけ書かれていた。紙の上に点々と落ちている青い雫は、まるで涙のよう。
「もし、これが当たっているとするなら……これは……愛の毒薬、か」
彼女が愛していた文豪の書いた戯曲。叶わぬ恋に絶望した男が飲み干した毒薬。彼女なら考え付きそうなことだ。床に置いた彼女の血液が染み付いた短剣が、ローレンスを死に急かすように見えた。彼女の望みなのかと錯覚するほど精巧に作られた舞台に怖気が走る。彼はわなわなと震える自分の手を見た。潤んでくる瞳。涙を零すまいと咄嗟に上を向くと、なぜか乾いた笑いが口から洩れた。
「――何で、僕は死ねなかったんだろうな」
戦場で散って行った若い未来ある兵士に対して、後ろめたい気持ちを感じながらも、ローレンスはやはりそう思わざるを得なかった。自分の心を支配する無気力感。椅子に優雅に腰かけるフィオナを見つめながら、彼はしばらく放心していた。
扉越しに聞こえてくる軽やかな蹄の音。御者が鞭打つ音も聞こえてきた。ノックが騒々しくこの部屋の静寂を乱す。フィリップだろうか。その音で我に返ったローレンスは、冷たくなった最愛の人を抱きかかえると扉に向かった。振り返ると、そこにはフィリップではなく、リチャードが待っていた。
「ローレンス様、行きましょう」
主人より一回り大きい武将は、言葉少なに主を促した。主君は顔を強張らせながらもしっかりと頷く。外に出ると、花輪に飾られた女はまだ生きているかのように、安らかな笑顔をうっすらと浮かべていた。吐息も鼓動も体温も失った彼女は、ローレンスの腕の中で眠っているのに遠い場所に旅立ってしまっていた。彼らは馬車に乗り込むと、御者席にいるフィリップに合図をした。高らかに鳴る鞭の音。馬は、雄叫びを上げるとリズムよく走り出した。
ローレンスは馬車に乗っている間ずっと、窓の外の景色ばかり見ていた。愛する人と過ごした思い出が、本がぱらぱらと風に捲られるように甦ってきた。「別れろ」その一言の重み。「今日からフィオナは、私の妻だ」残酷な兄の言葉の荊の鞭が彼の心を抉り出す。彼女の求めと助けに応じることのできなかった愚かな自分が憎らしかった。そして、兄を裏切ってまで愛しい女の求めに応じてしまった自分さえも。悩ましさで正面を見ることができない主人に、声をかけることも躊躇われたのか、リチャードは終始俯いたままだった。
馬車に揺られること、一時間。ローレンスらは白い大理石で造られた荘厳な神殿の前に辿り着いた。数えきれないほど美しい花々が生を謳歌するように咲き誇っている。滑らかに耳に届く祈りの文言。聞きなれたはずの温かい祈りのメロディーが今日はとても寒々しかった。
彼らの姿を目に止めたのか、一人の修道女が走り寄ってきた。柔らかな栗色の髪を風に靡かせながら、息を切らして彼女はやってきた。思わず心を満たす懐かしさ。ローレンスは、フィオナを抱えて馬車を降りた。彼のあとに、リチャードとフィリップも続いた。
「ローレンス様……」
白いローブを纏った大司教ウルスラは、息をのんで一瞬動きを止めた。
「ウルスラ……陛下から詳細は聞いているだろう。神に最も近いところに葬ってやってくれ」
白い騎士は、この言葉を絞り出すのが精いっぱいだった。
「――わかりました。ですが、私の方からもローレンス様にお話がございます」
強張る表情と声音。ウルスラと呼ばれた女性は他の巫女と神官を呼ぶと、彼らに指示を出してフィオナを引き取らせた。
天井の高い長い廊下を渡り、ローレンスらは、ウルスラに連れられて神殿の奥の小部屋に来た。小奇麗な部屋には一通りの家具があり、彼女はそこで生活しているらしかった。その部屋の奥に、壁に背を預けている青年がいる。神官らしい恰好はしておらず、ローレンスと同様に、ウルスラに招かれた客人らしい。焦げ茶色のフードを目深に被って素性を隠す出で立ちではあるが、帯剣をしている彼の風貌から、上級貴族のお忍びであろうか。そうであるならば、彼女を介して自分に面会するという煩わしいことをする必要はないのに、とローレンスは心中思った。
「お待たせしました、ギルバート。腰を掛けていてもよろしかったのに、殊勝なことです。もう、顔を隠す必要もございませんよ。ここにいるのは私とあなた。そしてローレンス様とその臣下の方々だけですから」
「つまらぬことで手数をかけたな、ウルスラ」
「ギルバートにはお世話になっていますから、不本意ですが」
「何か言ったか?」
「いいえ。何でもございませんわ」
棘のあるウルスラの笑顔に迎えられたギルバートは、おずおずとローレンスの正面の席へと腰をかける。フードを脱いで素肌を晒した彼は、まだあどけなさを残す青年だった。ローレンスを見るなり、彼はフードと同じ色をした短髪の乱れを直すと、畏まった調子で話を切り出した。
「ご挨拶が遅れ、申し訳ございません。我は元老院議長ギルバート=クラウディウスと申します。ローレンス陛下には以前に、公務にてお会いしたことがございますかと」
「ああ、覚えているよ。若くして元老院議長に就任した君の能力を僕はとても驚いた覚えがある。でも、君は上級法服貴族だろう。どうしてこんな回りくどい面会を望んだんだい?」
ギルバートは隣に座っているウルスラと顔を見合わせ、言葉を勿体ぶったように切る。こういう時の相手の反応は決まって悪いもの。ローレンスはわかっていた。今までの経験を考えると、この類の面会で良い思いをしたことは皆無である。
「――ローレンス陛下、どうかお気を悪くせずにお聞きくださいませ。フィオナ陛下のご逝去に関わりのあることにございます」
「何か表立って言えぬことがあるようだね。よかろう、話すがよい。リチャード、フィリップ。この部屋の見張りを頼む」
「御意」
ギルバートとウルスラが気まずそうに扉を見つめていることを察したローレンスは、自分の臣下を部屋から退出させて、見張りにあたらせた。壁伝いに主たちの衝撃的な話が聞こえてしまったとしても、彼らはきっと沈黙を守るだろう。怯える二人の招待者にローレンスは目配せをした。
「陛下が先日の国境戦線のため、長らく帝国を留守にしておいででしたのは、我らも存じ上げております。我ら二人も、戦争が始まる以前から元老院及び閣議にて行われた軍法会議に出席しておりました。……閣下は全くご参加されませんでしたよね」
過去を思い巡らすように、ローレンスは瞳を右上に泳がす。彼はまだこの密会の意図がまだわかっていなかった。招待者の顔がさらに険しくなり、どんよりとした空気がその場を支配する。微かに神殿の表から、痛ましいエレジーの振動が伝わってきた。
その数秒間の重々しい沈黙を破り、ウルスラが言葉を継いだ。心なしか彼女の声が震えている。時々漏れる彼女の詰まった呼吸が皇子の鼓動を早める。
「――いえ、ローレンス様が出席してはならない訳があったのです。なぜなら、あの会議は、あの国境戦争自体が、ローレンス様を謀るために巧妙に仕組まれた罠でございましたから。私たち二人も、その陰謀の一端を担うよう、指示を受けていたのでございます」
ウルスラは息も継がずに一気に言葉を吐き出した。目元は潤み、顔面は蒼白だ。
「我ら二人が出席いたしました閣議にて、そのお話がございました。サミュエル陛下の思し召しは、サミュエル陛下の奥方であるフィオナ陛下の姦通罪を適用すること。そして、その姦通の張本人であるローレンス陛下を暗殺すること……可能であるなら、お二方の御子を抹殺すること」
わなわなと震えて言葉も継げられないウルスラに代わり、ギルバートが陰謀の一端を吐き出した。怯えるような瞳でローレンスを伺う二人がいじらしく思えた。彼は被っていた羽根つき帽子を取り、テーブルの上に静かに置く。腰に差された剣の柄に手をかけると、慈愛に満ちた瞳で二人を見つめた。「いっそ、死んでしまえるなら本望だ」とでも言わんばかりに、剣を眼前の机の上に放り出した。
「もしや、君たちが僕の刺客かい?」
ギルバートはローレンスの諦観した態度に慌てた。敵意がないことを示すために、彼は腰の剣を鞘ごと机の上に供えると、皇子に向かって凛とした声で言った。揺らぎのない瞳がローレンスを見つめる。
「滅相もございません。我らは、幼い頃よりローレンス陛下に忠義を誓った者です。婚約の秘跡を辿ったお二方を不義と罵ることは我らには到底できません。どうか、我らをお疑いにならないでくださいませ」
ギルバートの肩に寄り掛かっていたウルスラも懇願する。二人を俄かに信じられることではない。だが、ローレンスら自身の状況を判断する材料がない以上、彼らを信用するしか道はなさそうだ。「自分が死ぬことは、どうだっていい。リチャードやフィリップには申し訳ないことをするが、彼らは新しい主君を見つけて宜しくやっていってくれるだろうという確信はある。だが、フィオナの忘れ形見を見捨てるわけにはいかぬ」ローレンスは、どうやら生を享受しなければならない宿命らしいことを受け入れた。
「――君らは、僕が今、置かれている状況を伝えに来てくれたということでいいんだな」
頷く二人。ギルバートは、「手短に話させてください」と言ってローレンスに許可を求める。彼は無言で彼の発言を促した。
「フィオナ陛下の殺害に関して、我らの独自の偵察から判断するに、サミュエル陛下の側近の内、最も手練れたドロシー将軍がその任務を担ったようです」
考えれば考えるほど、悪い方向へローレンスの思考が傾く。ドロシーは皇帝の側近のうち、特に暗殺を専門としていた。
「じゃあ、フィオナを殺したのは……サミュエルの勅命だというのか?」
ローレンスは、「本当にそう言い切れるのか?」と懐から例の小瓶を取り出した。青い液体が数滴残るその瓶を手に取って眺めるギルバートとは逆に、ちらりと隣からそれを目にしたウルスラが瞳孔を見開き、戦慄き始める。その様子を勘繰るように、目を細めて見つめる皇子。彼女のか細い悲鳴だけがちっぽけな部屋に残響した。肩を、声を、指先を震わせてウルスラはギルバートから瓶を受け取ると、異国語で書かれたそのラベルを二度見る。ローレンスは、真実を知っているだろう女の言葉を待った。
「君が知っていることを全て話してくれ、ウルスラ」
彼女は、大きく息を吸って乱れた呼吸を整えると、ぽつりぽつりと絞り出すように話し始めた。それは、二人が把握している以上に、泥沼の権力闘争の裏側の断片を物語っていた。
「――昔から聖職者は、影に生きよということを教えられてきました。ですから、ギルバートはもちろん、ローレンス様さえご存知でないことが数多くございます……私たち教会関係者には」
ウルスラは言葉を切った。二人も何も言わずに、彼女の次の言葉を促した。彼女は、非常に言いにくそうに、吐き出した。
「元々、ウェルト帝国は教会立国なのです。もう何百年も前の話ですし、サミュエル様が王権の神格化に躍起になっていらっしゃいますので、史実が書き換えられたとしてもおかしくはありません。今まで帝国がなかなか中央集権体制に移行できなかった原因もここに由来します」
「――王家と元老院の調整役に、枢機卿が設けられているのもそのせいか?」
ギルバートは問う。
「ええ。今から三十年前の叙任権闘争で、一旦教皇権力は地に落ちました。その仲介役として、枢機卿という役職が設けられたと聞きます。アーサー枢機卿の尽力もあり、ある程度の良好な関係は両者ともに築けていたとここ数十年は思います。ですが、最近新しくイノセント様が教皇に就任しましたことで、再び王家との対立が水面下で深まっています」
「――僕は、宗教権力の介入を極力排除しようと思っていたからね。兄上と共に」
ローレンスは零した。サミュエルほどの過激に王権強化を企みはしていなかったが、彼とて絶対王政上、過剰な教会の政治介入は懸念事項の一つであった。
「――ハルモニア教が創始されてから今まで、私たちが為政者に対して傲岸であれたのは」
青い液体が入った瓶を手に取って一度それに視線を落とすと、彼女は悲しげに継いだ。
「歴史の裏に携わってきたからですよ」
ローレンスの頭の中で絡まって縺れていた糸が、徐々に解れて二本の糸が格子に編まれているだけとなった。靄が晴れるように開けていく脳内回路。ギルバートは一点を凝視したまま、動かない。
「教皇側に脅迫されて、フィオナは自殺を……?」
「恐らくその可能性が高いかと」
「――では、ウルスラ。ここ数日におけるドロシー将軍の動向はどう説明を付けるんだ?」
「毒を用いて、私たち教会一派は暗殺を働きます。その小瓶が空になっている以上、フィオナ様の服用を認めざるを得ません。ローレンス様、その毒が床に零れていたわけではないのでしょう?」
「ああ。一滴も垂れてはいなかった」
ローレンスは、最愛の人の死に姿を思い出して声を上ずらせた。
「揮発性の高いものではないですし、フィオナ様がこのカンタレラを服用したとみて間違いはないでしょう。イノセント様に命ぜられた僧兵か神官がフィオナ様の自殺幇助をしたのでしょうね。擦れ違いになる形で、サミュエル様側近のドロシー様が誤って発砲したものと私は推測します」
彼女は酷く暗い顔をしていた。静謐に支配される空間。
「実を言うと、私が教会に対する意見書が教皇の怒りに触れて破門されてしまいました。もう、どうだってよいのです」絶望しかありません、と彼女は目を伏せた。
「私が破門されるだけで済むのなら、それで構わなかったのです。いつかはこうなることを予期はしていましたから。ですが、宗教の介入を渋る王家に対しての宣戦布告を黙って見過ごすわけにはいきません。フィオナ様の暗殺は、あくまでサミュエル様への報復なのです。だから、次の標的は……」
「――僕、というわけか」
時世というものは、案外悪戯好きらしい。ローレンスは思った。サミュエルを嫌う教会と教会を嫌うサミュエルの意図が今、完全に重なり合った。狡賢い二人のことだ、対象を葬るためには上辺だけの停戦協定も結びかねないだろう。それとも、両者の思惑に干渉しない形で自分を弱らすか。彼が一番気がかりなのは、彼女の残した忘れ形見のことであった。
「ギルバートよ、僕とフィオナの忘れ形見も知っているんだろう?」
「畏れ多くも」
「僕は、クラヴィーアに行く。二人とも、僕と来るか?」
咄嗟に顔を見合わせあうギルバートとウルスラ。彼らは強く頷いた。
「クラヴィーアに行くには、アインザッツからはどう行くのがいいだろうか。追われている身となると、堂々と正規の道は使いたくはないんだが」
悩みこむ三人。通常の旅人ならば、アインザッツの正門を通って南のプリローダ平原を抜ける。そのあと馬を五日ばかり南の方角へ走らせ、ギュアス盆地を過ぎると、クラヴィーアの森へと辿り着く。計十日程度の旅であろうか。もしくは、迂回路ではあるが、アインザッツの裏門から北のエレミア砂漠を通り、西の方角へ進んで自治都市フォンセとカデンツァを抜ける方法がある。こちらの場合はさらに、オーズィラ湿原を越えなければならないため合計二十日程度かかる。
「裏門から出るのが得策かもしれませんが、それはそれで足がつきそうですね……」
ギルバートが苦々しく呟く。無理もない。ウェルトの宮廷には皇帝直属の精鋭諜報員がいる。彼らの手にかかれば、目立つ五人の足取りを探すことなど、何の造作もないことだろう。
「もしかしたら、このアウロル大聖堂にある抜け道がアインザッツの外へ繋がっているかもしれません」
ウルスラが言うには、昔、と言ってもウェルト帝国が建国されるよりもずっと前のことで、ハルモニア暦元年にまで遡るのではないか、という頃、ハルモニア教は酷い迫害を受けていた。その当時の艱難を思い出すことができるよう、大きな教会であればどんなものでも地下礼拝堂と抜け道は必ず整備されているとのことだ。その話を聞いて、ローレンスが部屋の見張りを頼んでいた親愛なる部下を呼びに行こうとしたとき、突然の扉の開放音が小さな一室に響き渡った。部下からの切羽詰まった急報が彼ら三人を襲う。
「ロー……レンス、様……。急襲です……! 敵の、数と……装備の、様子から……直属軍の襲撃、では、なく……」
息を荒げながら、文官は告げた。彼の着こむ外套には血飛沫が点々と付着している。
「しっかりしろ、フィリップ! リチャードはどうした!?」
「リチャードは、不穏な気配を……感じて、外に出たところ、僧兵に囲まれたと……今、聖堂前で、私をローレンス様のもとに遣わすため……逃がした、と伝えるよう」
皇子は、短くギルバートに「帯刀せよ」と命じた。ウルスラには「抜け道はどこだ?」と尋ねる。
「大講堂のパイプオルガンの北西の床です、場所はわかっています。ですが……」
ギルバートが彼女の意を汲んで言葉を繋いだ。
「リチャード殿の忠義を無駄にするわけにはいかぬ」
「しかし!」
フィリップは、ウルスラの抗議に微笑む。
「ウルスラ様、我らは……このために、ローレンス様に命を捧げているのです。あの御方のために死ぬことができるのであれば、これ以上誉れ高いことはありません。リチャードが食い止めているうちに、早く」
喧しい爆音が、剣戟が遠くから聞こえてきた。
「彼は、私とギルバート様にローレンス様を託されました。大丈夫です、リチャードが死ぬわけはありません。頑丈だけが取り柄の奴ですから……」
ウルスラも、ギルバートも、ローレンスも彼の真意がわかってしまった。白い騎士の「頼む」との声が乱反射する。彼女は、無言で踵を返して大講堂へと向かい、ローレンスたちは彼女の後に続いた。
Lambency


