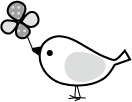ゆうぐれ
五月半ばの水曜日。カレンダーに印をつけたその日が明日に迫り、由布の家では朝から母が忙しく荷物を箱に詰めていた。先週末、保育園も退園し、持ち帰ったお昼寝用の布団やきんちゃく袋の類もみんな箱の中にしまってガムテープで封をした。新しい園が楽しみね、と母は笑った。
段ボール箱をテーブル代わりにしてコンビニのサンドイッチを食べた後、母は「家じゅうに掃除機をかけるから遊んできなさい」と、由布を外に出した。普段遊んでくれる近所の子ども達は皆、保育園や小学校に行っていて遊び相手などいないとわかっていたが、せわしなく準備をすすめる母に声をかけるのはためらわれた。
紺のポロシャツ型のワンピースと、ねだって買ってもらった水玉模様のリボンが巻かれた麦わら帽子をかぶり、由布は家を出た。きれいな遊具がそろった近くの公園が思い浮かんだが、由布はその反対方向に建つ古い市営団地に向かった。一番奥の棟のさらに外れに、小さな公園がある。
アーチ形のうんていとタイヤの列が並び、砂場がその向かいにあるだけの狭い公園には誰もいなかった。一人でもうんていに上ろうか迷った時、砂場の上にかかる藤棚の見事な紫の花に目をとめた。その下にある古ぼけたベンチに、由布は腰かけた。なんとなく、遊ぶ気にはなれなかった。
この服と帽子で、春の遠足に行った日が思い出される。木組みのアスレチックと巨大トランポリン、長い長いジップライン。男の子も女の子もはしゃぎまわり、「小学校に行ってもまた行こうね」そう笑いあった。思い出すほど、ベンチから立ち上がるのが億劫になっていく。
「おい」
とつぜん降ってきた声に上を向く。垂れさがる薄紫と濃い紫の花びらが視界いっぱいに広がった。
「どこ見てんだよ」
今度は前から声が聞こえてそちらを見やる。一瞬目を疑ったが、砂場の向こう側には確かに一人の男の子が立っている。首回りが少し伸びた黒のTシャツに、砂で汚れた運動靴。きかん気そうな強い眼差しが、保育園のいじわるな子に似ていて、由布は少し居心地が悪くなった。
「お前、何でここにいるんだよ」
「今日はお休みなの」
「どうして」
由布はだまった。すると男の子は砂場に入り込んできた。柔らかい黒い砂に靴の足跡が残る。
「砂で遊ばねえの?」
「……」
「じゃあ鬼ごっこしようぜ」
やらない。そう突っぱねようとしたが、男の子はさっさと砂場から出て、アーチ形のうんていの下に走り込むと、あっという間にぶら下がった。
「お前、鬼決め知ってるか?」
「だから、わたしは」
由布はベンチから立ち上がり砂場から主張するが、男の子は意に介さず両足を大きく何度か振り上げて、うんていに足をかけた。そのぶら下がった体勢のまま、片手を自分と由布の間で行ったり来たりさせる。
「ハイ、オーニきーめオーニきーめだーれにしよ。ほらお前だ!」
「わたし?」
保育園でいつもやっている鬼決めとは全然違う上に、リズムも合っていない。
「わたし、鬼なんておかしい!」
砂場のふちに立って声を荒げると、ぶらぶらしていた男の子はにやりとした。
「つかまえりゃいいだろ、歯抜け。その穴から口笛吹けんのか」
ほおが熱くなる。抜けた二本の前歯の跡をこっそりなめ、由布は駆けだした。日差しがさっと顔にあたる。男の子は素早く飛び降り、公園に二人の笑い声が重なって響いた。
「引っ越し?」
聞き返した男の子に、由布はうなずいた。沈みかけている太陽は、家並みのはるか向こうの雲をわずかに紅色に染める。追いかけあった二人の影も、次第に色のトーンを落としてゆく地面にまぎれて見えなくなっていた。
「なんだよ、いなくなっちゃうのかよ。せっかく遊べると思ったのに。おれはもっと遊びたいぞ」
由布に背中を向けて、男の子は空に向けて言い放った。そのTシャツの背中ははしゃいで転げた時の砂の後で白く汚れている。
「しょうがないの。お父さんのお仕事だから」
藤棚を支える柱の一本にもたれかかると、花の甘い匂いがわずかに香る。走り回って荒くなった呼吸が少しずつ落ち着いていく。男の子はちらりときつい眼差しを由布に向ける。
「大人ぶったつもりかよ。暗い顔して座ってたくせに」
「見てたの?」
「いいだろべつに。お前、一人でしょげるくらいなら、わあわあ泣いちまえばいいのに」
細い両腕が空に突き出され、男の子はうんと背伸びをした。
「慣れてる」
由布のつぶやきに、空に伸ばされた腕が若干下がる。由布はそのまま続けた。
「前の時も、その前の時もそうだった。新しいところに行くから。みんなで一緒に行こうって。最初は楽しかったけど、今は……みんなと離れるのがくるしい。私、あと何回、こんなにくるしいことしないといけないんだろう」
冷えた風が吹き、由布は麦わら帽子をおさえる。帽子を買ったホームセンターも、あさってには記憶の中の存在になる。公園の塀際に生える木々が枝を振るわせてざわめいた。
「ここにいたいか」
唐突に聞かれて、いきおいで由布はうなずいた。すると、男の子は振り返った。目に嬉しさやたくらみや、楽しみをめいっぱい詰め込んだ顔。
「そしたらおれのところに来いよ」
暗がりの中、澄んだ声がいっそう響いて聞こえた。
「鬼ごっこだってかくれんぼだって毎日できるし、お前の友達も連れて来たらいい。ずっと一緒にいたらいい」
友達も、歩きなれた道もある、この風景にずっと。男の子の砂っぽい手が由布の前に差し出される。由布は意を決して柱から背中を離した。スニーカーの足が一歩、一歩と前へ進む。あと三歩、二歩、一歩。
その時、音割れしたチャイムが響き渡った。触れ合おうとした手と手が一瞬こわばる。
「どうした、こわくなんかないぞ。お前、ここにいたいんだろ」
男の子は手のひらを広げている。砂に機関車や怪獣を描いた手。砂場の底まで掘り返しそうなトンネルを掘った手。
「……やっぱり、帰りたい」
手を下げた由布は、そういうのがやっとだった。ピンクの運動靴のつま先を見つめる。とても彼の顔を見ることができなかった。が、即座に声が飛んできた。
「バーカ、本気で言ってるわけないだろ。何へこんでるんだよ。……え? おい、なんでだよ。おれ、そんなにひどいこと言ってないだろ」
手で目元をぬぐい、由布はうなずいた。保育園のお別れ会でも出なかった涙が、あとからあとからあふれてくる。
「泣かせるつもりじゃなかったんだけどな」
ま、いいか。男の子は何故だか満足げにつぶやき、両手を半ズボンのポケットに突っ込んだ。そして、そのままうんていの隣に並んでいる、半分埋め込まれたタイヤの列のひとつに飛び乗った。やせっぽちの足が次から次へと身軽にタイヤを飛び移る。
「さよならっていうけどさ、どっかでまた会えるんじゃないか」
「ずっと遠くに行くのよ」
「けど、どっかにいるんだろ」
最後にひときわ高くジャンプして、男の子の両足が砂利を踏みしめた。
「おれ、お前のこと忘れない。だからお前もおれのこと覚えてろ。そしたらきっとまた会える」
「ここで?」
「さあ、どこだか。でも、楽しみにしてるからな」
男の子の視線がふいに上に向けられる。
「おい、見ろよ」
指差されたほうをふり仰ぐと、夜空の高みにひとつぶの光を見つけた。由布は涙を忘れて男の子に笑いかけた。
けれど、そこには半分埋め込まれたタイヤの列があるだけだった。
「ママ、ほらみて。ママの好きなむらさきのお花がある」
子どもたちのはしゃぐ声を聞きながら公園の横を通り過ぎようとした由布は、手をつないだ娘が指差す先の藤棚に目をとめた。あれから何度、引っ越しただろう。あの団地はあの後老朽化で取り壊されて新しくなったと伝え聞いた。
ふと見れば、娘が手を振っている。
「お友達?」
由布が尋ねると娘はうなずいた。
「いつもね、バイバイしてくれるから、わたしもバイバイするの。あの子、ママにもバイバイしてたよ」
まさか。由布は生垣の向こうの公園へ視線を走らせるが、いつもどおり子どもたちが遊んでいるだけだった。それでも確かに、彼はいるのだ。
「ねえママ、あの子、ママのお友達?」
娘の問いに由布は笑顔で頷いた。
「ええ、そうよ」
ゆうぐれ
学生時代みんなで作った文芸誌に載せたお話です。たまたま発見して、アップロード具合を見るためにも掲載します。
私は昔から幽霊とか魂とか、異界に属するものに心惹かれるところがあるのですが、そのイメージとしては当たり前にこの世界と共存している感じです。けれど、両者は異質なもので、世界の行き来は容易ではない。
今の自分が描くものはもっと社会的な題材ばかりなんですが、このお話の感じは今もあまり変わらず作品内に漂ってます。
あと読み返して爆笑したのが、この登場人物がどんなだったかすっかり忘れていたのに、今書いているお話のメインキャラと性格が大分かぶってます。そんな好きなタイプではないんですが・・・深層心理にいるのはこういう性格なんでしょうか。わからないものです。