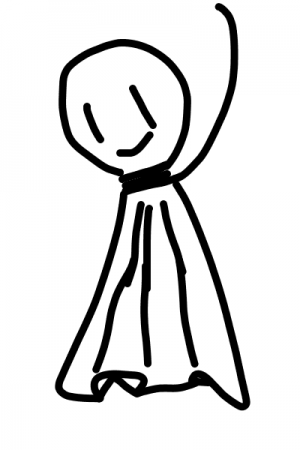お題箱
ピノの与える安堵(お題:ピノ)
唐突だが,人間関係というのはリソースの略奪と奉仕だと思うのだ。
この場合のリソースというのはなんでもいい。例えば金銭、例えば時間、例えば手間。友人に会いに行くにはそのために起床して身だしなみを整えるという手間がかかるし、恋人へのプレゼントには金がかかる。そして何より人は他人といる分だけ、自分のもつ限りある時間の何%かを奪われる。
奪われると書くとあまりにそれが悲劇的なことのように感じられるが要するに人は他者と接するとき、それを快とするも不快とするも、何かしらのリソースを頂戴し献上しているのである、というのが二十数年生きてきた私の現在のところの捉え方なのである。
「かよちゃん、かよちゃん。ほら、あーん。」
なぜそのような抽象的思考が日常生活において顔を出したかというと、すべてはこの、二十数年来の友人の奉仕的行動が原因なのである。
「ん……おいしい。」
「かよちゃん、ピノがおいしいのは当たり前だよぉ。」
ピノというひと箱にわずか六個しか包まれていないその六分の一を私に惜しげもなく与え、それでいながらふんわりと笑っている。ああ、これもまた人間関係において割くリソースのひとつだろう。彼女はピノ一個という実物に加えてピノ一個を食べることによって彼女が得られたはずの快をも私に略奪された、あるいは――己を目的語にして使う言葉ではないが――奉仕したのである。
このピノ一個を媒介にしたリソースのやり取りは周期的に生じる現象だった。私はあるコンビニでバイトをしていて、金銭というリソースを受領する代わりに時間というリソースを提供している。そして彼女はそのコンビニの向いにある和菓子屋で同じく時間を代償に金銭を得ている。そして互いのその時間が一致する瞬間がある。水曜日の午後十時から午後五時である。ここで重要なのはその始点ではなく終点である。共に午後五時に終わる、それは私たちの間で暗黙のうちの合意を生み出したのだった。すなわち、簡潔に言えば「十七時から一緒にあそぼ」。そんな約束を何度も繰り返すうちに、ある一つの習慣ができた。それこそ件のピノである。彼女は終業時間がくるや否や私のレジ打つコンビニに突撃し、ピノをひと箱買う。それとともに私は終業時間を迎える。そうしてあとは……ご覧の通り。毎回彼女はピノを一個、素早い再会を果たした私にくれる。きっかけは忘れたが、習慣となった今それはどうでもいい。
ところでまたも唐突に告白するが、私は彼女が好きである。否、そうではない、あなたは今友情としての好意を想定したことであろう。そうではない。私は恋情としての好意を彼女に寄せているのである。同性ではないかなどと批判、あるいは非難する向きもあろうが、残念ながらすでに持ち合わせてしまった感情を消すことが容易ではないことは多くの悲恋をつづった小説や詩が語ってくれることだろう。
先も言ったがピノというのはひと箱に六個入っている。このようにひと箱に数えられる程度の、他者に分けがたさを感じる菓子というのは他にもある。例えばプチシュー。メーカーにもよるが十個前後がひと包み。例えばガム。棒状に包装されているものだと十数個入っているのだろうか。そして例えば雪見大福。これはひと箱に二つしか入っていない。その中で彼女が選んだピノという選択。これはひょっとしたら私への心理的距離感を表してはいないか。何が言いたいかというと、つまり、彼女にとって私は個数の少ないピノを与えるだけのリソースを割ける相手だが、それは二個しか入っていない雪見大福というリソースを割けるほどの想いではない……。
我ながら拗らせているとは思う。彼女はピノを買うときも私にピノを与えるときもそのようなことは一切考えていないだろう。彼女はただピノが食べたいから、あるいは習慣になってしまったからピノを購入しているだけだ。そして単に礼節やマナーの一環として、あるいは習慣として私に与えているにすぎない。そんなことはわかっている。だがどうやってもやめられない、彼女が私に与えるものがピノであるよう願うことを。それが雪見大福に昇格してしまわないことを。
彼女には彼氏がいる。彼女がどれほどの想いを彼に寄せているかは近くで見てきたのだからよくよくわかる。どれほどつらくとも、彼女の笑顔を思えば二人の幸せを願うことができる。
しかし、しかしもし万が一ピノが雪見大福に変化したとき、まるで私は許しを得たかのように錯覚してしまいそうなのだ。私は二つしかない席のうち一方を彼女が、一方を私が占めるという甘い誘惑にあらがえなくなりそうなのだ。私は水を得た魚のごとく、彼女を彼氏から奪い去り、あるいは彼女から彼氏を取り上げてしまいそうなのだ。そんなことはあってはならない。絶対に。だから私は彼女が私に与えるものがピノであってほしいと願ってしまう。
そうして今週も私はレジで、彼女が持ってくるピノに安堵する。
お題箱