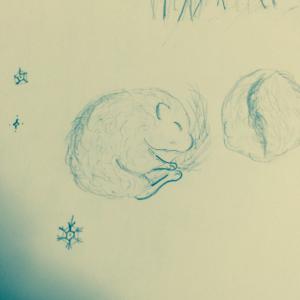モノクローム
ひとりで居るより、ふたりは淋しい。
白昼。カーテンを閉じても溢れる光が、静かな部屋をモノクロームに縁取る。積み上げた洗濯物、たべきれなかった朝食。それらに埋もれてあなたは眠る。
床に座った私はその口元に思わず手を伸ばした。息をしているのか、心配で。そうしながら反対の手でひろった眼鏡をかけ、その貌をみる。すこし髭の伸びかけた、血の気の無い頰に影を落とす長い睫毛が、不器用な手で化粧をする身にはうらやましいくらいに綺麗だった。
微かに震えた唇に安心した。きゅっと、お腹の底が縮んでいたことに気がつく。25にもなってこんなに怖いことが沢山あるなんて思わなかった。自分も、ゆっくり息を吸って、吐いてみる。いい加減に仕事に掛からなければ。肩まで伸びた髪を適当に束ね、パソコンを開いた。ブルーライトが自然光だけだった部屋に眩しい。三件入っていたメール、昨夜作り残した資料。あなたは眠り続ける。
「ねぇ はる。今年はどんな夢を見ているの」
画面越しに声を掛けども返事はない。私も端から待ってはいない。
カーディガンのボタンをいちばん上まで留めた。チャコールグレイのそれを、はるは またモノトーンかって笑ったけれど、目をきゅっと細め、似合うと言ってくれたことを覚えている。
いよいよ寒い十二月、あなたは今日も眠り続ける。春が来るまで眠り続ける。
一緒の暮らしをはじめて四年。私はなるべく家で済ませられる仕事だけを受けている。冬じゅう眠るあなたをひとり、置いていかない為に。
*
「美味しい」
「でしょう。このお店のドーナツは絶対小冬にたべて欲しかったの」
改装したてだという店は白っぽい壁やぴかぴかな床が浮き立って、そこに珈琲とミルクの湯気が甘く匂う。チョコのかかったひとつを持ち上げ、まるで自分がつくったみたいに美陽は胸を張り片目をつむった。彼女のトレイにはまだ苺のと蜂蜜(といっても砂糖をとかした代用品だが)のが載っている。学生の頃よりもさらにふっくりとした顔が、暖房に火照ってひどく紅い。よく動く目と、目が合った。
「ドーナツ屋さんになっているなんて知らなかった。美陽はいつでも美味しいものを見つけるね」
「ふふん、甘い匂いが私を呼ぶのよ。」
「ーそれよかあんたまた痩せたでしょう。どっかの母親じゃないけれど…ちゃんとご飯、たべてるの?」
ご飯、ね。
一応は手の届く食材を工夫して、きちんと魚を捌き、野菜を料理して、お箸もお皿もちゃんと並べる。
「…でも、あまりたべた気はしない」
駄目よそんなに細い首して折れちゃうわー。大げさに両手を振りつつも声には確かに労わりがあり、温かそうなセーターのピンク色は妙に眩しい。居たたまれずに俯いた。
ドーナツはココナッツの。飲みものは温かいミルク。ー向かいで珈琲のめないの?ってはるが笑っていない、食事はどうも味気ない。整った顔立ちにはどこか不釣り合いな 仔犬みたいな笑顔が浮かぶ。ふたりの部屋で ひとりものを咀嚼する音ははるの寝息を搔き消して煩い。
「いつでもうちに、遊びに来てよ。クリスマスにやったみたいにこれでもかってご馳走つくるから」
「…ありがとう。」
零れた声の頼りなさが、嫌だった。
店番の男は少年みたいに痩せて小柄で、だから案外大きな手で硬貨を受け取りながら店主だと名乗られたときにはおどろいた。
「お若いのにお店を切り盛りですか」
思わず年をきいたら同級生で、いくらか気安さをおぼえつい訊いてしまう。
「ああ…。このご時世ですから。店を持つの、夢だったんです。貯金なんてあっても仕方ないでしょう。」
ほんとうですね。深く頷く。この街で、お金なんてなんの役にも立たなくなってしまってから随分経つことを、改めて思い出した。
店の外は、傾いた日に切り出され裸並木が映えていた。風に、はなびらのように白い なにかが舞った。
「…雪、かと思った」
「本当だ。今日はよくとんでくるね」
ひとひら両手で捕まえてみる。指さきで摘むとはらはら崩れる 消しくずのように頼りないそれは、小鳥の羽根でも雪華でも無く。
「西町でも始まったんだってね、“風化” 」
「西町って結構近くじゃん。あーあ、明日は我が身だなあ。この街も壊れていく訳か」
その日までせいぜい呑気に暮らそ。甘いものなんてとびきり贅沢品だけど、たまには良いよね。美陽はマフラーを巻いて息を吐く。長い不安に疲れ果て、諦めた目。
風が運ぶ白い灰は、終わった街の死骸だ。もう、五年ほど前からだろうか。世界は徐々に白い灰に埋め尽くされている。建物が街路が皆、脆く変わってゆくのだ。色が失せ、白い砂糖菓子のように変わり、やがて風が削る灰となる。廃墟。海沿いからじわじわと、街は崩れていった。理由も止める術も見つからないまま、世界はスローモーションで終わりへと向かう。
「はる君の故郷は港のほうだっけ」
「うん。…真っ先に 風化 したところだよ、今は何にも残って無くて、それこそ一面 雪景色みたい」
いなかだけど、新鮮な魚の買える市場があって、そうそう、小冬の気に入りそうなちっちゃい図書館もあって。ひとつひとつ。言葉を選びだして教えてくれたはるの声を思い出す、低いけれどよく通る声を。すこし薄い色の髪や瞳、手のひらとおでこの温度が高いことなんかも思い出す。
リュックひとつでこの街に移って来た彼は時々酷い咳をして、細かな粉塵に肺がやられているのだと言って、
そうして冬には眠ってしまう。いまにも終わる世界に、恋の中に私をひとり残して。
「… きっと海辺の夢を、みているのかもね」
呟くと美陽は、優しく背中を撫でてくれた。そうかもね、って頷いて。
じゃあね、と曲がり角で手を振りあった。今では誰も、またねと言わない。良いお年を、も。だって世界は滅びていく。ぎりぎりの淵で、愛しいひとの居るところへと帰るだけだ。私は足を速める。ふたりの部屋が冷え切るまえに、灯をつけなければならない。
*
鍵をしまって電気をつけて、脱いだコートをハンガーにかける。口紅がおちて乾いた唇を結ぶ。冷たくなった脚に気づいてストーブをつける。闇に落ちた外の景色をカーテンで隠す。
平らな心で考えず流れるように。それらをこなす。
それからようやく、動きを止めて。微かな息遣いに耳を澄ませた。いつもの通り。
はるは寝返りをうったのか、くしゃくしゃの髪に横顔を隠して丸くなっていた。しゃがんで頰に指を触れると、温かくしめっている。柔らかな前髪をかき上げた。
目をひらかない恋人。
「嫌だ、」
呟いたのは無意識だった。
しまった。耳に届く自分の声。
その途端、灯した明かりも温度を上げてゆく暖房も寒色に染まった。冷たい手に呑み込まれていく。伸ばした指を引っ込めしゃがみこんだ。嫌だ、嫌だ、嫌だ。そう、言葉はいつだって毒々しく光って血管を巡り、私をこんなに侵してしまっていた。
「はる、」
手を伸ばそうとする。指が震える。薄くなってしまったその肩に掛けた。温かかった。
目を開けやしないくせに、うっかり涙をこぼさせてくれそうに、温かった。
会えないことなんてちっとも怖く無いんだ。
ここに居るのに返事も聞こえない、それがどれだけ胸を締めるのか?
温かい、温かい、温かいものなんていっぱい持ってる、
…余計寂しい。
「ねえ はる、この街もじき駄目になるよ」
「怖いよ」
「毎日灰が降ってくるよ?」
「ねえ、怖い」
「はるってば、」
溢れ出すと止まらない。叫ぶには絶望は冷たすぎる。
怖い、怖い。じわじわと息をうまく吸えなくなっていく。叫んで泣けたなら。声をひっくり返して、肩を掴んで揺すった。案外重い音で床に当たったその頭の感触にびくりと手を引っ込めた。
ーずっと平気なふりをしていた。来年も再来年も多分ぼちぼち暮らしていける、部屋では恋人が昼寝をしている、そんなふりを。
手に入らない野菜。奇病。やけになって開いては潰れる店。消える故郷。祝えない新年。ひとこと大丈夫って言ってほしいだけなのに、このひとは眠り続ける。
ーそばに居られる時間はもう、僅かなのに。
不意に喉に痛みが走った。むせる、咳をする。頭を細い糸で縛られるような痛みに涙が滲む。物言わぬ胸に顔を伏せたら、頭に響く咳に夏のこの恋人の姿が重なった。ああ、同じだ。はるも、肺を吐き出しそうな咳をしていた。
視界が眩む。
「…ねえ、
はやく目を覚ましてよ、」
息も絶え絶えに、囁いた。
ー夏がくるといい、そう思う。雪雲立ち込める街は要らない、指さきを絡めるだけで安心してしまうひとと共に、世界の終わりをこの部屋で。
こんなにも終わりの気配が怖くて、でも上手く叫ぶことも出来なくて。返事のない体に縋ることしかできない私に、すぐそばにいるのに言葉が無いとつよくなれない私に、
最後の夏をはやくください。
「お願い。」
一生懸命息を吸い込む。吐き出す。落ち着け落ち着くんだ。私が駄目になったら、このまま春になったら、何も知らないこのひとは。鼻からゆっくり息を吸う。さらにゆっくり、吐き出す。
咳が鎮まってくると、自分のより少しゆっくり刻まれる脈に気がついた。触れあったところが確かに、とく、とく、と。
息を吸い込む、長く吐き出す。人肌のつくる湿度の高い空気をあじわった。
ここに、いる。
まだ生きている、と思った。まだ、ふたり此処にいる。じわじわと希望を奪われてゆく部屋の底で目隠しをして、それでも『ふたりで』。
座ったまましずかに、ふたりぶんの呼吸を聴く。
カーテンの隙間に細い、ほそい下弦の月をみつけた。凍ったような、銀色だった。心地よく瞳をひやすそのひかりをみつめる。
体温をとじこめた部屋を渡る嗚咽は、柔らかな震動。
春の霞む月を楽しみだと言った。あなたはたしかにそう言った。
声を思い起こせば、ちゃんと耳元に居る。
…そんな嘘をじぶんにつこうとするには、月があんまりつめたく、ただあかるい。
また、夜が来てしまうのだ。
***
白菜にザクリと包丁を入れ、あかぎれの手で引き裂いた。
幾つかのかたまりに分けた、ずっしりと重いそれをザルに載せてベランダに出る。
小鳥が飛び去った空は、冬の朝に相応しいうす青い色をして広がっていた。鼻の奥につんとつめたい、清潔な匂い。
灰を指で払って、ザルを置き、野菜を並べる。
良いのが出回りにくくなった野菜をみていたら、ひょいと出会えた立派な白菜。ぎゅっと詰まった冬の味を、干して塩漬けにしてガラス瓶に閉じ込めるのだ。
花の香りのそよ風が愛しいひとをゆり起こしたら、しめしめ、と台所から引っ張り出して、ふたり分お皿に載せて、お茶漬けでもたべながら夢の話をして貰うのだ。
髪をさらって行く風は澄んでいる。終末の街は静か。遥か眺めれば、西には白い廃墟が光を受けて輝いていた。幸福な暮らしの記憶を閉じ込めた、砂糖菓子のように。
鼻を啜って部屋に戻った。ヤカンを火にかけ手帳の薄青い表紙をめくる。
やるべきことを数えるのは良いことだ。丁寧に暮らしを刻む音は随分、気を紛れさせてくれる。あなたの居ない時間を集めて、瓶に詰めては春を待つ。
今日は年の瀬、日曜日らしい。せつないほどに真っ直ぐな、日の帯が白く部屋に差す。
すくなくとも今日は終わらない、世界の隅で寝息を聴いている。
モノクローム
何気ない日々を描きたくて、だけどそれは余りにむずかしかった。
多鍵 様(https://t.co/J69eXBocMx)、由末イリ 様(http://slib.net/81260) に、世界を広げて頂きました。壊れた街に生きるひと、壊れる世界に抗うひと。こちらも是非。