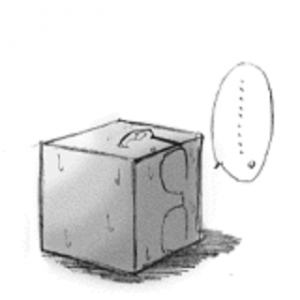1 2 2 4
すべての孤独な「私」へ──
映画を観ようと思い立った。
灰色の雲が空を覆う、冬の午後。ひと月ほど前には鮮やかな黄色い葉を全身にまとっていた街頭のイチョウの木からはすっかり葉が落ち、今は裸の枝が曇り空を鋭く突き刺している。
枯れ葉が舞う舗道を、私は一人で歩いていた。
妻は、友だちとランチしてくるから、と私に言い置いて昼前に出かけ、私はそこからの時間をすっかり持て余していた。
こどものない私たち夫婦は、共に過ごす時間と独りになる時間、それぞれをうまく使い分けなければならなかった。妻は外に出ることで時間を巧みに切り替えているようだが、私はいまひとつ、ひとりの時間を過ごすコツを身につけることができずにいた。
一人で映画を観る。何年ぶりになるだろうか。
妻とつきあうようになってからは何度も共にスクリーンを眺めたが、いつしかそんなこともなくなっていた。結婚してから二十年近く、一緒に暮らしてはいるが、私は妻とは違う方向を見ているのかもしれない。
午後の街は、人の流れも閑散として、ひどく静かだった。
昔は多くの人でにぎわったこの通りも、今は店もまばらで、シャッターが閉まったままの建物やコインパーキングが目立つ。
映画館は、かつての繁華街の真ん中にある。こんな寂れた街で今でも営業しているのは、ほとんど奇跡だとも言えた。
少年の頃活劇に心躍らせ、青年となってからは純愛に胸ときめかせたこの場所も、この街と同じように、今は静寂に沈んでいる。
特に観たい作品があるわけでもなかった。ただ、何かに出会ってみたかったのかもしれない。
映画館の古い建物の階段を上ると、額装されイーゼルに掛けられたポスターが私を出迎えた。誰もいない薄暗いホールでスポットライトを浴び、ぽつんと佇んでいる。
全面灰色で、中央に横書きでゴシック体の「1224」の白抜き文字。
他に何もない。
私はそのポスターをまじまじと見つめた。
配役も、監督をはじめとするスタッフの名も、そして配給会社の名すら記載されていない。
イチ、ニ、ニイ、ヨン。
あるいは、千二百二十四、か。
何の意味があるのかわからない。惹句もなければ劇中のスチールもないから、どんな映画なのか、まったく不明だ。他にかかっている作品はないようだった。
五分後に上映開始ですよ、と窓口の奥から年配の女性の声がした。落ち着いた、やわらかなその声に誘われるように、私はチケットを買った。
厚い扉をくぐって中に入る。まだ照明は落ちておらず、赤いシートがずらりと並んでいる。私の他に客は数人、みな一人で、思い思いの場所にまばらに座っている。
私もスクリーン正面付近を選んで座った。何か飲み物でも買っておけばよかったかと思ったが、比較的新しいシートに身を預けると、それもどうでもよくなった。
ほどなくしてブザーの音とともにすっと灯りが落ち、近日上映の予告編もなしに、上映は始まった。
スクリーンがぼんやりと白く光る。
続いて、どこかの地方都市の遠景が映し出された。今日と同じような重苦しい曇天のもと、ゆっくりと左から右へパンしていく。この街のように、かつてはにぎわい、今は寂れたちいさな街。まばらに建つマンションの下に、雑多な建物が身を寄せ合うように並び、ところどころに更地がのぞく。街路樹に葉がないから、季節は冬らしかった。
遠くから微かにピアノの音色が聞こえる。
悲しげな旋律。
ああ、どこかで聞いたことがあるような気がする。何の曲だったろう。思い出せない。
物語は、取調室の場面から始まった。
老境の男が、二人の若い刑事から取り調べを受けている。会話が微かに途切れながら聞こえるだけだから、どんな事件なのかはさっぱりわからない。老人はパイプ椅子の上で小さくなっている。手錠を嵌められた両腕を膝の間に落とし、背中を丸めた姿は、容疑者と呼ぶにはあまりに精彩を欠いている。若い二人の刑事は、書類に目を落としたまま老人には目もくれず、退屈そうに取り調べを続けている。老人も目を伏せたまま、時折言葉にならない言葉をぽつりぽつりと吐く。
カメラがゆっくりとズームアウトすると、その様子を眺めているスーツ姿の中年男がフレームインした。先ほどの映像がマジックミラー越しのものだったことがわかる。右の掌を向こうからは見えない窓につけ、小さな老人をじっと見つめている。
彼は、二人の若い刑事の上司だろうか。四十代なかばくらい、ごく平凡な顔。見たことのない役者だ。
やがて、彼は一人部屋を出た。
ぼんやりと廊下の白い天井を見上げ、彼はゆっくりと息を吐いた。白髪交じりの頭。目尻の皴。その横顔には、深い疲れの色が浮かんでいた。
彼は着古したトレンチコートを羽織ると、警察署から出た。空はやはり厚い雲に覆われていた。
ふと、彼は視線を感じて伏せていた顔を上げた。
ひとりの少女が、彼をまっすぐに見つめていた。濃い灰色のダッフルコートにマフラー、コートの裾から制服のプリーツスカートが見えている。黒のタイツにローファー、左手に革鞄を提げた高校生。セミロングの髪が、冷たい風に靡いていた。
彼と目が合うと、彼女はマフラーを右手でちょっと下げてから軽く会釈をした。
瞬間、彼は彼女が誰だったかを思い出した。
──黄色と黒のテープが揺れている。「立入禁止/KEEP OUT」の文字が何度も裏返る。警察による規制線。救急車と警察車両の赤色灯が物々しい光を繰り返し周囲に投げていた。
まだ若い彼が、白手袋を着けながら規制線をくぐる。
その奥に、白い瀟洒な二階建ての家屋。そこから担架で運び出される、シートで覆われた二つの遺体。それを彼は目だけで見送った。
その視線の先に、ランドセルを背負ったまま茫然と立ち尽くす少女がいた。ざわめく規制線の外側で、そこだけ時間が静止していた。
彼の目が止まる。
何が起きたのかわからず、困惑した顔の、まだ幼い少女。
その顔が、眼前の高校生となった少女と重なる。
彼女は今も、何か困惑したような顔で、彼を見つめていた。
幾年かの時を隔てて、彼は彼女と再会した。
彼女に何か声を掛けようとして、しかし彼は言葉を失った。彼が伝えるべきことなど、何もなかったからだ。彼はかつて捜査官としてその事件を担当し、犯人を捕らえてしかるべき法の裁きを受けさせた。ただそれだけのことだった。
彼女も、それをよくわかっているようだった。
話がしたい、と彼女は彼に伝えた。
彼は黙って頷いた。
彼は街角の古い喫茶店に彼女を招いた。コーヒーミルを模った看板、ショウウインドウにはサイフォンやコーヒーミル、背の高いケトルなどがディスプレイされている。
店は落ち着いた色合いで統一されていた。木製の格子で飾られた壁から、傘のついた洋燈がやわらかな光を落としている。低い天井には重厚な木の梁が渡され、組硝子があしらわれていた。
静かなピアノ曲が流れている。
狭い店の中に、他に客の姿はなかった。
赤い革張りのしっかりした椅子が並び、大理石が嵌められた木製のテーブルの縁は、ニスが剥がれかけていた。
彼は、ジャケットの内ポケットから煙草を取り出しかけてやめた。
彼女は何も言わず、俯き加減に座っている。
少し気詰まりになって、テーブルの隅に目をやる。グラニュー糖・ザラメ糖がそれぞれ入った硝子の砂糖壷が二つ並んでいる。
ブレンドを二つ注文すると、マスターは慣れた手つきでミルを回し、二本のサイフォンに粉を入れた。
見るともなしに、マスターがコーヒーを淹れる様子を目で追う。
湯を注いでそれぞれバーナーに掛けると、沸騰した湯はたちまちサイフォンを駆け上り、粉と混ざり合う。少し間をおいて軽く撹拌し、バーナーから降ろすと、布のフィルタで濾過されたコーヒーがゆっくりと降りていく。狭い店内に、甘い香りが満ちた。
マスターは無駄のない動きで二杯のコーヒーをそれぞれカップに入れると、白い小さなミルクポットと共にテーブルの上へそっと置き、カウンターの中へ戻った。
ブラックで口に含むと、豊かな香りが口の中に広がり、ほのかな苦みとやわらかな酸味を残しながら喉を下る。
彼女は少し遠慮がちにミルクと砂糖を入れた。音を立てないように、ゆっくりとかき混ぜる。
自分から話がしたいと告げておきながら、彼女が何かを話し始める様子はなかった。
尋ねたいことはいくらでもあった。あのあと今までどのように過ごしてきたのか。これからどうするつもりなのか。なぜ急に会いに来たのか。いったい、何を話したいというのか。
昔なら苛立っていたかもしれない。しかし俺が過ごしてきたこれまでの歳月は、待つことの大切さを俺に告げていた。
彼女は両手でカップを戴いてゆっくりとコーヒーを含むと、小さく息を吐いた。カップを静かに置き、右手で髪を軽くかき上げると、ふっと笑みをこぼす。
その笑みが、諦めを含んでいることに、俺は気づいてしまった。
ピアノ曲が続いている。悲しげな旋律。何の曲だったろう。思い出せない。
カウンターの中でマスターが静かに器具を洗っている。
彼女は黙ってテーブルの隅の砂糖壷を見つめている。その顔を見ていると、強いて問うことはためらわれた。
もしも俺に娘がいたなら、このぐらいの年頃だろうか。だとしたら、どんな子に育っただろうか。
あり得ない夢想が、脳裏を巡る。
俺が知らない彼女の過ごした歳月を、目の前の彼女から窺い知ることはできなかった。
時折、通りを行き交う人の影が窓の間に音もなくよぎる。
いつの間にか、コーヒーは冷めてしまっていた。
古風な柱時計が時を告げる。冬の短い陽が落ちて、窓の外はすっかり暗くなっていた。
彼女は結局、俺に何も話そうとはしなかった。
俺は彼女に連絡先を渡し、何か話したくなったら改めて連絡するよう伝え、帰るように促した。
彼女は時間を割いたことを申し訳なさそうに詫び、俺に礼を言った。
店の外へ出ると、頬に吹きつける風が冷たかった。気をつけて、と声をかけると、彼女はハイと返事をして小さく頭を下げた。
ここで別れる。彼女は右へ、俺は左へ。
俺は数歩歩いてから、何気なく振り返った。
彼女も振り返っていて、俺と目が合う。
俺はコートのポケットに両手を突っ込んだまま、彼女に苦い笑いを送った。
彼女はまた、小さく頭を下げた。
そんなことがあってから数日。
俺は忙しさに紛れて、彼女と会ったことも忘れかけていた。
夜、事務室に一人残って書類を整理していると、突然携帯電話が鳴った。
公衆電話からの着信。
彼女からだった。
突然の電話を詫びつつ、話をしても大丈夫ですか、と彼女は尋ねた。
事務室には他に誰もいない。
俺が大丈夫だ、と答えると、彼女はほっとしたような声で、よかった、とつぶやいた。
先日の非礼を詫びつつ、彼女はいまの暮らしについて訥々と話しはじめた。
引き取ってくれた親戚夫妻が実子のように接してくれること。多くの友人が支えてくれていること。よい教師に巡りあえたこと。
彼女の語る日常は、ごくありふれたものだった。妻も子もない俺には、どこか遠い世界の話のようでもある。
しかし俺は、彼女の声の奥に漠然と暗い響きを感じていた。
周囲の後押しで進学もできることになり、今は来月のセンター試験に向けて勉強しています、と彼女は語った。
そうか、それはよかった、と俺は自分の感じた不安を打ち消すように彼女に返した。
急に、電話の向こうで彼女が黙った。
どうした、と尋ねても答えはない。
しばらく沈黙が続く。次第に胸がざわめく。
『────』
すっと息を吸う音がして、彼女が何か言った。
俺はその言葉を聴き取れず、思わず聞き返した。
しかし、電話はそこで切れてしまった。
携帯電話から不通音だけが返ってくる。
胸騒ぎが、確たる恐れに変わった。
俺は立ち上がると、コートを掴んで外へ出た。
あてもないのに、夜の街を走る。
探さなければ。
早く見つけなければ。何かが起こる前に。
どこにいる。
息が上がる。汗が噴き出す。
どこだ。
吐く息が白くなって流れる。
通りを行き交う人が俺を振り返っては通り過ぎていく。
見つからない。
どこだ!
どこにいる……!
──ドアを開けると、部屋からは血の匂いがした。悲しげな旋律のピアノ曲が、微かに聞こえてくる。
彼女はソファに横たわっていた。眠っているような、白い顔。
それ以上、彼女の姿を見ることができなかった。
その後、何がどうなったのか、よく覚えていない。外に出たときには、既に深夜になっていた。
疲れ切って、体がひどく重かった。人通りの絶えた舗道を、よろよろと歩く。
街角のあちらこちらでイルミネーションが瞬いていた。
ああそうか、今夜は降誕祭か。なぜ今まで気づかなかったのだろう。
彼女の部屋に流れていたピアノ曲のもの悲しい旋律が脳裏に浮かぶ。
ああ、何の曲だったろう。思い出せない。
空気が澄みきっていた。イルミネーションのまばゆい光が眼を刺す。
不意に、それが滲んだ。
空を仰ぐ。
低い雲が街灯りを映して明るい空に、星は見えなかった。
涙が、頬を伝っていく。
吐いた息は白く凍り、次の瞬間には消えていった。
彼女は、最後の言葉を託す相手に、私を選んだ。
誰も、彼女が死んだ理由を知らない。
彼女は、私に何を伝えようとしたのか。
なぜ私は、それを聞き逃してしまったのか。
私は自分の両の掌を見つめ、それから強く握りしめた。
彼女を殺したのは、私だ。
奥歯を強く噛みしめる。握った両の拳が震えた。涙がとめどなく溢れ、いくら止めようとしても繰り返し嗚咽が漏れる。
もう決して、取り返しはつかない。
彼女は、私に何を伝えようとしたのか。
私はこれからの生涯で、その答えを探し続けることになるだろう。たった一人で、誰の助けも借りずに。
見つかることなど、永遠にないと知りながら。
了
1 2 2 4
この作品は、一九九五年一二月二四日に筆者が見た夢に、多少の脚色を加えたものです。