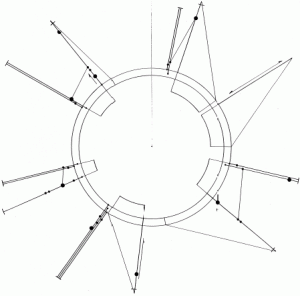無機質な部屋(2)
今まで何度となく想像した将来、幸せ、夢。
今までいくつもの岐路と出会った。何を選ぶのが正解なのか、誰を信じればいいのか。
答えがない事は分かっていた、分かっていてもつい考えてしまう。
私はいつの間にか敷かれたレールを見失っていた。
いや、見失うと言うよりも逃げ出したかったのかもしれない。
何が正しいと言うか、何を選んだ方がいいのか、何をしたほうがいいのかそれはきっと分かっていた。
分かっていても選びたくなかった。
私は他人とは違うのだと、所謂社会人なんてものにはなれないのだと。
やりたい事ばかりを追い求めて現実的なものからただただ逃げていた。
現に今もそうだ。自分の判断に対しての同意や後押しをしてくれる人を待っているだけ。
「啓ちゃん。」
こんな時に鳴らない携帯が憎くて憎くてしょうがない。
私の心に水を注いでほしい。枯れてしまいそうだ。涙もでない。もう、呆れて笑ってしまう。
「なんで泣きそうな顔してるの?」
私が絵が好きだと言うと啓ちゃんは興味津々に見せてと言ってきた。
その時期描いていたものをスケッチブックごと渡して見せた事があった。基本的には人の絵を描くことが多い。
誰を描いたのかと問われるが、間に静物デッサンなどの絵が挟まっていたからそう思ったのだろう。
「誰でもないよ」
「へぇ、凄いね。想像してこんなに描けるんだ」
「うーん、でも周りの子もそのくらいは描けちゃうからね」
「でも俺には描けないよ」
「だろうね」
少しふて腐れながら、でも楽しそうに絵を見ては感想を話してくれた。
「なんで泣きそうな顔してるの?」
「え?」
一瞬何の事かと思ったけれどどうやら絵の話のようだ。確かに笑顔の絵はひとつも無い。
特にこれといった理由はないけれど、その時は私の絵がどうというよりそう聞いてきた彼が好きだった。
彼にとっては素朴な疑問で、その素朴さがとても綺麗だと思った。眩しいとは違う、見つめていたい優しい灯りのように感じた。
「本当に綺麗なものは残さなくてもいいと思うから」
「でも、この絵も綺麗だよ」
「そういう事じゃなくて、楽しい事や嬉しい事はその瞬間で感じるもので、絵の中に閉じ込めちゃったら勿体無いよ」
「薫っぽいね」
普段無愛想な私が自分でも分かるくらい動揺しながら話していたのが面白かったのだろう。
少し茶化すように、それでもなんとなく分かるよといったように微笑んでくれた。
何か負けた気がしたけれどそれが心地よくもあった。
無機質な部屋(2)