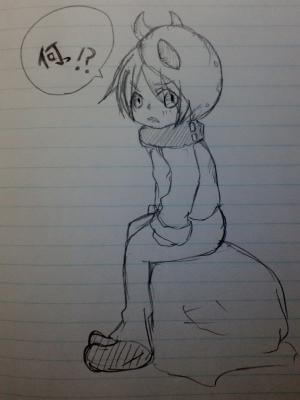いぬかぶり 第9話
佐藤君の話、第9話になります。
いま、このようにアップ作業をしている最中も外はものすごく暑いです。
こんな中で、スポーツなんて自殺行為じゃないかしら…なんて考えつつ、自分の腕を見てみると…。
明らかに日焼けして真っ黒になった自分の腕があるんですよ。
要するになにが言いたいのかって言うと、夏は苦手だなということです。
一切論理性のかけらもない話はここら辺で切り上げます。
失礼いたしました。
第9話を楽しんでくださることを期待しています。
それでは。
「おはようございます!」
勢いよくRosaの扉を開ける佐藤。
「お!」
「あら。」
朝9時半という、開店直後の店だけあって店内には多田とお母さんだけがいた。
店の中にはコーヒーのいい香りが漂っている。
「おかあさん、モーニングセットをお願いします。」
「はいはい。」
カウンターの端でお母さんが準備を始める。佐藤はカウンターに腰掛ける。
何気なくカウンターの向こうの椅子に目をやる。この間、杏が座っていた椅子。無意識のうちに彼女が座っていた椅子の方に目をやる自分がなんだか恥ずかしくなった。
「佐藤君今日は、杏さんは夕方から来るかしらね。」
お母さんの言葉に少し顔が赤くなるのに気づく佐藤。お母さんは、人の感情が手に取るように分かるらしい。
なんだか恐ろしい存在である。顔が赤いのを隠すために下を見ていると、ものすごい勢いで黒い何かが足元に突っ込んでくるのが見える。
「多田…さん?」
佐藤は目を丸くする。突っ込んできたのは多田であった。足元で多田はゆっくりと立ちあがる。いつもと同じように黒っぽい服に黒い眼鏡に黒髪。真っ黒な人だ。
「佐藤君、ずっと僕は君のことを待っていたのだよ。」
「言い方を考えてくださいよ、多田さん。恋人に会いたくて仕方がなかったように聞こえます。」
「待っていたのは本当のことだ。昨日君にしたい話があったのに、君は昨日店に顔を出さなかったじゃないか。」
「話って?」
「再就職先の話だよ。君のための話じゃないか。」
「え!?あの話ですか。」
そっとお母さんが佐藤の手元にモーニングセットを差し出す。ホットサンドにフライドポテト、サラダにオレンジ100パーセントのジュース。
佐藤はすぐにホットサンドにかじりつく。
「佐藤くんさぁ、話を聞く気あるのかい?」
佐藤は口にホットサンドを咥えたまま頷く。ハムとチーズが挟んであるシンプルなものだが、中でチーズが溶けている。
多田は、ポケットから紙切れを取り出す。そこには、見慣れない会社の名前とアドレス、所在地などが書いてあった。
「多田さん、これは?」
「この間言っていた会社のアドレスとか、もろもろ。アドレスが二つ書いてあるだろ。それ、一つ目が公式の会社のアドレスだ。もう一つは、そこの社長のアドレスだ。そこの社長とは長い付き合いだからな、特別に教えておくことが許されたのさ。」
多田は得意げに体を揺らす…踊っているらしい。(つくづく、この人は良くわからない人だと思う…。)佐藤は少し不思議な顔をする。
「いいか、佐藤君。すぐに連絡するといい。私からは社長に連絡をとってある。たぶん、社長も君からの連絡を待っているところだ。うん。で、さっきの紙に会社の地図も載せてある。必要になったらそれを使うとよい。」
ゆらゆら揺れながら、リズムに乗って言う多田。最後の「よい」の部分でさっと指を向ける。そして、ドヤ顔。
「お母さん、僕はこの人を信じていいのでしょうか。」
オレンジジュースに手を伸ばしながら、佐藤はカウンターの向こうにいるお母さんに心配そうに尋ねる。お母さんは首を傾げながら答える。
「うん。まあ、ね。普段からやっていることは異常…というか、妙で、理解に苦しむ部分もいっぱいあるけど、彼の身の回りの人間は割と信じてもいいかもね。彼があんな感じでしょ?しっかりした人が心配になって彼の周りに来ると思うのよね…。」
「なるほど…。」
佐藤は妙に納得した。さっきのお母さんの理論は根拠があるものとは言い難いものなのだが。
お母さんは客の注文の声に反応してカウンターから出てゆく。多田は依然として佐藤の近くにいたまま。
「おい、佐藤君。さっきの話だが、今日の午後にでも連絡することをお勧めするよ。」
「今日の…午後ですか!?」
「ああ。社長ができる限り君に早く会いたいと言っていたんだよ。熱烈なラブコールだろ。」
多田が手でハートマークを作っていたことは無視することにする。
「ここか…。芸能事務所、カロームって。」
佐藤はカロームの本社の入っているビルの目の前に立つ。多田のアドバイスを聞き入れて、お昼までいつもの店にいた後に、スーツに着替えてやってきた。ビルを見ると、カロームはビルの6階に入っているようだ。
「すみません…。あの、多田さんに言われてきたんですが。」
佐藤はカロームの受付に立つ。
「多田さん?」
受付の女性は頭の上に何個も?マークをのせて、佐藤を見る。
「どうした?」
フロアの方から、男が一人出てくる。以前、犬飼の時にも関わったスカウト担当のスタッフだ。このスタッフは犬飼の件があってから、会社に滞在する時間を長くしている。長くした成果は今のところ何もない。最近は会社内で、外で人探しして来いよ、という評価が出てきている。
「あのう、この人が多田って言う人に言われてきたと言っているんです。」
受付の女性は困った顔をしてスタッフに言う。
「君は?」
スタッフは佐藤に話しかける。
「佐藤晴彦と申します。ここで仕事の話を聞きたくて来ました。」
「どうゆうことだ?」
スタッフは佐藤に近づく。
「ちょっと、何しているのかね?」
後ろから、若い男が出てくる。社長だ。
「君が佐藤君かね?多田君から話は聞いているよ。ちょうど、さっき多田君から『佐藤君が君の事務所にやってくるから出迎えてあげて』って連絡が来たんだ。ほう、君が佐藤君か。確かに、多田君が言っていたように優しそうな男だ。」
社長は佐藤の後ろに回って肩を優しくたたく。
「君たちは自分の仕事に戻ろうか。この人は私が呼んだ人だからね。」
そういって、社長は付いて来るように促す。スタッフたちは呆然とした表情をしつつも、社長の指示に従った。
「佐藤君、上手くやるかね?」
お母さんは多田に話しかける。
「さあ。僕の知ったことじゃないよ。彼の力だからね、これからは。」
パソコンに出ているウィンドウにはグラフが出ているが、急な変化がそこには出ていた。その様子を見て、多田は作業を勢いよくする。
「何か変化あったか?」
後ろから高波が覗き込んでいる。多田は微妙な顔をする。高波は、佐藤が店を出て行った後にやってきた。この日は、酒井もいる。高波と一緒に来たのだ。
酒井の体には、以前Rosaに来た時にはなかった傷が何個かできていた。高波は多田のもとから、酒井のいるカウンターの方へ行く。
「酒井さん、体大丈夫?」
お母さん心配そうに酒井を見る。腕に何個か大きな傷ができていた。
「ああ、大丈夫ですよ。ちょっとこの間の人のタチが悪かった。うん。後ろに行くまでは良かったんだ。だけどな、あいつ気づきやがってよ~、ちょっと切られた。腹立ったね。」
少し顔を曇らせながら酒井は話す。
「まあ、やるべき仕事はやったんだし、何も落ち込むことはないぜ。」
高波が酒井の背中に手を回す。少し溜息をつく酒井。
「高波さん、かっこいいな…。俺にも手を回してくれないかな…。」
多田が少し離れたところにいる高波を酒井の方を見る。
「黙ろうか。女性との関係に飢えているのかな、あいつ。もしくは、男が好きとかそんなかんじのパターンか?」
「うるさい。男が好きはありえない。」
いぬかぶり 第9話
久々に高校の友だちにあってきました。
何も変わっていない友だちたちに安心しました。
自分も、何も変わっていないと思い、友達に「何も変わってないよね?」と聞いたところ
「いや、女の子になってる。女子力上がってる。」
との返事。
つまり…高校の時の自分はひどかった…と。
昔の自分を振り返って苦笑いしてました。
女子高時代ですもの。
自由にいきますよ。
スカートが濡れたからって、扇風機にかぶせて乾かしたりしますよ。
スカートをかぶった扇風機の首を振らせたりしますよ。
何なら、テープで顔を書いちゃったりしますよ。
全部してましたよ。
という、ノスタルジーに浸りながら、失礼しようと思います。
ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。
感謝しています。
また、お目にかかれることを願って。