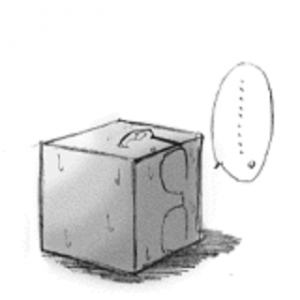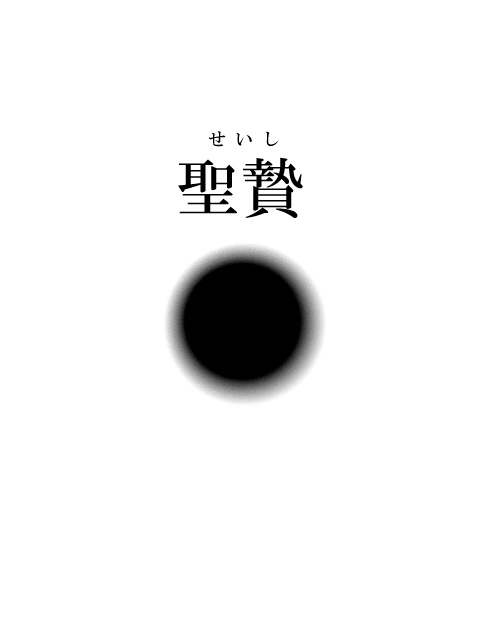
聖贄(せいし)
この作品には残酷な表現を含むため、十五歳未満の読者並びに強い暴力表現を苦手とする読者の閲覧を禁じる。
不波 流 拝
太陽がまもなく南中する。
石の祭壇の上は遮るものなどなく、熱せられた空気が躰の周りを立ち上っていく。
彼は両手両足を縛られ、二人の神官に脇から押さえられ、汗をぬぐうこともできず石の床に膝を突いていた。上半身の衣服を取られ、無駄のない筋肉が容赦ない直射日光の下に晒されている。彼の古傷だらけの浅黒い肌は、容赦なく照りつける日光を弾いていた。
群衆のざわめきが遥か下から聞こえてくる。その喚声……いや、騒音は気温と同様、時とともに熱気を帯びてきていた。
神官の一人が、太陽神に対する最大限の賛辞と感謝を述べている。
彼は苦々しい気持ちでそれを聞いていた。
彼は戦士であった。先ごろ戦争があり、彼は武運拙く虜囚となった。その事実は歴戦の勇士としての彼の自尊心を、大きく傷つけた。
戦場で死ぬならまだしも、こんな辱めを受けるとは。
彼は詮無いことと知りつつも、既に何度も繰り返した嘆きをまた思うた。
神官は白い衣服に極彩色の大きな仮面を着け、雲一つない天を仰いでいる。衣服に縫い付けられた宝石が、動く度にぎらぎらと光を返し、彼の眼を射た。
両脇の神官はじっと無言で仮面の奥から彼を見下ろしている。
戦士である以上、死は彼の一部であった。
俺は多くの兵を勇敢に殺した。自分の死を恐れたことなどなかった。
その俺が。
顎から落ちた汗のしずくが石畳に落ち、小さな染みを作る。それも乾いた熱風がたちどころに消す。
神官が祭詞を述べ終えた。
群衆の喚声が彼の耳を刺す。
彼は二人の神官によって両腕を引き上げられて無理矢理に立たされた。一瞬、蒼天の中央で凶暴に白く輝く太陽が目に入る。
後ろ髪を引っ張られて、彼は顔を上げさせられた。
目の前に祭詞を述べていた神官が立っている。太陽の黒い残像が仮面を着けた神官の顔に重なる。
神官の手には赤茶けた石の刃が握られている。
突如、彼は戦慄き始めた。
馬鹿な、怯えているのか、と彼は己を叱咤したが、震えはますます大きくなる。
虜囚となったときから、こうなることはわかっていたはずだった。彼はこれまでずっと怯懦を忌んできたから、戦士らしく堂々とその場に臨むつもりでいた。
ところが今や、彼は自分の躰を律することができなくなっていた。
噛みしめた奥歯ががちがちと音を立てる。
両脇の神官が彼を押さえる力を強めた。
正面の神官が彼の顎を押さえて上を向かせた。再び白い太陽が目に入り、彼は目を閉じた。
震えが止まらない。両脇で神官が押さえていなければその場に崩れ落ちていただろう。
次の瞬間、彼は胸に激痛を覚えて絶叫を上げた。
鳩尾から、腹へ。
刃がゆっくりと彼の肌を切り裂き、彼はもがきながら絶叫し続けた。その声に呼応して群衆の喚声がひときわ大きくなった。
ぼたり、ぼたりと血が石の床に滴り落ちる音がする。
痛みから逃れようと必死になって足掻くが、両脇の神官は暴れようとする彼を力の限り押さえつける。戦士だった彼の力でも、束縛を振りほどくことはできない。
彼の顔は涙と洟と涎でぐちゃぐちゃになっている。足に力が入らない。
顎を押さえていた手が外れ、再び目の前の神官の姿が彼の視界に入る。股間が勃起している。
仮面の奥の眼が、ぎらりと光ったように感じた。
神官は肌を裂いた彼の胸に右手を差し入れた。
彼は声を枯らさんばかりに絶叫する。
右手が拍動する心臓を掴む。次いで、そのまま乱暴に右手を引き抜いた。
ぶちぶちと血管がちぎれる音がした。彼の断末魔の叫び声が四囲に響き、群衆の喚声がそれに重なった。
彼の返り血が、神官の白い装束を汚す。宝石がぎらぎらと光る。
暗くなりつつある視界の中に、彼は自分の心臓を見た。鮮血を噴きながら拍動する彼の心臓。
神官が彼の心臓を両手に戴くと高々と太陽にかざし、雄々しい叫び声を上げた。
群衆がそれに応え、禍々しい喚声が都市に満ちた。
それが、彼が聞いた最後の音だった。
彼の心臓の拍動は徐々に弱くなり、神官の掌の中で遂に動かなくなった。
彼は、神の食物となった──
「何を騒いでいる!」
鉄格子の向こうから響いた鋭い声で、彼は跳ね起きた。
凶暴な太陽の下ではなく、いつもの薄暗いコンクリートの部屋。
荒い呼吸の中で、彼は自分がまだ生きていることを確かめ、そして密かに安堵した。
「またお前か。寝ているときぐらい静かにしろ」
鉄格子の向こうの声が、冷たく言い放った。
鼓動が早い。
「あの、今は何時ですか」
彼は鉄格子の向こうに尋ねた。
「午前三時二十二分。すぐに就寝しろ」
看守は短く言うと靴音を鳴らして廊下を去っていく。
彼は小さな窓の向こうを見た。四角く区切られた深い闇が覗いている。
自分の掌を見つめる。運動の時間以外は外に出ることのない彼の白い掌が、薄暗い中にぼんやりと浮かんでいる。
彼は再び横になった。
ここに来てどのくらいの時間が過ぎたのか、彼には確かな感覚がなかった。つい一昨日のことのようであり、遥か昔のことのようでもあり。時間というものが意味を失ってから随分と経っていた。
確かなのは、ここは「待機」のための場所であり、彼がいるこの建物のどこかに彼を吊るすための部屋があり、そのための装置が設えられているはずだということだった。
彼の部屋は狭かったが清潔で、それなりに快適ではあった。
彼は知っていた。
自分がいつか殺されるために生かされていることを。
ああ、それにしても嫌な夢を見たものだ、と彼は思った。単に見たのではなく、全身が粟立つような恐怖が今も肌に残っている。
彼は狭い寝床で寝返りを打った。
その日を迎えたとき、俺は立っていられるだろうか。
幾たびも繰り返した問いを、彼は思った。
それは今日かもしれない。
目をつぶると、自分の心臓の鼓動が強く感じられた。どこからか、他の収監者のいびきが聞こえてくる。
俺は生きている。いつまでかはわからないが。
狭く四角い部屋の隅で、彼はゆっくりと息を吸った。
聖贄(せいし)