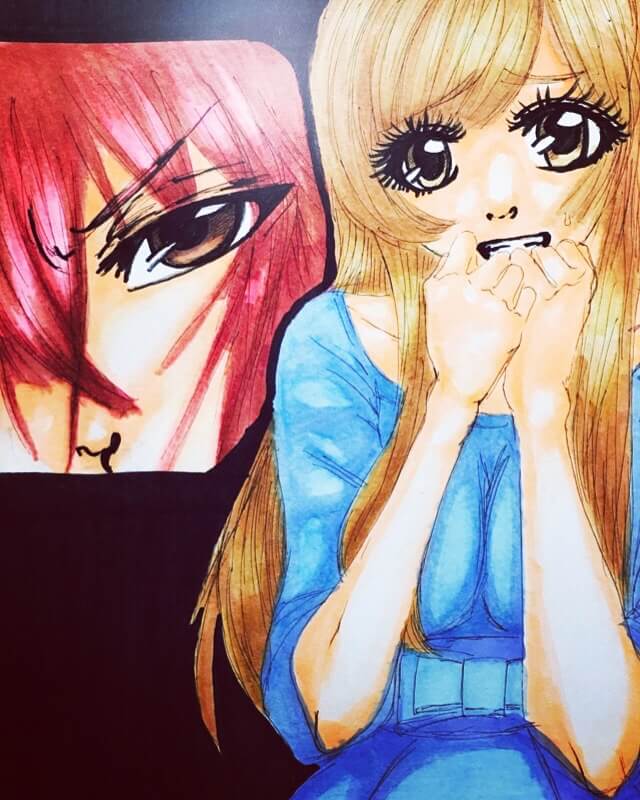
リラの花が咲く頃に 第5話
小説家になろうにて連載中の「リラの花が咲く頃に」第5話です。
駄文、乱文失礼いたします。
第5話 「大切な人を傷つけない為に大切なことは」
ーーピーンポーン
先生にお叱りを受けていると燕家のインターホンが鳴った。
「まさか…」
佳奈子は自分を犯そうとしてきたので大事なところを蹴り飛ばしてそのまま公園に取り残してきてしまった諒なのではないかと思った。途端にまた怖くなる。
「…怖いよ、先生どうしよう」
「覗き穴でまず確認して諒だったら俺が出てあげる。諒じゃないかもしれないよ?」
「そうだね、わかった。見てくる」
佳奈子は勇気を出して覗き穴を恐る恐る見る。ドアに触れる指がわずかに震えた。
「佳奈子、私れなだよ大丈夫?」
覗き穴を見る前に長年親友で互いに心を許し合って付き合ってきたれなの少し低音の優しい声がしたので急いで鍵を開けた。
「れな!」
開けると同時に勢いよくれなに抱きついた。
それをれなは優しく、包み込むように佳奈子を抱きしめる。
「怖かったしょ?!実害ない?!」
「‘‘実害”って?」
佳奈子は実害の意味がわからずポカーンとしている。その様子にれなは恥ずかしさで顔を真っ赤に染めながら彼女にその言葉の意味を教える。
「大きい声じゃ言えないけどあんた処女なんでしょ?あそこに諒のあれ入れられたかって聞いてるのよ」
意味がわかった佳奈子はれなと同じく顔を真っ赤に染めて「だっ…大丈夫」と声を震わせて答える。
「本当に…大丈夫なんだよね?」
「うん…その前に諒のあれ、蹴っちゃったから」
蹴っちゃった…その言葉にれなは目をまん丸に丸く見開いて「まじで…?」と驚いた様子だった。
佳奈子はまたあの時の状況を思い出して罪悪感に襲われていた。防衛本能からとはいえ、男性器というのは急所のひとつである。先生に先ほど教わったがもしかしたら諒はあの一撃で死んでしまった可能性がある。彼だってれなと同じく小学校からずっと一緒にいる幼馴染のひとりだ。泣いた時も嬉しかった時も悩みがある時もいつだって諒もそばにいて一緒に喜んでくれたり励ましてくれた。男性として好きにはなれないが友達としてとても好きだ。だからこんなことで失いたくないのだ。
しかし、れなは違った。
「よく自分守ったね。でも今は平気でも心に傷が残るかもしれない。もし残ってしまったら心療内科でも傷心旅行でもどこだって行ってあげるよ。私いくら幼馴染でも諒のことはすごく許せないわ。とりあえずここじゃあれだから入っていい?」
「あっごめんね。どうぞ」
佳奈子がどくと足元に27センチはあろう綺麗に磨かれた黒の革靴がきちんと並べて置かれているのが目に入ってきた。それを見、れなは先生が居間にいることをれなはさとった。
「…あとのことは先生にお任せするけどね。先生いらしてるのね。佳奈子、ご挨拶していいかな?」
「え、あ、もちろん」
れなは目を爛々と輝かせ、24.5センチの先の尖った黒のフラットシューズを脱ぎ揃えると「お邪魔します!」と勢いよく上がり込んで居間でコーヒーを飲んでいる先生の元へ挨拶しに短い距離を走って行った。
「こんにちは初めまして!聊斎(りょうさい)先生でいらっしゃいますよね?!」
「あっ…ええ、はい初めまして」
大倉山ジャンプ台からスキージャンプした様な勢いで170センチの長身の少女がどこからともなく飛んできていつのまにか足元に正座しているので先生は飲んでいたコーヒーをこぼしそうになった。
「小学校1年から佳奈子と親友やってます大佛(おさらぎ)れなです。今日はお忙しいところ佳奈子の為にありがとうございます」
佳奈子がお世話になっている人を見つけるとれなはいつも母親の様な言動になる。
「いえいえ、たまたま病院出たところで佳奈子さんからLINEがきたから来れただけで…」
「たまたま?じゃあ、タイミングよかったってことになっちゃいますよ?ここは『佳奈子さんが心配でいてもたってもいられなかったんです』って答えるべきだったんじゃないですか聊斎先生?」
それを後ろで聞いていた佳奈子が止めに入る。
れなが先生をどんな人物か姑並みの観察力で見ていると佳奈子にはわかったからだ。
「ちょっとれなやめてよ!初対面なんだから先生困っちゃうっしょ?!あっ、そういえばミュウは?」
「…ミュウ?あっそうださっきまで一緒だったんだけど途中マロンと目があったところで『先に行ってて』って言われちゃってさ」
ーー今からおよそ5分前のこと。
れなとみゆは環状通東駅のバスターミナルからバスに乗って中学校前から燕家へ向かって走っていた。3条1丁目の住宅街の十字路を左に曲がって進んでいくと坂内家の隣の犬小屋の前で黒柴のマロンがみゆに向かって吠え始めた。みゆは立ち止まり、マロンと対峙した。
『…先に行ってて』
『え?』
みゆがマロンに近づき目の前にしゃかみこむとマロンは落ち着き、甘えた様な声を出した。
『クゥーンクゥクゥーン』
そのマロンの姿にみゆは何かを感じ取ったのか、更にれなに先に佳奈子の元へ行くこと様に急かす。
『いいから早く行ってあげて。後で行くから』
……
れなは何が何だか分からぬまま渋々了解し先に燕家に来たのだと説明した。
「…にしても何だったんだろう、友達がピンチなのに」
小首を傾げているれなの様子で佳奈子は「れなでもみゆの行動は読めないんだなと思った。みゆは中学校の頃からずっと不思議ちゃん的存在で、時々行動パターンが全く読めないのは18歳の今でも変わらず、先程の行動については全くもって佳奈子にも尚更わからない。
再び先生の横に佳奈子が座ると先生にみゆの行動について聞いてみた。
「先生…ミュウって子の行動、読めますか?」
(多分…わかんないよね…普段一緒にいるうちらがわからないんだから)
聞いてみたあとに佳奈子はそう思った。先生だって会ったこともない不思議ちゃんの行動のことなどわかるはずがない。
しかし、その予想は外れる。
「マロンが…マロンがそのミュウちゃんに飼い主である諒になにがあったか教えてくれるのかもしれませんね。それをミュウちゃんが感じ取ったのかも」
れなと佳奈子は同時に驚きの声を上げる。
「「え?!」」
ーーその頃。
みゆは甘えるマロンの体を撫でたり、マロンの大好物だと何処でかはわからないが聞いていたたまご蒸しパンをこっそりあげたりして彼を構っていた。
「たまご蒸しパン、美味しかった?」
マロンはたまご蒸しパンをひとつペロリと平らげた。満足したのか尻尾を激しく振る。
みゆはマロンに質問した。
「ねぇマロン…諒くん今何処でどうしてるんだろう…わかる?」
すると、マロンは「わかるよ」と答えるかの様にみゆの膝にポンと右前足を置いた。
「わかるの?ねぇ、まずは諒くんがいるとこに連れてって!」
マロンはみゆに応える様に地面に打ち付けられた大きく太い釘に引っかかっているリードを器用に外してみゆに渡すと真っ先に突き当たりの畑の方へとみゆを引っ張っていく。みゆはリードを離さぬ様しっかりと握りしめて走っていった。
マロンが向かった先は燕家の裏、左手向かいの小さな公園だった。手入れがされずに伸び放題の茂みの向こうにあるブランコに諒は弱った様子で座っていた。
「ワン!ワン!」
「諒くんっ!」
リードを離すとマロンは諒の元へ駆けていった。それに諒も気づく。
「マロン…!なした?またひとりで散歩してんのか?!」
諒はいつも自分や祖母がいないと勝手に散歩してはちゃんと猫の様に戻ってくることを近所の人伝いで知っていたので今回もそうだろうと思った。しかし、遠くから近づくみゆの姿を見つけ、それは違うことに気づいた。
「ミュウ…お前が連れてきたの?」
みゆは静かに首を振る。
「じゃあ…」
「マロンに聞いたら連れてきてくれたの」
「…え?」
諒は一瞬訳が分からなかったが、普段からマロンは他の飼い犬より優れた能力があるような気がしていたので、その様な事があっても不思議ではないと思い納得がいった。
「そっかぁ、俺が何処にいるかミュウに教えてくれたのかマロン?」
マロンが大きく尻尾を振ると諒は「えらい、えらい」と頭を撫でて褒めた。
「あ…諒くん、怪我は?佳奈子ちゃんに蹴られたんでしょう?」
「あ、ああ…なんともないよ…ははっ」
諒は恥ずかしさで笑ってごまかした。好きな女の子に蹴られた上に逃げられるなんて男として情けなさすぎる。本当は蹴られたところに今でも鈍痛が走っている。
「そうかなぁ…本当は今でも痛いんじゃないの?」
見かねたみゆは諒に指示する。
「…諒くん、痛いかもしれないけどその場でジャンプして」
「は?ジャンプ?」
「いいからっ早く!」
みゆに指示された通り諒はブランコを降りてその場でジャンプした。
「あれ…?」
「下りてきた…?」
「…そうかも」
「そのままジャンプし続けて」
暫くジャンプし続けていると蹴られたことによって上がっていた睾丸が下に下がった。
「…あ、戻った…」
「よかったぁ…あとは氷借りて冷やしたたら佳奈子ちゃんに謝ろう」
「うん…てかなんでこんなこと知ってるの?」
諒はふと疑問に思った。女性であるみゆがなぜこんな応急処置法を知っているのだろうか。
しかし、みゆは「さあね」と答えるだけで燕家に向かう方向へさっさと踵を返してしまった。
「あっ…!マロン待て!」
大人しくおすわりしていたマロンもみゆについてスタスタと駆けて行ってしまった。それを諒は追いかける。
玉ねぎ畑の前の青壁の家の横まで追いつくと、マロンのリードを持って青壁の家で左折しようとしたみゆに声をかけた。
「待って…ミュウ待って!」
みゆが立ち止まるとマロンも動きを止め振り向いた。
「もう少し…時間ちょうだい…あんなことしちまったあとで俺…俺…佳奈子の顔見るのまだ怖いべ」
「諒くん…」
自分でもまさかずっと小学生の時から好きだった佳奈子を犯そうとしてしまったことが諒はまだ信じられずにいて、思い出す度に頭がパニックになっていた。
「俺…俺…佳奈子に…あんなこと…」
諒は力なくその場でへたり込んだ。恐怖を感じているのか両手は小刻みに震えている。
そんな諒の姿を見、みゆは直ぐ様彼を優しく抱きしめた。
「諒くん…まずは落ち着いて頭の中整理しよう」
「うん…」
「ゆっくり深呼吸して…」
みゆは諒を落ち着かせるために深呼吸させた。
少し落ち着いたところで彼の鎖骨や顔などをトントンと軽く指で叩いた。これを恐怖を感じた時など落ち着くために用いる一種のセラピー法である。それを5分間続けた。
「諒くん…少しは落ち着いた?」
「うん…落ち着いてきた…」
その証拠に彼の呼吸は先ほどより深く、ゆっくりになっていた。
「諒くん」
「ん…?」
「やってしまったことはまず自分の中でしっかり受け入れて反省しなきゃ」
「…そうだね」
諒の顔が曇った。きっと認めたくない気持ちもあったのかもしれない。
「女の子ってね体も心も凄く繊細なの。勿論男性より精神面は少し強いかもしれない。でも、こういうことがあると1番傷つくのは心身共に女の子の方なんだよ。やってしまった諒くんも蹴られて相当心も体も痛いかもしれないけど、佳奈子ちゃんを好きなら佳奈子ちゃんが近い将来好きな人とえっちする場面があったときに怖くならない様に今のうち謝ったほうがいいよ」
みゆは風俗をやっているだけあってそういった女性の気持ちに敏感になっていた。
「だから…謝りに行こうよ。諒くんきっと後悔しちゃうよ」
元の友達関係に戻れるかどうかは別として、諒の心が少しでも軽くなればと謝ることを勧めるが、
「…うん…でも」
諒の足はまるで重い足枷をつけられたかの様になかなか燕家へ向かおうとしない。佳奈子にまた拒絶されるのを恐れているのかもしれなかった。
みゆは諒が決断するまで幾らでも待つことを心に決めた。
30分…1時間…
待てど待てどみゆは来ない。
何度煎茶とコーヒーを入れ直したことだろうか。
インターホンが鳴ればみゆかと思い、れなは玄関に向かったが、 それはみゆではなく自宅で採れた野菜などのお裾分けをしにきた隣人だったり仕事から急いで帰宅してきた知世だった。
知世は帰宅早々れなを押しのけて姪っ子であり自分の1人娘のような佳奈子を心配する。
「ただいまっ!佳奈子大丈夫なのっ!?怪我はない?変なことはされて…あっ!されたよね⁈あーもう諒くんったらそんなする子じゃないと思ってたのに…人はわからないものだわ」
子供を産んだことはないし佳奈子も諒も自分の子供ではないのだが、責任感の強い知世は幼少期から見てきた自分にも責任はあると感じていた。
「どこで間違えたのかしら…産んだのは私じゃないけれど、あなた達を小さなときから見てきた者として諒くんがやってしまったことは私に責任があると思うわ…ごめんなさい佳奈子…」
その謝る知世の姿はまるで罪を犯した息子を持つ母親そのものであった。また、彼女の中では被害を受けた娘の母親の気持ちにもなっていて、ひとつの体で二重の心の苦しみを抱えていた。知世は佳奈子をきつく、力いっぱい抱きしめ、
「ごめんね…ごめんね佳奈子…ごめんね…恨むならおばさんを恨みなさい…ね?」
と涙を流した。
その姿を少し離れた灰色の革の光沢が光る長ソファーから見ていたれなと先生にも知世の二重の心の苦しみが先が鋭く尖った氷柱が突き刺さったように冷たく痛い程伝わってきた。知世からすれば1人でどちらの立場にも立っていて、怒りも悲しみも何処にぶつけようが全て自分に心の傷みとなって返ってきてしまうし、身内で賠償金は知世には発生しないものの、気持ちの問題などで知世は自分自身を痛々しい程に責めていた。
そんなおばを優しい佳奈子は責めたりしなかった。きつく抱き返すと自分が大きくなったせいか、153㎝の小柄な知世の体はわずか7㎝差でもとても小さく感じられた。こんな小さな体で育児放棄した母の代わりに毎日毎日抱っこしてミルクをあげたり、大きくなって10kgの米袋2つ、3つ分になっても抱き上げてくれたことを思い出すと佳奈子には知世を責めることができなかったのだ。
そして、数カ月前に母に「死んじまえ!」と言われた自分が今でも何不自由なく暮らせているのは知世のおかげであることを思うと、この人は本当におばである立場を超えて母親以上のことをしてくれていて感謝しても仕切れないと佳奈子は思った。この人が本当に血の繋がった母親ならばどんなによいか…視界が涙で滲む。
「いいよ、おばさん…1人で抱え込まなくていいし自分を責めないでよ。私おばさんのこと責めるつもりないよ、こんなに私に良くしてくれるおばさんに感謝してるし大好きだから…」
大好き…その言葉で知世は地の底で天から垂れる蜘蛛の糸を掴んだ様な気持ちになった。あるひとつの恋愛から女の幸せを掴むことができず、ひとりで生きることを選んだ女が、わけのわからない宗教に狂信してしまい、育児放棄したどうしようもない妹の代わりに育てている姪っ子に愛の言葉ひとつで心から救われる日がくるなんて知世は思ってもみなかった。
知世は先程流した涙とは違う涙を一筋、また一筋とごぼした。
(神様なんていないと思っていたけど…案外何処かにいるのかしら…言葉の中だとか…)
「ありがとう…私も佳奈子のこと、大好きよ」
この瞬間に知世の人生は今まで生きた中で1番、いや、何千倍と光り輝いた気がした。心のこもった愛の言葉は悲しみの中で生きている人間を地の底から救える程のパワーを持っているのかもしれない。
一方、その感動的な2人の空間の中にれなと先生は入り込めずにいた。ブッタやイエスキリストの背後に描かれる様な眩い後光が2人を覆っている様に見えたからである。
このまま少し離れた場所で祝福していたい気分だったが、れなはみゆのことが心配でもあった為隣に座る先生に一言伝えて2人の空間を邪魔しない様、彼女を探しに行く為に席を立つ。
そこで、あることを思い出した先生がれなを呼び耳打ちした。
「この辺、大昔に熊が出て大事件になったりしたし、刃物を持った人物などの不審者情報も昔ありましたので気をつけてくださいね…」
「え…そんなに危険な地域でしたっけ丘珠…もうさすがに熊は出ないだろうけど…気をつけます…」
ここ丘珠町はまだ北海道石狩国札幌群札幌村大字丘珠村と呼ばれていた1878年(明治11年)、1月11日から18日にかけて「札幌丘珠事件」という記録されたものとしては日本史上4番目に大きな被害を出した獣害事件が発生した場所であり、死者3名、重傷者2名を出したとされている。現在では熊は降りては来ないものの、餌求めて山を降りてくる野良狐が歩いているほか、人が少ないため絶好の場所なのか、時々女児や女子高生に車から声をかける不審者が出たりしている。
れなの背中に悪寒の様なものが走った。もしミュウの身に何かあれば…。
れなはソファーの位置から走って玄関でスニーカーに片足を突っ込んだ。と、そこでiPhoneが鳴る。
(…これは…もしや…)
赤のタータンチェック柄のストレッチショートパンツのポケットからiPhoneを取り出し電話に出る。着信画面には桜間みゆの表示。
「…もしもしっ!ちょっと!今何処なのっ?」
れなの心配をよそにみゆの口調は淡々としている。
『小さい公園の近くです。諒くんもマロンも一緒なんで今から連れていきますね。カップラーメンができるまでには着くと思う』
ーーブッ…プープープー…
「あっちょっ!…あーわや!ま〜たあの子は要件だけなの?!てか今の状況で諒連れてくるなよな…全く」
およそ3分後…みゆは予告通り諒とマロンを連れてやってきた。ドアを開けると直ぐ様れなは日頃のこともあり、みゆに注意した。
「ちょっとミュウ!電話出てよね!心配するしょや!」
れなは怒りのピーク時に北海道弁がでてくる。
しかし、怒りのピークを読めないのか、いや、読まないのかみゆは相変わらず淡々と答える。
「すいません充電10%きってて切れそうだったんでバスに乗ってるときに電源切ってたんです」
「全くもぅ〜友達のピンチに切るとは何事じゃいっ!いっつも寝る寸前まで携帯ちょして充電しないまま寝るからでしょ!それで連絡つかないんだからうちらなまら困るんだわぁ!今日からちゃんと充電して寝れ!」
れなのみゆを思っての説教もよそにみゆはいつも通りの淡々とした口調のまま「わかりました」と返事をした。
(本当にわかってんのかなぁ…仕事はなんでもテキパキこなす子だから多めに見てるけど、人の話たまにちゃんと理解してくれたのかよくわかんないんだよなぁ…)
本当に理解したのかわからないまま問い詰めたくなったが、今は長くなってしまいそうだと思い、みゆとマロンを居間に行かせることにした。
「ミュウ、とりあえず今はマロンと一緒に佳奈子たちのとこ行っててくれる?」
「はい」
みゆは靴を脱ぎ上がると玄関の片隅に小さなバケツ入っていた雑巾を拝借してマロンの足の裏を拭いてやって居間にマロンを連れていった。それに続いて靴を脱ごうとした諒をれなは止めた。
「待って、あんたはここに“おっちゃんこ”してなさい」
「なして?てか“おっちゃんこ”って子供扱いかよ…」
「なしてって佳奈子にあんなことにしたから決まってんでしょ?今の佳奈子にとってあんたは怖い存在でしかないの。わかるかなぁ…?」
諒はれなに言われて気づいた。謝って自分の中ですっきりしたい気持ちのほうが先行しているが、佳奈子の気持ちも考えてあげなくてはいけないのでは…?と。
「そうだな…俺ここにいるわ」
諒は玄関のドアを静かに閉めると上がり框に腰掛ける様に座った。
「諒のことだから本当は逃げたい気持ちも半分あるけど佳奈子に誤ってすっきりもしたいんでしょ?でもごめん。ちょっと待ってて」
れなが居間に行くと、しばらくして後ろから初めて聞く男性の低くく、色気がありつつも品のある凜とした声が彼を呼んだ。
「君が、諒くん?」
呼ばれて振り向くと諒と同じくらいの身長の、抜ける様な肌の白さと切れ長の美しい目をした男性が立っていた。
(この人なのか…佳奈子が“好きになった医者(おとこ)”って…)
そうだとわかると次第に目の前の美しい同性に男として妬けてくるが、今はその気持ちを抑える。
「はい」
「少し話しようか」
先生はそう言い、ふわっと優しく笑みを浮かべた。諒は少し身構えつつも彼と向き合うことにした。
男2人は玄関の床柱と引き戸との間にならんで座る。尻を置いた床板がひんやりと冷たい。
自分と17歳も年上の大人の男性とならんで座ることなど社会に出ていれば何度とあるのに諒は緊張していた。好きな女の子の恋人というだけでも妬けてくるのと、今隣にいる彼があまりにも美しすぎたことと大人の余裕があるのを感じて19歳の諒は既に同じ男として負けていることを認識し勝ち目がない悔しさとの葛藤の渦に落ちた諒はゴクリと音を立てて生唾を飲み込んでいる。
「佳奈子に蹴られて痛かっただろ?はい、保冷剤」
「あ…ありがとうございます」
タオルハンカチに包まれた小さな保冷剤を手渡され、諒は患部を冷やす。
軽く世間話をしたあと、先生は医学部時代から付き合いのある友人の話をする。
「医学部時代から付き合いのツレがいるんだけど、そいつ昔俺のいとこの女を好きになって振られたことがあってさ、気持ちをコントロールできなかったのか、諒くんと同じく蹴られてたよ」
「…まじですか」
「若さゆえの過ちって言うのか、気持ちをコントロールできずに暴走するやつはいるよ、恋愛に限らずな。
恋愛の面で言わせて貰えば本当にお前はその子を好きなのかってこと。俺からしたらただの欲でしか見てない様な気がしてさ」
「先生はあっちの欲はどうなんですか?モテそうだし」
諒からの思わぬ質問で話が本題から脱線する。
「…それ答えなくちゃダメか?俺だって欲はあるし強いよ?でも好きな女が嫌がることはしたくないから向こうがその気にならないうちはしないな。てか、其れ程モテないからな?」
「言い寄られることはあるでしょ?」
「あるけど好きじゃなきゃ申し訳ないけどって丁重にお断りするよ。でもそのあとの嫌がらせが半端じゃなくてここ10年は困ってるんだ。長くなるから話さないぞ?」
「先生も悩んでるんだな」
「諒くんだってバンドマンって聞いてるけど、モテるんじゃないの?佳奈子以外の女の子だっていくらでもいるんじゃなかったの?」
諒の表情が暗くなる。諒だって先生ほどではないが見かけは良いのでモテるのは確かだった。
「いたよ。でも佳奈子が好きだしバンドのためにも彼女は作らずにきたんだ。その度に申し訳なく思いながら断って…」
「なるほどね。でもさっきの話に戻すけど、そう言うことするやつって欲しかない気がしてるんだよ。諒くんはどうなの?佳奈子に対して佳奈子の気持ちを思いやるだけの愛情はある?」
問われて諒はしばらく黙っていた。実のところ本当は諒自身もよくわからなくなっていた。約10年間佳奈子だけを思っていたとはいえ、自分は佳奈子という女の子を本当に好きなのか。まだ精神的に未熟な19歳の彼には愛とは何かをわかっていないのだ。自分でも煩わしく思うくらい嫉妬心を剥き出しにすることはあっても、果たしてあの時は本当に好きだからこその行動だったのだろうか…?
「…俺本当に好きなのか…わかんなくなってきたよ先生…」
「今わからなくても、そのうち大人になったらわかるよ。何事も焦るんじゃない」
「…さっき話してた先生の友達はどうだったんですか?」
「諒くんより悲惨だけど続き、聞きたい?」
「俺より…悲惨…?」
「俺のいとこはあそこを蹴るだけじゃなく、何日か後にモエレ沼の排雪場横でたまたま見かけたからって気を抜いてるとこ見計らって後ろから飛び蹴りして落としたんだ」
モエレ沼の排雪場は札幌市東区にあるモエレ沼公園の近くに札幌市によっていくつか設けられた排雪場のひとつである。冬の間市内で除雪車によって排雪された雪がここに運ばれ積まれていくのだが、5月のゴールデンウィークあたりになっても解けきらずに真っ黒になって残っているのである。
「うわ…あのばっちぃ排雪場に落とされたらひとたまりもないな…好きだった気持ちも冷めちゃうだろうに」
「冷めるよな…いとこはそれ狙ったんだろうけど」
「もしかして…?」
「…今でも諦めてない。そのことがあっても振ったうえに排雪場に落とした相手を忘れずにいて、10年以上経ってもどうしてるか聞いてくるよ」
「その人…ドM?」
「ドM…かどうかはわからないけど、自分を追い詰めて何かを達成することは好きだって言うよ。マラソンとか」
「因みにその人今何科の先生なんですか…?」
「精神科医」
「まじですか…いとこも…?」
「うん、口腔外科医。家族、親戚、みんな何かしらの医者だよ」
「なんか…話には聞いてたけど、先生っておぼっちゃまなんですね…」
「大したことないよ。別にコネとかあるわけじゃないし。医者って言っても普通の人となんも変わらないから」
先生は居住まいを正すと、あらためて諒と向き合う。
「色々話したけど諒くん、わかってくれた?もうこれからは気持ち先走らせずに、相手の気持ちと立場をよく考えた上で行動しなさい。特に相手が好きな女の子なら尚更。恋愛ってのは究極の人間関係なんだ。脳の作りからして違う男女が惹かれあって友達や家族の枠を超えた関係を築いていくんだから難しいんだ。それが結婚となれば相手のその後の人生にも響いてくる。いいか?」
「はい」
「それを間違えたことによって自分だけでなく相手の人生を壊しかねない。お互いの心の傷どころじゃなくなることもあるよ。だからこれから出会うであろう女の子は大事にしろよ。俺も佳奈子大事にするから」
「わかりました…男の約束にしましょうよ」
「いいぞ」
歳の離れた男2人は笑顔で互いの拳をぶつけ合った。
「佳奈子に謝らないか?佳奈子の気持ちも聞かないといけないけど」
「謝りたいです。許して貰えるかはわからないけど…小学校からの関係をこんなことで壊したくないです…」
諒の頭の中で佳奈子と小学校からの思い出が駆け巡る。実の父に虐げられてきた諒にとって人との繋がりを作ることができた音楽と同じくらい佳奈子の存在は暗い人生に一条の光が差し込みような、それくらい大きなものだった。
「そっか…待ってろよ」
先生が佳奈子を呼びにいくため立ち上がる。しばらくすると佳奈子が居間から出てきた。
「諒…」
「佳奈子…」
互いに名を呼んだものの、暫く2人の間に沈黙が流れた。沈黙の後に先に口を開いたのは諒。
「さっきは…あんなことしてごめんな…謝ったところで許して貰えないとはわかってるんだけど…」
謝る諒の目には涙が滲んでいた。泣くまいと堪えているのが佳奈子にはわかった。昔から諒は涙脆いところがある。そのことを思い出し、佳奈子は彼を許すことにした。
「もういいよ。あんなことされて怖かったし友達だと思ってた人にされて悲しかったのもあるけど、どこかの知らないおじさんとかじゃなかったからいいかなって…。でもだからってもうあんなことはしてほしくないけどね」
「わかってるよ、もうしない。もう…佳奈子のことは傷つけたくない…大事な“友達”だから…」
「諒…」
その会話を居間の奥で聞き耳をたてて静かに薄ら笑いを浮かべている人物がいたことは、この時誰ひとり知るものはいなかった。
再び、不穏な不協和音が彼らの間に流れ始める…ーー
リラの花が咲く頃に 第5話
第5話、お読みいただきありがとうございます。
感謝です。
あなたは…恋の嫉妬に狂えますか…?


