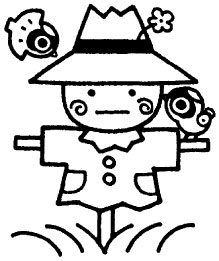僕らの冒険をめぐる物語
1
朝、ケイヤが躊躇いもなく教室に入ってきた。僕の席まで来ると、口を尖らせながら言う。
「なあ、翔。昨日、よっちんからメールがきたんだ」
ケイヤが携帯電話の画面を見せる。僕は携帯を持っていない。だから、よっちんからのメールは全てケイヤの携帯にくる。当たり前のことなんだけど、なんか面白くない。
『このごろ、イライラして、苦しくて、疲れて、本当に嫌になる』
画面にはこう書かれていた。
「これだけ?」
「いや、俺ビックリして、『どうしたんだ?』って返信したんだ。それで、帰ってきたのがこれ」
『ゴメン、なんでもないちょっと愚痴りたくなっただけ』
――あの、よっちんが愚痴りたくなるなんて……
僕とケイヤは目を合わせた。
――これは大変なことだ!
僕らは、小学三年生のときに同じクラスになった。六年生になって、ケイヤとは別のクラスになってしまった。よっちんは、引越しして学校まで変わってしまった。
だけど、僕らの友情は変わらない。三人の友情はいつまでも続くんだ。
――そう僕は信じていた。
三年生になった最初の席決めで、僕は窓側の一番うしろの席になった。僕の前の席がケイヤで、その前がよっちんだ。
ケイヤは授業中、よっちんの背中に消しゴムをぶつけたり、鉛筆のうしろで脇の下をくすぐったり、いろんなちょっかいを出していた。よっちんはその頃からぽっちゃりしていて、触ったら気持ちよさそうで、ケイヤの気持ちも分からないでもない。
よっちんは人がいい。そんなことをされたからって、絶対怒ったりはしない。ときどき振り返って、「やめてよ」って言うくらい。ケイヤはそのタイミングを狙っている。よっちんが振り返ろうとすると、そこに人差し指を立てて待っている。果たして、よっちんのふっくらとした頬に、ケイヤの人差し指が刺さっていく。
僕は真剣によっちんに同情した。
ケイヤはそれに飽きると、うしろを振り返って僕に話しかけてくる。話は面白いんだけど、いい加減で嘘も多い。そのことで僕とケイヤは喧嘩になったんだけど、その話は後でする。ケイヤは話し出すと止まらない。うしろを向いたまま話し続ける。
三年生のときの担任は森田先生。通称、ゴリ田。この学校の教師の中で一位、二位を争う凶暴な奴だ。必死に目配せして危機を知らせようとするんだけど、ケイヤはお構いなしで話し続ける。無視しようが、ハッキリともう喋るなと言おうが、話し続ける。そのうちチョークが飛んでくる。なぜだか、ケイヤはうしろを向いたまま、スッとかわす。チョークは僕の額を直撃する。
――そう、ケイヤはけっこう、うざったい奴だった。
三年生の六月ごろの話だ。僕らは同じ掃除の班だった。
放課後、掃除の後に三人でモップと箒で戦っていた。他のみんなはとっくに帰ってしまっている。
よっちんはすでに箒で切られて、机の上に仰向きに倒れている。ケイヤが机に飛び乗り、モップを振り上げる。僕はちりとりで防御の姿勢をとった。天井で何かが爆発した。白い粉と破片がすごい勢いで降ってくる。振り上げたモップで蛍光灯を壊してしまったんだ。
ケイヤの頭が白髪みたいになった。多分、僕の頭も。
――目撃者はいない。
黒板の上にかけられた時計の音が、こんなに響くんだって初めて気が付いた。校庭でサッカーをする上級生の声が聞こえる。
三人の目が同時に合った。そして、――心が通じた。
よっちんは掃除器具の入ったロッカーまで行くと、中から雑巾を一枚取り出し、戻ってきた。
「念のため、指紋は拭き取っておいたほうがいい」
よっちんは言った。
僕らは、慌ててモップと箒の柄を拭き、頭の粉を振り払いながら下駄箱へ走った。
次の日、ホームルームでそのことが問題になった。ゴリ田が「全員目をつぶって、やった奴手を上げなさい」って、テレビのワンシーンみたいで感動した。薄目で見てたけど、もちろん手を上げる奴なんかいない。
これで終わるのかと思ったら、人生はそんな甘いもんじゃなかった。授業の後、僕ら三人は職員室に呼び出された。誰かが僕らが残っていたことを言いつけたらしい。
「見てた奴がいるんだ、今のうちに誰がやったか言うんだ!」
職員室に入ったとたん、室中に響き渡る声で怒鳴られた。他の先生たちが一斉に視線を向ける。一・二年のとき担任だった恵子先生も、困ったような顔で見ている。恥ずかしい。ケイヤもよっちんも下を向いたまま動かない。
「見てた人がいるなら、その人に聞けばいいじゃないか!」
これはまずい。何がまずいって、一番まずいのは言ったのが僕だってこと。悪い癖が出てしまった。頭で考えたことが、つい口に出てしまう。
ゴリ田は顔を真っ赤にして怒りに震えている。マンガみたいに、耳とか頭のてっぺんから蒸気が噴出しそうだ。想像してたら、笑いそうになった。危ない危ない。ここで笑ったら一巻の終わりだ。
その後、僕らは一人ずつ、職員室の奥の部屋へ連れて行かれる。八畳くらいの広さで、テーブルを挟んで二人がけのソファーが対面して置かれている。面談や来客のときに使う部屋なんだけど、ほぼ取調室。
まず僕が呼ばれた。二人きりになると、ゴリ田は思いのほか大きい。白状してしまおうかと思った。実際に壊したのはケイヤなんだ。ただ、それだとなんか負けたって気がする。負けるのは絶対に嫌だ。だから、我慢した。頑張って我慢した。ちびりそうになっても我慢した。
三人とも正直に話さないのなら、全員の保護者を呼び出しだって、ゴリ田が言い始めた。そういうことは最初から言って欲しい。今更じゃ、引っ込みがつかない。
次はよっちん。気の弱そうなよっちんには、とても耐えられないだろうと思った。だいたい、よっちんは机の上で死んでたんだから、ほとんどかかわっていない。巻き添えを食っただけだ。よっちんが話してしまえば、僕が嘘を言ったこともばれる。仕方のないことだ、責められない。覚悟を決めた。
しかし、十分くらいして、よっちんは平気そうな顔で、ニヤニヤしながら出てくる。ゴリ田に見えないように、胸の前でこぶしに親指を突き立てている。
――よっちんは只者でない。僕はそのとき、初めてそのことに気が付いた。
最後にケイヤが呼ばれた。ゴリ田も疲れた顔をしている。ケイヤが部屋に入って五分くらいすると、ゴリ田が一人で出てきた。お前ら帰っていいと言う。ケイヤからはもう少し話を聞くから、先に帰れと。
僕とよっちんは顔を見合わせた。状況がよく飲み込めないが、仕方がなく帰ることにした。
「親を呼び出しだって?」
僕は校門を出るときに、よっちんに言った。親に、なんて説明しようかと、暗い気分だった。
「うん。言われたけど、脅しで言ってるだけだから、大丈夫だよ」
「何でそんなこと分かるんだよ?」
「だって、証拠もないのに親を呼び出しして、もし間違ってたら、問題になるじゃない。そんなバカなことしないと思うよ」
よ、よっちん。君は……
次の日、ケイヤは一時間目のチャイムが鳴るのと同時に、教室に入ってきた。
「どうした?」僕が聞くと、
「喋っちゃった、ゴメン」と、顔の前で両手のひらを合わせて、頭をぴょこんと下げる。
うしろを振り返っていたよっちんは、明らかに気が抜けたような顔をしている。
「何で?」僕が言うのと同時に、「起立」日直が号令をかけた。ゴリ田が来たのだ。僕らの会話は中断された。
ケイヤは大人しく授業を聞いている。
ケイヤの背中を見ていたら、殴りたくなってきた。僕とよっちんがあれだけ怖い思いをして黙ってたのに、当の本人がばらしちゃうって、どういうことだ! もしかすると、嘘つきのケイヤのことだ、あることないこと言って、自分だけ責任逃れしたのかもしれない。何で昨日は、こんな奴のことかばったりしたんだろう。すぐに言っちゃえばよかったんだ!
僕は憤然としながら授業が終わるのを待った。目の前の背中を五回包丁で刺して、ロープでグルグル巻きにして、三回火あぶりにした。四回目の火あぶりの準備をしているときに、やっと終業のチャイムが鳴った。
日直の号令が終わると同時に、僕はケイヤを問い詰めようと立ち上がる。そのとき、まだ教室に残っていたゴリ田が僕とよっちんの名前を読んだ。職員室に来いと。
――さっ、最悪だ!
僕とよっちんはゴリ田の後について、職員室に向かう。
「辻田くん、どうして話しちゃったんだろうね?」
よっちんがあんまりのんびりというものだから、余計に腹が立ってくる。辻田はケイヤの苗字だ。
「知るか! あの裏切り者が! 何であいつのために僕らが怒られなくちゃいけないんだ!」
「でも、どうしたんだろう」
「絶対ぶっ殺してやる」
職員室に入ると、昨日の個室に一緒に通された。ゴリ田は奥のソファーに座ると、僕らを手前のソファーに座らせる。
「お前ら、辻田にいじめられてるのか?」
怒られるとばかり思っていた僕は、予想外の質問にビックリした。
「蛍光灯のこと、辻田に無理やり口止めされたのか?」
「辻田くんがそういったんですか?」
よっちんはゆっくりとした口調で言う。
「じゃあ、辻田は蛍光灯をどうして割ったんだ?」
「辻田はなんて言ってるんですか?」
僕は話の流れが、上手くつかめなかった。
「イライラしたから、腹立ち紛れに蛍光灯をぶっ壊したって言ってたぞ」
「一人で壊したって?」
「違うのか? それを見られて、誰かに言ったら殴るぞって、辻田はお前らを脅したんじゃないのか?」
「「違います!!」」
僕とよっちんは声をそろえて言った。
結局、ケイヤはゴリ田の策にまんまと嵌ってしまって、僕らの親が呼び出されないように、自分ひとりで罪を被ろうとしたんだ。
あんなハッタリに騙されるなんて――、ケイヤはなんておめでたい奴なんだ!
以来、僕らは親友になった。川に石を投げで、誰が一番石を跳ねさせることができるか競ったり、ヤゴを捕まえたり、川に落ちて溺れかけてるよっちんを助けたりした。林の中を探検したり、蝉を捕まえたり、木登りして下りられなくなたよっちんを、どうにかこうにか、やっとのことで下ろしたりした。
どんなときでも、蜂に刺されたり、転んで前歯を折ったときでさえ、よっちんは泣き言を言ったり、愚痴をこぼしたりしなかった。ちょっと恥ずかしそうに、頭をかいてるだけだ。よっちんの口もとにはいつだって微笑があった。
四年生になってすぐ、よっちんの両親が離婚した。よっちんとお母さんが今まで住んでたマンションに残って、お父さんが出て行った。原因は多分、お父さんの浮気。
そのときでさえ、よっちんは弱音を吐かなかった。「ぼくは男だから、お母さんを守ってあげなくちゃいけないんだ」なんて、一丁前なことまで言っていた。
だから、僕とケイヤは、よっちんが愚痴を言うなんてこと信じられなかった。
僕はケイヤから携帯を奪い取り、何度もそのメールを読み返した。
「何かあったのかなぁ?」
僕は、プニュプニュして指で摘まむと最高に気持ちいい、よっちんの頬っぺたを思い出しながら言う。
「前のメールじゃ、まだ新しい学校に馴染めてないような感じだったよな。まさか、いじめられてるんじゃないだろうな!」
ケイヤは今にも怒り出しそうだ。
授業開始のチャイムが鳴った。ケイヤは渋々と教室を出て行く。担任が来て朝礼をした後、体育館へ移動するように言う。今日は一年のうちで最もエキサイティングでファンタスティックな日。そう、一学期の終業式。明日から待望の夏休みだ。
みんな廊下に出て、話しながら体育館へ向かう。誰もがいつもより口数が多い。
廊下でケイヤが追いついてきた。そして、少し興奮したように言う。
「翔、どうするよ?」
「どうするって――、何をだよ?」
「よっちんと約束しただろ。困ったことがあったら、いつでも助けに行くって」
「――まさか?」
「決まってるだろ!」
「でも、どうやって? よっちんの引っ越した先って、高速道路に乗って、車で三時間くらいかかるって、よっちん言ってたぞ」
「昨日の夜、地図見たんだ。一旦海まで出て、海沿いの道を走って行って、途中から山のほうに入るんだ。その山の峠を越えて、下りきって、県庁のある市を通り過ぎて、しばらく行ったらよっちんの家だ」
「……ケイヤの家の人が、連れて行ってくれるのか?」
「うちの親はダメだ、今、開催中だから来週までカンヅメで出てこれない。じいちゃんはボケてるし。翔の家の人は?」
「うちも父さん平日は仕事だし、最近忙しいみたいで、日曜日だって会社に行ってる。絶対無理だよ」
「しょうがない。俺たちで行くしかないか」
このとき、すごく嫌な予感がした。できれば答えは知りたくないと思いながら聞いた。
「……どうやって?」
「自転車だよ」
当たり前のように、ケイヤは言う。
「さっき、簡単に言ったけど、こっから海に出るのだって、かなり遠いよ。自転車で行くなんて絶対無理だって」
「距離はだいたい百五十キロくらい。さすがに、一日じゃ無理だから、俺の考えじゃ、峠を下った辺りで一泊すれば、次の日にはよっちんの家まで行けると思う。で、同じような感じで帰ってくれば、二泊三日で大丈夫だよ」
「どこに泊まるんだよ?」
「夏だし、野宿でいいよ」
「無理、無理、無理! 絶対に無理!」
「行くって約束したじゃないか!」
「でも、あのメールだけじゃ、本当によっちんが困ってるのか分からないよ。よっちんが来て欲しいって、言ってるわけでもないし……」
「よっちんの性格からして、来て欲しいと思ったって、そんなこと言うかよ」
「まぁ、そりゃ、そうだけど……」
「じゃぁ、明日の朝、出発な」
「ちょっと、待ってよ。うちの親、そんなのダメだって言うに決まってるよ」
「何言ってるんだよ! よっちんがどうなってもいいのかよ」
「そんなことないけど……」
体育館に着いたので、僕らは一旦別れた。
終業式では校長先生が何か言っている。はげ頭が揺れてるだけで、何を言っているのかまったく耳に入ってこない。晴れやかな気分で舞い上がるクラスメートの中、僕の気持ちは上下左右に揺れ動いていた。
もちろん、よっちんのことは心配だ。それと、旅行に行くようなところまで、自転車で行く覚悟とはぜんぜん別の話だ。しかも、野宿だ。蛾とか、ゴキブリとか、山のほうならムカデとか、もっとすごい虫もいるかもしれない――。
終業式が終わると、ケイヤが体育館の出口で待っていた。気付かない振りをしようと思った。が、目が合ってしまった。
「翔、いいこと思いついたぞ。今日から、俺んちに泊まれよ。三日間、集中して夏休みの宿題終わらせるとか言ってさぁ。そうすれば、翔の母さんも文句ないだろう。もし、翔の母さんから電話があったって、うちの爺ちゃんどうせ何言ってるかわかんないから、ばれっこないって」
ケイヤは、新しい法則を発見した物理学者みたいに、目をキラキラさせながら言った。
そのアイデアが、本当に有効かどうか、かなり疑わしかった。だけど、ケイヤは一度言い始めたら後には引かない。よっちんのことも心配だ。そして何より、よっちんに会いたい。抑えられていたよっちんに会いたいという気持ちが、一気に膨らんでくる。よっちんのあの柔らかい頬っぺたをプニュプニュしたい。
ケイヤもよっちんのことが心配だといいながら、本当はよっちんに会いたいんだと思う。
ここまできたら、覚悟を決めるしかない。こうなったら、峠の向こうだろうが、北海道だろうが、ブラジルだろうが、火星だろうが、自転車で行ってやる。待ってろよ、よっちん!! ほんの一瞬だけ、そんな気分になった。
「ケイヤ! よっちんに会いに行こう!」
言ったとたんに、後悔の念が押し寄せてくる。
頭に浮かんだことを、深く考えることもなく、口に出してしまう。僕はまったく成長していない……
家に帰ると、今夜からケイヤのところで夏休みの宿題の合宿をすることになったと、母さんに告げた。自分で言っていても、終業式の当日から宿題をするなんて、あまりにも白々しい。現実的じゃない。ファンタジーだ。
だけど、母さんは意外にあっさり許してくれた。拍子抜けするくらいに。
ダメだって言わないんだぁ…… このくらいの嘘、見抜けよ!
――こうして、僕らの自転車旅行は、実行可能となった。
夕方になり、着替えをデイパックに詰め、家を出た。物置から自転車を出しているときに、宿題を持っていないことに気付いて慌てて取りに戻る。自転車は去年の誕生日に買ってもらったマウンテンバイクだ。
ケイヤの家は僕の家から自転車で五分くらいの場所にある。マンションの八階で、眺めがいい。三LDKの間取りで、窓に面した二十畳くらいのリビング・ダイニングがある。雨の日は、よっちんと三人でよくその部屋でゲームをしていた。
ケイヤのお父さんは競輪の選手だ。有名な選手だったらしい。最近は、落ち目らしいけど、現役で選手は続けている。部屋には、優勝したときの賞状とか、トロフィーとかが所狭しと飾られている。ユニフォームを着て自転車に乗っている写真やポスターも貼ってある。なかなかカッコいい。
選手は競輪が開催される前日から最終日まで、宿舎に缶詰にさせられる。電話も禁止されて、原則、連絡は取れなくなる。八百長を防止するためなんだそうだ。だから、ケイヤのお父さんはあまり家にいることがない。
お母さんは、ケイヤが小学一年のときに病気で亡くなったらしい。ケイヤはそのことについては話したがらない。一度だけ、写真を見たことがある。とても綺麗な人だった。「俺の目は、母さんの目とすごく似てるんだって」写真を見ながら、ケイヤがつぶやいた。少しだけ嬉しそうだった。ケイヤの目は、二重で、涼しげで、そしてちょっと色っぽい。クラスに、ケイヤのことが好きな女子がいるって話を聞いたことがある。誰なのか僕は気になるんだけど、ケイヤはぜんぜんお構いなしだ。
ケイヤはほとんど爺ちゃんと二人で生活している。「俺が面倒見てやってるんだ」って言ってる。ケイヤの爺ちゃんは耳が遠くて、ちょっとボケてる。
僕はマンションの自転車置き場に自転車を置くと、ケイヤの部屋へ向かった。
「よし! 逃げずにきたな!」
マンションのドアを開けると、ケイヤが嬉しそうに立っていた。
「逃げるもんか!」
「今、晩飯作ってるから、テレビでも見ててよ」
中に入ると、カレーのいい匂いがした。
家事一切は、ケイヤがやっている。部屋はいつも片付けられている。一日一回、洗濯もしていると言っていたし、料理もお手の物だ。そういう意味では、僕はケイヤのことを尊敬している。
キッチンを覗くと、やけに大きな鍋でカレーを作っている。
「何でそんなにたくさん作ってるんだ? 何人前あるんだよ、それ?」
「えーと、十四人前。俺たちが出かけた後、爺ちゃんが食うものなくなるだろ。作り置きしておくんだ。一食分ずつ冷凍しておけば、爺ちゃん電子レンジくらい使えるからな」
「三日間も、毎食カレーでいいの?」
「大丈夫だよ。前の食事が何だったかなんて、すぐに忘れるんだから」
「……」
僕はリビングに向かう。大型の液晶テレビの前のソファーに爺ちゃんがぽつりと座っている。
「こんにちは」
挨拶すると、不思議そうな顔で僕のことを見る。耳が遠いから、聞こえているのかどうかも怪しい。何度もケイヤの爺ちゃんとは合ってるんだけど、僕のことを分かるときもあるし、、分からないときもある。ケイヤの父さんと間違えたり、爺ちゃんの小学校の同級生だったという幸一くんと間違えたりする。初めはビックリしたけれど、最近は慣れたもので、僕は適当にその役になって返事をしている。
爺ちゃんと並んでソファーに座った。前にも見たことのある、ドラマの再放送がテレビに流れていた。ドラマが終わるころ、ケイヤがカレーライスをお盆に載せて持ってくる。ソファーの前のテーブルにカレーを置き、テレビを観ながら、三人並んでカレーを食べた。そのカレーは僕の母さんの作るものよりも、なぜか懐かしい味がした。
夕方の報道番組が始まった。政治家の汚職事件のニュースの後、郵便局に強盗が入り、犯人が職員を人質に取って、車で逃亡しているというニュースをやっていた。
犯人の顔写真がテレビに映し出されて、顔がゴリ田に似ていたので、二人で大笑いした。僕らが笑うと、爺ちゃんもつられて笑い出だした。その笑い方がとっても楽しそうだったので僕らは嬉しくなって、もっと笑った。
カレーライスを食べ終わると、僕の母さんから電話があった。爺ちゃんに換わったけど、ほとんど話は通じなかったみたい。多分、よほどのことがなければ二度と電話はかかってこないだろう。
僕はケイヤと並んで食器を洗い、爺ちゃんのために、カレーとご飯をジップつきの袋に一食分ずつ分けて入れた。すべて冷凍庫に入れ、これでいいのか疑問だけど、とりあえず爺ちゃんの食料は確保された。
よっちんに行くことを知らせようとしたら、ケイヤが突然行ってビックリさせてやろうと言い出した。確かにそのほうが面白そうだ。メールで、あさって予定がないかだけを聞いた。
少しだけゲームをして、明日は早いのだからということで、信じられないくらいの時間に布団に入った。興奮していたのか、時間が早すぎたせいなのか、なかなか寝付くことができなかった。
夜明けとともに出発するつもりでいた。
が、残念なことに、目が覚めたとき、日は昇りきっていた。三人前のカレーを電子レンジで温め、爺ちゃんと三人で食べた。ケイヤは、よっちんの所へ行くから二日間帰ってこないこと、食事は冷凍庫の中に用意してあることを爺ちゃんの耳元で、かなり大きな声で言った。爺ちゃんは壁の向こうの世界を眺めている。なんとなく、うなずいたようにも見えた。
「何も喰わなくたって二・三日なら、人間って死なないよな?」
ケイヤは自分に言い聞かせるように言った。
僕はデイパックに荷物を入れながら、聞こえなかった振りをする。
天気はいかにも夏休みらしい晴天で、大きな入道雲が二つ、東の空に浮かんでいた。油蝉が喧しく鳴き始める。夏の太陽が、朝の清涼を蒸発させ、その粒子がキラキラと輝いている。
僕らはマンションの前で、自転車にまたがった。ケイヤも僕のと同じようなマウンテンバイクに乗っている。
僕は地面を蹴り、ペダルを思い切り踏み込む。
――僕らの冒険は、こうしてスタートした。
3
国道に出ると、西に向かって走り始める。しばらく行くと、川原にでる。川の両脇には土を高く盛った土手があり、その上がサイクリング・ロードになっている。対岸の土手までは五百メートルくらいの幅があり、内側に、野球やサッカーのグラウンドや、芝生の広場、ゴルフの練習場などがある。
サイクリング・ロードは河口まで続いている。海を目指して進んで行く。一キロごとに海までの距離を表示した標識が立っていて、今通り過ぎたのは、海から二十七キロという表示。これがどのくらいの距離なのか上手く理解できない。海まで自分だけの力で行けるなんて、考えたこともなかった。僕らは海よりも、もっともっと遠い所まで行かなければならない。それは素晴らしいことのように思えたし、とんでもなく無謀なことのようにも思えた。風はまだ、朝の爽やかさを少しだけ残している。日差しは、もうだいぶ高くなっていて、オーブントースターの遠赤ヒーターみたいに容赦なかった。
しばらく行くと、電車の鉄橋の下をくぐる。急に日陰に入り、目の前が真っ暗に感じる。同じ日陰でも、木の陰と全然違う。家の縁の下に入ったような、湿った日陰。
ここは昔、よっちんが川へ落ちた場所だ。
――四年生のころの話だ。梅雨に入り、何日も雨の日が続いた。日曜日、久しぶりに晴れたので、僕らは三人で、自転車に乗ってここまで来ていた。
多分、ヤゴとか、カニとか、水中の生物を捕まえにきていたんだと思う。
ただ、川の水量は多く、流れも速かった。水は濁り、うねっていて、水の中の獲物を捕まえるのは無理だと諦めた。
仕方なく、石を投げて何回水面を跳ねさせることができるか競い合っていた。
勝負はだんだんエスカレートしていく。水面に平行になるように、アンダースローでできるだけ低い体勢を保つ。手首のスナップを利かせて、回転をつけて投げるのがコツだ。できるだけ平たくて、丸い石を選ばなくちゃいけない。
よっちんが力いっぱい投げたとき、足が滑りバランスを崩してしまった。ゆっくりとコマ送りのように川の中へ落ちていく。
初め、僕らは笑っていた。ケイヤはよっちんのことを指差し、腹を抱えて笑っている。僕も、ドジとか、バカとか、そんなことを言いながら笑っていたんだと思う。少しして、様子がおかしいことに気が付いた。水かさが増えていて、背がつかないみたいだ。浮いたり沈んだりしながら流されていく。
僕はまだ泳げなかった。だから、助けに飛び込むなんてことできなかった。よっちんは流されていく。流れは思っていたよりずっと速い。よっちんはどんどん流されていく。
戸惑いながら、僕は見ているしかなかった。そのとき、ケイヤが川に飛び込んだ。
――よかった、ケイヤが助けてくれる。
安堵したのは束の間で、どう見てもケイヤはよっちんを助けているように見えない。明らかに、溺れていた。
僕も飛び込もうかと思った。思ったけど、飛び込んだところで絶対助けることなんかできっこない。三人で溺れてしまうだけだ。よっちんが流されていく。ケイヤも流されていく。二人とも苦しそうにもがいていた。沈んだと思うと、しばらくして浮き上がってくる。そして、また沈む。もし、次に浮き上がってこなかったら―― 考えるだけで、頭の中がグチャグチャになる。爆発しそうだ。僕は、何も考えられず、何もできず、ただ、流されていく二人について歩いているだけだった。
下流の岸に、大きな枝が打ち上げられていた。僕は走って行って、その枝を持ち上げようとする。重い。すごく重い。濡れていてヌルヌルする。
二人は流されながら近づいてくる。早くしないといけない。全身の力を使って抱きかかえるようにして持ち上げた。川に向かって投げ出す。まず、よっちんがそれにしがみつく。続いてケイヤも枝につかまった。その重量は想像以上で、流れも速かったから、思わず枝を離してしまいそうになった。ここで離してしまったら、よっちんとケイヤを助けられない。僕は必死にその枝を引っ張った。川岸の地面はぬかるんでいて力が入らない。滑りやすくて、僕まで川に引きずり込まれそうになった。どんなことがあったって、この枝を離してはいけない。すべての力を出して支える。
枝は、僕を中心に半円を描くようにして岸に近づいてくる。ようやく、岸に生えているアシの根元によっちんの手がとどく。ケイヤもつかまろうとするが、つかみ損ねて流される。まずい! と思ったとき、よっちんがケイヤの手をぎりぎりのところで握っていた。
ずぶ濡れの二人を岸に引き上げた。よっちんは「助かったよ。二人は命の恩人だ」と、口もとに笑みを浮かべながら、興奮ぎみに言った。ケイヤは助けるはずの自分が、結局助けられてしまったことに不満があるようだった。「もう少しで、俺が助けられたのに」そう言った後に、「ありがとう」小さな声で、僕とよっちんに恥ずかしそうに言った。
ケイヤは泳げなかったらしい。泳げないくせに、よっちんを助けるために、躊躇なく川へ飛び込んだんだ。僕にはその勇気がなかった。たまたまあそこに枝が落ちていたから、二人を助けることができた。もし、枝がなかったら、僕はどうしたのだろう。二人を助けるために、川へ飛び込んだだろうか。それとも、二人が浮かび上がってこなくなるまで、見ているだけだったのか。そして、その後、僕はどうしたのだろう。
濡れ鼠のような二人と、僕は自転車を押しながら、このサイクリング・ロードを歩いていた。後ろから見ると、二人の濡れた足跡が点々と地面を濡らしていた。濡れていない自分だけが仲間はずれになったようで、申し訳ないような、切ないような気持ちになった。
小学四年のころより、ケイヤの背中はだいぶ大きくなった。僕もあのころより、身長が十センチ以上伸びている。前を走るケイヤの背中を見ながら、僕は自転車をこいでいる。
今思えば、もし、僕がケイヤに続いて川に飛び込んだら、三人とも溺れて死んでいたかもしれない。冷静に考えれば、泳げないくせに飛び込むなんてバカだ。ケイヤは思い立つと、後先考えずに行動に移してしまう。今回の自転車旅行だってそうだ。
僕は、どちらかというと慎重に考えて、結局止めてしまうことが多い。僕一人だったら、こんな計画、立てるわけがない。ケイヤと一緒にいるだけで、いろんなことに巻き込まれてしまう。――本当に困ったものだ。
――だけど、ケイヤと一緒だと、なんかドキドキする。
川を上ってくる風が、気持ちいい。川面が太陽を反射して、きらめいていた。グラウンドでは、低学年がブカブカのユニフォームを着て野球の試合をしていた。帽子とグローブがやけに大きく見える。声援をおくる幼い声。ピッチャー・ゴロで必死に走る小さなバッター。
鳩が僕らと並んで飛んでいる。こんな近くで飛んでいる鳥を見るのは初めてだ。鳩はゆっくりと羽ばたき、目の前を横切って、青い空に高く舞い上がっていった。
「気持ちいいな」
僕はケイヤの横に並び、声をかける。ケイヤは僕のことを見ると、眩しそうに笑った。ケイヤの柔らかい髪が風になびき、いつも隠れている生え際が、むき出しになる。丸みがあって、形のいい額だ。意思の強さを表す太目の眉毛。お母さんの写真に似ている切れ長の瞳。薄い唇に、少しとがった細めの顎。ケイヤの顔をこんなにじっくり見たことなんてなかった。ケイヤを好きな女子って誰なんだろう。何か、ムカついてきた。前からランニングしている、太ったおじさんが近づいてくる。いつまでも二人で並んで走れる程、道幅は広くない。僕はペダルをこぐ足に力を入れると、ケイヤの前に出た。
空はどこまでも青く、入道雲は限りなく白く、大きかった。
河口近くになると、川幅はいっそう広くなり、対岸の土手は遥か向こうに見える。大きな橋がかかり、その先に海が見えてきた。カモメが僕らの周りを滑空していた。
長い橋を渡り切ると、去年、僕が家族で来た海水浴場があった。あの時は道が渋滞して、ここに来るまでにすごく時間がかかったんだ。三歳年下の妹が車の中に飽きてしまって、文句を言い続けていた。仕舞いにイライラした父さんに怒られてた。その道を、今、僕は自転車で走っている。
海岸沿いの道は、去年と同じように渋滞していた。歩道も海水浴客で溢れていて、にぎやかだった。人を縫うように自転車で走って行く。背中に照りつける太陽さえ、気持ちよく感じた。
しばらく進むと、メインの場所を過ぎたようだ。歩道の人はだいぶ少なくなって、走りやすくなった。車の渋滞は相変わらずで、ほとんど動いていないように見える。
僕らは車を追い抜き、スピードをつけて走っていく。渋滞に飽きあきした人たちが、僕らのことを羨ましそうに眺めている。僕らは数え切れないほど車を抜き去った。「ヒャッホー!」ケイヤがうしろで、喚声をあげている。僕もそれに釣られて、なにやら意味のない言葉を叫んでいた。
昼近くになったので、道路沿いにあったハンバーガーショップでセットを買い、海岸で食べた。遊泳禁止区域なのか、海水浴客は一人もいない。サーフィンをしている人達がいるくらいだ。夏の太陽は、真上から容赦なく照らし続ける。僕らはハンバーガーを食べ終わると、デイパックの横にスニーカーを脱いで、浜辺で足を濡らした。火照った体に、打ち寄せる波が心地よかった。波が引くとき、世界が海のほうへ引っ張られているような感じがする。不安定な足の裏の感覚。
短パンのギリギリのところまで、進んでいく。波が引いたときに、ケイヤがもっと前に進む。僕は負けじとその前に出る。ケイヤはさらに僕の前に進んだ。ケイヤは僕のことを振り返ると、自慢げに微笑んだ。
ケイヤのうしろから、ひときわ大きな波が押し寄せてくる。僕は後ずさりし、そして、浜辺に向かって駆け出した。ケイヤが異変に気付いて、海のほうを向いたときには、すでに手遅れだった。波はケイヤの目前に迫っており、逃げようと浜辺のほうを向き、三歩走ったところで、波に巻き込まれた。
波が去った後、そこには人影がなくなっていた。しばらくして、海の中からずぶ濡れになったケイヤが立ち上がっる。
僕は笑いながらケイヤに近づき、手を差し出す。ケイヤは僕の手を握ると、屈託のない笑顔を見せた。ケイヤはくるりとうしろを向くと、背負い投げの要領で僕のことを投げ飛ばす。不意をつかれた僕は、そのまま仰向けにひっくり返った。丁度そのとき、大きな波がやってきて、上下が分からなくなるほどゴロゴロと転がされた。鼻に海水が入ってすごく痛かった。
僕はケイヤのことを追いかけ、うしろから羽交い絞めにして引き倒した。立ち上がると、今度はケイヤが僕に襲いかかってくる。
しばらく、そんなことを繰り返し、散々海水を飲んで、クタクタになって僕らは海岸に上がってきた。トイレの横に、簡易シャワーがあったので、服を着たまま浴びた。一回分の着替えしか持ってきていない。この日差しだから、濡れたまま走ったって、すぐに乾いてしまう。
4
ケイヤはデイパックから地図を取り出し、現在位置を確認する。
「向こうに見える、あの山を越えて、下ったところが今日の目標だ」
ケイヤの指差す方向を見る。海岸が延々と続く向こうに、半島が突き出している。その半島に、薄紫色にかすんだ山々が連なっている。あれを超えるつもりらしい。
反対側を見ると、僕らの通ってきた海岸が見える。人でにぎわう海水浴場は色とりどりのビーズを散りばめたみたいに、カラフルな模様になっている。ずいぶん走ったはずだけど、思ったほど離れていない。山までの距離の三分の一くらいしかないように見える。その先に、峠の上り坂が待っているんだ。――身体が急にだるく感じる。
僕らは自転車をこぎ始める。風が強くなってきた。向かい風だ。ペダルは重く、いくらこいでも進まない。車の渋滞は解消されて、急に閑散とした雰囲気になる。午後の日差しは、勢いを増し、正面から僕らを照らし続ける。僕らは一言も喋ることなく、黙々とペダルに力を入れる。
ケイヤが僕の前に出る。正面からの風が少し和らいだ気がする。ケイヤは風よけになってくれているのかもしれない。それでも僕はケイヤについていくのがやっとだ。ケイヤのお父さんは自転車のプロなんだ、僕なんかとは生まれ持った才能みたいなものが違うのかもしれない。だからって、負けるわけにはいかない。僕はケイヤに必死についていく。
景色が少しずつ変わる。砂浜は岩だらけの磯となり、道路沿いに干物やみやげ物を売る店が目立ってきた。山はだいぶ近づいたが、その大きさがいよいよ実感できるようになり、よけい憂鬱になる。
あの山の向こうに、よっちんがいるんだと思うと、少し力が湧いてくる。よっちんとは春休みの引越しの日から、もう四ヶ月も会っていない。
「春休みに転校することになったんだ」
よっちんが突然言い出したのは、五年生の三学期がもうすぐ終わろうとしているころだ。
僕らの小学校は毎年クラス替えがある。四年のとき、五年のときは運よく三人とも同じクラスになることができた。昼休みに教室で、六年のクラス替えで奇跡は起こるかとか、そんな話をしていたときだと思う。
突然のよっちんの発言に、僕とケイヤは、意味を上手く汲み取ることができなかった。よっちんの得意な、センスのないジョーク、なのかと思った。それにしては、迫真の演技だ。最後のほうは言葉になっていなかった。
「本当かよ?」
ケイヤが言った。
「ごめん……」
よっちんはうつむいたまま答える。
「どこに引っ越すんだ?」
僕が聞くと、よっちんは聞いたことのない土地の名前を言った。
「遠いのか?」
「この前行ったときは、高速道路を使って、車で三時間くらいかかった」
「三時間……」
「…………」
「何でそんな遠いところに越さなきゃいけないんだ」
ケイヤがイライラした声で聞く。。
「母さんが再婚するんだ。その相手がそこに住んでる。母さんの職場の工場があって、そこの人なんだ。打ち合わせに本社に来ているときに、知り合ったんだって」
怒りのようなものが湧き上がってきた。だけど、それを何処に向けたらいいのか分からない。
「そんなのあるかよ!」
ケイヤが真っ赤な顔をして怒鳴っている。
「でも、お母さんが結婚するんじゃしょうがないだろう」
僕は聞き取れないような小さな声で、自分に言い聞かせるように呟いた。
「翔はそんなんでいいのかよ!」
「いいも悪いもないだろう。よっちんの家族のことなんだから」
「なんだよ!」
ケイヤはそういうと、教室から出て行ってしまった。
「新しいお父さんと一緒に住むのか?」
僕は、ケイヤが出て行った教室のドアを見ながら言った。
「うん。そうなると思う。ごめん」
「よっちんが謝ることないだろ」
「だけど……」
よっちんは四月の最初の週に引っ越すことになっていた。僕らに残された時間は三週間を切っている。もっと話さなくちゃいけないことが、たくさんあるように思えた。もっとしなくちゃいけないことも、もっと伝えなきゃいけないことも。
残された時間を大切にしなければいけないと、思えば思うほど、態度がぎこちなくなる。時間だけが流れていった。今まで、僕らはどんなことを話していたんだろう。いつも何をしていたんだろう。自然に振舞うことができない。
六年生を送り出す卒業式があった。毎年歌っている『今日の日はさようなら』が、何でこんなに苦しいんだって、腹が立つ。
式が終わった後、僕ら三人は並んで歩いていた。公園の前まで来た。ここはよっちんが、木登りして下りられなくなった場所だ。
「本当は、今年の初めに、引越しの話はあったんだ。早く言おうと思ってたんだけど、なんだか話しづらくて、ごめんね」
よっちんが目の前の小石を蹴飛ばす。
「お正月に母さんが、再婚したいって言い出したんだ。でも、もしぼくがどうしても嫌なら断ってもいいって」
「じゃあ、断ればよかったじゃないか。よっちんだって本当はそのほうがいいんだろ?」
ケイヤはよっちんが蹴った石を、もう一度蹴る。
「うん。よく分からない……
母さん離婚してから、ずっと落ち込んでて、ぼくは母さんが元気になるようにって、いろいろ努力したんだ。わがままは言わないようにとか、笑顔でいようとか、まあ、そんなことぐらいなんだけどさぁ。どんな面白い話をしても、母さんは少し微笑むくらいで、すぐに暗い顔に戻っちゃう。夜、一人で泣いていることも、一度や二度じゃなかったんだ」
公園には桜の木がたくさんあって、満開のときは花見の客が押し寄せる。お祭りみたいになる。蕾は大きく膨らんでいるが、まだ花は咲いていない。
「それがさぁ、去年の暮れから、母さん急に明るくなって、洋服も華やかになったんだ。よく笑うようになったし。そのころに田代さん、つまり今度の再婚相手に出会ったらしいんだ。
ぼくが嫌だって言ったら、またあの暗くて泣いてばかりいる母さんに戻ってしまうかもしれないし、それに、ぼくがどんなに頑張ってもできなかったことを、田代さんは簡単にやってのけたんだ。その実力は認めないわけにはいかないよ」
桜の木に、一輪だけ花が咲いている。今年見る、最初の桜だと僕は思った。
「その相手は、どんな奴なんだ?」
ケイヤは蹴っていた石を拾い、桜の木の根元に向かって投げながら言う。
「うん。とってもいい人だよ……。太刀打ちできないくらい」
よっちんも一輪だけ咲いた桜を見つけたようだ。上を向き、目を輝かせる。
「翔くんやケイヤ君と一緒に過ごすのよりも、ぼくは母さんが笑っていられることのほうを選んだんだ。裏切り者だよね。本当にゴメン」
「そんなことないよ……」
その後の言葉が続かなかった。お母さんの幸せを願うのは当たり前だし、僕だって、よっちんの立場だったらそうしたに決まってる。だけど、やっぱりよっちんと会えなくなってしまうのは寂しい。どうしようもないことなんだろうか? どうにかすることはできないのか? そのためだったら、僕はどんな努力でもする。一生懸命勉強して、今度のテストで百点取るとか、毎日ランニングして、運動会で一等になるとか―― 今の僕には努力することすらできない。
ケイヤも桜を見つけたようだ。上を向き見つめている。そしてつぶやくように言う。
「離れたって、俺たちの何かが変わるわけじゃない。どんなに離れていたって、住む世界が違ったって、俺たちが友達だってことには変わりないんだ。会えなくなることで、よっちんの家族が幸せになるなら、それくらいは我慢する。大丈夫。何も変わってないんだから、裏切りとかそんなことあるわけないよ」
よっちんが引っ越すころには、桜は満開になっているんだろう。僕らがどんなことをしようが、感じようが、春は勝手にやってきて、夏が来て、また冬になる。
――ただ、それだけのことなんだと思う。
引越しの日、僕とケイヤは見送りに行った。
よっちんのマンションの前は桜並木になっている。穏やかな春の風が吹き、風の形に桜の花弁が舞っている。
マンションから引越し業者の人がよっちんの勉強机を運び出していた。よっちんのお母さんが、僕らに挨拶する。その声が少しはしゃいでいるように聞こえた。僕らは首をすくめるようにして、挨拶を返す。
「できるだけ、丁寧に作ったんだけど」
よっちんは僕とケイヤそれぞれに箱を渡す。開けると中には完成したガンダムのプラモデルが入っている。よっちんはプラモデルを作るのがすごく上手だ。細かいところも精確に作るし、何より塗装の技術が半端じゃない。エアーブラシを使って、何回にも分けて塗り、その後研磨までする。とても時間がかかる。よっちんの部屋に行ったとき、飾られている何体ものプラモデルがあって、僕とケイヤで、すごいなって、見とれていたんだ。
「これ、俺たちのために、わざわざ作ってくれたのか? 時間かかったろう」
ケイヤは今にも泣き出しそうな顔をしている。
「うん、ぼくにできることってこんなことしかないから、一生懸命作ったんだ」
プラモデルの部品、一つひとつによっちんの気持ちが込められているのが分かった。夜中に丁寧にパーツを組んでいるよっちんの姿が、目に浮かんだ。
「ありがとう。大切にする」
僕が言う。隣のケイヤの口が、ありがとう、と動いたが、声が出ていない。
業者の人が、荷物の搬出が終わったので、そろそろ出発すると言う。それによっちんのお母さんが明るい声で答える。
「困ったことがあったら、いつでも助けに行くからな」
多分、ケイヤはそう言ったんだと思う。今にも泣き出しそうで、途切れとぎれだ。
「頑張れよ」
僕は手を差し出した。鼻の奥がジンとして涙が出そうになった。でも、泣かなかった。もし、泣いてしまったら、本当にこれで最後になってしまうような気がしたからだ。
よっちんも泣いていない。僕の目を見つめて、しっかりと手を握り返してきた。よっちんの手は、思っていたよりも大きくてしっかりしていた。おとなの手みたいに頼りがいがあった。
よっちんは僕との握手の後、ケイヤに手を差し出した。ケイヤはその手を握る。ケイヤは顔をクシャクシャにして、涙を流している。何か言ったが、よく聞き取れなかった。
「ありがとう」
よっちんは言うと、お母さんの運転する軽自動車に乗った。引越し業者の車に続いて、よっちんの乗った車もスタートする。
よっちんはうしろを振り返り、いつまでも手を振っている。僕とケイヤも車が見えなくなるまで、手を振り続けた。
横を見ると、ケイヤが服の袖で涙を拭っている。
強い風が吹き、一斉に桜の花弁が舞い上がった。桜色に染められた世界の中、僕はケイヤと二人だけで立っていた。
5
僕はケイヤのうしろを、遅れを取らないように、ペダルをこぎ続ける。
ホテルや旅館が目立ってきた。街の中心部には、お土産を売る店や、遊技場が並んでいる。温泉街特有の雰囲気だ。
この場所は突き出した半島の付け根にあたり、ここから山を登る道に入っていく。コンビニで飲み物を買って、道路の縁石に座って飲んだ。
目の前に山がそびえ立っている。自転車で超えようなんて、まともじゃない。ケイヤだって見上げて、自信のなさそうな顔をしている。誰がこんな計画立てたんだって、文句の一つも言いたくなる。今更そんなこと言ったからって、どうなるもんでもない。引返すってわけにもいかない。まぁ、行くしかなんだろうなと、覚悟を決める。覚悟は決めたが、自分から出発を切り出す気力がない。縁石に座ったまま、地面に点々と染みを作る汗の滴を数えていた。
ケイヤは立ち上がると、両手でズボンについた砂をはたいた。座っている僕のことを上から見下ろす。仕方ない。僕はゆっくりと立ち上がり、ゆっくりとズボンの砂を落とす。そして、ゆっくりと自転車にまたがった。
坂を上り始める。勾配はきつい。とたんによろめき倒れそうになった。自転車のギアを低くしてどうにか耐える。たいして進まないうちに太ももの筋肉がパンパンに膨らんではち切れそうになる。
傾斜にそってホテルが点在していたが、やがて建物はなくなり、山の中の道となった。
僕の前をケイヤが走っている。懸命についていこうとするが、引き離されてしまう。悔しい。悔しいけどどうしようもない。僕とケイヤの距離はだんだんと開いていく。
しばらく行くと、ケイヤが止まって、地図を広げている。道が左右に分岐している。僕が追いつくと、「少し休むか」と自転車から降りて、ガードレールの横に腰をかけた。僕もケイヤの横に座る。道が分岐する場所に『ようこそ○○温泉へ』という大きな看板が立てられていた。
「やっと温泉街から出ただけか」
「登りの四分の一くらいきたよ。大丈夫か?」
ケイヤが地図を見ながら言う。
「ェヘェェェ……」
僕は力なく笑うしかなかった。
「この道、どっちに行っても峠には出られそうだけど、左は大回りしてるから、右から行ったほうがきっと近いと思うんだけど」
ケイヤは僕に地図を見せた。僕は地図を見る余裕もなく、見もせずに頷いた。
出発する。太陽は山の斜面の向こう側に隠れている。空はまだ明るいけど、木々に囲まれた道は薄暗い。ヒグラシがいたるところで鳴いている。カナカナと高音で鳴き続ける声は不気味だ。また僕はケイヤに引き離され始める。負けるか、と思うのは気持ちだけで、身体が言うことを聞かない。せめて、歩いたりせず、自転車でこの山を上りきってやる。汗が額から流れて、目に入る。それがすごくしみる。涙が出る。何度も拭うんだけど、止まらない。
車はときどき擦れ違うくらい。近くに自動車専用の有料道路が走っているから、多くの人はそっちを使うんだろう。
うしろからすごいスピードで白いワゴン車が上ってきて、僕らを抜き去っていった。前を行くケイヤのすぐ脇を通り過ぎて、ぶつかったんじゃないかってドキリとしたけど、接触はしなかったみたいだ。
空は青からオレンジ色に変わってきている。ケイヤは僕の遥か先を走っている。僕だって、何度もくじけそうになりながら頑張ってるんだ。
うしろを振り返ると、上り口の温泉街が見える。けっこう高くまで上ってきている。その向こうに通ってきた海岸がかすんで見える。その先にも半島があって、海岸は全体で大きな弧を描いて湾になっているのが分かる。
――何かすごいところまで来てしまった。
多分、もう少しで峠にたどり着くはず。峠さえ越えてしまえば、あとは坂を下るだけだ。この坂を上り終えたら、峠かと思う。しかし、坂を越えると、少しの間平坦な道になって、先にまた上り坂が待っている。今度こそ! その先に頂上があると信じて、ペダルを踏む。
何度も失望を繰り返している。心が折れそうになった。そのとき、次の坂の頂上にケイヤが立っているのが見えた。ケイヤが手を振って笑っている。
僕は道いっぱいにフラフラしながら、ケイヤの元にたどり着いた。ケイヤは待ちかねていたようで、地図を見ながら言う。
「お疲れ! あとは下るだけだから、このまま行こうぜ。早くしないと日が暮れちゃう」
峠では、道が二股に分かれていて、ケイヤは左の道を下っていく。僕はデイパックからペットボトルを取り出し、水分補給するとケイヤの後に続いた。
「イエェェェ――」
全身に風を受けながらケイヤが叫んでいる。僕もそれに続く。風が気持ちいい。景色がうしろに吹っ飛んでいく。今までの苦労がすべて報われた気がする。
「麓まで競争な」
僕が並ぶと、ケイヤは楽しそうに言い、スピードを上げる。左右に大きく蛇行する坂道で、ケイヤはほとんどブレーキをかけずにカーブに入っていく。僕は我慢しきれず、ブレーキをかけてしまう。またもやケイヤに引き離される。
ケイヤはものすごいスピードで坂を下っていく。僕も必死に追いかける。
右側に分岐する道があったが、ケイヤはスピードを緩めずにそこを通過する。右側の道は、斜めうしろに分岐していたので、僕らの方向からだと見づらい。目的地を指す標識が出てたけど、木の枝が覆いかぶさって、よく見えなかった。
ケイヤはすでに前のカーブを曲がっている。僕は見失わないようにするのが精一杯だ。
そのとき、視界が開け、海が見えた。
――背筋が凍った。
「ケイヤ!!」
あらん限りの声を出した。
「ケイヤ! とまれ!!」
ケイヤは遥か先を走っていて、僕がどんなに叫んだって、声なんか届かない。
「ケイヤ! とまってくれよ」
声が届かないのは分かっているが、叫び続けた。
――お願いだから、ケイヤ気付いてくれ。
僕は叫びながら泣いていた。「ケイヤ!」叫ぶたびに、声はむなしく山々に吸収されていく。涙と鼻水とよだれで、僕の顔はグチャグチャになった。胃の辺りがムカムカして吐き気がした。全身を寒気が襲う。
――多分、今僕が感じているのは、恐怖だ。
目の前に広がる湾の形は、見覚えのあるものだった。麓に温泉街の街並みも見える。ケイヤはカーブを抜けることに集中して、景色なんて見ていないんだ。こんなことがあるはずがない。これは夢なんじゃないか。本気でそう思った。
僕らは上ってきた坂を、違う道で下っているんだ。
僕がカーブを抜けても、ケイヤの姿は見えなかった。次のカーブをすでに曲がってしまっているんだ。僕はもう叫ぶのを止めた。携帯を持っていないから、ケイヤに連絡することもできない。ケイヤについていくしかない。何も考えられなかった。ブレーキを握ることさえ億劫に感じた。
俺、方向音痴なんだ、そう言っているケイヤの姿が脳裏に浮かんだ。あれは確か、よっちんと三人で駅前に映画を見に行ったときだ。映画館の前で待ち合わせしたら、ケイヤがいつまで待っても来なくて、後で聞いたら、全然違う方向に行ってたんだ。
見にいったのは何の映画だったけ? 結局その映画は見れたんだっけ?
――何も思い出せない。
――もうそんなのどうでもいい……
覆っている木々が途切れ、視界が開けるたびに海は近づいてくる。僕はもう何も感じなくなっていた。
しばらく行って、道が合流したところで、ケイヤが待っていた。目がキョトンとして、顔が青ざめているように見える。ケイヤのうしろには『ようこそ○○温泉へ』と書かれた大きな看板が立っていた。
「道……、間違えたみたいだ……」
「……」
僕は何も答えない。
「……でも、今日中に山を越えておかないと、……明日、よっちんの所までたどり着けなくなる……」
「…………」
僕は何も答えない。
もう日は落ちてしまって、真っ黒な雲が空を半分くらい覆っている。温泉街にネオンが灯りはじめる。
「……もう一回上るしかないんだ」
ケイヤは言うと、自転車をこぎだした。
僕はもう自転車に乗る気力はなくなってしまって、自転車から降りると、それを引いて歩いて坂道を上りはじめる。ケイヤもしばらく進んだ後、自転車から降りて、歩きだす。どこかで雷の音が響く。
僕らは十メートルくらいの距離をあけて、一言も言葉を交わさず、自転車を押して、坂道を進んだ。
急に空が暗くなる。一瞬、閃光が走り、しばらくしてから地響きのような、雷鳴が轟く。
下からパトカーがサイレンを鳴らしながら上がってくる。こんな場所で、自転車を押していて、何か言われるかと思ったが、先を急いでいるらしく、僕らには目もくれずにパトカーは峠のほうへ消えていった。
大粒の雨が自転車のハンドルを握る右手の甲に当たった。雨か? 思ったときに、額に滴を感じた。首筋、左腕、と続いた後、一斉に雨が落ちてきた。
夜のような暗さになり、時折、稲妻が光る。間をおかないで雷鳴が響く。雲に近いせいか、今まで聞いたどんな雷よりも大きな音で、地面まで揺れている。雷が鳴るたびに、身体がすくみ上がる。自転車は金属でできているから雷は落ちやすいのだろうか。風は急に強まり、大きな木々がしなりながら揺れる。身体はあっという間にずぶ濡れになった。体温が奪われていく。引き返すわけにいかないし、止まることもできない。強い風雨に前を見ることもできずに、自転車の前輪を見つめ、ハンドルに力を込め、ひたすら、黙々と、坂を歩んでゆく。
僕がケイヤと喧嘩したときも、今みたいに強い雨が降っていた。三年の夏休みが終わって、二学期にも少し慣れてきたころだ。
昼休み、雨が降っていたからグラウンドには出られず、僕らは教室で話をしていた。
「昨日、梶山公園でこんなにでかい蛇を見たんだぜ」
ケイヤは両腕を一杯に広げて、蛇の大きさを示す。
僕はカチンときた。なぜかって言うと、昨日の日曜日も一日中雨だったからだ。雨の日にわざわざ梶山公園なんか行くわけがない。ケイヤのお得意のホラが出た。
ケイヤはよく嘘をついた。僕が虫が嫌いだと言うと、次の日に、体育館の裏で三十センチの大きなムカデがいたとか、自分の家には毎日十匹以上のゴキブリが出て、捕まえてビンに入れて飼っているだとか、そんな話をし始める。学校の帰りにUFOを見て、そこからパンダに似た宇宙人が出てきた話とか、夜眠れないときに墓場を散歩してたら変な世界に紛れ込んでしまった話とか、薄々怪しいとは思っていた。
前の週にケイヤが、自分の父親がオリンピックに出たことがあると言い出した。僕は半信半疑だった。家に帰って、父さんに聞いたら、そんな選手は知らないと言う。ネットで調べてもらったけど、自転車関係の競技で辻田なんて選手は、何年遡ったっていなかった。
やっぱり嘘だった。
僕はそのことで、敏感になっていたんだと思う。
「昨日、一日中雨だったのに、何で公園なんか行ったんだよ!」
僕は初めから喧嘩腰だった。
「あっ、違った、おとといだ」
僕はその一言で、キレてしまった。
「嘘つき!」
「嘘じゃないよ。昨日とおととい間違えただけだって」
気付いたときには、ケイヤの右頬を殴っていた。初めて、人のことなんて殴った。人差し指と中指の付け根が、ジンジンして痛かった。ケイヤはポカンとした顔をしたまま、突っ立っている。
「ケイヤの言うことなんて、全部嘘じゃないか! 最初に昨日って言ったじゃないか。嘘がばれたからって、また嘘つくのかよ。川原にワニなんかいないし、蟻の行列の中に、全身を黒く塗った小人が混じってるわけないだろ! お前のお父さんだって、オリンピックなんて出てないじゃないか!」
怒鳴っているうちに、感情が高ぶってくる。呼吸が苦しい。頭の芯で何かが弾けた。僕はケイヤに飛びかかった。そのとき、スローモーションで近づいてくるケイヤの拳が見えた。僕の左目にゆっくりと迫ってくる。直後、今まで受けたことのない衝撃が顔面に走った。――なるほど、殴られたときには、本当に星が見えるんだ、なんて間の抜けなことを考えながらうしろに倒れる。
「ふざけんな!」
僕は立ち上がると再びケイヤに飛びつく。今度はみぞおちにケイヤの蹴りが入る。息ができなくなって、目の前がクラクラする。だけど、僕は蹴り上げたケイヤの右足を抱えて離さなかった。そのまま突進したら、ケイヤはバランスを崩して倒れた。僕はケイヤの上に馬乗りになる。ケイヤの両肩に膝を乗せるとケイヤは動かなくなった。
「ケイヤの言ってることは、全部嘘じゃないか!」
僕はケイヤの胸倉をつかんで、上下に揺らす。ケイヤは悲しそうな目で僕のことを見ている。ケイヤは動こうとしない。
「この前だって……」
言葉が詰まった。
――何でそんな悲しそうに見るんだ。嘘をついたケイヤが全部悪いんだろ。もうそんな目で見るなよ。
――まずい! このままでは泣いてしまう。
クラスにいた全員が僕のことを見ていた。三年生にもなってみんなの前で泣いてしまったら、一生取り返しのつかないことになる。一言でも発したら、声が震えて、嗚咽になってしまいそうだ。
僕は慌てて教室を飛び出した。
一人で過ごす昼休みは、とても長く感じた。いつもなら三人で喋ったり、グラウンドでドッチボールしている時間だ。他の友達が体育館で遊んでいるのに入れてもらう気にもなれない。かといって、ケイヤがいる教室に戻るのも嫌だ。トイレで鏡を見ると、左目の下が、少し赤くなって腫れていた。手で触ると痛みが走る。僕は小学校の全ての階の廊下を歩き回り、時間を潰した。雨はまだ強く降り続いている。廊下の窓から外を見ると、泥の中に沈んだように暗かった。おやゆび姫に出てくる、金持ちのモグラの住む世界を思い出す。太陽のない暗い世界。きっとこうやって土の中に通路があって、教室がモグラの家だ。確か、おやゆび姫はツバメに助けられて、お花の国へ連れて行ってもらったんだ。
窓の外を見る。
――僕をどこかへ連れ出してくれそうな者は、どこにもいなかった。
やっと、五時間目の開始のチャイムが鳴った。僕が教室に戻ると、ケイヤとよっちんが何か話していた。僕のことを見て、話すのをやめる。僕はそのことで、よけい腹が立ってきて、乱暴に次の授業の教科書を取り出すと、わざと音をたてて机の上に放り投げた。
ケイヤの頬は赤くもなっていない。僕の右手は中指の辺りがジンジン痛んで、少し赤くなっていた。頭の中がシワシワし始めてきた。気が付いたら下唇を強く噛んでいて、かすかに鉄っぽい味がした。
五時間目が終わって、六時間目が始まるまで、僕は自分の席に座ったまま、窓の外を見続けていた。ケイヤはうつ伏して眠った振りをしている。よっちんがどうしたらよいか分からないみたいで、立ち上がって廊下へ出てみたり、戻ってきて席に座ったり、また廊下へ出てみたりと、三回くらい同じことを繰り返していた。
六時間目の授業が終わると、僕は一番に席を立ち、そのまま校門に向かった。校門を出たところで、よっちんが追いついてきた。
雨は小降りになったけど、二人とも傘を差したまま歩いている。よっちんは並んで歩くばかりで、何も話しかけてこない。雨の音と、よっちんと僕の湿った足音だけが聞こえる。
「なに?」
よっちんはなんにも悪くないのに、まるで責めるような口調になってしまう。
「うん」
よっちんは困ったように、頭をかいている。
「前から思ってたんだけどさぁ、ケイヤの言ってることって、嘘ばっかりじゃん! 僕は嘘つきは大嫌いだ。もう我慢できない」
「うん……」
「よっちんも、そう思うだろ?」
「だけど……」
「なんだよ?」
「……ケイヤ君のお父さんがオリンピック出たのは本当だよ。ぼく達が生まれる二年前にやった冬季オリンピックのスケートの選手だったんだ」
「冬のオリンピックまでは調べなかったけど……」
「ケイヤ君のつく嘘って、全部ぼく達を楽しませようとしてついているんだよね」
よっちんが傘をたたみながら、つぶやく。
確かに、ケイヤの嘘は、僕らを笑わせたり、怖がらせたり、つまり楽しませようとしてついているのかもしれない。自分を大きく見せようとか、見栄を張って嘘をついているわけじゃない。それは分かる。そして、僕らがケイヤの話で笑うと、ケイヤは本当に嬉しそうな顔をする。だからって、嘘をついていいってことにはならない。ケイヤがちゃんと謝るまで、僕は絶対に許さない。絶対にだ! ――僕はそう思った。
その後どうしたのか、ケイヤは僕に謝ったのか、思い出せない。僕があらためてケイヤのことを許したという記憶もない。気が付いたら、僕らは、いつもみたいに遊んでいたのだと思う。ただ、あのとき以来、ケイヤは嘘をつかなくなった――
雨は一段と激しさを増し、土砂降りだ。前を自転車を押して歩くケイヤの姿も、霞んでよく見えない。突然、閃光が光り、ケイヤの背中がフラッシュを浴びたように、浮かび上がる。地響きを伴う雷鳴が轟く。道を渓流のように水が流れる。
ケイヤはときどき振り返るが、僕と目を合わせようとはしない。僕がついてきているのを確認すると、すぐ前を向いて、自転車を押す。
ケイヤだって、わざと間違えたわけじゃない。それは分かっている。だけど、ゴメンの一言ぐらいは言うべきだろ。あいつは何で謝らないんだ! やっぱり腹が立つ。
最初、看板があった二股道でケイヤが僕に地図を見せたとき、僕は地図を見ることもしなかった。判断も責任もケイヤに押し付けていた。そして、ミスをしたときだけ責めるのは、卑怯なのか。僕にはケイヤを怒ったりする資格があるのか。よく分からない。疲れた。何も考えたくない。もう眠い……
いつの間にか、雨は小降りになっている。日は沈み、周りは真っ暗だ。道路灯に照らされた見覚えのある景色。やっと峠にたどり着いた。ケイヤが地図を広げる。僕は横に並んで、その地図を見る。
「さっき、この道をケイヤが見逃して、左のほうへ行っちゃたんだよ!」
責めるつもりはもうなかったけど、語気が少し強くなる。
「うん……」
ケイヤはそれだけ言うと、自転車に乗って坂を下り始める。
自転車のライトを点けるが、二人の持っているLEDライトは、こちらの存在を相手に知らせるもので、照明としての機能は高くない。峠に道路灯があった他は、道路沿いの照明はない。空はまだ厚い雲で覆われていて、自転車のライトがなければ、目の前にかざした自分の手も見えないほど暗い。僕はケイヤのライトを頼りに進んでいる。ケイヤはほとんど先が見えないはずだ。目の前に、急に山肌が現れ、ケイヤの自転車が危なくそれに接触しそうになる。バランスを崩して足をついた。
ケイヤは再びこぎ出そうとする。
「もう無理だよ!」
ケイヤは、黙って走り出すが、何メートルも進まないうちに、側溝に落ちそうになって慌てて自転車を止める。
「だから無理だって! これ以上進めないよ」
道の脇に車が一台止められるほどのスペースが開いている。僕はそこに自転車を放り出すと、地べたに座り込んだ。雨はやんだようだ。地面は濡れているが、僕だってビショビショだ、構うことはない。ケイヤは僕から三メートルくらい離れたところに座る。自転車のライトは点けてあるが、真っ暗でほとんど何も見えない。ケイヤが闇の中に薄っすらと浮かんで見える。僕と同じように膝を抱え込んでうつむいている。地面がヌルヌルして気持ち悪い。絶対、虫とか出てきそうだ。そう思うと、何も見えないのはすごく怖い。風で揺れて物音がするたびに、僕はビクリとする。二の腕のところで、何かが動いた気がした。慌てて払いのける。見えないから、虫がいたのか、滴がたれたのか分からない。とてもじゃないけど、こんなところで眠れるわけがない。
――だから嫌だっていったんだ!
お腹が減った。山の下まで降りる予定だったから、食べ物なんて持ってない。予備の食料くらい何か買っておけばよかったんだ。僕はデイパックの中からペットボトルを出して、水を飲む。
ケイヤは膝を抱えたまま動かない。まさか一人で寝てるんじゃないだろうな!
涙がこぼれる。止まらない。嗚咽が漏れそうになる。ケイヤに泣いてることを気付かれるくらいなら、死んだほうがましだ。歯をくいしばって、舌を上あごに押し付け、必死に堪える。落ち着いたかと思うと、次の感情の波がやってくる。左右の膝の間に顔をうずめて、呼吸を整える。ゆっくりと息を吸う。その息をゆっくりと吐く。息を吸う。吐く……
「おい、起きろよ」
ケイヤの声で僕は目を覚ます。どうやら、膝を抱えたまま眠ってしまったらしい。目を開けると、周りの景色が違っている。全てのものが青白い光に包まれている。濡れたアスファルトに僕の影がうつっている。ケイヤの顔もハッキリ見える。
空を見上げると、覆っていた雲は消え去り、真ん丸の月が高く昇っていた。手も服も、倒れた自転車も、全てが青く輝いている。木々の葉についた水滴が、月光を反射して煌き、巨大なクリスマス・ツリーのように見える。世界の全てが、青いセロファン紙を通して見たようだ。四年の夏休みの工作で作った、水族館を思い出す。煎餅の箱に青いセロファン紙を張って、中に厚紙を切り抜いた魚やサンゴを貼り付けた。僕はその世界に入り込んでしまったような錯覚を覚えた。
――まるで海の底みたいだ!
「もう少しマシなところまで移動しよう」
ケイヤはもう自転車に手をかけている。
道路に引かれたセンターラインが僕らの進む道を示すように光っている。これなら十分進むことができる。風は強く、濡れたまま、眠ってしまったため、真夏とはいえ身体は冷え切っていた。
「せめて、この風が防げる場所を探そう」
ケイヤは自転車にまたがり、僕のことを振り返る。
「う、うん」
僕は目をこすりながら立ち上がると、倒れていた自転車を起こす。身体の節々が堅く固まっている。一度伸びをして、自転車にまたがる。
それほどスピードは出さない。海の底を滑らかに進むイルカの気分だ。さっき間違えた、分岐を右に曲がる。両脇を木々に囲まれているが、正面には大きな満月がある。月の光がこんなにも明るいなんて、信じられない。青い世界が緩やかにうしろに流れていく。
カーブを曲がると、海が見えた。前とは違う形の海だ。月は海上にあり、海にも大きな月が揺らめいている。その周りに、航行する船のライトが瞬いている。陸地には家々の光が天の川のように連なっている。
僕はケイヤに並んだ。
「何か、すごいな」
「うん。宇宙旅行してるみたいだ」
ケイヤの瞳の中にも、無数の星が輝いているように見えた。飛んでいるみたいだった。ツバメの背中に乗って、僕は青い宇宙の中を飛んでいるんだと思った。
「ホント。すごいよな!」
「すげーな!」
「「スッゲー!」」
僕らは二人揃って、何度もなんども「スッゲー!」と叫びながら、坂を下った。
6
峠をほぼ下りきった辺りに、レストラン『サニー』と書かれた看板が立っている。白い壁にピンク色の屋根、開店当初はメルヘンチックな店だったんだろう。しかし、白い壁はいたるところのペンキが剥がれ、窓ガラスは割れ、内側から乱暴にベニヤ板で塞がれている。廃業して、そのまま放置されているようだ。
ケイヤはその前で自転車を止める。
「ここなら、中に入れるんじゃないか?」
「でも、何かやばそう」
「こんなところ、誰もいるわけないよ。朝になったら出て行けばいいだろう」
僕が言っているのは、幽霊とかお化けとかそういうのがいかにも出そうだと言ってるんだ。でも、お化けが怖いなんて言えない。
「テレビだと、犯罪をした逃走犯とか、こういうところに隠れてるよね」
「そんなのがいたら、捕まえて賞金もらおうぜ」
ケイヤは自転車から降りると、レストランの入り口に向かう。さすがにドアの鍵はかかっている。歩いてレストランの裏に回り、裏口や窓を一つひとつチェックする。
「翔! ここから入れる」
ケイヤが先から手招きする。店の裏側の窓が開いたようで、ケイヤの上半身はすでに半分中に入っている。僕がその窓の手前まで来たときには、ケイヤはすでにレストランの中に入っていた。
「大丈夫かよ?」
「大丈夫だって。早く来いよ」
ここで、躊躇することは男としての沽券にかかわる。
僕は半分開いた窓から身体を忍び込ませる。
入ってきたところを見ると、埃の溜まった床に、青白い影が窓枠の形に浮かんでいる。奥までは月光は届かず、闇がひかえている。ケイヤは部屋の探索にいっているみたいだ。姿が見えない。僕は不安に駆られ、「ケイヤ?」小さな声で呼びかける。
返事はない。
「ケイヤ!」
少し声を大きくするが、まだ返事がない。
目が慣れると、店の中は意外に広い。部屋の隅に、円形のテーブルやスチールの椅子が積み上げられている。カウンターの向こうに大きな厨房がある。壊れた棚や、廃材が積み上げられているようで、青白い闇の中に、不規則なシルエットが浮かんでいる。かび臭く澱んだ空気、湿気。汗が滲んでくる。くしゃみが出そうで、鼻がムズムズする。
「ケイヤ!!」
僕は手探りで奥に入っていく。窓からの月光に照らされていない影の部分は、真の闇があり、いくら目を凝らしても何も見えない。
――ガガッガン。足元にあった空き缶を蹴ってしまたらしく、静寂の中、けたたましい音が響く。僕は自分の出してしまった音に驚き、身をすくめる。そのとき、うしろに人影があった。
「ヒィッ――」
「奥まで行ってきたけど、暗くて何も見えないな」
「ケイヤ、脅かすなよ」
「何そんなビビッてるんだよ」
「ビビッてなんかいないよ!」
「ビビッてるって――」
「しーっ! 今、向こうの方から、何か音がしなかったか?」
カウンターの横から、通路が奥につながっている。多分その奥に、レストランの個室とか、従業員用の部屋とかがあるんだろう。そっちのほうから、床を金属のようなもので擦った音がした。
「音なんか聞こえなかったぞ。やっぱりビビッてんだよ」
「しーっ!」
僕とケイヤは顔を見合わせた。今度はケイヤにもハッキリ聞こえたはずだ。ドアが軋みながら開く音がした。
「隠れろ!」
僕らは積み上げたテーブルの下に潜り込んだ。
ドアが閉まり、足音が通路を近づいてくる。一歩いっぽのリズムが違う。多分、どちらかの足を引きずっているんだ。怪我をしているのかもしれない。足音はゆっくりと僕らのほうへ近づいてくる。
僕らのいる部屋の中央に、人影が見えた。右手に何かを握っている。影はやはり足を引きずっている。光の届かない暗闇に隠れている僕らのことは見えないはずだけど、その影は迷いもせず、こちらへ近づいてくる。
影は目の前で止まった。右手のものを僕らのほうへ突き出す。
突然のあまりの眩しさに、何が起きたのか分からなかった。強い光に照らされ、目が眩む。右手に握られていたのは、懐中電灯だった。光の向こうにいる人物の姿は眩しくて見ることができない。
「お前ら、こんなところで何しているんだ!」
低音の声が響く。僕は懐中電灯の光をさえぎるように手を前にかざしたまま、動けない。
懐中電灯の光りが僕らの顔から外され、やっと姿を見ることができた。
白髪交じりの長い髪。それに負けない長い髭。真夏だというのにマントを被り、まるで映画で見た、イギリスの魔法学校の校長のようだった。
「ダ、ダンブルド……」
「こいつ、浮浪者だ」
ケイヤは僕にしか聞こえないくらいの声で言う。確かによく見ると、髪の毛はボサボサだし、髭は伸び放題。マントと思ったのは汚い毛布だった。そして、ちょっと臭い。
「家出でもしてきたか」
浮浪者のおっちゃんは、威厳のある低い声で言った。
僕らはいつでも飛びかかれる体勢を取っている。
「ここはお前の家じゃないだろ!」
「生意気なことを言うな。朝までは目をつぶってやる。日が昇ったらすぐに出て行け」
そのとき、僕のお腹が大きな音をたてた。腹が減ると、本当に力が入らないんだ。
「なんだ、お前ら腹減ってるのか?」
浮浪者の前歯は二本しかなく、そのほかは抜け落ちている。歯と歯の間から、妙に赤みの強い舌が見える。
「食い物、もってないんか?」
「……」
「いつから食ってない?」
「……昨日の昼から」
「――いい物があるんだ。食わしてやろうか?」
浮浪者は二本しかない前歯をむき出し、ニタニタと笑っている。
お腹は減ったが、浮浪者に恵んでもらうつもりはない。だいたいどんなもの食べさせられるか分かったもんじゃない。
「いいからついてこい」
浮浪者は左足を引きずりながら、奥の部屋へ向かっていく。僕とケイヤはいつでも逃げ出せる体勢を取りながら、後についていった。脚が悪そうだから、逃げようと思えば、いつでも逃げだせる。
通路に出ると、左右にドアがある。浮浪者は右のドアを開けて入っていく。場所としては、厨房の奥になる。十畳ほどの広さで、従業員の休憩所とかに使っていたのかもしれない。奥の半分くらいのスペースには畳が敷いてある。僕らが中に入ると、「ちょっと待ってな」と言い残し、浮浪者は部屋を出て行く。
懐中電灯の明かりがなくなると、部屋は闇に包まれる。
「やばいって」
僕はケイヤに向かって言った。ケイヤの顔は暗くてよく見えなかったが、目だけが青く光っている。ケイヤまでが悪魔の使いで、僕は大きな罠に嵌められているんだ、なんて妄想してたら、背中がブルって震えた。
「なんかあったら、あんな浮浪者一撃で倒してやるよ」
ケイヤは口で言うほど、喧嘩が強くない。そして、僕はケイヤよりもっと喧嘩が弱い。おっちゃんは足は引きずっているが、体格はけっこういい。身長だって、僕の父さんより大きいくらいだ。でも、二人がかりならどうにかなるかもしれない。
僕らは畳の縁に座っていた。しばらくすると、通路から浮浪者の足を引きずりながら歩く足音が近づいてくる。その度に、通路を照らす懐中電灯の光が左右に揺れる。部屋の入口に浮浪者は立った。
――左手に紙袋を持ち、右手にはロープを握りしめている。
うしろ手にドアを勢いよく閉める。バタンと大きな音がして、ケイヤが驚いてビクリとする。
僕はケイヤと顔を見合わせる。窓はベニヤ板で覆われ、ドアは浮浪者の後ろだ。浮浪者を倒さなければ逃げられない。浮浪者はランタンを持っていて、それに灯を点す。部屋はオレンジ色の光に照らされ、浮浪者の影が大きく揺れる。
「お前ら、服を脱げ!」
――浮浪者は命ずるように言った。
「いいから早く脱げ! そんな濡れた服を着てたら、風邪引いちまうぞ」
浮浪者のおっちゃんはロープの端をカーテンレールにかけ、もう片方を壁に刺さった釘にかける。紙袋の中から洗濯ばさみを取り出し、僕に手渡す。
「脱いだら、これでロープに干しとけ」
僕とケイヤは、渋々着ていたTシャツと短パンを脱いで、ロープに洗濯ばさみで止める。デイパックの中身も濡れていたので、着替えに持ってきていた服も一緒に干す。白いブリーフ一枚しか身につけていないケイヤの痩せた身体が、オレンジ色の光に照らされている。
おっちゃんは、紙袋からカセットコンロを取り出すと、鍋にペットボトルから水を入れ、沸かし始める。その中に、缶を入れる。
「お前ら、運がいいぞ。丁度これを仕入れてきたところだ。賞味期限は二週間過ぎてるけど、缶入りのものの賞味期限なんて有って無いようなものだ」
鍋の中を見ると、入れられているのは缶入りのポタージュスープだった。それを湯煎で温めてくれているらしい。
「寒かったら、そこにある毛布にくるまってていいぞ」
横を見ると、普段おっちゃんが使っているのだろう毛布が畳の上に置いてある。多分、洗ったことなどないのだろう。何ともいえない風格がある。とてもじゃないが、恐れ多くて触ることさえはばかられる。
「家出か?」
「ううん、違う」
僕は引っ越した友達のところへ向かっていること。これまでの経緯をおっちゃんに話した。このおっちゃんは信用しても大丈夫なような気がしたからだ。
「そりゃまた、えらいシンドイことしとるな」
ランタンとカセットコンロの火に照らされて、鍋を覗き込んでいるおっちゃんの姿は、やっぱり魔法使いにしか思えなかった。
「おっちゃんはここに、一人で住んでるのか?」
ケイヤは目の前の鍋に話しかけるように言った。僕らは鍋の前に膝を抱えて座っている。
「まあな」
「寂しくない?」
「もう慣れたよ」
笑うおっちゃんの口に、二本しかない前歯が光っている。
「何でこんなところに住んでるんだ?」
「まぁ、いろいろあってな。ほれ、温まったぞ、飲んでみぃ」
おっちゃんは鍋から直接手づかみで缶を取り出すと、僕とケイヤに手渡した。
それは手で持つことができないほど熱くなっていて、僕らは上に放り投げてはキャッチし、持っていられなくなってまた上に放り投げる。手から伝わるその熱が気持ちよかった。
賞味期限のことは少し気になったが、もうそんなことはどうでもいいくらいお腹が減っていた。缶コーヒーみたいにプルトップを開けると、直接飲むことができる。
一口飲むと、その熱が、コーンの芳ばしい香りが、舌の付け根に染み入るような甘みが、疲れきった僕の身体の中へ溶けていく。僕とケイヤは、うっとりとスープの缶を見つめた。
今まで食べた物の中で、一番美味しい。世の中にこんなに美味しいものが存在したなんて、奇跡だ。目の前にいるのは、本物の魔法使いなのかもしれない。
「こんなところに一人でいて、怖くないの?」
僕は幸福な気分の中、おっちゃんに聞いた。
「ん? 人は夢とか希望を持っているから恐れを感じるんだ。夢も希望もなければ、ほとんどの怖いものもなくなるんだよ」
僕はおっちゃんの言っていることの意味がよく分からなかった。多分、大人は多少のことでは怖くないのだろうと思った。
魔法のスープが身体中にいきわたると、心地の良い眠気が襲ってきた。僕らはいつの間にか畳みに横になり、眠っていた。夜中に目を覚ますとランタンの灯は消され、おっちゃんは奥の毛布の中に包まっていた。
すぐ隣にケイヤが仰向けに寝ている。ケイヤの裸の肩と僕の肩が触れている。そこからケイヤの温もりが伝わってくる。ケイヤの呼吸する音が聞こえる。その音に合わせて、ケイヤの胸が上下に動いている。見ているだけでなんとなく心が温かくなる。もしかすると、こういうのが夢とか希望とかいうものかもしれないと、ふと思った。僕はケイヤといることで恐怖を感じているのだろうか。よく分からない。ただ、もしケイヤがどこか遠く、自転車なんかじゃ絶対に行けないような場所に行ってしまって、二度と会えなくなることを考えると、なんだか怖いなとは思った。
次に目覚めたとき、窓を塞ぐベニヤ板の隙間から、透き通った、境目のハッキリした光りが差し込んでいた。身体を起こそうとするが関節が悲鳴を上げる。足と腰が自分のものでないように固まっていた。ケイヤはもう起きて、窓のそばに立っている。おっちゃんの姿は見当たらなかった。カセットコンロやランタンも片付けられている。それらがあった場所に、コーンスープの新しい缶が置かれている。
ロープに吊るされたティーシャツを触ると、まだ少し湿っていた。気持ち悪かったが、洗濯ばさみを外してそれを着る。ちょっと我慢すればすぐに乾くだろう。
「おっちゃんは?」
「俺が起きたときには、もういなかった」
荷物をデイパックに詰め、コーンスープを手にもって部屋を出る。レストランには窓の隙間から漏れるなんスジもの光が、重なり合うように幾何学模様を作っている。
入ってきた窓から外に出ると、そこには光が満ちていた。眩しさに慣れるまで、しばらく目が開けられない。薄目を開けながら周りを見回すが、おっちゃんの姿はなかった。
自転車の脇で、冷たいままのコーンスープを飲む。魔法が解けてしまったのか、昨夜ほどの美味しさは感じられない。
おっちゃんが戻ってくる気配もなかったので、埃まみれの窓ガラスいっぱいに、『ありがとう』と指で書いてから、自転車に乗った。
7
山の斜面はまだ途中だったようで、緩やかな下り坂がしばらく続く。自転車は快適にスピードを上げ、木陰に入れば、わずかに残った朝の空気が僕らの髪をなびかせる。
道が平坦になると、日を遮る樹木は姿を消し、田園の光るような緑が目の前に広がる。雲はひとかけらもなく、突き抜けるような青空がどこまでも続いている。
建物の数が次第に増えてくる。最初にあったコンビニで僕らはおにぎりと飲み物を買った。時間は九時を過ぎたところだ。
「よっちんに電話してみようよ」
よっちんに近づいていると思うだけで、気持ちが高ぶってくる。僕はコンビニの前のガードレールに寄りかかり、おにぎりの包みを剥がしながら言った。
「そうだな、近くまで来てるって言ったら、よっちん驚くかな?」
ケイヤも興奮しているようだ。日焼けした真っ黒な顔に、目だけが輝いている。
「そりゃぁ、きっと驚くよ。ビックリしたよっちんの顔、直接見たかったな」
ケイヤは携帯電話を取り出すと、よっちんの携帯にかける。
輝いていた瞳が光を失い、眉間に皺をよせながら携帯をたたむ。
「電源が入ってないか、電波の届かないところにいるって」
僕らは目を合わせ、同時にため息をつく。
「まぁ、行くしかないか。早く喰って出発しようぜ」
ケイヤは携帯をしまうと、おにぎりを頬張った。
建物の間隔が狭まって、高いビルが目立ち始める。道は二車線になり、車の量が急に増えてくる。歩道も広く整備されていて、県庁舎の周辺はスーツを着た人達の姿が目立つ。
さっきから何度も電話をしているが、通じない。時間はもう十時になろうとしていた。あと一時間もすればよっちんの家に着いてしまう。
道路は三車線に広がる。大きな駅の前には何軒ものデパートや百貨店が立ち並んでいる。アスファルトが真夏の太陽を照り返す。街路樹にとまった蝉が、僕らの不安をあおるように鳴き続けている。
ケイヤが携帯を畳みながら言う。
「出かけてるってことはないよな?」
「用事がないって確認したの、おとといだからな」
「まぁな」
ケイヤは口をアヒルのように突き出している。
「会えなかったらどうしよう?」
僕が言うと、ケイヤは降りていた自転車にまたがる。
「行ってみるしかないって……」
ケイヤの後を僕は走っている。やがて、高いビルはなくなり、住宅街に入ってく。空き地が随所に見られ、畑や水田が目立ち始めた。
ケイヤは自転車を止めて、地図を広げる。
「多分、この辺のはずなんだけど……」
何度も、同じ道を行ったりきたりしている。
僕は地図を覗き込む。電柱に書かれた住所がここで、よっちんの家の住所がえーと、ここで、あぁー、ずーっと手前のところで右に曲がらなくちゃいけなかったんだ。
僕はケイヤの手から地図を奪い取ると、ケイヤの前に出て、自転車をこぎ始めた。
一軒家の前で、僕は自転車を止める。
「ここだ」
グレーの外壁の二階建てで、テレビのコマーシャルに出てくるような洒落た造りだ。門から庭を覗くことができる、芝が敷かれ、よく手入れされた花々が咲いている。
「立派な家だなぁ」
ケイヤはそう言いながら携帯電話を取り出す。やはり、よっちんは出ない。
ケイヤは僕に、目でインターホンを示す。そのボタンを押せということらしい。この家の中に、よっちんがいると思うと、胸が締め付けられる感じがする。出かけて会えないことを考えると、締め付けははもっと強くなって、痛みが走る。
ボタンを押そうと指を伸ばす。ケイヤを見るとゆっくりとうなずく。勇気を出してボタンを押す。家の中からインターホンの音が聞こえる。僕の心臓の音が、ケイヤにも聞こえるくらい高鳴っている。遠くで車が走る音が聞こえる。相変わらず、蝉はどこかで鳴き続けている。額の汗が頬を伝い、首筋に流れていく。家の中からは何も反応がない。
「いないのかなぁ?」
頭の芯がシワシワしてくる。息がしづらくなって、吐き気がする。
今度は、ケイヤがインターホンのボタンを押す。また、家の中で『ピンポーン』と音がする。僕らはそのままの形で、玄関の前に突っ立っている。ときどき、ケイヤと目線が合うが、二人とも何も言い出せない。ジリジリとした時間だけが流れる。
諦めかけたとき、玄関の扉が開いた。そこからよっちんのお母さんが顔を出す。
「あら、あなた達?」
僕らは満面の笑みでお辞儀をする。そして、ケイヤが言った。
「こんにちは。よっちんいますか?」
懐かしい響きだ。よっちんが引っ越す前、僕らはいつもこんな感じで、よっちんを呼び出していた。
「今、出かけてるんだけど…… もしかして、陽一にわざわざ会いに来てくれたの?」
「い、いないんですか……?」
眩暈がする。立っているのが辛い――
「そうなのよ。携帯に電話してみた?」
「電話したけど出ないんです」
「多分、図書館だと思うから、電源切ってるのかなぁ。行ってみる?」
よっちんのお母さんは図書館の位置を教えてくれた。
ここから十分はかからない。僕らはお礼を言うと、図書館へ向かった。
「よっかったなぁ、図書館で。ハラハラしたよ。ここまできて会えなかったら、悲惨だよ。でも、よっちん図書館なんかで何してんだ? 読書って柄でもないのに」
ケイヤと並んで走りながら、僕は安堵のため、少しお喋りになっていた。そのとき、急にケイヤが自転車を止める。
「どうした?」
「タイヤがパンクしたみたいなんだ」
見ると、後輪がペシャンコに潰れている。
「さっき通ったところに自転車屋があったから、そこまで戻るか。先に、図書館に行ってろよ。直したらすぐ行くから」
自転車屋があったのはよっちんの家のだいぶ向こうだ。
「僕も一緒に戻るよ」
「いや、よっちん見つけるまでは気が気じゃないから、先に行って探しておいてよ」
「分かった。よっちん捕まえておく」
僕らはそこで別れた。よっちんのお母さんに教えてもらった道は複雑ではなかったけど、念のため、地図に図書館の位置をペンで書き込み、ケイヤに渡した。
まったく知らない場所を一人で走るのは心細かった。離れてみて初めて、ケイヤの存在を強く感じる。一人になったとたんに世界は違って見える。
言われたとおりに道を進むと、程なくして、図書館に着くことができた。白い二階建ての建物で、入口に書かれた図書館という銀色の文字が少しはげてる。自転車を置き、入口の前に立つ。よっちんが中にいるのだと思うと、緊張する。自動ドアが開くとと冷房の冷たい空気が押し寄せてきた。図書館特有の紙とインクの匂いに包まれる。
一階の窓際にテーブルが置かれ、読書コーナーになっているが、そこによっちんはいない。本棚の間を一周し、確認してから、二階の閲覧室に向かう。階段を上がって左側の部屋だ。ガラスのドアがあり、そこから中を覗く。部屋の奥から二番目の席に一人で座るよっちんの姿があった。僕のことにはまだ気付いていない。本に目を落としている。
――よっちんだ。
なんか、すごくドキドキしてる。デートの待ち合わせって、こんな感じなのかもしれない。
僕はドアを開けて閲覧室の中へ入っていく。よっちんの机の横に立つけど、僕に気が付かないみたいだ。
「よっっちん」
言葉がかすれてる。
よっちんは読んでいる本から顔を上げると僕のことを見た。僕はドギマギしながら、突っ立っている。顔がすごく熱くて、汗が噴出す。よっちんは目をパチクリさせながら、ただをじっと僕のこと見ているだけだ。反応がない。ポカンとした時間が過ぎていく。
「しっ、翔くん!」
突然、我に返ったようによっちんは素っ頓狂な大きな声を上げる。部屋にいた全員が、僕らのことを見る。そして、よっちんは部屋に響き渡るような大きな声で言う。
「何で! 何で、翔くんがここにいるんだよ!!」
「分かったわかった。とりあえず、ここから出よう――」
僕とよっちんは図書館を出ると、抱き合い、そして僕はよっちんの頬っぺたを摘まんでプニュプニュして、再会を祝った。
「ケイヤも来てるんだ。自転車がパンクして、直したらすぐにここに来るよ」
「まさか、自転車で来たの?」
「そうだよ」
「嘘!」
「そうだろ。僕もケイヤが自転車で行こうって言い出したときには、嘘だろって、思ったよ」
「でも、どうして?」
「おととい、ケイヤのところにメールしただろ。それが気になったのと、お前のこの頬っぺたをこうやってプニュプニュしたかったからだよ」
僕はもう一度、さっきよりも少し力を込めて、よっちんの頬っぺたをプニュプニュした。
「ごべん。ぼひがへんにゃミェールしひゃったから」
よっちんは頬っぺたを引っ張られながら言う。
「ただ、会いたかっただけだから、気にしなくていいよ」
「でも、大変だったでしょ?」
「うん。大変だった――」
僕は目頭が熱くなってきた。本当に大変だったんだよ。本当に、本当に、本当に大変だたんだよ! ウゥッ……。でも、よっちんに会えてよかったぁー。ウゥゥッ……。僕は涙を堪えながら、もう一度、よっちんを抱きしめ、頬っぺたをプニュプニュした。
「何かあったのか?」
「うん…… 別に大したことじゃないんだけどね」
「言ってみなよ」
「うん…………」
「学校でいじめられてるんじゃないかって、ケイヤが心配してたぞ」
「――そんなことないよ。みんないい人だよ」
「ふーん。ならいいけど……」
僕らは図書館の自転車置き場の近くにあったベンチに座った。横に大きなケヤキが植えられていて、日陰になっている。風の通り道のようで、木漏れ日が涼しくゆれている。
「……」
…………
早くケイヤが戻ってこないかなと思った。あの距離を引き返したのだから、もうしばらく時間がかかるだろう。
「……」
「……じつはさぁ」
「……ん?」
「新しい父さんの方にも、僕と同じ年の子供がいるんだ」
「そいつにいじめられるのか?」
「いじめられてるわけじゃないけど、時どき、ぶたれたりすることはある。多分、僕が余計なこと言ったり、グズグズしてるからいけないんだと思うんだけど……」
「どんなことがあったって暴力振るうことないだろう!」
「このごろは、一緒にいるだけでこの辺りがモヤモヤして、すごく疲れるんだ」
よっちんは胃の辺りを押さえて、げっそりした顔で言う。そういえば、少し痩せたかもしれない。
「それは絶対ストレスだよ」
「母さん、今日は家にいるけど、普段は工場で働いてるんだ。夏休みになって、家にいるのは僕と二人だけになる。毎日一緒に過ごすのかと思うだけで、苦しくなってくる。今日も朝から、図書館に行くって、逃げてきたんだ」
「それって、けっこう重症だなぁ。お母さんに言った?」
「ううん。心配かけたくないし、多分、信じてもらえない」
「今から呼び出して、三人でやっつけちゃうか?」
「そういうわけにもいかないよ。家に帰ってから、絶対に言いつけられるし、もしかしたら復讐されるかもしれない……」
よっちんは寂しそうに微笑む。ケイヤなら何ていうんだろう? 僕がよっちんにしてあげられることって何かあるのか? 僕は何のためにここまできたんだ。もっと気の利いたことを言わなくちゃいけない。せめて、よっちんを明るい気分にさせたり、励ましたり、勇気付けたりできるようなことを――。
僕は何も言うことができなかった。考えた末に出た言葉が、
「困ったな……」
本当にバカみたいだ。
「ケイヤに電話してみよう」
僕が言うと、よっちんはカバンから携帯を取り出し、電話をかけた。
よっちんはしばらくケイヤと懐かしそうに話していたが、急にしかめっ面になって、何か一生懸命に考えながら話をしている。電話を切ってから僕に言った。
「ケイヤ君、迷子になってるみたい。分かりやすい場所を言っておいたから、ぼく達もそこまで移動しなくちゃ」
――やれやれ。
自転車を出してきて、僕らは図書館を出発した。よっちんはママチャリに乗っている。
僕はよっちんの後について走っていく。僕が来るときに通ってきた道をしばらく戻って、太い道路との交差点で右に曲がった。正面には大きな山脈がかすんで見える。本当に遠くのほうへ来たんだなと、実感する。道の両側には、パチンコ屋やファミリーレストラン、車が何台も並べられた中古車販売店が目立つ。道から離れると、建物よりも畑や田んぼのほうが占める割合が多い。
交差点でよっちんが止まった。
「ここで待ち合わせたんだ。ケイヤ君のいたところからだと、ここまで一本道だから、間違わないでこれるといいんだけどな」
「あいつの方向音痴は、想像以上に酷いからな」
8
自動販売機で冷たいお茶を買って、信号の手前のガードレールに寄りかかりながら飲んだ。主要な街道らしく交通量は多く、部分的に渋滞している箇所もある。信号で停まった車の中はエアコンが効いて涼しそうだ。
「あれ、ケイヤ君じゃない?」
僕らの来たのと反対側から、豆粒くらいの大きさで、自転車が近づいてくるのが見える。
「あぁ、あの汚い格好はケイヤだ」
もちろん、僕もケイヤと同じくらい汚い。
迎えに行こうと立ち上がったとき、信号待ちをしている白いワゴンの助手席に乗っている女の人と目が合った。なんとなく、訴えかけるような目で僕のことを見ている。そして――
『た・す・け・て』と口が動いたように見えた。
「え?」
僕はその人をもう一度見る。
再び、唇が『た・す・け・て』と動いた。窓がしまっているので、声は聞こえない。実際には、声は出していないみたいだ。
よっちんの肩をたたき、車に乗った女の人のことを目配せして知らせる。よっちんが何事かと車の助手席を見ると、また、女の人の唇が『た・す・け・て』と動いた。
間違いない。僕らに助けを求めている。女の人の右腕には、手錠のようなものが巻かれている。運転席を覗き込む。ゴツイ体格のスポーツ刈りの男がハンドルを握っている。
どこかで見たような顔だ。誰かに似ている。
――ゴリ田だ!
女の人、手錠、ゴリ田……
おとといケイヤの家で見たニュースを思い出す。
――郵便局に入った強盗だ――
信号は青になり、車はノロノロと走り出す。
僕とよっちんは車を追いかけるように、自転車をスタートさせた。
「郵便局に強盗が入ったの知ってるか?」
僕はよっちんに聞いた。
「そういえば、人質とって逃走中だって、テレビでやってたかも」
「あの車に乗ってるの、絶対、人質と犯人だ」
「本当に?」
「ああ。犯人の顔、ゴリ田に似てたから、間違いないって!」
「どうしよう」
「……とりあえず、見失わないようにしなくちゃ。僕はついていくから、よっちんは警察に電話してくれ」
「分かった」
よっちんは自転車を止めると、電話を取り出した。
僕は車の後をついていく。前からケイヤがやってくる。僕が迎えに来たと思って、のん気に手を振っている。
僕はケイヤとすれ違いざまに「ついてきて」と言うと、ワゴン車を追った。
ケイヤはUターンして僕に追いついてくる。
「なんだよ!」
「あの前の白い車、郵便局に入った強盗が乗ってるんだ」
「嘘だろ?」
僕は今見てきたことをケイヤに話した。
車は先に行ってしまうが、信号で停まっている間に僕らが追いつく。僕らが追いつくころに信号は青に変わり、並んだ車列がノロノロと動き始める。それを繰り返している。
突然、白いワゴン車は急発進し左の狭い道を曲がる。もしかすると気付かれたのかもしれない。加速し、細い道を進んでいく。僕らも必死に追いかけるが、車との距離はあっという間に開いていく。道の両脇に家はなくなり、畑の中の一本道になる。視界は一気に広がり、遠くに見える小高い山の麓までは、見渡す限り畑が広がっている。
道の中央を耕うん機がのんびりとしたスピードで走っている。車はそれが邪魔で先にいけないようだ。クラクションを鳴らし、うしろから追い立てる。耕うん機は道の端によけようとするが、動きが緩慢で時間がかかる。けたたましくクラクションが鳴らされる。
その間に、僕と白いワゴン車との距離は近づいてくる。やはり、ケイヤのほうがこぐのが速い。僕のはるか前を走っている。――追いついてしまったらどうするんだ? 興奮した頭の中で、もう一人の自分が警鐘を鳴らす。
耕うん機が左によけて、ワゴン車がそれをよけるのと同時に、ケイヤの自転車は耕うん機のさらに左、土がむき出しの部分を砂埃をあげて駆け抜け、車の前に出る。ケイヤは自転車で車を止めようとしているんだ。車の前で、ジグザクに走って前に行かせないようにしている。車はクラクションを鳴らし続ける。そして、痺れを切らす。
ワゴン車は急加速し、ケイヤの姿が、僕の視界から消える。
「ケイヤ!」
ワゴン車はそのまま走り去っていく。
「ケイヤ! 大丈夫か? ケイヤ!!」
追いつくと、自転車ごと、道路より一段下の畑の中にケイヤが倒れている。
「大丈夫か?」
「あのヤロー! いきなり迫ってくるから、畑の中に落っこちちゃったよ」
「怪我はない?」
「ああ、このくらい平気だよ」
よっちんが遥かうしろから追いかけてくるのが見える。
「一人で上れるか?」
「大丈夫だ」
警察への連絡が取れたか気になったので、よっちんの元まで戻った。
よっちんは真っ赤な顔をして、自転車で走ってくる。
「警察は?」
「こっちへ向かってる」
白いワゴン車は、この道を山の麓の方まで走り去っている。微かに白い車が動いているのが分かる。
犯人を逃がしてしまった。失望と悔しさと、わずかな安堵の気持ちが入り混じっている。しかし、あの女の人は連れ去られてしまった。口元のイメージが圧倒的で、どんな顔をしていたのかよく覚えていない。『た・す・け・て』と動く唇が、僕に助けを求めるその動きだけが、脳裏に焼きついている。いつだって、僕は何もできない――
よっちんの声で我に返る。
「この道を真直ぐ行くと、二股の道にぶつかるんだ。右に曲がれば山の中へ入っていく。もし、山の中へ入っていったら、一本道だからこっち側から追いかけるのと、警察が山の向こうで待ち伏せすれば、もう逃げられないと思う。そして、もし、左の道を選んだとしたら、あの道に戻ってくる」
よっちんは畑をはさんだ三百メートルほど向こう側を走る道を指差した。
まだ、終わっていない。まだ、あきらめちゃいけないんだ。
「分かった。そのこともう一度警察に連絡してよ。よっちんは後から来て」
よっちんのママチャリではこの畑を越えるのは無理だろうと思った。僕はよっちんを残し、ケイヤの元に戻った。
ケイヤは自転車を道路に上げようとしているところだった。
「ケイヤ! あっちの道だ!」
僕は指差し、道路から畑にジャンプした。ケイヤも後からついてくる。僕らは最近、空き地でマウンテンバイクに乗ってジャンプの練習をしていた。練習がこんなところで役に立つなんて思いもしなかった。横を走るケイヤに、向こうの道に犯人が現れるかもしれないことを伝えた。
畑の中を突っ切っていく。何個かキャベツを潰してしまったけど、緊急事態だからしょうがない。砂埃が舞い上がる。段差はジャンプで超える。
正面に、僕らより背の高いトウモロコシの畑が壁のように立ちはだかっていた。人一人がやっと通れるくらいの農作業用の道がある。僕とケイヤはそこを全速力で走り抜ける。ハンドルに当たって、何本かのトウモロコシをなぎ倒してしまう。ナスの苗木を、支柱ごと引き抜きながら突き進む。土が盛られた一メートルくらいの隆起があった。それをジャンプで乗り越えようとする。思ったよりもスピードが出ている。空中に飛んだ瞬間に恐怖に包まれる。ケイヤは上手く着地して走り抜けていった。僕は前のめりの姿勢で地面に突っ込む。思わずブレーキを握ってしまう。前輪がロックし、そのまま自転車は一回転する。背中を強く地面に打ち付けるが、耕された土の上なので、強いダメージは受けていない。ケイヤは僕のことを振り返りながら走り続けている。僕もすぐに立ち上がると、放り出され、タイヤだけが回転している自転車を起こして、再び走り始める。
畑を抜けて、道路に上ると、見渡す限り道路上に車はいない。息切れした呼吸を整える。
心地よい風が、全身の汗を乾かすように吹いている。その風が、道路わきに生えている雑草を揺らし、サワサワと音をたてている。小鳥のさえずりが聞こえる。シュウマイみたいな丸い雲が、早いスピードで幾つも流れていく。広大な田園地帯に雲の影が水玉模様をつくり、同じスピードで進んでいく。――なんかお腹が減った。
「大丈夫か?」
「全然、平気」
転んで泥だらけになったTシャツを叩きながら僕は答える。
「よっちんどうだった?」
「再婚相手にもよっちんと同じ年の子供がいたんだって。そいつがスゲー嫌な奴らしいんだ。よっちんのこと殴ったりするんだって」
「何だって! そんな奴、ボコボコにしてやろうぜ!」
「よっちんはそいつと、これからも一緒に暮らさなきゃいけないんだ。一回やっつければ済むって話じゃないだろ?」
「一回でダメなら、何回だってやってやる」
「だから、そういう話じゃ――」
「おい。見ろ!」
向こうのほうから白いワゴン車がこちらに近づいてくる。本当にこっちに戻ってきたみたいだ。ケイヤの表情が険しくなる。車の姿は次第に大きくなってくる。他の車はいない。
どうしたらいいのか分からない。僕らは無言のまま、近づいてくる車を見つめていた。
ケイヤは自転車にまたがったまま、道路を封鎖するように立ちはだかる。この道路は二車線なので、ケイヤだけでは完全に道は塞げない。
――マジかよ。
僕もケイヤと一緒に並んで道路を塞いだ。
白いワゴン車の姿は大きくなっていく。向こうは強盗の犯人なんだぞ。こんなんで止まるかよ! でも、僕だけ逃げ出すわけにはいかない。車はスピードを緩めずに近づいてくる。ケイヤのことを見る。ケイヤはじっと車を見据えたまま動かない。ケイヤを置いて逃げるわけにいかない。一人で逃げ出すくらいなら、このまま死んだほうがいい。僕は目をつぶった。
ずいぶん長い間、目をつぶっていたような気がする。もう車は来ないのか? 思った瞬間、ものすごい衝突音がした。同時に、握っていた自転車のハンドルに衝撃がはしり、僕は自転車ごと、よろよろと倒れる。僕の自転車の前輪に車は接触したみたいだ。目を開けると、ケイヤが車のボンネットの上を飛んでいる。飛んでいるケイヤの形が、影絵みたいに青空をくり抜く。金属が擦れあい、潰れる大きな音がする。倒れた僕の前を無数のオレンジ色の火花が移動していく。ケイヤの自転車が車の下に入り込んで火花を上げているんだ。去年、僕とケイヤとよっちんで花火をしたことを思い出す。――また三人で花火をすることなんてあるんだろうか……
ドスンという鈍い音がした。ケイヤが地面に転がっている。
車は、火花を上げながら蛇行して走り、ハンドルを取られたのか畑の中に落ちた。土埃が舞い上がる。突然、静寂が訪れる。さっきと何も変わっていないように、風がサワサワと道路わきの草を揺らす。遠くのほうで、蝉が鳴いている。僕の頬の下にあるアスファルトが、日に照らされ、焼けるように熱い。熱いけど、なんか気持ちいい。このまま眠ってしまいたい。
運転席のドアが開いて、中から犯人が出てくる。ふらつきながら、道路に上ってくる。僕が立ち上がろうとすると、ケイヤが僕よりも早く立ち上がり、犯人に向かって走り出す。
「ケイヤ!」
僕は叫びながら、ケイヤの後を追いかける。
「無理するな!」
ケイヤは犯人に追いつくと一瞬の躊躇いもみせずに飛びかかった。犯人はケイヤを振りほどこうと左右に身体を動かすが、ケイヤはしがみついたまま放れない。犯人はズボンのポケットから何かを取り出す。右手に持ったそれが銀色に輝いている。ナイフだ! もっと早く走りたいのに、手足の動きがスローモーションみたいになって歯痒い。犯人は右手を振り上げ、今にもケイヤを突き刺そうとしている。僕はギリギリのところで、ナイフを持った右手にしがみついた。犯人はゴリ田なんかより断然デカイ。身長が百八十センチ以上ある。腕の筋肉もすごく太くて、僕一人じゃとても押さえきれない。だけど、絶対にこの手を放しちゃいけないんだ! どんなことがあったって! 僕は腕に噛みつく。犯人は信じられないような力で僕を引き離そうとする。無理だよ! いくらなんでも、こんなの無理だ! ふと、犯人の肩越しにうしろを見ると、よっちんが自転車でこちらに向かってくる。犯人はよっちんには気付いていない。よっちんは真っ赤な顔をして、ママチャリで突進してくる。
よっちんはそのまま、犯人の背中に激突した。犯人はマントヒヒの雄叫びみたいな声を上げて、道路に倒れた。すかさずよっちんが犯人の胸の上に馬乗りになり、僕が右手、ケイヤが左手の上に乗って、押さえ込んだ。
さすがに三人に押さえられては動けないらしく、犯人はしばらく騒いでいたけど、そのうち大人しくなった。
遠くのほうからパトカーのサイレンが近づいてきた。
パトカーが何台もやってきて、たくさんのお巡りさんに囲まれた。犯人は手錠をかけられて、その中の一台に乗せられ、連れていかれる。犯人の乗っていたワゴン車の中から、人質になっていた女の人も救出された。救急車がやって来て、女の人は救急隊員に抱えられながら乗った。ケイヤは自分では大丈夫だと言ったけど、あれだけ激しく車とぶつかったのだから、念のために一緒に病院へ行くことになった。
「じゃあ、また後でな」とケイヤは言うと、笑いながら手を振り、救急車に自分で乗り込んだ。顔色が悪い気がしたけど、こんなことの後だから仕方がないと思った。
僕とよっちんは二人でパトカーに乗って警察署に連れて行かれる。同じような質問に、何度もなんども答えさせられてうんざりした。夕方近くなって、ケイヤの爺ちゃんを車に乗せて、僕の両親がやってきた。嘘をついてこんなところまで来てしまったので、絶対に怒られると覚悟してたけど、意外にもそんなに怒られずに済んでホッとした。母さんは僕を抱きしめると涙を流した。母さんに抱きしめられることなんて、何年もなかったので、恥ずかしくて、居心地が悪くて、くすぐったくて、本当に困った。
よっちんの家族も迎えに来ている。よっちんの新しいお父さんは、優しそうな人で安心した。驚いたことに、お父さんの連れ子という奴も警察の待合室に来ていた。本当に驚いた。そいつは勝気そうな目をしていて、鼻筋が通っていて、唇が生意気そうで、髪の毛が長くて、女の子だった。僕らの学校で一番可愛いと言われている、長瀬魅月よりも三倍くらい可愛かった。よっちんが出て行くと、よっちんの頭をポカンと平手で殴って、心配かけるなって、少し涙ぐんでいる。なんとなくだけど、今回のよっちんの悩みについて、僕はもう、そんなに心配しなくてもいいのかなって気がした。
ケイヤが病院から戻ってきた。みんなに囲まれて、少し恥ずかしそうに笑っている。爺ちゃんがケイヤの顔をなで回していた。ケイヤは爺ちゃんのされるがままになってじっと動かずに笑ってる。
ケイヤは調べがあるから、まだ帰れないみたいだ。ケイヤのお父さんもこちらに向かっていて、夜には着くらしい。ケイヤの爺ちゃんを残して、僕らは先に帰ることになった。
よっちんとケイヤの顔を見ていたら、急に涙が溢れ出てきた。どんなに離れていたって、住む世界が違ったって、俺たちが友達だってことには変わりないんだ、って、ケイヤが言っていたのを思い出す。そうだ、どんなことがあったって、僕らの友情は変わらない。よっちんも大粒の涙を流している。多分、これから僕らはたくさんの苦しいことや、恐ろしいこと、辛いことに出くわすんだと思う。怖いのはしょうがない。でも、逃げちゃいけないんだ。勇気を出して一歩を踏み出せば、きっとその先に何かが見えてくる。それは夢とか希望とかいわれるものなのかもしれないし、あるいは全く違ったものかもしれない。よく分からないけど、それでも僕らは一歩いっぽ進んでいくしかないんだと思った。
僕とよっちんはケイヤを残して部屋を出る。
――ケイヤは少し恥ずかしそうに笑っていた。
僕らの冒険をめぐる物語
読んでいただきありがとうございます。