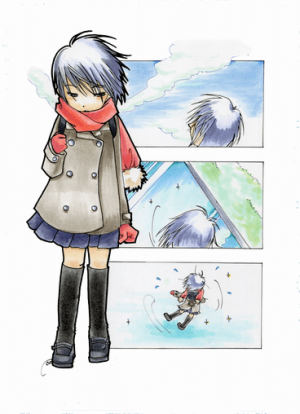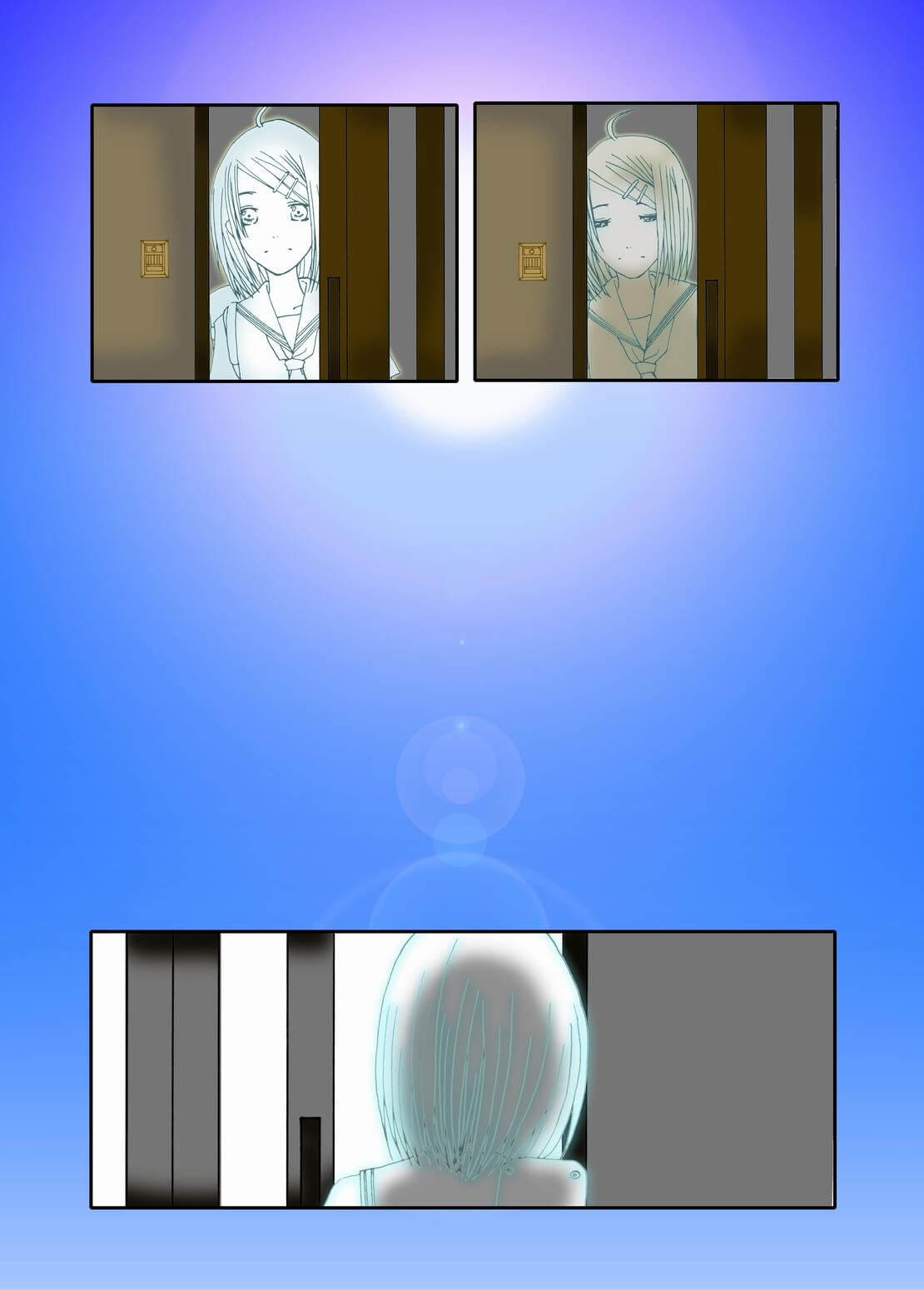
県立東雲高校文化祭へようこそ!【完結】
文化祭でクラスの出し物からのサボりを決め込んだ朱夏に現れる妄想の数々。
今日と変わらない明日を望む彼女の前に横たわる文化祭という名の非日常世界。
自称【どこにでもいる女子高生】朱夏が語る県立東雲高校の文化祭とは…
何気ない時間の流れの中で気づくのは青春の煌めきか、それとも戻らない日々の輝きか。
アマオトー1
誰もが小説になり得る人生を送っている。小説にならない人生を生きている者などはいない。
そう言って古文の芦田は出ていった。
この物語の語り手は龍蔵寺朱夏。
語るような内容があるとは思えない平凡な一人の女子高校生だ。けれども本当にすべての人が小説になり得る人生を生きていると言うのならば、高校最後の文化祭の前後の、あのたわいのない時間をどうか聞いて欲しい。特に何も起こらないことが当たり前で幸せで、そして不思議だったあのかけがえの無い時間を。
文化祭を控えた6月23日の夕方からこの物語を語り始めたいと思う。
アマオトー2
―◆―
「あか、帰ろ」
碧子が声をかけてきた。
朱 夏は書きかけの学級日誌を指さした。
「今日、遅刻っていたっけ」
「たしか前田が遅刻だったよ」
まえだーと碧子は話しかけ、あぁの返事がした。
「ってさ、あか」
朱夏は遅刻欄に前田1名と記入する。
「おわり?」
かけられた声にうなずいて机の脇からリュックを取り上げた。
「あか、いつも重そうにしてるよね。置勉すればいいのに」
「毎日持って帰っていると慣れるというか、最高六科目だからそんなにはね」
「ふぅん」
碧子は気のない返事をして
「職員室寄るでしょ」
まわりを見ると机が下げられてスペースを確保されだしている。掃除が始まっている。
「ホラ!」
碧子がうしろの入り口のドアで大きな声を出してうながした。
「あかは大学決めた?」
職員室まで並んで歩きながら碧子に訊かれた。
「碧子は決めたの?」
「あたしは明学。白金台ってトコで過ごしてみたいから」
「白金って、東京の真ん中かぁ…。私にはムリかな」
「あかなら入れるよ」
「ムリムリ」
「そーなの? じゃアレはなに?」
碧子は共有スペースに貼ってある紙を示した。
第○回模擬試験結果とある。
「日本史85だよ。全国8位って」
「まぁ、日本史はね」
「他は?」
「国語が53、英語は38かな」
朱夏はその紙をちらりと見てリュックを背負いなおした。
「3教科だと、いくつ?」
「58かな…」
「58!?」
「いつもは51くらいだし、たまたまだよ。今回は文化史が中心だったから他の人が出来なかったんじゃないかな」
朱夏と碧子は教室に近い東側階段を上がる。
県立東雲高校の校舎は三つの棟から成り立っている。北から職員室や事務室、生徒会室などが入っているA棟。普通教室があるB棟。そして特別教室があるC棟である。AからC棟をつらぬくように渡り廊下がつながっている。上から見れば漢字の五の文字のようになっている。
三年生の教室はB棟一階で職員室はA棟二階にある。
だだだだっと男子が駆け下りていく。学校内がさわがしい。
「この時期にやらなくても良いのに」
「なにを?」
「文化祭。六月ってありえないよ」
碧子が大げさに頭をふってみせた。
「そう?香風女子も同じ日だって聞いたけど」
「南高もらしいよ」
「人が来なくていい。人ごみ嫌いだから」
「模擬店禁止って時点でない」
「私はやらなくても良いと思ってる」
階段を上がりきると二年生のフロアになっている。
三年生のフロアに比べると華やかな感じだ。
A棟への渡り廊下を歩く。上に卒業生の進学先と名前が書かれた短い木の札が並んでいる。
「立命館がいたんだって思うよ」
碧子がつぶやく。国立文系コースにあって碧子はそうそうに私立に絞っている。
朱夏もつられて見上げる。けれど、見た先は山形大学人文学部の合格者だった。
職員室の前にはテーブルが置かれていて、荷物を置けるようになっている。
碧子がバッグをそこに置いたのを見て
「日誌置いたらすぐに出てくるね」
「私もちょっとだけ」
ドアをノックしてから一緒に入る。
担任の藤崎先生は席にいなかった。
「どうしたの?」
立ち尽くしていると隣の八木先生が聞いてきた。
「日誌出しに来ました」
「置いといて」
朱夏は日誌を置いた。
職員室の奥つまりは反対の方を見ると碧子が誰かに話しかけている。
朱夏もそちらに歩いていき頭を下げた。
「龍蔵寺も用?」
「いえ…。日誌出しに来ました」
「用は終わり?」
「はい」
「七組は文化祭なにするの?」
「先生、それはないですよ」
碧子が楽しそうに言う。
「男子が何か言ってるけど、よくわからない感じです」
「碧子、ちゃんと司会でHRにいたよね。実行委がそれ?」
朱夏はあきれた。
「男子が口だしするなって言ってるんだから良いんだよ」
「碧子、長くなるなら帰っちゃうけど」
「別に特にってことはないから。先生これから補習でしょ」
そんな時間かな…と言いながら羽場先生はPCでの作業に戻った。
「帰ろっか」
碧子が歩き出す。朱夏もうしろをついてゆく。
6月23日 晴 欠席なし、遅刻前田、早退なし 特記事項文化祭四日前
アマオトー3
―◆―
がしがしとタワシでカウンターの上につり下げられていた電灯のガラス球の内側をこする。
飛び散る水しぶきに朱夏は少し後悔していた。
「龍蔵寺さん、割らないように気をつけてね」
司書の郡司先生も隣で同じようにタワシを動かしている。
「結構おちるものね」と楽しそうだった。
「龍蔵寺さんのクラスは準備進んでる?」
「なんか男子主導で動いてて、よく分からないです」
水を入れてクレンザーを洗い流す。真っ黒な水が満ちていく。
朱夏は顔をしかめた。
「二年生の和泉ちゃんのクラスはお化け屋敷だって言ってた。龍蔵寺さんは古本市で大丈夫?」
「はい。大丈夫です」
朱夏はクラスの当番から逃げたので、古本市に引きこもることにしていた。
「でもずっとじゃつまらないでしょ。見に行って良いんだからね」
朱夏は少し淋しい目をしてから、ガラス球の中の水を捨てた。
電話の呼び出し音がして郡司先生が「あとお願い」と水を止めると司書室の方に駈けていった。
後ろのドアが開いて4人の生徒が入って来た。
中庭からは楽器の音がしている。さっきから吹奏楽部が練習を始めていた。
ガラス球をすすいで洗面所のスミに置いた雑巾の上に伏せて置いた。雫がつつ…と下に流れ落ちていく。
郡司先生がいた洗面台の洗いかけのガラス球の前に立ち、すすぎをして汚れを流す。さっきのガラス球の隣に並べて置く。
ポケットからハンカチを取り出して口にくわえてから手を洗った。ピッと水を切ってからハンカチで拭う。
カウンターに戻ると返却本が増えている。後ろの司書室とつながったガラス戸をあけて「先生終わりました」と声をかけた。
机で作業をしていた郡司先生が顔を上げてうなずいたのを確認してから戸を閉めた。
カウンター周りにはいろいろと雑多なものが散らばっている。カードの預かり箱、返却本の箱、ハンコのたぐいが2~3コ。朱夏は気がついてカチャカチャと4回入場者カウンターを押した。
数字が4回まわって32になった。下に開かれた日誌に昨日は28と書いてある。
朱夏はイスに腰掛けると床に置いたリュックから化学のクリアファイルを取り出した。
碧子から借りてきたプリントと並べて空欄を埋めていく。
molの計算があったので、再びリュックに手を突っ込んで電卓を取り出す。
碧子が暗算でしただろう数値を公式と照らし合わせながら時折電卓をたたいてなぞってゆく。
計算ミスを見つけてしまった。
朱夏は手を止めて、目の前にある付箋を一枚はがした。【○○になるハズ】と書いて貼っておく。
すべての空欄に書き入れ終わるとクリアファイルに入れて机の上に置いた。
さっきから中庭では音出しが終わった吹奏楽部の演奏が響いている。しばらく聞いていると“ジョニーが凱旋するとき”に変わった。
「先輩」
顔をあげると二年生の和泉ちゃんが立っている。
「ん? 何?」
「値札付けってどうなりましたか?」
「昨日終わったよ」
「じゃあ、今日は終わりですか?」
朱夏はうなずいた。
「私茶道部の準備があって…」
「大丈夫だから行って良いよ」
「ありがとうございます。あ、それと」
「それと?」
「これ」
渡された黄色い短冊状の紙を見ると何かの券のようだった。
「お茶立てるので来てください」
よく見ると300円と書いてある。
「いいの?」
「できれば」
朱夏はリュックから財布を取り出して300円を渡した。
「ありがとうございます。浴衣着るんで来てください」
バイバイと手を振って和泉ちゃんを送り出した。
カチッと音が響いて時計を見ると16時45分だった。
カウンターから出て、残っていた生徒に閉館を告げる。
「先生閉館準備して良いですか」
朱夏は司書室にヒョコッと顔を出した。
郡司先生は軽く手を振り返した。
カーテンを開けて窓のカギを確認すると生徒は全員いなくなっていた。
西側入り口ドアのカギを閉めて東側に歩いて行く。ついでに中庭を覗くと吹奏楽部も音楽室に戻るところだった。
6月23日 晴れ 来館者数32人 貸出13冊 返却8冊 世はすべてこともなし
アマオトー4
―◆―
朱夏は黒板を写している。
今は朱夏の苦手科目、英語の時間だった。
去年の修学旅行で京都に行った時、外国人に話しかけられてかろうじてtimeの単語で時間を尋ねているのは分かったから時計をみせてごまかした。
一応は進学希望だからとりあえず英語は必要だと認識はしている。でも認識する事と出来る事とは意味が違う。
あっと口を開いてから朱夏は消しゴムを取り上げてさっき書いた単語を消す。
ピーターラビットの執筆時のエピソードとナショナルトラストについて書かれた文章のようだけれど、正直関心が持てない。英語が出来れば分かるのかと言われれば、それさえも覚束ない。どちらが先で、後なのか朱夏にはよく分からない。
「松下、ここ訳してみろ」
碧子がすらすらと訳すのを聞く。かっこいいなと思う。
「先生」
男子が手を上げた。
「文化祭の準備して良いですか?」
「なんだ、終わりそうにないのか」
「はい」
「まぁ良いか。静かにやれよ」
「やった」
叫ぶ声がして教室中がざわつく。
朱夏は立ち上がらず頬杖をついて窓の外に視線を向けた。大きなケヤキの樹とその周りにベンチが据えつけられている。
朱夏の目が見開かれ、瞬きをしてもう一度見る。
「どうしたの」
目の前に碧子がいた。
「さっきあそこに白いセーラー服着た女の子が…」
「いないよ」
「だよねぇ」
これはやっぱりあれか? 文化祭の前に現れるとかいうやつなのか? などとくだらない妄想に引きずられていく。
「あか」
ポコンと碧子が朱夏の頭をノートではたく。
「碧子」
顔が近い。
「少しは手伝うそぶりくらいしてよ。さすがにさ」
「と言っても何をすれば良いのか」
「これ切って」
碧子から黄色と水色の色紙を渡された。格子状の線が印刷されている。
「カッターで良い?」
「良いよ。全部だよ」
「了解」
ペンケースからカッターを取り出して短冊状に切り分けていく。
前の席に座ってハサミで同じ作業をしている碧子に尋ねる。
「これってなに?」
「入場券」
「こんなに来るの?」
「さぁ男子が用意しろって言ったから用意しただけ」
つまらなそうにチョキチョキと切っている。
「結局なにをするの?」
「よく分かんない」
「碧子が分かんないんじゃ誰も分からないんじゃ…」
「これが買い出しリスト」
朱夏がのぞき込むと
コンクリートブロック-○個
ブルーシート-○枚
ベニヤ板-○枚
あゆ-○匹
…
「あゆ…? って魚の? 塩焼き?」
「いや、模擬店は禁止だよ」
「よく分かんないけど、藤崎先生よく許可したね」
「あの人、当日は招待試合でいないんだよ。どうでも良いって思ったんじゃない」
「招待試合?」
「この間配られたしおりくらい読んでよ。実行委で作ったんだから。野球、サッカー、あとはバスケかな。他校を呼んで試合する予定」
みどりーと遠くから呼ばれて「いまいく」と返してから、つつつと舞うように碧子は行ってしまった。
朱夏は手を休めると再び外に目を向けた。
空を見上げると少し雲がかっている。明日から雨の予報だった。
文化祭は明後日から二日間開催の予定である。
6月23日 曇 作った入場券300枚 当日の出し物は謎。
アマオトー5
―◆―
朱夏は手すりで組んだ腕にあごを乗せてベランダのから下を覗いていた。
中庭の中で一段たかくブロックが積まれたステージ状になっているところに吹奏楽部が陣取っている。
視線を右にずらせば大量のコンクリートブロックを組み上げている生徒達の姿がある。朱夏のクラスだった。
「龍蔵寺さん、あれはなに?」
「さあ、なんなんでしょう…入場券は作りました」
「藤崎クラスは前もとんでもないことしてたから」
「?」
「流しそうめん」
「よく許可出ましたね」
「タダだから大丈夫ってことで」
「食品だめって聞きました」
「藤崎クラスは謎ルート持ってるから。それより本当に大丈夫なの? 当番とか」
「碧子には大丈夫って言われてますし、そもそもシフトに入ってません」
「それならいいけど」
郡司先生に続いて朱夏も中に入る。
古本市の準備はすべて終わっている。
教室の真ん中に机を寄せて四つの島を作り、それぞれに本が山積みになっている。
ほとんどが生徒から集めたものだけれど、図書館で古くなって除籍された本もある。これはタダで持って行ってもらう。
出口に簡単に設けられたレジのところに座る。
廊下側の窓から見える景色は文化祭のもの。
ポスターを貼っては次の場所に走って行く背中が見えた。
朱夏は雑音を耳に入れながら、なにかトラブルが起こらないかなぁとぼんやりと不謹慎なことを考えていた。
ドラマや本や漫画で描かれる文化祭は不思議の国そのもので、前泊したりすると幽霊が現れたり、異世界に飛ばされたりするのだ。
ほうっとため息をつく。
積まれた本を見て朱夏はもう少しなにかないものかなぁと思う。
教室には朱夏の他に郡司先生と二年生が二人いてキャッキャッと楽しそうにしている。
「郡司先生、売り上げってどうなるんですか」
「全額返金」
「私たちに還元とかは…」
「家庭科部が出す屋台の食券500円分」
「はぁ」
「龍蔵寺さんも一生に一回なんだからまわってきたら。準備が見られるの貴重だし」
「……」
郡司先生の方を見るとあからさまに『行ってらっしゃい』オーラが漂っている。
朱夏は重々しく立ち上がった。
「そこらへんぶらついてきます」
廊下に出ると雑音が圧になって襲ってきた。
「こういうやる気オーラは苦手だな」ぽつりと朱夏はつぶやく。
6月24日 曇 文化祭前日 古本市で用意した古本952冊 売れ残りは必至
アマオトー6
-◆-
制服にジャージを羽織った女子とすれ違う。
朱夏はやっぱりこういう空気が苦手だ。
やけにお化け屋敷が多い。時々中を覗きながら気まぐれに歩いているといつの間にか玄関に来ていた。
上靴でたたきに降りようとして一瞬躊躇してから、タッと右足を降ろした。
外に出ようとしてギギッと重いドアを開けると雲間から漏れる日差しが思ったよりも強い。
まぶしさに思わず目を細める。
西門から出入りする自転車の生徒が多くいる。よどんでいるペンキの臭いが鼻をつく。
玄関から門の間にはクラブハウスがあって、その前の広場のような部分でベニヤ板を広げて金槌の音もする。うるさい…静かな場所はないのだろうか。
「しゅーかー!」
朱夏を呼ぶ声がする。
「アイスたべるー?」
「食べる」
ベニヤ板を囲む一群に近づいていく。
「どれ?」
広げられた袋の中に色とりどりのアイスがいっぱいに入っている。
「本当に良いの?」
「いいって。明日の準備だから」
「どんな準備?」
そんな会話を交わしながら袋に手を突っ込んで適当に触れたものをつかむ。パピコのコーヒー味。
「半分こする?」
「こんなにあるから大丈夫」
「碧子、知らない?」
「みどりなら生徒会室じゃない?」
「さっき実行委呼ばれてたし」
「それより朱夏、延長コードある?」
「延長コード?」
「男子がさ、電球ぶら下げるとか、ポンプがとか言ってて」
「図書室で見たことあったかな」
「ホント!?」
「今は古本市の扇風機に使ってる」
「だめじゃん」
「いいよ。男子なんかほっとこ」
「それくらいにして、運ぶの手伝ってー」
「あ、ごめん」
「じゃね、朱夏」
うんとうなずいて朱夏は手を振った。持ったアイスの冷たさで手が痛い。
朱夏は回れ右をして生徒会室のあるA棟に向かって歩き出した。
6月24日 曇時々晴 文化祭前日 塗っていた色数8色 どんなものになるのか、興味は持てない
アマオトー7
―◆―
生徒会室の扉に「文化祭実行委員会本部」と明朝体で印刷された紙が貼ってある。
中から出てきた青ざめた生徒に松下はいるのかと朱夏が訊くと「いる」とだけ答えて走って行ってしまった。
「しっれいしまーす…」
朱夏が控えめに扉を開くと何人かの生徒がいた。
「だーかーらー、大丈夫だって!」
「こんなのケガのうちに入らないから」
「いやいやいや。ムリでしょ、それ」
「―さんも入院したって聞いてますし」
朱夏は思わず首をすくめた。
どうやらトラブルが発生しているらしい。
「代役立てるって言ってるでしょ」
「リーハ、リーハ、リーハ!!」
「ごめん、あか。ちょっともめてて」
碧子が耳打ちしてきた。
「何部?」
「劇部」
あぁと朱夏は思う。出演者が出られなくなって講演スケジュールの見直しをしていたのだろう。
とはいえ、文化祭は文化部の三年生にとって引退に等しい最後の見せ場だ。そう簡単には譲れない事情がある。
「どうなるの」
碧子に小さな声で訊く。
「代役が立てられれば予定通り。スケジュールの調整はこっちとしてもやりたくないよ」
「できないと?」
「どっかの部活に時間をやることになる」
「どっかって見つかるの」
「さっき吹部の牛島が来て圧力かけていったよ」
「なるほど」
「それで、あか。こんなトコまでどうしたの?」
「これ」
アイスの袋を見せる。
「どしたの」
「食べる?」
「くれるなら食べるよ、そりゃあ」
朱夏はガサガサと袋を開けてパピコを取り出した。パキンと二つに割って片方を碧子に渡す。
「今、ここで食べちゃおうよ」
碧子は目の前のパイプ椅子を引くと朱夏に促した。
目の前では男子生徒二人と女子生徒三人の言い争いが続いている。
「たいへんそうだねー」
「そうだよー。委員長やらなくて良かった」
「結構久しぶりだけど、まだ売ってたんだね。コレ」
「小さい頃はよく食べたよ。半分しか食べさせてくれなくって、いつか二つ食べてやるって思った」
「そうそう、二つ食べたときは大人だ! って思った」
ちゅうちゅうとアイスを吸い上げる。
「こういう時ってやっぱり助っ人とかが現れて、劇部以上の演技とかしちゃうものなの?」
「バンドとかメンバー欠けて飛び入りが一日で弾けるようになっちゃうとか」
「奇跡だね」
「奇跡だよ」
ダンッ!
靴の底をたたきつける音がした。
「こりゃあ、そろそろ先生呼んでくるよ」
「そろそろ戻るね。ゴミどうしよっか」
「そこのゴミ袋に入れとく」
碧子はさっと朱夏の手から空になった容器を取り上げると席を立った。
6月24日 曇時々晴 文化祭前日 見かけた明朝体の文字数は十文字 【文化祭実行委員会本部】
アマオトー8
―◆―
「……」
朱夏はあきれているのかおどろいているのか感情がないのかよくわからないまま目の前の光景を目に入れていた。
「流しそうめんの再来ね」
「……」
さっき通った時に作っていた看板が大きく掲げられ、電気の無駄遣いもここまで行くといっそすがすがしいと思うくらいに電灯が煌々とこれでもかってついている。
「今回のテーマは『エコロジーLOVE。』じゃないの?」
「エコロジー…」
朱夏はぶんぶんと頭を振った。
『教職員にお知らせします。これより西門前にアーチを設置します。お手すきの方は集合してください』
ブチッ。
「今回はどんなアーチかな」
「三年に一度だから前の文化祭知らないですし」
「図書室にアルバムがあるから後で見たら?」
「時間が合ったら見てみます」
『郡司先生』
入り口にエプロン姿の二人組が立っている。
「なぁに」
「家庭科部です。試作品持ってきました」
タタタッと郡司先生は駈け寄るとパックを受け取り、レジ代わりの机に置くとそのまま黒板を眺めている。
「どうしました?」
「これ遠野さんが書いてくれたんだけど」
黒板には大きく「古本市」と結構な達筆で書かれている。
「なにか足りないものが?」
「わからぬ。なにも分からずに生きていくのが我々生き物の定めだ」
「李徴ですか…」
朱夏は二年生の時にやった『山月記』を思い出していた。
「遠傪でしたっけ?」
「何事かを成すにはあまりにも短く、何事をも成さぬにはあまりにも長い」
「あの…?」
「人生は一度きり、だからね」
「……」
「そこで、これをもう少しなんというかこう、まあ変えて欲しいんだけど、誰かいる?」
朱夏は天井を見上げた。
今日も安っぽいパネルが広がっている。
「思いつきません」
下から悲鳴が聞こえた。朱夏は好奇心でベランダに駈け寄りのぞき込んだ。
ブロックの一部が崩れ、水の重さでブルーシートが傾いて中に溜めていた水が流れ出している。決壊が始まっていた。一瞬で黒い部分が広がっていく。
「大丈夫?」
朱夏は大きな声で叫ぶ。
咲がキョロキョロと見回して上に朱夏の姿を認めると手を振った。
「あはは、大丈夫」
「朱夏もくるー」
「助けに行こうか?」
困った口調で言い返す。
隣のクラスから南埜先生が飛び出してきて『実行委員と藤崎先生はどこ行った!?』などとわめいている。
水浸しになった庭にふわりと波紋が広がる。
「降ってきた」
「ヤバいよ」
「片付けー!」
大声を上げながらあわただしく片付けが始まっている。明日適当に直すのだろう。
見上げると覆い被さる雲から伸びた白い筋がスッスッと増えていく。
6月24日 にわか雨 文化祭前日 流れた水247リットル超
損失 藤崎先生へ請求
アマオトー9
―◆―
「あめあめふれふれかあさんがー♪」
どどどと音を立てて降る水を見ながら歌う
「じゃのめでおむかえうれしいなー♪」
じゃのめって? と朱夏は思う。
窓の桟にはてるてる坊主がぶら下がっている。
「てるてるぼうずてるぼうすあしたてんきにしておくれー♪」
雨音がさざ波のように聞こえてくる。
童謡というのは残酷だ。
雨を止められなかったてるてる坊主がどうなるか。
てててっと窓辺を離れて本の山に向かう。
朱夏は少し嫌そうに顔をゆがめて、目についた一冊を手に取る。
パララ…とめくっていくとページが途中で止まった。葉書が一枚はさんである。
右手で引き抜いて左手に残った本を机に置く。
『西園寺鶫様』と宛名がある。
ピラッと裏返す。
「あか、まいったよ」
振り返ると入り口にさっき実行委員会に連行されていった碧子がいる。
「なに、ハガキ?」
スタスタと近づいてくる。
「あ、うん」
「これってやっぱり?」
朱夏は葉書の裏を碧子に見せる。
大きく『入道雲』がかかれている。
「にゅうどうぐもだよ」
「にゅうどうぐもだね」
「夏だよ」
「夏だね」
「暑中お見舞い申し上げます」
「残暑お見舞い申し上げます」
朱夏が言い直す。
「八月だよ?」
「立秋だね」
「スイカ食べたい。ヘチマ、朝顔、夏休み」
「スイカ、向日葵、蝉時雨」
「そういえばヒグラシの声って聞いたことない」
外では雨がどどどと降っている。
碧子も気まぐれに一冊取った。
「死に至る病」
「しにいたるやまい」
朱夏は繰り返す。
「キルケゴール」
「きるけごぉる?」
「こっちにも紙がある」
ピラと音がする。
「かたたたきけん」
つたない字を朱夏が読み上げる。
「つかおうか」
「つかえるの?」
碧子が教壇の前にある椅子に背中をむけて座った。
朱夏は肩甲骨の下に肘を思いっきり押し込んだ。
声にならない声がした。
ぐりぐりとねじ込んでいく。
碧子が体を前に逃がした。朱夏の肘が肩から離れる。
「劇部はどうなったの」
碧子は顔をしかめて必死に腕をうしろに回してさすっている。
「代役が間に合ったよ」
「それでどうにかなるの?」
「どうにもならないよ」
「どうにかしようね」
「あかが颯爽と」
「それはない」
「確か中学校の時って」
「手芸部だった」
「あのてるてる坊主はもしかして…」
「郡司先生が楽しそうに、そなたの首を~♪って歌いながら作ってた」
「まさか」
「まさかね」
6月24日 にわか雨 文化祭前日 てるてる坊主3つ 効果はどうだろう。
アマオトー10
―◆―
事件はいつも唐突に訪れる。
校内がざわついている。どこからか「落ちたの?」「二年生が…」「どうなってる!」などといった声が聞こえてくる。
朱夏は図書委員会に割り振られたB棟二階の学習室①にいた。
学①はB棟と渡り廊下の交わるところにある。したがって生徒の往来も激しい。
朱夏は廊下側に顔を向けてすぐに戻した。
「あか」
後ろのドアに碧子が寄りかかっている。
「んー。ああ碧子か。実行委員会は終わったの?」
「事件が…」
「二年生が落ちたんでしょ」
「うん……って!」
碧子がかみつくように駈け寄ってきた。
「そんな余裕かましてる場合じゃないよっ!」
「えー」
「ホラ! 行くよ」
「碧子が一人で行きなよ。後で教えてくれればそれで十分だよ」
「あか、それでも…」
と碧子が言いかけると「松下先輩!」と叫ぶ声がした。
遠くからサイレンの音がする。救急車が近づいてくる。
朱夏は持っていた本を置いて立ち上がった。そしてそのまま廊下に出て窓から下を見下ろす。
雨は上がった。
職員駐車場でも車の間を縫うようにしてベニヤ板を囲む生徒の姿がある。
「碧子、正門に来るの?」
朱夏が振り向くと碧子の姿はそこにはなかった。
朱夏はA棟の北側にある実行委員会本部に目を向けた。(実はここからではA棟との渡り廊下に阻まれて見えない。とりあえず気分的に)
碧子、あとは頼んだよ。朱夏は少しだけほほえむと窓から離れた。
6月24日 雨上がる 文化祭前日 駐車場の車53台 求めよ、さらば与えられん
アマオトー11
―◆―
物語が行き詰まってくると登場人物が増えるような気がする。
一人芝居というジャンルがある以上、登場人物は一人いれば充分だ。
小説にならない人生などない。
芦田はそう言っていた。
朱夏の人生は至って平凡なものだと思う。発電関係の機械製造会社に勤務する父と原子力関係の技術者の母、二つ年上で名古屋の大学に通っている姉がいる。
公立の小中学校を出て、ちょっとだけ勉強して市内で三番手の進学校らしい高校に入った。総合学科と言われる学科だったけれど、特に他の学校と変わらない。
と、ここまで考えて朱夏はやっぱり小説になどなりそうにないなと思う。
「あか」
うっと朱夏は顔を曇らせる。やっぱりこうくるのかとも思う。
「玄ちゃん! 帰ってきてたの?」
「姉に向かってその言い方はないなぁ」
「なにしにきたの?」
「暇だったから様子見に来た」
そう言って玄は自動車のキーをちゃらりと鳴らす。
「ウチもそうだったけどイマイチ盛り上がりにかけるね」
「香風は他にいろいろあるでしょ」
「この時期はメイポールダンスやって疲れ切ってる」
「香風も明日からだって聞いたけど」
「ふぅん」
玄は朱夏に近寄るとふいに頭をなでた。
「子ども扱いしないで」
「子どもだから」
「じゃない」
「子どもじゃない。アレ」
てるてる坊主を指さす。
「あれは郡司先生が作ったの!」
「そうなの」
「それよりなにしに来たの?」
「いや、私が来たらと事件が起きるかなぁって。で、どう?」
「事件なんかそうそう起こる訳ないじゃない」
「いやいや。こういうイレギュラーが登場したら起こるのがお決まりで」
「イレギュラー?」
「あかの人生におけるイレギュラーは私だから」
「そんなイレギュラーはいらない」
玄は頭に乗せた手をガシガシと少しだけ強くなで回す。
「もうっ、玄ちゃんっ!」
朱夏が怒るのも気にせず玄はなでまわし続ける。
6月24日 雨のち晴 文化祭前日 抜けた髪の本数(目視できただけで)57本。 髪は長い友達。
アマオトー12
―◆―
「あんた何組だっけ」
「七組。そろそろ本当にやめて」
朱夏はぶすっとした声で言う。払いのけてもムダなことはコレまでの年月で知っている。
「つれてって」
「なんで?忙しいんだけど」
「誰もいないじゃん」
「……」
「あ、そうだ。これ」
玄が手に持っていた紙袋を持ち上げる。なんとなく朱夏は受け取る。
「ヤバトンのTシャツ。欲しいでしょ」
朱夏は紙袋をのぞき込んでビニールに入ったものを取り出す。紺色の布がある。
「中見ないの?」
「いい。後で家で見る」
「何で」
「ネーミング的にここでは開けない方が良さそうだから」
「どうして」
「玄ちゃんが意気揚々と買ってきたものにはロクなものがなかったから」
「毎年クリスマス・プレゼントあげるじゃない」
「そうだね。ありがとう」
「心がこもってない」
「クマのぬいぐるみは殺人的に怖かったし、バッグは鉄板が入ってるんじゃないかってくらい重いし、防弾チョッキを喜ぶ高一がどこにいるの?」
「命より大切なものはない」
「だからって防弾チョッキはない」
「防刃の方が良かった?」
「大差ない」
「ベレッタとか」
「つかまりたくない」
「陸奥(むつの)守(かみ)とか」
「廃刀令違反」
「それってまだ有効なの?」
「廃止されたとは聞いてない」
「ところでここは何をしているの?」
「何も…って、古本市」
「古本ってあれ売り物なの」
「売り物です」
「さっき一冊取っちゃった」
「返して」
「タダって書いてあったけど?」
「除籍したのか。あれ創立当時からあるヤツもあるから相当に古い本だよ」
「転売する」
「は?」
「転売。これなんか多分いくらか値段つくから」
バッグからハードカバーの文庫本を取り出してみせる。
朱夏には確かに珍しいもののようにも思えた。
「はやくつれてって」
「どこに」
「あんたのクラス」
「そこの階段降りて左に行って真ん中あたり」
「つれてって」
「忙しい」
「誰もいないのに?」
「店番はいないと」
「つれてって」
「み・せ・ば・ん」
玄はちぇと言って本当に残念そうな顔をした。心なしかてるてる坊主に似ている。
6月24日 雨のち晴 文化祭前日 古本市残り951冊 閑話休題と閑古鳥って似ている。
アマオトー13
―◆―
学習室①にいると予想外に目立つ。
盗まれて困るようなものもないので勝手に出て行く。
東雲高は何が面白いのか死角がほとんどない。学校の周囲1キロは田んぼと畑だし、それを隔てる壁もすべてフェンスになっている。北と西は門があるから人目がある。東はグラウンドで、こんなときにのこのこ出て行ったら余計に怪しまれる。と、なれば残るは南側だ。
朱夏はB棟からC棟をつらぬく渡り廊下をC棟に向かって歩き始めた。
突き当たりに階段がある。左手は地学室を改装したPC室、右手には図書室がある。
なんとなく階段を登ってみる。11段上ったら踊り場でそこからさらに11段。全部で22段。
静かな空間があるのかと思ったら左手の美術室から怒号が響いた。
「あーっ」
「なにやってんだよ」
「どうすんの」
思わずのぞき込む。
裏側の木材をむき出しにしてカンバスが床に突っ伏している
やっちゃったんだ…と朱夏も同情する。
そろそろと持ち上げると油絵のコピーが床にくっきりと残っている。
美術部はぎりぎりまで絵を描いていたのだろう。完成を見ようとしたのか、運び出すところだったのかは分からないけれど、表の面を下にして床に倒れたと言うわけだ。
朱夏はそっと立ち去った。
渡り廊下は二階をつないでいるので行き止まり。向かいのLL教室からは英語部が英語劇の練習をしている雰囲気を読めば、下に降りるしかない。登ってきた22段を降りる。さらに22段。
一階に降りるとガラス越しに見える中庭で生徒が騒がしくしている姿は見えても、校舎の中は対象的に静かだった。上履きをキッと鳴らして後ろに向きなおると、ドアの向こうにはテニスコートがある。
朱夏はそのまま進むとガラス戸を押した。ガチと金属音がするだけで開かない。下のカギのノブを回して解錠する。
むっとした空気が襲いかかってくる。
一歩踏み出すと雨上がりの葉っぱがキラキラと輝いている。
化学室の外壁に背を預けると、ベストがコンクリートにすりつけられる感触がした。
足を引き寄せ膝の上にあごを乗せて、テニスコートを眺める。穏やかな六月の午後だった。
この時間が永遠ならいいのにと、朱夏は願った。
6月24日 文化祭前日 化学室の前に干してあった雑巾の数18枚 美術部には同情
アマオトー14
―◆―
どんなに願ったって、誰にでも平等に朝は訪れる。
と思ったらなんだか寒い。布団と肩の閒から入ってくる風は冷たく、体をどんどん冷やしてくる。
毛布を体にきつく巻く。
今度は鼻先が冷えてくる。体を丸めて寒さを凌ごうとするけれど、滲みてくる寒さは尋常ではない。まるで冬のようだ。
我慢ができずに起き出す。
ブルッとふるえる。そろりと足を床につける。意外と冷たくない。
息は白くないのを確認する。
枕元のデジタル時計を見ると6月25日20℃45%となっている。
温度計だけが壊れたのかと疑って、一度立ち止まり考えてみる。
どれが正しいのか。
日付が正しいのならば温度がおかしい。
温度が正しいのならば日付がおかしい。
湿度はこの際関係ないよね。
では、正しいのはどちらか。その答えを求めてカーテンの方を見る。遮光カーテンを囲むように光がぼんやりと広がっている。
求めよ。さらば与えられん。
朱夏は意を決するとカーテンを開けた。
白い壁がある。空間が白で満たされている。見上げれば空はねずみ色。
ガラスのスミがうっすらと白くなっている。触れてみても字は書けなかった、
寒いわけだ。
正しいのは日付の方だったのかと朱夏は思う。
ゴウンゴウンと低い音が外から響いている。
ベッドの上を見れば放り出されているエアコンのリモコン。愛称はこんこん。
恐らくはこうだ。
寝ている間にベッドのそばに掛かっているリモコンを左手で突き上げて外れたリモコンが布団の上に転がる。そのまま体の下敷きになったところでピッ。その後もゴロ…ピッ、ゴロ…ピッが繰り返され、設定が冷房・強風・18℃になったというわけだ。
まったくどんなことでも起こりうるのだと思うた。
笑ってくれ。この哀れな女子高校生を。
ちょっとだけ異世界? もしかして銀世界? とか期待した自分を恥じながらエアコンを止める。
窓を開けて六月の湿った空気を入れる。足下がむわっとする。
朱夏の意識も現実に引き戻される。
時計はやっぱり6月25日を示している。
とりあえず朝ごはんを食べよう。
6月25日 雨 文化祭1日目 室温20℃ まだ夢かもしれない。
アマオトー15
―◆―
古本市が行われる学習室①に行くとてるてる坊主の首が切られていた。
「先生、怖いです。子どももくるので取ってください」
「私は約束通りにしただけ」
とりつく島もない。
「龍蔵寺さんのクラスは何だったの?」
「つりぼり、だそうです」
「キャッチアンドリリース、ね」
「そういわれるとエコロジーですがけれど…結局昨日の決壊で鮎は4分の1亡くなりました。今日買ってくるとか」
という訳で、朱夏は臨時に300円の出費を余儀なくされた。断る手もあったけれど、当番を文化祭の間中フケる身としてはいたしかたない。
「そろそろ体育館に行きなさい。点呼始まっちゃうから」
出欠席は朝の体育館で取ることになっている。お化け屋敷などで教室が使えないクラスがあるからだ。
朱夏が体育館に入ろうとすると脱いだ上靴で体育館の隅はあふれかえっていた。少しばかりは踏みつけられる覚悟はしていると勝手に判断して、上靴を脱いで両手に持ちほっほっほっと靴の間を飛び石の上を渡るように飛んでいく。
―あか…
クラスの列の一番後ろに碧子が立っていて、出席簿を持っている。
―遅いよ。
「ごめんね。私が最後?」
「何人か来てないのもいるけど、サボりだよ」
「そう」
朱夏は腰を下ろした碧子の後ろに、すとんとしゃがみ込む。
オープニングセレモニー!みたいな派手なものはなく、淡々と事が進んでいく。
前の碧子の背中をつつく。
「藤崎先生は?」
「私にコレ預けてグラウンドに行ったよ」
碧子は出席簿を持ち上げる。
「なんてアバウトな…」
「いいんだよ、アバウトで。隣見てみなよ」
朱夏は隣の列を見る。南埜先生のクラスだ。
四角四面。カチコチに固まっている。怯えさえも感じさせる。
「人は自由を主張しないと。不断の努力で自由は維持できるんだよ」
「この状態は放置とも言うよね」
「まぁ、自由すぎても自由から逃亡するっていうよ」
「人はどうしたいのかね」
「さぁ? まずはこの蒸し暑い空間からの解放を望もう」
「とはいえ、この天気じゃ試合になんないよね」
「藤崎はやる気だったよ」
「うわぁ…」
泥にまみれた選手を想像して、お腹のあたりがジャリジャリするような気がした。
―開会宣言。
いつの間にかプログラムは進んでいる。壇上のマイクの前に昨日劇部に圧倒されていた男子らしき人が出てきた。実行委員長は彼なのだろう。
それからが長かった。彼は10分以上文化祭の歴史と名前の由来、今回のテーマについて一通りコンコンと話したのだ。三つの話題を話した事を考えるとむしろコンパクトだったかもしれない。けれども、それにしたって10分以上という時間は、この六月の、この雨の体育館で、この全校生徒の前で、話をし続けるというだけで悪夢であった。
―ここに開会を宣言します。
あとは流れ解散。
ステージの上に並べられた椅子はこの後行われる、吹部の午前の部用らしく、セレモニーでは演奏しなかった。
「じゃあ、学①に行くね」
「あとで様子を見に行くよ」
碧子と別れた。
6月25日 文化祭1日目 雨 開会宣言の時間14分56秒 自分で自分を褒めてあげたい。
アマオトー16
―◆―
ラベンダーの香りがする。
タイムリープとは時間跳躍と身体移動を同時に行うこと…と説明を受けても分からないものは分からない。
「小説にならない人生を生きているものはいない」
もう定年を迎えて久しい芦田が言った。
国立文系クラスの朱夏にとって古文は受験に直結する科目の一つだった。
英語-言い換えれば語学全般-が苦手な朱夏には英語の次に苦痛な科目でもある。
将来何の役に立つのかも分からない。
そんな気分で、あと2分で終わることを時計で見ていた。
ふいに授業を止めた芦田はかみしめように言った。
「皆が小説に足りうる人生を送っている。無論、私も含まれるのだろうが…いかんせん歳を取り過ぎた」
そこでチャイムが鳴る。
荷物をまとめて職員室に戻っていく芦田の背中がやけにくっきりと見えた。
あぁ、私はこの先を知っている。
このあと碧子が来てこう言うのだ。
「――」と。
あれ? 思い出せない。
ああ、コレはリアルタイムで進んでるから。記憶そのものがないのだから仕方がない。
でも、私はこの続きを知っているような気がする。
このあと碧子が来てこう言うのだ。
「朱夏」と。
あれ? なにかが違う。もう一度。
このあと碧子が来てこう言うのだ。
「あか! 起きなさい!」と。
「あと20分…」
ポコンと頭を叩かれる。「5分なら分かるけど。20分って人をなめてるの!?」
ラベンダーの香りがする。
「あか! これ以上この状態を続けるなら恥ずかしい話をするよ!」
雨の音もする。
雨? ラベンダーじゃなくって?
深町君はどこ?
暗い。どこまでも黒い。黒洞々たる闇があるばかりである。何も見えない。怖い。
「何も見えない。怖いよう…」
「目閉じてるんだから当たり前でしょ。こんなコントな会話を妹とする日が来るなんて!」
そういえば目を閉じてるような気がする。
意識して目を、まぶたをあげてゆく。だんだんと輪郭がはっきりとしていく。
「どうして玄ちゃんがここにいるの?」
「どうしてって、家の居間に私がいちゃ悪いの!」
「だって文化祭が…って、今日は何日?」
居間に掛けてある日めくりを見ると24日だった。文化祭の前日である。
「ウソ…」
「あ、忘れてる。母さんか」
玄ちゃんはそう言って立ち上がり日めくりを一枚はがした。
「帰ってきたと思ったらすぐに寝ちゃうから。さっさと制服着替えて来な。ごはんだよ」
「玄ちゃんラベンダーの香りがするけど」
「トイレの消臭剤買ってきたから」
「そっか。そっかぁ…」
朱夏は居間の家具調こたつの周りに敷いてある長座布団から起き上がるとペタペタ数歩歩いて自分の部屋の戸を引いた。
6月25日 雨 文化祭1日目 古本市の残り 847冊 未来のことは考えない。なぜならすぐに来るからだ。
アマオトー17
―◆―
少なくとも釣り堀は他のクラスに比べれば人がいるように見えた。
常に周りには6~8人がいたし、教室の中にも列があるっぽかった。
ただ、生き物を遊びにするのはいかがなものかと思う。
学①のベランダからは釣り堀の様子がよく見えるので古本市のお客さんがいないときはそこで下を見ていた。
「しゅーかー、やるー?」
朱夏の姿を認めた咲が下から誘っている。
「いいー。それより頼まれてくれない?」
「何をー?」
咲が朱夏の真下に来る。
「これ、家庭科部の食券なんだけど、適当に買っておいてくれない?」
「おっけ。なにか欲しいものある?」
「焼きまんじゅうだけ。あとは適当で」
「りょーかい」
「じゃ、行くよ」
朱夏はポケットを探って消しゴムを取り出した。食券に包んで下に落とす。
ナイスキャッチ。
下から咲の声が響く。咲は朱夏に手を振ると中庭に出ている家庭科部のテントの方に走っていった。
『すいません』と呼ばれたので急いで教室に戻った。
ちょっと背の高い男の子が本を持ってポツンとレジの前に立っている。
出されたのは『失われた時を求めて』。裏表紙をめくって値付けを確認すると値札がない。
「申し訳ありません。これはどの山から取ったものでしょうか?」
「あそこだけど」
除籍した本の山ではなかった。ならば値札が必ずついているはずなのに。
もう一度確認するけれど、やっぱりついていない。
「あのう…ダメなんですか?」
「え…いえ、大丈夫です」
郡司先生はいない。――ま、いいか。
「これは図書館で除籍した本だと思いますので、無料でお持ち下さい」
「タダってこと?」
「はい、どうぞ」
「……ふぅん」
男の子は持っていたバッグに本をしまうとちょっと頭を下げて出て行った。
正直なところ少し嫌な予感がしていた。ここから何かが始まるような、胸がもやもやするような、そんな予感が。
6月26日 雨 文化祭二日目 午前9:03分 首をちょん切られたてるてる坊主3つ 降水確率は何%から傘をもってゆくべきなのだろう。
アマオトー18
―◆―
一昨日の事件についてそろそろ話そう。
端的に言えばアレは事件とも言えたし、事故とも言えたし、事後処理が大変だったとも言えた。簡単に言おう。二年生が落ちたのだ。いや、落とされた、の方が正しいかもしれない。
文化祭の準備の日はやはり校内が浮つく。ざわつくし、気分が高揚するから気持ちも大きくなってしまう。
そんな中で事件は起こった。
実を言うと朱夏は事件の終わりを見ていた。
事件の後で碧子は事後処理と事情聴取で結構な時間拘束されていた。
ここまでを語ればおわかりかと思う。
「あか」
「碧子、実行委は良いの?」
「なんとか」
「劇部の公演って今日だったよね」
「これからだよ。一応フィナーレだからね」
「何時から?」
「11時と16時だよ」
「そうなんだ。結局、碧子出るんだって?」
「は? どこからそんな話が?」
「言ってみただけ」
「あか。そういうこと言ってると、これやらないよ」
碧子は手に持ったビニール袋を持ち上げる。茶色が透けて見えた。
「それは困る」
「咲から預かってきた。私にもちょうだい」
ガサッと碧子は朱夏にビニール袋を渡す。まだ温かい。中をのぞくと焼きまんじゅうが二本と焼きそばが一パック入っていた。
「それから、消しゴム」
朱夏の手の中に落としてくる。
「焼きまんじゅうでいい?」
「いただこう」
碧子は休憩用に黒板の前に置かれた椅子に座った。朱夏も隣に座り、中から焼きまんじゅうのパックを取りだした。輪ゴムを外してパカッと開くと良い香りがする。
「碧子、どっちにする?」
「こっちで良いよ」
無造作に自分から近い方の串を持ち上げる。
焼きまんじゅうは口のまわりじゅうをタレだらけにして大口で食べないとおいしくない。昔祖母がそう言っていた。
朱夏はこの歳になってもその食べ方でないとおいしくない気がする。年ごろの女の子としてはいかがなものかと思うけれど。
バクッと噛みつく。
やわらかい生地にタレの焦げた香りが香ばしく広がる。
「あか。はしたない」
碧子はちびちびと食べている。
「やっぱりこうやって食べないと」
「中身は変わらないでしょうよ」
「それで碧子。一昨日の問題はどうなったの?」
「バカだよ。釣り堀に落ちるなんて」
「まさかね」
「あのあと大変だったよー。藤崎ちゃん来ないし、南埜はカンカンだし、私は事情知らないのに缶づめにされるし」
「救急車が来てたけど?」
「あれは近所を通っただけ」
「なんだ。つまんないの」
「つまんなくて良い。平凡な人生が最も生きにくい人生。中庸が肝要なんだよ」
「にしても、落としたんだって?」
「んー、聞いた感じだと投げ込んだって感じだけど」
「盛岡、大喜びじゃない。柔道部に勧誘しないと。一本背負い?」
「背負い投げ、かな」
「にしても。そんな騒ぎ止められなかったウチのクラスって…大丈夫?」
「二人がふざけて走ってきて、そのままもつれ合うようにって感じらしいから、止める暇もなかったってさ」
「言い訳だね」
「言い訳だよ」
6月26日 雨 文化祭二日目 午前9:36 釣り堀の入場者累計243人。 意外と盛況だな。
アマオトー19
―◆―
11時からの劇部の公演を見に行った。というより郡司先生に学①を追い出された。それなりに静かで座れる所…と思って周りを見ていたら、劇部のポスターがふと目にとまった。体育館で行われる公演なら座る場所もあるだろうし。
劇はオーソドックスな「ロミオとジュリエット」をやっていた。ずいぶんはしょってあるようだけど。
客の入りは良いとこ3割くらい。このところの雨のせいで涼しかったし、暗くなっているのは眠気を誘う。
…ああ、ロミオ。あなたはどうしてロミオなの?
…どしてかなーと思いながら朱夏の意識は急速に薄れていった。でもこの舞台なんか変だ…
………はっ。寝落ちしてた。制服の上に出来たシミをハンカチで拭きながらステージを見る。
あれ?さっきからジュリエット見てないような。舞台上にいるロミオがジュリエットに話しかけると、舞台裏からジュリエットの声が応える感じだ。
なるほどね、と朱夏は思い当たった。
ロミオの一人芝居と化しているけれど、まあ、これはこれで良いのか。劇部の機転に拍手だ。
なんとか最後まで劇は進み、幕が下りた。最後のシーンだけはさすがにジュリエットいたけど。時間は12時05分で、そろそろお昼が恋しい時間だった。
学①にもどって焼きそばを食べようと席を立ったとたんに、幕の内側から人が倒れるような大きな音が響いた。悲鳴も上がる。
朱夏はちょっと興味をそそられたけれど、何も出来ることはないと考えて、その場を立ち去った。
体育館から外に出るとすこしひんやりとした。まだ雨は上がらない。
学①に戻りながらいくつかの教室を覗く。
お化け屋敷は学年ごとにあったから3コはあるはずなのに、3年生の場所も人があふれて並んでいた。
ヒョコッと7組の教室を覗くと、待合の椅子に何人かが座っている。小学生らしき女の子もいた。
「朱夏。どうしたの?」
「さっき劇部見て来たとこ。結構盛況だね」
「そう? 私たち何もすることなくって」
「咲、さっきはありがとう」
「いいよ。それよりあれでよかったの?」
「碧子と分けた」
「ああ、みどり大変そうだよ。さっきも実行委に連れてかれた」
「また? 今度も釣り堀関係で?」
「あはは。そうかもね」
「子どもが落ちたとか?」
「1年生の縁日のヨーヨーつりでプールに落ちた子がいたって聞いたけど。ウチはホラ。とりあえず男子が見てるから、まだない」
「1年生の縁日かぁ」
「面白かったよ。ホラ、これ。射的やってきた」
咲が広げた袋には雑多なものが入っている。
「私もあとで行ってみる。ヒマなら来てね」
バイバイと手を振って咲と別れた。
廊下ってこんなにも狭かったのかと感じるほど人であふれかえっている。
6月26日 文化祭二日目 雨 午後12:13分 ロミオの演者は1名。 ジュリエット。あなたは本当にジュリエットなの?
アマオトー20
―◆―
「失われた時を求めて」はマルセル=プルーストが書いた傑作だ。
400字詰めの原稿用紙にすると10000枚を超える長編である。日本語版は全7巻。
喫茶店で漂った一杯のコーヒーの香りから、人生の回想の旅にでる壮大な物語である。
と、こんなことはさておき。
先ほどの男の子が持ってきたのはそのうちの5巻であったことに朱夏は焼きそばを食べながら引っかかっていた。
家庭科部がもやしで量を増やしていた。しかも半生が混じってる。
「劇部はどうだった?」
郡司先生が訊いてきた。
「ひゅじひかったでふ」
ゴクン。
「涼しかったです」
「公演ができないところじゃなかったの?」
「キセキですね」
「キセキねぇ…フィナーレで演じるのはどうなりそうなの?」
「期待しない方が良いとは思います」
「そのときになれば分かるか。茶道部には行った?」
「茶道部?」
「和泉ちゃんが券買ってくれたのに来てないって探しにきたから」
「どこでやってるんでしたっけ?」
「合宿所でとか言ってたけど。ここはもういいから行って来たら?」
「はぁ…」
朱夏はあまり動きたくなかった。
こんなことを思っていると多分この後碧子が来るんだろうな、とか思っていると
「あか」と声がかかる。
「碧子」と顔を上げると玄ちゃんが立っている。
「さっき入り口で茶道部に券買わされちゃってさ!」
「行く。行けばいいんでしょ」
「行ってらっしゃい」本日二度目のお見送りの言葉をいただいて朱夏は玄を引きずるようにして教室を出た。
6月26日 文化祭二日目 雨 「失われた時を求めて」残り4冊 一冊は最初から行方不明。
アマオトー21
―◆―
にがい。そして熱い。
猫舌なのを意識させられるのはこういう時だ。
「先輩…」しかめた顔をしていると和泉ちゃんが「お菓子から食べるんですよ」と笑って言う。
なるほど。にがさを打ち消すために甘いものを食べるのではなく、先に口の中を甘くしておくのか。
となりで玄ちゃんがすましている。お茶菓子はもうない。
「どう? 青春の苦さが分かった?」などと言ってくる。
できればほろ苦いくらいで終わりにしてほしい。
「青春とはうら淋しく、陰鬱なものである」
「なによ、それ」
「どくとるマンボウ」
「航海記?」
「青春記。松本平をうすい霧が覆っていく。そういう風景である」
「朝霧か」
「夜霧かも」
「狭霧か」
「霧雨かも」
「それは霧じゃない」
そんな会話をしているうちにお茶が下げられていた。
「朱夏、あんたこれからどうするの?」
「そろそろ古本市の片づけを始める時間だから教室に戻る」
「そう。あたしはどうしよっかな」
「後夜祭は部外者立ち入り禁止」
「つまんないの。あんた制服貸しな」
「は?」
「それであんたがこれ着て帰る」
自分の服の胸元をつまんでバカなことを言い出す。
「んな!…んなバカな事言ってる暇があるなら香風の文化祭行けばいいでしょ!あそこはOGなら参加できるって」
「十分参加したから、もういいかなって」
「さっさとどっか行けっ!」
朱夏は足がしびれて動けなくなった玄を置いて立ち上がると、出口に向かってスタスタと歩き出した。
6月26日 雨 文化祭二日目 和泉ちゃんの浴衣の朝顔の数は8つ 大きな柄が鮮やかだった
アマオトー22
―◆―
「あかー。帰ろ」
「ねぇ、今日って遅刻いたっけ?」
朱夏は書きかけの学級日誌を指さした。
「え…誰もいなかったと思うけど…」
「ありがと」
朱夏は遅刻欄になし、0名と記入した。
「先に自転車置き場で待ってる」
碧子が歩き出す。
朱夏は机の脇にかけてあるリュックを持ち上げるとペンケースを放り込んだ。
廊下に出るとガラス窓のあちこちに真新しいセロハンテープの跡が残っている。お祭りの残りかすだ。
特段に思うことはない。
朱夏にとってあの時間は来るべくしてやってきて、過ぎ去るべくして過ぎ去った時間だ。例えるならそれは定期考査に似ている。あらかじめ日時とスケジュールが決まっていて、それに従って始まって終わる。自分はその通りにこなすだけ。それだけだ。
次は定期考査の後に球技大会が予定されている。これもいつの間にかやってきて、決められた競技に早く負けたいと思いながらも、少しだけ負けたら情けないなぁとかも感じて参加して、順位が発表されて終わるのだ。
「失われた時を求めて」が売り物でなく、郡司先生の私物だったように。
そうやって日々が過ぎていく。
青春の苦さを感じる間もなく。
パコンと後ろからはたかれた。
「あか。なに哲学的な何かを口走ってんの」
「碧子!? なんで?」
「あかがこれ忘れてくから」
碧子の右手には学級日誌がある。朱夏の右手には数学のノートがある。
「あれ?」
「文化祭ボケも大概にしなよ」
碧子が先に歩き出す。その背中を朱夏が追いかける。
6月30日 晴 文化祭終了から三日後 快晴と晴の違いは見上げた空の雲の量
アマオトー23
―◆―
小説になり得る人生が特別なのか。
特別な人生が小説になり得るのか。
結局はそんなとこなのだろう。それでもやっぱり朱夏の人生は小説になるものではないと思う。
芦田がこれを読むことはないけれど、これを読む機会があったら彼は何というのだろう。それでも誰もが小説足り得る人生を送っていると言い続けるのだろうか。
少なくとも何年か後に、これを読む機会が自分にあったとしたら、どう思うのだろうか。
それを楽しみにして今は明日が来るのを待とう。
今日とあまり変わらない明日が来る平凡な幸せにまどろみながら。
了
県立東雲高校文化祭へようこそ!【完結】
ありがとうございます。
夏と言えば、文中でスイカ、向日葵、蝉時雨と言っていますが、私にとっては地獄の【夏休みの友】しか思い浮かびません。
ぜんっぜんっ【友】じゃない!
どうやって言い訳を考えるかが夏休みの宿題でした。
究極は【ごみと間違えて捨てちゃいました】からの【じゃあ、コレやるから】【……】
とはいえ今回はおとなの【夏休みの友】として、1か月で書ききれるかチャレンジ!を自分で勝手に行い、出来たのがこの作品です。
シーン一つが一日分に当たります。サボった日もあったので、思うように分量が統一できていません。
文体がどちらかというとアニメの台本に近いですね…脚本なのかな、とか。
打ち込み終わりました。
では、また。
※よろしければツイートやいいね、お願いします。励みになります