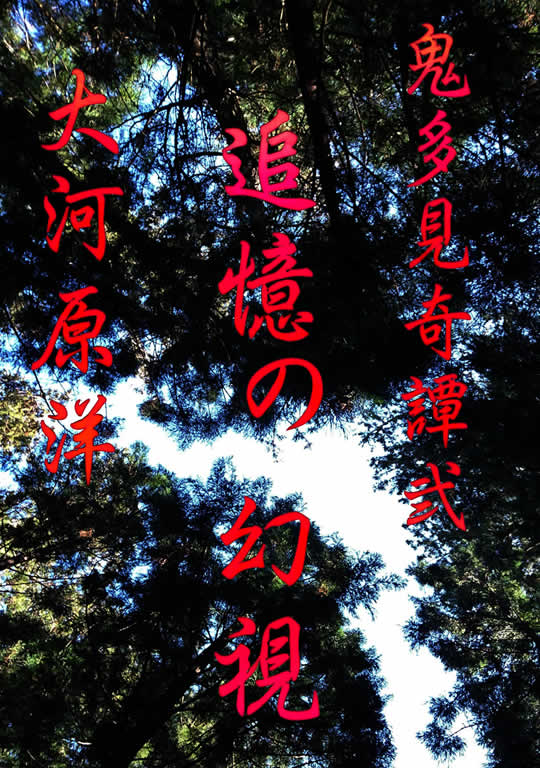
鬼多見奇譚 弐 追憶の幻視
〔一〕郡山
クルマの前の席から聞こえる、お母さんと紫織の陽気な歌声で正直頭が痛い。
唄っているのは歴代のプリキュアのオープニング曲だ。
わたしは溜息と共に、抱いている柴犬のボンちゃんに額を押しつけた。
「クゥ~ン」
窮屈なのかボンちゃんは身体をモゾモゾと動かす。
本当は安全のためにもゲージに入れたいんだけど、本人が断固として入ることを拒否した。
普段は大人しいのに、何故かゲージを見ると親のカタキみたいに吠え始める。
保護犬だった彼には、ゲージにトラウマがあるらしい。
だから、わたしと叔父さんが交代で抱いてクルマに乗っている。
チラリと隣の席を見ると、叔父さんは物憂げに窓の外を眺めていた。
でも、わたしの視線に気付いたのか、こっちに顔を向けた。
「代わろうか?」
叔父さんはボンちゃんを受け取ろうと腕を伸ばす。
「だいじょうぶ」と応えて、わたしは顔をボンちゃんの背中に埋めた。
クロシバのボンちゃんは、頭や顔の周りの毛はモフモフして柔らかいけど、背中の毛はけっこう硬くてゴワゴワしている。
この毛もそろそろ冬毛に抜け替わるだろう。
わたし、真藤朱理と妹の紫織、母の遙香、叔父の鬼多見悠輝と柴犬の梵天丸は、母の運転する日産ジュークで千葉県八千代市の稲本団地から福島県郡山市の祖父の家へと向かっていた。
途中、道の駅やコンビニで休憩をしたりしながら、四時間以上かけて郡山までたどり着いた。
紫織は放っておくとズッと3DSでゲームをしているから、お母さんが一時間おきぐらいに、しりとりをしたり、クイズを出したり、デジタルではないゲームをやらせている。
そして最終的に歌になったんだけど、どうしてプリキュアなのかは解らない。
幼稚園児じゃないって最初はイヤがっていた紫織だけど、唄わされるうちに楽しくなってきたのか今は熱唱している。
お母さんは楽しいというより、ヤケになっているみたいだ。叔父さんも郡山に入ってから憂鬱そうだ。
二人とも実家に帰りたくないんだ。
わたしは二週間前に起こった事件のことを、また考えていた。
凜と香澄、そして由衣。わたしはこの三人と、セーメイ様というコックリさんに似た占いをした。
わたしのせいで、凜と香澄は魔物に取り憑かれ入院する事になった。担任の萩原先生も巻き込んでしまい、入院だけでは済まず教職を続けることも難しくなっている。最後に由衣だけど、彼女はもういない。
叔父さんとお母さんはわたしのせいじゃないって言うけど、セーメイ様でわたしの『験力』が目覚めて、魔物を呼び寄せたのは事実だ。
この能力の事を教えてくれなかった叔父さんを、怒ったり恨んだりしていないと言えばウソになる。
だけど、わたしを守ろうとして色々苦労していたのが解ってしまうから、感情の整理ができず、モヤモヤが溜まる。
「キュ~イ」
ボンちゃんが身体をヒネって、わたしの顔をなめようとする。
どうやら気持ちを察してくれて慰めようとしているらしい。
「ありがとね……」
いじらくてわたしはボンちゃんの頭をなでた。
「またあるな……」
叔父さんが外を見ながら、ボソリとつぶやいた。
視線を追うと新興宗教の建物がある。
派手な看板が掲げられていて『アークソサエティ』と書かれている。
「郡山って新興宗教が多いね、震災の影響かな?」
「いや、前から結構あったけど、あのアークってのは震災後に若者を中心に信者を増やしてるみたいだ。
ま、宗教なんて新旧宗派問わず、ろくなモンじゃない」
「おじさんがそれを言うッ?」
わたしたちが向かっている祖父の家、つまりこの人の実家はお寺だ。
「だからこそ叔父さんは言ってるの。神さま、仏さまなんて空想の産物、プリキュアと一緒よ」
お母さんが唄うのを止めて断言した。言うまでもないけど、この人もお寺の娘だ。
「でも、おじさんは真言を唱えて呪術を使ってるじゃない」
「信仰なんて、一兆パーセントしてないけどね」
またこの人は、わけの解らない事をサラッと言う。
「朱理、真言自体に超常的な力なんてない、ただの言葉に過ぎないんだ。でなきゃ、真言を唱えれば誰でも超能力を使えるはずだ」
たしかに、真言を唱えたからって不思議な能力を使えるわけじゃない。それは解ってるけど、じゃあ何で真言なんて唱えるんだろ?
「あれは験力を変化させるための鋳型だ」
わたしの考えを見透かしたように叔父さんが答える。
「例えば叔父ちゃんの験力の特性は念動力だ」
視線を自分の前に座る紫織に向けた。
コイツは唄うのをやめた途端に3DSで遊び始めている。
「あッ」
紫織の手から3DSが離れ、空中に浮いた。
「オジちゃんッ!」
「ハハハ……悪い悪い。でも、お前も少しは験力について聴いといた方が良いんじゃないか?」
紫織はプッと頬を膨らました。
「いいよッ、どうせジィジのところで、べんきょうするんでしょッ?」
「だからこそ、予習は大事だろ?」
紫織は空中に浮いている3DSを両手でつかみ降ろして、ゲームを再開した。
かなり異様な光景だけど、なれとは恐ろしい物で、空中に物体が浮き上がっても何の感動も起きない。
叔父さんは「必要ないか……」とつぶやいて苦笑した。
紫織には、わたしより遥かに強い験力が秘められている。お母さんと叔父さんは、妹の能力を封印するつもりだ。お祖父さんに会いに行く最大の目的がこれだ。
わたしの験力も二人は封印するつもりだったけど、わたしはそれを拒んだ。
大切な人たちを傷つけ、生命を奪った忌むべき力。正直、こんなモノ欲しくない。
超能力者への憧れや、優越感が無いわけじゃないけど、それだけの理由で験力の修行を選んだわけじゃない。
「あれくらいの事なら別に真言なんて必要ない、でもこっちは必要だ」
叔父さんは右の掌を上に向けた。
「オン・アギャナエイ・ソワカ」
掌の上に一瞬、炎が現れる。
「ちょっと悠輝ッ、クルマの中で何するの!」
「あ、ごめん、姉貴。うっかりしてた」
「そういう危ないことは、着いてからにして」
「おっこられた♪」
「お前も、ゲームばっかやってると叱られるぞ」
「ふ~んだ」
「さて、気を取り直して。
今、唱えたのは火天真言。火天は修験道や密教じゃ、格下のキャラだ」
「キャラって……」
アニメやゲームじゃないんだから。ホントにこの人はバチアタリの化身だ。
「火天は炎属性としては最弱だけど、不動明王は最強クラスだ。
じゃあ不動が験力を強化してくれるのかと言うと、そんな事があるわけがない。
あくまで自分自身の験力を変化させているだけなんだ。
極端な例を挙げると、験力のない人間が火天真言を唱えようが、不動明王火界呪を唱えようが何の関係もない」
験力があっても修行しなければダメだ。現にわたしや紫織が真言を唱えても、何も起きない。
「修行って言っても、真言を何度唱えても何にもならない」
また、考えている事を見透かされた。これも験力なの?
「お約束で、肉体と精神を鍛えるってのは基本だけど、直接験力に影響を及ぼすのはイマジネーションだ。
火天はその名が示すとおり火を象徴する。でも、大きな炎じゃない。蝋燭やライター、せいぜいガスコンロの強火くらいだ。松明や焚き火になると強すぎる……
こんな感じで、自分の中でキャラとイメージを結びつけていく。
次に、そのキャラが自分自身と一体化しているイメージをする」
「それで験力が使えるようになるの?」
「験力というより『呪術』だね。もちろん口で言うほど簡単じゃない。実際、言葉じゃ上手く説明できないな。
どっちにしろ、先ず自分の特性の験力を使えるようにならなきゃ、『呪術』も使えない」
特性か……
叔父さんの話しだと、わたしのは『火』だ。魔物に取り憑かれた時、炎の塊を使って叔父さんを攻撃したらしい。
その記憶は無いし、叔父さんも詳し事は話してくれない。
紫織も同じ魔物に取り憑かれて、雷撃で叔父さんを襲った。
あの時は物凄かった。わたしは恐くて身体が動かなくなり、それで……その……失禁してしまった……。
妹にはそれほど強大で恐ろしい験力が秘められている。
わたしは紫織に比べると弱いけど、もう二度とこの能力のせいで誰かが傷ついたり、生命を奪われるのは絶対に嫌だ。
験力を封印しても現実から眼を背ける事にしかならない。
現にお母さんは封印しているのにも関わらず、験力を持つ姉妹を産んだ。忌まわしいこの力は封印したからと言って消えるモノじゃないんだ。
それにお母さんは紫織に取り憑いた魔物を験力でやっつけた。
封印は解けていないって言ってるけど、結局お母さんは叔父さんと同じ超能力者だ。
験力から逃げられないなら、叔父さんのようにちゃんとコントロール出来るようになりたい。
そしてこの呪われた力で大切な物を守れるようになりたい。それが出来れば、呪いは呪いでなくなる。
「で、結局どうすれば、験力をコントロール出来るようになるの?」
「そう結論を急ぐな」
「もうすぐ、爺ちゃんの家に着くから、そしたらウンザリするほど聞かせてもらえるわよ。今の話しとは、全然違うこと言われるだろうけど」
「ん? どういうこと?」
「爺ちゃんは、叔父ちゃんと違って考えが古いから、神仏を信仰する念いが云々っていう、くだらない話しを延々とするよ」
〔二〕戌亥寺
お祖父さんの家、と言うか戌亥寺は思っていた以上に大きなお寺だった。
小山の上に山門があり、そこまで階段が続いている。
その右側にはクルマを十二台止められる駐車場があり、一台白いクルマが止まっていた。
「いいのに乗ってるわね……」
お母さんがボソリとつぶやく。
「なんてクルマ?」
「FIATの500X Cross Plus」
「ふぃあっと?」
「紫織、テストに出ないから、覚えなくていいわよ」
「クルマに金かけるんなら、他に使うとこあるだろ?」
「ないんでしょ」
叔父さんのぼやきに、お母さんが辛辣に答えた。
この姉弟はよっぽど父親と折り合いが悪いらしい。
生まれて十三年間、わたしは母方の祖父母は亡くなっていると思っていた。なぜなら、この二人に祖父母について聞いてもはぐらかされていたからだ。
お母さんは、お祖父さんとお祖母さんはいないと言うし、叔父さんは家族はお母さんしかいないって言っていた。
本当はお祖父さんとの仲が最悪で、叔父さんは八年、お母さんは十七年も連絡を取っていなかた。
詳しいことは二人とも話してくれないけど、どうやら験力とお祖母さんが関係しているらしい。
わたし達はジュークを降りて階段に向かった。因みにウチのジュークの色はボンちゃんと同じ黒だ。
色とメーカーは違えどジュークと500X Cross Plus、どちらもSUVだ。いくら嫌っていても、クルマの趣味は似ているということか。
因みに叔父さんはクルマを持っていない、この人の愛車はGIANTというメーカーのATXというマウンテンバイクだ。
クルマを降りて、わたしはボンちゃんを解放した。
やっと自分の脚で歩けるのが嬉しいのか、ボンちゃんはわたしをグングン引っぱって階段を上がっていく。
気づくとお母さんたちを後に残して、ボンちゃんと二人で山門をくぐっていた。
三〇メートル四方の境内の正面に本堂があり、その左側には二階建ての住居が、右側には平屋のプレハブがあり『少林寺拳法』と看板が出ている。
わたしの視線は境内を竹箒で掃く、作務依姿の青年に向いた。
どことなく、叔父さんに似ている。
「ペットの連れ込みはやめてね」
ボンちゃんに気付いたその人は、迷惑そうに顔を上げてわたしに言った。
「あ、あの、わたし……」
年齢はわたしより上だけど、高校生ぐらいだろう。叔父さんの弟だろうか?
でも、お祖母さんは叔父さんが小さい頃に亡くなったはずだ。
お祖父さんが再婚したって話しも聞いていないし……
「君、ダレ?」
背後からお母さんの声がした。
振り向くとみんな追いついていた。
「明人?」
「ユウ……兄ちゃん?」
「おう、しばらく見ない間に大きくなったな」
「ユウ兄ちゃは、あんまり変わらないね」
二人が再会を喜んでる傍らで、お母さんは相変わらず納得いかない顔をしている。
「で、ダレなの?」
「誰って、従弟の明人じゃないか」
「あたしは知らない」
「あ、そうか、明人が生まれたのは姉貴がここを出た後か」
お母さんは嫌そうに顔をしかめた。年が気になったのだろう。
普段から若く見られることが自慢の母は、自分の年齢を意識すると精神的ダメージを受けるのだ。
「初めまして、門脇明人です……あの、遙香さん、ですよね」
「そうだけど」
「じゃあ、こっちが朱理ちゃんで、そっちが紫織ちゃんですね」
「初めまして真藤朱理です」
「こんにちは、しおりです」
お母さんたちが来たら、さっきと態度がずいぶん違う。
「ってか、何でお前がここにいるんだ?」
「いや~こっちの高校に進学して、ついでに……」
「坊主になりたいのか?」
「いや~、ハハハハ……」
「明人、親やウチのジジイに何か言われたんなら……」
「違う、ぼくが自分で決めたんだ」
「そうか? なら、いいけど」
「うん、アハハハ……」
「それより、犬を連れて来ちゃダメだったんですか?」
わたしはヘラヘラする明人さんが何となく好きになれず、思わずキツイ口調で聞いた。
「あ、ゴメン。実は……」
その時、けたたましい犬の鳴き声が聞こえた。
声に振り向くと、大きな白犬が物凄い勢いで突進してくる。
「ワンッワンッワワワン!」
「ガルルル!」
襲いかかられたボンちゃんが立ち向かい、ケンカが始まった。
白犬は秋田犬みたいだ。ボンちゃんの五倍以上はある。
これだけ体格差があるのにボンちゃんは全く怯まず、相手の懐に飛び込み首筋に噛みつこうとする。
秋田犬は完全に気圧されている。
ボンちゃんは小さくて大人しいが、決して臆病ではないし弱くもない。
わたしが魔物に襲われた時も命がけで助けてくれた。
だからと言ってケンカを放ってはおけない。リードを引いて離そうとするけど上手く行かなかった。
「政宗ッ!」
地響きのように轟く声がした。
秋田犬がボンちゃんから離れ、声の主のもとへ向かう。その声に威圧されたのか、ボンちゃんも後を追おうとはせず、身をすくめた。
お母さんと叔父さんが表情を強ばらせる。
作務依姿で坊主頭の男の人が、住居の玄関から出てきた。
「親父……」
叔父さんが小声で呟いた。やっぱりあの人がお祖父さん、鬼多見法眼だ。
お母さんの父親なのだから、若くても六十は過ぎているはずだ。
だけど、全然そんな年には見えない、身体も引きしまっていてスポーツ選手みたいだ。
少しだけ叔父さんに似ているけど、迫力と言うか威厳があって怖い。
お祖父さんの視線がわたしと紫織に向いた。わたしは無意識に一歩後ろにさがった。
「よくき来たなぁ~、おじいちゃんだよぉ~。朱理ちゃん、紫織ちゃん、初めまして」
相好を崩しお祖父さんがわたしの頭をなで、空いた手で紫織を抱き上げる。紫織はキャッキャッと声を上げてはしゃいだ。
「お腹すいてない? おやつの準備してあるからね。ままどおるとエキソンパイっていう美味しいお菓子があるから。
そうだ、夜はピザかお寿司でも取ろうか? それともどこかに食べに行く?」
お祖父さんは片手で紫織を抱いたまま、わたしの手を引いてボンちゃんごと家へ向かう。
この豹変ぶりについて行けず、お母さんと叔父さんに助けを求めて視線を送ると、二人ともポカンとしてる。
「な、なにアレ?」
「さぁ、孫が生まれると人が変わるって言うけど……」
「変わりすぎでしょッ? 気持ち悪いわ……」
「孫が来るって、ズッとソワソワしっぱなしでしたからね」
「あの親父が? 信じらんない」
あ、ダメだ、向こうもついて来てない。そう思った時、
「待てッ、親父!」
我を取り戻した叔父さんが声を上げた。
「自分の意に添わない息子と娘に声もかけたくないのは判るが、こっちにも都合ってもんがある」
お祖父さんが、叔父さんを振り返る。
「都合? 随分と身勝手な言いようだな」
「それも解っている。だから何を言われようと言い返すつもりは無いし、おれに関しては大学の費用も利子をつけて返す。だから朱理と紫織の験力を封印してくれ」
「父さん、あたしも頼むわ、お願いします」
お母さんは深々と頭を下げた。
わたしは験力の使い方を学びたいのであって、封印したいんじゃない。何度もそう言ったはずだ。
「それともう一つ。二人を守るための力が必要だ、協力してくれ」
「守る? 思い上がりも甚だしい」
「それでもおれはやる」
「簡単に修行や大学を投げ出したお前がか?」
「やりたい事があったからだ」
「やるべき事はどうした?」
「二十年間、親父のために人生を使ってきた。残りはおれが自由に使う」
「ならば何故、ここで親を頼る?」
「決まっているだろ、験力の封じ方を知っている人間を親父しか知らない。そして、親父以上に強力な魔物もおれは知らない」
「前者は判るが、後者はどうだ? 俺より強力な魔は本当に存在しないのか? そもそもお前に俺を倒せるのか?」
「だから協力しろと言っている。半年……いや、三ヶ月で親父を超える」
「二十年近く修行して出来なかったことが、たった三ヶ月で出来るのか?」
「試してみるか?」
一瞬で間合いを詰めて、お祖父さんに殴りかかる。
次の瞬間、あたしの手を握っていたお祖父さんの手が消えた。
視線をさまよわせると、さっきまで叔父さんが立っていた位置に紫織を抱いたまま立っている。
お祖父さんは紫織をそっと降ろすと、身を躍らせた。
叔父さんも素早くそれに立ち向かう。
目にも止まらぬ速さで拳と蹴りを繰り出し、同時に相手の攻撃をかわす。
叔父さんが間合いを取ると、足下の石が幾つか中に浮き、お祖父さんに向かって飛ぶ。
「フン」
お祖父さんが手をかざすと、全ての石が宙で止まり、今度は叔父さんに向かって飛んできた。
「ハッ」
叔父さんがそれを手で払い落とす。
「験力を使うか?」
「でなきゃ意味がない」
「余計お前が不利になる」
「望むところだ」
「口だけは一人前だな」
信じられない現象がわたしの眼の前で起こった。
お祖父さんが、二人、三人、四人と増えていく。
「なに、コレ……」
「まったく、気持ち悪い事が続くわ」
いつの間にか、お母さんが紫織と明人さんを連れてわたしの所に来ていた。
「あれがおじいさんの験力?」
「たしかにそうだけど、実際に増殖したわけじゃない、あくまで幻覚よ。叔父さんにだけ見せればいいのに、可愛い孫に自分の力を自慢したいんでしょ?」
「幻覚でも、ここにいる全員に見せるなんて……」
明人さんがの顔が青ざめている。お祖父さんの験力の強大さに改めて驚いているんだろう。
わたしもこの間の事件で信じられない物を幾つか見たけど、お祖父さんはそれを上回るかも知れない。
「ジィジ、忍者みたい」
確かにそうだけど、この状況で出てくる感想がそれなの?
叔父さんは少しも迷わずに、その中の一人を殴りつけた。次の瞬間、お祖父さんの姿が一つに戻る。
「さすがに騙されんか」
「中学生の時から見抜けている。いい加減、おれを舐めるな」
叔父さんが回し蹴りを繰り出すが、お祖父さんは素早く後ろに飛び退いてかわす。
「では、小学生に戻す」
不思議な現象が再びわたしの眼の前で起こった。叔父さんの身体がみるみる縮んでいく。
いや、縮んでいるんじゃない、若返っているんだ。
あっという間に叔父さんは、紫織ぐらいの年齢になった。
わたしは叔父さんの子供の頃の写真や動画を観たことがない。
記憶にある叔父さんは常に大人だ。実際には物心付く前から会っているから、高校生の頃の叔父さんも見ているはずだ。
だけど、それは幼稚園に通っている時で覚えていないし、例え記憶にあっても小学生未満の幼児にとって高校生は充分大人だ。
今、眼の前にいるのは、わたしよりズッと年下の子供だ。
なのにそれが叔父さんだと判る。眼の前で若返ったからなのか、面影があるからなのか、とにかく変な気分だ。
お祖父さんが叔父さんを蹴り上げる。
「くッ」
腕で身を守るが、お祖父さんは間髪を入れず正拳突きを次々に打ち込む。
今までに比べると決して激しい攻撃ではないけど、子供に戻った叔父さんは身を庇うのが精一杯で攻撃に転じられない。
「どうしたッ、さっきまでの威勢はどこへ行った?」
「クソッ」
いつもよりも幼く高い声で毒づくと、叔父さんは突き出されたお祖父さんの右腕に自分の両腕を絡め、顔面を蹴ろうと脚を振り上げた。
ところが脚の長さが足りず、簡単にかわされてしまう。
「届いているはずだ……」
そう、これは幻覚だ。叔父さんの身体は本当はもっと大きい。
「ただの幻ならな。だが、俺のは違う!」
お祖父さんが叔父さんの胸ぐらをつかんで投げ飛ばす。
「ぐッ」
地面に背中を打ち付けて、叔父さんは呻き声を上げた。痛みを堪えるために手足を縮めて身体を丸める。
「十年前の方がまだマシだった」
お祖父さんが、近づき叔父さんを見下ろす。
「こんな状態では三ヶ月どころか、三十年修行しても俺を超えることなど出来んぞ」
「うぅ……」
叔父さんの完敗だ。
と、わたしが思った次の瞬間、うずくまったままの身体がロケットみたいな勢いで空中に飛び上がり、お祖父さんに激突した。
「むッ?」
今度はお祖父さんが後ろに吹っ飛び、叔父さんの姿が一瞬で見慣れた大人の姿に戻る。
お祖父さんに体勢を立て直す隙を与えないよう、激しい拳の雨を浴びせる。
「タァアアァアアアッ!」
遂にお祖父さんが仰向けに倒れた。
いや、倒れたはずだった。
「なにッ?」
お祖父さんの身体が、それこそイリュージョンのようにパッと消えた。
「詰めが甘いな」
背後からの声に叔父さんが振り返ると、お祖父さんが立っていた。
「ウッ」
叔父さんが膝から崩れ落ちる。お祖父さんの拳を鳩尾に叩き込まれたんだ。
身体をくの字に曲げながらも、立ち上がろうと叔父さんは藻掻く。
「そこまでッ」
凜とした声が響いた。
「悠輝、いきなり飛ばしすぎると、修行する前に病院送りになるわよ。爺ちゃんも張り切りすぎ。孫が見てるからって、年寄りの冷や水はやめて」
「誰が年寄りだッ?」
「事実でしょ。紫織は面白がってるけど、朱理は完全に引いてるわ」
お祖父さんはわたしの顔を見て、ションボリした。
〔三〕祖母
「痛たた……朱理、もっと優しく」
消毒液を背中に吹き付けると、叔父さんが情けない声を上げた。
「自業自得」
わたしは突き放した。
今いるのは仏壇がある部屋で、わたしと叔父さん、それにお母さんしかいない。
お祖父さんは政宗くんとボンちゃん、そして紫織を連れて散歩に行った。明人さんはお務めだ。
この部屋に来てからお母さんは仏壇を眺めている。ううん、正確にはそこに在る遺影を見ているんだ。
そこにはお母さんと叔父さんによく似た女性が、優しく微笑んで写っている。
二人とも母親似だ、特にお母さんはそっくりだ。
「線香ぐらいあげたら?」
わたしは部屋に入るとすぐにあげたけど、お母さんは遺影のお祖母さんを見つめるだけで、叔父さんに至っては一瞥しただけだ。
「いいのよ。ここにお母さん……お祖母ちゃんは居ないから」
「わかるの?」
「昔からいない。少なくても叔父ちゃんは視た事はないな」
叔父さんが験力を発現したのは一〇歳だから、それ以前にお婆さんの霊はここに居なかったことになる。
亡くなってすぐに成仏したんだろうか?
お母さんは黙ったままだ。話すつもりはないらしい。
お祖母さんが亡くなったのは、叔父さんが本当に小さい時だったみたいだったし、未練はなかったのかな?
もし、この世に留まっていたとしたら、お祖父さんが強制的に成仏させたんだろうか?
だから、お母さんはあんなにお祖父さんを嫌っているのかな?
そこまで考えた時、わたしは以前から気になっていた事が頭に浮かんだ。
それはおばあちゃんの、父方の祖母、真藤昌子に関する事だ。
わたしたち家族は団地の五階に住んでいる。下の階が叔父さんの部屋なんだけど、もともとは昌子ばあちゃんが住んでいた。
亡くなった後、部屋は引き払うはずだったんだけど、わたしのワガママで手続きが遅れていた。
そこに引っ越し先を探していた叔父さんが入居を決めた。
おばあちゃんは、あの時、まだあそこにいたのだろうか?
験力の存在を知ってからズッと気になっていたけど、色々な事があったせいで、口にするタイミングを失っていた。
「ねえ、引っ越してきた時、おばあちゃん、まだいたの?」
叔父さんの身体が強ばった。
「ああ、いたよ……」
「なんで教えてくれなかったのッ?」
思わず声が大きくなった。
「ごめん、言えなかった」
「だから、どうしてッ?」
叔父さんは溜息を吐いた。
「言えると思うか?」
「それは……」
問い返されて、少し冷静になった。
「朱理がお祖母ちゃん子だったのは知っていたけど、お前に話して、親に伝わったらどうなる?
お母さんに怒られるのはいいとして、お父さんが知ったら、義理の弟が怪しい宗教に入信していると勘違いするかもしれないだろ?
まぁ、実際はその心配はなかったわけだけど」
験力の事をお母さんと叔父さんは秘密にしていたつもりだったけど、お父さんはお祖父さんから聞いて知っていた。
う~ッ、なんかモヤモヤする!
わたしは消毒液が入った容器を強く握りしめた。
「うぎゃあ!」
傷口に大量の消毒がかかり、叔父さんが悲鳴を上げた。
「自業自得!」
おばあちゃん、やっぱりいたんだ。
「ねぇ、おじさんが祓ったの?」
「イタタタ……。
そんな事するわけないだろ? 悪霊ってわけじゃないし、お前たちのお祖母さんだ。
毎晩、観音経を唱えたけど、それで祓おうとしたわけじゃない。
観音経を通じて、家族がみんな元気にしているって事を伝えただけだ。
お祖母さんは、叔父ちゃんが入居してから一ヶ月ぐらいで居なくなったよ。
たぶん、お前があの部屋で笑えるようになったからだろうな」
わたしはハッとした。
叔父さんが引っ越して来るまで、わたしがおばあちゃんの部屋へ行くのは、さみしい時や悲しい時ばかりだった。
あの部屋で笑う事なんてなかった。
やっぱり、わたしを心配して留まっていたのかもしれない。
でも、もう一度おばあちゃんに会いたかったな。
「ぎゃぁあああッ!」
叔父さんが三度情けない叫び声を上げた。
わたしが傷口を思いっきりひっぱたいたからだ。
「朱理、いきなり何するんだよ?」
「自業自得!
でも、これでカンベンしてあげる」
全てが納得できたわけじゃない。だけど、叔父さんの考えも嫌だけど解ってしまう。
それに、いつまでも過去に囚われるわけにはいかない。わたしは前に進むって決めたんだから。
「朱理……」
お母さんが何か言いかけた時、玄関が開く音がした。
タッタッタッと音を立てて、ボンちゃんが廊下を駆けてくる。その後を政宗くんがゆっくり付いてくる。
わたしたちのいる部屋の前に来ると、政宗くんが障子を開けた。いや、開けたのは政宗くんに乗っている紫織だ。
「コラッ、政宗くんをいじめちゃダメ」
わたしは紫織を政宗くんから引き下ろそうとした。
「いじめてないよ!」
「大丈夫、政宗は力持ちだから。
それより紫織ちゃん、落っこちないように気をつけてね」
玄関を閉めて、お祖父さんもこっちへやってきた。
「うん!」
「ジジイッ、犬は乗り物じゃない!
紫織だって、それなりの重さがあるんだ」
「アタシ、かるいよ!」
「お前が甘やかしている柴犬と違って、政宗は鍛え方が違う」
「犬が何を鍛えるんだ? それに見た目は小さいくても、梵天丸は並大抵の犬より勇敢で賢い」
「勇敢? ゲージを恐がって入らなかったんじゃないのか?」
「それは嫌な過去があるからだ! そっちこそ、図体がデカいくせに、梵天丸に負けたじゃないかッ」
「負けてなどおらんわッ。少し押され気味だっただけだ。
ウチの政宗がお前のチビ犬に負けるわけがないッ」
「ウゥ~ッ!」
「うわッ」
バカにされたと思ったのか、ボンちゃんがうなり声を上げた。
すると政宗くんが尻込みして、乗っていた紫織がバランスを崩して落ちかけた。
「ほらッ、言わんこっちゃない」
わたしは紫織を支えた。
「ボンちゃんが、いきなりうなるから……」
叔父さんが勝ち誇ったような笑みを浮かべた。
「チビ犬が何だって?」
「フン、そんな生意気な事は俺に勝ててから……」
低レベルだ……清々しいほど低レベルな親子ゲンカだ。
張りあっているが、どっちの犬も同じ武将から名前を取っている。
「子供の前よ、いい加減にしたら?」
お母さんが冷ややかな声で言うと、二人はバツの悪そうな顔をした。
〔四〕母の封印
夕食はピザを頼んだ。
だけど、美味しいとはとても言えない食事だった。
ピザが嫌いなわけじゃない。むしろかなり好きなんだけど、お母さんと叔父さんのピリピリした雰囲気のせいでとても味わえない。
お祖父さんは好々爺といった感じで、わたしと紫織に「美味しいかい?」とか「足りなくない?」とか聞きながら食べていた。
紫織は「おいしい!」とニコニコして食事を満喫していた。
わたしも、またションボリされると困るので、美味しいと口では言ったけど本心じゃない。
明人さんもわたしと同じようで、余り食が進んでいなかった。
ボンちゃんと政宗くんは、エサを食べたら丸まって寝てしまった。
飼い主の確執はさておき、犬は完全縦社会だ。ボンちゃんが政宗くんより上位という事で収まったらしい。
紫織もお腹がいっぱいになると眠くなるので、もう布団に入って寝てしまい、明人さんは後片付けをすると言って台所へそそくさと逃げてしまった。
居間にはお祖父さんとお母さん、叔父さん、そしてわたしが残った。
お母さんたちはわたしにも出て行って欲しいみたいだけど、これから話すことはわたしと紫織に関する事だ。
自分の事を勝手に決められるのは絶対に嫌だ、どんなに邪見にされてもテコでも動くつもりはない。
「それで、朱理と紫織の験力の封印はいつするんだ?」
「おじさん!」
「朱理、自分の力で周りの人を守りたい気持ちは解る。おれがそうだからな」
「だったら……」
「それでもダメだ。お前にこれ以上辛い思いや後悔をさせたくない」
「それでその辛い思いと後悔は、お前が背負い込むのか?」
お祖父さんが口を開いた。
「そうだ」
「それが傲慢だというのが何故解らん?」
「傲慢だろうがガマンだろうが構わない。おれは朱理と紫織を異能力がらみの問題に、これ以上巻き込みたくない」
「では聞くが、二人の験力を封印して、その子供たちはどうする?」
「だらから封印の仕方を教えろと言っている」
「お前が封印できたとして、その孫は? その曾孫は?」
「おれだっていつかは死ぬって言いたいんだろ? だったら他の誰かに託すさ、他の異能者に」
「自分の姪以外なら験力を使うのは構わないか? 相変わらず勝手だな」
「勝手なのは百も承知だと言っている」
そう言えば、お父さんもお祖父さんと同じ様な事を言っていた。
「なるほど、お前の考えはよく解った。
残念だが、封印の方法を教えられないし、二人の験力を封印する事も出来ん」
「何でよッ?」
今まで黙っていたお母さんが声を上げた。
「この忌々しい能力のせいで、あたしは……あたしと悠輝は散々嫌な思いや辛い思いをしてきた。どうしてそれを、娘たちにまでさせなければならないのッ?
親なら子供に同じ思いをさせたくないのは当然でしょッ。
父さんは今度も平気なのッ?
娘と息子にしたように、孫にも異能の使い方を教えて、不幸にするつもりッ?」
「お母さん……」
こんなに取り乱した母をわたしは見た事がない。
何があったかは判らないけれど、お母さんが験力を本当に嫌悪している事は理解できた。 こんなお母さんの前じゃ、験力を学びたいとは主張しづらい。
もちろん、こっちにだって決意と覚悟はある。わたしが背負っている物も決して軽い物じゃないんだ。
でも……お母さんが背負っている物って、一体どんな物なんだろう?
「遙香、悠輝、お前たちの気持ちは解る。俺も好き好んで孫に辛い思いをさせたいわけじゃない」
「じゃあ、どうして? あたしたちにした事を、またやろうとしているじゃないッ?」
「お前達にも、させたくはなかった」
「でも、実際やらせたよな?」
叔父さんが憎しみの籠もった眼をする。
「理由は解っているはずだ」
「その上で言っている。結局、姉貴を封印したんだ。なら、早い段階で二人にしてもいいはずだ」
挑むような叔父さんの言葉に、お祖父さんは溜息を吐いた。
「やっぱり、やらないんじゃなくて、出来ないだな?」
お祖父さんはこの言葉を静かに受け止めていた。
「何言ってんの、だって父さんはあたしを……」
「ダマされてたんだよ、姉貴。こいつの特技は何だ?」
「幻覚……って、え? ウソ……嘘でしょッ? あたしを二十年近く騙し続けるなんてッ!」
「だから苦労した。俺の験力だけでは足りないから、色々演出をして、お前を信じ込ませなければならなかった」
「どうして……あたしは封印してって欲しかったのにッ!」
「理由は簡単だ、験力を封じる方法など俺は知らん。仮に知っていたとしても、見たくない物があるからと言って目蓋を縫う奴が居るか?」
「じゃあそう言えばいいじゃないッ!」
「言った。だが、お前は納得しなかった。本当は出来るはずだと言って聞かなかった。あの時のお前の精神状態も考え、封印したと思い込ませる事にした」
「………………」
お母さんはうつむいて、視線をさまよわせた。
「つまり、姉貴に眼を瞑らせて、眼が見えなくなったと錯覚させたわけだ」
「そうだ」
「これで全て説明がつく。
紫織に取り憑いた魔物を姉貴は験力で斃した。にもかかわらず、特に封印に変化はないと言っていた。
もともと封じられていないなら、変化があるわけがない。再び自分で眼を瞑ればいいだけだ」
「とんだお笑いぐさね。
験力を使えるって判っていれば、あたしが由衣ちゃんを助けられたかも知れない」
「お母さん……」
「験力の使い方をまだ覚えていない朱理と紫織には、使えないと思い込ませる事自体が出来ない。
験力が無くなったと錯覚させたところで、いずれ覚醒する。そうなったら自覚がない分だけ余計に厄介だ、そう言う事だろ?」
「悠輝、あんた、気付いてたの?」
「そうじゃないかって不安に思っていた、姉貴が封印に変化が無いって言った時からね。
そもそも験力を封印した人間なんて姉貴以外に知らない。だから、姉貴の験力を感じても、封印されても験力その物は感知できると思い込んでいた」
叔父さんは悔しそうに顔をしかめ、「まんまとダマされた」と吐き捨てるように言った。
「結局、あたしたちと同じ事を孫にさせるって事ね」
お母さんはお祖父さんを睨み付けた。
「朱理、嫌でもお前は修行できるぞ」
少し悲しげに、叔父さんはわたしを見つめた。
〔五〕験力
「ドォリャアアアア!」
「ふんッ」
無駄に元気な雄叫び、プレハブに何かが激突する音、そしてそれぞれの飼い主を応援する犬の鳴き声……
人里離れた一軒家なので、ご近所からのクレームの心配はないが、わたしにとっては大迷惑だ。
わたしはスマホに手を伸ばした。
午前四時十二分、十月の現在、日の出までまだ大分ある。どれだけ早起きなんだろう?
「っるさいな、あのバカ父子……」
隣で寝ていたお母さんが、唸るように言った。寝起きはかなり機嫌が悪い。
この状況で未だに熟睡しているのは紫織だけだ。コイツは本当に大物になるかも知れない。
二度寝しようにも、こんな騒音の中じゃムリだ。どっちにしろ、修行を始めるつもりならこの時刻に起きなきゃダメってことなんだろう。
ブツブツ文句を言っている母と、熟睡中の妹を残して部屋を出た。
手早くジャージに着替え、上着を羽織って表に出ると、叔父さんとお祖父さんが闇の中、まだ闘っている。
これは修行なのか、単なる親子ゲンカなのか、よく判らない。
「朱理ちゃん、おはよう」
明人さんが、ボンちゃんと政宗くんのリードを持って立っていた。
「おはようございます。これは……」
「ああ、散歩に行こうとして出くわしてね。そしたら、またケンカになっちゃって」
明人さんは呆れたように、闘う二人に視線を向けた。暗くてよく判らないけど、どことなく羨ましそうだ。
「止めなくていいんですか?」
「ぼくなんかが割り込んだら、殺されちゃうよ」
「明人さんも、験力を使えるんでしょ?」
彼は顔をしかめたようだ。
「うん……使えるって言うか、在るにはあるけど……
お師匠やユウ兄ちゃんとは比べものにならないくらい弱いんだ」
「おじさんも験力は弱いって……」
「それはお師匠や遙香さんに比べてって意味だよ」
「そうなんですか?」
「ほら」
明人さんは闘っている二人に顔を向けた。
お祖父さんの正拳突きが、叔父さんの身体に触れる前に止まってしまう。寸止めをしているんじゃない、眼に見えない壁のような物で阻まれているんだ。
ううん、わたしには視えていた。お祖父さんが拳を打ち付けるたび、空気が震え波紋が広がる。それは闇の中で、輝いているかのようにハッキリ視える。
サイコキネシスで創った盾だ。
それは普通の視力で見える物じゃない、験力が目覚めたせいで視えてしまう物だ。
「験力を使った防御か、少しはやるが……まだ甘いッ」
お祖父さんは蹴りを見舞った、験力を込めた蹴りだ。
盾は砕けたが、叔父さんはそれを予測していたのか、身を屈めてかわし様に、身体を支えているお祖父さんの脚を払った。
だけど相手もそれを予測していて、片足で飛び上がりそれを避ける。
二人は間合いを取って睨み合った。
「お師匠はあれでも本気じゃない。でも、ぼくが相手だったら、あの半分の力も出さないよ」
考えてみれば弱いハズがない、わたしは叔父さんが魔物と戦うのを見ている。
たしかに、最終的には負けちゃったけど、あれは紫織の潜在能力が強すぎるからだ。
「朱理ちゃんも強いよ。だから、修行すれば叔父さんみたいになれるさ」
「あ、ありがとうございます」
明人さんは、そんなに嫌な人じゃないかもしれない。
「オン インダラヤ ソワカ」
お母さんの声が聞こえた、と思った瞬間、雷が叔父さんたちの上に落ちた。
あの時と同じだ、紫織が取り憑かれた時と同じ、強大な験力を感じた。
「何時だと思ってんの、人がせっかく寝てるのに……」
「お、お前、親に雷を落とすとは……」
「あ、姉貴、完全に術が解けたみたいだな」
叔父さんはともかく、さすがのお祖父さんもお母さんの剣幕にタジタジだ。
さっきまで吠えまくっていた犬たちも、シッポを又の間に垂らして沈黙した。
明人さんに至っては腰を抜かして、怪物を見るような目でお母さんを見上げている。
まぁ、ムリもないか。わたしだって足の震えが止まらない。
「もっと早く気付いてたら、こんな事にならなかったのに……」
小声で呟いたのをわたしは聞き逃さなかった。
お母さんもこの間の事件を悔やんでいるんだ。
「悠輝、あんた親父とケンカしに戻ってきたの?」
「それは……」
「じゃあ、サッサと梵天丸の散歩を済ませて、修行を始めるッ」
「はいッ」
「爺ちゃんも、政宗を連れて行って、朝のお務めがあるんでしょッ」
「はい」
「そして明人君、いつまで腰を抜かしてるのッ?」
「す、す、済みませんッ」
ブザマに手脚をばたつかせながら立ち上がり、ボンちゃんと政宗くんのリードを叔父さんたちに手渡すと、明人さんはそそくさと立ち去った。
散歩組は納得がいかないようだったが、それでも犬たちを連れ出て行った。
「さてと、朱理。アンタは自ら望んで験力の修行をするのね?」
「うん」
自分の意思を示すため、力強くうなずいた。
「わかった、どっちにしろ験力を封じる方法は無いものね。だけど、験力を持つとどういう事になるか考えた?」
「もちろん!」
「本当にちゃんと考えた?」
「考えたよッ、わたしの験力のせいで、誰かが傷つく事が二度とないように……」
「それよ、お母さんが気にしているのは」
「え?」
「たしかに、制御出来ない験力は良からぬモノを呼び寄せる。でも、使いこなせる異能力も周りの人たちを傷つける事がある」
「どういうこと?」
「それをこれから教えてあげる」
促され、わたしはお母さんの背中を追った。
〔六〕鬼多見春香
お母さんは脇道を通り、本堂の裏へと回った。
昨日は気づかなかったけど、裏には鳥居があって、石段が上へと伸びている。
あまり人が来るとは思えないけど、草が覆い茂ることもなく、それなりに手入れがされている。きっと明人さんとお祖父さんがやっているのだろう。
わたしはお母さんを追って石段を登った。
数分登り続けると神殿が見えた。
戌亥寺は昔から高野山系の修験道のお寺だった。
明治元年三月に政府によって出された神仏分離令により廃仏毀釈運動が起きた。
その影響で一度は神社になったものの、運動が下火になると現在の位置にお寺を再建築し、そちらがメインになっている。と、叔父さんが言っていた。
本殿の前には一対の狐……ううん、しっぽの形が違うから犬か狼だろうか。
とにかく石像があり、大分剥げているけど、それぞれ白と黒に塗ってある。
狛犬にしろ、狐にしろこんな異様な物を見た事がない。
でも、わたしの頭には政宗くんとボンちゃんの姿が浮かんだ。
大分古びているけど、本殿は思っていたよりも大きい。
お母さんは扉を開けると、サンダルを脱いで中に入った。
わたしも続くと、中はちゃんと掃除されていて清潔だった。
「座って」
わたしはお母さんと向かい合って座った。
「朱理、あんたは制御出来ない力がいかに危険かを理解している。
でも、制御出来るから、自在に使えるからこそ、大切な人を傷つける事があるのを知らない」
「どういう事? 使い方をミスるって意味? ピストルの誤射みたいに」
「いいえ、もっと悪いわ。それを今から身をもって体験させる」
「どういう……」
「百聞は一見にしかずよ」
そう言うと、指先でわたしの額に触れた。
次の瞬間、眼の前が真っ暗になった。
* * *
「おねえちゃん」
紫織に呼ばれてハッとした。
でも、そこに居たのは妹に似た男の子と、メガネをかけた真面目そうな少女だ。
おじさんッ?
男の子は昨日見た、子供に戻された叔父さんだ。
お祖父さんの幻覚だろうか?
あれ? そもそもここはどこだ? わたしはお母さんと本殿に居たはずなのに。
「きょうもカキコーシュー?」
「そうだよ。
早紀ちゃん、ゴメン、また悠輝の相手押しつけて。
本来、オヤジが面倒見なきゃいけないのに」
わたしの口が勝手に動いた。だけどこれ、わたしの声じゃない。これは……お母さんの?
「稽古が終わって、悠輝くんと少し遊んでいるだけです。
好きでやっているので気にしないでください、遙香先輩」
遙香……やっぱりお母さんだ! わたし、お母さんになってるんだッ!
しかも、叔父さんの年齢を考えると、二十年くらい前の世界にいる。
「ホントに? せっかくの夏休みなんだし、カレシと居たいんじゃない?」
早紀ちゃんは頬を赤くした。
「からかわないでくださいよッ。
それに……カレも受験生だから、あんまり会ってばかりも……」
「あらぁ、気ぃ使っちゃってるの? ケナゲねぇ」
「だからッ、からかわないでください!」
「アハハ、ゴメンゴメン。早紀ちゃん、かわいいから、ついイジワルしたくなるなるのよ」「もう……」
今度は頬を膨らます。
「それより、法眼先生、今日も法事ですか?
お盆が近いけど、このところ毎日ですね」
「うん……ま、法事って言うか、『副業』かな?
色々坊主も大変なのよ、食べていくには」
お祖父さんは拝み屋の仕事で留守にしがちなんだ。
早紀ちゃんにその事は秘密なんだろう。
「じゃ、悠輝、早紀ちゃんに迷惑かけちゃダメだからね」
「うん、おねえちゃんもイネムリしないで、勉強しろよ」
「アンタこそ、遊んでばっかいないで、夏休み宿題ちゃんとやりなさいよ!」
ようやく状況が飲み込めた。
これはお母さんの記憶だ。
そして、これがお母さんの験力なんだ。
お祖父さんの幻覚に似た能力なのだろう。実際、どうやっているのか想像もつかないけど、自分の記憶をわたしに追体験させているんだ。
自分の意思で話す事も身体を動かす事も出来ないけど、視覚と聴覚だけでなく、夏の蒸し暑さや木々の匂いも感じる。おそらく何かを食べれば味も感じるだろう、究極のヴァーチャルリアリティだ。
「起きなよ、遙香」
声をかけられてハッとした。
眼の前が、また真っ暗になっている。
「んん……終わったの?」
まぶたが開かれる。どうやらお母さんは机で寝ていたようだ。
早紀ちゃんとは別の女の人が覗き込んでいる。
場所も戌亥寺の境内から、どこかの室内に変わっている。
教室みたいだけど、学校じゃない。おそらく、塾か何かでやっている夏季講習なのだろう。
「せっかくお金払ってんのにさ、寝てちゃもったいないよ」
「授業はちゃんと受けてた。でも、坂本センセーのありがたい話はいらない」
「そう言わず聞いてくれよ」
背の高い三〇代前半ぐらいの男性が眼の前に立った。
「あ、センセ、いたの? ゴメン」
全く悪びれた様子がない、さすがお母さんだ。
先生もあきらめているのか、苦笑いをしているだけだ。
「それがこの夏季講習のウリりだからね。せめて寝ないでくれよ」
そう言って少し寂しげに教室から出て行った。
「ただの授業だけなら個別指導の方がいいよ」
「念ずれば花開く? 努力しても必ず報われるとは限らないけれど、努力しなければ絶対に結果は出ない? その手のありがたい話は、親父からミミタコで聞かせられてる。
そもそもこの講習、あたしゃヤだって言ったじゃない」
「うぅ、そうだけどさ……。普通の夏季講習じゃつまらないと思ったんだもん」
「名物『坂本達也先生の熱い格言』に惹かれたんでしょ?
まぁ、いいわ。玲菜に付き合うって、あたし自身が決めたんだし」
「アリガト。
ところでさ、この後ヒマ?」
「なに言っての? アンタ、今日、氷室に告白するんでしょ」
「シッ! 声が大きいッ」
玲菜さんは教室の一角を振り返った。
そこには数人の生徒が談笑していた。
中に一際目を引く男子がいる。恐らく彼が氷室さんだろう。
「ヤッパ明後日にする。講習最後の日の方がいいよ、うまく行っても行かなくても気まずくなるしさ」
「そんな事言ってると、結局告白できませんでしたって事になるわよ」
「だってアタシ、自分から告白したことなんてないモン……」
「だから? 何にだって初めてはあるでしょ」
「わかってるよ……わかっているけどさ……」
玲菜さんはくっつくぐらい顔を近づけた。
「ね、お願い、遙香の力で何とかして!」
「ダメだって言ったよね? アレは人に使っていい物じゃない」
一瞬、間を置いてお母さんは静かに言った。
「でも……」
「いくら親友の頼みでも、それだけは聞けない」
辺りに聞こえないように小さな声だけど、強い意志を込めた口調だ。
「……………………」
しばらく玲菜さんは、うらめしそうにわたしを……お母さんを見つめていた。
「わかってる。言ってみただけ……」
玲菜さんはゆっくりと席から立ち上がった。
「うん、玉砕してきなよ。慰めてあげるから」
「縁起でもない事言わないで」
ぎこちない動きで男子の一団に近づいて行き、例の男子に話しかけた。
他の男子にはやし立てられながら、二人で教室から出て行く。
何だかこっちまでドキドキする。これはわたし自身がときめいているのだろうか、それともお母さんの感覚を追体験しているだけか、あるいは両方か。
わたしは告白した事なんてないし、されたこともない。もちろん恋バナはするけれど、実際に告白の現場に居あわせた事もない。
さすが高校生は違う。玲菜さんはどうなるのだろうかと考えていると、また景色が変わった。
「ただいま~」
お祖父さん家の玄関だ。
廊下の奥から叔父さんと早紀ちゃんが「お帰りなさい」と言いながらやって来る。
「早紀ちゃん、まだ居てくれたの?」
「そろそろ帰ろうと思っていたところです」
「お昼、食べて行きなよ」
「そうだよ、いっしょに食べよう!」
「うん、でも……」
早紀ちゃんが口ごもる。
「あー、そうだね。早紀ちゃんの家でもお昼用意してあるよね」
お母さんは何かを察したようだ。
「は、はい……」
「え~、いっしょに食べようよぉ」
「悠輝、早紀ちゃんを困らせないのッ」
「ごめんね、悠輝くん。またね」
「う~、バイバイ、サキねえちゃん」
そそくさと早紀ちゃんは出て行った。
きっとカレシが待っているんだ。
何だか、恋がお母さんの周りに溢れているな。お母さん自身はどうなんだろ?
「で、宿題ちゃんとやったの?」
「やったよッ、サキねえちゃんに算数てつだってもらった」
「あんた、早紀ちゃんに押しつけてないでしょうね?」
「そんなことしてないよッ。日記は、ぜんぶおれがやった」
「全部って、日記最後まで書いたの?」
「うん」
「日記はその日の分だけ書くのッ」
「よしゅうだよ」
「日記は予習しちゃダメ!」
「だってわかってるもん」
「何が?」
「朝ごはん食べて、お父さんに拳法のれんしゅうさせられて、勉強して、お昼ごはん食べて、あそんで、夕ごはん食べて、テレビみるかゲームして、ねる。
夏休みは、このくりかえしだよ。お父さんは拳法とセッキョウいがいは、いそがしくていないし」
「たしかにそうだけど……」
お母さんは溜息を吐いた。
「ねぇ、悠輝、お姉ちゃんと旅行に行こうか?」
「ん? ジュケン勉強しないとダメだろ」
「お姉ちゃんは頭が良いからいいの、安女に通ってんだから」
安女、安積中央女子高校は、当時福島県でトップクラスの高校だったらしい。現在では名前が変わり男女共学になっている。
「いいの?」
「弟の分際で、お姉ちゃんに気ィ使わないのッ。
で、どこ行きたい?」
叔父さんが目を輝かせる。
「ハワイッ」
「うん、ハワイアンズね」
「本物のハワイ!」
「うん、本物のハワイアンズね」
「外国のハワイッ!」
「うん、スパリゾートのハワイアンズね」
「おねえちゃんッ!」
叔父さんが抗議の声を上げた時、チャイムが鳴った。
「あ、は~い!」
天の助けとばかりにお母さんは玄関へ向かう。
引き戸を開けると、真っ赤な目をした玲菜さんが立っていた。
「遙香、やっぱダメだった……」
「そっか……
悠輝、悪いけど、何か適当に食べてて」
叔父さんは不満そうだったけど、空気を読んだのか、うなづいて台所へ姿を消した。
お母さんは玲菜さんを奥の部屋に通した。
今は明人さんの部屋で、その前は叔父さんのだった。そして、二〇年前はお母さんが使っていたんだ。
「ちゃんと気持ちは伝えられた?」
「うん……。でも、氷室くん、カノジョいるんだってさ……」
「そうだったんだ…。彼女がいなきゃ、きっと玲菜のことが好きになってたよ」
「そうかな? アタシのこと好きになってくれたかな?」
瞳に涙があふれ、声が震える。
「なったに決まってる。あたしが男だったら、玲菜のことほっとかないもん!」
「アリガト、遙香。でもさ、アタシは氷室くんに好きになって欲しかったんだッ」
「玲菜……」
「遙香はさ、フラれた事ってある?」
「知ってるでしょ、無いわよ。だってあたしは……」
「誰かを好きになったコトなんて無い」
玲菜さんが挑むような視線を向ける。
「そうよ」
「だから、遙香にはアタシの気持ちがわからないんだ。
ありったけの勇気を振り絞って告白したのにさ、迷惑そうな顔されてさ、付き合っている娘がいるからって……」
「仕方ないよ。玲菜だって、二股かけられたかったわけじゃないでしょ?」
「氷室くんはそんなコトしないッ」
「そうだね、玲菜の男を見る目は正しかった。だから……」
「次の恋を探せって? そんなのムリッ」
「直ぐにじゃないよ……」
「ずっとムリだよッ、ムリに決まってるでしょ!
おねがい、助けてよ、遥香」
「あたしには何もできない」
「ウソ、できるでしょ。ううん、遥香にしかできない」
「それはダメだって言ったよね」
お母さんの口調が厳しくなった。
「なんで? だって遙香にはその能力があるんでしょッ?」
「あるからって、使っていいわけじゃない。やって良い事と悪い事がある」
「法律で禁止されてる? 遙香のお父さんがダメって言っただけでしょ?」
「どんな理由があっても、他人の心を操るなんて許されない」
「わかってるよ、そんなコト。それでもさ、どうにもならないのが好きになるってコトなんだッ! 親友でしょッ? 力を貸して!」
すがり付かれた勢いで、お母さんと玲菜さんはベッドに倒れた。
「あたしが周りに人を近づけない理由を知っているよね?
この能力のせいで、あたしは他人の考えている事がわかる。
知りたくなければ、覗き見なけりゃいい。でも、気になって仕方がない。
結局、ガマンできずに相手の考えを読んで、傷つく事になる。
何度同じ事を繰り返したかわからない。
便利どころか呪いだよ。
でも、玲菜は裏表がないから、あたしは友達になれた。
信頼できるから、この呪いの事も打ち明けた。
人の心を変えるのは、考えを読むのとは全く違う。
その人を破壊する行為なの。
お願いだから、あたしにそんな事させないで、あたしの信じている玲菜のままでいて」
玲菜さんはお母さんを見つめたまま、しばらく沈黙した。
重い時間が二人を包む。
「ズルイよ、遙香」
そう呟くと、立ち上がって背を向けた
「じゃあさ、アタシも同じコトするね。
氷室くんの気持ちを変えてくれないなら、絶交する」
「玲菜ッ?」
「遙香の超能力のコト、今までダレにも言わなかったし、その力を使ってくれって頼んだコトもない。
今度が初めて、最初で最後。
だから、お願い」
お母さんは玲菜さんの背中を見つめている。
「ごめん」
「そう……」
玲菜さんは部屋から出て行った。
お母さんは玄関まで見送ったけど、声をかける事が出来なかった。
「おねえちゃん、だいじょーぶ?」
叔父さんが心配そうに見つめていた。
お母さんは叔父さんをギュッと抱きしめた。
「悠輝、あんたは験力なんかに目覚めちゃダメだからね」
「え?」
「こんなモノない方がいい、あっても辛いだけよ」
わたしがお母さんの立場だったらどうするだろう?
凜と香澄から同じ事を言われたら?
わたしは二度と誰かを傷つけないために、験力の使い方を学ぼうとしている。
でも、それ自体が友情にヒビを入れる原因にもなり得るんだ。
「学生時代の友達、特に高校の友達は特別なんだ」
気付くとまた眼の前の場景が変わっていた。
また、あの教室にいる。この声はあの名物先生のだろう。
お母さんは座る者のない、隣の席を見つめている。
そこは玲菜さんの席だ。
「この講習も明日で終わりだけど、自分が通う学校とは別の友達が出来ていたら先生は嬉しいな」
新しく出来るどころか、お母さんは親友を失おうとしている。
「それじゃあ残り一日、みんなで楽しんで頑張ろう」
講義が終わり、お母さんは席を立った。
そして、一人の生徒を呼び止めた。
「氷室、ちょっといい?」
玲菜さんが告白したあの男子だ。呼び止められて戸惑ったような顔をしている。
「えっと、キタミだっけ?」
「うん、玲菜の事で」
「ああ、わかった」
氷室さんはお母さんを促して教室を出て、すぐ側にある小さな公園へ行った。
「大久保、今日欠席したな……」
「あんたは悪くないよ、カノジョが居るんなら仕方ない」
氷室さんは驚いたような顔をした。
「知ってるのか?」
「玲菜から聞いた」
「じゃ、オレに何の用が?」
「本当にゴメン」
お母さんは氷室さんの額に触れた。
何をするのかは明らかだ、彼の心を操るんだ。
眼の前にある場景の他に、玲菜さんの姿が脳裏に浮かんだ。
氷室さんの感情を書き換えるため、お母さんは玲菜さんの情報を流し込んでいるんだ。
その刹那、わたしの頭に早紀ちゃんの姿が一瞬よぎる。
「えッ?」
今のは氷室さんから流れてきた情報だ。どうして早紀ちゃんを知っているんだろう?
お母さんは手を放した。
氷室さんは焦点の合わない眼でボーッとしている。
「ウソでしょ……」
つぶやきが聞こえたのか、氷室さんは改めてお母さんを見た。
「あれ、オレ何してたんだ?」
戸惑いの表情を浮かべる。
「キタミ……やっぱりオレ……。
大久保に謝らなきゃ、あいつの連絡先知ってるだろ?」
「あ、ここに……」
お母さんは電話番号が書かれたメモを出した。
「サンキュッ、用意いいな」
引ったくる様にしてメモを取り駆け出す。
「い、今のカノジョはどうするのッ?」
「別れるッ。オレ、もう玲菜の事しか考えられないんだ!」
振り返りもせず、氷室さんは行ってしまった。どうしてお母さんが、早紀ちゃんの事を知っているかも気にならなかったみたいだ。
「鬼多見」
呆然と氷室さんの後ろ姿見送っていると、背後から声がした。
お母さんが振り向くと、そこには名物講師の坂本先生が立っていた。
「氷室に何をしたんだ?」
「先生には関係ない」
お母さんは無視して公園を出ようとした。
「待ってくれッ」
乱暴に腕をつかまれる。
とっさの行動なのだろう、お母さんは先生の腕をつかみ返し捻り上げる。流れるように身体を払うと、長身の男が簡単に宙を舞う。
「うわッ」
お祖父さんから教わった拳法だ、先生は無様に地面に転がった。
「また、親父みたいに説教する気? あたしの事は放っておいて」
「違うッ。知りたいんだ、どうしたら人の心を変えられるかを」
すがり付く様にお母さんを見上げる。
「なに言ってんの?」
「君が特別な力を持っているのは、初めから判っていた。でも、こんな事ができるなんて……なんて……なんて素晴らしいんだッ!」
恍惚とした表情を浮かべながら立ち上がる。
「僕にも霊力があるんだ。霊が視えたり、人の心の声が聞こえたり……
でも、人の心を変える事はなんて出来ない。どうしたら君と同じになれる?」
「………………」
「頼む、教えてくれッ」
「アンタじゃムリよ」
「え?」
「人の心を操るなんて最低よ。
そんな事をしたがるヤツはクズよ。
そしてあたしは、救いようのない最低最悪のクズよ」
「君は解っていないッ、その力は……」
「ノウマク サラバ タタギャテイ ビヤサルバ モッケイ ビヤサルバ タタラタ センダ マカロシャナ ケン ギャキ ギャキ サルバビキナン ウン タラタ カン マン」
早口に真言を唱えると、先生は人形みたいに固まった。
以前、叔父さんが魔物に取り憑かれた凜に使った『不動明王金縛り』だ。
「解ってないのはそっちよ。
アンタに人に物を教える資格なんて無い」
坂本を残して、お母さんは公園を出た。
それにしても、どうして氷室さんから早紀ちゃんの情報が流れてきたんだろう?
受験を控えたカレシがいるって言っていたけど……
「おねえちゃん、食べないの?」
子供の叔父さんがテーブルの向かい側にいる。
ここは戌亥寺の台所だ、戻ってきたのか。
眼の前には素麺がある。
「うん、食べていいよ」
お母さんは自分の汁を叔父さんに差し出した。
「食べかけのツユは、ほしくないんだけど……
ぐあい悪いの?」
心配そうに覗き込む。
「ううん、勉強で疲れただけ」
「だったら、ちゃんと食べないとダメだよ」
「ありがとう。じゃあ、アイス買ってきてくるかな? 悠輝のお小遣いで」
「それはヤだ」
叔父さんがキッパリ断る。って言うか、小学生にたかるなよ。
あきれていると、電話のベルが鳴り響いた。
叔父さんが、椅子から立ち上がって台所から飛び出す。
電話の音が鳴り止み、すましたの叔父さんの声がする。
「もしもし、キタミです。
あ……はい。
おねえちゃん!」
何かに気付いたのか、はじかれた様にお母さんは廊下に飛び出し、叔父さんから受話器を奪い取った。
「もしもし?」
〈あ、遙香、アタシ!〉
受話器から聞こえるのは、玲菜さんの明るい声だ。
〈氷室くんが電話くれて、会いたいって言うからさ、さっき行ってきたんだ。
そしたら、アタシのコト、やっぱり好きだってさ!
これって、遙香がしてくれたんでしょ?〉
「うん……ねぇ、氷室、今付き合っているカノジョどうするか言ってた?」
〈別れてくれるってさ! きっと今頃、向こうも電話をしている頃だよ〉
一点の曇りもない、喜びに満ちた声だ。
玲菜さんにとっては、恋が成就したばかりなんだ。周りの事など目に入らないないんだろう。
でも、氷室さんと付き合っていた人は、何の前触れもなく別れを切り出されるんだ。たまった物ではない。
お母さんが受話器を置いた。
見えている物がまた変わった。
今、眼の前にあるのは知らない家だ。
『荒木』と表札が出ている。この苗字は知らないけれど、誰の家かは判っている。
インターフォンを鳴らすと、中からか細い声がした。
「はい……」
「早紀ちゃん? あたし、遙香」
「先輩……どうしたんですか?」
「あの……今、だいじょうぶ?」
「ええ……」
玄関が開き、中から早紀ちゃんが顔を出す。
眼が赤く充血している。きっと、今まで泣いていたんだ。
「早紀ちゃん……」
お母さんは早紀ちゃんを抱きしめた。
「ど、どうしたんですか?」
戸惑いの声を上げる。それはそうだろう、お母さんがした事を彼女は知らない。
「ごめんね、本当にごめん」
「なんで謝るんですか?」
「あたしのせいなんだ。あたしが余計な事をしたから……」
「私がフラれた事を言っているんですか? どうして知っているんです? それに、先輩のせいって?」
「元に戻すから……。ううん、もう元通りには出来ないかも知れないけれど……
早紀ちゃんを傷つけるなんて、思ってもいなかった。
あたしが浅はかだったせいで、お詫びのしようもないけど」
お母さんは、早紀ちゃんから離れ、深々と頭を下げた。
「本当にごめんなさいッ」
今度は茜色の光が視界に飛び込んできた。
夕陽が辺りを染めている。
日中ほどではないが蒸し暑い。
どこだろう? 大きな池がある。
手入れが行き届いているから公園だろうけど、郡山の地理がよく判らないから特定ができない。
たしかなのは、ほとりのベンチに腰掛けているカップルが、玲菜さんと氷室さんと言う事だ。
「玲菜!」
お母さんの声に二人が振り向く。
「遙香、どうしてここに?」
「あんたと氷室を探してた」
玲菜さんが表情を曇らせる。
「アタシたちを? なんで……」
「わかってるでしょ? やっぱりダメだよ、こんなの」
「今さら……」
「どうした?」
氷室さんが心配そうに割り込んできた。
きっと二人がケンカをしていると思ったんだろう。
「氷室、ゴメン。あんたに非道い事をした」
「何言ってんだ?」
お母さんは、氷室さんの額を指先で触れた。
「やめてッ!」
「鬼多見……?」
何が起きるかを察した玲菜さんは叫び、氷室さんは戸惑った表情を浮かべた。
その刹那、お母さんが送った玲菜さんの情報が取り除かれるのが、わたしには解った。
「あれ? オレ……何で……」
狐につままれた様な顔をして、お母さんと玲菜さんの顔を交互に見比べる。
「氷室くんッ?」
「大久保……オレ、どうかしてた。悪いけど、お前とは付き合えない。昨日も言ったけど……
あッ、オレ、早紀に……」
「早く行ってあげてッ」
お母さんの気迫に気圧されながら、氷室さんはうなづくと駆けだした。
「待ってッ」
追おうとした玲菜さんをお母さんが止める。
「ジャマしないでッ」
「もう遅いよ、魔法は解けた」
「『解けた』じゃないでしょ、『解いた』んでしょッ。どうしてこんな事するのッ?」
玲菜さんは張り裂けんばかりの声を上げて、泣き崩れた。
「サイテーだよ、少しの間だけ喜ばせておいて、全てを奪い去るなんて、アタシに何の怨みがあるのッ?」
「ごめん……」
「あやまるくらいなら、初めからヤんなよ!」
玲菜さんが充血した眼で睨み付ける。
「おまえ、ナニが楽しいんだよ? アタシがツライ思いをするのが、そんなに嬉しいのッ?」
「そんな訳ないじゃない!
あたしは、玲菜を失いたくなかったから……」
「ナニ言ってのさッ、失いたくない? だからイヤがられせをするワケ?」
「違うってッ。あたしは、本当に玲菜に幸せになって欲しかった。
でも……それでも……やっぱり人の心を操るのは間違ってる。
それに、気が付いたの」
「ようは自分がいい子ちゃんになりたいだけだろッ。
アタシの心はどうなるの?」
「え?」
「おまえは自己満のために、アタシの心を弄んだ!」
「それは……」
「今度はアタシの心を変えるわけ? その超能力で」
「しない、するわけないでしょッ」
玲菜さんは鼻で笑った。
「どうだか、化け物の考える事なんてわかりゃしない」
「………………」
「もう二度と、おまえの顔なんて見たくないッ」
吐き捨てるように言うと、玲菜さんは振り返らずに去って行った。
お母さんはズッとその後ろ姿を見送っている。
どうすれば良かったのだろう?
全てうまく行く、みんなが笑顔になれる方法はあったのだろうか?
『制御出来るから、自在に使えるからこそ、大切な人を傷つける事がある』
これは実体験から出た言葉だったんだ。
友達に嘘は吐きたくないという理由から、わたしは凜と香澄に験力の事を話した。
もちろん二人を信じているから打ち明けたんだし、それは今も変わらない。
玲菜さんと同じ事を彼女たちが言うとは思えないけど、験力の事は黙っていた方が良かったのだろうか。
だけど、験力の事を話さなければ、由衣の死や二人を巻き込んだ事件の真相も伝えられなかった。
凜と香澄には知る権利があるはずだ。
考え込んでいたら、いつの間にか家に戻っていた。
「遙香」
廊下を歩いていたらお祖父さんの声がした。
「何?」
お母さんは茶の間に入った。
「言う事があるだろう?」
「必要ないでしょ、どうせあたしの頭の中を勝手に覗き見するんだから」
「何だその口の利き方はッ?」
「事実じゃない。父さんはいつだって、験力であたしを監視している」
「生憎、俺はそれほど暇じゃない。それに出来るからと言ってやっていい事と……」
「じゃあ何で知ってるのよッ」
お祖父さんは溜息を吐いた。
「お前は確りしているが、それでもまだ高校生だ。誤った事をする事もある。それを正してやるのが親の務めだ」
「都合のいい時ばっかり父親ぶらないでッ。
自分は完璧だって思っているのッ?」
「俺だってまだまだ未熟だ。過ちを犯す事もある」
「だったら人の事より、自分を何とかしなさいよッ。
少しは悠輝をかまってやったら? あの子の頭の中だって覗いてるんでしょッ?」
「ああ、悠輝に関してはお前の言う通りだ。
だが、今はお前のした事について話している」
「あたしが何したって言うの? あたしはたった一人しかいない友達を、失いたくなかっただけよ」
「そのために、やった事は許される事ではない」
「父さんだって人の思考を覗いたり、人の記憶を改ざんしたりしてるじゃないッ」
「それは認める。だが、必要な時だけだ。特に感情や記憶を変える時は、相手の人格は勿論、周囲にも影響が無いよう細心の注意を払っている」
「それだって父さんの都合でしょ? 玲菜は絶対に必要だったのッ、たった一人の親友で、何でも話せる相手だった。あたしは、もう独りぼっちよ」
「何を言っている、俺や悠輝が居るだろう。友達はまた……」
「出来るわけ無いでしょッ!」
お祖父さんが思わず口をつぐんだ。お母さんの声はそれほど悲痛だった。
「あたしは相手の心が解るのよ。見たくないって思ったって、仲良くなればなるほど不安になる。そして視て、絶望する。
人間は大人になればなるほど複雑になる、そんなの解ってる。
でも、そう思っていたって割り切れない。
玲菜はそんな中でも特別だった!
そんな玲菜を、あたしは傷つけた。
この能力……験力があるせいで……」
頬を何かが伝わるのを感じた。
涙だ。
お母さんは泣いているんだ。
「父さん、あたしの験力を無くして」
「莫迦を言うな、そんな事は出来ん」
「よく『あきらめるな』とか、『出来ないと決めつけるな』とか言ってるじゃないッ。
だったら、出来ないって決めつけないで、あきらめずに何とかしてよ!」
「遙香、お前は今、自分の一部が嫌いだから切り捨てようとしている。
験力は確かに重荷だ、それは俺にも解る。お前より遥かに長い間、付き合ってきているからな。
だが、どんなに邪魔でも、どんなに厄介な物であっても、捨て去る事は出来ない。
験力を否定する事は、自分自身を否定する事だ。切り捨ててしまえば、お前はお前でなくなる」
「それのどこがいけないのッ?
むしろ、そうなりたいって言ってるのッ。
あたしはあたし以外の何かに、ううん、普通の人間になりたいのよ!」
「見たくない物があるからと言って、目をくり抜く事はできんだろう?」
「あたしはそうして欲しいのッ。
父さんのありがたい説教も、もうウンザリッ。
安っぽい言葉になんて、もうダマされないッ。
一体どれだけ、いつまで耐え続ければいいのッ?
これが死ぬまで続くんでしょッ?
だったら今すぐ死んだ方がましよッ」
「簡単に死にたいなどと言うなッ!」
思わず身をすくめた、つもりだったけど、実際には身体は動いていない。
お祖父さんの迫力に、お母さんは全く屈していない。
「じゃあ験力を無くしてよッ!」
「まだ解らんのかッ、それは……」
「勝手な事ばかり言わないで!」
「それはお前だろうッ?」
「父さんでしょッ。
あたしは一度だって験力が欲しいなんて望んだ事がない。
なのに、これのせいでいくら苦しんでも誰も助けてくれない。
無くしてくれって頼んでもダメならどうすればいいの?
もう耐えられない……」
「…………………」
お祖父さんが射貫くような視線をお母さんに向けている。
「あたしが本気で死にたがっているって解った?」
自分の考えを、あえてお祖父さんに読ませたんだ。
お母さん、本当に辛かったんだね。
「どっちでもいい、父さんの好きにして。
あたしはもうガマンしないから」
お祖父さんは目をつむると、大きく息を吐き出した。
「解った。だが、やはり験力を無くす事は出来ない」
「なら……」
「待て、何もしないとは言っていない。
無くす事は出来ないが、封印する方法ならある」
「封印?」
「そうだ、験力自体はお前の中にあるが、二度と使う事が出来ないようにしてやろう」
「本当に二度と使えなくなるの?
騙そうとしていない?
嘘じゃないんなら、父さんの心を読ませて」
「読みたければ読むがいい。だが、それで信用できるのか?」
「…………………」
そうか、お祖父さんなら心を読ませたと思わせて、偽物の情報を与える事も出来るんだ。
「流石に娘に死なれては適わない、それぐらいは判るだろう?
それに、お前が居なくなったら悠輝も悲しむ」
お祖父さんがお母さんの背後に視線を向ける。
振り返ると襖の陰から、心配そうに叔父さんが覗いていた。
* * *
気が付くと暗い部屋の中にいた。
眼の前に人影がある、それが母だと気付くのにしばらく時間がかかった。
「どうだった?」
「わ、わたし……」
何を言えばいいのだろう?
「言わなくていいわ。
朱理が何を感じたか、何を考えているか、全てわかるから」
そうだ、お母さんに隠し事は出来ない。
……お父さん、大変だぞ。
「人の心配はいいの」
はい。
「口で話しなさい」
「はい。
使いこなせる験力も、人を傷つける場合があるって事はよく解った……」
「玲菜と早紀ちゃんの事が気になるのね」
「うん……」
お母さんは立ち上がると、本殿の外に出た。
星の輝きが弱くなり、夜明けが近い事を知らせている。
スマホを見ると、まだ午前五時を過ぎたばかりだ。
あれだけ長い時間を過ごしたはずなのに、現実では一〇分も経っていない。
「玲菜は卒業まで口をきかないどころか、眼を合わせようともしなかった。それ以降は一度も会っていない」
そっか、仲直りできなかったんだ。
「それだけ辛かったって事なのよ」
「早紀ちゃんは、氷室さんと元通りになったの?」
お母さんは左右に首を振った。
「二人でよりを戻そうと努力したみたいなんだけど、結局別れたわ。
早紀ちゃんが、氷室を信じられなくなったのよ。つまり、お母さんのせい」
「説明しなかったの?」
振り返ると、わたしの眼をまっすぐ見つめた。
「出来なかったし、してもいけない」
「どうして?」
「験力の存在を知ったら、今度は早紀ちゃんが頼ろうとしたかも知れない」
「お母さんは、封印したと思っていたんだから平気じゃないの?」
「それは関係ないわ、『力』の存在自体が人間関係を破壊するの」
「でも、拝み屋をやっているなら、祖父さんと叔父さんの験力は知られているんじゃない?」
「依頼人の立場としてね。叔父さんたちはお金を取って験力を使う。
でも、何でも請け負うわけじゃない。出来ない事は、出来ないってハッキリ断るの。
親しい相手にはそうはいかないから、自然と人と距離を取るようになるのよ」
そう言えば、叔父さんの友達を知らないし、そういった話しをしているのも聞いた事がない。
「お母さんも、験力を封印したと思い込んでから、友達が増えたし、結婚も出来た」
ん? 封印していたから結婚できた? と言う事は封印されてないってわかった今は……
「だから、余計な心配しない」
「はい……」
「朱理に自覚して欲しいのは、験力を使いこなせるだけじゃ、誰も救えないって事よ」
「でもッ」
「叔父さんでも、由衣ちゃんを救えなかった。お母さんが、封印が偽りである事にもっと早くから気付いていたら、結果は違ったかも知れないけど、後の祭りよ」
深く溜息を吐いて背を向けた。
「さあ、行くわよ。朝ご飯の支度、手伝って」
「待って」
立ち去ろうとする母の背中を慌てて呼び止める。
「わたしは助けてもらったよ、叔父さんにもお母さんにも。
二人がいなかったら、わたしだけじゃなく、凜と香澄、萩原先生も生きていない」
お母さんは脚を止めた。
「そうね……」
お母さんは手を顔に持って行って、何かをぬぐう仕草をした。
「ありがとう、朱理」
振り返った顔に微笑みが浮かんでいた。
「それはわたしの台詞だよ」
わたしはお母さんと手を繋いで、階段を降りた。
〔七〕修行の開始
朝食を終えると、お祖父さんから験力ついての講義を受けた。
やっぱり、叔父さんと言っていることが全然違う。
お祖父さんによると験力は、神仏の加護を得て森羅万象の力を自在に操る能力、と言うことらしい。正直、よく解らなかった。
他にも色々聞いたが、わたしには難しい事ばかりだ。
それより、その後やらされた座禅の方が、よっぽど修行をした満足感がある。
精神を統一し、自分の中にある験力に触れる。
と言っても、わたしは何となく感じる事はできるけれど、発動まではいかない。
一緒にやっていた紫織はすっかり飽きて、お祖父さんに何かと話しかけていた。
お祖父さんはニコニコしながら紫織に応えている、叔父さんに対する態度と全く違う。
これで修行になっているのだろうか?
休憩をもらって庭に出ると、叔父さんが古いMTB《マウンテンバイク》を担いで山門を降りようとしていた。
「おじさん」
「あ、朱理。修行は終わったのか?」
「休憩に入ったところ。
どこかに行くの?」
「ちょっとヤボ用で……」
言いかけて、叔父さんは口を閉じた。
「この間の事件で借りを作ったヤツがいるんだ。
コイツを整備に出してから会いに行く」
本当はわたしに事件を思い出させたくないから誤魔化すつもりだったんだろう。でも、もう隠し事をしないという約束を守ってくれた。
それにしても、八千代での出来事なのに郡山で借りを作るなんて……
わたしはふと『天城翔』という名前を思い出した。
萩原先生の友人を見つけてくれた探偵だ。
「それって、天城って言う探偵じゃない?」
叔父さんが眼を丸くする。
「何で知ってるんだ?」
「先生のお見舞いに行った時に、名前が出て覚えてたの」
「そうか。天城翔、本名は三瓶茂子なんだけど、腐れ縁で時々力を貸してもらってる」
「それじゃ、お礼言っておいて。先生、友達が生きていて本当に喜んでいたから」
「あぁ、わかった」
叔父さんは満足そうにほほ笑んだ。先生の事を気にしていたんだろう。
「あのさ……朝ご飯の時、聞けなかったんだけど……」
「お母さんの事か?」
「うん、知ってたの? お母さんが験力を封印した理由」
叔父さんはわたしをジッと見つめた。
「視せられたのか、あの時の事を?」
「うん……」
「そうか……。あの時、あの夏休み、お母さんの様子がおかしい事には気付いていた。それに、玲菜さんが関わっている事も。
でも、それ以上は知らないし、知りたいとも思わない」
叔父さんとお母さんと仲のいい姉弟だから、ちょっと突き放したような言い方が意外だ。
「あれだけが原因じゃないんだよ」
「え?」
「朱理も身をもって知る事になるよ、異能力者がどんな目に遭うか。いや、もう結構知っているはずだ」
それはそうだけど……。
「この自転車は、お母さんが買ってくれたんだ」
「え?」
いきなり話しが変わって、わたしは戸惑った。
「高校の入学祝いにね。まぁ、正確には、入学祝いにくれたお金で叔父ちゃんが買ったんだけど」
わたしは計算した。叔父さんは二六歳だから、高校入学は十一年前だ。
「お母さん、専業主婦になってたよね?」
「うん。もっと正確に言えば、お母さんが着服したお父さんのお金で買った。
それはともかく、ここを出てからも、お母さんは叔父ちゃんを気にしてくれていた。
験力があっても無くても、お母さんはお母さんだ。叔父ちゃんを育ててくれた、お姉ちゃんなんだ。何があってもそれは変わらない。
だから、お母さんが知って欲しい事なら聞くし、何も語りたくないなら知らなくていい」
「恨んでないの?」
「どうして?」
キョトンとした顔をする。
「だって、お母さん、高校を卒業したら、叔父さんを残して家を出たんでしょ?
淋しくなかったの?」
叔父さんは悩ましげに眉を寄せた。
「う~ん、そうだなぁ……
朱理、ここだけの話だぞ」
「うん」
「誰にも言うなよ」
「うん」
「特にお母さんの前では、一切思い出すな」
「うん……」
「本当に出来るか?」
「たぶん……」
「…………………」
叔父さんは疑わしそうに、わたしの顔を見た。
そんな顔したって仕方ないじゃないかッ。言わないのはまだしも、思い浮かべるのなんてコントロール出来ないよ。
「まぁ、仕様がないか。
淋しかったよ。今まで面倒見てくれたお姉ちゃんが居なくなったんだから。
出て行く時は泣いて嫌がったし、その後も何度も淋しくて泣いた……
って、何だよその顔は?」
「い、いえ、別に……」
しまった、感情が顔に出た。
「でも、恨んだ事なんてないな。
むしろ、今は出て行ってくれて良かったと思ってる」
「何で?」
「だってそうだろ?
もし、叔父ちゃんのために家に残ったとしたら、お母さんに返しきれない借りが出来ちまう。
家を出たから、お父さんとも出会ったし、朱理たちも生まれた。
幸せになれたんだ。
叔父ちゃんも、お前たちに会えて嬉しかったし……爺さんもそれは一緒だ」
「だから、お母さんが出て行って良かった?」
「ああ、結果オーライって事だな。
結婚して、子供も出来て、経済的にも困っていない。幸せと言って問題ないだろ?
その象徴だったんだよ、このバイクは。
また乗る事になるとは思わなかったけどな。
それにしても、爺さんが、よく捨てずに取って置いてくれたよ」
お祖父さんも、叔父さんの思い出を取っておきたかったんじゃないかな?
わたしは、ある事に気が付いた。
「おじさん、たしか十月生まれだったよね?」
「ああ、今月の十六日だよ」
「もうすくじゃない!」
「この年になると、どうでもいいよ」
そう言い残すと、叔父さんは自転車を担いで階段を降りていった。
どうでもいいって言ってたけど、わたしは叔父さんに何かプレゼントをしようと決めた。
お母さんが、叔父さんを気にかけていたように、叔父さんはいつもわたしを心配してくれている。
全てが上手く行くなんて事はないのだろうけど、わたしは決して独りじゃない。
失った友人を取り戻せないとしても、二度と失わないよう全力を尽くそう。
わたしは修行を再開すべく、本堂に向かった。
―終―
鬼多見奇譚 弐 追憶の幻視
お読みいただき、誠にありがとうございます。
拙作が少しでも楽しんでいただければ幸いです。


