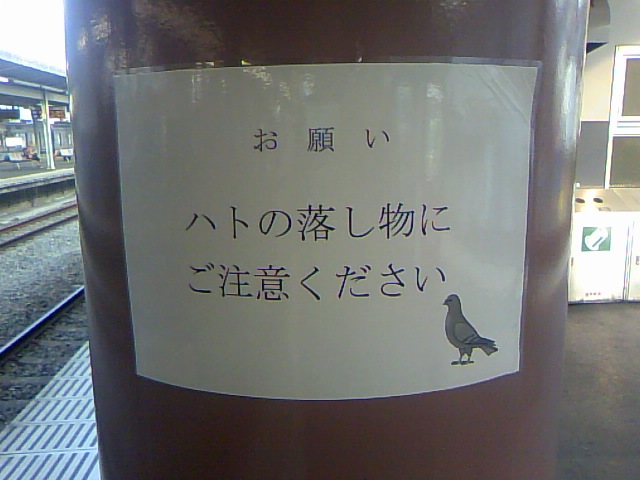
落し物
どこかの田舎町。
駐在所で警官が、空を眺めていた。
雲ひとつなく、目が覚めるような青さだった。
が、毎日変わり映えのない景色が、眠気を誘った。
警官は、空に向かってあくびを放つと、つぶやいた。
「今日も平和だ」
「おまわりさん!」
突然呼ばれ、警官は慌てて襟を正した。
小さな男の子が、泣きながらやってきた。
手には、空になった鳥かごを持っている。
「ど、どうしたんだい、坊や?」
「落し物をしたんだ」
「なにを落としたの?」
「ハトだよ」と、男の子は鳥かごを差し出した。
「……ハト?」
「うん、ハト」
「ポッポッポの、ハト?」
「ううん、違うよ」
「じゃあ、どのハト?」
「ぼくのは、クルックーって鳴くんだ」
「あ、ああ……クルックーの、ハトね……」
「ないの?」
「なにが?」
「ハトの落し物、届いてない?」
「いや、おまわりさんのところには、まだかな……」
「もし届いたら、知らせてくれる?」
「ああ、いいとも。どんなハトなのかな?」
「クルックーって鳴くんだ」
「あ、ああ、そうだったね……」警官はペンを取り、形だけの調書をとりながら言った。「鳴き声は、クルックーと……」
「あとね、とってもお利口なんだ」
「へえ、そうなんだ」
「うん、郵便屋さんなんだよ」
「郵便屋?」
「ユキエちゃんに、お手紙を届けてくれるんだ」
「ああ、伝書鳩か」
「ぼくね、とっても大切なお手紙を送ったんだ。だけど、それっきり帰って来ないんだよ……」
「なにか、特徴はある?」
「色が白くてね……」
「ふむふむ」警官は、調書を取りながら相槌をうった。
「お目々がパッチリで……」
「ほうほう」
「とっても可愛い声で、お話しするんだ」
警官は、顔をあげ「へえ、話ができるんだ?」と、たずねた。
「できるに決まってるよ。来年、小学生だもん!」
「ハトが!?」
「ユキエちゃんが」
「え、ユキエちゃん?」
「うん」
「ああ……じゃ、ハトは?」
「クルックー」
「あ、うん、それは分かったから……他に、ハトの特徴は?」
「おっきな音を鳴らすと、やってくるよ」
「いやいや、例えば名前とか……」
「なんじ」
「あ、ナンジ君って言うんだね?」
「ううん、いま何時?」
「え?……ああ、そろそろ三時かな」
「あ!ぼく、もう行かなきゃ」
「へ?」
「じゃあ、ハトが届いたら教えてね。バイバイ!」と、走り出す男の子。
警官は、慌てて声をかけた。「え、教えるって……どうやって!?」
男の子は振り返ると、満面の笑みで答えた。「ハトで!」
警官は、走り去る男の子を眺めた後、調書に目を落としてからつぶやいた。
「クルックー」
「あのう……」
不意な声に、警官は跳ねるように振り返った。
声の主は、沈痛な面持ちの女性だった。
手には、空になった鳥かごを持っている。
「ええ!?」警官は、驚きを隠さなかった。
「あの、大丈夫でしょうか?」女性は、不安そうにたずねた。
「え、ええ、もちろん。どうされました?」
「落し物なんです」
「落し物……。なにを、ですか?」警官は、鳥かごを凝視した。
「ハトです」
「……ハト?」
「ええ、ハトです」
「クルックーの、ハトですか?」
「いいえ」と、怪訝な顔を浮かべる女性。
「あ、ああ……そ、そうですよね!」警官は、乾いた声で笑った。
「クゥッークックックゥーの、ハトです」
「あ、やっぱり、そのハト……」
「やっぱり?」
「あ、いえ……どんなハトですか」と、ペンに手を伸ばす警官。
「クゥッークックッ……」
「鳴き声はわかりました!」
「はあ……」
「あれ?」と、ペンがないことに気づく警官。
「どうされました?」
「あ、いや、ボールペンが……」
「ペンなら、上着の後ろ襟にあります」
「え、そんな……」
警官が背中に手をやると、女性の言うとおりであることがわかった。
ペンのキャップをはずすと、ペン先からバラの花が飛び出した。
「……私、売れないマジシャンなんです」と、女性が言った。
「ええ、そのようですね……」
「え?」
「あ、いえ……すみません」
警官は、仕方なく引き出しから代わりのペンを出し、調書をとった。
「今夜、ステージで使う予定の大事なハトが、逃げてしまったんです。もしかしたらって思って、お伺いしたのですが……」
「そうでしたか……。でも、お力になるのは難しいかと……」と、女性に目をやった警官は、叫び声をあげた。「ええっ!!」
女性は拳銃を手にし、自身のこめかみに押し当てていた。
警官の腰にある拳銃のホルスターは、いつのまにか空になっていた。
「私、本気なんです……。だって、もう……失敗は許されないんですから……」と、天を仰ぐ女性。
「わ、わかりました!できる限りの協力はしますから、落ち着いて!」
「……本当に?」
「約束します!」
「じゃ、鳴き声は?」
「え?」
「あのハトは、なんて鳴きます?」
「え、えーと……くっくっくぅ……?」
「いいえ!クゥッークックックゥーです!」
「いや、その、クゥッークッ……」
女性は、引き金をひいた。
「ひいっ!」と、思わず目を閉じる警官。
恐る恐る目を開けると、銃口から万国旗が飛び出しているのが見えた。
「私、マジシャンなんです……」と、女性。
「え、ええ……よくわかりました」
「なんじです」
「え……ああ、ちょうど三時です」
「いいえ、ハトの名前。ナンジと言います」
「あ、ああ……ナンジ君ですね」
「くれぐれも、お願いします」と、言い残し、女性はうつろな足取りで駐在所を去った。
警官は、しばらく呆然とした後、拳銃がないことに気がついた。
急いで女性の後を追いかけようとするも、すでにその姿はない。
なにか手がかりがなかったかと、調書に目を通した。
そして、ひとつだけ記してあった言葉を、力なくつぶやいた。
「クゥッークックックゥー」
「よろしいですか?」
声をかけられ、警官は弱々しく頭を上げた。
そこには、息を乱し、額に汗を浮かべた男性が立っていた。
「落し物ですか、ハトの?」と、警官はうわごとのように言った。
「ええ!?」
「鳴き声は?」
「は?」
「ポッポッポ?」
「い、いや……」
「クルックー?」
「ちょっと……」
「じゃなかったら、クゥッークックックゥー!?」
「落ち着いてください!」
「え?あ、ああ……すみません、取り乱しまして……」
「実は、女性を探しておりまして」
「女性を?」
「はい」
「売れないマジシャンの?」
「は、はい」
「どこにいるんですか!?」と、男性につかみかかる警官。
「いや、それがわからないから来たんですよ!」と、警官を振り払う男性。
「あ……そ、そうですよね」
「彼女、もう訪ねて来たんですか?」
「え、ええ!先ほど……」
「そうでしたか……。すみません、ごめんどうおかけしまして」
「どういうことですか?」
「私なんです。ハトを逃がしたのは……」
「え!?」
「あいつに、マジシャンを辞めてほしくって……」
「おい、あんた!」
「え?」
「なんてことしてくれたんだ!!」と、再び男性につかみかかる警官。
「ちょ、ちょっと、止めてくださいよ!」と、警官を振り払う男性。
「あの人はな、いくら売れなくても、命がけでマジシャンやってんだ!」
「そ、それは……」
「それなのに、面白半分でハトを逃がしていいと思ってんのか!?」
「なにも、面白半分ってわけでは……」
「じゃあ、なんだ?あの人は命がけだぞ?そう、命がけだから……だから、拳銃を……拳銃をなくしちゃったんですよ。……ねえ、どこにあるか知りません、私の拳銃?」
「知りませんよ。でも、彼女がそこまで本気だったってのも、知りませんでした……だけど、私は……」
「ひどい人ね!」と、背後から声がした。
二人が声の方へ振り向くと、女性が立っていた。
「あなたが、逃がしたのね?」と、女性が男性につめ寄った。
「確かに逃がしたよ、でもこれには理由が!」
「聞きたくない!」と、言った女性の手には、拳銃が握られていた。
「待て!冷静になるんだ……」と、息を呑む男性。
「大丈夫。あれはきっと偽物です」と、警官が男性に耳打ちした。
それが聞こえたかのように、女性は空に向かって引き金をひいた。
銃口からは、万国旗ではなく、激しい破裂音が飛び出した。
警官と男性は、言葉を失った。
「マジシャンとして成功しているあなたには、私の苦しみなんてわからないのよ。……今夜失敗したら、道を失ってしまうのよ?……そうしたら、私……もう、あなたのそばには……」
「失ったらいいさ、そんな道!」と、男性が言った。
警官は、驚いた顔で男性を凝視している。
「僕がもっと腕を磨くよ。そうしたら、きっと他の道が……」と、男性が言いかけた時、空から手紙が降ってきた。
手紙は、男性と女性の間にふっと舞いおりた。
「ずっと言えなかった言葉が、ここに書いてある」と、男性。
「やっぱりあなた、すてきなマジシャンね」と、女性。
男性と女性は、手紙を拾い上げると、手を取り合って行ってしまった。
警官は、呆気にとられたまま、動けずにいた。
どこからか、ハトの鳴き声が聞こえてきた。
「クルックー」
「おまわりさん、ありがとう!」
見ると、ハトを落とした男の子がいた。
「あ、ああ、どうしたんだい?」警官は、我に返ったように言った。
「お礼を言いにきたんだよ!」
「お礼?」
「うん、帰ってきたんだ!」と言った男の子の鳥かごには、ハトが戻っていた。
「ああ、そうかい。良かったね……」
「でもね、ユキエちゃんへのお手紙は、なくなってたんだ。もう一回、書かなくっちゃ……」と、男の子。
「手紙って……あ、さっきの手紙!ねえ坊や、手紙にはなんて書いたんだい?」
「え、うんとね……『ぼくのお嫁さんになってください』って」
「ああ、お嫁さんか……。はは、そうか……」
「ねえ、誰にも言わないでね?」
「え、ああ、うん……。言わないよ」
「ねえ、さっきの音って、おまわりさんが、やってくれたんでしょ?」
「え、なにが?」
「だってさっき、鉄砲の音がしたから。おっきな音を鳴らすと、やってくるって言ったでしょ?」
「え、ああ……。あ、そうだ、そうだった!」
警官は、はっと気づきホルスターを見た。
そこには、拳銃が元の通りに戻っていた。
「はあ、良かった……」と、肩を落とす警官。
「あ、おまわりさん!」
「なんだい?」
「帽子に、ハトのフンが落ちてるよ」
「え?」
どこからか、ハトの鳴き声が聞こえてきた。
「クゥッークックックゥー」
「なんじだ」と、警官。
「もう三時すぎだよ」と、男の子。
「いいや、このフンの落し主の名前さ。は、ははは……」
「変なの。おまわりさん、どうして笑ってるの?」
空は、目が覚めるような青さだった。
頭上では、真っ白なハトが羽ばたいていた。
警官は、空に向かって笑みをこぼすと、つぶやいた。
「今日も平和だからさ」
(終)
落し物

