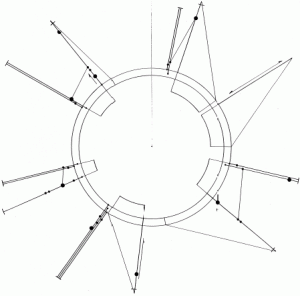無機質な部屋(1)
聞き慣れたアラームで寝返りをうつ。
カーテンの隙間からの不愉快な陽射し。
ああ、今日も目が覚めてしまった。
こんな事を呟いてはいるが、死にたいわけではない。
死にたいわけではないが、死にたくないわけでもない。
痛みもなく、苦しみもなく、ふわふわと消えていけるものならどんなに楽だろうと思う。
そんな事を誰かに語るわけでもなく煙草に火をつけ、約3分。
無意味な1日の予定を考える。が、考えるよりも先に煙草は灰になっていく。
無味乾燥な1日が始まる。
階段を降りて台所へ向かう。
家族は仕事に行っていて1人だ。
テレビをつけ、コンロに置いてある鍋をあさる。冷めている。
もうすぐ24。
何をしているんだろう。
もう50を過ぎた両親に養ってもらい、家の中をぐるぐるするだけの娘。
煙草も嫌がっているのを知っているが、やめられない。
何の役にも立たない。将来も見えない。不安、焦燥。
「生きてるだけで楽しいんだから」
地方のテレビ番組でおばさんが話していた。
正直、どうでもいいと思った。
このおばさんの人生が楽しいか楽しくないかなんて私には無関係で、きっと死ぬまで会う事もない。
なんて事を考えて、自分の荒んだ心を再確認させられる。
はっきり言って私は今の自分が嫌いだ。
私から見て周りが無味乾燥に見えるように周りから見て私もきっとそうなのだろうと思う。
もし、そう見えていなかったとしたらそれは言わば建物の外観のようなもので内装はボロボロ。
いつ崩れるかわからない心を笑顔の塗装でごまかして生きているだけにすぎない。
感情はいつも負の螺旋に迷いこみ冷たい壁を感じている。
憂鬱な脳内世界から電子レンジが私を現実に呼んだ。
せっかくの美味しいご飯も味気なく感じそうだったがとりあえずテーブルにならべ、それを口に運ぼうとした時、携帯の着信音が鳴った。
「おはよう、薫」
「おはよう、啓ちゃん」
啓ちゃんとは付き合いはじめて2ヶ月。
本当は付き合うつもりじゃなかったが、あまりの押しに負けてしまった。
とても感じの良い人だなとは前から思っていたけれど、付き合ってみると面倒見もよく、気遣ってくれているのがよくわかる。
「もう、起きてた?」
「さっき起きたよ。」
「そっか、出てこれそうだったらお店に遊びにおいで」
「そんなに会いたいの?」
「会いたいよ」
「ふーん」
心地良い会話。柔らかい声。優しい沈黙。
今の私の日常にはもう必要な人になっているのかもしれない。
「じゃあ、行ってくるね。大好きだよ」
「頑張ってね。私は嫌い」
「俺は好き、またね」
ご飯が冷めてしまった。
もう1度温めるか迷ったけれど、電子レンジなんて使ったら急に現実に引き戻されそうだったからそのまま食べることにした。
無機質な部屋(1)