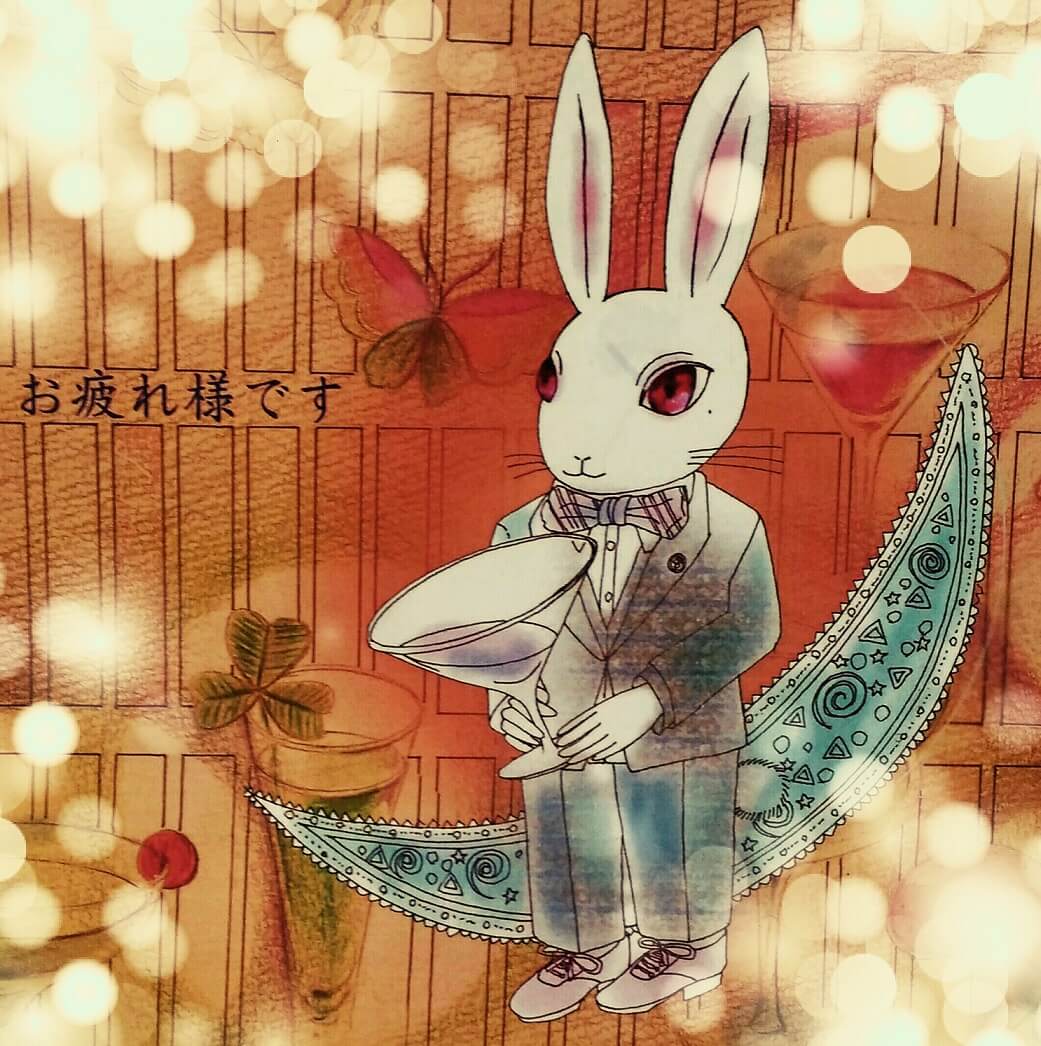
鬼は炬燵で丸くなる
人は現実の息が吸える世界と、頭の中にある心の世界の二つの舞台に生きている。人間の精神の在り方を問いかけるためにこの物語は書かれている。
2016年度文學界新人賞応募作品。
プロローグ
人は現実の息が吸える世界と、頭の中にある心の世界の二つの舞台に生きている。幼い頃から心の世界について知っていた訳ではないので、僕の視点からではその世界の成り立ちの全ては分からない。けれども、分からないなりに僕はその心の領域について語り、語ることで扉を開いていきたい。自分が今知っている以上のことを知るためには、他の人の世界観を知ることが必要だ。僕は語り、そして誰かからの返事を待ちたい。僕の世界観は他の人の当たり前から外れているかもしれない。それでも僕にとってその心の世界の存在は真実だし、一人一人が心に対して自分の立場を持ち語る自由がある。大人になるまで心の世界に気付けなかったのけものの僕なりに、言えることは可能な限り伝えたいと思っている。
一、
月に届きそうなくらいに、高くそびえ立つビルがあった。その日の月はもうすぐ満月になるくらいに満ちていて、通り過ぎる車のヘッドライトより明るく、大きな黄金色に輝いていた。満月は狂気を呼ぶと言われるけれども、例え狂気がその内心にあったとしても、誰もが普通に道を行く。高いビルは都心のビジネスホテルで、最上階に酒場が付いていた。
僕はその月に近い酒場に時々通っている。磨き抜かれた木製の壁のエレベーターで、ビルの最上階まで上がる。絞られた明かりでぽつんと照らし出された重厚な金属の扉を開けると、タキシードを着た店員が
「ようこそいらっしゃいませ」
と一礼して丁寧に出迎えてくれる。落ち着いた暗い店内でカウンターが輝いている。店の混み具合を確かめて席の希望を伝えると、店員は端正な微笑みを浮かべながら、洗練された身のこなしで窓際のカウンターまで案内してくれる。窓の外の夜闇には、見ているこちらが呑み込まれそうに大きな金の月があり、足元には街の細かな幾千の光が地表を覆っているのも見える。
この天空に近い場所では地表の都市の人工の光よりも、圧倒的に月光が強烈な存在感を放っている。夜の月が持つ神秘的で静かな光を大切にするために、店内では蝋燭の穏やかな炎の灯りが主要で、カウンターの酒瓶を照らし出すライトなど、電気は必要最小限だ。
酒場の窓から外を見ると、そこには巨大な月の円が迫っている。月の模様まで鮮明に目でなぞることが出来る。僕は窓に近いカウンター席に座って、夜空に浮かぶ月を眺めながら、ゆっくりと舌の上で酒を味わうのが好きだった。
その店には、光り輝く鉱石や星座をモチーフにした装飾や調度品が数多く揃えられていた。学生時代に地学が専門だった、バーテンダーの聞き耳うさぎの趣味だ。月球儀に天体望遠鏡、額縁に入れられた鉱石や天体の学術的挿絵、円形の軌跡が複雑に交差する金色の惑星模型、といった自然科学的モチーフが揃っている。
カウンターとテーブル席にはメニュー表があり、表がグランドメニュー、裏がオリジナルメニューになっていた。オリジナルカクテルを眺めていくと「神の手、鏡の女、女神のささやき、青のダンス、アラスカの氷、回遊魚、咲く炎、オーロラ、スター・サファイア、シルクの心臓、雪女」といったカクテル名が並んでいた。常連の客は普通のカクテルよりも、こうしたオリジナルカクテルを好むことが多かった。常連客はカウンターに腰かけ美酒を味わいながら、バーテンダーの聞き耳うさぎが語る、そのカクテルにまつわる話を聞くのを楽しみにしているのだ。僕もまたその一人だった。
店内にはラフマニノフが静かに流れている。カウンターにいる聞き耳うさぎは、揺らめく濃淡を持つ緑色の液体をグラスに注いでいる。その煌めくお酒はやがてタキシードを着た店員によって、ソファー席の方に運ばれていった。
「聞き耳うさぎさん」僕は声をかける。
「はい」彼は透き通ったまなざしをこちらに向け、静かに答える。聞き耳うさぎは眼鏡をかけた、スマートな年配の紳士だ。道具を布で拭う何気ない仕草にも、知的な抑制の効いた洗練が見られ、それは長年のバーテンダーとしての経験を感じさせる。僕はメニュー表から一つのカクテルを選び出して注文する。
「『雪女』をお願いします」
「かしこまりました」
聞き耳うさぎは幾つかの酒瓶を選び出して並べ、銀色に輝くシェイカーにお酒を量り入れて振り混ぜた。シェイクした液体をカクテルグラスに丁寧に注ぐ。
雪女という名前のオリジナルカクテルは、日本酒を使用した、雪が降り注ぐ様子を表現した白いお酒だ。細やかな氷の粒がグラスの中できらきらと静かに光っている様子は、冬の気候を思わせ、日本的情緒を感じさせる。僕は聞き耳うさぎに尋ねる。
「このお酒にまつわる話はどんなものですか?」
聞き耳うさぎは眼鏡の奥で瞳に優しい光を灯した。
「こちらのカクテルに使用している日本酒は、新潟県の山奥で収穫されるお米から製造されているものなのですが、そこは冬の豪雪地帯でもありまして、雪に閉ざされた山地なのです」聞き耳うさぎは語り始める。
「新潟のお米を使った日本酒」
「はい。その地方では冬、軒から大きなつららが垂れ、メートル単位で積もる大雪に備えて屋根を特殊な形にした民家が並び、黒字に白で書かれた宗教の看板がよく家々の壁に見られるような村が、今の時代にはあります。昔は雪に閉ざされ孤絶した山奥の住人もいたようで、そうした人々が語った雪女の伝説が伝えられています」
「その雪女の言い伝えがモチーフなんですね」
僕はそっとカクテルをすする。良く冷えた液体は飲み口が滑らかだ。やわらかな米の甘みが口一杯に広がる。
「そうです。吹雪の中白ずくめの美しい女が現れ、その女に息を吹きかけられると凍りついて死ぬという伝承です」
僕の頭の中に、吹きつける豪雪の中に佇む、白い着物の女性のイメージが広がる。
「伝統的な雪女のイメージは、吹雪による凍死などと関わっていて残酷な印象がありますね。しかし相当美しい若い女性を思い浮かべるので、憧れやロマンもあります。日本人が心に抱いている、冷たい感じの美女の原点や理想のような」僕がそう言うと、聞き耳うさぎは同意を示して頷いた。
「雪女の伝説の中には雪女との間に子どもを設けるというものもあります。やはり理想の女性として待ち焦がれた存在というところもあるのでしょうね」
「待ち焦がれた存在?」僕は引っかかりを覚えて聞き返す。
聞き耳うさぎは少し悲しげな笑みを浮かべながら言った。
「雪女の伝説が語られる元になったのではないかと言われていることなのですが、吹雪の山奥で孤独に暮らしている独身者や子のない老夫婦が、雪で外にも中々出られずに長期にわたって厳しい冬を過ごす内に、吹雪が戸を叩く音を、自分が待ち望んだ存在が来たのではないか、自分にとっての夢の嫁や子どもが我が家を訪れてくれたのではないかと考えたのが、雪女伝説の元になっていると言われています」
「それは寂しい話ですね」僕は聞いて胸が痛む。
「そうですね。切なくなりますし、孤独な生活で幻を思い描くそうした心理は分かるような気がします」聞き耳うさぎは言う「ところで猫さんも独身の方でしたよね」
僕は頷く「僕はまだ未婚です」
「私は昔は妻がいましたが、交通事故で早くに亡くしまして、以来一人です。孤独な生活というのは時に過酷なものですね」
「その通りですね」僕は実感を込めて同意する。「否応なしに頭を悩まされる時があります」
自分では異性のことで頭を悩ませたくないにも関わらず、無意識的に親密な異性の存在を頭が自然と求めることがある。そうした悩みは時に生きていくための大切な仕事への集中さえも脅かす時期があって厄介だ。
「結婚のご希望はご自身の中にはおありですか?」聞き耳うさぎが尋ねる。
「まだ学生だった頃には、人間は一人で生きていけるものだと思っていました。自分一人の時間が大切だったし、一人で過ごすことは苦になりませんでした」
「なるほど」
「けれども自分の意志とは関わりなしに、心が一緒に人生を生きていく相手を求めていることに、一人で暮らすようになってから気付いて、なす術もなく頭を悩ませながら相手のいない現実に切なさを感じることが度々あります」僕はまた少しお酒を味わいながら答えた。「そんな時に、共に生きられる相手が欲しくなります」
「猫さんはまだお若いですからね。きっとチャンスは巡ってきますよ」
「そうだといいのですが」僕は苦笑いをする。僕は自分にあまり自信がないのだ。
雪女のカクテルを見つめると、冬に雪の降る日の凍える寒さが思い出されてくる。それと同時に真っ白な雪の汚れのない美も呼び覚まされるようだった。
「日本では『雪月花』という言葉があるように、雪は風流なものの代表でもあります」聞き耳うさぎが言う。
「雪月花。懐かしい言葉ですね。昔、国語の授業で出てきました」
「雪の持つ儚さだったり、全てを浄化する降り積もる雪の風情などは、雪女という存在の美にも托されているのでしょうね」
雪女のカクテルは甘く凛とした味わいで、飲むと濃密な酔いが回った。美女に心を奪われたように舞い上がる陶酔感がやってきて、はらわたからカッと熱くなり、周りの風景がそっくり入れ替わるような世界の転換を感じた。見える世界の光の印象、蝋燭の炎やライトアップされた酒瓶や月明りがそれまでより一段明るく感じられた。心がゆっくりと解き放たれて、自由へと旅立っていく。
窓の外の月を眺めながら雪女のカクテルをゆっくりと味わっていると、少し離れたカウンター席に、この店で何度か見かけている、スーツ姿の会社員らしき女性が座った。月の光に照らされる彼女の横顔の華奢な頬は白く雪のようで、少し明るい色で染められた髪はアップにされうなじに優美な曲線を描いていた。雪女にしては優しげな雰囲気だな、と僕はアルコールが回り始めた頭で思った。
彼女はメニューを見つめると「女神のささやき」を注文した。以前に僕も頼んだことのあるカクテルだが、確かその時の聞き耳うさぎの話によると、死を考えている人に生きる希望と情熱を与えようという意図で作り出されたものだったはずだ。飲むことで生きることの大きな喜びを取り戻すことができるように、という願いが込められている。そのカクテルを注文した彼女の心の中にその意図があるのかどうか僕は気になった。澄ました表情をしているが心は苦しいのだろうか? 僕は彼女の横顔をそっと眺めながらその感情を読み取ろうとする。伏せたまつげの奥にある瞳の輝きは、かつて苦しみを見つめた奥深いもののようにも思える。滑らかな横顔の輪郭線を追うと、唇の柔らかで危うげなラインは、人生の喜びも過酷さも饒舌に語り出しそうに見えた。ふわりと持ち上げられた髪はしなやかで彼女の若さを感じさせ、手つかずのような繊細な耳には小さな真珠のイヤリングが揺れている。僕は彼女の横顔を照らす蝋燭の光と、複雑な影の調子に魅せられていた。カウンターに出された「女神のささやき」はルビー色の液体で、オランダのリエージュで作られたクリスタルグラスに入れて提供された。生きる源の血液を思わせるお酒だ。赤い光の揺れるグラスは彼女のしなやかな指の中に収まった。清純な笑顔を口元に浮かべて、彼女は聞き耳うさぎに「ありがとう」と言った。僕は頭がくらっとした。それが酔いに由来するのか、彼女に惹かれる心理の揺れなのか見分けはつかない。
「美味しい。少しハーブのような風味がするけれども何かしら?」
ひとくち「女神のささやき」を口にすると彼女はそう言った。聞き耳うさぎはカウンターの後ろを探って、何かの植物をひと束取り出して彼女に見せた。青みを帯びた花をつけた乾燥したポプリのようだった。僕がさりげなく視線を向けていると、聞き耳うさぎが気付いて、ほほえみながら僕にも植物を見せに来た。会社員の女の子はまっすぐなまなざしを僕に向けて軽く会釈した。僕も彼女に会釈を返した。
「この薬草は『古い幻』という名で呼ばれています。夏が近づく頃に、ステンドグラスで作られたような透き通る青い花を咲かせます。特有な風味を持っていて、スパイシーな中に甘さがあります。乾燥するとこのようにきれいにパリパリになるので、ハーブティーとして使われることも多いです」聞き耳うさぎが説明する。
「何かの薬効もあるのでしょうか」僕は聞いた。
「気分の高揚をもたらすようです」
「なるほど」カクテルに意図した効果が実際にあるのか。
「このハーブはどこで仕入れているんですか?」女の子が尋ねる。
「自分で森に行って採集しているんですよ」と聞き耳うさぎ。
「そうなんですか! 驚きました。素材にこだわっているんですね」彼女は目を丸くした。
「ちなみに聞き耳うさぎさんはどこでハーブ集めをしているのですか?」僕は質問する。
「車で二時間くらいかかる、近隣の県の山の中です。木漏れ日の煌めく様子がガラス細工の中にいるようで、私は光の森と呼んでいます。良いところですよ」
「行ってみたいわ」彼女が言う。
「地図を書きましょうか?」と聞き耳うさぎ。
「……いえ、すみません。私は運転が苦手なもので、とても山の中までは行けません。免許は持っているものの車もないし、教習所以外では運転したこともないも同然なんです」彼女は残念そうに首を振る。
「それでは猫さんに連れていってもらうのはいかがでしょう? 猫さんは運転がお好きな方ですよ。休日は道の駅や日帰り温泉まで一人でドライブするのが趣味の方ですから」聞き耳うさぎが提案する。僕は一瞬たじろいだ。急な展開で心の準備が出来ていなかった。でも彼女とお近づきになれるのは嬉しい。チャンスだとも思う。
「でも……いいんですか?」彼女は僕の方を窺う。僕は反射的に頷いていた。
「はい、大丈夫ですよ。運転には自信がありますから」いつの間にか僕の心臓は早鐘を打っていた。嬉しさで期待に胸が高鳴っている。
「じゃあお言葉に甘えて……」彼女が微笑んで僕を見つめる。「聞き耳うさぎさん。地図を書いて頂けますか」
「はい。喜んで」聞き耳うさぎは僕にそっとウインクを送る。
二、
彼女の名前は大水青と言った。約束の前の日の晩、僕は女性と二人きりで会うことについてあれこれと考えた。山に行くとはいえデートのようなものかもしれない。昼食には大水青がお弁当を作ってきてくれると言うからそれを楽しみにするとして、夜はどこかのレストランに予約を入れた方が良かったのだろうか。僕はそのあたり気が利かない。念のため候補の店を調べておこう、とインターネットでレストラン情報を検索する。お店を調べながら、WEBサイトの広告バナーに表示された宿泊施設の情報に、あらぬ妄想がわく。もしも大水青が積極的な人で、大人としてのさばけた肉体関係が求められたとしたらどうなるだろう。無言の了解で帰り道にホテルに行くような展開になったとしたら……僕は大水青のイメージで淫らな想像をしばらく働かせて、我に返った。いやいや、デートとはいえ初対面に近いのだから、強引に話を展開してはいけないだろう。清純そうな娘だから現実的にはキスもためらわれるかもしれない。いや、しかし我々は大人だ。デートをする以上ある程度男女関係に割り切ったところがあるのではないだろうか? それともデートではなく僕はただの車要員としてしか考えられていないのか。いやいや、そんなはずは……期待が渦巻き、いささか的外れな想像が次々に展開して、レストランを調べ終わる頃には、明日はやはりデートとして考えようと結論付けていた。
山に連れていく約束をした当日、駅から徒歩数分のところにある歴史資料館の前で僕たちは待ち合わせをしていた。僕が車を資料館に止めると、大水青は資料館の前にある木の長椅子に座って、燦々と降り注ぐ日差しの中、白の日傘をさして待っていた。大水青は薄手の白い麻のジャケットを羽織り、中にはミントカラーのシフォン生地のワンピースを着ている。山道を歩くことを想定して、下には伸縮性のあるズボンとスニーカーを身につけていた。一際目を引くのが、細い首筋につけた真珠のネックレスだ。パールの粒が一粒、白く清楚な輝きを放っている。
「おはようございます。今日はよろしくお願いします」
大水青はこちらを見つめて僕に笑いかけた。白く陶器のような肌は眩しく、なんて細やかな顔の造りなんだろうと思った。長い睫毛の上の瞼はほのかな真珠色の光で染まっている。生き生きとした表情からは、休日への期待と喜びが滲み出していた。僕は紺色の車の助手席のドアを開けて彼女を車内に案内した。
高速道路を経由して二時間くらい運転すると、地図にある目的地の山の中に入った。山の中腹の光の森に着くと、二人で車を降りて木漏れ日煌めく緑の森に足を踏み入れる。森林の清々しい香りがした。少し開けた日の当たる草地に出ると、レジャーシートを敷いて、大水青が作ってきてくれたサンドイッチの昼食を食べた。トマトの輪切りとスモークサーモンと、バジルペーストを混ぜたチーズが、ふわふわの丸い白パンに挟んである。サーモンの塩気ある旨みがチーズのまろやかな味わいと調和し、そこにバジルの風味のアクセントが付いている。分厚い輪切りのトマトは新鮮そのものでみずみずしい。サンドイッチにかぶりつくと色どり豊かな中身が現れ、味には素材選びの工夫と調和が感じられた。ひと手間かけた丁寧さのある美味しい食事だった。食べながら車の中で少し話していた、お互いの仕事のことや今の生活や家族に関する自己紹介の続きをした。要点をまとめてしまえば、お互いに会社員で一人暮らしをしていて、独身で今は相手がいなかった。
大水青の仕事は美容関係の商品を扱う会社の事務職だ。化粧品や洗顔料などの注文の電話を受け伝票に記入し、スキャンした注文伝票やFAXから商品名、数量、納期などを入力する。取り扱う商品数は千種類を超える。それというのもアイシャドウやファンデーションは色彩のバリエーションが豊富だからだ。細かな色名の違いであっても入力ミスは許されない。同じピンク色であっても、ローズピンクとコーラルピンクは全くの別物だ、伝票数は常に数百件あり、キーボード入力の手が休まることはない。時間帯によりオンラインショッピング関係の仕事や、商品・得意先管理の仕事もする。基本的にはコンピューターと電話を通じた内勤だが、時に商品展示会などで、各企業・お店の顧客対応をすることもある。女性の多いオフィスでの決まったメンバーで決まった仕事を繰り返す毎日だが、職場の同じ同僚とも管理職とも衝突などはあまりなく、適切な人間関係を築いているらしい。
僕自身は食品の流通関係の会社で営業と配送の仕事をしている。沢山の得意先を抱えて、日々トラックで運転してその日厨房で使う食材を届け、翌営業日の注文を取ってくる。その年担当になる部署によって得意先の種類がレストラン関係だったり、病院や介護施設の厨房関係だったり、ラーメン屋が多かったりと違ってくるのだけれども、今年は遠方にある特定の地域の担当になり、多様な得意先を任されていた。地元の給食センターから、葬祭関係のお食事の用意をする会社や、ホテルのバイキングを担当する食堂まで、毎日決まった得意先に荷物を配送する。様々な分野の業界を食品配達によって垣間見ることで、社会が動いて人が食によって生かされているという、人間の営みの現実を日々感じながら生きられる仕事だ。今年でやっと五年目になる。働き始めてから今までの時間をとても長く感じる。得意な運転が活かせる仕事なのはありがたいと思う。ただ、痛んだ食材へのクレームは、時に人の命に関わるし、得意先の信用問題にも関わるので、その分切実な顧客の怒りを身に受けることになるため大変だ。
食事を終えると荷物を片付けて森の中を歩き始める。静けさの中に小鳥の鳴き声と木の葉のざわめきが聞こえる。吹く風がはるかな高みにある枝の先を揺らすと、波のうねりのように枝全体が複雑になびくのだ。幾千幾万の緑の葉の隙間から、風が漏れるように透明な日の光が差し込んで、地上で煌めく木漏れ日となって揺れる。光の森と聞き耳うさぎが言っていたように、白く清浄な光が、高い樹影が立ち並ぶ広大な面積の空間に満ちている。大地から清らかな地下水を吸って息づく緑の植物に光が注がれる。その植物は光合成で清々しい空気を生成する。鮮やかな黄緑色の世界の中を目で探ると、様々な植物の姿が見えてくる。花の形が畳んだ提灯のようなもの、斑入りあざらしに良く似た謎の果実、実の先端に真っ赤な丸い房が付いた植物、紫色の花からサルバドール・ダリのひげのようなおしべがぴんと飛び出しているもの……見たことのない名前を知らない植物がそこかしこに発見できた。
「ねぇ、猫さん。どうして猫さんは猫と呼ばれているの? 猫を飼っているとか?」大水青が質問する。
「いや、アパート暮らしで猫は禁止だから飼えないんだ」
「それならなぜ猫という名がついたの?」
「十二支の話ののけものの猫が由来かな。鼠に騙されて、猫は神様の元に集まる競争に遅れてしまい、十二支の中に入れなかったんだよ」
「その話は知っているわ。あなたがなぜのけものなの?」
僕は迷いながら言葉を選んで言った。
「神の世界という名の精神世界、心の世界では、その存在に気付いていなかったのけものの猫の視点からでは、その成り立ちの全ては分からないんだ.僕は大人になるまで分かっていなかったから、心の世界のシステムの全ては理解出来ないことを知っている。だから猫なんだよ」
歩いていると小さな泉を木々の間に見つけた。綺麗な水が湧いているようだ。僕らは手ですくって、透明な冷たい水を飲む。
「言っていることがさっぱり分からないわ」
大水青は首を傾げる。
「うん。僕なりの心の世界の捉え方だからあまり気にしないで欲しい。この話は聞き耳うさぎと色々話す内に考えたことなんだ。聞き耳うさぎの兎っていうのも、十二支の話に関わっているよ。神様の下にいる十二支に当たる人々は、その考え方のタイプによってどの十二支になるか決まるんだ。思考の個性によるタイプ分けみたいなものだよ。彼は相手の心の声を聞いているかのように人の気持ちが良く分かる人だから、聞き耳うさぎと呼ばれているんだ」
「不思議な話ね」
「そうだね」僕は答える。野生世界では生物は常に生と死をかけて生きている。食うか食われるかの血脈みなぎる命がけの世界がある。そうした生と死の鮮やかな、動物としての生命の起源的な在り方が、人間を動物になぞらえて捉えるこの話にはあると僕は考えている。
光の森の雰囲気を満喫しつつ、背負ってきたリュックサックから図書館で借りてきた植物図鑑を取り出して、ハーブの探索に取りかかる。図鑑の植物と目の前の薬草を照らし合わせるのにはやや時間がかかったが、図鑑の説明のおかげでその薬草の特色を実際に体験することが出来た。例えば根を火であぶることによって青く美しい炎が見られ良い香りを放つといった特色は、図鑑の情報なしではまず気付くことが出来ない。大水青は「赤の帽子」という「川沿いに生息する動物たちのエネルギー源になっている」との説明が図鑑にある植物の、営養価の高い実を、ジッパー付きの透明な袋に熱心に採集していた。
僕は少し湿り気のある土壌に生えている、手を合わせたような形の葉を持つ薬草を見つけた。赤みがかった白い花は、開放感のある強い香りを放っている。僕が植物図鑑を読んでいると、大水青がそばに来てその花をじっと覗き込んだ。木漏れ日が彼女の瑞々しい生命力に溢れた表情と植物に白い光を投げかけている。
「お祈りをしている手みたいな、不思議な葉をしているわね。もう名前は分かった?」大水青が尋ねる。
「たぶんこの『水晶の椀』でいいと思う。今説明を読んでいたところなんだ」僕は開いた図鑑の右のページの写真を指差した。特徴的な葉の形が一致していた。
「本当ね。これで間違いないと思う」彼女が細い指先で植物に触れて確認する。「どんな薬草なの?」
僕は軽く図鑑の文章に目を走らせながら要点を説明する。
「お椀のような形の葉の間に、薬効のある水滴が溜まるようになっているみたいだ。地中の水分から吸い上げた水をゆっくりと葉の椀に貯めていく。のどに良い効果を発揮するので、古くから歌手に大切にされていた植物とある」
「毒はないの? 安全?」
「おそらく」
大水青は「水晶の椀」の葉の一つをそっと開くと、人差し指をその水滴に浸した。水滴は水晶玉のように濁りのない無色透明だった。彼女は指を口元に持っていき、ぺろと舐めた。
「かすかな苦みがあるけれど爽やかな味がする」
大水青が言った。僕も彼女をまねて「水晶の椀」の水滴を味わった。あまり味は分からなかったが、喉に清涼感が留まるように思えた。
僕と大水青は光の降り注ぐ緑の空間の中を共に歩いた。趣味の話になり、彼女は読み終えた古い雑誌の切り抜きが趣味なのだと語った。スクラップブックと言うらしい。
「裏側の写真が気になって切りにくいことはない?」僕は尋ねた。
「そうね。どちらも気に入っている写真があると表裏のどっちを切り抜くか迷うし、化粧品の顔写真の広告などが裏面にあると顔を切断するみたいで確かに少しためらうこともあるわ」
「思えば今の時代の呪いじみたいじめは、写真に画鋲を刺したり、写真の首を切ったりして行われる」
「まぁ悪意がなくても、顔写真を切られた雑誌のモデルさんが見たら嫌に思うでしょうね。まずありえない心配事ではあるけれども」
「昔の日本人が写真を撮られるだけで魂を取られると怯えた話を聞いたことがある」
「写真を人型を写すものとして重んじていた時代ね。でもね、雑誌スクラップは慣れてしまえば、抵抗なくどんどん切り抜けてしまえるものなの。直感的に選択して素早く。大体もう読まない雑誌なら、結果的にはもう見られることもなく焼かれて灰になってしまう紙の束なのよ。それを保存して自分の今後のライフスタイルのデザインに活かせるならば、私は呪い的な思想に基づく抵抗感よりも、雑誌の写真の再活用と未来への延命を選ぶわ」
僕は感心した。「そう言われればその通りだ」
「あとは趣味と言えるか分からないけれども、スポーツジムに通ってランニングマシーンで運動しているの。そこの休憩室が素敵で、マッサージチェアなどがあるその空間でリラックスするのが私にとって大事な時間よ」大水青は話を続けた。
「それはいいね。どんな部屋なの?」
「部屋の照明はオレンジ色の優しく暖かな光で、薄暗く落ち着ける部屋になっているの。天井が二等辺三角形に切り抜かれていて、そこに薄青く発光する海の絵が描かれている。大きなイトマキエイと銀の魚の群れが泳ぐのを海底から仰ぎ見ている感じで、層になった海面の光が透き通って見えるのよ」
「素敵な部屋なんだね」
「ええ。あと部屋の中央には、クラゲ型フロートの漂う円柱状の水槽があるの。水の色は仕込まれた照明で少しずつ変化して、ゆっくりと青からグリーンになったりする。その硝子の円柱の中を、ふわふわとクラゲが上下するの。それを見つめていると心が安まるのよね」
彼女はその空間を思い出すようにして語った。僕も話を聞いていると脳裏にその部屋のイメージがありありと見えるような気がした。
「海の世界をイメージしたマッサージルームなんて凝っているなぁ。良いジムだね」僕は言った。
「そうね、とても気に入っているのよ。ところで、あなたの趣味はドライブの他に何があるの?」
「聞き耳うさぎの酒場で夜空を眺めながらお酒を飲むこと」
彼女は頷いた「大切な趣味ね」
「実は憧れていることはたくさんあるんだ。でも僕には手が届かない」
「例えばどんなことに憧れているの?」大水青は聞く。
「そうだな。聞き耳うさぎのように、まるで心の声を聞くことが出来るみたいに、人が言えずに秘めている苦しみを知り、話しを聞く相手の気持ちを良く思いやって、大切に接することが出来る人に憧れる」
「分かるわ」
「あと、想像力を自在に飛翔させて、物語を作ることが出来る人や、気持ちや感情を込めて言葉を美しく歌い上げることが出来る人にも憧れる」
「小説家や作詞家、歌手、詩人といったところかしら?」
「そうだね。あとは、鮮やかで美しい世界を夢見て表現出来る人にも」
「画家や映画監督あたりかな?」
「実は職業として成立させている人になりたいという訳ではないんだ。ただ同じ人間として、そういう特別な力が与えられている人を羨ましく思う」
「あなたもそういう特別な力が欲しいと思う」
「強くそう思うよ」
「なるほどね」大水青は納得した様子だった。
「その憧れを込めて、読書や音楽・映画鑑賞やカラオケや人と話すといった、一般的な趣味も好きだよ」
「良いじゃない。多様な世界観のある人は魅力的よ」大水青は言った。
僕はちょっと頬を赤らめた。彼女はにっこりとした。
大水青が植物図鑑をめくって紫色の花を調べている間、僕は何かに呼ばれでもしたように引き寄せられて、森の岩壁の方を調べに単独行動をとった。この森には特にスズメバチや熊といった脅威はない様子だし、自分たち以外の人間はあまり見かけなかったので、少しの間僕が離れても、大水青が誘拐されるといった心配はあまりないと考えたのだ。僕は岩壁の奥の方に洞窟らしき裂け目を見つけたので、そこまで向かうことにした。大水青に向かって「ちょっと向こうの洞窟を見てくる!」と大声で伝える。遠くにいる大水青が了解の合図で腕で円を作る姿を確認した。
岩壁に沿って百メートル程歩いていくと、思った以上に大規模な洞窟の入り口が見つかった。人が集団でも踏み込めそうな様子だ。大水青と一緒に探検できる安全さがあるかどうかを前もって確認しておこうと思い、リュックから懐中電灯を取り出そうとしていると、いつの間にか背後に人が立っていた。僕が気配にびくっとして振り向くと、白い髪の老人がこちらを見下ろしていた。映画に出てくる年寄りの魔法使いみたいだ。しわがれた声で彼が言う。
「特別な能力を持つ存在になるための試練を受けたくはないか?」
僕はそう言われて頭が真っ白になった。少し間をおいて不安がやってきた。不気味なおじいさんだと思いながら何と答えようか考える。
「えっと……さっきの僕らの話を聞いていらっしゃったのでしょうか? 確かに才能を持つ人たちに憧れるというようなことを僕は言いましたが……」
「言葉は放たれると世界に通る。全ての意思は通じている」白髪の老人は言った。「試練に耐えれば神から特別な力が与えられる。試練の穴に来ないか?」
「この洞窟がその試練の穴ですか?」僕はおそるおそる尋ねる。
「そうだ。私について来なさい」言うと彼は洞窟の奥に消えていった。僕は混乱して迷ったが、どういうことなのか訳が分からないまま逃げるのは後で心残りになるような気がした、大水青には洞窟を見にいくことを伝えてあるということを自分の中の言い訳にし、一人白髪の老人の後を追いかけた。特別な才能というのがどういう事なのか気になってもいた。好奇心は猫をも殺すと良く言うけれども。白髪の老人は神がかりの宗教的修行者のようなものだろうか?
洞窟を進むと、岩壁の所々に火のついた蝋燭が置かれ足元を照らしているので、懐中電灯がなくても次第に闇に目が慣れていった。天井から円錐状の鍾乳石が牙のように無数に下がり、巨大生物の開いた口の中にいるように感じられる。湿り気を帯びた洞窟内の空気はひんやりとしている。見えない洞窟の上方の空間には、天井から並んでぶら下がる蝙蝠たちの身じろぎの気配がする。
しばらく歩くと平坦で開けた小部屋のような空間に出た。白髪の老人は中央の台のような岩の上に腰かけて待っていた。岩の上に蝋燭の灯りがあるようで、彼の輪郭が闇の中に浮き上がっている。老人は訊く。
「君の名は?」
「猫です」
「私は白の狸と呼ばれている」
「白の狸」僕は繰り返す。
「こちらにおいで」白の狸は岩の上から手招きをする。
岩の上はワゴン車の内部くらいの広さがあり、滑らかに磨いた平面になっていた。そこに遊牧民が手作業で刺繍したような柄の、分厚い毛織物が敷かれている。布の中央には金の香炉が置かれ、春が来て咲き出す花のような、陶酔感のある香りがそちらから流れてくる。その周りを幾つかの蝋燭が囲み、洞窟の岩壁をぼうっと照らしている。蝋燭の炎は僕と白の狸の大きな影を、岩壁の表面に揺らぎながら投影している。僕はスニーカーを脱ぎ揃えて敷物の上に座り、香炉を挟んで白の狸と向き合った。彼の放つ異様な威圧感の中に自分が呑み込まれていくのを感じた。
「ここで起こる試練について話しておきたいことがある」白の狸は語る。
「猫君はこれから目覚めている時の意識状態と眠っている時の意識状態の狭間に行き、その一種の白昼夢の世界で試練に挑むことになる。初めに言っておくが、心の世界で様々な存在が猫君に語る言葉は、猫君自身が持っているその人の情報に基づく魂のやり取りだ。猫君はその人の無意識的な思考にアクセスして言葉を聞く。言われる言葉は決してその相手の意識的な意見ではない。だから何を言われても現実を見失わないように。相手と関わった時の現実の思い出や会話を見失わないように」
「はい……」
僕には何のことか全然分からなかった。聞きながら僕は頭の中で、厄介なことに巻き込まれてしまった、大水青を待たせるかもしれない、後で何と言って謝ろう、といった心配をしていた。
「肝心なのは、脳裏にほのかに浮かぶイメージの世界だ。額の中央の辺りで視覚的な記憶を想起する。これが心の世界を思い描く基本だ。人間が書を読む時に自然と使っている視覚想起力と同じこと。あとは身体感覚と、視覚以外の五感の記憶を想起することも重要になってくる」白の狸は僕の目をしっかりと見据える。吸い込まれるような不思議に力強い黒い眼差しがそこにある。逃げられない感じがした。
「人の記憶は映像や音、匂いなどの感覚ごとに分かれて、脳内に断片的にしまい込まれる。人の記憶は言葉などからの連想によって引き出される。人は夢などにおいて、あるいは読書などにおいて、記憶を脳裏に引き出すことができる。視覚の記憶は喚起出来る。言葉によって人は記憶を混ぜ合わせて、イメージを作り上げることが出来る。それが心の世界で異常知覚ではなく、正常な文脈で脳内のイメージの世界を捉える前提になっている」
「なるほど……」
「身体感覚については少し準備運動をしよう。私の言葉に従って意識の焦点を変えてみて欲しい」白の狸は言った。要はこれから瞑想誘導のようなことをするのだろう。
「はい」
「靴下の感覚を持ち、両方の足の裏をイメージして」
僕は白の狸の言葉に誘導されて考えていく。僕は足の裏を意識する。山道を歩き回ってだいぶ疲労しているみたいだ。
「次に頭の上に見えない帽子を被る想像をして」
僕はかつらを被るようなイメージをした。
「正面を向きながら、魂になった内なる自分が後ろ向きになった状態を想像して」
言われた時は難易度が高そうだと思ったが、案外くるりと後ろ向きになる自分をイメージできた。
「最後に自分の目の中をイメージで覗き込んで」
このイメージを持った時、不思議と脳裏に鏡に映った自分自身の顔が見えるような気がした。
「猫君はどれくらい出来ていたか?」一通り終わると白の狸は尋ねた。
「たぶん全部出来たと思います」僕は答える。
「それならいい。猫君には素質がある」
突然蝋燭が吹き消され、暗闇の中で試練が始まった。香炉の花の香りがにわかに強くなり、まどろみのような温かさが僕を包んだ。香りを吸い込むと頭の中心部分がぼんやりと酔ったようになった。奇妙に電気的な痺れが頭の中に感じられる。
「これから猫君は悪い夢を見るよ」
白の狸の声が冷酷に洞窟の中に反響した。
「猫君の魂はそっとこの岩をすり抜けて、この洞窟の地下世界にどこまでも落下していく。やがて地下深い、青い地底湖の上に猫君の魂はそっと浮かぶ。イメージして欲しい。猫君は体育館よりも広い真っ青な湖にぽっかりと浮かんで、その地の底の世界から上空を見上げているんだ。そこからは地上に生きる人々の魂と、その先の天上世界の神々の存在が見上げられる。この時代に生きるあらゆる命の在り様が、この心の底からは良く分かるんだ。いいかい?」白い狸は言った。
「湖に浮かんで世界を見上げる自分をイメージ出来ました」僕は答える。
「これから君は今までに生きてきて得た人間関係と自らの罪を聞いて回らなければならない。私の声をシャーマンの先導役だと思って耳を傾けて欲しい」
「はい」
「猫君の中にある愛情の意図と憎しみの意図を巡らなくてはならない。一番好きな異性と、殺したい程憎い相手の心に耳を傾けるのがこの領域でのルールだが、猫君は愛情と憎しみのどちらの意図を巡りたいか?」
「……愛情の意図の方がいいかな」殺したい程憎い相手とは何やら物騒な話だ。
「ではこの地獄巡りでは、愛情の側を鍵にしよう」
「はい」
目の前の暗闇と脳裏の暗闇が混ざり合い、闇の中に無数の顔とまなざしが薄らと浮かび上がるような気がした。どれも冷たい目だ。白の狸が言う白昼夢が始まったのだろうか。
「猫君にとって一番大切な愛する相手は誰か」
僕は考えて一番最初に頭に浮かぶ相手の名前を言う。
「大水青です」
「それでは今の心の世界に彼女を呼び出してみよう。脳裏に彼女の姿をイメージして、その名前をはっきりと心の中に思い浮かべてみなさい」
僕は心の中で大水青の名を呼んだ。すると彼女の姿が、目の前の暗闇に透き通るように浮かび上がった。彼女の魂の姿は白い頬を膨らませて怒りを露わにしている。
「なんでいなくなったの? 一人でおいてきぼりにされて心細かったのよ。女の子を一人でこんな辺鄙な山の中に置いて、帰っちゃったわけ? 事件とかに巻き込まれたりさらわれたりしたらどう責任とってくれるのよ! 頼りない男。信頼して裏切られた気分!」
大水青の魂はものすごく怒っているようだった。
「ごめん。本当はすぐに戻るはずだったんだ。白い狸に捕まってしまって……」僕は言い訳をする。
「あなたの自己責任に決まっているでしょ! あなたは特別な力が欲しくて欲張ったのよ。自業自得だわ」
どうやら魂の世界ではあらゆる情報は共有されているらしい。
「猫君は特別な力が欲しいと欲張ったからここに来てしまったんだよ。大水青さんが言うように、欲に目が眩んだ猫君がいけなかったんだ」白の狸が言い添える。
「だいたいあなたの話の相槌の打ち方は意地悪なのよ。私がスクラップブックを趣味にしているという話をした時も、何あれ、写真の呪い? そんな薄気味悪いこと言われたくなかったわよ。せっかく楽しくスクラップを作る時間を大切にしているのに、あんなことを言われたら気にしちゃうでしょ。これから先雑誌が切りにくくなっちゃうわよ。あなたは人に対する配慮が足りないのよ。思いやりがないわ。本当に酷い人!」
「ごめん。思いやりに欠けていた」
僕はショックを受けた。何気ない自分の発言が想像した以上に相手にとっては不快なものになっていたということを知り後悔した。
「第一ねえ。あなたは下心があってこの山へのドライブを引き受けたたんじゃない? うぶなふりをしているのかもしれないけれど、分かるわよ。洞窟の暗がりにでも引き込んで、さり気なく腕を絡めたり身体を支えたりしたかったんじゃないの? まさかどさくさにまぎれてキスとか考えている訳じゃないわよね。ほとんど初対面なのよ? 恥を知りなさい!」
僕は唖然とした。
「そんなことを言われても……」
心当たりが少しあるだけに僕はしどろもどろになった。
「大体そうよねぇ。酒場で一人カクテルを飲むような孤独でキザな男についてきた私が愚かだったわ。優しそうで親切な人に思えたけれども、心の底では何を考えているか分かったもんじゃないわ。寂しいんじゃないの? 相手が欲しいんじゃないの?」
大水青の口ぶりには嘲笑が混じっていた。段々と表情も高圧的なものに変わっている。
「僕はそんなつもりはなかった。ただ君に憧れて好意を持ったから運転を引き受けたんだ。下心はあったとしても、君に気遣って抑えるつもりでいた。本当だよ」
僕は切実に訴えた。
そこで大水青の隣の空間に、すっと聞き耳うさぎのイメージが現れた。
「猫さん。あなたの下心は知っていますよ。あなたは昨夜大水青さんに対して淫らな期待を思い浮かべてしまいましたね。私も長年酒場に勤めていると分かりますよ。そういう人間の本音がね」
聞き耳うさぎは若干軽蔑の表情を浮かべて言った。
「えぇ。酒場では男女が出会い発展した関係になっていく例がよくあります。ご自分に正直になることですね」
僕はうろたえた。大水青が来る直前の聞き耳うさぎとの会話が大水青に知られていたら、とても気まずい。僕は相手が欲しいというような話を聞き耳うさぎに少し伝えていたのだ。
「もちろんその話しを踏まえての配慮でしたよ。あなたが大水青さんに色目を向けているのを察したものでね」聞き耳うさぎは言った。この心の世界においては自分の心の動きまで全てを知られているという裁きがあるのだ。「まぁ気の弱いあなたに言うのは酷ですが、風采の上がらないあなたには大水青さんはもったいないですよ。それでもあなたの孤独を哀れに思ったもので、縁を作る手助けをしたのです」聞き耳うさぎのイメージは薄れ、今度は正面から瞳を見つめてきた時の大水青のイメージが鮮明に脳裏に浮かんだ。
「本当に私のことが好き? 世界で一番愛している?」大水青が尋ねる。
「……本当に愛しているよ」僕は怯えながら答える。
「ふざけるな! 私にはまだ沢山の可能性があるんだよ。孤独なあなたとは比較にならないくらいの多様な人間関係があるんだよ。あなたに対しては私は今は相手がいないって言ったけれども、もし嘘で他に男がいたらどうするんだよ! 人を信じ過ぎるな! あと、前の相手と別れたばかりで傷ついて一人でいたい時期だったらどうする? もっと人を思いやれ、そして大事なことはちゃんと探りをいれて聞け! 植物採集の時だって、私のことを色々訊き出すチャンスだろ? いなくなって一人でどこか行くなんて論外だ。もっと私に興味を持って話を聞いて!」大水青は厳しく言い放った。僕は自信を失った。
彼女は優しい表情に戻って言った。
「まだ知りあって間もないでしょ? そんなお互いをよく知らない状態で、付きあってもいない人から一番に選ばれちゃうと戸惑うのよね。それは確かに私の側に下心が0なら、男の人の車に乗ってついてきたりしないけれどもね。約束よ、早まらないで」大水青のイメージは闇の中に消えていった。僕の心が受けたダメージは甚大だった。甘く見ていた現実の隠された悪意が、世界がひっくりかえって明るみに出てきたような感じだった。信頼していた人間の心の裏を見せつけられたようで、それが苦しかった。
大水青のイメージの次には、今まで交際したり、ほのかに思いを寄せた女性たちが入れ替わり立ち替わり現れて、僕を否定し責めていった。その後は尊敬するアーティストや作家たちから、僕が好きだと伝える度に憎まれ、僕の過去の過ちが次々と取り調べられて明るみに出て、その記憶にまつわる人々が現れては非難の言葉を浴びせかけていった。会社、大学、高校、中学、小学校、塾、習い事。過去に僕が所属していたあらゆる人間関係が心の暗がりに現れては、人々はみな侮蔑の言葉や「嫌い、死ね」の言葉を僕に言っていった。途中までは白の狸があらゆる人に化けて騙しているのかもしれないという、化け狸の幻術の疑いが頭の片隅にあったが、段々と思い出の中のその人本人に言われているような感覚で人々からの否定的な言葉を受けるようになっていった。僕はずっと責められる拷問のような苦しみの中で、次第に弱り、恥ずかしくて死にたい気持ちになっていった。脳裏に幻のように見える、記憶にある人々の視覚的なイメージ以外にも、不快な匂いが喚起されて苦しめられたり、全身が冷気で覆われがたがたと震えたり、脳みそに鈍い痛みや、怒気による熱さや痺れが生じたりと、多様な身体感覚が喚起された。僕の記憶の引き出しに仕舞いこまれている肉体的な反応が引き出されて、僕を苦しめるために利用されているような気がした。
心の世界の自分像は、他人から張り付けられたレッテルによってその多くが決まる。そうしたレッテルは大抵現実の自分自身の行動や発言によって生じるので、心の世界での自分は、他者の思惑というフィルターを通した鏡像のようなものだ。おそらく印象のレッテルを付けることで、相手の心のイメージに情報を書き込んでいくのだろう。心の世界で他者から書き込まれた自分自身に対する印象は、心の自分像に張り付けられた情報となって、心の世界において他の人から読まれるようになる。印象が他者に共有される。他者から書き込まれたその印象が滅茶苦茶なので、心の世界で僕は人から恥ずかしいイメージで見られ苦しむ。卑猥な視覚的イメージや性的な言葉が付けられていて、そう思われたくない人たちから淫乱と扱われる心の地獄は、壮絶さを伴う。これで自殺する人もいると思う。
みな自分の言い分を言っていく。僕自身の気持ちや本当の感情は伝わっていかない。僕自身の気持ちは意味を成さず、同じことが繰り返し責められる。同じ言葉が人を変えずっと言われ続ける。人々の無理解が苦しかった。突きつけられる恥や過去の過ちで、自分で自分が許せなくなった。人々の意見だけが次々と聞こえ、自分自身の心や、本当の気持ちがすり潰されて失われていくような気がした。本当はそうじゃないんだ、あの過ちにはこういった理由があった。君にはあんなことを言ってしまったけれども、その後僕はその発言への後悔をずっと引きずって生きてきたし、本当は切実に謝りたかったんだ、謝る機会が欲しかったんだと、僕は心の底から叫びたかった。しかしその考えは引き裂かれて、押し潰されて、なきものにされてしまった。人々の心を聞き続けることが本当に苦痛だった。
心のイメージの世界の中で、僕は浮かんでいた湖から水中に沈むことを望んだ。例えそれが溺れ死ぬことを意味していても、僕は青い水の中に沈んで、自分を責める人々の声から逃れたかった。僕は心の世界で、ゆっくりと水の底へと沈んでいった。やがて息は最後の泡になって青い湖面に浮かぶだろう。
大水青は猫が洞窟に行ったきり、長い間戻って来ないので不安になった。三十分が過ぎ、さすがに何かあったのではないかと心配になり探しにいくことにした。落盤事故や地下への転落などでなければいいけれどと考える。彼が言っていたものらしい洞窟はすぐに見つかったが、不思議なことに洞窟の入り口に彼のリュックサックが置いてあった。懐中電灯の端が荷物から突き出している。暗い洞窟の中に懐中電灯もなしでいくなんてどういうこと? と大水青は疑問に思った。洞窟の中を覗き込むと、なるほど蝋燭の灯火が点々と内部を照らしている。観光スポットとして整備されているようには思えなかったが、大水青は疑問と猫の荷物を抱えながら、洞窟の中に足を踏み入れていった。進んでいくと蝋燭の灯りが途切れる空間に出たので、大水青は猫の懐中電灯の灯りをつけて照らした。すると何者かの影がささっと跳躍し、洞窟の奥に逃げていくのが見えた。猫かなと思って照らし出そうとすると、何者かが逃げ去った台のような岩の上に、誰かが倒れているのが見えた。駆け寄って照らし出すと、猫が気を失って倒れていた。揺さぶっても目覚めない。他にも誰かがいるのかと恐れて、隈なく周囲を照らすと、至るところに生き物の骨が散らばっていた。中には明らかに人骨の髑髏だと分かる骨も見られた。大水青は人骨にぞっとした。ここで人が死んだのだ。おそらくは殺されて。洞窟のこの先に道は見えない。先ほどの逃げた人物は消滅していた。大水青は猫の傍に寄り添って、顔を近づけて何度も呼びかけた。大水青は心の中で天の神様に向けて祈った。「神様、どうかこの大切な人が生きていますように」
猫は青い湖の底に横たわり死んだように意識をなくしていたが、湖の底まで一筋のきらきらと光る糸が降りてくるのを見た。猫が糸の先を見ようとすると、大水青がこの糸の先にいるのだと直感的に分かった。猫は光る糸に手を触れ握る。すると猫はするすると湖から引き上げられ、天に引き上げられ、光る糸に導かれていって――
大水青が猫の頬をぱしぱしと叩きながら声をかけていると、しばらくして猫がはっと意識を取り戻した。大水青の顔を見ると、猫は弱々しくほほえんだ。
「ひとりにしてごめん。救い上げてくれてどうもありがとう」
大水青はほっとして猫の額を丁寧に撫でた。すると大水青は手のひらに違和感を覚えた。まじまじと猫の額を見つめると、そこには二本の角が生えていた。大水青はちょっと困った顔で猫に言った。
「あなた、鬼の角が生えているわよ」
大水青は洞窟から出てすぐに地元の警察に「洞窟に人骨がある」と通報した。僕と大水青も警察に呼ばれ、僕は白の狸とのいきさつを語った。結局現地を離れることが出来たのは夕方の六時を過ぎていた。僕は思いがけない騒動に巻き込まれたことを大水青に詫びて、彼女に夕食をご馳走したいと切りだした。彼女はあまり気を遣わないで欲しい、苦しい目に遭ったのはあなたの方なのだからと言ったが、時間も時間でお互いに空腹なので、やはり夕食を共にすることになった。僕はカーナビで、昨夜調べておいた飲食店の候補を表示する。車内には針葉樹の奥深い芳香を持つカーフレグランスの香りが仄かに漂っている。窓の外を流れていく夜の光が、香水瓶の薄紫色の液体を揺らめかす。「何か音楽をかけようか」と僕が言い、彼女が頷いたので、一番気に入っている音楽バンドのCDをセットした。四人組のグループで、透明感のある歌声の女性ボーカルを、実力派のギターとキーボードが支える。伴奏、作詩、編曲とそれぞれの才能を生かしたメンバー編成で、その音楽世界は儚く繊細で聴き飽きることがない。大水青は三つ目の曲を気に入って
「素敵ね。恋人を失った時の深い喪失感と無力さがひしひしと伝わるのに、暗くならずに白い光で清められているみたいな音楽」と言った。
「僕もその曲がとても好きだよ」と伝えた。言葉にならないところにも強い気持ちが込められているような気がして、空白が語る悲しみの深さを感じさせる歌詞だと思っていた。僕はそのことを大水青に伝えようとしたけれども、きちんとした言葉にならずに沈黙した。僕は時々上手く話すことが出来ない。今は緊張しているのかもしれなかった。心の世界で大水青の幻に言われたことは、本人が意識している本当の気持ちではないかもしれないけれども、心の奥にある本音ではあるのかもしれない。そう思うと僕は慎重になり、言葉は凍りついて出てこなくなった。額に生えた鬼の角の先から、疑心暗鬼に満ちた悪意が脳裏に流れ込んでくるような気がして、僕は運転中の視覚世界に意識を集中させた。
高速道路を下りて一般道に入れたのが八時頃だった。通り過ぎていく風景の中にモーテルを捉えたりすると、僕は一瞬否応なしに妄想に囚われ、すぐに気まずくその思いをかき消す。洞窟の悪夢が頭をよぎって、本当のところは大水青は僕のことをどう思っているのだろうと考えた。何とも思っていないのかもしれない。しかし幻の中で僕に対して向けたような否定的な思いを言わずに抱えていることは十分にあり得ることだし、僕も思い当たる発言は反省しなければならないと思っている。問題は大水青が僕に異性として見られることをどう思っているかというところだ。自然な欲求として僕は大水青に異性としての魅力を感じている。それに対して毛嫌いする程の抵抗を彼女が感じていたとしたら、いくら僕が鈍感でもさすがに彼女の素振りから分かるだろうという気がした。僕は今日の大水青の様子を思い返してみる。嫌われて避けられている印象はなく、むしろ自分から近づいてきて笑いかけてくれていた。あるいは洞窟での異常事態が起きてから、彼女は今日はデートとしては過ごしていないのかもしれない。その可能性は大きいと思った。僕はさりげなく彼女に尋ねたいと思った。助手席の様子を窺うと、彼女は眠ってはいないようだったが、音楽に耳を傾けて静かにしていた。僕は眠気覚ましにサービスエリアで買った缶コーヒーをひと口飲むと、大水青の思いを確かめる意図を持って話しかけた。
「僕らの初めてのデートだったのに、事件のような状況に巻き込まれてしまってごめん」
「いいのよ、あなたが悪いんじゃないんだから」彼女は自然に答える。僕はもう少し踏み込みたい。
「……今日はデートって言ってもいいのかな?」
「ん? なにそれ?」彼女は笑う。「光の森のピクニックは楽しかったわよ。ただ、警察沙汰は気疲れしちゃった。せっかくの休日だから、もっとハーブ探しの時間が楽しめたら良かったとは思ったわ。でも気にしないで。あなたは直接の被害者なんだから、私に気を遣わなくていいのよ。あなたが無事でいてくれて、それだけで本当に良かったんだから」彼女の声には少し疲労が滲むものの、本当に僕を思いやって言ってくれていることが感じ取れた。
「そうか。ありがとう」
僕は言ってしまいそうな言葉を抑えて飲み込む。本当はこの後の時間を彼女と楽しんで、事件で失った時間を取り戻したい。出来れば大水青と共に一夜を過ごしたい。でもそんな僕の欲望を露わにしてしまったら、彼女との信頼関係を壊してしまいそうな気がした。彼女の思いやりの気持ちをないがしろにしてしまいそうに思えた。被害者と言われて思い当たったけれども、僕は洞窟の儀式以来、変に気が高ぶっているのかもしれなかった。あの体験は僕にとっては異常事態だった。だからこそ本能的に異性を強く求めているのかもしれない。彼女を確実に自分の相手にしたいという焦りがあるような気がする。身に危険が迫ることで、生命は焦って行動を促すのだろうか。僕はハンドルを握りながら一つ深呼吸をして、色々な言葉を抑えて彼女に言った。
「君は優しいね。大水青が僕の無事を願ってくれたから、僕は無事に現実に戻ってこられたんだと思う。君の思いやりの心は本当に貴重で尊い」
大水青は照れたように僕にありがとうと言った。
「あなたこそ優しい人よ」
カーナビの音声案内が目的地周辺であることを知らせた。僕らはこぢんまりとした天ぷら料理のお店に入り、白身魚や海老や野菜の天ぷらを塩をつけて食べた。食事を終えると僕は大水青を車で自宅まで送り、別れた。我ながら良く理性を保って紳士的になれたものだと思った。自分の衝動に操られるようにして動くのではなく、理性で状況を判断して動くようにするのが、意識的に生きる上で肝心だ。そうでないと無意識に引っ張られて人生は望まぬ展開をするかもしれない。粘り強く焦らず前に進みたい。僕は家に帰るとどっと疲れが出て、シャワーも浴びずにベットに横たわって、そのまま眠りこんだ。
猫と大水青が洞窟に行った数日後、新聞に光の森の洞窟にまつわる記事が出た。警察による白の狸の捜査の様子がその新聞記事には書かれていた。
『洞窟のシャーマン、殺人で逮捕』
十五日午前、☆県山中の洞窟内にて、無職のTという六十九歳の男性を殺人の容疑で逮捕した。洞窟内で三人の白骨化された死体が発見され、被害者の身元を調べると共に、T容疑者の殺人の動機などについて捜査を進めている。調べによると容疑者はセミナーを主催して講演会などを行った業績が過去にあり、哲学やシャーマニズムに関心を深め長年の独自研究を行っていた。思索と瞑想の追求のため数年前から、☆県の山の中に籠って一人生活を送っていたという。独自のシャーマニズムの追求のため、生贄の儀式を洞窟内で行っていたと見られ、通りかかった観光客を洞窟に誘い込んでは、判断力を麻痺させる植物の香などの力を借り、被害者を瞑想状態に陥れては殺害していたものと見られる。T容疑者は容疑を否認しており「人々の霊的覚醒と悟りを目的に行っていた、救済のための儀式だ」などと供述している。
三、
額に角が生えてしまってからというもの、僕は夜がくる度にイメージの世界で旅をした。夜に布団で横になってから、脳裏に浮かぶ光景に集中する。するとその光景は動き出す。白の狸に教えられた世界観は僕の中で生きていた。しかし現実と同時にイメージの世界で二重に生きるのは生易しいことではなかった。日中仕事をしている時でも、実は頭の中の世界は動いているのだけれども、基本は現実の忙しい仕事に意識を集中させる。そうすると頭の中で自動進行する考え事には構っていられない。僕は身体を動かして重い荷物を運び、得意先と話して次の注文を取り、視覚世界に集中してトラックで長距離を運転する。心が苦しい時でも僕は何とか現実に適応して生きていた。しかし白の狸と関わった日から一週間くらい経った頃から、不眠がちの日が続くようになった。夜布団に入ってからの思考が辛くて、目が冴えて眠れなくなったのだ。ついに数量計算の時に無意識的雑念による差し障りが出てきて、寝不足による運転への集中力に危険を感じるようになったので、止むをえず会社を休むことにした。自分の担当は同じ課の同僚にお願いして、休日を挟んで一週間の連休を取った。休み中、僕はずっと布団の中で頭を抱えて考え続けていた。眠りは正しく訪れず断片的で、白昼夢と睡眠中の夢の境目が曖昧になった。頭の中の妄想と現実は地続きで、人々の悪意に取り巻かれ苦しみに溺れた。時々狂気による医者の受診も頭をよぎった。薬があれば考える苦しみから逃れられるのかもしれない。しかし今は考えることが課せられているような気がしたし、被害妄想が酷くて外に出ることさえ怖くなっていた。いつ何時事件や事故に巻き込まれるか分からないという、普段も当たり前の不安が、やけに切迫したものとして感じられて、道を歩けば殺されそうな気がした。
心の中でこんな状況に自分を陥れた白の狸を強く呪ったが、白の狸のことを考える度に、心の世界の状況を打開する助け舟の言葉が短く与えられるので、段々と僕は彼を畏れ心の世界で頼るようになった。特に心の世界で過去の人間関係を振り返って相手を友だちだと確認していく方法は、脳内状況を安定する方向に変えてくれたので救われた。ただ白の狸の方は警察の取り調べと心の世界の重圧で、それどころではない過酷さの中にいるようで、今忙しいと常に僕を追い払った。あらゆる人の面影が頭をよぎるが、大抵の場合人々は忙しく僕を煙たがった。特に大水青のことは繰り返し考えてしまうけれども、やはり彼女も仕事で忙しく、僕が彼女のことを考えると嫌がり、彼女のことを考える度に僕は考えたくないいやらしい妄想を引き出されて、より一層彼女に嫌われて心が傷つくのだった。僕は誰のことも上手く考えられず、本当は誰のことも考えず自分1人だけの思考世界で気を休めたかった。誰のことを考えても心が責められた。僕自身に変なレッテルがついていて、みなそのレッテルを見て僕を嫌っているような気がした。まるでいやらしい悪霊に取りつかれていて、その幽霊が生前にしたことで自分が責められているかのように心当たりのない濡れ衣も多かった。
僕は可能な限りの人間関係を、時間をかけて心の世界で解きほぐすようにした。友だちだと思える人には慎重に声を掛けて、友だちだと心の世界で確認し合った。心が責められる過去の過ちについては、よく相手の言い分を聞いた。昔あった嫌なことでどうしても許せない人には、自分の中で憎く許せないと決めた。好きな人には好きと言い、嫌いな人には理由をつけて憎いと言い、友だちは友だちにする。原理はシンプルだが一人一人を大切に扱い、人間関係にレッテルを張り整理していくのだ。そうして何百人もの人間関係を思い出す内に、実家から卒業アルバムを持ってきていれば良かったと思った。手元にある会社や大学時代の名簿は、心の世界で人間関係を確認するのに役に立った。心の世界で人は名前で繋がる。幻に出てくるイメージは僕の記憶の中にあるその人のもので、薄らと脳裏に浮かぶその表情は子どもの頃のままだったりする。次第に人に憎まれ、他者の言葉を聞き流すばかりだった心の中が安定してきた。聞き耳うさぎのことを考えた時、彼はお疲れ様ですと言いながら、美しく鮮明な青いカクテルのイメージを視覚喚起して見せてくれた。煌めくカクテルが見えると同時に、美味しい果実の風味が舌の上に喚起されて癒された。自分が落ち着いてきたかどうか確かめるために財布の中のレシートを使って計算をしてみると、集中して問題なく数量計算が出来た。自分の頭は戻ってきたようだ。健康な身体の人を行動不能にしてしまう、人間の憎悪の念の恐ろしさを改めて感じた。
僕はある夜、白の狸の存在を慎重に考えた。相当早いスピードでめまぐるしく苦悩している白の狸の思考回路の中に入り込んだ僕は、わずかに彼の「呼んだか?」という単語を聞きとった。僕と白の狸はその一瞬だけやり取りをしたようだった。彼の思考回路から離れると同時に、僕の頭にはあるアイディアが残っていた。それはつまり言葉による思考、言語による苦悩を離れて、言葉にされていない思考内容全体を捉えて、自分自身の悩みとして脳内情報を見よ、ということだった。心の世界で他者の生き霊から責められた言葉は、全部自分自身の頭の中の苦悩なのだ。その思考を受け入れた時に、今度は白の狸からはっきりとした言葉が届いた。「人が生きる限り苦悩は続く。今のお前には自分がない。他者に流されるな」その言葉をきっかけに、僕は脳内の存在に責められている時の自分の苦しみを客観的に捉える、俯瞰的な心の把握のしかたを徐々に確立していった。思考全体の流れや構成を捉えるようにして、一旦自分から離れて悩みを眺めてみると、それは死への恐怖や、人間関係の悩みや、性にまつわるコンプレックスなどの、心理学的にありふれた悩み事の枠組みの中に回収されていった。僕は白の狸にされたことを許した。僕は白の狸に対してこう念じた。「あなたは善人、生きていて」
休みを取って四日目くらいからまとまった眠りが取れるようになった。休みなく続く思考の中で、山ほど買いこんだ栄養ゼリーばかりを口にして、昼夜はもう分かっていなかった。僕はずっと眠れなかった分を取り戻すように、ひたすら眠り続けた。ただ、時々意識のある状態になり、夢の続きのような綺麗な白昼夢を見た。その眠りと目覚めのあやふやな長い休息の中で、僕は奇妙な物語を体験した。
脳裏に浮かぶその幻の中で僕は心の世界に降りて行き、神様と呼ばれる存在にそっと声を掛けて、額に生えてしまった鬼の角を取るためにはどうすれば良いのかを相談した。神様の世界は清浄で白く煌めいていて、静かで他の物音がしなかった。神様の背中には白い天使の羽と黒い悪魔の羽が生えていた。神様は黙って白の羽と黒の羽を一枚ずつ引き抜くと僕に手渡した。白の羽は一枚の紙に、黒の羽は羽ペンに姿を変え、ペンはひとりでに紙の上に文字と絵をかき出した。
「その地図にある図書館を探しなさい」
神様は言葉を残して消えた。紙の上には見事な地図が描き出されていた。遠くにある砂丘が示されている地図には、なぜか「かごめかごめ」の歌詞と、ドーム状の籠に入った鳥の絵が添えられていた。この絵が図書館を表しているのだろうか。僕は地図を持って砂丘への旅に出ることにした。
朝の四時過ぎに携帯電話の目覚まし時計機能が「ハバネラ」の曲を鳴らした。朝ごはんに焼き立ての香ばしいソーセージを挟んだロールパンと、バニラクリーム入りの菓子パンを食べる。昨夜アイロンをかけたYシャツの上にネイビーブルーのリネンジャケットを着て、早くに家を出て始発の電車に乗り込む。鈍行列車で一日がかりで遠く離れた土地の砂丘を目指す。
電車は空いており、座席に座ってカフカの「変身」を読んでいた。ざらついた砂嵐を感じるような、目がひび割れてしまいそうな文章だった。それは心象風景的な砂嵐だった。時々目を上げて、列車内にいる人々を観察する。派手な色のキャリーバックを持った男女が正面に座り、その横に上品で美しい初老の婦人がいた。落ち着きなく車内を移動する男子学生風の二人組は、一人は爽やかで眼鏡をかけており、もう一人は髪を明るく染めてキザな雰囲気を醸し出していた。
途中の駅のお弁当屋さんに立ち寄った。愛想の良い親しみやすい女性店員から、「こでまり」という駅弁を買った。新快速の列車のゆったりとした座席に座って昼食を取る。「こでまり」を選んだのは正解だった。ピンク色の粒々とした衣で揚げられたえびや、美味しいなすの煮物、品の良い味付けの漬物、中央にのったアナゴの照り焼き飯……食べられぬものは一つもなく、非常に満足のいく、美味しい、センスの良い弁当だった。残さずぺろりと平らげた。乗り合わせた女の子たちの早口の方言の会話を聞きながら、列車は先へ先へと進んでいった。
やがて外は闇夜に包まれた。乗換を重ねて、一両しかないささやかな運行の列車に行きついた。車内には僕と、二人組の少年と車掌さんしかいない。都市部とは違い外の風景にはあまり明りがなく電灯はまばらにしかない。列車の窓の外には死を感じさせるような、果てしない暗闇が広がっていた。外を見ているとじわじわと黒い恐怖心が染み出してくるようで、僕はぼんやりと可能性の死の恐怖を感じていた。砂丘に向かう道の途中で、殺されたり車でさらわれたりする予感が頭をぐるぐると回っていた。もうじきこの闇夜に徒歩で挑むのだ。
目的の駅にたどり着いた時にはもう夜中の十一時をまわるところで、切符にスタンプを押してくれた駅員さんは、疲れているのか少しなげやりな態度だった。駅前のファーストフード店で夕食を食べる。セットメニューとミントアイスを注文した。店内ではBGMに洋楽が流れている。しばらくお店で過ごしてから、決心して砂丘を目指し歩き始める。
商店街を抜け、神殿風の記念館を抜け、道にせり出す墓場を抜け、巨大な歩道橋を渡り、せせらぎが聞こえる美しい川を渡った。真っ暗なトンネルはとても恐ろしくて、懐中電灯の光の球に包まれながら、後ろを振り返らずに一気にトンネルを駆け抜けた。心の霊が心霊なのだと思った。自分の心に根差した恐怖が、暗闇に形を与える。夜闇の中に死の気配や憎悪の念が霊体として自分を取り巻いているように感じられ、お守りを握りしめて神様の加護を強く祈った。お守りを押し付けた胸のあたりに青白く輝く魂の鳥のような存在を感じて、その神々しい存在に命が守られている感覚を持った。
砂丘に近づくと止められた車や、寝袋に入ったバックパッカーたちが見られた。砂丘まで辿り着くと、サンダルを履き、懐中電灯で闇を照らしながら砂の中へ足を踏み入れていく。砂の上をうごめく大きな黒い甲虫を見ると、行きの電車で読んでいたカフカの虫を思い出した。
一人きりで真夜中の広い砂丘に立つと、世界は砂の白と海の黒と星空の青の三色で出来ていて、天空には輝く金色(こんじき)の満月があった。風が強く、砂丘の表面は波のように流れる風紋を描く。砂は風にのり僕の目に入って痛い。僕は満月を見上げてひとりきりの世界で、月の光を見つめながらくるくると回転し、バランスを崩してよろめいた。満月の方向から音にならない声が笑っているような気がした。W字に並んだカシオペヤ座がはっきりと見える澄んだ夜空で、風が雲を吹き飛ばしていた。僕はレジャーシートを砂の上に敷いて、寝転んで夜空の月と星を眺めた。
僕は数時間夜空を眺めていた。風の寒さにもだいぶ馴染んできた。ふと、砂を踏んで誰かがこちらに歩いてくる音が聞こえた。身を起して顔を上げると、満月の青ざめた光に照らされて、裸足の女がこちらに歩いてくるのが見えた。黒く長い髪はつややかで、蘇芳と萌黄の色を重ねた着物を身にまとっている。女性は微笑んでいたが、肌の向こう側に海岸の灯火と松林が透き通って見える。砂丘を彷徨う遊女の霊だろうか。
「お兄さんはおひとり?」女性は甘い声色で聞いてくる。
「君は?」僕は体感温度が急激に下がるのを感じた。
「私は躑躅(つつじ)よ。昔お店から逃げてここの海で男と死んだの」
「遊郭?」
「この格好、そう見えるのね。大体は合っているわ」躑躅の霊は答えた。「お兄さん、あたしと良い思いしたくない?」
「断るよ。幽霊だから君が怖いんだ」
「そう? 残念。じゃあ、お兄さん私の話を聞いてくれない?」
「いいよ」僕は答える。
躑躅は僕の隣のレジャーシートに腰を下ろすと、媚を含んだまなざしで僕を舐めるように眺めた。「お兄さん良い男ね」
「あまりそう言う人はいないな」
「私は好きよ」躑躅はシンプルに好意を伝えた。幽霊に好かれるとどうなるんだろう。乗り移られてついて来られるのだろうか? 若干心配になる。
「躑躅は祟るの?」
躑躅は目を細めてにぃっと笑うと答える。「男の人は大事にするわ。気持ちが良いもの。女は呪う。取り憑いて子どもを産ませるように仕向けて、赤子の魂を乗っ取って躑躅が生まれ変われるようにするの。そして母親になった女を子どもとして一生不幸にしてやる」
躑躅は悪霊だな、と僕は思った。
「でも生まれ変わりたいのなら、綺麗で優しい人を選ぶんでしょ?」
躑躅は首を振る。「この海に死ににくる弱い女を捕まえる。捕まえて死ぬのが怖くさせるのは簡単。死後の世界の恐ろしい幻を鮮やかに見せてやればいい。そして子どもを産まなくては生きていけない妄想を頭に取り憑かせればいい。相手の男は女を孕ませてくれれば誰でもいい。女が男を求めるように女の頭に憑依して操る。生まれ変わるなら美しくなくても構わない。肉体がちゃんとあればいい。美しいのは男に利用されてないがしろにされる苦しいことだから」
「躑躅は過酷な人生を送ったんだね」それが彼女の悪意に満ちた魂の原因なんだろう。
「今度は愛が欲しいわ。ねぇお兄さん。愛を頂戴」
「愛ってなんだろう?」
「躑躅の愛はねぇ……。ねぇ、躑躅はお兄さんの身体が欲しいわ」
「乗っ取るの?」
「いいえ、交わるのよ」躑躅は僕の上に覆いかぶさって押し倒した。その情景はどこかアンリ・ルソーの「眠るジプシー女」に似ていた。満月の下の砂漠にいるライオンと女の絵。「懐中電灯は消すわよ。行為の姿が明るい光に晒されると、そのイメージは心の世界に張り付けられて恥になるから。月明りの秘め事にしましょう。あと、口で咥える快楽は求めないで。日本の伝統の目が貞淑さを求めて、後々心を苦しめるから」
「僕には好きな人がいるから、君とは重なれない」僕は言う。大水青の姿を思う。
「あなただって魂に過ぎないじゃない。ここは想像の世界なのよ。自由になりなさいよ」躑躅は僕の身に付けた服を脱がす。僕の身体は金縛りで動かない。
「たとえ心の中でも、愛している人以外と交わることを考えたら、愛している人への裏切りになるんだ」僕は冷めた声で言う。「身体だけ求めて、心の伴わない行為は虚しいだけだと思うよ」
躑躅は手を止めない。「あなたには分かっていないわ。これは必然なのよ」僕ら2人は裸身になって、月明りの砂丘に横たわった。強い風は晒された皮膚に砂を吹き付けた。
躑躅の白い肉体は、金縛りで動けない僕の身体の上に重みを与えた。幽霊だけれども滑らかな肌の感触と体温と身体の重みがちゃんとある。躑躅は僕の唇に口づけをしたが、その吸いつくような透明な味わいのキスは、僕の心に不穏なざわつきを与えた。躑躅は僕の身体をいとおしむように愛撫しては、夜闇で見えない砂っぽい肌の上に、口づけによる温もりを与えていった。やがて躑躅の肉体は僕を包みこんだ。ゆっくりと揺さぶられる彼女の腰は、僕の理性を奪った。湧き上がる暴力的に彼女をめちゃくちゃにしてやりたい荒々しい衝動は、金縛りで封印された。僕は彼女の中で解き放たれた。海の波の音が聞こえ、潮の香りが風に乗って届く。潮の満ち引きと身体のリズムが呼応するかのように、僕は海との共鳴を感じた。躑躅は僕の身体から降りる時、悲しげな表情をした。
「本当はね、欲しいのは心なのよ」ゆっくりと身体を離すと「また逢いましょうね」とささやき、風に薄れて消えていった。青白い月の光の中で見えた彼女の潤んだ眼差しは、僕の心に焼きついた。躑躅が消えると、僕の身体は金縛りから解放されて自由になっていた。服を身につけると、僕はまた寝そべって夜の星を眺めた。
夜が明け朝の光が空を青からオレンジに変わるグラデーションに染める頃、僕は地図に書かれた図書館を探し始めた。サンダルを脱いで、足が砂に深々と埋もれるに任せた。砂の世界を数時間彷徨い歩く。急な斜面に足を取られ、海に滑り落ちるのではないかとひやひやすることもあった。諦めずに探し歩くと、力強い風が吹いてきて、砂の中に何かが埋まっているのが見えてきた。更に風が砂丘を吹き飛ばしていくと、巨大な卵型の図書館が砂の中から現れた。全体が硝子張りの鳥籠のような不思議な図書館で、地図に書かれた籠のような図と一致する。朝の光の中、僕は図書館の中に入った。
入り口の説明によると、この図書館で扱っている本は全て人間の魂であり、本の作者の人生という物語が封じられているのだという。表紙は魂の色で、本は羽ばたいて図書館内の好きな場所に住みついたり、あてもなく飛び回っていたりするらしい。飛行中の本を捉えるための網が貸し出されていた。図書の館外貸し出しについては一人五冊という制限があり、二週間後に返却する決まりになっている。閲覧室でじっくりと読書をすることもできる。
図書館内ではなるほど、本が飛んでいた。常に本棚から出入りしている。背表紙を上にして、ハードカバーを羽にして飛んでいる本もいれば、真ん中のページから開いて、紙の束をわしわしと動かしながら飛んでいる文庫本もいた。硝子の巨大な鳥籠の中を、何百という本の鳥たちが飛び回っているようだ。上空を見上げるとドーム状の天井から日差しとすっきりとした青空が見え、それを背景に本たちがたくさん飛び回っていて圧巻だった。
僕の目の前の棚の片隅にもじもじとしている文庫本がいて、読んで欲しそうに思えたので手に取ってみた。白く微細な煌めきのある表紙に、一粒の青い宝石が小さく印刷されている。タイトルは「耳」と書かれていた。
「耳」は悲しい話だった。主人公の女性は耳に青みを帯びたダイヤモンドのようなピアスをしているが、その石は亡くなった夫の遺骨から作られた人工宝石である。夫を亡くした自動車事故には主人公も巻き込まれており、彼女の右足には二十センチ程の深い傷跡が残っている。事故で夫は車から窓を突き破って外に飛び出しており、即死だった。雪の積もった坂道での衝突事故で、事故当時現場は路面凍結していた。夫の運転する車はワカサギ釣りのために冬山の湖に向かう途中だった。彼女が助手席に乗った状態で夫の運転する車が下り坂でスリップし、対向車に激突した。相手の車は女性が一人で運転しており、その女性は事故により大けがを負い、搬送先の病院で数日の延命処置の後死亡した。死んだ女性の夫への賠償金は、主人公の夫の生命保険から支払われた。大事な伴侶を事故で亡くした主人公は苦しみ悩み、過酷な精神状態に追い込まれる。耳につけた遺骨の人工宝石は死んだはずの夫の声を絶えず彼女の耳に届ける。そのあるはずのない死者のささやく声を聞きながら、彼女は少しずつ生きる力を取り戻していく。声を聞くことが彼女を支えた。その主人公は新婚旅行で行ったハワイの青い海と白い砂を背景に撮影した夫婦写真を大事に家に飾っている。夫婦の間に子どもはいなかった。夫はアルビノの色素を持たない人だったので、おそらく生殖能力に問題があったのだろうと思われる。物語は彼女の夫との大切な思い出を語ることによって進められていく。込められた愛の深さに胸が打たれる。
僕が閲覧席に座って「耳」を読んでいる間、数冊の本が僕の様子を見に来た。中には肩をつついたり、顔を覗き込んで首を傾げていくような素振りをする本もいた。おそらく「僕も読んでみない?」というお誘いとアピールなのだろう。少し離れた本棚では、本同士の熾烈な場所取り争いが勃発していた。相手のしおり紐を引っ張ったり、ハードカバーの角を相手に突き出して突進したり、相手をページで挟んだりしてバタバタしていた。本が傷つくのを止めるため、図書館員さんがやってきて喧嘩を仲裁していた。
この図書館で鬼の角を取るための情報や助けが見つかるのだとしたらどうしたらいいのだろう、と膨大な本の群れを見て不安になった。僕は本棚から気になった本を数冊取ると、また閲覧席に戻った。
パラパラと読んだ中で印象に残ったのは、王に仕える軍人の話だった。幼少時は湖畔の村で小石を集めて村の模型を作るのが好きな少年だったが、ある時大雨による大洪水で村は湖に沈んでしまい、移住しなければならない運命にあった。各地を彷徨う内に身体能力を買われて軍隊に入り、戦争で名誉を得ると、その国の王を守る役目の兵隊に抜擢される。ヨーロッパの国同士の戦争が巻き起こる中で、常に王の身を守るために、つるぎを抜いて戦ってきた。幼い少年の日に洪水で生き別れた妹のことを思い続けており、妹の面影を探し女性を見るうちに、妹と気立てが似た優しい娘と知り合い結ばれ子を成す。妻はピアノが上手い上流階級の娘だったが、王室付きの軍人ということで、生まれの貧しさには目をつぶり、結婚が許可される。感情の波は激しく私生活では妻に思わずどなることもあるが、生まれた息子を大切に思い、一緒にチェスで遊んであげたりする。戦の最中に肺を突き刺され、出血多量で亡くなる。息子がまだやっと十歳になったばかりの時だった。亡骸は生まれ故郷の湖の畔に埋められ、妻と息子はよく湖を訪れ、墓に花を供える。湖には血のように赤い睡蓮の花がよく咲き、湖面は輝く。本の表紙にはその湖と睡蓮が描かれていた。僕は、不運な生い立ちから自らの力によって納得のいく人生を獲得していく、主人公の強靭な精神力に憧れた。自分自身のものとは違った人生の形、生命の燃やし方を見たような気がした。
また、太陽と月の象徴性について研究した学者の本も面白かった。太陽は地球から見える空の世界の最も大きな光だ。世界中の神話で神格化されている。太陽が天の国の力の源であり、神の光だという捉え方は世界に普遍的だ。エジプトの太陽神や、日本古代の神話の女性神であるアマテラスオオミカミの存在が代表的だ。熱の源であることから生命力・情熱・若さを象徴し、光の源であることから啓蒙を意味するという。月は満ち欠けにより誕生・死・再生を想起させることが多い。潮の干満と夢を司る。また、満月は人間の狂気を引き起こすとされる。太陽と同じく世界各地で神と関連付けられ信仰されている。
手がかりが得られないので僕は途方に暮れ、この図書館でどうしたらいいか悩んだ。貸し出しカウンターにいる司書さんに
「この鬼の角を取るための情報を探しにこの図書館に来たのですが、手がかりになる本はどちらにありますか?」と質問した。司書さんは首をかしげた。
「あぁ、初めてこちらにいらっしゃった方ですね。本を一冊お借りになって外に出られると分かると思います。こちらが今月のお勧めの本となっております」
と言い、丁寧にお勧め図書のコーナーに案内してくれた。司書さんは
「ここの図書館の本は人の魂ですから、外の世界に出た時に案内して導いてくれるんですよ。あなたのお悩みもきっと本に宿る魂に聞けば解決の手がかりが得られると思います」と言った。
僕は彼女にお礼を言うと、その展示棚をよく見た。気になる本が一冊あった。和風の装丁で十二単のように蘇芳と萌黄色の重なった表紙の古そうな本だった。僕はその場でパラパラと中身を読んでみる。やがて引き込まれて、椅子に腰かけてじっくりと読み入った。
置き屋で働く遊女の一生が書かれた話だった。貧困の村に生まれ、両親が食いつなぐためのお金を得るため、十歳の時に人買いに売られた。顔立ちが整った美しい少女だったので置き屋に売られて、下働きを数年続けた後遊女になった。下働きの時から遊女の仕事の苦しく壮絶な現実を見ていたが、それでも遊女として働き出すと身を売る毎日に憂いを感じ、避妊により子どもを産む機能を失ったことへの心の苦しみに耐えられなくなり、死を願ってお客の男と逃げ出す計画を立てる。どんなに身体が熱く燃え上がっても、どんなに相手を愛しても、自分の愛は決して実ることがないのだと突きつけられて、悶絶するくらいもどかしい衝動と身体の疼きで死ぬほど悩まされる夜も彼女にはよくあった。とても恥ずかしく耐えられなかった。女として子どもを産む相手を求める自然な衝動が、遊女の肉体を叶わぬ疼きで脅かし、思考を絶えず死に追いやっていった。自分の愛した人との間に新たな命を授かりたい、子どもを産みたいという強い願望が、実際には身体の問題で子どもを産むことは自分には有り得ないのだという現実的な思考を押し潰して、彼女の心を激しく乱した。夜明けの晩に遊女と男は定められた部屋を抜け出して、檻に閉じ込められたような人生から逃げ出すために海を目指す。どんなに遠くまで逃げても、心の世界では常に人に追われているような不安を彼女は感じる。人生の最後に砂の上で遊女と男は激しく求め合った後、冷たい海に入り波にもまれて溺れ死んだ。
遊女の人生は救いのないもののように思えるが、遊女としての日々や人生最後の男との交わりの描写は、濃密かつ情熱的な官能性に満ちていた。仕事上の汚れや、暴力の痛みや、客の男の醜さへの嫌悪や、かけられる悪意ある言葉による心の荒みの絶えない日々の中で、彼女が性の快楽には人生の喜びを見出していたことに気付かされる。我を忘れられる昇りつめた瞬間に対する彼女の没頭は、読んでいて嫌悪するものではなくある種の救いさえも感じられる。暗闇の中の人生において生の輝きがその一瞬には彼女に訪れていたのだ。だから過激ではあるが、それを否定してしまえば彼女の命の在り方を否定してしまうことになる。彼女には人生を選ぶ余地がなかったし、それは善悪を超えた不幸で物悲しい定めだったのだ。妻のある男を愛しすぎたあまり、共に死ぬことによって男を自分自身のものにして独占してしまいたいという遊女の望みは、あるいは悪意ある妬みだったのかもしれない。子どもの産めない自分自身の負い目から、現実には彼女には手に入らない、子どもを産める相手のいる生活への憧れと、男の妻への嫉妬だったのかも知れない。それでもその遊女が妻から男を奪い取った悪人として死んでいったのは、悲しい運命が避けがたくそうさせたものだったのだろう。
また、彼女は遊女ならではの華やかで美しく設えられた、視覚世界の中で生きていた。光に透ける鼈甲の櫛の煌めき、細密な銀のかんざし、部屋に飾られた一輪の桔梗の花。螺鈿細工の鏡に、白粉を塗って着物を身に付けた己の美しい姿を見た時の陶酔感。美と快楽が彼女の人生の価値の全てだった。そういう耽美かつ官能的な物語だった。僕は読んでいて躑躅を思い出して不安になった。もしかしたらこの本の遊女は彼女ではないだろうか。
僕はその本の貸し出し手続きを済ませて図書館を出た。海辺に行き借りた本を開くと、本から透明な光る気体が溢れ出してきて、目の前に昨夜出会った躑躅が現れた。
「やっぱり君だったんだね」僕は悲しさを感じながら本の魂を見つめて語りかける。
「あなたなら見つけてくれると思っていた」躑躅の表情は切なげだった。
浜辺に座って海を眺めながら、僕は躑躅と話をした。僕は躑躅の魂の宿る本の感想を彼女に伝え、彼女はぽつぽつといくつかのエピソードの補足を話した。
「お店で働き始めた頃は、男に身を委ねて抱かれることは、快楽ではなかったのよ。お客さんによって乱暴に扱う人もいれば、丁寧に愛撫してくれる人もいて差はあったけれども、それでも絶頂感の快楽なんて、思春期に一人で辿りついたものとそうは変わらなかった。男が私の中に入ってくることに特に喜びは感じなかったわ。無感覚な中で悦びの演技をして、次々と男の相手をしていた。肌の温もりや私の身体を抱く腕の優しさが心地よいことも時にはあったけれど、頭が真っ白になって痺れるような快感は、訪れたとしても一瞬だけのものだった。だから私は性の喜びに対しては醒めた目で見ていたの」
「なるほど」
「その考えを変えてくれたのが、私が一緒に死にに行った男の存在だった。彼は私に愛の幸福を教えてくれた。それは肉体的な快楽から離れた、心の世界の好意による繋がりによる幸福感で、身を委ね相手に心を許すという好意の心が伴って初めて、女性は本当に満たされるという気付きがその時にあったわ。心を許し身を委ねると、燃え上がるように身体が反応するようになった。彼が帰っても身体の奥の疼きは消えなくて、夜眠る時まで彼の感覚の名残で花芯が潤い、肌が火照って汗ばんで、彼を求める気持ちが狂おしくて眠れなくなった」
「その男とは心中したんだろ?」
「そこは詳しく語ると違うのよね。そのことについてこれからお話するわ」
「ありがとう」
「私がその男と出会ったのはとあるお屋敷だった。入り口から屋敷に入ると、ぱっと桃色の明るい行燈の光が照らして、一面鏡張りの壁面に水が流れているの。流水の流れ着く先には一本の梅の木があったわ。照らし出された咲き誇る紅梅は、花びらをちらちらと散らし、赤い点を流水の上に漂わせていた。屋敷は回廊式に三階上まで伸びており、見上げるとそこにも梅の枝が見えるの。紅白梅の花びらが天上からひらりひらりと、照らし出された梅の木の上を彩る様は趣があったわ。私は薄暗い部屋の奥に暖かな橙色の灯火を点けてその男を待った。灯火に浮かび上がる遊女の私は、梅色の着物に金の帯、花のかんざし、果肉の唇」
「艶やかな雰囲気だね」僕は躑躅のかつての姿を目の裏に浮かべた。
「上客だったから最上のもてなしを求められていたのよ。そのために用意された御屋敷と部屋だったわ」
「なるほど」
「初めてその男と会った時、目が底なしに暗く奥深い印象があったわ。見つめられるとその闇に引き込まれていくような気持ちになった。その男は私を優しく丁寧に扱ってくれたし、彼の悩みや苦しみの奥深いところを語ってくれた。夫婦仲が上手くいっていないというありふれた話だったけれども、そこにあった彼の心の苦しみは切実な本物だった。話す内に自然とその男に惹かれていったわ。私自身の苦しみについての話もよく聞いてくれた。苦しみを共有することで、お互いに打ち解けられたという気がしたの。彼は週に一日は私を呼ぶようになり、次第に私と彼は親密になり、お互いを必要とする仲になっていった」躑躅は語る。
「2人でいる時ってどんな感じだった?」
躑躅は思い出すようにして語り始める。
「彼は私のところに来る時に、ちょっと疲れた顔なんだけれど、顔全体に私に会えて嬉しい気持ちを滲ませて、目がきらきらと輝くの。そして『どうも躑躅さん、またお会い出来て嬉しいです。御調子はいかがですか?』と丁寧に聞いてくれるの。社会の底で生きる弱者である遊女を、ちゃんと一人の人間と見てくれる、私の存在を尊重してくれる。そのことが嬉しくて、私は梅色の着物で立ち上がって、彼の目の前にそっと立って、『私も貴方にまたお会い出来て最高の気分。ずっとお慕いしながらお待ちしていましたよ』と紅をさした唇で微笑んで、彼の肩にそっと手を添えて胸にしなだれかかるの。彼は私を優しく抱きとめてくれて、じっと私の目の奥を見つめてから、そっと唇に接吻をする。彼の口に少し紅が付くので、私はそれを舐めてとるのよ。」
「丁寧で親密な人だね」
「行為をする前と後に私と彼は長く話すのよ。前には最近の悩みや出来事、後は親密に愛について語り合ったわ。平安時代の光源氏じゃないけれども、毎回私たちは愛の歌を交わした。墨を磨って、筆に浸して歌を詠む。彼の少し掠れた声が古書を思わせて、好きでいつもうっとりと聞いていた。彼がくれた歌は全部寄木細工の箱に鍵をかけて仕舞って、夜寝る前に良く読み返すの。彼の言葉は鮮やかなイメージ世界を思い起こさせるので、彼の文字に浸ってから眠ると色の綺麗な素敵な夢が見れるのよ。人から浴びる悪意に夢の中で惑わされがちな私にとっては、彼の言葉は心のよりどころであり救いだった。彼の言葉に感じてしまって涙を流す夜もあったわ」
「躑躅は当時どんな悩みを抱えていて、何を彼に話したの?」
「仕事柄子どもを産まないような身体にしていたのだけれども、そのことが心の中で過酷な程責められていて、自分の意志とは関わりなく心が常に苦しくなっていたの。何をしていても常に頭の中に死がちらついて離れなかった。明るい心で生きているように見える人が妬ましくて、人間は全員死にたい気持ちで日々を過ごすべきだと思っていた。どろどろとした呪詛の心で、人生を楽しんでいるように見える他人を妬んでいた。本当に死にたい気持ちが日々続いていて、あらゆる人から軽蔑されているような気がして、常に疑心暗鬼になっていたわ。それこそ現実の人間関係を見失いそうなくらいに。そういう苦しい時に出会ったからこそ、その男の示してくれる愛情が私にとっての救いになっていたの。でも本当は私が惹かれていったのは、その男の死の匂いだったのかもしれない」
「死の匂い」
「その男は最初に会った時からいつも、死にたいと口にしていたし、その死にたいという感情は彼を取り巻く空気の中にも濃く感じられていたの。私は良い香りの虜になるようにして、それに夢中になったのかもしれない。私自身がその死にたい気持ちに強く共感したから」躑躅は底の知れない暗い目をして言う。
「そうか」
「私たちは一緒に死ぬために御屋敷を抜け出して、砂丘の海に向かった。死ぬ前の最後にと、砂の上に着物を広げて男と私は交わった。私は強くその男を愛し求め、男も私を熱を込めて愛した。死を直前にして燃え上がる本能と溢れ出す気持ちが私と彼を快楽の頂点に押し上げていった。汗が絡み合い肉体の境界線が溶けて一つになった。彼が私の中を突き上げる度に私はのけぞり喘いだ。誰も他に居ない赤い月夜の晩に。彼と愛し合っている間、心の後ろめたさも悩みもどこかに去って、ただ目の前の彼のことで頭が一杯になり、絶頂の瞬間はこの世の全てが消えて、ただ幸福だけで魂が満たされていた。私は彼の存在を妻なる女から完全に奪い取って手に入れたと思ったわ。その後で私たちは小さな木の舟に二人乗りこんで、赤い月に照らされながら、ただ死ぬために沖を目指して海に漕ぎ出した」
「僕との月夜の交わりは、その時の再現のようなものだったのかな」
「そうね、私の魂はその記憶に執着していてこの地に縛り付けられていたから」躑躅は話を続ける。
「木の小舟が沖に乗り出し陸地がはるか遠くに見えるまでになった頃、男は急に苦しみ出し青ざめて悩み始めた。そうして『自分一人で死に向き合いたい、おまえは邪魔だ、先に死ね』と言って私を冷たい海の水に突き落とした。男から突き離され裏切られたショックで何が何だか分からないまま波にもまれ、私は暗く蒼い水の中でもがき苦しみ息絶えた。本当には心を愛されぬまま、一人で死んでいった。死ぬ間際は私を選んで魂共に逝ってくれない男と、男がおそらくその存在を考え悩んだであろう、顔も知らないその妻の存在を恨んだ」
僕は話を聞いて本当に躑躅を不憫に思った。「可哀そうに」
「そういうことだったから、本当のところは心中とは言えないのよ」
「分かった」僕は答える。
躑躅は置き屋でよく歌ったというかごめかごめを披露してくれた。
「かごめかごめ
籠の中の鳥は
いついつ出やる
夜明けの晩に
鶴と亀が滑った
後ろの正面だあれ?」
彼女の甘美な歌声が潮風に乗り、波が砕けた。
しばらくして躑躅の方から僕に質問をしてきた。「何か私に出来ることはある?」
僕は額に生えた角を取るためにこの図書館を探しにきたという話をした。「鬼の角を取る方法の手がかりはないだろうか?」
躑躅は答えた。「地獄で鬼になったのなら、手がかりは天の国にある。私は死者の国にいるから力を貸せるかもしれない」躑躅の魂はみるみるうちに膨らみ、大きな光る鳥へと姿を変えた。僕はその鳥の背に乗って、空高く舞い上がった。
四、
燦然と降り注ぐ太陽の光を身に受けながら、僕らはスカイブルーの風を切って、天の高みを目指して飛んでいった。日の光で暖まった空気の、生き物の吐息のような生々しい感触が、僕の顔を撫でていく。僕の目には見えないけれども、天空の世界には時々清められたような神々しい気配がある。もしかすると様々な神様の領域を、僕らは通り抜けて飛んでいるのかも知れない。気圧の変化で耳が詰まったような状態になった。脳に清々しい新鮮な空気が巡る。頭が高速で回転しているように冴えてきて、脳内に力強いエネルギーが満ちた。様々な思念に心責められて失った自信が、急速に取り戻せたような気がした。僕の心は力に満ちてきた。心の苦しみに囚われてよく見えなくなっていたまわりの風景も、まるで目を覆っていた膜が取れたかのように、鮮やかに視界に飛び込んでくる。グラデーションの鮮やかな青の世界が果てしなく広がり、見下ろすと地上がはるか下に広がっていた。あの広大な砂丘がここからはあんなにも小さく見える。空を飛ぶ鳥の目から世界を見下ろすと、一人の人間の心が抱える悩みはちっぽけなものだと気付かされる。狭い地獄で苦しみもがいていた時の自分に、この自由な視点を教えてあげたい気持ちになった。世界は本当に広いのだ。鳥になった躑躅の光の翼は大きく羽ばたいて、ぐんぐん飛んでいった。
空の上の雲の世界に辿り着くと、躑躅は「夢見の羊」の画廊に向かった。画廊は光を固めて作ったような、透明な硝子細工で出来ていた。壁は色とりどりの硝子の糸で編まれたように煌めき、薄く太陽の光を透かしていた。画廊に天井はなく、色彩を変える長い硝子細工の壁が、はるか遠くまで続いているようだった。その天井のない幅広い通路の入り口には、夢見の羊についての説明書きがあった。貫禄のあるひげ男の自画像も飾られている。画家の夢見の羊はもう死んで存在しないが、その絵の中に鮮やかな感情と強い魂のエネルギーを残して、作品の中で彼は生き続けている。夢見の羊が絵に描くのは、様々な人々が抱えるイメージの世界だ。他の人が頭の中に思い浮かべるイメージの世界に、夢見の羊はアクセスしてそれを絵にして描く。彼の絵を見ていると人々の心の在り方の多様さに驚かされる。僕と躑躅は左右の壁に無数の絵が掛けられた、夢見の羊の画廊を見て回った。躑躅は
「この画廊に手がかりがあると思う。これだと思ったら懸命に絵の世界に浸って、作者の声に耳を傾けてみるといいわよ」と人間の姿に戻って言った。
僕は「顔のある迷宮」と「神と出会う場所」という絵が気に入り、躑躅は「雨樽」と「ギターと日の光」という絵が好きだと言った。
僕の気に入った「顔のある迷宮」の絵は入り組んだ迷路の全体像を描いた古い絵地図だった。迷路の全体が不気味な顔に見える。罪人が鞭打たれた後この迷宮に放り出されたという。彼らは非常に危険な領域に、粗末な武器を携えて踏み込んでいくことになる。大蛇に飲み込まれたり、巨大な歯車に潰されたりといった彼らの末路が記されている。生き延びるためにはひたすら彷徨わなければならない。罪人は不安と絶望の内に虚空の神に祈る。この地図は罪人の地獄のような心の苦しみのメタファーを表現したものかもしれない、と僕は白の狸が引き起こした地獄巡りの過酷さを思い出して考えた。
またもう一つの絵である「神と出会う場所」に描かれたのは、地下洞窟で古代のシャーマンが炎を燃やしながら目を見開いて、神との共鳴を行っているところだ。シャーマンは老女であり、周囲には生贄に捧げられた者の髑髏が転がっている。洞窟の外には天空にあまたの星が散りばめられているのが見える。大地の精霊が頭髪を剃り落とした老女に宿り、今人間にお告げをせんとするようである。僕はこの絵を見ながらまた白の狸のことを思い出していた。僕は改めて自分の心の動きを見ると、白の狸を強く憎んでいるのか、その影響力を畏怖しているのか自分でもよく分からなくなった。心の世界のやり取りで瞬間的に赦しの気持ちを持ったこともあったけれども、彼によってもたらされた苦悩と心の痛みもまた僕にとっての真実だった。絵を眺めていると、心の奥に隠されたそうした本当の気持ちに光が当たって、自分の思いが見えてくるかのようだった。
躑躅が気に入った「雨樽」という絵で表現されているのは、雨水が屋根から流れ落ち、水樽へと流れ込んでいく様子だ。それは滝のようにも見える。血液が絶え間なく身体を流れ続けるように、その透明な雨水も氷が張る程に冷たい流れを滞らせることもなく、ひたすら蓄積されていく。やがて樽から水が溢れるまでそれは続くのだろう。夜が来て全ての明かりが消え、水の音のみが聞こえるようになっても、その密かな営みは続いていく。躑躅は「流れる水の表現が本物みたいに繊細で綺麗。私の目に見える現実以上に美しいかもしれない」と言った。僕は躑躅が死んでいった海水の冷たさをその絵を見て思った。
そして「ギターと日の光」は木版画で緻密に表現された静物画だ。描かれたギターへの持ち主の愛着や、それまでその楽器で繰り返し奏でられたであろう、軽快な楽曲を思わせる。楽しげな色彩が、見る者の心を穏やかにする。六月の朝の清らかな白い光と輝きが、画面に幻のような明るさを与えている。朝の新鮮な空気の中で、自分によく馴染んだギターを見つめる、持ち主のくつろいだ心が伝わってくるかのようである。
「私は御座敷でお琴をひいていたのだけれど、この楽器を見て演奏が懐かしくなったわ」と躑躅が語る。好きになって選ぶ絵には、選んだ人それぞれの内面が関わっているみたいだ。
僕らはそれらの絵にじっくりと時間をかけて見入った。それらの絵が理解できるような気もしたし、見るだけでは作者の心までは分からないような気もした。何回か通路を行き来して数多くの絵がかけられた画廊の全体を見回しているうちに、ある小さな絵の前で僕は強い既視感を覚えた。どこかでこの風景を知っているような気がする。
「この絵に何かあるような気がする」僕は躑躅に言った。彼女は頷いた。
「良く絵を見て、手がかりがあるといいわね」
僕はその絵の中に、光の森の中にあった小さな泉を見た。その清らかな泉の水面に、夜明けの朝日が映っている。その時僕の頭の中に、声にならない言葉がささやかれた。『朝日と共に自分の姿を、森の清らかな泉の水面に映しなさい』
「後ろの正面……」僕は躑躅が口ずさんでいたかごめかごめの歌詞を思わず口にした。頭には地図に書かれた籠の中の鳥の絵があった。自分が無意識に集めてきた様々な要素が、頭の中で繋がるような気がした。
「もしかすると、水鏡に姿を映すことが手掛かりなのかもしれない」
「どうしてそう思うの?」躑躅が尋ねる。
「今、夢見の羊の声を聞いたような気がしたんだ『朝日と共に自分の姿を、森の清らかな泉の水面に映しなさい』とね」僕は答える。
「後ろの正面って?」
「さっき躑躅が歌っていたかごめかごめの歌詞の『後ろの正面』という言葉だけれど、自分の後ろに在る太陽の光を、水鏡に映せば自分の正面に見ることが出来るとひらめいたんだ。それに太陽は地球から見える天の国の最も大きな光だ。世界中の神話でよく神格化されている。君は『地獄で鬼になったのなら、手がかりは天の国にある』と言った。太陽が天の国の力の源のように思える。地獄の鬼の角が生えた僕を変えてくれるのは、神格化された神の光、太陽の力だという気がするんだ」僕は図書館で読んだ、太陽の象徴性について思い出していた。
「信じてみるの? 声なき声を」
「信じてみようと思う」僕は頷いた。躑躅は再び鳥の姿に変身し、僕を背に乗せて地上へと降りていった。風の流れに身を任せて図書館にたどり着くと、僕は躑躅にありがとうと言って抱きしめて、図書館に本を返却して彼女と別れた。躑躅を思わず抱きしめたのは、彼女の生い立ちを色々と知って愛おしくなったからかもしれない。僕はまた電車に乗り、一日がかりで家に帰った。
眠りと目覚めの境目にある、意識を保った長い幻想の中から身を起こすと、僕は服を着替えて深夜二時に紺色の愛車に乗り込んだ。高速道路で車を飛ばし、途中サービスエリアで珈琲を飲んで、光の森がある山へと向かった。
夜明け前の森を懐中電灯で照らしながら進むと、以前見つけた泉に辿りついた。暗い樹影に覆われた森では、ほぅほぅとフクロウが鳴いている。僕は泉の脇にある岩に腰かけると、砂丘を巡る幻想を思い返していた。遊女の躑躅の存在や、賑やかな飛ぶ本の群れや、雲の画廊で眺めた絵や、砂丘の海と星空の光景が頭に繰り返し思い出される。
やがて暗い空の端が白み始め、遠くに山脈のシルエットが浮かび上がり、太陽がその山際から少しずつ顔を覗かせる。僕は泉の水面がその光を捉える瞬間を、まだ暗い水面を覗き込みながら待つ。静かな中に泉の湧水が立てる水音がにわかに強くなったような気がした。僕が向き合った泉の水鏡に、少しずつ光が差し込み、僕の姿も映りこみ始める。そして次第に黄金の光に包まれ出す世界の中で、クロード・モネの絵のように、赤い日の出がはっきりと泉に映った。
赤い光が僕の目を眩ませ、泉全体に鮮やかな光が満ちた。僕は背後に昇る太陽の光を目の前に見た。その強い光は僕を照らし出した。黄金色に満ちた照り返す水面の真ん中にはしっかりと僕がいた。僕は輝きの世界の中に生きていた。
ふと僕は白の狸に教えられた心の中でくるりと後ろを向く方法を、「後ろの正面」というかごめかごめの歌詞に引きつけて考えた。そして現実には泉に向かいながら、心の世界で後ろ向きになり、背後の太陽に向き合った。僕の心は光のただ中に入った。その一瞬僕の脳は雑念を忘れて、全ての生命の源の神を意識した。もし太陽がなければこの世界、生命は今の形で存在しえない。太陽の光で光合成をして生きる植物が生育出来なければ、それを食べて生きる動物も人間もいなかっただろう。生態系の食物連鎖のピラミッドは、太陽があるがゆえに今の形に成立し、保たれているのだ。また地球という星は太陽の重力の影響によって公転する惑星である。太陽なしにはそもそも地球が存在しない。地球の気温や海洋などの環境は太陽からの距離によって成り立っている。昼と夜の存在も季節の存在も、またこの太陽光によって成る。命の根源としての太陽が、直接に僕の身体を、生命を照らしている。それはなんと当たり前の日常的なことであり、また奇跡的なことであるのだろうか。
太陽光線を浴びた後、僕は額に手をやった。鬼の角は消えてなくなっていた。泉の水面に風が渡って、僕の姿と金の光は揺れて混じり合った。
その日の夜に僕は久しぶりに聞き耳うさぎの酒場に顔を出す。鬼の角が生えて以来足を運んでいなかったのだ。店に行くと運良く大水青もいた。彼女は壁の大きな星空の天球図を眺めつつ、飾りに置かれている透明なクリスタルと紫水晶とローズクォーツの小さな結晶のいくつかを、カウンターの上で並べ変えていた。カクテルグラスは空になり、底に僅かな青い液体が残っているのが見えた。
「あら、猫さん」大水青は僕に気付いて手を上げる。そしてじっと僕の額を見つめる。「鬼の角、取れて良かったわね」そして微笑む。
僕は大水青に、泉の脇で偶然見つけた四つ葉のクローバーをプレゼントする。
「良かったらどうぞ」
大水青は嬉しそうにする「どうもありがとう。幸運をもたらすクローバーね。どこで見つけたの?」
「夢の中でお告げがあって、とある泉に行ったんだ。そこで見つけたんだよ」僕は答える。大水青は、『ちょっと変わった人みたいね』という表情で僕を見たけれども、笑みを作った。
聞き耳うさぎは、光の森の事件について気にしていて尋ねてきた。白の狸のことはかなり大々的に報道しているメディアもあったようだ。
「洞窟内の白骨化した三人の遺体ですが、身元が分かったそうです。ピクニック中に行方不明になった高齢の男性と、休学中の美大生の女性、職場に現れなくなったコンビニのフリーター男性の三人でした。警察の取り調べによると、容疑者のTは殺人をした訳ではなく、Tが原因で引き起こされた瞑想状態から三人の被害者は現実に戻って来られなくなって、話すことも動くことも出来ない人形のような状態に陥り衰弱死していったようです。動けなくなる程の精神的な苦しみの状態が人為的に引き起こせてしまうというのはとても怖いことですね。」
僕は聞き耳うさぎが語る、光の森の洞窟死体遺棄事件の細かな情報を聞きながら、メニューを眺めてカクテルを選ぶ。
「スター・サファイアを一つ」僕は注文する。
「奇遇ですね。先ほど大水青さんも同じものを飲まれていたのですよ」聞き耳うさぎは言う。
「美味しかったわよ」大水青はそう言って、また新しくモスコミュールを注文する。
スター・サファイアのカクテルは濃い青の液体で、かすかに紫がかった神秘的な色合いだった。その香りはラベンダーのように安らぎを与えてくれる。夕暮れ時にできる青い影のように、液体は揺らめき、見る角度によって色を変化させた。僕は薄く光るグラスのふちに口をつける。
「このカクテルの由来は何ですか」一口飲んでから僕は尋ねる。
「妻の誕生石がサファイアで、婚約指輪がスター・サファイアのリングだったんですよ。その石がこのカクテルのモチーフです。彼女は天体観測が好きで、私とは星仲間として彗星の観測を通じて出会ったもので、その意味を込めて星の宿った石を選びました」聞き耳うさぎは答える。
「確か奥さんを早くに交通事故で亡くされたとお聞きしました」僕は思い出して言う。
「彼女とは十年以上共に生きました。亡くしたのは妻が四十六歳の時です。彼女は雪の積もった山に天文台での天体観測の準備で出かけ、坂道でスリップした対向車に激突され、その事故の怪我が元で死にました」
僕はそれを聞いて、図書館で読んだ「耳」を思い出した。偶然に現実と本がリンクしている。
「それはさぞお辛かったでしょうね」大水青が言う。
「お互いに四六時中心の中ですれ違い、夫婦喧嘩などもやりましたが、それでも彼女を看取ったあの病室の日々程に人間を愛おしく思い、儚い命をかけがえのないものと感じ、他者のために強く祈ったことは、私の人生に他にありませんでした」
「なるほど」僕は頷いて聞く。
「彼女の言葉で心に残っているものがあります。ぼろぼろに身体が傷ついた妻と共に過ごす最期の日々の中で、僕が思わず『君なしでは僕はこの先、生きていけないんだ』という言葉を言ってしまったことがあったのです。その時に彼女は星の世界の果てしない時間の話をしました。『宇宙が存在している果てしなく長い時間、あの星が誕生してから今現在に至るまでの長い歴史を思えば、一人の人間が生きられる時間がいかに短いか分かるでしょう。運命の許す限り生きなさい。辛かったら星々の長い時間のことを考えて耐えなさい。あなたにはまだ出来ることがあるから』そう妻に言われました。以来長く生きてきましたが、妻のその言葉に何度も救われています」聞き耳うさぎは懐かしそうにそう語った。
「『あなたにはまだできることがあるから』、って良い言葉ですね」大水青が言う。
「何度も辛い時に浮かんで、私を励ましてくれる言葉です」聞き耳うさぎは言う。「妻の死が残したお金を元にこの店を始めました。この店のコンセプトには随所に彼女を悼む気持ち、彼女の存在を思い起こさせる物事を込めています。スター・サファイアのカクテルも雪女のカクテルも妻の思い出から作られています。店内装飾の星々に関する品物もそうです。僕は今でも常に、亡くした妻を想いながら生きています」
そうか奥さんを亡くした事故が起きた雪山のイメージも、あの雪女のカクテルには込められているんだ、と僕は気付かされた。もし死者の霊というものがあるのなら、聞き耳うさぎの奥さんの魂は、いつでもこのお店にいて、聞き耳うさぎと日々共に生きているのではないだろうか。
その日僕と大水青はメールアドレスと、インターネットの日記のページを教え合った。その後の出来事を少し伝えると大水青と僕は上手くいかなかった。聞き耳うさぎの店で時々顔を合わせるくらいで、ドライブに誘っても断られるし、無論のこと一度として僕と大水青は寝なかった。大水青のネット上の日記を見るとすぐに分かったのだけれども、彼女の交友関係は多様で、一緒に遊びに行く友だちは男女問わず多くいるようだった。僕は彼女の日記に夢中になって、ほとんどその文章の中毒状態になるくらいに、欠かさず彼女の記事が更新されるのをチェックしていた。けれども、日記に感想を書き送っても、ほとんど無視されて時々しか返してくれずそのことに傷ついた。僕が彼女の存在に心を奪われているその十分の一も、大水青は僕のことを思ってくれてはいない。それが現実だと突きつけられた。ある夏の日の彼女の日記に、光溢れる青い海を背景にした交際相手とのツーショット写真が載せられていて、僕は大水青との交際を諦めた。現実の男女関係は妄想の世界のようには上手くいかない。現実は海の水のようにほろ苦い。それでも僕は大水青に恋をしていた。もう見ないようにしようと何度心に決めても、彼女の文章を読むことが止められずに、心の奥の未練を引きずっていた。我ながらストーカーじみていて気持ちが悪いなと思いつつ、一言も発言せずに無言で彼女の日記ページを読み続けていた。インターネットとはそういうことが可能な場なのだ。熱帯夜に大水青のことを考えると、身体がいつの間にか熱を帯びていて、触れる皮膚が汗ばんで吸い付いてくる。そんな時に、触れ合う相手の不在の虚しさが強烈に胸に迫るのだった。自分自身の存在が世界のどこにも繋ぎ止められず、虚空にぽつんと浮かんで四肢を持てあましているような気がした。胸が張り裂けそうに痛い片思いを振り切って、次の愛する対象を見つけたいと思いつつ、僕の心は動けなかった。自分の肉の身に切迫した切なさは皮膚を裂いて心臓を貫いていくようで、何度くぐり抜けてもこの苦しみは受け止めきれない。いくら考えまいとしても、自分の心はあてもなく、大水青の存在の周りを衛星のようにぐるぐると回り続けていた。
大水青のいない日に聞き耳うさぎにそんな悩みを伝えると、そんなものですよ、その心の痛みも一つの人生の味わいです、と言われた。僕は苦笑した。
僕は窓の外を眺める。今日もまた月の光がこの地球上に届いている。砂丘の躑躅も、監獄の白の狸も、今僕と同じ月を見上げているのかと思うと奇妙な感じがする。思えば平安時代の昔から、人間たちは僕が今見ている月と同じ姿の月を眺めてきたのだなと思った。月の光を見つめてその光の円に吸い込まれそうになった時の人間の心は、時代を超えてあまり変わらないのかもしれないな、と僕は考える。
エピローグ
小説を書きながらあれこれと頭悩ませることは狂うことに似ている。脳内に自分ではない他者の声を聞き、脳裏に色鮮やかな幻を見ることなしに人は小説を書けない。芸術作品を創造しようとした時、人は心の苦しみと闘うのだと思う。絵を描けば死にたくなり、小説を書けば気が狂う。しかしそもそも狂気とは何であろうか。単純作業すら難しくなり仕事に支障が出ることを狂いと呼ぶのか、叫んだり物を壊したりする客観的に見て反社会的な異常行動が出るのを狂いと呼ぶのか。病の狂気と正気の苦しみの境界線は微妙だ。脳内だけの狂気は傍目には分からない。理性を保ちながら静かに悩み苦しみ、自らの心と闘うことは、人の自然ではないだろうか。人は否応なしに悩む。自分の思惑を超えて悩み苦しむことは、全ての人が味わうことだと思う。他者ににこやかに接して、礼儀正しく振舞いながら、心の地獄を抱える人は、かつて僕が考えていたよりも多いのではないか。人間に共通する心の苦しみの領域は存在するのではないだろうか。そんなことを考えながら僕はこの物語を語ってきた。物語には、悲しみも苦しみも恥も、全てを受容する広さがある。そこに僕はすがるしかない。人間の心が抱える謎に挑んで立ち向かう生き方をすれば、いつか僕の前に答えは明かされるかもしれない。そのことを望んで、僕は人間の心に対する自分自身の立場を表現しようとした。
この物語を語ろうと思った意図は明確にある。精神病への認識を変える一つの繋ぎ目になりたいということだ。精神的な病の症状というのは、捉え方を変えることで自分にとっての意味合いが変わってくる。その苦しみの程度や過酷さは変わらないかもしれないけれども、信じている物語、自分にとっての心の世界観によって、人は精神的にぶれても現実世界で踏み外さずに堪え抜ける。そのことを伝えたくて、かつての自分が切実に必要としていた心の捉え方を、僕はこの物語に込められるだけ込めたつもりだ。人は物語によって狂い、また物語によって支えられる。この物語が心が辛い時の支えになるものであって欲しいと切実に思う。何が真実かは僕には未だに分からないのだけれども、実在する心の世界の在り方を僕は信じていきたい。人は人生という名の物語によって苦しみ、自分の生きた物語の責任を問われて心の地獄を味わうのだと思う。現実的には幻聴や幻覚を脳内で知覚した人は、統合失調症などとして医療機関で投薬治療を受けるか、社会的に見て異常行動がある場合には精神病院に入院させられる場合がある。その際には、犯罪を起こしかけた措置入院の悪人などと同じ場所で生きるケースもあり得るだろう。入院まではしなくても狂ってしまって言うことが妄想だと見なされれば、人前には出られなくなる。一昔前は狐憑きとしてお祓いがされたり、憑き物を出そうとして叩き殺されたりもしたようだ。座敷牢に閉じ込められることもあったという。また、そうした精神の病により投薬治療を受けた場合、産まれてくる子どもに薬の影響により身体的な障害が出ることもあるという。精神の病が子に遺伝する数値も高い。この物語の遊女躑躅は子どもが産めない身体の事で苦しんで死んだが、精神の病により子どもを産めない人生を選択せざるを得ない女性も多くいる。そういう過酷な現実があった上で、なお僕は狂気を人間の脳の自然な在り方の一つであるとこの物語で提示したい。物語の中の僕は幻覚も幻聴も妄想もある。それでも現実に生きようとしている。そのことを伝えたかった。幻覚は症状として決めつけられて否定されるけれど、それを味わっている当事者としては一つの心の現実であり、その中には真実も含まれていると僕は思うのだ。物語はその心の真実を語りうると僕は信じている。
鬼は炬燵で丸くなる
お読み下さりありがとうございました。


