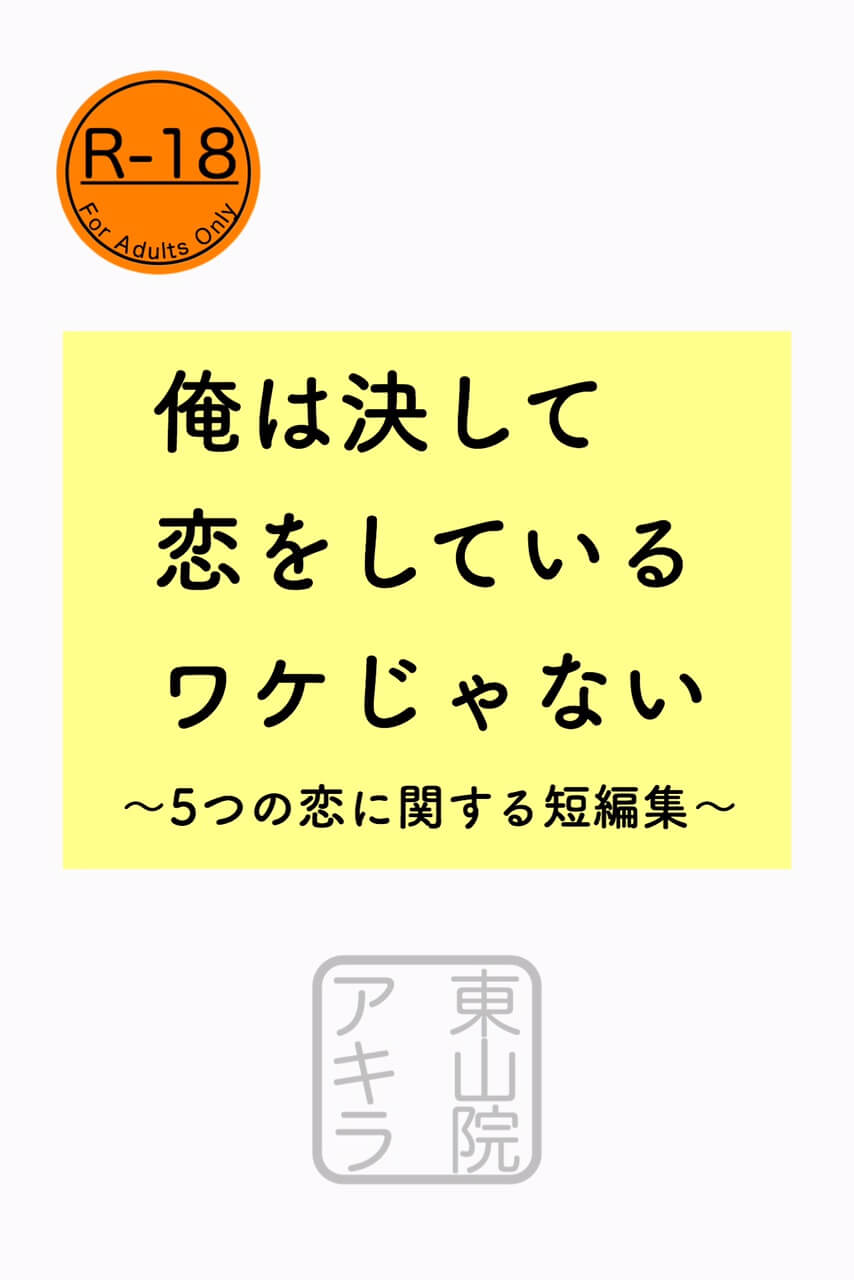
俺は決して恋をしているワケじゃない ~五つの恋に関する短編集~
一 俺は決して恋をしているワケじゃない
枕元に置いたスマホが朝七時を知らせてくれる。俺は暗闇の中からうっすらと目を開けると、カーテンの隙間から差し込む陽の光に目を細めた。その間にも、狭いワンルームの部屋には、アラームがやかましく鳴り響いている。
「はいはい。分かってるって」
独り言をこぼしながら、賑やかな電子音を黙らせる。大きくあくびをすると、だらだらとベットから起き上がった。
小さな部屋には似つかわしくない大きなベット。三ヶ月前までは、このベットにシゲルも寝ていた。あいつとは、五年前に知り合って、何となく一緒に遊ぶようになり、何となく付き合い始めた。その何となくの関係から、気が付いたら一緒に住むようになっていた。でも、些細なことがきっかけでシゲルとは別れた。
あいつは何事にも前向きで積極的だった。一緒に遊びに行く場所も、晩飯は何を作るかも、全部、向こうが決めていた。俺はあいつが決めたことは何でも受け入れた。一度だって、嫌だと思ったことはなかった。でも、シゲルにとってはそれが不満だったのかもしれない。
ある日、あいつに言われた。
「君は何でもいいんだね。僕じゃなくてもいいんだね」
俺は何も言い返せなかった。
そうかもしれない。何となく一緒に暮らし始めた関係は、俺が望んだことなのか、ただシゲルに流されただけなのか。そもそも、俺は愛だの恋だの興味があったのか。それすら分からなかった。
だから別れた。
付き合う相手を見つけることも、一緒に暮らす関係にまで発展することも、周りの友達は難しいと言う。でも、俺は苦労したわけでもなく、気付いたらシゲルと一緒に居て、いつの間にか一人になっていた。
あいつが消えてから、淋しいと思うことはなかった。それでも、ショックはあった。なぜなら、何かしらの自分の一面に愛想を尽かされたわけなのだから。たぶん、俺は恋愛には向いていないのかもしれない。そう思うと、気が楽になり、心の整理がついた。
俺は軽く汗ばんだシャツを床に脱ぎ捨てると、シャワーの栓を開いた。冷たい水が徐々に温水に変わる。手でちょうど良い温度を確認すると、パンツを脱いで寝ぼけた体に朝一番の刺激を与える。
頭に残った寝癖を直し、肌に張り付いた汗を洗い流す。少しだけ上等なボディソープで体中を泡だらけにする。メンズ用の洗顔石鹸を使い、シェービングを塗りたくって中途半端なヒゲをきれいに剃り落とす。今日一日の顔と体を整えると、鏡に映った頬に両手で気合いを入れてみた。
七時二十分。昨日、コンビニで買ったおにぎりと野菜ジュースで朝メシを済ませると、ワイシャツにネクタイを締めて出掛ける準備を整えた。部屋を出る前に、大きな鏡で最後の確認をする。
「大丈夫だな」
俺は自分の格好をチェックすると、スマホを取り出して時間を見た。
七時四十分。ドアを開けると明るい光が差し込んでくる。二階の玄関先から見える桜の木には深い緑の葉が揺れている。もうすぐ六月になるのに、夏のような明るい日差しに、五月の風が心地よい。
今日もきっと会えるだろう。
俺はそう思うだけで、足取りが軽くなる。マンションから数分歩いた一番近くのコンビニに立ち寄った。でも、店の中には入らない。用事があるのは、駐車場のすみにある喫煙スペースだ。
七時四十五分。いつもの時間、いつもの場所に、今朝もあの男がいた。白いタバコを咥えながら、耳にイヤホンをしてスマホをいじっている。歳はたぶん俺と同じくらい。いや、少し大人びた風貌をしているから年上かもしれない。
がっしりとした体格は何かスポーツをやっていたのだろう。広い背中にスーツがよく似合う。ブランドものを身に着けるようなチャラチャラした感じではない。既製品のスーツでも大柄の体格にビシッと決まると、カッコ良く見える。
俺はポケットからタバコの箱を取り出すと一本咥えて、何気なく近づいていった。灰皿を囲むようにして、その男の斜め前に陣取る。タバコに火を付けると、スマホを取り出してニュースのアプリを開いた。でも、本当はニュースなんかどうでもいいのだ。
男は眉間にしわを寄せて、自分の画面を見つめながら、白い煙を大きく吐き出す。太く黒々とした眉は目を凛々しく際立たせ、男が背負う重さを感じさせる。長く伸びた灰を人差し指で叩き落すと、口元に咥えなおす。他愛もない仕草だが、何となく惹かれてしまうのだ。
何を見ているのだろう。
俺は気付かれないように目を動かしてみる。あの表情はエロいものを見ている様子ではない。下らないゲームをしているわけでもなさそうだ。たぶん、ニュースや株価なんかをチェックしているのだろう。仕事は営業なのか。何かの管理職なのか。俺の知らない場所ではバリバリのやり手なのかもしれない。
男は耳にはめたイヤホンに手をかけて、ずれを直した。もみ上げは少し長め。黒髪は短くさっぱりと整えられている。流行のソフトモヒカンで、少し洒落っ気を感じさせていた。
何を聴いているのだろう。
俺は耳をそばだててみるが、国道を走る車の音で聞こえるわけがない。今流行っている邦楽か、不朽の洋楽か、あるいはラジオか。きっと、プライベートでもバリバリに遊ぶ方なのだろう。旅行でも誰かを積極的に引っ張りまわすタイプなのかもしれない。
七時五十分。今朝も男は短くなったタバコの火を灰皿で潰すと、カバンを右手に駅の方へ歩いていった。俺はその背中を見送る。たった五分余りの二人だけの空間。それは心が通い合っているわけでもなく、お互いが別の方向を向いた無意味な時間。
俺はあの男の名前も知らない。たった一言の挨拶を交わしたこともない。でも、それでいいのだ。男がどんな仕事をしていようが、何を聴いていようが、ノンケだろうがゲイの乱交サークルに参加していようが、不思議なことにどうでもいいのだ。
ある日、気付いた。
俺は決して、あの男に恋をしているわけではない。この気持ちは恋に恋するようなもの。そんな些細でくだらないもの。それでも嬉しかった。愛だの恋だのに不感症だと思っていた自分にも、そんな想いは確かにあった。それにやっと気付くことができたのだ。
そう思うと、俺はシゲルのことがたまらなく愛おしくなった。
二 温もり
――一九九○年。
カーテンが閉じられた薄暗い空間。窓の外は明るい陽の光で輝いているはずなのに、この高級ホテルのスイートルームには生々しく卑猥な空気で溢れている。
「おらぁ! ヘバッってんじゃねぇぞ!」
「うっす、うっす! 兄貴のタネ、俺のケツマンに流してくれ!」
俺は名前も知らないガチムチ野郎のケツを自慢のマラで犯している。どれくらいの時間、こいつのケツを掘っているのか、もう覚えてねぇ。相手は俺のことを兄貴と呼ぶが、半泣きでケツの快感に悦ぶ淫乱野郎はツラ構えからして、俺よりも年上だろう。下らねぇやつ! 俺は自分の快感だけを求めて、男のケツを犯しまくる。
俺は男子高の出身で、柔道部に所属していた。ある日、部活の先輩数人から生意気だと因縁を付けられて、体育倉庫で無理矢理ケツを犯された。初めて犯られた時はショックで涙を流したが、二度、三度と犯されているうちに、男の味を覚えてしまった。そのうち、俺は上級生の前で自らケツを差し出すような淫乱野郎に成り果てた。
だが、俺が上級生になるとケツを犯すことに興味を持つようになり、後輩を犯すようになった。先輩達に犯られたように、俺も後輩のケツを弄ぶことは当然のことだと思っていた。
俺は、後輩をレイプした時と同じように目の前の男のケツをむさぼっている。ケツの中の熱い粘膜が、俺の亀頭や竿に絡みつく。これは何物にも変えられない最高の気分だ。
「んんっ、うぐっ、うぐっ!」
俺がケツを犯している淫乱野郎の口には、別の男のマラが突っ込まれた。上の口も下の口も犯されて、最高の気分だろうな。実際、二人の男に弄ばれている淫乱野郎は恍惚の表情を浮かべている。
胸くそ悪りぃ! 涙目で喜んでいる男の表情を眺めていると、俺はヘドが出そうになる。
「おらっ! 俺のタネぶち込んでやるよ! 俺の子供孕めよ!」
「ああっ! 最高っす!」
俺はじわじわと登ってくる快感に身を任せて、力いっぱいに腰を一突きした。鈴口から飛び出す精液が男の直腸にドクドクと流れていく。
「あああぁ……」
俺のタネを受けた男は、女のような甘い声を漏らした。
俺は大きく息を吐き出すと、乱暴にケツから自分のマラを引き抜いた。犯されて悦ぶ男の姿を見ると、ツバを吐きかけたくなる。でも、そんなことをしてトラブルにでもなったら、このサークルから出禁になるかもしれない。俺は鈴口に残った精子をティッシュで拭き取ると、さっさとその場を離れた。
広いスペースに何人もの男達が肉欲に溺れている。俺がさっきまでケツマン野郎を犯していた隣のベッドでは二十代くらいの体の締まった男が、ずっと年上のオヤジにおもちゃにされている。向こうのソファーでは四、五人くらいのスーツの似合いそうなガッチリ系の男が、お互いのマラをしゃぶり合っている。その隣の床の上では坊主とスポーツ刈りの男が唇を貪りあっていた。
ここは誰でも入れるハッテン場とは違う。会員制の乱交サークルで、体育会系の肉体自慢なヤツしか参加ができない。トラブルだけはご法度だが、快楽のためなら何をやっても構わない。もちろん、秘密厳守。このサークルはゲイの世界でも水面下で活動する卑猥な連中の集まりだ。
俺は、人づてに知り合ったメンバーより、でかい図体を見染められて誘いを受けた。それまでハッテン場と名の付く場所にはどこにでも現れ、ゲイバーで獲物を物色し、無数の男と肉欲の限りを尽くしていた。だから、このサークルは俺にとっては安住の地とも言える。
四方八方から聞こえてくる複数の男達の卑猥な声を背にして、バーカウンターにある冷蔵庫からビールを取り出した。部屋の隅にあるソファーセットがちょうど空いている。名前も分からねぇ上等なソファーに疲れた腰を下ろすと、酒の缶を傾けた。汗ばんだ体にほろ苦い炭酸が染み渡る。
「うめぇ」
俺は小さく言葉を吐き出すと、周りを見回して次の獲物を探す。
背後に男が立っていた。いつから居たのか、全く気付かなかった。見たことがない肩幅の広い肉厚なガチデブ体系の中年男。新しい会員か? その男は大きな黒い目で俺のことをじっと見つめて、ラウンド髭を蓄えた口元を緩ませている。
こんなバリタチっぽい男がケツを掘られてヒィヒィ泣くんだよな。俺は目の前の男に色眼を使ってモーションをかける。
男は俺の誘いに応じるように向かいの椅子に座った。身を乗り出して、両膝に肘を付いて俺の顔をじっと見つめている。何だよ。俺の顔に何か付いてんのかよ? いつまでも突き刺さる男の視線に、目をそらした。
残った缶ビールを飲み干すと、俺はもう一度、男の方に目を向けた。男の股間にある太い竿は上向きに反り返り黒光りした亀頭をのぞかせている。男はニヤリと笑うと、背もたれに寄りかかり両足を広げて、自分の股間を見せ付けてきた。黒々とした陰毛から突き出た竿は天を突き上げている。だらんと下がった袋は大きく膨れ上がり、性欲の強さを感じさせる。
俺は空になった缶をテーブルに置くと、微笑を浮かべて立ち上がった。アルコールが体の血を活性化させ、股間へ血流が集中する。目の前のスケベな中年男に唇を合わせると、それを合図に俺のマラも強く反り返った。
「兄貴のケツ、俺に味合わせてくれないっすか?」
俺は舌を絡めながら、熱っぽい声で口説いた。
こいつがタチなのかウケなのかは知らねぇ。だが、俺は今まで何度も鼻息を荒くするバリタチのケツを味わってきた。年上だろうがなんだろうが、ちょっと甘い言葉を使えば、勝手に向こうがケツマン野郎に成り果てるんだ。
男は何も答えずに、舌を絡めてくる。俺は男の脂肪でふっくらとした大胸筋に手を動かし、大きな乳首を触ってみた。指先で黒い乳輪をなぞりながら、先端に刺激を与えると、乳頭は硬くなり男は吐息を漏らした。
俺はそのまま乳首から手を下のほうへ動かしてみる。へその下に張り付くように勃起した亀頭に手を這わせ鈴口に触れてみると、ぬるぬるとした感触があった。
「もう感じてるんすか? ガチガチじゃないすっか」
耳元でささやきながら、太い竿を軽くしごいてみた。男は目を閉じて、軽く眉間にしわを寄せている。へへっ。もう少しで、こいつも落とせる。
俺は、あの体育倉庫で先輩達に襲われてから、人生が変わった。それまで柔道で強くなり誰かを愛し、明るい未来があると信じていた。だが、先輩達は俺を性欲のはけ口にし、俺もその快楽に引きずり込まれた。先輩達からマラを突っ込まれ、女のように鳴いた。俺のケツの中に性欲の塊をぶちまけた時の先輩の顔は、人を屈服させた満足感以外の何ものでもなかった。あんな惨めな思いは二度としたくなかった。だから、俺が初めて後輩を襲った時は最高の気分だった。ケツの肉壁にこすれて感じるマラの心地よさを味わい、後輩が顔を歪め、涙を浮かべる様子を上から眺めて、優越感と征服感に浸った。
人間はしょせんサルだ。セックスで優位に立つことが最高なんだ。俺は今までもこれからもずっと男を征服していく。愛だの恋だの、夢だの希望だの。そんなものはまやかしだ!
俺は今でも格好の獲物を目の前にしている。竿の裏筋をなぞるようにして玉袋に指先を滑らせ、蟻の門渡りに微妙な刺激を与える。大抵のスケベな男はこの辺を触られて悦ぶ。こいつも例外ではないはずだ。
「お、おおぅ」
男は吐息を漏らした。
俺は性感帯からケツの穴へ指を動かす。もう少しだ。もう少しで、この男も俺に屈服する。じらすように指を動かしながら、相手の堕ちていく表情を見てやろうとした。
だが、男は俺と目が合うと、その目に鋭い光を宿した。もう少しで秘部に届こうとしていた俺の腕は強く握られ、大きく引き離された。俺がつかまれた腕に目を移している間に、男は椅子から立ち上がった。
俺はその気迫にたじろいだ。同じくらいの身長のはずなのに、なぜか大きく感じる。口を半開きにして言葉を捜していると、男は太い腕と大きな手を使い、軽々と俺の体を抱きかかえた。お姫様抱っこってやつじゃねぇか!
「や、やめろ!」
俺はようやく見つけた言葉を男に吐きかけた。
男は何も答えようとしない。俺が抵抗しても暴れても、頑として腕を下ろそうとしない。男は誰も使っていないベットを見つけると、俺のことを白いシーツの上に放り投げた。体重の重みを受け止めたスプリングが大きく弾む。俺は目の前の男を睨みつけた。
「ふざけんな! 何様のつもりだ!」
俺は頭に血が上って、腕を組み仁王立ちで俺を見下す相手に声を荒げた。
「黙れ……」
男は低い声でつぶやくと、俺の体に覆い被さってきた。
両手をつかまれ、男の少し汗ばんだ肌が密着する。男は器用に膝を動かすと、俺の股を開き、自分の股間を押し付けてくる。俺は黒い記憶が心の中に広がっていくのを感じ、体中の血が逆流する思いをした。
「頼む。や、やめてくれ」
俺はか細い声を漏らした。その様子にはさっきまで息巻いていたバリタチ風情は感じられないだろう。
男は俺を見つめ、手首をつかんでいた両手をゆっくり離した。その目は深く包み込むような黒い瞳をしている。俺はその視線に包まれるような感覚を受ける。抵抗して男の拘束から逃れることもできるはずなのに、手は力が抜けたようにシーツの上に横たわったままだ。
男はもう一度、唇を重ねてきた。ふっくらとした肉厚な唇からは温かい体温が伝わってくる。さっきとは違う。それは軽いレモンの味がするようで、俺が今まで味わってきた口づけとは全く違うものだった。俺はその味がもっと欲しくて、男の舌を追いかけるように、自分の舌を絡めた。生温かい粘膜が交じり合う。相手の舌先に触れると、心の奥底にある何かが締め付けられる思いをした。
男は唇を離すと、ゆっくり首筋から乳首へ舌を這わせてくる。優しい舌遣いは俺の肥大した乳首を包みこむ。その快感は脳天を貫くような刺激ではなく、傷を癒すような心地よさ。俺の強張った表情がいつの間にか解けていく。
だが、別の視線に気が付いた。ベットの両脇には数人の男が不敵な笑みを浮かべて、俺を見下ろしていた。汚らしい面構えをした男達は俺の体に手を伸ばそうとする。
「こいつは俺のモンだ! 触るんじゃねぇ!」
愛撫をしていた男は鋭い目付きに変わり、俺を隠すように片腕で抱えると、もう片方の手で男達を追っ払った。その迫力に圧倒された下衆野郎は、蜘蛛の子を散らすように消えた。
邪魔者が消えると、男は再び愛撫を始めた。ゆっくりと舌を這わせて、へそを舐めガチガチに反り返った俺のマラをすっぽりと咥える。
「ああっ、ああっ、あっっ」
俺はつい、声を漏らした。
どうしてだろう? こんな声は出さねぇはずなのに……。自分のことを抑えることができない。
男はマラを舐めながら俺の顔を見ると、その目元を少しだけ緩ませた。俺は目を閉じた。ねっとりとした舌遣い。温かい感触が竿を覆い、玉袋を包み込む。性感帯が敏感に反応し、膨らんだ亀頭の鈴口からはガマン汁が漏れるのが分かった。心を覆い尽くしていた何かは消え去り、代わりに包まれるような安らぎが広まる。
男は左右の膝裏に手を掛けると、俺のケツを大きく開いた。俺は催眠術にかけられたように、されるがままに身を任せた。不思議と恐怖心はなかった。この男になら、ケツを掘られてもいいと思った。いや、本当は、この男に俺の全てを捧げたいのだ。
ケツの穴にローションで湿らせた太い指が入る。固く閉ざされた蕾は少しずつ開かれていく。人差し指が根元まで入ると、今度は指が二本になった。俺は静かな闇に身を委ねた。一秒でも早く、男を受け入れたかった。
男は自分のマラを俺のケツマンに押し当ててくる。指とは比べ物にならない圧迫感がケツに広がっていく。俺は顔を歪めたが、大きく息を吐き出し、体の力を抜いた。男は俺の様子に気を配りながら、ゆっくりと挿入してくる。熱く燃えたぎる竿を根元まで入れると、優しく唇を重ねてきた。
俺は思わず男の広い背中を強く抱きしめた。
「大丈夫か?」
男は耳元で優しくささやきかける。俺は小さなガキのようにコクリと一つ頷いた。
それを合図に、男はゆっくりと腰を動かした。ガチガチの肉棒が俺のケツの中で擦れ合う。摩擦のような痺れる熱さが体を襲う。二度、三度と竿が出し入れされると、次第にスピードが上がってくる。男の亀頭が前立腺に当たるたびに、俺は声を上げそうになった。
「気持ちいいか? 我慢しねぇで、声出せよ」
男は息を荒げながら、甘い声でささやいてくる。
「はっ、あっ、あんっ、あっ」
俺は小さく声を漏らした。
男の突きが激しくなるにつれて、声は自然とでかくなる。快感に喘ぐ声。熱い吐息を吐き出すにつれて、俺は長く縛り付けられた鎖が解けていくように感じた。
男は腰を振りながら、俺の首と背中に肉厚な手を回してきた。うなじを包む手の温度と、背中を抱こうとする手の力を感じる。
「お前は、こんなところにくるようなヤツじゃない」
耳元でそんなことを言われたような気がした。
その言葉を確かめる間も無く、俺は前立腺から伝わる刺激に耐えかねて、タネをぶっ放した。それと同時に男も低い声を上げる。俺のケツマン奥深くに熱いものが注がれるのを感じた。
俺はシャワールームの鏡に自分の体を映してみた。名前も知らねぇ男達の汗と唾液が混じり合い、陰毛には精液がこびり付き独特の臭いを放っている。今日も何人の男と肌を合わせたのか覚えていない。だか、ケツの中にはあの男だけのタネが蓄えられている。
あの男に抱かれた後、俺は放心状態で少しだけ目をつぶった。いや、長い時間、寝ていたのかもしれない。再び目を開いた時には、あの男の姿は消えていた。
シャワーの栓を開くと、熱い湯が勢いよく流れる。外国製のブランドものの石鹸を泡立たせ、俺は汚れた体を洗った。シャワーを止めてバスタブから出ると、不思議と体が軽くなった気がする。ただ、あの男に抱かれた手の力と温もりは、いつまでも残っている。
俺は服を着て荷物を受け取りホテルの部屋を出た。ガチャリと閉じられた出口を振り返ってみる。今もなお繰り広げられている卑猥な賑わいは、この廊下までは届いてこない。俺は固く閉じられた扉を冷めた目で見流すと、背を向けて廊下を進み始めた。
最上階から吹き抜けの空間をエレベーターが降りていく。俺は自分の手を開いてみた。この手にもあの男の温もりが残っている。その小さな温度を包み込むように手を握りしめると、エレベーターの階数表示を見つめた。
「もう一度、逢えねぇかな……」
一階に到着したエレベーターの扉が静かに開くと、俺は眩しい光に目を細めた。
三 モテ筋ゲイの胸の内
――二〇一七年。
新宿はギラギラとした光に包まれている。駅から少し離れたこの場所も例外ではない。金曜日の夜八時。新宿二丁目の小さな店は看板の明かりを灯し、男達を迎え入れる。
俺は無数に掲げられた看板の一つに向かって歩いていく。その途中、路上にたむろする男達の視線を感じる。一人で居るものは俺をじっと見つめ、二人連れは声を潜めてこっちを指差している。でも、それはいつものことだ。様々な視線を体中に受けながら、真っ直ぐに目的の店を目指す。
メインストリートを外れて少し薄暗い通りにある小さな雑居ビルに足を踏み入れた。人が一人やっと歩ける程度の小さな階段を二階へ上がる。通路の一番奥にある店が、俺の行きつけのゲイバーだ。くすんだ茶色の古いドアを開けると、客の入店を知らせるベルが鳴る。
ここは小さな店だ。入り口の左手にカウンター席があり、十人も座れば圧迫感を感じる。並んだ椅子の背後にはコート掛けがあり、この季節では使っているやつは誰もいない。一番奥のスペースには棚があり、ゲイ雑誌や本が詰まっている。今夜もマスターとスタッフの二人だけで、数人の客を相手にしている。
「いらっしゃーい! タイヨウちゃん、待ってたわよー!」
入り口付近に陣取っていたマスターは、営業用のおネエ言葉を全開にして俺を迎え入れてくれた。俺は別に呼ばれたわけでもない。いつものようにただ飲みに来ただけだ。
「マスター、悪いけど充電させてよ」
俺は挨拶代わりに、空いている席に座ると自分のスマホを持ち上げて見せた。
「いいわよ。でも、今度アタシにも一発やらせなさい!」
マスターは手元の充電コードを差し出して、意地悪そうな目で笑う。その冗談には何も答えずに、俺は苦笑いを浮かべた。
マスターは俺の返事に気にする素振りも見せず、カウンターの裏にある大きな棚から焼酎のボトルを取り出した。
「で、今日もジムの帰り?」
「ああ、そうだよ」
マスターはコップに勢いよく酒を注ぎウーロン茶を入れると、カラカラと氷をかき回して、俺の前に置いた。
俺は仕事帰りに週五回、ジムに通っている。周りの連中からはやり過ぎだとバカにされるが、それは自分を磨こうとしない奴らのひがみだと思っている。俺はガキの頃から野球や柔道をやっていたから、基礎体力も高く体格も大きかった。就職をしてから、何気なく始めた筋トレにすっかりハマり、もう十年近く続けている。おかげで、腕は丸太のように太く、厚い胸板のバルクマッチョになることができた。スクワットで鍛えたケツも大きくプリッと弾むようになり、太ももの肥大によってスラックスがいつも窮屈に感じていた。
「頑張るわねぇ。ところで、アンタ、付き合ってる人はいるの?」
「いや、特には……」
俺は少し見栄を張って、わざとらしくあご髭を触った。
本当はそんなヤツ、全くもって誰もいないのだ。それどころか、最近はセックスもしていない。仕事と筋トレの疲れもあって、男と遊ぶところまで余裕がない。やろうと思えば、性欲を解消する男だって付き合う相手だって、簡単に見つかるかもしれない。でも、俺はそんなことをするのが嫌なんだ。
「じゃあさ。アンタのこと気になってる人がいるんだけど、会ってみない?」
マスターは自分のスマホを取り出すと、画面をいじってSNSサイトのプロフィール写真を見せてくれた。俺よりも少し年上か? 髪はド短髪ではなく少し長めだけど、スッキリとまとめられている。目や鼻のパーツは大きくて豊かに蓄えられた髭が目立っている。
「ま、少し詐欺画像っぽい部分もあるけど。いい子よ。興味あるでしょ?」
「せっかくだけど、そんな気分じゃないんだ」
俺はマスターのお節介をあしらうように、目の前の酒に口を付けた。
「もう! そんなこと言ってると、あっという間にジイさんになっちゃうわよ!」
俺の態度に気分を害したのか、愛想を尽かしたのか。マスターはスマホをしまうと、トイレに行ってしまった。
いつもこうなんだ。付き合っている男はいるのか? 顔もいいからモテるだろう? どうせ男と遊びまくってるんだろ? ゲイ雑誌から飛び出したような理想の男に、周りは色めき立つ。
でも、本当は、俺はそんなヤツじゃない。
「すごい筋肉ですね」
隣に座っていた四十代くらいの客が、俺に声をかけてくる。
「あ、そんなことないっすよ」
初対面の相手に向かって、少しだけ身を縮めて小さく言葉を返した。
「ちょっと触ってもいいかな?」
「……どうぞ」
俺は半袖シャツの袖を肩まで捲し上げて、肘を曲げて力こぶを作って見せた。何度も同じようなリクエストを受けるので、最初から理想の筋肉を見せてやる。腕を近づけてやると、男は上腕二頭筋をわしづかみにするようにして、筋肉の感触を楽しんでいる。
「すごいなぁ。めちゃめちゃ硬いね!」
男はそう言いながら、目を細めて黒目を動かす。俺は、その視線が乳首や股間に注がれていることに気付いた。
またか。こうやって俺は周囲からポルノグラフにされる。中には本気で俺に恋してくれている男もいるかもしれない。でも、それだって見た目を愛しているに過ぎない。肉欲に溢れた冷たい視線を浴びる気持ちは、お前らに分かるのか? 周囲の勝手な理想に無理やり当てはめられ、人格までも決め付けられる屈辱感を味わったことがあるか?
「コラッ! アンタ、うちの店はお触り禁止よ! 出禁にするわよ!」
トイレから戻ったマスターが助け舟を出してくれる。男は苦笑いを浮かべて、俺の腕から手を離した。
俺は袖口を元に戻すと、マスターと交代するようにトイレに逃げ込んだ。
マスターは自分の用を足した後、トイレも掃除をしたようだ。清涼感を感じさせるレモンの香りがする。棚の上にあるスプレー式の芳香剤がそれだろう。俺は閉じられたフタと便座を持ち上げると、チャックを降ろしてパンツの中から竿を取り出した。指で皮をつまんで引っ張るようにして亀頭を出すと、鈴口から的へ向けてジョボジョボと小便を流す。
尿意が治まると、さっきまで湧き上がっていた怒りとも取れる気持ちも消えていった。筋トレはモテるためにしているのではない。綿密に計画を立て、体を酷使して、食事にまで気を配る。様々な努力を積み重ね、肉体を磨き上げていく。ガキの頃に学校でやった工作のように、自分の体を作り上げてくことが楽しくてしょうがないのだ。ただ、それだけなんだけどな……。
俺はトイレの水を流すと、芳香剤を手に取り、小さな空間にレモンの香りを漂わせた。
席に戻ると、さっきの男はもういなかった。俺は椅子に座って、新しく作られた酒を口に含んだ。マスターがなぜか怪訝そうな顔をしている。
「アンタ、ちょっと臭いわよ。トイレのスプレー使ったの?」
「あ、使ったけど」
俺は肩の辺りに鼻を近づけて臭いを嗅いでみる。確かにトイレで感じたレモンの匂いが服に染み付いてた。
「だめよー。アレ強すぎるから、時間を置いてからじゃないと服にも付いちゃうのよ」
マスターはタバコを吹かしながら、眉間にしわを寄せる。
「それ、早く言ってよ!」
俺は肩や腹を手で払って匂いを消そうとした。だが、布地に染み込んだ臭いは簡単に取れるものではない。
「でも、レモンの香りか……。初恋はレモンの味なんて言うけど、本当はどんな味なのかしらね?」
俺の無意味な動作を見つめながら、マスターは頬杖を付いて口元を緩ませている。
「マスター。ギルバート・オサリバンのCDってどこでしたっけ?」
カウンターの奥で接客していたスタッフが声を上げた。
「あ、それ別の場所に置いたのよ。アツシ、こっちと交代して」
マスターはそう言うと、俺の目を見た。
「じゃ、タイヨウちゃんもゆっくりしていってね!」
右目でウインクをすると、マスターは奥へ行ってしまった。
俺はもう一度、服に付いた匂いを消そうとした。その間に、入れ替わりでアツシさんがやってきた。
「タイヨウくん、こんばんは」
アツシさんはいつも物静かで穏やかだ。俺よりも二つ年上で、優しいお兄ちゃんタイプ。店では会話の中に立ってグイグイと引っ張るのではなく、客の話に耳を傾けて何でも聞いてくれる感じ。ぽっちゃりとした顔から時々こぼれる笑みは誰が見ても癒される。だから、客の間でも人気がある。
「この前、アツシさんから教えてもらった映画見たよ」
「見てくれたんだ。どうだった?」
「うん。主人公がいろいろあったけど、最後はハッピーエンドで良かった」
俺は少しだけ嘘を付いた。映画を見たのは本当だが、最後の三十分は眠ってしまったので分からない。それでもアツシさんと話がしたくて、ネットに書いてあったレビューをネタに会話を続けた。
「気に入ってくれて良かった。また何か良いものあったら教えるよ」
アツシさんはそう言うと、目元を緩ませた。
次はちゃんと最後まで見てから話をしよう。俺の小さな心臓にチクリと針が刺さった。
アツシさんは俺の体や顔の話はしない。それは単に興味がないだけなのかもしれないが、俺のことを外見だけで判断せず、本当の姿を見てくれているような気がする。だから、俺はアツシさんと話をする時が一番好きだ。この店に来るのもこの穏やかな時間が欲しいから。俺はそのために、二丁目の冷ややかな視線に耐えながらこの店にやってくる。
「えーっ! マスターって乱交が好きなの?」
奥の席に座る一人の客から声が上がる。俺もアツシさんも同じ方向に顔を向けた。
「やあねぇ。昔の話よ。そんなサークルがあったの」
マスターは照れ臭そうに話している。
「で、今でもそのサークルには参加してんの?」
「いや。何度か通ったけど、ある時すっぱり辞めたわ。今は何かと厳しいでしょ? そのサークルも今では無いみたい」
客の質問に開けっぴろげに答えるマスターだが、タバコの煙を漂わせて遠い目をしている。
「あ、何かあったんだ! ヤッた相手のことが好きになったとか?」
「バカ! そんなことあるわけないでしょ!」
マスターは声を張り上げた。その頬は少しだけ赤く染まっているような気がする。
「いろいろあるんだね」
アツシさんの言葉に、俺は頷いた。
「あっ」
小さな声に反応して、俺は顔を上げた。
音を出さないテレビから、緑の風にそよぐ涼しげな渓流が映されている。
「この場所ってヤマメが釣れるんだよね。タイヨウくんは釣りしない?」
アツシさんは洗い物の手を止めて、テレビに釘付けになる。その目は小さな子供のように輝いていた。
「うーん、したことないけど。面白そうだなって思うよ」
俺はテレビを眺めるふりをして、わずかに目線を反らしアツシさんを見ていた。釣りに興味があるってのは嘘ではない。二人で静かな夏山の渓流で釣りをする風景を思い描いてみた。
「一緒に行けたら、楽しいだろうね」
アツシさんは俺に向かってニッコリと笑った。
「そ、そうだね」
俺は少しだけ声が上ずった。
「でも、休みが合わないよね。僕もお店休めないから」
そう言うと、目を細めて口元に笑みを残しながら、シンクに残ったコップを洗い始めた。
俺はコップを傾けて残った酒を乾いた身体に流し込んだ。中の氷と氷がぶつかり合う音が空しく響く。
その直後、ドアが開いて二人連れの客が入ってきた。
「あ。チェックして」
俺はカバンを持って立ち上がり、財布から千円札を二枚取り出した。
「じゃ、千七百円になります。タイヨウくん、またね」
アツシさんは丁寧にお札を受け取るとお釣りを差し出して、優しい笑顔になる。つり銭を受け取る時に、少しだけ触れた手が温かかった。
「じゃあ、また」
俺は軽く手を振ると店を出た。
雑居ビルを出ると、もうすぐ終電だというのに人通りが多かった。ああ、今夜は確か有名なナイトがあるんだっけ。
新宿駅に向かって歩いていると、遠く背後から呼びかける声が聞こえてきた。振り返ると、マスターがこっちに走ってくるのが見えた。
「ちょっと、タイヨウ! 待ちなさいって!」
店から百メートルくらいしか離れていないのに、よっぽど急いでいたのだろう。マスターは息も切れ切れで俺に追いつくと、腰を曲げ両膝に手を置いて乱れた呼吸を整えた。
「普段なら、絶対にこんなことしないんだけどね」
そう言うと、二つ折にした小さな紙切れを差し出した。
「何すか、これ?」
俺はその白い紙を受け取ると、マスターは言葉を続けた。
「アンタが本気で興味あるなら、連絡取りなさい」
その紙を開くと、アツシさんの名前とメアドが書いてあった。
「もうアンタのこと黙って見てらんないのよ。それに……」
マスターは言葉を続けようとしたが、途中で言葉を押しとめた。代わりに少し目を開いてニンマリと笑うと、俺の肩を叩いた。
「また、お店に来るのよ!」
そう言うと、背中を向けて歩き出した。少し高めの声でアローン・アゲインを夜の街に響かせて、来た道を引き返していく。
その歌声が消えると、耳に賑やかな雑踏が戻ってくる。俺はさっきテレビで見た涼しげな渓谷を思い出した。ポケットからスマホを取り出すと、メモに書かれたアドレスを一字一字確認するように入力する。
それまで突き刺さるように感じていた新宿のネオンは丸みを帯びたように柔らかくなり、面妖な繁華街の空気の中に少しだけ包まれるような優しさを感じた。
四 いわし雲の季節に
夕暮れの晴れ渡った空には小さな雲の塊が無数に浮かんでいる。
少し遅くなっちゃった。僕は途中のお店で買った小さな花を手におやっさんの元へ急ぐ。いつもの場所にたどり着くと、待ち合わせの相手はふて腐れたような態度をしていた。
「ごめんね。遅くなっちゃって」
僕は両手を合わせて、持ってきた小さな花束を渡した。
「待っていたぞ」
おやっさんは花を受け取ってくれるけど、まだ機嫌を直してくれない。
僕はかばんから缶ビールを取り出すと、プルトップを外して渡した。そうすると、ようやく機嫌を直して笑顔を見せてくれる。
僕は向かい合わせに腰を下ろすと、空を見上げた。
「今日はいわし雲が出ているよ」
その言葉に反応するように、おやっさんも同じ空見上げてくれる。
――十六年前。
僕は高校の時に交通事故で両親を亡くした。一人っ子で、身寄りは父方の伯父夫婦しかいなかった。伯父は、僕を高校までは出させてくれたが、その後は自分で何とかしろと言った。営業マンだった伯父は東京の方にも知り合いが多く、浅草にある小料理屋を仕事先として世話をしてくれた。
大きなかばんを抱えて、初めて東京にやってきた。思っていたよりも古くて小さなお店で、僕は初めておやっさんと出会った。
「好きな料理は何だ?」
無愛想な他人の言葉に、どぎまぎしながら答えた。
「に、煮付けです。イワシの……」
怖かった。おやっさんは五十手前くらいの年齢だったと思う。独身で子供もなく、親から継いだという小さな店を一人で切り盛りしていた。
僕はこの店に今日から、住み込みで料理人として働く。周りの友達は皆、進学したのに、自分だけ右も左も分からない世界に放り込まれて、泣き出したい気持ちでいっぱいだった。
「そうか」
おやっさんは小さくつぶやくと、僕を残してカウンターの中に入った。大きな冷蔵庫からタッパーのようなものを取り出し、別の棚から包丁を取り出す。僕は完全に放置されているようで、荷物を床に置くと恐る恐るカウンター前の椅子に腰掛けた。
店を見回してみた。小さかったが掃除が行き届いて、優しい木目調のカウンターが明るい雰囲気を漂わせている。おやっさんは鋭い目をして手元の包丁を扱っていた。ここからでは何をしているか、よく分からない。
鍋が沸騰する音が聞こえてくると、醤油と砂糖の柔らかい匂いが漂ってくる。僕はお腹の音を鳴らした。どれくらい時間が経っただろう。無口な料理人は鍋から何かを盛り付けると、カウンターに身を乗り出した。
「食べな」
それだけ言うと、僕の目の前に大きめの小鉢を置いた。
中には頭を切り落として半身にしたイワシの煮付けがあった。細かく刻まれた生姜も付いている。イワシの煮付けは、料理苦手な母が唯一得意だったレシピ。小さな時から食べさせられてきた素朴な料理が、僕は大好きだった。
「いただきます」
イワシの身に箸を入れた。少しの力でも絞まった身が柔らかく崩れる。一口大の大きさにした煮付けを口に運ぶと、イワシと甘辛い煮汁の旨味に生姜の香りが広がっていく。
「どうだ。美味いか?」
おやっさんは僕を見つめながら、少しだけ表情を和らげた。
僕は口の中をイワシでいっぱいにしながら頷いた。この味は決して母と一緒の味付けではない。それでも、料理ってこんなに優しくて、安心できるんだと思った。小鉢をわざと持ち上げ、顔を隠すようにして食べ続けた。初対面の人に泣いている姿なんて見られるのが恥ずかしかった。
空に漂うたくさんのイワシ雲はオレンジ色に染まっている。
僕は今でも、あのイワシの煮付けの味を思い出す。あの味はおやっさんそのものだったと思う。素朴だけど優しくて温かくて、他の何ものにも代えられない大切なものだった。
「また、あの煮付けが食べたいな。何度、やっても美味くできないんだ」
僕は少しだけ甘えた。
「精進が足りないな。俺がみっちり仕込んでやったじゃないか」
おやっさんは少しだけ厳しく、励ますように答えてくれる。
「なあ?」
「ん、なあに?」
おやっさんはうつむき加減で、僕に語りかけてきた。
「あのこと、やっぱり恨んでいるか?」
「また、その話? 何度も言っているでしょ。僕はおやっさんが好きなんだから」
おやっさんはいつも辛そうな顔で聞いてくる。その度に、もう僕は気にしてないって言っているのに。
――住み込み修行が始まって二年後。
火曜日はお店の定休日だ。僕は昼間に自由な時間をもらい、夜は料理人としての技術を一つ一つ教えてもらっていた。
でも、今夜はおやっさんが商店街の会合に出かけている。僕は先週教えてもらった出し巻き卵の作り方を一人で練習していた。七皿目のあたりから、形のきれいな卵焼きの姿が見えてくる。無数に転がる卵の殻の成果が、ようやく実を結んできた。
その時、店の引き戸が勢いよく開いて、顔を赤くしたおやっさんが帰ってきた。
「おう、けぇったぞぉー!」
会合の後はいつもお酒を飲んで帰ってくる。でも、今夜は少し飲み過ぎているみたいだ。
「おやっさん、大丈夫ですか?」
千鳥足で椅子に足をぶつけながら奥へ上がろうとするおやっさんに、僕は駆け寄って肩を貸した。
「おう、サンキューな! そうだ。お前、今日は先に風呂入れ!」
酒臭い息を吐きながら、ご満悦の表情をしている。
僕は首を振った。
「厨房の片付けがあるから、おやっさんからどうぞ」
「いいから、先に入れってんだよっ!」
おやっさんは笑顔で僕の頭をわしづかみにすると、髪をくしゃくしゃにした。
僕は舟を漕ぐ酔っぱらいを茶の間に座らせるとコップに入れた水を渡して、言われたとおりに風呂に入った。
湯船で体を温めて、体を洗おうとした時のことだ。突然、風呂場の扉が開く音がした。
「おう、体洗うのか? 俺が背中流してやるよ」
おやっさんが裸で前も隠さずに入ってきた。僕はその時、初めて師匠でもあり父代わりでもある男の裸を見た。もちろん、僕も裸を見せたことはなかった。
おやっさんは色黒でがっしりとした男らしい体格をしている。お腹は少し出ていたけど、太っているわけではない。股間にあるイチモツはふさふさとした陰毛に覆われて大人の男を感じさせた。太い竿がだらんと伸びて、赤黒い亀頭を覗かせている。背後にある玉袋は大きく膨れ上がっていた。
僕は目をそらして下を向いた。男同士のはずなのに、なぜか顔が赤くなった。おやっさんは石鹸とスポンジを手にすると、僕を腰かけに座らせた。
「お前は、好きな女とかいるのか?」
僕の小さな肩に手をかけて、スポンジで背中を擦ってくる。
僕は首を横に振った。高校生になっても女の子を特別好きとは思わなかった。それに両親が死んでからは、そんなこと考える余裕もなかった。
「そうか……」
おやっさんは一言だけ答えると、スポンジを握る力を少しだけ強くした。背中が泡だらけになると、僕はそこにある桶でお湯を汲んで背中を流してくれるとばかり思っていた。
でも、違った。
「前も洗ってやるよ」
そう言うと、おやっさんは僕の両脇に腕を伸ばしてきた。右手のスポンジで胸の辺りを擦り始め、左手でお腹を押さえるようにする。
僕は突然のことに驚き、腰を浮かして離れようとした。だが、強い力で引き寄せられて、後ろであぐらをかく男の股間に自分のお尻を埋める様に座り込んだ。
「お前は可愛いな」
おやっさんは耳元で、まだ酒臭い息をしていた。
石鹸の泡で二人の間にヌルヌルとした触感が生まれる。僕が身体を硬直させていると、おやっさんはスポンジを放り出し、素手で僕の胸や腹をまさぐり始めた。
「お、おやっさん……。だ、だめだよ」
僕は完全に頭に血が上ってしまい、這い回る手の上に小さな自分の手を重ねた。
でも、おやっさんは手の動きを止めてくれなかった。むしろ嫌らしい手の動きはますますエスカレートする。僕は乳首をいじられ、玉袋を触られ、緊張で縮みあがった竿をしごかれた。耳元におやっさんの舌が這う。僕のお尻の下にある大人のイチモツは硬くなっているのが分かった。
「この前、部屋でオナニーしてたな?」
おやっさんの卑猥な言葉が聞こえてくる。
どうして知ってるの? そんな恥ずかしいこと言わないでよ。僕は出来る限りの力を振り絞って、この状況から逃れようとした。
「い、嫌だ! おやっさん、やめて!」
僕の声が風呂場に響いた。
すると、おやっさんは手の動きを止めた。両脇から手を引っ込めると、その手を肩にかけて僕の体の向きを変えた。僕の目におやっさんの赤い顔と鋭い視線が映し出された。
パシッ――。
僕は頬を叩かれた。おやっさんは僕を叩いた瞬間、目を丸くして少しだけ口を開いていた。でも、僕の体を引き寄せて強く抱きしめると、近くにあった洗面器や椅子を乱暴に払いのけて、冷たいタイルの上に押し倒した。無防備に横たえられた僕の上に、大きな体が重なった。
「や、やだぁ!」
僕は裏切られた気持ちでいっぱいだった。
お父さんのように無口でも優しいおやっさんが好きなのに。でも、この風呂場で乱暴に肌を重ねる男は違う。おやっさんは、僕にこんなことをするために面倒を見てくれていたの?
僕は自然と涙がこぼれていた。
おやっさんは僕の涙から目をそらすように体中をむさぼっている。僕はこんなことをされて嬉しくないのに、体が言うことを効かなかった。舌先で敏感な部分を刺激されて、僕の股間は次第に熱くなっていった。
おやっさんの唇が重なり、肉厚で柔らかい感触が伝わってくる。口の中に入ってくる舌は温かく、粘膜からアルコールの匂いが伝わってきた。僕は力が抜けてしまい、深い悲しみだけが心を支配した。
おやっさんは僕の横に体を寄せると、乳首を舐め始めた。同時に、石鹸の泡が残った玉袋に指先の刺激が伝わった。
「……っ!」
僕は声にならない声を上げた。
おやっさんの手はゆっくりと竿に移動してくる。皮被りの亀頭を剥き出しにすると、その上に手を被せてきた。こそばゆい快感と神経を貫くような強い刺激が体中に走った。僕は自然と身をよじらせた。
「気持ちいいのか……?」
おやっさんは熱っぽい目で僕を見ている。
恥ずかしかった。僕が目をつぶると、おやっさんは僕の手を取り自分の股間へ運んだ。硬く反り返った竿は大きくて太巻みたいだ。棒でもつかむように握っているだけなのに、悦ぶ声が聞こえてくる。
「ああ、いいぞ」
おやっさんは眉間にしわを寄せた。僕は手の中で硬い竿が脈打っているのが分かった。
僕の竿はゆっくりとしごかれた。石鹸の泡の滑りも手伝って、オナニーよりも数倍の快感が襲ってくる。その時間は長くなかったと思う。
「あっ……!」
僕は我慢できなかった。気が付いたら、精液をお腹の上に大量に出していた。竿をしごかれた勢いも手伝って、汚い体液は僕の首元や、おやっさんの頬にも飛んでしまった。
一方的にイカされたのに、とんでもなく悪いことをしたような気がした。僕は相手の頬に付いた精液を拭き取ろうと手を伸ばしたが、おやっさんはその手を軽く押さえて首を横に振った。近くに転がった洗面器にお湯を汲み、体についた石鹸も一緒に洗い流すと、そのまま風呂場を出て行ってしまった。その横顔はとても悲しそうに見えた。
僕はショックだった。それはエッチなことをされたからでもなく、オナニーを見られていたからでもない。おやっさんが、あんな後悔を浮かべた顔を見せたことが辛かった。
おやっさんは言葉数が少なくて自分の感情を表に出すことが苦手なのだ。乱暴かもしれないけど、お酒の勢いに任せて、僕に素直な気持ちをぶつけてきた。
僕だって、本当はあの人のことが好きだ。でも、突然のことに正面から受け入れることができなかった。素直になれなかった自分が嫌だった。
少し風が出てきた。空に浮かぶいわし雲は少しだけ形を崩していく。
僕はおやっさんの飲み残したビールを一口飲ませてもらった。肌寒い体にアルコールが熱を与えてくれる。
「あの時はビックリしただけ。でもあの日から何か変わった気がしたんだ」
おやっさんは静かに僕の話を聞いてくれる。
僕はこの前、お店で流したギルバート・オサリバンの曲を思い出した。
――風呂場での出来事から、さらに半年後。
おやっさんは、あの夜から僕を避けるようになった。でも、それは嫌っているからではないと分かっていた。だから、僕はできるだけいつものように接するようにした。自分も、本当はおやっさんのことが好きなのに、その気持ちを伝えないのはずるいと思った。でも、いざとなると自分の思いを伝えるのは簡単なことではなかった。
ある日、おやっさんの部屋を掃除していた時、一枚のCDを見つけた。見たこともない古い洋楽のCDだった。普段、音楽なんか聞かない人なのに、ましてや洋楽というのが意外だった。
おやっさんが部屋を通りかかり、CDを手にした僕を見つけると、久しぶりに声をかけてくれた。
「お、懐かしいの見つけたな。その中のナントカ・アゲインってのが、好きなんだよ」
そう言うと、僕を手招きしてCDラジカセを取り出した。CDが回転を始め、おやっさんが好きだという曲が流れてきた。
スローテンポのツービートがゆったりとした気持ちにしてくれる。外国人の透き通るような柔らかい歌声がギターの旋律に合わせて響く。
「な。優しくて、良い曲だろ? 俺、英語は分からねぇけど、たぶん歌も、幸せなことを言ってるんだと思うんだ」
おやっさんは口角を上げて、久しぶりに笑顔を見せてくれた。
でも、僕は歌が進むに連れて眉をひそめた。これでも英語が得意なのだ。もし両親が生きていて大学へ行くことができたら、通訳とか英語に関わる仕事に就きたかった。確かに優しく包み込むような曲なのに、その歌詞は残酷で悲しみに満ちている。
僕は迷ったが、目線を落として声を上げた。
「おやっさん、この歌の歌詞知りたい?」
「知ってるなら教えてくれよ。どんな内容だ?」
僕はリピートでかかる曲の旋律に合わせて、丁寧に歌詞を和訳して伝えた。一節、一節、言葉が伝わるたびに、おやっさんも表情を沈ませていった。
最後の一音が静かに消えると、部屋は静寂に包まれた。
「俺、バカだな……。こんな歌だったなんて知らなかった」
おやっさんは赤くなった目をごまかすように、顔をくしゃくしゃにして笑った。
「別れって何処にでも誰にでもあるんだよね。それは突然で、とっても悲しくて辛いのに、一人で抱えて生きていかなくちゃならない。たぶん、そんな悲しみを癒そうとする曲なんじゃないかな?」
僕は後悔した。やっぱり教える必要はなかったのかもしれない。
「アツシ。親が居なくなって、やっぱり寂しいか?」
おやっさんは初めて、僕のことを名前で呼んでくれた。
「寂しくないって言ったら嘘だけど。今はおやっさんと一緒だから」
僕も湧き上がる涙を悟られないように、大きく目を細めて口を開いて笑顔になった。
「あのこと、恨んでいるか。許してくれないか?」
おやっさんは下を向いて、様子を伺うように小さな声を出す。
僕は何も答えずに、恋人の大きな首に手を回してキスをした。その行動に、おやっさんは驚いたような顔をしていたが、すぐに僕を抱きしめてくれた。
肩を寄せ合って見上げた窓はオレンジ色に染まり、いわし雲が空を覆いつくしていた。
――また、独りになってしまった。当然のように。
僕はアローン・アゲインの最後の歌詞を口ずさんだ。おやっさんは夕暮れの空気に溶けていく哀しげな歌を、静かに聴いていてくれる。
「ごめん。暗くなっちゃうね!」
湿っぽくなった空気を払いのけるように、僕は笑顔を作り直した。今日は報告があるんだ。
「僕ね。今度、付き合うことにしたよ」
「どんな奴だ?」
おやっさんは仏頂面で、少し拗ねたような態度でいるかもしれない。
「相手は僕よりも二つ年下でね。とってもカッコイイんだよ。でも凄く純粋で真っ直ぐな人だから」
僕は夏に渓谷で一緒に釣りをした相手と少しずつ距離を縮め、晴れてお付き合いすることになった。初恋とは違った感情。新しい気持ちを持つことができたのは、おやっさんのお陰だよ。
「今度、そいつを連れて来い。品定めしてやる」
まるで娘を持った父親のような言い草に、僕は苦笑した。
遠くからカラスの声が聞こえてくる。山間の丘陵地を切り崩したこの場所には、もうすぐ美しい紅葉が広がるだろう。
「じゃあ、帰るね。また来るから」
僕は立ち上がって手を振ると、名残惜しさを残しつつ背を向けた。
おやっさんは四年前に亡くなった。病室で見取る親戚も誰もいなくて、最後は僕だけが見葬った。
亡くなる直前まで、おやっさんは僕のことを心配してくれた。天国へ旅立つ三日前に遺書を差し出して、残ったものは全て僕に残すから好きにしろ、と言った。一人になった後、僕はいろいろ考えて小料理屋は処分した。それをおやっさんが望んでいたかどうかは知らないけれど、思い出が詰まったあの場所にすがるのではなく、おやっさんからもらった人を愛する喜びを活かす道を選んだ。だから、今は夜の街で、たくさんの人に出会える仕事に就いている。
僕は遠い空の向こうに漂ういわし雲を見上げると、足を止めた。
「僕、間違っているかな……?」
その問いかけに応じるように、背中に一筋の風が吹いた。
振り返ると、上杉源一と彫られたおやっさんの墓石があるだけだった。それでも僕は墓石と重なるように、あの優しい笑顔が見えたような気がした。
五 卓抜なる矢を放て
十二月の曇り空の下、枯れ枝に残った葉っぱが一枚飛んでいく。冬の乾いた風のせいで、肌に突き刺すような寒さを感じる。
俺は白い筒袖に身を包み、黒い袴に足を通すと身の絞まる思いがする。気合を入れようと、左半分だけ筒袖をはだけさせ、肩と胸を冷たい空気にさらした。肌脱ぎをする時は弓を引く緊張感と重なって、極限を漂うような切迫感すら覚える。
自分の身長よりも高く、しなやかな弓を力いっぱいに引っ張った。手を保護するカケを通して右手に、弦の緊張が伝わってくる。射位から二十八メートル離れた的に向けて、狙いを定める。
……今だ!
俺は矢を放った。冬の空気を貫くように駆け抜ける矢は、的を僅かに外れて安土に突き刺さった。
「ちっ!」
苦々しい思いに唇をかみ締めて、外れた矢を睨みつけた。
俺は親父の顔を知らない。おふくろは、俺が五歳の時に死んだと言ったが、それは嘘だと分かっていた。俺はおふくろに内緒で親父のことを調べた。昨日、その調査結果が届いたのだが、伝えられた真実は胸の内を激しくかき乱している。
「藤堂先輩、外しちゃいましたね」
声をかけてきたのは、一年後輩のシゲルだ。
シゲルは本座から歩み出て射位を確保すると、俺と同じように肌脱ぎをして射法八寸の動作を始める。弓を力強く引っ張った形で静止する。遠く彼方の的を狙う眼差しが凛々しい。
……ビンッ!
弦の弾ける音が響くと、矢は真っ直ぐに目標に向かって飛んでゆき、的のど真ん中に命中する。本来、弓を放った後も気を緩めるなと言うが、シゲルは的が命中すると、少しだけ口元を緩ませる。その一瞬だけ見せる表情に、俺は心臓に矢を打たれたような気持ちになる。
対する俺はどうだ? 弓を引けば少しは心も落ち着くかと思ったが、今日は効果がないらしい。それに、体のある部分のせいで、余計にそわそわする。
「先輩。もう弓、引かないの?」
「お、おう。今日は調子良くないからな」
シゲルはボケッとする俺の姿に目を丸くしている。俺は誤魔化すように言葉を並べると、的場から離れた。
俺はロッカールームへ入ると、ため息を一つ吐き出した。
「また、なんだよな……」
黒袴の紐を緩めてストンと落とす。帯を解いて白筒袖を脱ぐと、自分の股間を見つめた。動きやすいように着用しているセミビキニのパンツはくっきりとテントを張っている。
原因はシゲルのせいだ。俺の真似をするように、肌脱ぎなんかして締まった体を見せ付けるから。それに、あの笑顔だろ。平静を保て、なんて言う方が無理があるってもんだ。
俺はシャワールームに入ると、栓を大きく回して勢い良くお湯を流した。流れる水しぶきの音に紛れて、自分の股間に手を伸ばした。半立ちになった竿に手が触れると、すぐに血流が注がれ硬く反り返った。亀頭が膨らみ、鈴口からガマン汁が漏れてくる。もう片方の手で乳首を触りながら、目をつぶった。
妄想の中のシゲルは引き締まった体を恥じらいもなく見せ付けて、俺の胸に飛び込んでくる。
「先輩の胸って大きいんですね」
「シゲル。早く舐めてくれよ」
俺は躊躇なくシゲルの唇へうずく乳首を差し出す。その言葉に答えるように、シゲルは俺の乳首へ吸い付く。小さな舌が優しい刺激をもたらしてくれる。乳首の快感は徐々に股間に集中し、竿がビクンビクンと反応し、シゲルの素肌に亀頭が当たる。
乳首だけではもの足りない。俺はシゲルの頭を押えると、ゆっくりと唇をへその方へ落とし込む。熱く燃えるような股間は、可愛い後輩の小さな口を待っている。
「しゃぶっていいですか?」
シゲルは顔を赤らめて、竿を握ってくれる。俺が催促したのに、さもしゃぶりたくて仕方ないといったように。俺はそのウブな顔に優しく笑って、一つだけ頷く。それを合図に、シゲルは舌を出して大きく口を開き、亀頭からゆっくり口の中に運んだ。
ああ、最高だ……。
俺は温かい舌の温度に悦ぶ。シゲルは口の中で竿をいっぱいにしながら、亀頭や竿の裏筋に舌を這わせる。フェラチオの刺激に俺の雄は反応し、鈴口からガマン汁を漏らす。時々、シゲルは反応を確かめるように、上目遣いで俺を見てくる。その表情が俺の心にダイレクトに響いてくる。
もう、我慢ができない。俺は両手でシゲルの頭を押さえると、竿を喉の奥まで突っ込み、ピストンを繰り返した。乱暴なことして、ごめんな。でも、すげえ気持ちいい!
「……うっ」
俺は勢いに任せて、弓から放った卑猥な矢でシゲルの口の中を汚す。
耳にシャワーの爽やかな音が戻り、目の前には白い壁が映し出された。壁には自分で飛ばしたばかりの雄汁がドロドロと滴っている。
「くっそう!」
俺はその壁を睨みつけると、拳を強く突きつけた。
血は争えないってことか……?
ガキの頃の記憶だ。おふくろは俺の手をつなぎ、遠くに去っていく親父の背中を見送っていた。おぼろげな記憶の中で、おふくろは涙を流していた。
母子二人きりとなった俺たちは、おふくろの実家に身を寄せた。おふくろは昼夜問わず働き通し、俺は祖父や祖母から深い愛情を受けた。特に、祖父は親父代わりとして時に厳しく、時に温かく、俺を逞しく育ててくれた。弓道も祖父の影響で始めたことだ。
おふくろは俺の前では気丈に振舞っていたが、夜中に一人でよく泣いていた。それは子供ながらに、親父のせいだと気付いていて、俺は親父が憎かった。でも、周りの友達は当然のように父親がいて、ごく平凡な父子の幸せが羨ましかった。顔も知らない親父への憧れ。その想いは歳を重ねるにつれ、少しずつ強くなっていった。だから、俺はバイト代をはたいて探偵を雇い、親父のことを調べた。
親父は上杉源一という名前だった。再婚はしておらず、今も独身でいる。浅草で小料理屋を営んで、一人の見習いを住まわせ二人で暮らしているらしい。ここまでは良かった。だが、報告書の最後にこう書かれていた。
――尚、源一氏と見習いの男性は、職業上での師弟を超えた関係にある。
俺は添えられた写真を見て愕然とした。庭の縁側のようなところで、親父らしき中年の男性と、住み込みで働いているという若い男が唇を重ねていた。親父も俺と一緒だった。いや、俺は親父と同じ性癖だったと言う方が正しいのかもしれない。
シャワールームを出ると、俺は着替えて弓道場を飛び出した。どうしても、この目で親父の姿を見たかった。母を捨てた憎しみ、子供が抱く父親への想い、俺は親父の血を継いでゲイになったのか。様々な思いが交差し、胸の内が張り裂けそうだった。
俺は地下鉄を乗り継いで、浅草にやってきた。長身の弓袋は、どこにいても目立つ。外国人の観光客が多く、弓袋を抱えた俺の姿を珍しそうに眺めている。
親父の小料理屋は分かりにくい場所にあった。浅草寺を抜けて、途中、花やしきという小さな遊園地の脇を通った。俺もガキの頃は親父に連れてこられたのだろうか。楽しげな様子に目を細めながら、俺はいくつもの路地を抜けて角を曲がった。
ビルに囲まれた一角に、古びた一軒屋が見えた。看板には「和食 上杉」と書かれている。俺は準備中の札が下がった引き戸の前に立った。でも、いざここまでやってくると、目の前の戸を開いていいものか、決心が固まらなかった。
もたもたしていると、内側から戸が音を立てて開いた。写真で見た中年の男性が現れた。
「おやじ……」
俺はつい声を漏らしてしまった。
その言葉に、男性はいぶかしげな表情をしている。だが、少しの間を置いて、目を大きく開いた。
「……ハジメ? ハジメなのか?」
俺は言葉を失い、大きくうなずいた。
親父は近所の小さな喫茶店へ連れて行ってくれた。その店には客が一人しかおらず、店主と思われる年配の男性も暇そうに新聞を読んでいた。
古びたソファーに、ブレンドコーヒーが二つ並ぶ。
「元気だったか? 母さんも元気か?」
親父の言葉に、俺はまた無言でうなずいた。
「そうか……」
親父は目を伏せると、白い湯気が漂うコーヒーカップを口に運んだ。
写真で見るよりも、親父は俺にそっくりだった。目元とあごの形が瓜二つで、熱いものをすする時に片目をつぶってしまうのは親ゆずりだと知った。
「それは弓か?」
親父はカップを置くと、細長い弓袋に目を移す。
「ああ。じいちゃんに教えてもらって、ずっとやってる」
俺はやっと言葉を出すことができた。今まで病気で声が出なかったように押し黙っていたので、かすれ声になった。
親父は、そうか、と同じ言葉を繰り返す。
俺はそんな話をしにきたんじゃない。胸の内に抱えた怒りや悲しみをぶつけたかった。今まで生で感じたことがない父親の愛情というものを手に入れたかった。
でも、目の前にいる親父はどこか他人のようで、俺は言葉をためらっている。
「俺が悪りぃんだ」
親父が唐突に口を開いた。真剣な眼差しを俺に注ぎながら。
「俺はお前が生まれた後、母さんとは違った意味で別の人に恋をした」
俺は何も言わずに、親父の言葉に耳を傾けた。
「その想いを何度も抑えようとした。でも、できなかった。母さんに嘘を付くことだってできたかもしんねぇが、俺はそれが正しいことだと思えなかった」
親父は目を落とした。言葉を選ぶようにして話しているが、俺には親父が何を言いたいのか分かっている。
「でも、それって勝手じゃないか。周りは不幸にしていいのか?」
俺は親父をにらみつけ、言葉を返した。
親父はその言葉に唇を噛み締めたが、顔を上げると俺の目を見た。
「恋とはそういうものだ。恋は人を幸せにし、不幸にする。裏切られ、打ちのめされ、二度と立ち直ることができない思いをしても、人はまた恋をする」
俺は何も言い返せなかった。
親父は目線をまた弓袋に移して、言葉を続ける。
「弓道は心身鍛錬の道とも言う。だが、弓は使い方によっては人を傷つける」
俺も自分の隣に立てかけた弓を見つめた。
「お前も恋をするようになれば分かるだろう」
親父は初めて穏やかな表情を見せた。その目は少しだけ潤んでいるような気がする。
俺は言われなくても分かっていたような気がする。それなのに、わざと批判めいた言葉で親父を責めたのは、単に父親に甘えたかっただけなのかもしれない。
最後に、俺は小さな望みを抱いて口を開いた。
「おやじ、今、幸せか?」
「……ああ、もちろん」
その言葉を聞いて、どこか安堵する思いがあった。
夕暮れの雑多な街並みを進んでいく電車の中で、平穏な気分に包まれていた。俺は別れ際に、親父に二度と会わないと約束してきた。親父も、お前がそれでいいのなら、と承知してくれた。
もう憎しみはなかった。親父なりにおふくろを大切に思い、親父は自分の道を堂々と歩いている。他人は親父を批判するかもしれない。でも、唯一の息子である俺は、親父の生き方を少しでも理解したいと思った。俺も親離れをしよう。それで十分だった。
次の日は冬晴れの空が広がっていた。道場に続く道は静かで、ほのかな暖かさに包まれている。
「藤堂せんぱーい!」
後ろを振り向くと、シゲルが右手を上げて走ってくる。俺の元までたどり着くと、息を整えながら笑顔を見せた。
「先輩。今日、誕生日だよね! これ大したものじゃないけど」
そう言って、小さな包み紙を差し出した。
「あ。何か、悪りぃな。サンキュ」
俺は自分の誕生日を忘れていた。思いがけない後輩からの、しかもシゲルからのプレゼントに戸惑いつつ、包みを受け取った。
中身を開けてみると、黒い布地に風神の柄が入った下カケがあった。今使っているやつがボロボロで新しいのを買おうと思っていたのだ。
「ありがとう。早速、今日から使わしてもらうよ」
俺はもう一度、礼を言うと、シゲルは的のど真ん中に矢を射た時のあの笑顔を見せる。
「喜んでくれて良かった! 僕、先輩にいつも教えてもらってるから何かお礼がしたかったんだ」
そう言うと、俺と一緒に並んで歩き始めた。
白筒袖に身を包み、下腹をしっかり支えるように帯を締める。袴を履き紐で結わえると、身が引き締まる。さっきシゲルからもらった風神の下カケで三本の指を包み、鹿の皮で作ったカケを身に付ける。これで鋭敏な弦から手が保護される。下カケはまるでシゲルが優しく守ってくれるような感じがした。
本座で一礼をして、射位へ進む。
足踏み。遠くに見える的の正面に立ち横を向いて両足を開く。俺もこんな風にして堂々とシゲルに向き合いたい。
胴造り。両足をしっかり据えて、上半身をしっかりと安定させる。以前はずっと親父のことが頭にあった。でも、それは昨日までの俺だ。
弓構え。矢を構え、自らの呼吸を整える。親父は恋をすれば分かる、と言っていたが、俺だって今、恋をしているんだ。
打越し。弓矢を高く掲げる。この気持ちは何事にも変えがたい。切なくも、喜びに溢れている。
引分け。ゆっくりと弓を引き、的を見つめる。俺はもっと自分を高めたい。シゲルに惚れられるような男になりたい。
会。弦を最大限まで引き、静止する。シゲルへの想いは毎日強くなる。下ガケには温もりを感じ、風神が俺に力を与えてくれる。
離れ。的の正面を目がけて矢を放つ。この想いがシゲルに伝わって欲しい。いや、絶対に伝えてやるんだ!
残心。矢を放った後も姿勢を崩さずに、的のど真ん中に突き刺さった矢を見つめる。シゲル、いつか俺のものになってくれ……。
「先輩、やったね!」
背後から聞こえてくる小さな声。シゲルがあどけない笑顔をしている。後ろを振り向かなくても分かるのだ。俺は振り返らずに、ピースサインを投げかけた。これは俺からのささやかな宣戦布告。俺は愛しい後輩を射止めてやる。
シゲルの心に、卓抜なる矢を放て!
俺は決して恋をしているワケじゃない ~五つの恋に関する短編集~
二〇一七年も後半となりますが、新作を書き上げることができました。
今回は初の短編集として、五つの小さな物語を書きました。どの物語も一話完結で単独したストーリーです。ですが、最初から最後まで順番に読み進めて頂いた方には、気付いて頂けたと思います。ちょっとした工夫を凝らしてみました。本来なら、こういったことをする場合は、執筆前に綿密な計画を立てるべきですが、三作目あたりを書いている途中で急に思いついてしまったので、少し無理が生じてしまった部分があるのも否めないです。
今回は「恋」をテーマにしました。失って気付く恋心、退廃的に生きる自分を救ってくれた相手へのほのかな想い、誰もがうらやむ男の本音と恋、父代わりでもあった師匠に対する恋の追想、実父への思いと後輩への想い。様々な登場人物や境遇の中で、ある人を想い恋焦がれ、愛する気持ちが少しでも伝われば幸いです。
最後までお読み下さり、ありがとうございます。
二〇一七年七月


