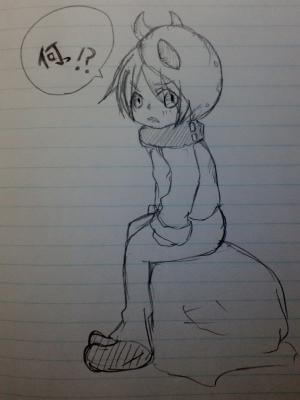いぬかぶり 第7話
お久しぶりです。大学の前期の授業がとりあえず終わった染谷です。
頑張って、久々のアップ作業をします。
本当は、もっとやりたかったのですが、部活とかいろいろあって…。
真夏の空のもとでのスポーツは大変ですね。
ばてますね。
そんな、無駄話をしていても仕方ないので、切り上げます。
ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。
楽しんでくださると、うれしいです。
「高波さーん。彼が佐藤って言う人?」
勢いよく店の扉を開ける男。それは、佐藤が初めて来た日にあっていた男(茶髪)の方だった。
楽しそうに笑っている。すぐに佐藤に近づいて話しかける。
「ねぇ、君が佐藤君?」
後ろから黒髪の方も入ってくる。さらにそれに続いて高波も入店。3人とも驚くほどイケメンだ。
「えぇ…。まぁ、そうですけど。」
「俺、酒井弘人っていうんだ。高波さんと同じ職場だよ。あとは…猫が好き。」
酒井は一人でどんどん話を始めてしまった。少し垂れた目が親しみやすさを感じさせる。
「あ、きょうは杏ちゃんの日だ♡」
嬉しそうに後ろから入ってきた男が言う。店に入ってきた3人の中で最もイケメンだ。
酒井がその黒髪の方に向かって言う。
「鬼塚。先に佐藤さんに自己紹介しろよ。」
「いやだ~。杏ちゃんと話をしてたいな~。」
どうやら、黒髪の方は鬼塚というらしい。カウンターの方から声が聞こえてくる。
「気持ち悪い。昨日、会ったのに彼のことを全力で無視していたらしいじゃない。ほんと、ありえないよね。」
鬼塚の方に冷たい視線を送る杏。本のページをめくる手は止まらない。
「来た!!杏ちゃんの罵声!!いいね。もっと言ってよ!」
鬼塚は嬉しそうに顔を紅潮させる。
「鬼塚気持ち悪いよ、早く自己紹介してよ。」
酒井は鬼塚の髪を引っ張る。
「痛たたた…。」
引っ張られるまま、佐藤の前に出てくる鬼塚。
「俺が鬼塚。高波さんと同じ職場で働いている。カッコいいことで有名なんだ☆」
ウィンクを佐藤に向かってする鬼塚。酒井に髪を引っ張られたままである。
「ドМで、女装が趣味の変態。女の子大好き。いじめてくれる人はもっと大好き。」
横から、酒井が補足説明をする。それを聞いて苦笑いの佐藤。高波は笑うだけ。
「お母さん、サバの煮つけを頼む。」
高波は佐藤・酒井・鬼塚のいるところから少し離れたカウンター席に着いて、注文をする。
「なんかあそこに意味わかんない人がいるんだけど無視しよう。」
酒井が多田の方をみて言う。
「多田君、いつもよくわかんないんだよね。」
多田は非現実的な形をした帽子をかぶっていた。そして、酒井が見た瞬間に決めポーズ。
「それ、****(某アニメキャラの名前)の帽子でしょ。」
食いつく鬼塚。目がキラキラしている。
「僕だったら、そのキャラの服までコピーするんだけどなぁ。」
「どんな格好ですか?」
佐藤は見知らぬ格好をいつの間にかしていた多田に驚きながら、鬼塚に聞く。横から、飛んできて鬼塚の口をふさぐ高波。
「初対面の人にあまりどうしようもないところを見せるものじゃないだろう。」
鬼塚に説得する高波。その高波の腕のにおいをかぐ鬼塚。
「高波君、いい香りがするね。今日も。ちょっとこの姿勢のままでいてほしいな。」
鬼塚の頭を殴る高波。高波の顔が少し赤くなる。酒井はニヤニヤしながら佐藤の方を見ながら、一言。
「ミニスカートヒラヒラ」
「おい!酒井~!!!」
ニコニコしながら言ってしまう酒井。鬼塚のことを腕で黙らせたままツッコミを入れる高波。
「俺はあんたらの後輩だからさ、あんまり強く言うことできないんだけどさ、あんたら馬鹿だろ!!」
カウンターのテーブルを強くたたく高波。杏は関係なさそうに本を読んだまま。
「♪~♪~♪」
ダース●ーダ―のテーマの着信音が店内に響く。誰も何の反応を示さない。
「あのう、誰かの携帯鳴っていますよ。」
佐藤は心配になって店にいる人に聞いてみる。
「酒井さーん、出てあげましょうよ。佐藤君が心配しているよ。」
お母さんが嫌そうな顔をしている酒井に言う。酒井はいやいやながら携帯を取り出す。
「はい、もしもし。」
電話の向こうの怒鳴り声が佐藤たちに聞こえてくる。顔を曇らせる酒井の顔を見て爆笑する鬼塚。
「わかりました。」
そう、一言言って酒井は電話を切る。
「おかあさん、僕の頼んだ奴はあとで帰ってきてから食べるから取っておいて。」
「はいはい。気を付けるんだよ。」
無言で酒井は走って店から出て行った。仕事の関係だろうかと考えながら、走り去る酒井の後ろ姿を佐藤は見送った。
「高波さん、みなさん楽しそうですね。」
佐藤は高波に話しかける。高波は鬼塚を抑えることをやめていた。
「まあな。楽しい…な。疲れるけどな。」
高波は静かに笑った。
藍沢は依頼人のことを隣のビルから眺めながらため息をついた。繁華街の中の古いビル。
その中で、依頼された仕事をこなす。藍沢が佐藤から来たメールに気づいたのは、メールがついてから1日たってからだ。
メールを返したのはそのメールを確認してから何時間もたってから。
藍沢には、佐藤のことをちゃんとした社員に育て優秀な社員にしようという計画があった。
すべては、佐藤が自分の手元に来て1日して終わってしまったが。社長との口論の後に、当の社長から来たメールを見て驚いた。
急な仕事を何軒も一気に持ち込んできたからだ。1カ月に普段やっている量の3倍はあった。
藍沢は横で同じように見張りをしている、本社から来た佐藤の代役の方を見た。彼の名は甲藤といった。
「なあ、甲藤さんよ。俺のところにあんたの上司から恐ろしい量の仕事が舞い込んできたのだが、あの上司は何を考えていると思うか?」
「さあ。私には何も。社長はあなたの行動を気にしていると思います。」
甲藤は窓枠に肘をつく。彼は本社にいる連中のなかでも珍しいくらい細身だった。藍沢は窓の近くにベンチを持ち込み、そのベンチに座って腕を組む。
「どういうことだ、甲藤。社長が何かそう思われることをしたのか?」
頷く甲藤。そして、彼は仕事に出る前に藍沢の行動に注意するように言われたことを話した。甲藤は、社長は藍沢のことが嫌いとしか考えていなかったから、その発言に驚いたといった。甲藤は藍沢の方を見る。藍沢は何かを考えているようだ。
「もしもさ、俺が何か目的を持って社長のことを殴りに行くと言ったらどうする?」
「えっ?」
甲藤は急な藍沢の発言に驚く。
「ど…どういうことですか?」
「そのままだよ。」
「あなたも社長も互いに嫌っているのは明らかなのですが、お互い大人なので実力行使に踏み切らないと思っていたのですが。」
「何回かあいつを殺そうとしたんだけどな…。上手くいかなかったな。」
自分の握りこぶしを見つめる藍沢。彼の口の端を持ち上げる表情は横から見ると美術品のような美しさがあった。
「実際になぐり合ったことがあるんですか?あの、社長に?」
ニコニコしながら頷く藍沢。さすがに、10時間耐久はつらかったよ、と笑う。
「そもそも、なんでそんなに局長と社長は仲が悪いのですか?局長クラスのような肩書の人間と社長は通じ合っていた方が、仕事がしやすいと思うのですが。殴りあうほど仲が悪いと仕事はしづらいですよね?」
椅子から立ち上がり、腕を組みながら繁華街を見下ろす藍沢。見下ろしたまま、呟く。
「彼にとって私は仕事の道具としては最高な存在なのだと思う。できることならば、俺が社長の座を奪いたいぐらいだ。あの社長の手腕は疑わしいものがある。だがな、社長は私のその考えが見えているらしい、すぐに私のことを本社から突き放したよ。支局は本部よりも扱いは下だからね、社長の方の座に上り詰める距離は長くなるわけだ。」
「独立はしないのですか?」
首を横に振る藍沢。
「あの会社はいいものがたくさんある。ゼロから作り始めるより、あるものを拡張した方がいいものが作れる。だから、乗っ取ることを考えている。」
「なんだか、あなたの話は殺し屋の話みたいで…面白いと言ったら失礼ですが、そんな感じがします。」
甲藤は笑う。藍沢は真顔で甲藤を見た。甲藤の笑いが一瞬で消える。
「俺は社長が大嫌いだよ。いつも俺の行動の邪魔をするからね。」
笑いながら話してはいるが、目は一切笑っていない藍沢に甲藤は何も言うことができなかった。
「おい、久しぶりだな。多田。さっきの話何とかなりそうかい?」
Rosaの店先で閉店時間になり、店から追い出された多田が携帯で話をする。電話の先はカロームの社長である。
「ああ。そいつは興味を持ったらしい。こっちから、あれこれ説明するよりお前から直接説明した方がいいと思うのだが…。どうだろうか。」
自分のパソコンとか作業用の器材を詰め込んだジュラルミンケースを椅子替わりにして、多田は話す。一方の社長の方は社長室で、一人で話す。時間は出社時間をとうに過ぎており、事務所に残っている人はほとんどいなかった。
「そうだな。確かに直接会って話をした方が、話が通じると思うな。うん。こっちは大体いつでも会うことができる。なんなら、こっちの連絡先を佐藤って言う奴に渡しておいてくれないか。それで、いつ会えるか調節しようと思う。」
「わかったよ。じゃ、今度ね。今度会うときは、あのアニメのDVDを持ってきてくれ。今じゃ、あれはもう売ってないからね。」
「わかったよ。今度な。日程があったら。」
いぬかぶり 第7話
体力に自信がないのに、ソフトボールをしています。
8月にもなると、ノックを受けるだけでも大変です。
焼けないようにするのも大変。
全身汗だくになるので、日焼け止めなんて落ちているにきまってます。
でも、焼けすぎるわけにはいきません。
一応、女の子なので。
といっても、地黒という事実は覆りません。
さて、次にアップするまでに、どれだけ元の状態をキープできているかが楽しみです。
ということで、ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。
また会えることを期待しています。
では。