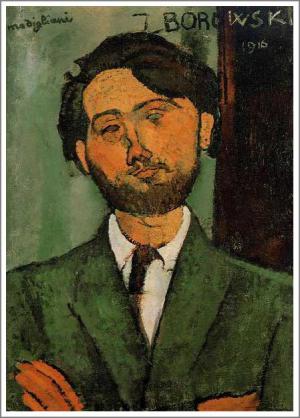求愛の彷徨(さまよい)
1
石川忠雄は、新潟県の地方都市で暮らしている。大手の製造業向け工具や機械の販売会社で働くサラリーマンである。生まれは、現在住んでいる町からさほど遠くない、山間の小さな村で生まれた。高校はこの町のそこそこの進学校に通い、やはりこの町の短期大学を卒業した。
高校の同級生は、大概四年制の大学に進学したが、忠雄はあまり勉強が好きでなかったので、受験勉強をしないで入れる学校を考えたら、地元の短期大学が妥当だったのである。
忠雄の高校時代は「普通」だった。普通というのは、最も多数の生活と同じだったことを示す。一般に持たれる高校生のイメージは、スポーツなどの情熱を持って打ち込むことがあり、良き友人に囲まれ、勉強もそこそこ楽しく、そして爽やかに恋愛経験をするといったところだろうか。しかし、実際にはこのようなケースは稀である。
最も一般的な高校生とは、スポーツなどとりあえずの興味で始めるが、途中で飽きたり思わぬトラブルでやめたりして、だんだん自分がそれを望んでいるのかわからなくなりながら、結局、暇つぶしのように続けている。友人はいるけれども、互いの利害の衝突で、離合集散を繰り返す。勉強は間違いなくつまらないのだが、拒否する勇気もなく、怒られない程度に嫌々こなす。こんなところであろうか。
最後に恋愛だが、高校生の最大の興味はここだろう。もちろん世間が望むような「爽やかな恋愛」を夢見ているのだが、そのような理想な恋愛関係と、内に秘めた激しい性欲が競合して、ぎくしゃくとした男女の付き合いになってしまう。大体、理想の男女関係とは精神的なつながりが大切なのか、肉体的な吸引力に身を任せるべきなのかわからない。そのような、葛藤の中の恋愛なのである。実際に異性と交際できた者も、できなかった者も、このような葛藤だけは体験する。考えてみれば高校生に限らず、人間は一生この葛藤の虜となっているのかも知れない。
とりわけ高校生にとっては、セックスを体験したかどうかは重要な問題だ。特に男子はどんな形のセックスであれ、体験できればヒーローであり勝ち組である。体験できなければ、負け組で灰色の青春時代となってしまう。一生を長い目で見れば、この体験の多少の遅い早いは大した違いではないが、男子高校生には、勝負の勝ち負けのような重大さがある。だから、恋愛においてその恋愛の対象よりも、仲間内のステイタスが行動のモチベーションとなっている場合が多い。だから世間が期待する「爽やかな恋愛」なんてないに等しいのである。
忠雄が「普通」の高校生だったということは、このような葛藤の真っ只中にあったということだ。現に彼は幾度となく、女子と恋愛関係になろうと挑戦した。しかし、忠雄は気のある女子の前では緊張してしまい、まともに話せなかった。まあ、高校生なら誰しもその傾向はあるが、スポーツができるとか、勉強ができるとか、売り込むものがあれば、そのたどたどしさも評価されるが、忠雄にはそのような「売り」は残念ながらなかった。
忠雄は、自分に「売り」がないから恋愛ができないのか、恋愛がうまくいかないから「売り」がないのか、その都度都合の良い方に言い訳をしていた。そのような無気力で、楽な短大進学を選び、恋愛経験もないまま高校生活を終えようとしていた。
だが、彼の高校生活は最後の最後に、奇貨が待っていた。それは、忠雄が進学する短期大学の合格発表日のことである。
短大の合格発表日、忠雄は合格は間違いないと思いながらも、今春から始まる新生活の舞台を、下見しておこうという思いで、短大のキャンパスまで発表を見に行った。自分の合格を確認した後、さして大きくはない短大のキャンパスを散策していると、幼なじみで同じ高校にいた、中山あゆみに行き会った。
「ああ、石川くん。」
忠雄が、その声に振り返るとそこには、グリーンのTシャツに紺のミニスカートを履き、グレーの洒落たジャケットを羽織ったあゆみが走りよってきた。
「あれ?中山?なんでここにいるんだぁ。」
忠雄は驚いた。驚いた訳は、あゆみは東京の大学に進学したと思っていたからである。
「あたしもこの学校に入るんだよ。」
「ええ!なんでー?東京へ行くんじゃなかったんか。」
「ううん、やめちゃった。」
忠雄は不審に思った。何故なら、あゆみは彼等の高校で優等生だった光彦という男と付き合っていて、東京の一流大学を目指している光彦を追いかけ、あゆみも東京の大学に進学するように勉強を頑張っていると聞いていたからである。
「だって、彼氏がいたんじゃぁ。」
「うん、別れちゃつたの。」
あゆみは少し顔を曇らせて、呟くように言った。
「別れたって、、、それは、、えぇー。」
と、忠雄が聞くと、あゆみは
「話聞きたい?じゃあどっかでお茶でも飲もうか。」
と、忠雄を誘った。忠雄はあゆみな申し出を承諾し、二人は校門に向かって歩きだした。
あゆみは忠雄の家の近くに住んでいる。幼いころから一緒に良く遊んだ。中学校までは同じクラスで良く話もしたが、高校ではクラスが違ったので、あまり話す機会はなかった。加えて、高校生になったあゆみは、突然女らしくなり忠雄には眩しく感じられた。そこに優等生の彼氏ができたと聞いたので、もう自分とは違う世界にいると思い込んだ。それでも、あゆみの動向を忠雄は気にしてはいた。
あゆみと歩きながら忠雄は、彼女の姿をよく見た。あゆみは、女にしては背が高いが、スレンダーな四肢を持っているので、華奢に見える。しかし、あゆみのヒップは横と後ろに広がり、腰のくびれと対象して絶妙な丸みになっている。そして、胸は程よく前に突き出し、大きすぎないが存在感を出している。モデル体系と言っても良いブロポーションで、整った顔立ちと合わせて、あゆみは美人と呼ばれる容姿をもっていた。
校門を出たところに喫茶店はあった。二人はその店に入り、窓際の席に座った。忠雄は、正面からあゆみを直視した。そこには、幼いころと違った女らしいあゆみがいた。忠雄は、幼なじみの気安さをすっかり失い、緊張してしまった。忠雄は、上擦った声で聞いた。
「なんで、あいつと、、、光彦だっけ、、別れた?」
あゆみは、忠雄の緊張した態度に吹き出しながら答えた。
「もう!忠雄ちゃんたら、何言ってるのかわからないよ!」
あゆみは、幼なじみの親しみを込めた呼び方に変えていた。
「うん、、、わりぃ、、」
「謝らなくてもいいわよ。忠雄ちゃんのそういうところ、ホットするなぁ。あいつなんか何時も偉そうで。」
「あいつて、光彦のこと。」
「そう、あいつ勉強できたもんね。一流国立間違いなしみたいよ。」
「勉強だけで、人間は決まらないよ。」
「うん、そう思いたいけれども、やっぱ世の中はね。あたしも、少しでも追いつこうと頑張ったんだけどなぁ。元があまり良くないからね。」
「そんなことねぇよ。」
「ははっ、あたし忠雄ちゃんと同じ程度だよ。背伸びしてもだめだった。」
「おっ、俺だってなぁー。」
「いいじゃない。あたし達似た者同士で。」
「そっかぁー。でもあいつ、なんでお前みたいないい女をふったんだぁ。」
「自分で言うのもなんだけどさぁ、あたしはいい女だと思うよ。でも、お似合いの相手ではなかったみたい。殿様と花魁みたいな関係だったのよ。二流大学でも東京の学校行けば、あいつとの付き合いが続くんだと思ってたら、『東京へ行ったら君と付き合わの付き合いがない』だってさぁ。」
あゆみは更に続けた。
「そうしたら、もうやる気なくしちゃってね。勉強しないでも行ける、この学校でいいやと思っちゃったわけなの。それで、そういえば忠雄ちゃんもこの学校だったなぁって思って、さっき探していたのよ。」
忠雄は答えて言った。
「まったくあの光彦ってやつは、ひでぇやつだなぁ」
「ほんと、ほんと、気持ち良く勉強できたのは、あたしを抱いてスッキリしていたおかげなのにねぇ」
忠雄は、あゆみの口から「抱いた」という言葉が出たのにたじろぎながら言った。
「だっ、抱いたって、お前あいつと、あの、、」
あゆみは淡々と答える。
「当たり前でしょ。男と女だもん。」
考えてみれば当たり前だが、忠雄は自分の目の前にいるあゆみの性体験の告白は、異次元世界の出来事のように感じた。忠雄は何を話したら良いか解らなくなり、
「そんなこと、どこでやってたんだ。」
と不躾で素っ頓狂な質問をした。しかし、あゆみは不快にも思わず答えた。
「最初はね、あいつの家でしたわ。家の人が留守の時にね。後は、人目につかないところを見つけてね。ホテルに行ったこともあるのよ。」
「ええっ!ホテル!高校生なのに!」
「あいつがね、まわりを気にしなくてもいい所で、ゆっくりセックスしたいなんて言い出して、それで行ったの。あいつ、自分で誘ったのに、ホテルに着いたらあたしにチェクインさせて、こそこそしてるのよ。」
忠雄は、あゆみの話の内容に加えて「セックス」という、具体的な言葉をあゆみの口から聞いて興奮と緊張でパニック状態になっていた。忠雄はまるで、卑猥な言葉を投げかけられた少女のように赤くなって下をうつむいた。しかし、頭の中は、あゆみのセックスの様子を想像し、そのため忠雄は勃起しそうな自分を必死にこらえていた。
その忠雄の様子を見て、あゆみはからかうように言った。
「あらあら、童貞君には刺激が強すぎたかしら。ウフフフ。」
「ばっ、馬鹿にするなよ!」
「そういう忠雄ちゃん可愛いわ。あたし好きよ。なんか、ホッとするのね。」
忠雄は、あゆみから性体験の赤裸々な告白と「好きよ」という気持ちの打ち明けを聞いて、彼女とセックスに至れるという期待を大きくもった。そして、このチャンスを何とか生かすための行動をしようと決意した。
とは言え、どうすればいいのかはわからずにいた。忠雄は、取り合えず反応した。
「おっ、俺だってなぁ!」
「俺だって何?」
あゆみは、たたみかけてきた。
忠雄は、とにかく世の中に有りがちな口説き文句を言ってみることにした。
「あ、あゆみ、、、ちゃん。俺、こ、子供の頃から、お前のこと、、、すっ、、好きだったんだ。」
言葉は途切れ途切れとなり、忠雄は汗びっしょりになっていた。しかも、全身がぶるぶると震えだした。あゆみは、その忠雄の様子を楽しむかのように言った。
「ありがとう、嬉しいわ。それで、どうしたいの?」
忠雄は、この言葉であゆみが自分を誘っていることを確信した。もう自分の欲望を面に出すべきだと思った。
「あの、あ、あの、お前と、、、セッ、、あの、お、お前が欲しいんだ。」
たどたどしく語る忠雄に、あゆみは答えた。
「忠雄ちゃん、お金持ってる?」
「え、ああ、一万円ぐらいなら。」
忠雄は、家を出るときに母親から貰った金があったので答えた。「まさか、金が欲しいのか」と一瞬怪訝に感じたが、どうもそうではないらしい。あゆみはホテル代があるかと確認したのだ。
「じゃ、行こうか。」
忠雄は「どこへ?」と確認しようかと思ったが、聞かないであゆみに従うことにした。もし、あゆみに騙されてひどい目にあったとしても構わないし、このチャンスを生かすためなら、一生を捨ててもいいと思った。
あゆみに促され、立ち上がり店を出た忠雄だが、あゆみと並んで歩こうとすると、緊張のあまり真っ直ぐ歩けなかった。しかも、鼓動は大きく高鳴りこのまま倒れるのではないかと感じるぐらいだった。あゆみは忠雄のその様子を見て、忠雄と腕を組み恋人同士のように寄り添った。あゆみに支えられて、忠雄は少し落ち着きを取り戻した。実は、忠雄のこのあまりに純情な姿はあゆみにとって望ましいものだったのである。
そのように歩いて、二人は駅の横町にあるラブホテルに着いた。忠雄は先程のあゆみの話から、自分がリードしてチェックインしなければと思ったが、あゆみが今日は自分がするからいいと言ってフロントに向かったので、ついて行くだけになった。部屋の鍵を渡され、二人はエレベーターに乗り目的の階の目的の部屋を見つけ、鍵を開けて中に入った。
2
ホテルの部屋は薄暗く、多少カビ臭い匂いがした。部屋の殆どをダブルベットが占めていて、その隙間に小さめのソファーとテーブルが置いてあった。部屋の隅にある磨り硝子のドアを開けると、そこはバスルームとトイレになつているらしい。忠雄は、広いベッドを眺め、これから行われるであろうあゆみとの情事を想像し、既に官能の頂点へと到達していた。
忠雄は、あゆみを抱き寄せようとした。あゆみはそれに導かれるかのように、スッと忠雄の腕の中へ滑り込んみ、二人は唇をあわせた。忠雄はあゆみの唇の柔らかさと身体の弾力を感じた。あゆみは、腕を忠雄の首に回し、自分の唇を更に強く忠雄の唇に押し付け、舌を彼の口の中に挿し入れた。忠雄は、あゆみの舌を受け止め、自分の舌を絡め合わせた。
あゆみは、一旦忠雄から身体を離して言った。
「あたし、シャワー浴びてくるね。汗かいちゃって気持ち悪いわ。」
と言って、バスルームに向かった。部屋の隅のドアを開け、あゆみは入って行った。最初に、バスタブに湯を入れる操作をする音がした。そして、あゆみが服を脱いでいる気配が磨り硝子越しに見えた。
忠雄は、バスルームを出たあゆみがどんな姿で現れるのか想像した。全裸で出てくるのだろうか。それとも、バスタオルを巻きつけてくるのであろうか、忠雄の想像は限りなく広がった。そして、期待をしながらひたすら待った。
シャワーの音が止まり、あゆみは出てきた。その姿は、忠雄の予想に反して服を着ていた。ただ、靴下と上着は着けずそれらを手に持っていた。あゆみは、忠雄の当惑を感じたのか、声をかけた。
「忠雄ちゃんにね、あたしの服を脱がす楽しみを残しておいてあげたのよ。」
忠雄はその通りだと思い、早くあゆみの服を脱がそうと立ち上がったが、あゆみに遮られた。
「忠雄ちゃんも、お風呂に入っておいでよ。あなたは、裸で出て来てもいいわよ。」
少し焦らされていると感じたが、忠雄はあゆみに従った。
忠雄はバスルームに行き、服を脱いで半分ほど湯が入っていたバスタブに身を沈めた。先程、この湯に全裸のあゆみが入っていたのかと思うと、忠雄の陰茎は痛いほどの最高の勃起状態になり、今にも爆発しそうだった。忠雄は、そそくさと身体に石鹸を塗りつけシャワーで流した。そして、パンツとズボンを履き、上にはシャツを羽織り、数カ所だけボタンを留め、あゆみの待つベッドルームに向かった。
ベッドルームに戻ると、忠雄の予想外の事が起こっていた。あゆみがベッドにうつ伏せになり、嗚咽しながら泣いていたのである。忠雄は、恐る恐るあゆみに声をかけた。
「あゆみ、どうしたの。」
あゆみの顔を覗き込むと、顔をくしゃくしゃにして、悔しさと絶望を表していた。
「抱いて、いいから抱いて。」
忠雄は、以外な展開に戸惑いながらも、あゆみの涙の原因が理解できた。あゆみは、恋人に捨てられた悲しみから立ち直っていなかったのだ。そして、その癒やしを忠雄に求めた。だが、いよいよ忠雄に抱かれ、失った恋との決別をする間際になって、悲しみと悔しさの虜となってしまったのだ。
忠雄は、良い対処方法など考えつかなかった。優しく慰めるのもこの状況だは変に思えた。それよりも何よりも、もう忠雄の興奮は頂点に達していて、自制して止めることなど不可能だった。忠雄は、あゆみが抱いて欲しいと訴えているのだから、抱いてやるのがあゆみのためになる、と信じ込むことにした。
果たして、この忠雄の選択は正解だった。悲しみにくれる女を前に、「自分を大切にしろ。」とか、「また、素敵な人に会えるよ。」などの優しさは、恋愛小説やドラマの中では使われるが、少なくともこの時のあゆみには不必要なものだった。あゆみは、今の自分になまじっかの優しさは、心を潰してしまうように感じた。きっと、誰かに優しくされれば潰れそうな心を守るために、彼女はその相手に、身体を捧げるしかなくなるだろうと感じていた。
それは余りに惨めだと思ったあゆみは、自分から誘い、しかもなまじの優しさなど出しようもない、経験のない忠雄が適任だと思い選んだのである。あゆみは、自分の感情やモチベーションを作り出すのは、脳が半分で性器が半分だということを経験でわかっていた。自分の肉体と性器に対する激しい接触が、傷ついた心を安定させると感じていた。それは、世間では「ふしだら」と言われるかもしれないが紛れもない事実だとわかっていたのである。
忠雄は、泣き伏しているあゆみを後ろから抱きしめた。あゆみの髪とうなじにキスをして、ベッドに押し付けられているあゆみの胸に手を入れた。先程気がつかなかったが、あゆみは既にブラジャーを外していた。柔らかいあゆみの乳房の感触が、忠雄の手につたわった。忠雄は、あゆみの身体を少し持ち上げるようにして、あゆみを仰向けにさせた。そして、乾いた涙の跡の残る彼女の顔にキスをした。
もう一度、あゆみの唇に深いキスをしてから、忠雄は、あゆみのTシャツをたくしあげそのまま脱がした。あゆみの形の良い乳房が忠雄の目の中に飛び込んできた。忠雄はたまらずあゆみの乳房にむしゃぶりついた。するとあゆみから「あっあー」と性感を感じた反応の声が漏れた。
忠雄は、あゆみの乳首を吸いながら彼女の乳房を揉んだ。女にしかないこの身体の部位に、今まさに接している自分、その姿を考えただけで忠雄は興奮した。彼の愛撫はあゆみの乳房から腹へと移り、いよいよあゆみのスカートに手をかけた。スカートは、ボタンを外して脱ぐタイプのものだっが、これもあゆみ自身によって、既にボタンは外してあった。忠雄は、スカートとその下の下着を一気におろした。そこには、あゆみの陰毛と足の間に隠れた肉襞の割れ目の一部が覗いた。
忠雄は、あゆみの性器をじっくりと眺めたいという欲望にかられたが、あゆみ嫌われるのではという懸念がその欲望を抑止させた。彼は、スカートと下着をあゆみから剥ぎ取り、彼女を全裸にすると自分も着ていた衣服を取り去った。
裸になった忠雄は、同じく全裸のあゆみの身体を抱いた。自分以外の肉体との深い接触は、忠雄にとって乳児のころの母親との接触以来だった。あゆみのすべすべとした肌の感触は、とろけるような快感を与えてくれた。
そして忠雄は、あゆみの足の間に自分の片足を挟ませて、太腿を使ってあゆみの性器を擦った。擦るたびにあゆみから、「ああ、ああん。」と声が漏れはじめた。あゆみの性感も上がりはじめていた。忠雄は、しばらくの間、足での性器への摩擦をしながら、あゆみの乳房を揉み、また、彼女にキスの雨を降らせた。忠雄がそれらの動きの激しさを増していくと、あゆみの興奮も高まり、かなり大きな声で彼女は喘ぎだした。
あゆみの高まりを感じた忠雄は、彼女の股に挟ませた自分の足を抜き、手を使ってあゆみの性器を愛撫した。忠雄は女の性器は敏感であるという、雑誌などで見聞きしてきた知識を動員して、慎重にあゆみの足の間を弄った。肉襞の割れ目に沿ってまずは膣口は避け、陰核を探り当て指の腹で揉んだ。指の動きに合わせて、あゆみは「ああー、あっああー」と喘ぐ。忠雄はあゆみの肉体を押し開く入口に触れたように思えた。そして、指を膣口に移動し、少しずつあゆみの膣の中に指を挿し入れた。指を入れてみると膣の中は案外広く感じた。それは男のすべてを飲み込む異次元への入口のようにも感じられた。
そして、忠雄はあゆみとの肉体の結合を試みた。あゆみの両足を開かせその中に自分の両足を入れ、指で膣口を探りながら陰茎の亀頭を当てた。忠雄は、亀頭の先に柔らかいあゆみの膣口を感じると、ぐっと陰茎を突き立てた。すると、忠雄の肉棒はあゆみの中に収まった。
あゆみは「ああー」と大きな声で喘いだ。しかし、忠雄の肉棒は少々の刺激で爆発しそうで、彼はあまり大きな動きができなかった。でも、忠雄の小さな動きにあゆみは反応し、全身をビクビクと振るわせた。忠雄の動きに合わせあゆみは腰を動かす。その刺激に耐えられず、忠雄は射精をしてしまった。だが彼は、射精後もあゆみの中の肉棒を動かし続けた。若い忠雄の陰茎は、一度の射精ぐらいでは萎縮せず、そそり立ったまま、あゆみの膣の中をかき回した。あゆみの興奮もさらに高まり、「ああー、いいー、いいー、気持ちいいー。」と叫びながら、忠雄の身体に抱きつき、「ああー、いくー、いくー。」と絶頂の寸前であることを伝えてくる。忠雄はなんとも言えぬ征服感と満足感でいっぱいになった。そして込み上げる興奮のすべてを、二度目の射精に込めて、あゆみの中に爆発のように吐き出して果てた。
あゆみは、全身を振るわせながら忠雄を強く抱きしめ、忠雄の射精を受け止めた。セックスを始める前のあの悲しい気持ちはかなり晴れた。確かに光彦という相手は失ったが、光彦が与えていたあゆみの肉体への喜びは、光彦に代わって与える者がいる。自分を愛し自分に興味を持ち、そして肉体に接触を求める者がいる。あゆみも大きく開いた喪失感を埋められたと感じた。
情事を終えた二人は、暫く抱き合った。互いの温もりが気持ち良く感じた。そして忠雄はあゆみに言った。
「あゆみ、凄く素敵だったよ。お前は最高さ。」
すると、あゆみがいたずらっぽく言った。
「ウフフ!、最高って、忠雄ちゃんあたししか知らないじゃないの」
「あっ!そういうこと言うかぁ」
「ごめん、ごめん、そんな忠雄ちゃんが好きだから、ついついからかっちゃうの。」
「本当に俺のこと好き」
「好きだよ。だからセックスしたんじゃない。それから、さっきは泣いたりしてごめんね。」
「いいよ。これからはお前が辛いときは俺が助けてやるからな。」
二人は、仲の良い恋人同士になったように見えた。しかし、人間の心は複雑である。理屈や見た目から想像もできない展開が待つ。
だが、とりあえず忠雄には夢の船出となりそうな予感がしていた。不安と言えば、あゆみが今後の二人の関係について、家族や新しい学校の友達に内緒にしようと提案したことだ。家族には結婚にでも至らない限り、バツが悪いので内緒にするのはわかるのだが、新しい友人には、この美人の恋人を自慢することを、忠雄は楽しみにしていた。
でも、忠雄はあまり深く考えなかった。何にしろ、今日この体験ができたこと自体忠雄には、幸運としか言いようがなかったからである。
3
四月になり、忠雄とあゆみは短期大学での新しい生活を始めた。忠雄は、学校の近くにアパートを借りて住み始めた。両親に「短大の勉強は何かと大変だから」と適当な理由を付け、実家からでも通学不可能な距離でもないのに、わざわざ家を出た。もちろん目的はあゆみと何時でも愛し合える場所が欲しかったからである。
忠雄とあゆみは、あの合格発表の日から二回、町で待ち合わせて会っていた。新生活の買い物という名目で落ち合って、実際買い物もしたりしながら、少し遠回りをして、郊外の人気のない夕暮れの公園で木陰に潜り込んで愛し合った。
野外でのセックスは経験の少ない忠雄には、落ち着かないものだった。だが、むしろその、落ち着かなさが早漏を防止していたようにも思えた。あゆみは、慣れているらしく野外でも絶頂に至っていた。
また、忠雄は面白い事に気がついた。スカートなら、下着だけ脱げばセックスはできる。いざとなれば、スカートを下ろして局部を隠すことができる。女がスカートを身に付けるのは、このためかも知れないと忠雄は考えた。
女というものは自らの肉体を固く守っているものだと、忠雄はセックスを体験する前は感じていた。しかし、あゆみという女から、その肉体、その性器を実感してみると、すべての女が自分の性器に男が接触してくるのを、心待ちにしているように感じ始めていた。特にミニスカートはそんな願望の、最も露骨な表現のように思えた。あゆみは、ほとんどミニスカートで出歩く。それは、忠雄にとって自分に対するセックスアピールとも取れるが、同時に他の男たちへの誘惑でもあることに、彼は少し嫉妬覚えた。
忠雄のアパートへの引っ越しは、一日で終わった。それほど遠くない場所でもあるから、生活必需品だけあれば充分と判断したからである。引っ越しの日は、同級生や友人は皆、自分たちの新生活の準備に忙しかったので、忠雄は両親に依頼するしかなかった。父親がトラックを手配して、持っていく荷物を積み込んだ。そのまま、アパートまで運び荷物を下ろした。朝から始めて昼過ぎには、作業はほぼ完了した。
母親は、「わざわざ家を出て、こんな所で暮らさなくてもいいのに。」とブツブツと文句を言いながら、部屋の掃除をしていた。実家からの通学でも、実は何の問題ないのに、本当の思惑を隠し、欺いて両親に金を出させ、引っ越しの手間までかけさせている自分に対し、忠雄は少し済まない思いがした。すっかり片付いたところで、忠雄の父親が微笑みながら言った。
「うん、いい部屋になったなぁ。まあお前、勉強もしっかりやれよ。」
この父親の言葉で、父親が忠雄の本当の意図をわかっていることを知った。もちろんあゆみとのことを具体的に知っている訳ではないが、この部屋で繰り広げられるであろう、息子の青春のドラマを予見しているかのようであった。しかも、それを容認している父親に対し、忠雄は、初めて男らしさを感じ、尊敬の気持ちが少し湧いた。
短期大学の入学式には忠雄の両親も参加した。忠雄はあゆみの姿を探しそして見つけたが、あゆみも両親と共に参加していたので、約束通り声をかけるのはあきらめた。
学校では、授業前にガイダンスとオリエンティーションの日が設けられた。忠雄は、アパートから歩いて学校へ出かけた。忠雄の学部の説明会場に向かい、そこで履修登録の説明を受けた。空いた時間に、あゆみを見つけたいと思ったが、学部が違うため学内では見つからなかった。終了間際、忠雄はあゆみの携帯に電話した。あゆみは明るい声で電話にでた。
「あっ、あゆみ。もうそっちは終わったかい。」
「うん、今終わったところよ。」
「そう、終わったら俺のアパートに来ないか。」
「うん、いいよ。」
「じゃあ、校門出たところで待ってるわ。」
忠雄は、あゆみと連絡が取れたことが嬉しかった。忠雄のアパートを舞台にあゆみとの「愛の生活」が始まる予感は、忠雄を幸福感の絶頂に押し上げた。
あゆみと校門で落ち合うと、二人は忠雄のアパートに向かった。忠雄はあゆみと手をつなぐか腕を組むかしたかったが、「回りに知られたくない」というあゆみの希望を尊重して、横に並んだだけで歩いた。あゆみもそれに従っていた。
アパートに着くと忠雄は入口の鍵を開け、あゆみを中に招き入れた。あゆみは「あら、いい部屋ね。」と月並みの世辞を言い、部屋の中心に置かれたテーブルの前に座った。忠雄の部屋は、居間と言える六畳の畳の間と二畳位の台所、そして狭いバスルームとトイレが一つになって設置されていた。部屋があまり広くないため、忠雄はベッドを置かず布団を上げ下げして寝床にしていた。
あゆみは、忠雄の部屋でくつろいだ。座り方も半分寝そべるようなラフな恰好で足を投げ出し、ミニスカートの中の下着が見えていても気にしなかった。二人は、今日の履修登録の話をし、一緒に履修できる科目を探したが、忠雄は「技術工学部」という理系の学部で、あゆみは「人間関係学部」というどちらかと言うと文系の学部だったので、共通の授業は一科目しかなかった。
そんな話をして午後六時になるとあゆみが言った。
「あっ、もう六時だ。忠雄ちゃんあたし八時には帰らなくちゃいかないから。」
帰るまで後二時間と告げるあゆみの意図を、忠雄はすぐ了解して言った。
「じゃあまず風呂に入るかい。」
と聞くと、あゆみは、
「時間もったいないから一緒に入ろ。」
と答えた。二人はそのまま服を脱いで狭いバスルームで身体をぶつけ合いながら、シャワーを浴びた。あゆみの白く細い姿態が忠雄は眩しかった。
バスルームを出て、二人は一つのバスタオルで身体を拭きあった。そして部屋に戻り忠雄は急いで、押し入れから布団を引っ張り出した。全裸で二人が布団に滑り込んだところで、忠雄が思い出したように、机から昨夜夜中に自動販売機で買ってきた、コンドームを出した。
「これ用意しといたんだ。あゆみを傷つけちゃいけないからな。」
あゆみは答えた。
「あっ、ほんと、ありがとう。」
「俺は、使わなくてもいいんだけどな。責任は絶対取るつもりだからな。」
「でも、使った方がいいわよ。忠雄ちゃんのためにもね。」
実際のところあゆみはホッとした。忠雄にいつ避妊を願い出て良いものか、悩んでいたところだった。あゆみは光彦との付き合いで、初体験こそ避妊をしなかったが、二回目から光彦は避妊具を用意していた。恋愛に舞い上がっていた当時のあゆみは、光彦の準備の良さに少々がっかりした。恋とは熱病のようなものである。愛の行為におけるリスクは避けるよりも、受け止める覚悟を持つことが、いやが上にも恋の炎を燃え立たせるものだ。そのような体験のあるあゆみは、忠雄に避妊を頼むことをためらっていたのである。
そういう意味では、あゆみは忠雄の「責任を取る」という宣言は嬉しかった。しかし、この時にあゆみには、忠雄に一生をかける覚悟はなかったのだ。あゆみは今始まった新生活に新しい出会いを期待していた。では何故忠雄と付き合っているのか。それは、女の肉体の喜びを知ってしまった彼女は、セックスする相手がいないという状況が恐ろしかったのだ。取りあえずでも、安全で安心なセックスの相手をリザーブしておきたかったのだ。
忠雄とあゆみは、全裸で滑り込んだ布団の中で、互いの肉体をぶつけ合い始めた。忠雄の部屋は、夕暮れの明るさをまだ残していたので、あゆみの身体をはっきり見ることができた。忠雄は今日こそあゆみの性器の形を目で見てみたいと思った。忠雄はあゆみの足を押し広げ、その間にある割れ目を見た。
「やだー、忠雄ちゃん恥ずかしいからそんなに見ないで。」
と言いながらも、あゆみは忠雄の凝視を容認し、なおかつ、忠雄が自分の性器にキスをしてくるのを待っていた。忠雄は、あゆみの性器の襞を指を使って広げて見た。そこには、大きく開いた膣口と小さな穴があった。襞の包皮をめくってみると小さく突起した陰核もあった。忠雄は、あゆみの性器に得も言われぬ愛おしさを感じ、むしゃぼるようにキスをした。
あゆみは忠雄に性器にキスをされ、挿入とは違った快感を味わっていた。実はあゆみは、性器にキスされるのが好きである。あゆみは自分の最も大切で敏感の身体の部位に、口を付けるという愛情行為に対して、快感を感じることは、当たり前と考えていた。また、友人たちに聞いて見ても「快感を感じる」という者が多くいた。しかし、彼女たちは彼女たちの母親から受け継いだ「女の性器は汚く恥ずかしいもの」という感覚も多少残っていた。それが、自分から「性器にキスをして欲しい」と要求することをとどまらせていた。
あゆみの膣に舌を挿し入れながら、忠雄は「この女は俺に全てを預けている。」という、あゆみとの共生感に安心を感じ、感激のような悦楽を欲しいままにしていた。充分堪能した後、忠雄はコンドームを装着し、あゆみの中に入り込んだ。忠雄は、数回のあゆみとのセックス体験で、一回の射精で彼女を絶頂まで持っていく技を習得していた。加えて、コンドームの使用は、刺激を軽減するため、今までより激しく、あゆみの膣の中を暴れ回ることができた。その忠雄の激しい動きと、あゆみの肉体に対する強い執着から生じる執拗な愛撫は、あゆみに今までにない性感の高まりをもたらした。二人はめくるめく官能の嵐の中で絶頂へと達した。
あゆみと忠雄は、絶頂から果てた後、余韻を楽しむように、抱き合っていたが、忠雄が身体を離し、あゆみの横に仰向けになると、彼女は身体を半身に起こし、忠雄の陰茎を手に取った。そして、忠雄の陰茎を口にくわえた。
「あっ、あゆみ、、あっ、」
と忠雄は、のけぞった。あゆみの口や舌が動くたびに、まるで電気が走るような刺激が全身を走った。それは、膣への挿入では得られない快感だった。あゆみの動きに合わせ、「あっ、うっ、、うっ、」と呻きながら感じる刺激に反応していると、忠雄は、自分の今の姿が、愛撫に反応するあゆみの姿と同じだと思った。そして、女の感じ方が少し理解できたような気がした。しかし、それ以上に、自分の陰茎をあゆみが口にしてくれたことに、大きな喜びを感じる忠雄だった。
あゆみは、フェラチオ自体嫌いではなかったし、この行為によって自分も強い性感を感じていたが、あゆみが忠雄にフェラチオをしてあげようと思った最大の理由は、忠雄と一生を共にする覚悟があゆみになかったからであった。「この男と自分はいつか離れていく。そうすれば、この男は他の女とセックスする。」という確定的な推測をあゆみはできた。矛盾しているようであるが、離れるのであれば、むしろ、自分とのセックスが最高だったと思わせたいと思ったのである。
あゆみのフェラチオに、忠雄は発射寸前になった。忠雄はあゆみに言った。
「ああ、あゆみ、出ちゃう、出ちゃうよ。」
あゆみはそれに答えて、
「出して、あたしの口の中に出して。」
これを聞いて、忠雄はあゆみの口の中に思い切り射精した。あゆみは、口の中に忠雄の精液を受け止め、そして飲み込んだ。
「ああ、美味しい。」
あゆみは言った。忠雄は、
「おい、本当かよ。」
と聞いた。
「うん、忠雄ちゃんがあたしの中にいっぱい入ったって感じ。」
というあゆみの答えに、忠雄は、自分の精液が胃腸で消化され、あゆみの細胞へと変化していく様子を想像した。そして、高まる興奮の中で、
「あゆみ、お前は、俺の女だ、俺の女だ、」
と叫びながら、今度はあゆみのすべてを吸い尽くすが如く、彼女の性器にむしゃぼりつき、そこに溜まった体液を舐め尽くした。あゆみもその激しさに身を捩りながら、忠雄の陰茎を握り締めた。もつれ合う二人は何時しか互いの性器を舐め合う形になった。そして、二人は再び結合し、更に高い絶頂を向かえた。
恍惚から醒めると、あゆみは急いで身体を起こして言った。
「あっ、もうこんな時間。帰らなくっちゃ。」
そして、バスルームのシャワーで、二人のセックスの結果である体液と汗を流し、急いで服を着た。忠雄は、あゆみに聞いた。
「あゆみ、明日も会えるかなぁ」
あゆみは答えた。
「あっ、ごめんね忠雄ちゃん。あたしちょっと今週は忙しいの。でも、日曜日なら会えるよ。」
「日曜日、そうかぁ、まっ、楽しみに待つよ。」
忠雄は、あゆみとこの部屋に一緒に住むことを期待していたが、少し肩すかしを食らった。でもまた会えるのだからと納得しようとしていた。あゆみは、忠雄とのセックスは悪くはないと感じながらも、新しい生活や出会いができないほどに会いたくはないたと思った。あゆみと忠雄は、最高のセックスを互いに体験しながらも、二人の間には温度差が生じていた。
4
忠雄は、毎日学校へ通った。受験が目的だった高校の勉強に比べて、短大の勉強は意外に面白かった。それに、あゆみと出会ってから、忠雄は自分の将来を考えるようになっていた。それは、勉強して少しでも良い就職をすることだった。とかく、仕事とか生活などは若い学生にとっては喜んで望むことでは有り得ない。確かにそれは、人生においてやりたくないが我慢しなければならない、負の部分である。僅かな楽しみのために、仕事という我慢すべきことで、多くの時間を犠牲にするのだから、若者はそのような、耐え忍ぶ生活などに期待が持ち難いものである。しかし、忠雄は恋人と共有できる時間がある、それがたとえ僅かでも、その幸福な時間のために、それ以外の時間を堪え忍べるように思えた。
あゆみと忠雄は、十日おきぐらいの間隔で会っていた。夕方あゆみが忠雄のアパートに行き、セックスをして帰るというのが基本だったが、休みの日に待ち合わせて出かけたり、あゆみが忠雄の部屋に泊まったことも一度あった。学校で会うと、「やあ」と軽く挨拶を交わし、短い立ち話をしていた。いかにも恋人同士という態度は見せなかったが、周りの者は薄々感づいたかも知れない。忠雄にとって、幸福な日々が二か月続いた。
六月の梅雨時になって、突然あゆみが次の会う予定を示してくれなくなった。「忙しいから、予定が立たない」と理由を言っていたが、迷惑そうな素振りに忠雄は不安を感じた。電話をしても「ごめん、ごめん。」と謝るけれども、あゆみの謝罪から忠雄に会いたいという情熱がなくなっているように思えた。
そんな状況が二週間続いた。そして、あゆみから電話があった。その内容は「別れたい」という意思表示だった。
「何でだよ、理由は。」
忠雄はあゆみを問い詰めた。
「忠雄ちゃんのせいじゃないから。あたしが悪いの。あたし、あたしね、、他に好きな人ができたの。」
忠雄は、衝撃を受けた。自分があゆみに夢中なように、あゆみも同じく自分に夢中だと信じていたからである。忠雄は、あゆみに聞いた。
「えっ、好きな人だって。だっ、誰だよそいつは。」
「そんなこと忠雄ちゃんに関係ないじゃない。」
忠雄は、憤慨して言った。
「関係ないってことはないだろう。」
責められるあゆみは泣き出した。そして、
「そういうこと言われるから嫌なの。あたしのことどんなに悪く言ってもいいから、ほっといて。ねえ、お願いだから。」
忠雄は、あゆみの号泣に戸惑いながら言った。
「あゆみ、一度会おう、なっ、一度会おう。」
「もうやめて、もうほっといて。会いたくないの。」
あゆみは、ここまで伝えると電話を切った。そしてその後、あゆみは忠雄の電話番号を着信拒否に切り替えたようだった。
次の日、忠雄は学校であゆみが受けている授業をしている教室の前で、あゆみを待ち伏せた。授業が終了して、学生が出てくるのを見張り、あゆみの姿を探したが彼女の姿はみつからなかった。ほとんとの学生が出て行ったあと、あゆみとよく一緒にいた女子学生を忠雄は見つけた。忠雄はなるべく平静を装いながら聞いた。
「あのう、あの、中山さんは今日は。」
女子学生は答えた。
「中山さんなら、今日は休みみたい。あ、あなた中山さんの幼なじみね。」
「うん、そう、ちょっと高校の同級生の集まりのことで連絡取りたかったんだ。なんか、電話も通じなかったからね。」
苦しい言い訳だったが、この女子学生はあゆみとそれ程親しくないらしく、あまり疑問にも感じなかった。そして、知っていることを教えてくれた。
「中山さん、駅前の『ジルバ』って言うスナックでアルバイト始めたみたいなの。そのアルバイト始めてから、学校よく休むようになったみたい。そこに行けば会えるかもね。」
忠雄は、逃げるあゆみをこんな風に追いかけている自分に嫌悪を感じた。だが、納得のいかない自身の気持ちを整理するためにも、そのスナックに行こうと思った。
スナック「ジルバ」は、駅の近くの路上に入ったところに一号店がある。その他にも二店舗を展開している。三十代半ばのマスターが経営しているのだが、この業界としては急成長が羨まれる店舗である。若者と女性客をターゲットにした、洒落た内装が受けているらしい。
月曜日、スナックが最も空いていると思われるその日に、忠雄はジルバに行こうと決めた。そしてその月曜日の日が暮れると、忠雄はあゆみがアルバイトしている一号店に向かった。ジルバ一号店は、駅前の路地を入った突き当たりの雑居ビルの中にある。隠れ家風の入り口で、扉を開けて中に入れば、街の喧騒から異次元に入り込んだかと錯覚する。流行りのJ-POPが流れる店内、男三人のグループと、カップル一組が既に入っていた。落ち着いたアンティークの雰囲気の店内を忠雄は見回し、カウンターの中で働いているあゆみを見つけた。水商売をするあゆみの姿は、元々派手な雰囲気を一層引き立たせ、群を抜いて輝いて見えた。
忠雄がカウンターに座ると、客の気配に笑顔で「いらっしゃいませ」と挨拶を投げかけようとしたあゆみの表情を曇らせた。あゆみは戸惑いながらも、自分が相手をするしかないと思い、忠雄の前に来た。
「来たの。」
あゆみはうつむきながら言った。
「ああ。」
忠雄もここまで来たものの、言う言葉が見つからない。しばらく、気まずい沈黙が続く。
「ねえ、もう堪忍してもらえないかなぁ。」
あゆみがつぶやく。その言葉に忠雄が少し激情して言う。
「堪忍て言ったって、何を堪忍すればいいんだよ。俺は何もわからないままだぞ。」
少し上がった忠雄のトーンを抑えたいような仕草をしながら、あゆみがつぶやく。
「他に好きな男ができたから別れたいって言ってるのに、それでわからないかなぁ、普通さぁ。」
あゆみのつぶやきを忠雄はその通りだと思った。実際、自分でも何がしたいのかわからない。別れるのだからあゆみを許す必要もないし、復讐したい訳でもない。
「俺はただ、、なんか惨めだ。」
と、忠雄が言うとあゆみは、
「ああ、あなたのこといい思い出になっていたのになぁ。」
忠雄は、ここに来たことを後悔し始めた。あゆみとの関係は、もうどうにもならないとはわかっていたのに、思い出まで汚してしまったように感じた。追い詰められた忠雄は、更に激昂して言った。
「もとはお前が悪いんだろう。なんで俺が責められなければいけないんだ。」
忠雄の大きめの声に、他の客や店のスタッフが怪訝な顔で注目し始めた。
カウンター内の、忠雄が座った反対側には、この店の店長らしい人物がいた。年の頃は三十代半ばで、その威厳から彼が店長であり、尚かつ「ジルバ」のオーナーであることが容易に想像できた。ボマードで固めた七三分けの頭髪に、整った顔立ち、加えてがっしりとした体格は、あたかも俳優のような圧倒的な風貌をしている。海千山千を乗り越えて来たことを想像させる、強固な自信を秘めた風格はから醸し出される男臭さに、忠雄は気後れを感じた。
店長は、ブルーのカクテルを作り、それを持って忠雄とあゆみの間に割り込んで来た。忠雄の前にカクテルを置き落ち着いた低い声で言った。
「お客さん、まあこれを飲んで落ち着いて下さい。」
忠雄は、店長の威厳にどぎまきした。店長はさらに続けた。
「とにかく、店の中でのトラブルは困ります。あゆみと話し合いたいのだったら、場所を用意しますよ。但し、私もご一緒しますよ。あゆみは、ただのアルバイトではないものでね。」
忠雄は、この店長の言葉とあゆみの店長にすがるような態度を見て、あゆみの新しい相手がこの男であるとわかった。忠雄は、店長と自分を比べ、男の格の違いを感じた。
「お勘定、お願いします。」
忠雄は、ふらふらと立ち上がりながら言った。
「お勘定は結構です。よろしかったら、ゆっくり飲んでいって下さい。」
との、店長の言葉に答えるすべもなく、忠雄は無言で出口に向かった。あゆみと店長に背を向けると、涙が溢れ出すのがわかった。女を寝取られ、しかもその男に諭されてすごすごと逃げ出す自分。この世で最も惨めでみっともない自分を感じ、周りのすべての者が侮蔑の苦笑を投げかけているように思えた。忠雄の顔はくしゃくしゃに崩れて、その顔で出口をくぐり抜け宵闇の街へと消えて行った。
宵闇の街を歩きながら忠雄は考えた。二枚目の強面で、しかも事業で成功して金持ちの男、派手で人目を引く美人のあゆみには、これ以上のお似合いはない。それは、誰が見ても明らかな事実だと思えた。「それに比べれば、俺は一体何だったんだ。」そう自己嫌悪しながらも、そんな高みが似合う女と短い間でも付き合い抱くことができた自分は、幸運だったのかも知れないとも感じた。自己嫌悪と自分を立ち直らせようとする思いとが、混在する自分を感じた。そして、悔しさは消えはしないけれど、明日からも生きて行ける自分自身を感じるのであった。
あゆみは、その日から学校には来なくなった。そしてその後、忠雄はあゆみが学校を辞めたことを知らされた。
5
忠雄は、あゆみのいなくなった学校に通い続けた。特段学校が面白い訳でもない。あゆみに捨てられた悔しさと悲しみが癒える訳でもない。ただ、この落ち込んだ気分で何もしなかったら、むしろ空虚な暗闇に、落ち込んで抜けられなくなるような、恐怖に駆られたからだ。学校に行くことに何かの期待があるわけでもなかった。だが、若い者たちの生活、いわゆる青春と呼ばれる日々は、彼らを絶望のどん底に沈めはしないものである。忠雄にも新しい輝きが近いていた。
忠雄と同じ学部に、篠田佳奈という女子学生がいた。佳奈は、背丈は低めでデブではないが少し太めの女だった。太めと言っても、スレンダーではないと言った方が良いかも知れない。スタイルは良いとは言えないが、仕草や表情に可愛げがある娘である。いつも多少子供ぽい服装をしている。忠雄の所属する学部は理科系なので、女子学生は少ない。従って、女子学生はすべて注目されるのだが、佳奈は特に人気者だった。よく男子学生に声を掛けられ、数人の男たちと共に連れ立って行く姿が良く見られた。
この学校に入学してから三カ月以上が過ぎたが、忠雄は女子学生と一緒の席には参加していなかった。あゆみという相手がいた忠雄は、その他の女とはあまり接したいとは思わなかったので、自然と疎遠になっていた。
あゆみと別れ、一カ月が経とうとした七月、もうすぐ夏休みに入ろうとする手前だの時期だった。突然、授業が終わった後の教室で佳奈が忠雄に話しかけてきた。
「今日は、石川君。」
佳奈は、少し恥ずかしそうにはにかみを見せた。赤を基調としたチェックのプリーツスカートに、レースのついた少女ぽい純白のブラウス着てはにかむ仕草。佳奈自身は気づいていないが、男にとっては堪らない佳奈の魅力がそこにはあった。
「ああ、今日は、、ん、何か。」
忠雄は突然の佳奈の声掛けに、少し驚いて応えた。
「うんん、別に用事がある訳じゃないんだけど、石川君とあまり話したことなかったから。」
「ああ、そうだね。まともに話すの初めてぐらいだね。」
と、忠雄が相づちを返すと佳奈は、
「もしかして、人間嫌い。そんなことないか、男の子とはしゃべってるもんね。まさか、女嫌いなの。」
忠雄は、あまり話をしたことのない相手に対して、唐突に踏み込んだ話題を持ちかける佳奈に苦笑しながら答えた。
「あはは、そんなことないよ。女の子は大好きだよ。」
すると佳奈は、
「じゃあ、あたしが嫌いなの。」
忠雄は、ちょっと驚いた。「この女、何考えているんだ。」と疑って佳奈を見ると、思い詰めたような表情にかなりの緊張が見て取れ、多少震えているようにも見えた。
「いや、、君のこと嫌いじゃないよ。」
と、忠雄が答えると佳奈は、
「ほんと、良かったぁ。」
と、固い表情のまま微笑んだ。忠雄は、「こいつは、俺のことが好きなのかな。」と思えた。そう思って見ると佳奈は、なかなか可愛らしい。あゆみのように欲情を掻き立てられるような迫力はないが、静かに抱き寄せてみたいような感じがした。そして、「もし、この女が望むなら付き合ってもいい。」と思った。
「これからもっと話しようよ。」
と、忠雄が言うと佳奈は、
「ああ、嬉しい。じゃあ、勉強わからないところ教えてね。」
「もちろんいいよ。いつでもどうぞ。」
「ありがとう、じゃ、また明日ね。さようなら。」
と佳奈が言うと、忠雄に手を振りながら走って帰って行った。忠雄と話をした緊張で、その走り方もぎこちなく見えた。忠雄は、佳奈の姿を目で追いながら彼女に対する興味が強く湧いてくるのを感じた。
次の日は夏休み前の最後の授業日だった。そして、忠雄と佳奈は同じ授業があった。忠雄は、教室で佳奈の姿を見つけるとその隣に座った。
「おはよう。」
と声を掛けると、佳奈はくしゃくしゃになるほど、嬉しそうに笑いながら、
「おはようございます。」
と挨拶を返した。
忠雄は、早くも佳奈の気持ちを確かめたくなったので、自分から積極的に佳奈に近づいたのだが、佳奈の喜ぶ姿を見て満足な気分になった。そして、このまま自分が佳奈を誘ってやろうと決めた。
この日は、この最初の授業と最後の授業が、佳奈と一緒だった。そこで、忠雄は後の授業が終わると佳奈を誘った。
「篠田さん。これからお茶でも飲みながら話しようよ。」
と忠雄が言うと、佳奈は、
「うん、いいよ。」
と嬉しそうに誘いに乗ってきた。そして、二人は校門の前の喫茶店に連れ立って行った。この喫茶店は、あゆみと再開した時に来た店である。忠雄は、あゆみとの事を思い出し可笑しくなった。「まさか、あの時みたいにそのままホテルへ、なんてことはないよなぁ。」と苦笑しながら席に座った。
この日の佳奈は、Tシャツにジーンズという地味な服装でいた。実は彼女は、昨日の忠雄への話しかけ方がちょっと強引過ぎたと後悔していた。そして、今日あまり着飾っていれば、物欲しそうな女に見られそうだと考えたのである。だが、意外に忠雄から誘われたので、ここへ来て、もう少しましな服を着てくればと後悔していた。忠雄は、その佳奈の気持ちが読めたので、その気持ちをフォローするように言った。
「今日の君の飾らない感じ素敵だね。素顔のような安心感があるよ。」
忠雄は、こんな事がスラッと言える自分に驚いた。そしてそれは、あゆみとの短い付き合いが与えたものだと思った。
「ごめんなさい。今朝忙しくてあり合わせで来ちゃった。」
佳奈は、言い訳をしながらも安堵していた。それから二人はそれぞれの身の上を語り合った。佳奈の家は学校の近くにあることや、彼女が詩を書く少女であることなど語り合った。佳奈は、自分を語り尽くした後忠雄に聞いた。
「あのう、石川君、今彼女っているの。」
忠雄は、答えた。
「えっ、今はいないよ。」
佳奈は、これだけは確認したかったらしく、思い切って訪ねた。
「あの、前に学校でよく話をしていた、あの、綺麗な人は、、、彼女じゃなかったの。」
忠雄は、驚いた。まさかここにもあゆみが出てくるとは思わなかった。
「いや、あの娘はただの幼なじみだよ。」
忠雄は真実を言わなかった。それは、実際のあゆみを知る者に、二人の関係を告げることによって、具体的にあゆみとの情事を想像されるのが嫌だったからである。あゆみとのあの熱いセックスは、自分の胸の内にしまって置きたかった。忠雄の答えを聞いて佳奈は、安堵したように言った。
「ああ、良かったぁ。あんな素敵な人が相手じゃあたしなんか、、、あれ、あたし何言ってるんだろ。」
つい漏らしてしまった本心に、佳奈は真っ赤に赤面した。
「ハハハ、篠田さんって可愛いね。そういうところ大好きだよ。ね、俺たち付き合おうよ。」
と、忠雄が佳奈に求愛する形にした。忠雄は思い出していた。あゆみに「男なら何がしたいかはっきり言え」と迫られたことを、そしてその教えを今守った。また、佳奈が自分に興味を持ったのには、少なからずあゆみが関わっていたことがわかり、あゆみとの短い付き合いの意味を噛み締めていた。
「えっ、石川君あたしと付き合ってくれるの。本当に。」
佳奈が、はしゃいで言うのに忠雄は、
「ああ、是非お願いします。」
「嬉しい、あたしも告白するわね。あたし、入学の時から石川君のこと好きだったの。でも、あなたに彼女みたいな人がいたから黙ってるしかなくって。でも、でも、あの人、学校辞めたみたいだし、、それで。」
「あの娘は、ただの幼なじみだよ。」
忠雄は、佳奈を遮るように強調した。
「ご、ごめんなさい。あたしって、、、バカね。」
佳奈は、自分の失敗に気付いた。自分の興味で、忠雄の触れられたくない部分に踏み込んでしまったと感じた。
「ねえ、もっと楽しい話をしようよ。折角付き合いだすんだから。」
と忠雄は、助け舟を出した。佳奈は、少し気を取り直して言った。
「そうね、じぁあ石川君のことなんて呼べばいいかなぁ。ううん、、たーくんなんてどう。」
「ああ、いいよ。」
忠雄は相づちを打った。
「たーくん、あたしの事は何て呼ぶの。」
「君の名前は短くて呼びやすいから、佳奈って呼んでいいかな。可愛い名前だし。」
「うん、呼び捨てでいいわよ。」
「たーくん。」
「佳奈。」
二人は、新しく定めた呼び方で互いに呼び合った。一気に二人の間に親密な空気が漂った。
佳奈は、忠雄の恋人という地位を得た喜びと達成感で舞い上がるような気持ちだった。二人は、お互いに関する他意もない会話を、長らく楽しんだ。充分に語り切った後、佳奈は言った。
「ああ、夏休みに間に合って良かったわ。」
この佳奈の言葉の裏にある誘いに気がついた忠雄は言った。
「なあ、夏休み二人で出掛けようよ。」
「うん、いいわね。」
当然のように佳奈は乗ってきた。
「海にでも行こうか。」
忠雄が聞くと、佳奈は、
「ううん、海より山がいいかなぁ。」
佳奈が海を拒んだのは、水着姿に自信がなかったのと、付き合い始めたばかりの忠雄と、肌を触れ合う状況を、どうこなしたら良いのかが、わからなかったからだ。佳奈は、忠雄に憧れていた時間が長いので、忠雄との身体の接触を望む気持ちがあった。しかし、忠雄は恋人として佳奈を認めてくれたものの、まだ数回話をしただけだ。その温度差を埋められるかどうか、佳奈には自信がなかった。忠雄は、佳奈のその気持ちはわからなかったが、
「うん、山もいいね。」
と合意した。続けて忠雄は聞いた。
「いつ行こうか。」
「そうね、ちょっと勉強のまとめもあるから、あさってでどう。」
と佳奈が答える。忠雄は、
「うん、いいよ。」
と合意した。
二人はその後、具体的に行く場所を検討し、待ち合わせの場所と時間を決めて別れた。佳奈は、一人になって明後日のデートが堪らなく待ち遠しかった。「かっこつけてあさってなんて言わなきゃよかったな。本当は明日でも会いたいのに。」と後悔した。忠雄は、家に帰って行く佳奈の姿を見送りながら、「ああ、あの身体をもうじき抱くんだな。」と思った。そうして佳奈の身体を見ると、彼女の胸や尻の膨らみに官能している自分を見つけた。
6
忠雄と佳奈が待ち合わせたのは、日曜日だった。二人は、駅で待ち合わせ長野県の県境にある高原へ向かった。電車に乗り、高原の駅に着き、ロープウェイを乗り継いで、海抜の高い爽やかな風の吹く高原に着いた。忠雄は半ズボンに水色のポロシャツ、佳奈は、ベージュのホットパンツに花柄プリントのキャミソールと、二人とも軽装だった。特に、足と腕をほとんど露出させた姿で、緑の高原をはしゃいで歩く佳奈は、山に舞い降りた天使のような愛らしさがあった。
二人は、高原のお土産屋に付属した軽食店で軽い食事とソフトクリームを食べた。佳奈が、
「あっ、お弁当作って来れば良かったなぁ。」
と、思いついて言った。
「へぇ、佳奈は料理得意なんだ。」
忠雄が聞くと、佳奈は答えて、
「うん、わりかしね。今度たーくんに食べさせてあげるからね。」
「へぇ、そりゃあ楽しみだなぁ。」
と忠雄は答え、恋人の手料理を食べるという初体験に心から期待した。
二人は、手をつないだり、肩を寄せ合ったりしながら高原を散策した。そして、人気のない林の木陰に入った。白樺の木にもたれ掛かる佳奈に忠雄は近づき、髪をそっと撫でた後佳奈にキスをした。佳奈は手を忠雄の前に折りたたんだままだったが、忠雄に従っていた。佳奈は、初めてのキスに緊張しながらも、うっとりとしていた。
「キスは初めて。」
忠雄が聞くと佳奈は忠雄の腕の中で小さく首を縦に振った。そして、忠雄の胸の中に滑るように潜り込み、体重を忠雄に預けた。忠雄は、わずかな布切れに包まれた佳奈のすべてを、今すぐにも開封してしまいたい衝動に駆られたが、佳奈の腰に手を回し抱きしめることでこらえていた。
忠雄と佳奈が、街に帰ってきたのは午後四時ごろだった。高原まで電車で一時間あまりだったので、朝早く出発した彼らは意外に早く帰ってきた。そこで佳奈が思い付いて言った。
「あ、そうだ。たーくんまだ時間早いから、あたしの手料理作ってあげるね。」
「そりゃあ、楽しみだなぁ。是非お願いするよ。」
と忠雄は答え、二人は食材をスーパーで買い込み忠雄のアパートに向かった。アパートに着くと、佳奈は米を研ぎ電気釜に仕掛けてから、買ってきた肉と卵を調理した。そして、野菜を切り多めのサラダを作った。小一時間程で、佳奈の手料理の晩餐が完成した。その間忠雄は、台所でまめに動く佳奈を眺めながら、初めて感じる幸福感に浸っていた。
晩餐は完成し、二人は今日の思い出を語りながら食事をした。佳奈の料理は、素晴らしく旨いという訳ではないが、安心できる家庭の味で、忠雄は満足だった。食事が終わり片付けが済むと、佳奈は忠雄の隣に座った。キャミソールとホットパンツから露出する佳奈の四肢を忠雄は眺めた。少し太めの佳奈の四肢は、むしろ肉感的で忠雄の欲情を誘った。忠雄は佳奈を抱き寄せキスをした。最初のキスとは違い今度は佳奈の口の中に舌を差し入れた。佳奈はわずかに戸惑いの抵抗をしたが、すぐ忠雄のディープキスを受け入れた。忠雄はめくるめく官能に遠慮無く勃起していた。
忠雄のキスは激しさを増し、そして彼は手を佳奈の乳房へと動かした。しかし、乳房に忠雄の手が触れると佳奈は、身悶えの抵抗を見せ、そして言った。
「だめ、、だめ、やめて、、、今日は許して、、お願い。」
忠雄が意外な抵抗に行為を中止すると、佳奈はなお続けて言った。
「明日、、明日、必ず来るから、、お願い、今日は許して。」
忠雄は、何故明日なのか理由はわからなかったが、無理やりも好まなかったので佳奈から離れた。佳奈は更に言った。
「ごめん、、ごめんね、明日、明日ね。」
「わかったよ。」
忠雄は、少し憮然となって言った。
「お願い、お願い、、あたしのこと嫌いにならないで。」
佳奈は、半べそになっていた。
「馬鹿だなぁ、嫌いになんかならないよ。」
と忠雄は佳奈を慰め、彼女の髪を優しく撫でた。
「じゃ、今日は遅くなるから帰るわね。」
佳奈も名残惜しそうに立ち上がり、出口に向かった。外はすっかり夜の帳が降りていた。
「送るよ。」
忠雄はそう言って、佳奈と夜の街を歩き出した。佳奈の家に着き彼女と別れ、初めて知った佳奈の家を眺めた。そして、こんな歩いて行ける距離の佳奈の家も知らないのに、ちょと急ぎ過ぎたかなと後悔した。しかし、佳奈の言う「明日」に期待を膨らませながら忠雄は帰った。
佳奈はその晩、家で念入りに無駄毛の処理をした。今日忠雄の求愛を拒んだのは、初体験の恐れもなくはないが、そのための準備不足を感じたからだ。まずは、自分の身体を曝すのに落ちはないか、下着は大丈夫か、また、今日は親に帰りが遅くなると伝えてなかったので、遅くなった原因を問われた時に、セックスを初めてしたばかりの自分が、果たして上手くやり過ごすことができるのか、などの心配が佳奈に忠雄を拒絶させたのである。
決して忠雄の誘いが嫌だった訳ではなかった。だから、佳奈は、準備不足を後悔していた。佳奈としては、会うこと自体が三回目の忠雄が、今日自分を求めてくるとは思わなかったのである。佳奈は、既に三カ月以上忠雄と関係を持つことを夢見てきたが、忠雄は、まだ様子を見る段階だと思っていた。でも考えてみれば佳奈も忠雄に心惹かれたときから、関係することを期待していたのだから、早い訳ではないと思った。セックスは愛の結果ではなく、むしろ愛の始まりだなと感じた。
風呂場で無駄毛を一通り処理した佳奈は、自分の部屋へ戻った。そして、下着を取り鏡で自分の性器を確認した。十八才の佳奈はそんなに陰毛は濃くはない。ただ、恥丘の陰毛はともかく、大陰娠付近のまばらに生えた毛は汚らしく感じた。佳奈は、小さなハサミを使い、丁寧にその毛を取り除いた。佳奈は自分の性器を見ながら、明日これを忠雄に差し出すことを想像した。今まで、誰にも見られたくなかったこの部分を、忠雄見せることを期待している自分が可笑しかった。そんな事を考えているうちに佳奈は肉体の興奮を感じ、陰部を指で弄った。佳奈は中学生の頃からオナニーをしている。皆がしていることだが、他人には知られたくない恥ずかしい行為である。でも明日からはそんな恥ずかしさから解き放たれて、忠雄という恋人とセックスをしていることを、人に知られても恥ずかしくない自分になれる。そんな期待の中、佳奈は肉体を燃え立たせていた。
次の日、佳奈は午後から弁当を二つ作った。忠雄が手料理を喜んでくれるからという理由もあるが、今夜、ものを食べる心配もせずに、ひたすら忠雄と愛し合いたいためという理由の方が大きかった。日暮れ前、佳奈は弁当を持ち、親には学校の女子学生のところに泊まると偽り家を出た。膝の少し上まであるフレアーな少し長めのミニスカートを佳奈は着けていた。本当は、セクシーな超ミニにしたかったが、親に疑われるのが怖くて、大人しい物にした。でも、ブラウスはレースの付いた佳奈らしい少女っぽさを強調したものを着ていた。
忠雄も夕方から準備を始めた。シャワーを浴び佳奈を待った。忠雄は佳奈をどう口説けば良いか考えていた。知り合ってから四回しか会っていないのに、好きだ好きだを連発するのもおかしいなどと考えていた。そうしているうちに佳奈やってきた。
「今晩は。たーくん。」
いつもながらの快活さを見せようとする佳奈だったが、どこか固い。
「たーくん、お弁当作ってきたんだ。食べる。」
「ああ、美味しそうだ。一緒に食べよう。」
忠雄は答え、そしてお茶の用意をした。用意ができると二人で食べ始めた。忠雄も何となく気が急いて慌てた食べ方になった。すると佳奈が言った。
「たーくん、急がなくてもいいよ。あたし、泊まっていくつもりだから。」
忠雄は佳奈の決心を感じて安心した。もうゆっくりと夜を楽しもうと思った。そして、
「そうか、家にはなんて言って来たんだ。」
「フフッ、親欺いて来ちゃった。」
「へえ、悪い子だなぁ。」
「あたし、好きな人のためなら何でもするわよ。」
忠雄は先程まで佳奈の口説き方を考えていたのに、逆に佳奈に口説かれていると思った。そして、佳奈の情熱を実感した。
食事が終わり片づけも終わると、忠雄はもう躊躇なく佳奈を抱き寄せた。昨日のように熱いキスを交わした。忠雄の激しい求愛に佳奈は少し恐れを感じ、身を震わせた。忠雄はそれを見て取って、考えてきた口説きの一言を佳奈に投げかけた。
「佳奈、初めてなんだろう。怖くないかい。」
小さく頷く佳奈に更に一言言った。
「俺も怖いよ。きっとお前から離れられなくなっちゃいそうで。」
この言葉は佳奈に響いた。佳奈は熱情を込めて、忠雄を抱きしめ進んでキスを返した。
「布団、引くよ。」
と言って、忠雄は押し入れを開け、布団を引いた。引き終わると佳奈は自らそこに横たわり忠雄を待った。照明は点けたままだったが、佳奈は気に留めなかった。
もうこの二人に迷いはなかった。忠雄は佳奈の上に被さり、彼女の首から胸へと唇を這わせながら、佳奈のブラウスを脱がしブラジャーを外した。佳奈の控えめな乳房があらわれた。忠雄は夢中でその乳房を吸った。
「あっ、あっ、ん、ん、ああ、」
佳奈の声が意志に関係無く漏れる。自分と違う自分が身体の中で暴れるようだつた。忠雄もシャツを脱いで裸になった。上半身の肌と肌が触れ合う。佳奈は忠雄の背中に腕を回した。そして、愛する男の肉体を堪能しようとした。全身が熱く火照った。まるで身体の中からエネルギーが巻き起こるようだった。そしてそれは、佳奈の下腹部に溜まり、爆発を起こすかのように感じた。佳奈は、自分の性器が充血し、体液で満たされていくのを感じた。
忠雄は、佳奈の意外な敏感さに驚いた。もしかすると、佳奈は処女ではないのではと思ったが、その真偽を確かめる必要もなかった。それならば、慣れた女のように扱えば良いと思った。佳奈の胸から腹へと激しく唇を這わせる。時々、甘噛みを加えると佳奈は海老ぞりに近い程、身体をのけ反らせていた。忠雄は、佳奈のスカートと下着を一気に脱がせた。そして、ソックスと一緒に佳奈の足から外し、彼方へと追いやった。忠雄の目の前には全裸の佳奈がいた。白い足の間には、陰毛が薄い黒のアクセントを醸している。忠雄は、佳奈の両足を広げ、その中心にある襞にキスをした。
「あっ、うわあっ、、わあっ、ああっ、」
佳奈の声は呻きに近づいた。佳奈は、忠雄の性器へのキスを、喜びを持って受け入れた。昨日性器の手入れをしながら、ここにキスをされることを想像した。そして、想像するうちに、それは佳奈の期待となっていた。佳奈は女を意識する年になってから、あれこれと未体験のセックスを想像し夢見てきた。それを、口に出して言えばはしたない娘と言われるだろうが、彼女は少女の夢のほとんどが、性への期待だと知っていた。今、佳奈は愛する男の前でそれを隠さなかっただけであった。
佳奈の性器は、黒ずみが少なく割れ目の部分も太腿の色と遜色はない。恥丘の陰毛も薄く、一目では無毛かと思う程である。そこに、くっきりと肉襞の割れ目がついている。まるで、幼児の性器のようである。忠雄は、性器については、佳奈の方があゆみより綺麗だと思った。そしてそれは、昨日の佳奈の丁寧な手入れによるところもあることを、忠雄は知る由もなかった。
全裸の佳奈を前にして、忠雄もズボンを脱いだ。バネ仕掛けのように高々とそそり立った忠雄の陰茎が現れた。忠雄は、自分の陰部を佳奈の太腿に押し付け、また、自分の太腿を佳奈の陰部に押し付けた。そして、上半身は佳奈をしっかり抱きしめた。佳奈は、太腿に硬く大きなものを感じた。今まで触れたことのない異様な感覚だった。佳奈は、忠雄の臀部に手を回しその全体像を確認しようとした。手で触る忠雄の尻と足に触る陰茎との両方を合わせると、忠雄の股に生えている陰茎のイメージができた。そして、自分に迫る男を実感して更に興奮を高めた。
次に、忠雄は佳奈の性器を指で弄りだした。膣の中に指を挿入し、ゆっくりと奥を目指した。佳奈は、強い刺激にビクンビクンと身体をくねらせながら、漏れる嗚咽を抑えることができなかった。佳奈は、これまでもオナニーでこの刺激は味わっていた。しかし、自分でだと刺激のたびに力が抜けてしまう。誰かに、とどまることなくこの刺激を与えられたらどうなるのだろう、と想像していた。今まさにそれが行われていた。佳奈は、忠雄にしがみつき自分の意識すら遠くさせるような刺激を受けとめていた。
「あっ、あっ、いい、、いい、、」
と、忠雄の与えられた性感をすべて受けとめていた。その姿は初体験とは思えないものだった。
7
佳奈の興奮が充分になったと感じた忠雄は、いよいよ挿入を試みた。佳奈の両足を少し開かせ、その間に移動した。指で確かめた佳奈の膣口に自分の亀頭を押し付け、ゆっくりと突き刺す。亀頭の先が佳奈の膣の中に入ると、佳奈が叫んだ。
「あっ、いっ、痛いっ、」
それと同時に佳奈の身体は、固くなりそれは忠雄の侵入を拒んだ。性感の高まりを積み上げてきた二人の雰囲気は一気に変わった。佳奈も、ここまでは忠雄のすることをすべて快感で受け止めていたのに、その興奮は冷めざるを得なかった。佳奈はこれまでの忠雄の愛撫は、オナニーで体験していたものだが、挿入は自分だけでは体験できなかった。まさに、今初めて体験しようとしている。ならば、しっかり忠雄を受けとめたいと思った。忠雄は、佳奈が処女であることに改めて気がついた。そして、興奮を抑えて対応しようと考えた。忠雄は、難しい工作をする職人のように、慎重に挿入を続けた。ゆっくりと少し抜いては、静かに奥へ向かう。これを繰り返しながら、少しづつ差し込んだ。
「うっ、痛、、ちょっと待って、、ごめん」
佳奈が申し訳なさそうに言う。忠雄も亀頭に粘膜が擦れる痛みを僅かに感じる。でも、二人ともやめるつもりはなかった。
「静かにいくからね。痛かったら言えよ。」
忠雄は、佳奈を励ましながら挿入を続ける。まるで、共同作業を遂行するように二人は続けた。やがて、忠雄の陰茎は佳奈の膣の中に、すっぽりと収まった。
忠雄は、挿入が完了するとしばらく動かないでいた。忠雄の心は佳奈の中に入り込めたと言う達成感で満たされていた。佳奈も鈍痛のために、先程のような快感はないものの、忠雄の肉体の一部が自分の中に入り込んでいることに、感動に近い気持ちが沸いていた。佳奈は再び、忠雄の臀部に手をかけ、自分と忠雄の結合の姿を実感しようとした。
「ああ、入ったのね。入ったのね。嬉しい。」
佳奈は、上づった声で言った。
「入っているよ、佳奈。お前の中は凄くいいよ。だから、もう少し居させてくれ。」
と忠雄が言うと佳奈の感激は更に高まった。
「ああ、抱いて、強く抱いて。」
佳奈は、忠雄にしがみついた。その後忠雄は、佳奈の膣の中が潤ってくるのに合わせて、陰茎を動かした。最後にはかなり激しい動きになった。佳奈は、痛みを乗り越えて性感を感じだした。
「ああ、佳奈。いくよ、いくよ。」
という忠雄の叫びと共に、忠雄の陰茎が最大に膨らみ佳奈の中で爆発したのを感じた。そして二人は、放心して抱き合ったまま悦楽の彼方に登っていった。
しばらくして、忠雄が起き上がった。男根を佳奈の膣から抜こうとして気がついて、ティシュペーパーを取り陰茎を拭いた。そこには、佳奈の血液がうっすらと着いていた。
「やだ、血出てるの。」
佳奈も、急いでティシュペーパーを取り、陰部を拭いた。
「あたしが初めてだったって証明できたでしょ。」
佳奈が悪戯っぽく言った。
「ああ、それはわかってるけど、最初のお前積極的だったなぁ。それに、処女を失ったら涙流すもんじゃないのかぁ。」
忠雄が聞くと佳奈は笑って答えた。
「本気で泣く女なんて今陽気いるかなぁ。いるとしても芝居だわ。」
「へぇ、そんなもんかなぁ。」
「だって女はずっとこうなることを待ってるのよ。男だって同じでしょ。」
「お前は芝居しないんか。」
「あたしは、そのままのあたしを見てもらいたいもん。芝居するあたしなんか好きになって欲しくない。」
忠雄は佳奈のおおらかさを愛しく思った。
「佳奈、お前、やっぱ、可愛いよ。」
「でしょ。」
二人は笑い合った。そして、血液の着いた身体が気になったのでシャワーを浴びることにした。
二人で浴室に入り、一本のシャワーをかけあった。全裸の佳奈を間近に見て忠雄の陰茎は、またむくむくと起き上がってきた。佳奈は、それを凝視して言った。
「凄ぉい、ねえ、触っていい。」
「ああ、お前のものだから遠慮するな。」
忠雄が言うと、佳奈は忠雄の陰茎を手に持った。大きくなりかけの陰茎が、一気に最大になった。
「わぁ、ビクンビクンしてる。なんか別の生き物みたいね。」
佳奈は目を真ん丸くして興味を示す。そして、忠雄の陰嚢を触りながら言った。
「ああ、これがたまたまかぁ。本当に中に玉があるのね。」
そう言いながら佳奈は、忠雄の陰茎をパクリとくわえた。忠雄は佳奈の積極さに驚きながら言った。
「佳奈、向こうでゆっくりしよう。」
二人は布団に戻り、互いの身体を心ゆくまで愛撫しあい、そして、二度目の挿入をした。二度目で佳奈は、絶頂に近いところまで登りつめた。
二人は、夜更けまで愛し合った後、一枚の毛布にくるまって全裸のまま眠った。忠雄は、自分に寄り添って眠る佳奈を愛らしく感じ大切にしたいと思った。ただ、二人目の女である佳奈とのセックスは、最初のあゆみの時とは少し気持ちが違った。何故なら、二人目だと比べることができる。あゆみとセックスした時は、女はあゆみしかいないように感じたが、今はすべての女に共通のするものを感じる。「女は皆、男とのセックスを期待している。」という当たり前の事実を実感したのだった。だが、当面は佳奈でいいと忠雄は思った。それは、他の女に対する興味を持たないのではなく、取りあえずは佳奈と安定した関係を築きたいと考えたからだった。
二人は、この後最高のサマーバカンスを過ごした。夏休み一ヶ月の間に何度も会った。海水浴にも出掛けたりした。佳奈は、水着姿で忠雄と肌の触れ合いを他者に見られることが快感だった。皆が、佳奈と忠雄がセックスをしていることを、想像するだろうことを思い、隠したかった一人の惨めな慰めから解放されたように思えた。夏休みが終わってからは、学校と忠雄のアパートとが二人の生活の舞台だった。アパートの鍵を預かった佳奈は、忠雄がいなくてもアパートを訪れ、食事の支度や忠雄の洗濯など、細々として忠雄の帰りを待った。二人とも同じ学部だったので、勉強も二人ででき支障はまるでなかった。二人は、ほとんど毎日セックスをした。また佳奈が忠雄のアパートに泊まることが多かったので、次第に佳奈の生活用品が増えていった。そして、この二人の関係は短大卒業まで続いた。
二年生になった頃、佳奈が忠雄に言ったことがある。佳奈は忠雄のアパートに泊まることが多かったので、さすがに隠しきれず母親に忠雄という恋人がいることを告げたらしい。母親は理解してくれたが、一度忠雄と会いたいと言っているとのことだった。忠雄は「いつか時期が来たら」と言い、その後一年間、忠雄は佳奈の申し出に答えなかった。そして卒業が近づき、二人共就職も決まった。忠雄は機械工具の販売業者に、佳奈は食品加工会社の事務職に就職が決まった。佳奈は忠雄と同じ職場に行くという儚い希望を持っていたが、忠雄が選んだ就職先は今年は女子の採用がなかった上に、恋人同士が二人で就職面接に来ると言うのは、一般世間の常識からすれば異様なことのようだ。しかも忠雄は、その一般常識通り佳奈と同じ職場など考えもしないようだった。やむを得なく佳奈は違う職場を探したが、何故愛し合うもの同士が同じ職場を探すことが、間違いなのか疑問に思った。
佳奈は不安だった。この二年間ほどの間、佳奈と忠雄は殆ど同じ場所で同じ時間を過ごした。それが互いの結び付きを強くしていたことは間違いない。なのにこれからはかなり多くの時間を別の場所で過ごし、違う目的で生きるのである。どう考えても、互いの結び付きが強固になる要素はない。佳奈は、忠雄との関係に担保が欲しかった。それは、結婚と言う形が佳奈に取っては理想の姿だった。短大の授業もすべて終了し、後は卒業式を待つだけになった頃、佳奈は忠雄に聞いた。
「ねぇ、たーくん。あたしの親に会ってくれる気持ちはあるの。」
「ああ、、、ん、もちろんあるよ。」
忠雄が答えるとさらに佳奈は聞いた。
「ねえ、いつ、いつ会ってくれるの。」
「まあ、、、仕事が落ち着いてからかな。」
佳奈は、明らかに不満を湛えながら詰問した。
「そう言ってばかりで、ちっとも考えてくれてないじゃん。」
忠雄は、言葉を失った。無言の忠雄に佳奈は問い詰めた。
「たーくん、あたしと結婚する気はないの。」
忠雄は、意表を突かれたが、まるで分別のある大人のように苦笑しながら答える。
「おいおい、俺たちはまだ若いし、いよいよこれから社会人になるんだ。今、結婚なんて考えている時じゃないだろう。」
佳奈は、少し激情して言う。
「あたしと結婚したら何か不便なことがあるの、、、、何も無いじゃない、、きっと二人で力を合わせた方が上手くいくのよ。当たり前だわ。」
忠雄は、ハッとした。佳奈の言うことは尤もである。互いに社会人となった時に、既婚者であることが寧ろプラスではあれマイナスは思いつかない。忠雄は、何故結婚に踏み切れないのか自問自答した。佳奈に不足があるわけではない。ただ、結婚と言うものがどういうものなのか、イメージできないだけだったとも言える。忠雄は何とか自分を正当化しようとした。それを打ち崩すかのように佳奈が言った。
「結局、あなたはあたしより大切なものが沢山あるのよ。あたしなんか、あなたの人生のオマケみたいなものなのね。」
忠雄はその通りだと思った。しかし、女については佳奈以外の女を期待していた訳ではない。ただ漠然とした人生の期待があっただけだった。その中に佳奈を必要な演者として組み込むことが結婚だとも思った。しかし、忠雄は佳奈の両親に挨拶する約束さえできなかったのだ。そして、佳奈の方が先に決意して言った。
「別れましょう。あたし辛いけど後であなたに捨てられて泣きたくないから。」
「そ、そんなことは、、、」
忠雄は「ない」と言いかけたが、断言できなかった。佳奈は、涙ぐみながらその日は立ち去った。後日、佳奈は私物を取りに来てアパートの鍵を返し、「さよなら」の一言と共に忠雄の前から立ち去った。忠雄は不思議に悲しくもなかった。ただ、二年ばかり夫婦のように付き合い、二百回を超えるセックスをした女に、もう会えなくなることが不思議な気がした。
求愛の彷徨(さまよい)