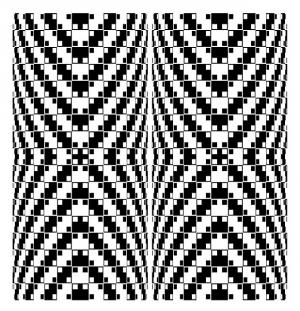断面図
こだわりとは癖であり、何かによって気づかされる時がきたりする。
その後、続けるかだね。
海洋深層水
そこは友人宅であって、小粋な休日を演出してる訳ではないにしても、誰かが振る舞ったボンゴレパスタと牡蠣のオリーブ煮、ホースラディッシュのマリネ何かがテーブルを彩っている。それに舌鼓みを打ち、各自がメルロなりシャルドネなり、はたまたピエモンテ産だったり、それこそ聞いたこともない横文字をぶんぶん振り回す。その奥手では一見紳士がペールエールに溺れかけていたりもする。ソファーは溶け掛けの時計よりも柔らかく今にも沈み、その隙間に淑女のガレはのめり込んでしまっている。
そんな状況であってpm8;00を回ると、テレビは低俗なバラエティが終わり、動物のドキュメンタリーが始まっていた。生とは真に神秘なもので、一同の口を塞ぎまた一同は人間を思いだし、粛々とした空気の中で食い入るように正面へと釘付けにされたのである。おしゃべりは一生を語れるほどに野放しに賢明でなく、ただひたすらの一生懸命に打ちひしがれるのである。
いよいよコーナーもクライマックス。今日一番の泣かせどころである。ナレーションの抑揚でそれを感じるも、誰もそんなところには意識がいかないほどに感情移入している。厳しい地に生まれてきた四人の子供。三匹は幼くして自然の力に朽ちた。小さな子供を小さな母一つ手で育て上げてきた。父は事をすますと新たな種を着床しに早々と消えた。母は男以上に種の偉大さを持って時に厳しくこの子を育て上げた。そして一人前として自立する直前。母はその姿を見ることなくして食物連鎖で生き耐える。我が子の目の前で猛禽類についばまられる。子はその姿を木の陰から見つめる。トラウマにならぬ程度に教訓として涙を呑んで、残された羽毛一枚を口で持ち厳しい大地へと消えた・・・。
インパクトは肝心である。それはこの状況に呑まれていた誰かの口を開かせる事となる。
「どんな・・・どんな死を望む?もしも死を迎えるその最期、その時は・・?」
勿論、ここでのこの発言の意図はどう看取られたいか、それが誰であるとかどこであるとかつまりはそう言うことなのである。ただあくまでもこの後の彼は勘違いはしていない。
誰しもが思い描いたことがあるように、生死後とは理想郷でもある。各々がその世界に浸り、甘美の渦の中に呑まれる中、彼はその世界のさらに先に浸ってしまった。何だかメレンコリア1に似ている。いいようもない憂鬱。彼は分かっている。発言の意図を、会話の流れを。それでも言う。そうしたかったから。
「輪切りにされてホルマリン漬けにされたい。」
彼は確かに所望している。それが瞬間に分かった長年の皆だから、誰からか自然と「何故?」という言葉が出た訳である。かくして一同は現代の光の三原色からセピアがかった彼の過去へと向かった。
若かりし頃は旅をするべきだ。ビートニクや高尚な文筆家だけでなく少し年老いた者でも口にする。いや年齢は関係ない。若くなくと説く者も、手軽に捨てる物が少なくてすむ。そしてまだ見ぬ世界にふれ未知を見ることにより新たなる自分を生み出し、さらなる活路を開く。明日の完成形の自分を創り出すのだ。
彼は確かにそう考えていたし、彼の中では確かなものとしてそうであった。だが、その時を持ってして果たしてそのように言い切れるかは後日談の事である。
低いトーンの色の中で、男は天すらも見れないでいた。それには二つの理由があって上を向くほどの筋力を使う気にすらなれないのと、地球には重力があって何かしらは常に転がっているということ・・・。可能性だけは捨てたくないのである。それを語る上でその頃が宿りゆくのは、彼の創造性と過去へのひたむきさ。過去の積み重ねこそが自分であり、それこそ最期には全ての過去の濃縮。こういう人間が出来ましたという集大成の理念に基づいているのだ。
セピアの中ーーーー男は今に始まった訳でないにしろ極貧、そして極限の状況に追い込まれていた。荷物はマーケットでチーズを食べてる際に盗まれた。ボロボロのジーンズのポケットにはいつの間にか穴があいており、引力により誰かの元へ引き寄せられた。
・・・3日になる。何も口にしてはいない。最後の水分は半日前に腹下しで体からさらばしている。体力が先か、気力が先だったか・・?互いはとにかく比例して働く。歩くことも出来なくなり4時間ほどこの美しい時計台の下に腰を掛けている。周りでは観光客が24コマにも満たずにカタカタとそれでいて列車よりも鮮明に動く。陽の光だけが男に陰影を与え、生命を感じさせた。眩しいほどの建築美の中ではゴミ箱と変わらず、フンデルトヴァッサーでも通りかかなければ、男は砂漠の果てまでも一日を陰だけで表す存在となっただろう。
初老の男性は幾つもあるスペースにあってあえて彼の隣を選んだ。やはり彼も幾つかの皮膚を持っているのであろう。
彼にとっては何番目の隣人であろう事か。時計台は歪みを見せて精一杯に背伸びをしている。
お世辞も紳士とは呼べないその初老の男性はまるで幾回りか過ぎ去りし日の彼の姿を見ているようで、その何十センチかの隙間に相対性では表しきれない輪廻が存在しているようであった。それほど二人には関係性を感じさせるシンパーシーがあった。未来と過去がそこにはあった。真っ直ぐな眼差しと伏せめがちな視線が・・・。その初老の男性も疲れてここに腰掛けたのか。確かに体はくの字に折れている。周りでは変わらずに観光客が当たり前の次元で時を楽しむ。
初老の男性はその時を確認できているのかいないのか、じっとそちらを見たままポケットに手をやった。中からは末の娘のように美しく自然な赤みを帯びたトマト。それをより輝かせるように薄汚れた袖で丁寧に拭く。その何たる水水しいこと。がぶりと口に入れた瞬間に小さな種はジュースとともに口角をたどり地面へ広がる。それを見送ると、男性は隣に座るうなだれる男を見た。そこに座る若かりし頃の自分を・・・。男はそれすらも意に介さないし、ましてや似ているなんて思ったりもできやしない。その視線にジュースは映っただろう。
男性はベチャベチャの手を拭うと反対のポケットからまたトマトを取り出した。それと万能ナイフを取り出すとトマトを横にして二つに切った。それを無言で男に渡す。ジュースを確認してから男の視線は定まった。生気を取り戻していた。それほどに欲求とは素晴らしい。その目は自然と元を辿りトマトの在処をしっかりと追っていた。そしてそれは目の前で止まったのだ。その瞬間に行為は芸術へと昇華された。二人は言葉を交わすことはなく、ただ黙々とトマトを食す。味わいは食材の無限をかいまみせる。弁は立たない。観光客に負けない幸せはそこにある。表情では計れない。喜びを持ってして気力を奪い返した。感じかたはガイドブックに載っていない。上辺でない本物がある。
そしてその空間は幕を下ろす。この世に時間の概念がある限り繰り返される。そこにはやっぱり夜が来ては誰もいなくなった。
その後の顛末だ。何もない男に残されていた国から着けていた首飾りを、自らの感覚に委ねて生きる物好きが高値で買い取った。血流にアルコールが入った。旅は旅となる。流れものに戻ることとなる。そしてその感覚が今の男を作りだした。こうして今ワイングラスを傾けるときになんか思い出す。あれはターニングポイントだった。
それでも脳裏に焼き付いているのは男性の存在よりもトマトである。顔なんてろくに見てもいないし覚えてもいない。それよりもあの真っ赤な艶。今にもこぼれそうなミズミズシサ。それだけは忘れようがないほどに鮮明に焼き付いているのだ。何よりも美しく、均等に種が散るあの断面図が・・・。
それからの人生で男はあの時の自らと似た境遇の者を見かけると何かを買い与えた。旅が終わって、財布を鞄にしまうようになってからもそれは続いた。むしろ、そのような者を求め探し出している節さえあった。紅葉感は特別なのかもしれない。
そして、反応を伺う。ケーキ、パン、パッションフルーツ・・・・。土地と季節で物は変わる。けれどもどれもが希望を失いかけた物へは最高のご褒美。一心不乱に誰もが貪った。形の美しさは胃の中でボトルシップのように元に戻るだろう。相手は思う。なんて素晴らしい行為だと・・・。それを男はしっかりと感じる。
いつものように満足げにあの頃の自分を救った男は、不気味に満たされている自分に気がついた。その行為によって特を求め、一時の益を得ようとしている自分に。それにハッとすると今までの欺瞞に満ちたそれに恥ずかしさを覚えた。何とも無惨で烏滸がましいことだと神へと悔いるほどに・・。ドロドロの疑念が蔓延った悪行。けれどもどんなに気持ち悪くなろうとも、こうして渡そうとしているこの半分のゆで卵はそれでも美しい。あのトマトと遜色ない。何も変わらないじゃないか・・・。そうなれば事はいとも簡単であった。男の美しさは美学なんかではなく、根本的に断面図に見初められていたのであった。パンの気泡や、ケーキのクリームの層。そして、トマトの種の均一化・・・。そこで織りなす断面図は男の胸を躍らせる。
男が断面図フェチになると、皆はカラーの世界に戻ってきた。画面にはそれ以上のドラマが織りなされているのに、それが誰かにはとても陳腐に思えた。そしてすぐにフィクションだと理解を示した。クレジットで脚本家の名前を覚えてやろうと思った。
その先に続きがあるのかは分からない。興味本位なのかレールの先なのか分からない。その美しさなんてより分からないし、中途半端な理解はしてはいけない。でも、その話における気持ちの強さは誰しもに分かった。それほどに引き込まれた。
そして男は語る。
「死んだら、脳のてっぺんからつま先まで32分割くらいの輪切りにしてもらいたいね。たっぷりのホルマリに浸かり眼球見開いて、世界を見るよ。液体の中で体のパーツがバラバラにならぬようにワイヤーかなんかで固定されて、在りし日のままプカプカと漂いたい。」
男はキラッキラで語る。まだ誰も口を挟まない。
「そして、その姿を、入れ物に感謝して・・見るんだ。ケースの向こうから皆と同じように・・誰よりも前でガラスにベッタリとはりついてね。くまなく満足いくまで見れたらそれは綺麗に成仏されるでしょう。何の未練もなくバイバイだ。」
男の姿に皆は先ほど浮かべた自らの最後に、それぞれの幸せの価値観を思い馳せた。先ほど以上に・・・。何だかんだで皆、同じような顔をしていた。それぞれの理想に溺れる皆に再び男の声が届いた。そんな空気を変えるような声のトーンであった。
「でもね・・・心配があるんだ。人間は死んだら痛みは感じないのかな?だれもそれを伝えることが出来ないだけで、手も動かないし、声も上げられない。眉間に皺をよせることもね・・・。本当は痛かったらやだよね。燃やされてる時も嫌だけど、輪切りも相当痛いぜ。・・でも。そうだったら痛みはどこまで続くんだろうね。感覚はどこまでだろう。それこそ地獄だね。」
話の興味は尽きないけれど、この手の話はすぐにお腹がいっぱいになる。誰かが正解を導くのにはとても難しい式が必要だ。それは面倒なので誰かは男に言ってやった。
「お前さ、今歯医者に通ってるだろ?」
「うん。親不知がそろそろやばい。」
「こないだも麻酔で口の端から液体垂れてたもんね。」
「うん。言われるまで分からなかったけど・・・。」
「うん。そうだろ。町の歯医者の麻酔ですらあれだけ効くんだから余計な心配だ。医者は上手くやってくれるよ。きっとね・・・。」
二人のグラスが中空でお洒落な音を上げた。
[カチン!!]
断面図
どうでもいい妄想でも色味をつければ時間は潰せる。