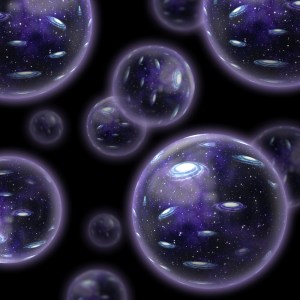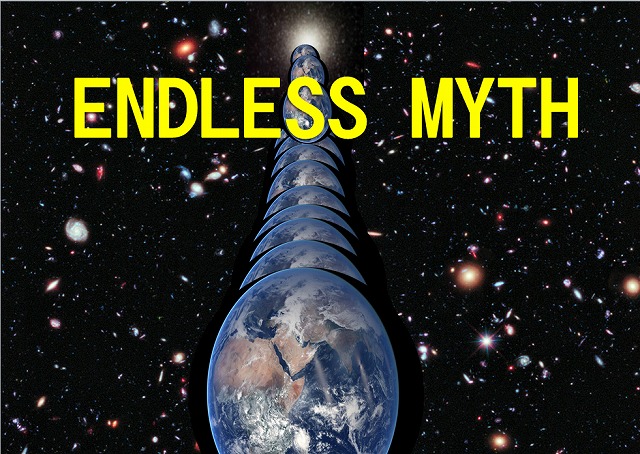
ENDLESS MYTH第3話ー25
25
中空を5つの影が飛行する。目指す先は旧ロシア領域、モスクワ付近だ。
そこへ向かう空は晴天に晴れ渡っていた。しかし天にある太陽は、彼がが知る太陽とは異なっていた。大きく肥大した真っ赤なそれは、太陽というより、赤色巨星だ。
テレパシーで5つの影は会話する。
「太陽も時間の問題か。雨上がりの向こう側には、終わりが待っていたということか」
珍しくテレパシーでは饒舌に口走るイ・ヴェンスだ。
「あれも地球と同じさ。人類かあるいはそれ以後の文明が無理やり延命措置を施した結果がボロボロの腐った地球と、何億回、何千億回めかの人工太陽だ。それも終わりだがな」
と、ニノラの皮肉が他4人の脳内に響く。
この様子を見ていると確かに皮肉を言いたくなる光景がどこまでも広がるのは、確かに皮肉も言いたくなるはずだ。
大陸はほとんどない。彼らの眼下には広大な海が広がっている。
彼らが居たのは、この時代の地球では稀な陸地であったのだ。
赤色巨星の熱にうなされながら、濁った海面を眼下に飛行する5人。
その目の前に薄く陸地が見えてきた。
5人の顔に緊張の糸が張り詰めた。戦場へ行く気分なのは分かっている。この先に自らの運命、産まれた理由が待っている。そう考えるだけでも、眉間が固くなる。
陸地に入るとそこは相変わらず、背丈ほどの植物とビルをも超える高さ、太さの巨木という概念を凌駕した樹木が竹林のように生息していた。
ふと幹の上に眼をニノラが転じた時、コブのような塊が複数認識できた。
思わず飛行の行き先を変更したニノラが高速で近づくと、そのコブが人の背丈よりも大きくて、ドーム型のアーチを描いた建造物であることが認識できた。
しかも1つではなくその建造物が密集した集落のようなコミュニティがそこにああった。
幹の上に着陸し、周囲を黒人青年が見渡すと、そこの幹だけではなく、周囲複数の幹、巨木の上に、無数の集落があった。
その中の1つの建物に接近するニノラ。相変わらず生命体の気配は皆無だ。
建物の表面を触ると、ザラザラと土の感触に似ている。粘土のような素材ではあるが限りあるニノラの知識から推測しても、粘土とは違う素材のようだ。
扉のない建物の中を覗くと、生活感は一切ない。そこに本当に生命体が以前は居たのか分からないくらいである。
使う用途が理解できない茶色の家具などは設置されていた。素材はやはり粘土のような茶色い素材である。
ここに暮らして生命体文明がなんてあるのか、想像することすらできない。ただ黒人青年の頭の中にあるのは、ここが人間以外の生命体が生活していたであろうことは確実だ、という考えである。
背後を見ると4人が中空で停止したまま待っていた。
訝しく黒人青年を見やる4人を尻目に、一瞬、自分たちがとてつもない世界にいる気がして、背中に水を浴びた気分になった。
その後、合流した5人は飛行して目的の旧モスクワへと飛行を続けた。
が、またしても5人の意識を吸い取った物が眼下に広がったのである。
直径が100キロを超えるであろう巨大な穴。それが眼下に突如として広がり、またその光の届かない暗闇が5人の好奇心を捕まえて離さなかった。
着陸した5人はその穴がただ土やコンクリートを固めただけのものではなく、金属と機械で覆っている、彼らが生きていた時代にはない技術が使われていることを把握した。
地球を破壊した隕石のクレーターではないかと思えるほどの穴を、縁に立ち5人は見下ろした。
この吸い込まれるような奈落を見ていると、5人はこのまま落ちていくような、そんな感覚に陥る穴であった。
これがどういった穴なのか、5人は知っていた。この世界をまさしく象徴する穴なのだ。
「こいつが地球を延命している栄養チューブってことか」
イ・ヴェンスが太い首を傾げ、穴の中をのぞき込みながら呟きを穴の中に落としてやった。
ニノラもこれに頷いて、少し間を空けて周囲を見やった。
穴の周囲は砂漠に覆われている。それは地球が口をポッカリ開けているようにも見えた。
そこから焦点をまた穴に戻してニノラは呟いた。
「技術的には分からないが、この穴は地球の核まで繋がっている。そして停止しようとする核の回転を、無理矢理持続させている。寿命が過ぎてもなお、機械に繋がれて、心臓を動かしているようにな」
少し不機嫌と嫌味が混じった言葉であった。
「ここまでして地球に拘る意味はあるのかねぇ?」
足元の小石を蹴飛ばし、穴へと落としてやったイラート。
と、小石は穴に落ちてすぐ何らかのエネルギーシールドに阻まれ、蒸発してしまった。
まだシステムは生きている。文明が消失したこんな世界でもなおも。
「ここからは遠いのか? 戦場は」
紛らわしい事に本当の姿を現すことのないバスケス・ドルザックがニノラの姿で問いかけた。
この種族、デンゴーホン人の徹底している部分は、声色までその対象者へ酷似させることであった。
種の保存の為、他者へ変化する進化を遂げた彼ら種族は、今は宇宙でも稀少種族されていた。
「そう遠くはない。飛べば旧モスクワまではすぐだ」
無愛想にイ・ヴェンスが言葉を穴の中へ投げ落とした。
「しっかし暑いなぁ。あのでっかい太陽、どうにかならねぇのか?」
だだをこねる少年の如く掌で顔を覆い、蒼天を覆う赤色矮星化した太陽を見上げた。
と、その赤い世界に黒く染みのように1つの点がイラート・ガハノフには見えた。眼を細めてそれが何なのかを確かめようとしたその時、正体に気づいたイラートは慌て、掌に稲妻を握ると、赤色矮星めがけ投げつけた。
この行動に周囲の4人がハッと眼を剥き、天に視線を上げた。
するとイラートが投げつけた稲妻の球体を突き抜け、一閃が地上へと降り注いだ。
地球の中心部までほられた穴の縁に立っていた5人は、一閃を回避すべく、八方へ飛ぶ。その直後、光の一閃は地上へ着弾、爆発と土煙を上げた。
光線。稲妻を投げたイラートがそう心中で呟いた。
そこに風が吹き土煙が晴れたところに、5つの影がぼうと悪霊の如く立っていた。
「なぁ、驚いただろう?」
不敵に笑みを顔にたたえていたのは、面長の男ファン・ロッペンだった。
ENDLESS MYTH第3話ー26へ続く
ENDLESS MYTH第3話ー25