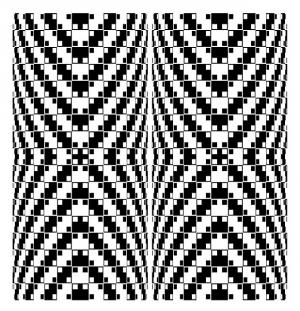貴族のファストフード
金持ちはわからんね。
誰かの創造+あるふぁ。
貴族のファストフード
少年の家はいわゆる豪邸であった。ただの金持ちではない。それこそ門から玄関まで距離があり、それ相応のセキュリティ。間に幾人かの人を挟まなければいけないほど。いわゆる庶民はそのエリアに近づく事を遠慮するほどの格式ある家であった。母の事は今となってはよく分からない。そのお母様は節目節目で目にした。ただ」、生まれ持ってのこの家柄でないのは普段は目にすることない父親の働きぶり故の事である。誤解して貰いたくはない。この父親は大変立派なあけなのである。
とにかく少年はかくいうべく食卓のあり方を知らない。だからあこがれもしない。父は生まれつきのそういう存在であり、身の回りには一般では召使いといわれる優秀な話し相手がいた。少年は彼らをそう捕らえていた。だからこそ姿をほとんど見せない父親はさぞかしいい人間である。そのことすらもまた少年は分かっていた。そこに帝王学は存在する。
まぁ、それはいい。話を食卓に戻そう。想像がつくように少年の家にはおあかかえのシェフがいて、厳選された互換を刺激する食材が並ぶ。それが少年委とっての過程の味であり、シャラン鳥もオマール海老も、蝦夷馬糞ウニも、その名前に屈することなく鮮度をきちっと見分けることが出来るのであった。それは一般人からしてみればとても交換な下であった。けれど少年には何度もいうようだがあたりまえなのである。この長い机の上座に一人で座る。昼と」版の二回。首元へナプキンをこさえれば一皿目を給仕が運ぶ。部屋の隅には執事が一人たち、頃合いを見て合図を出す。二皿目か・・?それとも水か・・・?少年尾都合にあわせての無言の食事。カトラリーと肉や野菜、果実の繊維をちぎる音だけが聞こえる。それが少年の食卓であり、少年はそれらの音が隙だった。
そういった食文化で育った少年の普通は庶民のそれとは異なっていた。では、それは一流なのか・・・?ある晩、いささか飲み過ぎた給仕人はそんな疑問を抱き、いたずら心に火がついた。裏門からこっそり抜けだし、マクドナルドへ向かった。夜はすっかり更けていた。
少年はいつものように寝る前の読書でその知性を高めているところであった。この時間に口にするものといえばホットミルクくらいのものであった。それも毎晩の事ではない。そしてそれえを頼む以外に部屋を訪ねるものなどいなかった。
しかし、その晩は違った。訪問者はドアをノックした。少年には様々な憶測が飛び交ったが、聞き慣れたその声にドアを開けた。ヒドく腰を折った給仕人がいた。酔っぱらっている事が少年にも分かった。
「ぼっちゃま、夜分にすみません。・・お腹空かないですか?こんな時間にどうかとは思ったのですが・・・。私お腹が空いたもので、ぼっちゃんにもどうかと・・いらぬ心配だとは思いますが、どうですか?」
そういうと給仕人は紙包みからまだ温かい照り焼きバーガーを取り出した。
「それは何かね?」
冷静を保ちつつも、少年の興味はその香りによってすっかり誘われていた。もう、口にすることは決まっていた。
「てりやきですよ。日本が生んだ傑作です。モスはもう閉まっていまってマクドナルドですがいかがですか・・?」
「ほう、それがマクドナルドか」
少年は唾を飲み込み、原がならぬよう気をつけた。ここに現れるはずのない父親を意識したのだ。
「それはおいしいのかい?」
給仕人は分かっているはずなのに大きなリアクションをした。
「あら、ぼっちゃま。召し上がったことないんですか!?ぼっちゃまともあろう博識な方が知らないなんて・・。それはまた罪な事を・・」
それは少年にとって待っていたgoサインだった。これで面目は保たれる。
「そうだね。見識の為に頂こうかな。」
少年は給仕人の手からハンバーガーを取る。給仕人は思わずニタッと顔に出てしまったが、少年はそれに気付くことはなかった。ほかほかのその中身が気になって仕方なかった。包装のポップさ、目を奪われながら今までにない雑さで開ける。それは少年にとってとても長く感じられた。それはすろーもーに・・それでいて優雅に開いているはずだった・・・。
ビリビリの包装紙が床に落ちる。書斎とも呼べるほどの重厚な少年の部屋。幾らか分からぬジュータンニ落ちたクシャクシャのそれは何らストリートと代わりはしない。ここは食卓でない。世界一の大衆は線引きを塗りつぶし、身分を超越した。
どれだけ寒い中を行っても、少しの・・チーズが固まりきらない温度であればハンバーガーは温かい。手の内は食べごろである。少年はそれは開いたこともないほどに大きく口を開けていた。自然と必然なハンバーガースタイル。執事の頭の中で様々なリアクションがリフレインの如く想像を帯びて繰り返された。一人クイズ番組。顔だけでなく型も震えていた。
・・・そして少年は初めてのハンバーガー。それも濃厚なマヨネーズ染みたテリヤキバーガー口いっぱいで受け止めたのである。
少年の舌はいつものように掌を開くように一つ一つの食材、それに付加する塩分、甘み、ウマミ・・・それらを個とし、それに+されるハーモニーを聞き入れる準備はできていた。押し流されそうな唾液の渦とも、細か作業を行う鼻孔を刺激臭で破壊されようとも、少年の佇まいは確かに禅としてあった。パウンドの堅さから、オーブンの余熱を想像し、薄力粉の割合を過去からの引き算で計算を出す。歯は確かにそれらを感じ、先に進んだ。
「ばぁぁぁぁーーーん」
少年は固まっていた。租借すら忘れて・・・執事も満面の笑みで止まった。ポップコーンがあったなら、その楕円形がくまなく一周していくかのように、重力を無視しては、強烈に濃厚な時間が少年の細胞を幾つか破壊した。
「うっまぁあぁぁ」
少年は白目をむいた。コンマ何秒を・・。それをみての執事の確信。まるで、テレビコマーシャル。物の価値は富田。そして二口目。少年の舌は受けてから攻めてへ・・・。めくるめく。その全てを堪能しようと密を吸う触覚を持った虫の如く・・・。貪るまでだ。頭を垂らしたまま・・・。持ち上げることもなく平らげた。包み紙に残ったソースを見て欲求を持った少年の心はそれこそに理性を取り戻した。
まるで全てがなかったかのように、胸にハンカチーフを納めるようにその包み紙を折り、ゴミ箱に捨てた。執事は紙ナプキンを差し出した。しかし、少年は片手でそれに答えると、引き出しからハンカチを取り、口を拭った。執事はそれを両手で受け取った。
「いかがでしたか?」
「いや、悪くはないね」
「左様ですか。それでは夜分に失礼しました。・・あ、ぼっちゃま」
「わかってる。歯はきちっと磨くって・・・」
「そうですね。ではおやすみなさい」
そういうと執事は場を後にした。老化をスキップし、さらなるアルコールを取ることとなる。刻まれるべく思い出として・・・。
少年はその晩、歯を磨かなかった。部屋中にたち困った臭いに悶々としつつ、歯の隅々を歯ブラシがいらぬほどに舐めきった。けれども誇り高きプライドは決してゴミ箱には視線すら行かせなかった。
少年の食卓には変わらずにカトラリーが並び、その様子を隅でひっそりと執事が見守る。・・何も変わりはしない。同じように舌を広げ、その食材たちを少年は待っている。舌の上から食堂に流れ、その鮮度にぼやくこともある。
一週間。なくなくシェフは自分のアシスタントを一人やめさせた。その晩・・
皆が眠りにつくと少年はこっそりと外へ出た。セキュリティーに抜かりはない。けれどまさか、少年の外出をだれも想像していない。その趣向。戻る分にも少年の頭脳を持ってすれば問題はない。
少年は決して世間知らずでない。父親と同じようにこの広い世界を知っている。町であたりまえでいるのも簡単だ。否、そう思う緊張感は家の人間と少年の胸の鼓動だけ痔委。
そうして少年の部屋には包み紙がある。下調べ通りに難なく変えた。袋を少し開けると少年は大きく唾を飲み込んだ。中から。さらなる包み紙を二つ取り出した。テリヤキバーガーが二つ。少年はゆっくりとその紙を開けると、こないだと同じように大口を開けた。そして、がぶりとと夢心地・・・。脳内麻薬のように少年の膝には力なくなる。
そして、夜が明けて、朝がくる。昼頃には首にナプキンをかけた少年が・・・。
「シェフ、この卵はいつのだい?卵黄に張りがないんじゃないか?」
シェフはあわて顔で今朝届いたばかりの生卵を口にする。
家政婦は少年尾部屋を片づける。無造作に捨てられたまるまるの包み紙と、分解解剖されたような半分のテリヤキバーガーがそこにはあった。
貴族のファストフード
かっこういいいよね。
貴族=プライドだね。