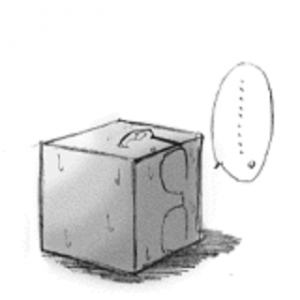彼女が死んだ
この物語はフィクションであり、実在する人物・地名・団体名等とは一切無関係である。また、本作には強い暴力表現を含むため、十五歳未満の閲読者は速やかに退出すること。十五歳以上の読者におかれても、その種の表現を受け入れられない者は閲読を控えられることを作者から強くお勧めする。
不波 流 拝
七月一一日、月曜日。
雨の夜に、彼女は死んだ。
死んだのが誰なのか、誰も知らなかった。だが、彼女は確かにその日その時、その場所で死んだ。
自分の拳銃で頭を撃ち抜かれて。
高級マンションの一室。降りしきる雨の中、幾つもの赤色灯がマンションの外壁に繰り返し光を投げていた。
床に、彼女の血が広がっていた。頭から床に突っ伏した形で、彼女は死んでいた。編み上げていた黒髪が、銃弾で撃ち抜かれてばらばらに広がっていた。
警官が現場に到着したとき、彼女の身体はまだ温かかった。救急隊員が彼女を起こしてストレッチャーに横たえた。彼女の血が、真白なシーツを汚す。彼女は目を大きく見開いた状態でこときれていた。生きていた時に怜悧だったその顔は、醜く歪んでいた。開ききった瞳孔が、室内照明の光を呑み込んでいた。救急隊員の一人が憐れに思ったのか、そっと彼女の瞼と口を閉じてやった。彼女の額には直径一センチメートルほどの弾痕がひとつ、黒々とした闇を晒していた。
彼女の死体は、青いビニールシートに覆われて救急車に収容された。
彼女が死んだ。
どこの誰ともわからぬまま。
死の一分前、彼女は一人の少女と対峙していた。全身に返り血を浴びて獣のように唸る少女に向けて、彼女は拳銃を構えていた。その次の瞬間に、自分が死ぬなどとは思いもせずに。鈍く黒光りする照準の向こうに見た少女の眼は、彼女を鋭く射抜いていた。それでも彼女は死の予感など欠片も感じていなかった。彼女の両手の中にある重量が、絶対的な力として自分を守護するだろう、そんな安心感すら抱いていた。それが慢心であることに、彼女が気づくことはなかった。
自分が信頼を置いていたその銃で額を撃たれ、彼女は死んだ。
死の三分前、彼女は自分の部下が目の前で殺されるのを見た。屈強な二人の男が、小さな少女に翻弄され、呆気なく仕留められるのを見て、彼女は高笑いを上げた。狂気の笑いを、彼女は笑った。彼女にとって、部下などたまたま手近にあったモノに過ぎなかった。利用できるものは何でも利用してきた。その結果がどうなろうと、彼女には全く関心がなかった。彼女にとっては、自分の生命ですら手段でしかなかった。どんなものでも、確実に思いのままになると思っていたし、それまでも彼女はそうしてきた。
意のままに利用できないものと対峙したとき、彼女は死んだ。
死の一時間前、彼女は部下に命じて一人の男を水責めにしていた。男がもがき苦しむのを、彼女は冷ややかな目で見ていた。彼女は人間の意志がそれほど強靭ではないことをよく知っていた。肉体は人が思っているほど頑丈にはできていないことも知悉していた。散々綺麗事を並べたその口が、いとも簡単に本人の意志を裏切るのを、彼女は何度も見てきた。そして、その裏切りを見るのが彼女の何よりの愉しみだった。ただ、彼女は自分の肉体が彼女自身を裏切ると考えたことは、一度もなかった。彼女は自分の身体に対して奇妙な自信を持っていたし、それまでそれを疑う必要もなかった。
自分の身体に裏切られたとき、彼女は死んだ。
死の一日前、彼女は部下に命じて一人の男を殺した。丸三日の監禁を経て、男はすっかり困憊していた。愚かな者ばかりだと彼女は思った。誰も自分の意志を毫も疑わない。そんな連中が、暴力の前にあまりにもあっさりと屈服する。彼女は「倫理」などという概念を一切信用していなかった。彼女にそれを求める人間を、彼女は醜いと感じ、憎んでいた。最後には力のある者だけが生き残るべきだと彼女は考え、そのように行動してきた。いささかの痛痒も感じることなく、彼女は男を殺し、死体を車ごと海に捨てた。それが彼女にとっての合理的判断だった。自分の利益になることだけを彼女は常に考え続けてきた。
その判断を誤ったとき、彼女は死んだ。
死の四日前、彼女は自分が死ぬことになる街に入った。この国はどこも同じような街ばかりだと、彼女は思っていた。どこへ行っても同じ規格で画一化され、冷えきって死にかけている街ばかりだと。熱気も混沌もなく、表面だけは綺麗に取り繕っているが、その裏側に薄汚れたものをこっそりと隠している。この国の人間たちと同じように。彼女はこの国に合わせて、表面を取り繕うことを上手にやってのけた。そしてそのおかげで、驚くほどの早さで自分の地位を向上させた。だから、彼女はこの国の瀕死の街を嫌悪していた。仕事でなければこんな街になんか来ないわ、と彼女は唾棄した。
彼女が軽侮したその街で、彼女は死んだ。
死の五日前、彼女は命令を受けた。流出した「商品」を回収せよ、と。彼女は自分の職務に極めて忠実だった。あらゆる手段を用いて障害を排除し、職掌に精励してきた。それが彼女のすべてであり、彼女の正義でもあった。業務後の隠蔽工作も器用にこなしてみせた。彼女の属している組織が何を目的にし、何を行っているか、どれだけの人間が関わっているのか、彼女はそれらの事情に全くの関心を示さなかったし、そのことは彼女にとっても組織にとっても好都合であった。人間関係や組織内での力学についても極めて冷淡だった。組織への忠誠心ではなく生業として、彼女はただ、下された指示をひとつひとつ確実に達成して組織の信頼を得てきた。
その達成に初めて失敗したとき、彼女は死んだ。
死の三年前、彼女はこの国に入った。密入国だった。彼女の組織はありとあらゆる手段を用いて「利益」を上げていたから、特に珍しいことではなかった。「先進国」と呼ばれていたはずのこの国が、実際にはひどくみすぼらしいものであったことに、彼女は密かに失望し、そして憎悪した。組織は彼女にこの国の人間を装うように命じ、彼女はそれに忠実に従った。ごく僅かな期間で彼女は驚くほど演技を上達させ、誰も彼女の出自を疑うことはなかった。しかし彼女は、決してこの国に同化しようとはしなかった。それは自分の出自に対する誇りなどという抽象的なものではなく、あくまで生活のための具体的な意志であった。彼女は糊塗された偽善ではなく、どこまでも露悪を愛した。
彼女が嫌悪したこの国で、彼女は死んだ。
死の八年前、彼女はこの仕事に就いた。他に選択肢はなかった。汚れ仕事だということはわかっていたが、女であることを使うよりはマシだと彼女は考えた。寝食の心配しかしたことのなかったそれまでの生活に比べれば破格の待遇で、彼女は組織に抱えられた。持ち前の頭の良さと、どこまでも合理的な行動で、彼女が頭角を現すのに時間はかからなかった。二年後には部下を与えられるようになっていた。暴力を用いることに躊躇はなかった。それまでも暴力には日常的に接していたから。いったい何人の人間を殺したのか、いちいち覚えているほど暇ではなかったし、その数を誇るような野卑さを彼女は嫌悪していた。立ち居振る舞いも洗練され、彼女は組織のなかで一定の存在感を発揮するようになった。殺すことは彼女の日常であった。
殺してきた者たちのことを忘れて、彼女は死んだ。
死の十三年前、彼女は初めて人を殺した。殺したのは見知らぬ男だ。ひどく蒸し暑い夜だった。男は彼女の体が目的だった。彼女は必死で抵抗した。男に唾を吐きかけ、腕を振りほどこうともがいた。だが男の力は強く、彼女はいとも簡単に叢に組み敷かれた。男の体臭が、彼女の嫌悪感を煽った。男は下卑た笑みを浮かべながら片手でズボンを下ろす。自分を汚されることへの恐怖よりも、男に対する激しい怒りが彼女の中で勝った。咄嗟にとった自分の行動を、彼女はよく覚えていない。気づくと、男は彼女の上にうつ伏したまま動かなくなっていて、彼女は右手に血まみれの石を握りしめていた。しかし彼女の怒りは収まらず、男の体を押しのけて立ち上がると両手で男の頭に力いっぱい石を投げつけ、無様な死に顔を足蹴にした。肩で息をしながら乱れた衣服と髪を整え、男の財布から金を抜くと、彼女はその場を走り去った。自分でも驚くほど平静で、彼女は自分の「適性」を知った。それ以後、彼女は自分の「適性」を積極的に利用するようになった。
「罪」というものを知らずに、彼女は死んだ。
死の二十一年前、彼女は孤児院に入れられた。何故そんな境遇になったのか、彼女自身も知らなかった。周りのこどもらは、誰もが「あたたかさ」に飢えていた。彼女も皆と同じように「あたたかさ」を渇仰した。しかし、誰もそれがどのようなものなのか、知らなかった。それに触れたことがなかったからだ。どれだけ求めても、それは決して与えられることはなかった。だから彼女は、同じようなこどもらの中で狡猾に振る舞うことを覚えた。利発なふりをして大人の目を欺くことを覚えた。その場を支配する者の意を汲んで、自ら率先して行動することに長けた。それが生きていくために必要なのだと、ほとんど本能的に彼女は知っていた。彼女は求めるのをやめた。その代わり、奪うことを覚えた。
あらゆるものを奪い取りながらも、決して満たされずに、彼女は死んだ。
死の二十七年前、彼女は生まれた。しかし、それが本当かどうかを彼女は知らなかった。どこでどうしてきたのか、確かな記憶を持たなかった。誰もがそういうものだと彼女は思っていた。だから彼女は「自分が何者なのか」に拘泥しなかった。彼女にとって「生きる」ということは当面の糊口をしのぐことであり、それがすべてであった。余りに自明のことであったので、そこに理由など必要なかった。
自分が何者であるかを知らずに、彼女は死んだ。
死の五日後、彼女の遺体は荼毘に付された。
彼女は身元不明者として扱われ、火葬に立ち会ったのは福祉事務所の職員だけだった。
彼女を焼いた煙は、梅雨の明けた晴天に向けて、ゆっくりと立ち上っていった。斎場の周囲ではアブラゼミが騒々しく夏の到来を告げていた。
彼女の遺骨は、規定に従って小さな骨壺に保管された。彼女の骨壺は、身元不明者たちの骨壺の列に加わった。
彼女が死んだ。
彼女が誰なのか、誰も知らない。
了
彼女が死んだ