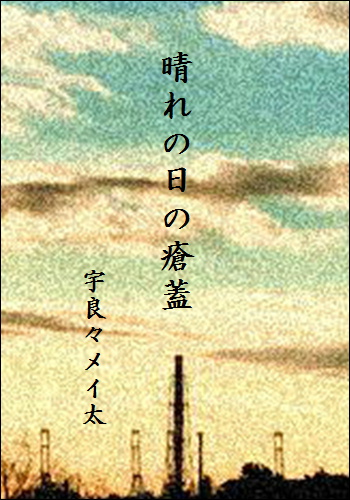
晴れの日の瘡蓋【第八話】
八、スイーツ
1
あの日以来、私たちはマコトのバイト先のカフェでちょくちょく会うようになった。
奥さんに案内されていつもの席に座り、彼はいつものように甘いものを注文する。
私は何にするか迷ったあと、結局彼と同じものを注文した。
マコトに会いに来たつもりだったんだけど、結局彼女とはこの日も会えずじまいだった。
夏休みも終盤、きっと課題に追われているのだろう。
連絡をくれればいつでも手伝ってあげるんだけど、今回は自分ひとりだけでやろうと努力しているのかもしれない。私がいると彼女のやる気に水を差しかねない。だからあえてこちらから連絡はしなかった。
そんなこともあり、マコトと会うよりも真木瀬君と会うことの方が多くなっていた。
連絡はいつも彼からくれた。
彼といると心が騒ぎ出した。
そして温かくて柔らかい何かが身体中に流れて行った。
私の中で衝動的なものが駆け抜けては消えてを繰り返す。
何かが変わろうとしていた。
ある日のこと、いつものようにマコトに会いに真木瀬君とカフェに入った。
「いらっしゃいませ。」という男の人の声がした。
声の方を見てみると、そこには見知らぬ男性がひとり、テーブルを拭いていた。
「あ、ここどうぞ」
彼はいつもと違う席に案内した。
「あの、笹之辺います?」
真木瀬君が言う。
「笹之辺・・・ああ、マコちゃんの知り合い?」
「高校の同級生です。あ、ちなみにこっちは先輩。」
「飛鳥里です。マコトとは幼馴染みなんです。」
男の人は手を叩いて思い出したように言った。
「ああ、サクラちゃんか!べっぴんさんになって全然わからなかったよ!俺のこと覚えてる?マスターの来海だよ!」
「えっ?私お会いしたことありましたっけ?」
「うん。随分前にマコちゃんと笹之辺のオヤジさんとで何回か来てくれたよ。」
「ええ!全然覚えてない。」
「あの時も可愛らしい子だなぁなんて思ってたけど、こんなに美人になるとはなあ。」
マスターはしみじみと言った。
「あの時はマコちゃんよりも小さくて本当にお人形さんみたいに可愛かったんだよ。いやあびっくりだな。背もマコちゃんよりも高くなっちゃって。」
興奮するマスターをなだめるように真木瀬君は言った。
「あの、怪我はもう大丈夫なんですか?」
マスターは少し冷静さを取り戻したようで、何回か咳払いをした。
「もうすっかり・・・とは言えないんだけど、何とか骨は元通りになったよ。」
「それは良かったです。」
「何だか初対面の子にまで心配かけて恐縮しちゃうなあ。まあ、とりあえずここどうぞ。」
私達がマスターから勧められた席に座ったその時、奥さんが買い物から帰って来た。
「あら、真木瀬君にサクラちゃん。いらっしゃい。あ、パパ!この子たちの指定席はあそこよ。」
そう言って奥さんはいつもの席を指差した。
「そうか、カップルシートだったな。」
「カップルシート?」
真木瀬君が言った。
「そう、あなた達が来てから私が命名したの。恋人達の特別席よ。」
そう言いながら奥さんは笑みを浮かべた。
「ちょ、ちょっと、恋人とか!」
真木瀬君は顔を真っ赤にしていた。
「そ、そうですよ、私たちまだ・・・」
私は動揺しながら言った。
「あれ?まだってことは、これから付き合うってこと?」
奥さんは満面の笑みで言った。
つい口が滑った。
「二人ともすごくお似合いだよ。真木瀬君もイケメンだしサクラちゃんも凄く美人だし、誰もが羨む美男美女のカップルだと思う。」
私たちは顔を真っ赤にさせながら、うつむいて黙ってしまった。
「もう付き合っちゃいなよ。」
奥さんの攻撃は止まなかった。デリカシーがないな。マスターは私たちの姿が滑稽に見えるのか、終始笑っていた。
私は何とかこの状況を打破しようと話をすり替えた。
「あ、あの!マコトは今日も来ないんですかあ?」
「ああ、マコトちゃんは昨日で終わり。とりあえずパパが帰って来るまでの約束だったから。あれ?聞いてなかった?」
「聞いてないですう・・・」
「そっか、マコトちゃんが来なくても、あなた達はいつでもいらっしゃい。特別席空けておくから。じゃあ、チョコレートパフェふたつね。今日は私の奢り。」
そう言って嬉しそうにチョコレートパフェを作り始めた。
パフェが運ばれてくると、私たちは急いでそれを平らげて、逃げるようにして店を出た。
行くアテもなくトボトボ歩いていたら、いつの間にか河川敷まで来てしまった。
風が心地よかった。真木瀬君は堤防にあぐらをかく。
ふと真木瀬君を見てみると、彼の口元にチョコレートがべっとりついているのに気がついた。
私はバッグからポケットティッシュを取り出して彼に差し出す。
「真木瀬君、口にチョコレートついてる。」
「え?マジか」
そう言ってティッシュを受け取ると、何枚か取り出してがむしゃらに口を拭った。
今度は彼が私にティッシュを差し向けてきた。
「サクラさん・・・・鼻」
「え?」
「鼻にクリームついてる。」
「え?うそ?マジ?」
彼は立ち上がるとティッシュを何枚か取り出して私の鼻を拭こうとした。
私は彼からティッシュを奪おうとする。でもその手は逃げていく。
「ちょっと、じっとしてて。」
彼は囁くように言った。その声がとても艶っぽく聞こえた。
私はなすがままになった。自然と私の指が彼の指に絡む。
私は恥ずかしくて彼の目が見れなかった。絡み合う指先から私のドキドキが伝わってしまったかもしれない。
2
一週間ぶりにマコトと会った。
何だか凄く久しぶりに会ったように感じる。
思っていた通り夏休みの課題に追われていたようだ。
久しぶりの彼女は何処か寂しそうな雰囲気を醸し出していた。
少し離れていたから、そんなのが見えるようになったのかもしれない。
「海に行こう。」
マコトは突然言い出した。
「海?」
「そう、泳ぎたい。だって夏休みなのに夏らしいことしてないじゃん。」
「いいね。海!」
「決まり!明日行こう!」
「明日か・・・」
「明日、まずいの?」
「いや・・・」
「何かあるの?」
「別に・・・・」
「何?」
「いや、真木瀬君もどうかなって思って。」
「はあ?何で真木瀬が出てくるの?」
「あの・・・みんなで行った方が楽しいかなって。」
「・・・・・私はサクラと二人きりがいい。」
「・・・・・そっか、そうだよね。」
急に不機嫌になった。お互い次の言葉が出てこなかった。
しばらくしてマコトの方が口を開いた。
「真木瀬、とりあえず誘ってみるか。」
そう言ってすぐ真木瀬君に電話をした。
「真木瀬、来るって。遅刻したら砂で全身埋めてやる。」
笑顔で言う彼女の目はまったく笑っていなかった。
待ち合わせ場所の品川駅に行くと、すでに真木瀬君が来ていた。彼が遅刻しなかったのはこの時初めてかもしれない。
むしろ遅れて来たのはマコトの方だった。
ホームには既に電車が来ていた。私たちは駆け足で乗り込んだ。
何駅か過ぎると席がまばらに空きだした。私とマコトは隣同士に、通路を挟んだ向かい側に真木瀬君は座った。
「海へ行こう」と言い出した彼女は終始ご機嫌ナナメだ。
いつものようなおしゃべりはない。
少しだけ重たい空気を感じる。
都心から離れるにつれて乗客が少なくなる。
しばらくして向かい側に座っていた真木瀬君が空いた私の隣に移動した。
私は彼を見て少しだけ笑って見せたけど、彼は何も言わず少し頷く。
さらに何駅か過ぎた頃、二人とも私の肩に寄りかかり寝落ちしていた。
肩に二人分の重さがのしかかる。
その重さに幸せを感じた。私にこうして寄り添ってくれる人たちがいることが凄く嬉しかった。
私はマコトの頭に自分の頭を寄せた。スースーという寝息が聞こえる。
しばらくして、今度は真木瀬君の頭に額を寄せてみた。心臓の音がする。多分それは私の音だろう。
その音が彼の心音と同調しているような気がして、とても心地良い気分になった。
そうしている間にいつしか私も眠ってしまった。
「サクラ!起きて。もうすぐ着くよ。」
私の腿をポンポン叩く。
目を開けるとマコトが私の顔を覗き込んでいた。
真木瀬君はまだ私の肩にもたれかかって熟睡している。彼女はその姿を見て大きな溜息をきながら、何も言わずに真木瀬君の頭を私の肩から離れさせようと、反対側に向くよう強く押した。
その拍子に彼は目を覚ました。
「・・・あれ?鮭は・・・?」
真木瀬君が言った。多分まだ夢の中なのだろう。
「鮭?」
「真木瀬、お前何言ってんだ?」
また眠ろうとする。
「って、二度寝するな!鮭って何なんだよ!」
マコトは真木瀬君の腿をベシベシと強く叩いた。
彼の見ている謎の鮭の夢と、現実世界にいるマコトの奇妙なシュチュエーションに私は吹き出してしまった。
いつものマコトに戻った。その嬉しさもあって私は笑いが止まらなくなってしまった。
三浦海岸駅のホームに降りると、空が灰色の雲で覆われているのが見えた。
「うわあ・・・嫌な空。」
マコトは言った。
「きそうだね、雨。」
「だから人が少ないのか。」
「いや、平日だからだろ。」
「そっか、夏休みだから気付かなかったけど今日は平日か。」
「しかも台風近づいてるぞ。」
「そうなの?」
「昨日の夜ニュースで見た。」
「だから風が強いのか。」
そう言い終えたところで計ったように強風が吹いた。
被っていた帽子が飛ばされる。私が追いかける前にマコトと真木瀬君が走り出した。
海岸へ着いた途端に雨が降り出した。
何かしようとするといつも雨だ。
私はきっと雨女に違いない。
何だかすっかりテンションが下がってしまった。
「まだ泳いでる人いるけど、どうする?」
マコトは言った。彼女もその状況に冷めきっていた。
「俺はいいや。」
同じく真木瀬君も冷めてしまっていた。
「何か冷たそうだね。」
「じゃあ、ご飯でも行こうか?」
「だな。」
とりあえず雨が酷くなる前に近くのファミレスに入った。そこからどうなったのか、あまり良く覚えていない。
ただ雨足が弱まるのをひたすら待っていた気がする。
何か話をした気がするけど、お互い空回りしていたように思う。
かつてのような安らぎをもう感じられなくなってしまっていた。
3
時刻は午後十一時四〇分。もうすぐ日付が変わる。
雨足は少し弱まったみたいだ。もう何時間もこうして机に突っ伏している気がする。
腕はすっかり痺れている。感覚はもうない。
今、ふと思い出したけど、あの時私、家の鍵を落としたんだよなあ・・・。
そういえばアパートの鍵掛けたっけ?
マコト帰って来てるかな?
もし、彼女がいたら気まずいな・・・。
携帯が鳴る。
感覚のない手を伸ばす。
うまく掴むことが出来なかったので、手で払って自分の方に引き寄せた。
着信は真木瀬君からだ。
私は痺れた手にありったけの力を込めて携帯を掴んだ。
晴れの日の瘡蓋【第八話】


