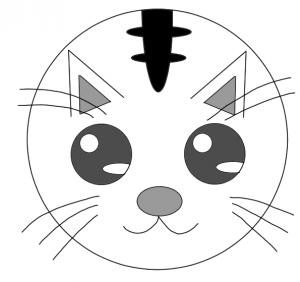オウカン
三題話
お題
「はい」
「ビンのふた」
「最終手段」
これで君とずっと一緒にいられる。
そう思ったんだ。
最終手段というより、最悪な行為だということは誰よりも自分が理解している。
立ち上る煙はゆらゆらと消えてゆく。
果たして彼女はこんな自分を見てどう感じるのか。
「…………」
遠くから、彼女の哀しそうな声が聴こえたような気がした。
◇
十数年振りだろうか、学生時代の友人が地元へ帰ってきたということで、久しぶりに会って飲もうという話になった。
いわゆる幼馴染として幼稚園から一緒で、こうして会うのは高校を卒業して以来だ。
旨い日本酒を買ってきたらしい。だから居酒屋へは行かず俺の家で飲むことになった。
「へぇ、お前はずっとココに住んでるのか」
「ああ。もう両親とも亡くなって今では独り暮らしだ」
「結婚はしないのか?」
「……そうだな。したくないわけではないが、あいにくそういう相手がいないもんでね。そういうお前はどうなんだ?」
「俺か? 俺も独り身だわ。仲間だな」
がしりと肩を組まれて息を吹き掛けられる。でも酒臭さは気にならない。自分の息も同じように酒臭いのだろう。
二人で飲んでいるが、一升瓶に入った日本酒はもう空になろうとしていた。
「ん、あれ、もうなくなっちまったな。ほれベイ太、この家に酒はないのか?」
「そのアダ名、懐かしいな。まあ当時は嫌で嫌でしょうがなかったけど」
「知ってる。助平のベイ太だからな。嫌なのをわかってたから使ってたんだよ」
「なんだよそれ。嫌がってるのを知ってたなら止めろよ」
今となっては笑い話に出来るほど、大人になれたのだろうか。
まあワザとそのアダ名を使っていたのは気付いていたような気がするし。
年月は平等に過ぎてゆく。
生きている人の時間は。
「なあ、ユウタ。この話をしたことはあったっけ」
「ん、なんだ?」
部屋の角に置いてある紙袋からオウカンの入った袋を取り出し、ユウタの前に置く。
ユウタはそれを持ち上げて、ジャラジャラと音を立てた。
「ああ、そういえばお前、オウカンを集めてたな。俺は興味なかったけど」
「これは、ヒーちゃんからもらったやつなんだ」
「…………そうか」
ヒーちゃん。小学生の頃に仲が良かった女の子。
毎日のように一緒に遊んでいた。
「ん、なんだこれ?」
袋を逆さにして広げられたオウカン。
「はあん、二つをくっつけてあるのか。それに、中に何か砂のようなものが入れてあるな」
ユウタは一つつまみ上げて、耳元で振っている。シャラシャラと音が聞こえていると思う。
「それのこと、誰かに打ち明けたかったんだ」
この地を離れる前に。
打ち明けてどうするのかはまだ考えていないけど。
「その中に入っているもの、実は、ハイなんだ」
「ハイ?」
「そう。焼けて残ったモノ。分かりやすく言えばイコツだよ」
「イコツって……まさか……」
「遺骨、だ。もちろんヒーちゃんのな」
その言葉で、ユウタの顔から笑顔が消え失せた。
一体何を思ったのだろう。ただ黙って俺を見つめている。
「そう、か。まさかそこまで強く想っていたとは、な。驚きだ」
あえてなのか、ユウタは軽い口調でそう言った。
「でもどうやって手に入れたんだ? そのほうが気になる」
「ん、どうって……普通に墓参りしたときに、な」
「はん、そりゃ普通だな。それで、そんな話を俺にしてどうするんだ?」
「別に、ただ誰かに秘密を打ち明けたかっただけだよ。深い意味はないんだ」
もしかしたら、言葉は間違っているかもしれないが、自慢したかったのかもしれない。
これだけ強く想っているんだ、と誰かにわかってもらいたかったのかもしれない。
自分でもどうして話す気になったのか、わからない。
「ははは、気持ち悪い話をしてごめんな。さ、うちにある日本酒を持ってくるから飲み直そうか」
◇
「ねえマーくん、どうしてこんなものを集めてるの?」
「ほら、このビンのふたって、オウカンって言うだろ。王様の冠。持っていると偉くなったような気がするんだ」
「あ、そうだね。形もなんだか似ているし」
彼女もオウカンを手に取り、まじまじと見ている。
「それじゃあ、マーくんは王様なんだね」
「うん。だからヒーちゃんはお姫様ね」
見つめ合った二人は、どちらからともなく顔を近付けた。
オウカン