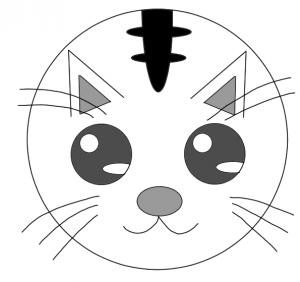sister-after-
夢乃が死んで、二ヵ月が過ぎた。
十月二十五日。本当なら今日は夢乃の十六歳の誕生日だった。
夢乃……俺の妹は俺の目の前で死んだ。俺の脳裏に儚げな笑顔を焼き付けて。
「く―――」
今でもあの瞬間の光景が頭から離れない。
夢乃は泣きそうな笑顔のまま、首元に当てたナイフを一気に引いた。その行為にどれほどの想いが込められていたのだろう。ためらいなく引かれたナイフは皮膚を裂き、頸動脈を切断して辺りに血液を撒き散らした。
夢乃の強い想いが噴き出したかのように、赤色の雨は俺に容赦なく降り注いだ。
そして俺は確かに見た。事切れるその時まで笑顔を崩さなかった夢乃が、前のめりに倒れ込む直前に一筋の涙を流したのを。
こんな終わり方しかできなかった夢乃は、しかしこれを望んでいたわけがない。
どのような想いを抱えて、どのような葛藤があって、どうしてここまで追い込まれてしまったのか。今となってもわからないでいる。
俺はあの時、夢乃に何をしてやれただろう。
受け入れていればきっと自殺することはなかっただろう。けれどそれは結末を先送りにしただけに過ぎない。
夢乃は気付いていたはずだ。もう出口はどこにもないのだということに。
あの濃密な三週間て夢乃は何度も感情を吐露していた。それはとても不安定で、すぐに壊れてしまいそうな危うさがあって、その姿は痛々しくて見ていられなかった。
初め俺のせいだと言った夢乃は、最期にありがとうと言って死んでいった。
その言葉の真意は俺にはわからない。
それこそが俺の罪なのかもしれない。
覚えている。前のめりに倒れたことで手が届くようになった夢乃を抱き寄せたときのあの冷たさを。
とめどなく溢れる血液は手で押さえただけでは塞き止めることはできない。痙攣する身体はただ絶望を伝えていた。
肌からは赤みが消え、熱も失われていった。
それは夢乃という一つの生命の終わりを表していた。
あの日から俺は脱け殻のような日々を送っている。数日間の入院の後、全てのことから逃げるように独りで暮らすアパートへ引き籠った。大学は休学し、バイトは辞め、両親とも景子とも連絡を取らないで何もすることなく二ヵ月が過ぎた。
両親からの追及にも警察からの事情聴取にも、俺はほとんど何も語らなかった。
夢乃を悪者にしたくなかった。それが俺にできる唯一の罪滅ぼしだと信じて。
新聞には小さく取り上げられたようだが、大々的に報道されることはなかったのが救いだ。
俺も、そして夢乃もきっと、世間に騒がれることは望んでいない。これは二人だけの問題で、俺と夢乃の出来事なんだ。
でもどうして夢乃は独りで死んだのだろう。夢乃がナイフを手にした瞬間、俺は自分が刺されるのだと思った。
でもそれはすぐに違うとわかってしまった。夢乃からは殺意が感じられなかったし、それに、夢乃は今すぐ消えてしまいそうな哀しみに満ちていたから。
夢乃は俺を残し、自分が消えることを選んだ。俺の心にこんなにも大きな傷を残して。
もしかしたらそれが夢乃の望みだったのかもしれない。
そしてそれは十分に叶えられている。
ずっと夢乃のことが頭から離れなくて、最期のあの時のことを毎日繰り返し思い出している。
まるで呪いのように、毎日繰り返される悪夢。
何をどうすれば良かったのか。
自問自答し続けても、出口の見えない迷宮に紛れ込んでしまって一向に真実(こたえ)は出ない。
無意味な変わらない毎日を過ごしてもう二ヵ月になる。
今日は十月二十五日。夢乃の十六歳の誕生日だ。
夢乃が高校生になって初めて迎える誕生日。
以前景子に言われたことを思い出す。
『もう夢乃ちゃんも高校生なんだから、誕生日プレゼントとかはちゃんと考えてあげないとダメだぞ。
背伸びしたくなる年頃だからねー。妹としてじゃなくて、一人の女性として最高のプレゼントを贈るつもりでいかないとガッカリされちゃうぞ。
特に好かれているのなら、なおさらね』
最後の一文は珍しく真面目な物言いだったから印象に残っている。景子が夢乃に会ったのはあの春休みの時の一度だけだったが、その時に何か感じるものがあったのだろうか。
それで俺は景子から言われた通り、夢乃に喜んでもらえるようなプレゼントを考えてみたわけだが、何も思い浮かばなかった。どうしても考え付かなかったらアドバイスくらいはする、と景子は言ってくれたが、何となく自分一人で考えないとダメだというニュアンスを感じ取ったからまだ助言を求めていなかった。
それにこの会話をしたのはまだ夏休みに入ったばかりの頃だったから、夢乃の誕生日まで考える時間は十分にあったのだ。
「夢乃……」
いつの間にかスマートフォンの待ち受け画面に設定されていた一枚の写真を見る。
春休み、俺と夢乃と景子の三人で酒を飲んだ時の写真。撮ったことは覚えていないがこうして残っている。
俺と夢乃はお互いの頬をくっつけて、赤ら顔のまま満面の笑みでピースをしている。
あの日はとても楽しかった。思い返すと顔が綻んでくる良い思い出。
そう、夢乃との思い出を良いものとするためには、夢乃と真剣に向き合わなければならない。
二ヵ月経ってようやくスタートラインに到達することができた俺は勢い良く立ち上がったが、立ちくらみで途端に座り込んでしまった。そういえばこの二ヵ月間ろくな食事を口にしていなかった。
酒のつまみとお菓子と、そして毎週日曜日にドアノブへ掛けられる袋に入っていた惣菜パンと栄養ドリンクが俺の命をかろうじて繋いでいた。
今日はちょうど日曜日。今は午前十時。だいたい午前中には届けられているようだが、どうだろうか。
俺は着替えて扉を開ける。ガサリという音とガンという音がほぼ同時に聞こえた。
「いたたたた……」
「あ、景子、ごめん」
毎週食糧を届けてくれていた主、景子はちょうどドアノブへ袋を掛けようとしていたところだった。
「ぐぬぬ……あ、久し振りだね、椎太。ふむ、その顔を見るに、ようやく立ち上がることができたというわけですか」
「……そうだな。景子には迷惑をかけた」
「仕方ないよ。うん、でも良かった。そろそろ警察と病院に通報しようと思ってたところだからさー」
景子の切り替えの早さはさすがだ。初めは少し涙ぐんでいたが、もういつもの調子を取り戻している。その冗談じみた軽いノリが今の俺には何よりありがたかった。
「いや、通報しようと思ってたのは本気だからね。椎太ってば外に出ないくせにあたしが食糧運んでくる音はしっかり聞いてたのはわかってるんだから。この逆覗き魔を逮捕してくださいーって」
「なんだよ、逆覗き魔って」
こうして俺のことを待っていてくれる人がいたことに感謝をする。毎週欠かさず来てくれることが唯一の心の支えだったことは否定できない。景子のおかげで、まだ生きている。
「それだけ元気なら、せっかくだからどこか食べに行く?」
「おう。でもその前に、最低限の栄養補給をさせてくれ」
俺は景子から袋を受け取り、中から栄養ドリンクを出して一気に飲み干した。
「それじゃあ、どこへ行こうか」
久し振りの陽の光は眩しすぎて、そのままトロけて消えてしまいそうだったけれど。
ようやくスタートラインに立つことができた俺は走り出さなくてはならない。
夢乃が何を想い、何を考え、どうしてあのような結末に至ってしまったのか。
他の誰でもない、俺だけは理解してやらなければならない。
それが俺にできる唯一の手向けだと思うから。
1/
景子と別れて、そのまま電車に乗り実家を目指した。こうして実家へ戻るのは年末年始以来だ。
窓の外を流れてゆく景色をぼんやりと眺めながら、俺は景子との会話を思い出す。
◇
「そういえば椎太は、その、夢乃ちゃんに捕まってる間はもちろん携帯とかには触れてないよね?」
景子には俺が夢乃に監禁されていたことは話したが、そこで何が行われていたのかは話していない。ある程度の予想はしていそうだが、俺に気を遣ってかあまり踏み込んで訊いてはこなかった。こういう気遣いはありがたい。
「そんなの当たり前だろ。それに地下だったから、たとえ手元にあったとしても連絡は取れなかっただろうがな」
「だよねー。じゃあ、やっぱりあれは夢乃ちゃんからだったのかなあ」
「……それ、どういうことだ?」
景子は自身の携帯電話をすばやく操作して、受信メールの画面を俺に示した。
「ほら、この日付はもう椎太が送ったやつじゃないでしょ。なんとなく、いつもと雰囲気が違うなあと思ってたけど、まさか夢乃ちゃんだったとは」
そこには俺が送った覚えのない、たくさんのメールが並んでいた。その初めのメールの本文を見てみると、俺が夏休みの間は実家へ帰るからしばらく会えない、という内容だった。
「あたしも椎太もあまりメールする方じゃないから。疑問形でも平気で数日空いたりするし。でもこのときはやけに返信が早いなと思ったのよねー。だからあたしもできるだけ早く返してたし。ほら、椎太はなんだかんだで寂しがりやさんだしー」
こうして見る限り、普通にやり取りしているだけのように感じる。夢乃は何のためにメールを送り続けていたのか。単に偽装工作のためだったのか、それとも他に目的があったのか……。
今はもうこの世にいない夢乃がココに残っているような気がして、俺はそのメールを次々と読み進めてゆく。
「……おい、どんなやり取りだよ、これ」
「ん? あー、この時の椎太はやけにエロかったよねー。懐かしいなー」
どんなことをされたいとか、どんな風にすると気持ちいいとか、そんな見るだけで恥ずかしくなるようなメールは今までにしたことがない。そもそもメールは、相手が見えないしただの文章だし、電話以上に苦手だ。話し言葉のままでは変になるし、まともに書けば堅苦しくなる。多少の変化は当たり前。それこそ、本人に成りすまして誰かが送信していても気が付かない。
「夢乃は一体何がしたかったんだ……」
「たぶん、だけどさ。あたしと椎太の距離感を知りたかったんじゃないかなー。けっこうきわどい内容も多かったし」
そう、なのかもしれない。今となっては夢乃の真意はわからないが、少なくともやり取りを続けようとしているように感じられる。内容がエロいことばかりだったのは複雑な気分だが、夢乃は俺と景子のことを深く知ろうとしたのかもしれない。
そのことを知られないようにしたのか、俺の送受信メールは綺麗に削除されていた。
その理由はわかりそうにない。
「それで、椎太はこれからどうするの?」
「……わからない。わからないけど、でも俺は見つけたいんだ。夢乃の望みや、俺はどうするべきだったのかを」
顔を上げると、景子は柔らかな笑顔でこちらを見つめていた。
「そっかそっか。いやー、あたしが夢乃ちゃんに嫉妬しちゃいそうだよー」
「どうしてそうなるんだ……」
「ジョーダンだよ。ジョーダン。それはきっと椎太にしかできないことだからね。頑張って、としか言えないけど、あたしはずっと待ってるから。椎太が納得のできる答えを見つけることができるまで。きっと見つけられると信じてるから」
まっすぐな瞳でそんな言葉をぶつけられて、俺は照れ臭くなって思わず視線を逸らしてしまった。
「ありがとう。できるだけ早く帰ってくるから」
◇
景子はいつも面白おかしくノリで動くタイプであるが、引くべきところは弁えている。本人はそう言われると照れてはぐらかしてしまうが、細やかな気遣いのできるとても優しい人なのである。
そういうところに憧れて、そういうところが好きなんだ。離れていても繋がっていると実感を得られる大切な存在。それは大きな心の支えだ。
でもここから先は俺と夢乃の問題。
俺は知らなくてはならない。夢乃の望みと俺が歩むべき道を。
たとえそれが不本意なものであっても――――
俺はそれを受け入れなければならない。
…
いくつか乗り換えをしてようやく辿り着いた地元の駅。前回帰省したのは年末のクリスマスが終わった後のことだったが、その時とまるで変わっていない。いろいろなことがあったからずいぶんと昔のことのように思えるが、あれから十ヶ月しか経っていない。
妙な懐かしさを覚えながら実家までの道を歩く。近付くにつれ胸の拍動が大きくなってくる。
緊張している。それは明白だった。
ゆっくりと歩を進め、二階建ての一軒家の門の前に立つ。車がないところを見ると両親は出掛けているようだ。
門を開いて敷地へ入る。一台分の駐車場を兼ねた小さな庭は手入れが滞っていて、雑草が伸び放題になっている。
二階を見上げると、そこは夢乃の部屋の窓。
玄関の前に立ち、鍵を開けてドアノブをひねる。
家の中はとても静かだ。ひんやりとした空気が身体を包む。
玄関の脇にある階段を使って二階へ上がり、ふわふわとおぼつかない足取りになりながら自分の部屋へ向かった。
一応まだ部屋は残されているものの、一部夢乃の荷物置場と化している。前回来たときよりも本棚のスペースが少なくなっていて、部屋の隅に置かれたダンボール箱の数が増えている。
窓際にある机の上に近寄ると、花柄の封筒が置かれていることに気がつく。
まるでスポットライトのように夕日で照らされている。
表に書かれた『椎太へ』というかわいらしい丸文字は、夢乃のもの。
中には綺麗に折り畳まれた便箋。夢乃の想いが綴られた俺宛の手紙だった。
…
夢乃からの手紙を読み終えた俺はベッドへ仰向けに倒れ込んだ。
「夢乃……」
呟く声は広がることなく消えてゆく。窓から差し込む西日が眩しくて目を閉じた。
俺は手紙の書き出しの一節を思い出す。
『この手紙が椎太に見られることなく捨てることができればいいな、と思います。』
そんな言葉から始まった手紙は、夢乃の揺れ動く心情が記されていた。
『私はずっと椎太のことが大好きでした。もちろん兄としてではなく、一人の男として愛しています。』
夢乃は自分で覚えていないほど昔から兄である俺のことが好きだった。思春期になり恋愛を理解できる年頃になると、妹としての自分と女としての自分との間で葛藤し、かなり苦しんだらしい。叶わぬ恋いは少しずつ心を蝕んでゆく。誰にも相談することができなかった夢乃は毎日のように泣いていたようだ。
でもその恋心を否定することはできない。普通ではないが、それが間違いだったとは言い切れない。人を好きになる気持ちはそれこそ人それぞれだ。俺のどこに惹かれたのかはわからないが、その気持ちは本物だった。
『何度も諦めようと思いました。妹としてでも椎太の側にいられればいい。そうすることが一番なのだと、そう思いました。』
叶わぬ恋は、諦めることでしか消化することができなかった。夢乃は何度も自分に言い聞かせることで、逆に傷付いていった。だけどそれは当然の報いなのだと受け入れてしまっていた。
なんと危うい、綱渡りのような対処法だろう。しかし誰にも言えない以上、そうするしかなかったのだ。その苦しみは夢乃にしかわからない。
もし俺が夢乃の気持ちに気が付いていれば、それでも何もできなかったかもしれないが、どうにかしてやりたかった。そうすれば、もしかしたら……。
『椎太に彼女ができたは聞いたときは驚きました。どんどん遠い存在になっていくような気がして、とても悲しくて、とても寂しかった。でも景子さんは椎太にお似合いな人だな、と思ったりもして、自分で自分がわからなくなって……』
夢乃の心は迷っていた。そのときの夢乃を支配していた感情は、好きな人を失うかもしれないという恐怖だったのだろう。不安に押し潰されそうになりながらも、それでも健気に、だけど密かに想い続けた。諦めるという選択をしていても、そう簡単に割り切れるものではない。
あわよくば、という想いは心のどこかにあったのだろう。
夢乃はずっと暗闇の中だった。どちらを選んでも報われることのない、まさに袋小路だった。
『椎太が振り向いてくれるかも、という気持ちはそのときに捨てた、はずでした。それでも好きだから、愛しているから、一緒にいるだけで心が満たされて幸せだから……私だけのものにしたいと思ったりしました。』
相手のことを一番に考える優しい心の持ち主でも、欲望という抗いがたい感情が芽生えてしまうことがある。それはとても魅力的で、心の隙間から甘い蜜となって浸食し、理性を包み込んで誘惑してくる。
夢乃は物静かで優しい女の子だった。でもそれは、本当の気持ちを押し殺して溜め込んでいただけなのではないか。こうした屈折した想いはかなりの負担になっていたと思う。自分の中の黒い闇と闘い続けることで、次第に心を擦り減らしていったのだろう。
いつか壊れてしまうのは当然の帰結だった。けれどその背中を押してしまったのは、他でもない俺自身だったのだ。
『春休みのあの日の夜、椎太にキスされて、体を触ってもらえて、私はもうこのまま死んじゃってもいいと思ったくらい嬉しかった。でも椎太は覚えていない。酔って寝ぼけていただけだから。それでも幸せだった。こんな私にはもったいないくらい、幸せだった。』
これが、俺の罪だった。夢乃は最後まで語らなかったが、この出来事が引き金だったのだ。俺はそれを全く覚えていない。だけどこれが真実なのだろうことは、今となっては疑う余地がない。
俺が夢乃を壊してしまったのだ。危ういバランスをかろうじて保っていた夢乃の心は、いとも簡単に崩れ去った。
本当の快楽を知ってしまった夢乃はもう後戻りなんてできなかった。例えどんな結末になろうとも求めずにはいられなかった。
この時、夢乃の心はある意味満たされた。満たされてしまった。決して叶うことがないはずの恋が、一瞬でもリアルに感じ取れてしまった。
それはとても温かくて心地好くて、歪んでいたけれど幸せだったのだろう。
夢乃にとっては恰好の口実となり、その想いは更に膨らんでいくこととなる。そして俺は夢乃に囚われ、欲望のままの三週間を過ごすはめになった。
──正直に言えば、あの時の夢乃は妖艶で魅力的で、このままでもいいかもしれないと思ったこともあった。それだけ夢乃の想いは熱烈だった。
『椎太を私だけのものにしたあの日。椎太に私の初めてを捧げたあの日。私は私でなくなった。きっとあの日に夢乃はいなくなってしまったんだ。椎太の妹は、もう……』
夢乃は、その想いを遂げるためには妹であることを否定しなければならなかった。妹としてではなく、一人の女の子として俺を求めたからだ。でも否定すればするほど自分の居場所はなくなっていった。それも当然か。俺の妹である事実は覆すことなんてできるわけがなく、夢乃は、別人になるしかなかった。その行為は自己の存在を否定することに他ならない。
夢乃ではない、誰かとして。俺の妹ではない誰かにならなければ心が耐えられなかった。兄妹の禁忌を犯そうとしていた夢乃は、その罪に囚われ苦しんでいた。
でも気付いていただろうか。自分以外の誰かになったら、もう何も得られなくなるということに。
今まで兄妹であることに苦しんでいた夢乃は、それを否定することで一時的に苦痛から解放された。
好きだから苦しかった。苦しいのに好きだった。その想いは確かに本物だったのに、安易な道へ逃げたことでその想いさえも穢されてしまった。
夢乃という存在はもう破綻していたのだ。この矛盾した想いを抱えたまま、どんどん深みに嵌まっていった。
『もう私の中には何も残っていなかった。あんなにも強い想いがあったのに……あんなにも苦しんでいたのに……あんなにも、誰よりも椎太を愛していたのに……』
もし夢乃がもっと早く間違いに気が付いていれば、もし俺がもっと早く夢乃の気持ちに気が付いていれば、あんな終わり方はしなかったのかもしれない。縋るものを失ってしまった夢乃はそのまま消えることを選んだ。
苦しむことは辛いこと。だけどそれが何よりも確かな愛の証だったのに。
それすら失った夢乃はまさに、欲望を満たすだけの獣となった。
そこには愛は存在しなかった。
『どうしてこうなってしまったんだろう。私は、ただ椎太を愛していただけなのに。
もう、わからない。』
そして、手紙の最後にはこう綴られていた。
『椎太、今までありがとう。
でもごめんなさい。私はもう後戻りなんてできないから……』
◇
目を開けると、すでに日が沈み部屋の中は暗くなっていた。
どうやら眠ってしまっていたらしい。頭の後ろで手を組んだまま寝ていたせいで、両腕が痺れて感覚がなくなっている。
ぼんやりとした頭で天井を見つめる。
夢乃はもうこの世にいない。そのことを誰よりもわかっているのに、どこか夢乃を感じてしまう。
……あの手紙を読んだせいだろうか。より深く夢乃の気持ちを理解してしまったから、以前より身近に感じてしまう。
そんなことは、あり得ないのに。
薄暗い部屋の中で後悔の念に苛まれる様はとても滑稽だ。今更何もできることはないのに、何かをできるような気がしている。
なぜか、笑えてきた。乾いた笑いが空しく響いて消える。
部屋の中はとても静かだ。机の上にある目覚まし時計の秒針が、チッチッチッと規則正しく時を刻む。
どれくらいそうしていただろうか。やがて外から車のエンジン音が聞こえてきた。
両親が帰ってきたらしい。玄関が開く音。階段を上る足音。そしてその足音は俺の部屋の前で止まった。
扉が開かれるのと俺が身体を起こしたのは同時だった。
「──椎太」
退院以来に見た母親の顔は、別人かと感じるほどやつれて見えた。
2/
次の日、俺は夢乃が眠る墓の前まで来ていた。
両手で花束を持ってその場に佇む。
夢乃が好きだと言っていたパンジー。ちょうど今くらいの時期に実家で育てていたのを覚えている。
パンジーは、片想いをしている人にはぴったりな花であるらしい。好きな人にプレゼントすれば、花言葉で内に秘めた想いに気付いてくれるかもしれない、と。夢乃はそのことを知っていただろうか。それを知っていたからこそ好きな花だったのだろうか。
もちろん知っていただろう。花が咲いたら俺にいちいち報告してきたのも、そのアピールだったのかもしれない。俺が花言葉なんて知るはずもなく。だからこそ意味があったのだ。
夢乃にとっては、直接告白することはできないが故の代償行為だったのだろう。
俺は墓石に花束を立て掛け、両手を合わせて目を閉じる。夢乃の最期の笑顔を思い出して胸にずきりと痛みが走った。
夢乃はもう帰ってこない。その当たり前の事実を、俺はこの時ようやく実感して、夢乃を失った悲しさから涙を流すことができた。悔いることがあるとすればそれは、直接謝ることができなかったこと。夢乃にもう一度会えるのならばちゃんと謝りたい。例え赦してもらえなくても、それでも謝り続けたい。
ひんやりとした風が吹いて、立て掛けた花束が悲しげに揺れる。空には雨を予感させる暗雲が垂れ込めて、まるで夢乃の気持ちを代弁しているかのよう。
俺は虚空に手を伸ばした。もしここに夢乃がいるのなら、抱きしめてやりたかった。
夢乃はいろいろなものを失ってしまったと言ったが、そんなことはない。俺の中にはこんなにも夢乃が残っている。恋人にはなれないけれど、大切な家族であることに変わりはない。
だから俺は罪を背負う。夢乃の分も一緒に。
夢乃が抱いた想いも、夢乃が苦しんだ痛みも、夢乃が選んだも、俺が背負う。
夢乃は昔から一人で抱え込み過ぎだ。どうすることもできなかったかもしれないが、もしも二人で考えることができていたならば、もっと違う未来があったかもしれない。
目を開いたところで、ぽつりぽつりと、空から少しずつ溢れ出す。
頭上は厚い雲に覆われて辺りが暗くなっていた。本格的に雨が降り出すまではそう時間はかからなかった。
「夢乃……もっと、泣けばよかったんだ」
悲しいときも苦しいときも、一人で耐えてきた夢乃。幼い頃はなんとなく察することができたが、大きくなるにつれてわからなくなっていった。兄妹なのだから、決して無視したりはしなかったのに。
夢乃は、それが許せなかったのだろうか。
見上げた空から容赦なく冷たい雨が降り注ぐ。だんだん重く冷たくなってゆく身体。この不自由さが罪の証となる。
俺はこの場から動けなかった。
雨に濡れた花束が、風に吹かれて倒れ込む。
そのゆっくりと倒れる様は夢乃の最期を思い出させる。
あの時、俺は赤い雨に濡れながら夢乃を抱きしめた。
花束を拾い上げて胸に抱く。がさりとビニールが悲しげな音を立てて、微かな甘い香りが心を乱してゆく。
ひどく胸が痛む。夢乃はこの痛みを抱えていたのか。
俺はこの痛みを忘れない。
それが俺の中に夢乃が生き続けている証だから。
◇
その日の晩、雨に長く打たれていた俺は熱を出して寝込んでしまった。
意識は朦朧として頭は鉛のように重い。熱を帯びた身体はふわふわと、まるで別人のものとなってしまったかのようで落ち着かない。
風邪薬の効果はまだ出ないようだ。苦しげに息を荒くしながらも、だんだんと眠気が強くなり目蓋が重くなってくる。
視界は揺れて、輪郭を失ってゆく。
そのままゆっくりと夢の世界へ落ちていった。
…
暗闇。周りには何も見えない。
その何も無い空間にただ佇んでいる。何をすることもなく、何を考えることもなく。
どれくらいの時間そうしていたのだろう。ふいに後ろから声が聞こえてきた。
「────しいた」
消え入りそうな微かな呼び声。その声に懐かしさを感じた。
ゆっくり振り返ると、そこには一人の女の子。
「…………」
俺は息を呑んだ。驚きと喜びと、悲しみと戸惑いと、いろいろな感情が入り交じってうまく表現することができない。
振り返った先には、夢乃が立っていた。
俯いていて表情は見えないが、その立ち姿は確かに夢乃だ。高校の制服に身を包み、両手はまるで祈るように胸の前で合わせていて……それは少し震えているように見える。
「夢乃、どうして」
ようやく顔を上げた夢乃の表情は、困っているような怒っているような、それとも悲しんでいるような、感情を読み取れないものだった。夢乃は口を噤んだままこちらを見ている。何かを言おうとしているようだが黙ったままだ。
俺はその場で夢乃を見つめる、お互いに歩み寄ることもなく、無言のまま、静かに時は過ぎてゆく。
手を伸ばせば届きそうな距離。だけどそれがとても遠く感じる。
夢乃は目を閉じて、ゆっくりと深呼吸をした。そして俺に笑顔を向ける。どうしてそんなに泣きそうなのか。どうしてそんなに、俺の心を締め付けるのか。
「……え?」
夢乃は小さく口を開いて何かを呟いたようだったが、声は聞こえなかった。だけどその動きは確かに『ごめんなさい』だったように思う。謝りたいのは、俺のほうなのに。
そして夢乃は俺に背を向けて、離れていこうとする。
「おい、夢乃──」
なぜか、その場から動けなかった。
「夢乃っ!」
叫んでも、夢乃は歩みを止めない。
「夢乃……」
遠くなり、姿は闇に溶けて見えなくなった。
自分だけが取り残されて、周りには何も見えない。何も聞こえない。胸がざわつき、急に不安が襲いかかってきた。
暗闇が怖いわけでも、独りが寂しいわけでもない。
俺は何に怯えているのだろう。
寒気を感じて両腕を抱く。指先はひんやりと冷たくなっていた。
ああ、そうか。『何もできないこと』が怖いのか。ちゃんと夢乃に謝りたいのに、それをすることができない。俺はなんて無力なのだろう。
きっと夢乃も、この苦しみを抱えていたに違いない。内に秘めた想いだけが膨らみ、いつ限界を迎えるのか、終わりの見えないカウントダウンに怯えていたんだ。
俺は想う。もし夢乃が俺のことを好きにならなかったら、普通の兄妹でいられたのだろうか。その普通さえ俺にはわからないのだけれど。それでも夢乃がこんなにも早く、俺の目の前で死ぬことはなかったはずだ。
そう考えてしまうことが、夢乃を一番傷つけていたというのに。
「夢乃……戻ってきてくれ……」
悪寒が酷くなる。がたがたと震える身体は治まってくれない。
その時、背中から温もりが伝わってきて胸の前に柔らかな手が重ねられた。ふんわりと漂う微かな甘い香りは、俺の良く知る匂い。
たったそれだけのことで、身体の震えは消えてなくなった。
「もう、そんな顔をされたら離れられないじゃない」
「──夢乃」
優しく重ねられた手を取りゆっくり振り返ると、そこには夢乃がいた。
「ねえ椎太、本当に私でいいの……?」
その問いに対する答えは一つしかない。俺は夢乃を引き寄せて、強く強く抱きしめた。
溢れる想いはどこまでも、溢れる涙は見せないように。鼻を夢乃の頭に押しつけて息を吸うと、胸いっぱいに広がる甘い香り。それはとても心地好くて愛おしい。
「夢乃、俺は──」
顔を上げると、遠くに人影が見えた。暗闇だから見えるはずがないのに、なぜかそれが誰なのかわかってしまった。
彼女は必死で何かを叫んでいる。こちらへは近づいてくることはなく、だけど右手を伸ばして、俺に何かを訴えようとしている。
しかし、彼女の声は俺には届かなかった。
まるで消音のテレビを観ているかのような虚無感。向こうが必死であればあるほど滑稽に見えて、こちらの心は反比例に冷めてゆく。それを悟ったのか彼女は大人しくなり、悲しげな眼差しをこちらへ向ける。
それは初めて見る表情。俺の知らない彼女がそこにいた。
心にちくりと痛みが走る。無意識に何かを感じ取っている。
もしもここで引き返すことができていたのなら、それで終わっていたのだろう。だけど俺はそれ以上に、どうしようもなく馬鹿だったのだ。
「ねえ、どうしたの?」
夢乃が顔を上げて俺を見る。鼻同士がぶつかりそうな距離で見つめ合い、互いの呼吸が重なり合う。今の俺には夢乃しか見えていない。
ちらりと視線を前に戻すと、そこにはもう何もなかった。さっきのは幻だったのか。今ここには俺と夢乃の二人しかいない。
「俺は、夢乃がいいんだ。夢乃がいれば、それでいい」
その言葉を聞いた夢乃は目を見開いて驚き、そして静かに笑みを浮かべた。それはとても幸せそうな、だけどどこか悲しげな。
「私も、椎太がいてくれたらそれだけで幸せ──だから、ずっと私のそばにいて……」
それはまるで呪文のように、俺の中に響きわたる。
…
目を覚ますと、そこは真っ暗だった。
寝起きで頭だけでなく視界もぼんやりして、何も考えられない。少しずつ焦点が定まってくると、ようやく視界が開けてくる。
ここは実家にある俺の部屋。いったいどれだけ眠っていたのだろう。
妙な夢を見たせいで頭が混乱している。そんなことはあり得ないのに、俺はどこかに夢乃を感じてしまう。夢乃はもうこの世にいないというのに。
「夢乃……」
小さな呟きは虚空に霧散する。広がることもなく、誰に伝わることもなく。ただ自身にのみ届く呪いの言葉。
「夢乃……」
呼べば目の前に現れるというのか。そんな馬鹿なことはないとわかっているのに、俺は求めてしまう。
「夢乃……」
それ以外のことは考えられなかった。今の俺の中には、夢乃しかいない。
身体を起こすと頭がふらふらと落ち着かない。
俺は膝に顔を埋めて、震える身体を強く抱きしめた。
──目を閉じればもう一度会えるのではないか。
そんな淡い願いは当然叶うことがなかった。
3/
俺はまた、夢乃の墓の前に立っていた。数日前のパンジーはまだ色鮮やかに横たわっている。
もう十一月になるというのに立っているだけで汗ばんでくる陽気だ。水を撒くと水滴がキラキラと輝いて、まるで宝石を散りばめたかのよう。俺はその場に佇んで、流れてゆく透明な水をぼんやりと眺めている。
夢の中で、俺は夢乃を選んだ。後悔の念が産んだ幻想だったとしても、あの時は、確かに夢乃と再会していた。
だけどどれほどのリアルを感じていたとしても、夢であったことに変わりはない。あの夢乃は夢乃であり得ないし、俺が脳内で作り上げた都合の良い幻想でしかない。
それでも……俺は信じたかった。
夢乃は俺に会いに来てくれたと。
それこそ都合の良い話だけれど。
こんなにも、夢乃のことを、愛してた。
兄妹のものでしかないけれど、夢乃が大好きだった。もしも兄妹ではなかったら、恋人同士になっていたかもしれない。それを夢乃に伝えられればよかったのに。
空を見上げると、輝く太陽に目が眩んだ。
その光の中に、夢乃が見えた気がした。
◇
帰ろうとしたとき、ポケットの中のスマホが震えた。取り出して画面を見ると、そこに表示されているのは景子の番号。俺は動かそうとした親指を一瞬ためらって、だけど数コールの後に通話ボタンを押して電話に出た。
「……もしもし」
「あ、椎太……その、どうだった?」
恐る恐る話しかけてくる景子。そういえばこちらへ来てから全く連絡をしていなかったことに、今更気が付く。
「……ああ、ごめん。連絡、してなかったな」
「ううん、それはいいの。待ってるって言ったのに電話しちゃって、ごめんね」
景子がこちらを気遣っていることが痛いほど伝わってきて、俺は胸が苦しくなった。自分でもわかっている。今の俺は、どっちつかずで心が揺れている。
……どちらかといえば夢乃のほうに傾いているだろう。だから余計に気まずい。
「景子、今はまだ帰れそうにない。もう少し、時間がほしい」
こんなのは言い訳だ。結論を出すことから逃げているだけということはわかっているのに、俺はその一歩を踏み出すことができない。
時間が解決してくれるとでも? いや、余計逃げ場がなくなって苦しくなるだけだ。
そのこともわかっているのに、俺はまた、同じ過ちを繰り返そうとしている。
「うん、わかった。椎太の気が済むまで、気持ちの整理がつくまで、ずっと待ってるから」
そんな俺の心中をどれだけ察したのだろう。景子はいつものように、俺に優しい言葉を掛けて、信頼して、待っていてくれる。今はその気遣いが俺の心に突き刺さる。
申し訳ない気持ちになりながら、だけど俺はその言葉に甘えて、逃げることを選んだ。
それは最悪の選択であったことに間違いはない。
これが夢乃が望んだ結末なのだろうか。
囚われて、逃げられなくて、いつまでも離れられない。
俺は最期まで、選択することができなかった。
/
『椎太、今までありがとう。
でもごめんなさい。私はもう後戻りなんてできないから……』
そして私はペンを置いた。
読んでもらえるかわからない手紙。椎太が見つける頃には、私はもうこの世にはいないだろう。
そう、この世にはいないのだ。
椎太はこの手紙を読んでも私の気持ちを理解することができないだろう。だってそういう人だから。人の感情に疎いというか、何も考えていないというか、事なかれ主義の日和見主義というか。とにかく他人の気持ちがわからない人なのだ。
だけど好きになってしまったのだから仕方がない。
わかってもらうためじゃない。呪いを残すためなのだ。
椎太の中から一生消えない呪い。
だから先に謝っておく。
椎太、ごめんなさい。
だけどこれで、私のことは忘れないよね。
sister-after-