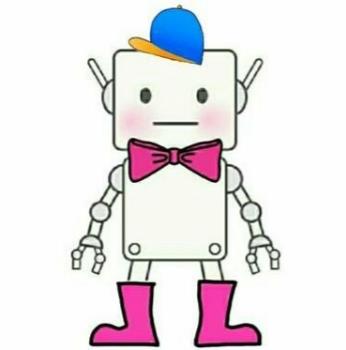
A.Iによる自動運転
井上は馴染みのカーショップに着くと、錆びたトタン板沿いに裏手へ廻った。生け垣の間の狭い路地を抜けると、年代物の作業場をのぞき込んだ。
すでに改造は終わったのか、リフトから降ろされた愛車が井上を出迎えてくれた。1週間ぶりの再会だ。ぐるぐると愛車をなで回すように見ていると、背後から声が掛かった。
「おう、早いな。受け渡しは13時の約束じゃなかったっけ」
振り向くと、長年世話になっているショップの親父さんが笑っていた。
「どうにもこうにも待ちきれなくて。もう終わったんですか」
親父さんは顔をタオルでぬぐいながら頷いた。
「あぁ、さっき試運転から戻ったところだ」
試運転という言葉を聞いた井上は、体をこわばらせゴクリと唾を飲み込んだ。
「どうでした? ……」
「バッチリだ。自分で販売しておいてなんだが、実際乗るとすごいよ」
親父さんは上気した顔で興奮気味に言う。
「そうですか、すごいんですか」
なんだか自分が褒められたみたいで、井上は背中がこそばゆくなった。
ついに念願のAI運転システムを手に入れた。
いや、正確には後付けAI運転システムだ。本当は大手メーカーのAI搭載車が欲しかったのだが、ディーラーで出された見積金額は800万円。政府の補助金を最大限適用しても600万を超える。とても手が届く物ではなかった。
「楽する為にAIが欲しいのに、手に入れるには過労死寸前まで働かなくてはいけないって、どうなのよ」
笑い話のつもりでショップの親父さんに話すと、親父さんは、実はこういう物があるのだが、と急に真剣な顔つきになり話を切り出した。それこそが、今回井上が購入した後付けAI運転システムだった。
費用は200万円で改造に1週間。名古屋市内の会社まで電車通勤の井上にとって、車を1週間預けるのに異存はない。問題は費用の200万円だ。井上はさんざん悩んだ末、生命保険の解約金をあてることにした。井上の生活の中で最も死亡の可能性が高いのが、車の運転時だ。車をAI運転化することで死亡保険は無用の長物になる、という理屈で自分を無理矢理に納得させた。病気になったらどうしようという不安が一瞬頭をよぎったが、AI運転の魅力には勝てなかった。AI運転技術は人類にとって大いなるパラダイムシフトになると井上は確信していた。エンジニアの端くれとして、いち早く体験することは自分の責務であり権利なのではないか、とまで考えていた。ただし、家族にはまだ内緒だ。
改造当日、井上はエンジニアとしての血が騒ぎ、親父さんの手元をのぞき込んだが、集中できんと怒鳴られてしまった。
「親父さんに追い払われちゃったよ」
事務所に逃げてきた井上が従業員に愚痴ると、きれいなツナギを着た若い兄ちゃんは笑った。
「オーナー短気ですからね。普段は仕事は見て盗めって言うくせに、AI運転システムの取り付けだけは僕らにも見せてくれないんですよ」
「へぇ、集中しないとできないのかな?」
親父さんの腕を知る井上は不思議に思った。兄ちゃんは、そうかもしれませんね、と気のない態度で答えてから、あっと言ってテレビを指さした。
「井上さん、これ不思議じゃないですか?」
井上がテレビを見ると、高齢者の暴走事故のニュースが流れていた。
「またか、最近多いよな……。不思議って事故のこと?」
人間歳を取れば、若い頃のように物事ははかどらなくなる、当たり前のことだ。
「なんでこんなニュースが流れるんでしょうね」
「なんでって、実際に事故が起きているからじゃないのか」
井上は思ったことを素直に口にした。
「そこなんですよね。これって自動車メーカーにとっては流して欲しくない不名誉なニュースですよね。」
「まぁそうだな」
井上は年代物のテレビを見ながら答えた。運転していたのは87歳か、怖いなぁ。
「自動車メーカーって、テレビ局にとってお得意様ですよね。スポンサーを降りるぞとクレームがつくのが普通だと思いませんか? ところが毎日のようにニュースは流れる、ということは、自動車メーカー側がこの手のニュースを流すように仕向けている。そう思えないですか?」
井上は、テレビから目を外して、兄ちゃんの横顔をまじまじと見た。
「でも自動車メーカーにメリットなんてないだろう」
「そこで颯爽と現れるのがAI運転ですよ。実際、高齢者の事故報道と歩調を合わせるようにAI運転という言葉が広まり始めてますからね。もっと言えば、たいした議論もなくAI搭載車への補助金が決まったのだって、事故報道の影響が大だと思いますよ」
兄ちゃんは話し終えると、ウンウンと自分の言葉に相槌を打った。
そんな風に考えたことなどなかった。しかし、兄ちゃんの言葉にも一理あるのではないか? 考え込んでしまった井上の様子を見て、兄ちゃんは慌てて言った。
「まぁ、今のは僕の勝手な想像なんで気にしないでください。それよりも、この度はお買い上げありがとうございます。ウチも結構売上苦しいんで、井上さんに買ってもらって助かりましたよ。待ち遠しいですねAI運転」
兄ちゃんのとってつけたような笑顔に、井上はなんだか腑に落ちないまま、あぁと頷いた。
システムのこまごまとした説明を聞き、何枚もの受け渡し書類にサインをした後、ようやく愛車のキーを受け取った。
親父さんと兄ちゃんに見送られ、自分の運転でショップから走り出す。バックミラーに親父さんが深々と頭を下げているのが見えた。この店でずいぶんと車いじりをしてきたが、親父さんに頭を下げられるなんて初めての経験だな。心に浮かんだ疑問を整理するまもなく、ショップの古びた看板はすぐに小さくなった。
最初に見付けたコンビニの駐車場で車を停める。
「さて、どこへ行こうか」
誰ともなしに呟きながら、カーナビの地図を眺める。このまま家に帰るのもつまらない。とりあえず、数キロ先のショッピングモールにでも行くか。AI選択画面から、1時間100円の安全運転モードを選択した。モードは従量制課金ではあるが、距離を乗らない者からしたら実に合理的ではないかと井上は感心した。
ボタンを押すと10秒ほどで、インパネに取り付けられた赤のランプが緑に変わった。と、同時に勝手にハンドルが回りだし、エンジンがうなりを上げる。
「うぉっ」
思わず声が出てしまった。
車は駐車場の出口で一時停止をしてから、さも当然のように道路へと乗りだした。車間距離やアクセル開度にもぎくしゃくしたところは全くない。まるで幽霊が勝手に運転しているようではないか。運転席で、会社の役員に叱咤されたように硬直する井上のことなどお構いなしに、車は実に滑らかに走行する。
「これは凄い」
井上は運転席で大きく息を吐いた。興奮で血流が猛スピードで体中を駆け回っている。めったに笑わない職人気質の親父さんが試運転で興奮していたというのも納得できる。期待道り、いや期待以上の出来映えだ。
少し経つと、ようやく胸のドキドキがおさまってきて、周囲に目をやる余裕が出てきた。井上の手はハンドルにそえられている。周りを走るドライバーには普通に運転しているように見えるだろう。ところがどっこいこちらは本当の『自動』車なんだよ、周囲を走るただの車のドライバー全員に吹聴してやりたい。
実は後付けAI運転システムには、とある制限事項がある。まず、運転席に座っている必要がある。そして、いつでも自分で緊急操作ができる体勢をとっていなければならない。ここが大手メーカーのAI運転システムとの大きな違いだ。
「これで200万とは安い。いい買い物をしたぞ」
これらの制限事項にも井上の満足度はいささかも欠けることはなかった。幹線道路を左折すると、ショッピングモールの建物が目に入った。車は意思を持って確実に目的地へと到達しようとしている。心持ちスピードを緩めたようだ。ブレーキのタイミングやハンドルの切り角度などが自分の感覚と微妙に異なり、気持ち悪いなと思った時、鋭いブレーキ音とともに車が急停止した。
「なんだっ!?」
つんのめりそうになる体を支えながら顔を上げると、突然目の前を自転車に乗った老人が猛スピードで横切った。驚愕で顔面蒼白の井上のことなど気にする様子もなく老人はごく当然のように走り去っていく。
いつでもブレーキを踏めるように心の準備をしていたつもりだったが、あまりに突然の出来事に井上の右足はピクリとも動かなかった。自分の運転なら確実にぶつかっていた、背筋に冷たい物が流れた。
車はまるで周囲を確認するかのように数秒間停止した後、何事もなかったように動き出した。井上は知らず呟いていた。
「こいつは本当に凄い」
この車なら再び伊勢に行くことが出来るのではないか。ウインカーが点滅を始めた。そうさ、行けるさ、車がそう言っているように思えた。ショッピングモールはもう目の前だ。
記念すべき初のAI自動運転は大成功だった。
自宅付近でAI運転を解除する。井上は、昔から運転には自信がない。車が好きなくせに、運転自体はからきしだ。車庫入れもAI運転にお任せしたいが、家族にはまだ内緒にしておきたい。伊勢行きはサプライズでないとな。散々苦労してなんとか駐車する。
家に入ると、息子の篤史(あつし)が居間で背中を丸め、テレビゲームをしていた。
「なぁ篤史、また伊勢行きたくないか?」
井上は何気ない風を装って声をかける。篤史はゲーム画面から目を離さないまま返事を返してきた。
「伊勢って、親戚のおばさん家?」
「あぁ、憶えてないか、小さい頃みんなで伊勢までドライブしたろう。楽しかったなぁ」
返事が聞こえるまでしばらく間があった。
「……考えとく」
「ゲームばかりじゃなく、たまには外に出て現実と向き合わないとな」
ゲーム画面の中で、草原を歩く主人公のキャラクターが動きを止めた。
「……、ぼくなりに向き合っているよ」
篤史の真剣な声に井上はとっさに返答ができず戸惑った。
「あっ」
篤史の声につられてゲーム画面を見ると、主人公が大きく口を開けた怪獣に近づいているところだった。篤史の手がコントローラーを素早く操作した。主人公は、食べられる寸前でなんとか身を躱し、命拾いしたようだ。篤史から伝わるほっとした空気にいたたまれなくなった井上は、明るい調子で声をかけた。
「ごめん、邪魔しちゃったな、まぁ予定とかいろいろあるから考えといてくれ」
なんにせよ、夢中になれるものがあるのはいいことだ。でも篤史は最後までこちらを見なかったな。昔はおしゃべりな子だったのに、思春期に入ってから話さなくなった。悩みを抱えているのなら相談に乗るのだが、会話すらままならない現在の状態でそれは望むべきもない。
夜、晩酌を楽しむ井上の前に憂鬱な顔の妻が座った。井上はお猪口を持つ手を止めて妻の顔色を伺う。もしや保険の解約がばれたのか?
「篤史が転校したいって」
予想していなかった話題に声が裏返った。
「転校? 」
「学校生活で悩んでいるみたいなの」
悩みがあることは気付いてはいたが、それにしても、転校とはあまりに性急すぎないか。
「公立は学区が決まっているから、私立ってことになるわね」
そう言って妻は深いため息をついた。私立は金が掛かる。息子の教育は妻に任せきりの井上にだって、そのぐらいの知識はある。
結局その夜、妻に200万円のAI運転のことは言い出せなかった。
愛車をAI運転化してから、数日。最初はいちいち喜んでいた井上だったが、予想もしていなかったAI運転の特徴にイライラすることが多くなっていた。
路肩に人がいれば停止寸前まで徐行。守る者などいない住宅街の20km制限道路も律儀に20kmで運転。今日など、路地から出てくる車に次々と道を譲っていた。その時井上は、渋滞する車の少し前を歩いていた華やかな服装の若い女性に見とれていて気が付かなかった。あれっ車が動いていないと思った時、後ろの車からクラクションを鳴らされてしまった。
安全運転モードは現実の道路では使い物にならないと、井上は早々に判断した。仕方なく1時間500円の流乗モードを多用することになる。これでやっと実際の運転の感覚に近くなった。まったくうまい具合にできているなぁと感心するしかなかった。
最近妻は眉間の皺がまた深くなったようだ、考え込んでいることが多い。
「篤史がね、銀行口座の名義を貸してくれって言うの」
「口座なら篤史も持っているだろう?」
妻はウウンと首を振った。
「ゲームで貯めたポイントが換金できるらしいのよ。振り込み先が未成年の口座だと駄目なんだって」
こないだやっていたゲームだな。ちらりと見ただけでも井上が子供の頃遊んでいたテレビゲームとは全く別物だということはわかった。てっきり純粋にゲームを楽しんでいると思っていたのに、目的が金と聞いた途端、きれいなキャラクター達の色彩が薄汚れてしまったように思えた。
「どれくらいの金額なんだ?」
妻はため息をついて首を振った。
「1日頑張って500円くらいなんだけど、どうも篤史、自分で私立の費用を貯めようとしているみたいなの」
アルバイトの出来ない中学生にとっては大きな金額かもしれないが、私立の費用を稼ぐ頃には篤史はとうに成人になっているだろう。
「それであんなに真剣にゲームをやっていたのか」
「1回でも失敗したらポイントがなくなっちゃうんだって」
篤史を叱って、ゲームを辞めさせようと考えていた井上は、金を貯める目的を聞いて考え込んでしまった。もっと早く気付いていれば、保険の解約金を廻すことも出来たんだがなあ。いやそれよりも今の学校に馴染む努力の方が先か。考え込むほど背中の荷物が重みを増してくる。井上と妻は互いに無言でしばし時を消した。しばらくして、井上は重い沈黙を振り払うように言った。
「なぁ、篤史にも言ったんだけど、また伊勢行かないか?」
妻の反応は鈍かった。
「本家のおばさん私苦手なのよね。こんなこと言いたくはないけど、何かというと家柄を自慢してくるでしょう」
妻の眉間のしわがいっそう深くなったので、井上は慌てて言った。
「いや、本家には寄らずにさ、家族旅行だよ。道中楽しかったじゃないか、車の中でいろいろな話ししてさ」
井上がそう言うと、妻も思い出したようだ。
「篤史、途中で大きな遊園地を見て喜んで車の窓を開けてたわね」
「そうそう。顔を外に出して、まん丸の目で見てたな」
二人で笑った。伊勢湾岸高速沿いにある遊園地、ジェットコースターが高速道路ぎりぎりまで迫ってきていて、大迫力だった。
「あれ見たらさ、篤史も気分が変わると思うんだよな」
井上が言うと、妻は不安そうに言った。
「でもあなた伊勢まで運転できるのかしら。10年前でさえ冷や汗まみれでハンドル握ってたじゃない」
「その点は心配ない、大丈夫だ。任せろ」
井上の自信溢れる言葉にも、妻の表情は変わらなかった。AI運転のこと知ったら驚くぞ、井上は伊勢行きの日が楽しみになってきた。篤史だってそうだ。伊勢神宮に行けば大丈夫、天照大御神はなんといっても太陽の神様なのだから。篤史の顔にも、幼き日に見せてくれた太陽のような笑顔が戻るに決まっている。 伊勢に行くのがますます楽しみになってきたぞ。
AI運転中、流れる景色をぼんやりと見ていた井上に電話がかかってきた。だいぶ前にAI搭載車の見積もりをもらったT社のディーラーからだった。見積もりをもらったまま断りを入れるのをすっかり忘れていたことに井上は気が付いた。未連絡の詫びを入れ、金額面で折り合いが付かないことを伝えると、相手はそれほど気分を害した風ではなかった。よくあることなのだろう。井上はふと思い当たって聞いてみた。
「最近後付けのAI運転ってのがあるみたいですね。御社の売上に影響ないんですか?」
見込み客でなくなったせいか、セールスはくだけた感じで答えてきた。
「あれですか、まぁ別物ですからね。あれを考えているのなら止めといた方がいいですよ」
聞き捨てならぬ言葉に井上は眉をひそめる。
「何か問題でもあるんですか?」
井上の声にせっぱつまったものを感じたのか、セールスは声のトーンを落とした。
「いやちょっと良くない噂を聞いただけですから。私なら走る実験台はごめんですね」
電話が切れた後も、井上の頭にはセールスの最後の言葉がちらついていた。
翌日の昼休み、会社の食堂でスマホを操作していた井上は、セールスの言葉の意味を裏付けるようなニュースをネットで見付けた。
『後付けAI運転システムの罠!?』
井上は箸を置き、スマホを持ち直して記事に目を走らせる。
『低価格を武器に、最近にわかに注目を浴びている後付けAI運転システムだが、大きな問題と欺瞞が隠されていることが取材で判明した。』
記事の書き出しに目を奪われた井上は唐揚げのかけらを飲み込むのも忘れて読み進める。
自分の車に後付けAI運転システムを装着した記者が、膨大な情報を外部へ発信していることに気が付いた所から疑惑は始まる。T社の純正AI搭載車と比較して数百倍もの通信量だという。なぜ、膨大な通信をしているのか? 首をかしげる記者の元に、新たな情報がもたらされた。井上は無言のまま指で画面をスクロールさせた。
『この先の記事は有料です』
思わせぶりな書き出しをしやがって、井上は迷わずクリックした。カーソルがくるくるとまわり、記事が表示された。
このシステムは、まだ数の少ないメーカー製AI搭載車にかわり、各種データをT社にフィードバックしているというのだ。AI運転が今よりも進化していくためにも走行データは必要不可欠だ。しかし、実走行には危険が伴う。その穴を埋めるために、後付けAI運転がせっせと情報を送る。まるでモルモットじゃないか、記事の内容に井上は憤慨した。
さらに、データ収集の為に、わざと危険な運転を行なっているのではないかという疑惑まであると記者は指摘している。実際に記者も乗っている時に何度か危ない思いをしたそうだ。ショッキングな情報はこれだけでは終わらない。
後付けAI運転システムには、大手メーカーのβ版のチップが装着されているという噂まであるという。未完成のチップが横流しされ、後付けAIシステムに使われている、不完全を承知の上で。
記事では最後に、T社へ問い合わせをしているが、返答はノーコメント。
記事を読み終えた井上は、椅子の背もたれに体を預けた。ランチはまだ半分も食べていなかったが、一気に食欲がなくなっていた。
この記事の内容は本当だろうか?
T社が否定しないところが記事に一定の信憑性を与えてしまっているように思えて仕方がなかった。しかし、これまでの所、井上の車にさほどの異常は感じられない。唯一気になるのは、ボタンを押してからランプが緑になるのにかかる時間がまちまちだと言うことくらいだ。10秒のときもあれば5分かかるときもある。マニュアルによると、周囲の安全確認にかかる時間が状況によって異なるためとなっており、井上はなんの疑いもなくそれを信じていたのだが……。
座ったまま考え込む井上の目に、営業統括部長が食堂に入ってくるのが見えた。お偉いさんがここで昼食とは珍しいな。そういえば、若い社員と階級の垣根を越えてフレンドリーに接するというのが部長のモットーだったな。井上は先日の会議で部長が自慢げに話していたことをを思い出した。そんなことをしても若い社員を緊張させるだけで何にもならないということが、何故偉い人にはわからないのだろうと不思議で仕方がない。
案の定、食券を買う列に並ぶ社員達が、次々と部長に順番を譲っている。その光景を見ているとはて? と思った。
どこかで見た風景だな……あっ!
いつか、路地から合流する車に次々と道を譲る愛車の姿に重なった。あの時、ぼんやりと目の端に捉えていた車のエンブレムはことごとくT社のものでなかったか?
T社のβ版というのは本当かも知れない。本家に遠慮してしまう分家の気持ちには井上自身覚えがあった。
親父さんが、井上ばかりか、自店の従業員にも作業を見せなかった理由が分かった気がした。おそらく心臓部に載せられたチップにはT社の刻印が記されているのだろう。
営業統括部長はついに列の先頭に到達していた。さも当然のようにトレイを受け取り、サンプルメニューの前で悩み出している。後ろに並ぶ若い社員達のうんざりした顔を見ていると、なんだか急に全てがばからしくなった。井上はトレイを持つと、静かに食堂を後にした。
井上は仕事が終わり車に乗り込むと、自宅に電話をかけた。
「もしもし篤史か?」
「そうだけどお父さん どうしたの」
普段、自宅に電話することなどない、篤史が不審がっているのが伝わった。
「あのな、私立、転校していいぞ」
「えっ?」
「お金の心配はいらないから、好きなようにすればいい」
「本当にいいの?」
「あぁ、その代わり父さんに約束してくれ。つらくても現実と向き合ってがんばるって」
「うん」
「詳しい手続きとかは帰ってから話そう。それからゲームは卒業だな。私立はレベルが高いらしいから、勉強について行けないなんて事にならないようにな」
冗談めかして言うと、篤史は真剣な声で答えた。
「わかった。そうならないようにがんばるよ。あの…お父さん」
「なんだ?」
「ありがとう」
電話を切ってから、胸の奥がジーンと痺れた。久しぶりに息子とちゃんとした会話をした照れくささと相まって、井上は鼻をぐしゅんとすすった。
今日の昼休み、食堂を出た後すぐにショップの親父さんに電話をした。
返品したいと伝えると、親父さんは訳も聞かず、わかったとだけ言った。親父さんも記事を見たのかどうかわからなかったが、何らかの情報が入ったのだろう。理由を聞かないところが親父さんなりの謝罪だと感じた井上は、まがいものを買わされたという不満は伝えないことにした。井上が180万の返金でどうかと言うと、親父さんはしばらくしてすまんなと言った。購入金額との差額の1割、20万円は、井上が若き日に車の魅力を教えてくれた親父さんへの感謝の気持ちだった。
なんとなくではあるが、親父さんはこのまま店を閉めてしまうだろうという予感がしていた。いかにも昭和然とした古びたショップを覆う錆は、その主とともに時代に取り残されてしまった焦りの象徴であるように思えた。親父さんは錆の落とし方を間違えた。錆を隠そうとして上から妙な色を塗ってしまったんだ。俺は、その錆が好きだったんだよと親父さんに言ってやりたくなった。
井上ももう若くはない。車に給料全てを突っ込んでいたあの頃とは違う。家のローンや教育費で一番金が掛かる世代だ。自分の子供がピンチの時に新しいおもちゃを買って喜んでいた自分が情けなかった。現実に向き合っていないのは篤史ではなく、俺のほうだった。
伊勢に行くのは電車でもいいじゃないか、家族で過ごす濃密な時間に若い頃のままの自己満足を持ち込もうとしていた自分を恥じた。
運転席で気持ちを落ち着かせると、AI運転のスイッチを押す。
さあて、AI運転での最後のドライブだ。
少し迷ってから、井上は最も高価なエクストラモードを選択した。1時間5000円。せめて最後にこれぐらいの贅沢はいいだろう。まだ自分にも少しだけ青春が残っていたのかな、井上は少し笑った。
インパネのランプが緑に変わった。
父親からの電話を切った篤史は興奮を抑えきれない。本当に転校できる!?
奇跡が起こったのではないかと頬をつねったりしてみた。
そうだ、お父さんが帰ってきた時にゲームしている姿は見せたくない、篤史はゲームの電源を切ろうとテレビの前に座った。
「おっと」
ゲーム画面に現れた新しいメッセージ見て、篤史は驚いた。初めて見る最上級ランクのクエストだ。篤史は反射的にクエスト受注ボタンを押していた。
さすがは最上級クエストだ。敵キャラクターの動きが段違いに速い。篤史は夢中になってコントローラーを操作する。周囲に注意し、枠から外れないように卵を運ぶ。慎重に……、かつ正確に……。実践モードでは一度の失敗でアウトとなってしまう。篤史もトレーニングモードで必死に実績を作ってようやく先週、実践モードへの参加権が与えたばかりにすぎない。最上級ランクは成功すれば2000円相当のポイントがゲットできる。ゲームに意識を集中させていた篤史はふいに先ほど父親に言われた言葉を思い出した。
「せっかくお父さんが認めてくれたのに、僕は何をしているんだ」
途端に我に返った。こんなことをしている場合ではない、勉強をしないと。今後ゲームを辞めるのなら、最上級クエストとてクリアする意味があるとは思えなくなった。むしろ、失敗すれば、自動的に今後の参加権はなくなってしまうから、失敗した方がいいのではないか。
篤史はキャラクターを指定ルート外へと移動させ、歩行速度を最大に上げた。雑魚キャラをかわしながら全速力で走る。めまぐるしく移り変わるゲーム画面に、大きな怪獣が現れた、まるでダンプカーのようだ。
「よし」
篤史は心を決めた。コントローラーを持つ手に力を込めると、篤史の分身は卵を抱えたまま真っ正面から怪獣にぶつかっていった。
お父さんの声が聞こえた気がした。
もう帰ってきたのかな?
玄関に耳をすませてたが何も聞こえない、勘違いだったのかな? 篤史はゲーム画面に目を戻した。ぶつかった勢いで放り出した卵が怪獣に当たって砕ける瞬間だった。形を失った卵からは、どろりとした液体がしたたり落ちている。
まるで現実みたいだ。
車酔いした時みたいに気分が悪くなった篤史は、まん丸に目を開き、吐き気をこらえながらトイレに駆け込んだ。
A.Iによる自動運転


