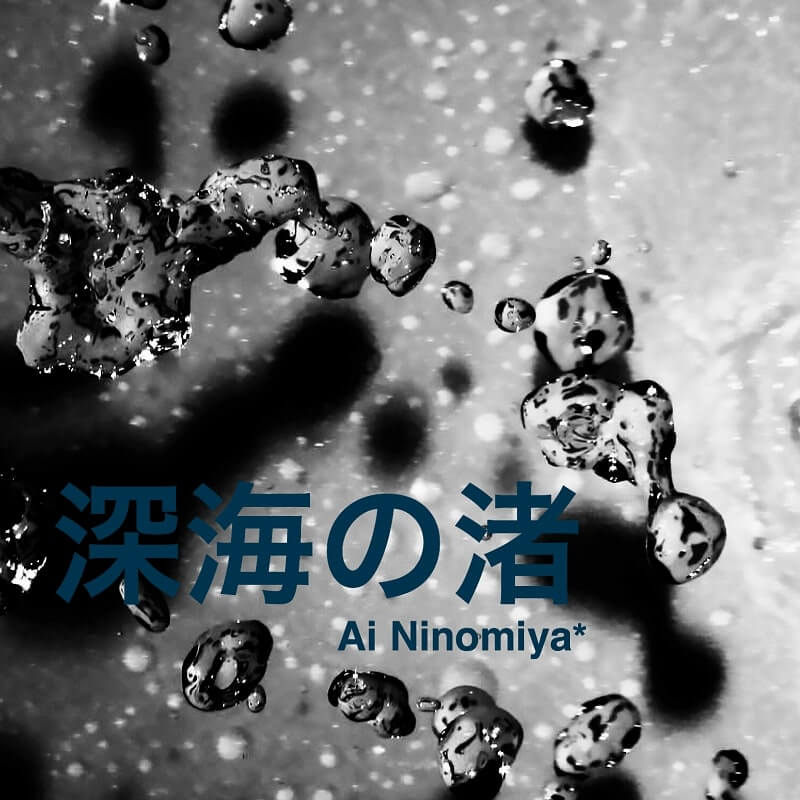
深海の渚
『深海の渚』
「人って空を目指すよね」
李芙が急にそんなことを言った。
「は?」
「空を飛びたいとか。ほら、飛行機発明して、それからロケットもできて。宇宙に飛び立って。どんどん空を目指すよね」
「何言ってんの?急に」
私がクスッと笑うと、李芙もクスッと笑った。手を繋いで歩いて、遊歩道の途中で。平穏な日々っていうのは突然何かのせいで終わってしまうかも知れない。だから私は毎日を大切に生きるんだ。あなたの手の温かさがそんな事を感じさせてくれる。海はキラキラ光っていて、夏の終わりを感じる風が波を作っていた。
「俺も空を目指したかったんだけどなあ」
「パイロットとか、そういうの?」
「いいね、パイロット」
「でも全然だめじゃない、高いところ」
「そうなんだけどね」
照れくさそうに笑って、空を見上げた李芙の横顔はきれいだった。
李芙との出逢いは大学院の研究室でだった。私がアクアリウム技術者の資格を取ったばかりの頃で、水の中に住む生き物たちの環境を勉強したいとやってきた大学に彼はいた。半年前のことになる。
「胡李芙です、はじめまして」
丁寧にお辞儀をした、白衣を着た人。この大学での水質調査やバイオ技術の第一人者だと聞いて逢いに来た。もっとおじいちゃんみたいな人が出てくるのかと思ったら、自分と変わらない歳の人でびっくりした。
「則本夏那子といいます。宜しくお願いします」
「宜しくお願いします」
研究室で、学会に発表した研究内容の話を聞いて、それから大学内にある大きな水槽を案内してくれた。
「とても暗いんですね」
それは深い蒼色をしていた。光は極力少なく小さく優しく、届くか届かないかのような蒼い水槽。
「深海にできるだけ近くしてあります。本来はもっと真っ暗なんですけどね」
「深海?珍しいですね」
「そうですかね?水族館に深い海の水槽が少ないだけです」
「確かにそうですけど」
「あなたは?どんな水槽をこれから作っていく予定なんですか?」
「できるだけ本来の海に近いものを」
「というと?」
「決まっていません」
「決まってない?」
「はい、そうやって夢は描いているものの、世界にはいろんな水槽があります。それを超えようとか今までになかったものを作ろうと思っても、なかなかどれがそれに当たるのか、わかりません」
「なるほど」
「でも、これは好きです。深海の水槽」
水槽の硝子にそっと手を添えてみる。近づいてゆっくり目をこらさないとわからないくらいに暗い水槽。時折キラリと光るのは何か生き物が動いてるからだろう。
「生き物があまり見えないのに惹かれるのはどうしてでしょうか」
「それはきっと、生命の原点がここにあるからではないですかね?」
「原点?」
「生命として地球に存在し始めたその時から、姿かたちを変えていないものも多い。この水槽にも何種類か、そんな種の生き物がいます」
「そうなんですか?」
「いますよ」
私を見てにっこり笑った。優しいけれど、意味深な笑みだった。
「カフェにでも行きますか。ここの深海を見た後はやっぱり光の入るカフェのテラスが1番いい」
「またこの水槽、見に来てもいいですか?」
「どうぞ、いつでも」
その後、大学内にあるカフェに移動した。水槽のある施設には人があまりいなかったのに、こちらは賑わっていた。普通の大学って感じだ。そう、普通じゃなかったんだ、深海の水槽のある施設の雰囲気は。建物も古い。敷地内に新しく建てられた校舎に比べると、もう使われなくなった建物を明け渡されたみたいな場所だった。
「胡先生、先生の研究されてる施設は人が少なかったですね、やっぱり難しいんですかね、こういう研究するっていうのは」
「そうですね、あまり好む人はいませんね。みんなやっぱり明るい場所のほうが好きなんでしょう。自分たちの未来を考えると、ここのほうがいい。こうやって空の見えるような」
話しながら視線を向けたのは、カフェの天井から床までの一面に大きく張られた硝子の向こうに広がる大学の中庭と、きれいな青空。この日はとてもよく晴れた日だった。
「あ、先生ってのはやめてくださいよ。たぶん、同い年です、則本さんと俺とは」
「そうなんですか?」
「はい、先ほど履歴書見させていただきました」
「あ、そうですか」
「半年間のこちらでの研究には協力させていただきます」
「本当ですか?ありがとうございます」
「いえ。それにしてもそろそろやめませんか?」
「なにをですか?」
「敬語で話すの」
「あぁ・・・」
お互い小さく笑って。温かい陽の入るカフェでコーヒーを飲んだ。
「リフ、でいいよ」
「名前で?」
「だって、名字だとコだけになっちゃうから」
「あぁ、確かにそうだけど。あの、失礼ですけど、中国のかたですか?」
「いや、国籍はアメリカになる」
「アメリカ?」
「祖父の代から完全に国籍はアメリカ。とはいっても、俺の場合は日本語しか話せないし。日本の暮らししか知らないんだけどね。親は英語話すけど」
「そうなんですか?」
「でもたぶん、祖先はアジアのどこかの国で間違いないと思う、調べたことはないけど」
「ごめんなさい、いきなり失礼なこと。きれいな名前だなと思って」
「きれい?」
「なんか、きれいです」
「名前を褒められたのは初めてだな」
小さく照れくさそうに、クスクスと笑っていた。これが、初めて李芙と逢った日のこと。
研究室には毎日足を運んだ。だけど、李芙がいるのは珍しいことだ。ほとんど研究室にはいない。
「今日も李芙はどこかへ?」
「今日は千葉の漁港に行ってますね」
「そうですか」
研究員は数名いて、みんな物静かで、どこか話し方が李芙に似ている。だからかな、ここにいるととても落ち着く。そしてあの深海の水槽も毎日覗きに行った。水槽にそっと手を当てて、暗いその中に目をこらす。そしたら声をかけてきた人がいた。李芙の仕事を1番メインで手伝っている大学院生の子だった。
「則本さん」
「はい?」
「あの、お願いがあるんですけど」
「なんでしょうか?」
「これからも毎日来られます?」
「あ・・・迷惑でした?」
「いえ、違います。もし毎日来られるんだったら、この水槽の餌やりをお願いできないかなと思いまして」
「餌やリ?」
「Prof.李芙に頼まれているんですが、やることが多すぎてつい忘れそうになるんです。時間が決まっていて」
「そういうことだったらお手伝いしますよ?」
「本当ですか?助かります」
「培養の方法と決まった時間が指示されてるので覚えてもらってもいいですか?」
「もちろんです」
深海の水槽にはたくさんの生き物がいる。一見何もいないように見える水槽だけど、餌をやるとよくわかった。蒼いだけのように見える水がゆっくりと水槽の中で動く。時折小さな泡が揺らめく。敷き詰められた砂が小さく動いたり、黒い影がすぅーっと通り過ぎることもある。
「何がいるんだろう、この中には」
水槽の中にいる生き物たちの説明はどこにも無い。何種類生息しているのかもわからない。ただ、そこに命はたくさん存在した。
「生命の原点がここにある・・・」
李芙の言葉を思っていた。不思議だけれど惹かれるこの水槽を見ていると、自分がいつか作ろうとしている何かが思い描かれる気がしてならなかった。
次の日研究所に行くと李芙がいた。数日ぶりに見た気がする。
「Prof.李芙、おはようございます」
「おは・・・よ。何それ?」
「え?」
「リフでいいって言ったのに」
「あぁ、研究所のみんながそう呼んでるから、つい」
「あの呼び方もあまり好きじゃないんだ。俺はそんなに偉くもない。みんなは学生だから仕方ないかなと思うけど、則本さんは普通に呼んでよ」
「はぁ・・・」
「昨日ね、珍しい深海魚が漁港にあがったんだ」
「そうなんですか?」
「あんな海面に近い場所を泳いでいるなんておかしいぐらい深いところにいるやつなんだ」
そう言って李芙はため息をついた。
「あ、深海っていうとあの、水槽の餌やりを私が担当することになって」
「深海の?」
「ちゃんと培養の方法も決まった時間も、古瀬くんから聞いてちゃんとやってるので。良かった・・・でしょうか?私がやって」
「大歓迎です」
「よかった。餌をやると、水槽の様子がなんとなくわかる気がしてとても落ち着くんで、このまま続けさせてもらってもいいですか?」
「いいよ、お願いします」
「ありがとうございます」
李芙は私から視線を逸らすと、大きなバッグから書類を取り出してはデスクに広げる。また何か資料を作っていたんだ。とてもたくさんの量だ。
「喜ぶと、思う」
「え?」
「こっちの話です」
李芙はこちらを向くことなく、小さく微笑むと、書類をまとめて隣の部屋に移動していった。私は私で、李芙のまとめたレポートや数冊発売されている書籍に目を通していた。勉強になることは山のようにある。だけどイマイチ集中力が続かない。隣の部屋のドアに目をやるけれど、李芙が出てくる様子はなく、また本に視線を戻す。李芙が書籍に使っている言葉は優しい。難しい言葉は使わない。子供にもわかりやすいものだ。地球上の水質について。水と生きることとの関わりについて。メインはそこだけど、どれも他人事ではない文章で綴られている。まるで、水そのものが李芙自身かのように感じるんだ。李芙の書いたものに触れれば触れるほど、ペットボトルの水でさえ、愛おしく思えるようになった。
「則本さん」
呼ばれて顔を上げると、隣りの部屋からいつの間に出てきたのか李芙が立っていた。
「飯、行かない?もう昼だよ」
「あ、うん、はい」
大学内になる展望レストランに移動した。カフェとはまた違った雰囲気でここも好き。研究室では海の中にいるような感覚になるけれど、ここやカフェに来ると、この大学が山に近い緑に囲まれた立地にあるんだったってことを思い出させる。ただ、このレストランからの視界には遠く海が見える。
「李芙は、海が好きなの?」
「海?あぁ、好きだね」
「マリンスポーツとか、そういうのは?」
「そっちは全然。運動はしないなぁ」
日替わりのランチを手に、窓際の席に向かい合わせに座った。
「李芙の書いたものを読んでいると、自分が今海の中にいるみたいな感覚になるんだよね」
「それは面白いね」
「面白いって、書いたのは李芙だよ?」
「そうだけど」
「だからてっきり、海にはよく行くのかと思って」
「海には行くよ。昨日みたいに深海魚があがったって聞いたらすぐ飛んでいくし、水質調査もしょっちゅうだ。ただ船は苦手で、酔うんだよね」
「そうなの?」
「だから陸地専門。川とかいろいろ水辺には行くけど、入りはしない。泳ぎにも行ったことないかな」
「泳ぎに行ったことないの?子供の頃とか」
「行かなかったね、親がどちらも海が嫌いで」
「そうなんだ?でも、どうして今の研究を始めたの?」
「水族館、かなあ」
「水族館?」
「両親ともに海が嫌いなくせに、水族館にはよく連れてってくれたんだ」
「へえ」
「だけどここは疑似の海だ、って。母さんが・・・」
「疑似」
「まぁ、どうでもいいよ、そんな話」
「深海の水槽、あれは?あれもやっぱり疑似のひとつなの?」
「あれは・・・俺の1番大切な場所かな」
どうしてだか、その言葉を聞いたあと、私は何も彼に言葉を返せなかった。会話をすることなく食事をして、また研究室に戻った。静かな研究室だけど、研究のために置かれたいくつもの小さな水槽に設置されたポンプの音が心地いい。電話なんかも鳴ることはない。水の中に溢れる泡の音に気を取られていた。ぼーっとしていた。その時、急に李芙が立ち上がった。引いた椅子が後ろの棚に当たった衝撃でいくつかの資料が床に散らばった。
「あ、悪い」
慌てて李芙はしゃがんで書類を集めた。近くにいた子もそれを手伝いに近寄った。もちろん、私も。李芙が見ていたのはインターネットの何かの記事だ。何かはわからなかった、文章が全て英語だった。日本語しか話せないって言ってたのに、読めるんだ?そう思いながら拾っていた書類の中に1枚の写真を見つけた。李芙だ。中央に少し若い頃の李芙がいた。左右にいるのは、お父さんとお母さんかな。じっと写真を見ていると、李芙がその写真をすっと私の手から抜き取った。
「ありがとう、大丈夫だから」
書類をまた棚に戻すと、椅子に座りなおしてまたパソコンに視線を向けた。右手で口元を覆うようにして。それはきっと李芙にとって何か大事な内容だったんだろう。それ以上何も手を貸せなくて、私はまた自分のいた場所に戻った。
「明日は事務所に顔を出さないといけないので、深海の水槽、餌をやることができないんだけど」
「いいよ、明日は俺がやるから、ありがとう」
「それじゃ、お先に。お疲れさまでした」
「お疲れさま」
今日、あの後、李芙と話したのはこれだけだった。
研究室に通うようになって2週間が過ぎた。その日は、敷地の1番奥にある研究室に向かうまでに何度も耳にした。大学生たちがその話題で賑わっていた。
「古瀬くんも、春節祭の花火大会行くの?」
研究室で1番話すようになったのは、深海の水槽の餌やりを私に頼んだ古瀬くんだ。
「え?ぼくは・・・行かないです」
「どうして?彼女とか誘っていかないの?」
「彼女も、いないんで」
「あ、ごめん」
「いえ、地味なもんで。女性も苦手だし」
「あ、私も一応女なんだけど?」
「あー、則本さんは話しやすくて好きですよ」
「いいよ、なんか言わせたみたいじゃない、私が」
そんなやりとりを聞いていたのか、李芙がクスクスと笑った。
「まるで古瀬が脅されてるみたいじゃん」
「違うよー、ちょっと聞いてみただけで。ここ来るまでに花火大会の話題耳にしたから、みんなどうなのかなと思って」
「そういう則本さんは?行くの?誰かと」
「いや、私も、おひとりさまなんで・・・」
李芙に聞かれてそう答えると、古瀬くんが泣き真似をしながら言った。
「なんだぁ!ぼくと一緒じゃないですか、則本さんひどいっすよー」
「ごめん古瀬くん、そういうつもりじゃ」
またクスクスと笑い声が聞こえてくる。だけどこっちまでつられる、そんな優しい笑いかただった。
「ほんとごめん。古瀬くん、仕事しよ」
「はい」
みんなそれぞれ、持ち場に移動する。朝のはじまり。1日のはじまり。そしたら李芙がそっと後ろから私の肩をたたいた。振り向くとすぐ近くに李芙の顔があって思わず固まってしまった。
「一緒に行く?花火大会」
「え?」
耳元で小さい声で囁くから、小さな声で聞き返した。
「一緒に?」
「一緒に」
「いいの?」
「1番行きたかったのは則本さんでしょ?」
そしてまたクスクスと笑う。
「そういうわけじゃないけど、でも花火は見たい・・・かな」
「じゃあ行こうよ」
「うん・・・」
私の肩をトントンと叩くと、彼は自分のデスクに戻って行った。息が止まるかと思った。その日は早く終われるように、自身のレポートを一気にまとめた。花火、行きたいんだ。李芙と、ふたりで。李芙も早くに仕事が終われるように調整してくれていた。大学の展望レストランから見える海。そこからでも花火は見れるけど、できれば海の近くで見たい。そう言うと、いいよって李芙は答えてくれた。
仕事が終わると、大学から海までの距離を並んで歩いた。大学外の場所をふたりで歩いたのは初めてだ。白衣を着ていない李芙も不思議な感じだ。この人は一々この世界のものを感じながら生きている。ふたり並んで歩いている時にそう思った。風が吹くとなびく髪と共に風を感じて、舞い散る桜の花びらを目で追ってみたり。走り去る子供の声がすると視線を移して声に耳を澄ませ、自転車のチェーンの音がした方に目をやるとそっと微笑む。
「則本さんはさ、好きな音ってある?」
「好きな音?音楽とか?」
「いや、音」
「音・・・なんだろう」
「俺はね、泡の音が好きなんだ」
「ビールとか炭酸とかそういうの?」
「違うよ、則本さんは酒好きなんだ?」
「違うけど、いや、飲みはするけど」
李芙はクスクス笑う。今日はこれを何度聴いただろう。
「水の中の泡の音」
「あ、水槽とか?」
「そう。目で見るのも好き」
「泡を、見るの?」
「ほら、ダイバーとかがさ、海に潜ってる映像とか見てると酸素ボンベから大きな泡が出るだろ?」
「あぁ、あれね」
「あれを見てるのも、その音を聞いてるのも好き」
「李芙って変わってるよね」
「なんで?」
「だって、海に入ったことないのに」
「確かにね」
「でも、嫌いじゃないかな、泡の音」
「則本さんはビールのほうでしょ?」
「違うってば」
手を挙げて叩こうとしたら、李芙がそっと身をかわして、そのまま海の方に向かって走った。追いかけようとするけど、運動はしないと言っていたわりには李芙は足が速くて、追いつけなくて。私がパンプスを履いていたからっていうのもあるんだけど、必死で追いかけて走って。そしたら泣きそうになってきた。
「待って!李芙!」
踏切の手前まで走っていた李芙は、ゆっくりと走るのをやめると振り向いた。私は、その李芙に向かって必死で走った。そしたら李芙の方から走って戻って来た。
「ごめん」
手を差し出される。掴まるようにして立ち止まって大きく息をする私の背中に手をそっと当てると、李芙は私の顔を覗き込んだ。
「ごめん、ふざけすぎた」
「いい、けど・・・。足速い・・・から、李芙」
「ごめん」
李芙はそっと私の頭を撫でると、微笑んだ。
「ゆっくり歩こう」
私の右手をそっと握ると、手を繋いでそのまま歩き出す。呼吸は落ち着いてきたけど、心臓は落ち着く暇がなかった。繋いだ李芙の手の温かさが優しくて。それからずっと手を繋いでいた。空がだんだんオレンジから深い蒼に変わっていって。
「深海の水槽みたいだね」
私が言うと、李芙は笑った。
「花火はさすがに上がらないけどね」
空には大きな花火がいくつも舞い上がった。
「きれーい」
見上げる私の隣で、李芙も「そうだね」と言った。繋いでいた手がふいに解かれて、花火の上がる空から視線を外すと、李芙は急に後ろから私を抱きしめた。
「寒いから。このほうが暖かい」
「え?」
思わず周囲を見回したけど、みんな空を見上げていて私たちのことなんか見ている人はいない。
「きれいだねぇ、花火」
「う・・・うん」
花火に気を戻そうと思うんだけど、後ろから回された李芙の手が私の手を掴んでいることのほうが気になって、今思えば花火がどんなだったかなんて、あまり覚えていない。その後1時間ぐらい、花火が終わるまで私たちはずっとそうしていた。花火大会の終わりを伝えるアナウンスが流れだすと、少しずつ周囲の人が動き出す。李芙は後ろから急に私の肩に自分の顎を乗せると耳元で呟いた。
「ねぇ、俺たち、付き合う?」
「え?」
振り向こうにも振り向けなくて、李芙の呼吸する動きだけが背中から伝わってくる。
「どうする?俺は、則本さんのこと好きだよ」
どう・・・しよう。すぐに返事ができなくてドキドキしてしまって。そしたら李芙はそっと手を解いた。私から離れて、隣りに立った。
「返事はいつでもいいよ」
「う・・・ん」
「俺は好きだよ」
「うん」
好きだよって言葉は耳に残る。意識していなかったわけじゃないけど、言われたら止められなくなる。好きになってしまう。それで、いいのに。どうして私は迷っているんだろう。そもそも李芙には彼女はいないんだろうか。聞いたことがない。だけど付き合う?って言われたってことは、きっといないんだよね?家に帰ってからもそんなことをずっと考えていて。湯船に漬かりながら李芙のことを思っていたらのぼせてしまった。喉が渇いて冷蔵庫を開けて、ミネラルウォーターのペットボトルを取ろうとして、すぐ隣にある缶ビールが目に入った。
「則本さんはビールのほうでしょ?」
クスクスと笑う李芙を思い出す。だめだ、やっぱり好きだ。私はミネラルウォーターではなく、缶ビールを手に取った。
「好きだよ、泡の音」
独り言のように呟いて、缶ビールを開けると、私はグッと一気にビールを飲んだ。
事務所から仕事の依頼が入った。桜はとっくに散ってしまった頃。李芙に、私も李芙と付き合いたいと返事をした後のこと。
「高知にね、新しい観光名所になるような水族館を建てる話が出ている。そこの水槽のデザイン、管理をあらゆる事務所に募集をかけているらしい。うちにもその話が来た。大きなチャンスでもある。ぜひみんなの力を貸してほしい」
デザインと管理、私にも参加するよう声がかかった。
「すごいね、新しい水族館の仕事なんて」
「でも、アイデアが全く浮かばなくて」
「まぁ、気負っちゃうよね、そういうのって」
いつもの展望レストランで、李芙が私の話を聞いてくれていた。
「1つね、やりたいものはあるんだ」
「どんなの?」
「深海の水槽」
「深海?」
「ここにある深海の水槽の、もっと大きいのを作りたい」
「あれは、難しいよ。ほとんど魚たち見えないしね、水族館には向いてないよ」
「ううん、そんなことない」
「大きなマンタとかジンベイザメとか、キレイな色の熱帯魚とか。あぁいうののほうが人気あるでしょ。イルカを真下から見れる水槽のトンネルとか」
「そうだけど、そういうのは他の人にでも作れるでしょう?」
「他の人?」
「私に作れるのは、あの深海の水槽だと思うんだ」
「そう?変わってるね、則本さんは」
「じゃあなんで、李芙はあの水槽を作ったの?」
「あれは・・・個人的な趣味だよ」
「ほら」
「なに?」
「そういう人だっているんだってば」
「あのねぇ、世の中に俺みたいなやつがどれほどいんだよ。いないよ」
「そんなことないよ。深海の魚のぬいぐるみとかグッズとか、そういうのちょっとしたブームになったじゃん」
「あんなの一時だよ、やめときな」
「なんで?李芙なら、いいね、って言ってくれると思ってた」
「いいね、って?俺が?言わないよ」
そう言うと、李芙は一気にランチを口に運んで、急いで席を立って行ってしまった。その後、研究所に戻ったけど李芙はいなかった。何処に行ったんだろうと施設内を歩いていると、李芙を見つけた。深海の水槽の前で。近づいていくと、私に気付いた李芙が私を見た。
「これ、則本さんの仕業?」
そう言って、自分の座っているベンチをトントンと叩いた。カフェの壁沿いにいくつか置いてあったベンチを1つ、学校側に頼んで移動させてもらった。李芙の問いかけに、私は大きく頷いた。
「いいね、ここにベンチ。どうして今まで置かなかったんだろう、俺」
深海の水槽の真正面に置いたベンチから、李芙は水槽を見上げるように視線を上げた。そんな李芙の表情が優しかったから、私はすぐに李芙の隣に座りに行った。
「李芙、ごめんなさい。さっきは勝手に思い込みでいろいろ話して」
「いや、俺もちょっと言い方悪かった」
「言い方?」
「深海は、地上には要らない」
「どういう意味?」
「所詮、疑似な場所だからさ」
「でも、そんなの水族館はどれもそうでしょ?動物園だって、人間が作り上げた疑似の場所だよ」
「そうだよね」
李芙はそう言ってから目を閉じると、小さな声で言った。
「今から話す話、信じてくれなくてもいいから」
「うん・・・なに?」
「この世に人間って、2種類いる」
「2種類?人種的な?」
「違うよ、それならもっとたくさんあるでしょ」
「そっか」
「1つは、則本さん」
「私?」
「1つは、俺」
「どういう意味?」
「則本さんは、1番最初に人間としてこの地球上で進化した人種」
「うん、それで?」
「俺は、それから何百年もあとに、同じように人間という種類に憧れて進化した人種」
「それは、なに?」
「則本さんはもう、人間なんだよね」
「なんだか、意味わかんないんだけど」
私はいつもの李芙みたいにクスクスって笑った。李芙も同じように笑ったけど、その後少し、表情が硬くなった。
「俺はまだ進化の途中」
「途中?」
李芙は、私の手を取って、李芙の左耳のすぐ後ろのところに触れるように持って行った。
「触ってみて」
「え?」
「何かあるでしょう?」
「何かって?」
「耳の後ろ、ちゃんと触ってみて?」
そこには硬い、もうひとつ耳のようなものがある。
「右側にもあるよ」
私の方を向いて、そう言いながら李芙は優しく笑った。私は恐る恐る、李芙のもう片方の耳の後ろにも手をやった。普段は髪に隠れて全くわからない場所。そっと片方の髪をかき上げて私はそれを見ようとした。李芙は逃げもしないで、大人しく子犬のように小さく視線を落としてじっとしていた。それは、とてもきれいな透明のプレートのような丸い形のものだった。
「ここでもね、呼吸ができるの」
「呼吸?」
「これが完全に消えてなくなるまでは、俺たちはまだ進化の途中なんだ」
「なに言ってんの?これはなに?」
「もともとこれはもっと大きくて、長くて、水の中のほんの微量の酸素をここから取り入れてた」
キラキラときれいなそれから私は手を離すと、少し李芙と距離を置いて座った。
「怖いよね、急にそんなこと言われても」
「李芙ってなに?」
「まだね、人間には発見されていない種類になるんだ」
「発見されてないって、なに?」
「深海に住んでる」
「なに言ってんの?」
「信じてくれなくても、いいよ。いいんだけど、則本さんには伝えておきたいなって思った」
李芙は、深海の水槽に目をやりながら、さっき私が触れたそれを隠すように髪の襟足をそっと整えた。
「人間はね、早くに進化した。地上に上がって、言葉を使い、道具を使い、文明を作った。俺たちはね、もともといた場所が深すぎて、体や感情はどんどん進化したいと願うのに、なかなかその思いには届かなかった。やっとの思いで祖先の何人かが地上にたどり着いた頃には、この地球上には見たことのない世界があった。そこに紛れ込むようにして、この体の違いを隠すようにして、今の形にまで進化した」
李芙が急に私を見たので、ドキッとした。
「俺のこと、怖い?」
「わから・・・ない」
「そっか」
そう言って大きく深呼吸する。李芙は李芙なのに、違う人みたいに見えた。
「俺は地上で生まれてるから。深海の様子も状態も知らない。俺たちが進化した種類だって話は子供の頃に聞かされたけど、それでも普通に人間だと思ってたし。ある時までは」
「ある時、って?」
「両親が人間をやめるって言いだした時」
「人間をやめる?」
「進化ってのはすごくすごーく時間がかかるのに、退化するのはあっという間なんだ」
私はその時、思い出した。写真があった。李芙が前に書類を落とした時に一緒に拾ったあれ。
「写真、あったよね?李芙と映ってた人ってご両親?」
「写真?・・・あぁ、あるよ。見せたっけ?」
「前に李芙が書類を落とした時に私が拾って」
「そうだっけ」
李芙は懐かしそうに、微笑んだ。だけど、すぅーっと涙を流した。
「この深海の水槽は、俺の故郷なんだ。だけどあくまで疑似だ。偽物だ。だから他にはいらない。ここだけでいいんだ」
涙をさっと拭って、李芙は立ち上がった。
「ごめんね、変な話をして。妄想にも程があるよね。今日はもう帰るよ、古瀬に伝えといてくれる?」
歩きながら白衣を脱ぐと、李芙はそのまま廊下を歩いて行った。
深海って何?李芙の故郷って何?家に帰ってからずっと、インターネットで深海魚ばっかり検索していた。あのきれいに光っていた丸いプレートみたいなものは何?本来はもっと大きくて、長くて、酸素を取り入れられるっていうあれ。どれだけ調べても、そんな種類の深海魚なんていない。嘘なんだよ。李芙の妄想なんだよ。だけど、触れたあの首筋の感触と、李芙の言葉が蘇る。
「人間には発見されていない種類になるんだ」
テーブルに広げたままの資料が目に入って自分の現実にも引き戻される。
「そうだ、水族館の構想もまだ立てられてない」
パソコンに映し出された深海魚の写真たちが目に入る。深海の水槽、どうしよう。李芙はあんなに嫌がっているのに、作りたいと思うのはどうしてだろう。
「偽物・・・か」
私が目指している仕事ってのは一体何なんだろう。疑似の世界を作るだけの仕事なんだろうか。アクアリウム技術者の資格って持っていて一体何の役に立つんだろう。偽物を作る仕事。所詮本物には勝てない仕事。自分自身も何が何だかわからなくなってきた。だけど途轍もなく逢いたいんだ、李芙に。
次の日研究室に行くと、李芙はまたいなかった。
「今日も海行きましたけど?」
古瀬くんは試験管をゆらゆらと振りながら答えた。何か調合を頼まれたらしい。資料をデスクにたくさん広げて、こちらを見る気配もなく資料と資料を行ったり来たり睨みつけるみたいにしていた。
「何処の海か知らない?」
「知らないですけど、海の中を見たいって言ってましたね」
「海の、中?」
入った事ないのに?海の中に?泳いだこともないのに?なんで?嫌な予感がしたんだ。李芙は何をしようとしてるんだろうって、不安になったんだ。急いで私は携帯を手に取った。李芙に電話をかけた。ずっと呼び出し音ばかりだった。ずっと、ずっと、呼びだしているけれど出る気配はない。だけど留守電にもならない。私は携帯を耳に当てたまま研究室を走り出た。呼び出し音を聞きながら。
「もしもし?」
「李芙?」
「どしたの?」
「何処にいるの?海って何処の?」
「なんで?」
「なんで?じゃないよ。逢いたいの」
「嬉しいね、俺も逢いたい」
「何処にいるの?教えて?今から行くから」
大学の構内を走りながら、私は李芙の居場所を聞き出した。
「待って、何もしないでそこに居て?私がつくまで」
「どうして?」
「一緒に、確認したいから」
「なにを?」
「海の中」
李芙がいると言った場所は、前に花火を見に行った海岸の傍だった。ヨットハーバーが近くにあって、だけど平日だからこのあたりに人はあまりいない。トラックはたくさん行き来していた。こんな場所からマリンタワーを見たのは初めてだ。李芙は埠頭の先のほうに立っていた。風が強くて、キラキラ光ってる。李芙の首筋のあれ。
「李芙!」
声をかけると、振り返った。李芙は笑顔だった。走り寄ると私は李芙に抱きついた。
「どしたの?則本さん」
「逢いたいって言ったでしょ?」
「言ってたね。俺もね、逢いたかった」
「何してるの?こんなところで」
「則本さんも言ってたじゃない?海の中を確認するんだ」
「何をするつもり?」
「ちゃんと来るまで待ってたから、今度は則本さんが、ここで待っててくれる?」
「だから、何をするの?」
「海に入るよ」
普通にそう言うけれど、海に入る格好もしていない。李芙はいたって普通の服装で。救命具とかそういうのもない。それよりまだ海に入る季節でもない。この場所は海水浴場でもなければ、海に人が入るような場所でもないんだ。
「どうする気?」
「ここで、待っててね」
李芙は、優しく笑った。嫌なんだ、そうやって微笑まれると、怖くなるから嫌なんだ。李芙はゆっくりと歩いて、李芙の腕を掴んだ私の手を払いのけて、そのまま埠頭の先まで走って海に飛び込んだ。
「李芙!!!」
なんで?どうして?どうしよう。大きく波が揺れている。海はとても暗くて何も見えない。曇り空の今日は特に視界なんてあるもんじゃない。何度も李芙の名前を呼ぶけれど、李芙の姿はない。誰かを呼びに行こうか。時間だけが経つのが怖い。どうしよう。どうしよう。どうしよう。
「あぁ!!!!」
大きく叫びながら李芙が海面に顔を出した。そして大きく咳き込んだ。とても苦しそうに咳き込みながらまた水の中に潜ろうとする。
「李芙!やめて!もう」
私の声なんて届いていないんだろう。李芙が沈んでいった場所に残る大きな泡だけが李芙の場所を意味している。
「嫌だよ、李芙!」
大きかった泡はどんどん消えて、大きかった波は小さく揺れる程度に変わっていく。
「李芙?李芙?」
上から見下ろしていたって、海面は何もなかったように静かになっていって。私は止まらない涙と声にならない声で李芙の名前を叫んだ。嫌だ。嫌だよ。どうしていなくなるの?どうして?泡が消えちゃったよ。そこに李芙はいるのに。なんで?何も考えられなくなって、私もそのまま海に飛び込んだ。ドンって大きな音がした。それから静かに聞こえてくる。泡の音。李芙が好きだって言ってた海の中の泡の音。目を開いたって何も見えなくて、必死でもがくように手を動かした。だんだんと息が苦しくなって怖くなってくる。
「リ・・・フ・・・」
海の中で声に出そうとしたって泡が音を立てるだけで、どんどん息が苦しくなる。恐怖に震えてきた。そんな体を、誰かがぎゅっと抱きしめた。とても力強かった。何も見えないけれど、キラキラ光る何かが視界に入って、そしたら唇が何かで塞がれた。李芙だ、って思った。私を抱きしめる感触でわかる。そして段々と呼吸が落ち着いてくる。ゆっくりと目を開けると、暗い海の中でもはっきりとわかった。李芙が私にキスをしていた。びっくりして体を離すと、唇が離れてまた呼吸が苦しくなる。李芙は、私を力いっぱい抱き寄せて、またキスをした。息が・・・呼吸ができる。李芙の唇から届く。さっきまでの怖い気持ちがふっと消えて、安心に変わっていく。抱きしめてくれる李芙に私も抱きしめ返した。唇から届く酸素は、私を一定の呼吸に落ち着かせた。そのまま海面まで泳ぐと、ふたりで水の上に顔を出した。
「何やってんだよ!」
いきなり李芙はそう叫んだ。
「だって・・・李芙が見えなくなったから」
「だからってなんでおまえまで飛び込むんだよ」
「だって・・・」
「だってじゃないよ!」
海から上がって、濡れたままの衣類でいるわけにもいかず。近くにあったヨットハーバーの事務所に声をかけた。
「すみません、ふたりではしゃいでたら海に落ちてしまって・・・」
李芙はそんな風に話して、建物の中に入れてもらった。涙が止まらない私に、事務所の人は「怖かったんだねぇ、海に落ちて」といろいろしてくれた。李芙は、男がしっかりしないとダメじゃないかと怒られていた。いい歳をして・・・と。確かにそうだ。子供みたいにふたりで海に飛び込んだ。
やっと気持ちが落ち着いて、寄り添ってくれる李芙に安心して。事務所の人が出してくれたホットコーヒーを飲んだ。
「ごめんね」
李芙は小さな声で謝った。私は首を横に振った。
「何かわかった?海の中」
「うん、わかった」
「そっか」
「うん。俺はまだ、人間に、なれてないみたい」
「え?」
「まだ、これは呼吸ができるらしい」
そう言って自分の首筋にそっと手を持っていった。海の中で、キラキラ光ってた。そして私は、それに助けられた。それがなんだか、悲しかった。
それからゆっくりそこで時間をつぶして、事務所の人が乾燥機にかけてくれた衣類を受け取って、着替えた。海に飛び込むときに私が置いて行ったバッグだけが無事で、あとは全部水浸し。
「俺の携帯、ダメんなった」
李芙は電源の付かない携帯を見せて笑った。
ふたりで研究所に戻った時には夕方になっていた。
「お帰りなさい。則本さんまでいなくなっちゃうから手が足りなくて。言われてた培養できましたよ、Prof.李芙」
古瀬くんは一日中デスクにいたようで、食べたコンビニおにぎりのゴミや失敗してやり直した試験管等が散乱していた。
「この培養何に使うんですか?」
古瀬くんがそう言った途端、李芙は何かを思い出したように走りだした。
「え?李芙?どうしたの?」
その後を追いかけると、李芙は深海の水槽の前で立ち止まった。硝子に手を当てて、大きく叩く。
「父さん?母さん?」
「李芙?どしたの?」
「父さん?どこ?」
水槽を叩くのをやめると、李芙は水槽の裏手に回って階段を急いで登った。水槽の上部に登れるスペースがあって、そこから水槽の中を見下ろした。私もその後をついて水槽の上のスペースに行った。
「母さん?」
李芙はそう言ったかと思うと、次の瞬間、水槽の中に落ちるように入って行った。
「え?李芙!?」
暗い深海の水槽に大きく波が起きて、ベンチの置いてある廊下側に水が溢れ出る。さっき乾いたばかりの衣類をまとった李芙が水の中でふわっと立っているように見えた。髪がゆらゆらと水の中で揺れる。あまりよく見えなくて、私は階段を急いで降りた。ベンチのある廊下のほうに移動すると、水槽の正面から、中にいる李芙がよく見える。ゆっくりと李芙は、その水槽に敷き詰められた砂の上に座りこんだ。そっと砂の上をなぞるようにして、何かを探していた。そしたらキラッと光るものが見えた。色のほとんどない。
「魚?」
ヒレと、長く揺らめく触手のようなものが見える。そしたら水の中で李芙は笑った。というか、驚いた。彼はそこが地上であるかのように、呼吸をしていた。あの光るプレートを使って。そんな李芙と目が合うと、李芙は笑った。ゆっくりと立ち上がって水面に顔を出すと私に声をかけた。
「さっき古瀬ができたって言ってた培養、持ってきてもらえる?」
「培養?」
「早く!」
「わかった」
研究室に戻って古瀬くんから培養を受け取ると、また水槽に戻った。李芙は水槽から出て、上のスペースに座っていた。
「貸して、それ」
頷いて培養を渡すと、それをゆっくりと水の中に注いでいく。
「よかった、生きてた」
水槽の中で時折キラキラ光る。
「この水槽はね、人間をやめて深海魚に戻った父と母のために作ったんだ」
「お父さんとお母さん?」
「あれ、あの大きな透明なのが父さん。で、こっちの少しグレーがかった透明のやつが母さん」
丁寧にそれぞれを指さしながら優しく笑う。
「人間をやめたって、こういうこと?」
「ふたり揃って海に戻るって言って。俺が止めるのも聞かないで海に戻って行った。だけどその後すぐに漁港に引き上げられたんだ。人間でいる時間が長すぎて、深くまでなかなか辿りつけなかったんだ。それを俺が引き取った。まだ人間が見つけていない種類だから。大騒ぎになる前に何処かに移動させなきゃって。研究するからと言って譲りうけて、すぐに水槽を作った」
「お父さんと、お母さん?あの写真の?」
「そう、あの写真の」
「李芙も、海に戻るとこうなるの?」
「どうだろうね」
「だって、お父さんとお母さんは・・・」
「則本さんは、信じてくれるんだね。俺の話」
水槽のポンプの音を聞きながら、上のスペースにふたりしゃがみこんで向かい合っていた。
「信じないわけにいかないよ」
「そう?」
「ごめん・・・なさい」
「ん?」
「今日、私が餌をやらなかったから、だよね。こうやって李芙が焦ってたのって」
李芙は、小さく笑った。
「元はと言えば、俺が海に入りたいって思ってしまったからだ」
李芙は水槽の中に視線をやると、愛おしそうに見ていた。前髪から雫がゆっくりと李芙の鼻をつたった。私はそれをそっと手で拭った。李芙が私を見たので、私もじっと李芙の顔を見た。
「李芙は、人間をやめないで?」
「それはどうかな・・・」
「やめないでよ」
私は李芙にそっとキスをした。
「父さんと母さんが見てるよ」
そう言われて私は李芙を抱きしめた。
「いいの、見ていてほしいの」
「そう?」
「うん」
「俺たちはね、感情があるんだ」
「感情?」
「魚には珍しいでしょ。ていうか、人間以外の生き物では珍しいよね」
「そう・・・だね」
「感情を持っているから、思っちゃったんだよね」
「何を?」
「違う姿に進化してみたいって」
「李芙も、そう思うの?」
「俺は、わかんないな。生まれた時からこの姿だから」
「お父さんとお母さんは?」
「生まれた時は進化の途中で。人間からしたら、気味の悪い生態だっただろうね」
「そんな・・・」
「そういうもんだよ。見たことのないものを見るって」
抱きしめたままの私の体を李芙はぎゅっと抱きしめて、それからそっと離れた。
「また濡れちゃったね」
「ほんとだね」
その日は李芙の家で一緒に過ごした。1つのベッドで寄り添って眠ろうとしていた。何もかもが、李芙は普通の人間なのに、時々、李芙の首筋に触れると何かを感じる。だけどそれが愛おしい。
「ねぇ、李芙は、名前なんていうの?」
「名前?」
「えっとね、李芙たちの深海魚の時の名前」
「あぁ、無いよ」
「無い?」
「だってまだ人間が見つけてないんだ。誰も名前なんて付けてくれてないよ」
「そっか。そうだ、誰かが見つけて初めて、名前が付くんだもんね」
「そうだよ」
「あの水槽にいることは誰も知らないの?」
「知らないだろうね、誰も見に来ないし」
「古瀬くんとかは?」
「彼もそうだけど、研究室のみんなが興味あるのは、生物の生態ではなくて水質に関してだから」
「あ、そうなんだ?」
李芙は、またクスクスと笑った。
「いろいろ、気になる?」
「気にならない、っていうと嘘になる」
「だろうね」
「聞きたいことはいっぱいある」
「そっか。よかったよ、則本さんに俺のこと話して」
「どうして?」
「信じてくれる気が最初からしてたんだ」
「そう?」
「うん。一目見て好きだって思った」
「うそ・・・?」
「ほんと。だから、俺のこと知ってくれると嬉しいなと思った」
「うん」
「俺たちはね、人間よりは進化は遅いけど、感覚だけは進化してるよ」
「感覚って?」
「わかるんだ、なんとなくいろんなことが」
「どういう?」
「だから、この人は俺のことを好きになってくれるだろうな、とか」
「うそぉ?」
「ほんと。暗い海の底で、何も見えない状況で身の回りを判断して生きてきたんだ。不安な感情も、怖いっていう感情も、取り除くためにはインスピレーションを研ぎ澄ますことはとても大事だった。水槽の中にいる父さんも母さんも、言葉は話せなくなったけど、なんとなく伝わるんだ」
「どうやって?」
「水槽の向こうとこっちにいてもね、わかるんだ。言葉みたいな何かが、届いてくるんだ」
「じゃぁ・・・」
「ん?」
「今、私が何を考えてるか、わかる?」
そう言うと、李芙は体を起こして私を見下ろした。何も着ていない李芙の上半身はとてもきれいで。白い腕がそっと伸びて私を包む。そして抱きしめると、耳元でそっと言った。
「そんなに聞きたい?」
「うん」
「俺の口から?」
「うん、聞きたい」
李芙は私の首筋を唇で伝うと、それから耳元で言った。
「夏那子のこと、愛してる」
こんなにも、李芙の姿は私と変わらないのに。李芙は言う。
「まだ、人間とは少し違う」
「普通じゃん。気にし過ぎてるから、李芙はそう思うだけだよ」
李芙の首元にあるもう一つの呼吸器は、前より柔らかくなった。それは、研究室のある施設に設置された、深海の水槽の中にいる李芙の両親のものに近かった。深海の水槽に餌をやり終えて正面に戻ってくると、水槽の中を覗いていた李芙は私に言った。
「これって、どんどん硬くなって、ある日ポロって取れちゃうんだろうなって思ってた。でもまた退化しちゃった」
首元に手をやって笑いながら李芙は言う。原因は知っている。あの日、それを使ったからだ。海に飛び込んだあの日。1回だけでなく2回も。研究室に戻ってから、この水槽の中に李芙は入って行った。そんなことを思いながらそっと水槽の硝子に手をそえると、キラッと光った。グレーの色をしているから、李芙のお母さんだ。柔らかな長いキラキラ光る触手がエラの少し上の部分にあって、その柔らかさが李芙の言う退化を表しているんだ。
「どう?深海の水槽は。話進みそう?」
あれから数ヶ月。高知に新しくできる水族館に深海の水槽を作るというアイデアを採用してもらった。
「あ、うん。やっぱり思っていたような大きいものは作らせてもらえないみたいだけど」
「だろうね」
「え?わかってたの?」
「最初に反対したでしょ?人気ないって」
「そんなことないよ。でもやっぱり、深海魚は捕獲してくるのが難しいとかいろいろあって」
「そっか。それで、ひとつ提案があるんだけど」
「提案?」
「俺からじゃなく、俺の母さんから」
「お母さん?」
私は、水槽のほうに目をやった。いつもはただの暗いだけの水槽なのに、今日はやけにキラキラ光っているなと思っていた。
「発表しては、どうかなと思って」
「発表?」
「新種の深海魚を見つけたって」
「え?どうやって?」
李芙はフッと笑った。
「ここに、いるでしょ。2匹も」
「お父さんとお母さん?」
「堂々と、俺たちの研究ができるでしょ」
「研究って、材料になっちゃうんだよ?」
「そうだけど殺されるわけじゃない。むしろ大事に扱われるよ、海洋生物学者はこぞって調べたがるだろうから」
「そんな・・・ご両親を売るみたいなのって」
「売るんじゃないよ。見てもらうんだ」
「見てもらうって?」
「夏那子の作った深海の水槽で」
「え?」
「そこで預かってもらう。俺もそこで研究をする。ダメかな?」
「移り住むってこと?」
「そうなるね」
「ここの研究は?」
「続けるよ。場所が変わるだけ。だけどこの水槽の中身が無いと困るんだ」
「何が困るの?」
「ここの水槽の中に使われている海水、それに与える培養は現在の実際の海と、あらゆる濃度が異なるんだ」
「どういう風に?」
「古代の状態にほど近い」
「古代って、どのくらい?」
「俺たちの仲間が進化したいって思い始めるより前の海だ」
「何が違うの?」
「欲望を抑えられる」
「それ、何の意味があるの?」
「俺たちはこれ以上進化したいなんて思わないほうがいいんだよ。現に俺の親は退化を選んだ。結局はこっちのほうがいいってことだ」
「李芙も、そう思ってるの?」
「ん?」
「今の状況が嫌なの?あんな風に戻りたいの?」
「戻るもなにも、俺はあの姿だった時期がないから、わからないけど」
そう言った李芙の言葉にホッとした。李芙も、深海魚に戻りたいって言いだすのかと思った。あの日海に飛び込んだみたいに。
「李芙みたいな人は、この世界にたくさんいるのかな」
「いるだろうね」
「みんな、李芙みたいに呼吸器が2種類あるのかな」
「どうだろう。もうなくなったやつもいるんじゃないのかな」
「どうしてそう思うの?」
「俺みたいに、こんな水槽から離れられないようじゃ進化はますます遅れるだろ。俺は特別環境が悪いんだろうな。街を歩いていても、研究で世界にも行ったけど、俺と、父さんや母さんが水槽越しに何かを感じ取り合うみたいに、会話をしなくても何かを感じ取れる相手に出逢ったことがない。進化を選んだ俺たちの仲間のうち、やっぱり退化を選んだか、もしくはとっくに人間に進化しきったのか、どっちかなんだよ」
「それが本当だったら、私が深海の水槽を新しく作って、その環境で李芙が研究を続けるのは良くないってことになるんじゃないの?」
「それは違う」
「もし本当に古代の状態に近い深海の水槽を作ってもらえるんなら、生きることに苦しくなってる実際の海の深海魚を救えるかもしれない」
「どういうこと?」
「捕獲して水槽に入れられた深海魚は、昔の姿をそのまま維持できる環境で生きられる。深海の世界にこれ以上歪が起きないための大事な水槽になるはずなんだ。今の地球の海は、歪過ぎてる」
水槽の中ではキラキラとお母さんの触手が光っていた。
「俺は、そのためにこの姿である必要があるんだ。研究を続けなきゃいけないんだ」
「李芙は、退化はしないってことだよね?」
「え?」
「ずっとこのまま、一緒に居てくれるんだよね?」
「どうしたの?急に」
「いつか、李芙も戻って行ってしまうんじゃないかって、毎日怖かったんだ」
「そんなこと考えてたの?」
「考えるよ。怖かったよ、ずっと」
「ごめんね、不安だったよね」
「でも、いいの?深海の水槽は、やっぱり、疑似だよ?」
「いいんだ。それでも必要だ。誰かが、俺の仲間を救わなきゃいけないんだ。生きている間に」
それから少しして、李芙は学会に新種の深海魚を発見したと発表した。人の出入りのほとんどなかったこの施設の深海の水槽が一気にピックアップされた。高知にできる新しい水族館の人間が私の手がける水槽に興味を示さないはずがなかった。私がこの、胡先生のもとで研究をしていたことも知っている。当初小さいスペースを取る予定だった深海の水槽は、日本で1番大きな深海魚専用の大きな水槽へと製作変更が決まった。李芙が、新種の深海魚の飼育をその水族館に依頼したからだ。
そのタイミングで、李芙のいる研究室での私の半年の研究が終了した。私は自然と研究所を去ることになった。なんだかんだ、弟みたいに慕ってくれた古瀬くんが、驚くほど号泣しながら送り出してくれた。
「高知の水族館、できたらぼく、ぜったい行きますからぁ~」
「ありがと。古瀬くんも水質の研究がんばって」
「はい、Prof.李芙も居なくなっちゃうって言うし、俺も高知、行っちゃおうかなあ」
「その時はぜひ声かけて。私も李芙からは遅れるけど、高知に移り住む予定だから」
「やっぱりあれですか?結婚とかしちゃうんですか?Prof.李芙と」
「何言ってんの?わかんないよ、そんなことは」
李芙に誘われて、この半年の間に一緒によく歩いた遊歩道を歩きに行った。
「人が空を目指すみたいに、俺たちはまず海から出ることを目指したんだ」
「で?さっきのパイロットになりたかったって話に行きつくの?」
「本当にさ、子供の頃なりたかったんだ。パイロット」
「へえ」
「でも、小学生の頃に俺たちの祖先の話を聞かされてね、父さんに」
「そんな小さい時に?」
「俺が、地上で生まれた初めての子孫になるんだ。他にもきっといるとは思うけど。それでね、早くに知らせておく必要があったんだろう。もとから地球上に存在する人間とは違うってこと」
「もっと大きくなってからでもよかったんじゃ?」
「そういうわけにいかないよ。唯一残ってしまった2つ目の呼吸器のことは知られてはいけない」
「それって、春に海に飛び込むまで、試してみたことはなかったの?あの時初めて、まだ呼吸ができるって・・・」
「あぁ、プールとか浴室とか試してみたことはあったよ。だけど、海水じゃないと使えないって父さんから言われて。それでずっと、海には入るなって言われて育った。俺もなんだか怖かったしね」
「そうなんだ」
「うん・・・」
「まだ、李芙の知らないこと、いっぱいあるね、私」
「いいじゃない。新しいことこの先ちょっとずつ知れたら楽しいでしょ?」
「そんなにたくさんあるの?私の知らないこと」
「わかんないよ?実は夏那子と同い年ってのは嘘で、もう100年も生きてるとか」
「うそ?」
「嘘だよ」
「もぉ!!!」
李芙を叩こうとした私の手を掴むと、李芙はそのまま私を引き寄せて抱きしめた。
「これからもずっと、俺と一緒にいてよ」
「うん」
「怖くない?」
「怖くない」
「ねぇ、これって一応プロポーズなんだけど?」
「え?そうなの?」
「夏那子って、鈍感」
「もっとわかりやすいのにしてよ。わかんないよ」
李芙は、抱きしめていたのをやめると。私の前にきちんと向き合って立った。
「俺と結婚する?」
息が止まりそうだった。わかりやすいようにって言ったのは私なのに。
「結婚しようよ」
李芙は、普通に、私の愛した人だよ。思うほどに涙が溢れて、言葉にならない言葉で、私は「うん」と頷いた。
新種の深海魚として発表された李芙のお父さんとお母さんは、予定通り、新しい水槽に移動した。それには李芙も立ち会った。新種発見ということで、名前を決めていいと言われ、李芙が名前をつけた。それは李芙のお父さんとお母さんの名前を並べたものらしくて。全く意味のわからない長い暗号みたいな名前なんだけど、決まったからにはそれが彼らの名前だ。水槽の前に、写真と共に名前を書いたプレートが添えられた。
水槽のデザインには悩まされた。深海の水槽は、研究所にあったものと同様、光をほとんど与えない、とても暗いもので。訪れた人を誘導するためのライトが足元にある程度で、ほとんど真っ暗に近い。それでも時々キラキラと光るのは、その新種の深海魚だっていうのは世間に知れ渡った。他にも珍しい深海魚が一緒に水槽に入れられた。李芙の培養して作ったその海水はとてもきれいな透明度を保って、黒い土で覆われているんじゃないかと思われがちな深海の底に、まるで砂浜でも存在するかのようなきれいさだった。それもある意味人気になった。
水族館が閉館してからの時間に李芙はここによくやってきて、水槽の前に胡坐を書いて座っては、じっと水槽を見つめていた。それは邪魔をしてはいけない時間で。きっと水槽の中を泳ぐ魚たちと何かインスピレーションを使ってコミュニケーションを取っているんだ。それが終わると、必ず私を抱きしめにくる。何を話したのかは毎回聞かなかった。
それから少しずつ、李芙の首筋が硬くなって。いつしかそれが無くなった。その頃から、李芙は閉館した後の水槽の前で、よく泣いていた。
「もう、何も聞こえないんだ」
「何もって?」
「父さんの思っていることも、母さんの思っていることも、全くわからないんだ」
それは、李芙が人間に進化し終わった証拠だった。嬉しいけれど、喜べなかった。口数の減った李芙を抱きしめるのが精一杯だった。深海の水槽の仕事に携わっている限り、こんな日は来ないと思っていたのに、実際にはやってきた。だけど何とも言えない心境だった。
「李芙も、この中に返りたかった?」
問いかけると、李芙は首を振った。
「本当に?」
そしたら大きく頷く。
「大丈夫、俺にはこれを守っていく仕事があるから」
「うん」
「夏那子のことも守るから」
「うん」
「大丈夫だから」
そう言う李芙は決して大丈夫には見えなかった。
「そのために私を選んだんでしょ?私には何でも話してね」
「ありがとう」
「李芙の深海魚としての姿は知らないけど、でもわかる気がするから」
「うん、ありがとう」
「きっとお父さんに似て、すごくきれいなんだよ」
「そう?」
「うん、透明度は1番だと思うよ」
「俺の?」
「そう。体の部分は海の向こう側がきれいに見えるくらいクリアで、呼吸器はとても優しく光って、しなやかでとても長いの」
「どれくらい?」
「体の倍ぐらい、いや、もっと長いの」
「もっと?」
「そして見えない先でも李芙は必ず私を見つけて、会話をする」
「夏那子と?」
「うん、ちょっと想像して、私も深海魚になった気分で話してみたり、して」
「いいね、それ」
「李芙はきっと、暗い中でも私を探してくれる」
「うん、探すね」
「そんで、触手を使って言うんだよね」
「なんて?」
「俺たち、付き合う?って」
「なんだよ、それ」
李芙がクスクスって笑った。それだけで泣きそうだった。
深海の渚


