
太平洋、血に染めて 【劇場版】
・プロローグ用BGM
https://www.youtube.com/watch?v=qGWAjxkbLlo
https://www.youtube.com/watch?v=zDG0_txuy-Q(予備)
*オープニング
https://www.nicovideo.jp/watch/sm36655046
https://www.youtube.com/watch?v=MZ53MjipFzM(予備)
*** プロローグ ***

一九九九年七の月。天空より舞い降りし恐怖の大王によって人類は滅ぼされるだろう。かつて、ある偉大な預言者はそう断言した。そして運命の一九九九年が訪れ、いよいよ人類滅亡のカウントダウンが始まった。核戦争、あるいは巨大隕石の衝突か。根拠のないデマが飛び交い、パニックに陥る人々。だが結局、何事もなく一年が過ぎ、さらに一年、また一年と月日は流れ、やがて恐怖の大王の名は人々から完全に忘れ去られるのであった。
しかし、人の心から完全に悪が消えることはない。恐怖の大王は独裁者の弱き心に宿り、世界征服という巨大な野望に目覚め、ついに動きだした。
欲望。憎悪。狂気。冥府の鬼ならぬ、人が自らの手によって造り上げた地獄。大地は火の海となり、海は血の朱に染まる。恐怖の大王が、世界を焼き尽くす。終わりのない戦いに、人々は絶望する。そして、大五郎たちも太平洋をさまよいながら希望の光を探しつづけているのであった!!
――太平洋、血に染めて――

空が紅い。海も朱い。空母の甲板にいるのは大五郎とヨシオのふたりだけ。ヨシオは舳先で仁王立ちになり、腕組みをしながら夕陽を見つめている。ヨシオがなにものなのか、大五郎にはわからない。空母の乗組員には見えないが、彼はいつもカタパルトオフィサーのイエロージャケットを羽織り、おなじくカタパルトオフィサーのヘルメットを身につけていた。
舳先の示す水平線の向こうに、夕陽が半分沈みかけている。
「おじさん、ばんめし!」
大五郎はヨシオのズボンをひっぱった。ヨシオは腕組みを解くと、だまったまま左舷のタラップに向かって歩きはじめた。大五郎も、だまってヨシオのあとにつづいた。
甲板の上に長く伸びる、ふたつの黒い影。右舷中央にそびえるブリッジは、ミサイルの直撃を受けて上半分吹がき飛んでいる。ブリッジのまわりには、まん中から〝くの字〟に折れた戦闘機やヘリコプターの残骸が転がっていた。動力は生きているが、スクリューや舵は魚雷で破損している。この空母は自力で航行することができないのである。生き残ったわずかな乗組員と避難民の集団を乗せたまま、ただ当てもなく太平洋をさまよいつづけているのだ。
夕食が済むと、大五郎はひとりで格納庫へ向かった。空母は外から見ると大きいが、艦内は通路の幅が狭く、どの部屋も小さかった。
ちょうど甲板の真下に位置する格納庫は、とても広かった。艦首から艦尾までつづく、まるで立体駐車場のようなところだ。格納庫は戦闘機やヘリコプターなどを収納する場所で、ここで整備をしたりするのである。だが、この空母には飛行可能な航空機は一機も残っていなかった。本来なら航空機で埋めつくされている格納庫には、フォークリフトや航空機をけん引するためのトーイングカーが数台残っているだけだった。
格納庫の天井には、梱包材の〝プチプチ〟のように並んだ丸い照明が端から端までつづいている。空母の中には陽の光が差し込まないので、通路や部屋には常に明かりが灯っていた。
大五郎は左舷にある航空機用の大型エレベーターのほうに向かった。そこには、スクラップになった戦闘機が一機だけ放置されているのだ。戦闘機といっても、キャノピーが失われたコクピットの部分だけだ。それでも、大五郎は十分満足していた。操縦桿を動かしたり、スイッチをいじったり、遊園地の乗り物よりも楽しいと大五郎は思っていた。
――カチャン
大五郎がコクピットで遊んでいると、ちょうど反対側の隅のほうで物音がした。大五郎はコクピットから身を乗りだして音のしたほうを見やった。
「あっ」
男がひとり、格納庫の隅でなにか作業をしている。長い金属のパイプや戦闘機の増槽――機体の外に取りつける燃料の増加タンク。シッポのないマグロのような形をしている――をトーチバーナーで溶接して、なにかを組み立てているようだ。大五郎は男のほうへ行ってみた。
「おじさん、なにしてるの?」
大五郎が声をかけると、男はバーナーの火を消してゆっくりとふり向いた。
「イカダをつくっているのさ」
青い顔で男が笑った。ものすごく哀し気な、いや、どちらかといえば不気味な笑顔である。マユの端が下がっていて、とても残念そうな表情に見える。そして青白く濁ったうつろな瞳は、完全に喜怒哀楽を失っていた。
「坊や、名前は?」
静かな声で男がたずねてきた。
「だっ、だいごろう!」
いささか戸惑いながら大五郎は声を張った。
「お、おじさんのなまえは?」
疑わしい表情をしながら大五郎も訊ねた。
「ブラウンだ。ガーランド・ブラウン」
「がー……らんど……?」
大五郎は「はっ」とした。以前に観た映画で似たような名前を聞いたことがあるのだ。その映画の登場人物も、どことなくこの男に似ていたような気がする、と大五郎は思った。もっとも、その映画のタイトルは忘れてしまったのだが……。
ガーランドがふたたび作業をはじめた。
「おじさん、イカダをつくってどうするの?」
「逃げるのさ」
ガーランドは作業をつづけながら答えた。
「どこに?」
「どこでもいい。とにかく、この空母から脱出するんだ」
「どうして?」
トーチバーナーの火を消すと、ガーランドはゆらりとふり向いた。凪いだような青白い眼が、じっと大五郎を見つめてくる。
「ここにいたら死ぬからさ」
ささやくような声で言うと、ガーランドは弱々しく首をふった。かすかに笑みを浮かべているが、マユの端が下がっているので泣いているようにも見える。そして、声にも張りがない。顔色も、まるで死体のように真っ青である。どこか体の具合でも悪いのではないか、と大五郎は一応心配してやった。
ぼそぼそと呟くような小さな声でガーランドがつづける。
「この空母は、もう動かないんだよ。無線も通じないし、レーダーも故障している。そして水も食糧も底を尽きかけている。いいかい、ダイゴロー」
ガーランドが大五郎の眼をのぞき込んできた。
「ここでじっと救助をまっていても、助かる保証なんてどこにもないんだよ」
「でも、うみにでたらサメにくわれるよ?」
「もちろん、危険なのはわかっているさ。でも、おじさんは生きる努力をしようと思う」
そう言って残念そうな表情でほほ笑むと、ガーランドは妙な歌を口ずさみながらふたたび作業をはじめた。
すべては~主の~御手に~♪
「へんなうた!」
大五郎は飛び跳ねながら笑った。
「おまじないさ」
ガーランドは歌いつづけた。大五郎も、夜の格納庫に元気よく歌声をひびかせるのであった。
いつの間にか眠っていたようだ。大五郎はスクラップになった戦闘機のコクピットで目を覚ました。ガーランドは、まだ作業をつづけているのだろうか。
「あっ」
ガーランドがトーイングカーを使ってイカダを運んでいる。左舷のエレベーターに乗せて甲板に運ぶつもりらしい。
鉄パイプで組んだイカダは大人が五、六人ほど乗れる大きさで、浮力は航空機用の増槽だった。〝川の字〟に並べた三本の空の増槽の上に、正方形に組んだ鉄パイプを溶接しただけのシンプルなものである。そして、増槽の両端部分には小さなキャスターがひとつずつ取りつけられており、地上でも楽に運搬できるようになっていた。
いよいよ船出である。大五郎も、はりきってエレベーターに向かった。
「おじさん、できたんだね」
トーイングカーの運転席でガーランドが親指を立てた。やはり、彼は残念そうな顔でほほ笑んでいるのであった。
エレベーターが甲板についた。空は、まだ薄暗い。風はなく、波も穏やかそうだ。
「おじさん。このイカダ、どうやっておろすの?」
甲板に上げたのはいいが、ここからどうやって海におろすのか。大五郎には見当がつかなかった。
「まず、イカダの後部に、このロープを結びつけるんだ」
ガーランドがイカダの後部に長いロープの端を結びつけた。そして、空母の舳先にある適当な突起物に、もう片方の端を結びつけた。それから、鉄パイプに鉄板を溶接してつくったオールを別のロープでイカダに結びつけた。
「あとは、こうするのさ」
ガーランドがイカダをうしろから押しはじめた。
「おっこちた!」
海に落ちてゆくイカダを指差しながら大五郎は叫んだ。
「でも、おじさんはどうやってイカダにのるの?」
「このロープを伝って降りるんだよ」
舳先にある突起物に結び付けたロープをつかみながらガーランドが言った。
「ダイゴロー、きみも来ないか? おじさんと一緒に脱出するんだ」
「やだ!」
「ここにいたら、まちがいなく死んだよ?」
大五郎の顔のまえにあたまをかがめてガーランドは言う。
「ダイゴローは、死ぬのが怖くないのかい?」
「こわくない!」
「ダイゴロー。きみはまだ小さいから、死ぬということがどういうことなのか、よくわかっていないんだよ」
「おいらは、こわくない! みんながいるから、こわくない!」
「きみってやつは」
ガーランドが呆れたようにため息をついた。哀愁を帯びた瞳で大五郎の眼を見つめながら、ガーランドは弱々しく首をふっていた。
「それじゃ、おじさんは行くよ。元気でな、ダイゴロー」
「おじさんも、げんきでね!」
ガーランドがロープを降りていく。背中には、大きなリュックを背負っている。三日分の水と食料が入っているらしい。
「さよなら、おじさん!」
大五郎が手をふると、ガーランドもイカダの上から手をふって応えた。
舳先の示す水平線が、にわかに輝きはじめた。日の出である。
すべては~主の~御手に~♪
白みはじめた空に、ガーランドのさわやかな歌声が響き渡る。大五郎は舳先でひざを抱えながらガーランドを見送っていた。
「まぶしい!」
大五郎は掌で陽の光をさえぎった。白く輝く太陽の中へ、ガーランドのイカダが消えてゆく。
「――え?」
イカダの右側から三角形の黒い背ビレが走ってくる。白く輝く波を切り裂きながら、走っている。ガーランドのイカダを目指して、まっすぐ走ってゆく。
「あっ!」
黒い背ビレがイカダを切り裂いた。イカダはばらばらに砕け散り、ガーランドは海に投げ出されてしまった。ガーランドが溺れている。溺れながら、なにか叫んでいる。
「おじさん、あぶない!」
ガーランドに向かって大きなサメが飛び跳ねた。
「くわれたーっ!!」
大五郎は絶叫しながら飛び上がった。
ガーランドは大きなサメにひと口でのみ込まれてしまった。
「おじさーん!」
朝陽に向かって、大五郎は叫んだ。
きらきらと輝く水面に、イカダの残骸がきらきらと輝きながら漂っている。
すべては~主の~御手に~♪
空耳だろうか。大五郎の耳に、ガーランドのさわやかな歌声が聞こえてきたような気がした。
「おじさん……」
大五郎が例の歌を口ずさもうとしたとき、うしろのほうから足音がひとつ、ちかづいてきた。
「あっ」
ヨシオである。彼は大五郎の傍らに立つと、腕組みをして水平線を見つめはじめた。
「おじさん、おはよー!」
ヨシオはだまって水平線を見つめている。やはり、返事をしてくれないのだろうか。大五郎がそう思ったときである。
「小僧、名は?」
「だいごろう!」
「大五郎、か。いい名だ」
「おじさん、あのね……」
大五郎は、さっきの出来事をヨシオに話そうと思った。
「……なんでもないや」
やっぱりやめた。たとえ話したとしても、おそらくヨシオは関心を示さないだろう。
大五郎はヨシオのとなりで水平線を見つめながら、ガーランドの歌をそっと口ずさんだ。
大きな戦争があった。
世界は核の炎に包まれ、国家という国家は消滅した。
生き残ったわずかな乗組員と避難民たちを乗せ、大海原をあてもなく漂う一隻の航空母艦。
ここは太平洋のド真ん中。
羅針盤の針がくるくる回る。天国と地獄を交互に指しながら、くるくる回る。
今日も夕陽は真っ赤に燃える。
空と海を朱に染めて。
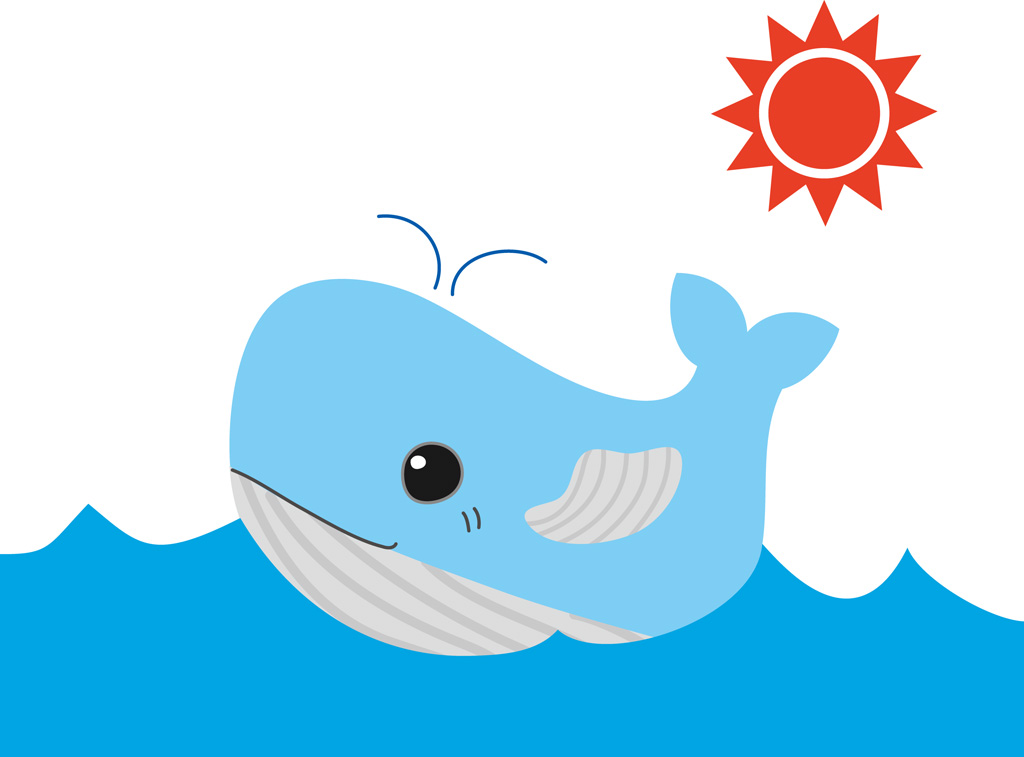
「おじさん、このふねはどこにむかってるの?」
大五郎はヨシオの顔を見上げながら訊いた。
「さあな。空母の動力はまだ生きているらしいが、スクリューは魚雷で破壊されている。おまけに、操舵室もミサイルで吹き飛んでしまった」
舳先の示す水平線に目を向けたままヨシオが言う。
「この空母がどこに向かっているのか。どうしても知りたいのなら、この蒼い海にでも訊くんだな」
ヨシオのメガネが朝陽を受けて白く輝いている。その輝きの奥で、彼はいったいなにを見ているのか。大五郎にはわからなかった。
ミサイルの直撃を受けて上半分が吹き飛んだブリッジの側面には艦番が白くペイントされている。ほとんど消えかかっているが、数字で「88」と記されてあった。そのブリッジのそばで、大勢の老若男女が車座になっている。右手に杖をもった老人がひとり、中央であぐらをかいていた。長老である。彼らは長老の話を熱心に聞き入っていた。
ヨシオは仁王立ちで腕組みをしたまま、舳先の示す水平線のほうを見ている。大五郎も、おなじ格好をして水平線を眺めていた。
「あっ!」
およそ三百メートルほど前方に、赤い大きな柿の種のようなものが浮かんでいる。
「あかいクジラだ!」
赤い物体を指差しながら大五郎は叫んだ。
「いや、あれは軍艦だ」
静かな口調でヨシオが言った。
「でも、たいほーがついてないよ?」
「ひっくり返ってるから見えないのさ」
そうつぶやくと、ヨシオはゆっくりと舳先のほうへ歩きはじめた。大五郎も、ヨシオのうしろをついて行った。
カタパルトオフィサーのイエロージャケット、そして、おなじくカタパルトオフィサーのヘルメット。しかし、この空母の乗組員でヨシオのことを知る者は、ひとりもいない。いったい、ヨシオは何者なのか。ヨシオは、なぜそんな格好をしているのか。大五郎は不思議そうにヨシオの背中を見つめながら思うのだった。
舳先に立つと、ヨシオは腕組みをして軍艦の赤い船底をにらみつけた。転覆している軍艦の全長は、海面に出ている部分だけでもこの空母の三分の一ぐらいはありそうだ。ヨシオのよこに立ちながら、大五郎はそう思った。
「まずいぞ。このままじゃあ、ぶつかっちまう!」
空母の乗組員らしき男がうろたえている。舳先のほうに、野次馬たちがぞろぞろと集まりはじめた。
「おお、あれは!」
うしろのほうから強引に人混みをかき分けるようにして長老がやってきた。
「シーサーペントじゃ!」
長老は大五郎のよこに立つと、赤い船底を杖で指示しながら叫んだ。
転覆した軍艦のそばに、大きな黒い影が浮かんでくる。
「モーガウル……いや、チェッシーか」
差し迫った表情で長老がなにかつぶやいた。ハゲた頭頂部を汗できらきらと輝かせ、カッと見開いた眼は血走り、まるで生まれたての仔馬のようにガクガクブルブル震えている。この老人は、その名の通り、以前は小さな村の長老だったのだ。中東の、小さな村だ。しかし、その村はもう存在しない。世界は核の炎で焼き尽くされ、長老の村も消滅してしまったのだ。
「む!」
ヨシオのメガネが強く光った。
「あっ!」
指差しながら、大五郎も声を上げた。現れたのはシーサーペントなどではない。いつぞやのクジラだった。クジラは潮を噴きながら、軍艦のまわりをゆっくりと泳ぎはじめた。いったい、これからなにがはじまるのだろうか。ヨシオのズボンを右手でぎゅっとにぎりしめながら、大五郎はじっとクジラの様子をうかがった。
「あっ、艦に体当たりしたぞ!」
舳先の隅で、だれかが叫んだ。
艦尾の方向から軍艦に体当たりしたクジラは、そのままあたまを押しつけるようにして泳ぎはじめた。
「あっ、ぐんかんをおしている! ぐんかんをどかそうとしてるんだね、あのクジラ」
大五郎はクジラを指差しながらヨシオを見上げた。ヨシオは腕組みをしたまま、だまってクジラを見つめている。
みんなも不安げな表情で静かにクジラを見守っている。クジラは大きな尾ビレを上下に動かしながら、必死に泳いでいる。しかし、軍艦はなかなか動かない。赤い船底は、すでに空母の前方、およそ百メートルのところまで迫っていた。
「だめだ。やっぱり、オレたちはここで死ぬんだ」
ひとりが弱音をもらすと、にわかに甲板中が悲観的なムードに染まりはじめた。
「どうせ救助は来ないんだ。遅かれ早かれ、こうなる運命だったのさ」
「助かったところで、もう帰る場所はないんだ。これ以上地獄を見るぐらいなら、死んだほうがマシだ」
そのときである。
「いいかげんにせぬか!!」
長老が杖を甲板に突き立てながら声を荒げた。
「みなの気持ちはよくわかる。ワシも、故郷を……あの生まれ育った村は、もう思い出の中に消えてしもうた。じゃが、まだ消えずにのこっている物が、ひとつだけある」
長老はいったん言葉を切ると、赤い船底にゆっくりと向きなおった。
「それは……希望、じゃ」
静かに、だが、力強い口調で長老がうなずいた。みんなも神妙な面持ちで長老の話に耳をかたむけている。ヨシオは聞いているのかどうかわからないが、落ちついた表情で腕組みをしながらじっと赤い船底をにらんいた。
長老も赤い船底をにらみながらつづける。
「まだ死ぬと決まったわけではないのじゃ。最後の最後まで、希望を捨ててはならんのじゃ。あきらめてはいけないのじゃ。見るがいい、あのクジラを」
長老が杖の先でクジラを指し示すと、みんなが「あっ」と声を上げた。
「うごいた!!」
大五郎も赤い船底を指さしながら叫んだ。はじめはゆっくりだった。そして、動きはじめると徐々に勢いがつき、赤い船底は見る見る空母からはなれてゆくのであった。
「希望……か」
ヨシオがポツリとつぶやいた。
「やった! 助かったぞ! オレたちは助かったんだ!」
青空にひびき渡る歓喜の声。ようやくみんなの顔に笑顔が戻った。だが、長老だけは、なぜか複雑な表情をしていた。
「野生の動物たちは、一瞬一瞬を全力で生きているのじゃ。真剣に生きておるのじゃ。自ら命を断とうとするのは……人間だけじゃ」
ひとつため息をついてうつむくと、長老は何度か首をよこにふった。
「あっ、クジラもよろこんでるよ!」
大五郎は笑顔でクジラを指さした。
クジラは軍艦を押しのけると、まるでみんなを励ますかのように空母のまわりを一周するのであった。
「……ありがとう、トリトン」
クジラを見つめたまま静かな口調でヨシオが言った。
「ありがとう!! トリトン!!」
どういう意味なのかよくわからないが、大五郎もクジラに向かって叫んだ。すると、トリトンは大五郎に応えるかのように空高く潮を噴き上げながら、ゆっくりと海の中へ帰ってゆくのであった。
「あっ、にじだ!」
トリトンが噴いた潮が虹になった。
「おじさん、トリトンがにじをつくったよ!」
大五郎は虹を指差しながらヨシオの顔を見上げた。しかし、ヨシオはやはり返事をしなかった。この男は、いたい何者なのか。そしてなにを考えているのか。それを知る者はだれひとりとしていなかった。
「さよなら、トリトン!!」
水平線の向こうにとどくぐらい大きな声で大五郎は叫んだ。
太陽がまぶしい。水平線には夏雲が浮かび、空はどこまでも青く晴れ渡っている。そして蒼い海には、大きな虹の橋がかかっていた。
「きれいだね、おじさん」
ヨシオは腕組みをしてだまっている。でも、きっと胸の中では返事をしているにちがいない。ヨシオのメガネに映る虹の橋を見上げながら、大五郎はそう思うのであった。

甲板を疾走する赤いトレーラートラック。その行く手を阻むように立ちはだかる銀色の拳銃。トラックは、まっすぐ拳銃に向かって突っ込んでゆく。そして、ぶつかったと思った瞬間、トラックのまえから拳銃の姿が消えた。
トラックは急ブレーキをかけ、甲板のまわりを注意深く見まわした。だが、どこにも拳銃の姿は見えない。トラックは、にわかに慌てはじめた。いったい、やつはどこへ? そのとき、何者かの黒い影がトラックの頭上をよこ切った。はっとして空を見上げる。太陽にかさなる黒い拳銃の影。やつだ。そう思った瞬間、とつぜん黒い影の形が変わった。さっきまで拳銃の形をしていた黒い影は、こんどは人間の形に姿を変えたのだ。やつめ、ついに正体を現したな。
「こい、デストロン!!」
赤いトレーラートラックも人間の形に姿を変えて迎え撃つ。
「ゆくぞ、サイバトロン!! こんどこそ決着をつけてやる!!」
デストロンが猛スピードで太陽から突っ込んでくる。サイバトロンはよこに飛び退き、かろうじて攻撃をかわす。だが、やつは空中を飛びながら、ふたたびアタックをかけてきた。反撃、いや、まにあわない。サイバトロンは攻撃を避けるため、天高く飛び上がった。だが、デストロンはすさまじいスピードで追撃してくる。させるか――サイバトロンは間一髪のところでデストロンの攻撃をかわす。そして、勢いあまったデストロンは、そのまま小高い山に激突するのだった。
「ぐわっ!!」
青空にひびき渡る悲鳴。
やったか――サイバトロンが山のほうをふり返る。雪でまっ白に染まった、大きな山だ。しかし、山頂付近は大規模な雪崩により、きれいに禿げ上がっている。そしてやつは、デストロンは、無傷のまま山の頂に堂々と立っていた。
では、いま悲鳴を上げたのは、いったいだれなのか。サイバトロンが戸惑っていると、とつぜんデストロンの足もとで山がグラグラと揺れはじめた。噴火か――サイバトロンがそう思った瞬間だった。大きな山がグルリとよこに回転した。そして、その裏側から巨大な顔が現れたのだ。
「きさまは、ユニクロン!」
デストロンが慌てて山からはなれ、身構える。そしてサイバトロンもビームライフルを構え、ユニクロンに狙いを定めた。そのとき、一本の長い大きな手が山の下から現れ、天に向かってグングンと伸び上がった。ついに動きだしたユニクロン。はたして、彼らの運命やいかに――?
「これ、痛いではないか」
山頂を撫でまわしながらユニクロンが言った。
肩まで伸びる長い白髪。だが、頭頂部は額の生え際から禿げ上がっている。そして、胸元まで伸びた、まっ白なアゴひげ。まるで仙人のような老人でる。
「いけない子じゃ」
そう優しい声で叱ったのはユニクロンではなく長老だった。
「おいらじゃない。ですとろんが、やったんだ」
大五郎は片方の手にもったおもちゃを長老の顔のまえにかざして見せた。
「なるほど、デストロンか。わるいやつじゃな」
あたまに大きなたんこぶをつくった顔で長老がニコリと笑った。
たしかに、デストロンは悪者である。
「めっ!!」
大五郎はデストロンのあたまをちからいっぱい掌で叩いて叱りつけた。
「まだ釣れないのか、じいさん?」
ハゲあたまのよこで言ったのは、渋色のくたびれたカウボーイハットを被る男。ハリーである。
「やはり、エサがわるいみたいじゃな」
「たしかに、コッペパンで海の魚を釣ろうなんて、おかしな話かもしれないな」
長老は艦首右舷にあぐらをかいて座り、釣り糸を垂らしていた。ハリーは長老のよこに立って葉巻をふかしながら、ぼんやりと水平線をながめている。
大五郎は長老の傍らで遊びながら、すぐそばの舳先にふと目をやった。甲板作業員の黄色いヘルメットを被り、カタパルトオフィサーを示すイエロージャケットを羽織った男。大五郎たちに背中を向ける格好で仁王立ちになり、腕組みをしているのはヨシオである。彼は、いつものように舳先に佇み、じっと水平線を見つめていた。しかし、日本人である彼が、なぜカタパルトオフィサーの格好をしているのか。彼は、いったい何者なのか。いつからこの空母に乗っているのか。彼の正体を知る者は、だれもいなかった。
長老が釣竿をにぎったまま、うとうとしはじめた。やはり、海の魚はコッペパンなど食べないのだろう。
大五郎は、ふたたび赤いトレーラートラックと銀色の拳銃のおもちゃで遊びはじめた。このおもちゃは格納庫の隅に無造作に置かれた木箱の中にあったのだ。とうぜん持ち主をさがしてみたが、だれも名乗り出ないので大五郎が預かることにしたのである。
このおもちゃは、とても複雑な仕組みになっていて、ふたつとも人型ロボットに変形できるようになっていた。大五郎は、さっき人型に変形させたサイバトロンを、もういちどトレーラートラックに変形させることにした。
「とらんす――」
――そのときである!
「フィッシュオン!!」
いきなり叫んだのは長老である。彼は甲板に立ち上がると、竿を大きくしならせながら、ものすごい勢いでリールを巻き上げはじめた。
「こっ、この手ごたえは……やつじゃ! リヴァイアサンじゃ!」
長老は熱狂的なUMAマニアなのである。
「しっかり巻き上げろ、じいさん」
ハリーは慌てて葉巻をふみ消すと、長老の竿に手を添えながら手伝いはじめた。
「サメだ」
釣り糸の先をにらみながらハリーが言う。
「こいつはサメだ」
「くわれる!」
大五郎がおどろいて飛び上がると、ハリーは陽気に笑った。
「こんどはオレたちが食う番だ」
だいたい百センチ前後だろうか。黒い背ビレの主は、まるでパトカーの追跡をふり切ろうとする暴走車の如く、海面の下を激しく暴れまわっていた。そして、黒い背ビレの主が大きく飛び跳ねたときである。とつぜん、ハリーと長老が弾かれたようにうしろへ吹きとんだのだ。
「はうぁ!」
長老が背中から倒れ込んで後頭部を強打した。そのよこで、ハリーも尻もちをついて転がった。
「痛てて……」
先に起き上がったのはハリーである。彼はカウボーイハットを被りなおしてからゆっくりと甲板の上に立ち上がった。
「やれやれ。糸を切られちまった」
ハリーは掌をもち上げて苦笑した。
「御馳走に逃げられたサメも、さぞ悔しがってるだろうな」
皮肉交じりに嘲笑するヨシオの背中を見てハリーがマユをひそめる。
「それじゃあ、あんたをエサにして釣ってみようか? あんたを食ったサメで作るフカヒレスープは、さぞうまいことだろうよ」
「サメ肉ソーセージのホットドッグも、なかなかいけるぜ?」
そう言ってヨシオが肩をゆらすと、ハリーはカウボーイハットの鍔を下げて呆れたようにため息をついた。
「食えないやつだぜ、まったく」
新しい葉巻に火を点けながら、ハリーも肩をゆらしていた。
長老は、まだ起き上がってこない。甲板の上に仰向けになったまま、ピクピクと痙攣している。長老は口から白い泡を吹きながら、気を失っていた。
大五郎は気を取りなおしてさっきのつづきをはじめることにした。
「とらんす――」
――そのときである!
「ヒャッホーゥ!!」
けたたましい奇声が青空にとどろいた。後部甲板のほうからだ。いったい、なんの騒ぎだろうか。大五郎は甲板に座ったまま声のするほうをふり向いた。
右舷中央にそびえる大破したブリッジ。そのよこから左舷舷側にかけて散らばったブリッジの破片や航空機の残骸。その隙間の向こう側を、なにかがものすごいスピードで走りまわっている。あれは、トーイングカーだ。飛行機を駐機場までけん引するための作業車両である。トーイングカーはティッシュペーパーの箱のような形をしている平べったい車で、むき出しになった運転席にはフロントガラスもドアもなく、最高速度は三十キロ程度だった。しかし、残骸の隙間を走りぬけるその影は、それ以上のスピードが出ているようだ。
「あっ」
ブリッジのそばにある真ん中から〝くの字〟に折れた戦闘機の残骸の向こうから、一台のトーイングカーがものすごいスピードで飛びだしてきた。運転しているのは、モヒカンあたまの男。スネーク率いる謎のモヒカングループである。モヒカン男のトーイングカーは大五郎たちのそばでタイヤを鳴らしながら急ハンドルを切り、ふたたび残骸の向こうに走り去って行った。
やつらのリーダーであるスネークは、かつてギャングのボスだったらしい。その立場は空母に来てからも変わらないようで、彼はいまでも大勢の手下を従えている。この空母にいる彼の手下は、およそ数十人。彼らはグループの一員であることを証明するために、みんなモヒカンあたまになっていた。だが、リーダーであるスネークはドレッドヘアを肩まで伸ばし、口のまわりからアゴにかけてヒゲを蓄えていた。
「やつら、トーイングカーを改造しやがったな」
ハリーが忌々しそうに紫煙を吐き出した。
「ろぼっとに、へんけいするの?」
大五郎が赤いトレーラートラックのおもちゃを見せながら訊くと、ハリーは肩をゆらして笑った。
「エンジンのリミッターを解除したのさ」
やつらのトーイングカーは通常の三倍のスピードはでるだろう。大五郎にはよくわからないが、ハリーはそう言った。
「海のギャングのつぎは、陸のギャングか。やれやれじゃな」
長老が杖につかまりながらヨロヨロと立ちあがった。
「やっぱり、ですとろんはきらいだ!」
大五郎は銀色の拳銃のおもちゃを左舷の甲板から海に投げすてた。
お昼になった。
食堂の入り口を入ると、大五郎はいちばん奥のテーブルに向かった。入口正面から奥に向かって並ぶ長テーブルの、いちばんうしろの席だ。そして、いちばん端にカベを背にして座るヨシオのとなりに腰をおろした。テーブルをはさんでヨシオの正面にハリー、大五郎の正面には長老が座っていた。昼時なので、食堂はにぎやかだった。どちらかというと、空母の乗員よりも難民のほうが多いように見える。なにがあったのかは知らないが、大五郎たちが救助されたときには、すでに正規の乗組員はほとんどいなかったのだ。もっとも、舵を失ったこの空母は海の上をさまよっているだけなので、人手不足の心配はないのだが……。
大五郎はコーンスープをひと口飲んでからコッペパンに手を伸ばした。食事は一日三食だが、いつもコーンスープと小さなコッペパンがひとつだけだった。ただ、朝食にはときどき野菜サラダが添えられることもあった。食料が不足しているのである。質素な食事だが、口に入るものがあるだけマシだと思わなくてはならない。この海の向こう、壊滅的な被害を受けたであろう地上には、飢えに苦しむ人々が大勢いるのだ。それにくらべると、大五郎たちはまだ恵まれているほうだった。
「いただきます!」
大五郎が大きく開けた口の中にコッペパンを押しこんだときである。
「みなの者ぉぉ!! よおく聞けぃ!!」
食堂にひびき渡る、けたたましい叫び声。
大五郎はコッペパンにかじりついたまま声のしたほうをふり返った。食堂の入り口のまえに、たくさんのモヒカンあたまが並んでいる。まるでどこかのヘヴィメタルバンドのように、みんなそれぞれ顔に派手な隈取りのメイクを施している。そのうちの何人かは、長さ百センチほどの白い鉄パイプのようなものを肩にかついでいる。その鉄パイプは変わった形をしていて、片方の先端部分がやや太く、そこだけ赤い色で塗装されていた。
モヒカンたちの先頭に立っているのは、口ヒゲを蓄えたドレッドヘアの大男、スネークである。いま叫んだのも、おそらく彼だろう。はたして、彼らはなにをしようとしているのか。大五郎はコッペパンをかじりながら考えた。モヒカンあたまに隈取りのメイク。ヘヴィメタル。歌。大五郎は「はっ」とした。ライブだ。まちがいない。だから、みんなメイクをしているのだ。ヘヴィメタルバンドよろしく、過激にライブでもはじめるつもりなのだ。大五郎も歌いたい。みんなで、思いっきり歌いたい。ひさしぶりの余興である。大五郎は、ワクワクしながらコンサートがはじまるのをまっていた。
「ヒャック!」
スネークの声におどろいた長老が〝しゃっくり〟をした。大五郎の向かいの席で、コップの水を少しづつ口に含みながら胸を叩いている。
スネークが親指で自分の胸を示しながらつづける。
「いいかぁ! たったいまから、この艦はオレたちが支配することになった! 逆らうやつは容赦なく海に叩き込むから覚悟しやがれ!」
にわかに食堂がどよめき立つ。
はたして、やつらの目的はなんなのか。この艦を乗っ取ってなにをするつもりなのだろうか。いずれにせよ、難民たちにどうにかできる相手ではなさそうだ。おそらく、ヨシオでも勝ち目はないだろう。大五郎がそう思ったときである。
「きさま ヒャック ら~!」
ふいにひとりの男がイスから立ち上がった。
「きさまらの血は、な ヒャック に色ぢゃぁ~!!」
しゃっくりをしながらスネークを指さしたのは長老である。
「なぁにぃ~?」
スネークが眉間にしわを寄せて長老をみらみつける。
「キサマぁ~、このオレに――」
「ヒャック」
「うるせぇジジィ! 話してる途中でシャックリすんじゃねえ!」
「やめら ヒャック れない、と ヒャック まら ヒャック ない」
「ジジイ」
スネークの眼が冷たい光を帯びはじめた。
「長生きしたかったら、オレをあんまりイライラさせないことだ」
スネークがすごむと、みんな怯えた表情をしながらだまってうつむいてしまった。唯一、落ちついた様子で他人事のように食事をつづけているのはヨシオだけだった。
大五郎が口の中のコッペパンを飲みこみ、コーンスープの器に手を伸ばしたときである。
「おい、そこのメガネの男」
ヨシオを指差したのは赤いモヒカンあたまに丸い黒縁メガネの男。
「テメェ、カシラの話を聞いてるのか」
コバヤシである。
大五郎は、となりに座るヨシオをふり返った。彼はコバヤシを無視しながら、マユひとつ動かさずに食事をつづけている。
「ヤロォ、いい度胸してるぢゃねえか」
赤いモヒカンあたまの眼が血走った。
「まあ、まて」
スネークがコバヤシの肩をつかんで制した。コバヤシはおとなしく引き下がったが、丸い黒縁メガネの奥で血走った眼はヨシオをにらんだままだった。
不敵な笑みを浮かべながらスネークがヨシオを指差した。
「テメーはたしか、ヨシオだったな。どうだ、オレと勝負してみるか? 勝ったほうがこの艦の支配者になるんだ」
すると、ヨシオはいったん食事を中断し、横目でスネークをにらみつけた。
「勝負の方法は?」
「チキンレースだ」
「チキンレース?」
「そうだ。車はオレたちが用意する。どうだ、受けて立つか?」
スネークを横目でにらんだまま、ヨシオはしばし沈黙した。スネークは鋭い眼でヨシオをにらみながら返事をまっている。
「……いいだろう」
ヨシオの返事を聞くと、スネークは黄色い歯を見せてニタリと笑った。大五郎はコーンスープの中に目をおとして顔をしかめた。そしてスネークの黄色い歯をにらみながら、手にもったコーンスープの器をそっとテーブルの上にもどした。
「勝負は明朝十時。甲板でまっている」
そして、スネークは最後にこうつけ加えた。
「逃げるなよ」
もういちどニヤリと笑い、彼は手下どもを引き連れて食堂のドアを出ていった。
「やれやれ。面倒なことになってきたぜ」
そう言ったハリーも、どこか他人事のような口調である。
「ところで、ハリー」
コッペパンをちぎりながら、ヨシオがハリーに声をかけた。
「ほう。あんたから声をかけてくるなんてめずらしいな」
意外そうな表情でハリーが笑った。
ヨシオはメガネを軽く押し上げると、静かに話をつづけた。
「おまえに手伝ってもらいたいことがあるんだが、協力する気はあるか?」
「まずは話を聞こう。手を貸すかどうかは、それから決める」
「ヒャック」
しゃっくりをしながら長老が指をボキボキ鳴らした。
「わしにも遊ば ヒャック せろや」
首を左右にふってボキボキ鳴らすと、長老は不敵に笑うのであった。
いったい、ヨシオはなにをたくらんでいるのだろうか。そして、チキンレースとはいったいなんなのか。よくわからないが、なにか面白いことがはじまりそうな予感がする。大五郎も、ヨシオたちの話にまぜてもらうことにした。
翌朝。約束の時間である。
大五郎は長老とふたりで先に甲板に上がっていた。ヨシオとハリーは準備があるので遅れてくるらしい。スネークたちは、すでにブリッジのまえに集合している。そして左舷側の甲板には、大勢のギャラリーが集まっていた。
大五郎と長老は、艦首左舷のタラップのそばでヨシオたちをまっていた。
「ヨシオはまだかぁ!!」
ドレッドヘアの男がイラついた口調でがなりたてた。スネークである。まわりのギャラリーたちも、不安そうにざわめきだした。
――そのときである!
「あっ! エレベーターが動きだしたぞ!」
左舷のほうで、だれかが叫んだ。左舷後方の大型エレベーターが上がってくる。これは、航空機を格納庫から飛行甲板に上げるための装置なのだ。
「あっ」
大五郎はエレベーターの下から現れた黄色いヘルメットを指差しながら叫んだ。
その瞬間、とつぜん甲板のあちこちから悲鳴が上がった。みんな掌でカベをつくり、眩しそうに顔を背けている。いったい、なにが起きたのだろうか。
「うおっ!」
スネークも両腕で顔をかばうように身構える。
「ぐわっ!」
ほかのモヒカンたちも、にわかにうろたえはじめた。やつらも、やはり顔のまえで掌のカベをつくっているのであった。
「ぬおっ!」
長老も体を丸めるように身構えながら、慌てて着物の袖で顔を隠した。
そして、つぎの瞬間。
「まぶしい!」
大五郎は掌で顔を覆いながら尻もちをついた。まるでカメラのストロボのような眩い閃光が、大五郎の眼に突き刺さったのだ。
まちがいない。ヨシオだ。これは、ヨシオのメガネが陽の光を反射したのだ。そうにちがいない。
「ソッ、ソロモンが……焼かれている?!」
すぐよこで長老が呻いている。だが、呻き声はひとつではない。甲板のいたるところから聞こえてくる。どうやら、みんなも〝ソーラ・システム〟の直撃を受けたらしい。
まだ目がくらんでいるので、大五郎には周りの状況がわからない。目が開かないので、立ち上がることすらできない。小刻みにまばたきを繰り返しながら、ゆっくり目を馴らしていく。両手で顔を覆い、指の隙間からのぞき込むようにまばたきをする。しばらくそれをつづけていると、徐々に周りの景色が見えはじめてきた。
大五郎は、ゆっくりと顔から掌をはがした。甲板に尻をつけたまま、じっとエレベーターのほうに目を凝らす。
「ああっ!」
陽の光――いや、闘気だろうか。メガネが燃えている。まるで灼熱の砂漠に照りつける太陽のように、白く、激しく燃えている。その黄色い人影は、堂々と仁王立ちになって腕組みをしていた。
「おじさんだ!」
ヨシオである。
はじかれるように立ち上がると、大五郎はヨシオのそばに駆け寄った。
「またせたな、ぼうず」
言ったのはヨシオではない。こちらに背を向ける格好でトーイングカーに寄りかかる男。
「あっ、かうぼーいのおじちゃん!」
ハリーである。彼は肩越しにふり向くと、葉巻をくわえた顔でニヤリと笑った。
「見ろ、ヨシオたちだ」
にわかに周りが騒がしくなってきた。どうやら、みんなも視力がもどってきたようだ。
ヨシオがスネークたちのほうへ向かって歩きはじめた。ハリーもあとにつづく。大五郎も、ふたりの間に入り、ついて行った。
「よく来たな。てっきり逃げ出したのかと思ったぜ」
スネークの声が甲板にひびき渡ると、ヨシオは甲板の真ん中で足を止めた。彼はスネークと少し距離をとって対峙し、仁王立ちになって腕組みをした。
「ここは太平洋のド真ん中だ。たとえ泳いで逃げたとしても、フカのエサになるだけさ」
落ち着いた口調でヨシオが言った。
「くわれる!」
大五郎もスネークに向かって叫んだ。
すると、スネークが眉間にシワを寄せてギロリとにらみつけてきた。
「ひえっ!」
とっさにヨシオの足にしがみつく。大五郎は、そのままヘビににらまれたカエルのように固まった。
「おい、そいつはなんだ!」
スネークが指差したのは大五郎ではない。彼の人差し指が示しているのは、左舷のエレベーターに並ぶ二台の黒いトーイングカーである。
「あのクルマのことか?」
スネークを見たままヨシオが言った。彼らのトーイングカーには、それぞれ車体前面にフレアパターンの塗装が施こされている。
「そうだ。このチキンレースはオレたちの車でやるんだ。勝手なマネは許さねえ」
どうやらスネークが気に入らないのは大五郎ではなく、ヨシオたちのトーイングカーだったらしい。
やれやれ、おどかしやがって――安堵した大五郎は、ホッと胸をなでおろすのであった。
「でも、オレたちの車のほうが性能はいいぜ?」
ハリーが親指でトーイングカーを示しながら言った。
「このゲームの主催者はオレだ。オレのルールに従ってもらう」
用心深いスネークは、なかなかヨシオたちを信用しようとしない。
「者ども! クルマの準備をするんだ!」
スネークが号令をかけたときである。モヒカンのひとりが、なにやら慌てた様子で彼のほうへ駆け寄ってきた。モヒカンがスネークの耳元でささやきはじめると、ハリーはヨシオをチラリとみてうなずいた。順調に作戦が進んでいるということだろう。一方、スネークはアゴをさすりながら、疑わしい表情でモヒカンの話に耳をかたむけている。そして、彼の獲物を狙うライオンのような鋭い目は、じっとヨシオの顔をにらみつけていた。
モヒカンあたまはなにを話していたのだろうか。こんどはスネークがコバヤシとなにかを相談しはじめた。ふたりとも、ブリッジのそばにある自分たちのトーイングカーをチラチラと気にしながら話している。
「点火プラグを外してあるんだ。動くわけないさ」
大五郎の右に立ちながら、ハリーが小さくつぶやいた。彼はくちびるに葉巻をはさんだまま、カウボーイハットの鍔で顔を隠してほくそ笑んでいた。ヨシオはずっと大五郎の左で仁王立ちになり、無言で腕組みをしている。とても静かな表情だが、彼の冷たく光るメガネからは、なにやら殺気のようなものが感じられた。
やがて相談が終わると、スネークは鋭い眼のままヨシオたちのトーイングカーを指さした。
「おい、そのクルマは本当に速いんだろうな?」
「もちろんだ。おまえさんのクルマより速いぜ」
ハリーが眩しそうに目を細めながら答える。
「通常の五倍のスピードは出るはずだ」
そうつけ加えると、ハリーは「ふーっ」と紫煙を吐きだした。
「ハッタリじゃねえだろうな?」
スネークが探るような眼でハリーをにらみつけた。
すると、ヨシオがスネークを挑発するように嘲笑を浮かべて肩をゆらした。
「どうした。怖いのか?」
「なっ……!!」
スネークの鋭い眼が、にわかに血走った。
「キ、キサマぁ~……」
彼は拳をブルブルと震わせて顔をまっ赤に紅潮させながら、沸々と怒りをたぎらせている。それでもなお、ヨシオは腕組みをした格好で嘲笑を浮かべていた。スネークの赤い顔のうしろで、丸い黒縁メガネの男がじっとこちらをにらみつけている。コバヤシだ。彼は、スネークが最も信頼を寄せる腹心なのだ。ほかのモヒカンたちは、スネークから少し距離をとってブリッジのまえに控えている。彼らの手には、それぞれ鉄パイプや角材などの凶器がにぎられていた。
艦尾のほうにできた人だかりは、みんなヨシオたちを応援するギャラリーだった。彼らもスネークたちが怖いのだろう。みんなできるだけ遠くに離れて見守っているのであった。
「……面白しれぇ。見せてもらおうか。テメェらのクルマの性能とやらを!」
口のまわりにヒゲを蓄えた顔でスネークがすごんだ。
スネークたちのトーイングカーは動かなかった。もちろん、故障ではない。ゆうべ、ヨシオたちが細工したからだ。
「よし、ぼちぼちはじめようじゃねえか。おい、クルマをまわせ!」
相変わらずスネークは偉そうに仕切っている。ヨシオとハリーはエレベーターまで歩いて戻ると、トーイングカーに乗って引き返してきた。
「おーらい、おーらい!」
大五郎は彼らのトーイングカーを、さり気なく艦首のカタパルト射出位置に誘導した。舳先に向かって並ぶ、二本のカタパルトライン。右舷側のラインにヨシオ、そして、ハリーは左舷側のラインにそれぞれトーイングカーを駐車した。
カタパルトの射出位置から舳先までの距離は、およそ八十メートル。
「スタート地点は、ここでいいか?」
ハリーはトーイングカーを降りると、スネークに向かってそう尋ねた。
「それじゃ距離が短すぎる。もっと手前からだ」
「このクルマは、かなり無理な改造をしたんでな」
ハリーの傍らに立ちながらヨシオが腕組みをした。
「これ以上の距離は、おそらくエンジンがもたないだろう」
「たいりょくの、げんかい!!」
大五郎も腕組みをして叫んだ。
甲板の上には、まだ戦闘機などの残骸が散乱していた。それに、甲板にもダメージを受けている。ほとんど無傷の艦首以外は、デコボコしていてとてもまっすぐ走れそうになかった。
「まあ、いいだろう。そんなに早死にしてえんなら、好きにするがいい」
そう言うと、スネークは不敵な笑みを浮かべながら肩をゆらした。コバヤシもニタニタと気色悪い笑みを浮かべている。ほかのモヒカンたちも、マヌケ面でヘラヘラと笑っていた。
「笑ってないで、さっさと乗ったらどうなんだ?」
冷めた目でスネークを見ながらヨシオが言った。
「そう慌てるな」
スネークは傍らにコバヤシを呼びつけると、なにやら言い含めてから「行け」というようにアゴで指図した。
コバヤシがこちらを見てニタリと気色悪い笑みを浮かべる。
「レースをはじめるまえに、テメーらのクルマを調べさせてもらう!」
コバヤシがそう叫ぶと、ハリーは俄かに表情を曇らせた。彼は葉巻をくわえたまま足もとに目を落とすと、カウボーイハットの鍔を下に引っ張って顔を隠した。
「どうする、大将?」
横目でヨシオを見ながらハリーがささやく。
ハリーは、いささか動揺しているようだった。しかし、ヨシオはまだ冷静さを保っている。彼は、相変わらず堂々と仁王立ちになって腕組みをしているのであった。
「ついに彼の出番が来た、というわけか」
かすかにうつむくと、ヨシオは口もとで薄く笑った。
「彼?」
「うしろを見てみろ」
ハリーが妙な顔をしながら肩越しにチラリとうしろをふり向く。
「なっ……!」
ハリーの顔が恐怖に引きつる。
「い、いつのまに……?!」
いったい、ハリーはなにを見たのだろうか。大五郎も、恐る恐るハリーの視線の先をたどった。ゆっくりと、ゆっくりとトーイングカーをふり返る。
ゴゴゴゴゴゴ……
冷たい殺気を放つ謎の影。大五郎は、いったん動作を止めてゴクリとつばをのみ込んだ。
「なむさん!」
ふたたびハリーの視線を追いはじめる。ゆっくりと、ゆっくりと……。
ゴゴゴゴゴゴ……
視界のはしで、なにかが揺れている。白いなにかが、風に吹かれて揺れている。これは――。
ゴ……!
「いたっ!」
ついに、大五郎は「彼」を目撃してまうのだった!
肩まで伸びるまっ白な髪をなびかせながら、「彼」はこちらに背を向ける格好でトーイングカーのボンネットに立っていた。
「……勇気とは、怖さを知ること」
うしろ姿のまま「彼」が語りはじめる。
「――恐怖を我が物とすることじゃあッ!」
どこかで聞いたことのあるようなセリフを叫びながらふり返えると、「彼」は視線の先をビシッと杖で示しながらポーズをとるのであった。
「なまはげじゃあーっ!!」
鬼の形相で凄む「彼」を指さしながら大五郎は尻もちをついた。
「落ちつけ、ぼうず。じいさんだよ」
ハリーが「彼」をアゴで指しながら言った。
「え?」
大五郎は尻もちをついた格好のままボンネットを見上げた。
額から頭頂部にかけて禿げあがった白髪あたま。そして、胸元まで伸びる白く長いアゴひげ。よく見れば、ただの長老であった。
「やれやれだぜ」
大五郎はガッカリしたようにため息をつくと、掌を持ちあげて肩をすくめるのであった。
コバヤシの指示のもと、ふたりのモヒカンがトーイングカーを調べはじめた。大五郎たちは、右舷のカタパルトラインから少しはなれたところに立ちながら、彼らの様子をうかがっていた。
「抜け目のないやつらだぜ。くそっ」
ハリーが葉巻を足もとに落としてふみ消しながら舌打ちをした。長老は甲板に横になって腕枕をしながら、のんきに昼寝をしている。
大五郎は、ハリーのとなりに立っているヨシオの表情をうかがった。彼は、太陽を背にし、堂々と仁王立ちで腕組みをしている。いつものように、舳先の示す水平線を静かな表情でじっと見つめていた。
コバヤシは二台のトーイングカーの間に立ってモヒカンたちを指揮している。
「車体の下も調べるんだ」
コバヤシはモヒカンたちに指示を出すと、丸い黒縁メガネの奥からギョロリとヨシオの顔をにらみつけた。ヨシオの反応を見ているのだ。少しでもヨシオが動揺したり、おかしなそぶりを見せれば、この作戦は失敗するだろう。しかし、その心配はなかった。ヨシオはいつだって、なにが起きても他人事のように落ち着いているのだ。たぶん、この世にはもうヨシオを驚かせることなどなにもないのだろう。大五郎は、なんとなくそう思った。
「アニキ、これはなんですかね?」
コバヤシを呼んだのは、右舷側のトーイングカーを調べているモヒカンだ。
「どうした?」
コバヤシは車体のよこに立つと、もういちどヨシオの顔をにらみつけた。
だが、ヨシオの表情は動かない。彼は、堂々と仁王立ちになって腕組みをしているのであった。
「なにか、言うことはないか?」
ヨシオをにらんだままコバヤシが試すように訊く。
「オレを気にせず、つづけるんだ」
「ハッタリかましやがって」
見下すような態度で鼻を鳴らすと、コバヤシは車体の下にあたまを潜らせた。
「ローンチ・バーだな」
ヨシオがなにかつぶやいた。
「まずいな。あれを外されたら、もうカタパルトで射ち出すことはできなくなっちまう」
心配顔のハリーとは対照的に、ヨシオの表情は静かなままだ。
ヨシオが言ったローンチ・バーとは、艦載機の前脚部分に取りつけられている射出バーのことである。空母から発艦するときは、この部分をカタパルトのシャトルに接続させて射ち出すのだ。
「ようやくカタパルトも直ったってのに……なんてこった。ちくしょう」
「落ちつけ、ハリー。やつが見ている」
ヨシオはブリッジに背を向けているが、スネークの冷たい視線は感じているようだ。
トーイングカーを見たままヨシオがつづける。
「案ずるな。カタパルトに頼らずとも、なんとかなる。あのトーイングカーは、一定以上のスピードに達するとアクセルがもどらなくなるんだ。おまけにブレーキも作動しなくなる。つまり、ローンチ・バーを外したところで結果はおなじ、というわけだ」
「それはわかってるが、まだテストもしてないんだぜ? もし正常に作動しなかったらどうするんだ?」
「そうだな。そのときは、うしろからぶつけてムリヤリ海にたたき落としてみるか」
ヨシオが冗談めかして肩をゆらすと、ハリーは呆れた顔で首をふった。
ちょうどヨシオたちが話し終わると、コバヤシが車体の下から顔を出した。
「おい、こいつはなんだ?」
コバヤシがトーイングカーのよこをつま先で小突きながら言った。
「こいつとは、どれのことだ?」
ヨシオがとぼける。
「この前輪の間にある棒みてえなやつだよ。こりゃあ、いったいなんのためについてるんだ?」
コバヤシが言うと、大五郎のよこでとつぜんハリーが吹きだしながら笑いはじめた。
「ひょっとして、てめえの股の下にぶら下がってるやつのことを言ってるのかい?」
からかうような口調でハリーが言うと、甲板中からドッと笑い声が上がった。モヒカンたちも、みんなゲラゲラ笑っている。だが、ヨシオとスネークの表情は、相変わらず渋いままだ。
大五郎は、コバヤシのほうをチラリとふり向いた。彼の肩もふるえている。だが、コバヤシは笑っているのではない。丸い黒縁メガネの奥で血走しる三角の眼。彼は額に青筋を立てながら、メラメラと怒りの炎をたぎらせていた。
「静まれィ!!」
笑い声をかき消したのはスネークである。
「ごまかそうとしても無駄だ。さあ、答えてもらおうか」
スネークがギロリとヨシオをにらみつける。しかし、ヨシオはふり向かない。彼は舳先の示す水平線を、じっと見つめていた。
鋭い眼でヨシオの背中を捉えたままスネークがつづける。
「答えられねーんなら、そいつは外させてもらうぜ?」
すると、ヨシオは舳先に背を向けてスネークに向きなおった。
「ブレーキだ」
彼はメガネを白く輝かせながら答えた。
「なにィ? これがブレーキだと?」
コバヤシが胡散臭い顔で片方のマユを上げながら言った。
「そいつは緊急停止用のブレーキでな。エンジンに直接つながってるんだ。もし無理に外せば、エンジンが〝おシャカ〟になるだろう」
ヨシオはスネークに目を向けながらコバヤシに忠告した。
「カシラ。野郎はこう言ってやすが、どうしやす?」
コバヤシには答えず、スネークは腕組みをしながらじっとヨシオの顔をにらみつづける。殺気を宿した彼の眼は、鋭い刃物のように冷たく光っていた。しかし、ヨシオの様子は変わらない。マユひとつ動かすことなく、堂々と仁王立ちになって腕組みをしているのであった。
すると、スネークがとつぜん大きな声で笑いはじめた。
「なかなか肝が据わってやがる。気に入ったぜ」
スネークがコバヤシたちを呼びもどした。
「あとはオレがカタをつける。オメェらは下がっていろ」
「ですが、カシラ。いいんですかい? もし罠だったら……」
「バカヤロウ、ビビってんじゃねえ!」
弱気なコバヤシをスネークが叱りつけた。
「久しぶりに楽しいゲームになりそうなんだ。邪魔するんじゃねえ」
スネークがこちらに向かって歩き出した。
「いよいよか。血が騒ぐぜ」
緊張した面持ちでハリーが言った。
「ちがさわがしいぜ!」
大五郎も、ハリーのよこで身構えた。
ヨシオも舳先に背を向ける格好で仁王立ちになり、腕組みをしながらスネークを待ち受ける。長老は大五郎たちのうしろで控えている。右舷側のトーイングカーのそばに立ち、静かに出番が来るのを待っていた。
スネークがゆっくりと近づいてくる。まるで獲物を狙うライオンのような鋭い視線をヨシオに向けながら、近づいてくる。
「じいさん」
ヨシオは長老に背中を見せたまま合図した。
「御意」
小さくうなずき、長老は静かにトーイングカーからはなれてゆく。いったい、長老はなにをしようとしているのか。そして、ヨシオはなにをたくらんでいるのだろうか。
「来るぞ」
ハリーがゴクリとつばをのみ込んだ。いよいよレースがはじまる。はたして、ヨシオたちの作戦は成功するのだろうか。
ヨシオまで、あと数メートルというところでスネークが足を止めた。大五郎はそそくさとハリーのうしろに隠れると、彼の足の陰からそっと顔をのぞかせた。
「終わりだ。スネーク」
ヨシオがゆっくりとスネークを指差した。
「てめえは長く生きすぎた」
「ほざきやがれィ!」
スネークもヨシオを指差した。
「死ぬのはテメエのほうだ」
スネークがヨシオとにらみ合っている隙に、ハリーはそっとトーイングカーまで後退りした。おそらく、ローンチ・バーをシャトルにセットするのだろう。大五郎も、ハリーと一緒に後退りした。だが、まてよ、と大五郎は思った。スネークは舳先を向いた格好で立っている。いま動けば、確実に気づかれてしまう。いったい、ハリーはどうやってローンチ・バーをセットするのだろうか。
ハリーはトーイングカーのそばに立つと、ブリッジのほうにチラリと目をやった。どうやら、なにかの合図をまっているらしい。大五郎も、ブリッジのほうに目を向けた。すると、まもなく事件は起こった。
「あっ、テメエ!」
ズボンのポケットを抑えながらコバヤシがうしろをふり返った。
「このジジィ! よくもオレのマリファナを……!」
コバヤシのズボンからマリファナを抜き取ったのは長老である。
「マリファナ? タバコじゃないのか。ふん、どおりでマズいわけじゃ」
長老がコバヤシの顔に紫煙を吹きかけて挑発した。
「ヤ、ヤロウ、なめやがって!」
コバヤシは傍らのモヒカンから瓶ビールをひったくると、大きくふりかぶった。
「くたばれジジィ!!」
そして彼は、長老のあたまをめがけておもいっきりビール瓶をふりおろした。
「真剣白刃取り!!」
長老はコバヤシの攻撃を受けとめるため、あたまの上で両手をかまえた。
はたして、長老の運命やいかに?!
「……ぬかったわ」
長老が血まみれの顔で不敵に笑った。ハゲあたまから、噴水のように血が噴き出している。長老は見事にドリフのコントを再現してくれたのだ。
スネーク、そして甲板に集まっている全員が、このさわぎに注目していた。その隙に、ハリーは無事、ローンチ・バーをシャトルにセットすることができたようだ。
「つぎの一手で、ケリがつく」
ハリーが新しい葉巻に火を点けた。
「あとは〝発艦命令〟を待つだけだ」
パーキングブロックほどの大きさのシャトルは、まるで口を大きく開けた魚のような形をしている。しかし、車体下部のローンチ・バーに接続してあるので、外からは確認できなかった。もちろん、どちらにスネークが乗り込んでもいいように、二台ともシャトルにつないであった。無論、射ち出すのはスネークが乗るトーイングカーだけである。
「好きなほうに乗れ」
ヨシオはスネークが先にトーイングカーに乗るよう促した。彼を警戒させないためである。
「おなじことだ。テメエが死ぬことには変わりねえんだからな」
スネークはそう言うと、左舷側のトーイングカーに向かって歩きはじめた。同時に、ヨシオも右舷側のトーイングカーに向かい、乗り込んだ。
「今日は、絶好の海水浴日和だぜ」
トーイングカーのシートにケツを押し込みながらスネークがつづける。
「心行くまで、たっぷりと楽しんでこい」
スネークが運転席で腕組みをするヨシオの顔を見ながらニタリと笑った。
「こんな日は、ビーチで日光浴にかぎる」
ヨシオが舳先に視線を向けたままスネークに返す。
「おまえが泳いでこい」
ハリーがヨシオのトーイングカーにやってきて、運転席のよこに回り込んだ。
「それじゃ、オレは管制室でスタンバイしている」
ハリーが運転席のヨシオにこっそりと耳打ちをして親指を立てた。それから彼は、左舷に集まるギャラリーの中にまぎれ、こっそりと左舷のタラップを降りていった。ハリーは統合カタパルト管制室に向かったのだ。カタパルトラインの間、ちょうど艦首中央に管制室が見える。およそ二メートル四方の半地下になっているドーム型の構造物で、甲板にでている部分は、だいたい大人のひざ下ぐらいの高さしかない。天井部分以外はガラス張りになっていて、外側に扉はなく、艦内からしか入ることはできないのだ。そして、ふだん使用しないときは甲板の下に収納されていた。大五郎も、管制室にはよく遊びにいくのでよく知っていた。
トーイングカーの運転席は、車体の左側にあった。大五郎はヨシオのトーイングカーの右側に立ちながら、レースがはじまるのを待っていた。
「シートベルトを締めろ」
ヨシオがスネークに促した。もちろん、ヨシオも自分の腰にシートベルトをまわしている。しかし、スネークは鼻で笑い飛ばして拒否しやがった。
「そんなもんは必要ねえ」
だが、ヨシオは言う。
「臆病風に吹かれて逃げだされると困るんでな。いちおう締めてもらおうか」
ヨシオはそう言うと、スネークを横目で見ながら薄く笑った。
すると、スネークはハンドルに手をかけたまま肩をゆらして笑いはじめた。
「面白れぇ。いいだろう」
スネークは、まんまとヨシオの口車に乗せられるのであった。
トーイングカーにフロントガラスやドアなどはない。もちろん、助手席もない。そして運転席はむき出しになっており、シートの背もたれも腰の少し上ぐらいまでしかない。言ってみれば、遊園地にあるゴーカートのようなものだ。ちなみに、シートベルトはヨシオたちが改造して取りつけたものである。
「さて、準備はよろしいかな?」
長老が血まみれの顔でヨシオのトーイングカーにやってきた。どうやら、スタートの合図をだすのは長老らしい。大五郎はヒマなので、長老と一緒に合図をだすことにした。
ヨシオがメガネの奥から統合カタパルト管制室をうかがった。大五郎も、スネークに背中を向ける格好でチラリとうかがう。数メートル先のカタパルトラインの間。管制室の青みがかったウィンドウガラスの中に、ぼんやりとカウボーイハットの影が見える。この青いガラスは透明度が低いので、ちかくまで行かないと中の様子はほとんど見えないのだ。
「じいさん。合図をたのむ」
ヨシオが腕組みを解いてハンドルを握った。
「スタンバイ!」
長老は彼らのトーイングカーの間に立って掛け声を上げた。
「すたんばい!」
大五郎も長老のよこで叫んだ。
長老が大五郎にうなずき、スネークのほうを向いてスタンバイする。大五郎も長老と背中合わせに立ってヨシオのほうを向き、スタンバイした。トーイングカーのエンジンが激しく唸る。大五郎は長老と動きを合わせて周囲を指差しながら安全を確めた。後部甲板、左舷、右舷、そして、トーイングカーの周辺も異常はない。大五郎は、最後にブリッジのほうを指さした。上半分が吹きとんだブリッジのまえで、コバヤシたちが冷笑を浮かべている。どうやら、みんなハリーが管制室にいることに気がついていないようだ。
「レディ……」
長老が左足をよこに伸ばすようにして姿勢を低くし、左手を腰のうしろに回して待機した。顔は血まみれのままである。そして、大五郎も長老とは逆の右手を腰のうしろに回して待機した。そのまま長老の合図をまつ。つぎに長老が合図したとき、もう片方の手を舳先に向かって水平に上げたとき、すべての工程が完了する。そして、それを合図にハリーがカタパルトの射出ボタンを押すのだ。これは、カタパルトオフィサーが戦闘機を発艦させるときに行う動作なのである。
「少しスピードが出すぎるんでな。あまり強くアクセルを踏み込まないことだ」
舳先を見たままヨシオが言うと、スネークもまえを向いたまま鼻で笑った。
「テメエのほうこそ、ブレーキを踏み外すなよ」
青空にひびき渡るエンジンの咆哮。
「グッドラック!!」
長老の右腕が舳先を示す。
「ぐっどらっく!!」
大五郎も張りきって舳先を示す。
その瞬間だった。
「――ホントだ速ぇエェぇェー?!」
スネークが運転席でのけ反りながら絶叫した。彼を乗せたトーイングカーは、まっ白な蒸気の煙を引きながら、すさまじいスピードで遠ざかってゆく。舳先を目指し、どんどん遠ざかってゆく。一方、ヨシオのトーイングカーは動いていなかった。彼は腕組みをしながら、運転席に座ったままスネークを見送っていた。
「あっ、目にゴミが! 目が痛てェ!」
スネークが掌で顔を覆いながら悲鳴を上げている。
「あぁァ~、目が……目がァ!」
「カシラ、あぶねェッ!!」
ブリッジのまえからコバヤシが叫んだ。その瞬間、スネークのトーイングカーが甲板を飛びだした。
「目がぁァぁァ~!!」
甲板に悲鳴だけをのこし、スネークは空高く飛んでゆくのでした。
「ばるす!」
大五郎は飛び上がってよろこんだ。
大きく弧を描いて白い尾を引きながら、スネークのトーイングカーが海の上に落ちてゆく。滑走時間は、わずか二秒弱。あっという間の出来事だった。
スネークが走り去ったあとのカタパルトラインからは、まだ白い煙が立ちのぼっている。そしてコバヤシたちは、ただ呆然とブリッジのまえに立ち尽くしていた。
スネークを見送ると、ヨシオはトーイングカーから降りて仁王立ちになり、静かに水平線をにらみつけた。
「外道の最期は、こんなものだ」
ひとり言のようにヨシオがつぶやいた。
そろそろハリーが管制室から戻ってくるころだ。そう思って大五郎が左舷に目をやると、タラップの下からカウボーイハットがひょっこり現れるのであった。
「あっ、おじちゃんがかえってきた!」
ハリーが葉巻をプカプカとふかしながら、ゆっくりと歩いてくる。
「ヘイ、大将。うまくいったな」
ハリーは疲れた顔で笑いながらヨシオに言った。
「ああ。優秀な管制官のおかげで、な」
腕組みをした格好でヨシオが答える。
「カタパルトの圧力をフルパワーにセットしたんだ。奴さん、小便をちびるヒマもなかったろうぜ」
ハリーはヨシオの肩にポンと手を置き、まぶしそうに目を細めてサムズアップをした。ヨシオもメガネを白く光らせながら、口もとでフッ、と笑った。
はたして、このふたりは仲が良いのか悪いのか。大五郎には、よくわからないのであった。
「英雄じゃ」
長老が小さくつぶやいた。
「英雄じゃ」
天に杖を掲げながら、もういちどつぶやく。
「英雄じゃ……英雄じゃ!」
徐々に声を大きくしながら、長老は繰り返し唱えつづけた。
「英雄だ!」
ギャラリーたちからも声が上がりはじめる。
「英雄だ! 英雄だ!」
みんなでトーイングカーを囲むように輪をつくり、ヨシオを称える。青空には、いつまでもヨシオコールが轟いていた。
「ハリー」
ヨシオがハリーにうなずき、合図する。
「全員、左舷舷側に整列!!」
ハリーが大声で指示をだすと、みんなは歓喜の声を上げながら左舷に殺到した。海を正面にして立つ格好で、横一列に並ぶ。列の先頭、空母の舳先にはヨシオが立った。
「あっ、カシラ!」
ギャラリーの中に交じってコバヤシが海に叫んだ。
大五郎も、ヨシオとハリーの間に立ちながら海を見やった。海面に突きだしたあたまが、波に揺られて流されている。スネークだ。彼は、必死に両手をふり回して波をかきわけている。しかし、どう見ても泳いでいるようには見えない。
「お~い! 助けてくれー!」
海面を叩きながらスネークが叫んでいる。やはり、彼は溺れていたのだ。
「おっ、オレは〝カナヅチ〟なんだーっっ!!」
すると、ヨシオは傍らのハリーにうなずき、最後の指示を出した。
「帽ふれ!!」
みんなに号令をかけると、ハリーはカウボーイハットを頭上で大きくふりはじめた。そのよこで長老も杖を大きくふっている。みんなも、スネークに向かって帽子や手拭いをふりながら見送っている。なにも持っていない者は、両手を大きくふって見送っていた。大五郎も、ハリーのとなりで大きく手をふりながらスネークを見送った。
――そのときである!
「きた!!」
大五郎は叫んだ。スネークの背後に迫る三角形の黒い背ビレを指差しながら。
※ばるす・・・・・古より伝わる滅びの呪文。

水平線が明るくなってきた。また、新しい朝がやって来る。大五郎は空母の舳先でヒザをかかえながら、朝陽が顔を出すのをまっていた。ヨシオも一緒である。彼は、相変わらずカタパルトオフィサーのヘルメットを被り、おなじくカタパルトオフィサーのイエロージャケットを羽織っていた。そして、いつものように腕組みをして仁王立ちになり、じっと水平線の向こうを見つめているのであった。
「でてきた!!」
大五郎は立ち上がって水平線を指差した。
夜が地球の裏側へ帰ると、海はキラキラと輝きながら目を覚ました。そして、空も明るく太陽にあいさつをするのであった。
「おはようございます!!」
大五郎も元気よく大声で太陽にあいさつをした。
「――ああ、おはよう」
「え!?」
大五郎は、おどろいて顔を上げた。いまのはヨシオの声ではない。まさか、本当に太陽が返事をしたのだろうか。それとも、ただの幻聴だったのか。大五郎が不思議そうに太陽を見ていると、背中のほうから足音がちかづいてきた。
「あっ」
ふり向くと、黒いマントの男が立っていた。右のマユから左の頬にかけて流れる三日月形の大きな傷跡。羽佐間九郎である。
「ブラックジョークせんせー!」
「おいおい、その呼び方はかんべんしてくれ」
九郎が居心地わるそうに笑った。九郎はブラックジョークと呼ばれる世界的に有名なヤブ医者なのだ。しかも、九郎は医師免許を持っていないという。挙句の果てに、目玉が飛び出るほど高額な治療費を請求するのである。しかし、無免許の医者に高額な治療費を払う患者などいるはずもなく、彼の収入は正規の医師よりも少なかったという。
九郎がヨシオのとなりに立った。
「今日も、いい天気になりそうだな」
そう言ってヨシオをジロリとにらんだ。しかし、ヨシオは答えない。だまって腕組みをしながら、朝陽でメガネを輝かせていた。
朝陽に目を向けながら九郎がつづける。
「いま我々が洋上で見ているこの朝陽を、この蒼い砂漠の向こうで見ている人間がいるかもしれない。だが、はたしてどれだけの人間が生き残っているのか。おまえさんが見ている水平線の向こうにあるのは、楽園ではなく地獄かもしれないな」
皮肉を言って苦笑すると、九郎はマントをなびかせながヨシオの傍らをはなれていった。
結局、ヨシオはひと言もしゃべらなかった。
九郎の背中を見送ると、大五郎は舳先の示す水平線に向きなおった。はたして、あの水平線の向こう側はどうなっているのか。九郎の言うように、核の炎で焼き尽くされ、なにも残っていないのだろうか。この地球上で生き残っているのは、自分たちだけなのだろうか。母さんや父さんは、もう……。
朝陽に目を細めながら、大五郎は歯を食いしばった。そんなはずはない。母さんや父さんは、きっとどこかで生きているにちがいない。いまこの瞬間、あの水平線の向こう側で、この朝陽を見ているにちがいない。大五郎は、白ばみはじめた空に父と母の面影を浮かべた。まだ、世界は終わっていないんだ。かならず、あの水平線の向こう側にたどり着いてみせる。生き残って、おまえよりも輝いてみせる。大五郎は、心の中で太陽に誓った。
「おじさん、あさごはん!!」
大五郎は気を取りなおしてヨシオに笑顔を向けた。ヨシオは返事をしない。ヨシオは太陽に背を向けると、無言のまま左舷のタラップへ足を進めた。大五郎も、だまってヨシオのうしろをついていった。
「あっ」
大五郎は慌てて足を止めた。ヨシオが急に立ち止まったからだ。
「楽園など、この世には存在しない」
太陽をふり返り、ヨシオがつぶやいた。
「たとえあったとしても、人が住めば、たちまち地獄に変わるだろう」
ヨシオがなにを言っているのか、大五郎にはわからなかった。だが、めずらしくまともなことを言っているのかもしれない。大五郎は、なんとなくそう思うのであった。
朝食を済ませると、大五郎はヨシオとふたりで甲板へ上がった。舳先の示す水平線の上で、太陽が白く輝いている。ヨシオはだまったまま、舳先のほうへ向かって歩きはじめた。日差しがあったかいね、と言おうとしたが、大五郎は言葉をのんだ。彼はきっと返事をしないだろう。大五郎は、ヨシオの背中を見ながらこっそりとため息をついた。
舳先に立つと、ヨシオは腕組みをして仁王立ちになった。いつものポーズである。大五郎も、ヨシオのよこでおなじ格好をした。
「まぶしい!」
太陽がまぶしい。あたりまえである。生まれたときから、ずっと変わらず輝きつづけているのだ。月だって、生まれたときからずっと夜空を照らしつづけている。地球も、生まれたときからずっとまわりつづけている。それがあたりまえのように。
大五郎は、ふと思った。人間にとってのあたりまえとは、いったいなんなのだろうか。朝起きて、朝食を摂って、仕事に行って、昼食を摂って、仕事から戻って、夕食を済ませて、それから風呂に入って寝る……。でも、これではあまりにもつまらない人生である。夢のかけらもありはしない。しかし、それがあたりまえなのかもしれない。
大五郎は、ちらりとヨシオの顔を見上げた。この男は、いったいどんな人生を歩んできたのだろうか。ヨシオが自分の過去を語ったことはいちどもない。彼の過去を知るものは、だれもいないのだ。しかし、大五郎は思うのである。彼にとってのあたりまえは、きっと普通の人のあたりまえとはちがうのだろう、と。
「あと三日」
黒いマントをなびかせながら九郎がやってきた。
「あと三日で食糧が底をつくらしい」
ヨシオのとなりに九郎が立った。ヨシオは水平線に目を向けたまま、だまっている。
九郎が朝陽に目を細めながらつづける。
「水も……飲料水も、不足している。せめて雨でも降ってくれればいいんだが……」
白いシャツに黒いベスト。スラックスも黒い。そして、九郎はいつも黒いマントを羽織っていた。
「人は、いつかは死ぬものだ」
ふいにヨシオが語りはじめた。九郎は目を伏せている。ヨシオの話を最後まで聞こうとしているのだろうか。水平線に目を向けたまま、ヨシオがつづける。
「むかし、ある友人が重い病気で入院してな。オペは成功したが、予後不良で根治が見込めない、と言われた。だが、そんな友人に対し、医者は延命治療を施すことを決定した」
腕を組んだまま、ヨシオが天を仰いだ。
九郎はだまって目を伏せている。黒いマントが、潮風でバサバサとなびいていた。
「死ぬとわかっている人間を、なぜ生かそうとする?」
ヨシオが九郎のよこ顔に問いかける。
「無駄だとわかっているのに、なぜ助けようとする? 医者とは、いったいなんなのだ?」
ヨシオは九郎のよこ顔をじっとにらんだまま、彼が答えるのをまっていた。
「五体満足で健康なのに、つまらないことで自ら命を絶つやつもいる」
水平線に浮かぶ太陽に目を向けながら、九郎が静かに語りはじめた。
「だがな。病気になって、しかも余命いくばくもないとわかると、大抵の人間は必死に生きようとするもんだぜ? 自分には、まだやり残したことがある。恋人、そして家族と、もう少し一緒に過ごしていたい、ってな」
ヨシオも太陽をにらみながら、じっと九郎の話を聞いている。
「生きる理由は、それだけでいい。むずかしく考える必要はないのさ」
九郎も氷のような冷たい瞳で太陽を見つめていた。感情が凪いだような、しかし、どこか寂しそうな冷たい瞳。そういえば、ヨシオもおなじような瞳だった。このふたりは似た者同士なのかもしれない。大五郎は、なんとなくそう思った。
「あんたも、むかし死にかけたんだってな」
朝陽でメガネを白く輝かせながらヨシオが言う。
「いっそのこと、死んで楽になりたいとは思わなかったのか?」
「死んだほうがマシだ。たしかにそう思ったこともある。じつは、いまでもときどき死にたくなることがある。急患の依頼で休暇が中断されたり、手術料を踏み倒されたときとかにね」
冗談めかして笑う九郎のよこ顔を、ヨシオは腕組みをしたままジロリとにらんだ。
ヨシオによこ顔を見せながら九郎がつづける。
「だれだって一度や二度ぐらい、死にたいと思うときはあるものさ」
九郎は目を伏せたまま静かに口もとでほほ笑んでいた。そのよこで、ヨシオは腕組みをしながら太陽をじっとにらみつけていた。
大五郎は甲板の上にひざを抱えて座りながらふたりの話を聞いていた。もっとも、むずかしい話なので大五郎にはよくわからなかった。
カラン……
ブリッジのほうで人の気配がした。ふり向くと、三人の若者がブリッジの近くにある大型のヘリコプターの中へ入っていくのが見えた。三人とも若い男である。ヘリコプターは風防が割れている程度で、ほかに目立つ破損個所は無いように見えた。しかし、エンジンや電気系統が故障しているので動かなかった。
ミサイルの直撃を受けて上半分が吹き飛んだブリッジの側面には、艦番が白くペイントされている。ほとんど消えかかっているが、数字で「88」と大きく記されてあった。そして、ブリッジのちかくにある一機の戦闘機に、大五郎は以前から興味をひかれていた。この戦闘機の尾翼には、まるで燃え上がる炎のようにまっ赤な鬣をもった白い一角獣がマーキングされているのだ。とてもきれいな絵である。しかし、なぜか人を寄せつけないオーラのようなものを感じる不思議な絵なのだ。でも、いちどでいいからこの一角獣が自由に大空を飛んでいる姿を見てみたかった、と大五郎は思った。
ふたりの話は、まだつづいている。内容はむずかしくてよくわからないが、大五郎はとりあえず最後まで聞くことにした。
「ところで、おまえさんの友人とやらは、その後どうなったのかね?」
朝陽に目を細めながら九郎が訊ねる。
「死んだよ。オレが……殺したんだ」
「殺した?」
九郎が冷たい瞳でヨシオをふり向く。ヨシオは水平線を見つめたまま、腕組みをしながらつづける。
「あいつの主治医は、最後まで安楽死に反対していた。だから、オレが殺したんだ。その道のプロを雇って」
「その道のプロ?」
「ドクター・キコリの名は、あんたも知っているだろう?」
「ドクター・キコリだと!?」
その名を聞いた途端、九郎の顔色がにわかに変わった。
ドクター・キコリのうわさは大五郎も聞いたことがある。枯れてもいない丈夫な木を切る樵の如く、助かる見込みのある患者を平気で安楽死させてしまう、死神のような医者なのだ。
「やつに頼んだのさ。あいつを楽にしてやってくれ、と」
「ばかなことを。私なら救えたかもしれないというのに……」
ため息混じりに九郎があたまをふった。
「べつにあんたが気にすることはないさ」
静かな口調でヨシオがつづける。
「オレは、あいつを苦痛から解放してやったんだ。あいつも、きっとあの世で感謝してるにちがいないさ」
「――きさま!」
いきなり九郎がヨシオの胸ぐらにつかみかかった。
「いったい、なに様のつもりだ。思い上がるんじゃない!」
九郎は陽の光をよこ顔に受けながら、殺気の宿った冷たい瞳でヨシオをにらみつけた。
しかし、ヨシオの表情は変わらない。相手の眼を、ただじっと見ているだけだった。
「せんせー、おちつけ!」
大五郎は九郎のマントを掴んで引っ張った。
九郎がヨシオをにらんだまま手をはなす。
「医者は神ではない。私にも治せない病気はある。救えなかった命もある。だが、私はつねに全力を尽くしてきた。おまえさんのように、簡単にあきらめたりはしなかった」
ふたりの真剣な眼がにらみ合っている。だが、あいかわらずヨシオは冷めた表情のままだった。
しばし無言でにらみ合うと、ヨシオはメガネを押し上げて太陽に向きなおった。
「……生と死は表裏一体。この世に生を受けた瞬間から、すでに死は約束されている。だれも……死神からは逃げられないのさ」
死神なら、もうここに来ているだろう。そう思いながら、大五郎は九郎の顔を見上げていた。
「まだ三日ある。私はあきらめない」
さわさわと潮風が吹きぬけ、九郎のマントがふわりとなびく。
「かならず逃げきってみせる。かならず」
しばし太陽をにらみつけると、九郎はマントを翻して左舷のタラップのほうへ歩きはじめた。そのとき、ヘリコプターがとつぜん爆発し、まっ赤な炎に包まれた。
ヘリコプターから立ち上る黒煙が、大きなドクロのかたちになっている。
「おしおきだべー!!」
大五郎は、あの三人がヘリコプターの中にいることを九郎におしえてやった。
「なんてこった」
九郎は黒いマントをなびかせながら、まっすぐに黒煙が立ちのぼるヘリコプターのほうへ駆けだした。ヨシオはヘリコプターに背を向ける格好で、肩越しに立ちのぼる黒煙を見上げている。関心がないのか肝が据わっているのか、相変わらず無表情である。大五郎は、とりあえず九郎のあとを追い駆けだした。
はたして、三人の若者たちは無事なのであろうか。
黒煙を上げて燃え上がるヘリコプターのそばで九郎が片ひざをついた。大五郎は、そっと九郎の背中越しにのぞき込んでみた。男がひとり、うつぶせに倒れている。そのすぐちかくには、もうひとり仰向けに倒れていた。
「こいつはひどい」
ひとりは虫の息、もうひとりは左足に火傷を伴う複雑骨折。重傷だが、まだ間に合う。九郎はそう言った。それからヘリコプターの中をチラリとて「あの男は手遅れだ」と、ため息混じりに首をふった。大五郎もヘリコプターの中をのぞこうとしたが「おまえさんは見ないほうがいい」と、漆黒のマントで視界を遮られた。
まわりが徐々に騒がしくなってきた。ふと大五郎が顔を上げると、いつの間にか大勢の野次馬たちがまわりを囲んでいた。
「重症のふたりだけオペ室へ運ぶんだ。急げ!」
九郎が野次馬たちに指示を出した。
「助かるのか?」
いつの間にか大五郎の傍らにヨシオが立っていた。
九郎がゆっくりと立ち上がる。
「ひとりは虫の息、むずかしいだろう」
燃え上がるヘリコプターの炎に目を細めながら九郎がつづける。
「だが、もうひとりのほうは助かる。かならず助けてみせる」
そう言うと、九郎は迷いのないまっすぐな眼をヨシオに向けた。
ヨシオは九郎の視線を避けるように顔を背ける。
「あんたは……まだ、商売をつづけるつもりなのか?」
「私は医者だ。たとえ世界がどう変わろうとも、私は変わらない」
九郎は目を逸らさない。ヨシオは腕組みをしながら立ちのぼる炎をじっと見つめている。
「……もし、助けられなかったら?」
試すようにヨシオが訊くと、九郎も炎に向きなおった。
「そのときは医者をやめるさ。二度とメスは握らん」
「たいした自信だな」
「賭けるか? もし助かった場合は、おまえさんが手術料を払うんだ」
「たとえ手術が成功したとしても、おなじことだ。三日以内に救助が来なければ、オレたちは死神に追いつかれるんだからな」
ヨシオが言うと、九郎は顔を伏せて肩をゆらした。
「なにがおかしい?」
口もとに嘲笑を浮かべる九郎のよこ顔を、ヨシオがジロリとにらみつけた。
「死神が怖いか?」
顔を伏せたまま九郎が言う。ヨシオはなにも答えず炎に視線を戻した。
「まだ生きている。まだ、希望はある。私も、おまえさんも、まだ死んじゃいない」
九郎はマントを翻しながらヨシオに背を向けると、左舷のタラップのほうへ二、三歩進んで立ち止まった。そして肩越しにヨシオをふり向く。
「それとも、こんどは自分で安楽死を試してみるかね?」
ヨシオのマユがピクリと動いた。そしてみじかい沈黙のあと、ヨシオは静かに口を開いた。
「手術料は……いくらだ?」
「七千万だ。命の値段にしちゃあ、安いもんだろう?」
そう言って静かに笑うと、九郎はマントをなびかせながら左舷のタラップを降りていった。
ヨシオは腕組みをしたまま、ジッと炎に視線を注いでいた。
虫の息だった若者は、やはり手遅れだったようだ。患者はひとり。オペがはじまって、まもなく三時間がたつ。
大五郎はヨシオと一緒に手術室の外でまっていた。ヨシオは手術室の入り口のよこで腕組みをしながらカベに寄りかかっている。大五郎も、ヨシオのとなりでひざをかかえていた。
はたして、若者のオペは無事に成功するのだろうか。
「終わった」
九郎が手術室のドアから出てきた。
「助かったのか?」
足もとに目を落としたままヨシオが訊いた。
「もちろんだ。私が失敗するはずないだろう」
九郎は血で汚れた青いサージカルガウンを脱いで丸めると、通路のカベ際にあるベンチの上に放り投げた。
若者は助かった。左足は修復不可能なので切断し、手遅れになったもうひとりの足をもらい、つなげたようだ。爆発の原因もわかった。どうやら手榴弾の安全ピンを、うっかり抜てしまったらしい。
大五郎は、ヨシオと一緒に手術室のドアを入った。部屋の奥にあるベッドの上に、まるでミイラ男のような姿の若者がよこになっていた。
「せ……先生」
若者が苦しそうにかすれた声をしぼり出した。手術は終わったばかりである。まだしゃべるのもつらそうだ。
「どうした」
ベッドのほうに向かいながら九郎が返事をした。
「先、生……た、助けてくれたのは、あ、ありがたいんですが……そのう……」
あたまだけ起こすと、若者は足のほうに目を向けた。
「あっ!」
大五郎は思わず声を上げた。
「ちっちゃいあしと、おっきいあし!」
つないだ左足が右足よりも長く、そして大きかった。
「こ、これじゃあ、み、右と左で……く、靴のサイズが、合いません」
若者は、いまにも泣き出しそうな声で九郎に訴えた。
九郎はそんな若者を無視するように背を向けると、淡々とした足取りでデスクに向かった。
「なるほど。それでブラックジョークと呼ばれているのか」
皮肉を言ってヨシオが笑った。九郎は、こちらに背を向ける格好でデスクの上のカルテにペンを走らせている。さっきとは、まるでちがう反応だ。他人の命に対しては、怒ったり、悲しんだり、喜んだりもできる。だが、自分のことになると、たとえ口汚く罵られてもまったく気にしたりはしないのだ。ヨシオといい、九郎といい、このふたりがなにを考えているのか。大五郎にはさっぱりわからなかった。
「オペは失敗、だな」
ドアに向かいながらヨシオがつぶやいた。
「――だが、命は助った」
九郎の言葉にヨシオが足を止めた。約束は足を治すことではない。若者の命を助けることだ。賭けは、九郎の勝ちである。
「たしか、七千万だったな」
九郎に背を向けたままヨシオが訊いた。
「そうだ」
キャスター付きのオフィスチェアから立ち上がると、九郎はヨシオに向きなおってこうつづけた。
「ただし、円ではなくドルで、だ」
冷たい瞳で九郎が薄く笑う。ヨシオは肩越しにふり向き、相手の顔をジロリとにらみつけた。
七千万ドル。日本円に換算すると、いったいどれぐらいの金額になるのか。大五郎には想像もつかなかった。
しばし九郎をにらみつけると、ヨシオはドアに向かって歩きはじめた。九郎は呼び止めようとしない。ただじっとヨシオの背中を見つめているだけだ。ヨシオが部屋を一歩出る。そして廊下でふと立ち止まった。
「命の値段、か」
背中を見せたままヨシオがつぶやく。
「まあ、いいだろう。陸に上がったら、請求書を送ってくれ」
そしてヨシオはふり向くことなく、静かに去ってゆくのであった。
ヨシオの背中を見送ると、九郎はオフィスチェアに腰をおろしてデスクに向かった。
「それを聞きたかった」
やわらかい声で九郎がつぶやく。カルテにペンを走らせながら、九郎は穏やかな顔でほほ笑んでいた。大五郎も、廊下を遠ざかってゆくヨシオの足音を聞きながら、嬉しそうにほほ笑むのであった。
ちかくを通りかかった軍の輸送船に大五郎たちが救助されたのは、その翌日のことだった。だが、輸送船が空母を発見したのは、たんなる偶然ではないのだという。
輸送船の艦長はこう語った。
ちょうど任務を終えて帰還する途中のことだった。われわれのまえに、とつぜん大きなクジラが一頭現れて、潮を噴きながら海面をぐるぐると泳ぎはじめたのだ。最初はただ遊んでいるだけだと思っていたのだが、どうもちがうらしい。われわれがクジラをよけて目的地へ向かおうとすると、船の進路を塞ぐように立ちはだかって、動こうとしないのだ。いったい、このクジラはなにをしようとしているのか。不思議に思いながらもしばらく観察していると、私はあることに気がついた。このクジラは、ひょっとしてわれわれをどこかへ案内しようとしているのではないか、と。私は自分の勘を信じ、そのクジラのあとについていくことにした。
クジラは背中を海面に出しながら、われわれを先導するように泳ぎつづけた。夜になっても、休むことなく泳ぎつづけた。そしてわれわれも、夜通し船を走らせた。星空に輝く満月が夜の闇を照らし、キラキラと光る静かな海を、一頭の大きなクジラが泳いでいる。船乗りになって三十余年。夜の海は見慣れているが、こんな幻想的で神秘的な光景は見たことがない。まるでおとぎ話の世界を旅しているようだ、と私は思った。
やがて夜が明け、水平線が白みはじめたときだった。さっきまで目のまえを泳いでいたクジラの姿が、いつのまにか消えていた。はたして、あのクジラは幻だったのだろうか。私は、なんだかキツネにでもつままれたような気分になった。そして、そんなふうに考える自分に、思わず笑ってしまった。陸の上ならともかく、ここは太平洋のド真ん中だ。いくらキツネやタヌキでも、クジラにまでは化けられないだろう。しかし、仮に化かされたのだとしても、あまり悪い気分はしなかった。むしろ感謝したいぐらいだった。あの不思議な夜の出来事は、おそらく一生忘れることはないだろう。私はクジラの消えた海を、しばしジッと見つめていた。
空はすっかり明るくなり、水平線の上には太陽が顔を出していた。いつまでもぼんやりしているわけにもいかないので、気を取りなおして引き返そうと思ったそのとき、私は太陽の中に小さな黒い影がひとつ浮かんでいるのに気がついた。もしや、あのクジラだろうか。私は掌で陽の光をさえぎり、黒い影に目を凝らした。そして、その影がクジラではないことは、すぐにわかった。あれは船だ。それも、かなり大きな船のようだ。そのとき、伝令の声が私の耳に入ってきた。その船は、どうやらわが軍の空母らしいという監視員からの報告だった。それを聞いた瞬間、私は確信した。あの空母だ。数週間まえに横須賀港を出たまま行方不明になっていた、あの空母にちがいない。きっと、あのクジラは空母を助けるために、われわれをこの海域まで導いてきたのだろう、と。
そして艦長は、最後にこうつけ加えた。
――ひょっとしたら、あのクジラは海神の化身……トリトンだったのかもしれない――
そして大五郎も思った。そのクジラは、きっと〝あのトリトン〟にちがいない、と。
(ありがとう、トリトン!!)
大五郎は胸の中で叫んだ。さよなら、トリトン。またどこかで会おう。この広い太平洋のどこかで、いつかまた……。
救助作業は順調に進められ、昼過ぎには全員の移乗が完了した。最後に空母をはなれたのは羽佐間九郎だった。彼は全員が救助された後も空母に残り、しばしヨシオとふたりきりで話し込んでいた。そして、輸送船に乗り込んだのは、九郎だけだった。
――オレは〝こいつ〟と旅をつづける。自分の運命を見極めるために――
そう言ってヨシオは独り、空母に残ったのだった。
空母が夕陽の中へと消えてゆく。小さな黒い影となって、まっ赤な夕陽の中へと消えてゆく。
「おじさん、さようならーっ!!」
大五郎は叫んだ。輸送船の甲板から、ちからいっぱい叫んだ。
三週間、あの空母で海の上を彷徨った。一日一日が、とても長かった。とても不安だった。この空母から早く逃げ出したいと思っていた。そして、ようやくあの空母から脱出できた。なのに、あの空母が慕わしくてたまらないのだ。あの空母に帰りたくてたまらないのだ。もういちど、ヨシオと一緒に夕陽を見たい。あの空母の舳先に立って、夕陽に叫びたい。なぜそんなふうに思うのか。どうして涙が止まらないのか。大五郎には、自分の気持ちが理解できなかった。
「おじさん、さようならーっ!!」
空母が見えなくなっても、大五郎は叫びつづけた。水平線の向こうに向かって、ちからいっぱい叫びつづけた。
夕陽が紅く燃えている。まっ赤な血のように。空と海を朱に染めて……。

―― 完 ――
太平洋、血に染めて 【劇場版】
*エンディング
https://www.youtube.com/watch?v=ejjv3o484xs
https://www.nicovideo.jp/watch/sm140656(予備)
【映像特典】
https://www.youtube.com/watch?v=1HmGi9pPzho
https://www.youtube.com/watch?v=2Ml5QLXn0f8
https://www.youtube.com/watch?v=e-V0dKwyu6E
太平洋、血に染めて 【劇場版】
野良猫
©NORANEKO 2017
2017年2月6日 第一刷発行
発行者――野良猫
発行所――株式会社 ガット・エランテ
野良県クジラ市マグロ町一丁目2番22号 〒222-2222
電話 出版部 5656-22-××××(ゴロゴロ・ニャーニャー)
販売部 5625-22-××××(ゴロニャーゴ・ニャーニャー)
業務部 2020-22-××××(ニャオニャオ・ニャーニャー)
デザイン――ストレイ・キャット
本文データ制作――ガット・エランテ プリプレス制作部
印刷――珍獣印刷株式会社
製本――珍獣印刷株式会社
printed in japan


