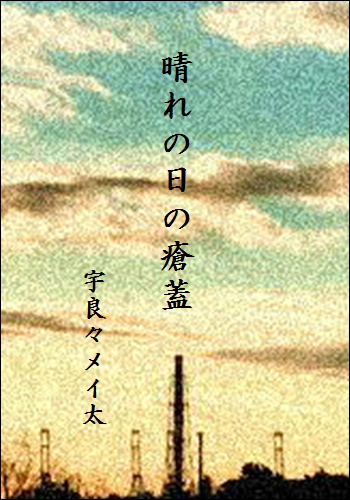
晴れの日の瘡蓋【第七話】
七、春
1
順風満帆。
それが高校入学までの私の人生だった。
サクラのおかげで受験も無事終わり、夢の高校生活が始まった。
憧れの制服。サクラと同じ制服。
これから楽しい青春時代の幕開け。そう思うだけでトキメキが止まらなかった。
高校生になったサクラは急に大人になった。中身は今まで通りだったけど、顔つきや身体つきがぐっと大人っぽくなった。それは制服のせいかも知れない。
彼女は誰が見ても美人だと言える。
変な話だけど、私は彼女にときめいていた。
彼女に対して憧れている。
多分それはあの時、観音さまを見た時の衝動に近かいものだったと思う。
私も彼女のようになりたいと思った。
いや、彼女になりたいと思った。
同じ制服を着て同じ学校へ行く。
その夢が叶った。
高校生活は本当に夢のようだった。一瞬にして過ぎ去った幻。
ようやく失くしたパズルのピースを見つけたような思いだった。
入学してすぐに私はクラスの全員と仲良くなった。担任の先生も良い人だったし、授業にも難なくついて行けた。
そして何よりサクラにも毎日会える。これはもうワクワクが止まらない。
入学してすぐ私は迷わずサクラのいるグラフィックデザイン研究会に入った。会員は私を入れて五人。そのうち一人はニィだった。ニィは生徒会に所属していたのでほとんど顔を出さなかったけど、ほかの会員は毎日ほぼ同じ時間に集まって、完全下校時間までくだらない話をして過ごしていた。
この名ばかりの研究会でもサクラは一人真面目にパソコンに向かって作業をしていた。
何かに打ち込む彼女は輝いている。この事に気付いたのは高校に入ってからだった。
そんな楽しい学園生活が三か月目に突入する頃、悔しくも私はおじいちゃんの書斎で一人悪夢にうなされていた。
自分が火炙りにされて泣き叫んでいるところで目が覚め、またウトウトすると同じような夢が繰り返される。
母親が持ってきたリンゴジュースは飲み干した途端に全部もどしてしまった。
こんな日に限って希は友達を連れてくる。隣の部屋で馬鹿騒ぎする。
母親に「お姉ちゃんが熱出して寝てるから静かにしてあげて」と注意されても、最初だけ大人しくしててもすぐに騒ぎ出す。本当にバカは困る。
とにかくこのバカどもから逃げたかった。
とりあえず母親に必死に訴えて、おじいちゃんの書斎に布団を敷いてもらい、肩を抱かれながら何とか安息の地に辿り着いた。
私がこんな目に合うハメになったのは、もう一人のバカのせいだ。
寝込む前の日、私は真木瀬と居残りをしていた。
二人とも課外授業のレポートを期日通りに提出しなかったのが居残りの原因だった。
この時、真木瀬はずっと嫌な咳をしていた。
「何?風邪?」
「あー、そうかもしれない・・・」
「ちょっと、うつさないでよ。」
「いや、お前だったら大丈夫だろ。」
「何でよ。」
「バカは風邪引かないって言うじゃん。」
「はあ?つうか、その言葉ウソじゃん。あんた普通に風邪ひいてるし。」
「じゃあ、俺はバカじゃなかったつう事じゃん。」
「じゃあ、バカだけに感染するタイプなんじゃない・・の・・・?・・ハクシュン!」
「・・・バカだけに感染するタイプだったみたいだな。」
「嫌な奴・・・ハ・・・クション!」
バカからバカ風邪をもらって私もバカになってしまった。
熱が三十九度あった。久し振りに熱を出した。
同じクラスだった真木瀬とは何かと一緒になる事が多かった。
まあ、クラスの男子の中では一番話しやすいヤツだったと思う。
真木瀬は末っ子で、希みたいな育ち方をしていた。だから彼と接すことに何ら違和感はなかった。学校にも弟がいるような感覚だった。
真木瀬との関係を周りから勘違いされることもあった。
ヤツはよく遅刻する。そんな時は必ずクラスの子に「今日、真の彼氏どうしたの?」なんて言われて迷惑を被った。しかも毎回お決まりのように。
病みあがり、学校へ行くと早々に最悪な事が待ち構えていた。
「真木瀬君と笹之辺さんは出来るだけ速やかにレポートを提出出来るように、お互い協力して下さいね。」
先生が優しく言った。だけど彼女の目は少しも笑っていなかった。
まるでクラスの問題児を見るかのような目をしていた。
クラスでグループを作って、テーマに沿ってディスカッションすると言う授業だった。
テーマは「社会的影響」だったと思う。
そのグループ決めの時に私と真木瀬は休んでしまい、勝手に私たちは組まされてしまった。
多分、これは意図されたものだったに違いない。
クラスのみんなは絶対ニヤケ顔で私と真木瀬を一緒のグループにしたに違いなかった。
悪意を感じた。
放課後、私は真木瀬とファストフード店でテーマについて話し合った。
二時間が過ぎてもお互い何も出て来なかった。二人ともとっくの昔に飽きてしまっていた。
「笹之辺さあ、何か無いの?」
「何にも出て来ない。真木瀬の方は?本当に何もないの?」
「無い。」
「じゃあ、どうすんの?」
「そんなの俺に聞くなよ。」
「・・・そもそもウチらだけじゃ無理じゃない?」
「・・・だよなあ。」
「ちょっと、聞いてみるか。」
私はニィに電話した。
留守電になったので彼は諦めた。
次にサクラに掛けてみると彼女はすぐに応答した。
「もしもし?サクラ?レポートのテーマ決まらない。助けて。」
「(テーマ?どんな?)」
「テーマ何だっけ?」
「社会的影響だよ。」
「そうそう、社会的影響。」
「(社会的影響?うーん、そのテーマなら何でもいいんじゃない?自分たちの身近なものから発展して行けばいいと思うよ。)」
「身近なもので社会に影響与えるものか。なんだろう・・・」
「(私が思うのは美術とか、広告とか、テレビとかかな。)」
「美術、広告、テレビかあ。なるほど!」
「じゃあ、新聞とかどうだろう?」
「新聞?」
「そう、俺中学の時、新聞部だったし。」
「・・・・・・・真木瀬。」
「は?」
「お前それ早く言えよ。」
「何が?」
「新聞部!」
「何で?」
「そんなにいいネタがあって、何で気付かないんだよ!」
あいつはいつもこんな調子だった。本当にどこか抜けていた。
ある程度話をまとめて私たちは店を出た。生暖かい空気が私たちを包む。
空は重々しい灰色の雲で覆われていた。急がないと雨が降る。
真木瀬も同じことを思っていたんだろう。空を見上げた後歩く速度を速めた。私も彼の歩幅に合わせて速歩きした。
彼のスピードがだんだん速くなって行く。私は真木瀬の背中を追った。
置いていかれそうになる私に気付いたようで、彼は歩くスピードを緩めた。
二人並んで歩く。少しだけ心が通い合ったように感じた。
今思えばこんなのが楽しかったんだと思う。何だか凄く普通な感じがした。
このまま本当に真木瀬との関係が進展して行けば面白いかもしれないなんて心のどこかで思っていたんだろう。
あの子を想うよりよっぽど普通な事だ。
家に着いた瞬間に雨が降り出した。私は駆け足で階段を上がり自分の部屋に入ると制服のまま机に向かった。
とにかくレポートを作るための資料を集めなければならない。真木瀬は多分何も考えてないだろう。私が率先しないと何も出来ない。
ネットで調べたり、古新聞を広げて見たりしたものの、素材となるものは見つからなかった。何をどうしたらよいのか私自身まるで解っていなかったのだ。頭がパンクしそうになった。
焦りでイライラがピークに達しそうになった時、真木瀬から電話が入った。
「横浜?」
「そう。」
「何で?」
「取材だよ。」
「取材?」
「横浜に新聞の博物館があるんだけど、そこへ行けば何か見つかるかも。」
「それって取材じゃなくて見学じゃないの?」
「どっちだって良いよ。とにかく行動あるのみだよ。とりあえず今度の日曜に行くから予定空けといて。」
そう言うとヤツは私の都合も聞かずに切った。
二人で行くことには少しばかり抵抗があった。どこか真木瀬のことを意識しすぎていたきらいがあった。考えすぎだった。
二人より三人の方が良い。その方がうまく行くだろうし、何よりも楽しそう。
私はサクラを誘った。
彼女は快く了承してくれた。
強い雨が降りそそぐ。
不意に私は窓の外を見た。
まるでシャワーのような雨だった。
灯りのないおじいちゃんの家の方を見てみると、庭の方でビニール傘をさした人が佇んでいた。
その人が父親であることは背格好でわかった。
「何してんだろう。」
傘なんてもう役に立たないくらいヒドい雨だ。
五分ほど経ってから何もなかったかのように振り返り我が家に入った。
父は不思議な人だ。何考えてるのかよくわからない。
彼と親子らしい会話をしたことがあっただろうか?
あまり覚えてない。
多分今まで褒められることも怒られることもなかった。・・・と思う。
毒にも薬にもならない人畜無害無味無臭な人だ。
おじいちゃんとは何もかもが正反対だった。
真木瀬からの誘いで意欲がすっかり失せてしまった。
根拠は無かったけど、とりあえず彼に任せていれば何とかなりそうな気がしていた。
時刻は十一時半、人生は成るように成る。果報は寝て待てである。
2
トイレに行こうと一階へ降りた所で父親と鉢合わせた。
「・・・オカエリナサイ。」
私の心無いアイサツに「タダイマ」と彼もまた心無いアイサツで返して来た。
「さっき外で何やってたの?」
「いや、昨日猫が軒下で死んでたんだよ。とりあえず衛生課に電話して遺体を引き取ってもらったんだけど、今日見てみたらね、この子がいたんだ。」
そう言うと父親は抱えていたバスタオルからびしょ濡れになった子猫を出して見せた。
「さっきまで泣いていたんだけど、疲れたのか、お腹が空いたのか、急に大人しくなったよ。元気になればいいんだけど。」
「そうなんだ。・・・死んじゃったのはこの子のお母さんだったのかな?」
「多分な。」
「先生この子どうするの?」
「・・・さて、どうするかな。とりあえず、辛い思いをした分は取り返さなきゃな。」
そう言うと彼は子猫の身体を拭いてあげながら居間に入って行った。
こんなことが前にもあった気がする。
でも、良く覚えていない。
その時も心が通じ合っていないやりとりをしたのだろうか。
3
多分、父と私は歯車が合っていないんだろう。
ムリヤリ合わせようとすると、それが余計にカラ回りしていった。
中学の入学式の日のことを思い出す。
「あ、制服まだ脱いじゃダメよ。」
母親が言った。
「えー、何で?窮屈なんだけど。」
「お父さんがもうちょっとで帰って来るから待っててあげて。」
「どうして?」
「写真撮りたいんだって。」
「写真?さっき学校で散々撮ったからもういいよ。」
「何言ってんの。お父さん楽しみにしてるのよ。」
「えー、制服なんて先生見慣れてるんじゃないの?」
「娘の晴姿なんだから。たまにはお父さんの言うこと聞いてあげてよ。」
「めんどくさいなあ。」
「そんなこと言わないで。」
私は写真が嫌いだ。撮るのも撮られるのも。
「・・・あとね、おじいちゃん。」
「え?」
「おじいちゃんにも制服姿見せてあげたら?」
「・・・・・・・」
「・・・おじいちゃんね、このところ真のこと気にしてたよ。真の制服姿、おじいちゃんに見せてあげたらきっと大喜びするよ。」
「・・・うん、そうだね。見せてくるよ。」
「そうしてあげてね。真の中学校入学を誰よりも喜んでくれてるんだから。」
母親は安心したような笑顔をしていた。
「あと真、お父さんのこと先生って呼ばないでね。」
父が帰って来る前に、サクラが訪ねて来た。案の定サクラの手にはしっかりデジカメが握られていた。
まるでアイドルにでもなったような気分だった。
ちっとも嬉しくなかった。みんな私の魂を吸い取るつもりなんだろう。
中学校の制服はもっさりしてて、どうにも好きになれない。しかも全然身体に合っていなかった。
サクラにも散々写真を撮られた。どうして着ているものが違うだけでこうもみんなテンションが上がるのか私には理解出来なかった。
玄関の外へ出た時、不意におじいちゃんの書斎のある二階を見た。
おじいちゃんは部屋の中から窓越しにこちらの様子を窺っていた。おじいちゃんと目が合うと、彼は少しだけ笑みを浮かべた。
私はすぐに目をそらした。
父の帰宅。私はすっかり心身ともに疲れ切っていた。
そんなのもお構いなしに父はおじいちゃんの家の庭で無心にシャッターを押し続けた。
そういえば父親のこんな姿を今まで見たことがなかった。
私はてっきり娘には興味がないのだと思い込んでいた。
それとも何か裏があるのか。何だか言い表せないような気色悪さでいっぱいになった。
父は一度も笑う事なくシャッターを押し続けている。
何か変な感じだ。これが父の愛情表現であるならば、ヘタクソすぎるにもほどがある。
終始私も笑うことなく写真に収まった。
私も彼同様、こういうことはヘタクソなんだ。
ようやく撮影会が終わって部屋で普段着に着替え終えた時、おじいちゃんに会いに行くことを思い出した。
「まあ、明日の朝にでも行けばいいか。」
慣れないことで疲れ切っていた私は、とりあえずその日あったことが夢か幻であることを願いつつベットに倒れ込んだ。
そこから記憶がない。
多分眠ってしまったのだろう。
次の日おじいちゃんのところには行ったのかな。
全然覚えてない。
行っている事を願うばかりだ。
4
「真、入ってもいいか?」
突然、父が部屋のドアを開けた。
「ちょっと、もう入ってんじゃん!ノックしてよ!」
「すまん。」
「何?」
「ちょっと頼みがある。」
「え?何?」
「実はくるみ屋珈琲の来海がバイク事故起こして入院したんだ。さっき見舞いに行ってきて、まあ、本人は至って元気なんだけど、両脚の骨折っちゃってて、当分店に出られないらしいんだよ。来海が帰ってくるまででいいから、その・・・真にアルバイト頼めないかって言われちゃってね。どうかな?お父さんの親友を助けると思って引き受けてくれないか?」
生まれて初めて父から頼みごとをされた。
「でも、先生的に大丈夫なの?アルバイト。うちの学校はアルバイト禁止なんだけど。」
「お父さんの教え子にご両親がお店をやってる子がいてね。その子は忙しい時に店を手伝って小遣を貰ってる。手伝いであれば大丈夫だと思うよ。もしバレても父親の知り合いの手伝いをしてるって言えばいいよ。」
「学校の先生がそんなこと言っていいの?」
「親友からの頼みなんだ。今回は特別だ。なあ、頼むよ。」
現役の高校教師が校則違反行為を推奨して良いのか。友情はルールをも超越してしまうのだろうか。
まあ、その気持ちは解らなくもなかった。
またマスターからの直々の頼みということもあったので私はその話を引き受けることにした。
父は「ありがとう。頼むな。」と言うと、何かを思い出したように突然変な事を言い出した。
「真。」
「何?」
「お前、お母さんの高校時代の姿に似て来たな。」
「はあ?何言ってんの?超気持ち悪いんだけど。」
「・・・すまん。」
一体何を考えているんだろう。本当に気色悪かった。
父と喫茶店「くるみ屋珈琲」のマスター、来海さんは幼稚園時代からの幼馴染だった。
父にとって家族同然なのだろう。私もマスターとは仲がいい。子供の頃から本当に良くしてくれた。
「くるみ屋珈琲」にはおじいちゃんと一緒によく行ったものだ。
私はお店のミートソースが大好きで、休みの日におじいちゃんにせがんで連れて行ってもらった。
マスターは必ずプリンに生クリームをたっぷりかけたデザートをサービスしてくれた。それも私のお気に入りだった。
剣道の帰り道、店の前を通りかかると「マコちゃん、お腹すいたろ?おやつ食べて行かないか?」と必ず声をかけてくれる。私もマスターからのお誘いを期待してワザと店の前を通っていた。
町のオアシス「くるみ屋珈琲」は町で一番古い喫茶店だ。今のマスターは三代目。輸入食品会社の社長だったおじいさんが趣味で始めたとのことだ。
娘さん、つまりマスターの叔母さんが日系ブラジル人の実業家の所へ嫁いだという縁があって、ブラジルのコーヒー豆農家と親しくなり、現地で買い付けをして行くうちに、コーヒーの奥深い味わいにすっかり魅了されてしまったようだ。そこで本場のコーヒーの味を町の人たちに知ってもらうために会社の一階を改築して「喫茶店くるみ屋珈琲」をオープンした。
お父さんが社長を務めていた時に輸入食品会社の業績が振るわなくなったのを機に、会社を畳んで喫茶店の方に本腰を入れたという。
「この町の移り変わりを温かく見守って来たこの店が、いつまでも町の人たちの憩いの場所、町のオアシスであって欲しい。」
マスターは初めて来るお客さんにいつもこう言った話をしていた。
子供の頃から何度も何度も聞かされていたので、内容をすっかり覚えてしまった。
生まれて初めてのバイトが来海さんのお店で本当にラッキーだと思った。
これには父に感謝せずにはいられなかった。
晴れの日の瘡蓋【第七話】


