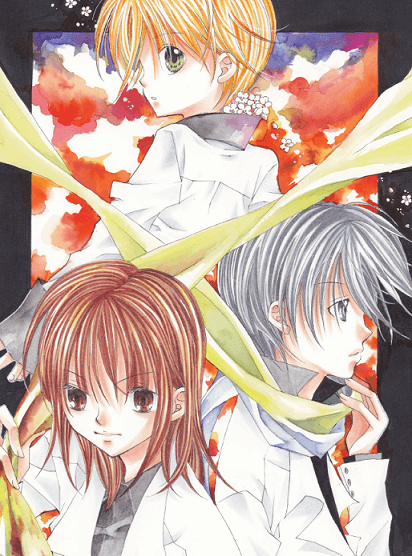
カリアの綱
目が覚めると、そこは百五十年後の世界だった。

薄ぼんやりと、灰色の壁が見える。
無機質な、冷たそうな色。
それが天井だとわかるまで、数十秒を要した。
どうやら、私は今、目が覚めたところらしい。
夢を見た覚えはない。頭が鈍って働こうとしない。
どうして、私は、眠っていた……?
とにかく、頭が働くまでじっとしていようと考える。
遠くから、靴音が聞こえた。
私は動けなかった。
動こうという気も起こらない。今の重い体では、きっと指先一本も動かない。
私の視界に、誰かの顔が映った。さっきの靴音の主だろう。
少年のようだ。
幼さの残る顔……。十六歳くらいだろうか。
私はその顔を観察した。
グレーの髪。髪よりも色素の薄い瞳。唇は淡く赤い。表情は、無表情。
彼は何を考えて、私を見ているのだろう……。
何だか、……眠い。
瞼が重い。
機械音がした。何かが、開いている。
「おはよう」
少年が喋った。
「ごきげんいかが? カリア」
カリア……、
『雁亜』?
「また眠るのは勝手だけど、少し寝すぎじゃないかな? 君が眠ってから、百五十年経つんだよ」
ひゃくごじゅうねん……? それって、どのくらいだっけ……。
いつの間にか閉じていた目を開ける。少年は微笑んでいた。
「起きられる?」
「……たぶん」
答えたのは私だ。これが自分の声かと、少し驚いた。低い声だった。
私は、ゆっくりと体を動かした。両手で上半身を持ち上げる。一度は失敗して倒れそうになったが、少年が受け止めてくれた。二度目には成功して、私は何とか起き上がれた。
部屋の全景が目に映った。
天井と壁は全てグレーのコンクリート。かなり広い場所で、左右を見渡すと先が見えないほどだ。横に広いようだ。右斜め前には階段がある。それから、少し離れた正面の壁にはデジタルで時計が表示されている。百五十年五日三分五秒、と。どんどん時は刻まれ、秒数が増えていく。
「僕のことを覚えている?」
私は首を振った。初対面だと思っている。
「そう……。眠っている間に、記憶が弱ったのかな。たぶん、じきに思い出すよ。僕も昨日はそうだったから」
少年は、「立てる?」と訊いた。
「君が支えてくれるなら、立つことは出来そうだ」
そう答えると、少年は私に手を差し出した。私はそれを取り、よろけながらも二本足で立ち上がった。
私は、カプセルの中に入っていたようだ。本当に薬のカプセルみたいな形だ。同時に、さっきの機械音を思い出す。あれはカプセルの上部に付いているガラスの蓋を開ける音だった。私は、ガラス越しに天井を見ていたのだ。
(蓋を開ける、音……)
ふっと、既知感を覚えた。
この場所には、数十ものカプセルがある。私は端から三つ目のカプセルに入っていた。あとは、コンピューターや機械が立ち並んでいる。その機械が何をするためのものか、私にはよくわかった。今すぐにでも操作できる。
(何故、そんなことがわかるんだろう……)
少年は私の手を引き、階段の前まで連れて行った。
「すぐ外に出る? みんな、お待ちかねだよ。雁亜が目覚めるのが一番遅かった。僕も、さっき起きたばかりなんだけどね」
「外…には、何がある?」
「本当に覚えてないんだね」少年は少し困り顔になる。「自分の名前もわからない?」
「雁亜。さっき君がそう呼んでいた」
「そう、雁亜。君は学者だ。専門は生物やら細菌やら、幅広い」
「わからない……。そうだったような気もする」
まだ、頭がぼんやりする。何もわからない。
「君は私の知り合い?」
「そうだよ」少年は答えた。「名前を、ユカといいます」
「私は君を何と呼んでいた?」
「ユカ」
「じゃあ、ユカと呼ぼう。私の記憶が戻るまで、いくつか質問すると思うけど、構わない?」
「もちろん。僕は君の助手だから」
ユカは柔らかく微笑んだ。
ここに居てもどうしようもないので、外に出ることにした。階段は長く、急だった。しかも光がないので、ユカが持ってきた懐中電灯で先を照らして歩いている。
階段がなくなると、その先には何もなかった。ユカは頭の上を示す。見ると、マンホールのような入り口がくっついていた。どうやら、ここから外に出るらしい。私はもう疲れきっていた。彼が言うには百五十年眠っていて、体もなまっていたようだ。
「待っててね、今開けるから」
「ここは地下?」
「そう。地中深くに造られた場所だよ。君はよく知ってるはずだけど」
ユカはマンホールに付いているハンドルのようなものを回す。それが八回を数えたとき、「開いたよ」と私に言った。
これで、外に出られるようだ。私は何故だか緊張してきた。さっきの薄暗い場所が地下なら、外はどんなところなんだろう……。私はそれも知っているんだろうか。
ユカはマンホールの蓋を押し上げる。
何本かの光が差し込んだ。それは本数を増し、あっという間に私の視界を真っ白に変えた。眩しすぎて目が開けられない。
「雁亜。大丈夫?」
「……目が慣れるまで、もう少し待ってくれないか」
「わかってるよ」
すぐ傍のユカの声。私は、ゆっくりと目を開けた。視界はぼんやり白いけれど、だんだんと形を成してきた。マンホールの下に梯子がある。そこを上り、マンホールから外に出るようだ。光は私の居る暗闇を照らし、今まで上ってきた階段もやはり灰色だったと知る。
ユカが先に梯子を上り、私を見る。まだ少し眩しい視界を引きずり、私は梯子を上った。
マンホールの外は、壮観だった。
まず最初に風が吹いて、それが私の目を塞いだ。通り過ぎて目を開けると、だだっ広い荒野だった。地面には砂が溜まり、遠くに傾いたビルが見える。他には、何もない。空が高くて手が届かない。雲が空を覆い、太陽を隠している。この風景も、何だか灰色な感じがした。
マンホールから外に出ると、ユカはすぐ蓋を閉めた。
「砂が入っちゃうんだ。地下には精密な機械があるから困りもんだよ」
私はユカの肩を借り、立ち上がる。ユカと私はそんなに身長は変わらないが、少しだけユカの方が高かった。
風が吹いて、少しだけ肌寒い。私は裸足だったので、足の裏で直に砂を感じた。右を向いても左を向いても、同じ景色。遠くにビルがあって、ここには何もない。褐色の砂があるばかり。それが風に舞って、視界を塞いでいる。
「集落に行こうか」と、ユカが言った。「みんな雁亜を待ってるよ」
「みんな、私のことを知っているの?」
「もちろん。君はすごく有名なんだよ」
ユカは当然と言わんばかりに笑った。
「私の記憶がなくても大丈夫?」
「調子を合わせておけば問題ない。きっとすぐ思い出すよ。案外、みんなに会ったら思い出すかもね」
ユカは私の手を引いて歩き出した。方向はわからない。砂で視界が遮られていると思えないほど、ユカの足取りはしっかりしていた。
――好きなものを一つだけ、持っていくことを許可しよう。
私の足取りが止まり、ユカが振り向いた。
「どうしたの?」
何か聞こえた。
外からではなく、私の内から。
「何でもない」
私は首を振った。ユカはまた歩き出す。
さっき聞こえた声を、思い出す。
あれは、紛れもない。
私の声だった……。
*
「好きなものを一つだけ、持っていくことを許可しよう」
そう言うと、皆、それぞれ違ったものを持ってきた。私が許可したのは、それくらいの自由はあってもいいと思ったからだった。
五十三人の人々は、五十三通りの荷物をカプセルに詰める。カプセルに入らないような大きなものを持ってきた者は、居なかった。
私は、何も持っていかなかった。未来にまで託したいと思うものは、一つもなかった。自分が残るだけで十分だ。
目覚めたいとも、思わない。このまま死んだって文句はない。
カプセルが棺桶になったって、別に構わなかった。
*
どれだけ歩いたという距離感はない。周りの景色が一定なので、概算することもできない。感覚的に測るしかないが、私は寝起きで、その感覚も怪しかった。
時間を持て余すのも嫌なので、私はユカに質問をした。
「ここは何処?」
「僕らがかつて住んでいた国だよ。百五十年前は、こんなじゃなかった。ここは都会だったんだよ。高層ビルが立ち並んで、空気が澱んでいて……。今では想像できないけど」
「何故、こんなに寂れてしまった?」
「人が居なくなったからだよ。流行り病とでも言うかな、人類は絶滅したんだ」
「でも私たちは人類だ」
「そうだね。絶滅というには語弊がある。僕たち以外の人類は居なくなったんだよ」
私は考え込んだ。何がなんだか、さっぱりわからないのだ。
「あっち」
と、ユカは左側を指差した。
「あそこには、雁亜の研究所があったんだよ」
小さく、建物が見える。だがそれが自分の研究所だとはとても思えなかった。
風が強く、砂が舞う。私の髪も、風に踊っている。それで気付いた。私の髪は、少しだけ長い。肩よりも二センチくらい下で、少し邪魔だった。
私はユカを見た。彼は、ショートより少し長めの髪で、それでもずいぶんすっきりしていた。色はグレー。また灰色だ、と私は思った。
ユカについてしばらく歩く。彼は唐突に足を止めた。
「ほら、着いたよ。あれが集落」
そこは、少しなだらかな下り坂になった、窪んだ土地だった。その窪みにテントが張られている。いくつくらいあるだろうか……、三十は確実にある。それも全てが黄色いテント。そこだけが異空間みたいになっている。
集落には、人もたくさん居た。テントの周りをうろついていたり、土を掘り返していたり――
「坂になってるから気をつけてね」
ユカは坂を下りていった。私もユカに付いて行く。
集落が近付くにつれ、色んな音が耳に入ってきた。話し声、土を掘る音、足音。それから、匂い。ちょうど食事時なのかもしれない、食べ物の匂いがする。
数人の人が、私とユカに気付いた。彼らは私を見て一様に驚き、ぽかんと口を開けている。歩いていた者も、話していた者たちも動作を止めて。一体私は、彼らの中でどういう存在なんだろう?
「雁亜博士」
と、誰かが言った。
「お目覚めになられた!」
「雁亜博士が目覚めた!」
一瞬にして、凄い騒ぎになった。
止まっていた人たちは走り出し、テント中に私の覚醒を伝えに向かう。人々は私とユカの周りに集まり、感激して泣く。
私は何もできず、立ち竦んだ。そうしているうちに、人だかりは増していく。最終的には、ここにいる全ての人が私を囲んだようだった。彼らは泣いているか、感激して何も言えないでいるかどちらかだった。
「ご無事で……何よりです」
「いやあ、心配しました。もしかして博士は目覚めないんじゃないかって」
「ユカ博士と雁亜博士が居なかったら、やっていけませんからね」
という言葉がちらほら聞こえた。
「みんな、雁亜が帰ってきて嬉しいんだよ」
ユカが私に囁いた。
私は人だかりを見回してみた。見知った顔は一つもない。
「世界はこんなになってしまいましたけど」
「私たちはこれから、生き延びねばなりません」
「最後の人類ですからね」
ユカも言っていた。人類は、私たち以外絶滅したと。
何故、絶滅した?
何故私たちは残った?
ここは何処なんだ?
「あの、雁亜を休ませてもらえませんか? まだ目覚めたばかりなんです」
ユカが言うと、人々はハッとした。
「気付きませんでした。申し訳ありません」
「雁亜博士、こちらへどうぞ。テントしかございませんが……。今、建物を探索して、使えるものを調べておりますので」
案内してくれる人について、私は歩いた。後ろの人々の視線を感じながら。ユカも私に付いてきた。
一番端のテントに案内された。「ごゆっくりどうぞ」と、案内人は頭を下げ、行ってしまった。
「まだ、思い出せない?」
「全く」
私は肩を竦めた。それでも、記憶がないということは、私をそれほど困らせなかった。いずれ思い出すかもしれない。それにこの状況では、あってもなくても同じことのような気がする。
「しばらくはここで暮らすんだ。今、引越し先を探してるから、見付かるまで。といっても、雁亜の記憶が戻ったら、こんな説明必要なくなるけど」
テントの中には、毛布や衣類、乾燥させた食料、小さな机、その他諸々日常品が装備されている。生活に困ることはないだろう。
「お腹すいてる?」
私は自分の腹部を確認する。
「特には。食べようと思えば食べられるくらい」
「それだったら、食べた方が良い。百五十年ぶりのご飯になるよ」
百五十年。そんなにも、私は眠っていたのだろうか。
食事を持ってくる、と言って、ユカはテントから出て行った。
私はテントを見渡す。色は黄色で、非常用といった感じだ。少し狭い。五歩歩いて端に着くくらい。
机の上に鏡が乗っていた。それに近付いて、自分の顔を映してみる。大してがっかりもしなかったし、驚くこともなかった。私の髪は薄い茶色で、目は焦げ茶。髪の長さは想像していた通りで、顔はほっそりしている。年齢は十代後半、十五~十八といったところ。そして、無表情。見方によってはとても眠そうな顔だ。
自分の頬に手を当てる。鏡に手が映った。自分の顔だという感じは特にないが、そうでないとも言い切れない。
「お待たせ」
両手にトレイを持って、ユカが現れた。
「シチューだから食べやすいと思うけど」
ユカはトレイを下に置く。トレイには、スプーンと、茶色のシチューがあった。湯気をたてている。少し食欲が湧いた。
「鏡を見てたの?」
「そう」私はスプーンを手に取る。「私は、女性だったんだ」
「うん。わからなかった?」
ユカもスプーンを手に取り、食べ始める。
シチューの香りは嗅覚を刺激する。私はスプーンでシチューをすくい、口に運んだ。かなり熱くて吐き出しそうになる。二口目は冷ましてから食べた。ほんのり甘くて濃厚な味。どろっとした重みが舌に乗る。
「美味しい?」
「あまり」私は正直に答える。「味はいいのに、この食感が気に食わない」
ユカは私を見て、にこりと笑った。
「やっぱり雁亜だね。眠る前も同じこと言ってたよ」
そうして、嬉しそうにシチューをすくう。
目の前の少年は、私の知らない私を知っている。一体どれだけ、私のことを知っているのだろう。
「雁亜。僕のことは?」
手を止めて、低い声でユカが訊いた。
「僕のことは、どう思う?」
「別に、何とも……」
まだ会ったばかりじゃないかと喉まで出かかったが、押しとどめた。ユカと私は初対面ではないらしいからだ。
代わりに、
「私は君を思い出せない。君を見ていても何の感情も浮かばない」
と言っておいた。
ユカは、そうだろうね、と吐き出す息と一緒に言った。
「たぶん、それが本音だよ。僕は嫌われても好かれてもいなかったんだね……」
その表情が少し寂しそうで、何だか悪いことをした気がした。
それからは、何も話さなかった。シチューは食べれないほど口に合わないわけじゃなく、食べていると、だんだんと頭が冴えてきた。補給した栄養で、頭が働き出したようだ。周りの景色がはっきり映る。ユカの輪郭も、髪の一本一本までよく見えた。
食べ終わったのは、二人ともほぼ同時だった。ユカは満足げな顔で、二人分の皿を手に持った。
「これ、置いてくる」
「私が持っていこうか?」
「雁亜が出て行ったら大騒ぎになるよ」
あとでこの辺りを案内する、と言って、ユカはまたテントから出て行った。
ユカ、それに集落の人々……
ここには何人の人間がいるのだろう。
ここ以外では、人間は絶滅したと、ユカは言った。一体、どうして? 人間とは、地球上に溢れていたんじゃなかったか?
そういう一般的な知識や言語はわかるのに、自分のこととなるとさっぱりだった。『カリア』は『雁亜』と書くだろう、ということは、ぼんやりとわかるけど。
ふと目線をやると、テントの入り口に子供がいた。
年齢は五歳くらい。髪は、私より明るい、金に近い色。目は深緑だ。期待と緊張が入り混じった瞳で私をじっと見ている。少年か少女かは、よくわからなかった。少年にしては女性的な可愛らしい顔をしているし、少女というには少し髪が短すぎ、ボーイッシュな服装だ。
「集落の子供?」
尋ねると、子供はびくっと身体を硬直させ、小動物みたいに縮こまった。だが、私を見る視線は外さない。
「中に入らないのか?」
違うことを尋ねてみる。
「入っても……良いの?」
高くて細い声だった。おずおずと、子供は訊き返す。
「私は構わない。君が入りたければ入ればいい」
ようやく、子供は少し笑った。それから、テントに一歩を踏み入れた。
「そこに座るといい」
さっきユカが座っていた場所だ。子供は申し訳なさそうに、でも嬉しそうに腰を下ろした。
私と子供は向き合う形になった。
子供は何も話さなかった。ただ、テントを眺める。それから、私に目をやる。
「名前は?」
「スグリ。さんずいに州って書く州に、食べ物の栗。で、洲栗」
指を巧みに動かして、私に説明する。年齢の割にしっかりした子供だ、と私は思う。
「この集落の子供?」
「はい、そうです」洲栗は歯切れ良く答える。先生を前にした生徒のようだ。「雁亜博士が目覚めたって、今、大変なんです。あの、僕も、嬉しいです」
「敬語は使わなくて良い。必要ない」
「あ、はい。えっと、使いません。あ、これも敬語かな……」
「もっと楽にすれば良いよ。緊張してるの?」
「はい、じゃなくて……。うん、とても」
洲栗は顔を真っ赤にしている。肩は顔を挟もうとしているように上がって、声も少し上ずっている。
洲栗は深呼吸をした。
「僕、雁亜博士が憧れなんだ……。眠る前、一度だけ会話したの、博士は覚えてないよね?」
「雁亜でいい。自分が学者だと、まだ実感がないから」
洲栗を緊張させないよう、できるだけ柔らかく話す。
「君と私は、どんなことを話した?」
「怖くないかって、博士…雁亜が僕に訊いたんだ」洲栗はぐっと握った手に目線を落とす。「僕は、嘘をついた。怖くないって言ったけど、本当はすごく怖かった」
洲栗は意を決して、私に目線を移す。
「雁亜は、僕の年齢を知ってる?」
「五歳くらいに見える」
「九歳だよ」
反射的に訊き返しそうになった。この子供が九歳? どう見ても五歳、よく見て七歳にしか見えない。
洲栗は続ける。
「そんな歳なのに、怖がっていたら情けないと思う?」
「いや、どんな年齢でも、怖がることはある。むしろ怖がらない方が怖い。怖いという感情は、とても大切なものだ」
まだ驚きを引きずりながら、それを隠して洲栗に話す。
洲栗は、ほっとした様子で微笑んだ。私と会って初めて見せた素の顔だ。
「雁亜が目覚めて良かった。雁亜に大丈夫だって言われると、本当にそんな気がする」
洲栗につられて、私も少し微笑んだ。微笑み方を憶えていた気はしないのに、自然と頬の筋肉が緩んだ。
ユカは遅いな、と思う。何をしているんだろう。
洲栗は立ち上がった。
「また、来てもいい?」
「好きにするといい。今度はお茶でも淹れよう」
照れたように微笑んで、洲栗はテントの入り口に向かった。出て行く直前、ばいばい、と手を振った。
この集落には、あんな子供までいる。一体どういう集まりなんだろう。唯一わかっているのは、『雁亜』はその集団の中で重要な存在であること。おそらく、リーダー的なものだろう。
それから……、
キーワードの『百五十年』。
地下にあったあのデジタル時計を思い出す。あれはたぶん、眠っていた時間だろう。
ユカに訊けば詳しく教えてくれるだろうか。一体何がどうなって、私はこんな場所にいるのかと。
ユカが戻ってきたとき、すぐに訊こうと思ったが、彼の方が先に口を開いた。
「遅くなってごめん。あのね、みんながパーティーを開こうって。無事にみんな目覚められたってことで、雁亜に感謝する意味で」
「私に感謝?」
「雁亜が一番の功労者なんだよ」ユカはにっこり笑う。「僕は二番目」
さっぱり実感が湧かない。
「パーティーは今日の夜だって。唐突だよね。雁亜はそれでいい?」
「反対する理由がない」
私は少し笑った。
「そうだね」つられてユカも微笑む。「出来れば、それまでに記憶を取り戻した方が良い。パーティーで、雁亜はきっと演説を迫られるよ」
「何とか誤魔化せないか?」
「当たり障りのないことを言っておけば、大丈夫。もし、どうしても駄目だったら、目覚めたばかりで疲れたって言って引っ込めばいい」
もし、雁亜の記憶がないと人々に知られたらどうだろう。彼らは私を雁亜と認めるだろうか? 頼りにしていた雁亜の記憶がなくて、絶望するだろうか。何にせよ、隠した方がよさそうだ。
「本当は正装したいとこだけど、この世界にそんなものないからね」
ユカは笑った。
「この格好でいいの?」
私は自分の服装を見た。ゆったりした、通気性のよさそうな布地。上はシャツで、下はズボン。シャツには青いラインが入っていた。
「他に着替えは少ししかないよ。白衣は着たほうがいいかもね。博士だから」
「博士ね……」
博士という実感はないのだけど、今夜は振りをしなければいけない。それも、今夜だけではなく、これからずっと。
早く記憶を取り戻したいのに、何故か思い出したくなかった。何か嫌な思い出でもあるのかもしれない。
*
私が開発したこの薬品は、今、試験管の中で身をよじっている。いく筋もの光が混ざり合い、適度な光を放つ。
「もう、明日だね」
声が聞こえて振り向くと、助手である彼が立っていた。
「それを使うのがだよ」
彼は付け足した。さらに、「緊張してる?」と訊いた。
「別に。このまま生きても死ぬし、これを使ってもいずれは死ぬ。同じことだろう」
そう言うと思ったよ、と彼は笑った。
「君の仕事を手伝ううちにね……、君の考えてることがわかってきたんだ。しかも、それがそのまま僕に入ってくる。僕も、今、緊張してないんだよ」
「昨日はすごく緊張していると言わなかったか?」
「そう、昨日はね。でも、今は別。土壇場だと結構覚悟が決まってくるもんだね」
私には彼の言っていることがわからなかった。私の考えと彼の考えは、全く違うものだ。私の考えが彼に理解できるなんてこと、あるはずがない。私にだってよくわからない部分があるのだから。
「雁亜に会えてよかったよ」彼は言った。「人生が変わった気がする」
「良い方に? それとも、悪い方?」
彼は少し微笑んだ。「もちろん、決まってるよ」
*
一人の方が落ち着くだろうから、と言って、ユカは私を一人にしてくれた。確かに、一人の方が気が楽だ。ユカや洲栗は私を知っていても、私は彼らを知らない。見知らぬ人なのだ。危険か安全かもわからない。
私は大きく伸びをして、また鏡を見た。私の顔。博士? この顔にも既知感はない。
毛布があったので、それを伸ばして横になった。テントはごつごつして痛かったが、なんとか我慢する。
ここは何処なんだろう……。
『人類は滅亡した』
じゃあ私たちはなぜ生きている?
そもそも、ここは地球なのか?
そうでない可能性も有り得る。環境の悪化などの原因で地球に住めなくなり、宇宙へロケットを飛ばした。それに乗っていたのが私たち。別の星に着くまで百五十年、ロケットの中で眠っていた……。
くだらない仮説に笑ってしまう。私が起きたのは地下でロケット内ではなかったし、太陽はちゃんと見えていた。仮に太陽の見える他の星であるとしても、地球から百五十年もかかるはずがない。
結論からいって、ここは間違いなく地球だ。それも、砂に覆われた。一体どうしてこんなことになったのだろう。
考えているうちに眠ってしまったようだ。目を覚ますと、室内がぼんやり暗くなっていた。夕方のようだ。お腹がすいた……。頭はさっきよりスッキリしている。
白衣が置いてあった。きっとユカだろう。それを羽織って、外に出てみる。誰もいなかった。遠くで物音がする。
風が吹いて、砂が目に入って痛かった。
窪んだ土地なので、地平線は見えない。少し乾燥している。雨が降ってほしいと思った。
遠くから誰かが来た。近付くにつれ、ユカだとわかった。話ができる距離になると、彼は微笑んで私に言った。
「起きたんだね。よかった。今ちょうどパーティーの準備が終わったところだよ」
「タイミングが良かったみたいだな。白衣は着ていった方がいい?」
「その方が博士らしく見えるね」ユカは私を見る。「雁亜、頭がすっきりしたでしょう。歯切れがよくなってる」
「そうみたい。眠ったら、ずいぶん頭が冴えた」
「百五十年眠ってたからね」
何気なくユカが言ったとき、右側頭部がずきりと痛んだ。立ちくらみを併発した痛みだ。ユカの言った「百五十年」のせいだと思った。それと同時に、私は記憶を取り戻しかけている、と感じた。
ふと、気配を感じて、東の空を仰いだ。
「どうしたの? 雁亜」
「あれ……」私は空を指差す。「雨でも降るのかもしれない」
ずっとずっと遠い、見えるか見えないかのところに、黒い点が浮いていた。なんだか嫌な感じがした。
「雨ならちょうどいいよ。少し乾いてるから」
ユカは軽く言ったが、私は釈然としなかった。
「それより、こっち来て。雁亜が来ないと始まらないんだよ」
ユカは私を引っ張っていった。東の空には、まだ『あれ』が漂っていた。
会場は、古びたビルの一室だった。
私とユカは、道ながら話をした。
ユカの口からは、『雁亜博士』がどれだけ偉大な学者だったかという解説が出てきていた。それが自分のことだとは到底思えず、他人事のように聞き流していた。賞をいくつ取ったとか、どれくらいの研究所を持っていたのか、とか。
「ニコロ」
ほとんど聞いていなかったその説明の、その一単語を、私の耳は確かに拾った。そしてその単語が、頭の中でぐるぐる回った。
「…がね、開発したその薬品を点検しようとしたんだけど……」
再び作動し始めた私の耳が拾ったユカの言葉は、さっきの単語とは何の繋がりも持っていなかった。
『ニコロ』
これは……。
この薬品は……。
はっと気付いたとき、私はビルの前に居た。
五階建て。地下もある。昔はシンプルなグレーの造りで、機能的だった。今は、黒ずんで見るも無残な残骸。
ここは、研究所だ。
そのとき初めて、胸が詰まる感じが押し寄せた。「懐かしい」に近い、でもどこか「苦し」くて「痛い」……。
この場所に来たことがある。頭のどこかでちゃんと憶えているのだ。ただ、思い出せない。思い出したくない……。あともう少しで蓋が開くのを、必死で押しとどめている。私はきっと、何か許されないことをしたのだ。
*
私とユカ以外の全員は、もうシェルターに収まっていた。目覚めたとき、彼らは何処にいるのだろう。百五十年後の世界か、はたまた死の世界か?
「許可しちゃってよかったの?」
私はゆっくり振り返る。
「カプセルに入るのだから、特に咎める気はない」
「ふぅん…」彼は唇を尖らせる。「確かに、いいんだけどね」
私は五十三個のカプセルを眺めている。生物の蛹のようだった。カロンから免れるための蛹は、ちゃんと孵化できるんだろうか。
「この世をどう思う?」私は口を開いた。「一体どうしてカロンが氾濫し出したんだろう? 人間はもう繁殖すべきではないってサインだったんじゃないだろうか」
「哲学的なことを言うんだね」彼は少し笑った。「そうだね……、もしそうだったとしても、神様がそんなサインを出したとしても、雁亜はそれに勝ったってことだよ」
「勝ったんじゃない。逃げただけだ」私はすぐ否定する。「それもほんの少し、長らえただけなんだ」
私の作り上げた、五十三個の蛹たち。
ふっと、このままカプセルに入らず、本当に逃げてしまおうかと考えた。それはとても魅力的な案で、一瞬私はそれに囚われた。
「僕らも行こう。百五十年後の世界へ」
彼に言われてハッとした。そう、私は、見届けなければならない。この世の最後を。
私と彼は、隣同士のカプセルに入った。
最後に、彼と会話をした。
「百五十年後がたとえ死の世界だったとしても」彼は言った。「僕は雁亜と一緒にいるよ。最後までね」
私は、小さく呟いた。「おやすみ。ユカ」
*
パーティーは、研究所の一階で催された。テーブルと椅子が用意され、五十数人の人が集まっている。これが、集落にいる全員らしい。パーティーといっても、会場は古びてコンクリートに亀裂が入っているし、テーブルは今にも足が折れてしまいそうだ。紙コップと紙の皿の上に乗った料理だけが、唯一パーティーという名にふさわしかった。
人々は、しきりに私に飲み物を注いだ。水が主で、あとはオレンジジュースとアップルジュースだった。冷凍保存してあったのを解凍したのだと聞いた。
誰かが、そろそろ雁亜博士に演説を、と言い出し、私は部屋の中央に立たされた。ユカが心配そうに見ている。ユカから二席離れた場所に洲栗がいて、うずうずしながらこっちを見ていた。
会場が、しんと静まり返った。
私は、私の記憶を呼び覚ます。そして、口が動くままに任せた。
「さきほど、私は起きたばかりだが、研究は成功したと確信している。この、砂にまみれた世界は私の予想の範疇であるし、こうして無事に五十四人が目覚めたからである。まだカロンの恐怖は拭えていないが、その突破口もこれから探していこうと思う。そう、それには、ユカ。君の協力が不可欠だ」
私は目だけを動かし、ユカを見る。
「こうして無事に目覚めを迎えられたのも、私の助手であるユカの助力が大きい。改めて、ここに感謝する」
ユカに向かって、圧倒的な拍手が起こった。ユカは微笑んで立ち上がり、一礼する。
辺りがまた静かになった頃、私は話を再開した。
「ここに残されたのは、私とユカを含めた五十四の最後の希望である。この希望の芽を、大事に育てていかなければならない。水の確保、居住の定着……これからも課題は山積みだが、我々は最後の人類として生き延びねばならない」
私は、会場を見回した。そして、一礼する。
「百五十年後の世界へようこそ――」
会場は、割れんばかりの拍手で包まれた。本当に、会場が揺れて崩れるんじゃないかと思うほどだ。全員が立ち上がって手を叩いている。とりあえず私は、無事に演説を終えられて安堵した。
次は、ユカが挨拶をする番だった。
「雁亜博士の言うとおり、僕らは最後の希望です。細い細い綱を渡って、こうして生きているわけです。この世界はまだ分からないことだらけですが、大丈夫。僕と雁亜博士がいるんですから。明日から、調査を再開します。この世界を住みよい場所にしていきましょう。みなさん、ご協力を宜しくお願いします」
再び、拍手が沸き起こった。涙ぐむ者までいる。さまざまな年代の男女が集まるこの場所は、何だか異様な感じがした。多くは二十代~三十代に見える者で、男女の比率は同じくらい。ただ一人、洲栗だけが小さな子どもだった。
演説を終えると、ユカは私の隣に来て、小声で尋ねた。
「思い出したの?」
「違う。思った通りに言っただけだ」私も小声で返す。「『カロン』が何のことなのかわからないが、浮かんできたから口にした。あれで良かったか?」
「上等だよ」ユカは隣の椅子に座った。「でも、一安心だ。あれだけ演説できるんだから、もう思い出しかけてるってことだよ、雁亜」
ユカは肩を落とし、椅子にもたれた。
『カロン』……『ニコロ』……『百五十年』……
私の中で、そのキーワードが渦巻く。次第に気持ち悪くなってきた。
『この世をどう思う?』
『このまま生きても死ぬし、これを使ってもいずれは死ぬ』
視界が廻る。渦巻く。
『どうしてカロンが氾濫し出したんだろう?』
『僕らも行こう。百五十年後の世界へ』
気持ちが悪い。私は、思い出そうとしている――
違う。思い出したいんじゃない。だからこうして、目覚める記憶を必死に押し戻している。まだ出てくるな。私は思い出したくない……!
ハッと気付くと、洲栗とユカが目の前にいた。
「雁亜? 大丈夫?」
ここは、パーティー会場だ。元は研究所の。
心臓が波打つ。脈が速い。冷や汗が止まらない。
何とか頷いて、平静を装って二人を見る。
「すまない……少しぼーっとしていたんだ」
「それならいいけど」ユカは心配そうにしている。「この子が、雁亜に飲み物を注ぎたいって」
洲栗がペットボトルを持って立っている。
「ああ……、お願いする」
そういえば、喉が渇いた。私はカップを差し出す。
頭がくらくらする。手が震えて、カップが揺れる。洲栗も、ペットボトルが重いようで、震えながら上手に注いでくれた。「ありがとう」と言って、オレンジジュースを飲む。飲み物が体を巡り、頭の揺れがマシになった。
カーテンが揺れて、冷たい風が舞い込んだ。不気味な音をたてて、風が室内を舞う。
「風が強いね」ユカが言った。「天候が悪くなってる。嵐になるかもね」
ユカの言葉に、洲栗が震えた。
「じゃあ、テントは大丈夫かな?」
「ちょっとの雨なら平気だと思うよ。ただ、風っていうのはちょっとマズイかな」
私はカップを傾け、ジュースを飲み干した。
異変は、その後すぐに起きた。
地震のような、振動が起こった。どんどん大きくなる。まるで何か得体の知れないものが近付いてきているかのように。
「何だ!?」
「何が起こったんだ!」
取り乱す人々と、悲鳴。テーブルの下に隠れる人々。
振動だけではなかった。爆音がして、窓が割れ、破片が室内に舞い込んだ。揺れで立っていられない。
私は壁を伝って窓に近付く。
「雁亜! 危ないよ!」
ユカの叫び声。
爆風が舞い込み、ガラスの破片がそこらを飛ぶ。
嫌な予感がする……。
今までのものより一回り大きい振動が起こった。近付いてきたユカが私の腕を引き、テーブルの下に引っ張る。だがもう、そのテーブルですらガタガタ震えていた。
「雁亜……。危ないよ」
「危ないのはこれからだ」
テーブルの下は、人々でぎゅうぎゅう詰めになっていた。洲栗は、誰か男の人に守られていた。
私はユカを振り返った。
「竜巻が迫っている」
ユカはぽかんと口を開け、真っ青になった。
「大変だ…」
「テントは吹き飛ばされる。ここも危ない」爆風がうるさいので、声を張り上げる。「すぐに避難しよう。私が見たところ、かなり大型だ。あと三十分もすれば、直撃だ」
「三十分で、安全な場所へ避難するって? 一体どこへ――」
私は床を指差す。
「地下だ。私が目覚めた場所、あっただろう」
「こんな状態で、三十分で辿り着けないよ!」
「ならここで死ぬか? 竜巻がそれなければここは直撃、建物の下敷きになるぞ」
ユカは迷っていたふうだったが、少し考えると、深く頷いた。
「博士! 雁亜博士!」皆が私を見ている。「どうなっているんですか! 私たちは、どうすれば――」
「竜巻が迫っている!」
私は声を張り上げる。私の近くの者しか聞こえないので、一人ひとり伝達していった。
「今すぐ地下へ避難する。先頭にユカ、最後尾に私がつく。慌てずゆっくり、ユカについていくんだ」
ユカと目を合わせる。彼は、頷いて、テーブルの下から抜けた。振動と風で立っているのも辛い。何とか壁を伝い、入り口まで辿り着いた。幾人かもそれに続く。私は最後尾についた。
私の前にいる洲栗が、心配そうに私を振り返っている。何か言ったようだが、聞き取れなかった。私は洲栗の背中に手を当て、小さな体が飛ばされないようにした。
階段は壁で囲まれていたので、すんなり降りることが出来た。ここまでで十分少々かかっただろうか。時間がない。
外は、砂嵐だった。前が見えない。五十幾人は手を繋いだ。
(ユカ……君にかかっている)
もしユカの方向感覚が間違っていたら、私たちは野垂れ死にだ。
洲栗の小さな手が放れないよう、私はぎゅっと握った。
砂が目に入って痛い。前が見えない。
ふと横に動くものがあり、それがこちらに飛んできたテントだと気付いたときには遅かった。私の左肩にそれは当たり、洲栗の手が放れた。
「……りあ!」
洲栗の声が、風の合間から聞こえる。
「先に行け!」
ありったけの力を込め、叫んだ。
立ち上がろうとすると、ずきりと肩が痛んだ。骨もやれたかもしれない、動かせない。私は立ち上がれなくなった。
(さあ、どうする……)
群れからも離れ、一人。視界は三十センチもきかず、左肩の損傷と風で立ち上がれない。嵐はそこまで迫っている。
『ここで死ぬのか?』
はっきりした声が聞こえた。私の、内側から。こんな声、外側だったら嵐で聞こえない。
『まだ遣り残したことがあるだろうに。見届けるのではなかったか?』
私の記憶が、語りかけている。
そうだ……。見届ける。それは、私の罪であり、責務だ。
右手を地面につける。痛む左手も添える。が、駄目だった。足を上げようとすると、風で私は地面に倒れた。
(どうする……)
砂嵐の中に影が見えた。動いている。こっちに向かっている。
(洲栗!)
間違いない。小さな影。私の視界に入ると、洲栗は泣きそうな顔で私に手を差し伸べた。爆風でよろめきながら。
私は、その手を取り、慎重に立ち上がることができた。
風は先程より強度を増していた。うなり声が聞こえる。何度か私と洲栗のあいだをテントが通っていった。
「方向はわかるか?」
「たぶん、こっち!」洲栗は叫んだ。「大丈夫、方向感覚はいいんだ」
風が私と洲栗の手を引き裂こうとする。放れそうになるたびに、ぎゅっと握り直す。一度でも離れればおしまいだ。
洲栗の方向感覚は、確かに正しかった。私たちは、地下へ続くマンホールを見つけることができた。
「雁亜!」
マンホールから、ユカが顔を出している。
私は、まず、洲栗を入れた。それから、ユカの手を取り、穴に避難する。
「雁亜、大丈夫?」
「ああ…。私は平気だ」
ユカは両手を上げ、マンホールの蓋を閉めようとする。轟音はいくらかマシになっていた。
「おかしいな……蓋が閉まらない」
「それは、とてもまずいんじゃないか?」
地下は深いが、この風なら砂が入る。そうなれば、機材がめちゃめちゃだ。
無残なテントの残骸が、穴の上をかすめていった。
「駄目だ、動かない!」ユカが叫んだ。「まずいよ……どうしよう!」
閃いて、私は駆け足で階段を下りた。
「ユカ、扉から離れろ!」
「でも、閉めなきゃ――」
「良い方法がある」
私は急いで階段を下りていった。左肩が痛むが、それどころではない。
地下には五十数人の人々がいた。構わず、とにかく機械を作動させる。
「起動が遅い」
「そりゃ、こんなに大型だし、起動より性能だって雁亜言ったじゃない」
息を切らして、ユカが壁にもたれる。
「雁亜博士、何か?」
「黙っていろ。今思い出している」
壁一面の大型ディスプレイが、青く作動する。私はすぐ、特定の画面を出した。
「雁亜。それって……」
Warningと表示が点滅する。
「これしかない」
私はYesを選択した。
地下中の危険信号が鳴り響き、一瞬にして赤く染まった。
「カプセルに寄るな! 今からカプセルが閉まる。出られなくなるぞ」
叫んで、じっと画面を見つめる。
図画で入り口付近が表示され、みるみる蓋が閉まっていくのがわかる。
完全に閉まった表示になり、ひとまず安堵する。
「非常事態の緊急モードにしたんだね」ユカが言う。「そうすれば、蓋は閉まり、全てシャットアウトだ。考えたね」
「一応確認してきてくれるか」
「了解」
ユカはまた、階段を上がっていった。
ふう、と溜息を吐き、私は壁にもたれた。
「雁亜博士…」
人々が心配そうに私を見ている。
「ああ、大丈夫だ。ここにいれば安心だ。竜巻が過ぎたら、住居を確立しよう。竜巻で飛ばされない家を」
五十幾人かはほっとして、よかった、と呟く。
とことこ、洲栗が近付いてきた。
「僕、知ってるよ。それってレンガの家でしょ?」
「ああ。狼は死んでしまうね」私はしゃがんで洲栗の目線に合わせた。「さっきは、ありがとう。洲栗は私の命の恩人だ」
洲栗はほんのり頬を染め、照れくさそうに私を見た。
「だって、雁亜がいなくちゃ、僕らどうしようもないもの。お父さんにはすごく心配かけちゃったけどね」
「お父さん……」
さっき洲栗といた男性だろうか。
「自分の身も危ないのに、私のために来てくれてありがとう」
「ううん、いいの。雁亜がいてくれれば、僕は嬉しい」
『嬉しい』……。
それは一体、どういう感情だっただろう?
遠い昔、私はそれを知っていた気がするのに。
きっと人間は、生きていくうちに鈍感になっていくのだろう。
「図々しいが、ひとつだけ願いを聞いてくれないか?」
「うん、なあに?」
洲栗は頬を火照らせたままだ。
「教えてほしい。洲栗は少年? 少女?」
「あ、僕はね、男の子だよ」にっこり笑って彼は答える。「よく女の子みたいって言われるんだけど。声が高いけど、僕は男の子」
「洲栗少年か」つられて私も頬を緩める。「私を救ってくれて有難う、騎士(ナイト)」
「どうしたしまして。僕も嬉しいよ」
肩をすくめ、顔を真っ赤にして答える。
階段から、ユカが降りてきた。
「大丈夫だよ、ちゃんと閉まってた」
「有難う」私は立ち上がる。「じゃあ、洲栗。また」
洲栗は小さく手を振った。私はユカに近付く。
「蓋に異常は?」
「大丈夫。ひび割れもなかったし、これで安心だよ」
「あとで地下の機械も確認しよう。恐らく心配ないと思うが」
私とユカは部屋の隅にいた。人々は安心して、寝床を確保したりしている。
「百五十年で世界は変わるものだな」私は呟いた。「人類は滅亡し、地球は無残だ」
ユカはそっと私を見た。私は部屋を眺めている。
「全部思い出した。私の立場も称号も、全て。…君のことも」
目をやると、ユカは真剣に私を見ていた。
「…僕は誰?」
「君は私の義弟だ。侑夏」
侑夏は目を伏せ、再び開けたときには、
「おかえり。雁亜」
吐き出すように小さく微笑んだ。
あの女のことは「蛇女」と呼んでいた。蛇のように気性が荒く、粘着質で執念深いからだ。その反動か、娘の私は冷静で、大抵のことでは動じなくなっていた。
蛇女は教養もなく、使う言葉も悪かった。私のことは、いつも「カリア!」と叫ぶように呼び、嫌味な目線で私を見た。
蛇女は私に仕事をもってくる。私はそれを着々とこなす。
「期日をわかっているでしょうね。遅れたら承知しないよ」
「あんたがこの研究所を使えるのはアタシのお陰なんだよ。ちょっとは感謝したら?」
それでも、新しい男と一緒にいるときは、少しはマシになった。あの男と最後まで一緒にいたのかは知らない。
侑夏の存在に、蛇女は動じなかった。侑夏は、私の父の後妻の息子で、年は私より二つ下だった。まあ、後妻といっても、蛇女と父は結婚していなかったのだけど。蛇女は侑夏に取り入ろうとした。「お父様はお元気?」なんて、わざとらしく。蛇女は父の送金で暮らしていたから、見捨てられたら困るんだろう。もっとも、それは私も同じだったが。
私は本当に、あの女を憎んでいた。
目を覚ますと、地下にいた。嫌な夢を見た……取り戻した記憶が見せた夢は、大半が蛇女のものだった。
昨日は皆で地下で眠ったのだった。カプセルで眠る者もいれば、床で寝る者もいた。私は、カプセルに入らず、床に横になった。あれに入ったらまた百年ほど時を越えてしまいそうだった。
隣に洲栗が寝ていた。あどけない顔で、私の服の裾を掴んでいる。起き上がろうとするが、洲栗の手が私を引き止める。
「申し訳ありません、雁亜博士」
長身の男が現れ、私に言った。昨日、洲栗と一緒にいた「お父さん」だ。
「洲栗、手を放しなさい」
「いや、このままでいい」私はすぐに言った。「よく眠っているようだ。起こさないでおこう」
「すみません」男は軽く頭を下げる。「洲栗は博士をとても好きなようです。昨夜もさんざん聞かされましたよ。よろしければ、またお話をしてやってください」
「ああ…」私は男をじっと見る。「君が、洲栗の父親?」
「ええ、憶えていらっしゃらないでしょうか。私は、博士の研究所で働いていました。百五十年前、とんでもないワガママを聞いて頂いて――」
「私が君の?」
「カプセルに好きなものをひとつだけ入れていいとおっしゃって頂いて、皆家宝やら写真やら持ってきたのに、私はこの洲栗を」
「ああ…」
思い出した。確かに一人、いた。好きなものをひとつだけと言ったら、子どもを連れてきた者が。
「カプセルに入ったから、許可した。それだけだ」
「有難うございます。私にとって宝は、洲栗だけですから。この子を死なせたくなかった」
「それでは、これからも協力して貰わないと。カロンの解毒剤を作らなくては」
「ええ、でも、出来るでしょうか」
「カロンの知識なら、百五十年前も今も、私はトップだ。私が出来なければ、諦めてもらう他ない」
男は微笑んだ。
「ええ、博士……。全力でお手伝い致します」
調理班(料理の得意な者・保存食を作った者)が全員に料理を配り、私たちは食事をした。
「食料、まだテントに移してなかったんだ。助かったね、テントは全滅だから、酷いことになってるよ」
隣で侑夏が愉快に言った。テントに大したものがなくてよかった、と付け足した。
食後、全員が集まり、談合が開かれた。
「役割分担を決めたいと思います。まず、必要だと思われる係ですが――」
侑夏はコンピュータ画面に表示する。
「食事係――まあ、これは当番制でもいいですね。水質調査班。地質調査班。あと、住居を探す班。機械のメンテナンス兼見張り班。それから、細胞学・遺伝学に詳しい人は僕と雁亜についてカロンの対策を練りましょう。それくらいでいいでしょうか」
「諸々得意分野は決まっているはずだ。それぞれの分野に合わせて分かれてくれ。人数が足りなかったら、その都度調整する」
「それじゃあ、水質調査を希望する人はこっちへ。地質はこっち、住居班は――」
侑夏の指示に従い、人々が移動を始める。
「雁亜」
「洲栗。どうした?」
「僕はどうすればいい?」
「そうだな…」私は少し考える。「掃除をしてほしい。この機械は精密で、埃や砂に弱いんだ。やってくれるか」
洲栗は微笑み、頷いた。
「まかせて。僕、がんばる」
洲栗は私の隣でじっとしていた。見渡すと、水質調査班の人数が少ないが、足りないことはなさそうだった。
「早速今日から活動を始めてほしい。調査班は、何か食料になりそうなもの、畑を耕せそうな場所、他に何か異常があればすぐ知らせること。無線は用意してある。特に水質調査班。水は切実な問題だ、すぐに調査をしてほしい」
侑夏に目をやる。彼は首を振った。
「それでは、開始」
一斉に人々が流れ動いた。調査班はスチールボックスを持ち、ただちに地上へ向かった。残ったのは、機械のメンテナンス兼見張りと、細胞学・遺伝学の科学者、それと掃除係だった。
「全員の血液検査をしてみてはどうでしょう」一人が提案した。「百五十年経って、どうなっているかわかりません」
「そうだな。健康診断をしてみよう」私は言った。「今日の夜、全員の採血と身長体重測定、筋力検査を行おう」
「カロンについては、どうなさいます?」
また一人が発言をした。
「薬品、顕微鏡、一通り揃っている。百五十年前と差はないはずだ。とにかく、カロンの弱点を探し、解決策を練る」
「ニコロを使って、何とかできませんか?」
「その方法も検討中だ。ともかく、カロンの弱点を探す。何か異常があればその都度知らせてほしい」
科学者たちは、地下室の机に向かい、顕微鏡と薬品を操る。
私も所定のデスクに座った。隣が侑夏のデスクだ。彼は優秀で、私の専属の助手である。
「…雁亜。怪我、してるね?」
ぎくりとした。左肩の怪我は、誰にも隠していた。
「見せて」
「大丈夫だ」私は平静を保つ。「昨日テントが当たったんだが、今日になったら痛みは治まった」
「テントが当たったんでしょ? すぐ治るわけないよ」
「いや、でも、確かに痛みはないんだ」
そういえば、おかしい。昨日は骨が折れたかと思ったが、今日は痛みがとれている。
「あとで診てもらってよ。でも、医学に詳しい人、居たかなあ……」
「そういえば、ここは科学者の巣窟だな」
ざっと周りを見渡す。見知った顔は少ない。私の助手は数人いるが、顔など憶えていない。白衣を着た科学者たちは、必死に顕微鏡に向かっている。
「皆、カロンにやられているのか?」
「うん……。大体は発達の停止、老いの促進、内臓の疾患だね。僕らみたいに幼児化する例は少ないみたいだ」
「あそこにもいる」私は目線を動かした。「洲栗の例は幼児化だ。もしくは発達の停止。私の見たところ、幼児化だな。もう止まっているようだが」
「でも、いつまた悪くなるかわからない」侑夏が重い口調で言う。「悪性のカロンを持ってる人がいたら、ちょっと、まずいことになる」
「ちゃんと検査しただろう」
「潜伏してる可能性がある。健康診断でそれも検査しよう」
私は溜めていた息を吐き出した。
「KAiser-wandern/ROb/lebeN ……『さすらう皇帝が命を奪う』。これでカロンとはうまく言ったものだ」
「単なる遺伝子疾患の一種だよ。対処法がないっていうだけ」
「それもそうだが、カロンは他の遺伝子疾患と違うところがある。我々科学者はカロンの正体を掴みきれていない……影を見れば、すぐ他の細胞物質に隠れ消えてしまう。そしてそれは、我々の遺伝子にとてつもない影響を及ぼす。『さすらう皇帝』だ」
いつからか、カロンは世に氾濫し出した。遺伝的な疾患が異常に増え、百五十年前は二人に一人以上、カロンにやられていた。悪性のカロンは、突然心臓発作や脳溢血を起こし、人を死にいたらしめる。良性は、発達不良や内臓の疾患を引き起こすが、そこで止まる。外見が変わるだけで、死ぬことはないのだ。
遺伝子に潜伏する皇帝。そのうち悪性のカロンが氾濫し、人類が生き残るのはもう無理だと思われた。
遺伝的なカロンの一部は形を変え、伝染するようになったのである。カロンの病は世界中に蔓延した。
「私の開発したニコロは……」私は思い出す。「一部の人類の命を、少しだけ長引かせた」
侑夏はにこりと微笑んだ。
「今は一部でも、そのうち変わるよ。雁亜は大変なことをしたんだ」
私は頷いた。
十六で止まっている、私の体……。
二十歳までは、カロンに脅かされず生きてきた。が、突然、半年に一つ若くなっていった。今では、十六歳の頃の身長と外見だ。実際は二十九だというのに。
侑夏は私より少しだけ早くカロンにやられたらしく、十四だと言っていた。実際、本当に私の二つ下なので、不便はない。
私と侑夏は、これ以上年をとらない。外見と身長、体重……全て変わらない。このままだ。寿命が来れば突然死ぬ。全く、皇帝に支配された体だ。
一日中顕微鏡とコンピュータに向かっていたが、データを確認するのに多くの時間を費やし、進展はなかった。気付いた頃には夜は更けていた。といっても、ここは地下なので暗くはならないが。
食後、血液検査、その他諸々が行われた。検査班は、おそらく夜中までかかる作業になるだろう。
「採血は終わったか?」
洲栗に尋ねてみる。
「注射なんて久しぶりだよ」洲栗は眉を寄せてる。「ちょっとだけ、怖かった。でも、でもね、シェルターに入ったときよりはマシだよ。あのとき、僕、震えてたんだ」
「今日は震えなかったのか。偉いな」
「へへ…」洲栗は肩に顔をうずめる。「僕、もっともっと、強くなるよ。そんでもって、雁亜を守ってあげるからね」
「昨日だって守ってくれただろう。本当に頼りになる騎士だ」私は顔を上げる。「父親が呼んでるぞ」
「あ、ホントだ。じゃあまたね、雁亜」
一度転びそうになりながら、微妙なバランスで走り、洲栗は父親のもとへ向かった。
「子ども好きなんて知らなかったよ」
いつの間にか後ろに来ていた侑夏が言った。
「そういうわけじゃない」私は腕を組み、洲栗を見守る。「興味があるんだ。彼の言動は、私の理解を超えている」
「あの子…洲栗っていったっけ?」
「そう。彼は自分の身を呈して私を守った。どうしてそんなことをする? 子どもは大人に守られるのが自然だろう」
「いや、正しいんじゃないかな。自分の身よりリーダーを優先する。集団が存続していく上で重要だよ」
「そうだろうか。それに、私を守ると言った。あんな小さいのにだ。どうして……。年長が年少を守るのが当然。新しい命を守らなければ、続いていかないからだ。あの子の言ったことは、逆だ」
「雁亜の苦手な感情論だね」侑夏が言った。「ねえ、雁亜。一つだけ好きなものを持っていっていいって、言ったでしょう? 雁亜は何を持ってきたの?」
「何も……。ここまで持ってきたいものなんてない」
そう、と侑夏は呟いた。
「僕は何を持ってきたかわかる?」
「何を持ってきたんだ」
侑夏はにこりと微笑んだ。
「今日は天候が悪いからね。明日見せてあげるよ」
侑夏の微笑みは、洲栗のとは別物だ。洲栗の笑顔は本当に心を許した笑みで、時折ハッとすることがあるが、侑夏は違う。どうにも気が許せない、というか、安心しない。心のどこかで警戒しているようだ。それは、侑夏が私の義弟だからだろうか。
「嵐は、去っただろう?」
「まだ名残が少しあるかな。風が強い。明日には完全に去ると思うよ」
何気ない会話の裏で、私は侑夏を測っている。
同じ血が半分混ざった、この義弟を。
*
残念ながら医学の心得がある者はいなかったが、応急処置の出来る人物はいた。洲栗の父親だ。
「もともと医者を目指してまして」と、彼は言った。「少しだけなら、治療もできます。お役に立てればいいんですが……」
彼は私の肩を診察してくれた。
「私は病気の薬は作れても、外科に関しては素人だ。よろしくお願いする」
もう痛みは消えていたし、大したことないだろうと思ったが、侑夏が診てもらえとうるさいので、私が折れた。診察していると、みるみるうちに彼の顔色が変わった。
「この怪我を負ったのは……、本当に昨日ですか?」
「そうだ。風でテントが飛んできた」
「博士」顔を青くして、彼は私を見る。「この傷はもう治っています。皮膚も塞がっている」
「大した怪我じゃなかったんだな」
「いえ……。大怪我だったはずです。骨が折れて…、少なくとも、ヒビは入ったでしょう」
彼は、信じられない、と呟いた。
「説明してくれ」
青ざめたまま、時折口ごもりながら、彼は話し始めた。
「いいですか。博士の左肩には、確かに傷痕があります。酷い傷で、範囲も広く、裂傷を負っています。この分だと骨に影響があったはずです。ですが――」
口にしていいのか迷っている様子で、彼は、戸惑いながら話した。
「治っているのです。たった一晩で。今この傷は、もう痕にしかなっていない。かさぶたみたいなものです。骨も、私の診たところ、つながっている」
「こう言いたいのか? 昨日大怪我を負ったはずが、一晩で治ったと」
「信じがたいことですが……」
反論したかったが、彼も戸惑っている様子なのでやめておく。とりあえず、私にとって悪い結果にはなっていない。
「どうもありがとう。助かった」
「いえ…。お役に立てませんで」
私は部屋の隅の侑夏のもとへ向かった。私に気付くと、侑夏は心配そうに近寄ってきた。
「どうだった?」
「治っている」
「そう…」彼はほっと肩を下ろした。「それなら良かった」
「本当にそう思うか?」
「何?」
「いや…」私は顔をそむける。「血液検査の結果は、いつ出るんだろう」
「まだかかると思うよ。雁亜、眠ったら?」
「ああ……そうする」
私は寝床に向かう。背後から、鋭い侑夏の視線を感じていた。
地下の一室に布団を敷き、寝床にしてある。私はその部屋の一番角の布団に入った。数人が眠りについている。部屋は照明が薄暗くしてあった。
眠ってしばらくして、人の気配がした。起き上がると、洲栗がそこにいた。
「どうした?」
「隣に寝てもいい?」
見ると洲栗は枕を持ってきている。
「眠れないのか」
こくりと、小さく頷いた。「怖い夢見ちゃったんだ」
「だが、ここは女性専用の寝室だ」
「お願い。僕、女の子みたいって言われるから、大丈夫だよ。お父さんもお仕事があって、先に寝てなさいって言われて、それで……」
この世の破滅のような、洲栗の顔。何故、他人にこんな弱い部分を見せられるのだろう。そうして保護を求めているのだろうか。それが、子どもなのか。
「……許可しよう」
洲栗は満面の笑みを浮かべた。
「ありがとう」
さっきは泣きそうな顔をしていたのに、もう微笑を浮かべている。私の一言で、彼の表情が変わる。全く……、嫌いな言葉だが、理解不能だ。
洲栗はいそいそと布団に入り、枕の上に頭を乗せ、私を見てにこりと笑った。私もまた、布団に入る。
「さっきね、僕がどんどん小さくなっちゃう夢を見たんだ。親指より小さくなっちゃうんだよ。怖かった」
カロンの幼児化だ、と直感した。おそらく幼児化への恐怖が見せた夢だろう。
「それで……最後にはどうなったんだ?」
出来るだけ穏やかな口調で尋ねた。
「ちっちゃく、ちっちゃくしぼんでね……」洲栗は両手をどんどんしぼめていく。「ポンッて、破裂しちゃうの」
両手を大きく広げて、私に説明する。
「そこで目が覚めたんだ。怖かった」
「それは怖いな」
「でしょう? もう、一人で寝ていられなくなっちゃったんだ。…迷惑だった?」
「いや、興味深い話だ」私は洲栗に言った。「それはおそらく、カロンの幼児化を表しているんだろう。わかるか? カロンの毒で、洲栗の体は小さくなっていく」
洲栗はひとつ頷いた。
「おそらく退化はそのうち止まるだろう。案ずることはない。洲栗は、いつから小さくなり始めたんだ?」
「一年半前かな……。あ、カプセルに入る前ね。どんどん小さくなっていくんだ。止まらない」
「そうすると、まだ小さくなっているかもしれないな……。今日、身長と体重を測っただろう? 明日もまた測ってみるといい。それで止まっていたら、カロンの幼児化は止まっている」
「そうだといいな。僕、これ以上縮みたくないよ。背が小さくなっちゃう」
あんまり真剣に洲栗が言うので、私は何だかおかしくなった。
洲栗は小さく欠伸をした。
「早く寝ないと明日に差し支える」
「うん、そうだね」そうして、私を見てにこりと笑う。「おやすみ、雁亜」
洲栗は布団にもぐった。楽しそうな顔で。
さっきまで怖がっていたのに、この変容はどうだろう。
世の中の子どもが特殊なのか、洲栗が変わっているのか。他にサンプルがないので比較しようがない。少なくとも、私は、洲栗のような子どもではなかった。思い出したくない幼少時代……。
今夜は、あの夢を見ないといい。
*
食事当番だというので、洲栗は朝早く目を覚ました。隣にいた私も、つられて起きてしまったので、当番を手伝うことにした。ついでに、自分が当番に当たったとき、スムーズにできるように覚えておこうと思った。
食事は、何てことはない。レトルトのようなものだ。真空パックを開けて、鍋で温める。火は使わず、電気仕様だ。同時にご飯を温め、五十六の皿に盛る。飲み物も用意し、テーブルをセッティングすれば、完了。
食事当番は洲栗の父と洲栗、他数人だった。彼らはしきりに私を止めた。「博士はお休みください」「私たちがやりますから」それを振り切って、手伝った。私が側にいると緊張するようで、数人の科学者はおぼつかない手つきだった。
「ありがとう、雁亜」
洲栗がにこりと笑って言った。
「『雁亜博士』だろう、洲栗」
父親が嗜めたが、すぐ私は言った。
「いいんだ。洲栗に博士なんて呼ばれてもくすぐったい」
「そうですか…?」
「さあ、準備もできた。皆を起こしてくるとしよう」
五十数人が起きるまで、数分かかった。それぞれの席に着座し、各々食べ始める。
食後、洲栗の父親がやって来た。
「昨日の博士の怪我の件、私なりに考えてみたのですが」
彼は少々寝不足のようだった。
「シェルターに入って、ニコロを使われましたよね。ニコロの副作用で、免疫・自然治癒力が上がったんじゃないでしょうか」
「有り得るな。目覚めるときは毒を消す治癒のニコロを使ったわけだから――ニコロが、私の傷を治したわけだ。となると、この効果は一時的だな」
「ええ、でも、良かった……。雁亜博士の傷が治って」
私は背の高い洲栗の父を見上げた。
「この件は改めて研究するとしよう。ご苦労だった」
「いえ、私は何も」
「夜を徹して推論を組み立てたのだろう?」
彼は、照れたように笑った。少し、洲栗に似ていた。
それから、検査を終えた科学者たちがやって来た。
「皆の持つカロンは全て良性でした。潜伏している可能性もありますが、まあ、大丈夫でしょう。検査も異常なし。数人健康状態が悪い者がおりますが、病気ではありません」
「何よりだ」
「昼食時に皆に報告しようと考えておりますが、よろしいでしょうか?」
「そうしてくれ」
私はまた、顕微鏡に向き直った。試すことがあったのだ。洲栗の父の言った、自然治癒力の増加……。
ふと気付いて手を見ると、昨日の注射の痕が消えていた。跡形もない。
(どうやら本当のようだな……)
思わぬ効用があるものだ。害がないといいんだが。
私は辺りを見渡した。
ニコロによって、ほんの僅か生き長らえた人々。そう、それは、ほんの僅かだ。いずれは絶滅するというのに……。
「雁亜博士」
呼ばれて私はハッとした。科学者の一人が、私の側に立っている。
「水質調査班より、無線で連絡が入っております」
「ああ…。すぐ行く」
私は立ち上がった。
無線はメインコンピュータと連動になっている。私は研究室から通路を抜け、操作室へ向かう。途中、調理室から音がして覗いてみると、洲栗が朝食を片付けていた。
「あ、雁亜」洲栗はすぐ私に気付いた。「何処行くの?」
「水質調査班から連絡が入った。ひょっとすると、外へ出るかもしれない」
「気をつけてね」
「そのつもりだ。洲栗も、仕事を頑張ってくれ」
うん、と頷いた洲栗の腕に、私の目は釘付けになった。
そこには、くっきりと、紛れもない注射の痕があった。
予想通り、私と侑夏は外に呼ばれた。水源を発見したと彼らが言ったので、確認に赴くことになったのである。
「乗り物でもあればよかったんだけどね。結構遠いなあ」
「機械工学の科学者に、今度作ってもらうよう提案しておく」
私たちは、足場の悪い砂を引きずって歩かねばならなかった。
「今日は晴れてよかったなあ。暑いくらいだ」
「嵐の後だからな。それにしても、いつ嵐が来るかわからない。気を付けておこう」
荒廃した建物を横目に、私たちは歩いていく。百五十年前だってこんなに歩いたことはなかった。私はいつも研究所に居て、朝も夜もわからない状態だったから。
「あ、雁亜……。あそこ、僕が住んでたマンションだよ」
ボロボロの、もはや屑となったコンクリートを指差して、侑夏が言った。
「人間は、時間には敵わないね」
「時間と、自然には太刀打ちできない」
風が吹いて砂が舞うと、コンクリートは更に無残に見えた。
「半永久的な素材のコンクリートって言ってた割に、脆かったな」
「眠っていた間に何か起きたのかもしれない。地下にまで影響がなくて良かった」
「砂まみれの世界になるってことは、予想してたんでしょう?」
侑夏は歩き始めたので、私もついていく。
「そうだ。人類は掃除の時代だと、誰かが言っていたな。掃除をしていなければ、高層ビルなど百年で砂に沈む」
砂が靴に入り込み、ざわざわする。私にはコンクリートの方が合っていると感じた。
「もう、人類は誰一人残ってないのかな」
「そのようだな。皆、カロンにやられてしまったんだろう」
この地球には、私たちだけしかいない。多少の生物はいるとしても、人類は五十六人だけ。それも、もうすぐ滅びてゆく。一体私がしたことは何だったんだろう。
数人の人影が見えてきた。白衣を着ている。水質調査班だ。
「雁亜博士、侑夏博士! ご苦労さまです」
彼らは一礼した。
「水源というのは?」
「ここです」
砂の土地に長い棒が差し込まれている。
「地下十メートルまで探索しましたら、水が出てきました。吸い上げて、飲み水にできれば――」
「掘って井戸を作った方がいいな。それよりまず、その水が飲み水になるか調べなくては」
私が言うと、科学者たちは頷いた。
「現在、一部吸い上げて調査しているところです」
私は周りを見渡した。砂からところどころコンクリートやゴミが突き出し、少し離れたところに建物がいくつかある。
「お誂え向きなものがある」
私は手招きし、侑夏を呼んだ。
「あの辺りの建物、使えないだろうか」
「他の建物よりは、しっかり残ってるようだけど……」
「いつまでも地下にいる訳にいかない。水源に近い場所に移動しなければ」
「大仕事になるね」侑夏は呟いた。「まず井戸を掘って、建物の掃除をして、大移動」
「それだけだ。それから、この砂漠を何とか畑にする。無理なら、保存してある土を使って菜園を作る。食べ物を確保しないといけない」
「やけに前向きだね」
「そうしないと生きていけないだろう」
侑夏はじっと私を見た。
「雁亜は生きることに否定的な気がする」
核心を突かれた。悔しいが、それは当たっていた。侑夏はさらに言い募る。
「人類なんて滅びればいいって思ってるでしょう?」
砂漠のような百五十年後の世界。
私が知っている最後の世界は、カロンの病で絶望的な場所だった。
もう、人類に生き延びる余地はなかった。
誰が言い出したか憶えていない。私のニコロを使って、一部だけでも生き延びようと。それが、百五十年後まで眠りにつく、このプロジェクトだ。
「人類なんて、とっくに滅びた」
言い出したのは、ひょっとすると侑夏だったかもしれない。
侑夏はどう思っているのだろう。この砂漠の土地が地球だと? 人類を生存させたいと?
すぐ側にいるのに、侑夏の心は百五十年より遠い気がする。
*
カロンの打開策と平行して、引越しの計画も練られていった。地下にあった機械を改造し、科学班が井戸を掘る。残った人員で手分けして建物を掃除し、荷物を運ぶ。二週間で引越しを終える計画を立てた。
「よろしいですか? 博士」
研究者たちが一斉に私を見る。
「異論はない」
その一言で、決定した。各々がそれぞれの仕事につく。
(二週間か……)
それなら、大丈夫だろう。私の仕事に支障はない。
翌日から、引越しの準備が進められることになった。今夜はゆったりした最後の夜だ。
夕食の後、食事当番の洲栗を手伝っていると、私は侑夏に呼び出された。
「一体どこへ行くんだ?」
侑夏は階段を上がっていく。
「お楽しみだよ」
手には水の入ったバケツを持っている。それと、小さな袋。
長い階段を抜け、蓋を開け、外に出るともう暗かった。何もない真っ暗な空間。
侑夏は砂の上にしゃがんだ。
「何をしているんだ」
「雁亜も座って」
訳もわからず、私は侑夏の正面にしゃがみ込んだ。
「見てて…」
侑夏は袋から何やら細長い紙切れと、ライターを取り出した。手際よく、紙切れに火をつける。
紙切れの先が、真っ白く発光し、辺りを明るく染めた。
「花火だよ」侑夏は小さく呟いた。「一つだけ持ってきていいって言われて、僕は綺麗なものを持っていきたいと思った。選んだのがこれだよ。夏の風情だね」
ジジと音を立てて、火花が消えた。
侑夏は紙切れをバケツに捨て、袋から数本花火を取り出し、残った袋を私に差し出した。
「雁亜の分」
「花火か……」
実際この目で見るのは、二度目だった。研究所の前で、近くの子どもたちが遊んでいたのを見て以来だ。
袋を受け取ると、かなり軽かった。風でも吹いたら飛んでいってしまう。
侑夏がライターに火をつけた。私は花火の一本を火に近付ける。
静かだった。全ての音が闇夜に溶けていったようだ。
花火の発する微かな音と、それでも眩しいほどの閃光。
静寂を壊したくなくて、ずっと黙っていた。まるでこの世のすべてを圧縮したかのような闇に、ぽつんと灯る火。暗い世界に取り残された私たちに、よく似ていた。
小さな命が終わり、火が消えた。バケツに入れるよう侑夏が言うので、焦げた花火を投げ入れた。
侑夏はライターに火をつける。私はまた、新しい花火に火をともす。
「美しいものだな」私は呟いた。「綺麗というより、美しい」
「うん。僕もそう思うよ」
ほんの小さな呟きが、よく通って聞こえる。夜の魔力だ。小さなものが大きくなる。
「侑夏は、どうして研究者になった?」
「父親がね……。僕はIQも高かったから、お誂え向きだったんだよ」
私たちはじっと花火を見た。そして、花火に語りかけるように話した。
「君と私の父親は、同じだ。二度会ったことがあるが――典型的な実業家だったな」
「雁亜の研究所を作ったのも、ビジネスだったのかもね。でも、もう、あの人はいないよ。この世界には誰もいない」
「あの女もいない……」ぽつりと呟いた。「あの蛇女も、さすがに百五十年は生きていないだろう」
「あのひとはカロンにやられてなかったね、珍しく。僕らの幼児化は父親ゆずりだ。カロンは遺伝によるところが大きいから」
「あの女になど似たくない」
花火が消えた。侑夏の花火だけが光る。ふと空を仰ぐと、星空が花火のように散りばめられていた。
世界は、こんな美しいもので満たされていたのか……。
百五十年前、私の周りには醜いものしかなかった。
視線を下げて侑夏を見る。彼は花火に熱中していた。
「君が羨ましい……。あの女の血が入っていないのだから」
侑夏はふと顔を上げた。
「時々嫌になる。私の中に、まだあの女が生きているような気がする」
自分が信じられなかった。これは、弱音だろうか? 警戒している侑夏にこんなことを話すなんて、血のつながりのせいか、この夜のせいか……。
「雁亜はあのひとが嫌いだったね」
「今も嫌いだ。憎んでいる」
「根本的に反りが合ってなかったんだろうね……タイプがまるで逆だ。無理やり、研究させられてたんでしょう。研究は嫌い?」
「興味のあることなんてない。ただ、淡々と与えられた仕事をこなしただけだ。感情移入せず、先入観がないから業績を上げられたのかもしれない」
「それもあるけど、違うよ」侑夏は確信に満ちたふうに言った。「雁亜は天才なんだ。類稀な、誰も持っていない頭脳を持ってる。だから、ニコロを生み出せたんだ」
(ニコロか……)
私は誰にも言わず、ひとりで、ニコロを開発した。それが出来たとき、私は解放されると思った。この薬品は、今までのしがらみを取り払うだろう……。それが今や、まだ科学者たちの中にいる。
いっそニコロで、私の記憶を全て消してしまえばよかった。そうだ、そうすればよかった。あの女も消える。
侑夏が最後の一本に火をつけた。
小さな小さなオレンジが、闇に浮かんだ。
「それは……他の花火と違うようだ」
「線香花火だよ」侑夏は答えた。「派手ではないけど、すごく綺麗で儚い」
「ニコロの光に似ている」
私は線香花火に見入った。
百五十年前に、この儚いものと出会いたかった。そうすれば、何か、変わっていたかもしれない……。
だがもう、後には退けない。人は滅びの道を進むしかないのだ。私のせいで。
*
夢はよく見る。抽象的なものから、色が付いた現実的なものまで。
今夜の夢に現れたのは、ニコロだった。
花火の色のようなニコロが、全身を廻る。巡り巡って、頭の先からつま先まで、行き渡る。そして私は、眠りにつくのだ。二十九年の生涯を終えて。
目が覚めると、少し汗をかいていた。冷や汗だ。ニコロの淡い光の残像が、まだ残っている。
普段より長く眠ってしまい、起きたらちょうど食事の時間だった。食事が終わると、引越しの手順が説明される。私はカロンの解毒剤製作が最優先なので、引越しの班には入らなかった。水質調査班によると、掘り出した水は濾せば飲めるとのことだった。建物も、掃除と補強をすれば十分住めるそうだ。計画は順調だった。
私はまた、仕事についた。引越しのため、地下の人員は少なくなっていた。
洲栗の父親の話した、ニコロの副作用による驚異的な再生能力。この理由は、すぐに解明できた。私の指に小さく傷をつけて確かめたところ、傷はすぐに塞がった。顕微鏡で確認すると、傷を受けたところの細胞が一度全て死に、すぐにまた新しい細胞が現れてくるのだった。驚くべき回復機能だ。恐らくはニコロの効用だろう。
(こんな副作用があるとは、予想外だ……)
一体どうしてこんな作用が現れたのか、研究の余地がある。が、あまり他に逸れてはいけない。私の本来の仕事は、カロンの解毒剤を作ることだ。それも、あまり意味のない仕事だが……。
休憩をとり、珈琲を取りに行くと、食堂(として使っている部屋)には数人の人間が居り、洲栗もいた。
「お仕事ご苦労様」洲栗はにこりと笑った。「休憩に来たの?」
「ああ。珈琲を飲みに」
「僕、淹れてあげる」
洲栗はカップを用意し、珈琲メーカーに向かった。
「火傷をしないように」
「大丈夫」
火傷してもニコロの副作用があれば大丈夫か、と考え、思い出した。
洲栗の腕には注射の痕があった。私は消えていた。
私たちが眠るとき、同じニコロを使ったはずだ。どうして洲栗には回復能力がない?
洲栗は、一生懸命な目で、珈琲とにらめっこしている。
慎重に珈琲を注ぎ、私に差し出す。
「はい」
「有難う」
それを受け取って、私はしゃがみ、洲栗と目線を合わせた。
「この前注射した腕を見せてくれないか」
「いいよ」
洲栗は腕を伸ばして私に見せた。薄く、痕が残っている。
「………」
通常の治癒力だ。どうして、私だけ? いや、それとも、洲栗だけに回復能力がないだけで、他の人にはあるかもしれない……。ひょっとすると使ったニコロの量の違いだろうか。
推論を巡らせていると、洲栗が不思議そうな顔をしていた。
「もういい。どうも有難う」
珈琲を手に立ち上がり、研究室に戻ろうとすると、洲栗の声が引き止めた。
「あ、あのね、雁亜」
振り向くと、もじもじしながら、洲栗が言った。
「雁亜の研究してるとこが見たいんだ。…僕、研究室に入っちゃダメ?」
「構わないが……」
「ホント? 昨日、お父さんには仕事の邪魔になるからダメだって、断られちゃったんだ。今、お父さん外の仕事でいないから、ちょっとだけ。内緒で、お願い」
洲栗は私の白衣の裾を引っ張る。
「あまりはしゃいではいけない。他にも研究者がいるから。邪魔にならないと約束出来るか?」
「もちろんだよ」
頬を赤く染めて、洲栗は大仰に頷いた。
洲栗を連れて、研究室に戻る。彼は口をぎゅっと結んで、震える手で白衣を掴んでいた。私のデスクは、広い室内の真ん中にある。室内は広いので、一つ一つのデスクは距離がある。洲栗のために、小さな椅子をひとつ用意し、座高を上げた。彼は目を輝かせて、デスクの上の顕微鏡やらパソコン、試験管を眺めた。
「雁亜。その子……」
侑夏が洲栗に気付いた。
「邪魔にはならない」
「僕、絶対邪魔しません。だからここに居させてください」
洲栗は小さな声で、きっぱりと言った。
「…まあ、雁亜がいいって言うならいいけど」
洲栗は、ありがとうございます、と一礼した。
「何か面白いものはあるか?」
尋ねると、洲栗は楽しそうに椅子に登った。
「うん。凄いね、かっこいい!」
私も椅子に座った。
「ねえ、雁亜。この綺麗なの、何?」
洲栗が示したのは、試験管のオレンジ色の薬品だった。
「ああ、それはニコロだ」
「ニコロ…。雁亜が開発したっていう? 僕、意味がよくわからないんだ」
「そうだな……簡単に説明すると――」私は試験管を手に取る。「人間の体は数え切れないほどの細胞でできている。ニコロは、細胞に一瞬にして浸透する。そして、細胞ひとつひとつを支配してしまうんだ。つまり、人間の体を好きなように操れる」
洲栗はぽかんと口を開けた。「凄いね」
「百五十年前…悪性のカロンの氾濫により、人類の生き残りは無理だと思われた。そこで私たちは、このニコロを使って生き延びる策を思いついた。誰にも秘密の、極秘プロジェクトだ。他人が知れば、自分も生き延びたいと言うだろうから。さて、ニコロを使って、どうやって生き延びられただろう?」
「えーっと……。僕らはシェルターに入ってずっと眠ってたんだから……ニコロで体を眠らせちゃったんだよね」
「まあ、そういうことだ。詳しく言えば、ニコロに一定量の毒を持たせて人間の体に投与し、仮死状態にする。死なない程度に量を調節するのが難しいところだ。シェルターで、最低限の栄養素は送り続ける。それでずっと眠っていたわけだ」
「そっかあ…」洲栗は納得したが、すぐに考え込む。「でも、だったら、どうやって起きたの?」
「シェルターに百五十年のタイマーをかけ、時間が来たら新しいニコロを身体に投与するようセットしておいた。その新しいニコロは、体に巡った毒の解毒剤だ。毒が消えた人たちは仮死状態から目を覚ます。こういうわけだ」
洲栗は目を見張って、しばらく驚いていた。
「よく考えたねえ…」
「洲栗は何も知らずにシェルターに入ったのか?」
「お父さんが、この中に入れば死なないですむからって」洲栗はぽつりと話し出す。「僕は、りっちゃんやカオくんも一緒に連れていきたいって言ったけど、駄目だって」
「りっちゃん?」
「僕の友達……。この世界には、もういないね」
洲栗の悲しそうな顔。
私の胸が、ざわざわ騒ぎ出す。なんだろう、この落ち着かない感覚は。ひょっとしてこれが、悲しみっていうものか? だったら私も、今の洲栗みたいな表情をしているのだろうか。
洲栗は、それでも笑ってみせた。
「ありがとう、雁亜。あのままだったらお父さんも僕も死んでたんだよね。雁亜は凄いよ。これだけの人を救ったんだから」
小さな洲栗が、ますます小さく見えた。
*
それから数日は、引越しの準備で忙しかった。井戸も八割がた完成し、建物の補強もあと僅か。明後日には越せるだろうという段階まで漕ぎつけた。
私はその間に、ある推論を組み立てた。この驚異的な回復力についての推論だ。おそらく、目覚めのときに使用した解毒剤のニコロの影響だろう、と。だがそれなら、どうして洲栗だけ回復能力がないのか気になった。
人々は、この世界での生活に慣れつつあった。最後の人類なのだから我々が死んではならないと、連日のように繰り返した。そんな気負いもあって、引越し作業は考えていた以上の早さで進行した。
現場を視察に行くと、人々は私に笑顔を向けた。
「このままいけば、この世界でも暮らしていけますよ」
「雁亜博士のおかげです。ありがとうございます」
この世界でも暮らしていける……。
私にとっては、この世界の方が暮らしやすい。確かにカロンの研究はしているが強要されないし、何よりあの蛇女がいない。極楽だ。
なのに。それなのに、私の中の蛇女の陰影はますます濃くなっていった。
毎夜毎夜、あの女の声がする。私の中に流れる、あの女の血のせいだろうか。カリア!と、怒鳴るように呼びつける下品な声。私の間近から聞こえたようで、夜中に辺りを見回すこともあった。そのお陰で、この頃は寝不足だ。これは、私の罪の意識なんだろうか。
「雁亜。少し休んだら?」
侑夏の声が聞こえ、ハッと現実に戻ると、私は顕微鏡の前にいた。
「大丈夫だ」
「最近、やつれてるよ」
「カロンの研究に熱中しているんだ」
適当に答え、試験管を手に取る。
オレンジ色が身をよじる、試験管。私の開発したニコロ。
「……僕はね、それを見たとき、本当に革命が起きたと思ったよ」
隣で侑夏が話し出したが、私は振り向かなかった。目を合わせれば、この義弟に何もかも見破られそうだったから。
「これを使えば、カロンの解毒剤だって作れるんじゃないかと思ったんだ。結局、世界は滅びて、こんな形になったけれど」
私も思い出した。
何日も何日も誰にも秘密で研究し続けた、この薬品のことを。
蛇女の目を盗んで、私はこの薬品作りに没頭した。誰にもこの薬品の存在は知られないはずだった。
ようやく完成し、試しに使用してみると、顕微鏡の中でニコロは十分な働きをした。
(これで、私は解放される……)
そう思った矢先のことだった。
「雁亜。何してるの?」
ぎくりとして振り向くと、侑夏がいた。
「もうすぐここ、閉まるよ。――雁亜?」
「なんでもない。すぐ行く」
「片付け、手伝うよ」
断る間もなく、侑夏は私の側に来た。
「カロンの研究?」
どう誤魔化そうか考えている内に、侑夏は顕微鏡を覗き込んだ。私の緊張は最高に達した。どうか侑夏がその薬品の意味に気付かないよう――が、侑夏は考えていた以上に優秀だった。
「雁亜。これは……」
侑夏は側の試験管に目をやる。
「見て! すごいよ!」侑夏は叫ぶ。「細胞が変わってる……。どうしたの、これ!」
誰にも秘密のはずだった。
侑夏に見つかり、彼はそれを私の開発として研究者たちに発表した。それがニコロだ。ニコロは、人類最後の延命装置として、プロジェクトを組み立てられた。
人類が生き延びるため?
そんなことのために、この薬品を開発したんじゃない。
私は私を解放するために――
「ニコロは世界を変えたんだ」
侑夏の言葉で、現実に戻る。
そう、これが現実。
私はまだ、研究者としてここにいる。
蛇女に囚われたまま――
*
気が付くとすぐ側に蛇女がいた。
いつものように罵声を投げかける。
ヒステリックな叫び声。
お前は、もう死んだはずだ――
ずっとずっと、私の側には蛇女がいた。
あの女は私を縛り付ける。私の頭脳が類稀なものだとわかると、
すぐに父親に連絡し、研究所を建てさせた。
私は研究所から出られなかった。
あの女がそれを許さなかったから。
一日と一月の区別もつかない毎日。
ただただ、起きては仮説を立て、実験。
蛇女は私を管理することを生きがいとしていた。
私の名誉は、あの女の名誉。
それなら、
私の命も、あの女の命なのか……。
うなされて起きると、世界はまだ闇の中だった。
ひっそり静まり返る室内で、自分の心臓の鼓動だけがうるさい。
少し落ち着いて、背後を確認した。寝静まる人々だけで、あの女はいない。
それでも、あの女に触られているような、嫌な感じが全身を覆った。
ここはあの女が生きている時代じゃない。
こんなにも囚われているのは、私が蛇女を殺しきれなかったからかもしれない。
だから、まだ生きているかのような感覚を味わう。
ニコロを開発しても、百五十年後まで逃げても、
どうしてあの女に付き纏われるのだろう。
朝は、洲栗が起こしに来た。というより、彼は私の様子を見に来ただけだったようだ。そこへたまたま、私の目が開いた。洲栗は、心配そうに私を見ている。
「雁亜、大丈夫?」
私は息を切らしていた。また、あの女の夢だ。
「……大丈夫だ」
私はゆっくり起き上がり、背後を確認する。大丈夫。
「雁亜、うなされてたんだ。何だか疲れてるみたい……。もしかして、病気じゃない?」
「悪い夢を見ただけだ。大丈夫、もう起きる」
「あ、朝ごはん、もう食べちゃったよ。みんなが雁亜は疲れてるから寝かせておこうって言ってね」
洲栗は私の先を歩き、ドアを開けた。
その小さな背中を見て、ぎくりとした。
洲栗は、こんなに小さかったか……?
ひょっとすると。
嫌な考えが思考を支配した。
「……洲栗…」
「なぁに?」
振り返って、にこりと笑う。
「後で採血をしよう。注射だ。いいか?」
「えー、また注射?」
「我慢するんだ。いいな?」
「雁亜が言うなら……」
渋々、洲栗は承諾した。
手が空いたら洲栗の採血をしてほしいと言うと、洲栗の父親は不安げな顔をした。
「洲栗が何か…?」
「サンプルが欲しいだけだ。子どもの細胞の」
「ああ、そうですか」
明らかにほっとして、父親が笑った。
「仕事が終わってからでいい。今は、忙しいだろう?」
「引越しの準備の途中です。夜になるかもしれませんが――」
「構わない。では、夕食が終わった後にでも頼む」
この、嫌な嫌な予感が当たらないよう、祈ることしかできなかった。
*
午後になって、補強工事が終わったと連絡が入った。井戸の方もあともう少しといったところだ。
「では、明日にでも移動をしよう。井戸もその後でいいだろう」
「そうだね」と、侑夏は頷いた。「善は急げだ。今夜荷造りをして、明日の午前に移って、重い荷物は後からトラックで運ぼう」
もうすぐ、この地下ともお別れ。といっても、研究施設は地下にしかないので、私は毎日ここへ来なければならないが。
夕食時に明日引っ越すと発表すると、人々から拍手が起こった。涙ぐむ者までいた。皆、一様に安心している。この世界で暮らしていけると確信を持ったからだろう。私にはその全てが白々しく見えた。
それから私は忙しかった。引越しの荷造りをし、機械のメンテナンスをし、指示を与え、百五十年経って一番忙しかった。
そう、だから、洲栗の父に血液を貰っても、すぐには調べられなかった。
「ああ、ご苦労だった。そこへ置いてくれるか」
と言って、また、目まぐるしく働いた。
出来るだけ早く引っ越したい。
それだけが、私を突き動かした。万が一引越しの日程がズレれば、全てが水の泡になってしまう。私がここに来た唯一の理由が、日の目を見なくなってしまう。
何とか荷造りと点検を終えると、もう真夜中だった。私は床についたが、頭が冴えてなかなか眠れなかった。
明日は、いよいよ引越し……。
そのとき私は、洲栗の採血のことをまるで忘れてしまっていた。
*
その朝は快晴だった。
誰もが、自分たちの行く先を疑わなかった。
この空のように、希望に満ち溢れていると思っている。
だがその日、
次から次へと、災難が降り注ぐことになる。
朝食を終えると、私は引越しの計画を説明した。
「まず、侑夏と科学班で、建物の点検を行ってほしい。補強工事が完全かどうかの確認だ。その間に荷造りの終わっていない者は終えること。点検が終わったら、全員で固まって移動する。地下を空っぽにしておくのは心許ないので、これから交代で二人ずつ、誰か残ってもらうこととしよう。何か質問は?」
「水質調査班です。井戸はまだ未完成ですが――」
「今日は引越しに専念してほしい。明日から再開しよう。炊事以外、今日は全ての作業を引越しとする」
他に質問がなかったので、そこでお開きとなった。
「雁亜。じゃあ僕たち、行って来るね」
侑夏はショルダーバッグを背負っている。
「無線は持ったか?」
「もちろん。確認が終わったら連絡するから、みんなで来てよ」
階段を上ろうとした侑夏の足が、不意に止まる。
「とうとう引越しだね」
「ああ」
「…行ってくるよ」
何か考え込んでいるような口調だった。
気にかかったが、侑夏がそのまま行ってしまったので、引き止めなかった。
次に、洲栗が私の側にやって来た。小さなバッグを背負っている。
「引越しの準備は終わったか?」
「ばっちりだよ」
洲栗はバッグを背負いなおす。それでもバッグは、肩からずり落ちてしまう。
「紐が長いんだ。貸してみろ」
洲栗はバッグを下ろし、差し出した。
「雁亜も、準備終わった?」
「ああ。特に荷物はないからな。後はここで侑夏の連絡を待ち、指示をするだけだ。――ほら、出来た」
バッグを受け取りお礼を言って、洲栗はじっと私を見る。
「侑夏博士って、雁亜の弟さんなんでしょう?」
「そうだ」
「雁亜、侑夏博士のこと好き?」
深いところを突かれて、私はハッと洲栗を見た。
「僕、何だか雁亜と侑夏博士がわからなくて……。嫌い合ってはないんだけど、好きって感じでもない気がするの」
全くこの子は何て洞察力が鋭いんだろう。動揺を隠して、何でもないように言葉を紡ぐ。
「侑夏と私は、半分しか血が繋がっていないんだ。その辺りの姉弟よりは、他人に近いんだろうな」
「でもね、侑夏博士、いい人だよ。いつも雁亜のこと心配してるもん」
そういえば、侑夏は私の肩の怪我にも気付いた。私があれほど隠していたのに。
「だから、きっと仲良くなれるよ」
洲栗の笑顔は確信に満ちていた。
「そうだといいな……」
気の許せない侑夏。
時々、彼に全て見透かされているような気がするのは、何故だろう。
*
それは、突然の連絡だった。
引越しの準備が佳境に入り、私が一番忙しくしているときだった。
五十数人が一斉に移動するのだ。並ぶ順番を考えたり、荷物を整理し、機械をメンテナンスし、打ち合わせをし――とにかく、目まぐるしかった。
「雁亜博士。無線で連絡が入っています」
一人の科学者が、慌てて私のところへ駆け寄ってきた。
「後にしてくれないか」
私は息を切らし、振り向かずに答えた。
「それが、引越し先でトラブルが発生した模様で――」
「トラブル?」
そこでようやく、私は振り向いた。
科学者は顔面蒼白している。
「何とか向こうだけで解決出来ないのか」
真っ青な科学者は、淀んだ口調で告げる。
その次の一言で、私は奈落の底へ叩き落された。
「侑夏博士が負傷されたそうです――」
私の目は、何も映していなかった。
突然、何の音も受け付けず、真っ暗になった。
『侑夏博士が負傷――』
科学者の声だけが聴こえる。
だがそれは耳に残っているだけで、頭にまで届かない。意味がわからない。
侑夏が、怪我を?
一体どれくらいの?
多分、大したことはない。彼は慎重な人間だ。
だが、彼の意識があるならば、私に心配かけまいと連絡させないように指示を出せたはずだ。
ということは……?
落ち着かせようと思考を巡らすのに逆効果で、不安が突き上がってくる。
自分の呼吸音が聞こえる。
「それで…、侑夏の具合は?」
何とかそれだけ尋ねる。
「分かりません。無線ではそこまでは……」科学者の口調がもどかしい。「ただ負傷した、と繰り返すばかりで……」
私は研究室を飛び出した。
地下中を回り、駆け回る。乱暴にドアを開け、洲栗の父親を捜した。
彼は、五番目に開けたドアの向こうで、洲栗と荷造りをしていた。
「博士?」
「雁亜…」
私は彼の腕を目いっぱい引っ張った。
「来い!」
「あの、博士……」
彼を立たせると、その高身長を見上げて言った。
「侑夏が怪我をした」
「え…」
「どの程度の怪我かはわからないが、すぐに来てほしい。君の力が必要なんだ」
彼は神妙な顔つきで、
「私にどこまで出来るかわかりませんが、全力で侑夏博士を助ける努力をします。――洲栗、そこにある鞄を取ってくれるか」
そう言うと洲栗は彼に出来る最大限の速さで鞄を持ち上げ、父親に渡した。
「雁亜博士と出かけてくる。洲栗は荷造りの続きを」
「わかった。行ってらっしゃい」
洲栗も神妙な顔つきで、深く頷いた。
私と洲栗の父親は、倉庫から科学班が作った乗り物を取り出し、地上に出た。あいにく一台しかなかったので(侑夏達が乗って行ってしまった)、重量オーバーの二人乗りだ。バイクのような形で、砂の上でも走れるよう設計してある。洲栗の父親が運転、私は無理やり後ろに乗った。
「博士、鞄をお願いします」
彼はアクセルを踏み、現場へと急いだ。
ここから向こうまでは、少なくとも十分かかる。
どうかそれまで、侑夏が生きていますよう。
侑夏の怪我が大したことないよう。
私は本当に、祈るほかなかった。
自分がこんなに無力なんだと思い知らされた。
たかだか五十数人救ったところで、人類を救ったわけではない。
もうこの世界に人類が生きる余地はない。
私が本当に有能なら、カロンの解毒剤を作り、世界全体を救うのに。
『雁亜は天才なんだ』
本当に天才なら、こんなことで動じはしない。
天才とは、孤独なものだ。こんな風に、失うのが怖かったりしない。
でも、一部の冷静な頭脳が、冷たい声質で話す。
侑夏のことをどうしてそんなに気にかける? どうして彼を失うのが怖い?
――私は侑夏を嫌っていたはずじゃなかったのか?
違う。彼を生かしておかなければ、私の願った景色が見られないからだ。
ただ、それだけ。他に意味はないんだ。彼は私の綿密な計画の一部なのだから。
「博士。少し、思ったんですが」
洲栗の父親が、ふと言った。
そこで現実に戻った。私は、砂の上を走っている。後部には砂の波ができていた。
「ニコロの異常なまでの治癒力……あれがあれば、侑夏博士の怪我も大したことないかもしれな――」
「馬鹿なこと言うな! あれが侑夏にあるはずないだろう!」
気が付くと、動揺を声に出して怒鳴っていた。
声が震える。
冷静な自分はどこかへ飛び、もう止まらなかった。
「あの効果は侑夏にはない! あれは、私と五十四人の人たちだけのものだ! 侑夏にあってたまるか!」
息継ぎもなしに叫び、心臓が最大限まで高鳴った。
そう、あの効果が侑夏にあってたまるか――
あるはずがない。
すみませんでした、と、小さく彼が謝る。それすら、私は聞いていなかった。
砂くずを掻っ切って、侑夏のもとへ進む。
*
建物が見えると、私は飛び降りて駆け出した。乗り物を止め、後ろから、侑夏の父親が付いてきた。鞄の重さも、全く感じなかった。とにかく、侑夏のもとへ。彼を失ってはならない。
中に入ると、塗料の匂いが鼻をついた。それと同時に、私を呼ぶ声が聞こえた。
「博士! 雁亜博士!」
反射的に振り返ると、白衣を着た科学者が居た。
「侑夏は」
「こちらです」科学者は歩き出す。「建物が腐っている部分がありまして、侑夏博士がそれを発見し――その途端、崩れて……侑夏博士が下敷きに」
ドクンと、心臓が鳴った。
後ろから洲栗の父親が付いてきているのを確認し、科学者に続いた。
科学者の先導で、歩き出す。眩暈と震えで、今にも吐きそうだ。こんなプレッシャー、今までに感じたことはない。質の悪い緊張だ。
現場に着いたときには、もう倒れる寸前だった。自分がこんなに脆いとは意外だと考え、少し気を落ち着かせる。
瓦礫の周りに、数人の白衣が集まっていた。私に気付くと、彼らはすんなり道を開けた。
侑夏は、その真ん中にいた。
頭を打ちつけたらしい。額に傷があるようだが、血で染まってよく見えない。白いはずの白衣が真っ赤に染まり、侑夏は目を閉じぴくりとも動かない。
「瓦礫は退けましたが、侑夏博士が――」
「このままじゃ失血死の危険も……」
「馬鹿、雁亜博士の前だぞ」
さっきまで、あんなに元気に笑っていたのに。
こんなのは、嘘だろう?
こんな侑夏は、偽者なんだろう。
洲栗の父親が、侑夏の脈をとった。焦った顔で、額を触る。侑夏の顔が少し動いた。
ふらりと、私の足が動いた。侑夏から遠ざかった。怖い。
が、気力を振り絞って、私は侑夏のもとへと歩き始めた。ぺたんと座ると、侑夏の表情がよく見えた。
「侑夏……」
「博士。声をかけてあげてください。…博士?」
偽者だ。侑夏はただ一人、
「博士!」
この世界に、
「しっかりしてください!」
洲栗の父親の顔が、すぐそこにあった。
冷静になると、視界の揺れが止まった。
「…ああ。私は、何をすればいい?」
「侑夏博士を励ましてあげてください。私は応急処置をします」
「危ないのか?」
「…非常に」
侑夏の顔から血の気が引く。それもそうだ、血液はどんどん流れてゆく。私の白衣も侑夏の血で染まった。
「聞け、侑夏。お前はこんなところで死ぬ奴じゃない。ここで死んではいけないんだ」
私は侑夏の手を取る。冷たい手。
「私の声が聞こえるか。聞くんだ。私の望みを絶やすな。お前だけは生き延びるんだ、侑夏」
いっそ。
侑夏にニコロの治癒力があったらよかったのに。洲栗の父親が言ったように、あの驚異的な回復力が。
百五十年前の判断が間違っていたのだろうか。これは、私の望みを叶えまいとする天罰か。
誰が絶えても、侑夏に絶えてほしくはない。彼の血が流れるなら、私の中のあの女の血が流れてしまえばいい。
ああ本当に、あのニコロの治癒力が――
「………りあ…」
真っ暗闇から声が聞こえた。
何も見えない。当たり前だ、目を閉じているのだから。
瞳を開けると、鮮やかな赤と、侑夏の瞳が見えた。
「…侑夏……」
冷たかった侑夏の手に、温度が戻ってくる。確かな脈拍も伝わってきた。
「私がわかるか?」
「…僕は、倒れたの……?」
答えあぐねていると、侑夏は大きく瞬きをし、次の瞬間には身体を起こした。
「侑夏博士!」
私はもう、何も言えなかった。手が、胸が震えて、言葉を忘れてしまった。
「博士! 大丈夫なんですか」
「え? …うわ、何、この血! え、僕の?」
洲栗の父親も私も、呆然と侑夏を見ている。
「博士、でも、この頭は――」
「あ、痛っ! いたた…怪我してる。コブでも出来たかなあ」
信じられない、と洲栗の父が呟いた。
その場に拍手が巻き起こった。
信じられないのは、こっちも同じだ。
侑夏の笑顔を見て、ほっとした。
だが、心の奥底で、危険信号が鳴り響いていた。
侑夏は何故助かった?
ニコロの治癒力じゃないのか?
まさか。侑夏にあるはずがない。
だって……。
その場は無理をして笑っておいたが、心の中の動揺は膨らみ、今にもはち切れそうだった。
ともかく侑夏が無事だったので、引越しは着々と行われた。私と侑夏、洲栗の父親は、別室で侑夏の診察をすることとなった。私はその様子を見守っていた。
「…もう、傷は塞がっています……」
例によって驚いた表情で、洲栗の父が言った。
「瓦礫が頭に落ちてきたんです。即死だっておかしくないのに――」
「打ち所が良かったんですね」
ケロッとした顔で侑夏が言う。
「打ち所なんてもんじゃありません。見ましたか? 一メートルはある大きな瓦礫ですよ。大抵死にます。それに、あんなに血を流したのに……ふつう出血多量です」
侑夏はぽかんとして、苦笑混じりに私を見た。
「僕、運が良いみたい」
「…そのようだな」
「博士。もう、本当に何ともないんですか?」
「はい。触るとちょっとピリッときますけど。すぐ治っちゃいますよ、これくらい」
私は侑夏をじっと見ていた。まさか、彼に再生能力が? 馬鹿な……。
「あ、そうだ。引越しの準備――」
「侑夏。君はここに残っていろ。私たちは行こう」
「でも、僕、もう大丈夫なんだよ」
「私は自分の見たものしか信用しないことにしている。君は大怪我をした。安静にしておくのがいいだろう」
「ちぇ…、もう平気なのに。何かあったらすぐ呼んでね」
不貞腐れた侑夏を置いて、私たちは部屋を出た。
長い廊下を歩きながら、私は洲栗の父に言った。
「ニコロの再生能力については、誰にも伏せておいてほしい」
「侑夏博士にもですか?」
「ああ…」私は声を低くする。「あの効果が誰にもあるものだと決まった訳ではない。怪我をしてもすぐ治ると知れたら、無茶なことをしでかす者が増える。それに、あの効果は一時的なものかもしれない」
「そうですね。わかりました。この事は私の胸に収めておきます」
「頼む」
侑夏の驚異的な治癒能力。
言いようもない、漠然とした焦燥が突きあがり、私は目眩がした。
すぐにでも再生能力について確認をとりたかったが、引越しで忙しく、今日は無理なようだ。焦燥を抱えながら、それを表に出さないよう必死で堪え、働かねばならなかった。広い建物なので、二・三人で一部屋使えるようになっている。元々マンションなので、小さい個室が細々とある。私の部屋は一階で、侑夏の隣だ。なかなか広く、窓から殺風景な砂漠が見えた。カーテンがないので、後で付けなければ。
夕食は、個人の部屋で摂ってもいいことになった。今日は引越し初日なので全員で食べることになり、広いステージがある部屋が食事部屋となった。
当然のように演説を迫られ、前に立つと、不安げな人々の顔が見えた。
「皆、集まったな」
「雁亜博士。侑夏博士は無事なんでしょうか」
どこかから声が聞こえた。侑夏が負傷した事実は知れ渡っているようだ。
「瓦礫に頭を打ちつけてコブができただけだ。心配ない」
会場の空気が変わり、明らかに安堵した雰囲気になった。
「今日は一応大事をとってあるが、明日からは復帰できるだろう。心配をかけてしまったな」
無事引越しを終えられて良かっただの、これから世界を良くしていこうだの、適当なことを喋っている間――私は侑夏のことを考えていた。彼に治癒力があるということは、私の仮説が揺らぐということだ。一から考え直す必要がある。
今日の食事にはワインも付いてきた。一体誰が持って来ていたのだろう。軽く飲むと、焦燥感が増した。どうして、何故、侑夏に……。
袖を引っ張られ振り向くと、洲栗が立っていた。
「ああ、どうした?」
「雁亜こそ。さっきから呼んでるのに、ちっとも気付かないんだもん」
「すまない、考え事をしていたんだ」
あのね、と洲栗は切り出した。
「侑夏博士に、これを……。渡して欲しいんだ」
彼が差し出したのは、ビーズ細工の腕輪だった。
「良くなりますようにってお願いしながらね、編んだんだ」
「ビーズなんてよく持ってたな」
「ポケットに入ってたの。百五十年前から入れっぱなしだったみたい」
洲栗はいつものように、ニコッと笑った。
つられて私も頬が緩んだ。
どうせ今、仮説の確認は出来ない。明日研究所でやるしかないのだから、焦ったって仕方がない。
「よし…、じゃあ、渡しに行こう」
私は洲栗の手を引いた。
「えっ僕も?」
「自分の手で渡すといい。きっと喜ぶ」
「……緊張するなあ」
まるでテントで私に会ったときのようだった。洲栗は腕輪を握り締め、恐々と、でもどこか嬉しそうにしていた。
侑夏は元気だった。ちょうど食事を食べ終わったところで、私たちを歓迎してくれた。
「暇だったんだよ。来てくれてありがとう」
大怪我を負ったとは思えない。いつもの侑夏だった。
私は洲栗の背中を押し、侑夏の前に立たせた。彼は緊張でガチガチに固まっている。
「君は、えっと……洲栗君?」
「はい」
「洲栗君かな、洲栗さん?」
「あ、僕、男の子です」
洲栗はうつむいてもじもじしている。
もどかしくなったので、私は侑夏に言った。
「君に渡したいものがあるそうだ」
「僕に?」
侑夏は私から洲栗に目線を移す。
意を決して、洲栗は腕輪を差し出した。
「これ……侑夏博士が良くなるようにって、お願いして作りました」
「へえ、綺麗だなあ」侑夏は微笑んで洲栗に言う。「これ、僕に?」
「はい」
「貰って良いの?」
「貰って欲しいんです。あ、えっと、受け取ってください」
侑夏はふんわりと微笑んで、洲栗の手から腕輪を取った。
「綺麗だね。嬉しいよ、ありがとう」
うつむいていた洲栗が、花火のような眩しい笑顔になった。
「これならすぐ良くなりそうだ。洲栗君のおかげだね」
「ありがとうございます!」
「お礼を言うのはこっちだよ。どうもありがとう」
洲栗は今にも泣きそうな顔で、頬を真っ赤に染めていた。
「あ、じゃあ僕、戻ります。まだ引越しの片付けがあるから」
両手と両足が揃って出そうな勢いで、洲栗は部屋を出て行った。
一部始終を見ていた私は、そっと侑夏に呟いた。
「子どもに優しいとは知らなかった」
侑夏は意地悪い表情を浮かべて、
「興味があるだけだよ」
と、言った。
辺りはもう真っ暗だ。廊下の窓から月光が覗いた。
私は、数人の科学者たちと建物の最終的な見回りをしていた。三階の部屋を見回ると、一番角が洲栗とその父親の部屋だった。
そこで、ほんの少しの異常があった。
「洲栗はもう眠っているのか」
ベッドに横たわる洲栗と、その隣にいる父親。だが、すぐに様子がおかしいことに気付いた。
「少し熱を出したようなんです。引越しで疲れたんでしょう」
「薬は」
「飲ませました。処置はしてありますから、大丈夫です。明日には下がると思います」
それならいいがと思ったが、少し引っかかった。
さっきまであんなに元気だったのに、ほんの一時間で熱を出して寝てしまうのか……。
「容態が悪くなったらすぐ知らせてくれ。それから、君も寝不足にならない程度の看病を」
父親が仰々しく礼をし、私と科学者たちは別の部屋を回った。
このほんの少しの異常が、大きな災いの種になる。
*
私の願いは、もうすぐ叶う。
部屋の明かりを消し、窓の外を覗く。今夜は三日月だ。
百五十年前、私がかけた魔法、そして罪。
引越しが終わった。侑夏も生きている。前途洋々のはずだ。
なのに、この不安はなんだろう?
心を掻き乱し胸騒ぎを誘発する、この嫌な感じは。
あの侑夏の尋常ではない治癒力が、引っかかっている。
窓の外の虚空を見つめる。申し訳程度の数個の星。
誰にも邪魔はさせない。
この計画に幕を引くのは私だ。
ニコロの溺れる世界には、神ですら介入できない。
*
目が覚めると、窓から日光が差し込んでいた。少々眩しすぎるので、カーテンを今日取り付けようと考えた。
起き上がって着替え、食堂へ向かうと、もう人々は揃っていた。丁度いいのでここで朝食を摂ることにした。
隅に人だかりが出来ていたので見てみると、復活した侑夏が中央にいた。
いつも通り食事をし、片付けをする。
が、そこに、洲栗はいなかった。
父親の姿しかない。まだ寝込んでいるのだろうか。
気にしながらも、乗り物に乗って外へ出る。
建物から数十メートル離れた場所に、なだらかな砂の坂がある。あそこからなら、建物を一望できる。きっといい眺めだろう。
地下の研究所に戻り、誰も居ないのを確認する。研究室の明かりを点ける。血液検査のとき全員から採った血が、どこかに保存してあるはずだ。予想通り、冷凍庫の鍵を開けると、そこに五十六の試験管があった。
なるべく人目につかない方がいい。特に侑夏には知られたくない。
大急ぎで、私と侑夏、洲栗、その他八本の試験管を取り出し、解凍する。五十六全てを調べていたら誰か来て見つかってしまうので、いくつか見繕ったものだ。
(これは……)
顕微鏡を見た私は、全身に鳥肌が立った。
細胞を傷つけて、その治癒力を調べる。そうしたら――
(何故……)
その結果分かったことは、
驚異的な治癒力があるのは、私と侑夏ふたりだけだった。
脆くも私の推論は崩れた。
私と五十四人の人々にはあっても、侑夏にはないはずだった。
考えられるのは、この効果がニコロによるものではない場合だ。だが、だとすると何だ? 侑夏と私の共通点は、義理の姉弟であること。血のつながりか? いや、血のつながりが何だというんだ。洲栗たちだって親子じゃないか。
全くわからない……。一体どうしてこんなことになったんだ。
心臓が脈打つ。私の中に流れる血。血の中のニコロ。
誰が知っているなら教えてくれ。どうしてこんなことが起こった? これは、私の計画に差し障りのない現象か?
もう時間がないんだ……。滅びの時を迎えるまでに、私はこれを解明できるだろうか?
午前中に研究をし、昼食はこちらで摂る。それから、夕食までの間好きな時間研究をし(好きなときに休憩をとって良い)、建物に戻る。それが研究者たちの間で決まったルールだった。
研究者たちがするのは、主にはカロンの解毒剤製作、そしてこの世界の調査だった。科学者たちは乗り物の製作に勤しんでいる。それもこれも、この世界で生き延びようとすればこそだ。私はそれらの全てを裏切っている。
昼食の折り、洲栗の父親を見つけ、声をかけた。
「洲栗は良くなったのか」
「いえ、それが……」
彼は暗い顔で答える。
「どんどん、熱が上がっていて……。治る兆しが見えません。疲れだとは思うのですが」
そわそわ落ち着かずに、彼は視線を泳がせた。
「こんなところで何をしている」私はしっかり彼を見た。「洲栗が苦しんでいる。すぐ戻ってやれ」
「ですが、仕事が……」
「そんなもの、他の研究者で足りる。だが洲栗の看病は誰がする? 他の誰が代われるんだ」
暫く放心して立ち上がり、彼は大きく礼をした。
(洲栗が……)
走り出す彼の後姿を見ながら、歯車が徐々に狂っていくのを感じていた。
頼りない体内時計を頼りに、人々は研究のきりがつくと建物に帰っていく。今度、時計も作らねばならない。
「雁亜! 待ってよ」
片付けて帰ろうとすると、隣の侑夏が呼び止めた。
「僕もすぐ終わるから。一緒に帰ろう」
侑夏の後片付けを手伝い、私たちは長い階段を上って地上へ出た。
「カロンの打開策は考えついた?」
マシンのエンジンを入れ、乗り物に乗って建物へ向かう。
「考え中だ。侑夏こそ、何か思いついたか?」
「ぜーんぜん。駄目だね。まずカロンの弱点を探らないとどうしようもないのに、肝心のカロンはなかなか姿を現さない」侑夏は大仰に溜息を吐き出す。「でもまあ、急いて焦ることはないよね。悪性のカロンを持ってる人はいないんだし、ゆっくりやろう」
「悪性のカロンか……」
私は呟いた。ゆっくりやる時間などないことを、侑夏は知らない。研究が全て無駄になることも、今はまだ知ることはできない。侑夏がそれを知ったときには、全てが終わっている。
住居に戻ると、まだ夕食の準備が整っていなかった。
「じゃあ、散歩しない? 研究所に篭りっきりだと体がなまっちゃうよ」
侑夏に連れ出された形で、私は再び外に出た。
昼間見た丘を越えて、しばらく行っても、景色は変わらなかった。壊れた建築物、砂、砂……。植物は見当たらなかった。
私たちは適当なところでスクーターのような乗り物を止め、乗り物に腰掛けて話をした。
「この世界で生き抜くには、あとは何が必要だろうね?」
「食料の確保。それから、医療設備の充実。後者は難しいだろうが、前者は出来ると思う。保存した土があるから、それに種を蒔いて育てれば良い」
話しながら、こんなことを考えても無駄なのだと思った。
「そうだね。早速明日からでも始めよう」
だが、侑夏を誤魔化すためには生きていく方法を考える振りをしなければ。この、優秀な義弟を騙すため。
ふと気がつくと、侑夏はじっと私を見ていた。
「…何だ?」
「いや、よかったなあって。雁亜が前向きになってくれて」
「今まで私は後ろ向きだったか?」
「というより、否定的だったじゃない。人が生き延びるのにさ。今はちゃんと考えてくれてるから、嬉しくなっちゃったんだよ」
案ずることはない。義弟はちゃんと騙されている。
「確かに、人が生き延びることに興味などないが、この世界ではそれしかすることがないだろう。退屈しのぎだ」
「それでも、嬉しいよ」侑夏は微笑む。「雁亜と違って、僕は人が生き延びることに賛成なんだ。この世界は人類が蒔いた種だからね。こんな、ボロボロの世界になったのは」
「だからだ。人類は居なくなった方がいい」
「いや、僕はね、生き延びてちゃんと後始末をしなきゃって思うよ。そこが僕と雁亜の考え方の違いだ」
「相反する考えだな。決して絡まることはない」
百五十年後の世界でも、空は青く、雲が浮かんでいる。自然は変わらないのに、生き物だけが居ない。
「そういえば……、ここには人間以外の生き物がいないんだろうか」
「カロンにやられたんじゃない? 時たま伝染性のカロンがあったからさ、うつっちゃったんだと思うよ。でも、探してみたらいるかもね。生き残りが」
「不気味だな」
こんな世界の片隅で、ひっそりと息を潜め、暮らしている存在がいたのなら――。
「そろそろ戻ろうか。夕飯できてる頃だよ」
頷いて、私はスクーターのハンドルを握った。
夕食はパンとスープ、それから野菜だった。食料は一年分蓄えてあるので、緊急の課題ではない。夕食時、洲栗の姿を捜したが、見当たらなかった。まだ寝込んでいるのだろうか。
『ちっちゃく、ちっちゃくしぼんでね……』
洲栗の見た、幼児化の夢。
初めて会ったときよりも、彼は縮んでいたように思えた。ひょっとすると、幼児化がまだ止まっていないのかもしれない……そう思い、血液検査をしたのだった。まさかないとは思うが、『それ』を考慮に入れれば、可能性は二つ。一つは、ただ単に幼児化が止まっておらず、間もなく止まる場合。そしてもう一つ。…これは、考えたくない可能性だ。
思考を巡らせていると、だんだんと不安になってくる。食事を終えると、私は洲栗の部屋へ向かった。
ノックをしても、返事がない。灯りが部屋の隙間から洩れているので、誰か居るだろう。「入るぞ」と声をかけ、ドアを開けた。
洲栗の父親の、後姿が見える。それから、荒い息遣いが聞こえる。
「博士…」
やつれた顔の父親が振り返った。
「…洲栗は」
父親は、困惑した顔で首を振った。
「わかりません……薬を与えても注射をしても、熱が下がらず……先ほどは発作で呼吸困難まで……」
不吉な予感で高鳴る心臓を引きずって、洲栗を見た。
嫌な既視感で鳥肌が立った。
顔全体を紅潮させ、苦しそうに何とか呼吸をする、その姿。
「…洲栗」
倒れこむように、私はベッドに腕を乗せ膝を床につけた。
「洲栗。私の声が聞こえるか?」
反応はない。側に寄ると、洲栗の荒い呼吸が生々しく聞こえた。
(これは…!)
「博士にうつったら大変です。ここは私に――」
私は立ち上がった。それから、部屋を出る。廊下を歩いていたが、ゆっくりしている場合ではない、すぐさま走り出した。
矢も盾もたまらず、スクーターに乗り込む。
「雁亜。どうしたの?」
誰かの声。構っている暇はない。
ハンドルをきつく握り、夜の砂漠を滑走した。ライトはないので、もう勘に頼るしかない。研究所へ。
そんなはずはない。こんなことは……。早く確認したい。最後の可能性は有り得ないと。
乗り捨てるようにスクーターを降り、地下研究所へ下りる。常駐の監視員に「研究室を使う」と言い置いて、奥へと進んだ。
研究室のドアを開けるとき、ふと声が聞こえた。
「雁亜。一体、どうしたの…」
息を切らした侑夏が、通路の端から現れた。
「全速力出すから、追いつくまで時間かかったよ。あれじゃオーバーヒートしちゃうよ。…雁亜?」
構っている暇も、声を出す余裕もない。
研究室の明かりを点し、冷凍庫からこの前採決した洲栗の血を取り出した。
「ちょっと持ってろ」
試験管を侑夏に預け、急いで顕微鏡をセットする。終わると試験管を侑夏の手から奪い、血液を垂らし、顕微鏡を覗いた。
「……!」
あまりのことに、私はしばらく動けなかった。
「雁亜?」
よろめく私の体を、侑夏が支えた。体が震えているのが、侑夏の手を通してわかった。
今、自分の目で見たものは、恐ろしく残酷な事実だった。
「大丈夫? 真っ青だよ。一体――」
「…もう、一人で立てる」机に手をつき、何とか気を落ち着けようとする。「侑夏。その顕微鏡を見てみろ」
訝しがりながら、言われた通りに覗き込む。
侑夏は私と似たような反応を表した。体が小刻みに震え、眩暈を起こしたようだ。
「雁亜。これ……」
「洲栗の血液だ」私は言った。「最初の検査のときは、恐らく潜伏していたんだろう。今になって……」
侑夏はもう何も言えなかった。
私は、もう一度顕微鏡を覗きこんだ。
さすらう皇帝の哀れな犠牲者。
カロンの姿は捉えきれないが、この細胞の変形具合。
洲栗の体の中に、悪性のカロンがうごめいていた。
この辛い宣告を洲栗の父親にするか、私と侑夏は大層悩んだ。だが、放っておいても洲栗は死んでしまう。カロンの解毒剤はないのだ。それなら最後の別れができるようにと、私たちは話すことに決めた。
月明かりの忍び込む、廊下。
彼は、最初その事実を受け入れられなかった。嘘でしょう、そんな馬鹿な、と繰り返した。
「私が嘘でこんなことを言うと思うか」
真実だと悟ると、彼は廊下に崩折れた。
「洲栗…!」
夜でよかったと思った。昼間だったら、苦渋に満ちた彼の表情が私の記憶に刻まれてしまう。
「洲栗君は、もってあと十日でしょう。発熱、嘔吐、意識の低下……悪性カロンの典型的な症状です」
「このまま苦しみ続けて、死ぬというのですか……」
「解毒剤を作れるよう努力する。だが……覚悟しておいてほしい」
私が十年以上研究し、カロンだけはどうしても及ばなかったのだ。あと十日でどうにかなるとは思えなかった。
「洲栗の側にいてやってくれ」
彼はよろめきながらも立ち上がり、部屋に戻っていった。
「辛いね」
侑夏がぽつりと呟いた。
「悔しい」
と、私は言った。
これだけは、私の手に余る。どうしようもない。何もできないのが悔しくてたまらない。
だけどどうして悔しいなんて感情が生まれるのだろう。人間なんて滅んでしまえばいいのに。洲栗の生をどうしても望んでしまう。
失うのが怖い。百五十年経って、私が学んだ教訓だ。今さら知っても、私の罰が色濃く浮き上がるだけだ。
「どうしようもない……本当に」
気持ちを紛らわすために壁を殴ったが、殴った手の痛みが跳ね返り、余計に辛くなった。
*
希望の朝とは程遠い、翌日の朝日。この眩しさが残酷だと思った。
私はカロンの解毒剤製作に没頭した。同時に洲栗のカロンが伝染性のものではないことも確認した。
洲栗は、この世の最後の犠牲者として死ぬのだ。
あんな小さな体に、苦しみを溜め込んで。
悪性カロンを持つ者が居たことは、皆には伏せておいた。どんな混乱を招くかわからないからだ。
「雁亜。何か成果はあった?」
隣の席の侑夏が訊いた。
「あったらもっと気が楽になっている」
「そうだね…」
落ち込んだ侑夏の声。私は再び顕微鏡を覗きこみ、薬品を使用する。カロンの弱点は本当にないのか?
全ての細胞に潜り込み支配するところは、カロンとニコロは類似している。ただ、カロンには毒があり、ニコロは無害だというだけだ。
辛そうな洲栗を思い出す。
こんなにも研究と向き合ったのは初めてだ。そしてこんなに追い詰められたのも。
昼食を抜き、丸一日試験管と向き合った。だが、成果は上がらなかった。
「雁亜。今日はもう帰ろう」
侑夏に止められるまで、私は集中し切っていた。細胞の世界から、現実の大きな研究室へ戻る。
「根を詰めすぎたら毒だよ」
「そんなもの……カロンの毒には敵わない」
「雁亜が倒れたら、誰がカロンの研究をするの? 僕じゃ雁亜に及ばないからね。しっかり休んでおかないと効率悪いよ」
侑夏は私のデスクを片付け出した。
「…何かしていないと落ち着かないんだ」
「わかるよ。僕も同じ。ただ、僕の方が少し冷静なんだ」
こんなに、と私は呟いた。
「こんなに焦ったのは二度目だ……。一度目は、侑夏が怪我をしたとき。私はどうしてこんなにも冷静さを欠いてしまうのだろう」
「今まで、いろんな感情を押さえ込みすぎたんだよ。今は雁亜のお母さんがいなくて、開放的になってるんじゃないかな」
蛇女。
どこかであの女が笑っているようだった。
こんな私を見て、高らかに。あの毒づいた顔で。
*
洲栗の部屋を訪ねてみると、洲栗はよく眠っていた。
「今は発作もおさまっています」
「君の方がやつれている。看病で疲れたのだろう」
「いえ…、洲栗に比べれば、これくらい」
といっても、父親は目に見えてやつれていた。
「明日は看病に侑夏を派遣しよう。君も少し眠るといい」
「そんな! 侑夏博士は――」
「他の者に頼めば悪性のカロンのことが知られるかもしれない。それに、私が抜ければカロンの研究が妨げられる。適役は侑夏しかいない。不服か?」
「いえ、滅相もありません! よろしくお願い致します」
私は洲栗をじっと見た。もうすぐ、この子どもは動かなくなる。
眠っている洲栗の顔。
「最後まで頑張るんだ、洲栗。君は強い騎士だから、出来るな?」
手をとると、それは熱く湿っていた。
「カロンに負けてはいけない。もう少しだけ耐えてくれ――」
それから三日間、とにかくカロンの研究をし続けた。侑夏と洲栗の父親は、一日交代で洲栗を診ている。洲栗は、時折意識は取り戻すが、非常に危険な状態にあった。
私は何の成果もあげられなかった。カロンにはどの薬品も効かず、細胞が変形したまま戻らない。これを元に戻すことができれば、治るはずなのに。
洲栗が倒れて五日目の夜、私は洲栗の部屋へ向かった。このところはそれが決まりごとになっている。
洲栗の父は眠っていた。今日は侑夏が看病の担当のようだ。
「差し入れを持ってきた」
「ありがとう」侑夏は少し疲れているように見える。「ちょうどお腹減ってたんだ」
私は椅子に腰掛け、洲栗を見る。熱で乾燥した肌、やつれた体。元気な洲栗はどこへ行ってしまったのだろう。
「栄養剤を打ちながら様子を見てるんだけどね……」パンを食べながら侑夏が言う。「思わしくない。もう、発作が起こるたび緊張し通しだよ。今にも呼吸困難で危なくなりそうで」
侑夏の腕には洲栗からの贈り物があった。
「…カロンの解毒剤は、まだ完成していない。解毒剤の切れ端すらつかめない」
「さすらう皇帝だからね……。皇帝に牙をむけるのは、何だろう? 僕には何もない気がする」
洲栗の呼吸音が部屋を満たす。小さな体で、精一杯生き延びようとしている。
あと二日だ、洲栗。
二日だけ耐えてくれ……。
*
翌日は、少しだけ雨が降った。通り雨のようですぐに止んでしまったが、人々は喜んだ。
住居も確立した。食物も作れそうだ。よかった、この世界で命を脅かすものはない。助かったんだ。……そんな薄っぺらな安堵が、そこら中に満ちていた。
昼休みに、私は研究所を抜け出した。侑夏と一緒だ。住居に戻り、洲栗の様子を見て、すぐに出た。
「あ、ねえ、雁亜」侑夏は前方を指し示す。「あんなところに丘があったんだね」
私が前に見つけた、住居の前の丘だ。
「行ってみようよ」
侑夏はスクーターを走らせ、丘へ向かった。私も後についていく。
頂上でスクーターから降り、侑夏は砂の上に座り込んだ。
「すごい。建物がほんとによく見える」
予想通り、住居や外に出ている人々が一望できた。生き残った最後の人類たちが、必死で生き延びようとする様がよく見える。そう、この光景だ。
私も砂に座り込んだ。
「洲栗のことを考えているのだろう?」
尋ねると、侑夏は図星というように真顔になった。それくらい、見抜いている。洲栗が心配で居ても立ってもいられず、はしゃいでそれを隠そうとしていることくらい。
「そうだよ」と、侑夏は言った。「僕はあの子に生きててほしいんだ。何もできない自分がもどかしい」
「それなら私だって一緒だ。どれだけ研究しても、カロンの解毒剤を作れない」
「雁亜に不可能なら、誰にも不可能だ。結局カロンは倒せないものだったのかもしれない」
「十年以上研究して、至った結論がこれか」
全く滑稽だと思った。生まれて初めて本気で研究したというのに。自分の無力さを痛感するだけに終わった。
カロンは消せない。洲栗を助けられない。
私と侑夏は、もう何も言わなかった。
カロンの研究は、結局空振りに終わった。いつまで経っても何の取っ掛かりもできないのだから。昼間侑夏と話したときに、私はもう決めていた。カロンの研究をやめようと。
――もう、カウントダウンは始まっている。
ニコロは密かに時を刻んでいるのだ。
今日が最後の夜だ。私は侑夏を部屋に呼んだ。
「どうしたの、雁亜」
少し疲れた顔をして、侑夏が現れた。
「久しぶりに、一杯やらないか」
テーブルの上に、グラスとウィスキーが用意してある。地下研究所から持ってきたものだ。
「どういう風の吹き回し?」侑夏は微笑する。「でも、いい風だね」
向き合って座り、私たちは乾杯をした。
静かな夜だった。窓から入る風が、アルコールで火照った体に心地良い。最後の晩餐だな、と私は思った。
「お疲れさま……、雁亜」
そっと侑夏が呟いた。今まで聞いたことのないトーンの声だった。
「一体何に?」
「カロンの研究と、これまでの人生に」
ああ、侑夏は気付いているのだ。私がカロンの研究をやめたことに。
「侑夏も……。今までよく頑張ったな」
私の中で、ニコロが時を刻む音が聞こえる。
「雁亜ほどじゃない。雁亜には敵わないよ。だからね……、僕はずっと、雁亜に憧れてたんだ。まるであの洲栗君のように」
今初めて言うけどね、と呟き、ささやくような声で侑夏は話す。
「類稀な頭脳で研究者の頂点に立った僕の義姉……。ずっとずっと、憧れてた。雁亜みたいになりたいと思って、真面目に勉強して、研究者になったんだ。だから……、雁亜の研究所に行くことが決まったときは、本当に嬉しかった。人生で一番……」
侑夏は顔を上げ、私を見た。
「雁亜は、僕と初めて会ったときのこと、憶えてる?」
「研究所で、皆に紹介したときだろう」
「ううん……」侑夏は首を振る。「その前日に、僕ら会ってるんだよ。雁亜はきっと憶えてないけど。その前の晩、雁亜はずっと研究してたね。僕は雁亜の母親に連れられて、君に会いに行った。君の母親が僕を紹介したんだ。『義弟の侑夏君よ』って」
そんな話は全く覚えがなかった。
「雁亜は顕微鏡と向き合って、振り向かなかった。ただ、軽く返事をしただけだった。それだけで僕は嬉しかった。ずっと憧れてた義姉に会えたんだからね」
グラスの中で氷が鳴った。
「僕はずっと雁亜に付いて行こうって決めたんだ」
「百五十年後の世界までもか」
「そう……。ずっと一緒だよ。死ぬときだって」
あいにくだが、侑夏。
君が死ぬのは、私が死んだずっと後……。
私は最後の最後まで、君を裏切り続ける。
君は私を恨むかもしれない。
それでも私は、私の決断を変えはしない。
さようなら、侑夏。
グラスの中で、氷が溶けて消えた。
*
最後の朝が訪れた。
天候は快晴。
雨じゃなくてよかったと、少し安堵する。
昨日の夜、侑夏が部屋に戻ってから、急いで作った懐中時計。日の出の時刻で時間を合わせ、カチカチと音を立てている。現在、午前六時。タイムリミットまで、あと六時間。
窓の隣まで椅子を持って行き、じっと空を見ていた。
百五十年前も、同じことをしていた。
研究室以外、私は部屋に閉じ込められているも同然だった。
窮屈な部屋よりは、広い広い空を見るのが好きだった。そうしていると、まるで自分が自由になったかのように感じられる。
朝食の準備ができました。ドアの外で誰かが言う。
私は立ち上がり、空を見納めにした。
これから、望んだ景色を見る。
そして死んでいく。
それでいい……それが、私の望んだことなのだから。
朝食は、トーストとサラダ、パスタなどさまざまなものが揃っていた。侑夏は私の隣で食事をとった。いつもと同じ、他愛もない会話。これももう最後だ。
午前八時。調子が悪いと言って、研究所には行かなかった。
住居の中をうろつくと、畑を作る者、井戸から水を汲み上げる者、掃除をする者。生き延びようとする者たちが目についた。
侑夏が怪我をした場所へも行ってみた。もう瓦礫は片付けられていた。
失うのが怖いと、あのとき初めて思った。自分が天才でもないと自覚した。
竜巻、健康診断、引越し。この世界でも色々あったと、それらの全てを思い出していた。
午前十時半。
洲栗の部屋へ向かった。
中に入ると、都合よく誰もいなかった。栄養剤を取りに行ったか、火照ったタオルを濡らしに行ったんだろう。
「洲栗……。聞こえるか?」
ベッドに肘をついて、ささやいた。
すると、顔を真っ赤にした洲栗が、目を開けて私を見た。
「…かりあ……」
声が嗄れている。目も虚ろだ。
「ぼくは、しんでしまうの?」
私は洲栗の手を握った。
「一人では死なせない。決して洲栗を一人にしない。約束だ」
洲栗は一生懸命頭を動かし、頷いた。
「だから、もう少し我慢してくれ」
「ぼく…、がんばるよ」洲栗は荒く息を吐き出した。「さいごまで、がんばるから……」
「本当に……強い騎士だ」
洲栗は、にこりと笑った。
雁亜博士、と背後から声が聞こえ、振り向くと洲栗の父親がいた。
「具合はもうよろしいのですか?」
「ああ……」
私は立ち上がる。
「侑夏は一緒じゃないんだな。今日は看病の日じゃなかったか?」
「今日は具合が悪いので休むと、先程おっしゃっていました」
「侑夏が?」
そんな話は聞いていなかった。
「まあ、いい……」部屋を出て行く直前、父親に言った。「午後十二時。あと一時間半後、この部屋にいて洲栗の手を握っていてくれ」
「博士…?」
「頼む」
理由を訊きたがる父親を置いて、部屋を出た。
建物を歩き終えて、私は外に出た。部屋に戻る気は、もうなかった。運動する者、畑を作る者、井戸を使う者。五十六の命。
私は砂の上を歩き出した。時刻は午前十一時。
昨日侑夏と話した丘へ向かう。砂を踏みしめながら、一歩一歩、丘の頂上へ。
着いたときには、午前十一時十四分。
腰を下ろして、住居を見やる。本当に見晴らしが良い。窓の中で動く人影、外にいる人々、全てが視界に入る。
もうすぐ、私の望みが叶う。
見たかった景色が見られる。
洲栗を一人で死なせずに済む……。
タイムリミットはすぐそこ。刻々と時を刻む。
ようやく解放される。
活気の溢れる住居を、しっかりと見ておこう。もうすぐそれも消える。
目を閉じて、これまでの人生を思う。幼い頃は思い出したくもない……。もうすぐあの女から、解放される。
思いを馳せていると、残りあと十五分になっていた。十一時四十五分。
私は驚くほど落ち着いていた。むしろ、洲栗を一人にさせずに済むこと、解放されることで喜んでいた。ただ、最後に望んだ景色をじっくりと見られるように。それだけを考えた。
残り、あと十分を刻んだときだった。
背後で砂を踏む音が聞こえた。
「ご一緒していいかな。僕も」
驚いて振り向くと、いつものような笑みを浮かべた侑夏が立っていた。
歯車が狂ったことで、私は冷静さを欠いた。一体どうして侑夏が? 具合が悪いんじゃなかったのか? 別れは夕べ済ませたはずだ。どうしてまた会わなきゃいけない?
混乱を鎮めるまで数秒かかった。
「具合はいいのか」
「ん? 平気だよ」
侑夏は私の隣に座った。私は立ち上がる。
「研究に戻る。侑夏も洲栗の看病に戻って――」
「無駄だよ。もうすぐ皆死んじゃうんだから」
侑夏は、恐ろしくゆっくりと振り向いた。
「十二時まで、あと何分?」
「…何故私に訊く?」
「時計持ってるでしょう。夕べ部屋に材料があった」
「……八分だ」
「座りなよ、雁亜。ここが特等席なんだから」
侑夏に帰るつもりはない。が、私もここで退くわけにいかない。侑夏の隣に腰を下ろし、彼を睨んだ。
「これは命令だ。戻れ」
「僕が側に居ちゃ嫌なの? 死ぬときに一人になりたいの?」
侑夏の瞳の中に、焦った私が映る。
「……何を言っている?」
「僕も見たいんだ。雁亜と一緒に、人類が滅びる様を」
――まさか。
全て知っているのか――?
「あと、七分を切ったかな」侑夏は話し出す。「雁亜、全て計算した上でここを選んだんだね。引越しの時だよ。こうして、一番眺めが良い場所を選んだんでしょう。人々の最後の様子がよく見えるように」
声質がいつもと違う。突っ張っているというか、張りがある声……。侑夏はいつものように笑うのに、私にはその裏の、笑っていない顔が見えた。
「だから、僕は今日この時、雁亜はここに来ると思った。僕は雁亜を一人にしたくなくて、こうして来たんだよ。ずっと一緒だって、昨日言ったでしょう?」
時間が迫る。
最後の最後で、計算が狂った。大間違いだ。侑夏が一緒だなんて――。
「雁亜は人類を滅ぼしたかったんだね」侑夏は一方的に話す。「僕が余計なことをしたから、ニコロを研究者たちに発表したから、こんなことになったけど」
一体どうして?
私のシナリオじゃない。
侑夏は何も知らずに、全てが終わった後気付くはずだったのに。
何故――…
「僕は全て知ってるんだよ」
頭がぐらりときた。
侑夏の声が頭に響く。
この後の展開が予想できない。
全て知ってるだと? 私の計画を?
「邪魔をしに来たのか」
驚くほど弱々しい、掠れた声だった。
「見届けに来たんだよ。――ほら、あと三分を切ったんじゃない?」
十一時五十八分。あともう少し。
「一分を切った……もう、苦しみだす人もいるかもね」
侑夏の冷静な声。
そうだ……私は、見届けなくては。私の罪を。
まだ人々に異変はない。十二時きっかりに、それが起こるよう調節してある。
残り三十秒。
じっと目を凝らす。
馬鹿らしい住居。この狂った世界。
全て消えてしまえ――…
懐中時計がカチカチと鳴る。
針は十二時を回った。
「………」
私は、何も言えなかった。言葉にならない。
建物は、そのまま。人々も、変わりない。掃除をする者動く者働く者――。苦しんでいる様子はない。
生きている。
「死なないよ」
侑夏の声。
私は振り向けなかった。あまりのことに、体が反応しない。今竜巻が来ても、私は逃げられない。
「僕がすり替えたんだ」
ようやく目が侑夏をとらえた。
彼は、薄く笑っていた。
「ごめんね……、雁亜」
頭を整理して事態を把握するまで五分はかかった。私のシナリオでは、十二時きっかりに人々はもだえ苦しみ、死んでいくはずだった。そしてその光景を絶好の位置で見届けた私も、五分後には息絶える――。
それが何故、誰も死んでいない?
どうして侑夏がここにいる?
「まだ、時間はあるから。ゆっくり話そう」
風が吹いて砂が舞った。私はようやく口を開いた。
「全て知っていると言ったな。何を知っているというんだ」
いつもの私の口調だったので、少しホッとする。
「全部だよ。雁亜が何のためにニコロを開発したのかも、ニコロに何を混ぜたのかも」
侑夏は淡々と話し出した。
「まず、ニコロ……。これは、お母さんを殺すために作ってたんだね」
「見通していたのか。そのとおり、私はあの蛇女を殺すためにニコロを作った。あれなら、誰にも気付かれずあの女を殺せる……」
「ニコロに毒を持たせて体中に蔓延させ、心臓発作か何かに見せかけて殺すってとこ?」
「そんなところだ。そうすれば、私ほどの頭脳を持つ者でなければ、ニコロの仕業だと気付かない。自然死になるはずだった」
「一つ疑問が残るんだけど。雁亜ほどの頭脳があれば、ニコロを使わなくても都合よく殺せたんじゃない?」
妥当な質問だと思った。私は少しだけ笑う。
「それではつまらないだろう。あの女が私に押し付けた研究で、無様に殺してやりたかった」
そっか、と侑夏は呟いた。
私は何をしているのだろう。どうして侑夏とこんな会話を?
「でも、今度はお母さんじゃなく、人類を殺そうとしたよね。それも、こんな風に時間が経ってから」
私は侑夏を見た。
「本当にわかっているようだな」
「眠る前にも言ったでしょう。雁亜の考えてることはわかるって」
侑夏は一度顔を伏せ、もう一度上げて天を仰いだ。
「百五十年後の世界まで辿り着く方法は――ニコロに毒を含ませ、仮死状態にする。それから解毒剤のニコロを打ち――起きる。僕は不思議だったんだ。これなら、ニコロじゃなくてそこらの毒薬を注射し、また解毒剤を注射して起きるって方法でもいいんじゃないかなって。まあ、あの当時はニコロが開発された直後だったから、ニコロを使ったのかとも思ったけど」
そう、ニコロでなければならなかった理由がある。
それを今、侑夏が口にしようとしている。
「時間が正確に計れないからだよね。他のでは、雁亜の計画に差し障る」
その通り……。
心の中で息を吐き出す。
「目覚めるときの解毒剤のニコロ。あれが、毒だったんでしょう。確かにあれは眠るときの毒を消す解毒剤。だけど、その解毒剤は人体に毒でもあった。人々は新たな毒を持って目覚めたってわけだ。時間が来たら毒が回り、命を落とすように調節して」
「ああ……、その調節が難しかったな。五十四人の身長体重健康状態を全て調べ上げ、毒の回り具合を推測する」
「雁亜の計画は完璧だよ。今日午後十二時、人々の体内で眠っていたニコロが突然暴れだす。そのはずだったんだよね」
「そうならなかったがな。ようやく落ち着いて考えられるようになった」
「うん、いつもの雁亜の口調だ」
侑夏。全てはこの義弟が握っている。
「……君はいつ私の計画に気付いた?」
「百五十年前……眠りにつく二晩前だよ。一応、解毒剤をチェックしてたら、何だかおかしいなと思ってね」
「大したものだ」
おそらく、侑夏以外の研究者では気付けなかっただろう。解毒剤が毒だなどと。
「僕は急いで、中身を本物の解毒剤に代えた。五十四人全部ね。休む暇もなかったよ」
「成程……。それで誰も死ななかったのか」
この義弟は、私よりも一枚上手だった。百五十年前からずっと、私に黙っていたのだ。全てを知っていることを。
「雁亜は人類を滅ぼしたかったの?」
「そうだ」断定的に答えた。「あの女を殺し損ねて、さらに、私に人類が生き延びる計画を立てろと言う研究者に腹が立った。周りを見捨て、自分たちだけ助かろうという厚かましさ。シェルターが足りないだの何だの言っていたが、結局は自分の保身のためだ。私は人類を滅ぼし、その最後を見届けてやろうと思った」
ニコロに毒薬を含ませた瞬間。私の罪はもう始まっていた。
「ただ滅ぼすのなら、簡単だ。目覚めのニコロを完全な毒にして、二度と起きないようにしてやればいい。…だが、それではつまらない。愚か者に相応しい最後がある」
私は住居を見た。まだ生きている、その愚か者たち――。
「これから生き延びられる。助かった。…そんな希望に満ちているときに、叩き落してやりたかった。そしてその瞬間を、特等席で見たいと思った。だから時間をかけ、引越しをし、この場所を選んだ」
私は侑夏を振り返る。
「人類は滅びるべきではないと言っていたな。だから、解毒剤を代えたのか」
「そうだよ。この人たちの罪はこの人たちで償うべきだと思ってね。それに、無駄に命を刈るのは間違ってると思ったんだ」
侑夏も住居を眺めていた。都合よく生き延びた罪人たちを。
「腑に落ちないことがあるんだけど」と、侑夏が切り出した。「雁亜の計画では、どうせ皆死んでしまうよね。なのに何故、洲栗君を助けようとしたの? カロンの解毒剤を死に物狂いで研究して」
洲栗の温かい手を思い出す。最後のときの、あの笑顔さえも。
「…洲栗は、一人ぼっちが嫌いだ。一人で眠ることも出来なかった位なんだ。そんな洲栗に孤独な死を迎えさせるのが嫌だった。今日まで生き延びて、一緒に死ねば、一人じゃないだろう」
「そう…」
また、風が吹いた。砂が目に入るといけないので、瞼を閉じた。
目を開けると、侑夏がこっちを見ていた。
「雁亜。今何時?」
「十二時…、十四分」
侑夏はまた、そう、とうつむいた。
「もう一つ、疑問があるんだ」
何だ、と私は尋ねた。
「どうして僕には、本物の解毒剤を使ったの」
それは侑夏が一番訊きたかったことだ、と直感した。案の定、侑夏の眼差しはこの上なく真剣だった。
「五十四人の人々と、雁亜……。雁亜の分は、人々の死を見届けられるよう、少しだけ遅く毒が回って死ぬようになっていた。だけど、僕のには……」
苦しそうに言葉を切って、顔を上げた。
「僕のニコロには毒が入っていなかった。本物の解毒剤だった」
つまり、と侑夏は続ける。
「僕だけは死なない。生き延びられるようになってたんだ」
侑夏の瞳には迷いが浮かんでいた。取り乱した様子。訊きたくないけど、訊かなきゃ――。
「僕だけこの世界に残すつもりだったんだね。たった一人で……。雁亜もみんな、消えてしまった世界で。ニコロを発表したことで、お母さんの死を妨害した僕が憎かった? だから僕に孤独を与えようとしたの?」
答えて、と侑夏は言い募る。
澄み渡った青い空を見上げる。私の心は落ち着いていた。
「最初は、侑夏も殺そうとしていた……」ゆっくりと、私は話し出す。「だが、侑夏のニコロに毒を入れようとした瞬間……、手が止まったんだ。そして動かなかった。どうしても、出来なかった……。義弟だからだろうか。何故だかわからないが」
侑夏を振り返る。そして、彼に言った。
「君を殺せなかった」
それは、今までで一番感情的な言葉だった。
「侑夏だけは、生きていてほしかった」
これが根底の、奥底にある感情なのか。侑夏を死なせたくない。たとえ誰が死んでも、私が死んだ後も、生きていてほしい――。
侑夏はしばらく目を閉じていた。
それから不意に、音も立てずに瞼を開けた。
「ありがとう……、雁亜」
それは義姉に向けられた言葉だった。
何に対してのお礼かは、わからない。わからないまま受け止めておこうと思った。
すっきりしたが、何処か切ない……。この青い空のように。
突然、侑夏の呼吸音が乱雑になった。隣で苦しそうにもがく音。
「侑夏…?」
彼は胸を押さえ、全身に力を込めている。引きつった顔、苦しそうな呼吸。
「…まさか……」
「ごめん……、雁亜」
洲栗に似た、掠れた声。
片目が開いて、私をとらえた。
「僕は、ずっと、謝りたかった……。君の計画を、二度も邪魔してしまったこと。だけど僕には、ああするしか……」
「一体何をした!」
ドサリと音がして、侑夏は砂の上に倒れた。
「人々が死ぬ様は…、見せられないけど……、僕で我慢…してくれないかな……」
途切れ途切れの言葉。
まさか。
「あの時間差の毒を、自分に……?」
侑夏は顔の筋肉を動かし、何とか微笑んでみせた。
「ほんと、時間を調節するの、難しいね……。ちょっと、ズレてるみたい……。雁亜みたいに、上手くは、な……」
「侑夏!」
叫んだ私の視界がぐらついた。
一瞬にして、激しい心音の高鳴りと、呼吸困難が起こる。
息ができない…! 体が熱い!
苦しい……!
「やっぱり、僕は、半人前だ……」
侑夏の顔が隣にあった。ああ、私も倒れたのか。
「雁亜の毒は、僕が倒れて五分後に…、設定した、はずなのに……。僕より先に、死なないでね……僕が死ぬところを、見届けてから……」
「侑夏……」
体に力が入らない。視界が狭まる。
「雁亜を、一人にはしないよ……。一緒にいこう」
私の手に、侑夏の手が触れた。
ああそうか、だから……。
死の直前で考えたことは、ニコロのことだった。やっぱり私は骨の髄まで研究者なのかもしれない。
ただ、最後に呟いた言葉は、義弟に向けての言葉だった。
「おやすみ……。侑夏」
舞い上がる砂の波。果てしない空。私は、この地に眠る。
乾いた風の中で、私は、満足だった。
侑夏は最後まで私と共にいてくれた。それで十分だった。
未練もなく死ねるのは、何と幸福なことだろう。
そう、幸福……。
生まれて初めて、それを味わっている。
なあ、侑夏。
幸福を感じるまで百五十年もかかったなんて、
君が知ったら笑うだろうか?
侑夏の睫毛。形の良い鼻。
そう、この少年は、私の義弟。
半分だけ血のつながった……。
「!」
完全に目を覚ますと、私は、砂の上に横たわっていることに気付いた。隣に侑夏がいる。
「…死後の世界か……?」
そんな非科学的なこと、信じてはいない。
なら、ここは何処だ?
ボロボロの住居が見える。井戸もだ。
「生きている……?」
心臓に手を当ててみた。左手の脈を測った。
確かに、鼓動を感じる。
毒で倒れて、それから……。どうして私は生きているんだ?
ハッとして、私は侑夏の体を揺さぶった。
「侑夏。生きているか? 侑夏!」
両手で、ありったけの力を込め、肩を揺する。
「んー…」
「侑夏!」
そっと目が開き、青とグレーの混じった目がのぞいた。
全身の力が抜け、その場にへたり込んだ。
「え…」侑夏も起き上がる。「え、僕、生きてる? ここって死後の世界?」
「全く…、思考回路が私と一緒だな」
気が付くと私は笑っていた。声をあげて、思いっきり。
涙を流して、私たちは笑う。今までの人生分笑ってしまうような。
「どうして私たちは生きているんだろうな」
「わからないよ……、はは、何でだろうね。僕、何かミスしたのかなあ」
私たちは笑い続けた。腹を抱えて、足をばたつかせて。
そしてその後、異変に気付いた。
「! 雁亜っ」
「……侑夏?」
気付くのも同時だった。
「どうしたの、その姿!」
「どうしたんだ、その声」
声が揃って、私たちはお互いの顔を見つめた。目が離せなかった。少年の侑夏の顔が、大人びているのだ。更に、声変わりまでしていて、今では低い声になっている。
「雁亜が大人になってる……。今は二十歳か、ちょい過ぎって感じだよ」
「侑夏こそ。今は十六……十八くらいにも見えるな」
そしてその後の推論も、二人一緒だった。
「まさか」
「カロンが消えた?」
幼児化で成長を妨げていたカロンが消え、一気に年をとったに違いない。おそらく、幼児化が始まった年まで成長が戻ったのだろう。となると、私は今二十歳の体だ。
「カロンが消えたなんて……」
呆然と侑夏が呟く。
「……そうか。わかった」
私の中で、全てが整頓され、きっちりと方がついた。
「わかったって?」
「私の推論は間違っていなかった」
「僕にわかるように説明してよ」
侑夏に急かされ、私はどこから切り出したものかと考えた。
「君が大怪我したとき、一瞬にして治っただろう。私のこの肩もだ。実は骨が折れていたらしい」
「ああ、あれ。打ち所がよかったんじゃないの?」
「違う。不思議に調べたんだが、傷つけられた細胞が一度全て死に、またすぐに新しい細胞ができていたんだ。恐ろしいまでの再生能力だった」
「それって……」
「私は、この治癒力はニコロの効用だろうと思った。百五十年前の実験ではこんな効果がなかったから、目覚めたときの解毒剤兼毒とニコロが何らかの反応をきたし、治癒力が増加したのだろうと」
「成程ね」侑夏は頷く。「僕もそう思う。だけど、ニコロにそんな副作用が……」
「今までずっと腑に落ちなかったんだ。目覚めたときのニコロの効用ならば、侑夏には絶対に再生力がないはずだった。侑夏だけは本物の解毒剤を使っていたから。だが、侑夏にも治癒力があり、私にもあり、他の人たちにはなかった。それも当然、」
「解毒剤兼毒のニコロを使っていたのは、僕と雁亜だけだったから!」
「その通りだ」
私と侑夏は目を合わせて笑った。
「細胞が一度全部死んで再生する……。だから、カロンに毒された細胞は死んで、新しい細胞が現れ……、今こうしてカロンが消えてしまったわけだ」
「そう、そしてその恐るべき治癒力は、侑夏の仕込んだ毒までも消してしまった。だから私たちは、こうして生きている」
「たぶん、細胞に傷がつくと生まれ変わるシステムなんだろうね。だから、ニコロの時間差の毒が現れて、すぐに細胞を再生し出した――カロンも消し去る、恐ろしいまでの力で」
本当に……。
最後の最後で、何てどんでん返しだ。
私のシナリオは、完璧に書き換えられてしまった。
「さて……」侑夏が呟く。「死に損なってしまったけど、これからどうしよう?」
「私を裁判にかけてもいいぞ。五十四人の殺人未遂で」
「五十五人だよ。雁亜も雁亜を殺そうとしたんだから」
「どっちにしろ大量殺人だな。で、どうする。裁判にかけるか?」
侑夏は首を振った。
「それなら僕だってお相子だ。天下の雁亜博士を殺そうとしたんだからね。この件は、二人だけの秘密にしておこう」
「異存はない」
私たちは目を合わせて、また笑った。
「雁亜は一度死んだんだよ。今雁亜の体にあるのは、新しい細胞だからね」
「ああ……。妙にスッキリしているのは、悪い部分が死んでしまったからだろう」
あの女も、もう私の中にはいない。
「人類を道連れに死のうと思っていたのに……。空振って、そんな気もしなくなってしまったじゃないか」
意地悪く侑夏を見ると、彼もまた意地悪く微笑み返した。
「雁亜と一緒に死のうと思ったのに。これじゃ、死ぬときまで一緒かわからないじゃないか。どっちかが先に寿命がきたら、終わりなんだから」
私たち二人の望みは、全て掻き消えてしまったわけだ。
この砂のように、風に運ばれて、どこかへ消えていったのだろう。
後には何も残らない。
ふと、泣きたい気持ちになった。この世界には、私と侑夏。
侑夏まで居なくなってしまったら、私はどうなるのだろう。取り乱して後を追うだろうか。
苦しいほど人に依存している。侑夏の存在が私の支え。何て不確かで不安定なんだろう。
それでももう、二人で生きていくしかない。
いや、二人じゃないか……。
「やるべきことがあったな」
私は立ち上がって、住居を眺めた。
「そうだね。まだ、助ける人がいたね」
私たちは、住居に向かって走り出す。
砂の上に、二人分の足跡。
待っていろ、洲栗。今、助ける。
「あ、ちょっと待った雁亜!」侑夏が急ブレーキをかける。「あの、毒のニコロ、研究所だよ。取って来ないと」
「そうだったな。それに、注射する量を誤ったら危ないかもしれない」
「大丈夫だよ、ともかく洲栗君にあの再生能力をつけさせればいいんだから。行こう!」
侑夏が私の手を引いた。
温かな侑夏の手。
それは、この世界の全てに通じている。
私の生きる理由……。
これから私の生きる全てを、君の頭の中に刻んでおいてほしい。
そうして、私が先に死んだならば、それを思い出してくれ。君の記憶の中で、私たちはずっと一緒だ。そしてその記憶が死んだとき、二人一緒に消え去るんだ。
この世界に軌跡を残す必要はない。ただ、君の中にだけ。
これからの人生を、全て捧げよう。
私の大切な、その笑顔に添えて。
カリアの綱


