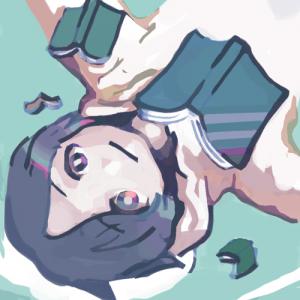個人的に200円程度で済ますことのできる殺人
三年前に肺がんで死んだ伯父から小さい頃にもらった金属バットで今俺は伯母を殺した。
多分死んでると思う。頭は割れてるし、そこから脳髄が飛び散って部屋の片隅に散乱してるし、手はピクリとも動かないし目は瞬きしないし、なにより俺がどれだけ不機嫌だろうとお構いなしにしわくちゃの顔を更に歪ませて作った笑顔が無かった。
俺は血なまぐさい和室の真ん中に座り込み、頭を両膝の上に乗せて三回だけゆっくりと深呼吸した。すると頭は驚くほどすっきりして、手先のしびれも緩和されていった。しばらくその体勢で呼吸を整えてから顔を上げ、伯母の死体を背景に両手を視界に入れてグーとパーを交互に作り、自分の手が指先までちゃんと自分の意思通りに動かせることを確認してから立ち上がった。
脱衣所で返り血が染み込んでしまった服を脱ぎ、一応洗濯機に入れる。給湯器をオンにして熱めのお湯を出し、適当なバスタオルをそれで濡らしてから地肌についた皺でも生えてきそうな血を拭き取る。パンツ一丁で玄関まで行き、ボストンバッグに入れておいた換えの服を着て外に出ようとしたけれど、一旦踏みとどまって踵を返し、伯母の死体がある居間へ再び向かう。
やっぱり伯母は死んでいて、生き返りそうにもなかった。完全に死んだ。殺した。俺が殺した。完全に俺が伯母を完全に殺した。
俺は居間の中にある物を伯母以外全てごった返して古臭い長財布を見つける。中には四万六千七百二十二円入ってたから全部自分の財布に突っ込んだ。俺の所持現金は六百二十円から四万七千百四十二円になった。
外に出てみるとやけに清々しい気持ちで星空を見上げることができて、体はいい感じに火照っていて今なら勢いだけでフルマラソン走れるんじゃないかってくらいだった。けれど俺は四十二.一九五キロを走るわけでもなく歩いて一キロ弱の駅に向かった。
電車の中にはくたびれたサラリーマンと夜遊び大好きそうな大学生っぽいやつらが数人乗ってて、座席も十分座れるくらい空いていたけど俺はなんとなく座らずに吊革掴んで立ったまま発進を待った。
電車に揺られながらあくびを噛み殺していると吊革を掴んでいたはずの自分の右手が無くなっている感覚に襲われた。慌てて右手に目をやるけど、そこにはちゃんと吊革を掴んでいる俺の右手が存在していて、ちゃんと手首から腕まで繋がっていて、それは俺の右手だった。だけど感覚がない。俺の右手の感覚がない。ふと気づけば左手の感覚もなかった。でも左手もちゃんと俺の体に繋がっていた。俺は左手でグーとパーを交互に作ってみようとするが、思ったように手が動かない。まるで左手に内包されている肉が全部凍結してしまったかのように動かない。同じように右手も吊革を離すことがうまくできない。俺は目を閉じて深呼吸を繰り返す。できるだけ多くの酸素を右手と左手の隅々まで行き渡らせるように、丁寧な深呼吸をゆっくりと繰り返す。七回くらい深呼吸をしたあたりでじんわりと両手の感覚が戻ってくる。俺はまだまだ深呼吸を繰り返して血液をフルで循環させる。
電車が止まり、南大沢に着く頃にはなんとか俺の両手は俺の両手に戻っていた。だけどまだどこかよそよそしい感じは残っている。親指がうまく動かせなかったり、薬指がちゃんと曲がらなかったり。
改札を出て、小さなエスカレーターに乗って下の道路に降りる。駐輪場に一台だけ自転車が止めてあるのが見えたので、そちらに歩く。
自転車は駐輪場にロックはされているが、車輪にチェーンが巻かれているわけでもなかったので、俺は精算機に六番を打ち込み二百円精算してやる。誰の所有物なのかもわからない自転車に跨って夜空を見るとひどく冷たい風が顔にぶつかって砕けてどっか行った。
さっきまではあんなに体が火照っていたのに今はどうしてか酷く寒い。こんなに寒いんだったら手の一本や二本凍りついて動かなくなっても当然だとグリップを掴む両手を見てみるけれど、一応それらはまだ俺のものであってくれるらしい。俺のものじゃない自転車のグリップをしっかりと掴む俺の手。俺の手ってこんなに小さかったっけ。縮んだんだろう。まあいいや。
それにしてもなんでこんなに寒い?
そりゃ年も開けて間もないこんな時期のこんな時間だから寒いのは当然なんだけど、でもさっき伯母を殺した時はもっと暖かかった。
なんで伯母を殺した時に見上げた星空はあんなにも暖かかったのに、知らない誰かの自転車に跨って見る夜空は冷たい?
人殺しなんてやった後に窃チャなんてスケールの小さいことやったから、スケールどころか心身ともに縮こまってしまったとでも言うんだろうか。これじゃあフルマラソンどころかシャトルランすら満足にできそうにない。
あーあ。
なんとなく不完全燃焼な感じ。
伯母を殺したことでハイになって完全燃焼すっ飛んで電気毛布にでもなった気持ちだったのに、今では焦げた小さな木彫りの狐みたいになってしまった。
最近では二十四時間営業の喫茶店って少なくなってきてるらしいけど、南大沢には意外にも二十四時間営業の喫茶店がある。ガソリンスタンドと提携しているその喫茶店はその特性上利用客もいつの時間でもちらほら居て、俺が入店したときにも全席の四分の一くらいは埋まってた。俺はカフェインを摂ると胃が痛くなってしまうタチなので適当にオレンジジュースのLサイズを頼む。別にLサイズのオレンジジュース持って喫煙席座ったって誰も文句は言わないはずだ。言ってきたら殺してやる。
換気の効いてない煙たい喫煙席に座って、タバコを喫おうと一本取り出したときに灰皿がないことに気づいて隅に積み重なってるのを持ってきて火を点ける。はータバコ美味い。伯母殺した後に喫茶店で喫うタバコ美味い。オレンジジュースも意外に美味いし、言うことないなもう。
しばらく俺がタバコを喫い続けてちまちまとオレンジジュースを飲んでいると、スマホがブルッと震えたのをポケットの中で感じた。取り出して見るとメールで友達の成沢木津句(愛称キック)が今何してんの? と訪ねて来たので、喫ってる途中のタバコを灰皿に押し付けてから伯母殺して暇だから喫茶店いる、と返事を打って送信した。次のタバコを取り出そうと箱の中を覗くがどうやらメールを返信するために消したやつが最後の一本だったらしい。やってくれたぜキックの野郎。
すぐに俺の送信したメールに返信が来る。
Re.俺も暇だから行ってもいいか? (どこの喫茶店?)
Re.イイよ来いよ (いつものガソスタのとこ) その代わりタバコ買って来て。切れた。
Re.おっけすぐ行くわ (お前カフェイン摂れないくせによく喫茶店行くな) 銘柄は?
Re.うるせ、 銘柄→ラッキー
Re.おっけおっけ。
キックが来るまでの間、俺はタバコがないからオレンジジュースも飲む気になれなくて、ずっとテーブルの上に両手を乗せて指をわちゃわちゃやってた。動くじゃん右手、握れるじゃん左手。どうしてさっきはあんなによそよそしかったんだろう。俺と一緒に伯母を殺した両手なのに。もはや運命共同体なのに。これからも一緒にやっていこうぜ、じゃなきゃ困るって。タバコ喫えないじゃん。ジッポライター使えないじゃん。オレンジジュース飲めないじゃん。電車の吊革掴めないじゃん。バット握れないじゃん。伯母殺せないじゃん。
いやいや伯母はもういないって。厳密には死体はあるけど、その死体の中身、肉とか骨とかじゃなくてもっと本質的なモノ(魂とか……あとなんだ。なんもないか)はもうこの世界にはいなくて、多分白くて広くて暖かい場所に行ってしまったんだろう。いいこった。それはいいこった。あんなボロ屋の和室でブラウン管のテレビ見ながらせんべいで歯を鍛えてお茶啜るだけよりかは、白くて広くて暖かい場所で俺のことしわくちゃの笑顔で見ててくれたほうが全然マシだって。感謝してくれよ。あとキック早くタバコ持ってこいよ。
気付いたら喫煙席には俺以外誰もいなくなってた。煙たいのも感じなくなってた。てかこんなに広かったっけ喫煙席。軽く三十席はあるぞ。ん? ここ喫茶店の喫煙席じゃないじゃん。教室じゃん。俺が通ってた小学校の教室じゃん。そう気付くと隣には小学生の背丈に縮んだキックが座ってた。反対の席には中学二年生の時に列車衝突事故に巻き込まれて死んだ神田三奈木(愛称カンミ)が座ってる。
「ようカンミ、久しぶり」
「久しぶり、ちーくん」
「お前死んだんじゃなかったっけ」
「お前がそう思うんだったらそうなんだろうな」とキックが横槍を入れる。「ただしお前ん中だけではな」
お前には何も訊いてねえよキック。それよか早くタバコ持って来い。
「まあまあ落ち着けって、両手震えてんぞ」
「そうそう、ちーくん両手真っ白になってる」
「え?」
本当だ。
俺の両手は真っ白になってて、指紋すらも見当たらない。まるで石膏で作られたみたいにサラサラの真っ白けっけになってしまっていた。右手に鉛筆、左手に金属バットを持ってる。
教室のドアが開いてキョーカンが入ってくる。キョーカンって言うのは担任の浦田先生の裏のあだ名。厳しくて教官みたいだからキョーカン。
キョーカンは俺の両手と同じくらい白いチョークでカッカカッカと黒板に文字を書き始める。
『人殺しはなぜいけないか』
あー思い出した。
そういえば、俺が小学生の時にいじめられっ子の関峰くんが死んだんだった。そしてその次の週の道徳の時間にキョーカンがいきなりこんなこと言い始めたんだ。
「人殺しに関わらず、人間が命を寿命以外で奪われたり、自ら断ったりすることは、なぜ世間的にいけないことだと言われているか、分かるやついるか?」
キョーカンのその問いに、クラスメイトは皆黙って沈黙を作った。だって何言ったってキョーカンは怒るだろうと皆知っていたからだ。
その沈黙を受けてキョーカンは教卓をトントンと叩く指を一旦止めて、喋り始めた。
「なぜ命が理不尽に奪われるのがいけないのか。その答えは一言で説明できる。いいかよく聞け」そしてキョーカンは言った。「だって命失くなったら楽しいことできないだろ?」
俺は人生で初めてキョーカンの言ってることに関心した。確かにな。生きてなきゃ楽しいことできないもんな。死んでしまったら何もできないもんな。でも生きていても楽しいことなんてあるか? あんまりないぜ楽しいこと。だけど死んだら絶対楽しいことできないんだろうな。そう思って心の中で頷いた当時の俺を俺は思い出した。
「ちーくんはなんで人殺しはいけないと思う?」
カンミが訊いてくる。
「いや、今キョーカンが言ってたじゃん。死んだら楽しいことできないって」
「それは死んだ人の目線の話でしょ。あたしは殺した人の目線のことを聞きたいんだよ」
「なんで俺に聞くんだよ」
「だってちーくん伯母さん殺したじゃん」
「なんで知ってんの?」
カンミは何も言わずに俺の左手を見た。俺も俺の左手を見ると、汚い血で汚れて凹んだ金属バットが握られていた。更には教卓の上には伯母の死体。でもよく見たらそれは死体じゃなくて、生きた伯母だった。生きている伯母が、何も言わずにしわくちゃの顔をさらに歪ませて作った笑顔でこっち見てる。
おいおい勘弁してくれ殺したはずじゃんあんた。しつこい笑顔だな見飽きたぜそれ。俺は席から立ち上がって伯母に向かって行こうとしたところで左手をキックに掴まれる。
「離せよキック、伯母殺せないじゃん」
「何言ってんだよちーお前授業中だぞ」
は?
授業中じゃないってここ教室じゃないから、喫茶店だから。二十四時間営業の喫茶店だから。てかキックお前いい加減早くタバコ持って来いって。
「おまたせい」と言ってキックが俺の向かいの席に座る。そんでラッキーの新箱を投げてよこす。
「おう」俺はタバコを受け取る。「キック、俺今寝てた?」
「いや知らんけど起きてたように見えたぞ。目開いてたしなんか両手わちゃわちゃしてたし。何寝不足?」
「あーまあそんなかんじ。とりあえずタバコサンキュ」
「おう」
キックはアイスコーヒーらしき液体をストローで啜ってからタバコを取り出して、咥えて火をつけようとするが、その動作は止まる。
「ああ灰皿ねえや」
「持って来いや」
「ここ灰皿どこに置いてあんの」
「そこそこ」と俺はさっき俺自身が灰皿を取得した場所を指差すが、そこには灰皿なんて置いてなかった。
「ないやん」
「店員に言って貰ってこいや」
「おっけ」とキックはタバコを箱にしまって席を立って行った。
俺はラッキーの封を開けて一本取り出して火をつける。はーやっぱタバコ美味いわ。
すぐにキックは店員に水に濡れた灰皿を貰って俺の向かいの席に戻ってくる。そしてマルボロのブラックメンソールに火をつける。
「お前寒いのによくメンソールなんて喫えるな」
「寒いの関係なくね?」
「でも暑い時ってメンソール喫いたくならね?」
「それは分かる」
「じゃあ寒い時はメンソール喫いたくなくない?」
「それは分からん」
あっそとそれ以上会話を続けるのをやめて俺はオレンジジュースを飲む。いい加減こんな夜中にタバコバカバカ喫ってオレンジジュースなんて果汁のあるもん飲んでたらカフェインじゃなくとも胃が痛くなってくる。
「あーお腹痛い」
「あ、そういえばさ」とキックは俺の腹痛を無視したように話題を振ってくる。「お前伯母殺したって本当なん?」
「殺したよ」
「まじか」
「てかなんで知ってるん?」
「いやお前がメールで言ってたやん」
ああ、そうだっけ。覚えてないわもうそんなこと。
「何で殺したん?」
「金属バット」
「いやいや凶器じゃなくて理由よ」
「そこ求める?」
「普通そうでしょ」
「理由なんて今更覚えてないわ。多分殺したかったから殺したんだろ」もう伯母なんてどうでもよくない?
「なに、衝動的な感じ?」
「そうそうそんな感じ」
「軽いなーお前」と言ってキックはタバコの灰を灰皿に落としてコーヒーを飲む。
「良いなお前、コーヒー飲めて」
「え、ちーお前コーヒー嫌いなんじゃないの?」
「違えわ。むしろコーヒー好きだわ」
「じゃあなんでオレンジジュースなんて飲んでるん」キックはタバコで俺のオレンジジュースを指す。「しかもLサイズ」
「悪いか、殺すぞ」俺は右手で握りこぶしを作ろうと思ったけれど、また右手が言うことを聞かない。
「お前は悪くなくて俺が悪いわ。殺さないでくれ。だからその振り上げた中途半端な手を降ろせ。なんだ、波動拳でも出すのか」
「いや実はなんか両手が言うこときかないんだよね」
「麻痺してるってこと?」
「多分そんな感じ」
俺は上げた腕を降ろして、咥えたタバコの火を灰皿に押し付けて消した。だけれどその一連の動作はまるで要介護レベルの老人みたいなぎこちなさだった。
「病院行けば?」とそんな俺を見て苦笑いを作ったキックが言う。
「何? 病院行って先生に伯母殺してからなんか両手が痺れるんですよねぇとか言うんか。一発で牢獄連れてかれるわ」
「いやいやお前人殺しといて捕まらずに済むとでも思ってんのか」
「思ってちゃ悪いか」
「全然悪くない」とキックは言う。「お前は見た目は悪だけど、基本的に良いことしかしない奴だからな。悪くないよ」
「そう言ってくれるのはお前だけだよ」
「だろ、俺カッコイイべ」
「かっこよくはないな」と言いながら俺はまたしてもぎこちない動作でタバコに火をつける。「ああ、あと俺窃チャとかいうすげーちっこいこともしたわ」
「お前それは駄目だろ」キックはちょっと真面目な表情で俺を咎めた。
「お前の価値基準が俺にはわからんよ」
「自転車盗んだらその持ち主絶対困るじゃん」
「だが、俺の伯母を俺が殺したところで困る人は居ないから、別に人殺しは良いと?」
「まぁ、そんな感じだな。ちーが伯母殺したところで俺の中で困る人は居ないけど、自転車が失くなったら困る人はすぐ思い浮かぶもん」
あー確かにそう言われてみるとそうかも知れない。俺はなんてことしてしまったんだろう。
「俺は取り返しのつかないことをしてしまったのかもしれない」
「いや取り返しはつくだろ。あとでその自転車置いてあった場所に戻しておこうぜ」
「やだ、めんどい」俺はうつむいて煙を吐きながら言う。タバコの煙が目に染みて涙が出そうだ。
「そんなこと言ってるから両手麻痺してるんじゃねえの?」
「マジ? そのせい?」
「俺はそうだと思うね」とキックはタバコを喫いながら言う。
「ところが残念。窃チャする前から手は麻痺してます」
「今の俺はちょっとかっこ悪かったな」
「だな」
そして二人で軽く笑って、タバコを喫う時間に入る。無言で二人で煙を吐いたり喫ったりしてる。とかやってるともう時刻は朝方で、いくら真冬と言ってもあともう少しで日が登りはじめてくるだろう。喫茶店の喫煙席から見る空は少しだけ明るく白みがかっていて、昨日が本当に昨日に確定して今日という一日が今日として確定していく。
いつのまにか喫茶店に客は俺たち以外おらず、店内は酷く静かになっている。
「あのさーキック」と俺は尋ねる。
「なにさ」キックがこっちを見る。
「小学校の時キョーカンが言ってたこと覚えてる?」
「あー懐かしいなキョーカン。しかしキョーカンの名言集なんていちいち覚えてないわ」
「あの、あれよ、関峰くんが自殺した次の週の道徳の時間に言ってたこと」
「あれね、なんだっけ……人殺しがなぜいけないかってやつだ」
「それそれ」
「確かに人殺したら楽しいことなんて出来ないよな」
ん? 違くね?
「人が死んだら楽しいことなんて出来ないって話じゃなかったっけ」
「あれ、そうだっけか」
「まあどっちでもいいか」
「いや、ハッキリさせておこうぜ」とキックは身を乗り出してくる。
「お前いきなり熱くなんなよ」と俺はキックの顔に煙を吹きかける。
「いやいやハッキリさせておこう。そうしないと俺は気がすまない。そうしないと俺はお前を許さない」
「勘弁してくれ」
「勘弁してほしかったらこれからやるちょっとしたゲームで俺に勝つことだな」
「お前好きねそういうのほんと」俺はこうなったらキックの思い通りにさせるしかないことを知っているので諦めた。「じゃあさっさとゲームを始めてくれ」
「お前なんかデュエリストっぽいな」
「意味分からんから」
「まあまて、……そうだなー」と言ってキックはあたりを見渡し始めた。ゲームに使えそうなものでも探してるんだろうか。しばらく店内を見渡していたキックだが、ゲームに使えそうな素材が見つからなかったのか目の前のコーヒーが入ったグラスを指差した。
「このグラスに入っているのは、アイスコーヒーでしょうか、それともコーラでしょうか」
「それクイズじゃん」
「クイズバカにすんな、クイズだってゲームだ」
「そうかい」と言って俺はキックの前に置かれたグラスを見た。「どう考えてもコーヒーだろ、さっきお前自分で言ってたじゃん」
「いや、俺は自分でこれがコーヒーだなんて一言も言ってないぜ」
え、そうだっけ。
「いやだとしても流れ的にコーヒーだろ」
「FA?」
「FAFA」
しばしの沈黙を作るキック。俺はタバコをふかしてキックが音を上げるのを待つ。もうそろそろ本格的に朝になりそうだ。
「不正解」とキックは言った。
「いやんなわけないじゃん。ふざけろ」
「これはコーラです。まじでコーラです。飲んでみる?」
「いやいいわ。コーラにもカフェイン入ってるから」
「え、そうなん?」
「またひとつ勉強になりましたね」
「本当ですわね」
そんで二人してお上品に見せかけた下品な笑いを店内に響かせる。
「もうそろそろ行こうぜ」とキックはタバコを灰皿に押し付けて、グラスの中身を飲み干して言った。
「何しに、どこへ行くん」俺もつられてとりあえずオレンジジュースを飲み干す。
「盗んだチャリ返しに行くんだよ」
「え、まじで返しに行くの?」
「当たり前だろ。それで全部チャラだ」
「伯母殺したこともチャラになんねえかな」
「なるんじゃね?」
「まじで? たった二百円俺が損するだけで?」
「なるっしょ。少なくとも俺の中ではチャラになるよ。お前が二百円損するだけで俺の知りうる限り困る人は居ない」
キックはテストカンニングしてたのが先生にバレた時くらい軽い笑顔で俺を見た。伯母のように皺がしわくちゃに刻まれていない、若い笑いだ。若くて、とても、軽い。俺もつられて軽く笑って頷いた。
二人で席を立って、トレーにグラスと灰皿を乗せて店員に渡す。
「ごちそうさまでしたー」
「ありがとうございましたー」と店員は業務的な笑顔で言う。その店員の後ろに募金箱が見えたので、俺はそこに歩いていって財布の中身を全部突っ込む。
店員が唖然としているのを横目に見ながら、行こうぜとキックを促す。
「お前景気いいな」
「いや、たった今景気最悪になったけどな」
「伯母殺しといて見知らぬ子どもたちのために大金叩けるお前に免じてカラオケ俺がおごったる」
「まじで?」
「おう」とキックは店の外に出た。「その前に自転車、返しに行くぞ」
「わーかりました」と俺も外に出た。
空はもう半分ほど明るくなっていて、今日もなんにもない一日が始まる。
結局俺は伯母を殺したけど、キックのいんちきゲームに負けたことで二百円でそれは済んだことになった。
俺にとっては伯母を殺したことはこの先死ぬまで記憶に残り続ける殺人になったけれど。
キック的には、二百円程度で済ますことのできる殺人ならしかった。
風はキンキンに冷たくて未だに俺は焦げた木彫りの狐だけど、知らないだれかの自転車のグリップを握る両手は、確かに俺の両手だった。
個人的に200円程度で済ますことのできる殺人
喫茶店で他の人がどんな話をしているのかも気になりますけれど、それよりも気になるのはその人達がなにをして喫茶店に来ることになったのかっていうその経緯だったりします。
だからもしかしたらこんな人が居るかもしれないですね。みたいな話です。