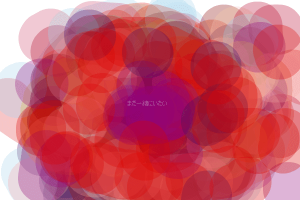ticket-歌唄い-
低いステージと隙間の空いたフロアであの人はギターをかき鳴らす。それを恍惚の表情で見つめるのはわたし。
あの人はわたしを妹のように大切な存在だと言う。それがどれほど残酷なことか、わたし以外誰も知らない。
あの人と一緒にいるために、わたしは好きでもない「あなた」と夜を重ねていく。
あなたの言葉に、幾度助けられたことでしょう。手を離したくないのは今だけでしょうか。
終電を逃すことなど慣れっこになっていた。
ただ過ぎる時間を待つには短すぎるほど簡単にその時間は迫っていき、あっというまに日が昇る日々だった。
その日も気がつけば日付が変わっていて、「あなた」も酒を進ませ楽しそうだった。
なぜかいつもあなたといる日は、居なくなった誰かのことを思い出す。
その話をぽつりぽつりと繋げていくと、いつだって悲しそうな顔をした。
そうしていくうちに、あなたの顔が少しずつわたしの目に吸い込まれていった。
『きみの気持ちはおれが知ってる
自分で言えないならおれが言う』
そう言って、誰にも分からない速度で重なったふたりの手が離れることはなかった。
こっそりと影が重なり、言葉に出さないまま店を出た。あなたの荷物をわたしが背負い、あなたが車輪を回らせて、あなたの部屋は真っ暗だった。
好きなもので溢れたリビングに腰を下ろした。
どこを見てもあなただった。
あなたの過去や、あなたの未来さえも覗けそうなその空間はどこか遊園地のようで、いつまでも見ていられた。
あなたは聞いた。
わたしはうまく答えられなかった。
だから聞いた。
あなたは
『当たり前でしょう。だからこうしてる。』
今だけは縋るように信じていたいその言葉に背を押され、身を沈めたベッドの上で、カーテンの隙間から漏れる光に気付かないふりをした。
もう朝が来ていた。
眠るあなたを起こさぬように、そっと家を出た。
通勤の波と逆方向に歩きながら、忘れたアクセサリーに気付いたのはもう家に着く頃だった。
まだ、あなたに会いたい。
ticket-歌唄い-