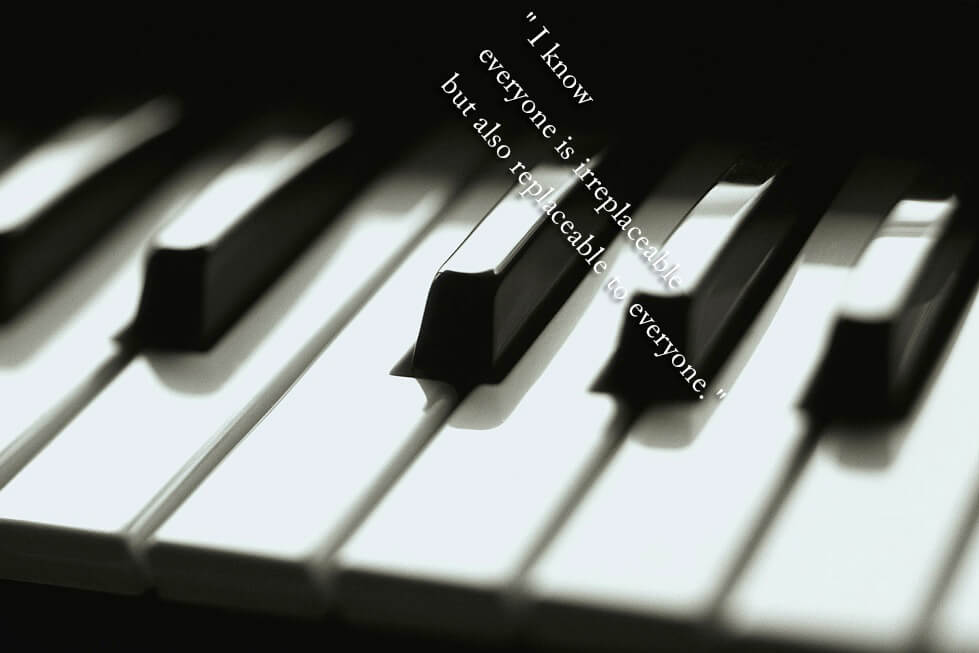
閉鎖病棟、「ドビュッシー」、施錠ドアでのメモ
詩を書き残すってことはだな、僕にとって、大した意味はないはずなんだ。
しょせん、こうやって、真夜中に書きつける陰気な作業なんだ。
目的があるとすれば、二つだけなんだ。
生きてるだけじゃ意味がないところに鬱病患者の人生への態度的価値って架空のモニュメントを打ち立てたいっていう、僕の不器用無様な抗いであって、
あとは、他の誰でもない、あの人でもこの人でもない、過去も将来も仮定せず、いまこうやって、僕の詩を読んでくれている、君のために、書いてる意味は確かにあって、
そのために、冬の抑鬱に塞がれた頭に突貫工事で言葉をぶつけて、他でもない、君との出来事の証言を、真夜中の人恋しいインスピレーションで、白い画面に録音しているようなものなんだけどな。
この詩の、存在理由。
僕が住んでるのは大してろくなこともない僻地で、保守的で閉鎖的な空気の強い田舎なんだけれども。
だから都会に住んでる人にはちょっと感覚が分かってもらえないかもしれないな。
「精神障害者」であるということをカミングアウトすることは非常に困難な地帯なんだ。
大学病院の精神科病棟に入院すると必ずこんな規則を厳守させられたりする。
「入院している間は一緒に入院している患者の住所・連絡先は尋ねてはならない」
「入院してる時は親しくしても退院したらお互い赤の他人。絶対に退院後に連絡しあったり会ってはならない」
ただ、精神科の病棟、特に大学病院の精神科というのは閉鎖病棟が多いわけでさ、
閉鎖病棟というのは「閉じ込められている」わけだから、他の診療科の病棟とは全く違った独特の空気が生まれるわけだ。
これを言葉で表現するのは難しいね。敢えて極言して言い表すなら、
閉鎖病棟の中で「小さな仮想社会」が出現する、なんて形容がふさわしいかもしれない。
閉じ込められている病棟の中で、
医者や看護師といった人間たちは「為政者」のようなもんで、
患者というのは「囚人」とか「民衆」のようなもんでさ、
出入り不自由な環境の中で必然的にこんな「役割」とか「階層」ってのが仮想的に生まれ、そういう作られた「偽の現実」に沿って人間が行動して、その中で悲喜こもごも物語が起こるっていうわけ。
(「スタンフォード実験」ってのをネットで調べてもらえば僕の言いたいことが伝わるかもしれない)。
閉鎖病棟ってのはさ、退院して外に出れば本当の現実があるわけで、あくまで作られた環境が仕向ける仮想的な社会に過ぎないんだよな。
でも閉じられた環境の中だからこそ、人はその世界を実に実直に、切実に、その中で起こった出来事を一生忘れられないものって、受けとめる話に、僕らは頻繁に出会う。
8年前になるんだけど、とある大学病院の精神科閉鎖病棟に入院しちまった時に、仲良くなった患者さんの一人にある女性がいたんだ。
仮に彼女のことを「ドビュッシー」って名づけておこうか。
なぜなら「ドビュッシー」は音大でピアノを専攻していたから、病棟のキーボードでよく僕の好きなドビュッシーを弾いてくれたんだ。
閉鎖病棟で唯一金髪で、いつも派手な装いで病棟の中で目立っていたけど、境界例人格障害ってのを患った、ひときわ思いやりのある、でもそれだけに誰にも見せない傷を負った繊細なひとだったよ。
夜中に眠れない僕は病棟のデイルームで日記をよく書いていたんだけれども、同じく眠れない「ドビュッシー」は僕の隣で座って、ただ黙ってよくそこにいた。
喫煙室で一緒に煙草を吸いながら、冗談を言って笑いあっていたけれど、笑っているのに泣いてるような目をしてるような、そういう儚い眼差しを見せるのが、「ドビュッシー」って人だったんだ。
「ドビュッシー」は実は僕のことを好きだったんじゃないかと思っていたんだ。僕の自惚れだったかも知れないけどね。
でも「あなたの主治医はハンサムだけど、あの人よりもあなたの方が優しいと思う」と言ってくれたことだけは、今でもよく覚えてるんだよね。
「ドビュッシー」が僕より先に退院した日のことだったよ。
閉鎖病棟の施錠ドアの手前で彼女と仲の良かった患者たちがさ、みんなで「ドビュッシー」を見送った。
退院したら、それはもう「一生のお別れ」を意味するんだ。
「ドビュッシー」は僕に病棟を出る前に、「見送って」とも言うわけなかったし、僕も見送るとは言っていなかった。
そういうのは絶対に寂しいに決まってるから、そういう約束は敢えてしないものなんだ。
だが、どういう気まぐれな気持ちが働いたんだろうね、僕は寸前になって「ドビュッシー」を見送りに施錠ドアのところに向ったんだ。
「元気でね」って、僕。
「ありがとうね」って、「ドビュッシー」。
彼女は手を差し出して僕に握手しようとした。
握手した瞬間、「ドビュッシー」が手のひらに秘かにメモを隠し持っていることが分かった。
彼女の手のひらを深く握り返し、看護師の連中に不自然を悟られないようにしながら、注意深くメモを受け取って、何気なく握手を終えるようなふりで、さっと手を引いた。
この一瞬に賭けた「秘密」を終えると「ドビュッシー」は僕をもう一度見ることはなく、開けられた施錠ドア通り過ぎて、背中向けたまま再び閉まるドアの向こう側、永遠に行ってしまった。
病棟のトイレの個室に入って僕はもらったばかりの四つ折のメモを開いた。
携帯の電話番号。
それと、
「いつか二人で、あなたの好きなキューバリブレ飲もうね」。
今になって、よく思い返すんだ。
8年前のあの人は、退院の時に別れの見送りの約束もないまま、僕が彼女を閉鎖病棟の施錠ドアに見送りにくることを信じて、事前にあのメモを用意しておいたのだろうかってね。
「ドビュッシー」は僕が見送りに来ようとも来るまいとも、どっちの「運命」であろうとも構わないつもりで、あのメモを忍ばせて、僕が現れるかどうか、賭けたんだろうか。
僕が彼女の見送りを「寂しい」からやめてたら、あのメモは彼女一人だけの中で処分される顛末になる紙切れだった。
だがそんな運命の線上で、医者や看護師なんかの絶対的な咎めを掻い潜り抜けて届けようとした、「ドビュッシー」の、秘かな「意思」のこもったメモだった。
僕にとって、書き綴った電話番号の数字があれほど意味を持った「相手への言葉」となるって経験は、あれが最初で最後なるのかもしれないな。
僕は唐突に、8年前の、僕の出会った「ドビュッシー」のことを思い出してた、昨日の午後のことさ。
「ドビュッシー」の携帯に、ついに今日に至るまで8年間、僕は電話していない。
だから、彼女が、いまどこの世界で生きているか、まったくわからない。
なぜ僕が「ドビュッシー」に電話しなかったことについてなんだが。どのような理由を書いても嘘の羅列になるような気がするんだよな。
心を病んでた人間を、心を病んだ人間が、
「小さな仮想社会」での劇的な出来事に向って感情の向うままに、「ただ向う」わけには、いかないから。
だって、
つまみ食い程度に美味しく甘受できるような半端さで、本当の現実を生きられるわけがないじゃないか。
気取っていうわけじゃないけどさ、
「ドビュッシー」と、僕は、
あの閉鎖病棟で、出会った瞬間から、
永久に、離別する、そういう運命だった、
ちぎれていくように、引き離されていく、そういう運命だったって、
今でも、そう思うしかしょうがないんだよな。
僕は、僕の、もとの現実ってところで、「ドビュッシー」は、「ドビュッシー」の、もとの現実ってところで、
帰っていかなくちゃならなかった。
僕と、「ドビュッシー」が、もし、閉鎖病棟以外の場所で、再会して、彼女との約束どおり、僕の好きな、キューバリブレを二人で飲むとすれば、
それは、二人が、もう一度偶然に出会う、そういう運命の繰り返しの奇跡が、なくちゃいけない。
そうじゃなきゃ、会ってはならない。
本当の現実ってのはさ、
閉鎖病棟の仮想社会ほど、簡単な仕掛けで動いてるわけじゃない。
僕と「ドビュッシー」は、本当の現実で生きなくちゃならなかった。
それが閉鎖病棟で、「閉じ込められた偽の現実」で出会った僕と「ドビュッシー」が生きる、ただひとつの道だった。
いまごろ、「ドビュッシー」がどうやって、だれと一緒に暮らしてるか、わからない。
わからないけど、たまにこうやって思い出して、想像はするのさ。
もう一生、永久に会うこともないだろう。
そのまま、僕らの人生が、やがておわる。
あの閉鎖病棟で手渡しあったメモが、
もはや、僕の手許から去って、もうどこでもなく、どこかに、消えたみたいに、ね。
いつかどこかで、「ドビュッシー」が、僕の詩を読んでくれるような、そんな運命があってもいいよなとか、
そんなくだらない夢想ぐらいはするんだ。
だから、こうやって、この詩を書いたんだけどな。
こうやって、僕は、もしかすると、あの人を探しているかもしれない。
もしかして、君が読んでいるかもしれないと、
少しだけ、いま思ってみる、 この詩の レゾンデートル。
閉鎖病棟、「ドビュッシー」、施錠ドアでのメモ
8年前に書いたものに手を加えた。
だから入院していたのは今から16年前ということになる。
作者ツイッター https://twitter.com/2_vich


