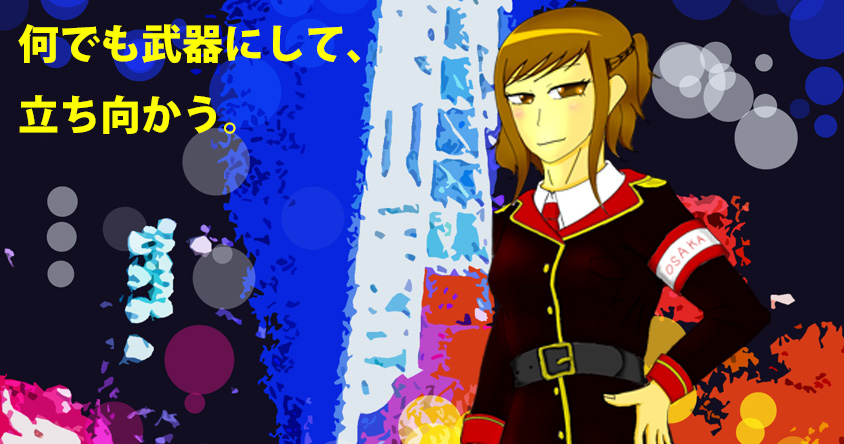
麻獣 -ASAKEMONO-
西暦2025年―――。
新種の特殊麻薬《MONSTER》が開発された。
大阪・ミナミの繁華街を中心に日本はその麻薬によって汚染される一途を辿っている。
それに溺れた人間は皆、麻獣《アサケモノ》という怪物に変貌し、殺人や破壊などの犯罪行為に手を染める。
そんな超危険な存在を成敗し、街の治安の改善すべく、自らが得意とする武器を駆使して麻獣を倒し、取り締まる物たちがいる。
人々はそれを、麻獣取締官《レギュレーター》と呼ぶ。
この物語は、恐怖の怪物に立ち向かう力を持った者・麻獣取締官《レギュレーター》たちによる物語である。
第1話
西暦2035年、4月。
平日の朝でも通勤中の会社員や観光客が歩く人ごみが多く存在する戎橋。その橋から見えるタンクトップを着た男性が大きく両腕を挙げたイラストの看板が目印の言わずと知れた大阪のシンボル街・道頓堀。
先月高校を卒業し、今月末に19歳を迎える俺、逆瀬川勇人はそこにあるエビスヒルズに来ていた。
今から6年前。天王寺駅前のあべのハルカスや梅田のグランフロント、ステーションシティに対抗すべく、ここ道頓堀も何か目立った商業施設を作ろうと建てられたのが、このエビスヒルズである。以前まであった戎橋ビル、H&Mなどが入ったラズ戎橋、そしてそれらの向かいにある五階建ての建物となっているTSUTAYA戎橋店の三つを合体、改装させ一つの施設へと生まれ変わった。この施設の誕生により、治安が悪いというイメージの強かった道頓堀、というかミナミ近辺の街に「この付近は危なっかしいけどヒルズあるし買い物でもしようかな」といって訪れる人が増えた。
とはいえ、俺は生まれた頃からここから少し離れた兵庫の西宮から宝塚間にある田舎町で暮らしていた。高校は部活の推薦で大阪の私立校に進学したものの、そこでの生活の九割がその部活動によって占められていため、此処のような「ど」が付くほどのメジャーな都会街に来る機会は少なかった。そのため、このことに関して俺が持つ知識はは新聞やニュースで得た程度のことだけで、実際の雰囲気を目の当たりにしたことはない。
この施設は当時の名残からか、三つのタワーに分担されており、Tタワー、ラズタワー、そしてオフィスタワーがある。改装工事により三つとも十五階建てのビルに統一されており、九階あたりが渡り廊下で繋がっている構造となっている。
「ふぅ、今日からここが俺の職場か」
オフィスタワーの入り口を前に俺は立ち止まった。
何故俺がここに来ているのか。
何を隠そう、俺は今日から麻獣取締官として働くべく、この建物の五八階にある麻獣取締局大阪本部へと、その身を投じようとしているためである。
麻獣取締官とは、最近巷を騒がせている怪物の一種・麻獣に対抗することができる唯一の力を持った細胞・SK細胞を所有した人間及び麻獣を退治すること、特殊麻薬を取り締まることを主な職業とした人間のことを指す。
そして麻獣殺しの天敵となる麻獣について説明すると、暴力団やギャング、犯罪組織が敵対している団体を倒す、街を制圧する等、自らの目的を果たすために利用する危険なモンスターである。
2025年に、とある研究者によって発明された液体型特殊麻薬・MONSTERを服用した人間が、満月の夜にその満月を見た瞬間に麻獣へと姿を変える。その麻薬はコカインやMDMAと言った一般的な麻薬と同様、所持者側が人に勧め飲ませて洗脳させるケースが多いが、暴行や殺人の為の力を欲する所持者自らが薬を服用し麻獣となっていくケースもある。簡単に言えば薬物中毒者がバケモノになっていく感じである。
麻獣と化した人間は力が倍増し性格が凶悪化する。そして、殺人や器物破壊、強盗などの犯罪行為を無意識に行ったり、組織同士の紛争の一環として格闘させたりと、街の治安悪化の大きな原因の一つとなっている。
麻獣取締官とは、そんな狂暴な輩を成敗し取り締まることが仕事の職業である。
ただ世間にとって、もちろん俺自身にとっても、この仕事に対してあまりいいイメージは持っていない。むしろ、常に危険が潜んでいて、いつ死んでもおかしくない仕事だ。今まで野球しかしてこなかった俺に務まる根拠もないのに素質があるなんて言うから、望んでこの仕事をする人の数はごく僅かである。
ここまで言うと、何故俺がそんな危険な仕事に就こうと思い立ったのか疑問に思う人が殆どだろう。それについてまた長くなるが説明するとしよう。
ついこの間…とはいえ2年ほど前になるだろうか。その頃まで俺は高校球児のピッチャーとして地元メディアからそこそこの注目を浴びた経験を持つ男だった。
俺は物心つくころからの野球少年である。中学生の時から、将来プロ、そしてメジャーで活躍できるピッチャーになることだけを意識して効率的な努力を行ってきた。その努力が実を結び、先述した大阪にある甲子園の常連として有名な野球の強豪校、桃里学園高校からスカウトされ、スポーツ推薦でそこに進学した。
強豪校だけあって早朝から夜まで行われる過酷な練習についていくことも、俺の倍以上の実力を持った多くのチームメイトからレギュラーの座を奪取することも非常に難しかった。それでも野球が好きで野球しかしてこなかった俺にとって、この苦境を楽しいと思えたことと、「この努力が目標への道を切り開く方向へと導いてくれる」というポジティブ精神を持つことで乗り切ることができた。
そして高校2年、秋の公式戦。リリーフで登板した俺は、球速160キロの速球を連投し、相手打線を3回無失点9者連続三振の好投で抑えた。そんな俺の剛速球と好投を見た世間は黙るわけがなく、高校野球の情報を取り扱う各スポーツ雑誌が次世代のドラフト目玉候補選手として俺の特集を組んだ。そして、監督からも「来年の夏大、お前エースで行くからな。」と告げられた。エースになり、甲子園のマウンドで今日のような高等をすれば世間からの注目もさらに多くなり、もちろんプロのスカウトの目に止まる可能性だって高くなる。そう考えた時、俺のモチベーションは最上限にまで達し、感情も高ぶっていたことを今でも覚えている。
この時、俺は子供の頃から目指していたプロ球界での活躍という夢に大きく近づいたと実感した。
しかし、現実はそう簡単にいかなかった。
高校三年の健康診断。内科健診の際、医者の方が何か違和感を覚えたらしく、レントゲン診断や細胞診断などで体内を徹底的に調べられた。
その結果、俺の身体にSK細胞が存在していたことが明らかとなった。
野球に限らず、サッカーにしろ剣道にしろSK細胞を持ったスポーツ選手は試合に出ることはできない。その理由は試合中に細胞が持つ能力が発動してしまう恐れがあり、それが発動してしまうと試合に支障が発生するためだという。俺はその細胞が持つ能力とやらについて、麻獣を倒す以外の具体的な用途を知らなかった。俺はそれに関して詳しい説明を受けていなかったこと、これまで投げてきたが能力が発動しなかったことを盾にして必死に反論した。それでも、高校野球連盟は「今後細胞が成長すれば能力が発動する可能性だってある」と論破され、俺の試合出場は認められることはなく、俺は野球を辞めざる得ない状況になってしまった。
俺はわずか17歳の若さで憧れだった球界への道を謝絶された。
野球を失った俺は、卒業後の進路をどうするかで路頭に迷っていた。そんな時、すでに麻獣殺しとして活躍している一つ上の幼馴染の女友達から「一緒に麻獣を殺さないか。お前ならその素質があるかもしれない。」と誘われた。
マスコミは俺が野球をやめた原因を怪我という風に理由づけている。今までは細胞の規模がわずかな小ささだったので、能力は発動しなかった。それでも、SK細胞を持っていたにも関わらず野球をしていたと知られれば、大きな問題となるからだ。彼女には俺が細胞をもっていたことを話していなければ、知っているはずもない。俺を麻獣殺しの道へと誘うということは、もしかして彼女はそのことに感づいているのか。
だが、そんなことは当時の俺にはどうでもいいことだった。今後のプランが白紙でこれと言った希望もなかった俺は彼女のお世辞に騙されたと思って麻獣殺しになる決意をした。
こうして俺は、麻獣殺しの試験を受けた。通常は筆記試験、体力試験、面接試験の3項目あるが、俺は彼女の推薦により体力試験1項目のみの受験だった。筆記と面接を免除できるほどの推薦が通るあたり、彼女には一体どういった権限を持っているのか試験中ずっと気になっていた。しかし、元球児で体力には当たり前のように自信のあった俺はあっさりと合格し、晴れて麻獣殺しとなり現在に至る。
「はぁ…ホンマ、やっていける気せんわ…」
入り口を前にして俺は大きくため息をついた。
死と隣り合わせの仕事に就き、不安がないわけがない。だが、野球という唯一と言える生きがいを失った俺だ。生きがいがないなら死んでも構わない。それに自殺して死ぬよりはそうして死ぬ方がよほど良心的だ。そう覚悟を決めて中へと入っていった。
局長室で麻獣取締局局長と大阪本部の支部長に挨拶と自己紹介を済ませた俺はそこを出てすぐのソファで教育係となる先輩が来るのを待つように指示される。
局長は見た感じ50代あるいは60代程度の男性でそれに相応した体系と顔立ちをしていた。そして支部長は二枚目俳優のような顔立ちをしている大よそ30代前半の男だった。
2人とも厳格そうな雰囲気とは裏腹に、柔らかい人格だった。仕事は確かに危険そうなイメージではあるが、彼らのそんな人格からして意外とゆるいだったりするのだろうか。
そんな事を考えていたその時だった。
「アンタが逆瀬川勇人君やね?」
「はい!そうで……あっ」
局長や支部長が着用していたものと同じ全身赤がかった黒い軍服風の制服に女性用の指定スカート、脚には黒いストッキングを着用し、首元まで伸びているウェーブのかかった茶髪をハーフアップにした女性が俺の名を呼び、こちらに歩み寄ってくる。
「ウチがアンタの世話係を務める、小林園子や」
彼女こそ、俺にこの麻獣取締官の仕事を紹介した張本人である。
「ふふっ、久しぶりやな勇人! 長い間見ぃひんうちに、デカなったやん!」
園子は元気に溢れた笑顔で俺に話しかける。
「あぁ、久しぶり。何しろ俺が中学卒業して大阪越してから3年間会えへんかったもんな」
彼女とは幼少期からの幼馴染であり、当時は俺と彼女と彼女の弟、彼女の同級生の女友達。この四人で仲良く遊んでいた。園子はまだ20歳と若い年齢ではあるが、俺より一つ年上の姉貴分である。それでも彼女は「歳なんて気にせんと、気軽に接してもええんやで」と、俺にタメ口で接することを良しとしており、俺はそれに甘えて彼女にタメで接している。その関係性は現在も尚継続している。
「あら? アンタもしかして、園子姉ちゃんがあまりに美人になったから見惚れててんちゃうの? 顔ちょっとデレーってしてんで?」
その言葉通り大人に成長しつつも中身は変わらぬ園子を見て懐かしむ笑みを浮かべる俺に対し、彼女はニヤついた表情でからかってくる。
「なっ…べ、別にそんなんちゃうわい! それに美人って自分で言うなや!」
「冗談やんか~、そんな怒んなや~」
このように彼女は俺のような親しい友人に対して毎度からかうように絡んでくる。彼女との初めての出会いも当時野球のできる友人がおらず、一人で壁当てキャッチボールをしていたところに「寂しいやつやな」と嘲笑いながらも相手をしてくれたのが始まりだった。そんな俺を含め老若男女問わず、どんな人間ともこんな感じに上手くコミュニケーションを取れるのが彼女の長所である。
「それよりさ、何で俺なんかにこんな仕事を勧めたん?」
「アンタさぁ、SK細胞持ってるやろ?」
「っ! 園子姉、何でその事知ってんの?!」
俺は核心をつかれ、内心焦っていた。心の奥にしまい込んだ秘密を表情や勘から見抜いてしまうのも彼女の特技である。
「ガキん時から野球一筋やったアンタが、怪我ごときで野球やめるなんておかしい思ったもん。なーんか原因があるんやったらそれしかないって勘付くんは、当たり前やんなぁ?」
SK細胞は特殊な訓練及び治療を通して、細胞を持たない人間にも組み込むことが可能となっている。その特殊な訓練と言うのは「好きを極めること」である。診断の際に俺を診てくれた医者の話によると、俺の場合は野球を極めることが細胞を生み出す訓練となっている。生まれた時は特にこれと言って特殊な細胞を持たずに生まれてきたが、野球の練習を繰り返し行うことで細胞が生成されたらしい。
園子は麻獣殺しになる前、麻獣殺しの養成学校に通っていたため、それに関しては精通しているはずだ。野球一筋だった俺を知る彼女だからこそ、勘付いたのだろう。
「せやから、この大阪支部の取締官主任であるウチが直々にアンタは野球に対する情熱を強力な麻獣に立ち向かえる力に変換できる言うて局長と支部長に推薦したわけよ!」
「えっ?! 園子姉って、高卒でこの仕事就いたから……まだ2年目やんな? それでもうキャプテンなん?!」
「言うてウチはアンタ程やないけど、体力には結構自信あるんやで? 1年でキャプテンになることくらいウチにとっちゃ朝飯前やで!」
「せ……せやな……」
園子の運動神経は毎度惜敗するも俺と競り合うほどの実力だった。そんな彼女に調教されるのは腑に落ちない部分はあるが、年齢においても社会的立場においても彼女の方が先輩なので、それは仕方がないと渋々受け入れる俺であった。
「ほな早速やけど、アンタの実力確認がてらトレーニングするから。ホラ、ついてきて。」
「……ホンマに唐突やな」
そう呟きつつも、俺は彼女の後へとついて行った。
俺と園子はエレベーターの中で、9階へと降りていく。
「ウチらが今いるこのビルがオフィスタワー。13階から15階が麻獣取締局の本部になってて、あとはオフィスタワーって名前やから色んな会社が事業所を置いてるんや。」
「へぇ。にしてもここの中ってホンマに大きいんやな」
「言うてハルカスやグラフロとかに比べたらそんなにやけどな」
「その辺もここもニュースとかで見た映像のイメージしかなかったし、実際のデカさ見てビビったわ……」
「アンタ、3年間大阪にいたのにこの辺のことも知らへんの?」
「あのなぁ、3年間部活漬けだった俺に大阪観光する暇なんてあるわけないやろ」
「まぁ、それもそうか。アンタは根っから野球小僧でそれ以外のことなんて興味なかったもんな」
そんな他愛無い昔話をしていると、エレベータが目的地のフロアに到着し、中にチーンという音が鳴り響いた。
「この9階は渡り廊下になってて、こっからラズやTに行けるわけよ!」
エレベータを出て右に曲がると、そこにはラズタワーへと繋がる全面ガラス張りの渡り廊下があった。俺たちはその渡り廊下を歩いていく。前方を見ると右手にTタワーが、側面からは道頓堀がそれぞれ見える。
「ほんでこのラズタワーには演習場があるから、アンタにはそこでトレーニングを受けてもらうで」
彼女は目と鼻の先に見えるラズタワーを指さしてそういうと中へと入り、俺もそれについて行った。
エビスヒルズの施設の一つ、ラズタワー。8階まではエビスヒルズ名義以前のままH&Mなど様々な店がある。ここも9階は渡り廊下になっていて、10階は会議室、11階から13階は麻獣殺し用のトレーニング施設となっている。そして14、15階は天然温泉があり、戦闘に疲れた麻獣殺しはもちろん、一般人も利用している。
俺たちはここの12階にある基礎演習場に入った。
「因みに演習場は11階から13階まであって、この基礎演習場は銃とか剣とか武器の使い方を練習する場や。で、下の11階が基礎体力を鍛えるトレーニングジム。上の13階が模擬戦闘ができる戦闘演習場になってて、どれも麻獣殺しやったらいつでも使えんで!」
「マジかよ! いくら施設デカいからって訓練環境充実しすぎやろここ!」
「そら、他の支部からも訓練に来る麻獣殺しもおるくらいやから、多少はな?」
大型施設のメリットを最大限に生かしまくっている環境と言えるのではないだろうか。球児時代にこんな環境で筋トレと化してみたかったなぁ、としみじみ思うくらいだ。
ここ12階の中は個室が左右それぞれにズラッと並んでおり、入って右側が近接型、左側が遠距離側の演習室になっており、奥の中央には「仮装備室」と書かれた扉がある。
「一応部屋には銃や刀とかは用意してるけど、それ以外の武器使わせろや~ってなったらあそこで武器をお試し装備できるで!」
「銃とか以外でも麻獣倒すって噂では聞いてはいたけど、マジなんやな…」
「せやで。ほら、スリッパとかスプレー使ってゴキブリ殺す風習あったやん?それが進化してスリッパやスプレーみたいな武器の定義がないモンでも麻獣を倒す武器に変える力をウチら麻獣殺しは持ってるんや!」
拳銃や刀と言ったごく一般的な武器と呼ばれるものは、専門店や海外などで高値で買ったり取り寄せたりする。安くても5万から10万、高額なものだと100万、3000万とえげつない価格である。そこまでの資金をもらえずコスパを良くしたかったのか、代わりに身近にある比較的安物の道具を武器に変えるという発想は、すごい発想とは思うが同様にバカバカしいとも思う。良い意味でも悪い意味でもその力を作った人の頭を割って中を見てみたいものだ。
「あ、そうや。麻獣殺しには経験積むことでえられるすごい技があんねん。野球とかも継続することで上達して自分にしか出来へんプレーが出来たりするやろ?それと同じで、繰り返し武器使うたらオリジナルの必殺技が使えるようになる。いわゆる神技ってヤツや!」
「神技? それはSK細胞と関係してるんか?」
「せやな。この細胞があると、麻獣を倒せる魔球が投げられるワケよ!」
「魔球?! マジで?!」
「おう! 例えば燃える魔球とか風を起こす魔球なんかも簡単に投げれてまうで~?!」
園子はウキウキとした表情で説明する。
「こんな漫画やラノベみたいなことがあってええんかよ……。俺は今までただ野球しかしてこなかった人間やぞ……」
「スカウトされて麻獣殺しになる人間は大体そんな感じやで」
先ほどの武器の話といい、今の神技の話といい、初めてのことで何が何だか理解しづらい俺は呆れるしかなかった。
本当にその神技とやらの力によるものなのか、俺にもよくわからない。ただ、もし後者ならば俺は超能力者である、という事なのか。全く信じられずにいた。
「まぁ、まずはやってみんと分らんもんやからな。ってことで演習開始、ブタのケツじゃ! ホラさっさと入って!」
「お、おう」
俺たちは遠距離型の演習室へと足を踏み入れた。
演習室の中はおよそ六畳分の広さで、向こうに人間のシルエットの形をした的がある。そして入口に入ってすぐ左に戦闘服に着替えるための更衣室のようなものがあり、俺は動きやすいようにとそこでスーツからグレーの半袖のスポーツウェアに黒のジャージパンツに着替えた。
「さっきも言ったとおり、武器に関してはこれと言って決まりは無いからどんなもん使っても大丈夫や。一応仮装備室から野球ボール持ってきたで。ほい、投げてみ。」
「う~ん…ボール投げるの久々やし、上手く投げれるかなぁ…。」
「攻撃にさえなったらそんなんどーでもええって! はよ投げろ!」
俺は言われるがまま、両腕を真上にあげて的に向かってボールを投げてみた。球の威力は以前と変わらずノビがある。炎が出たりとか風が起きたりとか、そういった特殊な何かは出なかった。
「何やねんアンタ! 自信ないとか言いながら結構ええ球投げるやんけ!」
「えぇ、俺も普通に投げたつもりやぞ?! それも久々に……まさか球がこんなに伸びるとはたまげたわ……」
球速はおよそ120キロ近くと言ったところだろうか。全盛期に記録した160キロのそれに比べると遅くはなったが、それでも球筋は衰えていなかった。野球を辞めてから間がありながらもこれだけの球が投げられることへの驚きと同時にそれに対して少し誇らしい気持ちにもなった。
「けど……この威力やとちょっとした妨害程度のダメージにしかならへんなぁ……」
「うん……何回か投げれば感覚を思い出すかもしれんし、もっと投げてみよう」
その後数時間、数十球投げ続けたが、それでも投げる球から炎は出てこなかった。
「アカンかぁ~……技術的な面は見た感じ問題ないんやけどなぁ……」
やはり麻獣を倒せる魔球なんてただの幻想ではないだろうか。投げているうちにそんな疑いを持った俺だが、実際の神技とやらを見たことが無いので、勝手にそう決めつけるのは良くないことだ。そもそも素質があると言われてもまだ仕事を初めてばかりの俺がそんな魔球を投げれるのはハッキリ言って異常な話である。まぁ、その点に関しては長い目で見る必要があるのだろう。
そんな事を考えていると腹の虫がぐう、と鳴く音がした。
「まぁ腹も減ってきた頃やし、ここらで飯にしよか」
園子は腕時計を確認し、昼食の時間が近づいてきたと判断する。
「あ、あぁ。そうやな」
突然の空腹の音に焦った俺は顔を少し赤くして頷いた。
「このビルの中にな、めっちゃうまいラーメン屋あるって有名らしいで!」
「ラーメンやって?!」
「しかも、アンタ好物のヤサイマシ系のトッピングもセルフで好きなだけできまっせ?」
悪魔の誘惑のように俺の耳元でささやく園子。
「よし、行こう!」
俺はラーメンという食物が大の好物である。その中でも、モヤシやキャベツなどの野菜類と豚肉が山盛りにトッピングされた『ヤサイマシ系』『二郎系』などと称される種類のものは格別である。それをセルフでできるとあれば喜ばないわけがなく、俺の腹の虫が勢いよく鳴き始めた。
「よっしゃ、ほな行こか」
昼飯を摂りに向かうべく、トレーニングルームをあとにする。
Tタワー。ここもエビスヒルズの施設の一つである。5階までは以前までと変わらず、TSUTAYAやスターバックスコーヒーなどがあり、6階から8階はカメラのキタムラや洋服の青山、エディオンなどのTポイント加盟店が集まる、ちょっとしたショッピングモールとなっている。九階は他二つの施設同様渡り廊下がある。10、11階の武器整備室や12、13階の研究室を通過して、十四階の食堂、というかフードコートに辿り着く。
ここはラーメン、たこ焼き、ビビンバ、ハンバーガーをはじめクレープやソフトクリームと言った食後のスイーツまで手軽に美味しく幅広く食べられる店が多く存在するフロアだ。道頓堀に遊びに来た一般の人に向けたものだが、麻獣殺しやこの施設内で働く人たちも多く利用しており、その人たちに向けた社員割引制度がある。時間も正午に少し入ったため、中は多くの人で非常に混雑している。俺は昼食を注文するために、ラーメン屋の前に並ぶ行列の中にいた。
「さすがにこの時間帯は混んでるなぁ」
「当たり前や。特にここはラーメン以外にも行列作ってる要因があるからな」
「え? 何それ?」
「お、列動き出した。次がウチらの番や」
注文を済ませお目当てのラーメンを受け取った俺と園子は、二人用のテーブルにそれを置き、向かい合って席に座った。
俺は当初の目的通りヤサイマシの特盛ラーメンを注文した。
「ホンマにそーゆーえげつないの好きやなぁ、アンタは。」
「うるさい! これくらい野菜多い方が栄養バランスええやろが!」
呆れた顔で苦笑いする園子に対して俺は正論を投げかけて反論する。
「それに、園子姉だってメシ誘っといてホンマはそっちが目当てなんやろ?」
俺が指差したそっちとはフリフリの衣装に身を包んだ赤い髪のショートボブヘアの二次元の美少女キャラのアクリルキーホルダーである。
「そらそうよ! ここでしか手に入らん限定品やからね!」
園子が持っているキーホルダーは『魔法少女ユーコ&キクヨ』、通称「ユーキク」というアニメのもので、俺と園子が生まれてくるずっとずっと前から放映されている長寿番組である。開始から数十年経つ現在もなお、幼少児や小学生はもちろん、萌え系や美少女系アニメを愛好しているか子供の頃からずっと好きで応援している所謂「大きなお友達」と呼ばれる大人のファンなど……老若男女問わず愛されている作品である。園子は幼少時にそのアニメの魅力に引きこまれて以降、ブルーレイ全巻セットからキャンペーン限定のグッズまでを買い揃えてしまう熱狂的なファンである。
その作品はタイトルの通り「由子」と「菊代」という二人の主要登場人物が存在しており、園子が手に入れたのは前者の名で呼ばれているものらしい。
「う~ん……ホンマはキクたんのが欲しかったんやけどなぁ。はぁ、何でランダム制なん……まぁまぁ由子ちゃんも嫌いじゃないし、むしろこの子もこの子で可愛いから好きやしええんやけどな!」
園子はキーホルダーに軽く口づけると顔をにやつかせた。園子はこれがきっかけで、美少女系や萌え系のアニメや漫画及びそこに登場する美少女キャラを愛するようになり、三次元の女子に対しても愛のありすぎるスキンシップをしてしまう変態と化してしまった。勿論男性など恋愛対象外としてしか見ていない残念な人間である。三次元ならまだしも二次元の美少女に公衆の面前でよくもまぁこんな恥ずかしいことができたものである。
「相変わらずやな、園子姉は。そのうち犯罪行為に手を出さんか心配になるわ」
「はぁ? そんなことせんわい! ウチはこれでもその辺の境界線はハッキリしてるつもりやし。オタクは皆変態犯罪者なんて偏見はとっくの昔に廃れた話やって、それ一っ番言われてるから! そこを勘違いされるんはウチらにとってはホンマ迷惑やからな!」
「はいはいそうですか……。」
俺はちゃんと聞けと言わんばかりの力説を軽く聞き流す。まぁ、オタクが皆悪い人間ばかりではないと思うし、良い人間もたくさんいるだろうから事実であることに間違いはないのだが。
「あ、そういや園子姉。」
「ん? 何?」
「例の麻獣はもう見つかった?」
俺がこの話題を出した途端、彼女の表情が少し暗くなった。
「まだ見つかってへんよ。まぁ、あいつは結構希少なタイプの麻獣らしいからそう簡単には見つからんよ」
例の魔獣、というのは五年前に園子の祖父を殺害した麻獣である。
園子の祖父はかつて警察官として日々町と国の平和のために頑張っていた。定年退職後は、一家代々でたこ焼き屋を経営しており、孫娘である園子も幼い頃からその店の仕事をよく手伝っていた。それもあって園子と祖父は深い絆で結ばれていた。
そんなある時、暴力団がみかじめ料を要求に店に毎日しつこくやって来る。祖父は当然のごとく頑なに断り続けた。しかし、それにしびれを切らした暴力団側が例の魔獣を使って祖父を殺しにかかった。その後、暴力団員たちは逮捕されたものの、問題の麻獣の行方は分かっておらず、特徴などの情報も極めて少なく、捜索が難航している状態らしい。
園子はその麻獣に祖父の仇を討つべく麻獣殺しになった。
「けど、希少やからこそ燃えるって言うかさ……アイツをいつかとっつかまえて成敗したるって目標持ってたから、ウチもここまで努力できたんかなって思う」
「フッ、そうやな……。なんか園子姉昔と比べてしっかりしてるよう
に見えるもん」
「こうしている前にウチと言えば、将来何もやりたいことなかったから、ただのうのうと過ごしてたからさ。じいちゃんがあの世行ったんは、ウチに遺言として道を示してくれたんかなぁって思ってな。じいちゃんの仕事とかユーキクとか見てこういうヒーローへの憧れはあったから、この仕事は楽しく貪欲にやってるし、ウチにとっては誇りに思ってる!」
俺も彼女の祖父には幼い頃に色々と面倒を見てもらっており、世話になっていた。それ故に訃報を耳にした時は俺も彼女と同じくらいの悲しみを味わった。けど、今こうして目標を持って頑張っている彼女を見ていると、祖父も天国で喜んでいるだろうと、他人ながら思う。
「せやから、アンタもこの仕事に誇りを持ってくれたら、お姉ちゃんとしては嬉しい限りやから、頑張りや!」
「ハハハ……まだまだわからんこと多いけど、精進するよ」
飯を食いながら話していると、壁掛け時計は昼休みが終わろうとする時間を指していた。
「お、時間そろそろ時間やな。ほな仕事戻ろか。」
「そうだな」
俺と園子は椅子から立ち上がってその場を去った。
麻獣殺しの仕事をし始めてからおよそ3週間が経った。
今日も俺はいつものように訓練を受けるべく、園子のもとへと向かっていた。
ただ、今日はいつもの演習室ではなくオフィスタワーの地下にあるスタンバイルームに来るように言われており、そこへと向かうエレベータに乗っていた。
その部屋は任務に備えての武器の装備や調整を行い、そこから現場に向かうための場所となっている。そうなると今日は現場に出てのちょっとしたパトロールの付添だろうか。そんなことを考えている間にエレベータは地下に到着した。
「おう、来たな。」
園子が首元のボタン位置に赤いリボンを襟の中に通し付けた白いポロシャツの上に紺のベストと、白橡色したチェックのスカートに濃い茶色のローファー、そこから膝下までの長さの黒いソックス、そして太ももに巻きつけているポーチ…いかにも学校の制服らしき服装で立っていた。
「園子姉、何でそんな格好してんの?」
「戦闘服や。」
「せ…戦闘服? コスプレやろ? それって…」
「断じてコスプレやないで! ほら、軍服やとさすがに激しく動きづらいやろ? やから、戦闘任務の時だけ動きやすい服装に着替えんねん。これも武器と同じく特に規定とかは無くて、自分にとって動きやすい服装やったら何でもええわけや!」
「それで、制服ってことか…」
「せやで! 麻獣殺し特有の力で、何着ても攻撃で受けるダメージは変わらんからデザインも自由や! 今まで着てきた制服が地味やったからこういうアニメとかでよく見る派手なの着てみたかってんな~! あぁ~想像だけで可愛い美少女の匂いがする~! たまらんわぁ~!」
彼女は二次元の美少女になりきっている喜びで、ご満悦の表情を浮かべ、戦闘服もとい制服を自慢した。想像で匂いを感じ取る部分は、流石萌え豚である、と褒めるべきだろうか。
「なるほど…。そりゃまた変わったシステムやな…」
制服を着て戦闘に出て武器も何でもアリとは、まるで漫画やアニメみたいで本当にファンタジー色の強い職場である。
「それで、今日の訓練は?」
ちょっとしたパトロールならば、スーツを着ていくと教わったはずだが。
「決まってるやろ。今日の訓練は特別実戦形式や。アンタをほんもんの任務に連れて行くからそのつもりでな」
「は? いきなり実戦?!」
この3週間の間、実戦はおろかそれ形式の演習も経験していない。ぶっつけ本番で麻獣を殺せというのか。そんなことを言われた俺は驚愕の声しか出せない状態だ。今までの人生でこれほど鬼畜の所業と言える扱いを受けたことはおそらくなかったかもしれない。
「あのさぁ……、俺はまだ模擬実戦すらやったことない人間やぞ? それでいきなり実戦任務って鬼畜すぎへんか?」
「本番で実力を発揮してこそ仕事人や。アンタはそれ相応の実力が付いたって判断したからその本番をウチが用意したんやで?」
園子はにやついた薄目の顔で俺の目の前数センチの距離まで詰め寄った。
「それに今回のターゲットは新人でも倒せるレベルのクソ雑魚やから、大丈夫やって!」
とはいえいくらなんでも無茶苦茶すぎる。まぁ、そんな強気で大胆な部分が彼女の性格なので仕方がないのだが。
「とにかくボサッとしてんと、はよ着替えんかい!」
「はいはい……」
俺は渋々とした顔でロッカーの一室に入り戦闘服に着替えを始めた。
戦闘服基いつもの制服に着替えた俺は園子と共に、通天閣が仁王にそびえ立つ新世界へとやってきた。
夜空には営業時間を過ぎ、人通りも少なくなり暗くなった街に薄黄色の明かりを灯すように満月が輝いていた。
「時間も時間からか知らんけど、不気味なほど静かやな・・・・・・」
「こういう静かなときほど麻獣が頻繁に出てくるもんやからな。気ぃつけや。」
街が静寂に包まれているその時だった。
「ぎゃぁああああああっ―――――」
中年と思わしき男の呻き声が密かに響いているのが聞こえた。
「どうやらターゲットがどっかで喚いとるようやな。行くで、勇人!」
俺と園子はその声がする方へと向かう。
悲鳴の発声源である串カツ屋付近に着くと、麻獣が暴れている。
麻獣へと姿を変えた20代程度の顔立ちで、やや筋肉質の男は頭から猫の耳の形をした毛深そうなものを生やして八重歯が鋭く尖っており、顔色は極端に白く、目は虚ろな状態で狂気に満ちた表情をしている。
「あれは猫型麻獣、吸血猫。トマトジュース味のクスリを飲んだ人間の末路と言える姿や。」
「ちょっと待って?! クスリにも味とかあんの?!」
「知らんかったん? 麻獣になると外見や動きに、色々な種類の変化が出ると思うけど、その変化を決めるんがクスリの味ってことよ。」
「なるほど。にしてもトマト味のジュースってどんなやねん……」
俺はまた一つ珍しい知識に触れ、関心と同時に困惑の表情も沸いて出た。
変わったしょうがないのかもしれない。実際宜しい事ではないのは確かではあるが・・・・・・。
「そんなに気になるんやったら、いっぺんクスリやってみたら?」
「冗談言うな! んな事したら人生壊れるやろ!」
既に飲食店の入り口に飾られた看板やビリケン像が一部壊されている。50代程度の中年サラリーマン2人が麻獣による攻撃被害を受けて倒れていた。
「あの麻獣は尖った爪や八重歯を使って攻撃する麻獣や。あのおっさんらもそれでやられたんやな。」
「まんま猫やな。全く捻りがないな。」
「そんなもんウチが考えたわけやないんねんから、言うたってしゃーないやろ! まぁ、捻りがないんは確かやけど。」
作者に対する批判話をしていると、麻獣が俺たちの気配に気づき、こちらを睨みつけた。
「ぐぉおおおおおおおおおおっ!!!!!!」
麻獣は狂った咆哮と同時に両手を挙げて威嚇の体勢を見せた。
「おっと、しょうもない話しとる場合やないみたいやな。」
園子は太ももに装着していたポーチから自身の武器であるたこ焼きをひっくり返す用の棒、通称・ピッグとお好み焼きをひっくり返したりきったりする用の鉄製のヘラを取り出した。
「勇人、ウチがピンチになったらそのボールでバックアップ頼むで!」
「お、おう!」
俺も腰に付けたポーチから武器として野球ボールを取り出す。
園子が敵に向かって駆け寄ると、向こうも鋭く尖った爪で園子を引っ掻こうと右手を大きく挙げる。すると、金属と金属がぶつかり合う音がした。園子は麻獣の爪と爪の間にピッグを置いていた。彼女はそのまま麻獣を押し倒して、攻撃を防ぐと同時に地面にぶつかった衝撃によるダメージを与える。
「ぐぐぐ……」
再び起き上がった麻獣。今度は吸血攻撃を試みようと、口を大きく開いて園子に襲い掛かる。
「うにゃぁあああああっ!!!」
しかし直前まで来たところで、園子がヘラを横に大きく振って強力なビンタ攻撃を食らわせた。
「しょっぼ。攻撃がワンパターンすぎるんじゃ。」
その後も園子は麻獣に対し激しい猛攻を仕掛けて、ダメージを与えていく。
たこ焼きとお好み焼きの為だけに作られた道具でケモミミ生やした一見すると変態と思わしき男性を成敗するという端から見ればシュールとしか思えない光景だが、アクション映画のに登場する格闘家ヒロインのようなしなやかな園子の動きに俺は見惚れていた。
「す、すごい…」
麻獣取締官として、死と隣り合わせで麻獣と戦う世界、そしてそんな世界で戦っている彼女の強さに感銘され、俺は思わずその言葉を口から漏らした。
「はぁ……はぁ……」
園子は激しい動きによる疲労からか、息を荒げ動きを止めた。麻獣がその隙をついてゆっくりと襲い掛かる。
「園子姉、危ない!」
俺が叫んだその時だった。園子はヘラを手にしている左手を下に、そしてピッグを手にしている右手を後ろに突き出した後、大きく深呼吸をして気力を高めだした。するとピッグとヘラから薄暗い光が発し始めた。
「あ、あれは……?!」
迫りくる麻獣が園子の目と鼻の先まで来たその時、彼女は目にも見えぬ一瞬のスピードで麻銃の背後へと通り過ぎた。
すると麻獣が両手で自身の目を覆い、何やら悶えている様子を見せている。
「フフッ・・・・・・」
園子はにやりとした微笑を浮かべる。
「ヒャッヒャッヒャーッ! 見たか勇人! これがウチの神技、”疾風刺殺"や!」
「今のが神技?!」
「そ! このピッグであいつに目潰ししたったんや! こーゆー道具でもええ必殺技になるもんやからホンマ最高やわ!」
「ハハハ・・・・・・ホンマ、色々とすげーな。」
園子が高らかに自慢するその時、呆然としながらその自慢を聞いていた俺が手に持っていたボールから彼女が技を発動したときと同様の光が発せられている。まさか俺にも……という歓喜の気持ちと驚愕の気持ちが入り混じり、ただただボールを眺めずにしかいられずにいた。
「勇人!それをこいつに当てるんや!」
「えぇ?!」
「ええから早よ投げろ! トドメ刺したれ!」
俺は言われるがまま、光るボールを麻獣に目掛けて思い切り投げてみた。その時俺は信じられない光景を目にする。投げた球から炎が燃え上がっている。その炎の球もとい投球攻撃は、球速およそ170キロ程度の速さで麻獣の体に直撃する。そのまま炎は麻獣の身体に移り始め全身を覆った。暴れ回って振り払おうとするも炎は消えることはなく、焼き尽くしていく。
「う……うせやろ?」
練習のときは普通の球でしかなかった俺の投球が、少年向け野球漫画のような魔球になるとは・・・・・・投げた俺自身も未だに信じられない状態である。炎が消えると同時に麻獣は意識を失い、全身が焦げた状態で倒れた。
その後、現場に警察が駆けつけ麻獣はパトカーで連行された。麻獣は普通の人間へと姿を戻していた。
「なぁ、園子姉。麻獣って元の姿に戻るもんなん?」
「麻獣はいっぺん満月見たら興奮状態なってああなるけど、時間たったら自然と薄れてって元に戻るんよ。麻獣になってたときの記憶は飛ぶけどな。」
「ふーん……。捕まった麻獣はこれからどうなんの?」
「更生施設に身柄押さえて、二度とクスリに手出さんように色々やってるらしいで。けど、身体の負荷とかが普通のヤク中の倍の時間から社会復帰できるようになるまでに治すにはそれなりにかかるんやって。」
「まぁ、あんな姿になったらそらそうなるよな……。」
人でない姿に変われば、全うな人間に戻れるのも当然時間がかかるのかもしれない。MONSTERに限らず、ごく一般の麻薬が原因で堕ちていった人間にも言えることだ。
麻薬は一度味わっただけで人生を大きく狂わされると教わったが、今回実際の現場を見る限りその想像以上のものだった。麻薬の力により衝動的に犯罪行為に走り、気がつけば牢獄の中にいる。そして世間からの信頼を得られるまで、一度きりの人生の貴重な時間を失うことになる。それでも、薬物を使用している人間がこの世界に数多く存在していることが事実である。麻薬を作る人間や売る人間達が卑劣な手口を利用して服用させているのか、使う人間が抱えている心の闇を一時的な快楽に変えるために自ら手を出しているのか……いずれにせよ、俺はこうした形で人の人生が壊れていくのが許せない気持ちでいる。
「そんなことより、初めての任務はどうやった?」
先ほどまでの俺の暗い思考を切り替えさせようとしてくれたのか、園子が明るい笑みを浮かべて問いかける。
「そうだな……もう色々ありすぎて頭おかしなりそうやわ。」
「フフッ、まぁ初めてやったらそうなるわな。」
他人事みたいに笑う彼女の態度に少し腹が立ったが、彼女に悪気はないので怒りの感情はそこまで沸かなかった。
「けど、取締官になってそんなにたってないのにもう神技が出るなんてなぁ…。」
「そらアンタは毎日結構な数投げて練習しとったから、技の習得なんかあっという間やろ。」
確かに俺は初めての訓練で投げて以降、休憩時間を返上して多くの時間を練習に費やした。実戦で戦力になるためには当然のことだ。
「それはそうやけど、だからって3週間ぽっちでああなるもんか?」
最初に投げたときに長い目で見る必要があると思った。ただそれは最低でも1年以上はかかるのではないかと俺は予測していた。
「せやから、勇人には野球に対する情熱があったから早く覚醒したんやで。最初に投げれへんかったんはアンタが野球に少し遠ざかってたんが原因ちゃうの?」
園子に言われて俺はハッとした。確かにそうかもしれない。プロの夢を絶たれてから俺は野球とは一切関わりを持たなかった。その時の辛く悔しい気持ちが再びこみ上げてきそうな予感がしたからだ。
「練習も当然大事やけど一番大事なんはやっぱり情熱とかやる気とかその辺やな。その情熱が練習を繰り返すことでまた燃え上がったんやと思うで。」
思い返してみれば、練習で投げていたときは苦しい気持ちはそれほどなく、むしろ楽しく投げていた。ただ楽しいという一言にとどまるものではなく、楽しくて懐かしい気持ちで投げていたことを思い出した。それが長い間静めていた野球への情熱が日々の練習を重ねるうちに自然と戻っていたというのか。やはり俺はまだ野球が大好きな野球バカだったんだな。何だか嬉しいような安心したような……そんな気持ちになった。
「けど、アンタは技ひとつ覚えてやっとスタートラインに立てたところやから、一人前にはまだまだ遠いけどな!」
園子に言われると少し悔しいが、ぐうの音も出ないほどの正論なので反論はできなかった。
今回の任務を通して、俺は改めて思った。
俺はプロの野球人として生きることだけを目標に生きてきた。そのために血の滲むような努力を沢山してきた。だが、努力をしてもプロになることはできなかった。現実という世界は厳しく残酷なものだから、それは仕方のないことだ。
ならば、プロの野球人になるために努力してきた経験を武器にして生き方をすれば良いじゃないか。
そう思った俺は取締官として麻獣と戦う日々を精一杯頑張って生きていこう。 そう心に決意した。
麻獣 -ASAKEMONO-
最後までお読みくださり誠に有難うございます!
本作の続きは『カクヨム』にて月に1回のペースでの発表を予定しております。
https://kakuyomu.jp/works/1177354054881111212
また、本作に対する意見や感想、批評等ございましたらコメント欄または下記のコンタクトにお送りいただけると幸いでございます。
Twitter:@Laymon_krs
Mail:Laymon160322★gmail.com
(★を@に変換)
それでは、今後とも烏丸れーもんおよび『麻獣-ASAKEMONO-』をよろしくお願いいたします。


