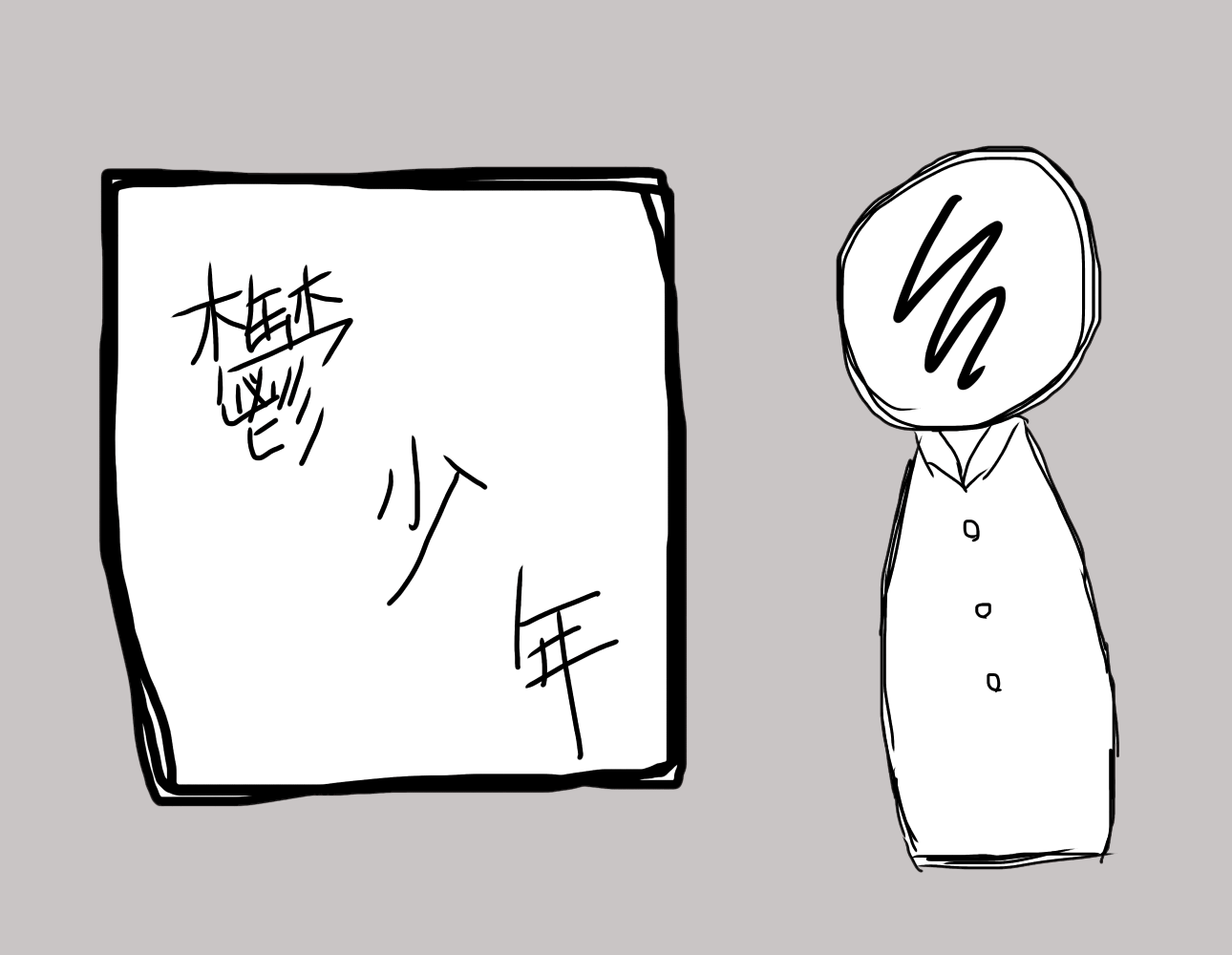
鬱少年シリーズ
鬱少年と蜜柑
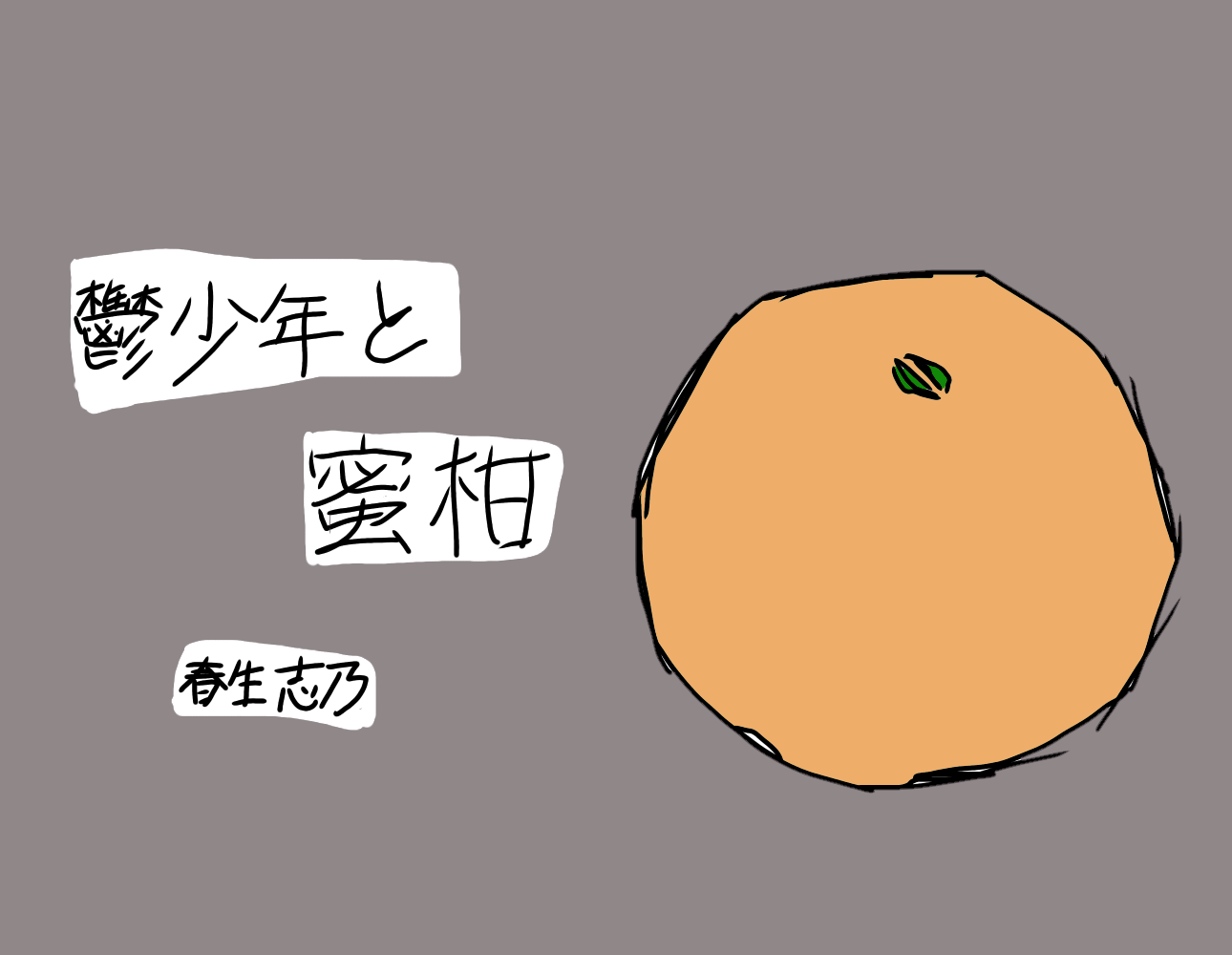
少年はいつからベッドの上にいるのか分からない。
けれど何度も朝が来て何度も夜が来た。
普通の人間なら、何度も同じことを繰り返していれば頭が狂ったようにおかしくなる。
けれど少年はその行為すらおかしいと思わなくなっていたのだ。
少年は思った。
こんなことを繰り返しているのなら死んでいても生きていても同じことだ。
久しぶりにベッドから起き上がり、少年はリビングへ向かった。
そこには誰もいなかった。
もう自分を必要とするものは誰もいなくなったのだ。
落胆という言葉よりも、少年には安心という言葉の方が先に思いついた。
誰にも必要とされないのなら、いつ自分自身が居なくなっても大丈夫なのだ。
少年はナイフを手にって、腹部に押し当てた。
その手はガタガタと震えていた。
震える手をもう片方の手で押さえつけても、思うようにナイフは当たらない。
ついにはナイフを落とした。
泣き崩れた少年は、途方に暮れた。
自分は死ぬこともできないのだ。
自分で招いたことなら、自分で終わらせるしかない筈なのにそれすら出来ないのは、死ぬことよりもよりも苦痛だった。
少年はその場から立ち上がりベッドへと戻ろうとした。
その時目に入ったのは、一つの蜜柑だった。
少年は思いついた。
ペン立てからペンを取り出し、蜜柑に自分の似顔絵を描いた。
似顔絵と言っても簡単な物だったが、なんとなく自分分身のように見えた。
少年はもう一度ナイフを持ってきた。
机に蜜柑を置いて安定させると、ナイフをそのまま一気に振り下ろした。
そのとき、スローモーションになったような気がした。
蜜柑の皮が破れ、一気に中の実が辺りに飛び散った。
少年はその光景を見て安堵した。
落ち着いた心で、ベッドに入り、また深い眠りについた。
鬱少年と男
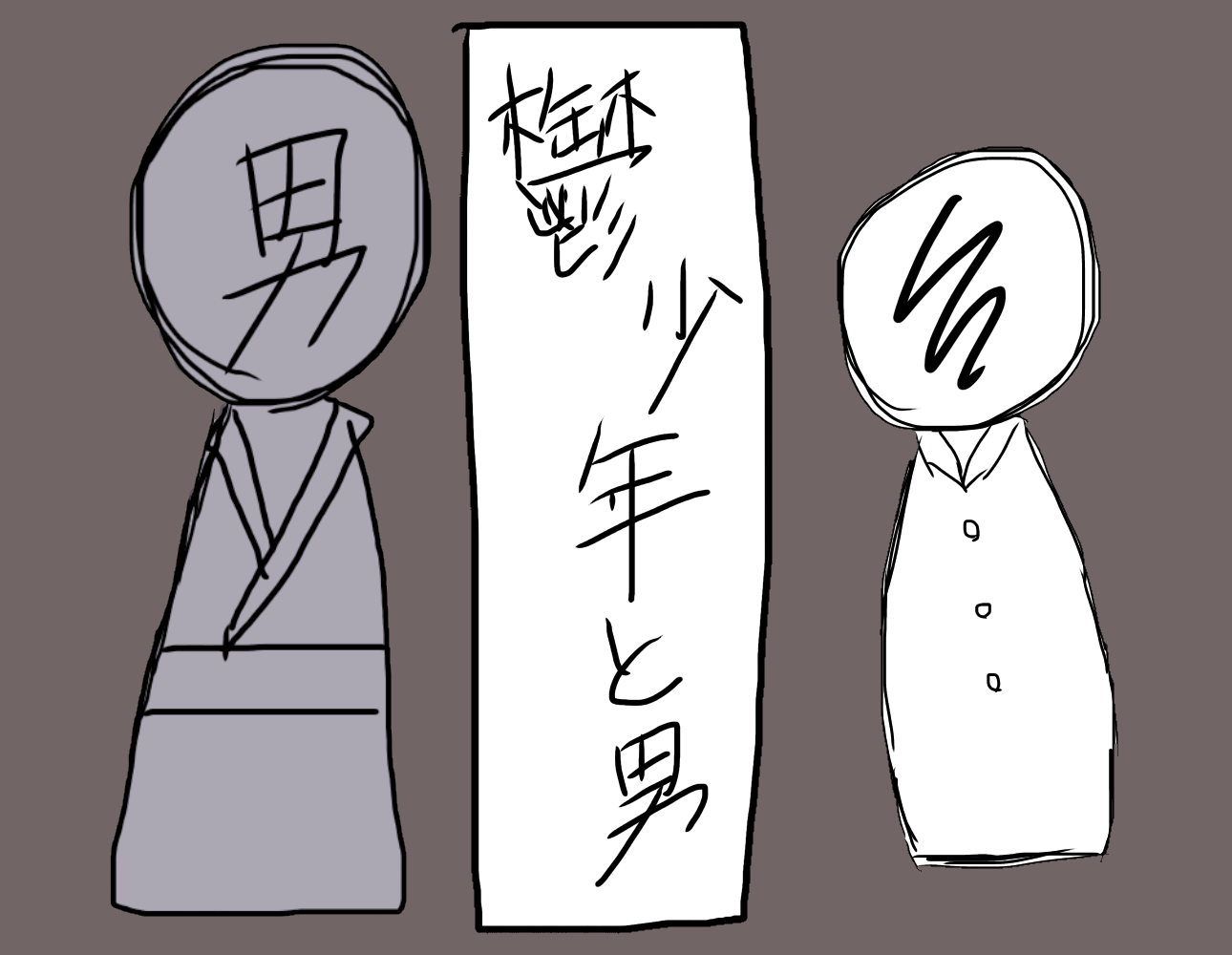
少年は何日もベッドの上にいた。
これで月が上ったのは多分十回目ぐらいなのではないだろうか。
少年は起き上がることにも無力で、ただひたすら天井を見た。
裸電球へ向かって掲げた手は痩せ細り、白かった。
薬の影響からか食欲は最も沸かない。
年頃ならば分かる性的な欲求や人への愛など何もない。
少年の目の前には「死」しかないのだ。
少年は絶望に手を下し、再び目を瞑った。
少年が目を開けると、いつものベッドから見える景色とは違う場所にいた。
少年はベッドではなく、座布団に座っていた。
一瞬目を丸くしたが、少年は悟った。
やっと自分は死ぬことが出来たのだ。
少年は喚起した。
もう何も考えなくていいのだ。
そんなことをしていると、襖の戸が開いた。
そこにいたのは痩せ細った着流しの男だった。
少年は何事かと、あたふたしたが、男はただ無表情で少年の向かいの座布団に腰かけた。
「自分が死んだとでも思ったのか」
少年は首を縦に振った。
男は急須に茶の葉を入れながら言った。
「死ぬことはそう楽なことじゃないだろう。死ぬまでに色々考えたり、やっぱり死なない方がいいのかとか、そんなことばかり考える」
少年はただ男の語る口元を見ていた。
「そんなことを考えているうちにいつの間にか時間が経って、また同じことの繰り返しをしてしまったと、さらに絶望する」
少年は男に脳内を見透かされているのかと思った。
「僕が言えることは、死んでも尚、人は苦しむということだ。死んだら死んだで、本当にこれが自分にとって良いことだったのかと悩むことになる。生きているうちは死という逃げ道があるが、死んでしまっては、もう逃げ道はなくなるんだよ」
それでも死にたいと思うか、男はそう言って僕の目を見た。
その目は冷たくてまるで死人みたいだった。
輝きもなく全てに絶望したかのような、そんな目だった。
僕は何も言わず俯いた。
「君は若いから、考える余地はあるよ。僕も君くらいの時はそうだった。君にはまだ時間が沢山あるのだから」
男は僕に茶を渡してきた。
その手に触れたとき確信した。
この男はもう生きてはいない。
手の体温がなかった。
僕がそれに気付いた時には、もう既に気失っていた。
再び目を開けると僕はいつものベッドの上にいた。
手にはひんやりとした感覚が残っていた。
鬱少年シリーズ


