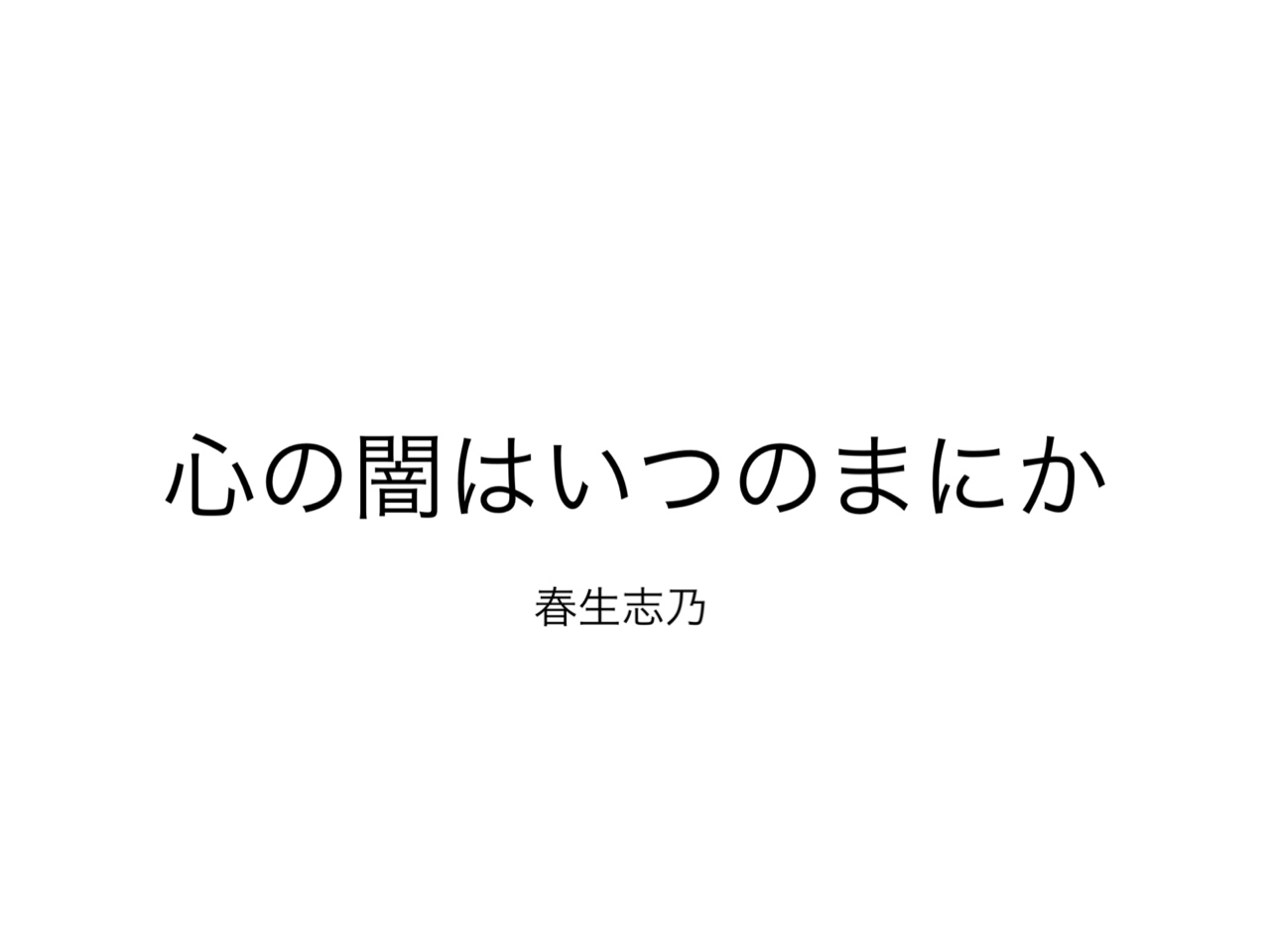
心の闇はいつの間にか
いきなりだが、私は世間一般的に言われている鬱病だ。
僕が鬱病だと知ったのは最近のことで、教授から「いい加減病院に行け」とメールが来たことで、病院に行く決心をした。
僕自身は全く鬱病だと思ってはいなかったが、医学に詳しい教授を信じ病院へ行くと、教授の言った通り、案の定鬱病と診断された。
医師から軽い質問を受けた。
「あなたは死にたいと思った事がありますか?」
僕は考える間もなく答えた。
「死にたいと考えた事がない人なんて、この世にいるのでしょうか?」
先生は何かを記入した後、また質問をしてきた。
「貴方は自分のことが好きですか」
「いいえ、嫌いです」
「外に出るのが怖いのですか。それは何故ですか」
「沢山の人が僕の悪口を言っているように感じるからです。僕は僕を守るために家から出られません」
僕は自分の事を好きだと思った事がないし、何もできない、他人に迷惑ばかりかける屑だと思っている。
だから外に出たら流れていく人皆が僕を罵っていくのだ。
「このようになってしまったきっかけなど、自分ではわかっていますか」
「わかりません」
先生はカルテを読みながら言った。
「気づかないうち、子供の頃からのストレスや、今の現状に心がついてきていないようですね」
「はあ」
「子供の頃、どんなことがあったかや、自分がストレスだと思っている事は思い出せませんよね?」
「何も思い出せません」
「とりあえず心を落ち着かせるような薬を出しておきます。眠れないとも仰っていたので睡眠薬も出しておきますね。とりあえず一週間飲んでみて様子を見ましょう」
その時の診察はここで終わった。
僕は家に帰ると真っ先にベッドに入った。
自分が精神病だったなんて、誰にも言いたくない。
そんなことが頭を過った。
僕は処方された薬を手に取ると、枕もとに置いていた水を飲み、薬を体内に入れた。
すぐに深い眠りに落ちた。
しばらくして目を覚ますと、いい匂いがした。
肉の焼ける匂いだ。
重い体を起こし、ベッドから降りる。
リビングからはカチャカチャと食器の音がする。
「あ、おはようございます」
そこにいたのは後輩の斎だった。
斎 伊織は僕の一個下の後輩だ。
「可愛い女の子じゃないのか。萎える」
「先輩に可愛い女の子の友達なんていないでしょう」
図星だったので何も言い返さなかった。
斎は料理をテーブルに置き、僕を椅子に招いた。
「どうせまた何も食べていないんでしょう」
「そうだけど、今食欲ない」
「まあ薬のせいでしょうね」
何故こいつは薬のことを知っている。
「すみません。先輩の様子を見ようと先輩の寝室に入ったら、枕元に薬があって見てしまいました」
「ほんとデリカシーないな」
すみません、と謝る斎の顔は無表情で何を考えているのかもわからなかった。
いつも無表情なので、僕は慣れている。
「食べれる分だけでいいんで、食べてください」
「わかった。残すけどごめん」
暫くお互い無言の空間が続いた。
先に話を切り出したのは斎だった。
「先輩、大学に来ない間何してたんですか」
「あー。ちょっとした文を書いてた」
「先輩らしいですね、どんな文ですか?」
僕は斎にどんな事を書いていたのか話した。
人間は、何の目的で生きているのだろう。
毎日勉強や仕事に追われ、けれどそれが当たり前みたいになっている。
それは生きる目的ではなくて、人間が勝手に作り出したルールであって、本当の生きる理由なんかではない。
ルールを無視すれば邪険に扱われたり、いじめの対象になったり、最終的にはおかしいやつなんて言われる。
ルールに縛られずに生きている人間の方がよっぽど利口なのではないだろうか。
ルールに歯向かわず生きている人間は、ただ自分が除け者にされるのが怖いだけだ。
今私はルールに生きているが、利口な生き方だと思わなくなってしまった。
「先輩は考えすぎなんですよ」
斎はいつも変えない表情を困らせて言った。
「先輩が考えすぎて生きてる以上、治らないと思います」
「何でそう思うんだよ」
「だって、人間なんてやりたいと思った事が絶対にできるわけじゃない。縛られていようが縛られていまいが、その人自身ができることなんて限られてる。だからみんな限られた中で、一番やりたいことをやっているんだと思いますよ」
斎はコーヒーを啜りながら言った。
「お前は頭がいいから、そんな簡単に言えるんだ」
「俺より、先輩の方が頭がいいですよ。そんな考え、普通の人ならいちいちしませんから」
斎は無表情だが根は優しい。
いつもこいつの正論に甘えてしまう。
「先輩の考えは否定しませんが、これ以上落ち込まないように試行錯誤してくださいよ。考えすぎた果てに自殺なんてどこぞの小説家じゃあるまいし」
「そうだな。その時になったら考えるよ」
僕はタバコに火をつけようとしたが、タバコを取り上げられた。
「今は落ち着いて、何も考えない方がいいと思います」
「タバコくらいいいじゃないか」
「興奮して眠れなくなりますよ」
斎は僕の手を引いてベッドに落とした。
「俺は帰りますけど、先輩は寝てください。教授には俺から何とか言っておきますから」
「これじゃどっちが先輩かわかりゃしないな」
「明日また来るんで、その時は落ち着いてまた話しましょう」
僕は斎の背中を見送った後、静かに目を閉じた。
鬱病と診断され、消沈していたが、斎のような物分かりの良い人間がいれば、僕自身の回復には兆しが見られそうだ。
他の患者にも、同じような理解者が居れば、この病気に苦しむ人が少なからず減るのではないか、僕はそう思った。
心の闇はいつの間にか


