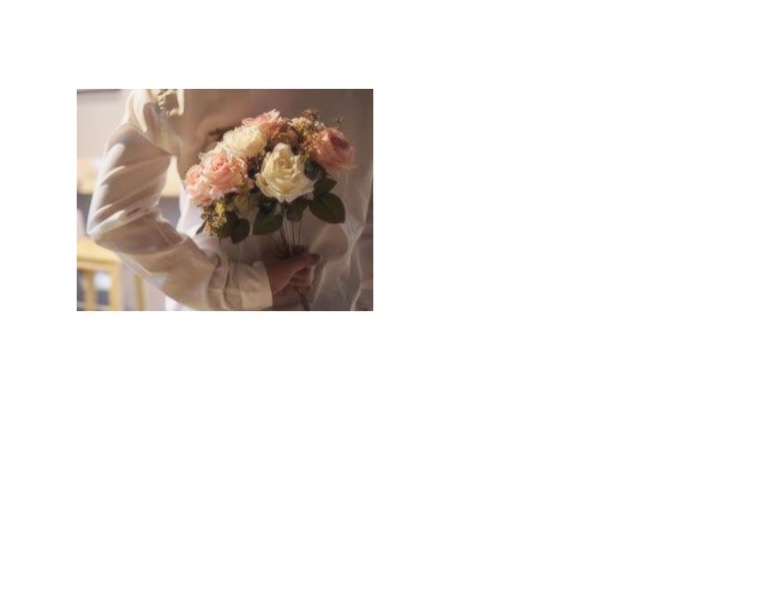
花束
「どう思う?」
さっき届いたばかりの段ボールを次から次へと開けながら、僕に話しかけてきた明里に、持っていた段ボールを床に置いて彼女へと視線を移した。
『ん?何が?』
「これから二人でやっていけると思う?」
これはこっちで、なんて呟きがら、食器を次から次へと棚に片付けていく手早さは仕事柄なのだろうかとふと思った。
『んー、どうかなぁ。ってか今更?』
僕が聞き返すと、「それもそうね」と笑って手を動かし始めた明里を見て、近くにあった大きな段ボールを上に重ねて奥の部屋へと運んだ。
駅から徒歩七分の二LDK、南南東向きの一番角の部屋へと引っ越しを決めた一番の理由は、便利が良いからだった。
お互いの職場が同じ沿線上になり、引っ越しシーズンに丁度いい部屋が空いたことも重なり、いくつか見て回った中の初見でこの部屋に決めた。
明里はアンティークショップの販売員をしている。今年の春から都内の店舗へと移動が決まり、僕は仕事で帰宅時間が不規則なため、出来るだけ通勤のしやすい土地へ引っ越そうと考えていた時、彼女も同じことを考えていた。
付き合って五年が経ち、お互いの生活リズムも知っていること、お互いの両親から結婚の二文字を匂わされていることを含めると、同棲という流れになるのはごく自然のことだった。
『……明里のモノ多すぎないか?』
「女の子はこれくらい普通よ。っていうか浩平が少なすぎるんだよ。」
『男なんてこんなもんだと思うけどなぁ。』
明里は、ヴィンテージや年代物の小物を扱う雑貨屋で働いている。
雑貨が好きで、他店にも足を運んでは気に入ったものがあればコレクションに加えているあたりは、趣味と実益を兼ねている、とでも言うべきなのだろうか。
まだ完全ではないが、ある程度仕上がった部屋を見回し、明里の荷物量に驚く。
軽く僕の三倍はあるだろう荷物が、前に住んでいた部屋によく収まっていたものだと、別の意味で感心した。
「浩平、少し休憩しない?」
『うん。そうだね。』
南向きの窓からは、薄橙色の夕陽が部屋を照らしていた。
「ブラックでいい?」
『あ、うん。ありがとう。』
机はまだ届いていなかったから、近くにあった空き箱をひっくり返し、その上に仕切りとして入っていた平らな段ボールで簡易テーブルを作った。
まだ何もひいていないフローリングはひんやりとしていて、桜の蕾は日に日に膨らんでいたが、まだ三月なのだと改めて感じる。
『このコーヒー、香りがいいね。』
明里からマグカップを受け取り、嗅いだことのない香ばしいコーヒーの香りが部屋に広がると、新居の香りと一緒に吸い込んだ。
「でしょ?この間お客さんから頂いたの。名付けて、明里ちゃんスペシャル!」
『……お湯を注いだだけだろ。』
「分かっちゃったか。まぁ美味しいからいいじゃない。」
笑みを浮かべた明里は、マグカップに息を吹きかけながら慎重に口を付けた。
それを横目に僕もゆっくりと口を付けた。
「桜、いつ頃咲くのかなぁ。」
『確か、再来週末には咲き始めるってテレビで言ってたよ。』
このアパートのすぐ横には、桜の木が三本程植えられていて、幼い頃に遊んだ懐かしい遊具がいくつかある小さな公園があったはずだ。
初見のとき、今年はベランダから花見ができると明里が嬉しそうに話していた。
『早くお花見したいなぁ。あ、今年は目黒川を歩くのもいいかも。』
頭上が一面ピンク色の花びらで覆いつくされる景色を想像しているのだろう、目を瞑ってマグカップを両手で包み込む明里は、 穏やかな表情をしていた。
ゆっくりとした空気が二人を包む。
明里とは、無言の空間でさえ心地よく感じる。
もともと口下手で人の話を聞くほうが向いている僕にとって、何か言葉を発しなければと焦って口走っても会話が続かず、気まずい空気の中で終わってしまうことが多く、何ともいえない気持ちになることが多かった。
彼女と初めて会った時もそうだった。でも彼女は、僕が言った何気ない言葉に笑ってくれて、言葉に詰まったときには「私、無言の時間って好きなんです。」と笑顔でフォローをしてくれた。
だから気にしないで、と微笑んだ彼女を見たときには、きっともう好きだったのだろう。
明里は、膝にかけていたウールケットを肩にかけると、僕に背を向けるように窓と向かい合わせに立った。
僕に向かって伸びる明里のシルエットが、僕の足に少しだけ重なる。
『ねぇ、こーへい。どう思う?』
思い出にふけっていると、突然話しかけられ、どもりながらも返事をした。
『…どうした?』
「…これから二人で、やっていけると思う?」
何度目かの同じ問いかけに、彼女がどんな考えを持って僕に投げかけているのかは分からなかったが、ゆっくりと口を開いた。
『これからのことは分からないけど、一緒にいたいと思ってるよ?』
彼女の背中に向かってかけた当たり障りのない言葉が、冷たくなった空気に紛れていく。
耳には届いているだろうけど、その奥にはきっと届いていない。
動揺をごまかすように流し込んだコーヒーは、先程よりも苦く感じた。
「……うん。私もそう思ってるよ。」
だけどさ、最後は私がフラれると思うんだよね。」
彼女の突然の言葉に、コーヒーを吹き出しそうになり、顔に力を入れて慌てて口に手を当てた。
危なかった、もう少しでフローリングを茶色に染めてしまうところだった。
『い、いきなりっ……』
抗議しようと窓際に目をやると、微動だにしない明里の後ろ姿が目に入り、言葉につまってしまう。
『…と、りあえず、一緒にいてみようよ』
彼女は短い返事をして、僕のほうへゆっくりと振り返った。
「浮気しても言わないでよね?
知らなかったら、悲しくもならないし、一緒にいられるでしょう?
だから、ちゃんと隠し通してよね。」
明里との間に、微妙な間が通りすぎる。
それは、いつも感じる心地よい間ではなくて、息が詰まるような苦しい間だった。
「……っあ、もうこんな時間。そろそろ夕ご飯の買い出しに行かなきゃ。」
雲に隠れた夕陽で表情が見えなかったが、明里が腕時計を見るようにうつむいた瞬間頬を伝った一筋の雫と、少しだけ震えた肩は僕の見間違いではなかった。
抱き寄せた明里の身体は、僕の胸の中にすっぽりと収まり、右胸の辺りが湿った。
『……っつ、もしかしたら、一緒にいる時間が増えたらっ、浩平が私に飽きちゃうかもしれないでしょ?
そんなときに魔が差して、浮気しても、っ、私に絶対バレないようにしてね、?」
懸命に笑おうとする彼女の考えを理解できていなかった自分に嫌気がさす。
揺らいだ声色に胸をわしづかみにされているようで痛かった。
同時にこんな時でも僕に自分の気持ちを伝えようと強がる明里が愛おしくて、抱きしめる腕に力を入れた。
「ちょっ、苦しいって、浩平」
僕の胸を押す彼女を、さらに抱きしめる。
「こーへい?」
『ごめん。』
「……え?」
『不安にさせて、ごめん。』
明里が抵抗することなく僕の胸に体重を預ける。
『明里と出会ってから僕は、明里しか女の子に見えていないから。』
「……嘘。この間、レジでアメをくれた店員さんのこと見て赤くなってた。」
明里の言葉に、不謹慎にも顔が緩む。
『少しだけ明里に似てたから。』
「……私、あんなに美人じゃないもん。」
『ありがとう。そんなに見てくれてて。』
「……ばか。」
明里の体温が僕にも移って、全身に広がってじんわりと暖かくなる。
「……ごめんね、面倒くさくて。」
『いや、僕もごめん。言葉にしなくて。』
「本当だよ。ばか。」
明里の優しい怒声に、少しだけ安堵する。
胸から離れた明里の目尻には、涙が残っていた。
それを親指で拭って、唇を重ねた。
片付けを進めて居住スペースを確保した頃には、窓の外は夕闇に包まれていた。
夕飯の買い出しに、新居から一番近いスーパーまで手を繋いで歩いた。
片道十分のスーパーまでの距離が、一瞬に思えた。
買い物中も、その帰り道も、明里の手を離さなかった。
「買い物しづらいよ」と頬を染めて笑った明里は、出会った頃と同じ笑顔を僕に向けていた。
大雑把な僕に怒りながらも、キッチンに立って二人の好物を作って、安くて美味しいワインで乾杯した。
美味しい料理に舌鼓を打ちながら進んだお酒に、アルコールに弱い明里と僕は酔っ払って赤くなったお互いの顔を見て笑い合って、
最終便で届いたソファに身を沈めた。
明里がお気に入りのお店で見つけたブラウンレザーのソファは、吸い付くように柔らかい革の手触りと、長く使えるシンプルな形に二人で即決した。
座り部分が広めのローソファで、アーム部分も幅広く枕代わりにもなる作りで、まるで第二のベッドのようなデザインだ。
明里曰く、ケンカしても僕が快適に寝られるようにとの配慮に突っ込みを入れたくなったが、そんな時のことも考えてくれてることのほうが嬉しかった。
引っ越しの当日に配達してもらえるように手配した甲斐があり、二人で手を繋いで寄り添って眠った。
話し下手だから、なんて理由で目の前の大切な人を不安にさせて、改めて自分のふがいなさを理解して、でもそんな僕を受け止めてくれた彼女の優しさと大切さを再確認した。
思っていることは、いくら近くにいたって、言葉にしなきゃ伝わらないのだから。
『僕は明里と、これから何回だって何十回だって、抱き合って、手を繋いで、キスもして、たくさん思い出を作っていきたいんだ。
そりゃ、ケンカもするどろうけどさ。でもそのたびに、謝るし感謝の言葉も忘れない。
もしかしたら、謝る回数のほうが多くなるかもだけど、許して。』
そう言うと明里は、「しょうがないなぁ」と目を細めて笑った。
星を閉じ込めたような瞳は、月明かりに照らされてきらきらと輝いていた。
「どう思う?これから、二人でやっていけると思う?」
タオルケットから顔を覗かせた明里が、先程と同じ質問を投げかけた。
『どうかな?これから始めてみないと分からないよ。
……でも、
僕は、明里が好きだよ。』
そう言って、彼女のおでこにキスをした。
花束
某3ピースバンドの歌詞より。彼らの曲を聞くといつも想像力が爆発します。


