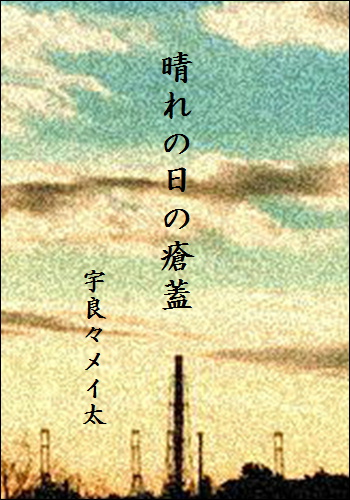
晴れの日の瘡蓋【第六話】
六、吉日
1
学校帰り、彼女の学校の前で私は待ちぼうけていた。
とっくに授業は終わっているはずなのにマコトは姿を見せない。
約束をするぐらいなんだから、部活に出ているってことはないだろう。
いつもなら彼女の方が待っているのに、この日は様子が違った。
四〇分ぐらいして、彼女が正門から出てきた。
「ごめん、遅くなって。」彼女は駆け足しながら言った。
「ちょっと、剣道部覗いてた。」
「剣道部に入るの?」
「いや、入らない入らない。ただ、どんなもんかなあって。」
「どうだった?」
「うーん。何とも言えないなあ。」
「またやればいいのに。」
「いや、そんな時間ないよ。今の私には部活より勉強が第一。剣道部に入ったら、そっちに集中しなきゃだから、勉強時間がなくなっちゃう。」
「両立出来るよ。」
「無理無理。うちの剣道部厳しくて有名だから。よっぽど頭良くないと両立なんて無理。」
「マコトだったら大丈夫だよ。頭いいから。」
「それ本気で言ってんの?この前の中間の結果見たでしょ?あんな結果だったらサクラと同じ高校行くなんて夢のまた夢だよ。ホラ、とにかく今は勉強勉強!」
マコトは笑顔でそう言った。
とりあえず元気だった。いや、何かを吹っ切るようにムリヤリ元気を演じているみたいだ。
こうやって待たされることが何回かあった。
毎回剣道部を覗いては自分に踏ん切りつけていたように見える。
また剣道を始めていたら、多分彼女はずっと彼女らしくいられたんだと思う。
無理にでもやらせるべきだったのだろうか。いや、私の意見なんて聞かないだろう。
そもそも私自身心からまた彼女に剣道を始めて欲しいと思っていただろうか。
マコトがまた剣道を始めたらきっとそれにのめり込む。
私をおいてけぼりにして。
マコトの新しい目標に寄り添っていれば、マコトは私から離れることはない。
マコトと一緒にいられる時間を失いたくなかった。
こんな私のイヤらしさにマコトは気づいていただろうか。
マコトの新しい目標を見失わないよう、私に出来ることなら何でもしてあげたい。
誰かのために尽くしてあげたいと思ったのは初めてだった。
おじいちゃんが亡くなってから、マコトが家族と会話しているところを見たことがない。
彼女はいつもおじいちゃんの部屋でひとり寂しそうにしていた。彼女の喪失感がどれ程のものなのか正直私には解らない。
安易に解ると言ってしまえばそれは彼女に対してあまりにも失礼なことだ。
大切な人との永遠の別れ。私はまだ経験がない。所詮私は他人。彼女の心を満たすことなんて出来るわけがない。
そう思っていても、みんな幸せそうにしていた笹之辺家に戻って欲しいなんて考えている。
叶うわけもないのに。
受験勉強がいよいよ本気モードに突入する頃には、彼女のヘタクソだった文字も上達していた。
マコトは大雑把に見えて実は繊細なところがあり、それでいて私なんかよりずっと器用だった。
二人でお絵描きをしていた時も、悔しいけど彼女の方が上手かった。
私はマコトからインスピレーションを受けることが多い。実際、今でも彼女のアイディアや作品が私の基礎になっている。
謙遜してるけど、実は勉強も出来る。ヘタしたら私なんかよりずっと頭が良い。彼女に勉強を教えてあげている時でも私の方が考え込んでしまうことがあって、そんな時はちゃんと自分で答えを出していた。
合格発表の日、彼女は今まで見せた事のない笑顔で喜んでいた。しきりに「ありがとう。」を繰り返していたけど、私はただ彼女の勉強に付き合っていただけ。私がいなくたって普通に受かっていたと思うし、それで結果がちゃんと出ただけだ。
新学期。私と同じ制服に身を包んだマコトがいる。
あどけない顔つきが少しだけ大人になった。女らしくなった。
私との距離が広がった。そんな気がした。
新生活が始まって早々、既に彼女のまわりには人が集まっていた。
彼女は年齢性別関係なく誰に対してもありのままで接する事が出来る。
人に会う度に壁を作ってしまう私とは正反対だ。本当に羨ましい。
彼女には一切壁がないのだろう。まるで自由に空を飛び回る鳥のようだ。少なくとも私にはそう見えていた。
相変わらず私には閉塞感が付きまとっていた。
誰かと一緒にいても、心のどこかで冷めた自分がいる。
もうひとりの自分が激しく私という人間を嫌う。
もうひとりの自分はお母さんそっくりだ。
私の大嫌いな私。
いつも目の前に立ちはだかる。
三年前のクリスマスに表参道のカフェで家族三人最後の時間を過ごして以来、お母さんとは一度も会っていない。
この頃には既に新しい彼氏と暮らし始めていたようで、時折会話の中にそれを匂わすようなニュアンスがあった。
この時のお母さんは、もう私の母ではなく、只の一人の女にしか見えなくなっていた。母が女になる姿を見ても特段何も感じなかった。
この時ほど自分という人間が普通ではないと感じざるを得なかった。
目の前にいた母だった人を見ていると、唯々哀れに思えて仕方なかった。これからもこの人は誰かを愛する事も、誰かに愛される事もないのだろう。彼女にあるのは自分を見て欲しいという欲求だけ。自分の分もわきまえず、自分が持っている以上の事を見せつけようとする。
なんて悲しい生き方なんだろう。
お父さんは少なくとも家族というものを最後まで愛していた。愛していたからこそお母さん、そして私が傷つかないための選択をした。
その事を黙ってただ飲み込む。マコトと同じだ。
私はそう言う人が愛おしくて仕方がない。非力なのはわかっているけど、何とかしてあげたくなる。
最後の時間は淡々としたものだった。結局お母さんと一言も話さないまま終わった。
このまま一生会えなくても、それはそれで別に構わないと思った。
正直、あの人がどうなろうと私の知ったことじゃない。
お母さんが家を出て行ってから、私とお父さんは学校から十五分ほど歩いた場所にあるマンションに引っ越した。
新しい場所での生活が始まった日の夜、私は今までのことを全部に話した。
お父さんが、お父さんの心が再び彼女の元へ戻ってしまわないように、これまでに彼女にされたことを洗いざらい話した。
これまでお母さんから罵声を浴びせられたり、何度も手を挙げられることがあった。その都度私というものが消えて失くなっていった。
彼女は私といると不機嫌になった。
自分は憎まれる人間で、私が存在しているだけでみんな嫌な思いをするのだと思っていた。だから私はいつも〝良い子〟であることを心掛けた。
お父さんはひとしきり話を聞き終えると、静かに口を開いた。
「咲良、すまなかった。君が辛い思いをしていたことはわかっていたのに、それなのに何もしてやらなかった。俺は父親失格だよ。本当に。それよりも彼女を、お母さんを信じたい気持ち、守って行きたいという気持ちのほうが強かったんだと思う。お母さんは今まで他の人よりずっと辛い思いをしてきたんだよ。幼い頃に両親が離婚して、どちらとも彼女を置いて出て行った。それ以来彼女の叔父さんと叔母さんの家で子供時代を過ごしたんだ。自分に両親がいないことへの負い目があったんだと思う。彼女の性格は彼女の人生そのものだ。彼女は虚勢を張ることで何とか生きてこられた。多分、俺は同情していたんだと思う。何としてでも守らなければいけないと思った。それが俺の使命だと思った。」
お父さんは時折鼻を啜らせていた。
「実は君とお母さんのことでずっと悩んできた。出来ることなら二人を守って行きたい。それがお父さんの願いだった。でも結局俺がハッキリしないから、何もかもどっちつかずで今日まで来てしまった。もっとしっかりすべきだった。咲良にはお母さんのような辛い思いだけはさせたくない。それには遅すぎたかもしれないけど、これから咲良が前に進んで行けるようにしてやらなけりゃならないと思う。何があっても咲良だけは守って行きたい。そう心から思う。だから君が帰って来られる場所を無くさないために・・・俺は・・・お父さんは努力するよ・・・だから、どうか許して欲しい・・・」
お父さんは泣いていた。お父さんの涙を見て私も泣いた。
お父さんの帰る場所はどこかといえば、それは間違いなく私だろう。
私の帰る場所は・・・・
2
「サクラ!」
私は咄嗟に目の前にいるマコトを見た。
「ちょっと、話聞いてんの?」
「ごめん、ちょっと疲れちゃって・・・」
「最近ちょっとボーッとしてることが多いよ。何かあったの?」
「いや、大丈夫。で、どう?ちょっとは進んだ?レポート。」
「全然!」
「そんな威張って言わなくても・・・。真木瀬君はどう?」
「うん、いや、全然。」
「真木瀬・・・・、このテーマでやるって言ったのお前じゃん・・・。なんすかこの体たらくは・・・。」
「う、うるせえなあ、お前、何にもアイデア出さなかったじゃん!俺ばっかに期待してんじゃねーよ!」
「真木瀬さあ、最初俺に全部任せとけとか何とか言ってなかったっけ?」
「はあ?言ってねーよ!俺はアイデア出しただけだし。」
「何その無責任。あーあ、二人だけとかムリ。しかも真木瀬なんかとじゃあ!」
「こっちだって嫌だよ。・・・・よりによって俺らバカ二人が組むことになるなんてなあ・・・」
「真木瀬、バカはお前だけだ。一緒にするな。」
「・・・・そうですね、すみませんでした、笹之辺さん。訂正します。バカはあなただけでしたね。」
「・・・・・むかつく。」
「フ、フフフフ・・・・」
「・・・・何笑ってんの?サクラ。」
「だって、なんか夫婦漫才みたい。」
「・・・サクラさん、やめてもらえません?こいつと一緒に、しかも夫婦設定にされるとか、マジありえないんで。」
「だって、マコト、二人ともなんかカワイイ。二人とも凄くお似合いだと思う。」
「ちょ、ちょっとサクラ!本当に怒るよ!」
「先輩、本当勘弁して下さいよ!」
こんな他愛もない二人のやりとりで少しだけ癒されたような気がした。
真木瀬君と会ったのはこの日が初めてだった。
彼らは学校で出された課題に取り組んでいた。課題の内容は覚えていないけど、取材のために横浜の新聞博物館に行くと言うので、マコトに頼まれて私はそれに付き合った。
このコンビ結成のきっかけは、課題の班を決める時に二人ともたまたま風邪で休んでいたということ。欠席裁判ってやつだった。
同じようなタイプの二人がコンビを組むことになってしまった。
二人とも凄く仲が良く見えた。二人は姉弟みたいで、まるで希くんとケンカしているような感じに見えてどこか懐かしく思えた。
この日から私たちは三人で遊びに行くようになった。
私が楽しみだったのは二人の会話だった。
真木瀬君とマコトの会話は、昔、笹之辺家で見ていた笹之辺君や希君とのやりとりに似ていて、小学校の頃に戻ったような感覚だった。
私の新しい居場所はここかも知れない。そう思うと心の枷が外れて行くようだった。
夏休みが始まる頃、マコトは近所の喫茶店でアルバイトを始めた。
このお店はマコトのお父さんの同級生の店で、家の近所にあるのは子供の頃から知っていたけど、私は一度も行ったことがなかった。
アルバイトを始めたきっかけは、マスターがバイク事故で入院してしまい、自分が不在の間だけでいいから店の手伝いをして欲しいと頼まれたからだと言う。
私たちの高校はアルバイト禁止だったけど、知人のお店の手伝いということで、学校には特別許可を貰っていた。
アルバイトを始めて何日か経った頃、私と真木瀬君は彼女の様子を見に喫茶店に入った。
「ちょっと、何しに来たの?」
マコトは恥ずかしそうに言った。
「ちゃんと仕事出来てるかチェックしに来た。」
真木瀬君は言った。
「何だそれ。」
「調子はどうだ?」
「どうって、別に何にもないよ。」
「もうとっくにクビにされたかと思ったけど、まだいたんだな。」
「ああもう腹たつ!!もう、目障りだからさ、サクラ置いて一人で帰っていいよ。」
「何でだよ!俺は客だぞ。もてなせよ!」
店に入っていきなりこんな感じだった。
私は可笑しくって仕方がなかった。
とりあえず私たちは奥さんに案内された席に着いて、アイスティとチョコレートパフェを注文した。
二人向き合っていたら、だんだん何を話したらいいかわからなくなってきた。
真木瀬君はチョコレートパフェのクリームをスプーンでずっとかき混ぜている。
私は私でアイスティの氷をストローで突いていた。
カフェに入る前はマコトの話でそれなりの会話が出来ていたのに、ここへ来て急に話すことがなくなってしまった。
この時、自分の心が硬くなっているのを感じた。なぜか凄く緊張していた。
こんな時、笹之辺君なら自分から色々話てくれるだろう。
でも目の前の彼は何も言わない。
何か話さなきゃって考えれば考えるほど気まずい空気になって行った。
彼もこの空気を感じていたようで、会話を必死に探していたのだろう。
パフェの上に乗っていたアイスが溢れ落ちてているのに全く気づいていない様子だった。
スプーンでかき混ぜる彼の手を見ると、長くてキレイな指をしていた。
それを眺めていたら、自分が夢の中にいるような錯覚に陥った。
何を思ったのだろう。私はパフェのバナナを取って自分の口に放り込んだ。
真木瀬君は驚いて私を見た。
私も自分のした事に気が付いて、思わず真木瀬君を見た。
彼は目を丸くして私を見ている。
だんだん恥ずかしくなって私は彼から目をそらした。
その様子を見て真木瀬君は吹き出した。
私も恥ずかしさと自分のしたことがバカらしくて吹き出してしまった。
そこから私たちは笑いが止まらなくなった。
晴れの日の瘡蓋【第六話】


