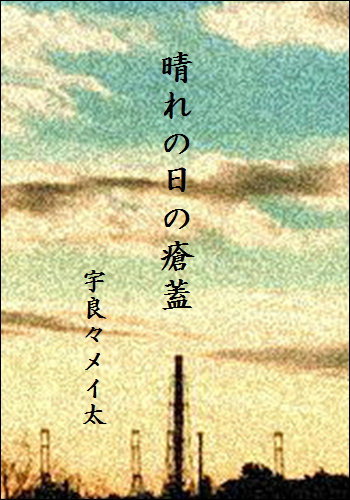
晴れの日の瘡蓋【第五話】
五、日常
その日、いつも通り家を出たところで、おじいちゃんに呼び止められた。
「真、今晩御飯でも食いに行かないか?中学校のこととか色々聞かせて欲しいんだよ。」
「学校?別に普通だよ。特に話すこともないし。」
「まあ、そう言うな。今日は時間あるのか?食いたいもん何でも食わしてやるぞ。」
「あんまり時間ない。最近忙しいから。」
「そうか。」
「また今度にしてくれない?」
「今日はダメか?」
「うん。」
「そうか。」
そう言うおじいちゃんの目は寂しそうだった。
「じゃあ、行ってくる。」
「おお、行ってこい。」
少し歩いたところでまたおじいちゃんが声をかけて来た。
「真!勉強頑張れよ!」
私は少し恥ずかしくなって「わかってるよ!」と言ってその場から逃げるように走った。
中学生になると反抗期もあってか、家族といることを恥ずかしく思うようになっていた。あの怪我の日以来おじいちゃんと会話する回数は減り、面等向かって喋ったのも久しぶりだった。
その時の私は美術部と演劇部を掛け持ちしていて、部活が終わるとサクラと待ち合わせて近所の図書館で勉強に集中したり、その上、週三日は塾にも通っていたので、帰宅するのは大体午後六時、遅い時は九時を回っており、事実本当に忙しかった。
当時私には新しい目標があってそれに向けてとにかく猛勉強するしかなかったのだ。
授業が終わって部活に少し顔を出したあとすぐ帰宅した。その日もサクラに勉強を教えて貰う予定だったけど、急用が出来たとかで来られなくなり、私はいつもより早めにうちへ帰った。
夕食までの間ちょっとだけ眠るつもりがぐっすり熟睡してしまい、目覚めると朝になっていた。
外へ出るとおじいちゃんが庭の植木に水をやっていた。私に気づいていない様子だったので、そのまま何も言わずに学校へ向かった。
生温かくて柔らかな風が通学路を通り抜ける。風の行方を追って振り返ると、そこにはおじいちゃんが何時ものように庭の世話をしている。何も変わることのない、何ものにも変えることのできない、いつもの日常だった。
夕方、私はいつも通り帰路を歩いていた。同じ部活の女の子たちと何気ない会話をしている。
向こうからサイレンをかき鳴らしながら救急車がやってきた。
私たちの日常を飲み込みそうな勢いですぐ横を通過する。
少しだけ右手が疼く。
心の底の方で何か不吉な予感がした。
胸がざわめいている。
一瞬私だけ残して世界が止まったみたいだった。
生温かな風が私たちを包み込むと、世界は再び動き始める。
私は何事もなかったかのように、元の〝日常〟を続けた。
彼女たちと別れ、玄関を開けるとニィが青い顔して玄関口で突っ立っていた。
ニィは何か言おうとしていたけど、目が泳ぐばかりでハッキリしない。
「なに?どうしたの?」
私の言葉に少しばかり冷静さを取り戻したようだった。
ニィは唾を飲むと口を開いた。
「じいちゃんが、倒れた。母さんが、真が帰って来たら、すぐ病院に来るようにって・・・。でも、どこ運ばれっかわかんないから、とりあえず家で待ってって真に言いなさいって・・・。」
この時私はどんな顔をしていたのだろうか。
とにかくニィの発した言葉の意味がわからなかった。
いや、わかりたくなかった。
予感の正体を見るのが怖かった。本当に怖くて仕方がなかった。
喉の方から頭のテッペンに向かってツーンとする何かが走り抜けた。
頭の中は正常でいようとしているのに、身体が言うことを聞かない。
一時間ぐらい経った頃、電話が入った。私はずっと玄関口に座ったまま。
ニィが電話に出る。母親からだ。ニィが病院の場所を聞くと、間髪入れずにタクシーの手配をした。
病院へ着くとロビーのイスに弟が座ってるのが見えた。私はニィに手を引かれて弟の方へ向かった。足に力が入らない。それでもまだ私はいつも通りの日常を装うとしている。
「希、じいちゃんは?お母さんはどこ?」
「おじいちゃんのとこいる。」
「どこの部屋かわかるか?」
二人の会話が歪んで聞こえていた。
フワフワ雲の上を歩いているような、風邪を引いて熱が出た時と同じような感覚だった。真っ白な空間を泳いでいる。周りの人たちや景色がグニャグニャ歪んでいる。何が何だか解らない。気を失いそうだった。
どうやっておじいちゃんの前に来たのか覚えていない。
目の前でおじいちゃんが眠っている。私はただおじいちゃんを見つめていた。
まるで映画を観ているように現実味を欠いた世界。
おじいちゃんにそっと触れてみると、少し温かった。
その手を握ると、また握り返してくれそうな気がした。
程なくしてお父さんが病室に入って来た。仕事を途中で切り上げて駆けつけたのだろう。彼はおじいちゃんの顔を見ると深い溜息を吐いた。
「詳しい原因は調べてみないとわかりませんが、恐らく脳出血でしょう。こちらに搬送された時にはもう息を引き取られていまして・・・・。残念です。」
「・・・・でも何故、親父、身体は健康そのものでしたよ。毎年の健診でも脳に異常なかったですし、三年ぐらい前から酒もタバコもきっぱり止めてましたし・・・」
「お父様が倒れられていた時、運動をなさっていたようで、竹刀で素振りですか?それをされていたようです。過度の運動をされると血圧が上昇して血管が破れてしまうことがあります。今回それが原因でしょう。」
先生とそんな会話をしていた。
「・・・親父、痛くなかったか?辛かったよなあ。」
しばらく沈黙したあと、そう言いながら彼はおじいちゃんの頭を撫でた。
霊安室前のソファに何時間座っていたんだろう。
誰とも何も話していない。親戚や従兄弟たちが出たり入ったりしている。
私はまた迷子になる。またあの光景がチラついた。
人の孤独を嘲笑っているのだろうか。
それとも・・・・・。
「マコト!」
その声の方に目を向ける。サクラがいる。
私は立ち上がる。サクラの顔を見ると急に感情が戻った気がした。
心から温かいものが溢れてくるのを感じた。
近づいてくるサクラに飛びつくように、私は彼女に抱きついた。
彼女の胸の中で嗚咽が止まらなかった。
彼女は私を強く抱きしめる。
「わ、私、おじいちゃんに・・・なんで、なんで!私・・・大バカだ!」
「今は何も言わなくていいよ・・・」
彼女も泣いているのがわかった。彼女が着ていたブラウスの胸の部分は、私が流した涙で濡れていた。
おじいちゃんが亡くなった日がおばあちゃんの命日だったということに後になって気づいた。仏壇の上にはおじいちゃんとおばあちゃんの遺影が仲良く並んでいる。
おじいちゃんと幼馴染だった理髪店のマスターはその遺影を見て「きっと昌子さんは伸太郎を一人にしておけなかったんだよ。何だか最近覇気が無かったからなあ。なんか生きる目的が無くなったような、会うと何か寂しそうにしてたんだよな。ヤツがそんなんだったから、昌子さん自分の命日にひょっこり帰って来て伸太郎を連れて行っちまったんじゃねえのか。」なんて事を口にしていた。
私が二人の約束を叶えていたら、おばあちゃんもおじいちゃんを連れて行かなかったのかも知れない。
そう思うと狂いそうだった。それは次第に罪悪感へと変わって行った。
心にポッカリ穴が空く。よく言われる言葉だ。
これがどう言う感覚なのかまるで解らなかったけど、おじいちゃんが亡くなって初めて理解出来た。
パズルのピースを一つ無くしたような感覚。どうにも出来ない悔しさ。
そんな私に気づいていたようで、サクラは今まで以上に私の側にいてくれた。
彼女がいれば少しだけ心が満たされた。普通でいられた。
サクラがいないとおかしくなりそうだった。私は彼女に依存していた。
もし、あの時サクラがいなかったらどうなっていただろうか。
今考えると、おじいちゃんの夢を叶えるために、また剣道を始めていたかも知れない。
今とは違った人生を送っていたのかも知れない。
でも私はサクラの胸の匂いを知ってしまった。もう離れることは出来ない。
とにかくサクラを独り占めにしたくって堪らなかった。
晴れの日の瘡蓋【第五話】


