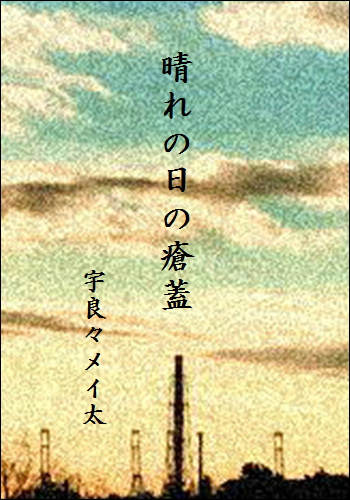
晴れの日の瘡蓋【第四話】
四、友達
1
笹之辺家の庭に咲く牡丹の蕾が膨らみだしていた。
マコトのおばあちゃんが丹精込めて育てていた牡丹は、今年もちゃんと咲こうとしている。私はこの景色に心底安心していた。
花壇いっぱいの牡丹の前で、新しい制服に身を包んだマコトはお父さんに写真を撮って貰っていた。私も促されてマコトの隣で何枚か撮って貰った。
マコトと出会った頃は、彼女の方が私を見降ろしていたけど、その頃になると、私が彼女を見降ろすようになっていた。彼女の身体はまだ小学生のままなのに、制服に包まれている姿が何だかチグハグで笑いを堪えるのが必死だった。マコト自身そのことを気にしていたみたいで、終始ご機嫌ナナメだったのが何とも可愛らしかった。
私の人生の中で一番輝いていた日々。
私は笹之辺家に自分の居場所を感じていた。ここへ来ると自然に振る舞える。誰かの顔色を窺いながら、ビクビクしなくてもいい。私にとってはもう一つの家族だった。
本当の家族なんてとてもじゃないけど見せられるものじゃない。マコトにだってずっと隠してきた。私が二度と帰りたくない場所、戻りたくない日々。
マコトは私の家族について知りたがった。特にお母さんのこと。お父さんは私が笹之辺家に遊びに行くと必ず迎えに来て挨拶をしていたので、みんなお父さんのことはよく知っていた。でも私は意図的にお母さんの話は一切しなかった。笹之辺家のような幸せな家庭に持ち込むべきじゃないと強く感じていた。
私が小学校五年生、マコトが小学校四年生のときに、あまりにもしつこく私のうちに行きたいと彼女がせがむので、私もいつも彼女のお家にお世話になりっぱなしで申し訳ないという気持ちもあり、最後は根負けしてマコトをうちへ招き入れた。
両親ともに仕事で遅くなる日を見計らって、彼女を自宅マンションに入れた。
彼女はうちにあるものを珍しがった。中国の人形やフランス製の置物、私の部屋にあったドイツ製のおままごとセット、パズル、ピアノやヴァイオリン、お父さんが趣味でやっていたフォークギターやエレキギターに目を輝かせていた。中でも私が持っている画材セットに興味があったようで、まだ使ったことがなかった数十色の水彩ケーキに見惚れていた。
それから私たちは時間も忘れて絵を描いた。
お母さんは私の描く絵を知らない。今まで一度だって見てくれたことがなかった。マコトのお母さんだったら、きっと褒めてくれるだろう。いつもそんなことばかり考えていた。
(私はあなたとは違う)
私たちが絵を描くことに夢中になっていると、「咲良!ちょっと!」という怒鳴り声がお風呂場の方から聞こえた。なぜお母さん帰ってきてるの?私は焦った。
マコトがびっくりして私の顔を見ていた。私は「いいの。気にしないで。」と言い、お母さんのところへ走った。
「あんた、お風呂掃除忘れたでしょう。今日、朝言ったよね!」
そこから延々お説教が続いた。この日は特に機嫌が悪くて、話は徐々にエスカレートしていった。「あんたは本当に能無し」だの、「あんたなんかいなくなっちゃえばいいのに」だの、とにかく友達が来ているということを言う暇もないくらい延々怒鳴り続けられた。私は恥ずかしさでいっぱいになりながらお母さんに謝り続けた。私はとりあえず笑顔で恥ずかしさを紛らわした。その顔が気に入らなかったようで、お母さんは「人が怒ってるのに、あんたなんでヘラヘラしてんの?」と私の頭を叩く。ひとしきり怒鳴ると怒鳴り疲れたようで、「もういい。」と一言吐き捨てて自分の部屋に入って行った。
私は笑顔を作り何事もなかったように振る舞った。部屋に戻るとマコトは驚きのあまり茫然としていた。
「何かあったの?」
マコトは心配そうに言った。
「ううん、大丈夫。何もない。」
私は作り笑顔でそう答えた。
「お母さん?」
「うん、そう。」
「なんで怒ってるの?何か悪いことしたの?」
「うん、いいの。大丈夫。・・・ごめん、今日はもう遊べない。帰ってもらってもいいかな。」
「でも・・・。」
「だから、ごめん、また今度。」
そう言うと、マコトは何かを感じ取ったようで「わかった。」とひとこと言ってうちを出た。
それからというもの、私とマコトの間に見えない壁のようなものが出来た。彼女はあの日のことを何も言わない。それが逆に私たちの距離を広げていた。
私は距離を縮めようと、彼女の顔色を窺っていた。そんな風にしている私にマコトは勘付いた様子で顔を歪めた。
「怒ってるの?」
「別に。」
「怒ってるの?」
「怒ってないよ。」
「恐い顔してる。」
「フツーだよ。」
「フツーじゃないよ。」
「こういう顔なの!」
そう言って膨れっ面になる。私はマコトのそんな顔になぜか安らぎを感じて、思わず笑みをこぼす。
私が笑うとマコトの顔が和らいだ。
「フツーがいいんだよ。」
「フツー?」
「そう、ふつう。今の感じで。」
「今がふつう?」
「うん、サクラはふつうの子だよ。私と同じだ。」
「マコトと同じ?」
「うん、おんなじ。私もサクラもふつうの女の子。それでいいんだよ。」
私はマコトのこの言葉に救われた気がした。
〝ふつうでいいんだよ〟
マコトは正直な人だと思う。自分が嫌だと思うものには、彼女の表情がそれを教えてくれる。
私は彼女のそういうところに憧れている。私は自分の心を悟られないように、いつも人の顔色を窺いながら生きてきた。この世界のすべてのものに怯えていたんだと思う。生きるということに極端なまでに怯えていたんだろう。
マコトは私とは違う。とても心の強い人間だと思う。彼女といれば私も強い人間になれる気がした。
何をするにもマコトは私の手を引っ張って先を行く。いつも私の手の先にはマコトがいた。マコトの後ろ姿を見ていた。その身体がどんどん小さくなって行く。私は彼女の向かう先に僅かな希望を抱きながら進んでいく。
中学生になると私はマコトを心の拠り所とするようになった。今思えばそれはほとんど依存状態だったのかも知れない。心が痒くなる。私自身のコントロールを失う。今までの私じゃない私が自分を支配して飲み込もうとしている。初めての感覚だった。心と身体、頭と精神が分裂して行くようだった。それを唯一繋ぎ止めて、私たらしめてくれていたのがマコトだった。
その頃になると私は家には帰らず、マコトの家で寝泊まりするようになった。家に帰っても誰もいない。何もない。両親とも仕事に追われて家を空けることが多くなっていた。それを笹之辺家の人たちは不憫に思ってくれて、私が半ば居候状態になっていても暖かく迎え入れてくれた。
私たち、まるで本当の姉妹のようだったと思う。二人で遊びに出かけたり、マコトに勉強を教えてあげたり、また、くだらない話で夜通し盛り上がったり、朝起きたときも、眠るときもマコトがいた。
私が迷っている時にはマコトがそれにいち早く気づいて答えをくれた。私は彼女に共感する。私には自分というものがなかった。そんな私に彼女も気づいていたのだろう。だから後になって、私が彼女に対して思っていることを口にするだけで、急に顔色を変えてそっぽを向くようになった。
一緒にいると彼女の弱い部分も見えてしまう。私だけが知っている彼女。彼女もまた何かに依存している。
抱きしめた彼女は何よりも小さく感じた。いつも虚勢を張って生きてきたんだろう。みんなそうだ。心は常にか弱くて、それを悟られないために自分を大きく見せてる。弱いのは私だけじゃない。私もあなたも同じ。それが〝ふつう〟ってものなんだろう。
2
その日珍しくお母さんから連絡を受けた。
〝本当の家〟へ帰る。リビングに行くとお母さんはソファに座って黙りこんでいた。何も言わずに突っ立っていたら、お母さんは振り向かずに「こっちに来なさいよ。」と静かな口調で言った。
私は数秒躊躇ったあと、お母さんの座っているソファの前に座った。
お母さんは何も言わずに目を閉じている。
「あの・・・」
私はこの奇妙な沈黙に耐えられず言葉を発した。お母さんは目をつぶったままで何も言わない。沈黙は続く。
私は立ち上がりその場から逃げようとした。
「あんた、どうしたい?」
お母さんは一言そう言った。
「え?」
「お父さんと一緒いるのと、私と新しい生活を始めるのとどっちがいいの?」
私はこの言葉の意味を咄嗟に理解した。でも私は理解していないかのように振る舞った。
「何が?」
「解ってるでしょう?私はね、あんたが察しがいいのをわかってるから。」
そう、私は家族が今どうなろうとしているのか理解していた。でも何も言わなかった。
「あの人と違って、あんたは私に似てる。だから、これからどうなるのか、自分がどうしたらいいのか解ってるでしょう?」
お母さんの言う通り。私には解っている。
「あの人は、あんたの父親は結局何も解ってなかった。さっきね、話し合ったの。最後の話し合い。お互い価値観が違い過ぎた。窮地の時こそ理解してくれるのが夫婦だと思ってたのにね。今、私には理解してくれる人がいるの。でも、あの人を、あの人への愛情が完全に冷めたわけじゃない。だから、もう一度だけチャンスをあげたのに、結局私を信用していなかった。夫婦って信頼関係から成り立つものでしょう?あの人、私の前でハッキリと信用してないって。」
お母さんは一人で話していた。
「咲良、お母さんの会社無くなっちゃうの。誰にも頼らずに一人で頑張って来たのにね。最初はあの人にも色々助けて貰ったのは確かだけど、私が寝る間も惜しんで働いて、人脈を築いて今日までやって来られた。小さな会社だったけど、私にとっては子供同然なの。命をかけても守りたいものなの。あの人は私にアレコレ指図するだけ。最初だけ口を出して後はほったらかし。それで潰れそうになると自分の指図した事を棚に上げて、お前のやり方じゃ、いつかこうなると思ってた、もう潮時だ。諦めろ。だって。でもね、会社を助けてあげるって言ってくれる人もいるのよ。それを話したらあの人何て言ったと思う?そんな話はまやかしだ、君は経営者向きじゃない。そんなメリットのない話を持ちかける人間は君に特別な感情を抱いているか只の馬鹿だ、だって。これでハッキリしたわ。あの人、はじめから私のことを馬鹿にしてたのよ。私の人生を否定したのよ!」
お母さんは少しヒステリックに言った。
「ここでもう一度だけ私を信用してくれたら、こうはならなかった。全部あんたの父親のせいよ!ねえ、咲良、あんたどうする?あの人について行っても幸せにはなれない。家族に理解のない人だから。実はね、さっき言った会社を助けてくれる人が生活の面倒も見てくれるのよ。彼も会社経営者で、広告代理店の社長さん。凄く仕事も出来てお金も持ってる。その上、何よりも優しい人よ。前の奥さんとの間に息子が一人いて、年も咲良と同じ。それで私の仕事がまた軌道に乗れば、その人と一緒になる事も考えてる。」
お母さんは気持ち悪いくらい優しく言った。同情を得たかったのだろうか、または私を利用する気だったのだろうか。更に戯言は続いた。
「私は、あの人たち(多分自分の両親のこと)とは違う。あんたを置き去りにはしない。私が今日まで頑張って来たのも咲良のためでもあるんだよ。わかるよね?寂しい思いだけはさせたくない。私はこれまでもあんたの事で悩んできた。思って来たのは本当だよ。」
「お父さんはどうなるの?」
私は言った。
「どうなるって、後は自分で何とかするしかないんじゃないの。」
「お母さん、ちょっと聞いてもいい?」
「何?」
「お母さん、私がいつもどこで何をしてるか知ってる?」
「何?そんなの今どうでもいいでしょう?」
「どうでもよくない。私がどこにいて何をしてるか、一度でも気にしたことある?」
「私は、あんたを信用してる。あんたは悪い事は出来ない。私の子だもん。」
この一言が異常に気持ち悪かった。
「そうじゃなくって、私がいつどこでどんな思いをしているとか心配になったこととかないの?お父さんは私がどこにいて、どんな人と一緒にいるか知ってるよ。ちょっと前までちゃんと夜遅くなると必ず迎えに来てくれてたもん。それに時間が取れれば必ずどこかへ連れて行ってくれた。お母さん、私の誕生日会を毎年開いてたの知ってる?」
「そうなの?でもプレゼントあげてるじゃない。」
「お母さんがくれたのって、小学校二年の時だよね。スケッチブックと色鉛筆。あれ以来一度もくれたとことない。」
「ウソよ!ちゃんとお父さんにお金渡してプレゼント一緒に買っておいてって。」
「お父さん、お母さんからなんて一言も言わなかった。」
「そんなのお父さんのせいじゃないの!私だって仕事がなければあんたの誕生日を祝っていやりたかったけど、仕方ないじゃない。私には責任があるの。あんたも大人になって、責任ある立場になれば私の苦労がわかるよ。何もわかってないくせに、自分のことばかり言うんじゃないの!」
私は自分に抑えて抑えてと言い聞かせた。湧き上がる感情。今にも爆発しそうだった。
「誕生日を祝って欲しいんだったら、これからそうしてあげられる。私は今まで苦労して来たんだから、もっとそう言う自由な時間を・・」
「私私って、お母さんいつも自分のことばっか!」
ついに抑えることが出来なくなった。
「自分のことばかりなのはお母さんでしょう!お母さんが家にいない時、お父さんも私もどんな思いでいたか考えたことあるの?もう沢山!新しい彼氏と一緒になりたいんなら勝手に一人で行けばいい!私はお父さんといる。もう私たちに関わらないで!」
「あんたは!」
そう言うとお母さんは立ち上がり私の頬を引っ叩いた。気がつけば私の頬を涙が伝っていた。
私は走って自分の部屋に行き、クローゼットの中に隠しておいたあのスケッチブックを引っ張り出すと、またお母さんの前に戻ってスケッチブックを彼女の前に叩きつけた。涙が止まらなかった。息が荒くなっている。こんな感情は初めてだった。身体中痺れている。
私はそのまま振り返らず家を飛び出した。なぜか胸の中はスッとしていた。
晴れの日の瘡蓋【第四話】


