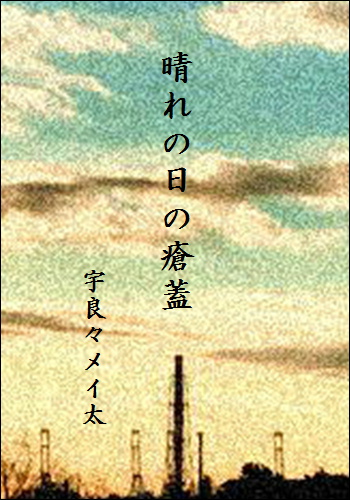
晴れの日の瘡蓋【第三話】
三、右手
1
小学校時代のとある日、いつものようにおじいちゃんの部屋で天井を見上げていた。
少し開けられた窓から風に乗って金木犀の香りが運ばれ、その心地よさについウトウトと眠りに落ちそうになる。
ちょっと前までどうも消化不良気味で気分が優れなかった。とにかく弟の面倒を見させられるのがめんどくさかったので、竹刀を持って逃げるように河川敷に行ったまでは良かったものの、そこで素振りをしていたら、酔っ払ったホームレスのオッチャンにイチャモンつけられて、怖くなって早々うちへ戻るハメになってしまった。
秋の風は心を浄化してくれるようだった。おじいちゃんはどこかに出かけていた。定年後も色々と忙しそうにしていた。
土曜日はサクラがうちへ遊びに来る。私は学校が休みだったけど、ニィとサクラは私立なので土曜日も関係なく学校があった。毎週土曜日はニィがサクラを連れて来る日だった。
その頃の土曜日のパターンは決まっていて、朝ニィが学校へ行った後に起きて、そこから日曜日の剣道の稽古に向けて自主練習。昼におじいちゃんの家で一緒にテレビを観ながら、おばあちゃんの作ったご飯を食べて、その後少し昼寝をする。目が覚めるとおじいちゃんは出かけていない。渋々うちへ帰って、弟と遊んでやる。ほぼこれの繰り返しだった。
大体午後三時になると、ニイはサクラを連れて帰宅した。私は弟とテレビを観ている。ニイと二階へ上がる前に、毎回彼女がこちらの様子を窺っていたのは知っていたけど、私はまるで意識していないようなフリをした。何故だかわからないけど、この頃の私は必要以上に弟にちょっかいを出すようになっていた。テレビのチャンネルをワザと変えてみたり、彼の分のおやつを取ってみたりして弟が泣き出しそうなことばかりしていた。案の定、母親に怒られて逃げるように家を出た。
そのうち私があまりにもしつこく嫌がらせをするものだから、彼も私と遊ぶのが面倒になったのだろう。私が居間に入ると弟はそそくさと外へ出て行くようになった。弟が勝手に外へ出ると、なぜか私が母親に怒られた。私は外で一人で遊ぶ弟を家の中に入れて、とりあえず納戸の中に閉じ込めて、(弟はバカだからお菓子があるとか、珍しい昆虫がいるとか言うと素直に従った)その隙に家から逃げた。
金木犀の香りの中、夢うつつになっているとこに、ニィがノックもせずいきなり部屋のドアを開けた。その後ろにはサクラがいた。
「サクラちゃんがマコトと話たいんだって。」
サクラは黙ったまま私の前に正坐した。ニイが一階にいたおばあちゃんに呼ばれて部屋を出た。彼女は沈黙したままだった。
「なに?」
私はサクラの顔を見ないまま言った。妙にドキドキしていた。
彼女は少し間をあけて口を開いた。
「これ」
私は彼女の手元に目をやった。彼女は紙袋を差し出していた。
「あげる」
そう言うと彼女は紙袋を置いてうつむいた。私は彼女と同じように正座して、差し出された紙袋を取った。中には絵本のような作りのスケッチブックと、木のケースに入れられた五十色入りの色鉛筆が入っていた。多分外国のものなんだろう。一目見て高価なものだということは判った。
「この前ありがとう。」
サクラは言った。私は贈り物とありがとうの意味が解らなかった。
「なにが?」
「イチゴ大福。」
「イチゴダイフク?」
「この前イチゴ大福くれてありがとう。」
ただ私はおばあちゃんに教えられた通り、まずは仏様、そして次にお客様がいたら自分が戴くより先にお出しするという事をしただけだ。そんな当たり前のことでお礼されるなんて思っても見なかったので、逆に申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
「・・・いいの?」
サクラは頷いた。私はスケッチブックの一ページ目を開き、机の上にあったおじいちゃんの万年筆を取ってヘタクソなサクラの似顔絵を描いた。それを自分の顔の前持って行き「ありがとう。」と彼女の声色のように言うと、サクラは今までに見たことのない弾けるような笑顔を見せた。
小学校に上がると同時に、私は剣道を習い始めた。これはおじいちゃんの勧めだった。警察官だったおじいちゃんは、定年後、町の剣道場で後進の指導に当たった。初めはニイと一緒に通っていたけど、彼は一ヶ月で脱落。結局私一人続けることとなった。
おじいちゃんは私に素質があると誉めてくれた。私はそれが嬉しくて毎回必ず稽古に出かけ、また毎日欠かさず自主練習に励んだ。その甲斐があってか、三年生の時に区の大会で優勝、さらに次の年に一つ上の学年の部で優勝し、都大会に出場して三位入賞を果たした。勝てば勝つほどおじいちゃんは喜んでくれた。おじいちゃんは町内の知り合いという知り合いに自慢して廻った。私は町でちょっとした有名人になった。
有名になることは照れくさかったけど、おじいちゃんが喜んでくれてる事だけが何よりも嬉しかった。私は剣道を一生続けて行こうと思っていた。おじいちゃんの道着姿を見て私もおじいちゃんのようになろうと決意していた。
おじいちゃんは温厚で誰に対しても笑顔を絶やさなかった。
その見た目は、温厚な性格とは違って、筋骨隆々な体つき、眼光は鋭く、あの眼で睨まれたら誰もがオシッコちびっちゃうんじゃないかってくらい眼力が半端なかった。
一見怖そうな風貌だけど、みんな怖がるどころか、常におじいちゃんを慕っていた。
よくみんなが言うのは、とにかく昔から正義感のカタマリみたいな人だったらしい。イザコザが起こると必ずおじいちゃんが駆り出され間に入った。
おじいちゃんの言葉には説得力がある。
納得させるだけの何かがあった。
まるで魔法のようだった。
昔、私がニィとワケもなくケンカになって彼のお腹に蹴りを入れた挙句、腕に噛み付いて泣かせてしまった時、おじいちゃんからお説教された事があった。おじいちゃんから受けた最初で最後のお説教だった。
「こりゃあ、真、完全にお前の負けだな。」
おじいちゃんは笑いながらこう言った。でもその眼はしっかり私を捕らえて放そうとしなかった。
「お兄ちゃんもつい捲し立てるように言ってしまったんだろうよ。これは戴けねえな。でも、お兄ちゃんが何を言ったか知らないが、先に暴力に訴えたのは真だろ?今回は喧嘩両成敗じゃない。完全に先に暴力を振るった真が悪い。そうじゃないか?」
ニィは弁が立つ。いつも私を言い負かそうとする。私はそれが嫌だった。私がニィに口喧嘩で勝てる訳がない。それを必死に訴えると、おじいちゃんは先ほどの笑顔とは打って変わって今度は尋問するような口調で言った。
「じゃあ今どんな気分か言ってみろ。」
「・・・・・・・・・・・・・・・・」
私はおじいちゃんから視線をそらした。
「俺の目が見れないって事は、自分が悪いって認めてるのと一緒なんじゃねえのかい?」
これを言われるとますますおじいちゃんの方を見れなくなった。
「お兄ちゃんは何かお前を傷つけるような事言ったか?」
多分言ってない。覚えてないけど。ニィがヒドい事を言うワケがない。これだけは絶対だ。私が勝手にヒステリックになってただけだ。いつものように。
私は馬鹿なんだ。言葉を知らない。でも腕力ではニィより自分が勝っているという自負だけはあった。今思えば、何があっても彼は手を出す事はなかった。私はその事をわかった上で、暴力を振るった。何て卑怯なんだろう。
「真な、お兄ちゃんは痛かったと思うぞ。殴られたり噛み付かれたからじゃなくてよ、そんなん何てことなくてな、兄貴だから、男だから、妹に手を挙げられない自分の優しさって言うか、やり返したくてもそれを絶対に許さない自分の心がな、グッと堪えた時の痛みって相当辛いもんなんだ。お兄ちゃんは優し過ぎるんだよ。お兄ちゃんが泣いたのは、お兄ちゃんの本心を真にわかってもらえなかったからじゃないか。自分が正しいなら言い返せばいい。でもお前は言い返せず暴力で捩じ伏せた。お兄ちゃんにしちゃあこれは悔しい事だと思うぞ。」
さすがにこの時は自分の行いを反省せざるを得なかった。
これ以来、私は自分から暴力を振るう事を禁じた。
まあ、やられた時はしっかりやり返してやるんだけど。
私は兄弟の中で一番おじいちゃんに可愛がられてきた。
真という名前もおじいちゃんが付けてくれた。
ニィの名前の「静」と、弟の名前の「希」は父親によって付けられていて、これは笹之辺家の男子は父親が名付けるという我が家の伝統に則ったもので、男子の名付けだけは、例え親であろうが一切口出しする事は許されなかった。
おじいちゃん自身、他の家族の前では決して言わなかったけど、「静」「希」という女の子っぽい名前をどうも気に入っていなかったようだ。
女の子の私はおじいちゃんに託されて、「真っ直ぐな人間であれ」という願いが込められ「真」になった。
私の名前はおじいちゃんから貰った一生の宝物だ。
私自身、私という人間を客観的に見てみると真っ直ぐな人間だとは到底思えない。
私が生きてきた二十年間は常に他人の期待を裏切るものだった。
そのことをずっと悔やんできた。
その反面、自分は常に正しいんだという自負だけはあった。いや、そうやっていつも自分を守っていただけなんだろう。
おじいちゃんという人間は常に正しかった。それを私は子供の頃からずっと見て来た。物事を正しいと思わせるだけの根拠があった。
弱さは決して見せず常にピンと背筋を伸ばして生きていた。
2
冬になると右手が痺れる。まるで血が通っていないかのように冷たくなっていた。そんな時、よくサクラは私の右手を握ってくれた。彼女も冷たい手をしていた。だけど不思議と彼女の手から温かいものが流れてくるのを感じていた。彼女が手を握ると痺れが治った。
私の右手は使いもにならない。それは小学校六年の時に負ってしまった怪我のせいだった。小学校六年生になったとある日、私は台所に立っていた。これは言わばオンナの嫉妬心ってヤツだった。くだらない感情だ。
その時はもうサクラは家族同然となって、いることが当たり前になっていた。いつからだったか、ごく自然に炊事を手伝うようになった。うちの母親の隣で料理や洗い物をしながら談笑する姿は、本当の親娘のようだった。そんな二人の楽しげな様子を見ていると、何とも言えないグツグツした感情が湧き上がった。
その時私は一週間後に剣道の予選大会を控えていて、おじいちゃんは私以上に私の体調を気遣っていた。とにかく怪我病気には気をつけろ、体を傷める真似はするなと、ハサミを使おうとするだけで「手を切らないようにしろ」と、少しうるさいくらい気遣っていた。あんなにナーバスになっているおじいちゃんを見るのは初めてだった。確かにおじいちゃんは以前とは違い、弱さがチラホラ見え隠れするようになっていた。
その年の秋、おばあちゃんが亡くなった。一年前に膵臓に癌が見つかって、おじいちゃんや家族の看病も虚しく最期はホスピスで息をひきとった。ふくよかだったおばあちゃんの身体は抗癌剤の副作用ですっかりと痩せてしまい、髪の毛も全部抜けてしまっていて、かつての面影はなくなっていた。吐き気と倦怠感で凄く苦しいハズなのに、会いに行くといつも楽しそうにしていた。おじいちゃんは毎日おばあちゃんの病室へ出向き色々な話をしてあげていた。後で知った話なんだけど、話の殆んどが私のことだったらしい。おばあちゃんが苦しんでいる時は夜通し側にいてやり献身的な看病をしていた。おじいちゃんは私の試合のことばかり話ていたようで、元気になったら真の試合を見に行く、それが二人の約束だった。
その日のおばあちゃんはいつになく元気だった。食事もちゃんと取って自分の足でトイレに行き、看護師さんとも笑顔で会話していた。おじいちゃんはそんなおばあちゃんを見て安心していた。
「ちょっと風呂入りに帰るが、何かいるもんあるか?」
「・・・いいえ、お気遣いなく。」
「じゃあ、ちょっと行ってくる。」
「・・・お父さん。」
「ん?何だ?」
「・・・行ってらっしゃい。」
「ああ、行ってくる。」
これが二人が交わした最期の言葉だった。夜九時を回った頃、おばあちゃんの容態が急変した。昏睡状態に落ちてそのまま眠るように息をひきとった。
おじいちゃんはおばあちゃんの最期を看取ることが出来なかった。ホスピスから連絡を受けたおじいちゃんは、取り乱すことなく私達の家にやってきて「ダメだったよ。」と一言おばあちゃんが亡くなったことを家族に伝えた。
父親の運転する車の中でみんな茫然としていた。私たち子供は何が起きたのか理解出来ずにいた。けど、ニィだけは祖母の死を理解したようで、目に涙を浮かべていた。おじいちゃんはずっと窓の外を眺めていた。その姿はいつも通りのおじいちゃんだった。
おばあちゃんのお葬式が終わってからも、おじいちゃんはいつも通りを装っていた。でもそれが〝装い〟だったことは私が一番よくわかっていた。おじいちゃんはおばあちゃんとの約束をずっと心の中に潜めていた。おじいちゃんには私の試合におばあちゃんを連れて行くことしか頭になかったのだろう。それが私に対しての過度な気遣いになっていった。
3
その日、私は初めて自ら台所に立った。母親は「試合が近いんだから止めておきなさい。」と何度も忠告していたけど、それが逆に私の燻っていた嫉妬心に燃料を投下する結果となった。サクラにはやらせて私にはやらせてくれない。お母さんは私よりもサクラの方が大事なんだ!もうどうにも止められなかった。嫉妬心は大炎上していた。
夕食はカレー。母親は渋々玉ねぎを炒める仕事を私に与えた。私は納得行かなかった。以前、サクラに皮剥きの指南を手取り足取りしてあげてるのを、こっちは見ているのだ。それがいい。それを教えて欲しい。サクラの時と同じように手取り足取りに。私は炒め役を拒否し、ジャガイモの皮剥きを教えて欲しいと頼んだ。母親は何度も「止めておきなさい。」と忠告するも虚しく、最後は半ば強引にジャガイモとナイフを取って、その歪なジャガイモの体に刃を入れた。結果は母親の予想通りだった。
林檎の皮剥きの要領でナイフを入れていく。このイメージだけは明確だった。ジャガイモの表面にナイフを滑らせて皮と肉を削いでいく。ジャガイモを回転しながら切っていき、それがキレイな螺旋を描くのだ。ナイフの刃を親指で支えながら切る。それも知っている。おばあちゃんがやっているのを何度も見てきた。簡単なことだ。さあ!とナイフを皮に滑らせた瞬間、ナイフを支えていた親指が濡れたジャガイモの上で滑り、親指の方がナイフよりも先にゴール地点へと到達、その後を追いかけるようにしてナイフの刃が指の腹へ食い込み、気が付けばジャガイモから血が滴り落ちていた。
最初は何が起きたのかよくわからなかった。母親が悲鳴のような声でそれを指摘しているのを聞いて、ようやく親指を切ってしまったことに気付いた。痛みはじわじわとやってきた。大粒の涙が頬を伝った。母親がすぐさま救急車を呼び、救急隊員から応急処置の方法を聞くと、引き出しから大量のタオルを取り出しすぐに止血処置が施された。救急車に乗ったのは人生で二度目だった。
一度目は全く記憶に無いんだけど、三歳の時に玄関口の段差で躓き額を切って運ばれたらしい。約七年ぶり二度目の失態だった。事態は予想以上に深刻で、傷は右手親指第一関節上の皮膚を破り、肉が裂かれ、骨付近まで達していた。診断結果は長母指屈筋腱損傷。簡単に言えば神経が切れてしまっていた。 これを聞いた時、それがどんな状態のものか、全く理解出来なかったけど、何か大変な事をやらかしてしっまたことだけはとてもよく理解できた。病院でのやり取りはよく覚えていないけど、母親曰わく、なぜか私は何も言わずに担当医を睨みつけていたらしい。先生は褒めてくれていたのか、はたまた呆れていたのか、よくわからないけど「君は強い子だね」と言ったのを今でも鮮明に覚えている。
治療を終えてロビーで母親と会計を待っている時に、おじいちゃんが血相を変えてやって来た。母親が電話したのだ。私はおじいちゃんに会わせる顔がなかった。絶対悲しませてしまう。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだった。
おじいちゃんは私を見るなり「お前、大丈夫か!手は!」少し取り乱しているようだった。こんなおじいちゃんを見たのは初めてだったから、私はとても動揺していた。
「なぜ包丁を持たせたんだ!」
おじいちゃんは間髪入れずに母親を怒鳴りつけた。周りの人たちが驚いているのが見えた。それでもおじいちゃんは母親に怒鳴り続けていた。母親は泣き出していた。おじいちゃんがこんなに怒るのも、母親が子供のように泣いているのも、初めて見る光景ばかりだった。看護士さんが驚いた顔をしてこちらに近づいて来る。病院内がざわめく。
お母さんは悪くない。これは私のワガママが招いたこと。これ以上お母さんに恥をかかさないで。私は立ち上がりおじいちゃんに言った。おじいちゃんの怒鳴り声に負けないよう大きな声で。
「お母さんは悪くないよ!おじいちゃん何にもわかってないのに、勝手に怒らないでよ!」
病院内が静まり返る。私は耐えきれず泣いた。おじいちゃんは今どんな顔をしているのだろう。怖くて顔が見られなかった。
おじいちゃんに怒鳴ってしまった。凄く悪いことをしてしまった。おじいちゃんに合わせる顔がない。それから私はおじいちゃんを避けるようになった。
予選会はもちろん不参戦。右手は死んだのだ。ペンを持つことも出来ない。
実のところ私はもともと左利きで、小学校に上がってから矯正したということもあり、右手が使えなくても左手で何とか字を書くこととも、お箸を使うこともかろうじて出来た。努力次第では、また剣道だって出来る。頑張って行けば試合に出て勝つことも出来たと思う。ただ、問題は心の方だった。
怪我から半年経った頃、学校から帰宅して玄関のドアを開けようとした時に、庭の牡丹の手入れをしていたおじいちゃんに呼び止められた。
「真、そろそろ稽古、どうだ?」
私は「うん」とだけ応えた。
おじいちゃんとは、もう何ヶ月も話してないような感じがした。おじいちゃんとはあれ以来あまり口を利かなくなってしまった。本当はまた昔のように仲良くなれれば、なんて思ってたけど、何を言えば、何を話したらいいのかまるでわからなかった。
この頃になると、もうすぐ中学生になる私は自分の部屋を与えられ、それもあってか、おじいちゃんの書斎で過ごすことはなくなっていた。土曜日の夕食以外でおじいちゃんに会うこともなかった。
4
私は久しぶりに稽古に出かけた。その時はただおじいちゃんに申し訳ないという気持ちだけ。一から出直そう!とか、今度は絶対に試合に出て勝ち進んで行くんだ!といった心意気は皆無だった。
しばらくぶりに身に付ける防具はズッシリと重く感じた。鈍っていた身体に半年前までの自分を思い出させるように、ひとつひとつ稽古をこなしていった。私自身はあの頃の感覚が戻ってくるのを感じていたけど、やはりおじいちゃんの目は節穴ではなかった。一通りメニューを終えると、いきなり試合稽古をやらされた。
相手は一年下の女の子で、私が一番仲の良かった子だ。彼女はいつも「マコトちゃんのように強くなりたい。」と言ってくれるとても可愛い後輩だった。何度も手合せをしたけど、正直、私の相手ではなかった。私は彼女に胸を貸す程度、ほんのお遊びぐらいにしか思っていなかった。
格下だと思っていた相手に負けることほど惨めなものはない。三本勝負、見事に三本とも取られた。悔しいを通り越して情けなさでいっぱいだった。
稽古が終わって彼女が心配そうに声をかけてきたけど、何を言っていたかまでは覚えてない。私は愛想笑いをして、その場から逃げるように立ち去った。
多分、おじいちゃんは私に発破をかけたつもりだったんだろうけど、それは見事に失敗した。これで完全に挫けてしまった。この日の稽古が私の剣道人生最後の稽古となった。
雨が小降りになったのだろう。雨樋からカンカンカンと水の滴る音だけが響く。カーテンレールにはもう何日も干しっぱなしのタオルがぶら下がっている。横たわりながら手を伸ばす。届く訳がない。そのままグー、パー、グー、パーとむすんでひらいてを繰り返す。右手は冷たいままだ。痺れで感覚も麻痺している。
何度か変な気が起きた。感覚もないクセにこの手はまだサクラの手の温かさを覚えている。イライラする。残酷な温かさだ。掌の肉にこびりついている温かさ。いっそ切り開いて全部かき出してやりたい。もう私はここには生きていない。ここにいるのはサクラの残骸。光と闇。中宮寺の菩薩の輝きのようなその眩い光に、闇は最も簡単に飲まれた。
晴れの日の瘡蓋【第三話】


