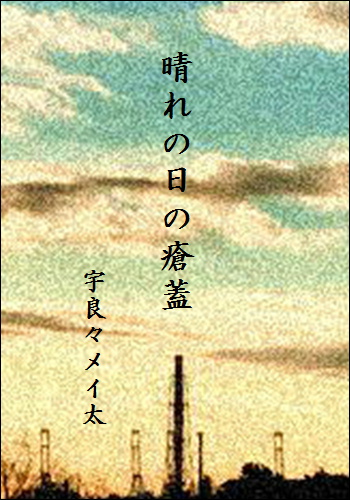
晴れの日の瘡蓋【第二話】
二、リフィル
1
あ・・・・
これ、リフィルじゃん・・・・
化粧水がボトルから手のひらに落ち、それが溢れて排水口へと吸い込まれていく。
私は慌てることもなくその様子をただ見つめ続ける。
買ったばかりの真新しい化粧水。
一度も使うこなく全部流れていった。
私の手のひらでは、すべてを受け止めることは出来なかった。
実はこんなことは初めてじゃない。
ただ黙って溢れていくのを見ている。
気がつけばボトルは空になっている。
これが私の二十一年間のすべてだった。
「怒ってるの?」
「別に怒ってないよ。」
あの子はいつもムスッとした顔で応えた。
そんな顔を見ていると私は可笑しくなってしまって顔を背けるのが毎度のことだ。
多分あの時もそう言うだろうと期待していたのだけど、あの子は何も言わず目をそらした。
器が粉々に砕かれる。
私は確かにその音を聞いた。
私は誰かに受け止めてもらわないと何も出来ない。
溢れて流れて行くばかりだ。
本当に弱虫なのだから仕方がない。
弱いからいつもこんな風だし、実はそれが嫌で仕方がなかった。
自分を嫌う。
消えてしまいたくなる。
あの子はそんなのをすぐに見透かして、不機嫌そうな表情を浮かべていた。
立ち止まる。
世界はこんなにも静かで、何にもない。
私という人間はなんて空っぽなんだろう。
自分がいなくなってしまったようにフワフワしている。
強くなれるかも。
そう思ったのはマコトがそばにいたから。
満たされる。
重さを感じられる。
はなっから私には自分を感じられるほどの重さなんてない。
いつも彼女の背中を追いかけて来た。
私は迷いを捨てて進む。
後ろを振り向かないように。
ずっと気付いていたんだと思う。
私はあの子に依存し切っていて、すっかり彼女の人生の中に収まっていた。
結局今日まで弱虫のままで来てしまった。
身体が急に重くなった。これは私の重さじゃない。
「ごめんね」
頰を抓る。めい一杯抓ってみた。何だかまだ夢の中にいるみたいだ。
お父さん、まだ怒ってるかな。
あんなに怒ったお父さんを見るのは初めてだった。せっかく始めた自分の暮らしもこれで終わりなんだろう。
一人暮らしは専門学校に入ってから始めた。でも半月も経たないうちにマコトが転がり込んできて、憧れの一人暮らしは叶わなくなった。
マコトが私の部屋にやって来たとき、正直安心していた。心底ほっとした。一人で生きていくなんて私には出来っこなかった。実際はそうじゃなかったのかもしれないけど。
雨音。
さっきから雨の匂いがすると思っていたら、やっぱり降り出してきた。時折強い風が吹いて、雨粒を部屋の窓に打ち付ける。窓の水滴が影を作って暗い部屋に斑模様を描く。机に突っ伏している私の手にも斑模様が映っている。
お父さんと暮らしたこの家の私のこの部屋は何も変わらずさっぱりとしたままだ。
ここに何回くらいマコトが来たんだろう。多分数えられるくらいしか来てない気がする。彼女と会うのはいつもあの部屋だった。
部屋を埋めるたくさんの本、時計の音、天井のシミ、線香の香り、部屋の真ん中にはマコトがいる。記憶の中の彼女は今でも日の当たるあの場所にいる。彼女の部屋で色々な事を知った。
そういえば雨の匂いもマコトが教えてくれた。それだけじゃない。笑うことや怒ること、感情のすべて。私が知らなかったものの全てをマコトは持っていた。私は本当に羨ましくて仕方がなかった。家に帰ると自分に充てがわれた現実の痛みを知る。その痛みを、この先ずっと抱きながら生きて行かなければならないと思っていた。
もしかしたら何も知らなければ幸せだったのかも知れない。最近そんな風に思うことがある。私には私の生きる場所があった。弱虫で臆病な世界。強さなんて望まない世界。無知な私の、いや私達の世界。
マコトと初めて会った日、私は自分の生きる世界とは違う、新しい世界を知った。
お父さん、お母さん、笹之辺君、希君、おじいちゃん、おばあちゃん、そしてマコト。
あんなに賑やかな晩御飯は今まで経験したことがなかったから、私は本当にどうして良いかわからなかった。マコトのお母さんが「サクラちゃんも遠慮せずどうぞ召し上がれ」と言ってくれても遠慮してしまい手が付けられないでいた。笹之辺君もそんな私に気付いていたのか私のことについて色々と話していた。私の両親が共働きで、お父さんが経営コンサルタントをしていること、お母さんが会社を経営しているということを、まるで自分の親の自慢をするように話していた。彼は多分はそれがどういった仕事なのか解っていなかったと思う。
彼はしきりに私の両親がとても偉い人なんだということを説明していた。家族のみんなも何も言わない私に気遣ってくれて、学校で何を学んでいるかとか、どんな習い事をしているかとか、色々尋ねてきたけど、それも私が黙っているものだから、すべて笹之辺君が答えていた。私はたまに笹之辺君の言うことに頷くだけ。こんなに色々聞かれたのも初めてだった。
「苺大福食べてもいい?」
マコトがおじいちゃんに甘えるように言った。
「後にしなさい」とお母さんの注意も聞かずにマコトは箱を開けて苺大福を一つ取り出し、駆け足で私の席までやって来て苺大福を私の前に置くと 「どうぞ」と一言だけ言って、また駆け足で自分の席に帰って行った。
私は咄嗟にマコトの顔を見た。彼女は少しぎこちない笑みを見せると、おじいちゃんの方へ顔を向けた。
「ありがとう。」私はつぶやいた。
「やっと笑った」と笹之辺君が少し声のトーンを上げて言った。
私はこの日のことを誰かに話したくて仕方がなかった。私が初めて見た新しい世界といものを、その時芽生えた新しい感情というものを、私一人では到底理解出来そうになかったから。とにかく他の人に聞いてもらいたい、そんな衝動に駆られていた。この時初めて自分の望むものはこれだと思った。
一番聞いて欲しかった人はお母さんだったんだと思う。私が望んでいたこと、それは全部あの日の家族団欒にあって、お母さんにもそれをあげたいと思ってしまったのだろう。
それがお母さんにとっても良いものであると信じ切っていたのだろう。
私はお母さんの帰りを待って、遅くまで起きていた。十二時を過ぎてもお母さんは帰って来なかった。私は眠りに落ちそうになるのを堪えながらソファの上で今日の家族の絵を描いていた。絵の中の家族は私達家族で、そこにはあの楽しい団欒風景を描いた。
午前一時を回った頃、玄関の扉の開く音がした。私はスケッチブックを持って駆け足で玄関に向かった。
お母さんはヒールのまま玄関の扉にもたれかかって動かない。仕事で疲れていたのか、アルコールで意識が飛んでいたのか、とにかくこの時お母さんの様子が違うことを察した。フラつきながらヒールを脱ぎ捨てヨタヨタ中へ進む。お母さんは私がそこにいる事は気付いていたみたいだったけど、目も合わせてくれない。そのまま私の前を素通りしてダイニングの方へ向かって行った。何歩かフラつきながら進んだところで立ち止まると、振り返る事なくお母さんは言った。
「・・・・・で・・・そうなの。」
私はこの時自分がこの後どうなるのか解った。
「何であんたはいつもそうなの!」
そう言うと私の所までドタドタ音を立てながら駆け寄って、私の頬を思いっきり抓った。
「何でこんな時間まで起きてるの!あんたそうやって反抗ばかりして楽しいの?ねえ!楽しいのかって聞いてんだよ!私、言ったよね?自分の事は自分で出来るようになれって!お前何を聞いてたの?私が何も言わなかったらお前はこんな時間まで起きてるのか!」
私は「ごめんなさい」を繰り返した。
「あんた何回そうやって謝った?何も変わってないじゃない!私はあんたが何でも完璧に出来るようにしてやってるのに、あんたにやる気がなかったから私が苦労した意味がないじゃない!今朝あんた私に何で怒られたか解ってる?言ってごらん!ほら言いなさい!」
喋ろうとしても泣き声が邪魔をして言葉に出来なかった。
「泣いたって許されないよ!言うまでこうしてやるから!」
お母さんはもう片方の頬も抓り始めた。酔っているせいかいつもより力が入っていて堪えられないほど痛かった。痛みで涙が止まらない。スケッチブックが床に落ちる。
「か・・・髪が・・・むす・・・ひっひ・・ひとり・・で、結べなかた・・・」
「で、結局どうなったの!」
「マ・・ママ・・に・・し・・して・・もらった・・・」
「それも何回言われてるの!一度や二度じゃないでしょ!あんたそんなんじゃ生きて行けないよ!私はあんたの年の頃には全部完璧に出来てたよ!私の母親、あんたのおばあちゃんになるはずだった人はあんたは年にはもういなかった。ひとりで何でもやらなくちゃ生きていけなかったの。私に何かしてくれる人なんて誰もいなかった。どんだけ辛かったか、あんた解る・・・?」
抓る力がスーっと弱くなった。お母さんは涙声だった。私が悪い子だから、お母さんを悲しませている。この時、罪悪感でいっぱいになった。
「お願いだから何度も言わせないで・・・。あんたを見てると私が不幸になる・・・お願いよ・・・」
「・・・ごめんなさい。」
お母さんは抓るのを止めてそのまま私の涙を拭って頬を軽くポンポンと叩くと、こちらに聞こえるような重い溜息を一つ吐いて寝室へと入って行った。
私はその場でもう少し泣いていたかったけど、これ以上お母さんを悲しませたくないと思って、スケッチブックを拾って自分の部屋に入った。
その日の朝、私は自分で結った髪のことでお母さんに怒られていた。
自分ではちゃんと結えたと思っていたけど、お母さんはそれが気に入らなかったみたい。
お母さんは乱暴に私が結ったポニーテールをほどいて近くにあったコームで髪をといた。その時、怒りに任せてがむしゃらにコームを入れてといたものだから、コームの歯先が皮膚を引っ掻き、耳の辺りから頭皮にかけて無数の傷が出来てしまった。しかもそれは叩くように何度も何度も繰り返された。
私は髪を垂らして、お母さんが付けた傷を隠した。とにかく恥ずかしい気持ちでいっぱいだったのを今でも覚えている。
2
雨は次第に強くなって行く。雨の音は大嫌い。とにかく憂鬱になる。私は顔を伏せた。少しばかり眠たくなってきた。
お父さんはおばあちゃんのところにいるらしい。多分私のことで行ってるんだろう。親になるって大変だ。大人になった娘でも親からすれば子供なんだろうな。子供はこうして身勝手に育ってしまうものなのに。
急に眠たくなって来た。もう何でも良いや。何もかも忘れてこのまま眠っちゃおう。お父さんいつ帰って来るんだろう。それもどうでも良くなって来た。
沈黙
私は、夢を見た。
あの日の夜の風景だった。一家団欒、でもそれは笹之辺家の団欒風景じゃなくて、お父さん、お母さん、私、そしてなぜかマコトがいる。私はお母さんにあの絵を見せる。その絵には描いた覚えのないマコトの姿もあった。
お母さんは嬉しそうに笑っている。お父さんはその絵を絵のレベルにそぐわない立派な額縁に入れて飾っている。マコトがそれを見て笑った。私もそれが可笑しくって思わず笑ってしまった。お父さんは苦笑いをしながら「これはうちの美術館の特別展示物だからこれぐらい立派にしておかないとダメなんだよ。」と言う。それを聞いたお母さんも思わず笑っていた。
私はお母さんに抱きついた。お母さんも私を強く抱きしめている。お父さんが写真を撮る。ふとマコトの方を見ると彼女が不機嫌そうな顔をしていた。私は彼女に尋ねる。
「怒ってるの?」
マコトは何も言わずに固まっている。
「ねえ、怒ってるの?」
私はマコトに近づいてもう一度彼女に言った。マコトは人形のように固まったままだった。眼差しは一点に向けられて、私も彼女の見ている方へ目をやった。
視線の先には額縁に入れた団欒の絵が壁に掛けられ飾られていた。でもそこに描かれていたはずのマコトの姿はなかった。私は必死に言い訳を考えていた。
すると突然「あんたなんかと出会わなければよかった」とマコトは言い放った。
私はあまりにも突然過ぎて言葉を失ってしまった。
それを見てお父さんとお母さんは笑っている。私は何か言い返さないとと思い言葉を探したけど何も出てこない。
マコトは悟った様な目、違う、突き放すような目で私を見つめている。
お父さんとお母さんの方に目を向けて助けを求めるんだけど彼らは笑うばかり。
マコトの方に振り返った瞬間、マコトは私の頬を叩いた。
私は悔しくなってマコトの頬を叩き返した。何度も。しかしマコトは石のように硬くなっていて、全く動じることがなかった。
お父さんとお母さんの姿が霞んで行く。次の瞬間、またマコトは私の頬を叩いた。
私は泣き出した。子供のように泣きじゃくる。
その隣でお母さんも泣いていた。でもその姿は私と同じ姿形をした女の子だった。泣きながら何かを言っている。女の子は急に泣き止むと私を睨みつけて言った。
「あんたなんかいなくなっちゃえばいいのに。」
胸が苦しくなった。心臓が喉の奥から口に向かって飛び出しそうだった。
胸のつかえで目が覚めた。胃がムカムカする。吐きそう。私は急ぎ足でトイレに向かった。遠くの方で雷の音が聞こえる。
全部吐く。胃の中の物と一緒に嫌な事もみんな嘔吐してやった。少しだけ気分が晴れた。
いつ頃からだろう。こんな感じの夢を見るようになったのは。その度にマコトの事を遠くに感じる。そして自分が大嫌いになる。
目の前にはマコトがいる。そう信じていたのに、いつしか私一人で歩んでいるのに気づいた。振り返ると彼女は立ち止まってずっと空を仰いでいる。私は彼女からはぐれないように、また元の場所へ戻る。それの繰り返しだった。
私はもっと先へ進みたかった。でも彼女はそんな気持ちも知る由もなく佇んでいる。これからどうなるなんて誰もわからない。ただ彼女が留まるのであれば私も少しだけ寄り添ってみよう。それは私の甘さだったのかもしれない。
3
今日みたいな雨の日、ドアの向こうの彼女はまるで捨て猫のようだった。
何も言わない彼女がいじらしく思えて仕方がなかった。今思えば、うちに帰してやる事が優しさだったんだろう。私は彼女の中で起きている事を察した。これは私のためにも彼女のためにもならない事くらい、とっくにわかっていたハズなのに。
「私、バイトして家賃の半分払うよ。」
マコトはぎこちない笑顔で言った。彼女なりに気を遣ってくれていたのだろう。でもマコトのことは彼女の家族以上に知っている。今までやったバイトも長続きしなかった。毎回バイト先の誰かともモメて、結局居場所がなくなって行かなくなる。誰とでも仲良くなれるんだけど、自分から折れる術を知らない。自分がこうだと思ったことは絶対に譲らない。そして不機嫌になって誰とも話さなくなる。私にだってそうだった。働くことは嫌いじゃないらしいけど、彼女の我の強さというものが自分の居場所を失くす原因になっているみたいだった。彼女特何かをしてくれるっていう気持ちはありがたかったけど、彼女のそんな性格が心配だった。正直なところ私は彼女のそういう部分をあまり信用していなかったのかもしれない。
「別にいいよ。そんな無理しなくても・・・」
「無理なんかしてないよ。自分の部屋が決まるまでお世話になるんだから、それぐらいはさせて。」
「それならバイトしたお金を一人暮らしのために貯金したら?」
「貯金もするよ。もう、うるさいなぁ。私が払うって言ってんだから払うの!サクラは受け取ってればいいんだよ!」
マコトはふくれっ面でそう言うと、畳んであった私の布団に顔をうずめた。
同居が決まると、マコトは何とも彼女らしい気遣いを見せた。
その日は朝から彼女の姿が見えなかったので、バイト探しに行ってるんだろうなんて思っていたら、何やら両手いっぱいに買い物袋を抱えて帰って来た。
「そんなに沢山何買って来たの?」
マコトは含み笑いをしながら「生活必需品」とだけ言うと、おもむろに買い物袋からカラフルなシャワーカーテンを取り出し封を開け広げ始めた。
「そんなカーテン、どうするの?」
「サクラも一人になりたいでしょ?だから私が視界に入らないように部屋を作ります。」
「部屋?」
「そう、部屋。」
マコトは洗濯用のロープを取り出して部屋のちょうど真ん中に持って行き、ロープの端っこを部屋の壁に画鋲で取り付け始めた。
「ここにこのカーテンを掛けて部屋を仕切るの。」
カーテンを広げて見せる彼女の姿が馬鹿らしくも可愛げで私は思わず笑ってしまった。
「笑うことないじゃん!こっちはマジなのに!」
そう言いながらカーテンを掛けて行く。そんな彼女を見てると妙に和んでしまった。
「完成!」と言って出来上がった仕切りを見ると、私の身長だったら余裕であちら側が見渡せてしまう、なんとも不恰好な〝部屋〟が完成していた。
私はまた笑ってしまった。
「ほら、そこ笑わない!」
マコトもそこは判っていたようで、顔を赤くさせながら言った。それが本当に可笑しくてお腹を抱えて笑った。さらに顔が赤くなった。
「もういい!寝る!」と言いながら小さな身体をさらに小さくさせて、彼女は〝部屋〟の向こう側に姿を隠した。
ベランダ側の日の当たる〝部屋〟が私の場所で、カーテンの反対側に寝袋を敷いて彼女は寝ていた。
「そんなので寝ていたら身体壊すよ。」と言っても彼女は「平気、気にしないで。」と聞かない。人が親切に言ってあげたってあの子はいつも聞き入れなかった。
最初は寝袋で寝ていたマコトだったけど、次の日、目覚めると案の定私の布団に入り込み隣でスースー寝息を立てていた。
それはもう当たり前の光景だった。子供の頃からずっとこんな感じだった。
始めは別々に寝ていても、朝起きたら必ず隣でマコトが眠っていた。彼女は私に寄り添うようにして眠る。その寝顔は無垢なまま。
複雑な気持ちだった。
4
彼女の寝顔を見ているといつも、私達同じもののような気がしてならかった。ただお互いの弱さを共有して、傷を舐め合っているだけに過ぎなかったのかもしれない。私はマコトの事が大好きだ。出来ればずっと一緒にいたいと思ってる。でも私は私で色々決着を付けないきゃならないことがある。いつからこう思うようになったのかはわからない。もっと自分で見聞きしなければならないものがこの世界には山ほどあったのに、他の誰かが見聞きしたものを私はそれをさも自分が見聞きした事のように済ませていた。今までずっとそこに踏み出して行ける勇気を持てず、長い時間を言い訳探しのために費やしてきた。「私一人で何が出来る?」いつも頭の中で問い詰められていた。
マコトといれば安心だった。でもそのことに一体何の根拠があったのか。一体何に私は安心していたのだろうか。結局私は彼女を傷つけていただけだった。彼女の人生にこれ以上関わってはいけない。子供時代はもう終わった。マコトはどうだかわからないけど、少なくとも私はそこに留まっていることは望んでないし、私達はここにいてはいけない気がする。
そんなことを考えるといつも頭がこんがらがっていた。
いつからだろう。私は自分の中に自分の意思というものの存在を自覚するようになった。マコトを置いて行ってでも踏み出さなきゃと思った。
高校卒業後、大学への進学を望んでいたお父さんの思いを振り切って、私はデザインの専門学校へ進んだ。私が子供の頃から唯一好きだったのは絵を描くことで、将来何になりたいとか考えていなかったけど、漠然と絵を描いて生きていきたいと思っていてた。これは服飾デザイナーから自分の会社を立ち上げたお母さんの影響なんだろう。
中学の時、選択授業でグラフィックを学ぶ機会があった。その授業は文化祭のポスターをデザインするというもので、私の作品がその年の学園祭で実際に使われた。講師の先生も私には素質があると言ってくれた。この時私は図々しくも、これで生きて行ける気がしていた。
私がデザインの道へ進みたいって言ったら、お父さんは、それなら美大に進んだらどうかと提案してくれたけど、私は中学の時に習った先生に教わりたかった。だからその先生が校長を務める学校へ行きたかった。
でもそれは表向きの理由で、本当は自分で決めたことに賛同して欲しいという気持ちの方が強かった。だからこの時はとにかく最後まで自分の思いを通した。
誰かに自分の意思を伝えたのは生まれて初めてだった。お父さんは渋々ながらも最後は「咲良の決めたことなら」と承諾してくれた。これからは自分の力で生きて行く、私なりの決意表明だった。
これで良かったんだ。そう強く思ってはいながらも、まだ誰かに引っ張って行ってもらう事を望んでいた。つくづく自分の弱さを実感した。自分がこれから見ようとしているものを心のドコカで疑っている。今もそう。
自分が決めたということに対して、少しはスッとするかと思ったけど、そんなことはなかった。だからあの時、マコトが私の部屋にやってきたことに安心出来たんだと思う。なんてワガママなんだろう。
5
雨が一段と強くなっている。何か思い立ったように台所へ向かう。何かを忘れているような気がしてならなかった。
キッチンにはコンビニ弁当の空き容器やペットボトルがゴミ袋の中いっぱいになっている。自炊をした形跡がない。お父さんは毎日コンビニ弁当か外食で済ませているんだろう。しょうがないな。
冷蔵庫を開ける。缶ビール三本とペットボトルのお茶一本と牛乳一パックと袋の空いた食パンしか入っていない。しかも食パンは一昨日で賞味期限切れ。牛乳は昨日までの期限となっている。とりあえず食パンは捨てて、牛乳を少しだけ味見したあとそのまま流しに捨てた。
部屋で携帯が鳴っているのが聞こえた。急いで部屋に戻る。
笹之辺君からだ。
「・・・・もしもし?サクラ?身体の調子はどう?」
「うん、大丈夫。」
笹之辺君にはお世話になりっぱなしだ。
「親父さん帰ってきた?」
「ううん。まだ。」
「そっか・・・・・。」
「何?」
「いや、マコトと連絡取れたかなって思って・・・。」
「あれから連絡してない。」
「そっか。迷惑掛けてごめん。」
「何で、笹之辺君が謝るの?」
「いや・・・あいつバカだから。」
「連絡、取れたの?」
「いや、あのバカ出ないんだよ。」
「そうなんだ。」
「親が心配してて、なぜか俺にばっかり聞いてくるもんで。」
「そう。」
「そんなに心配なら自分達で行けばいいのに。自分の子供に怯えててどうすんだって話だよ。」
「・・・・・・・・・。」
「サクラ?」
「・・・・何?」
「本当に、申し訳ない。」
「・・・だから何で?」
「妹の事で負担かけちゃって・・・・」
「・・・・・・・・。」
「本当は俺達で何とかしなきゃならない事なのに、結果全部押し付ける感じになっちゃって・・・」
笹之辺君の話を割るように私は言った。
「私達、出会わなければ。」
「え?」
「・・・・ううん、何でもない。」
「・・・・・そっか。」
笹之辺君は最後に「身体大事にな。」とだけ言って電話を切った。
謝らなきゃならないのは私の方。私がマコトを追い込んだ。マコトの人生をメチャクチャにしたのは私だ。それでもマコトはまだ、あの日の事を黙っている。死んでも自分からは言わないつもりだろう。それなのに私は彼女を裏切り続けている。今も。
笹之辺君と連絡取り合っている事をマコトは知らない。彼女のことは、ほぼ毎日メールで笹之辺君に報告している。笹之辺君は妹の事を一番思っている。 そんな彼の気持ちを踏み躙る事は出来なかった。
6
初夏のある蒸し暑い夜。とにかく寝苦しくって仕方がなかった。それなのに隣で眠る彼女はお構いなしにイビキをかいていた。マコトは代謝が良いらしく着ていた白いシャツが透けるくらい汗ダクになってた。なのに私は汗ひとつかけず、またそれが原因でとにかく気怠くって仕方がなかった。次の日も朝から授業があって、寝なきゃいけないのに眠れない。どんな環境でも平然と眠れるマコトの神経に少し苛立ち始めていた。
天井を見つめる。真っ白で無機質だ。マコトのおじいちゃんの部屋とは違う。あの部屋に泊まった時も、マコトのイビキを聞き流しながら天井を見つめていた。古い時計の秒針の音をカウントしていると、いつの間にか寝てしまっていた。
新聞配達のバイクの音が止まっては鳴りを繰り返し、だんだんこちらに近づいて来る。もう寝るのを諦めようと思っていたら、マコトのイビキが止んだ。
「ニィには言わないで・・・。」
マコトは泣き出しそうな声で言った。寝言のような気がして、私は何も答えなかった。彼女もそれ以上何も言わなかった。
私は卑怯だ。彼女は苦しんでいる。自分で何とかしなきゃいけなかったのに、苦しい事はすべてマコトに押し付けていた。それどころか彼女を置いて自分の好きなように生きていこうとしている。罪悪感でいっぱいになった。
私は彼女の右手を握って彼女の頭に自分の頭を寄せた。髪は汗の匂いとシャンプーの匂いがした。
その時、マコトの手に少しだけ力が入ったのを感じた。
晴れの日の瘡蓋【第二話】


