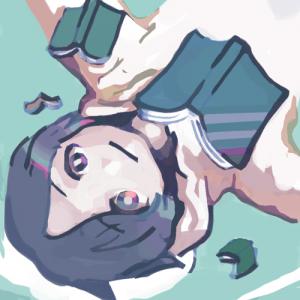途中下車前途無効
Sometime Dropのサンプル用に書いたものです。
人生にレールが敷かれているのはわたしだけだと、今までそう思ってきたんですよ。
人生にレールが敷かれているのはわたしだけだと、今までそう思ってきたんですよ。
前方の窓の向こうに流れている景色は、わたしの気分を高揚させるのには充分でした。同時に、その景色はわたしの気分を憂鬱にさせる矛盾点を隠していました。その矛盾点に気付くのは、決まって同じような景色をもういちど観た時だけでした。二度目で気付き、三度目はありませんでした。
外の景色がめまぐるしく変わる時、中の景色も微妙に変化します。
わたしは遠くまで見渡せる景色の中を進まされている時間が好きでした。遠くに山が観え、その手前に小さく町が広がっているのが観えました。山は自身のどっしりとした存在感を体現した様にそこに居座っていて、何本も電柱が窓際に音もなくひゅっと通り過ぎて行くのに対し、山だけは時間が重たく感じる程ゆっくりと通り過ぎて行くのでした。
逆にわたしは賑やかそうな街中を見るのが嫌いでした。景色は忙しなく変わりますし、音は聞こえないはずなのに五月蠅く感じるからです。ビルが眼前を支配して、ぱっと次は見ているだけで目眩がきそうな人混みを映し、またコンクリートの壁がやって来る。そんな時わたしは視線を落とし、のっぺりとした床に映しだされた影を見るのでした。太陽が薄暗い空間に温かい日光を注ぎ込み、わたしという存在の輪郭を切り取って床に貼り付けていました。肩の辺りまで伸びた髪と、耳の部分に被さるノイズキャンセル機能が搭載された大きなヘッドホンだけがわたしを形取る為に必要な素材でした。頭の上では電線が墨汁を漬けた筆で一線を引いたように見えますが、その線は何かの幼虫のようにゆっくりと上下に揺れていました。そしてそうやって影を見つめていると、素早くカーテンを引かれたように、一瞬で全てが影に覆われるのでした。
ちなみにヘッドホンから伸びたコードの先には音楽プレイヤーが繋がれていましたが、耳には何も届きません。無音です。それもそのはず、そうでなければ困ってしまいます。ノイズを消す為に使っているのですから、ノイズが耳に届いたら本末転倒です。
…………どうやらここにも矛盾点が隠れているようでした。
わたしの前方にある窓は外との唯一の境界線であり、同時に外の景色を届ける為にいちど必ず通されるフィルターの機能もありますが、それでも綺麗なものは綺麗に観えて、ばっちいものはばっちく観えるのでした。
暗いトンネルの中を通されたことも多くありました。外が暗いと私の居る空間が明るく思えるのが不思議でした。窓の向こうが明るかろうが暗かろうが、中の光源の強さは変わらないのですから。
窓の向こうには景色など無く、フィルターは機能を働かせず、そこにはひとり、わたしが映っていました。何処にでもいそうな、平凡な女の子です。姿形がではなく、存在がです。窓に反射するという、それだけでわたしはわたしが思っていたより存在感が薄い人間なんだと気付かされるのでした。
あれ? フィルター機能、少しは働いてるじゃないですか。最悪でした。
どれほどの時間を、わたしは座ったままで過ごしたでしょう。変わるものは外の景色だけなので、時間経過が分かりませんでした。体内時計なんて既に壊れて埃を被っていました。
徐ろにわたしはヘッドホンを外してみました。
無音でした。
何も耳に届きません。
思わずわたしは両手を耳に当ててちゃんとヘッドホンが外れたのかどうかを確かめました。しかし両の手の平はぺったりとした二つの耳に虚しく接触しました。
わたしは立ち上がって辺りを見回します。
当たり前のようにここにいる人間はわたし独りだけでした。
そして窓の向こうを見てぎょっとするのでした。
景色が無かったんです。
トンネルに入ったわけではないことは瞬時に理解できました。何故なら窓の向こうに広がっているのは黒一色ではなく、白一色だったからです。
ペンキを塗りたくったような光景でした。これでは一見しただけでは進んでいるのかすら分かりません。しかし僅かな揺れは足元から伝わってくるのでどうやら進んでいるようでした。
…………何処に?
一体全体、わたしは何処に進まされているのでしょう。
そもそもわたしは進まされているのでしょうか、それとも戻らされているのでしょうか。もう随分と長い間ここにいたので、景色が無くなってしまっただけでそれすらも分かりませんでした。
どうしましょう。
わたしは困りました。
しかし自分で気が付きます。
わたしはあまり困っていないようでした。
逆に落ち着いているようでした。
眠気さえ感じました。
白一色の光景がわたしの頭の中にまで侵食しているようでした。水の溜まった水槽の中に、一滴だけペンキが落っこち、融け合い、全体の色が無色透明から白へと変わりつつありました。
わたしはすとんと椅子に座り込みました。このまま身を任せて眠ってしまおうと。それでいいじゃないかと。そう思いました。
瞼がカーテンコールの時に降りてくる幕の様に閉じていきます。白一色が暗闇に包まれていきます。
その時私は視界の果てに見つけました。
山です。
窓の向こうに山が見えてきたのです。
わたしは閉じかけた瞼をぐっと堪えます。随分と重たく感じましたが、そこは我慢です。我慢して待っていれば、また山の観える景色が拝めるのです。頑張りましょう。
そうして暫くの間、瞼を閉ざさず視界を捉え続けていると、いつか観たような気がする山のある町の景色が窓の向こうに広がりました。しかし空は白く、窓という境界線から町までの空間も真っ白でした。わたしは自身がガッカリしてしまうのではないかと不安になりましたが、そんなことはありませんでした。
逆にわたしの気分はいつもの様に高揚して来ました。
いえ、いつもとは何処か違う高揚感でした。なにかが体のなかでむずむずしているような、そんな感覚があります。その感覚は次第に体全体に広がっていき、そこでわたしは自分自身がむずむずしていることに気が付きました。
衝動。
理由などありませんでした。用意する暇すらありませんでした。
わたしは椅子から立ち上がって前方に数歩進み、窓枠の端にある取っ手をつまんで思い切り持ち上げました。
風が全身にぶつかってきました。思わずよろめきますが、取っ手を掴んだ両手をそのまま引き寄せる形で体重を前へと向け、その勢いのままにわたしは外へ飛び出しました。
待ち構えているであろう強い衝撃に体を丸くしましたが、その必要はありませんでした。
わたしはすたんと真っ白な地面に降り立ったのです。
そこでまた気付きます。
音が聞こえてくるのです。
そういえば先程窓を開けた時にも、心地良い風の音が耳に確かに届いていました。
わたしはその場でつま先を上げて真っ白な地面に叩きつけます。タン、と平坦な音が耳に届きます。とてもつまらない音でしたが、何故だかわたしは嬉しくなってしまい、そこでタンタン、タンンタン、と足を鳴らします。
ひとしきりその音を楽しむと、目の前に広がる景色をフィルターを通さずにこの目でしっかりと見据えます。
空も地面も真っ白。もはやどこまでが地面でどこからが空なのか区別がつきません。しかし遠く前方には小さく町が見え、そしてその向こうにどっしりとした山が存在しています。
辺りを見渡してみると、看板がひとつ、近くに立っているのを見つけました。近寄って内容を確かめてみます。どうやらあの町のへの案内図のようでした。
このまま真っ直ぐ。
そう書かれていました。
丁寧に移動手段によってかかるおおよその時間も書かれています。
徒歩一生。
「まぁ、いいでしょう」
わたしは首にかけたヘッドホンを看板に引っ掛けました。
そしてわたしは歩き始めます。
一歩進む度に、足元から色が広がっていくような気がしました。
気分はウキウキ、最高です。
途中下車前途無効
前は地の文ばっかの小説書いてたけど、最近は台詞で回す面白さに気付いて作風が変わったような気がします。